第1節 我が国グローバル企業の収益力向上
1.付加価値ベースの収益力向上
(1)収益力向上を巡る議論の経過
日系グローバル企業51の売上高や営業利益率などの収益力に関する一般的な指標が、欧米系グローバル企業のそれらと比較して低い水準にあることは、通商白書をはじめとして指摘されてきた。例えば、2015年版通商白書では、世界のグローバル企業357社を対象に財務分析を行った結果、日系グローバル企業は、売上高、営業利益及び売上高営業利益率に関して、欧米系グローバル企業と比較すると相対的に低成長・低収益であることが指摘されている52。特に、多角化が進んでいる企業における成長性及び収益性の低さが指摘されている。
第Ⅱ-3-1-1-1図は日米欧の上場企業の収益構造について、売上原価率などの財務指標に注目して比較している。まず、売上原価率は、生産性を議論する際に重要な「付加価値」に最も近い会計上の概念である売上原価を示す指標である。我が国グローバル企業は、欧米グローバル企業と比較して売上原価率が高いことから、売上高が低い又は中間投入額(製造原価など)が高いという意味において、付加価値の創出に課題があると考えられる。売上高と売上原価の差は粗利を表しているが、売上原価率が高いということは粗利の幅が小さいことを示しているので、粗利から販売費及び一般管理費を差し引いた営業利益も小さくなり、その売上高に対する割合である営業利益率は、自動的に低い割合となっている。さらに、法人税などを控除した後の純利益についても同様のことが言えることから、純利益率も低い割合となっている。
第Ⅱ-3-1-1-1図 世界の上場企業の収益構造(中央値、%)
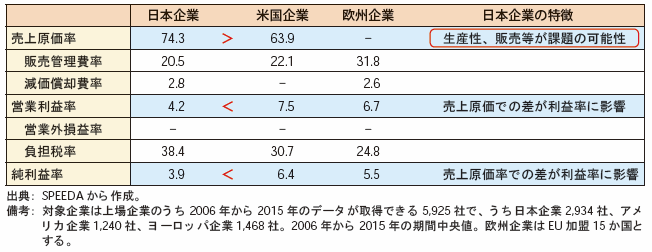
平成25年度年次経済財政報告では、日本企業の競争力分析の中で、我が国の製造業企業の収益力(総資産利益率)が、米国やドイツの製造業企業と比較して相対的に低いことを指摘している53。その要因として、前掲の2015年版通商白書では、成長力や収益力が高いとされる設立・再編からの経過年数が比較的短い、いわゆる若い企業が少ないこと、また、事業の多角化が進んだ企業において研究開発投資の効率性が低下していることなどを指摘している54。
さらに、前掲の平成25年度年次経済財政報告では、我が国製造業企業の横並び志向やリスクテイク行動の消極性が、抜本的な製品差別化を抑制するとともに過当競争を助長した結果、利幅の薄いビジネスモデルに偏る傾向を生んでいるとして、製造業上場企業の売上高のハーフィンダール・ハーシュマン指数で寡占度を計算し、日本が米国及びドイツと比較して市場の寡占度が低く、過当競争や収益性の低さに繋がっている可能性を指摘している55(第Ⅱ-3-1-1-2図)。
第Ⅱ-3-1-1-2図 製造業上場企業の売上高から見た寡占度
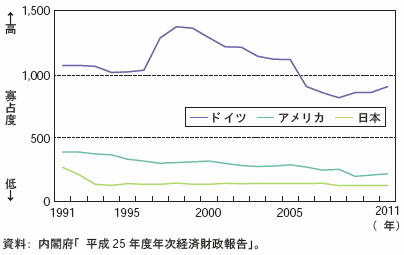
なお、我が国の人口10万人当たりの上場企業の数を見ると、上記の状態と整合している56(第Ⅱ-3-1-1-3図)。
第Ⅱ-3-1-1-3図 各国の上場企業の総数及び人口10万人あたり企業数
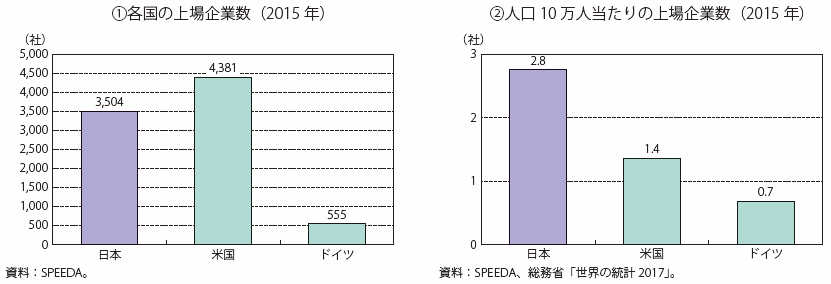
以上のような問題意識のもとに、収益力向上に向けた取組として、産学官の連携や企業経営のガバナンス強化といった事業環境整備の重要性、人材の多様性やイノベーション人材確保の重要性、及びIT活用の重要性などが唱えられてきた57。
51 経営指標の国際比較は、「多国籍企業」の定義が一般的に用いられることが多いが、本節では、より広い意味の「グローバル企業」との呼称に統一している。本節で用いているグローバル企業とは、UNCTADが定義する多国籍企業(http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Transnational-corporations-(TNC).aspx)の範囲に含まれる企業のほかに、在外子会社等を持たずに輸出している企業(輸出企業)を含む企業群のことである。
52 経済産業省(2015)、p. 216。
53 内閣府(2009)。
54 経済産業省(2015)。
55 平成25年度年次経済財政報告第2章。また、ドイツのハーフィンダール・ハーシュマン指数について、国内売上に占める輸入の割合が高いため、ドイツ企業だけで計算した同指数は高めに出やすい面があると述べられている。
56 ドイツでは世界的な大企業であっても上場していないことがあり(例えば、自動車部品メーカBosch)、日本及び米国と単純に比較出することはできない。
57 経済産業省(2015)。
(2)収益力・生産性・価格決定力の関係
我が国が持続的に経済成長するためには、所得と支出の好循環を生み出し続けていくことが必要であることから、生産と投資の主体であるとともに、労働の対価として賃金を分配している企業が経済成長に果たしている役割は大きいといえる。GDPの内訳を見てみると、企業をはじめとする市場生産者58が生み出した付加価値額は名目ベースで約9割を占めている59。このことから、企業が生み出す付加価値に注目することは、経済活動をとらえる上で重要な視点となる。
企業の付加価値額は、売上高から、原材料費や流通経費など外部から調達した財・サービスに係る費用(中間投入額)を控除して計算することができる60。付加価値額の内訳は、一般的には「人件費」、「減価償却費」、「当期利益」及び「支払利息・賃料」などから構成される。つまり、企業の生産・営業活動における入口(調達)と出口(売上)の差を表した数字と考えることができる。
ここで、名目付加価値額について考えてみよう。前述のとおり、企業の粗利に相当することから、ROE(株主資本利益率)やROA(総資本利益率)などの財務指標と同様に、企業の収益力を表す指標とみなすことができる。名目付加価値額と財務指標との違いは、前者がGDPのようにマクロ経済に関わる集計量との親和性の高さに注目できる一方で、後者が株主の視点から収益力あるいは保有資産・負債の効率的利用を評価することを目的として使われている点にある。
企業の収益力を名目付加価値額として考えるとき、実質付加価値額は名目付加価値額を付加価値デフレータで割ることによって求めることができる61。この関係をかけ算の形に整理すると、「名目付加価値額=実質付加価値額×付加価値デフレータ」となる(第Ⅱ-3-1-1-4図)。
第Ⅱ-3-1-1-4図 収益力、生産性及び価格決定力
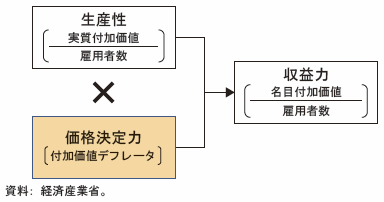
第Ⅱ-3-1-1-5図 収益力と名目付加価値額の対応
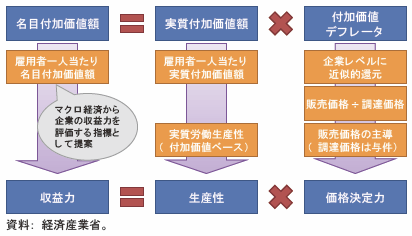
ここで、この関係式の両辺を雇用者数で割ると、一方で、収益力は「雇用者一人当たり名目付加価値額になる。他方で、実質付加価値額は「雇用者一人当たり実質付加価値額」となるので、これは「実質労働生産性」を意味することになる。また、付加価値デフレータはそのままの形で変わらない。
付加価値デフレータは、企業が生み出す製品・サービスに体化された付加価値の「価格」とみなせる指標である。(名目)付加価値額は、前述の通り、企業の売上高(販売価格×販売数量)から原材料費(調達価格×調達数量)を控除したものであるから、販売数量と調達数量が一定と仮定すれば、付加価値デフレータの変化は、調達価格の変化と販売価格の変化から決まることになる。よって、付加価値デフレータは、「価格転嫁の動向を見極めるための指標」、すなわち「価格決定力」を表すものと言えるだろう62。
上述の関係式から明らかなことは、企業が収益力を向上させるためには、生産性を向上させるだけでなく、価格決定力もまた同時に高めることが重要になるということである。生産性の向上が実現しても、製品価格が低下することになってしまっては、収益力の向上は実現できないのである。
価格決定力の向上は、原材料費や人件費など中間投入の費用(調達価格)が上昇した場合に、調達価格の上昇分を販売価格に転嫁する力(価格転嫁力)も高める(第Ⅱ-3-1-1-6図)。価格決定力がない場合、企業が付加価値を維持するためには、利益を圧縮したり、中間投入の間で相殺したりすることになる。このような場合、設備投資の減少や人件費の削減への誘因が働きやすくなると考えられる。ここまでの議論から、企業が付加価値の維持・拡大に主眼を置いて、製品の品質に応じた価格を主導的に決められる価格決定力や中間投入コストの上昇分を販売価格へ適切に転嫁できる価格転嫁力を有することは、企業の収益力にとっても、経済の成長にとっても有益な結果をもたらす可能性があることがわかる。よって、付加価値に注目して、生産性の向上や価格決定力の強化を図ることが、企業にとっては雇用、設備投資及び配当などの原資を確保することになり、我が国の経済成長に貢献することになり得る。
第Ⅱ-3-1-1-6図 価格決定力と付加価値
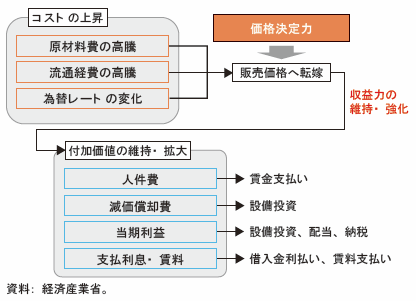
58 財貨・サービスを経済的に意味のある価格で供給する生産者を指し、非金融法人企業、金融機関、家計(個人企業)が該当する。さらに、我が国の国民経済計算では、こうした市場産出に加えて、自己最終使用のための産出の一部(持ち家の帰属家賃等)が含まれている。
59 2015年の数値。内閣府「国民経済計算(GDP統計)」ホームページ(http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/menu.html)、年次推計、フロー編付表2(経済活動別の国内総生産・要素所得)。
60 これら以外にも、外貨建てで製品を海外に輸出した場合、あるいは原材料を海外から購入した場合などである。為替レートが変動することで為替差損益が発生した場合には、当該差損益を売上高に反映させることで、(円ベースの)付加価値額は変動する。
61 名目GDPを物価でデフレートして実質GDPを求めることと同様の計算である。
62 中小企業庁(2014)、第1部第1章第3節参照。
2.我々が直面している課題
低迷している収益力の向上に向けて、前項では、付加価値に注目することによって、収益力・生産性・価格決定力の関係を見いだした。付加価値に注目して企業を評価すると、そのGDPに占める割合の大きさから、我が国の経済成長につながっていることが明らかである。本項では、収益力向上と経済成長の両立に向けて、我々が直面している課題について、収益力の決定要因、生産性上昇と雇用縮小、及び資本収益率と人材投資という視点から、それぞれ検討していく。
(1)価格決定力の低迷
①価格決定力(付加価値デフレータ)の国際比較
一人当たり名目付加価値額を収益力の指標としたとき、前項において論じたように、企業の収益力は、実質労働生産性と付加価値デフレータの積に等しくなる(第Ⅱ-3-1-1-4図)。よって、企業は生産性の上昇に向けた努力とともに、価格決定力の強化にも努めることが収益力向上のために必要である。
しかしながら、我が国企業では、生産性の上昇は実現できても、価格決定力を高めることができていないことが現状である63。実際、経済産業省が今年実施したアンケート調査では、価格決定力を「有していない」とした企業が58.9%と半数以上なのに対し、「有している」と回答した企業は僅か24.2%となっている(第Ⅱ-3-1-2-1図)。
第Ⅱ-3-1-2-1図 我が国企業の価格決定力の有無
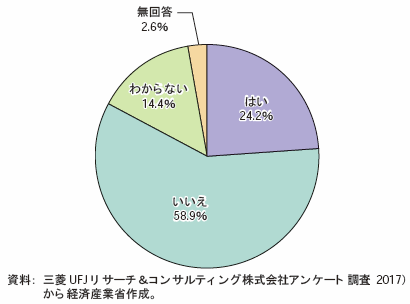
第Ⅱ-3-1-2-2図①は、我が国、米国及びドイツの産業全体の収益力(一人当たり付加価値額)の変動要因分解を行った結果である64。これを見ると、我が国では、1970年代以降の収益力が、ほぼ下降傾向にあり、産業全体が実質労働生産性の伸び率上昇の果実を付加価値デフレータの伸び率低下によって喪失しており、生産性の改善が収益力の向上に結びついていないことが見て取れる。米国は、1970年代以降1990年代まで、我が国と比較して付加価値デフレータの伸び率が緩やかに下降してきたが、2000年代前半に一旦上昇し、2000年代後半に再び伸び率が下降している。ドイツも我が国と同様に1970年代以降、収益力がほぼ下降し続けているが、日本ほど伸び率は低くなっていない。この要因は、各国のインフレ率の推移、市場における競争圧力増加、製品のコモデティ化による市場価格の低下圧力等の様々な要因が影響しているものと考えられる。なお、米国と日本の生産性(一人当たり付加価値額=収益力)に格差が生じている理由は、両国の価格戦略の違いが影響していること、すなわち日本企業が1990年代からのデフレに対応し、利益を削ってでも低価格化を実現することで競争力を維持してきたこと、との指摘がある65。
第Ⅱ-3-1-2-2図① 米日独の全産業収益力(一人当たり付加価値額)の変動要因分解
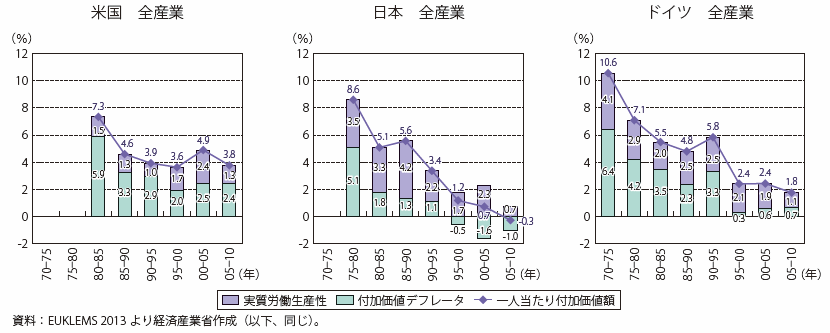
第Ⅱ-3-1-2-2図②は、3か国の製造業収益力の変動要因分解を行った結果である。製造業全体では、米国が比較的高い収益力伸び率を維持する一方で、日本とドイツは1970年代以降、収益力伸び率がほぼ下降傾向にある。特に日本の製造業における収益力伸び率は、生産性の伸び率が上昇した一方で、付加価値デフレータの伸び率がマイナスとなったため、収益力の伸び率を押し下げる形となった。米国及びドイツと比較して、日本は国内経済状況低迷の影響が大きかったこともあるが、前述したとおり利益を削って低価格化を目指した、すなわち価格決定力を行使できなかった可能性がある。
第Ⅱ-3-1-2-2図② 米日独の製造業収益力(一人当たり付加価値額)の変動要因分解
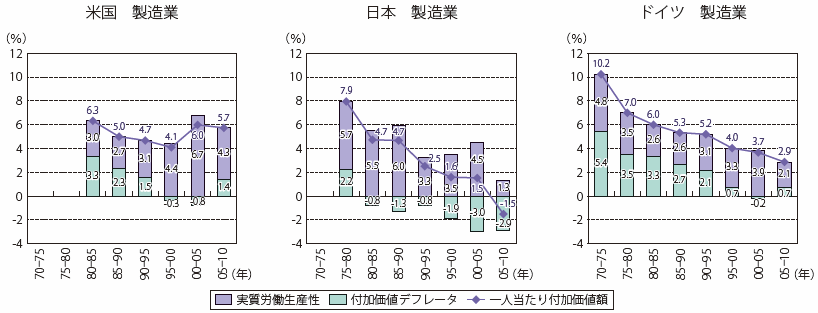
第Ⅱ-3-1-2-2図③は、製造業の産業別に収益力の変動要因分解を行った結果である。産業別に見ると、米国の化学品・医薬品、及び鉄鋼・金属製品は、付加価値デフレータが高い伸び率を示しており、収益力を伸ばしていると見られる。日本とドイツでは同産業の付加価値デフレータの伸び率は低い傾向にあるものの、ドイツは生産性の伸び率を維持し、収益力の伸び率は確保している。一方で、日本は化学品・医薬品では近年、生産性、付加価値デフレータの両方の伸び率が落ち込んでおり、鉄鋼・金属製品は、生産性、付加価値デフレータの変動が大きくなっている。
第Ⅱ-3-1-2-2図③ 米日独の製造業産業毎の収益力(一人当たり付加価値額)の変動要因分解
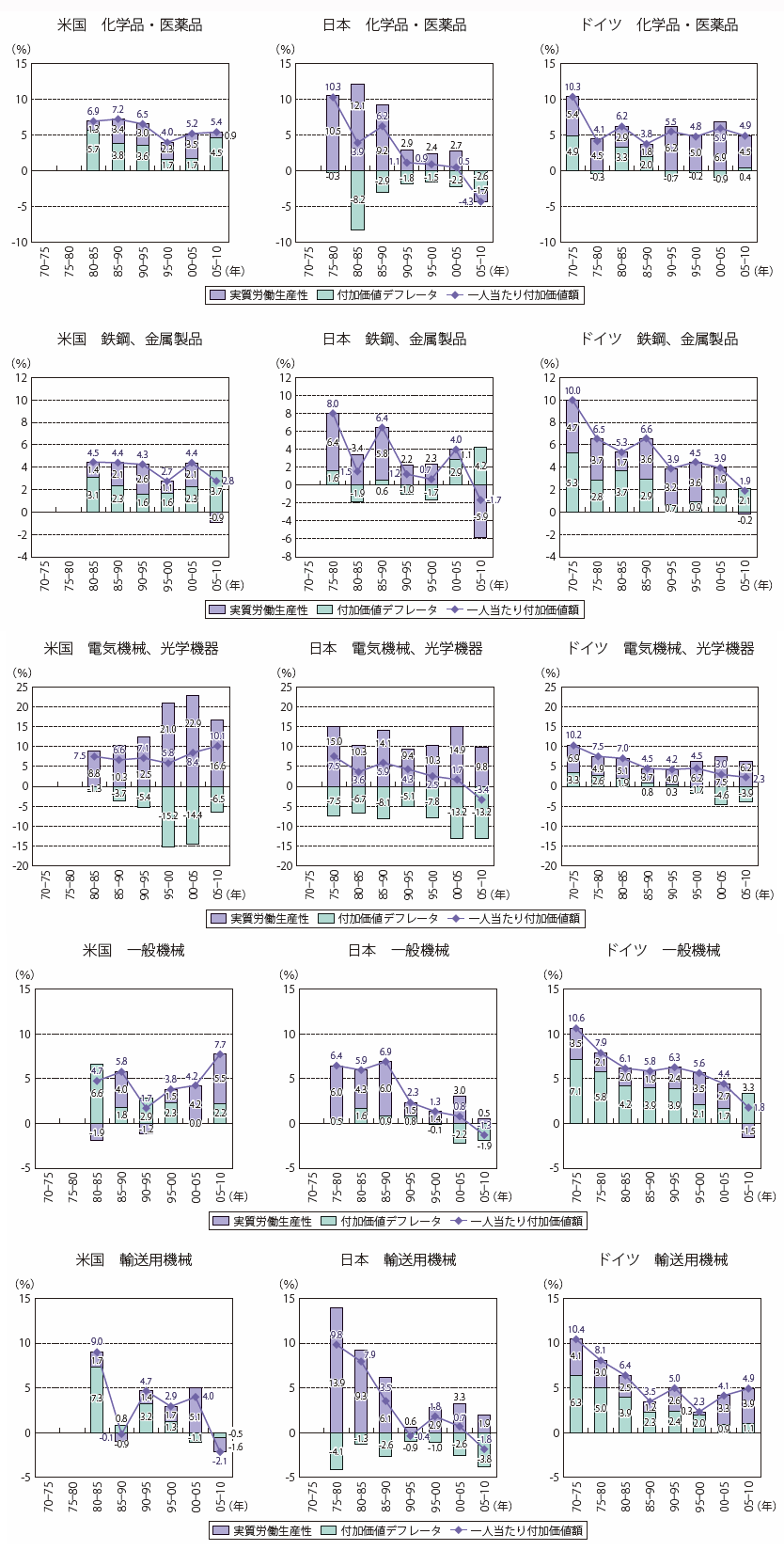
- Excel形式のファイル(米国 化学品・医薬品)はこちら

- Excel形式のファイル(日本 化学品・医薬品)はこちら

- Excel形式のファイル(ドイツ 化学品・医薬品)はこちら

- Excel形式のファイル(米国 鉄鋼、金属製品)はこちら

- Excel形式のファイル(日本 鉄鋼、金属製品)はこちら

- Excel形式のファイル(ドイツ 鉄鋼、金属製品)はこちら

- Excel形式のファイル(米国 電気機械、光学機器)はこちら

- Excel形式のファイル(日本 電気機械、光学機器)はこちら

- Excel形式のファイル(ドイツ 電気機械、光学機器)はこちら

- Excel形式のファイル(米国 一般機械)はこちら

- Excel形式のファイル(日本 一般機械)はこちら

- Excel形式のファイル(ドイツ 一般機械)はこちら

- Excel形式のファイル(米国 輸送用機械)はこちら

- Excel形式のファイル(日本 輸送用機械)はこちら

- Excel形式のファイル(ドイツ 輸送用機械)はこちら

電気機械・光学機器では、3か国とも労働生産性の高い伸び率を示している一方で、付加価値デフレータの伸び率は低下しており、市場での価格競争圧力が増していることが伺える。
一般機械では、我が国企業の生産性、付加価値デフレータの伸び率が大幅に低下しており、収益力の伸び率がマイナスになっている。これは、国内設備投資が低調なことも影響していると考えられる。他方で、米国企業は近年、生産性、付加価値デフレータの伸び率が大きく、高い収益力の伸び率を維持している。また、ドイツ企業は、生産性の伸び率は低下傾向にあるものの、付加価値デフレータの伸び率は高い水準を維持しており、堅調な収益力の伸び率を維持している。
輸送用機械では、我が国は生産性の伸び率は維持しているものの、付加価値デフレータの伸び率が低くなっている。これは、限られた日本市場に多くの競合他社が存在しているため、価格上昇を図れなかったこと、1990年代以降はインフレ率の下落等が影響した可能性がある。他方、ドイツは、付加価値デフレータは下降しているものの、労働生産性の伸び率上昇は維持しており、価格決定を主導できる製品を供給していることが伺える。
第Ⅱ-3-1-2-2図④は、非製造業の収益力の変動要因分解を行った結果である。米国では、付加価値デフレータの伸び率が全体的に見ると3か国の中で高い水準を維持しており、我が国及びドイツの非製造業と比較して収益力が高いことを示している。ドイツの付加価値デフレータの伸び率は下降傾向にあるが、我が国ほどの下落や変動は見られず、収益力の向上には貢献していると考えられる。我が国のサービス業の付加価値デフレータ伸び率が低い傾向にある背景には、国によってサービスに対する要求水準が異なるため生産性の客観的な国際比較は困難としつつ、我が国は高いサービスの品質に見合った価格設定を行っていないとの見方もある。すなわち、サービスを高品質化し、実質労働生産性を高めたにも関わらず、企業が人件費を抑制し価格転嫁が行われない傾向にあるとの指摘がされている66。
第Ⅱ-3-1-2-2図④ 米日独の非製造業産業毎の収益力(一人当たり付加価値額)の変動要因分解
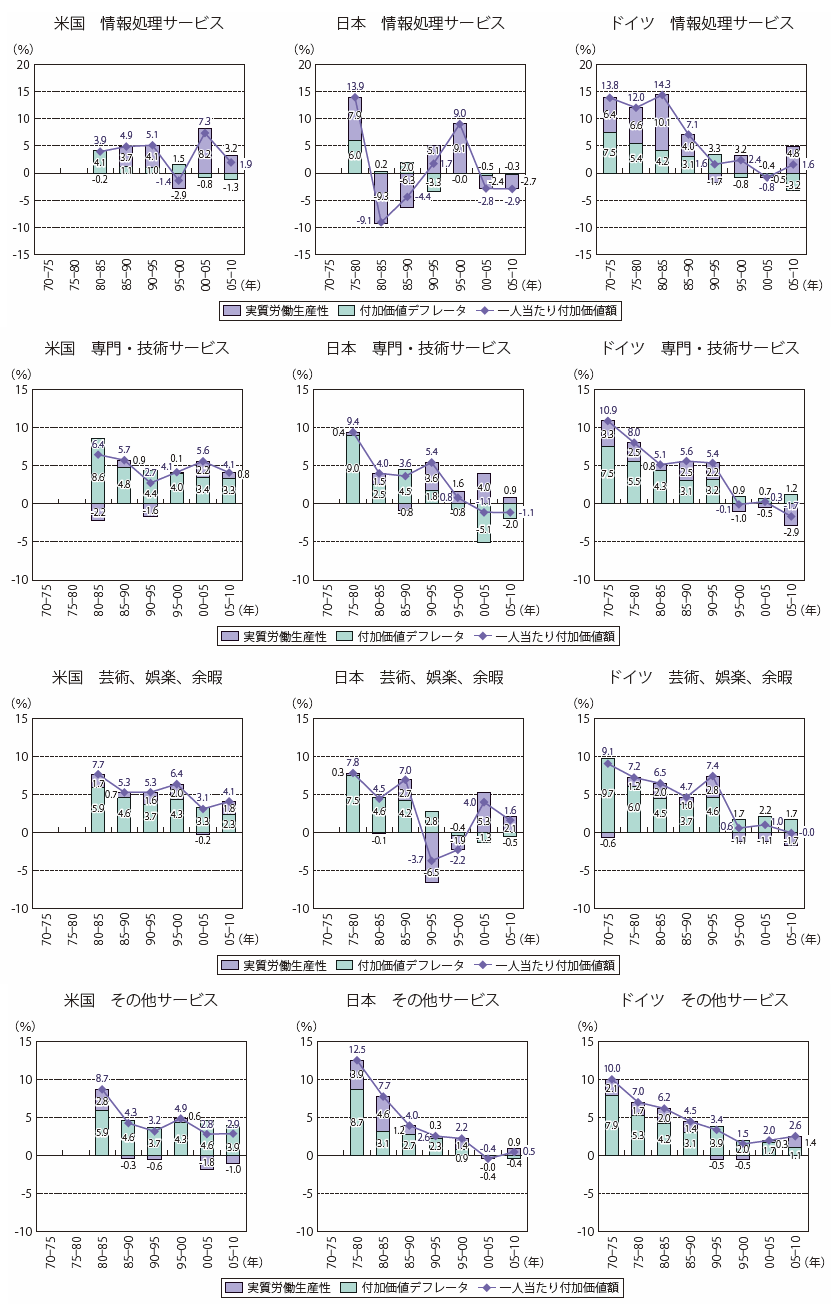
- Excel形式のファイル(米国 情報処理サービス)はこちら

- Excel形式のファイル(日本 情報処理サービス)はこちら

- Excel形式のファイル(ドイツ 情報処理サービス)はこちら

- Excel形式のファイル(米国 専門・技術サービス)はこちら

- Excel形式のファイル(日本 専門・技術サービス)はこちら

- Excel形式のファイル(ドイツ 専門・技術サービス)はこちら

- Excel形式のファイル(米国 芸術、娯楽、余暇)はこちら

- Excel形式のファイル(日本 芸術、娯楽、余暇)はこちら

- Excel形式のファイル(ドイツ 芸術、娯楽、余暇)はこちら

- Excel形式のファイル(米国 その他サービス)はこちら

- Excel形式のファイル(日本 その他サービス)はこちら

- Excel形式のファイル(ドイツ その他サービス)はこちら

63 中小企業庁(2014)、p. 43。
64 名目付加価値額、実質付加価値額(実質労働生産性)、及び付加価値デフレータの関係式の両辺に自然対数をとって変化率(伸び率)で表し、線形関係式に変換しているので、「名目付加価値額伸び率=実質労働生産性伸び率+付加価値デフレータ伸び率」という関係式になる。
65 公益財団法人日本生産性本部(2016)「労働生産性の国際比較2016年版」
66 山田(2015)及び経済産業省(2014)。
②価格決定力(付加価値デフレータ)が弱い理由と強化に向けた方向性
我が国の付加価値デフレータの伸び率は、米国、ドイツと比較して低い傾向にあることから、価格決定力が強くないということが分析から明らかになった。すなわち生産性の伸び率が高い場合でも付加価値デフレータの伸び率がマイナスとなり、収益力の伸び率が押し下げられてしまう可能性があると考えられる。我が国の付加価値デフレータ伸び率が低い、すなわち価格決定力が相対的に弱い理由については、長く続くデフレの影響も大きいとは思われるが、他にも過当競争により企業が価格決定力を主導できていない可能性がある。この点、2013年6月に閣議決定された「日本再興戦略」は、国内企業同士での消耗戦が行われていることを指摘し、過当競争を解消して、収益力を回復することを目標の1つに掲げている。また、産業革新機構の志賀俊之会長兼最高経営責任者(CEO)は「日本企業の自己資本利益率の低さは過当競争が原因」と指摘している67。
また、あるプライシング(価格決定)の専門家は、日本企業は、市場からの撤退を躊躇する傾向があり、市場シェアを非常に重要視していると指摘しており68、過当競争との関連性が示唆されている。
経済産業省が実施したアンケート調査では、実際に利益率よりも売上高、利益の絶対額を重視した経営方針でビジネスを行っている企業が多いが、今後重視していくものとしては利益率と資本効率が伸びつつあることが伺える(第Ⅱ-3-1-2-3図)。
第Ⅱ-3-1-2-3図 企業が重視する経営目標の変遷
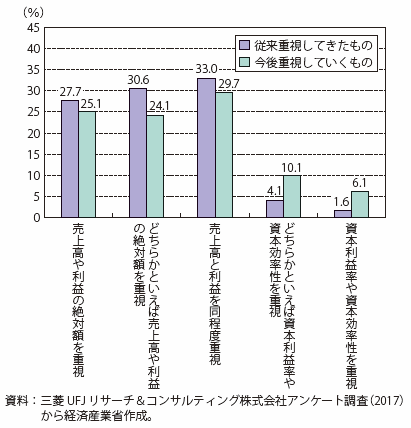
日本機械輸出組合の調査によれば、世界売上高シェアで首位となった業種は、日本企業が2業種(事務機械、工作機械)、北米企業が8業種、欧州企業が3業種、アジア企業が6業種で、日本企業はグローバル市場において必ずしも高い市場シェアを占めているものではないことが伺える(第Ⅱ-3-1-2-4表)。このことは、我が国企業の製品が、他の競合国との製品差別化が図られていないため価格競争に巻き込まれている可能がある、もしくは、価格競争力が無いために市場シェアを確保できずに収益も確保できない状況に置かれている可能性を示している。
第Ⅱ-3-1-2-4表 2015年度 地域企業種別の世界売上高シェア
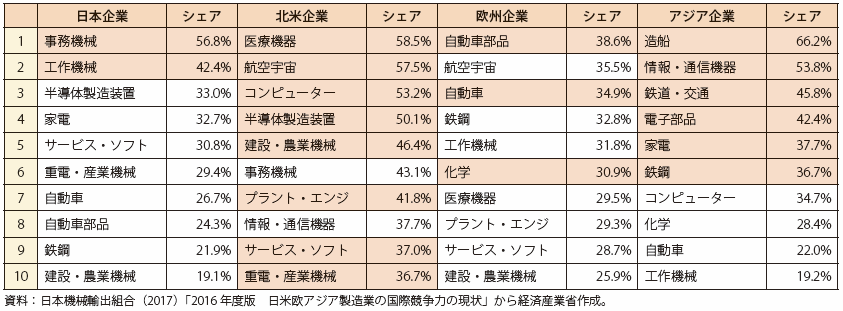
この点、我が国とドイツについて輸出構造の観点から分析した調査によれば、ドイツは低付加価値の多岐に渡るボリュームゾーン製品(食料・加工品、石油製品、木材、雑製品等)の輸出に加え、高付加価値製品(自動車、プラスチック加工機械、工作機械、発電機等)でも日本より輸出額で上回っており、この分野で日本と競合しない輸出製品の輸出額が大きいという。また、日本は価格より数量の拡大が輸出を牽引したのに対し、ドイツはドル建て輸出価格を引き上げて価格を重視したとの指摘もある69。このことから、我が国企業は、ボリュームゾーン製品の資本集約化・効率化や高付加価値製品における差別化を実現できず、双方の世界的な市場獲得に失敗していることが懸念され、その要因について分析していく必要がある。
付加価値デフレータの伸び率が低いことは、企業が自ら価格決定を主導できない可能性があることを意味し、望まずして価格競争に巻き込まれていくことに繋がる。この点、各国企業が価格競争に巻き込まれていると思うか否かについて調査した結果を国際比較した資料によれば、「価格競争に巻き込まれている」と回答した企業の割合は、日本が最も高く、ドイツや米国を大幅に上回っている(第Ⅱ-3-1-2-5図)。
第Ⅱ-3-1-2-5図 自社が価格競争に巻き込まれていると感じている企業の割合
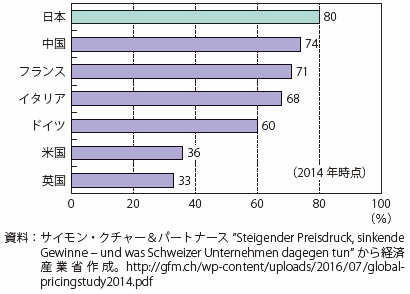
この調査結果は、先に分析した我が国企業の価格決定力の弱さ、及び過当競争による消耗戦に陥っているとの分析結果が、企業側の実際の認識から見ても誤りでないことを示唆している。経済産業省が企業ヒアリングを行ったところ、日本には国内的にも国際的にもプライス・リーダーシップを取れないビジネスが多いと懸念する声もあった。
価格競争のきっかけとしては、過剰設備、コモデティ化、市場の低成長及び産業構造が主な要因として指摘されている(第Ⅱ-3-1-2-6図)。企業同士が競合相手を追い落とすための価格引き下げ競争が行き過ぎれば、企業の利益を損なうことになり、これを長期間継続することは望ましくないとの分析が、過去の欧米企業の事例から指摘される70。
第Ⅱ-3-1-2-6図 価格競争の原因
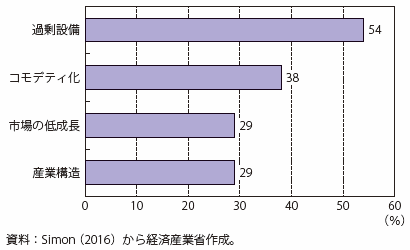
我が国企業が世界市場で価格決定力を有するようになるためには、技術力を活かしてイノベーションを実現し、汎用品とは差別化された製品を開発することによって、新規市場の創出とニッチ市場でのビジネス展開を図ることが必要であると考えられる。(第Ⅱ-3-1-2-7図)。そして、技術力によるイノベーション実現やニッチ市場向け製品開発や市場開拓を行ってビジネスを成功させるために、研究開発の強化とともに潜在的な市場の発掘、もしくは新たな市場の誕生可能性、潜在的市場・新市場向けに必要となる技術・製品を自社で見極める必要がある。
第Ⅱ-3-1-2-7図 価格決定力を有するために必要と考える要因
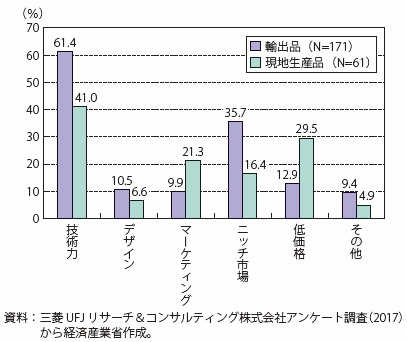
以上、我が国企業の付加価値デフレータの伸び率は、米国及びドイツの企業と比較して低くなっており、このことが企業の収益力にマイナスの影響を及ぼす傾向にあることが明らかになった。ただし、実際の企業経営における価格決定の判断は、経済や市場の状態、競合他社の動向、商品の位置付け等、様々な要因を分析して決定されることに留意が必要である。
また、日本企業は収益率が低い代わりに、欧米の企業より安定度が高いので、リスクとリターンの関係を考慮すれば、それほど収益力が低いわけではないとの分析71もあることから、収益率とリスクのバランスを考慮しながら、改めて価格決定力に目を向ける必要があると考えられる。
67 2015年8月28日付け日本経済新聞社インタビュー。
68 Simon(2016).
69 大木(2015)。
70 Raju-Zhang(2010)。
71 中野(2016)。
(2)生産性上昇と雇用縮小のジレンマ
企業が収益力を向上させる要因として従来から議論されている生産性について、雇用との関係に注目して議論していく。生産性上昇と雇用縮小が共存するという悩ましい状況である「ボーモル効果72」について分析して、生産性上昇と雇用拡大を実現している(ボーモル効果が表れていない)産業に属する企業の特徴を統計解析に基づいて明らかにする。
72 ボーモル効果は、米国経済学者ボーモルと同ボーエンによって見出された「ボーモル病」という現象に端を発する(Baumol-Bowen(1965))。ボーモル病は、一義的には生産性の上昇しない職種の給与が、労働市場を通じて生産性の上昇した他業種の給与に引っ張られて上昇することをいう。
①ボーモル効果に関する国際比較
生産性が上昇することは、中間投入に対する産出の比率が高まることを一般的に意味している。生産性の上昇とともに市場の成長(需要の拡大)も起きれば、生産性の上昇は雇用の確保・拡大につながる。しかしながら、需要が拡大しなければ、生産性の上昇は労働者を減らす誘因になるだろう。このようなボーモル効果について数字を交えて説明するならば、次のような状況を考えることができる。一人の労働者が1日に5台の機械を作っている状況から、1日に10台の機械を作っている状況に変われば、生産性が2倍になったことになる。ここで、労働者が10人で機械を作っているとしたら、生産性の上昇によって1日の生産量は50台から100台に増えることになる。このとき、生産性の上昇とともに市場の成長(需要の拡大)も起きれば、生産性の上昇は雇用の確保・拡大につながる。しかしながら、生産(供給)が1日100台に増えても、需要が1日50台のままであれば、生産性の上昇は労働者を半数に減らす誘因を帯びることになるだろう。
つまり、生産性上昇率の高い産業において資本集約化などによって労働需要が減少し、生産性の上昇にともなって製品価格も低下する。その結果、その産業の製品に対する所得弾力性が極端に高くない限り、生産性上昇率の高い産業の生産額は次第に減少し、産業の規模(雇用)も縮小していく。他方、生産性上昇率が相対的に低い産業は、相対的に労働集約的であるため、生産性の高い産業で余剰となった労働力を吸収して、次第に産業規模を拡大していく。こうして、生産性上昇率の低い産業の規模(雇用)の拡大が続き、結果として経済全体の成長率が鈍化していく。
我が国、米国及びドイツについて産業別の労働生産性上昇率と雇用者数成長率の関係を概観してみよう。第Ⅱ-3-1-2-8図~第Ⅱ-3-1-2-10図は、我が国、米国及びドイツについて、各産業の2010年~2012年の年平均労働生産性上昇率を横軸に、同期間の年平均雇用者数成長率を縦軸にとってそれらの分布をみたものである73。
第Ⅱ-3-1-2-8図 我が国の産業別労働生産性上昇率と雇用者数成長率
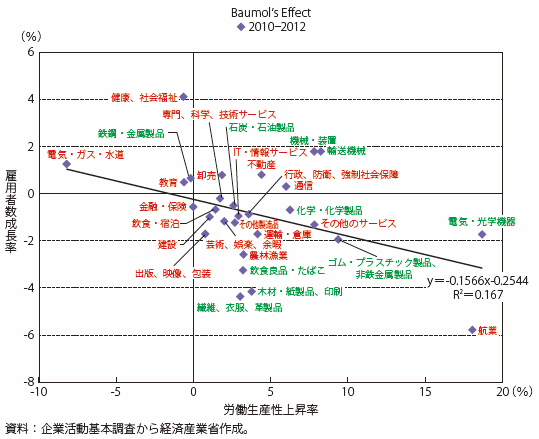
第Ⅱ-3-1-2-9図 米国の産業別労働生産性上昇率と雇用者数成長率
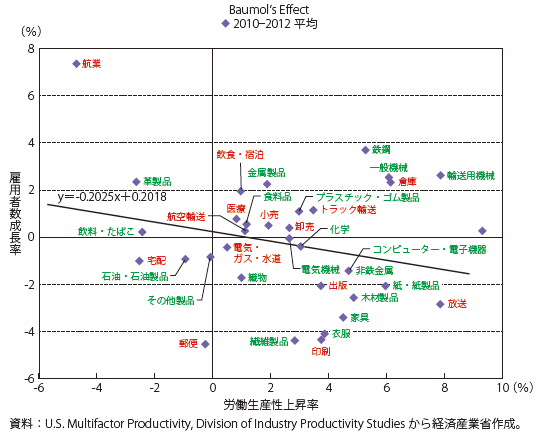
第Ⅱ-3-1-2-10図 ドイツの産業別労働生産性上昇率と雇用者数成長率
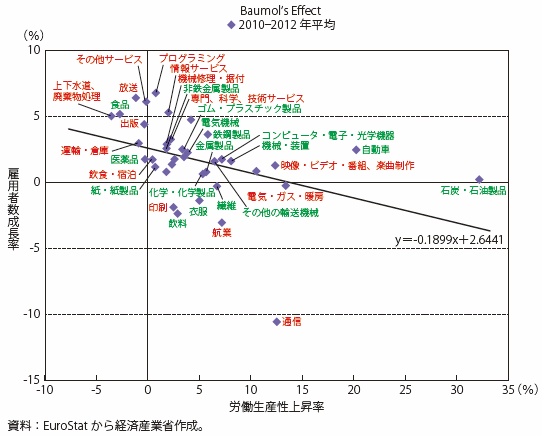
第Ⅱ-3-1-2-8図は、我が国の製造業11業種(緑色)及び非製造業(農林水産業、鉱業、行政機関等を含む)19業種(朱色)をプロットしたものである。同図を見ると、生産性上昇率が高い産業ほど雇用者数成長率が低くなる傾向にあり、我が国においてボーモル効果が生じていることが見て取れる。そして、製造業、非製造業を問わず、ほとんどの産業が、生産性は上昇しているが雇用者数は減少している第四象限に集中していることが分かる。これらの産業には、農林漁業、鉱業、建設のほか、専門・科学・技術サービス、運輸・倉庫、小売、IT・情報サービス、飲食・宿泊などといった非製造業が8産業、電気・光学機器、ゴム・プラスチック製品、非鉄金属製品、繊維、衣服、革製品、化学・化学製品及び飲食料品・たばこなどの製造業が7産業も含まれている。
生産性と雇用のいずれも伸ばしている産業を第一象限にプロットしている。製造業では機械・装置及び輸送機械の2つの産業が、非製造業では不動産、通信、卸売の3つの産業が分布していることから、これら5つの産業が主として我が国の経済成長を牽引していることを示している。後述する米国及びドイツでは、我が国と比較して生産性と雇用の両方を伸ばしている産業が多様に存在しており、特定の産業が不振になったとしても国全体の経済への影響は軽減されると考えられる。生産性と雇用の両方を伸ばすことができる産業を多様化させていくことは、我が国が持続的な経済成長を実現していくために必要なことである。
なお、第二象限(労働生産性上昇率マイナス、雇用者数成長率プラス)を見ると、鉄鋼・金属製品のほか、電気・ガス・水道や健康・社会福祉、教育といった産業がプロットされており、公益や社会保障関係の産業が中心であることが分かる。
他方、同期間の米国の労働生産性上昇率と雇用者数成長率の関係を見ると、おおむね右肩下がりとなっているのは我が国と同様であるが、我が国と比べてはるかに多くの産業が第一象限に位置している(第Ⅱ-3-1-2-9図)。すなわち、生産性上昇率の高い産業ほど雇用者数は減少ないしはその伸びが縮小する傾向にあることは我が国と同様であるが、労働生産性の上昇と雇用者数の伸びを同時に達成している産業の数は、産業分類が両国で異なるので厳密な比較はできないものの、米国が我が国を大きく上回っていることが見て取れる。
製造業21業種(緑色)のうち、鉄鋼、一般機械、輸送用機械、金属製品、プラスチック・ゴム製品及び食料品の6産業が、非製造業13業種(朱色)のうち、倉庫、トラック輸送、飲食・宿泊、航空輸送、卸売、小売及び医療の7産業が第一象限に位置している。他方、生産性は上昇しているが、雇用者数は減少している第四象限には製造業、非製造業合わせて13の産業が位置しているが、それらには、コンピュータ・電子機器、非鉄金属、木材製品、家具、衣服、繊維製品などの産業が含まれていることが分かる。
次に、同期間のドイツを見てみると、生産性上昇率と雇用者数成長率の関係が右肩下がりであることは我が国や米国と同様であるが、生産性の上昇と雇用者数の成長を同時に達成している第一象限に位置する産業の数は圧倒的に多い(第Ⅱ-3-1-2-10図)。その数は、産業分類が一致していないため厳密な比較はできないものの、製造業(緑色)で自動車、コンピュータ・電子・光学機器、鉄鋼製品など計12産業が、非製造業(朱色)では、プログラミング、情報サービス、映像・ビデオ・番組、楽曲制作、専門、科学、技術サービスなど6産業の計18産業が位置している。
これとは対照的に、生産性は上昇しているけれども雇用が縮小している第四象限に位置している産業の数は、鉱業のほか、通信、電気・ガス・暖房、衣服、繊維などわずか7産業である。生産性も雇用も減少している第三象限に位置する産業は存在していない。
73 生産性に関しては、本来、ここでは労働生産性ではなくTFP(全要素生産性)を、産業規模に関しては雇用者数ではなく労働時間も考慮した労働投入指数を用いるべきであるが、特にドイツについてデータの制約から2010年以降のデータが取得できない。そのため、3か国とも労働生産性及び雇用者数のデータを用いている。
②生産性と雇用の両立に不可欠な要因
ドイツのようにボーモル効果を抑制できている産業・企業は、そうではない産業・企業と比較して、どのような特徴を有しているのだろうか。生産性上昇と雇用増加を同時に達成している企業(ボーモル効果抑制企業)について分析し、生産性と雇用の両立に不可欠な要因を明らかにする。
本項①において我が国の産業において生産性と雇用の変化(第Ⅱ-3-1-2-8図)から明らかなように、ボーモル効果を抑制できている産業は米国・ドイツと比べて少なくなっている。この事実を裏付けるかのように、経済産業省が我が国のグローバル企業に対して実施したアンケート調査において、企業は、研究開発及びブランド力向上などの重点的な取組によって売上高あるいは利益の増加があったものの、それらの取組が雇用・賃金の増加に結びついていない傾向にあることが明らかになった(第Ⅱ-3-1-2-11図)。これらの企業は、ボーモル効果が発生していることになるが、我が国においても少ないながらもボーモル効果を抑制できている産業が存在しており、その産業に属する企業をボーモル効果抑制企業と呼ぶことはできる。以下では、経済産業省「企業活動基本調査」(以下、企活。)の個票データを使用したパネル・プロビット・モデル74によって、ボーモル効果抑制企業の特徴を定量的に分析する。
第Ⅱ-3-1-2-11図 企業が重視する取組が売上、雇用等の増加に繋がったか
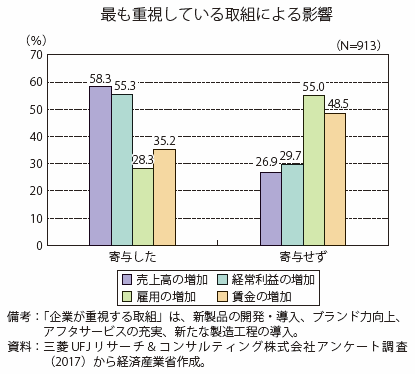
モデルの被説明変数は、各企業の労働生産性上昇率75と雇用者数成長率の組合せによる状態変数(1又は0)である。生産性と雇用者の変化の組合せが4パターンあるので76、それぞれのパターンに応じて状態変数の値を割り当てたモデルを推計している。
本分析で使用するパネル・プロビット・モデルは、状態を表す質的従属変数を、何らかの変数で説明しようという推計方法である。本推計において、質的従属変数は各企業の労働生産性上昇率77と雇用者数成長率の組合せによる状態変数(1又は0の2値変数)である。生産性と雇用者の変化(上昇・増加と低下・減少)の組合せが計4パターンあるので78、それぞれのパターンに応じて状態変数の値を割り当て、4本の推計式(モデル)を立てて、労働生産性の上昇と雇用者数の成長を同時達成するために重要となる企業属性・特性を明らかにすることを目標に推計を実施している。
質的従属変数(被説明変数)について、まず、生産性上昇・雇用増加モデル(モデル1)では、生産性上昇と雇用増加を同時達成している企業に1を割り当て、そうではない企業に0を割り当てている。このモデルは、ボーモル効果抑制企業モデルと言える。次に、生産性低下・雇用増加モデル(モデル2)では、生産性は低下しているが雇用は拡大している企業に1を割り当て、そうではない企業に0を割り当てている。さらに、生産性低下・雇用減少モデル(モデル3)では、生産性も雇用も減少させている企業に1を割り当て、そうではない企業に0を割り当てている。最後に、生産性上昇・雇用減少モデル(モデル4)では、生産性は上昇しているが雇用は減少している企業に1を割り当て、そうではない企業に0を割り当てている。このモデルは、ボーモル効果発生モデルと言える。なお、これらのモデルの番号は、第Ⅱ-3-1-2-8図から第Ⅱ-3-1-2-10図の第1象限から第4象限に対応するように付番している。
説明変数について、4モデル共通で、市場占有率、一人当たり自主研究開発費、一人当たり委託研究開発費、一人当たり無形固定資産又は一人当たりソフトウェア資産、一人当たり広告・宣伝費及び一人当たり直接輸出額を用いている。これらの説明変数は、企活個票データから抽出可能な項目の中で、生産性と雇用に関係する可能性が高いものを選択している。
まず、市場占有率は、業種別に集計した売上高の合計に占める当該企業の売上高である。市場に対する影響力の強さに関わる変数であることから、市場価格への影響や生産量の変化を通じた供給への影響によって、生産性及び雇用に効果を持つと考えられることから、説明変数に選択している。
次に、一人当たり自主研究開発費及び一人当たり委託研究開発費は、いわゆる研究開発費を企業内で実施するものと企業外で実施するものを分けて考えている。研究開発投資は生産性にプラスの効果を持つとされているが、雇用に対する効果は定かではない。ここでは、企業内での実施に伴う自主研究開発費が雇用に対してプラスの効果を持つであろうことを想定して、これらの項目を説明変数に選択している。
次に、一人当たり無形固定資産又は一人当たりソフトウェア資産は、資本収益率に対する効果が確認されており79、生産性と雇用に対する効果を予想して説明変数に加えている。なお、企活の調査項目に変更があったため、一人当たり無形固定資産は2003年から2014年まで、一人当たりソフトウェア資産は2006年から2014年までとしている。推計においては、期間を分けた上で、いずれかを説明変数に選んでいる。
次に、一人当たり広告・宣伝費は、ブランド力の代理変数として使われることが多く、企業収益に対してプラスの効果を持つと考えられることから、企業収益を通じて生産性及び雇用に対する効果もあると予想できる。
最後に、一人当たり直接輸出額は、ターゲット市場が国内に限らず海外も含んでいるという点で、生産規模の大きさを暗に意味することになるので、規模の経済性による生産性に対する効果及び規模そのものによる雇用に対する効果を持つと思われる。
上述の質的従属変数及び説明変数に企活から抽出・加工したパネルデータに基づいてパネル・プロビット・モデルによる推計を実施した結果が、第Ⅱ-3-1-2-12表である。
第Ⅱ-3-1-2-12表 企業の労働生産性、雇用者数の変化と企業属性
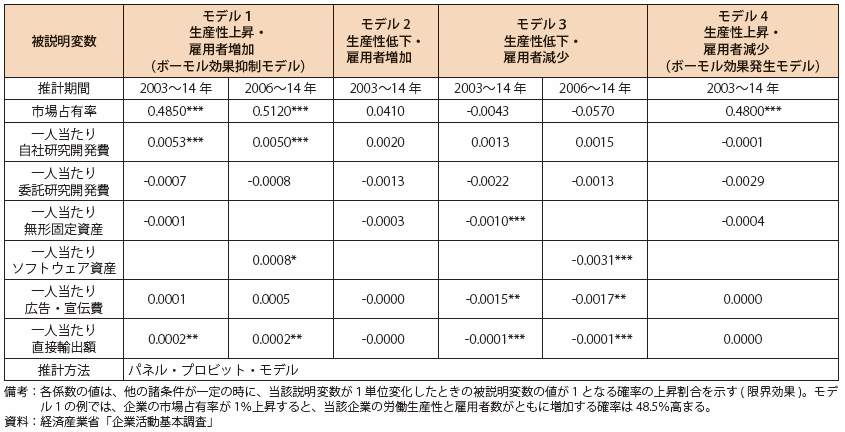
ボーモル効果抑制モデル(モデル1)の推定結果を見ると、統計的に有意な説明変数は、市場占有率、一人当たり自主研究開発費、一人当たりソフトウェア資産及び一人当たり直接輸出額となっている。2003-2014年推計では、市場占有率0.485、一人当たり自社研究開発費0.0053、及び一人当たり直接輸出額0.0002となっており、2006-2014年推計では、市場占有率0.485、一人当たり自社研究開発費0.0053、一人当たりソフトウェア資産0.0008及び一人当たり直接輸出額0.0002となっている。統計的に有意な説明変数が多い2006-2014年推計を例にして直観的な説明を加えると、ある企業の市場占有率が1%上昇すると、当該企業の労働生産性と雇用者数がともに増加する確率は51.2%高まることを意味している。
ボーモル効果抑制企業とは対照的な企業について推計したモデル3(生産性低下・雇用者減少)では、一人当たり無形固定資産、一人当たりソフトウェア資産、一人当たり広告・宣伝費及び一人当たり直接輸出額が少ない企業ほど、労働生産性と雇用者数を同時に減少させる確率が高くなることがわかる。
その他の推定結果(モデル2、モデル4)では、ボーモル効果発生モデル(モデル4)の市場占有率以外の説明変数は統計的に有意にはなっていない。労働生産性又は雇用者数のいずれか一方だけが増加している企業では、本分析で取り上げた企業属性を表す説明変数と生産性・雇用者の状態変数との関係は弱いことがわかる。
本推計には留意すべき点がある。推定結果は、対前年比の労働生産性や雇用者数成長率を算出できた既存企業についてのものである。新たに設立された企業が参入したり倒産・廃業した企業が退出したりすることが産業レベルでの生産性上昇率や雇用者数に与える影響は計測できていない。例えば、前期に存在した生産性の低い企業が、当期にある産業から退出すると、企業レベルでは前期の集計対象からも当期の集計対象からも脱落して、集計結果には影響を与えないけれども、産業レベルの集計では、退出した企業以外の企業の生産性に変化がなければ、当該産業の今期の平均的な生産性上昇率を低下させることになる。逆に、前期には存在しなかった生産性の高い企業が、今期新たにある産業に参入した場合、企業レベルでは同様に前期の集計対象からも当期の集計対象からも脱落して、集計結果には影響を与えないけれども、産業レベルの集計では、参入した企業以外の企業の生産性に変化がなければ、当該産業の今期の平均的な生産性上昇率を高めることになる。
上記推計の4モデルについて、それぞれのモデルに対応する企業のデータに基づいて産業別構成比(付表1)を算出してみると第Ⅱ-3-1-2-8図の分布とは異なる結果になることがわかる。例えば、第Ⅱ-3-1-2-8図の分布では、輸送機械産業はボーモル効果抑制産業(第一象限)に位置しているが、上記推計データによる分類では、輸送機械産業に属する企業のうち生産性も雇用も増加させている企業(ボーモル効果抑制企業)の割合はわずか18.4%である。
他方、生産性は上昇させているが雇用は減少させている企業(ボーモル効果発生企業)の割合は23.7%、生産性も雇用も減少させている企業の割合は16.2%、生産性は低下しているが雇用は増加している企業の割合は24.2%となっている。つまり、産業レベルでボーモル効果抑制産業に位置していても、企業レベルではボーモル効果抑制企業が大多数を占めているわけではないということである。
ボーモル効果抑制企業の割合が高い業種の上位は、複合サービス業33.3%、医療福祉業31.0%、鉄鋼26.7%、物品賃貸業26.7%、及び一般機械26.0%である。また、ボーモル効果発生企業の割合が高い業種の上位は、宿泊業32.3%、電気・ガス・熱供給・水道業32.28%、非鉄金属29.4%、運輸業・郵便業26.9%、及び繊維工業26.5%である。
74 北村(2005)、p. 112。
75 本推計で念頭に置いている労働生産性は、実質労働生産性のことであるが、推計にあたっては、労働生産性と雇用者数のそれぞれの増減から2値(1又は0)を設定しているので、名目値であっても実質値であっても本質的な相違は無い。ただし、増減を判断するための労働生産性は、業種別のデフレータが存在しないこと及び個別企業の価格情報としてデフレータを一律に適用できないことを考慮して、近似値として名目労働生産性を使用している。
76 いずれの企業においても変化があったので、パターンの中に変化なしを組込む必要がなかったため、4パターンとなっている。
77 本推計で念頭に置いている労働生産性は、実質労働生産性のことであるが、推計にあたっては、労働生産性と雇用者数のそれぞれの増減から2値(1又は0)を設定しているので、名目値であっても実質値であっても本質的な相違は無い。ただし、増減を判断するための労働生産性は、業種別のデフレータが存在しないこと及び個別企業の価格情報としてデフレータを一律に適用できないことを考慮して、近似値として名目労働生産性を使用している。
78 いずれの企業においても変化があったので、パターンの中に変化なしを組込む必要がなかったため、4パターンとなっている。
79 Miyagawa, et al.(2016).
3.収益力改善に向けたイノベーション環境の創出
(1)人的資本投資の改善によるイノベーション実現の促進
我が国において、産業レベル・企業レベルの収益力、生産性、及び価格決定力の向上と雇用の増加が進みにくい背景には、市場にとって新しい製品を供給するようなイノベーションを実現できず、価格競争が激しく利幅の少ない製品で利益を確保せざるを得ない状況に置かれている可能性があることは前項までの分析や先行研究で示してきたとおりである。我が国が価格決定力を向上させ、雇用増加に繋がるようなイノベーションを実現するために何が必要かについて以下で分析していく。
収益力・生産性・価格決定力の向上を図るためには、さらなるイノベーションが必要となる。OECDが公表している『オスロ・マニュアル80』に定義されているイノベーション類型に従えば、収益力などに対する各種イノベーションの作用は、第Ⅱ-3-1-3-1図のように対応づけられるだろう。
第Ⅱ-3-1-3-1図 収益力・生産性・価格決定力とイノベーション類型の対応
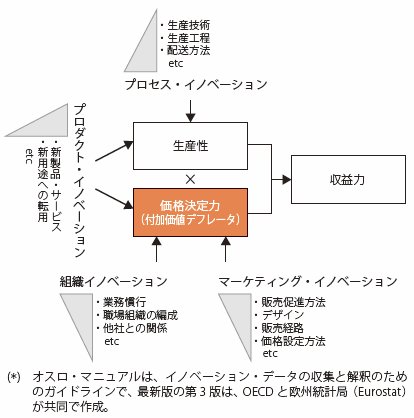
経済産業省が行ったアンケート調査によれば、我が国企業は最も重要な取組として、市場にとって画期的な製品やサービスの開発や導入を挙げており、イノベーションが収益力、生産性、価格決定力にとって重要なものであることは認識しているものの(第Ⅱ-3-1-3-2図)、文部科学省科学技術・学術政策研究所が実施した「第4回全国イノベーション調査統計報告」によれば、日本のイノベーション実現状況はイノベーション類型のいずれにおいても先進諸国と比較して低い値となっている81(第Ⅱ-3-1-3-3図)。
第Ⅱ-3-1-3-2図 企業が重視している取組
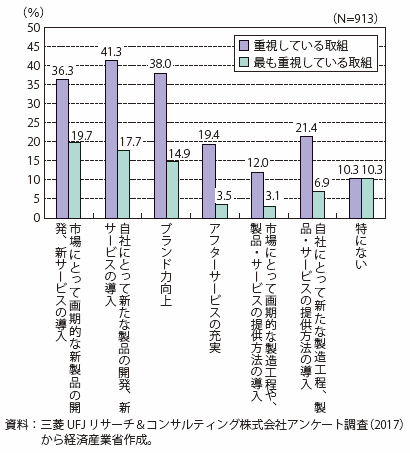
第Ⅱ-3-1-3-3図 4つのイノベーションのいずれかを実現したと回答した企業の割合
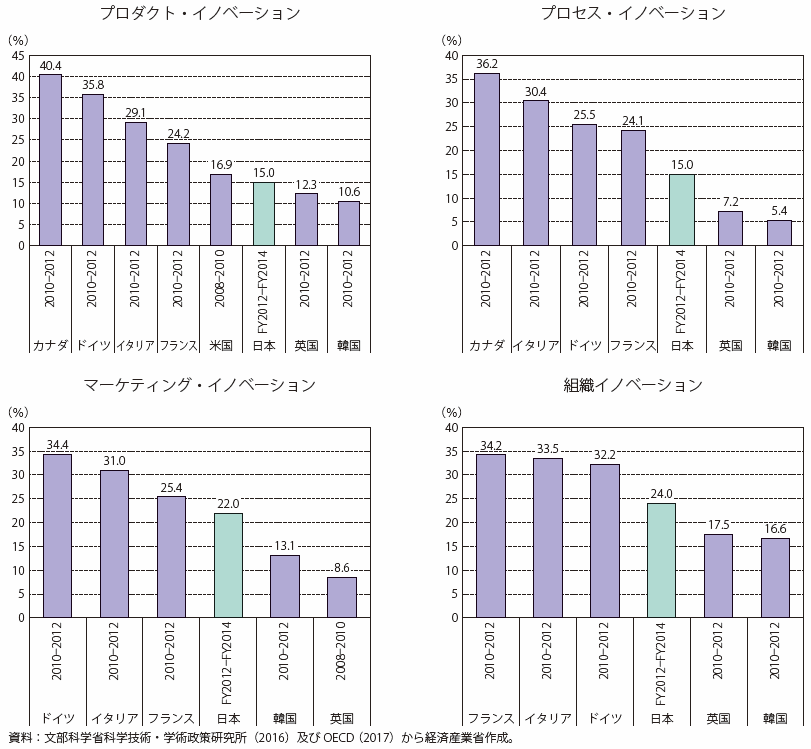
- Excel形式のファイル(プロダクト・イノベーション)はこちら

- Excel形式のファイル(プロセス・イノベーション)はこちら

- Excel形式のファイル(マーケティング・イノベーション)はこちら

- Excel形式のファイル(組織イノベーション)はこちら

我が国のイノベーションの現状と課題として、産業構造審議会研究開発・イノベーション小委員会は、①顧客価値の獲得に関する環境変化への対応の遅れ、②自前主義に陥っている研究開発投資、③企業における短期主義、④人材や資金の流動性の低さ、⑤グローバルネットワークからの孤立を挙げている。近年、グローバル化、市場ニーズの多様化、新興国の台頭を背景として、製品ライフサイクルの短期化や企業間競争が激化しており82、企業がイノベーションを加速させていくためには、社外との適切な連携を通じたオープン・イノベーションを推進していく必要性が高まっている。
今後は、プロダクト・イノベーションを担う高度人材の育成・確保とともに、自社内の技術に留まらず、広く他の企業、大学、研究機関等とのネットワークを活用したオープン・イノベーションによる技術開発への転換が求められる。
雇用流動化の高まりや非正規雇用の社員が増える中、企業内教育へのインセンティブは低下しており、高度人材の育成を巡り私的利益と社会的利益の乖離が生じているとの指摘もある83。実際に我が国企業の人材育成のための投資額及び無形資産投資全体に占める人材育成投資の割合は、国際的に見ても低い水準にあるといえる(第Ⅱ-3-1-3-4図及び同5図)。
第Ⅱ-3-1-3-4図 人的資本投資と研究開発等に関する国際比較(2000年→2010年)
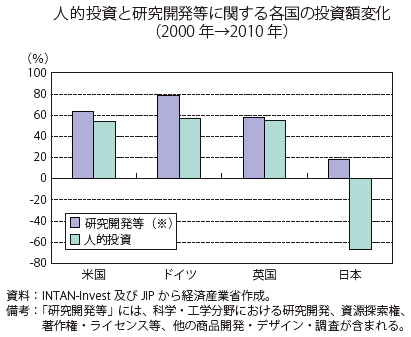
第Ⅱ-3-1-3-5図 人的資本投資の国際比較
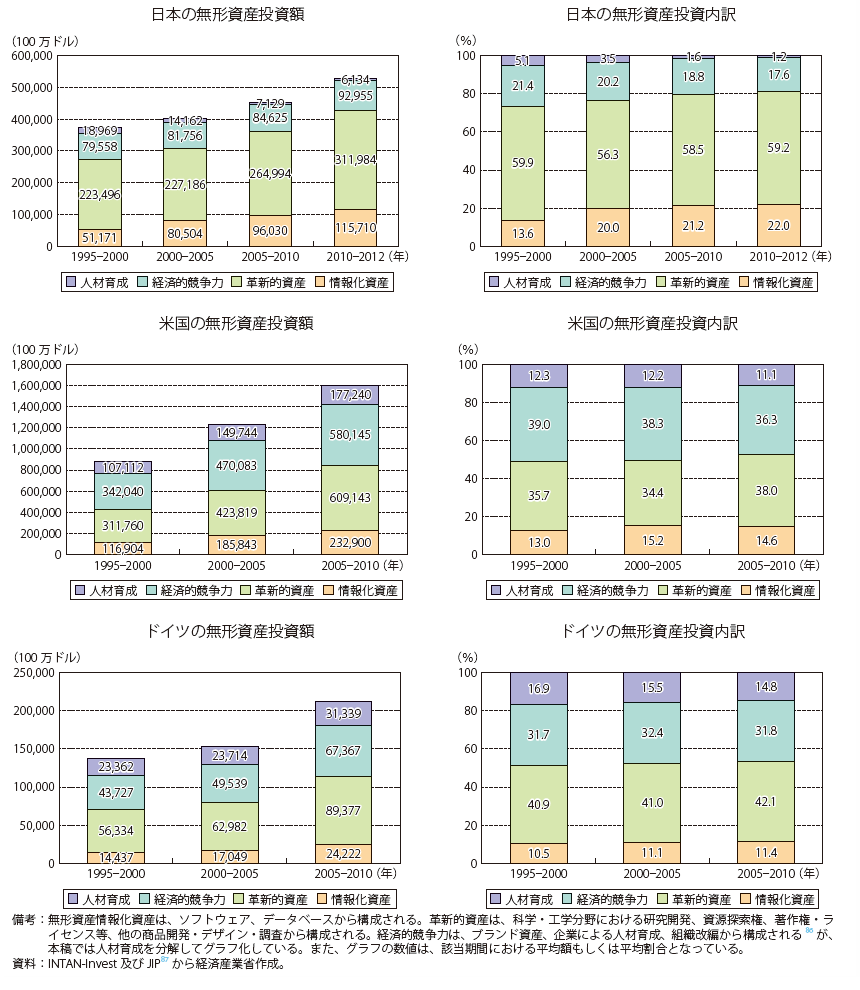
- Excel形式のファイル(日本の無形資産投資額)はこちら

- Excel形式のファイル(日本の無形資産投資内訳)はこちら

- Excel形式のファイル(米国の無形資産投資額)はこちら

- Excel形式のファイル(米国の無形資産投資内訳)はこちら

- Excel形式のファイル(ドイツの無形資産投資額)はこちら

- Excel形式のファイル(ドイツの無形資産投資内訳)はこちら

さらに、我が国企業における人材育成投資84は、バブル経済崩壊直後の1991年をピークに減少に転じ、1990年代後半に一時的な増加を見せた後は、2000年代を通じて大幅な減少を続けている(第Ⅱ-3-1-3-6図)。また、企業における定型的な業務を非正規雇用労働者が担うようになったことにより、企業内教育のインセンティブが低下した可能性がある。
第Ⅱ-3-1-3-6図 我が国企業の人材育成投資額の推移
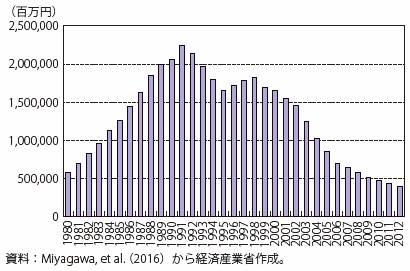
また、国際的なアンケート調査によって、我が国グローバル企業の人的資源への投資傾向を海外のグローバル企業と比較してみると、今後1年間で自社の人的資源への投資額を増やす予定があると答えた企業は「大幅に増加」と「増加」を合わせて63%と、調査対象国中もっとも低くなっている(第Ⅱ-3-1-3-7図)。
第Ⅱ-3-1-3-7図 人材育成投資の国際比較
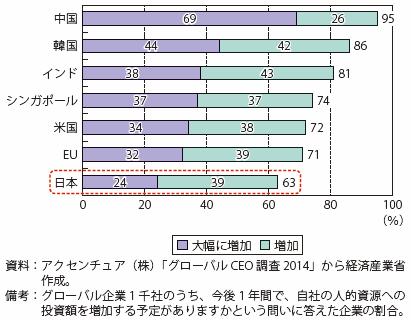
今後も人材育成投資が下がり続けた場合に、我が国の経済成長にどのような影響があるかを考えてみる。我が国では資本投入が低迷を続けた結果、資本蓄積を示す指標である資本係数(資本ストック/実質GDP)が2000年代に入ってほとんど上昇していない。
そして、この資本蓄積低迷の原因の一つは、バブル経済崩壊後の我が国の資本収益率(営業利益/資本ストック)の傾向的低下であるとする指摘がある85(第Ⅱ-3-1-3-8図)。
第Ⅱ-3-1-3-8図 資本収益率の低下と資本蓄積(資本係数)の低迷
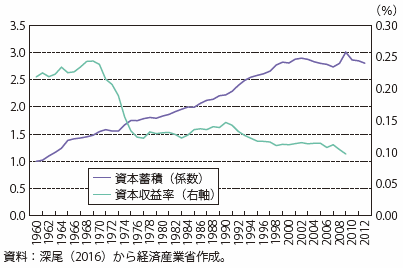
この資本収益率低下の要因について、前掲出のMiyagawa, et al. (2016)では、資本の限界収益率を被説明変数とし、実質賃金、IT投資、研究開発投資及び人材育成投資88などを説明変数とする要素価格フロンティアモデルを構築して推計を行っている。
推計結果をみると、人材育成投資に係る係数は正で有意となっており、その値も0.361(モデルa)、0.205(モデルb)と相対的に大きな値を示している。企業における人材育成投資が資本収益率の増加に対し、ひいては資本蓄積(設備投資)の増大に対し、重要な役割を果たしていることが確認できる89(第Ⅱ-3-1-3-9表)。すなわち、我が国の人材育成投資が低い水準のまま推移していけば、資本収益率の上昇や設備投資の増加がさらに困難になる畏れが生じる可能性もある。
第Ⅱ-3-1-3-9表 資本収益率の変動要因に係る推計結果
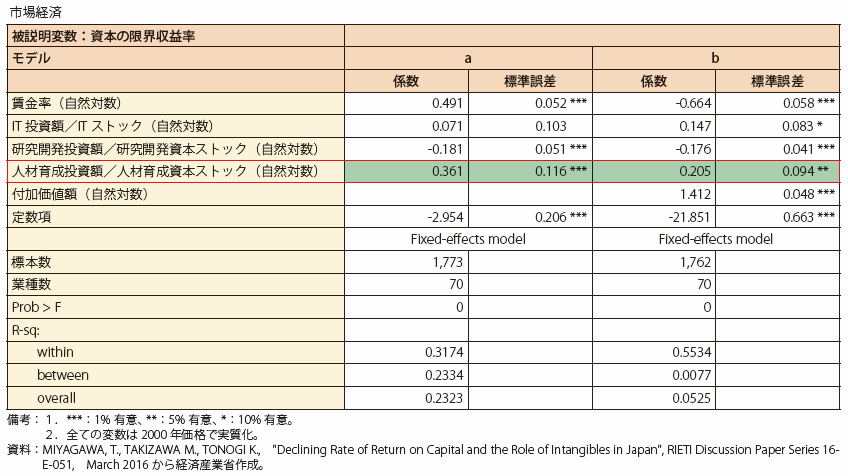
80 OECD (2005).
81 文部科学省科学技術・学術政策研究所(2016)では、調査方法は各国間で完全に統一されておらず、各国特有の回答性向が存在するため、国際比較可能性には限界があるとしている。
82 経済産業省産業構造審議会産業技術環境分科会研究開発・イノベーション小委員会(2016)。
83 日本経済新聞、2016年9月21日、朝刊26面。
84 ここでの人材育成投資額は第Ⅱ-2-7表において推計した人材育成投資額を用いている。
85 例えば、Miyagawa, et al.(2016)を参照。また、資本収益率と資本蓄積の関係については、田中・宮川(2011)を参照。
86 宮川・浅羽・細野編(2016)。
87 日本の人材投資については、JIPデータベースのうち、学習院大学宮川教授の推計担当分を使用。
88 ここでの人材育成投資額は、厚生労働省「就労条件総合調査」などを使って推計した産業ごとの職場外研修費用を用いている。なお、IT投資額、研究開発投資額及び人材育成投資額推計の詳細については、Chun, et al.(2015)を参照。
89 Miyagawa, et al.(2016)では、併せて資本の平均収益率を用いた推計も行っているが、推計結果は大きくは変わっていない。
(2)まとめ
我が国のグローバル企業における収益力の改善が指摘され続けてきている中にあって、収益力向上と経済成長の両立を表す指標として、付加価値に着目して、生産性(実質付加価値)と価格決定力(付加価値デフレータ)を用いた分析結果を示した。また、アンケートなどから、我が国のグローバル企業は高い生産性を示しているにもかかわらず、価格決定力に不安を抱えていることが明らかになった。
現状の課題として、価格決定力の脆弱性、生産性上昇と雇用縮小の同時発生への対処、及び資本収益率と人材投資の低迷を指摘した。まず、付加価値デフレータ(価格決定力)の低下が生産性の上昇を相殺して、収益力を押し下げる要因になっていることを、概念整理とデータから示した。この事実は、生産性の改善とともに価格決定力の強化が収益力の改善に向けて重要であることを示している。また、生産性の上昇とともに雇用が減少するボーモル効果が表れていない、すなわち生産性上昇と雇用拡大を同時に実現している企業群の特徴を、企業活動基本調査に基づくパネル・プロビット・モデル推計から、市場占有率並びに従業員一人当たりの自主研究開発費、ソフトウェア資産及び直接輸出額の高さであることを明らかにした。生産性上昇とともに雇用拡大に注目している理由は、企業の付加価値に対する人件費(雇用)の割合が大きいだけでなく、経済全体では雇用確保・失業率低下などに結び付くためである。さらに、資本収益率が低迷を続けている状況にあって、傾向的低下を示している人材育成投資が、その変化に対してプラスの効果を持っていることが明らかになった変動要因推計からは、人材育成投資の減少を反転・増加させることが収益力の改善に向けた一助となり得ることが示唆される。
ここまでの分析結果をまとめると、我が国企業は、生産性の上昇に注目するだけではなく、価格決定力の強化にも注目して収益力の向上を図る必要があると考えられる。また、収益力を向上させるためには人材育成投資を拡大し、イノベーションを実現していくことが有効であるが、我が国の人材育成投資は米国及びドイツと比較して低い水準に留まっているのみならず、投資額も近年では減少傾向にあるため、現状ではイノベーションの実現で他国に遅れをとり、将来的には収益力向上を実現できず、グローバルな市場でビジネスを主導できない可能性もでてくる。
今後、我が国企業の収益力を高め、雇用を拡大し、経済成長を実現するためには、人的資本投資を強化し、イノベーションを実現し、過当競争に巻き込まれない価格決定力の高い差別化された製品・サービスで、国内市場に留まらずグローバルな市場を開拓していくことが重要である。そして、企業収益力の改善を経済成長に結び付けるために、ボーモル効果を抑制して生産性向上・雇用拡大に効果が認められた研究開発などへの投資や輸出の促進が必要となる。
