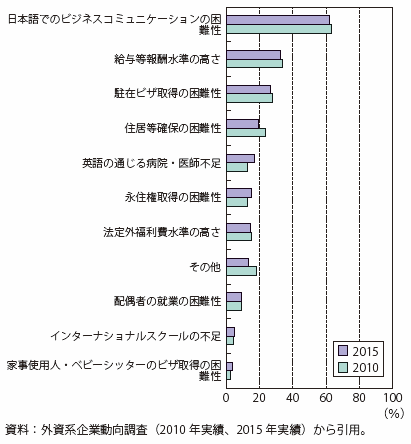第2節 我が国のイノベーションの創出に向けた課題
1.我が国のイノベーション能力に関する国際的な評価
世界経済フォーラム(WEF)が毎年発表している国際競争力指標によれば、日本のイノベーションランキングは2016-2017年版の報告書では、2015-2016年版の5位から順位を下げて8位となっている。「企業の研究開発投資」、「科学者・技術者の有用性」及び「特許協力条約に基づいた特許申請」では高い順位となっている一方、「イノベーション能力」及び「研究開発における産学連携」が上位10か国と比較して低い順位となっている(第Ⅱ-3-2-1-1表)。
「イノベーション能力」の指標が低い理由については、以前は企業に対して「自前の研究開発能力」が問われていたが、2013-2014年版以降は、「イノベーション能力の保有」が問われるように変更されたことの影響が指摘されるとともに、日本の企業経営者の自国への評価が低下した可能性や、研究開発の成果を社会的価値につなげる力やオープン・イノベーションに対する日本の弱みが示された可能性があるとも指摘されている90。
我が国のイノベーションの課題としては、①顧客価値の獲得に関する環境変化への対応の遅れ、②自前主義に陥っている研究開発投資、③企業における短期主義、④人材や資金の流動性の低さ、⑤グローバルネットワークからの孤立が挙げられており、これらの課題を解決し、イノベーション創出をしていくためには、オープン・イノベーションの推進が重要だとされているが、自社単独のみで研究開発する企業の割合は61%となっており、半数以上の企業で10年前と比較してオープン・イノベーションが活性化していないとの分析もされている91。このことは、第Ⅱ-3-2-1図において「研究開発における産学連携」の順位が相対的に低いことにも表れていると考えられる。
第Ⅱ-3-2-1-1表 WEFイノベーションランキング2016-2017年版
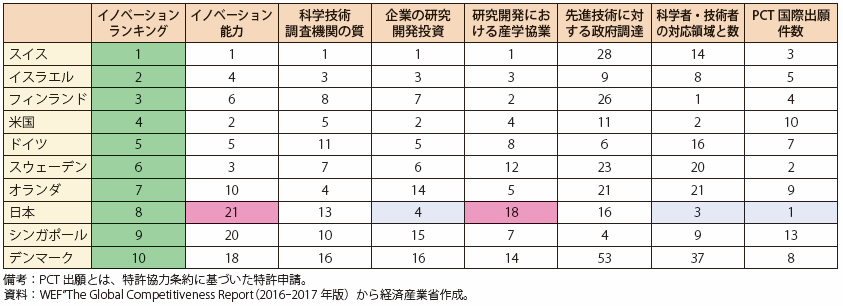
90 内閣府(2017)「世界経済フォーラム(WEF)国際競争⼒レポートにおけるイノベーションランキングの現状の分析について」、矢野(2016)「国際競争力後退の要因は何か」みずほ総合研究所
91 産業構造審議会 産業技術環境分科会 研究開発・イノベーション小委員会(2016)「イノベーションを推進するための取組について」
2.イノベーションを生み出す新たな産業社会の実現に向けた3つの課題
これまで蒸気機関の発明から動力を獲得した第1次産業革命、電力・モーターによる動力が革新した第2次産業革命、コンピュータの発明・発展による自動化が進む第3次産業革命に続き、我々は大量の情報を基に人工知能が自ら考えて最適な行動を取ることが可能となる第4次産業革命を迎えている。この第4次産業革命により、①実社会のあらゆる事業・情報が、データ化・ネットワークを通じて自由にやりとりが可能になる(IoT)、②集まった大量のデータを分析し、新たな価値を生む形で利用可能になる(ビッグデータ)、③機械が自ら学習し、人間を越える高度な判断が可能となる(人口知能(AI))、そして④多様かつ複雑な作業についても自動化が可能となる(ロボット)。こうした一連の変化が同時期に生じることでこれまで実現不可能と思われていた社会の実現が可能になるが、同時に産業構造や就業構造が劇的に変わる可能性もある。
こうした技術のブレークスルーは、①これまでの大量生産・画一的サービスから、個々のニーズに合わせたカスタマイズ生産・サービスへのシフト(例、個別化医療や即時オーダーメイド服、各人の理解度に合わせた教育)、②社会に眠っている資産と個々のニーズをコストゼロでマッチング(例、UberやAirbnb等のシェアリングエコノミーサービス)、③人間の役割、認識・学習機能のサポートや代替(例、自動走行、ドローンによる施工管理・配送)、④新たなサービスの創出、製品やモノのサービス化、データ共有によるサプライチェーン全体での効率性の飛躍的向上を可能とするなど、第4次産業革命の技術は全ての産業における革新のための共通の基盤技術であり、様々な分野における技術革新・ビジネスモデルと結びつくことで、全く新しいニーズの充足が可能になる。
さらに、こうした様々なものがつながることで新たな付加価値が創出され、従来独立・対立関係にあったものが融合し、変化することで、サイバー空間とフィジカル空間が高度に融合し、人々が快適で活力に満ちた質の高い生活を送ることのできる、人間中心の超スマート社会、「Society 5.0」の実現が期待される。
これらの第四次産業革命という技術革新をきっかけとする革命を、最終的な未来社会像であるSociety 5.0へとつなげていくためには、産業のあり方を変革していく必要がある。平成29年3月に開催されたドイツ見本市(CeBIT)では、我が国が目指すべき産業の在り方として新たに「Connected Industries」の概念を世界に向けて発信した。「Connected Industries」とは、データ、技術、人、組織等が様々なもの・ことのつながりによって新たな付加価値創出と社会課題解決がもたらされるような産業のあり方であり、その概念図が第Ⅱ-3-2-2-1図となる。
第Ⅱ-3-2-2-1図 Connected Industries
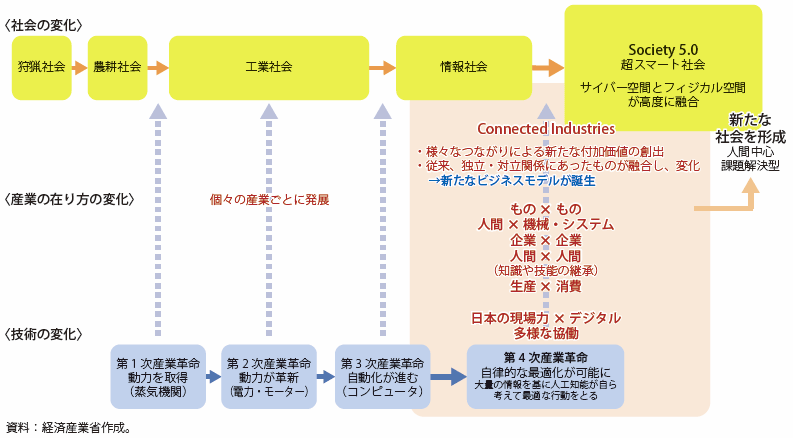
こうした新たな産業社会の実現に向けて、通商政策の観点からは、大きく分けて以下の3つの課題がある。1つ目は第4次産業革命の中で個人がより人材としての能力・スキルを絶え間なく向上させていくこと、人的投資を個人レベル、企業レベルさらに社会レベルでのシステムを構築していく必要がある。2つ目は個人と個人、企業と企業あるいは産業と産業間の交流を促進してイノベーション創出力を高めるためにオープンイノベーションに向けた取組が重要となってくる。さらに3つ目として、より高度な知識・経験を持った人材や企業を日本国内に取り組むため、内なる国際化として高度人材の受入や対内直接投資拡大もさらに進めていく必要がある。以降、それぞれの課題についてふれていきたい。
(1)人的投資の現状と課題
技術革新から社会まで含めた変化が見込まれる中、こうした変化に対応していくためには当然ながら人材・雇用面でも大きな変化が求められてくる。
目指すべき将来像としては以下が考えられる。
まず、個人に注目すれば、付加価値の源泉の変化に対応し、「人生100年時代」に能力・スキルを生涯アップデートし続け、ひとりひとりがプロフェッショナルとしての価値を身につける必要が出てくる。その前提として、市場環境やライフステージの変化に対応しつつ、常に自身のキャリアをリデザインし続ける「キャリア・オーナーシップ」を持つことが求められる。
企業の側から見れば、競争力のコアが「知の源泉たる人材」に移行したとの認識に立ち、多様な能力・スキルを持った人材を惹き付け、プロジェクト・ベースで付加価値を生み出すシステムを企業活動の中心に据えることが求められる。そのためには、人材のニーズに応じて時間・場所・契約形態等にとらわれない柔軟かつ多様な「働き方」を取り入れるとともに、職務内容を明確化し、「仕事の内容」や「成果」に応じた評価・処遇を徹底する必要があろう。
さらに社会全体として、「知の源泉たる人材」を獲得・育成・最適配置するエコシステムを、国全体として構築していく必要がある。企業が人材教育や保障の多くを提供していた時代が現実には過去のものとなる中、第4次産業革命やグローバリゼーションの影の側面を最小化させるためにも、社会保障制度等の社会システムの刷新も必要となる。
こうした時代の変化に適応した人材を創出・育成していくために必要な施策については、第3部で紹介することとし、本節では、人材投資に関する現状と課題及び全体戦略について概観したい。
①人材投資・人材育成の抜本拡充
前節では、我が国のグローバル企業は高い生産性を示しているにもかかわらず、価格決定力に不安を抱えていることが明らかになったが、収益力の改善のためには、生産性の上昇に注目するだけではなく、価格決定力の強化にも注目・対応する必要があると考えられ、また、人材育成投資の減少を反転・増加させることが収益力の改善につながることも指摘している。
企業にとって人材確保から人材教育への人的資本投資の流れが、イノベーションを創出し、それが生産性上昇と価格決定力強化を通じて、収益力改善に結びつくことが期待されている。
人材確保や人材教育を考える際、第4次産業革命下で求められる人材像(能力・スキル)や人材需給の把握・見える化を進めていくことが政策の柱となる。
とりわけ重要となるITやデータを扱うスキルについては、経済産業省の委託で実施した「IT人材最新動向と将来設計に関する調査結果」によれば、IT人材の人材不足は今後ますます深刻になると予測されている。IT人材全体として2030年に約59万人(中位シナリオ)が不足、最大約79万人(高位シナリオ)まで不足するとの調査結果が出ている(第Ⅱ-3-2-2-2図)。
第Ⅱ-3-2-2-2図 IT人材不足の推測
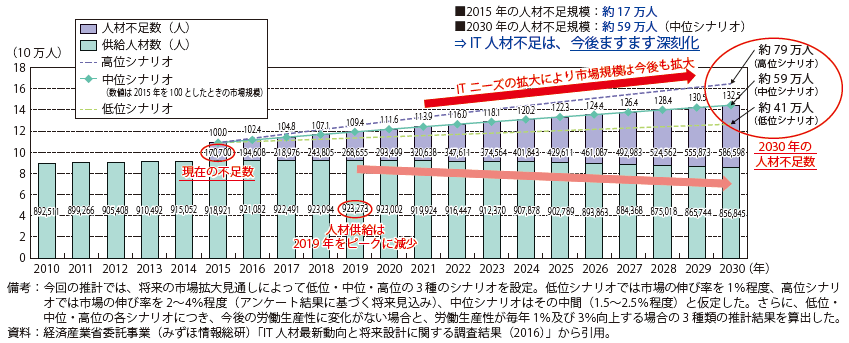
さらに、第4次産業革命下では、人工知能、ビッグデータ、ロボットやIoTの専門家が重要となることから、こうした先端IT人材についても2020年までに約5万人が不足するとの推計が出されている(第Ⅱ-3-2-2-3図)。
第Ⅱ-3-2-2-3図 先端IT人材不足数の推測
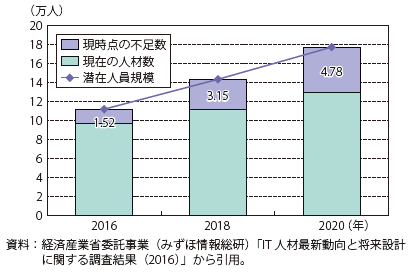
他方、同じ調査では、「新しい技術を活用して業績や顧客満足度の向上を目指す、顧客志向の先端的なIT投資(またはIT利活用)」(以上、「攻めのIT投資」と定義)の重要性は広く認識されているものの、実際に「攻めのIT投資」を実現できていると回答している企業は半分程度しかいないとしている。また、「攻めのIT投資」を促進する人材については8割を越える回答者が「大幅に不足している」「やや不足している」と回答し、「攻めのIT人材」の不足が深刻であることが明らかになっている。
さらに、「攻めのIT人材」を確保、育成していくためには、各社のIT人材の個人のスキルアップが重要となってくるものの、日本のIT人材は、会社の教育・研修制度や自己研鑽支援制度に対する満足度が、国際的に比較した場合、満足度がかなり低いようだ(第Ⅱ-3-2-2-4図)。加えて給与・報酬に対しても同様に満足度は低いとの回答が多い(第Ⅱ-3-2-2-5図)。
第Ⅱ-3-2-2-4図 会社の教育・研修制度や自己研鑽支援制度に対する満足度
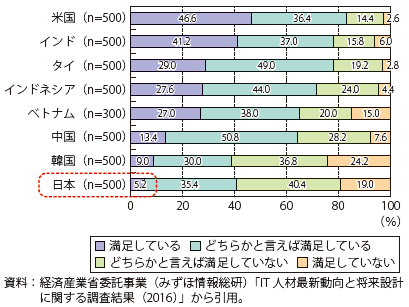
第Ⅱ-3-2-2-5図 給与・報酬に対する満足度
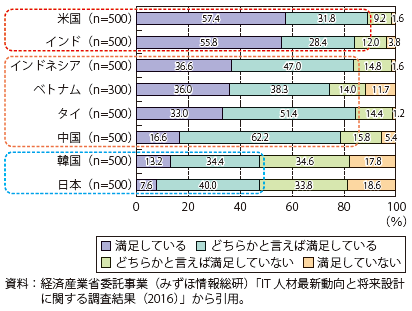
②柔軟かつ多様な働き方の実現
第4次産業革命の下で量・質の両面にわたっていかに人材を確保・育成していくかが鍵となるところ、終身雇用、職務無限定、年功序列、メンバーシップ型といった特徴を有するとされる「旧来の日本型雇用システム」について、職務内容を明確化し、それを達成するためのスキル・コンピテンシーを強化することができるシステムへと進化させ、労働時間や在勤年数による評価だけでなく、成果に基づく評価を重視し、時間、場所、契約にとらわれない柔軟な働き方を促進するとともに、自ら転職・再就職しやすい環境を整備していくことが重要となってくる。
(2)オープンイノベーションの現状と課題
ヘンリー・チェスブロウ92准教授によると、イノベーションを起こすためには、企業は海外も含めた大学や他企業との連携を積極的に活用することが有効であるとされている。我が国では、特に海外からの資金や人材の交流が少ないことから、これらの交流を増やしつつ、企業・大学・ベンチャー企業等、各プレイヤーが連携して付加価値を創出するためのオープンイノベーションを推進して行き、様々なつながりにより新たな付加価値が創出される産業である「Connected Industries」を実現して行くことが重要である。ここでは、特に我が国の研究面における他国との交流について、近年急速に共同研究が増えつつある中国と比較して分析していく。
92 ハーバード・ビジネス・スクールの助教授で、オープンイノベーションの提唱者。
①我が国の研究者の国際的なネットワークにおける課題
2003年から2013年にかけて、世界全体で国際共著論文が大きく増えている。我が国の共著関係の伸びは相対的に少ない(第Ⅱ-3-2-2-6図)。それに対して中国は2003年から2013年にかけて科学論文数も共著関係も大幅に伸びており、それ以外のドイツ、英国等の先進国においても伸びが見られ、日本はこれらの国と比較して遅れを取っている。
また、共同特許件数の推移で見ても中国は欧米との共同研究を大幅に増やしていく中、日本は減少している(第Ⅱ-3-2-2-7図)。我が国は、2000年は欧州、米国との共同特許件数はそれぞれ353件、227件であったが、2014年にはそれぞれ204件、208件と減少している。それに対して、中国では2000年は欧州、米国との共同特許件数が40件、24件であったのが、2014年にはそれぞれ442件、308件となっており、10倍以上にまで成長している。国際特許の件数で見ても、日本は欧米中で比較した場合に唯一減少している国である。
第Ⅱ-3-2-2-6図 世界の研究者の国際ネットワーク(共著関係)
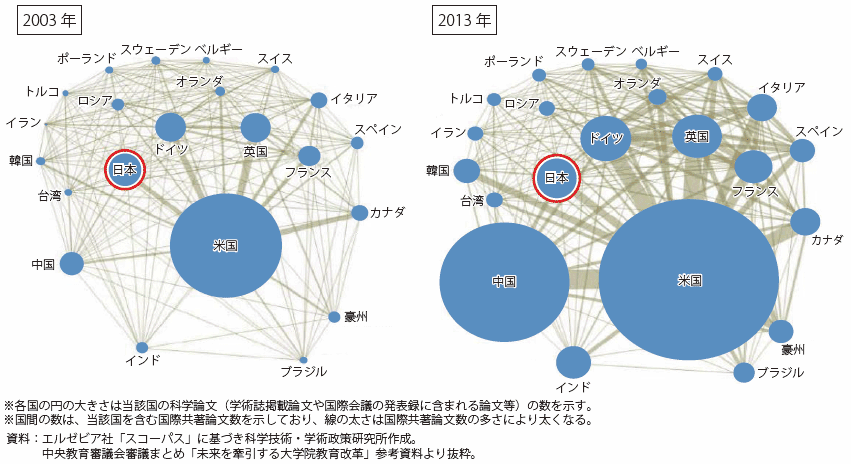
第Ⅱ-3-2-2-7図 2000年と2014年における国際特許件数とそのうちの共同特許件数
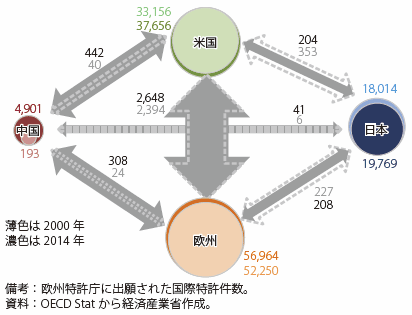
日米欧の間だけでなく、全世界との共同特許件数でみても、中国は2008年には我が国を抜いており、既に我が国よりも2倍程度多い。それに対して日本は他の先進国が1999年と比較して伸びているのに対して下がっている(第Ⅱ-3-2-2-8図)。
第Ⅱ-3-2-2-8図 共同特許件数(件数)
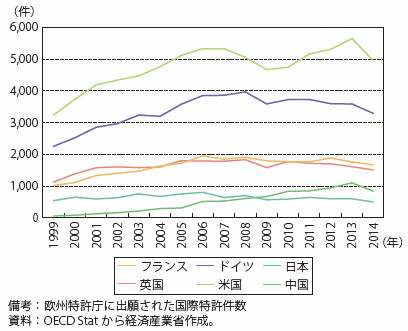
②中国における国際共同研究の成長とその要因
中国が急速に共同研究を伸ばしている理由の一つとしては、留学生の存在が挙げられる。米国等に留学した中国人は帰国後も引き続き、留学をしてきた国との共同研究を行うことがあり、これによって中国は急速に共同研究を伸ばしてきたことが考えられる93。
実際にグラフで見ても、中国の急速な共同研究の伸びは留学生の伸びと関連性があるように見受けられる(第Ⅱ-3-2-2-9図)。以下の上図は2000年から2014年にかけての日中における米国への留学生数と共同特許件数を推移で示したものである。
第Ⅱ-3-2-2-9図 米中の米国への留学生数と共同特許件数の推移
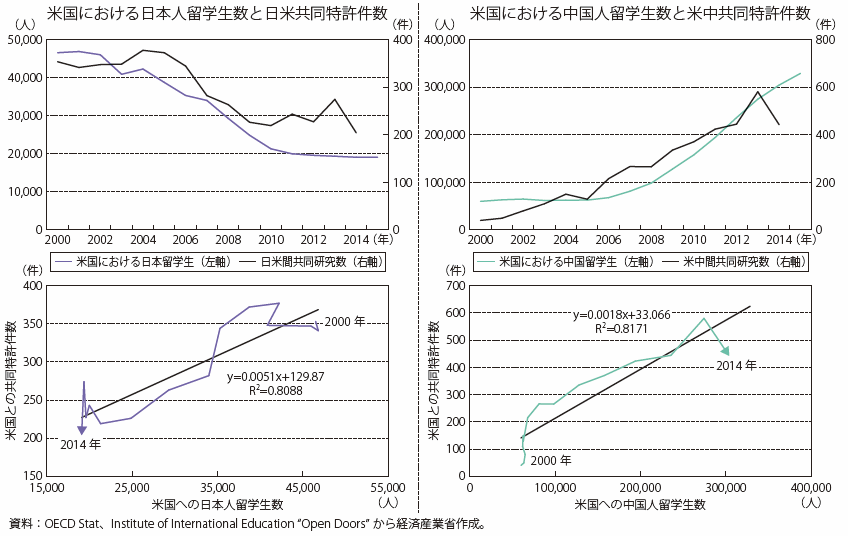
これを見ると、日本は米国への留学生数及び共同特許件数が同じ2000年から2010年にかけて両方とも同じような傾向で下落していることが分かる。同様に中国においては、留学生数が急増しているのに従って共同特許件数も増加傾向となっている。
下方のグラフに関しては、中国と日本で横軸を米国への留学生数、縦軸を米国との共同特許件数にして、時系列での推移をみたものである。これを見ると、日本は2000年から2014年にかけて、留学生数が減ると共に共同特許件数も減少していることが分かる。また中国は日本とは逆に、2000年から2014年にかけて、留学生数も共同特許件数も上昇している。さらに、中国人留学生の帰国比率が2005年の29.5%から2016年には79.4%と大幅に増加している。単純な人数の増加等も寄与しうるため、一概には言えないが、少なくとも留学生数と共同研究に関しては一定程度の関連があることが推測される。
第Ⅱ-3-2-2-10図 中国人留学生の出国者数と帰国者数の推移
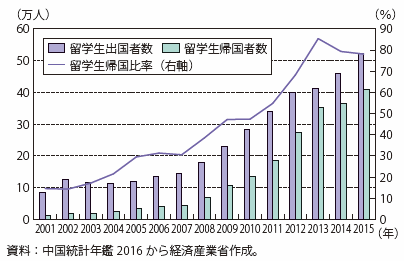
93 アナリー・サクセニアン「最新・経済地理学」(2008)
(3)内なる国際化の現状と課題
我が国が更なるイノベーションを促進させていくためには、前述したとおり人材投資(第1節で説明)や内なる国際化(高度外国人材受入れや対内直接投資の増加)を推進していくことによって、企業間や企業と大学との交流が国内だけに留まらず海外とも積極的に行われていくことが重要である。ここでは、我が国が抱えている高度外国人材の流入に関する現状と課題について述べた後に、対内直接投資に関しても言及していく。
①高度外国人材をめぐる現状と課題
まず高度外国人材について述べていくと、研究者は過去15年間で約8,700人が流出しており、研究者が1万人近く流入した米国や中国とは大きな差がある(第Ⅱ-3-2-2-11図)。この理由の一つとして、外国人材の日本の職場に対する否定的な見方が考えられる。日本への留学生・元留学生による日本への評価によれば、約83%が日本で住むことについては魅力的であると評価しているが、日本で働くことに対しては約51%が否定的な評価を下している(第Ⅱ-3-2-2-12図)。
第Ⅱ-3-2-2-11図 1999年~2013年の研究者の流出入数
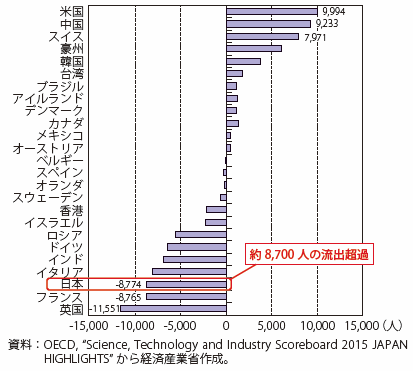
第Ⅱ-3-2-2-12図 日本への留学生・元留学生による、日本の生活及び就労魅力度の評価
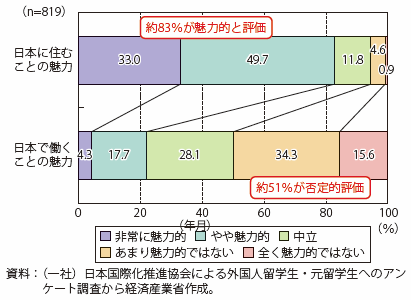
日本企業に対して外国人材からは、キャリアパスの明示、昇進・昇格の期間短縮、能力や成果に応じた評価に関する要望が多いため、これらを改善していくことが重要である(第Ⅱ-3-2-2-13図)。
第Ⅱ-3-2-2-13図 外国人材の定着のために日本企業が取り組むべきこと
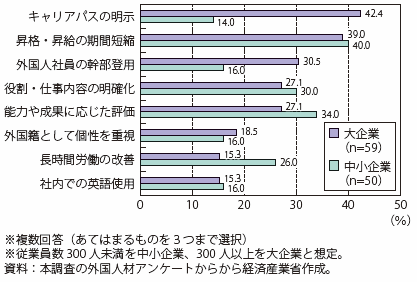
②対内直接投資における現状と課題
次に、対内直接投資に関して述べていくと、第2章第2節で述べたとおり、我が国は対内直接投資が他の先進国と比較すると非常に低い値で推移している。他方で、研究開発拠点の投資先としては、近年魅力が急速に上がってきている(第Ⅱ-3-2-2-14図)。この理由としては、インフラが整備されていることや市場としての魅力が挙げられている(第Ⅱ-3-2-2-15図)。
第Ⅱ-3-2-2-14図 外国企業から見てビジネス拠点タイプ別の投資先として最も魅力的なアジアの国・地域
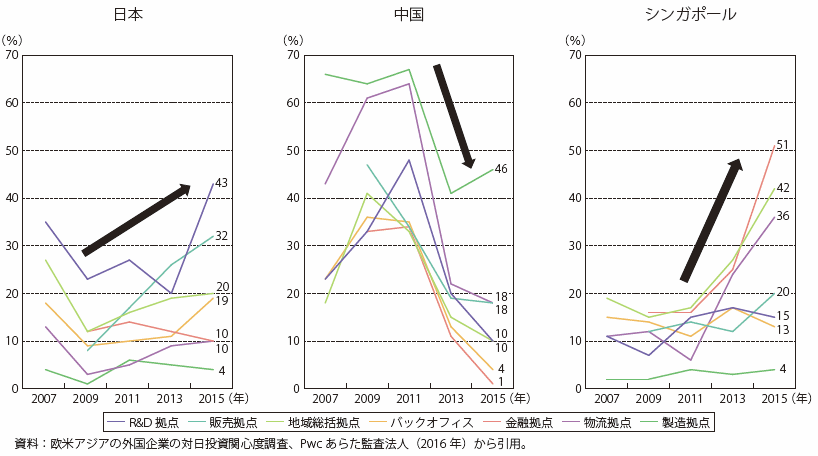
第Ⅱ-3-2-2-15図 日本で事業展開する上での魅力(合計)
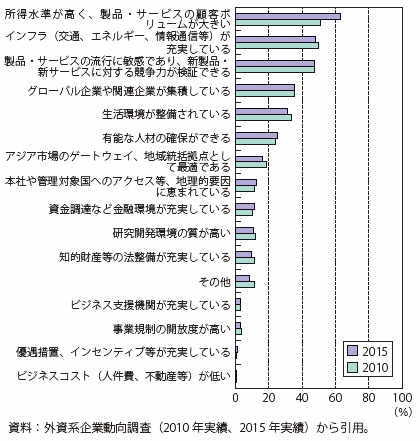
他方で、その他の魅力については依然として低い状態である。この理由として、突出して高いのはビジネスコストの高さである。2010年と2015年を比較した場合でも数%上昇しており、我が国のビジネスコストは海外企業が直接投資をする際の阻害要因になっていることが分かる(第Ⅱ-3-2-2-16図)。また、ビジネスコストの内訳を見ていくと、人件費、税負担、事務所賃料の3つがメインであることが分かる。今後とも海外からの直接投資を増やしていくためには、外国企業が直面するビジネス上の課題の改善を行っていくことが重要である(第Ⅱ-3-2-2-17図)。
第Ⅱ-3-2-2-16図 日本で事業展開する上での阻害要因(合計)
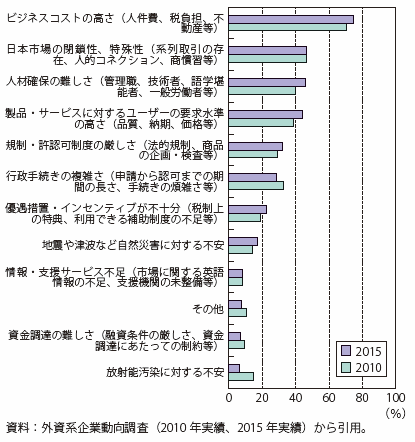
第Ⅱ-3-2-2-17図 日本のビジネス(事業活動)コストにおける阻害要因
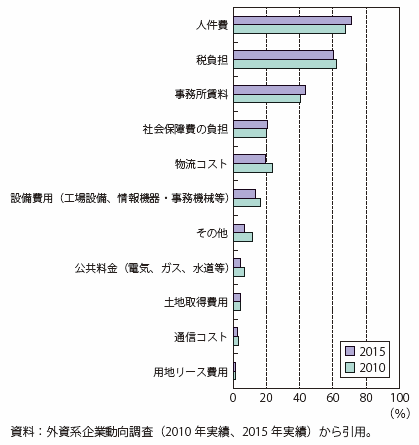
また人材雇用面としては、外国人の雇用と日本人の雇用の両方の面においてコミュニケーションの困難性や給与水準の高さが阻害要因となっており、その他にも日本人材に関しては労働市場の流動性に欠けること、外国人材に関しては在留資格取得の難しさが挙げられている(第Ⅱ-3-2-2-18図、第Ⅱ-3-2-2-19図)。
第Ⅱ-3-2-2-18図 日本人の人材を確保する上での阻害要因
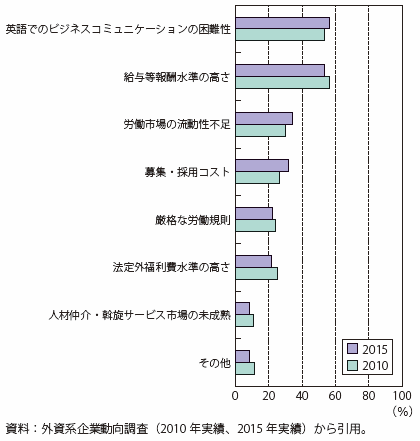
第Ⅱ-3-2-2-19図 外国人を雇用する上での阻害要因