第1節 ローカル中堅中小企業のGVCへの繋がり強化
1.日本の企業規模別直接輸出
(1)概況
中堅・中小企業の直接輸出額は、新興国経済の拡大等を背景に2000年代前半に大きく増加した(第Ⅱ-4-1-1-1図)94。2008年の世界経済危機により一旦落ち込んだものの、世界経済の回復等を背景に、2014年にかけて再び増加している。年間百万円以上輸出する企業について見ると、企業数は緩やかに増加し、1社あたり輸出額は企業数以上に伸びていることが分かる(第Ⅱ-4-1-1-2図)。
第Ⅱ-4-1-1-1図 日本の直接輸出額推移(企業規模別)
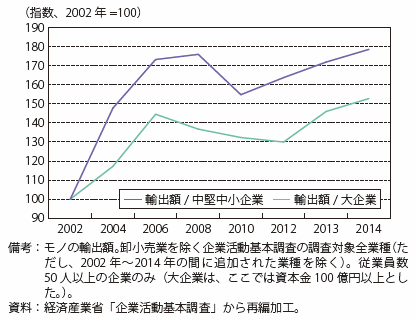
第Ⅱ-4-1-1-2図 一社あたり輸出額(企業規模別)
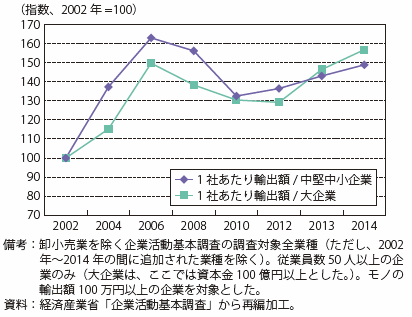
少子高齢化の進展により内需の伸びには限界が想定される一方で、海外市場向けの輸出は多くの分野で成長しており(第Ⅱ-4-1-1-3図)、さらにeコマースの発展95(第Ⅱ-4-1-1-4図、第Ⅱ-4-1-1-5図)を背景に、中堅・中小企業の製品が内外の消費者の目に触れる機会が拡大していると思われる。
第Ⅱ-4-1-1-3図 我が国の品目別輸出額の伸び97
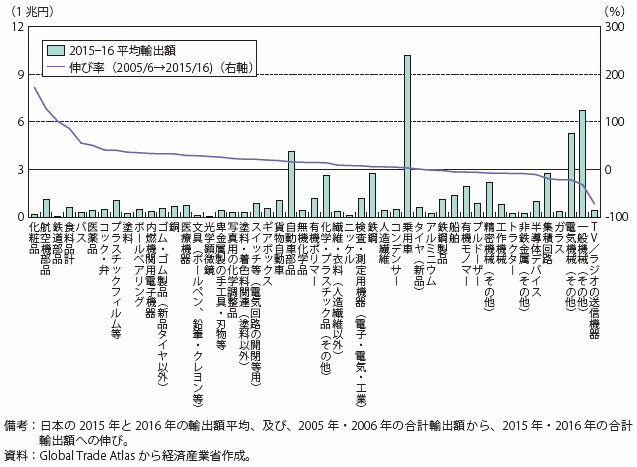
第Ⅱ-4-1-1-4図 世界の越境eコマース市場規模(見込み)
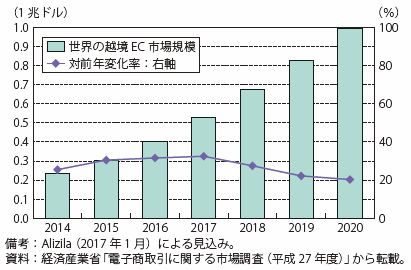
第Ⅱ-4-1-1-5図 日本からの輸出でeコマースを利用した企業割合(規模別)
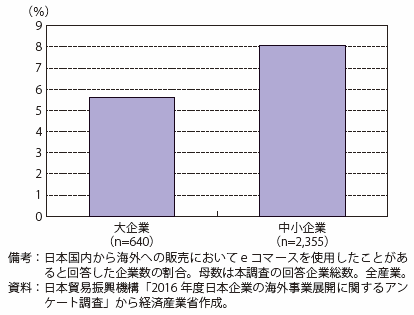
他方、中小企業による輸出は伸びているものの、英独仏と比べて中小企業の輸出割合は低い。引き続き直接輸出の促進を図るとともに、中小企業が海外市場にアクセスする際のハードルを引き下げ、外需から持続的に稼ぐことが期待される(第Ⅱ-4-1-1-6図)96。
第Ⅱ-4-1-1-6図 各国の輸出企業割合(中小企業)
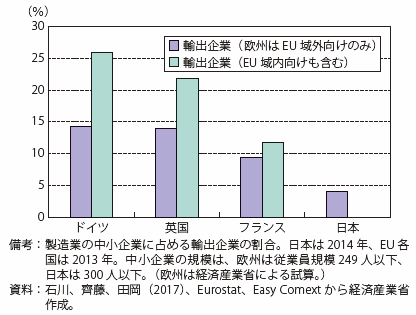
94 本節における企業規模は、中小企業は、従業員数300人以下若しくは資本金3億円以下。中堅企業は、非中小企業で資本金100億円以下、大企業は非中小企業で資本金100億円超とした。
95 経済産業省(2016b)、独立行政法人日本貿易振興機構(2017)。
96 日本の輸出割合については、石川、齊藤、田岡(2017)を使用した。同レポートについては、本節2.(1)「日本の間接輸出の現状」を参照。
97 食料品は、ここではHS2~4類、7-12類、16-21類を含む。
(2)直接輸出による企業の業績改善効果
輸出が伸びた場合には企業の売上げが拡大し、結果として業績が改善することが期待されるため、以下では、輸出による業績改善効果について確認する。
まず、企業活動基本調査に基づいた分析によると、2010年から2014年にかけてモノの輸出額が伸びた製造業企業のうち、従業員数、営業利益、及び賃金が伸びた企業の割合をそれぞれ見てみると、中小企業については、賃金、営業利益、従業員数のいずれも、増加した企業の割合が非輸出企業を上回った(第Ⅱ-4-1-1-7図)。
第Ⅱ-4-1-1-7図 モノ輸出額が伸びた企業の業績改善(非輸出企業との差)
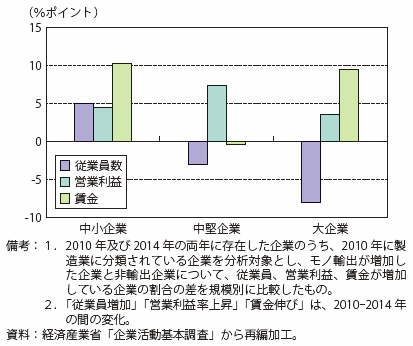
一方、大企業や中堅企業については、輸出が伸びた企業は、営業利益と賃金の伸びが非輸出企業を上回るものの、従業員の伸びは非輸出企業を下回っている。輸出の伸びが従業員の増加には結びつかない企業が多い背景としては、生産効率化による人員削減や、内需の好調により非輸出企業と差が生じたことなどが考えられるが、これについては別途分析が必要である。
次に、中小企業に焦点を当て、輸出形態と輸出が伸びた品目に基づいて、①モノだけを輸出していて輸出が伸びた企業のほか、②サービスだけを輸出していて輸出が伸びた企業、さらに、モノとサービスの両方を輸出している企業のうち、③モノとサービスの両方の輸出が伸びた企業、④モノの輸出だけが伸びた企業、⑤サービスの輸出だけが伸びた企業、に分類して分析した。
その結果、サービス輸出だけが伸びた企業を除いて、従業員、営業利益、賃金が、非輸出企業よりも改善したことが確認できた(第Ⅱ-4-1-1-8図)。
第Ⅱ-4-1-1-8図 輸出伸びカテゴリー別中小企業の業績改善(非輸出企業との差)
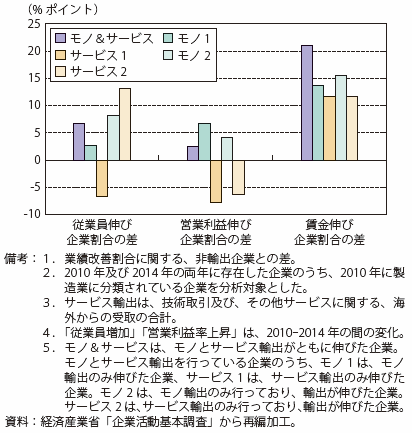
なお、輸出形態ごとの企業割合、輸出が伸びた内容ごとの企業割合、またそれぞれにおける業績改善度合いについては巻末の補論に示した。
(3)輸出と労働生産性
直接輸出を行う企業の労働生産性は高い。これは、海外市場に製品を供給するためには、必要な固定費用を負担しても利益が確保できるだけの高い生産性が求められることが背景にある98。
輸出内容別に確認すると、輸出企業の中でも、特に、モノとサービスを共に輸出している企業は、大企業の割合が高いことも影響し、生産性(労働者あたり付加価値、2014年)が9.5百万円と高い(第Ⅱ-4-1-1-9図左)。
第Ⅱ-4-1-1-9図 非輸出企業の労働生産性水準
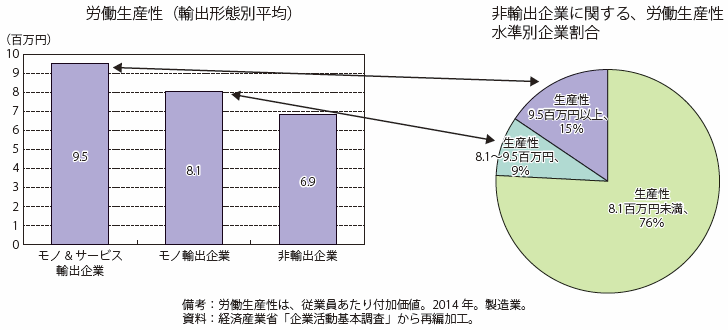
一方、直接輸出を行っていない企業の中にも労働生産性が高い企業は存在する。製造業では、非直接輸出企業の24%が、モノ輸出企業の平均的な労働生産性水準(同8.1百万円)を上回っている。さらに、モノとサービス輸出企業の労働生産性(同9.5百万円)をも上回る企業が15%存在する(第Ⅱ-4-1-1-9図右)。
こうした、直接輸出を行っていないが生産性の高い企業については、それぞれ経営判断があるにせよ、少なくとも輸出に要する固定費用の観点からは輸出ポテンシャルを十分に有する可能性が高い。
このような輸出ポテンシャルが高い企業について、企業規模別、また都市と地方別に確認する。企業規模別に見ると、生産性が、モノ輸出企業の平均水準(8.1万円)を超える非直接輸出企業が、中堅企業で5割、中小企業で2割程度確認された。規模別の割合で見れば大企業よりも見劣りするが、実数で見ると平均水準よりも高い企業の相当数が中小企業であることから、直接輸出の拡大を図るポテンシャルを有する企業の数は大きいと示唆される(第Ⅱ-4-1-1-10図、第Ⅱ-4-1-1-11図)。
第Ⅱ-4-1-1-10図 非輸出企業の労働生産性(企業割合)
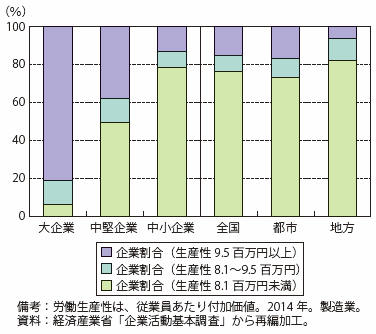
第Ⅱ-4-1-1-11図 非輸出企業の労働生産性(企業数)
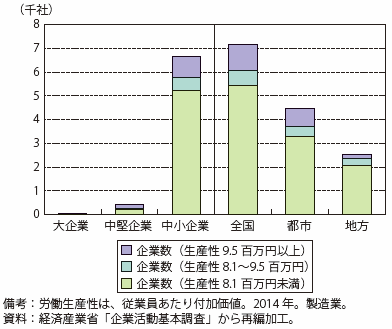
一方、中堅・中小企業の多くは労働生産性が低い。また、都市と地方を比較すると、地方では、都市に比べて生産性が高い非直接輸出企業が少ない99,100。これについては、都市における大企業の多さが影響している可能性もあるものの、中小企業に絞って比較しても、地方企業の労働生産性は都市を下回っている(第Ⅱ-4-1-1-12図)。
第Ⅱ-4-1-1-12図 非輸出中小企業の労働生産性(都市・地方別)
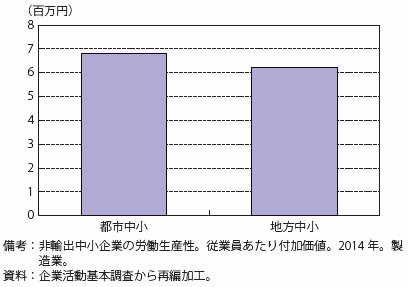
98 経済産業省(2016a)。
99 企業活動基本調査に基づくデータにおける都市と地方の区分については、都道府県のうち、都市を、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県とし、その他を地方とした(Forslid-Okubo (2014)に基づく)。
100 主な事業活動が地方であるにも関わらず、本社所在地が都市にある企業をできるだけ除外するため、本社事業所数が1の企業のみを対象とした。以下、本節では、企業活動基本調査に基づいた都市と地方の比較に関しては、同様に本社事業所数が1の企業のみを対象とする。
(4)直接輸出を行わない理由
直接輸出に必要なプロセスの中には、多くの中小企業にとって対応することが難しい内容が幾つも存在する。具体的には、与信管理(信用管理)、為替の変動への対応、輸出先の法律/商慣習/知財などの把握、販路開拓などが挙げられる。
アンケート調査101によると、間接輸出や越境eコマースを行っている中小企業の多くは、直接輸出を行わない理由として、ノウハウの構築に手間がかかる点や、海外ビジネス人材の不足、海外顧客ニーズに関する情報不足などを挙げている(第Ⅱ-4-1-1-13図)。また、販路確保ができない理由としては、海外個別企業に対する営業ができないと回答する企業が多い(第Ⅱ-4-1-1-14図)。
第Ⅱ-4-1-1-13図 直接輸出をしない理由(中小企業)
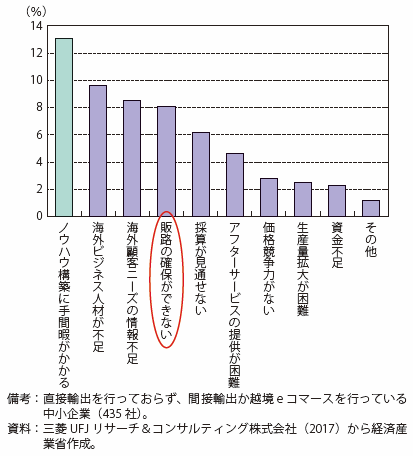
第Ⅱ-4-1-1-14図 販路確保できない理由
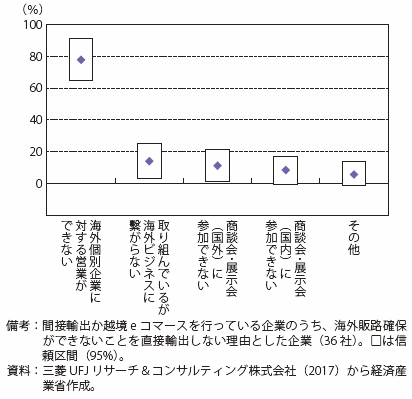
これらのうち輸出ノウハウや海外個別企業に対する営業といった面については、輸出手続や販路確保に強みを有する商社をうまく活用することで解消することが可能であり、中小企業にとって、間接輸出は外需へのアクセスのための有効な手段となっている(第Ⅱ-4-1-1-15図)。
第Ⅱ-4-1-1-15図 輸出等の開始・拡大に資すると考える取り組み(中小企業)
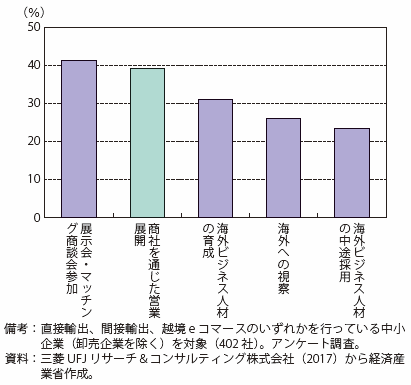
101 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社(2017)による。2017年1月~2月実施。本アンケートにおいて、「間接輸出」とは、商社や卸売業者、その他関連企業や顧客企業など、資本関係のない「仲介企業」を通じた輸出としている。
2.日本の間接輸出の現状
(1)企業取引データに基づく間接輸出分析
以下、本項(2.(1))では、石川、齊藤、田岡(2017)による分析を引用し、我が国における間接輸出の現状と効果について確認していく。
なお、石川、齊藤、田岡(2017)では、東京商工リサーチの企業取引データを使用しているが、「間接輸出企業」については、データの制約上、直接輸出を行っている卸売企業又は製造業の企業に対して販売する企業を対象とする。したがって、実際には当該「間接輸出企業」の製品が海外向けに輸出されていない場合も含まれる可能性があることに留意する必要がある102。
前項において、中小企業は全体的に労働生産性が低いこと、また都市よりも地方では労働生産性が低いことを確認した。資金力や域外市場に関する情報が乏しい中小企業、特に地方の中小企業の多くにとって、直接輸出に要するコストが大きな負担となっていると考えられ、外需へのアクセス手段として、直接輸出に加えて、中堅規模の専門商社や地域をはじめとする商社の活用が重要になってくると考えられる。
①間接輸出企業の割合
石川、齊藤、田岡(2017)によれば、我が国で直接輸出を行う製造業企業は5%と少ないが、間接輸出企業はずっと多い。
間接輸出企業は、製造業の中で企業数の39%、被雇用者数の42%、売上げ高の33%、付加価値の50%を占める(第Ⅱ-4-1-2-1図)。付加価値ベースで見ると、直接輸出企業や非輸出企業よりも大きな割合を占めていることが分かる。
第Ⅱ-4-1-2-1図 輸出企業割合
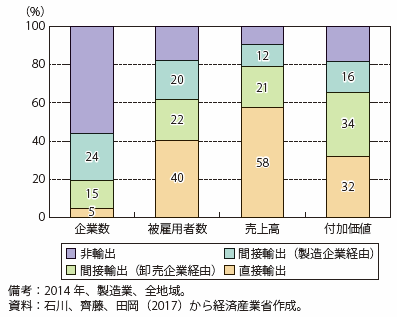
都市と地方を企業数で比較すると、地方の間接輸出企業割合(34%)は都市の44%よりも低いが、地方では非輸出企業が63%と都市の48%よりも高いことから、間接輸出のポテンシャルという側面からみると、地方にとっては間接輸出が特に重要になってくる(第Ⅱ-4-1-2-2図)。また、直接輸出企業は首都圏、関西、東海に相当程度が集中しているが、間接輸出企業については、九州、瀬戸内海、日本海沿岸、東北などへと広がりが確認できる(第Ⅱ-4-1-2-3図)。
第Ⅱ-4-1-2-2図 輸出企業割合(都市/地方別)
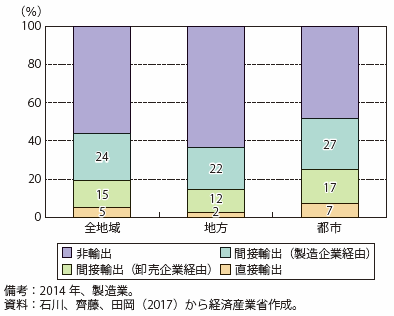
第Ⅱ-4-1-2-3図 輸出形態別企業密度マップ
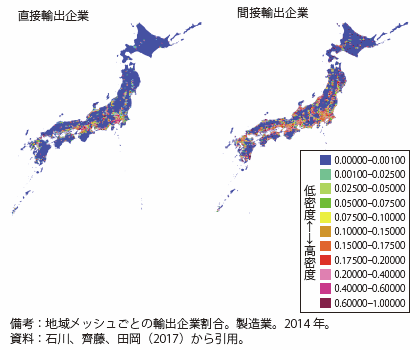
次に業種別に見ると、間接輸出企業を含めて輸出割合が高いのは、非鉄金属製造業、電子部品・デバイス等製造業、電気機械等製造業などであった。逆に食料品や窯業・土石品などでは20%に満たない(第Ⅱ-4-1-2-4図)。
第Ⅱ-4-1-2-4図 業種別輸出形態割合
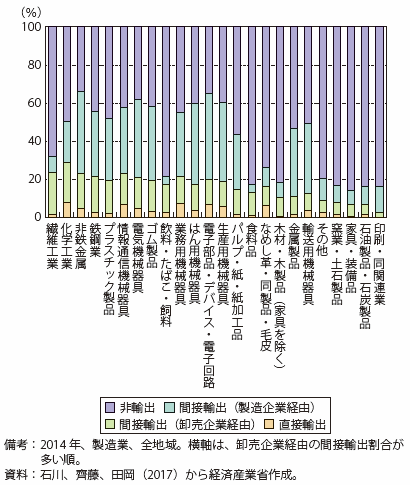
なお、商社103経由の間接輸出企業の割合は、繊維、化学、非鉄金属など、素材系の製造業が多い。素材系の製造業については、直接輸出企業割合が2%未満と僅かであっても、商社経由の間接輸出企業割合が5%を超える業種が多い(第Ⅱ-4-1-2-5図)。さらに製造業経由の間接輸出割合も多く、間接輸出によって外需にアクセスする企業が多いことが分かる。
第Ⅱ-4-1-2-5図 直接/間接割合(業種別)
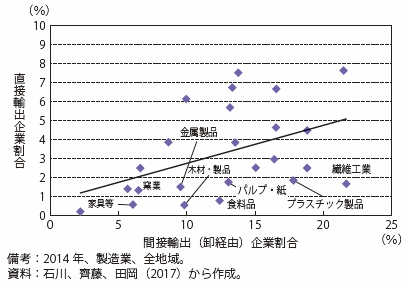
食料品製造業や飲料製造業については、外需につながっていない非輸出企業が8割前後と他の業種に比べて多い。間接輸出により海外市場へのアクセスを拡大する余地が大きいと考えられる。
②規模依存性
企業規模別に輸出企業割合を確認すると、企業規模が小さいほど直接・間接輸出企の割合が小さく、企業規模が大きいほどその割合が大きい(第Ⅱ-4-1-2-6図、第Ⅱ-4-1-2-7図)。
第Ⅱ-4-1-2-6図 直接輸出企業割合(企業規模別)
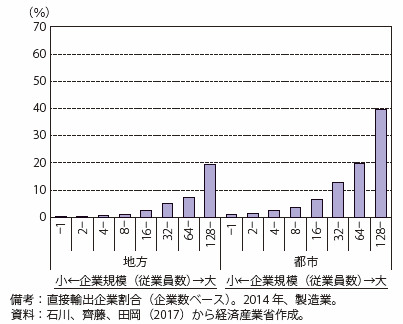
第Ⅱ-4-1-2-7図 間接輸出企業割合(企業規模別)
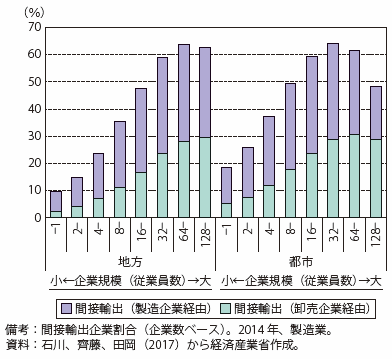
特に直接輸出については規模依存性が高く、また同じ規模の企業の場合、地方では、都市に比べて直接輸出企業の割合が小さい。間接輸出企業については、同じ規模であれば地方と都市で同程度の割合となっている。
以上より、直接輸出は、中小企業、特に地方の中小企業にとってハードルが高いことが示唆される。
③間接輸出を行うことによる効果
間接輸出を行うことによりどのような効果が生じているのだろうか。
2014年から2016年にかけて日本の輸出額は減少しているが、輸出形態別に確認すると、売上高は非輸出企業を除き伸びている(第Ⅱ-4-1-2-8図)。
第Ⅱ-4-1-2-8図 売上高の成長率(製造業・輸出形態別)
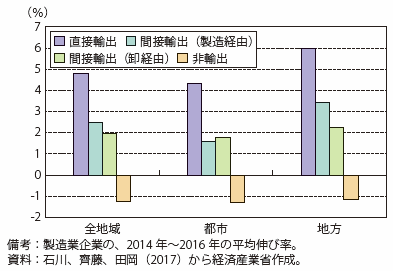
同期間における売上高の成長性を回帰分析104すると、直接輸出企業が最も成長性が高く、次いで製造業経由間接輸出企業、卸売業経由間接輸出企業の順となっている(第Ⅱ-4-1-2-9図)。
第Ⅱ-4-1-2-9図 売上高の成長性に関する回帰分析結果
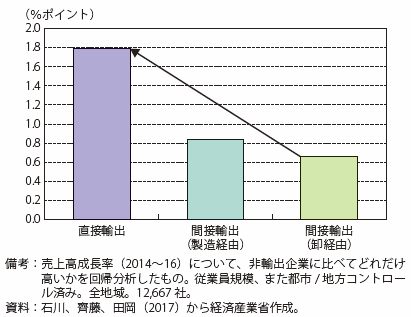
また、間接輸出企業は、非輸出企業に比べて、直接輸出を開始する傾向が高い。
2014年時点で輸出を行っていなかった企業のうち、2年後に直接輸出を開始した企業は、製造業企業経由が97社、卸売企業経由が164社、非輸出企業が84社であった105(第Ⅱ-4-1-2-10図)。それぞれに占める割合は、製造企業経由が0.29%、卸売企業経由が0.81%であり、僅かではあるが、非輸出企業に比べると、それぞれ2倍以上、7倍以上の割合であり、直接輸出へのステップとなる可能性があるといえる。
第Ⅱ-4-1-2-10図 直接輸出を開始した企業数
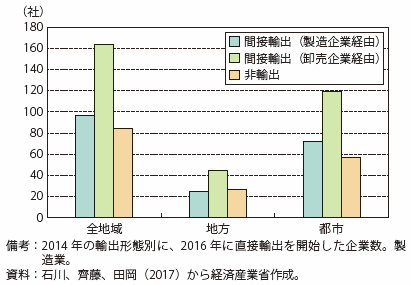
さらに、都市と地方の違い、及び企業規模の違いといった属性を調整して回帰分析しても、卸売企業経由の間接輸出企業は、非輸出企業に比べて、輸出開始傾向が有意に高いことが確認された106。
商社を介して間接輸出を行っていた企業が、当該商社を経由せず自ら同じ顧客に販売することは、当該商社との契約により制限されることが一般的であり、商社経由の間接輸出が簡単に直接輸出に移行することは考えにくいものの、間接輸出を行う経験を通じて海外市場や輸出に関する知見を獲得することで、直接輸出を行う上でのハードルが軽減する可能性が考えられる。
(参考)
アンケート調査107によれば、間接輸出と直接輸出の開始時期が近い企業の割合は、都市の方が地方よりも大きく(第Ⅱ-4-1-2-11図)、間接輸出から直接輸出に移行するタイミングが、都市の方が地方よりも早いことを示唆する108。
第Ⅱ-4-1-2-11図 間接輸出から直接輸出への移行
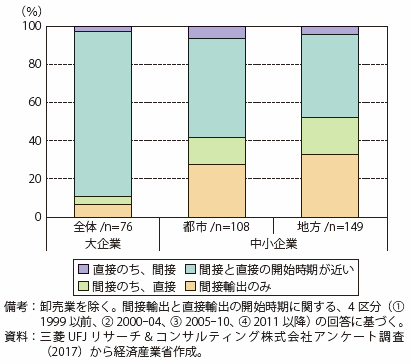
102 卸売企業」については、ここでは中堅中小企業の輸出を担う専門商社や地域商社を中心として議論するが、中堅中小企業と大手商社との取引も存在しうるため、分析には、大手商社を含む。都市と地方の区分については、47都道府県のうち、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県を都市、その他を地方としている。
103 「商社」については、ここでは中堅中小企業の輸出を担う専門商社や地域商社を中心として議論するが、中堅中小企業と大手商社との取引も存在しうるため、分析には大手商社を含む。
104 企業規模、及び都市・地方の違いといった属性について調整。
105 全数調査でないことに留意。
106 なお、製造業企業経由の間接輸出企業については、企業規模の違いをコントロールすると有意性が消える。
107 MURJリサーチ&コンサルティング株式会社(2017)による。本アンケート調査において、「間接輸出」とは、商社や卸売業者、その他関連企業や顧客企業など、資本関係のない「仲介企業」を通じた輸出としている。
108 MURJリサーチ&コンサルティング株式会社(2017)によるアンケート調査のデータにおける都市と地方の区分については、都道府県のうち、都市を、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県とし、その他を地方とした(Forslid-Okubo (2014)に基づく)。
(2)中小企業にとっての間接輸出
次に、主に間接輸出に関するアンケート調査109に基づき、中小企業がどのように間接輸出を利用しているのかを確認していく。
なお、本項において、「間接輸出」とは、商社や卸売業者、その他関連企業や顧客企業など、資本関係のない「仲介企業」を通じた輸出としている。
①間接輸出によるメリット
アンケート調査によると、間接輸出の結果、新たな市場へのアクセス確保などによって、多くの中小企業の業績が改善している。特に、経常利益の増加に寄与したとの回答は、中小規模の間接輸出企業の約50~60%に上り、直接輸出と余り差がない。海外市場に製品を供給するためには、必要な固定費用を負担しても利益が確保できるだけの高い生産性が求められるが、一般的には生産性が高くない中小企業であっても、間接輸出を通じて外需にアクセスすることは可能であり、それによって経常利益の改善が図られたといえる。ただし、雇用と賃金に対しては、間接輸出・直接輸出ともに、その改善に寄与したとの回答割合は低い(第Ⅱ-4-1-2-12図)。
第Ⅱ-4-1-2-12図 各項目に輸出が寄与したと考える企業の割合(中小企業)
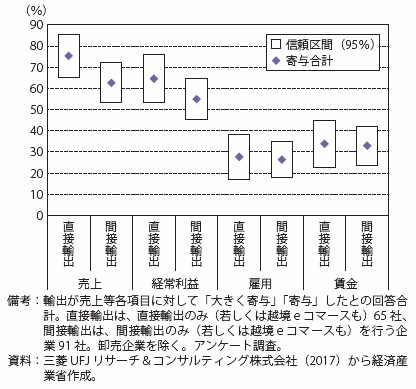
なお、同アンケート調査によると、直接輸出及び間接輸出の両方において、増加傾向にある企業の割合が大きい(第Ⅱ-4-1-2-13図)。
第Ⅱ-4-1-2-13図 直接輸出・間接輸出の傾向
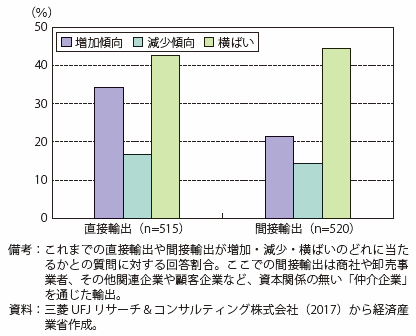
以下は、商社を活用し、新たな分野で間接輸出に成功した企業の事例である。売上げに占める割合は大きくないものの、当該間接輸出を通じて評価されることで、新たなビジネスにもつながっているとのことである。
〈事例:商社を活用した間接輸出110〉
株式会社ハタダ.(東京都大田区)は、1955年に創業された、従業員50名ほどの精密工業用ゴム製品メーカーであり、以前より、国内企業(主に、カメラ等精密機器メーカー)向けに精密ゴム部品を開発・生産している。タイヤ用のゴム製造技術を基盤とした優れたゴム配合技術と、金型製造技術を自前で有するという、一貫した生産体制が強みである。
第Ⅱ-4-1-2-14図 航空機用客室窓用シェード

2009年、航空機分野への参入を図るため、その分野に知見のある総合重機企業OB(以下、専門人材)を顧問として社内に採用した。その専門人材のアドバイスにより、JIS Q 9100111を取得し、その後の商社とのコミュニケーションがきっかけとなり、最終製品(ボーイング787用客室窓用シェード)を、国内外の航空会社から受注することに成功した。
航空機分野では高い安全性が求められることから、新規企業が大企業に対して単独で営業することは困難であり、自社製品のアピールや情報収集は、専門商社と共に行う必要があると言われる。同社が利用した専門商社は、為替リスクの負担や輸出手続全般に加えて、国内外の航空機関連の販路に有する強みを活かして、同社と航空会社、航空機メーカーとのコーディネート(ミーティングアレンジ、プレゼンテーション、フィードバック等)等の機能も担い、これが同社製品の開発と納品につながった。同社の主力である様々な精密ゴム製品は、他企業の製品に組み込まれる形で、以前から間接輸出がされていたわけではあるが、最終製品の海外企業への納品は初めてであった。
同社によると、当該間接輸出商品が同社の売上げに占める割合は大きくないものの、航空機分野で要求される厳しい基準を満たす製品を生産している企業として評価されることで、新たなビジネスにつながっているとのことである。なお、同製品については、日米で意匠登録されており、世界シェア100%となっている。
②間接輸出を開始する際の課題
うまく製品を海外販路に乗せ、企業に利益をもたらすためには、輸出コストが低いとされる間接輸出においても、やはり乗り越えるべき課題がある。
アンケート調査によれば、間接輸出開始時には、海外顧客ニーズの把握、及び販売力のある仲介企業の確保という2項目が企業にとっての主な課題であることが分かる。なお、両項目を課題とする割合は、間接輸出の拡大時には顕著に低下していることから、特に間接輸出を開始する際に重点的に対応することが求められているといえる(第Ⅱ-4-1-2-15図)。
第Ⅱ-4-1-2-15図 間接輸出の開始時・拡大時の課題
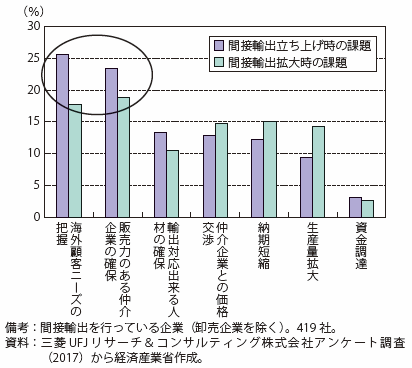
次に、間接輸出開始時の主な課題について、同時に選択されている課題と両項目を選択する企業の割合を確認したところ、「輸出人材の確保」を選択する企業は、そのうち半数近くが「仲介企業の確保」を同時に選択している。仲介企業を活用しつつも、何らかの形で、自社内に輸出に対応する人材を確保することが求められているといえる(第Ⅱ-4-1-2-16図、第Ⅱ-4-1-2-17図)。
第Ⅱ-4-1-2-16図 間接輸出立ち上げ時の課題が同時に選択される割合
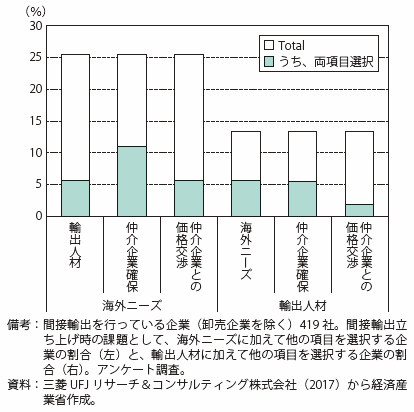
第Ⅱ-4-1-2-17図 間接輸出立ち上げ時の課題の同時選択イメージ
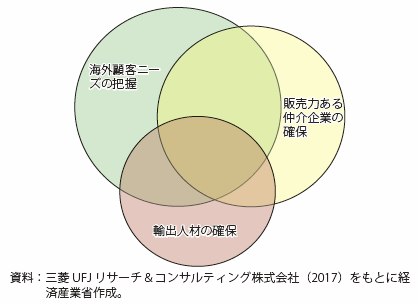
なお、間接輸出開始のきっかけの多くは相手先からの要望であるが、積極的な営業活動を挙げる企業も多い(第Ⅱ-4-1-2-18図)。この中には、国内商社に対してではなく海外顧客に対する積極的な営業を行うケースも想定される。輸出そのものは商社を経由する場合であっても、当該企業自らも商社と協力して営業活動を行うことによって、より明確に自社製品及び自社の強みを顧客に伝えることが可能となる場合がある。適切な仲介企業の確保に加えて、輸出人材の確保を始め輸出に対応するための体制を企業が整えることは、このような積極的な営業を支える要因となり得る。
第Ⅱ-4-1-2-18図 間接輸出につながったきっかけ
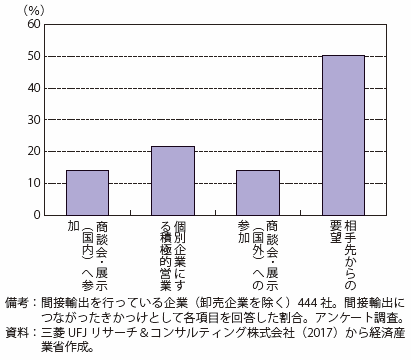
〈事例:中小企業と仲介企業とのマッチング支援112〉
東京都中小企業振興公社は、海外に販路を求める中小企業に対して適切な商社を紹介する支援を行っている。
同公社には、中堅商社やメーカー出身者など、海外ビジネス経験と輸出実務の双方の知見を有する人材が、多数の業種にわたり在籍しており、海外販路開拓を希望する中小企業の商品を理解し、経験と実績に基づいて、市場性を見極めながら適切な専門商社へとマッチングしている。
なお、商談会等への参加によって海外の顧客を見つけた場合であっても、中小企業はその後に話を続けることができないケースが多い。そのため、同公社は、中小企業が海外の顧客を既に見つけている場合についても、多岐にわたる顧客とのやりとり(契約に至るまで、契約時、支払関連、輸送関連等)を含めて担当する、市場や製品の特性に応じた適切な中堅商社を紹介している。
また、間接輸出であっても、通常は当該中小企業が一定のリスクを負うことになることから、同公社では、販路開拓を希望する中小企業に対し、人的・組織的・資金的に海外輸出に取り組む体制を作るようアドバイスしている。また、海外展開のプラン作りから販路開拓が実現するまで、さらに海外との取引が実現した後についても、税制や為替を含めた経営支援を行っている。
③輸出商社の偏在
地方では、卸売企業のうち直接輸出を行う企業の割合が低く、企業規模が最も大きいカテゴリーであっても、都市の最も小規模のカテゴリーよりも輸出企業割合が低い(第Ⅱ-4-1-2-19図)。
第Ⅱ-4-1-2-19図 直接輸出を行う企業割合(卸売企業)
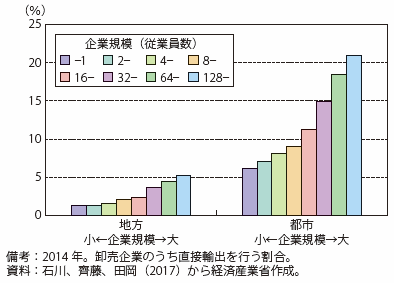
アンケート調査によれば、卸売事業を行っている企業のうち、海外の販路に強みを有する企業はごく一部に限られる。具体的には、卸売事業を行う企業のうち外国企業との関係に強みを有するのは、海外に商圏を置く企業の2割弱、都市企業の3割弱、卸売登録企業の2割にとどまる(第Ⅱ-4-1-2-20図~第Ⅱ-4-1-2-22図)。
第Ⅱ-4-1-2-20図 卸売業務に関して有する自社の強み(商圏別)
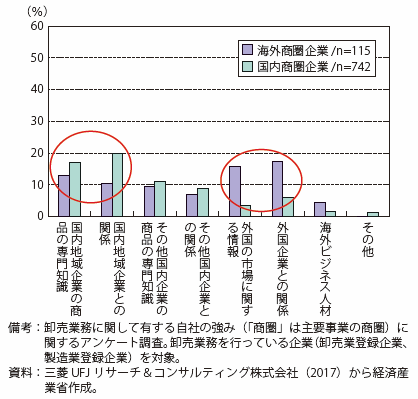
第Ⅱ-4-1-2-21図 卸売業務に関して有する自社の強み(都市・地方別)
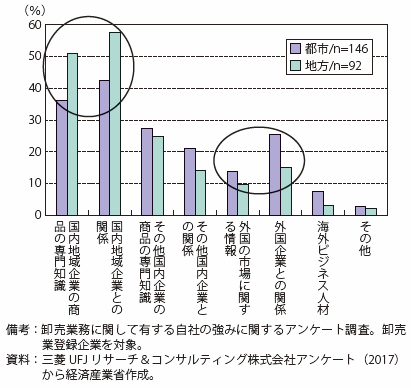
第Ⅱ-4-1-2-22図 卸売業務に関して有する自社の強み(製造・卸売業別)
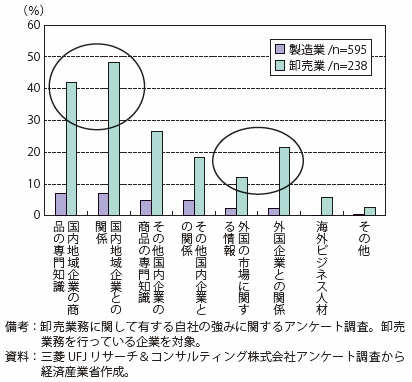
一方、仕入先である国内地域に関して強みを有する卸売企業は、海外に強みを有する卸売企業よりも多い。具体的には、卸売事業を行う企業のうち国内地域企業の商品の専門知識に強みを有するのは、国内に商圏を置く企業の2割弱、地方企業の5割、卸売企業の4割強(第Ⅱ-4-1-2-20図~第Ⅱ-4-1-2-22図)であった。
すなわち、海外販路に強みを有する卸売企業と、仕入先である国内地域に強みを有する卸売企業は、一致しない可能性が高い。
以上を踏まえると、地方企業の間接輸出促進のためには、(1)海外販路に強みを有する企業が、いかに地域の良い製品を見つけるか、逆に、(2)国内地域に強みを有する卸売企業が、いかに海外に販路を開拓するか、という課題に取り組むことが必要であろう。
アンケート調査によれば、(2)に関して、直接輸出を行っていない卸売企業は、輸出を行わない理由について、内需を重視しているからというだけでなく、情報やノウハウがないからとする割合も多い(第Ⅱ-4-1-2-23図)。地域の製品の強みをよく知る卸売企業が、国内市場のみならず海外市場にも目を向ける際には、まず彼らの輸出力の向上が求められているといえる。
第Ⅱ-4-1-2-23図 卸売企業が輸出を行っていない理由
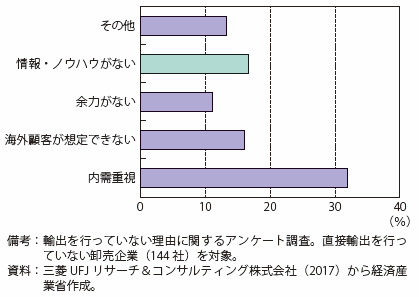
なお、中小企業の製品を海外市場につなぐのは、商社だけでなく製造業企業である場合も多い。以下は、海外販路につながる可能性のある大企業と、地方の技術に強みを持つ企業を掘り起こしてマッチングする新たなビジネスモデルの事例である。
〈事例:地方企業の技術を掘り起こすマッチングシステム113〉
リンカーズ株式会社(東京都中央区)は、2012年に創業された、従業員50名のベンチャー企業であり、ものづくりを中心とした全国の中小企業と国内外の大企業をマッチングするプラットフォーム「Linkers(リンカーズ)」の運営を主力の事業としている。
同社によれば、大企業が新製品をつくる際、100ピースのうち最後の1ピースが足りず開発が前に進まないといった状況が多く起こるが、その足りないピースは、「Linkers」のマッチングシステムを通じて掘り起こされた地方の中堅中小企業の技術によって解決されることが非常に多いという。
同社の企業マッチングシステムでは、発注者が選定条件を掲載すると(企業名は非公開が可能)、それを見た全国500以上の産業支援機関(自治体、第3セクター、銀行、大学など)に所属する2,000名以上のコーディネータ(目利き)が、その条件に合った地元企業をプラットフォームに推薦(登録)する。発注者は、コーディネータを介して登録された詳細な条件リストに基づいて、候補を絞ることができる。
第Ⅱ-4-1-2-24図 リンカーズによるマッチング(イメージ)
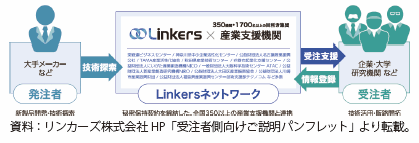
同社によれば、全国から50~100社の候補企業を募った上でマッチングが行われるため、マッチング成功率は9割と高い。発注側の要望に対し、即時に多くの受注候補を集められる理由は、地方中小企業とコーディネータの信頼関係、及びネットワークの網羅性にある。また、発注者側から、落選した中小企業に対し細かいフィードバック(どこが良かったか、どこに問題が生じたか)が行われる点が、同社のシステムの特色であるという。落選した中小企業は、発注者側から評価されることで、次への挑戦意欲が生まれ、オファーに対して継続的に手を挙げてくれるようになるという。
中小・中堅企業の優れた技術を大企業の要求と結びつけることは非常に困難である場合が多いが、人との信頼関係、ITを利用した網羅性・即時性を特徴とする同社のマッチングシステムは、これをスピーディーに実現している。リンカーズは、海外企業からの受注も検討しているところであり、地方の中堅中小企業による間接輸出や直接輸出の拡大に貢献する可能性が期待される。
なお、地域企業を掘り起こすシステムとしては、中小企業基盤整備機構による「ジェグテック」も評価されている。日本の優れた技術・製品を有する中小企業と国内大企業や海外企業とのマッチングを強化するために、WEBマッチングシステムを通じて、地域企業の輸出拡大を支援している。
109 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社(2017)。2017年1月~2月実施。
110 ヒアリング(2017年2月)。
111 品質マネジメントシステムの国際規格ISO 9001をベースに、航空宇宙産業特有の要求事項を織り込んだ規格であり、欧米における同様の規格と国際相互認証される。
112 東京都中小企業振興公社へのヒアリング(2017年3月)、同公社ウェブサイト。
113 ヒアリング(2017年2月)、リンカーズ株式会社ウェブサイト。
3.越境eコマースの活用
間接輸出に加えて、越境eコマース(海外向け電子商取引)は、海外顧客へのアクセスが容易であることから、海外市場に関する情報に乏しく輸出のネットワークを持たない中小企業にとって、海外市場へのアクセス拡大の有効な手段となる可能性がある。
アンケート調査によれば、越境eコマースに関するメリットとして、海外特有の市場やニーズを容易に開拓できること、また初期導入コストが低いことなどが挙げられている(第Ⅱ-4-1-3-1図)。
第Ⅱ-4-1-3-1図 越境eコマースに関してメリットを感じる項目
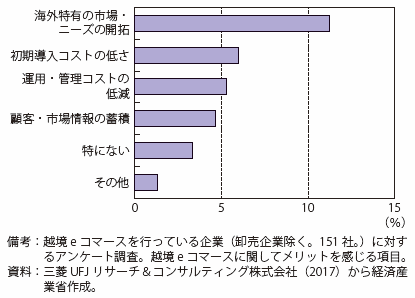
一方、eコマースについては、これを海外への販売に利用する企業が多い114ものの、eコマースの売上げに占める海外向けの割合は、僅か1%に満たない企業が非常に多い(第Ⅱ-4-1-3-2図)。
第Ⅱ-4-1-3-2図 eコマース売上げの海外割合
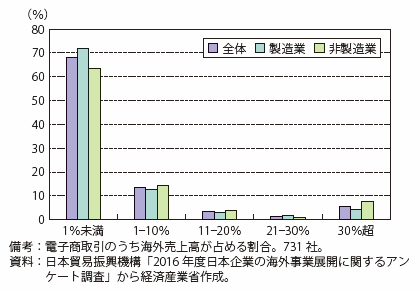
日本貿易振興機構の調査によると、越境eコマースに関する課題として、決済システムや配送に関するリスクを挙げる割合が最も多かった。また、制度や規制に関する情報の不足、通関手続や関税支払といった、輸出特有の制度に関する点を課題に挙げる割合も多い(第Ⅱ-4-1-3-3図)。海外市場に気軽にアクセスできるメリットがある一方、輸出の手続をはじめとする負担が求められること、またクレジットカードの不正利用といった支払などに関するリスクが生じることに留意する必要がある。
第Ⅱ-4-1-3-3図 越境eコマースにおける課題
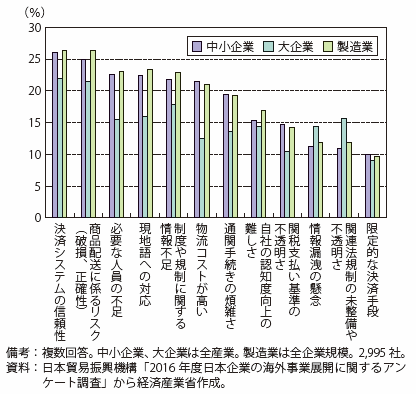
越境eコマースをうまく利用して中小企業による海外市場へのアクセスを拡大するためには、こうした課題に対応していくことが必要である。
〈事例:越境eコマースを活用した商社の新たなビジネスモデル115〉
ライフスタイルアクセント株式会社(熊本県熊本市)は、2012年に創業された、従業員20名のベンチャー企業であり、メイドインジャパンの工場直結ファッションブランド「Factelier(ファクトリエ)」展開、及び同名のインターネットサイトでの国内外販売を主な事業としている。
同社は、高い技術力をもつ日本のアパレル工場が、コスト競争で苦しんでいる状況を変え、世界一流の日本ブランドを作るという目的の下、起業された。
同社は、2017年4月現在、訪問した国内の600工場から45の世界最高水準の技術を持つ工場を選び、共に商品開発をしている。そして、工場側が、コストダウンよりも質の向上に注力できるよう、商品価格(工場希望価格の2倍が販売価格となる)を自ら決めさせている。また、従来何層にも重なっていた商社や小売店を通さないことで、下請ではなく直販に近い形とし、加えて、ものづくりをリスペクトするために、セールは一切行っていない。
工場の中には、その高い技術力への信頼から、著名な海外ブランドのOEM生産を請け負っている工場も多いが、利益率が低いのに加え、工場の名前は一切露出することがない。一方、ファクトリエブランドでは、生産者側が適正な利益を確保するだけでなく、「Factelier by工場名」というタグがつけられる。同社によると、工場名を出すことで、生産者のモチベーションが飛躍的に上がったという。
第Ⅱ-4-1-3-4図 ファクトリエのビジネスモデル(イメージ)

同社の販売及び決済は、完全にeコマースのみとしている。eコマースによって、海外も含めて新たな顧客を開拓し、また、在庫を最低限に抑制することが可能となっている。
ただし、新たな顧客の開拓とリピーターの確保のため、同社は、インターネットに頼るだけではなく、在庫を持たない試着のみの店舗も持ち、店頭イベントや工場ツアーの実施といった工夫を行っている。
また、サイズ感や着心地、質の良さを伝えきることができないというインターネット販売のデメリットを補完するため、直営店4店舗の他、全国の地域パートナーショップ(地域一番店)と提携し、商品に実際にふれて試着できるようにしている。
こうした取り組みを背景に、国内のみならず、海外からの注文も増加しており、2017年1月には台湾に海外一号店を開設している。
同社は、生産者と一心同体で地方の製品を開発・販売する、新型のSPA116的な役割を果たしているといえよう。地方の工場が、同社と提携することによって、より品質の高い商品開発ができ、直販に近い形で、海外にも進出できるのは、大きなメリットである。
なお、同社の場合、自社のホームページを介して越境eコマースを行っているが、不正利用のリスクがあるので、そのシステム対策を行った。また、各国における商標の取得、原産地証明の取得、翻訳作業など、輸出のための様々な手続や作業に対応する必要があった。こうしたコストや業務を同社が対応することにより、生産者はファクトリエを通じて、国内市場のみならず、国外市場に対しても容易に進出し、ものづくりに専念することが可能となっている。
114 eコマースを海外への販売に利用する割合は、eコマース利用企業の47%(独立行政法人日本貿易振興機構(2017))。
115 ヒアリング(2017年2月)、ライフスタイルアクセント株式会社ウェブサイト。
116 specialty store retailer of private label apparelの略で、商品企画から製造、小売までを一貫して行うアパレルのビジネスモデルを指す。
4.海外ビジネス人材
アンケート調査によると、輸出の開始や拡大に際しては、展示会やマッチング商談会への参加や、商社を通じた営業展開に加えて、大企業を中心に、海外ビジネス人材の確保を挙げる企業割合も大きい(第Ⅱ-4-1-4-1図)。
第Ⅱ-4-1-4-1図 輸出等の開始・拡大に資すると考える取り組み
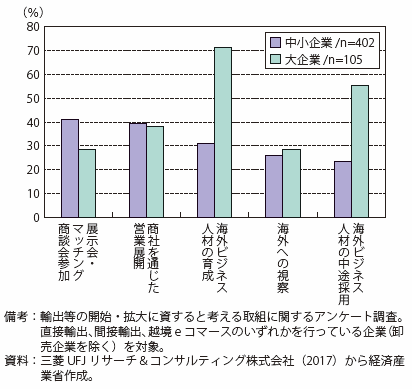
また、海外ビジネス人材のうち具体的にどのような人材が必要とされているのかを確認すると、大企業については、外国語に堪能な技術者や外国語人材、また同業の海外ビジネス経験者を挙げる割合が顕著に高い。
なお、間接輸出しか行っていない場合であっても、商社に全て頼るのではなく、商社と協力して海外販路を開拓することは、企業及び製品のアピールに有用である。また、直接輸出を目指して独自に新たな販路を開拓する場合なども考えられることから、海外ビジネス人材を必要とするケースが想定される。
アンケート調査では、中小企業については、外国語に堪能な技術者を挙げる割合は大企業ほど高くないものの、間接輸出しか行っていない場合であっても、外国語に堪能な技術者や外国語人材を挙げる割合が一定数確認されている(第Ⅱ-4-1-4-2図、第Ⅱ-4-1-4-3図)。
第Ⅱ-4-1-4-2図 輸出等の開始・拡大に際し重要と考える人材
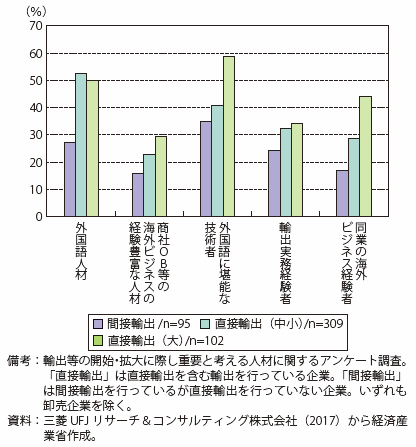
第Ⅱ-4-1-4-3図 輸出等の開始・拡大に際し不足している人材
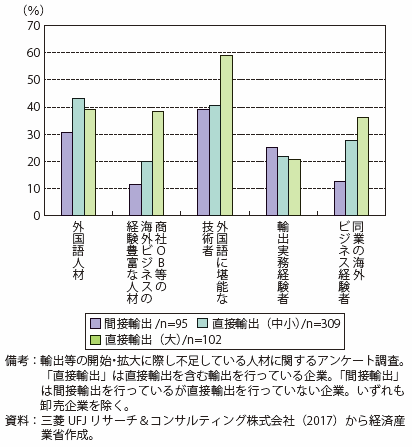
なお、中小企業にとって、海外ビジネス人材を新たに複数確保することは難しいことから、実際には、ここに挙げられたような要素をできるだけ同時に兼ね備える人材が必要とされるケースが多い。
なお、貿易に通じた人材の確保や育成に対する支援が有用、若しくは非常に有用とする回答は、輸出を行う企業の半数を超えている(第Ⅱ-4-1-4-4図)。
第Ⅱ-4-1-4-4図 人的確保に対する支援の必要性
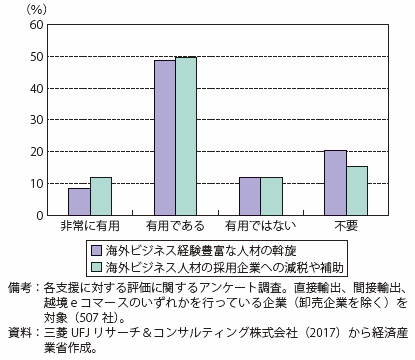
〈事例:輸出人材育成支援〉
中部経済産業局は、中部地域の中堅中小航空機部品サプライヤーを対象に、「航空機産業海外ビジネス商談実務研修」を開催117し、海外への販路開拓を支援している。同研修は、大手商社OBや新輸出大国コンソーシアムの専門家が講師を務め、また、航空機関連の在日米国駐在員による模擬商談など実践的な商談・交渉スキルを学ぶ内容となっている。その他、各企業の要望に応じて、個別コンサルティングや商談後のフォローアップも行っている。
航空機産業が集積している同地域では、従来、中堅中小部品サプライヤーの多くが大手重工との取引に依存しており、航空機部品の製造技術を有していても自ら販路を開拓しようとする動機が弱かった。しかし、近年、国産旅客機MRJや米ボーイングの新型機「777X」の開発などを背景に、航空機部品分野において新規参入のビジネスチャンス拡大が期待される中、自ら需要を獲得しようとする機運が生まれている。そのため、「技術はあるが、売り込むノウハウがない」と言われる中堅中小部品サプライヤーが、自ら、自社の強みを発信し、海外販路を開拓して新規ビジネスチャンスを獲得できるような人材を育成することが、同研修の目的となっている。
なお、同研修は、国際航空宇宙展(2016年10月開催済み)、エアロマート名古屋(2017年9月開催予定)といった国内で開催される国際商談会の他、国外で開催される国際商談会やエアショーをビジネスチャンスのターゲットとした、同地域における中堅中小航空機部品サプライヤーのプロモーション活動の一環である。この一連の活動には、上記研修の他、英語版企業ディレクトリ118や海外ビジネス支援ガイドブックの作成といった取り組みも含まれている。
第Ⅱ-4-1-4-5図 中堅中小航空機部品サプライヤー向け海外ビジネス支援
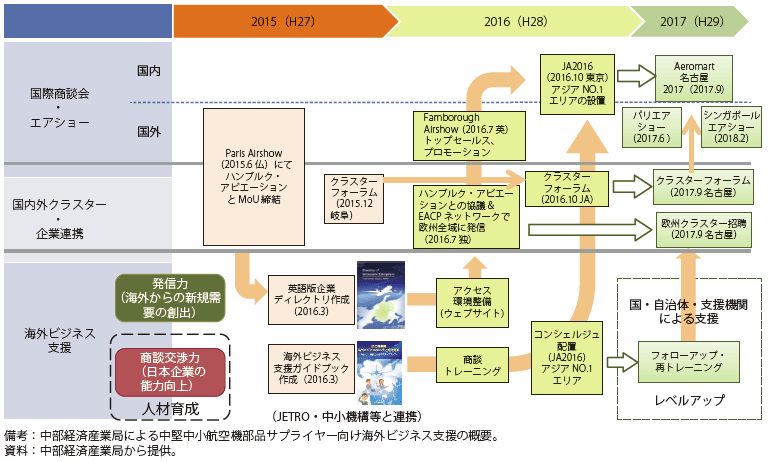
117 一般社団法人中部航空宇宙産業技術センターとの共同主催、JETROとの共催である。
118 中部経済産業局管轄地域及びアジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区認定地域(愛知、岐阜、三重、富山、石川、長野、静岡)に所在する企業情報を検索できるツールであり、海外の航空機クラスターへの共有や、海外からの航空機ミッション団への営業ツールに活用されている。(http://search.c-astec.jp/)
