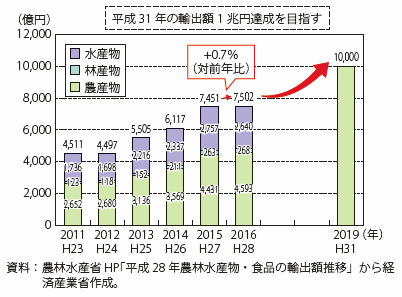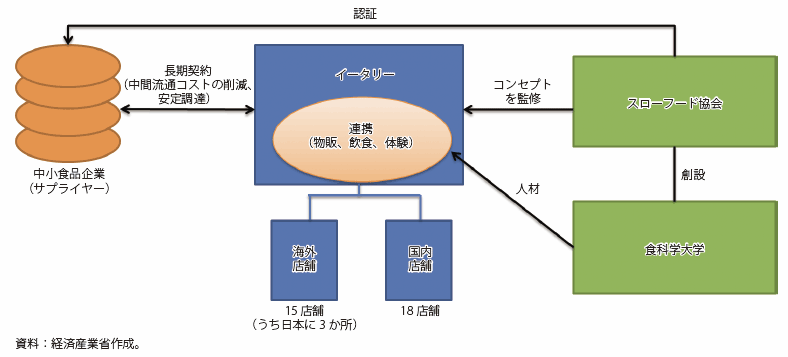第2節 地域経済の生産性向上
包摂的成長の重要性については第1章第4節において述べたとおりだが、地域経済がグローバル化の恩恵を受けられるようにするためには、まずは地域の生産性を向上させることが必要である。地域の生産性を向上させるための観光、農業、中小企業などにおける具体的な支援策については第Ⅲ部で述べるが、ここでは地域経済の生産性の現状について記載する。
地方においては、農業やサービス業は重要な産業基盤であり、就業者数で見ると、農業とサービス業だけで7割以上の就業者比率となっている。地域にもグローバル化の恩恵が行き渡るようにするためには、これらの産業の生産性を向上させることが重要である(第Ⅱ-4-2-1図)。
第Ⅱ-4-2-1図 産業・地域圏別就業者比率
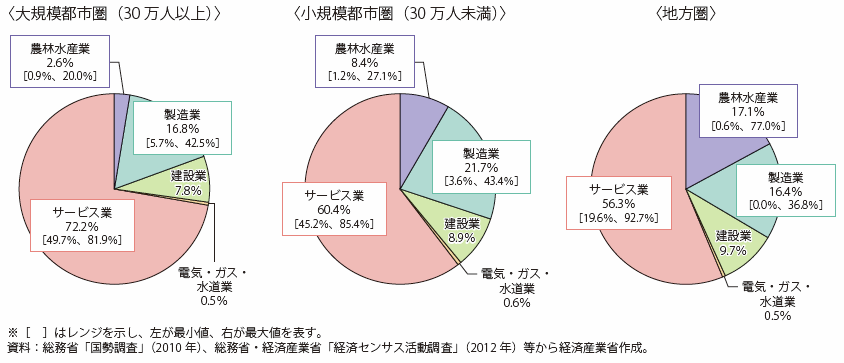
産業別に我が国の労働生産性を見ていくと、都市圏の製造業が一人当たり約900万円であるのに対して、農業は都市圏・地方圏ともに一人当たり300万円を下回る状態となっており、1/3に満たないことが分かる。またサービス業に関しても、大規模都市圏では製造業に匹敵する生産性の高さをもっているものの、地方圏においては地方圏における製造業の半分以下の生産性となっているため、地方圏のサービス業の生産性に関しても上昇させていくことが重要である(第Ⅱ-4-2-2)。
第Ⅱ-4-2-2図 産業・地域圏別労働生産性
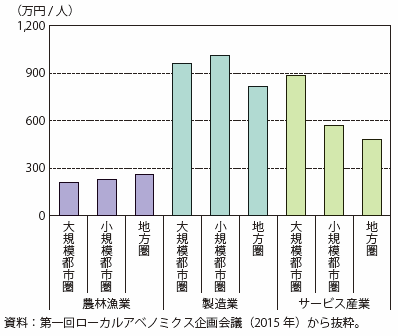
地方圏のサービス生産性を上昇させていく上で重要な分野の一つとして観光が挙げられる。世界的に見た場合には観光客数は世界16位とまだ低い値にあるものの、我が国の観光客数は近年急上昇しており、2016年には2404万人に達した。2011年の622万人から4倍程度となっている(第Ⅱ-4-2-3図、第Ⅱ-4-2-4図)。
第Ⅱ-4-2-3図 訪日外客者数推移
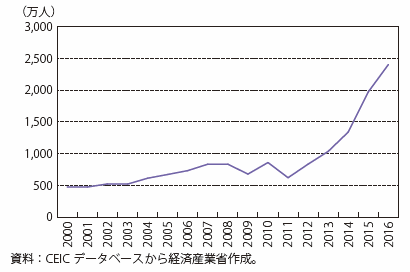
第Ⅱ-4-2-4図 2015年の訪日観光客数比較
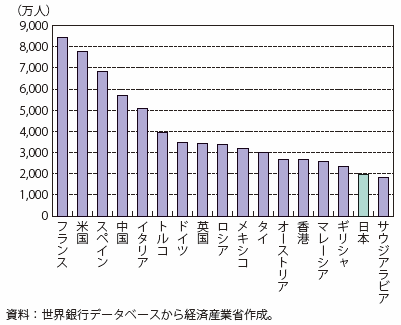
我が国は観光産業の中でも特に文化サービスの単価が低く設定されており、生産性についても低いと言われている119。実際にフランスと比較しても我が国の観光関連消費は宿泊施設サービスや飲食供給サービスに偏っていることから、文化サービスの生産性の向上等を通して、生産性の高いインバウンド産業を育てていくことが肝要(第Ⅱ-4-2-5図)である。
第Ⅱ-4-2-5図 インバウンドにおける観光関連消費の内訳
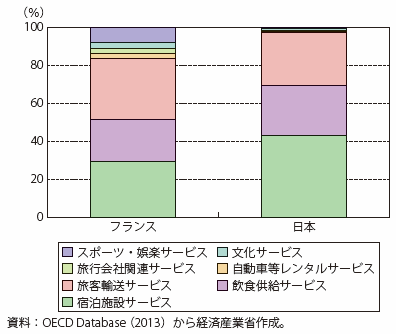
119 デービットアトキンソン「新・観光立国論」
このように、我が国地域では農業、サービス業の従事者の比率が高いものの、現状では生産性が低いため、第Ⅲ部で紹介するような人材投資施策等によって生産性を高めることが重要である。