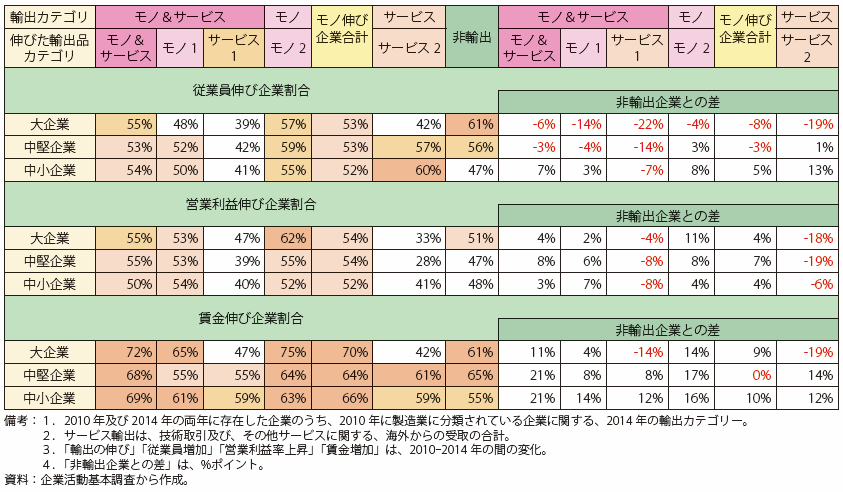補論
補論1 所得格差における金融資産及び最高取得税率の影響
第Ⅱ部第1章第2節2.の先進国における国内格差の現状では、日本を除く先進国ではジニ係数が拡大傾向にあること、上位1%及び10%の所得層の所得比率をみると米国では上位層の所得比率が高まっていることが示された。
他方、所得格差の要因分析では、IMFによる分析では金融資産が説明変数として含まれていない、また、経済産業省による分析では金融資産は所得格差拡大に有意に寄与しているとは言えないとの結果も紹介している。
米国の上位所得層の総所得に占める割合が増えている要因としては、後にみるように金融資産の上昇の影響が推察される。したがって、本補論では、所得格差における金融資産の影響及び最高所得税率について米国を例としながら補足することとしたい。
まず、米国の上位層の資産比率の推移についてみてみると、米国は上位1%層が保有する資産は1990年から2014年の間に全資産の27%から37%まで10%ポイント上昇している(補論第1-1図)。この37%という水準は所得で見た時の20%よりも資産の上位1%層への集中度が高いことを示しており、その傾向は上位10%層が約7割の資産を所有することと合わせると益々資産の上位層への集中度が強まっていると見受けられる(補論第1-2図)。
米国の格差拡大の要因の1つとして上位所得層が保有する金融資産が挙げられるのではないか。米国の上位所得層については、年収100万ドル以上の人は投資所得や事業所得の割合が総所得の約7割を占める一方、賃金所得は3割を占めるにすぎず、年収20万ドル以上100万ドル未満の人は同様に賃金所得の占める割合が6割程度なのに対し、それ以外の所得階層の人の賃金所得の割合は約8割というデータがある(補論第1-3図)。ストックオプションや金融資産に対する税制優遇等もあわせると賃金が総所得の大半を占める中・低所得層と金融資産が所得の多くを占める上位所得層では、土台となる賃金の差に加えて金融資産が上乗せされることから、市場動向によって資産価格の変動はあるものの、金融資産が所得格差に与える影響は低くはないと見込まれる。
もう1つの要因としてアンソニー・アトキンソン氏は『21世紀の不平等』の中で所得税率の最高税率の引き下げの影響についてふれている。補論第1-4図は主要国におけるトップ1%の所得シェア変化と最高限界手取り率の変化を示したものだが、最高税率の引き下げの結果としての手取所得比率の増大は、総所得に占めるトップ1%が占めるシェア拡大と相関しているようだと述べている1。米国では最高税率が1980年に70%だったのが、35%に下がった。
補論第1-1図 上位1%層の資産比率
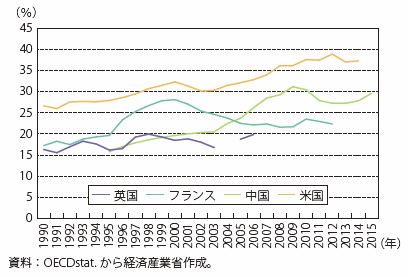
補論第1-2図 上位10%層の資産比率
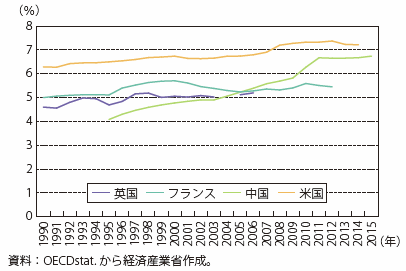
補論第1-3図 米国における個人所得階層別収入源シェア(2013年)
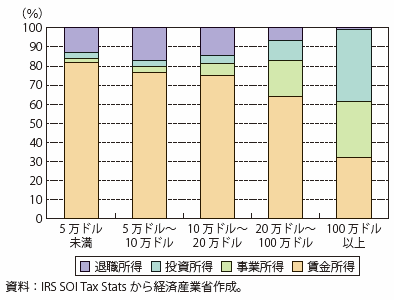
補論第1-4図 主要国における最高所得税率と上位1%の総所得に占める割合の変化
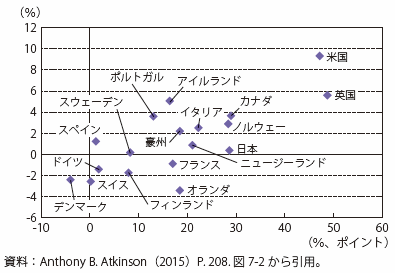
上記のとおり、米国においては金融資産が所得格差に影響を与えていることが推定されるものの、先進国を対象とした第Ⅱ部第1章第2節3.のIMFによる格差の要因分析では金融資産が説明変数として出現していないこと、同4.の我々の分析でも金融はジニ係数拡大にプラスに寄与するとは統計学上認められないとの結論があることとの関係をどう考えるべきだろうか。
先進国における金融資産については国際比較可能なデータが不足しており、米国以外の先進国において金融資産が所得に占める割合が高いかどうか、金融資産が所得格差にどのような影響を与えているかの実証研究も限られており、現時点では明確な回答は持ち得ないため、今後さらなる研究が待たれるところ。
1 Anthony B. Atkinson(2015),p. 209.
補論2 所得に占める賃金シェア増減による格差への影響
この補論では所得に占める賃金シェア増減による所得格差への影響について補足することとしたい。
アンソニー・アトキンソン氏の著書『21世紀の不平等』によれば、所得に占める労働賃金の割合については、ピケティとズックマンのデータによると、日本を除く全ての国で1970年代から2000年代にかけて賃金のシェアが減少している2。賃金のシェアの増大は、所得格差の縮小を意味するかという問いに対し、リカルドの時代の英国のような階級社会では、賃金のシェアが1ポイント増えると、ジニ係数が1ポイント下がるとの論文がある。今では予想されるジニ係数の減少はずっと小さいが、それでも賃金シェアの変化の影響はいまだに相当大きいと言われている。ダニエル・チェッチとセシリア・ガルシア・ペニャロサは、OECD16カ国について1970年から1996年までを調べた結果として、賃金シェアの1ポイントの増加が、ジニ係数の0.7ポイントの減少を伴うとしている3。
2 Anthony B. Atkinson(2015),p. 80.
3 Anthony B. Atkinson(2015)P. 82
補論3 近年の格差拡大の要因分析に使用した指標
第Ⅱ部第1章第2節4.近年の格差拡大の要因分析に関する実証分析に使用した指標とその詳細や出典については、以下の表にあるとおりである。全ての指標において、自然対数をとって分析を行っている(補論第3-1表)。
本文では、技術革新の説明変数としてICT投資/GDPを使っているが、他の説明変数に変更した場合の影響を確認するため、技術革新の説明変数をビジネス部門R&D/GDPに入れ替えて(その他の説明変数、被説明変数、期間、対象国は同じ)分析を行ったところ、ビジネス部門R&D/GDPについては有意性が認められなかった。従って、技術革新の説明変数としては、ICT投資/GDPの方が適切と思われる。2つの説明変数が異なることで有意性が変わる理由としては、ビジネス部門R&Dが企業の生産性向上や新製品開発等による新たな市場開拓によって企業業績に影響を与える性質を有するものの、格差につながる経路が必ずしも明確でないのに対し、ICT投資は企業で働く労働者に求めるICTを使いこなす技能レベルに影響を与え、労働者の賃金格差に影響が生じる可能性があるためではないかと思われる。
補論第3-1表 近年の格差の要因分析に使用した指標一覧
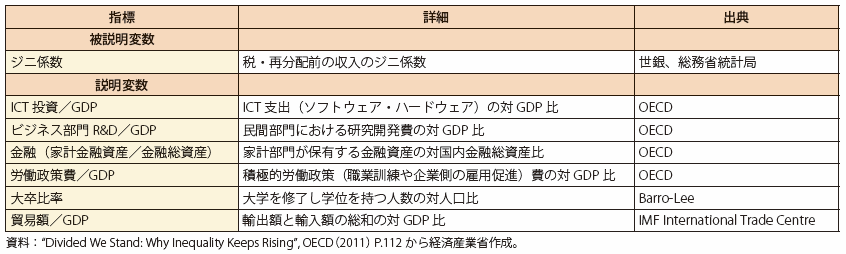
補論4 都道府県別製造業労働者一人当たり貿易額変化、推計モデル、及び使用統計
①都道府県別製造業労働者一人当たり貿易額変化
都道府県別製造業労働者一人当たり輸出額変化(ΔEXPit)及び都道府県別製造業労働者一人当たり輸入額変化(ΔIXPit)の定義は、Autor, et al.(2013)及び Dauth, et al.(2014)を参照している。
あるt年に都道府県iで製造業に従事している労働者数をLitとして、同都道府県で製造業の業種jに従事している労働者数をLijtとすると、これらの比率Lijtt/Litは都道府県iにおける業種jの労働者割合(都道府県別製造業種労働者割合)を表すことになる。
また、あるt年とそれ以前のt-1年の間の産業jにおける輸出額又は輸入額の変化をそれぞれΔXjt又はΔMjtで表して、全国で製造業の業種jに従事している労働者数をLjtとすると、これらの比率ΔXjt/Ljt又はΔMjt/Ljtはそれぞれ製造業の業種jに従事している労働者一人当たりの輸出額変化又は輸入額変化を表すことになる。
これらの都道府県別製造業種労働者割合Lijt/Litと製造業種労働者一人当たり輸出額変化ΔXjt/Ljt又は同輸入額変化ΔMjt/Ljtの積は、都道府県の製造業種ごとに労働者一人当たり輸出額変化又は輸入額変化を表すものになる。
(都道府県別製造業種労働者一人当たり輸出額変化)

(都道府県別製造業種労働者一人当たり輸入額変化)

本分析では、都道府県を主体として注目していることから、都道府県別に製造業種労働者一人当たり輸出額(輸入額)変化の製造業種を合計して、都道府県別製造業労働者一人当たり輸出額変化及び都道府県別製造業労働者一人当たり輸入額変化を、次のとおり定義している。
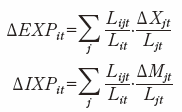
②推計モデル
ある都道府県iにおける製造業雇用者割合の変化(ΔLit)を被説明変数として、都道府県別製造業労働者一人当たり輸出額変化又は都道府県別製造業労働者一人当たり輸入額変化、及び地域属性Xtを説明変数とするパネル推計モデルを用いてパラメータを推定している。
(輸入) ΔLit=αt+β1ΔIXPit+X'itβ2+eit
(輸出) ΔLit=αt+β1ΔEXPit+X'itβ2+eit
なお、都道府県別製造業労働者一人当たり輸入額変化と都道府県別製造業労働者一人当たり輸出額変化の間に強い相関(0.889)があったため、多重共線性を避けることを意図して推計式を別立てにしている4。
また、Autor, et al.(2013)及び Dauth, et al.(2014)は都道府県別製造業労働者一人当たり貿易額変化を操作変数とする操作変数法の二段階最小自乗推計になっているが、本分析では貿易相手国を特定しない形で世界との貿易を分析対象としていることから、通常の最小自乗推計としている。
地域変数は、Autor, et al.(2013)を参照して、我が国において同様の性質を有すると考えられる変数を地域変数として加えている。我が国の統計で補足できない変数は一部捨象又は代替している。推計にあたっては、いずれの地域変数も各期の期首時点の数値である(例えば、1990年と1995年の変化を推計する場合、地域変数の期首年は1990年となる)。製造業労働者割合は、雇用面で見た地域属性を表している。大学卒・大学院修了者割合は、高等教育を修めた人材の規模を表していることから、都道府県の知的水準の変数となる。外国人割合は、Autor, et al.(2013)では移民割合になっているが、我が国の移民数は少ないことから、都道府県人口に占める外国人登録者数を外国人割合としている。女性労働者割合は女性の労働参加を表す地域属性変数である5。
③使用統計等
貿易統計は、財務省「貿易統計」(1990~1993年)及びGlobal Trade Atlas(1994~2007年)を使用している。なお、貿易統計の通貨換算は、Thomson Reuters発表の日次終値から算出した年平均レートを用いている。都道府県産業別労働者数は、RIETI「JIPデータベース」及び「R-JIPデータベース」を使用している。都道府県別人口総数及び都道府県別生産年齢人口は、総務省「国勢調査」及び「人口推計」を使用している。最終学歴人口及び女性労働者数は、総務省「国勢調査」を使用している。なお、最終学歴人口及び女性労働者数に関して非調査年の欠測値については前後の調査年の数値に基づいて線形補間している。外国人登録者数は、法務省「在留外国人統計」を使用している。
都道府県別製造業労働者一人当たり貿易額変化の算出、及び都道府県別製造業労働者一人当たり貿易額変化による製造業労働者割合変化の推計にあたっての貿易品目分類と産業分類の対応付は、総務省「平成23年(2011年)産業連関表-貿易統計コード対応表」、RIETI「産業連関表基本分類(1995年)、JIP分類、日本標準産業分類細分類(第11回改訂)、国際標準産業分類(Rev.3)、EUKLEMS分類との対応表」、及び徳井他(2013)6に基づいて対応表を作成した。
4 Dauth, et al.(2014)は地域労働者一人当たり輸出額変化と地域労働者一人当たり輸入額変化を1 本の推計式に入れて推定している。
5 我が国において地域的な属性を詳細に分析するためには、年齢階級に留意する必要がある(Abe(2016))。例えば、日本海側の地域における壮年期(55歳以上)の女性就業率が、その他地域の就業率の高さと逆転することは有名である。
6 徳井他(2013)。
補論5 直接輸出による業績改善効果
本補論では、直接輸出による業績改善効果について、輸出が伸びた内容ごとに分類して確認する。
対象業種は製造業とし、2010年から2014年の輸出額の伸びに基づき企業を区分する。業績改善は2010年から2014年の変化に基づく。
まず、輸出している内容ごとに企業をカテゴリー区分しその企業割合を確認すると、モノとサービスの両方を輸出している企業は、大企業の54%を占めるが、中小企業では10%にとどまる(補論第5-1表)。大企業の多くは、モノだけでなく技術取引をはじめとするサービスを海外に輸出しており、モノだけを輸出している企業、またサービスだけを輸出している企業を合わせると全体の85%が輸出を行っていることが分かる。
一方、中小企業に占める輸出企業の割合は43%と小さいが、企業数で見れば中小企業は多く、モノとサービスの両方を輸出している企業の6割以上を中小企業が占め、モノだけを輸出している企業の8割以上を中小企業が占めている。
次に、輸出企業のうち、輸出額が伸びた品目ごとに企業をカテゴリー区分する。
モノが伸びた企業割合を見ると、モノとサービスの両方を輸出している企業のうち、66%がモノの輸出を伸ばしている(42%がモノ・サービス両方の輸出を伸ばし(伸びた輸出品カテゴリー「モノ&サービス」)、24%がモノの輸出を伸ばしている(同「モノ1」))。モノだけを輸出している企業についても、同じく66%の企業が輸出を伸ばしている(同「モノ2」)(補論第5-2表)。
モノ・サービスの両方を伸ばした企業割合を見ると、モノ・サービス両方を輸出している大企業と中堅企業では半数以上が該当する(同「モノ&サービス」)のに対し、中小企業では34%にとどまっている。
また、サービスの輸出が伸びている企業割合は、モノとサービスの両方を輸出している企業の61%(同「モノ&サービス」が42%、同「サービス1」が19%)、サービスだけを輸出している企業のうち39%(同「サービス2」)であった。
補論第5-1表 輸出カテゴリー別企業数と割合
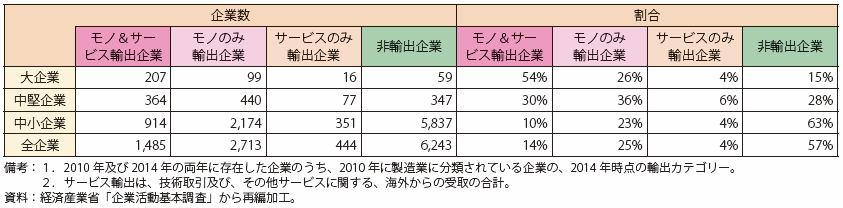
補論第5-2表 各輸出カテゴリーに占める、伸び品目別企業割合
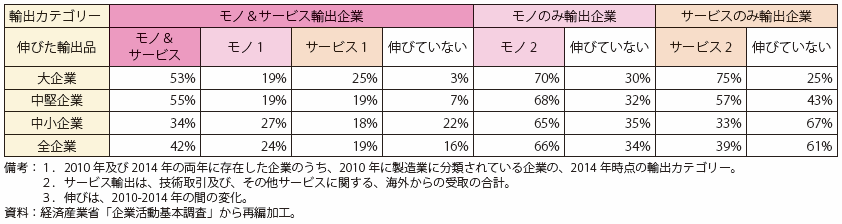
このように輸出が伸びた品目ごとに企業をカテゴリー区分した上で、業績改善度合いを見てみると、補論第5-3表のとおりとなる。
補論第5-3表 製造業企業の、業績改善企業割合(伸びた輸出品別)