

- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2018

- 白書2018(HTML版)

- 第1部 第2章 第3節 アジア
第3節 アジア
1.ASEAN
2017年に設立50周年を迎え、域内の経済統合や対外経済関係を更に深め行く東南アジア諸国連合(ASEAN)121の経済動向を概観する。
(1)経済統合の深化を目指すASEAN
ASEANは、2015年12月、「ASEAN経済共同体(AEC)」を設立し、1990年代から推進してきたASEAN10か国の経済統合に向けた一連の取組において大きな節目を迎えた。これまで、「AECブループリント2015」に基づき、モノ、サービス、資本、人の移動の自由化に向けた様々な取組が行われてきた。現在は、そこで達成した成果を踏まえ、2025年に向けてのASEAN統合のロードマップである「AECブループリント2025」に基づき、一層高度に統合された経済へ向けた制度・政策の構築を推進している(第Ⅰ-2-3-1-1表)。
第Ⅰ-2-3-1-1表 2025年に向けたASEAN統合のロードマップ(AECブループリント2025)
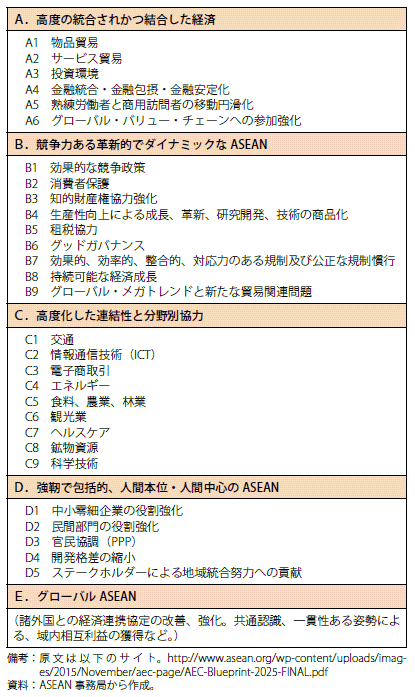
ASEANの人口は6億人を超え、米国の約2倍に該当する(第Ⅰ-2-3-1-2図)。また、名目GDPは日本の2分の1を超えている(第Ⅰ-2-3-1-3図)。一人当たりのGDPはまだ低水準にとどまっているものの、後発国を中心に今後上昇することが見込まれる(第Ⅰ-2-3-1-4図)122。また、財・サービスの貿易、対内直接投資の規模からも、ASEANは世界の成長の重要な一極を担っていることが分かる(第Ⅰ-2-3-1-5図)(第Ⅰ-2-3-1-6図)(第Ⅰ-2-3-1-7図)。
第Ⅰ-2-3-1-2図 ASEANの人口(主要国・地域との比較)
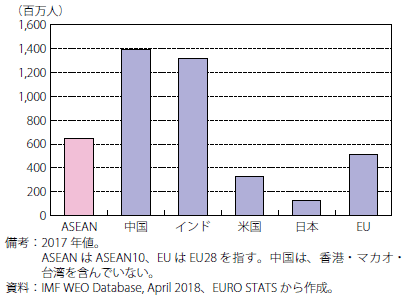
第Ⅰ-2-3-1-3図 ASEANの名目GDP?(主要国・地域との比較)
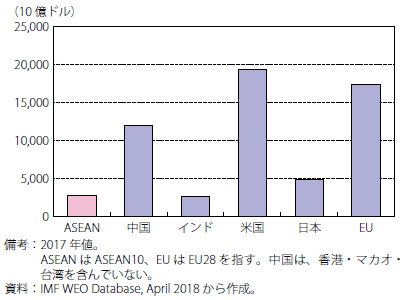
第Ⅰ-2-3-1-4図 ASEANの一人当たり名目GDP?(主要国・地域との比較)
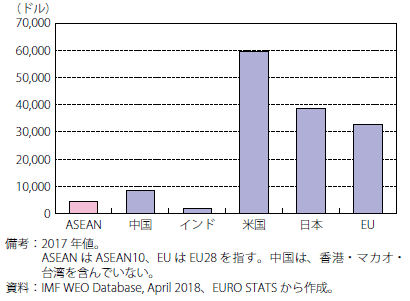
第Ⅰ-2-3-1-5図 ASEANの財貿易(輸出入)額(主要国・地域との比較)
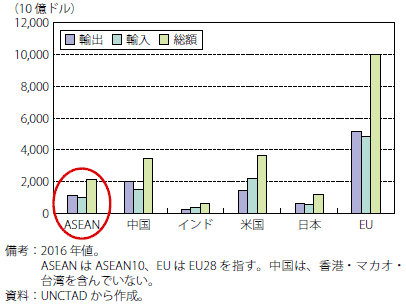
第Ⅰ-2-3-1-6図 ASEANのサービス貿易(輸出入)額(主要国・地域との比較)
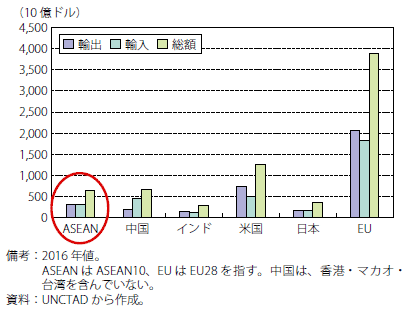
第Ⅰ-2-3-1-7図 ASEANの対内直接投資額(ストック)(主要国・地域との比較)
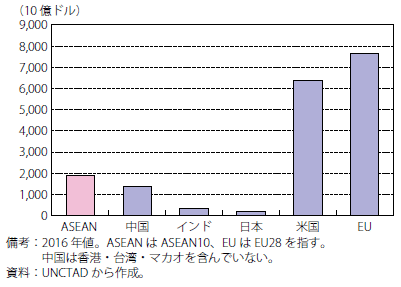
成長著しい東アジアと南アジアの間に位置するASEANは、個々の市場規模では小さいため、大規模かつ統合された市場を形成し、効率性を実現することで、今後、より競争力ある地域経済として存在感を維持、拡大していくことになろう。
121 1967年に設立された。原加盟国のインドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの5か国から、1984年にブルネイ、1995年にベトナム、1997年にラオスとミャンマー、1999年にカンボジアが加盟し、10か国へ拡大した。
122 ASEANの一人当たり名目GDPは、最上位のシンガポールと最下位のミャンマーで約46倍もの開きがある(IMF WEO 2018年4月版)。また、ASEAN事務局の公表によると、ASEANの一人当たり名目GDPは、2007年の2,373ドルから、2016年の4,034ドルと、10年間で70%上昇している。
(2)マクロ経済動向
IMFによると、2017年のASEANの経済成長率123は5.2%となり、前年の4.7%を大きく上回った(第Ⅰ-2-3-1-8図)。なお、ASEAN各国の成長率は以下である(第Ⅰ-2-3-1-9図)。
第Ⅰ-2-3-1-8図 ASEANの実質GDP成長率の推移(主要国・地域との比較)
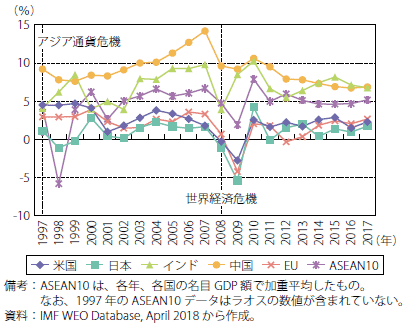
第Ⅰ-2-3-1-9図 ASEAN各国の実質GDP成長率の推移
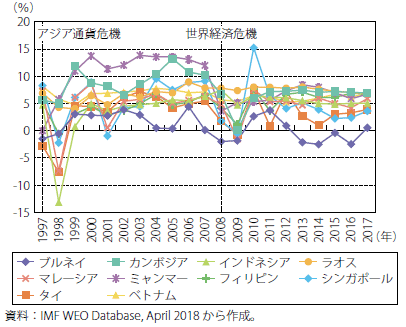
ASEANの経済成長(需要項目別)のけん引役は、所得上昇による旺盛な個人消費、インフラ開発に伴う投資(総固定資本形成)の増大、各国の強みを生かした輸出といえる。国により差はあるものの、総じて、個人消費は、変動幅が大きい投資や輸出と比べ、ASEAN成長に安定して寄与している(第Ⅰ-2-3-1-10図)。また、産業項目別にみると、サービス業の寄与度が最も大きく、製造業がそれに続いている(第Ⅰ-2-3-1-11図)。
第Ⅰ-2-3-1-10図 ASEAN主要国の実質GDP成長率及び需要項目別寄与度の推移
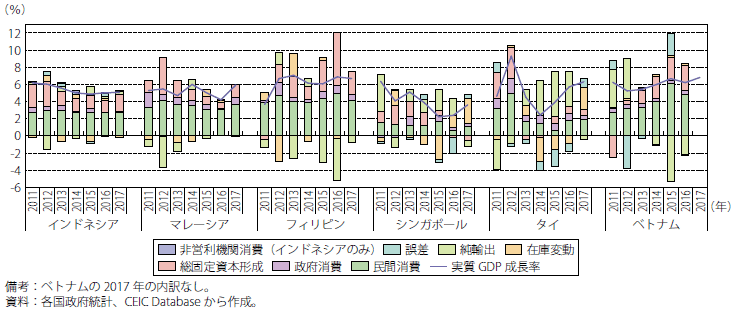
第Ⅰ-2-3-1-11図 ASEAN主要国の実質GDP成長率及び産業項目別寄与度の推移
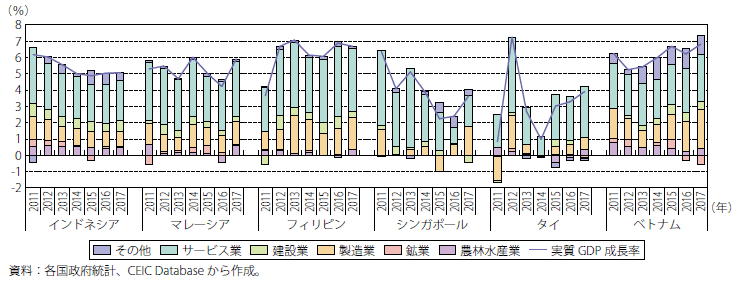
123 IMFで公表しているASEAN10か国の実質GDP成長率を各年・各国の名目GDP額で加重平均したもの。
(3)ASEAN貿易の推移
①域内貿易の底堅さと、中国依存度・貿易赤字の拡大
2000年代に入りASEANの対世界貿易は拡大している。2015年、2016年と、中国の景気減速、原油価格の下落等による世界的なスロートレード現象を背景に減少したものの、2017年は一転復調した。
ASEANの対世界輸出金額は、1998年から2017年の20年間で、3.9倍に増加した。対米国は2.1倍、対EUは2.6倍、対日本は2.8倍である一方、対中国は8.9倍と大きく増加した。なお、ASEAN域内貿易は足下で減少するものの、4.4倍と底堅く推移している(第Ⅰ-2-3-1-12図)。
第Ⅰ-2-3-1-12図 ASEANの輸出金額と輸出先の推移
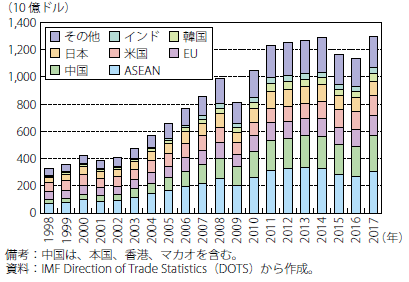
同期間、ASEANの相手国・地域別輸出先割合は、対米国が21%から11%、対EUが17%から11%、対日本が12%から8%と低下する一方、対中国が9%から20%と上昇した。なお、ASEAN域内貿易は、21%から24%と底堅く推移しているが、足下では低下傾向にある(第Ⅰ-2-3-1-13図)。
第Ⅰ-2-3-1-13図 ASEANの輸出先割合の推移
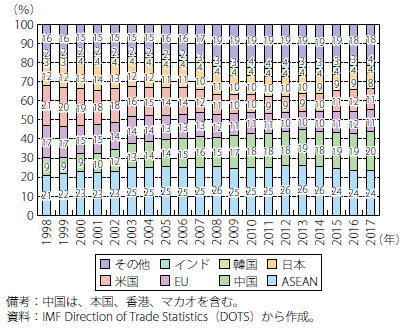
一方、ASEANの対世界輸入金額は、同期間で4.5倍に増加した。対米国は1.9倍、対日本は2.2倍、対EUは3倍である一方、対中国は13.9倍と大きく増加した。なお、ASEAN域内貿易は、4.6倍と底堅く推移している(第Ⅰ-2-3-1-14図)。
第Ⅰ-2-3-1-14図 ASEANの輸入金額と輸入先の推移
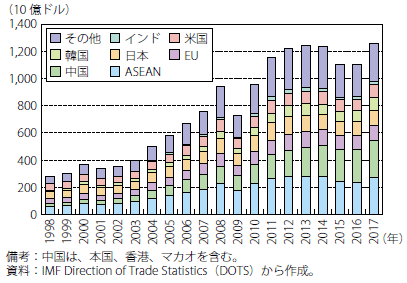
同期間、ASEANの相手国・地域別輸入先割合は、対米国が17%から7%、対日本が18%から9%、対EUが14%から9%と低下する一方、対中国が7%から21%と上昇した。なお、ASEAN域内貿易は、21%から22%とほぼ横ばいであるが、2006年、2007年の25%をピークに低下傾向にある(第Ⅰ-2-3-1-15図)。
第Ⅰ-2-3-1-15図 ASEANの輸入先割合の推移
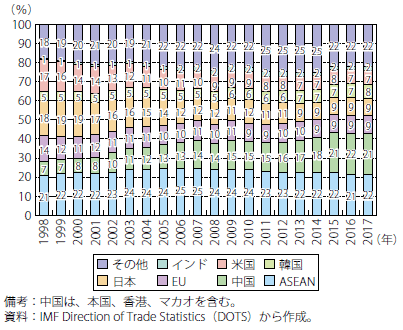
以上より、ASEANの主要貿易国だった米国、EU、日本の割合が縮小する一方、中国の存在感が拡大したことが分かる。これは、2001年のWTO加盟を背景に、中国が高い経済成長とともに貿易額も大きく伸ばしたこと、2005年発効のASEAN中国自由貿易地域(ACFTA)によるASEAN中国間の経済的相互依存関係の深化等が関係していると思われる。
なお、ASEAN物品自由貿易協定(ATIGA)により、原則2010年までの関税撤廃(後発国については2015年まで)が進捗したASEAN域内貿易は、金額では底堅く推移しているといえるが、シェアとしては中国に奪われつつあるという一面が見える。
次に、1996年から2016年で、ASEAN主要6か国124の貿易相手国の推移(順位・金額・割合)を見ると、中国への依存度は上昇している。各国にとって、中国は1、2位の輸出相手国になっており、4位であるフィリピンでさえ、輸出総額に占める中国の割合は高い(第Ⅰ-2-3-1-16表)。同様に、各国にとって、中国は1位の輸入相手国になっている(第Ⅰ-2-3-1-17表)。
第Ⅰ-2-3-1-16表 ASEAN主要6カ国の輸出相手国上位10か国の推移
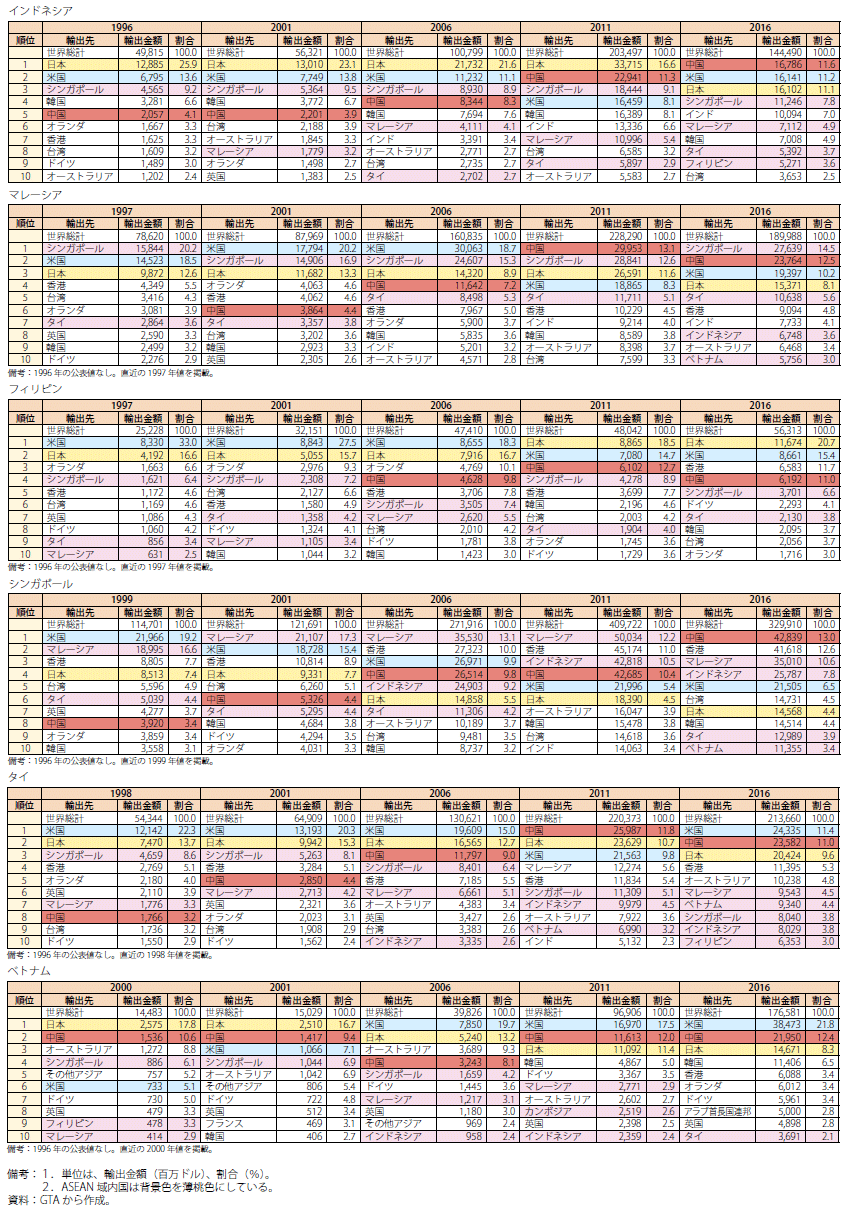
第Ⅰ-2-3-1-17表 ASEAN主要6カ国の輸入相手国上位10か国の推移
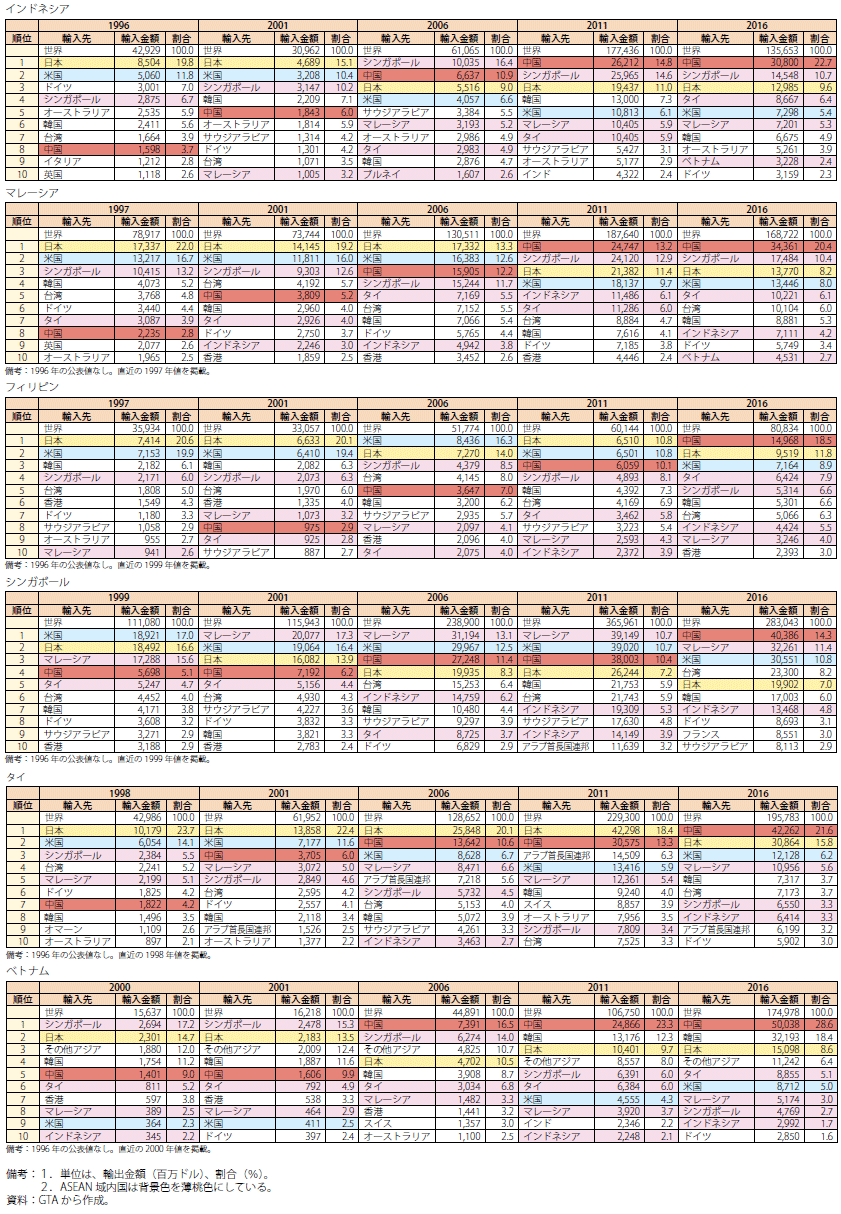
なお、ASEAN各国と中国との貿易総額125と、輸出入それぞれの中国依存度をプロットすると、後発国のカンボジア、ラオス、ミャンマーは、貿易総額が相対的に小さく中国の影響度が大きいこと、ベトナムは、後発国であるにもかかわらずシンガポールと同規模の貿易総額であること、輸出より輸入の依存度が高い国が多いこと等が分かる(第Ⅰ-2-3-1-18図)。
第Ⅰ-2-3-1-18図 ASEAN各国の貿易に占める中国の割合
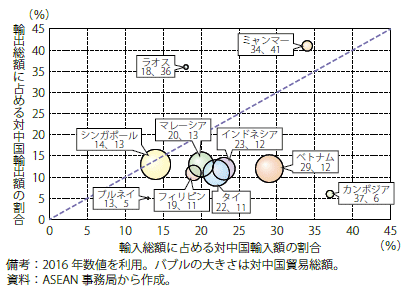
以上より、ASEAN貿易に占める中国依存度は高く、個人消費、輸出が成長の主な原動力であるASEAN経済は、中国経済の動向と密接に連動する状況になっている。
次に、ASEAN対中国の貿易収支126の推移を確認する。対中国の貿易赤字は増加傾向であり、特に、世界経済危機の影響を受けた2010年以降、急速に拡大している(第Ⅰ-2-3-1-19図)(第Ⅰ-2-3-1-20図)。
第Ⅰ-2-3-1-19図 ASEANの対中国貿易の推移
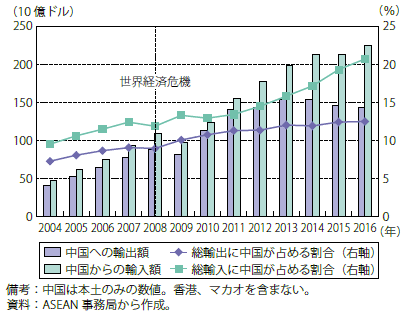
第Ⅰ-2-3-1-20図 ASEANの対中国貿易収支の推移
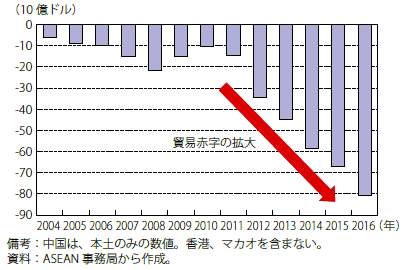
なお、貿易収支の内訳を2007年と2016年で比較すると、貿易赤字拡大の要因である品目は、一般機械及びその部品(HS84)、電気機械及びその部品(HS85)、鉄鋼(HS72)、鉄鋼製品(HS73)であることが分かる(第Ⅰ-2-3-1-21図)。
第Ⅰ-2-3-1-21図 ASEANの対中国貿易収支の品目別内訳(2007年と2016年の比較)
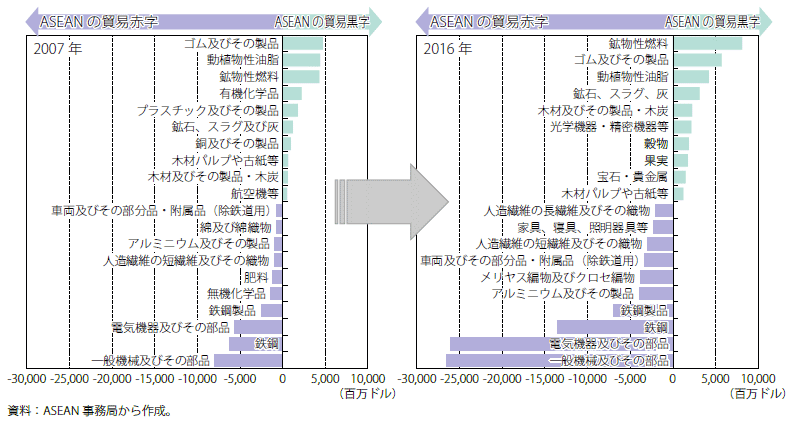
124 インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムを指す。
125 ASEAN事務局の公表値を利用。
126 ASEAN事務局の公表値を利用。
②中国との貿易構造の変遷
次に、ASEANと中国の貿易構造の変遷を、品目の変遷や中間財貿易の状況なども踏まえながら見てみる。
まず、分業モデルの代表例を挙げる(第Ⅰ-2-3-1-22図)。貿易(分業)は、一般的に、大きく分けて「垂直型」と「水平型」の2つがある。「垂直型」は、先進国と開発途上国間の工業製品と一次産品の取引が典型的であり、工業製品の付加価値が一次産品より高いことが想定される。一方、「水平型」は、タイプ1(工業製品の異業種間の取引)、タイプ2(工業製品の同一業種内の取引)、タイプ3(一つの製品を生産するために、その部品などを取引)が代表的な例として挙げられる。
第Ⅰ-2-3-1-22図 垂直型分業と水平型分業のモデル
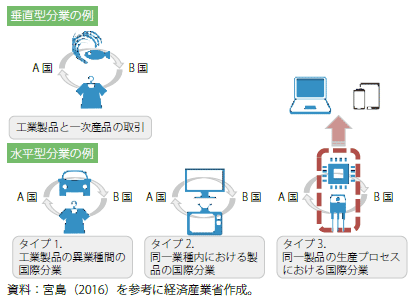
1997年から2017年まで、ASEANの対中国貿易上位10品目の推移をHSコード4桁分類で確認する。
輸出については、1997年時点で、一次産品とその加工品が大きな割合を占めている。具体的には、1位の石油精製品、2位の原油、10位の軽油が石油関連製品であり、4位のパーム油、6位の天然ゴムが農産物関連製品であり、5位の合板は木材関連製品である。なおIT関連製品(最終財・部品どちらも含む。以下同様。)では、3位にコンピュータ部品、7位に集積回路が登場してきているが、まだ、総輸出金額に占めるシェアは小さかった(第Ⅰ-2-3-1-23表)。
第Ⅰ-2-3-1-23表 ASEANの対中国輸出上位10品目の推移
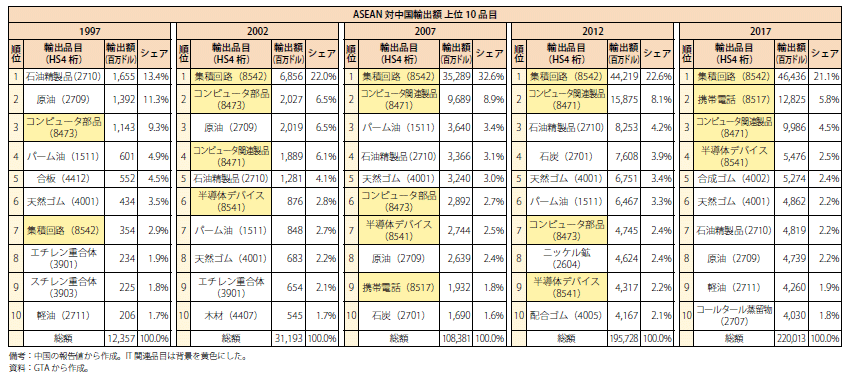
一方、輸入については、1997年時点で、4位の客船・貨物船等、6位の鉄鋼半製品等工業製品が主である他、1位のコンピュータ部品を筆頭に、輸入上位10品目のうち3品目がIT関連製品となっている(第Ⅰ-2-3-1-24表)。
第Ⅰ-2-3-1-24表 ASEANの対中国輸入上位10品目の推移
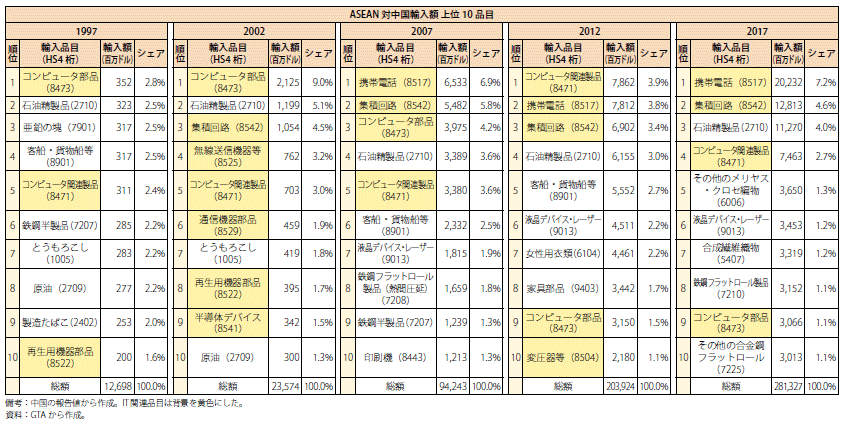
これが、2000年代に入ると、輸出入ともに、年々IT関連製品の貿易金額は増加し、全貿易品目に占めるシェアも上昇した。特に、コンピュータ関連製品(HS8471)、コンピュータ部品(HS8473)、集積回路(HS8542)が目立つ。なお、足下の変化としては、2006年時点ではランキングに登場していなかった携帯電話(8517)(最終財、部品どちらも含む。以下同様。)が、2007年に、輸出では9位、輸入では1位に急浮上していることが挙げられる。
ASEANと中国は、IT関連製品を互いに輸出入しながら、これを生産する「水平型分業」を急速に発展させた。同じHSコードのIT関連機器が輸出入どちらの主要品目にもなっていることから、これは、主に、第22図の水平型分業タイプ3に該当する。
しかし、上述のような水平型分業も存在する一方、ASEANは鉱物性燃料(主に、原油、軽油、石炭など)、天然ゴムといった一次産品関連の品目を中国に輸出し、石油精製品、繊維、鉄鋼、家具などといった工業製品を中国から輸入する、という従来の垂直型分業も引き続き存在し、むしろ足下で存在感を増しているように見える。
また、生産工程別127にASEAN対中国貿易の推移を確認すると、輸出は部品が、輸入は加工品が主力であることが分かる(第Ⅰ-2-3-1-25図)(第Ⅰ-2-3-1-26図)。
第Ⅰ-2-3-1-25図 ASEANの対中国輸出(生産工程別金額)の推移
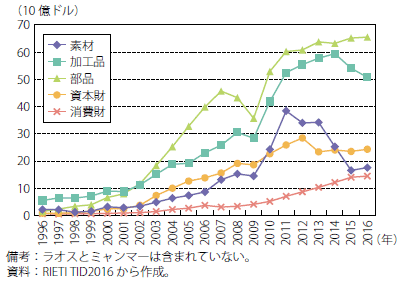
第Ⅰ-2-3-1-26図 ASEANの対中国輸入(生産工程別金額)の推移
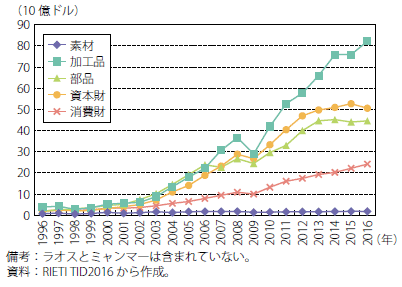
輸出割合は、1996年には14%であった部品が、2006年の45%のピークを経て、その後下落傾向にあったが、2015年以降は上昇している(第Ⅰ-2-3-1-27図)。なお、輸入割合は、加工品が上昇傾向にある(第Ⅰ-2-3-1-28図)。
第Ⅰ-2-3-1-27図 ASEANの対中国輸出(生産工程別割合)の推移
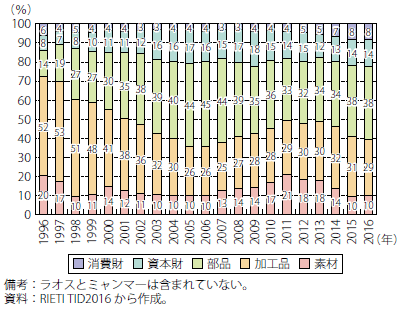
第Ⅰ-2-3-1-28図 ASEANの対中国輸入(生産工程別割合)の推移
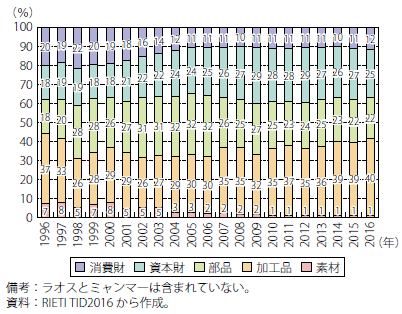
127 127 RIETI TID(2016)の分類法による。13分野に整理された産業を、さらに、素材、中間財(加工品、部品)、最終財(資本財、消費財)の3つのカテゴリー(5つのサブカテゴリー)に分類している。これは、国連のBEC(Broad Economic Categories)分類を基に、貿易財の生産工程における性質から各産業の貿易データを3つのカテゴリーに集約し、SNA(System of National Account)の基準により分類したものである。(https://www.rieti.go.jp/jp/projects/rieti-tid/)
さらに、生産工程別の内訳を検証すると、中間財(加工品・部品)、中でも電気機械の部品の相互貿易が多いことから、電気機械を中心に水平型分業タイプ3が発展しているといえる。これは、電気機械産業が東アジアに構築したグローバルバリューチェーンが関係していると思われる。
注目すべき点は、ASEANの輸出が、電気機械の中間財(部品)に大きく偏っていることである。今後、中国における電気機械の部品の内製化が進むと、ASEAN中国間の貿易構造を大きく変化させる可能性がある(第Ⅰ-2-3-1-29図)。
第Ⅰ-2-3-1-29図 ASEANの対中国輸出(生産工程別・品目別金額)(1996年、2006年、2016年の3時点)
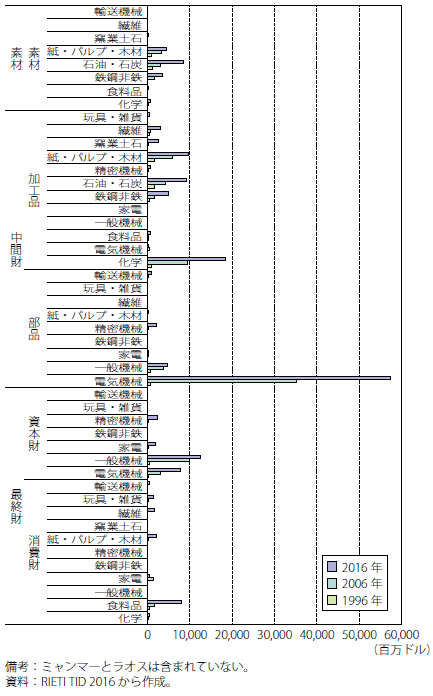
なお、鉄鋼非鉄の加工品、電気機械と一般機械(共に資本財)の中国からの輸入が多いことも注目できる。これらは、ASEANの旺盛なインフラ需要や個人消費が背景にあると考えられる(第Ⅰ-2-3-1-30図)。その他の特徴を含め、表にまとめた(第Ⅰ-2-3-1-31表)。
第Ⅰ-2-3-1-30図 ASEANの対中国輸入(生産工程別・品目別金額)(1996年、2006年、2016年の3時点)
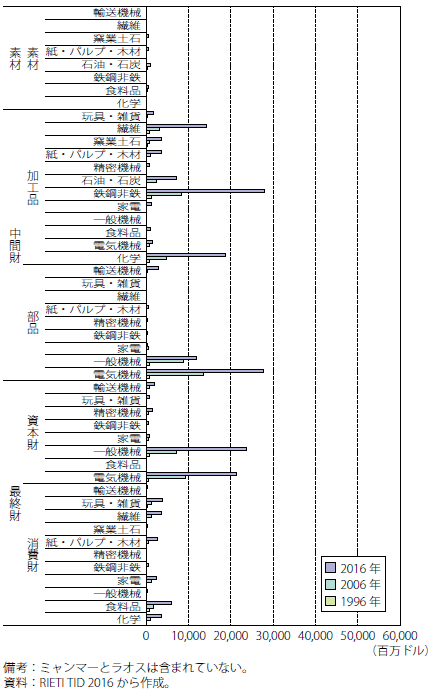
第Ⅰ-2-3-1-31表 ASEANの対中国貿易(生産工程別・品目別金額)の特徴
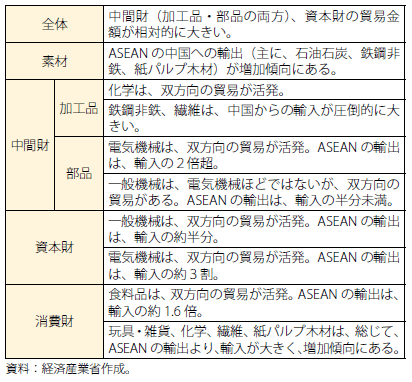
③中国との分業構造~産業内貿易指数による分析~
ここでは、産業内貿易指数(貿易特化係数)を用いて「水平型」「垂直型」貿易(分業)がどのように、どの程度、進展しているかを分析する手法128に従い、1996年から2017年までのASEANと中国の分業構造の変遷を検証する129。
まず、垂直型、水平型の2分類の割合を見ると、1996年で29%、1997年で30%しか占めていなかった水平型は、1998年に46%と急上昇し、2005年まで40%台を維持した。しかし、2006年以降、2014年の27%まで総じて低下し、垂直型の存在感が増した。2015年以降は一転上昇し、2017年では49%と垂直型と均衡するまでになった(第Ⅰ-2-3-1-32図)。
第Ⅰ-2-3-1-32図 ASEANの対中国貿易:産業内貿易指数による2分類の割合の推移
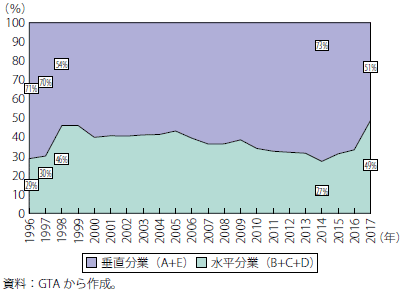
128 宮島・大泉(2008)の手法による。
129 GTAの中国側からの報告値を利用した。なお、HSコード4桁分類(全1,264品目)で指数を算出した。産業内貿易指数は、以下の式により算出される。
ASEANの対中国貿易の産業内貿易指数=(ASEANの輸出-ASEANの輸入)/(ASEANの輸出+ASEANの輸入)
産業内貿易指数は1から▲1までの数値をとり、1に近いほど、ASEANの輸出は中国に対して競争力があり、逆に、▲1に近いほど、ASEANの輸出は競争力がないことを示す。また、0に近い程、ASEANと中国が同一品目をお互いに取引(産業内貿易)していることを示す。指数を算出した上で、産業内貿易が貿易全体のどれくらいを占めるのかを明確にするために、係数の値の幅により、次の5つのカテゴリーに分ける。
A:ASEANが特に優位な品目(指数が0.6超)
B:ASEANがやや優位な品目(指数が0.2超0.6以下)
C:優位性が見極めにくい品目(指数が▲0.2以上0.2以下)
D:中国がやや優位な品目(指数が▲0.6以上▲0.2未満)
E:中国が特に優位な品目(指数が▲0.6未満)
上のカテゴリーごとにそれぞれの貿易総額に占める割合を計算し、このうち、B、C、Dを合算したものを「水平貿易(分業)指数」、A、Eを合算したものを「垂直貿易(分業)指数」とみなす方法である。
なお、その内訳である5分類の割合を見ると、1997年、1998年を除き、常に「ASEANが特に優位な品目」が、「中国が特に優位な品目」を上回っていたが、2012年以降は、逆に推移している(第Ⅰ-2-3-1-33図)。
第Ⅰ-2-3-1-33図 ASEANの対中国貿易:産業内貿易指数による5分類の割合の推移
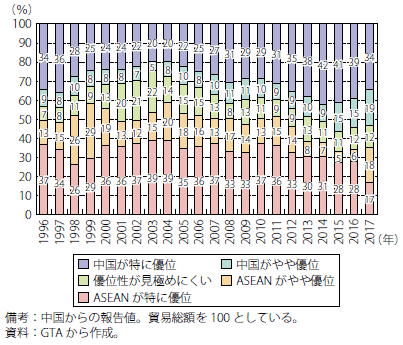
次に、第Ⅰ-2-3-1-32図と第Ⅰ-2-3-1-33図を金額ベースで見る。2000年代に入り、水平型が増加したものの、垂直型が常に水平型を上回っているほか、2009年以降2014年まで、垂直型が急増した。2015年以降は、一転、垂直型が急減し、2017年で、水平型とほぼ均衡した(第Ⅰ-2-3-1-34図)。
第Ⅰ-2-3-1-34図 ASEANの対中国貿易:垂直型分業と水平型分業の貿易額の推移
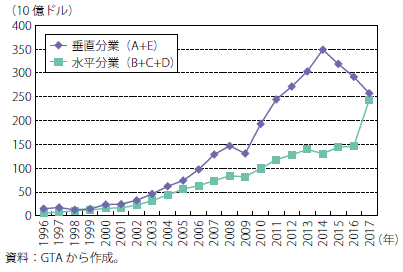
なお、その内訳である5分類の金額を見ると、2009年から2014年までの垂直型の増加には、「中国が特に優位な品目」が、また、2014年以降の水平型の増加には「ASEAN特に優位な品目」の減少が、主に寄与しており、「優位性が見極めにくい品目」は余り変化がなく、低い水準のままである(第Ⅰ-2-3-1-35図)。
第Ⅰ-2-3-1-35図 ASEANの対中国貿易:産業内貿易指数による5分類の貿易額の推移
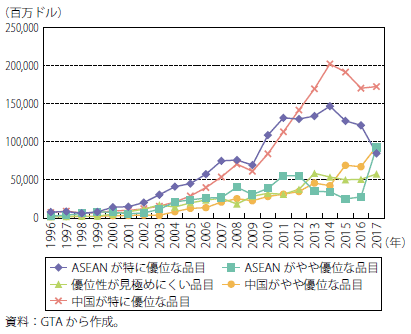
以下、第Ⅰ-2-3-1-35図を各国ベースに分類すると、各国で特徴が異なっている。大まかに4つのグループ(第Ⅰ-2-3-1-36図)に分けて掲載する。
第Ⅰ-2-3-1-36図 ASEAN各国の対中国貿易:分業タイプによるグルーピング(イメージ)
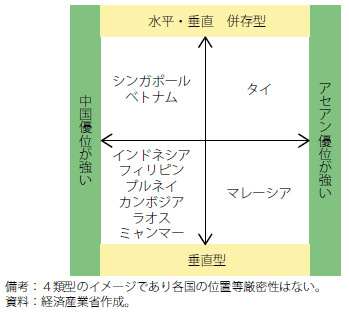
【水平垂直分業併存型 かつ 特に優位な品目の金額:ASEAN>中国】
第Ⅰ-2-3-1-37図 タイの対中国貿易:産業内貿易指数による5分類の貿易額の推移
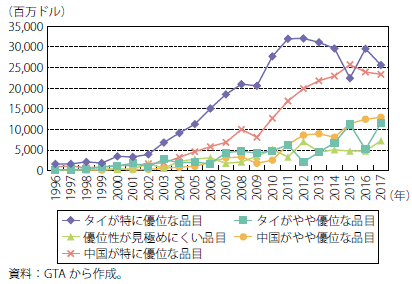
【水平垂直分業併存型 かつ 特に優位な品目の金額:中国>ASEAN】
第Ⅰ-2-3-1-38図 シンガポールの対中国貿易:産業内貿易指数による5分類の貿易額の推移
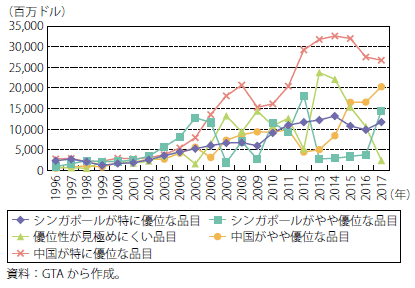
第Ⅰ-2-3-1-39図 ベトナムの対中国貿易:産業内貿易指数による5分類の貿易額の推移
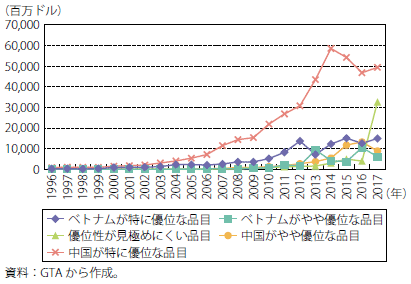
【垂直分業型 かつ 特に優位な品目の金額:ASEAN>中国】
第Ⅰ-2-3-1-40図 マレーシアの対中国貿易:産業内貿易指数による5分類の貿易額の推移
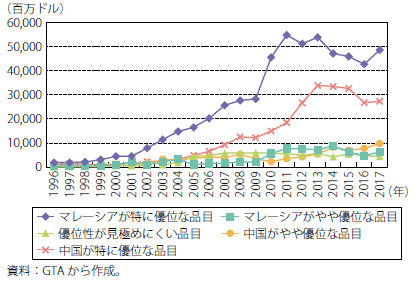
【垂直分業型 かつ 特に優位な品目の金額:中国>ASEAN】
第Ⅰ-2-3-1-41図 インドネシアの対中国貿易:産業内貿易指数による5分類の貿易額の推移
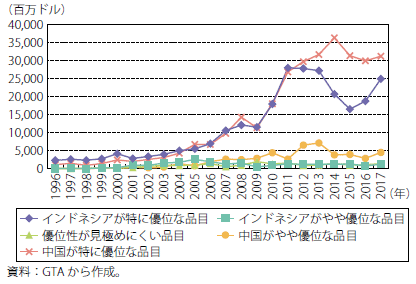
第Ⅰ-2-3-1-42図 フィリピンの対中国貿易:産業内貿易指数による5分類の貿易額の推移
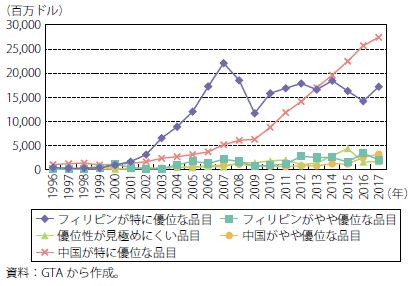
第Ⅰ-2-3-1-43図 カンボジアの対中国貿易:産業内貿易指数による5分類の貿易額の推移
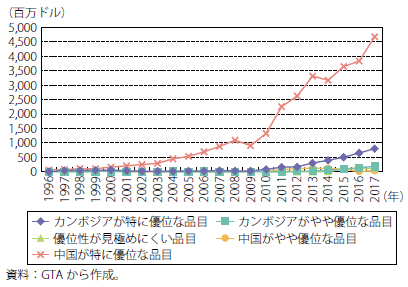
第Ⅰ-2-3-1-44図 ブルネイの対中国貿易:産業内貿易指数による5分類の貿易額の推移
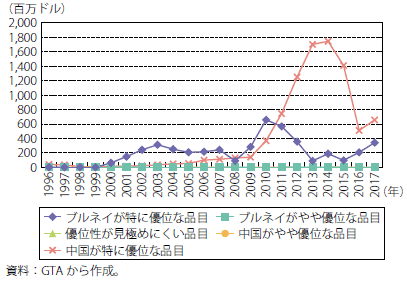
第Ⅰ-2-3-1-45図 ミャンマーの対中国貿易:産業内貿易指数による5分類の貿易額の推移
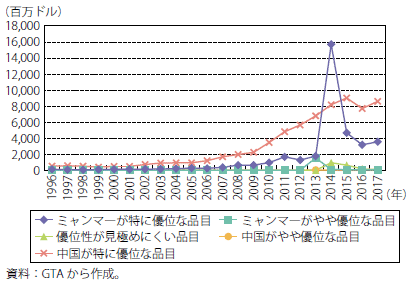
第Ⅰ-2-3-1-46図 ラオスの対中国貿易:産業内貿易指数による5分類の貿易額の推移
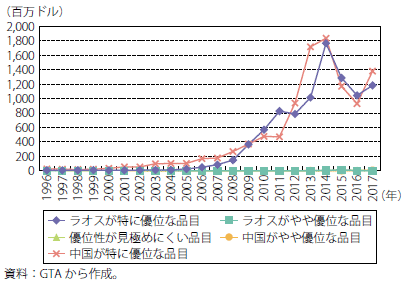
以上のASEAN対中国貿易の検証から、以下が考えられる。
- 2000年以前のASEAN対中国貿易は、天然資源や農産品、それらの加工品などを輸出する一方、工業品を輸入する、という垂直型分業の特徴が色濃かったが、2000年代以降、世界的なIT関連製品の需要増を背景に、輸出入ともにIT関連製品が主役となったことで、水平型分業も大きく進展した。
- 水平型分業が進展したとはいえ、垂直型分業は、常に、水平型分業を上回っており、2009年以降は、更に存在感が増している。これは、ASEANは、一次産品(例:タイの天然ゴム、マレーシアのパームオイル、インドネシアの原油)など、伝統的に競争力を持つ品目が、変わらず対中国貿易の強みであるからだろう。また、近年はカンボジア、ラオス、ミャンマーといったASEAN後発国が中国と完全に近い垂直型分業関係を強めていることで、ASEAN全体としても、その傾向が強くなっている面もあろう。
- なお、一次産品と工業品を貿易する垂直型分業では、工業品がより付加価値が高いことが想定されるため、これが、対中国貿易赤字拡大の一つの要因と考えられる。これを解消するためには、ASEAN、特に一次産品に富む国々は、その強みを生かしつつも、産業高度化を図る必要がある。
- 2015年以降、水平型分業が再び上昇し、2017年では、垂直型、水平型が均衡するまでとなった。これは、原油等資源価格の低下や中国の景気減退といった外的要因の影響が大きいと思われるが、分業の新たな局面も反映している可能性もある。
- 2015年以降の水平型分業の上昇要因を検証すると、主に、ベトナムの携帯電話(HS8517)、集積回路(HS8542)130、タイのコンピュータ関連製品(HS8471)131、シンガポールの集積回路(HS8542)132が寄与していることが検証できる(第Ⅰ-2-3-1-47図~第Ⅰ-2-3-1-50図)。いずれも、対象品目の貿易構造が急激に変化したことが見てとれる。
- 急激な貿易構造の変化の裏には、世界的な需要の増減のほか、グローバル企業の立地選択によるサプライチェーンの変化などがあるものと考えられる。
第Ⅰ-2-3-1-47図 携帯電話(HS8517)にかかるベトナムの対中国貿易額の推移
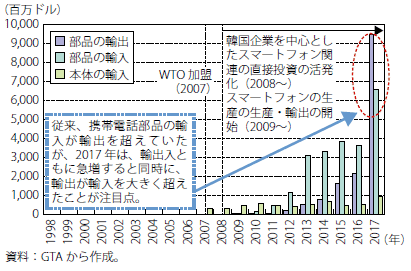
第Ⅰ-2-3-1-48図 集積回路(HS8542)にかかるベトナムの対中国貿易額の推移
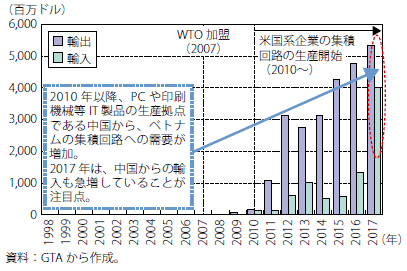
第Ⅰ-2-3-1-49図 コンピュータ製品(HS8471)にかかるタイの対中国貿易額の推移
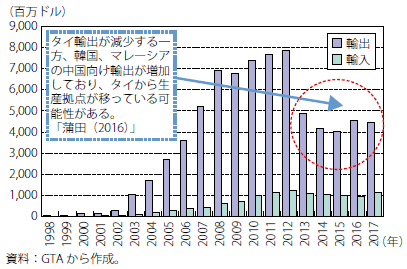
第Ⅰ-2-3-1-50図 集積回路(HS8542)にかかるシンガポールの対中国貿易額の推移
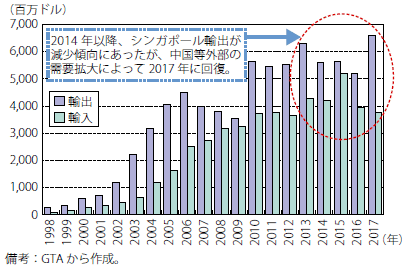
130 集積回路は、2015年は「ベトナムが特に優位な品目」、2016年は「ベトナムがやや優位な品目」、2017年は「優位が見極めにくい品目」と推移した。一方、携帯電話は、2015年は「中国が特に優位な品目」、2016年は「中国がやや優位な品目」、2017年は「優位が見極めにくい品目」と推移した。
131 コンピュータ関連製品は、2015年は「タイがやや優位な品目」、2016年は「タイが特に優位な品目」、2017年は「タイがやや優位な品目」と推移した。
132 集積回路は、2015年、2016年は「優位が見極めにくい品目」、2017年は「シンガポールがやや優位な品目」と推移した。
(4)ASEAN外国直接投資の推移
ASEANの貿易拡大、国際的分業の深化について上述したが、これは、外国直接投資の活発化と密接に関わっている。ASEANの経済発展、工業化には、外国直接投資が大きな役割を果たしてきたからだ。ここでは、ASEANの外国直接投資の変遷を検証する。
①ASEANの対内直接投資
1996年から2016年までの約20年間、世界からASEANへの対内直接投資額(フローベース)は、1997年のアジア通貨危機、2008年の世界経済危機、自然災害等の影響で一時的な減少も見られたが、2014年までは総じて増加傾向にあった。足元の2015年、2016年では減少している。なお、ストックベースでは、20年間一貫して増加している(第Ⅰ-2-3-1-51図)。
第Ⅰ-2-3-1-51図 ASEANの世界からの対内直接投資額(フロー・ストック)の推移
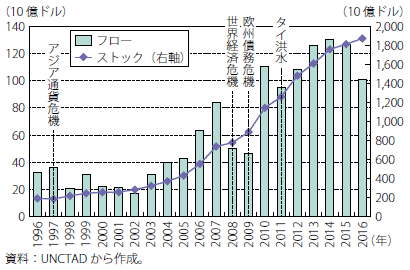
ASEANへの対内直接投資額を投資国別に見る。
2016年は、投資額が多い順に、EU(全体の33%)、ASEAN域内(25%)、米国(12%)、日本(12%)、中国(10%)、韓国(6%)となっている。なお、直近7年間の推移を見ると、欧州債務危機のあった2012年を除き、EUからの投資は存在感が大きいほか、ASEAN域内からの投資も堅調に推移しており、特に2016年は共に大きく増加した。中国からの投資も2016年に大きく増加し、米国、日本の投資額と比肩している点も注目される(第Ⅰ-2-3-1-52図)(第Ⅰ-2-3-1-53図)。
第Ⅰ-2-3-1-52図 ASEANの世界からの対内直接投資額(フロー)の推移(投資元別)
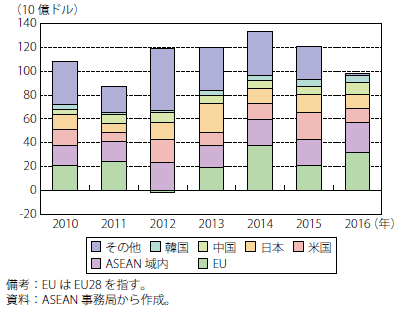
第Ⅰ-2-3-1-53図 ASEANの世界からの対内直接投資割合(フロー)の推移(投資元別)
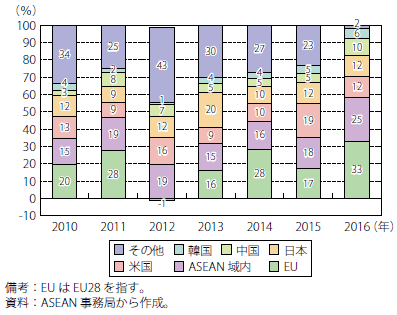
次に、ASEANへの対内直接投資額を業種別に見る。
2016年は、投資額が多い順に、金融保険業(全体の35%)、卸売・小売・自動車オートバイ修理業(20%)、不動産業(9%)、製造業(8%)となっている。2013年以降、金融保険業の割合が年々上昇している一方で、製造業の割合が年々下降していることから、製造業からサービス業へのシフトが読み取れる(第Ⅰ-2-3-1-54図)(第Ⅰ-2-3-1-55図)。
第Ⅰ-2-3-1-54図 ASEANの世界からの対内直接投資額(フロー)の推移(業種別)
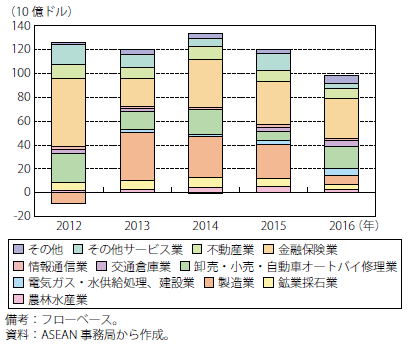
第Ⅰ-2-3-1-55図 ASEANの世界からの対内直接投資割合(フロー)の推移(業種別)
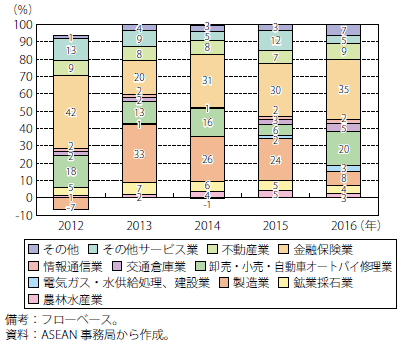
次に、ASEANへの対内直接投資がASEANのどの国へ向かっているかを確認する。
2007年~2016年の10年間のフローを単純平均すると、シンガポールが53%と過半数を占めており、インドネシアが14%、マレーシアが9%、ベトナムが9%、タイが8%、フィリピンが3%と続く(第Ⅰ-2-3-1-56図)。同期間の推移を見ると、ベトナムは携帯電話の生産拠点となったことなどを背景に底堅く推移し、2016年では、シンガポールに次ぐ第2位の直接投資受入れ国となった(第Ⅰ-2-3-1-57図)
第Ⅰ-2-3-1-56図 ASEANへの対内直接投資額(フロー)に占める各国内訳
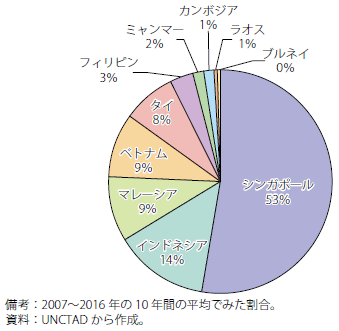
第Ⅰ-2-3-1-57図 ASEANへの対内直接投資額(フロー)の推移(各国別)
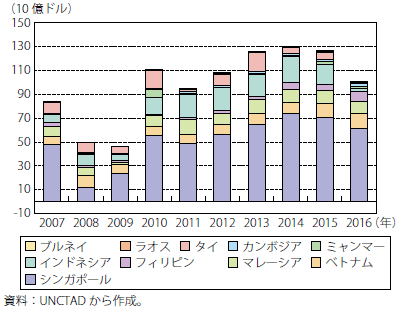
ASEANの対内直接投資面でも中国の存在感は大きくなっている。年によって異なるものの、先発主要国については、フィリピン以外で10%前後の割合を占めるほか、後発国では、ラオスが60%超、カンボジアとミャンマーが20~30%台と高い割合を占めており、中国から積極的に投資が行われていることが分かる(第Ⅰ-2-3-1-58図)(第Ⅰ-2-3-1-59表)。
第Ⅰ-2-3-1-58図 ASEANの対内直接投資額(フロー)に占める中国の割合と各国への投資額の推移
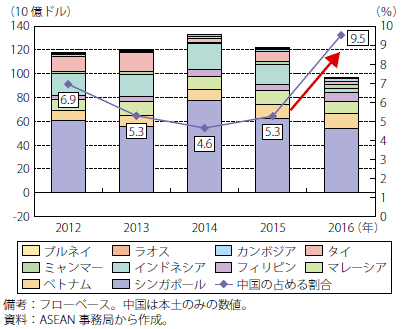
第Ⅰ-2-3-1-59表 ASEAN各国の対内直接投資額(フロー)に占める中国の割合の推移
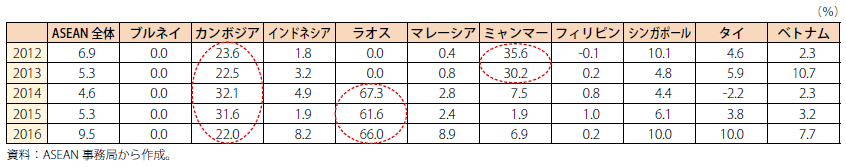
②ASEANの対外直接投資
ASEANの対外直接投資額は、対内直接投資額の約54%133(2016年ストックベース)に当たる。1996年から2016年までの20年間、ASEANの世界への対外直接投資額(フローベース)は、対内直接投資と同様、1997年のアジア通貨危機、2008年の世界経済危機、自然災害等の影響で一時的な減少も見られたが、2014年までは総じて増加傾向にあった。足元の2015年、2016年では減少している。なお、ストックベースでは、世界経済危機の影響があった2008年以外、20年間一貫して増加している(第Ⅰ-2-3-1-60図)。
第Ⅰ-2-3-1-60図 ASEANの世界への対外直接投資額(フロー・ストック)の推移
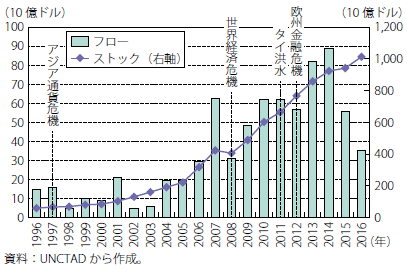
133 ASEANの対内直接投資額は約1.9兆ドル、対外直接投資額は約1兆ドル(いずれも2016年ベース、UNCTAD)。
ASEANの対外直接投資額の内訳を各国別に見る。
2007年から2016年の10年間を平均すると、投資額が多い順に、シンガポール(全体の55%)、マレーシア(22%)、タイ(11%)、インドネシア(6%)、フィリピン(4%)、ベトナム(2%)となっており、ブルネイ、カンボジア、ラオス、ミャンマーはほぼ0%である(第Ⅰ-2-3-1-61図)(第Ⅰ-2-3-1-62図)。
第Ⅰ-2-3-1-61図 対外直接投資額(フロー)に占めるASEAN各国の割合
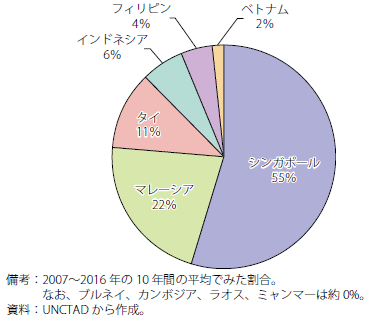
第Ⅰ-2-3-1-62図 ASEAN各国の対外直接投資額(フロー)の推移
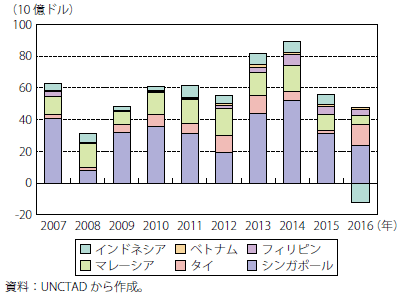
ASEAN各国の対外直接投資の推移から、ASEAN域内への投資割合を確認する。ASEAN事務局からASEAN全体としてのデータが公表されていないため、ここでは、対外直接投資の約9割を占める、シンガポール、マレーシア、タイの上位3か国分を国ごとに見ることとする。
シンガポールの対外直接投資額は、2007年から2016年までの10年間をみると、2015年を除き、年々増加している一方、ASEAN域内への投資割合が、2008年の23.7%から、年々なだらかに下降し、2016年は17.8%となっている(第Ⅰ-2-3-1-63図)。
第Ⅰ-2-3-1-63図 シンガポールの対外直接投資額(フロー)の推移(国・地域別)
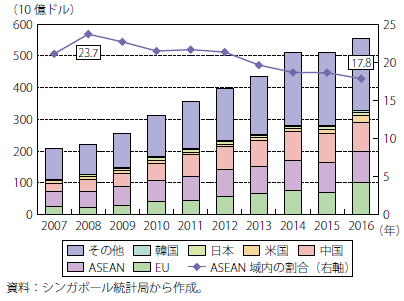
マレーシアの対外直接投資額は、総じて減少傾向にあり、ASEAN域内への投資割合も、2009年、2010年と40%を超えていたが、2016年は19.2%と低くなっている(第Ⅰ-2-3-1-64図)。
第Ⅰ-2-3-1-64図 マレーシアの対外直接投資額(フロー)の推移(国・地域別)
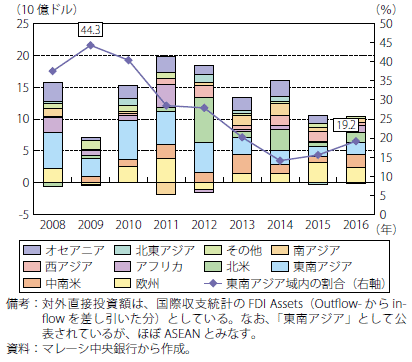
タイの対外直接投資額は、2011年以外、2007年から2012年まで増加したが、2013年以降2015年まで減少し、2016年は一転急増している。ASEAN域内への投資割合は、年ごとで不規則的な変動があるものの、2016年は35.4%と相対的に高いものとなっており、タイがASEAN域内への投資に重点をおいていることが分かる(第Ⅰ-2-3-1-65図)。
第Ⅰ-2-3-1-65図 タイの対外直接投資額(フロー)の推移(国・地域別)
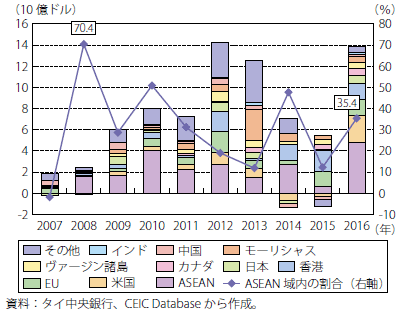
以上から、ASEANの対内・対外直接投資は、共に足下は鈍化しているものの、総じて底堅く推移しているといえる。一方、ASEAN域内での直接投資は、割合が低下傾向にあるなど、域内統合の勢いが伸び悩む面も見える。
ASEANがAECを設立した大きな目的の一つは、海外からの直接投資先に選ばれる地域になることである。AECブループリント2025では、第1の柱「高度に統合され結合した経済」の「3.投資環境」の中で、「ASEAN包括的投資協定(ACIA)により開放され透明で予測可能な投資レジームを設立することにより、グローバルな投資先としての魅力を高めること」が目標とされている。
2007年から2016年の10年間を平均すると、世界の外国直接投資は、EU(28%)、米国(15%)、中南米(10%)、中国(8%)、ASEAN(6%)、アフリカ(5%)、インド(2%)に向かっている(第Ⅰ-2-3-1-66図)。また、同期間の推移をみると、ASEANは中国と比肩する規模ではあるものの、緩やかな増加傾向にある中国とインドと比べると、足下で伸び悩みの傾向が見て取れる(第Ⅰ-2-3-1-67図)。
第Ⅰ-2-3-1-66図 世界の対外直接投資額(フロー)の投資先の国・地域別割合
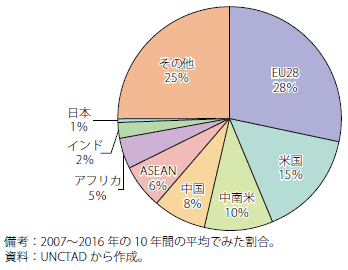
第Ⅰ-2-3-1-67図 世界の対外直接投資額(フロー)の投資先の国・地域別推移
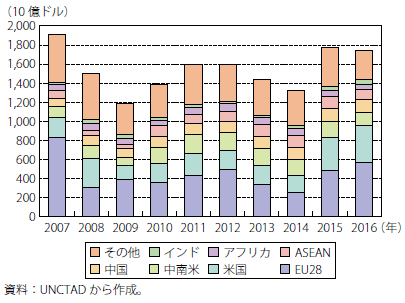
これまで、ASEANは、外資系企業による直接投資やオフショア・アウトソーシングを受け入れることで、生産拠点を集積させ、貿易を拡大し、経済成長につなげてきた。しかしながら、OECDが公表している海外直接投資制限指数134で、外資系企業の業務遂行に対する投資規制の度合いを確認すると、ASEANは、世界の水準と比較すると、まだ障壁が多く残っていることが分かる(第Ⅰ-2-3-1-68図)。また、ASEANにおいても、国によって大きく差がある。例えば、カンボジアはOECD加盟国平均よりも規制が緩い一方、フィリピンはASEANの中でも最も厳しいと評価されている。加えて、各国では各々保護育成したい産業があり、高い外資規制がかけられている(第Ⅰ-2-3-1-69図~第Ⅰ-2-3-1-76図)。
第Ⅰ-2-3-1-68図 ASEAN各国の海外直接投資制限指数(主産業における主要国・地域との比較)
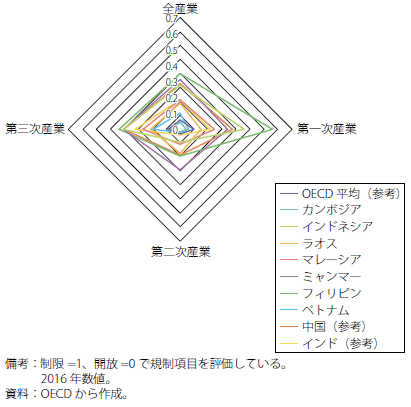
第Ⅰ-2-3-1-69図 カンボジアの海外直接投資制限指数(産業別)
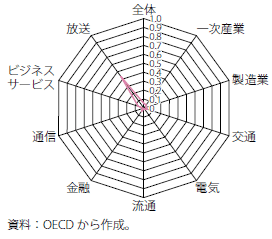
第Ⅰ-2-3-1-70図 インドネシアの海外直接投資制限指数(産業別)
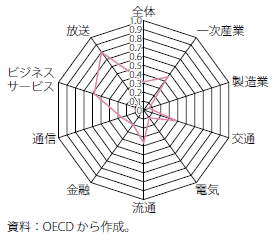
第Ⅰ-2-3-1-71図 マレーシアの海外直接投資制限指数(産業別)
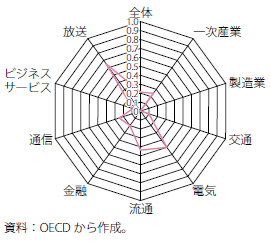
第Ⅰ-2-3-1-72図 ミャンマーの海外直接投資制限指数(産業別)
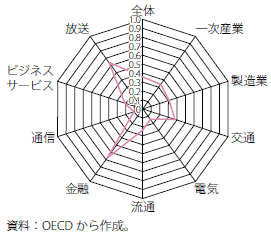
第Ⅰ-2-3-1-73図 ラオスの海外直接投資制限指数(産業別)
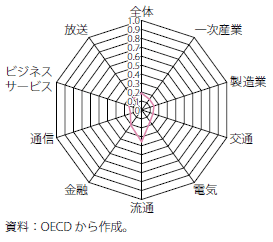
第Ⅰ-2-3-1-74図 フィリピンの海外直接投資制限指数(産業別)
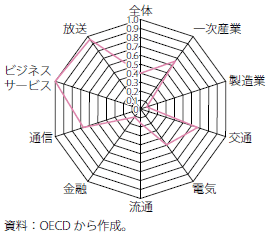
第Ⅰ-2-3-1-75図 ベトナムの海外直接投資制限指数(産業別)
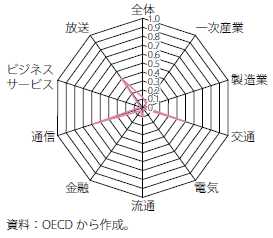
第Ⅰ-2-3-1-76図 OECD?(各国平均)の海外直接投資制限指数(産業別)
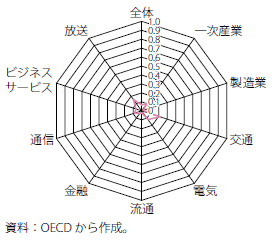
ASEANがこれまで以上に世界の直接投資先として選ばれるためには、ASEANとしてAFAS及びACIAによる自由化の着実な履行を進めると同時に、各国レベルでも個々の投資障壁を積極的に撤廃するといった海外投資誘致策の実施が肝要である。
134 海外直接投資に対する法的規制を測定し、OECDが公表している指標。62か国すべてのOECDとG20の国における外国直接投資の法定制限を測定し、22のセクターをカバーしている。具体的には、海外直接投資に対する主な4つの規制(①外資の持ち株制限、②差別的なスクリーニング又は承認メカニズム、③主要人材としての外国人雇用に関する制限、④その他、業務上の制限。)の見地から測定される。なお、0(オープン)が最も規制が弱く、1(クローズ)が最も規制が強い、として評価される。
(5)ASEANをめぐる自由貿易協定(FTA)
現在、ASEANは、域内FTAであるASEAN自由貿易地域(以下、AFTA)のほかに、域外対話国と5つのASEAN+1FTAを有している。ここでは、これらASEANをめぐるFTAを概観する。
①FTA形成が加速した背景と各FTAの概要
AFTA形成の発端は、1990年前後、「グローバル化」と「リージョナル化」が同時並行的に進行していたことが背景にある135。「グローバル化」は、多角的貿易交渉GATT(関税と貿易に関する一般協定)ウルグアイ・ラウンド合意の機運の高まりである136。また、「リージョナル化」は、南米のメルコスール、北米のNAFTA、欧州のEU設立である。さらに、中国では南巡講話を経て海外からの投資ブームが起こりつつあった。こういった世界的動向の中、当時のASEAN加盟国において、自らも地域統合を進め外国から投資を呼び込まなくては、という機運が生まれ、それが1993年発効のAFTAを誕生させることとなった。
2000年代に入ると、中国とのFTA(ACFTA)を皮切りに、次々とASEAN+1FTAが形成され、2005年から2010年の間に計5つが発効することとなった(第Ⅰ-2-3-1-77表)。これは、ASEANと中国との間の貿易自由化により、他の域外対話国が、ASEAN向けの輸出競争力が低下することを懸念し、ASEANとのFTA形成を急いだことが背景にある。
第Ⅰ-2-3-1-77表 ASEANをめぐるFTAの交渉開始、発効、関税削減完了年
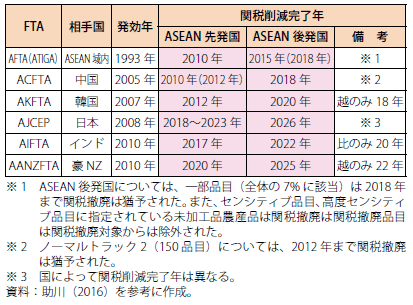
なお、各FTAの概要や近年の状況等は、発効順に以下の通りである。
135 助川(2016)
136 同ラウンドで、GATTはWTOに発展改組された。
ASEAN物品貿易協定(ATIGA)
当該FTAの核ともいえる物品貿易の関税削減、撤廃措置については、段階的かつ後発国に配慮した関税撤廃スケジュール137に従い、先行加盟国6か国については2010年1月までに、ほぼ全ての品目について関税が撤廃された。また、2018年1月、インクルージョンリスト(IL)の一部品目で猶予を与えられていた後発加盟国4か国(CLMV138)についても、一部の未加工農産品や武器及び鉄砲弾等を除き、一気に関税が撤廃された。この結果、後発加盟国の自由化率は、前年2017年の91.1%から、2018年の98.0%に向上し、AFTAの2018年の自由化率は98.8%と世界でも高い水準を達成した(第Ⅰ-2-3-1-78図)(第Ⅰ-2-3-1-79表)。
第Ⅰ-2-3-1-78図 ASEANの単純平均特恵税率の推移
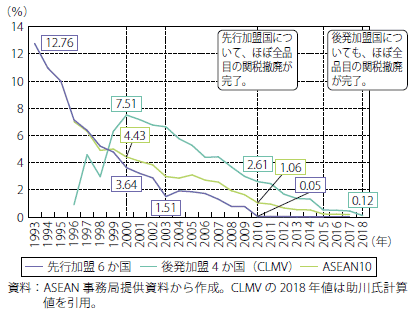
第Ⅰ-2-3-1-79表 ASEANをめぐるFTAの自由化水準
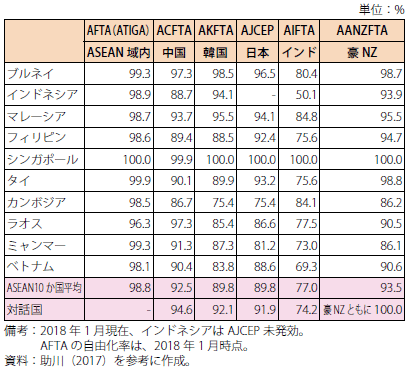
なお、関税面のみならず、サービス貿易はASEANサービス枠組み協定(AFAS)、投資はASEAN包括的投資協定(ACIA)によって、自由化を促進しているほか、人の移動に関しては、ASEAN自然人移動協定139が発効(2016年6月)しており、人材の域内移動の円滑化が図られた。
さらに、貿易投資関連の課題を直接企業が提起できる枠組みである「ASEAN投資・サービス・貿易解決システム(ASSIST)の導入(2016年8月)、2020年までに域内貿易にかかる取引費用を10%削減する目標の採択(2017年3月)といった運用面での改善も図られていることが注目される。
137 AFTA形成のための共通効果特恵関税(CEPT)協定では、全品目を、①適用品目(IL)、②一時的除外リスト(TEL:関税引下げ準備が整っていない品目)、③一般的除外品目(GEL:防衛、学術的価値から関税率削減対象としない品目)、④センシティブ品目(SL:未加工農産物等適用品目への移行を弾力的に行う品目)、⑤高度センシティブ品目(HSL:米関連品目等)に分類し、ILの関税削減、撤廃を行う。TEL、SL、HSLは順次ILに移行し、関税削減、撤廃を実施する。なお、CEPT協定に持ち込まれていなかった事項やルールを一本化したものが、2010年に発効したASEAN物品貿易協定(ATIGA)である。
138 後発加盟国4か国である、カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムは、頭文字をとってCLMVと呼ばれている。
139 域内のビジネスを目的とする出張者や事業拠点間を移動する幹部人材、専門人材に対し、通関手続の統一化、透明性の向上を目指すものであり、単純労働者は対象に含まれていない。
ASEAN-中国自由貿易地域(ACFTA)
ACFTA物品貿易協定における対象品目の分類は、AFTAの共通効果特恵関税(CEPT)に類似している140。さらに、AFTAにおけるASEAN先発国の適用品目(IL)の関税撤廃年と、ACFTAにおけるASEAN先発国と中国のノーマルトラック品目についての関税撤廃年が、同じ2010年に設定されたことから、利用が増加したと言われている。
2018年1月より、ASEAN後発国との間でも関税が原則撤廃された。加えて、関税撤廃の例外品目であったセンシティブ品目の関税がそれまでの20%以下から、一気に5%以下に引き下げられた。関税率が撤廃された品目は全体の94.8%を占め、関税率が5%以下の品目を加えると98.2%になる。他の国・地域と比較しても、中国のASEANに対する関税撤廃、引下げの水準は群を抜いている141。
近年の他の動きとしては、2016年7月に改訂議定書が発効したことが挙げられる。物品貿易章において、原産地規制の見直しとともに、新たに税関手続・貿易円滑化に係る節が設けられ、関税分類に関する事前教示制度が導入されるなど透明性の向上が図られた。また、サービス貿易章において、3回目となる譲許表の交換が行われたほか、技術協力章では電子商取引に関する記載が新規追加された。
140 全品目を、①アーリーハーベスト品目(農水産品)、②ノーマルトラック品目、③センシティブ品目、④高度センシティブ品目に分類している。
141 大泉(2018)
ASEAN-韓国自由貿易地域(AKFTA)
近年の動きとしては、2016年8月までに韓国、タイ、フィリピン、マレーシアを含む7か国で物品貿易第三改訂議定書が発効したことが挙げられる。これまで、ノーマルトラック品目とセンシティブトラック品目でそれぞれモダリティ(関税引下げ方式)のみ示されていた関税削減スケジュールが統合され、国ごとに品目別にリスト化されるなど、利便性の向上が図られた。
ASEAN-日本包括的経済連携協定(AJCEP)
近年の動きとしては、2017年11月にサービス貿易、投資に係る規定を追加する改訂議定書について閣僚レベルでの交渉が終結したほか、ASEAN10か国で唯一本協定による特恵関税が適用されていなかったインドネシアが、2018年3月から適用を開始することとなった。
ASEAN-インド自由貿易協定(AIFTA)
AIFTAは、品目数の80%及び貿易額の75%をノーマルトラックに指定、品目によって2013年末又は2016年末までに関税を撤廃するとした。また、総品目数の1割を占めるセンシティブ品目について、うち4%に当たる品目を2019年末に撤廃することとなっている。なお、2015年には、サービスと投資分野の協定が発効している。
ASEAN・豪州・ニュージーランド自由貿易協定(AANZFTA)
AANZFTAは、物品貿易、サービス貿易、投資、経済協力等のみならず、上の4つのFTAでは掲げられていなかったEコマース、人の移動、知的財産、競争政策などが初めて対象となったことに特徴がある。ASEAN先発国は2013年、後発加盟国は2020年以降に、9割前後の品目を無税化する。
その他の国・地域とのFTA
ASEANは、2017年11月に香港との間でFTAと投資協定を締結し、2019年1月発効の見通しとなっている。
②FTA形成による効果と今後の展開
各FTAの総品目に対する関税撤廃品目の割合は異なっており、ASEAN10か国平均の水準は、ATIGAが98.8%ともっとも高く、AANZFTAの93.5%、ACFTAの92.5%、AKFTAとAJCEPの89.8%、AIFTAの77%が続いている(第Ⅰ-2-3-1-79表)。
ATIGAの自由化度の高さは、ASEAN域内における分業体制の進展、各国産業の競争力の向上、市場のスケールメリットをアピールした外資企業の誘致といったメリットを生んでいるが、その一方、企業に選ばれる国、選ばれない国が生まれるという負の側面も否定できない。それゆえ、関税撤廃の代わりに非関税障壁を設け、国内産業保護を図るといった自由化に逆行する動きも見られる142。
なお、現在の焦点は、ASEAN+1を超えるFTAを目指し、交渉分野も物品貿易、サービス貿易、投資、経済技術協力、知的財産、競争、紛争解決を含む包括的FTAとなるRCEPである。RCEPを提案したASEANの役割は大きく、AECを深化させると同時にRCEPを推進し、アジア太平洋の地域経済枠組みにおいて、イニシアティブを発揮しようとしている。
142 例えば、自動車産業が未成熟なベトナムは、ATIGA等に基づき2018年から自動車の関税を撤廃したが、それと同時に、従来よりも輸入に必要な手続を煩雑にしたため、関税撤廃を実質上骨抜きにしていると批判をされた。
2.インド
2014年5月のモディ政権発足以来、2022年までの「新しいインド」の達成を掲げて、積極的に構造改革を進め、またデジタル経済が急速に発展するインドの経済動向を概観する。
(1)マクロ経済動向
①GDP(GVA143)
実質GDP成長率(年度ベース144。以下、前年比/前年同期比)は、2014年度から7~8%台と拡大した。2017年度は、2016年11月の高額紙幣廃止や、2017年7月のGST(物品・サービス税)導入という大改革の断行による混乱により、一時的な鈍化が見られた。しかし、官民による設備投資の復調により、第1四半期の5.7%を底に、第3四半期まで、再び拡大傾向にある。GDPの5~6割を占める民間消費の寄与は、足元でやや低下傾向にあるものの、底堅く推移している(第Ⅰ-2-3-2-1図)。
第Ⅰ-2-3-2-1図 インドの実質GDP成長率及び需要項目別寄与度の推移
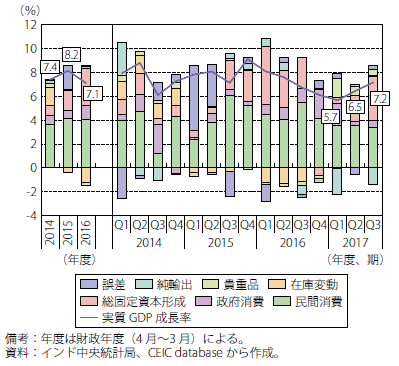
実質GVA成長率もGDPと同様の動きであり、主に、GVAの5~6割を占めるサービス業が寄与している。GVAの2割弱145を占める製造業は、「メイク・イン・インディア(インドでものづくりを)」キャンペーン146によって、大々的に外資系企業の誘致を図ったことが奏功し、2014年度、2015年度で寄与度が上昇した。その後、上述の構造改革による影響で2016年度の寄与度は鈍化、2017年第1四半期はマイナスとなったものの、第2、第3四半期は復調傾向にある(第Ⅰ-2-3-2-2図)。
第Ⅰ-2-3-2-2図 インドの実質GVA成長率及び産業項目別寄与度の推移
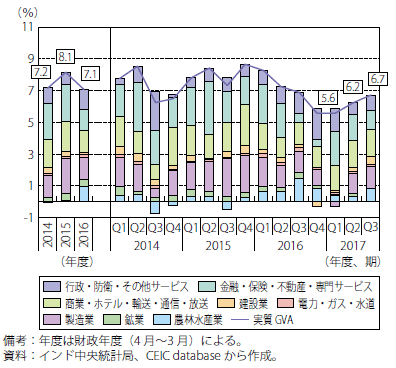
なお、IMFは、同国の実質GDP成長率を、2017年度は6.7%、2018年度は7.4%、2019年度は7.8%と、主要国の中でも最も高い成長を予想している(第Ⅰ-2-3-2-3図)。
第Ⅰ-2-3-2-3図 インドの実質GDP成長率の推移(主要国・地域との比較)
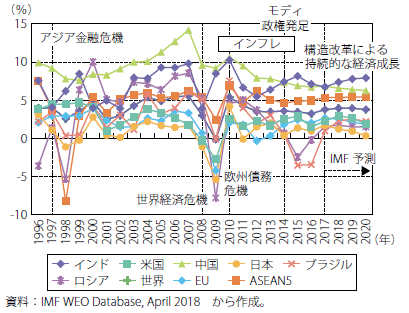
143 生産側から推計された実質総付加価値。純間接税に左右されるGDPより、月次景気指標に近い動きをするとして評価されている。
144 インドの財政年度は、日本と同様、4月から翌年3月である。
145 2017年度の製造業のGVAは全体の18.2%を占めている。
146 製造業のGDP比を当時の15%から25%に引き上げようという製造業振興政策。なお、現在は、「メイク・イン・インディア」を発展させた「メイク・イン・インディア2.0」が提唱されている。同計画では、今後、2桁成長が見込める分野として、「資本財、自動車、防衛産業、医薬品、再生エネルギー」の5分野を挙げている。
②貿易
貿易収支は赤字が常態であり、その増減は、輸入の約半分を占める原油価格に大きく左右されている。2013年以降、原油価格の低下等により赤字は縮小傾向にあったが、2017年は、原油価格の持ち直しのため再び赤字が拡大した。なお、2017年は、原油以外の品目147の内需拡大も、貿易赤字の拡大に寄与した(第Ⅰ-2-3-2-4図)。
第Ⅰ-2-3-2-4図 インドの貿易収支の推移
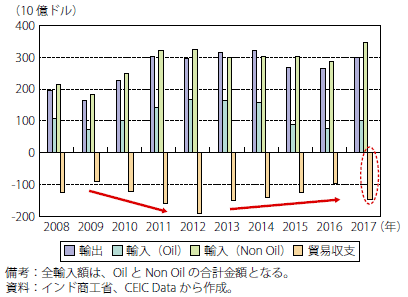
次に、貿易の主要相手国・地域と、主要品目の変化をみるために、2008年と2017年の2時点を比較する。
輸出先の1位は、アラブ首長国連邦に代わり米国となった。なお、米国の構成比は、11.5%から15.4%と拡大した。輸入先の1位は、2時点とも中国が1位であるが、その構成比は、10.5%から16.2%と拡大した。地域としては、EU28の構成比が輸出入ともに縮小した一方、ASEANが拡大した。また、SAARC148への輸出拡大も注目される(第Ⅰ-2-3-2-5表)。サプライチェーンの変化や、モディ政権の「近隣国第一政策」に基づく周辺国との関係強化や、「アクト・イースト政策」下でのASEANとの関係強化等により、今後も変化、深化する可能性がある。
第Ⅰ-2-3-2-5表 インドの貿易金額と構成比(主要国・地域別)の2時点比較
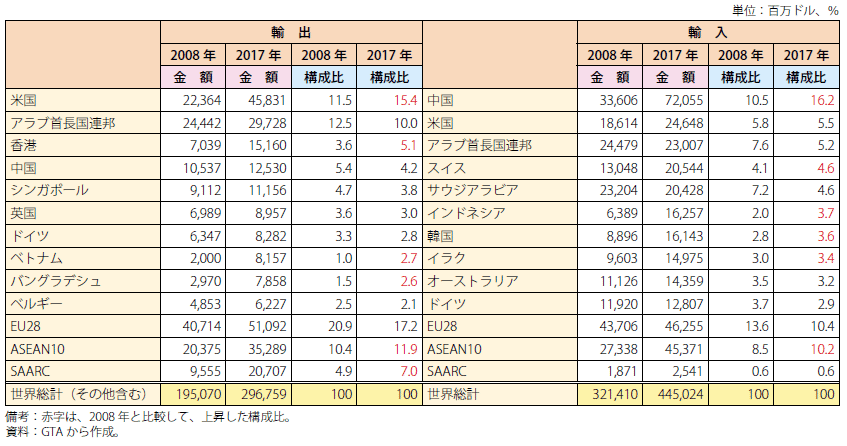
同様に、主要品目を確認する。輸出入ともに、宝石・宝飾品、鉱物性燃料の構成比が大きいことは変わらない149が、一般機械や車両の輸出、電気機械の輸入の拡大が注目される(第Ⅰ-2-3-2-6表)150。
第Ⅰ-2-3-2-6表 インドの貿易金額と構成比(主要品目別)の2時点比較
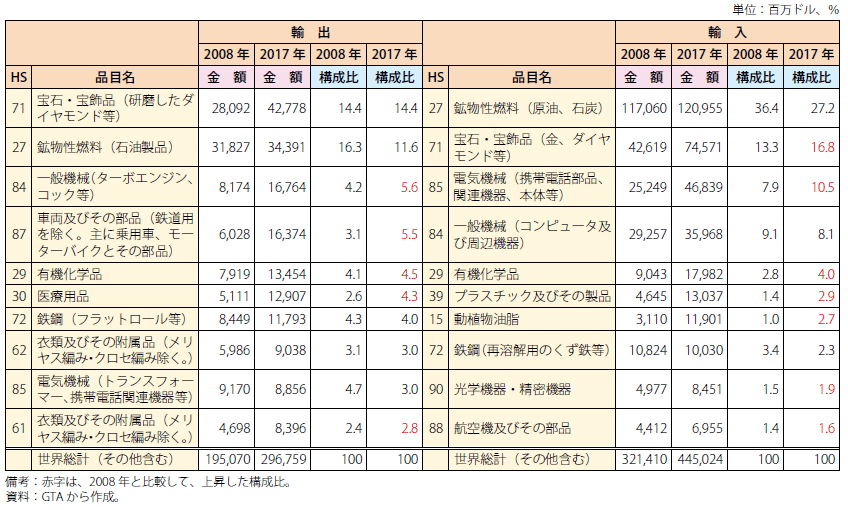
147 第Ⅰ-2-3-2-4 図には内訳を掲載していないが、貿易データを検証した結果、主に、金や携帯電話関連部品等の内需拡大が要因である。
148 南アジア地域協力連合(SAARC:South Asian Association for Regional Cooperation)を指し、加盟国は、南西アジアの8か国(インド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、ネパール、ブータン、モルディブ、アフガニスタン)である。
149 インドの貿易は、原油を輸入して国内で精製した石油製品の輸出、ダイヤモンド等の原石を輸入して国内で研磨した宝飾品の輸出といった加工貿易が占める割合が大きい。
150 日本は、インドの輸出先としては19位、輸入先としては14位である。インドから日本へ、主に鉱物性燃料(石油製品等)を輸出し、日本からインドへ、主に一般機械(印刷機、プリンター等)を輸入している。
③投資
対内直接投資は、モディ政権が発足した2014年度以降急増した。国別にみると、2016年度は1位がモーリシャスで、次いでシンガポール、日本151の順であった(第Ⅰ-2-3-2-7図)。業種別にみると、近年、通信、貿易、電気機器分野への投資が活発である(第Ⅰ-2-3-2-8図)。
第Ⅰ-2-3-2-7図 インドの対内直接投資額の推移(国別)
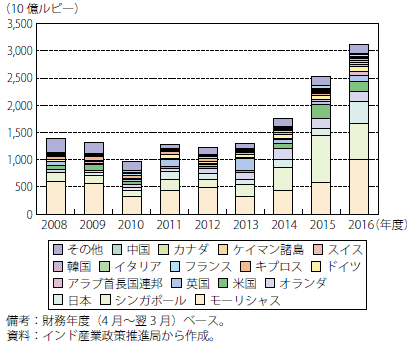
第Ⅰ-2-3-2-8図 インドの対内直接投資額の推移(業種別)
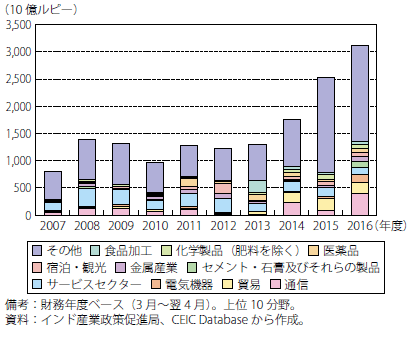
151 日本からの投資分野は、輸送機器を主とした製造業関連、保険、金融分野であった。
(2)グローバル化の推進と構造改革の継続
2018年1月、モディ首相は、世界経済フォーラムの年次総会(ダボス会議)のオープニングで基調講演を行い、保護主義に傾く世界に警鐘を鳴らし、グローバル化を推進すべきと力説した152。また、IT(情報技術)や科学の進歩により、直近20年で世界は大きく変化したことに言及し、新興国を含めた、多極化した新たな国際秩序を構築すべきと訴えた。なお、国内の施策に関しては、「根源的な社会・経済改革を続ける」と表明し、外国資本を呼び込むための市場開放政策や税制改革などの進展をアピールした。
2014年5月の就任以来、モディ首相は、高い支持率153に支えられ、これまで実現困難だった構造改革を、矢継ぎ早に実行に移している。同国の歴史に刻まれる大改革としては、2016年11月、事前周知なく断行した高額紙幣の廃止154や、2017年7月、幾つもの税が課され複雑な体系となっていた間接税を一本化するGST(財・サービス税)の導入が挙げられる。
これらのドラスティックな構造改革は、インド経済の一時的な混乱、成長鈍化を引き起こしているが、同国を新興国からグローバルな大国へ脱皮させ、持続的な成長を実現するために不可欠な過程だと、国内外から支持されている155。
152 インドがダボス会議に参加するのは、1997年以来、約20年ぶりのことであり、基調講演は初めてのことだった。
153 ピューリサーチセンターの調査によると、就任3年を経た2017年11月時点の支持率は88%であった。
154 モディ首相は、2016年11月8日午後8時、テレビ演説で、11月9日午前零時(演説のわずか4時間後)から、現行の500ルピー(約800円、1ルピー約1.6円に相当)紙幣と1,000ルピー紙幣を無効とする旨を発表した。国民は、11月10日から12月30日までに、廃止対象の紙幣を銀行に預け入れるか、新紙幣(500ルピーと2,000ルピー札)に交換する必要に迫られた。これによって、銀行口座を開設する国民が増加した。なお、インド準備銀行によると、発表後1か月で、旧紙幣の9割を回収できたとしている。
155 主要平均株価指数であるインドムンバイSENSEXが過去最高値を更新し続けている(2018年2月現在)ほか、格付機関Moody’sが2017年11月、2004年1月以来約14年ぶりに格付を上げた(Baa3からBaa2に上昇。外貨建てベース)。
(3)ICT政策「デジタル・インディア」の進展
モディ政権の構造改革の中には、「メイク・イン・インディア」「スキル・インディア」「スタートアップ・インディア」「クリーンインディア」「スマート・シティ」等、数々のキャンペーンがある。ここでは、それらの中でも、国民生活に密接な影響があり、近年急速に進展している「デジタル・インディア」を取り上げる。
これは、2014年8月、構造改革の旗艦という位置付けで発表されたICT政策であり、①全国民に対するデジタルインフラの提供、②行政サービスのオン・デマンド化、③デジタル化による国民のエンパワメント化、の3つに焦点156がおかれている。そして、これらの達成のため、9つの柱を設定し、2018年度まで段階的に計画を遂行し、すべての村落にデジタル化された電子行政サービスを提供することとしている(第Ⅰ-2-3-2-9図)。
第Ⅰ-2-3-2-9図 デジタル・インディア・プログラム達成のための9つの柱
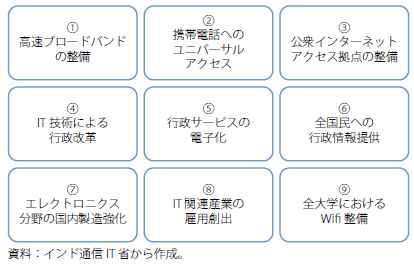
インド政府のHPには、各種デジタル政策を広く国民に周知し、利用を促すために、ピクトグラムや写真を多用して視覚的に理解しやすくするなど、啓発のための工夫が見て取れる(第Ⅰ-2-3-2-10図)。
第Ⅰ-2-3-2-10図 インド政府HPで周知されている各種デジタル政策のトップページ(4例)

156 インド政府は、これを、3つのキービジョンエリア(three key vision areas)と表現している。
①国民ID(Aadhaar:アーダール)の普及
国民固有識別番号Aadhaarとは、指紋と虹彩をつかった生体認証システム157で、国民一人一人に付与される固有の12桁の番号である。現在、総人口の13.1億人のうち、約9割の国民に対して発行されたと公表されており、世界最大のIDプラットフォームといえる158。
Aadhaarは、身分証明書類が不備な貧困層に社会保障などの行政サービスを確実に届けることなど、行政サービスの効率化が本来の目的であった。政府は、さらに、金融包摂159の手段としても活用されるよう、Aadhaarと連携する新たなシステムやサービスを提供している160。
157 この大規模生体認証システムは、日本電気株式会社(NEC)が提供している。NEC報道資料によると、NECの指紋認証技術・顔認証技術は、米国国立標準技術研究所が実施したベンチマークテストにおいて、世界1位の照合精度を有するとの評価を得ている。
158 2010年に発行が開始されたが、モディ政権になり登録者が急増した。
159 ファイナンシャルインクルージョン(financial inclusion)は、貧困層が低いコストで金融サービスにアクセスできるようにする政策を指すことが多い。
160 プライバシー保護、情報漏洩の観点から、複数の訴訟がおこされた。原告側は、「指紋や虹彩の情報取得が個人のプライバシーの権利を侵害している」と主張する一方、政府側は、「憲法ではプライバシーを基本的人権と規定していない。」と反論した。これに対し、最高裁判所は、「プライバシーの権利は憲法で規定されており、Aadhaarのプライバシー侵害のリスクについて留意すべき」との見解を出している。こういった背景を受け、政府は、今後の活用方法について見直しをせまられている。なお、2018年3月末までとされていたAadhaarと銀行口座の紐づけ期限は延長され、新しい期限は未定のままである(2018年4月現在)。
②国民に浸透するキャッシュレス化
同国は、銀行口座普及率が低いことから、現金取引比率が8~9割ともいわれており161、銀行の支店やATMが存在しない農村部も少なくない。現金取引は非効率的であるほか、政府が経済実態を把握できないという重大な欠陥を生じさせていた。
先に述べた高額紙幣の廃止という構造改革は、ブラックマネーの撲滅162が主目的であったが、結果的に、インド国民の決済手段を現金から電子(キャッシュレス)へシフトさせる大きなきっかけとなった。さらに、国民IDの浸透、電子決済手段の利便性の向上等が、同国のキャッシュレス化に拍車をかけている。
161 高額商品である自動車、二輪車の購入においてさえ、インドでは現金払が少なくない。(現金支払の割合は、自動車購入時が約1~2割、二輪車購入時が約6割と言われている。)
162 インドの地下経済はGDPの約2割を占めるといわれており、統計上表れないブラックマネーの存在が長年の問題とされてきた。
③多様な決済手段と民間との連携による利便性の向上
同国の主な電子決済に、UPI、USSD、デビットカードやクレジットカード、PPI、モバイルバンキングが挙げられるが、高額紙幣の廃止が行われた2016年11月以降の取引金額と件数の推移を見る。
UPI(Unified Payment Interface)は、スマートフォンに銀行アプリなどをダウンロードし、リアルタイムでの送金や小売店での支払を行うプラットフォームであり、政府が最も普及に注力していることから、足元での取引規模は急伸している(第Ⅰ-2-3-2-11図)。
第Ⅰ-2-3-2-11図 UPIの取引(金額と件数)の推移
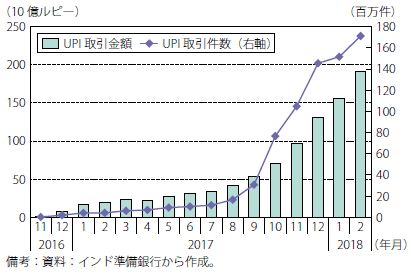
USSD(Unstructured Supplementary Service Data)は、主に、金融包摂の観点から、2012年より提供されてきた金融サービスであり、スマートフォンやインターネット環境がなくとも、SMSなど携帯電話(フィーチャーフォン)の基本的な機能を使って送金ができる。取引規模は小さいが、インド国内で使われている12言語に対応しており、農村部における金融サービスの利用度を大きく向上させたとされている。足下でも底堅く利用されているが、取引金額、件数ともに下降傾向にある(第Ⅰ-2-3-2-12図)。
第Ⅰ-2-3-2-12図 USSDの取引(金額と件数)の推移
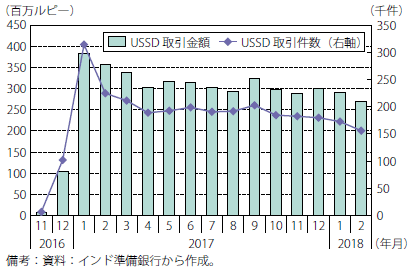
デビットカードやクレジットカードは、POS(Point of Sales)を通じて行う支払だが、他の手段と比較すると、取引件数は最大であり、取引金額とともに増加傾向にある(第Ⅰ-2-3-2-13図)。
第Ⅰ-2-3-2-13図 POSにおけるデビッドカードとクレジットカードの取引(金額と件数)の推移
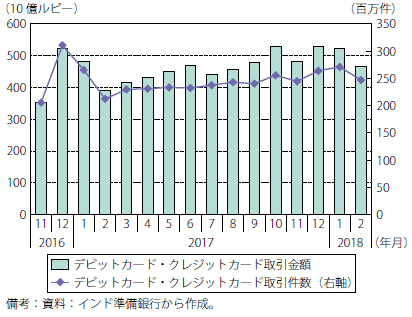
PPI(Prepaid Payment Instrument)は、主に、ウォレット等電子プリペイド支払システムを指しており、支払前に、デビットカードやインターネットバンキングで資金のロードを行う必要がある。オンラインショッピングやスマートフォンを使った店舗での支払に利用されるものであり、利用額の制限があるものの、取引金額、件数ともに増加傾向にある(第Ⅰ-2-3-2-14図)。
第Ⅰ-2-3-2-14図 PPIの取引(金額と件数)の推移
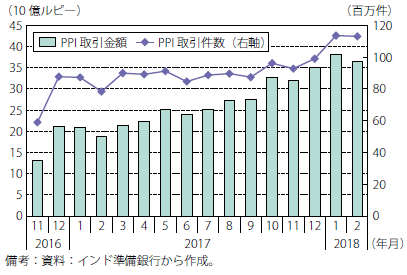
モバイルバンキングは、携帯電話からインターネットを経由して利用する銀行サービスを指すが、足下では、取引の減少傾向が顕著である(第Ⅰ-2-3-2-15図)。
第Ⅰ-2-3-2-15図 モバイルバンキングの取引(金額と件数)の推移
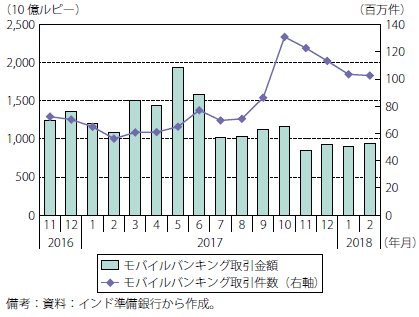
以上をまとめると、高額紙幣の廃止の直後、総じて、電子決済の取引は増加したが、その後の増減の傾向は決済手段ごとに異なる。これは、国民が各自のニーズに合う手段を嗜好していることや、サービス拡大により利便性が高い手段に利用が集中していること等が反映されていると思われる。
同国のキャッシュレス化の進展は、政府のみならず、民間企業参入の影響も大きい。例えば、PPI方式を採用しているEウォレット国内最大手のPayTM(ペイティーエム)は、その簡便さ163が支持され、屋台から大規模モールまで、至るところで利用可能となっている。また、外資系企業の参入も活発化164し、デジタル決済市場は拡大している(第Ⅰ-2-3-2-16図)。
第Ⅰ-2-3-2-16図 デリーの屋台や移動販売車の写真(キャッシュレス化の風景)
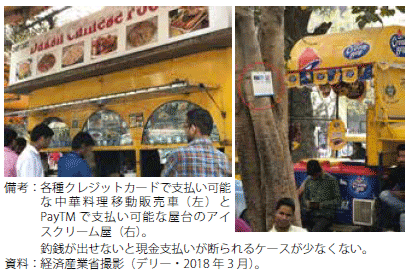
モディ政権のデジタル政策が、前政権と異なる点は、各種デジタル化施策にかかるシステムを、行政サービスに閉じることなく、様々な民間サービスと連携可能なオープンアーキテクチャ165にしたことである。まずは政府主導166でインフラを整え、そこに国内外の企業が参入し、各社のサービスを紐づける。その利便性が高くなったサービスを国民が利用することで、結果的に政府のインフラ利用度が高くなる、といった流れである。
163 スマートフォンの専用アプリに、銀行口座から必要な金額を入金し、支払店の専用QRコードで決済する。
164 例えば、米国Google「Tez」、「Amazon Pay」や、韓国「サムソン・ペイ」などが挙げられる。なお、現在(2018年3月時点)、米国facebook傘下の「WhatsApp」が電子決済サービスを開始するための試験を行っていると報道されている。WhatsAppはインドで2億人以上が利用しているメッセージアプリケーションであるため、今後の電子決済市場を大きく変えると予想されている。
165 ハードウェアやソフトウェアの使用を全部又は一部を一般公開し、誰でもその仕様に準じた製品を作れるようにすること。
166 実際には、インド決済公社(NPCI)が担当する。
(4)電子商取引市場の拡大
①急速に拡大する電子商取引市場
インドの電子商取引による小売売上高は、2017年の201億ドルから、2022年には523億ドルまで年々拡大すると予想されている(第Ⅰ-2-3-2-17図)。また、電子商取引の取引額を世界の主要国と比較すると、中国や米国といった電子商取引先進国には及ばないが、平均伸び率は39.4%(2016~2020年)と、同国における電子商取引の急速な拡大を示唆するデータもある(第Ⅰ-2-3-2-18図)。また、2024年には日本を抜いてアジア太平洋で第2位、世界で第4位の電子商取引市場規模となる見込みとするデータもある167。
第Ⅰ-2-3-2-17図 インドの小売市場の電子商取引による売上高の推移
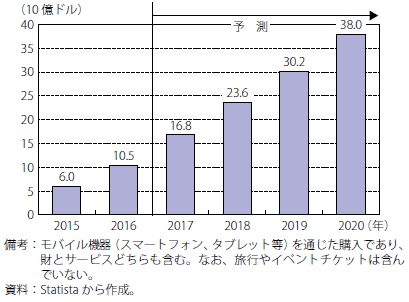
第Ⅰ-2-3-2-18図 インドの電子商取引(B2C)の取引額(主要国との比較)
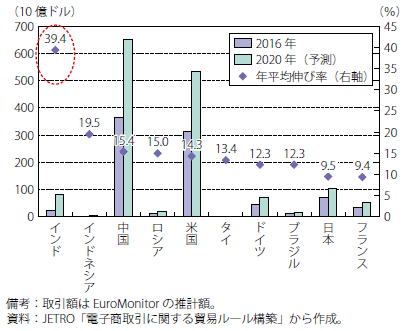
167 第Ⅱ部第1章第1節2.「デジタル貿易の拡大」を参照。
②市場をけん引するMコマース
インド商工会議所(ASSOCHAM)とデロイトの共同調査によると、2017年におけるオンライン商品購入168の82%169がモバイル機器を通じたものだという。同国のインターネット環境が世界の主要国と比べてまだ後れをとっている一方、2016年の4G誕生による高速化や、加入料の低下により、スマートフォンを主とする携帯電話の所持者は年々増加し、オンラインショッピング市場をけん引している(第Ⅰ-2-3-2-19図)(第Ⅰ-2-3-2-20図)。
第Ⅰ-2-3-2-19図 インドのMコマース小売売上金額の推移
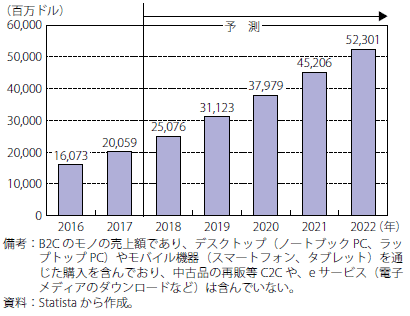
第Ⅰ-2-3-2-20図 携帯電話加入者数の推移(主要国・地域との比較)
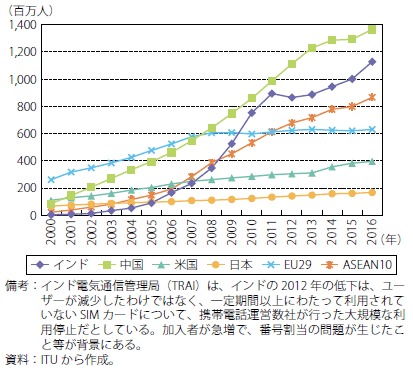
このような状況を反映し、インドでは電子商取引(Eコマース)をMコマース(Mobile E commerce)と言及することも多い。固定電話通信回線などインフラの整備が先進国と比べて大幅に遅れていたことで、先進国とは異なる一足飛びの進展をしている。なお、企業によっては、インターネットのウェブサイトを閉鎖し、スマートフォンにダウンロードするアプリの提供のみを行うなど、スマートフォン等モバイル利用者に対象を絞ったサービスへ転換する動きもある。
同国の100人当たり携帯電話加入者割合を見ると、2016年は85.2%であり、主要国・地域と比べるとまだ増加の余地があることが分かる。また、都市が159.4%である一方、農村は56.3%にとどまっていることから、今後、農村において利用者が増加すれば、更に電子商取引市場が拡大することが予想される(第Ⅰ-2-3-2-21図)。
第Ⅰ-2-3-2-21図 携帯電話加入者割合(主要国・地域との比較)とインドにおける都市・農村別の内訳
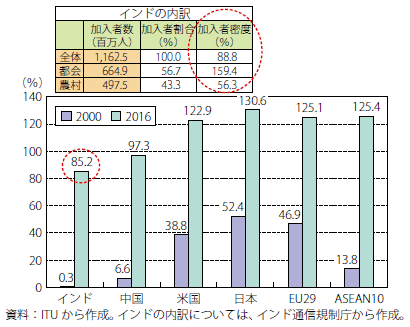
168 レポートでは、Shopping queriesと表現されている。
169 2016年は、76%であった。
③地場・外資系企業を含めたIT関連企業の競争激化
近年、地場・外資系を含めたIT関連企業の競争が激化している。
例えば、前述した電子商取引市場は、巨大企業の占有率が高いが、追加出資や企業買収等、競争に拍車がかかっている。また、巨大企業に限らず、旅行、健康関連、配車といった特化したサービスを提供する電子商取引事業者や、前述した決済サービス提供企業においても、同様の状況である170。
一連のデジタル化を促進している携帯電話についても、携帯キャリアが10社(国営企業2社、民間企業8社)存在しており、同国における通信業界の競争の激しさが伺える171。各社の顧客獲得のための価格競争により、通信業界は低収益構造となっている172(第Ⅰ-2-3-2-22図)。
第Ⅰ-2-3-2-22図 利用者数による携帯キャリアの占有率
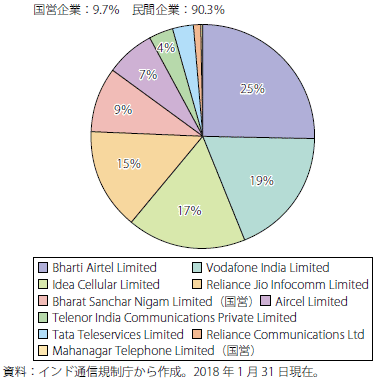
なお、近年のIT企業数や利益等を確認すると、企業数は減少傾向にある一方、利益はわずかながら増加傾向にある。この推移から、IT企業が低収益体質から脱却するため、M&Aなど事業再編を行っている一面が見て取れるほか、今後も乱立する企業が淘汰される可能性が予想される(第Ⅰ-2-3-2-23図)。
第Ⅰ-2-3-2-23図 インドのIT企業の数、売上額・支出額・営業利益の推移
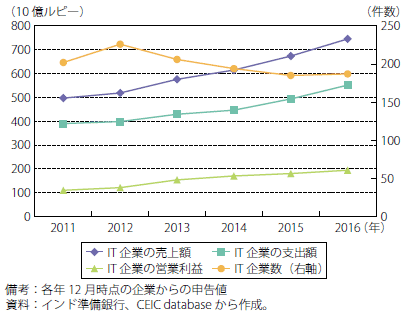
170 2016年、モディ首相が、法人税控除を含むベンチャー支援策「スタートアップ・インディア」を打ち出したことが、ニッチな分野に特化したベンチャー企業数の増加を促した。インドにはIT技術者が多いという背景もあり、電子商取引分野での企業が数多く誕生したと考えられる。
171 インド通信規制庁は、毎月、“Access Service Provider-wise Market Share in term of Wireless Subscribers”を公表している(http://trai.gov.in/release-publication/reports/telecom-subscriptions-reports![]() )。
)。
172 通信業界の低収益構造は、近年、新規事業者が参入したことで更に進んだと言われている。例えば、ある新規参入事業者が、音声通話を無料にするなど通信料の大幅値下げを行ったことを受け、他社も自社の顧客維持のため、値下げをせざるを得ないといった状況になっている。
