

- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2018

- 白書2018(HTML版)

- 第1部 第2章 第6節 中東及びアフリカ
第6節 中東及びアフリカ
1.中東
中東諸国226は、一部の国・地域において政情の不安定さを抱える一方、石油等の資源を支えに成長し、産業の多角化に向けた改革に取り組む国・地域も存在している。本項では、中東諸国の経済の動向を、サウジアラビアの例を中心に見ていく。
226 本書における中東諸国とは、UAE、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、シリア、トルコ、バーレーン、ヨルダン、レバノンの計14か国を指す。
(1)マクロ経済動向
まず、中東諸国の経済を概観する。中東諸国の経済規模を見ると、2016年時点でトルコが全体の29.8%と4分の1以上を占めている。続いて、サウジアラビアが全体の18.3%の規模となっており、この2か国で中東諸国全体の約5割の経済規模を占める(第Ⅰ-2-6-1-1図)。
第Ⅰ-2-6-1-1図 中東における国・地域別GDPシェア
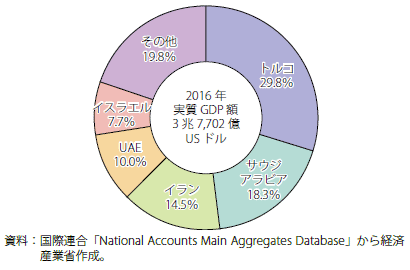
中東諸国は世界有数の資源国が集まる地域であり、世界の原油確認埋蔵量の47.7%、天然ガス確認埋蔵量の42.5%を占める。また、2016年時点での世界全体の鉱物性燃料227輸出額1兆5,095億ドルのうち、4分の1以上を占める4,264億ドルが中東から輸出されている(第Ⅰ-2-6-1-2図)。
第Ⅰ-2-6-1-2図 中東諸国の資源確認埋蔵量及び輸出シェア
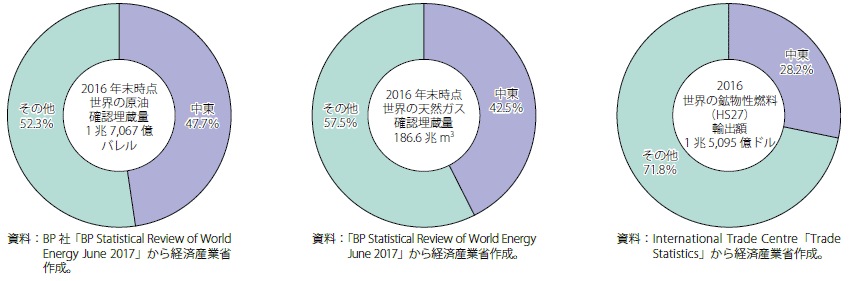
中東の輸出入品目を見ると、国・地域によって状況は異なるものの、中東全体でみると鉱物性燃料が2016年時点で全輸出額の42.8%を占めており、貿易において獲得する外貨収入の半分近くを鉱物性燃料から得ていることになる(第Ⅰ-2-6-1-3図)。
第Ⅰ-2-6-1-3図 中東の輸出入額の推移と貿易品目
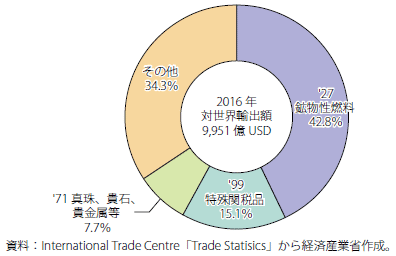
鉱物性燃料に依存した経済構造が続く中東の産油国では、原油価格が大幅下落した2014年以降、貿易収支の黒字幅の急激な縮小と軌を一にして、大幅な財政赤字を抱えることとなった。これは、中東の産油国の政府収入の大半が原油輸出によって賄われているためである。2016年以降、OPECの減産合意等により徐々に原油価格は回復傾向であるものの、財政収支の黒字化には至っていない国・地域が多い(第Ⅰ-2-6-1-4図)。
第Ⅰ-2-6-1-4図 中東の産油国の財政収支(対GDP比)推移
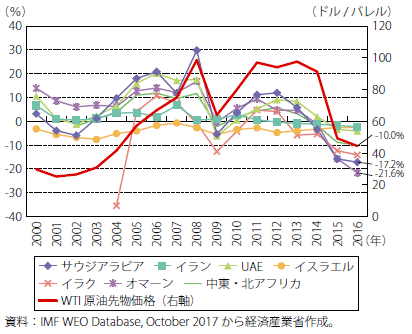
このように原油は相場によって収入額が大きく変動することに加え、天然資源であるためにその可採年数には限界が存在228する。こういった問題意識から、中東の産油国は、持続可能な経済・社会体制の構築のため、石油だけに依存しない産業構造を目指し、国内改革を進めている。例えば、サウジアラビアは2016年に「サウジ・ビジョン2030」を、UAEは2010年に「国家ビジョン2021」を、クウェートは2010年に「国家ビジョン2035」をそれぞれ発表し、産業の多様化等に取り組んでいる。
以下の項ではサウジアラビアを、経済構造改革に取り組む中東産油国の一例として、同国のマクロ経済動向と絡めながら取り上げたい。
227 HSコード27類を指す。
228 英国のブリティッシュ・ペトロリアム社が公表している「BP Statistical Review of World Energy June 2017」によれば、中東の石油の可採年数は69.9年とされている。
(2)サウジアラビアのマクロ経済動向
まず、サウジアラビアのマクロ経済動向を概観する。
サウジアラビアは中東域内において、トルコに次ぐ2番目の経済規模を持つ中東屈指の経済大国である(第Ⅰ-2-6-1-1図参照)。実質GDP成長率の推移を見ると、2000年から2017年では年平均で前年比+3.5%の成長を達成している。主に成長をけん引する項目は、2000年代前半までは輸出であったが、徐々に民間消費と総固定資本形成寄与が拡大している。足元では2016年以降2年連続で実質GDP成長率は低下しており、2017年の実質GDP成長率は、前年比▲0.7%と世界金融危機以来8年ぶりのマイナス成長となった。(第Ⅰ-2-6-1-5図)。
第Ⅰ-2-6-1-5図 サウジアラビアの実質GDP成長率の推移(需要項目別)
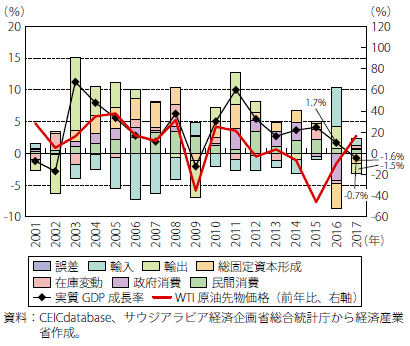
サウジアラビア政府の財政構造を見ると、2017年の歳入額(暫定値)のうち63.2%と半分以上を石油関連の収入が占めている。上述したように、2014年からの石油価格下落によって中東の産油国の歳入は急激に減少し、財政赤字が拡大する国が続出したが、サウジアラビアも例外ではなく、2014年以降3年連続で大幅な財政赤字となり、2015年、2016年には対GDP比で10%を超える額となった(第Ⅰ-2-6-1-6図)。急増した財政赤字を受けて、サウジアラビア政府は公務員給与や補助金の削減等の緊縮財政を行ったが、これを要因の一つとして政府消費がマイナス転化したことに加え、民間消費と総固定資本形成を押し下げたことでGDP成長率は低下し、2017年にはマイナス転化に至った。
第Ⅰ-2-6-1-6図 サウジアラビアの歳入割合と財政収支額の推移
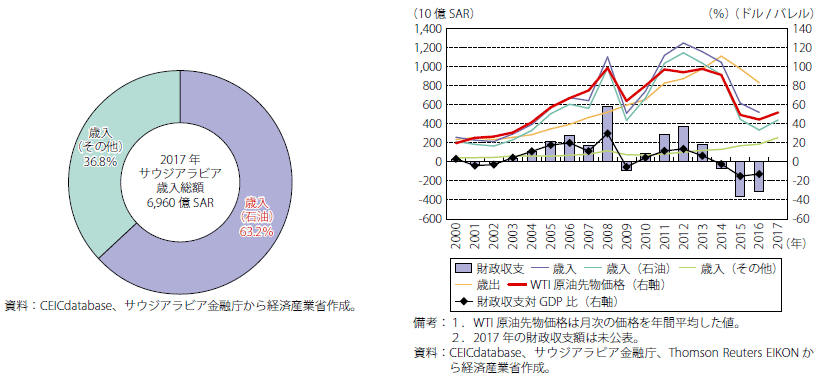
サウジアラビアは中東最大の石油産出国である。石油の確認埋蔵量は、2016年時点で、ベネズエラに次いで世界第2位の規模であり、1日あたりの生産量も世界最大の米国に次ぐ規模である(第Ⅰ-2-6-1-7図)。
第Ⅰ-2-6-1-7図 世界の石油確認埋蔵量と生産量
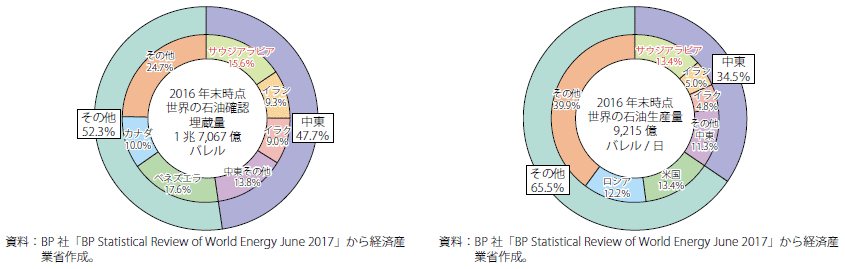
サウジアラビアの産業構造シェアをみると、石油部門が同国の主要産業であることが確認できる。石油部門は、2017年時点で産業全体の43.0%に及ぶ規模を有している。2000年代初頭と比較し、石油部門のシェアは徐々に縮小し、民間の非石油部門のシェアが拡大しつつあるものの、未だ石油部門はサウジアラビアのGDPにおいて半分近いシェアを占める最大規模の産業である(第Ⅰ-2-6-1-8図)。
第Ⅰ-2-6-1-8図 サウジアラビアの産業部門別シェアとその推移
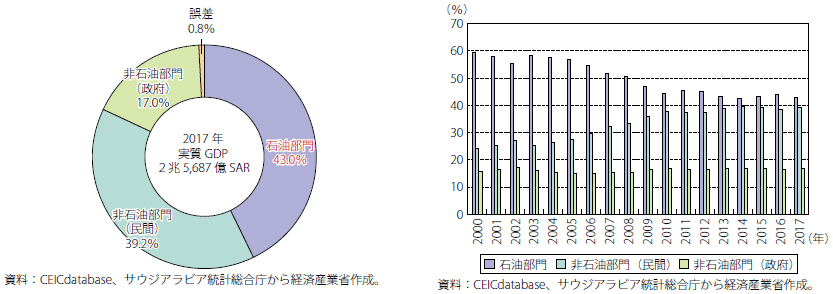
サウジアラビアの実質GDP成長率の産業別寄与度をみても、石油部門を含む鉱業及び採石業が長年にわたってGDP成長率に最大の寄与を示していることがわかる。しかし、上述したように2017年の実質GDPはマイナス成長であったが、最大のマイナス要因は鉱業及び採石業であった(第Ⅰ-2-6-1-9図)。
第Ⅰ-2-6-1-9図 サウジアラビアの実質GDP成長率の推移(産業別)
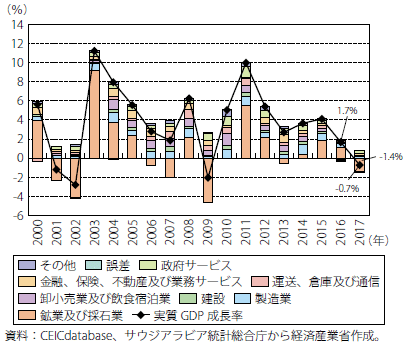
次に、サウジアラビアの貿易動向を概観する。2017年の貿易収支額は3,493億サウジアラビア・リヤルであり、輸出額は8,289億サウジアラビア・リヤルで前年比+20.4%、輸入額は4,797億サウジアラビア・リヤルで前年比▲8.7%となった。石油価格の下落とともに、2012年以降4年連続で貿易収支の黒字幅が減少していたが、石油価格の回復と輸入額の減少によって、2016年以降2年連続で黒字幅が回復した(第Ⅰ-2-6-1-10図)。
第Ⅰ-2-6-1-10図 サウジアラビアの輸出入額の推移
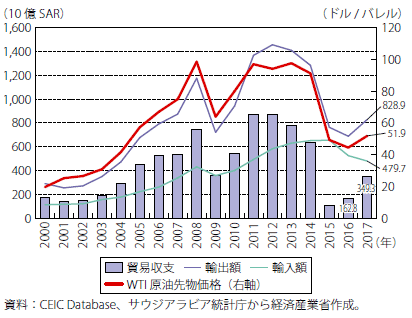
品目別に見ると、石油を含む鉱物性燃料が輸出全体の78.9%を占める最大の輸出品目となっており、獲得した外貨により一般機械や自動車等を輸入するという貿易構造になっている。石油価格の変動によって外貨の獲得額は大きく影響を受ける(第Ⅰ-2-6-1-11図)。
第Ⅰ-2-6-1-11図 サウジアラビアの輸出入品目(2016年)
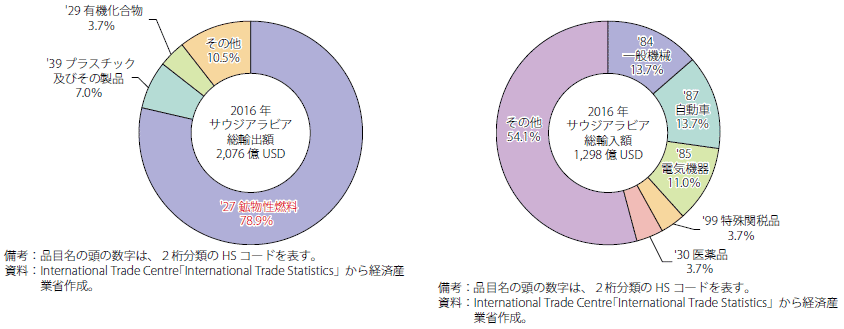
サウジアラビアの貿易相手を国・地域別に見ていく。まず輸出相手国を見ると、2000年代初頭は、米国が輸出相手国の第2位となっていたが、徐々にその存在感は縮小し、代わって近年では中国を始めとしたアジア圏の存在感が増してきている。輸入相手国についても、2000年代初頭より構成国は変わらないが、中国が急速に輸入額を伸ばしてきており、輸出入双方において中国の存在感が増している(第Ⅰ-2-6-1-12表)。
第Ⅰ-2-6-1-12表 サウジアラビアの貿易相手国変化
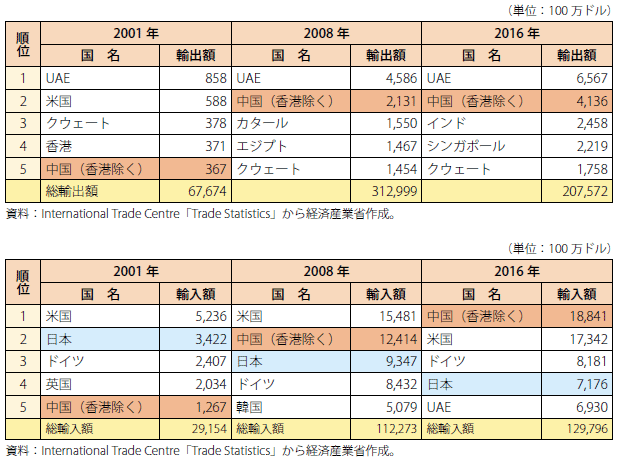
次に、サウジアラビアの産業・社会政策上大きな課題となっている、高止まりする失業率についてみていく。
サウジアラビアでは外国人労働者を多く受け入れており、国内の労働力人口のうち78.0%が非サウジアラビア人である(第Ⅰ-2-6-1-13図)。
第Ⅰ-2-6-1-13図 サウジアラビアの国籍別労働力人口のシェア(2016年)
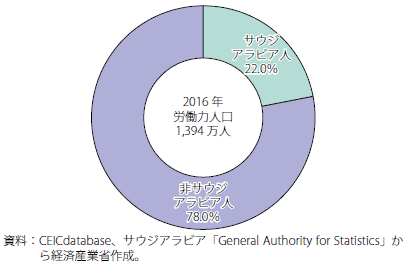
国籍別に失業率を見ると、サウジアラビア人の失業率が非常に高く、2016年時点で12.3%とサウジアラビア人の労働力人口の1割以上が職に就けていない状態となっている(第Ⅰ-2-6-1-14図)。年代別では、特に若年層のサウジアラビア人の失業率が非常に高くなっており、20~24歳では45.0%、15~19歳では63.2%にのぼる。サウジアラビア人の人口構成は、25歳未満が全人口の49.0%を占めており、政府部門による雇用では吸収しきれなくなったサウジアラビア人失業者が多く存在229する(第Ⅰ-2-6-1-15図、第Ⅰ-2-6-1-16図)。
第Ⅰ-2-6-1-14図 サウジアラビアの国籍別労働力人口のシェア推移
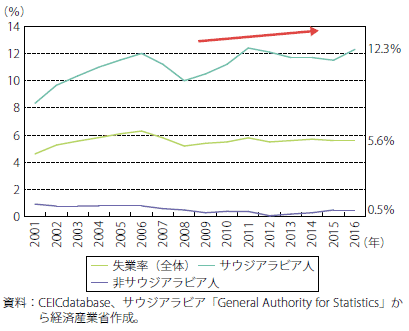
第Ⅰ-2-6-1-15図 サウジアラビアの年齢別国籍別失業率(2017年第3四半期)
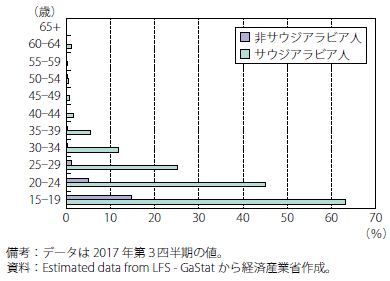
第Ⅰ-2-6-1-16図 サウジアラビアの年齢別国籍別人口(2018年1月)
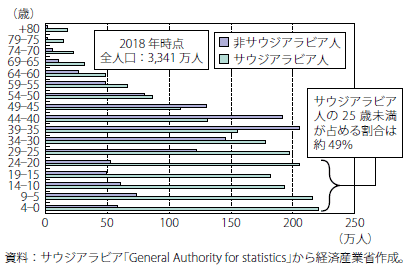
229 国民への補助が手厚いサウジアラビアでは、そもそも一度も職に就いたことがない失業者も多く存在する。
(3)サウジアラビアの「サウジ・ビジョン2030」とその進展
上記のように、石油への依存度の高い経済、財政赤字、高い失業率等の問題を抱えるサウジアラビアは、これまで「開発五カ年計画」230の中で各課題に対して是正策を打ち出してきたが、抜本的な改革には至っていない。このような状況の中、これまでの開発五カ年計画を踏襲、発展させる形で、2016年4月にムハンマド皇太子(当時は副皇太子)により発表された新たな国家開発計画が、「サウジ・ビジョン2030」である。
「サウジ・ビジョン2030」は、1.アラブとイスラム世界の中心、2.グローバルな投資大国、3.アジア、欧州、アフリカの3つの大陸のグローバルハブ、という3本の柱に基づき、①活気ある社会、②盛況な経済、③野心的な国家、という3つのテーマを定めている。加えて、目標とする項目それぞれに具体的な数値目標が付随している。主な目標は、これまでの開発五カ年計画で掲げられてきた「雇用の創出」、「海外からの直接投資誘致」、「民間部門の振興」、「産業の多様化」を引き継ぎつつ、新たに女性の社会進出等を奨励している。また、2016年6月には、「サウジ・ビジョン2030」を達成するために2020年までに達成すべき目標を具体的な目標値とともに定めた「国家改革計画2020」を発表した。
「サウジ・ビジョン2030」の実現のため、サウジアラビア政府は様々な国に協力を求めている。そのうちの一か国が我が国との「日・サウジ・ビジョン2030」231である。
また、サウジアラビアは我が国のみでなく、中国にも働きかけを行っている。2016年にはムハンマド皇太子、2017年にはサルマン国王がアジア歴訪の一環として中国への訪問を行っている。サルマン国王訪中の際には、石油化学、石油備蓄等の分野での協力が合意された。
「サウジ・ビジョン2030」に関する中国への協力要請の背景には、サウジアラビアと中国の経済関係の深化がある。サウジアラビアにとって中国は第2位の輸出相手国、第1位の輸入相手国である(第Ⅰ-2-6-1-12表)。また、中国にとってサウジアラビアは第2位の原油輸入国である(第Ⅰ-2-6-1-17図)。貿易面に加え、中国の対外経済協力(プロジェクト完成額)の推移を見ると、2016年の最大の相手国はサウジアラビアとなっている(第Ⅰ-2-6-1-18図)。
第Ⅰ-2-6-1-17図 中国の国・地域別原油(HS2709)輸入シェア(2017年)
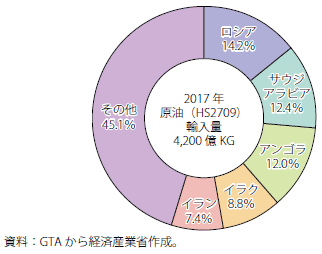
第Ⅰ-2-6-1-18図 中国の国・地域別プロジェクト輸出額の推移
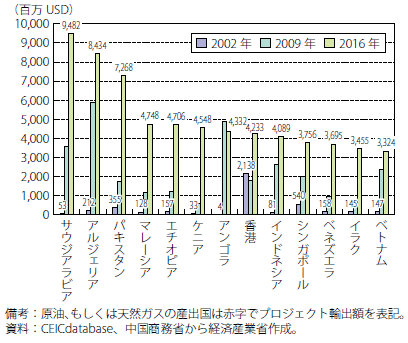
なお、中国の対外経済協力(プロジェクト完成額)は、地域別ではアジア、アフリカ、中東へ、国別ではサウジアラビアを始めとする資源国のシェアが高い傾向が見られる(第Ⅰ-2-6-1-19図)。
第Ⅰ-2-6-1-19図 中国の国・地域別プロジェクト輸出額シェア
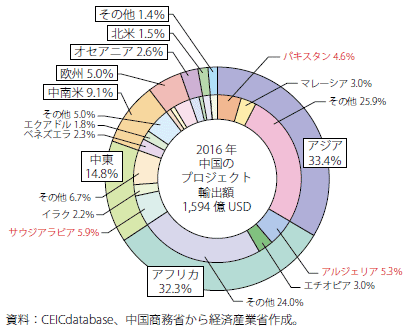
上述のとおり、サウジアラビアは、人口の約半分が25歳未満と豊富な若年層人口を抱える。現状では、この世代の雇用確保が問題となっているが、視点を変えれば、サウジアラビアは、確実に将来にわたって需要が拡大していく市場であるといえる。また、「サウジ・ビジョン2030」による一連の改革は、石油依存の産業構造からの脱却という目的に加えて、こうした若年層の要望を捉えた社会改革としての側面もあり、映画館の解禁(本年4月)や女性の自動車運転の解禁(本年6月予定)など、象徴的な改革が次々と実行されている。これは、内外企業にとっては新たなビジネス機会の創出にもつながる。今後、日本企業が、このようなビジネス機会を的確にとらえていくことが期待される。
230 現行のものは第10次開発五ヶ年計画で、対象期間は2014~2019年。
231 「日・サウジ・ビジョン2030」の具体的取組内容に関しては、本書第Ⅲ部第2章第5節を参照ありたい。
2.アフリカ
(1)マクロ経済動向
アフリカ大陸は、世界の「ラストフロンティア」と呼ばれて久しい。
アフリカ連合加盟55か国・地域のGDP合計は、約250兆円である。アフリカには、石油、天然ガスを始め、コバルトやプラチナ、クロム等の鉱物性資源が潤沢に存在する。現在も複数の地域で資源開発が進められており、今後とも継続的資源獲得が見込める地域である(第Ⅰ-2-6-2-1図)。
第Ⅰ-2-6-2-1図 アフリカにおける資源の賦存状況
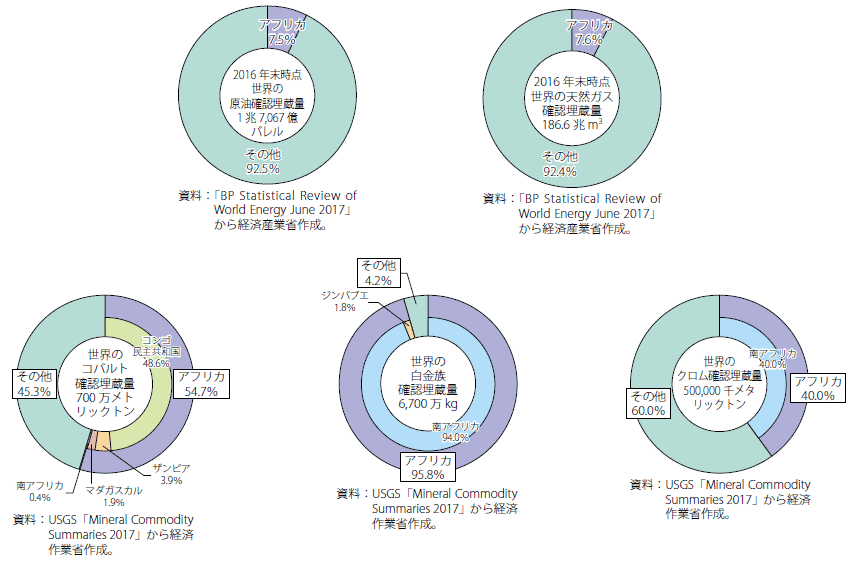
また、アフリカの人口を見ると、2015年時点で中国と同程度である12億人の人口を擁する。今後も長期的な人口拡大が見込まれており、2050年には25億人に達すると推計される(第Ⅰ-2-6-2-2図)。
第Ⅰ-2-6-2-2図 地域別の人口推計
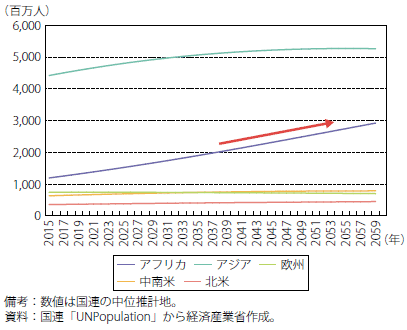
他の地域で今後減少が見込まれている生産年齢人口の割合も、アフリカでは増加が継続する見通しで、その割合は2050年には62%まで拡大すると推計されている。資源の賦存状況のみならず、生産年齢人口の増加の面から見ても、アフリカは今後とも成長が期待される有望な地域であるといえる(第Ⅰ-2-6-2-3図)。
第Ⅰ-2-6-2-3図 地域別の生産年齢人口推計
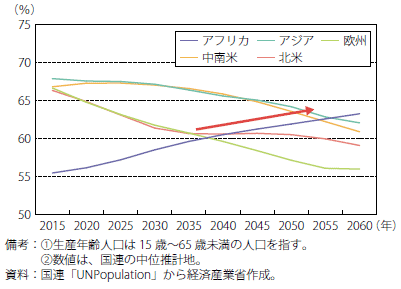
アフリカの実質GDP成長率は、2000年から2016年までの間平均4.5%である。また、GDP成長率の需要項目別寄与度を見ると、アフリカの成長のけん引役は消費である。増加を続ける人口等の要因により、民間消費は2000年から2016年までの間平均3.0%の寄与を示している(第Ⅰ-2-6-2-4図)。
第Ⅰ-2-6-2-4図 アフリカの需要項目別GDP成長率の推移
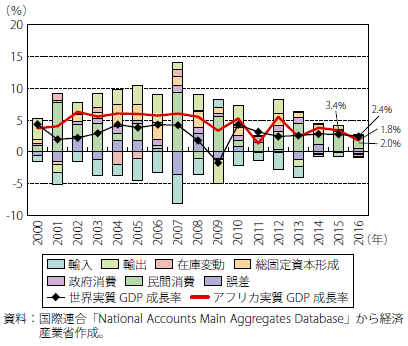
一方で、アフリカの主要産業は農業であり、旺盛な消費を満たすための工業製品はほとんど域内で生産されておらず、輸入によって賄われている状態である。
アフリカ諸国の主な外貨獲得手段は、自国で採掘される鉱物性資源を諸外国へ輸出することである。2016年時点のアフリカ諸国全体の対世界輸出品目を見ると、鉱物性燃料が35.2%、貴石等が12.7%、鉱石が4.0%と、鉱物性資源が全体の50%以上を占めている(第Ⅰ-2-6-2-6図)。
第Ⅰ-2-6-2-6図 アフリカの対世界輸出品目のシェア(2016年)
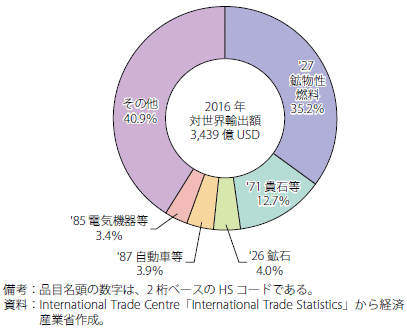
そのため、輸出で獲得できる外貨は商品市場の価格変動に影響されやすい。国内の主要産業である農業に加え、貿易収支もまた不安定な状態であり、産油国も含め、大幅な財政赤字を抱えている国も多く見られる。このような状況の中、アフリカ諸国は経済構造を強じん化させるためにも、工業化を推進しており、各国政府が定める経済開発計画にも「工業化」の文言が盛り込まれている。
(2)主要貿易相手国の変化
続いて、アフリカにおける貿易構造を見ていく。前述したように、アフリカの主要な輸出品目は、鉱物性燃料や貴石、鉱石等、自国で採掘される鉱物性資源である。これらを、我が国を含む先進諸国に輸出し、獲得した外貨によって電気機器や自動車等を輸入している(第Ⅰ-2-6-2-5図)。しかし、近年この貿易相手国に変化が現れている。
第Ⅰ-2-6-2-5図 アフリカの対世界輸入品目のシェア(2016年)
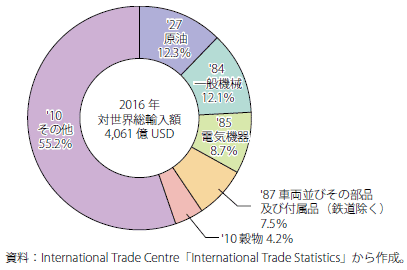
2000年代初頭は、米国を筆頭に、イタリア、フランス、英国と欧米先進諸国がアフリカにとって主要な輸出相手国であった。しかし、その後中国が欧州諸国、そして米国を抜き、2016年には第一位の輸出相手国となっている。加えて、上位輸出相手国への輸出比率が徐々に縮小しており、輸出相手国の多様化が進んだことが伺える(第Ⅰ-2-6-2-7図)。
第Ⅰ-2-6-2-7図 アフリカの対世界輸出国・地域別のシェアの変化
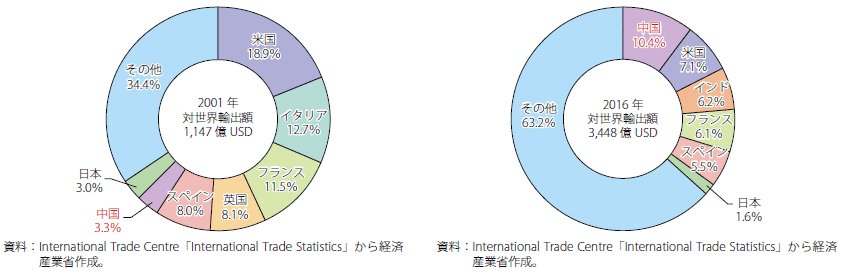
続いてアフリカの輸入相手国を見ると、輸出と同じく2000年代初頭は、フランス、ドイツ、イタリア等の欧州諸国と米国を含む他の先進諸国からの輸入が全輸入額の大半を占めていた。しかし、その後中国がシェアを拡大し、2016年には16.6%を占め第一位の輸入相手国となっている。また、輸出と同様に上位輸入相手国のシェアが縮小しており、輸出先のみならず輸入先の多様化も進んだことが伺える(第Ⅰ-2-6-2-8図)。
第Ⅰ-2-6-2-8図 アフリカの対世界輸入国・地域別のシェアの変化
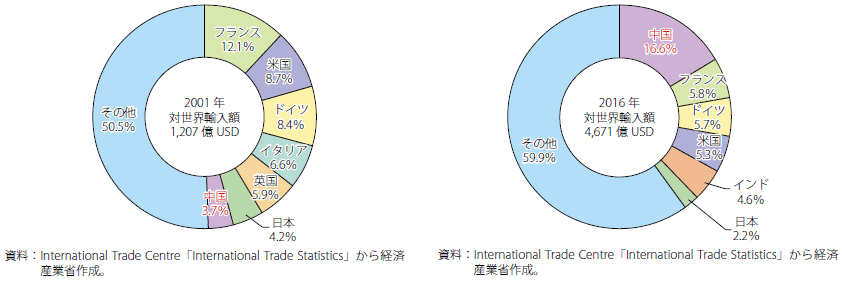
輸出入のどちらにおいても、アフリカにとって中国の存在感は大きく拡大しており、貿易における緊密化が急激に進展している。加えて、近年輸出入双方においてインドの存在感が増していることも伺える。これは、インドが2009年よりアフリカに対する税制優遇措置である特定市場スキームを開始し、インドで製造した製品の輸出を行いやすくしたことが背景にある。特定市場スキームは2015年4月に改訂され、その他のスキームと一体化された。
一方、我が国は、アフリカとの貿易関係における存在感は乏しい。2016年時点でアフリカにおける我が国の輸出シェアは1.6%、輸入シェアは2.2%である。現地のニーズや所得に合った製品がつかめない、現地の商制度や法律がわからない、アフリカという地域の安全面のリスク等、様々な懸念により、我が国企業のアフリカ向け輸出や進出は遅れている。そこで、第三国を経由した輸出、進出が模索されており、上記のような制度を持つインドを拠点、足掛かりとし、アフリカへの輸出、進出を行う企業が、少数であるが徐々に現れてきている。
(3)域内貿易の推進に向けた動き
アフリカでは、域内貿易を推進する動きが活発化している。この動きを象徴するものがアフリカ連合加盟55か国・地域による「アフリカ大陸自由貿易圏(AFCFTA)」設立に向けた取組である。2012年1月にエチオピアのアディスアベバで開催された第18回アフリカ連合加盟国首脳会議の総会において、2017年のAFCFTA設立決定が採択され、2015年6月に交渉が開始された。交渉は2つのフェーズに分かれ、第1フェーズではAFCFTAの設立協定と物品貿易、サービス貿易、紛争解決メカニズムの各分野の交渉がなされた。このうち物品貿易については、90%以上の品目を自由化することにより、現在平均6.1%ある域内貿易関税を引き下げることに合意がなされた。
2018年3月にルワンダのキガリで行われた第10回交渉フォーラムにおいては、フェーズ1の残された論点について議論が行われ、ついに発足が合意された。アフリカ連合加盟55か国・地域のうち11か国は合意を見送ったものの、各国の批准を経て2018年末までの発効を目指すこととなった。232,233
国連アフリカ経済委員会は、AFCFTAによる関税撤廃でアフリカの域内貿易は52.3%増加し、同時に非関税障壁も削減される場合には貿易促進効果は2倍に上ると試算している。また、アフリカの域内貿易構造は、域外貿易構造と比べて資源以外の品目の輸出割合が高いことから、域内貿易の活発化が、域内各国の資源以外の産業における雇用創出につながることが期待されている。
2018年末からは、交渉の第2フェーズとして、知的財産権、投資、競争政策について交渉がなされる予定になっている234。
232 国連アフリカ経済委員会「African Continental Free Trade Area - Question and Answers」
233 AFRICAN BUINESS PARTNERS「週刊アフリカビジネス第388号(3月26日発行)」を参照。
234 交渉第2フェーズで追加的に交渉がなされる可能性があるトピックとして、電子商取引のための環境の円滑化が挙げられている。
