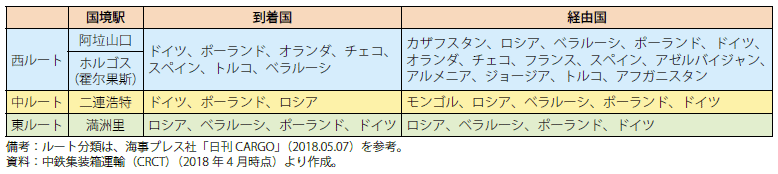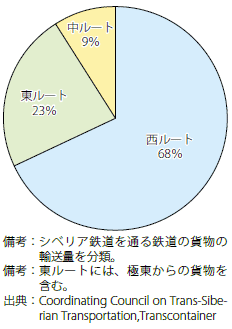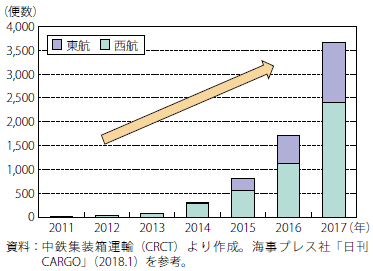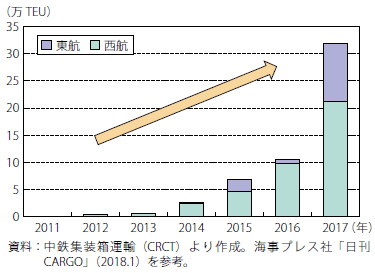第3節 中国の対外貿易投資に関する分析
1.貿易
(1)中国と世界の貿易概況
中国は、2001年のWTO加盟以降僅か15年程度で米国と並ぶ世界最大規模の貿易大国となった。世界の輸出額全体に占める各国の輸出額の割合を見ると、主要先進国の割合が軒並み低下する中で、中国だけは右肩上がりにシェアを拡大し、2004年に日本、2007年に米国、2009年にドイツを追い抜き、2017年は13.0%と世界第1位の輸出国となった。米国は、2000年頃に約12%の割合を占め世界第1位の割合を有していたが、それ以降は割合が徐々に低下していき、2017年は8.8%で中国に次ぐ第2位の割合となっている(第Ⅱ-3-3-1-1図)。
第Ⅱ-3-3-1-1図 主要国の世界輸出に占める割合
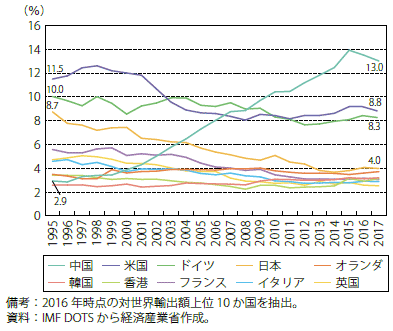
次に、世界の輸入額全体に占める各国の割合を見ると、主要先進国が輸出と同様に輸入においても世界に占める割合を漸減させる中、中国は大幅に割合を伸ばしており、2003年に日本、2009年にドイツを追い抜き、2017年には10.3%と米国に次ぐ第2位の輸入大国となっている。このことは、中国が世界の生産拠点、及び米国に次ぐ巨大な市場として、世界の貿易に強い影響力を持つようになったことを示している。この点、人口数では中国と並び巨大市場となる潜在力を有するインドは、貿易面からは中国ほどの存在感を示すには至っておらず、世界貿易に占めるシェアは、輸出で1.7%、輸入で2.4%(2017年)に留まっている(第Ⅱ-3-3-1-2図)。
第Ⅱ-3-3-1-2図 主要国の世界輸入に占める割合
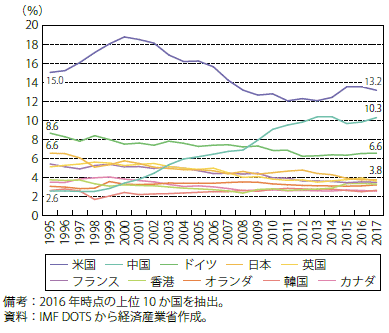
続いて、世界各国にとっての貿易相手国としての中国の存在感の増大についてみていく。
まず、世界各国にとっての最大の輸入相手国について見てみると、2000年には地理的に近接する国が多く、欧州は英国等の一部の国々を除きドイツ、アジアは日本、北米及び中南米は米国が主要な最大の輸入相手国となっていた。しかし、2017年には、カナダ、メキシコ、中南米の一部諸国及び欧州諸国を除き、中国を最大の輸入相手国とする国・地域の数が増加し、世界の約30%(189か国・地域133のうち57か国・地域)と最大を占め、第2位で約15%(同28か国・地域)の米国、第3位で約13%(同24か国・地域)のドイツを大幅に上回っている。また、カナダ、メキシコ及び欧州諸国は、それぞれの域内の中心的工業国である米国やドイツからの輸入が最大であるが、米国は中国が最大の輸入相手国に、ドイツはオランダに次ぐ第2位の輸入相手国が中国となっている(第Ⅱ-3-3-1-3図)。
第Ⅱ-3-3-1-3図 世界各国の最大輸入相手国2000年から2017年の変化
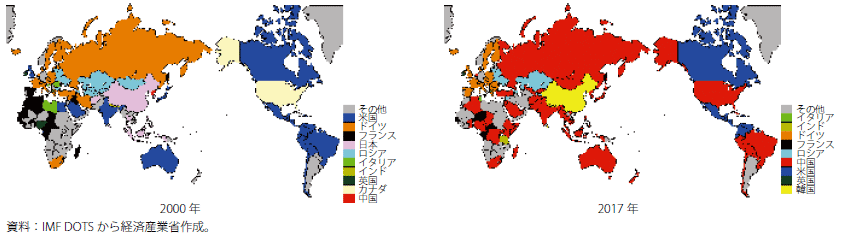
133 IMF DOTSで2017年のデータが取得できた国・地域(2018年4月時点)。
次に世界各国にとっての最大の輸出相手国を見ると、2000年では主に米国、ドイツ、日本が占めていた。しかし、2017年になると、各国の最大の輸出相手国は、ASEANや豪州では日本に代わって中国となった他、アフリカ、南米では米国に代わって、中国を最大の輸出相手国とする国が増加し、世界の約16%(189か国・地域のうち30か国・地域)と第1位である米国の約19%(同35か国・地域)に次ぐ第2位の規模で、第3位であるドイツの約12%(同22か国・地域)を上回っている(第Ⅱ-3-3-1-4図)。
第Ⅱ-3-3-1-4図 世界各国の最大輸出相手国2000年から2017年の変化
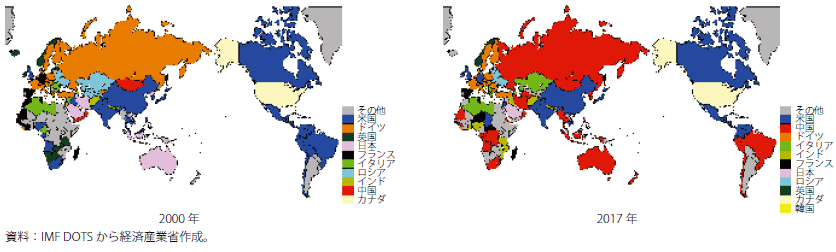
次に、2000年から2017年にかけて、各国の総輸出入に占める中国の輸出入の割合が具体的にどう変化をしたかを確認する。
まず、2000年と2017年の各国の総輸出に占める中国向け輸出割合の変化を見ていく。東アジア・大洋州地域においては、各国の総輸出に占める中国向け輸出の割合は、2000年には10%以下の国が多かったが、2017年にはモンゴル、韓国が20%超となり、日本も6.3%から19.0%まで上昇し、同地域合計での対中輸出割合は2000年の13.2%から2017年には31.7%へと他地域に比べて大幅に上昇した。他に対中輸出割合が10%以上となった地域は、ASEAN地域(同3.8%→13.8%)、中南米(同1.0%→10.2%)、ロシア・CIS(同4.9%→12.1%)、アフリカ(同2.3%→11.9%)、中東(同6.7%→10.6%)となった。北米(同1.8%→7.6%)、欧州(1.0%→4.0%)の対中輸出割合は相対的に低い。いずれの地域でも、2000年から2017年にかけて中国への輸出割合は全体として増加しているが、特に東アジア・大洋州地域を始め、トルクメニスタン、ミャンマー、ラオス、イラン等で大幅な伸びが目立つ(第Ⅱ-3-3-1-5表)。
第Ⅱ-3-3-1-5表 総輸出に占める中国向け輸出の割合(2000年から2017年の変化)
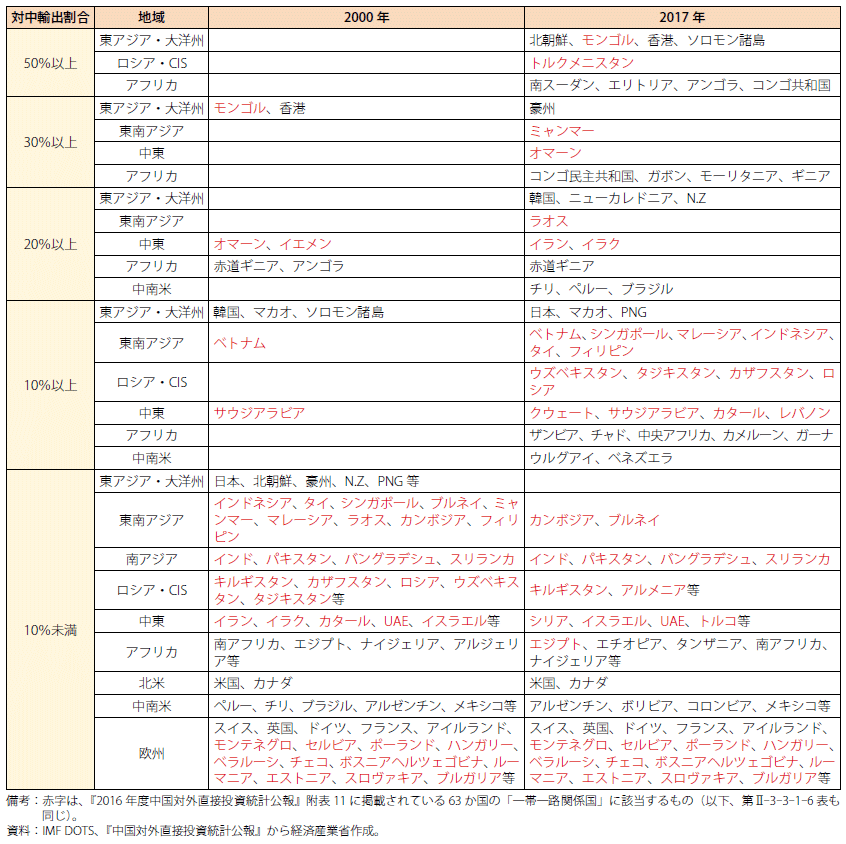
同じく2000年と2017年の各国の総輸入に占める中国からの輸入割合の変化を見てみると、東アジア・大洋州地域においては、中国からの輸入割合30%以上が2か国から4か国、20%以上が1か国から5か国、10%以上が2か国から4か国と、中国からの輸入割合を増やした国が大幅に増加し、同地域全体の対中輸入割合は19.8%から29.1%と急拡大した。
ASEAN地域においては、2000年には全ての国で対中輸入割合が10%未満だったが、2017年には20%以上が5か国となった他、全ての国が10%以上となり、同地域の対中輸入割合は5.0%から19.5%に大幅に高まった。他にも北米(7.0%→20.1%)、ロシア・CIS(1.7%→20.0%)、南アジア(3.9%→17.8%)、中南米(2.3%→17.7%)、アフリカ(3.0%→14.1%)、中東(3.8%→11.1%)、欧州(2.7%→7.3%)と全ての地域で対中輸入割合がこの17年間で高まってきた(第Ⅱ-3-3-1-6表)。
第Ⅱ-3-3-1-6表 総輸入に占める中国からの輸入の割合(2000年から2017年の変化)
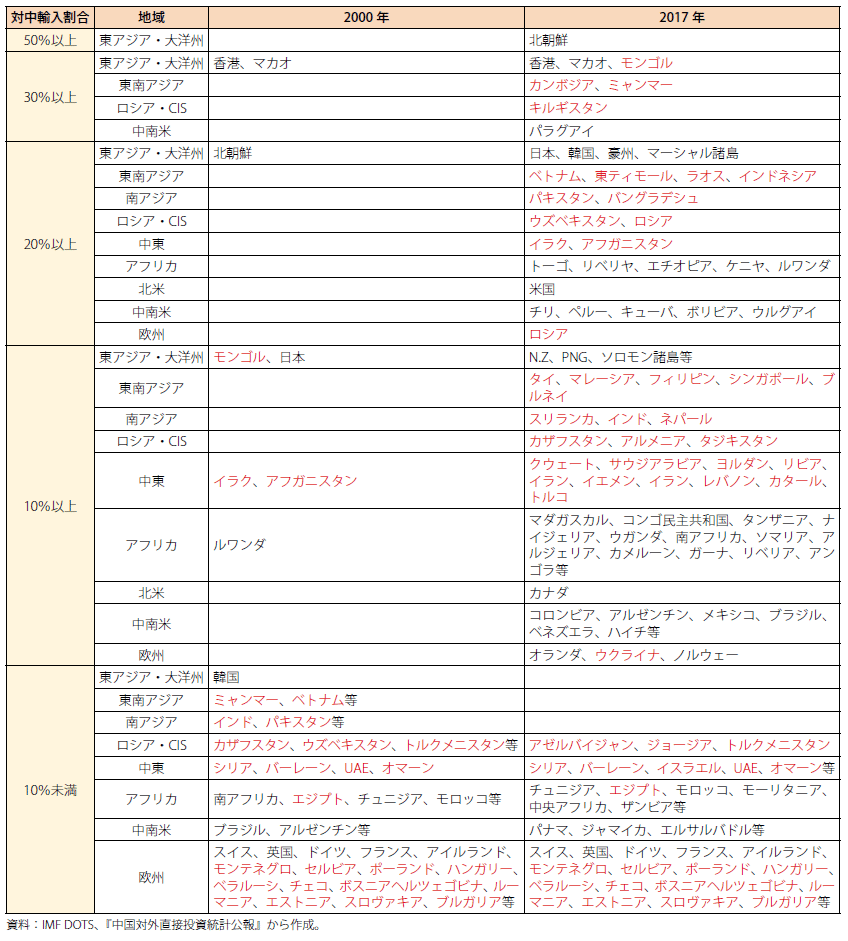
各地域の対中輸出割合と対中輸入割合を比較すると、対中輸入割合の増加が対中輸出割合の増加より大きい傾向にある。
続いて、中国の貿易相手上位10か国・地域の顔ぶれの変化を見ていく。
まず、輸出相手上位10か国・地域をみると、2017年は米国が最大で、EU28、香港、日本、韓国と続いている。この5か国・地域は、2000年の上位5か国と同一である(第Ⅱ-3-3-1-7図)。他方で、中国の輸出総額に占める米国向け輸出額の割合は、2006年以降は20%超から低下傾向になったが、2015年から上昇に転じ、2017年には19.0%となった。EU28向け輸出の割合は、2011年以降に減少傾向で2017年には16.4%となった。主要上位10か国・地域向けの輸出額が中国の総輸出額に占める割合は、2000年の80.7%から2017年には64.5%まで下がっており、中国の輸出先が多様化していることが伺える。また、2017年には、ベトナム、インドが中国の輸出相手国の上位に位置するようになった(第Ⅱ-3-3-1-8表)。
第Ⅱ-3-3-1-7図 中国の主要輸出相手国向け貿易額の推移
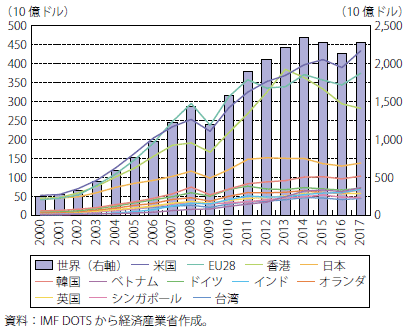
第Ⅱ-3-3-1-8表 中国の輸出額上位10か国・地域の占める割合の変化
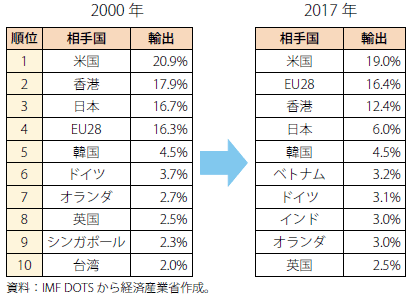
次に、中国の輸入相手先上位10か国・地域を見ると、対EUからの輸入額が最も大きく、韓国、日本と続いている。上位5か国・地域の顔ぶれは2000年、2017年共にEU、韓国、日本、台湾、米国で変化はないが(第Ⅱ-3-3-1-9図)、米国、EUが割合を上昇させた一方で、日本は2000年の18.4%から2017年は9.0%と割合が大幅に低下した(第Ⅱ-3-3-1-10表)。主要上位10か国・地域134からの輸入額が中国の総輸入額に占める割合は、2000年の64.1%から2017年は60.3%と若干低下した。
第Ⅱ-3-3-1-9図 中国の主要輸入相手国向け貿易額の推移
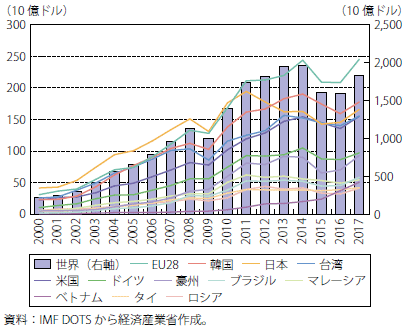
第Ⅱ-3-3-1-10表 中国の輸入額上位10か国・地域の占める割合の変化
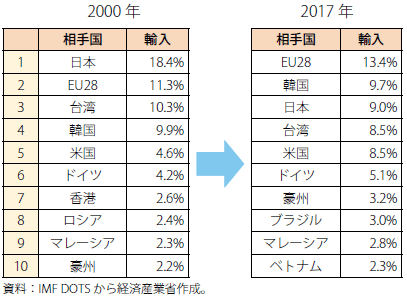
134 重複を避けるため図表の上位10か国・地域のEU加盟国英国、ドイツ、オランダの貿易額を差し引いて割合を算出。
次に、中国の貿易統計により、2000年と2017年の中国の貿易収支の黒字上位10か国・地域と赤字上位10か国・地域の変化を見ていく。
中国の貿易黒字相手国・地域の上位3位は香港、米国、オランダで変化がない一方、2017年にはインド、ベトナム、UAE、パキスタン等が上位に入り、中国が新興市場向けの輸出を活発に行っていることが伺える(第Ⅱ-3-3-1-11図)。上位3か国との貿易における輸出入に占める品目の割合では、米国への輸出は、履物や玩具からパソコン等(HS8471)10.1%、携帯電話機等(HS8517)10.7%等の工業製品が主となり、輸入は農産物の他、航空機・宇宙飛行体(HS8802)9.3%、自動車(HS8703)8.5%、半導体(HS8542)7.0%等の工業製品の占める割合が高くなってきた。
第Ⅱ-3-3-1-11図 中国の貿易黒字相手国上位10か国の変化
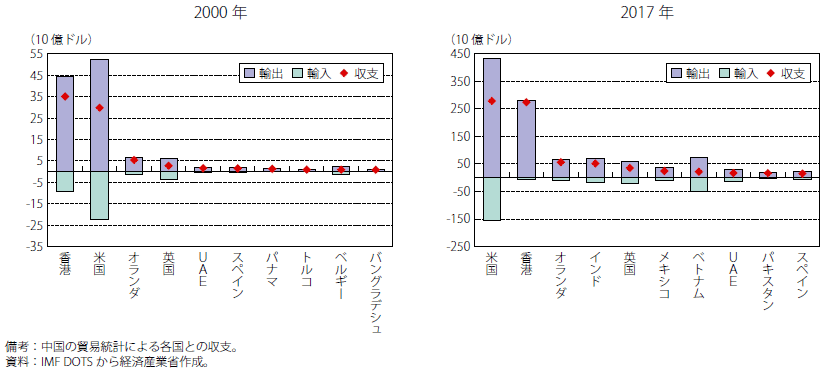
中国の貿易赤字相手国・地域の上位2位は台湾、韓国で変化はないが、2017年には日本、ドイツ、スイス等の工業国が上位に入ってきた。中国がより高付加価値な資本財、消費財及び部品を先進国から輸入するようになったと考えられ、中国の貿易構造が変化したことが示唆される(第Ⅱ-3-3-1-12図)。
第Ⅱ-3-3-1-12図 中国の貿易赤字相手国上位10か国の変化
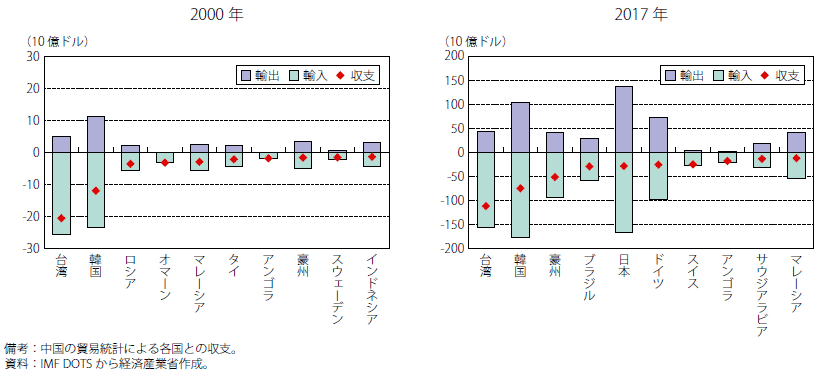
中国の貿易赤字相手上位3か国・地域との貿易品目(HS4桁)を見ると、台湾への輸出に占める品目の割合は半導体(HS8542)19.7%、台湾からの輸入に占める品目の割合も半導体(HS8542)51.9%が最大となっており、双方で半導体産業の分業体制が進んでいることが分かる。
韓国への主要な輸出品は、農産物や石炭の一次資源から、2017年には、輸出品目では携帯電話機等(HS8517)14.3%、半導体(HS8542)8.8%等の技術力を要する工業製品が主となった。また、韓国からの輸入品は半導体(HS8542)36.9%、液晶デバイス(HS9013)5.7%が主たるものである。これらのデータから、中国と韓国との間にも電気機器産業のサプライチェーンが構築されていることが示唆される。
また、2017年時点で第3位の豪州、同4位のブラジルにおいては、資源輸入の割合が高く、鉄鉱石等(HS2601)は豪州からの輸入の53.8%、ブラジルからの輸入の29.7%を占めている。また、原油(HS2709)は、アンゴラからの輸入の97.2%、ロシアからの輸入の57.6%を占めている。その他、スイスからの輸入は腕時計等(HS9102)14.4%が最大となっており、中国における工業の発展や市民の消費力の向上が示唆される。
次に、中国が推し進める一帯一路の関係国135と中国との貿易関係についてみていく。一帯一路関係国で中国からの輸出が多い上位10か国のうち6か国がASEAN加盟国(ベトナム、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン)であり、他はインド、ロシア、UAE、イランとなっている。輸入が多い上位10か国でもASEAN加盟国が6か国を占め、他はロシア、サウジアラビア、イラン、インドとなっており、一帯一路関係国の中ではASEANと中国の貿易関係が特に強いことを示している。
一帯一路関係国との貿易額は、2017年で中国の輸出総額の28.1%、輸入総額の24.7%を占め、一帯一路関係国合計で収支を見た場合、中国の2,201.4億ドルの黒字となり、対EU収支の1,295.4億ドルを超え、対米収支の2,788.1億ドルに迫る規模となっている(第Ⅱ-3-3-1-13図)。
第Ⅱ-3-3-1-13図 中国と米国、EU、一帯一路関係国との貿易額比較
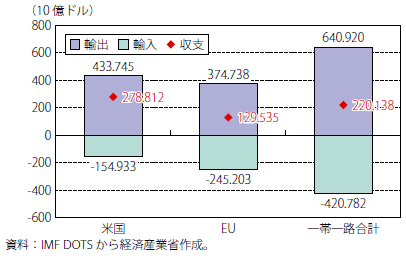
135 『2016年度 中国対外直接投資統計公報』附表11に掲載されている63か国のうち貿易データが存在する62か国・地域。
一帯一路関係国との収支を国別にみると、中国の最大の貿易黒字国はインドで、携帯電話等、半導体、パソコンを主要製品として輸出しているが、輸入は輸出に比して大幅に少なく、宝石、精銅等が主要品目となっている。第2位の貿易黒字国であるベトナムについてはインドと異なり、中国からの輸出と輸入の双方が大きく、携帯電話等、半導体、繊維製品等を主に輸出し、輸入も同様に携帯電話等、半導体、テレビ等の部分品、綿糸等が主な品目となっており、両国間で電気製品や繊維製品の分業がなされていることを示唆している。
また、中国の最大の貿易赤字国はサウジアラビアで、主な輸入品目は原油、輸出品目は携帯電話等、エアコン、繊維製品となっている。その他、一帯一路関係国で中国が貿易赤字となった国は、中国の主要輸入品目が原油や鉱物となる資源国が多い傾向にある(第Ⅱ-3-3-1-14図)。
第Ⅱ-3-3-1-14図 中国と一帯一路関係国との貿易収支
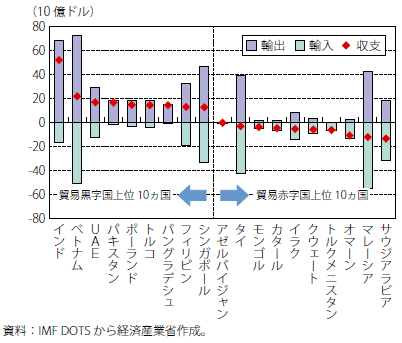
続いて、中国の主要輸出品目を概観した上で、各品目の輸出競争力についてみていく。
まず、中国の主要輸出品についてみると、電気機器(電話機、集積回路、テレビ・モニター)、一般機械(自動データ処理機械、事務機器部品、プリンター)、家具、衣類、精密機械(液晶デバイス、医療用機器、自動調整機器)となっている。機械品目が多いが、軽工業品も上位を占めている(第Ⅱ-3-3-1-15図)。
第Ⅱ-3-3-1-15表 中国の主要輸出品目の金額と主な輸出先(2017年)
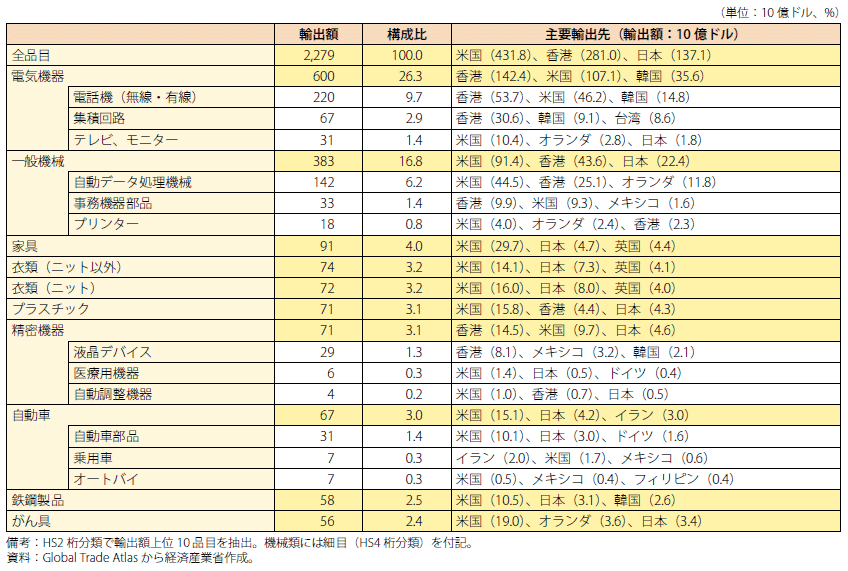
さらにHS4桁ベースで個別品目別の輸出額の推移を見ると、軽工業品やテレビ等の家電の輸出金額は横ばいとなっている一方、携帯電話やパソコン等のハイテク製品の伸びが大きく、後述する世界輸出におけるシェアの高まりと共に、中国がハイテク製品の世界的な生産拠点に成長してきたことを示している(第Ⅱ-3-3-1-16図)。
第Ⅱ-3-3-1-16図 中国の上位輸出品目の推移
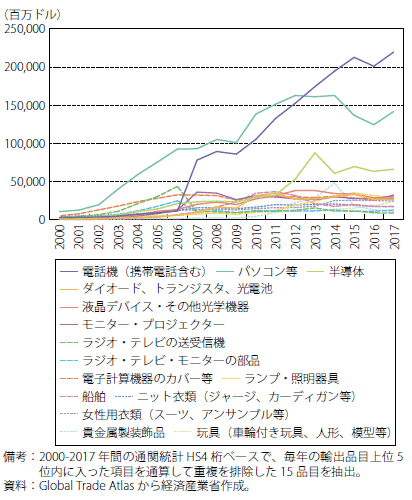
一方、中国の主要輸入品は、電気機器(集積回路)、一般機械(自動データ処理機械、半導体製造装置、事務機器部品)、精密機械(液晶デバイス)等の機械類のほか、鉱物性燃料、鉱石などの資源や、大豆などの食品となっている(第Ⅱ-3-3-1-17図)。
第Ⅱ-3-3-1-17表 中国の主要輸入品目の金額と主な輸入先(2017年)
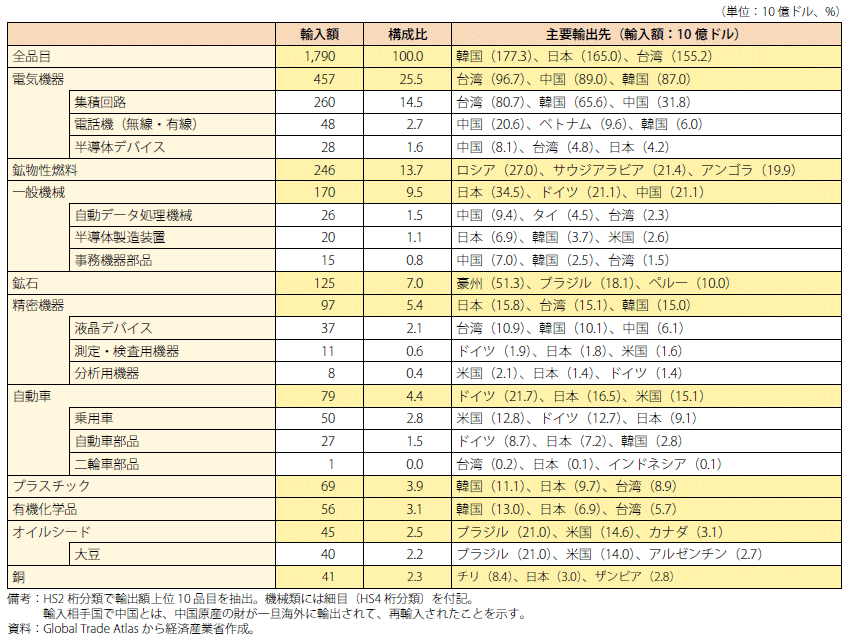
さらにHS4桁ベースで個別品目ごとの輸入額の推移を見ると、集積回路の輸入が原油を上回る勢いで急速に伸びてきている。他にも液晶デバイスやダイオード等の半導体デバイスが鉄鉱と共に輸入品の上位を占めており、中国がハイテク製品の生産を行うために海外から多くの部品を輸入していることを示している(第Ⅱ-3-3-1-18図)。
第Ⅱ-3-3-1-18図 中国の上位輸入品目の推移
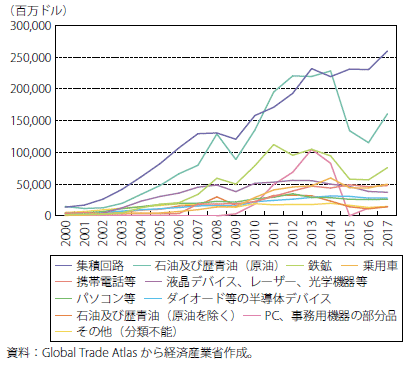
次に、中国の主要輸出品目が世界の輸出において、どの程度の存在感があるのかを世界の輸出合計に占める中国のシェアの推移からみていく。
まず、皮革製品、履物、衣類など軽工業品については、2000年代初頭から世界シェアを上昇させてきており、最近では横ばいとなっているものの、世界輸出の約40%の割合を占めている。一方、2000年代初頭にはシェアが低かった一般機械や電気機器がその後シェアを高め、2016年には一般機械が約20%、電気機器が約30%となり、WTO加盟後の15年余りの間に輸出競争力を大きく高めたことが伺える(第Ⅱ-3-3-1-19図)。
第Ⅱ-3-3-1-19図 中国の主要輸出品が世界輸出に占めるシェア
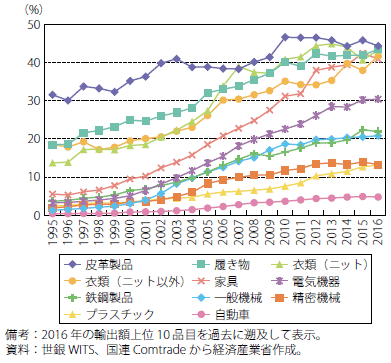
中国の主要輸出品の競争力を貿易特化係数136で見ると、衣類、履物等の軽工業品が2000年代初頭から現在まで高い貿易特化係数を維持していることがわかる。ただし、中国の輸出額全体に占めるシェアは次第に低下した。代わって、電気機器、一般機械が、2000年代初頭にマイナスであった貿易特化係数をプラスに転じるとともに、輸出額全体に占めるシェアを拡大し競争力を高めている。
なお、同時期に、日本は、電気機器、一般機械の輸出特化係数及び輸出額全体に占めるシェアが次第に低下し、代わって自動車が最大の輸出品目となっている(第Ⅱ-3-3-1-20図)。
第Ⅱ-3-3-1-20図 中国の主要品目の競争力(貿易特化係数)
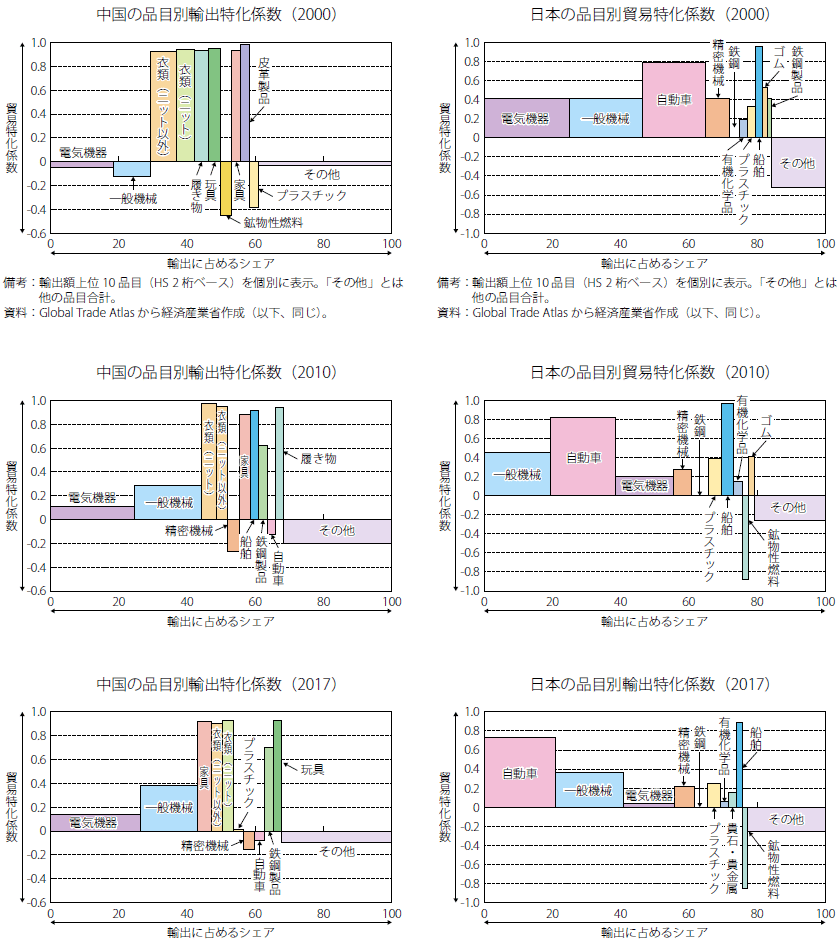
- Excel形式(a)のファイルはこちら

- Excel形式(b)のファイルはこちら

- Excel形式(c)のファイルはこちら

- Excel形式(d)のファイルはこちら

- Excel形式(e)のファイルはこちら

- Excel形式(f)のファイルはこちら

次に、各国が中国の過剰生産能力化を問題視するいくつかの品目(鉄鋼及びアルミニウム137、太陽電池セル138、化学製品及びセラミック製品139)について、輸出の推移をみてみる。
各品目の世界輸出額合計に占める中国の輸出の割合を、他の主要輸出国の割合と比較すると、2000年当時は、鉄鋼、アルミニウム、太陽電池セルの中国のシェアは、他の主要輸出国と比較して小さなシェアだったが、急速にシェアを拡大し、2010年以降は中国が概ね世界最大の輸出国となっている。特に鉄鋼やアルミニウムにおいては、世界全体の輸出金額の伸びが緩やかあるいは下降している中、世界全体の輸出額に占める中国のシェアが顕著に拡大している(第Ⅱ-3-3-1-21図)。
第Ⅱ-3-3-1-21図 鉄鋼、アルミニウム、太陽電池セル輸出に占める主要国の割合
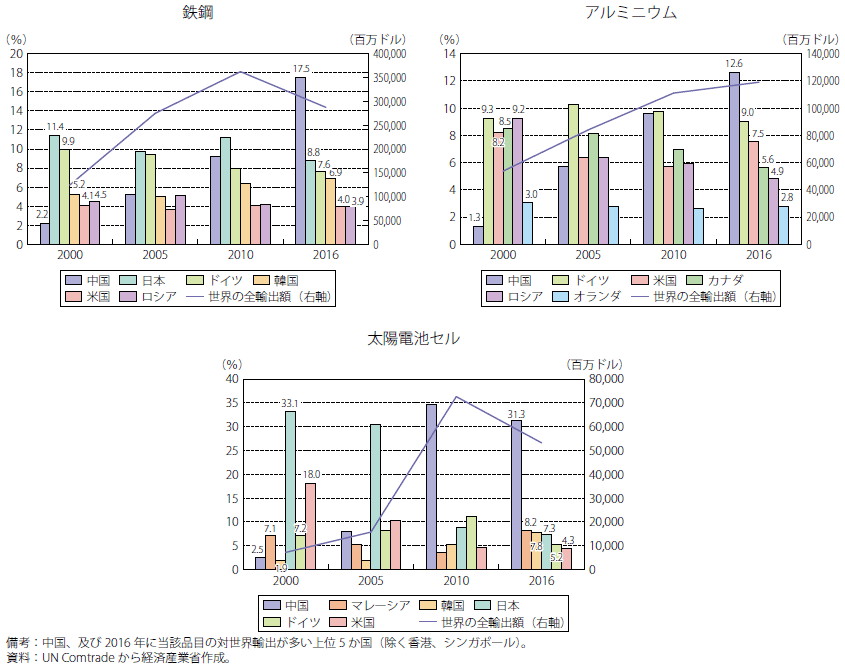
セラミック製品は、世界の総輸出額も伸びているものの、中国の輸出金額が占める割合が大幅に拡大しており、中国製品が同部門で市場を席捲していることが伺える。また、化学製品のうちEUや米国のAD措置の対象となった炭酸バリウムについては、世界全体の輸出額が落ち込んだ2000~2005年においても、中国の輸出額が占める割合は上昇している。他にも中国の過剰生産が指摘される高重度ポリエチレンテレフタレートも世界の総輸出額が微減する中、中国は輸出額に占める割合を大幅に伸ばしている(第Ⅱ-3-3-1-22図)。
第Ⅱ-3-3-1-22図 セラミック、化学製品輸出に占める主要国の割合
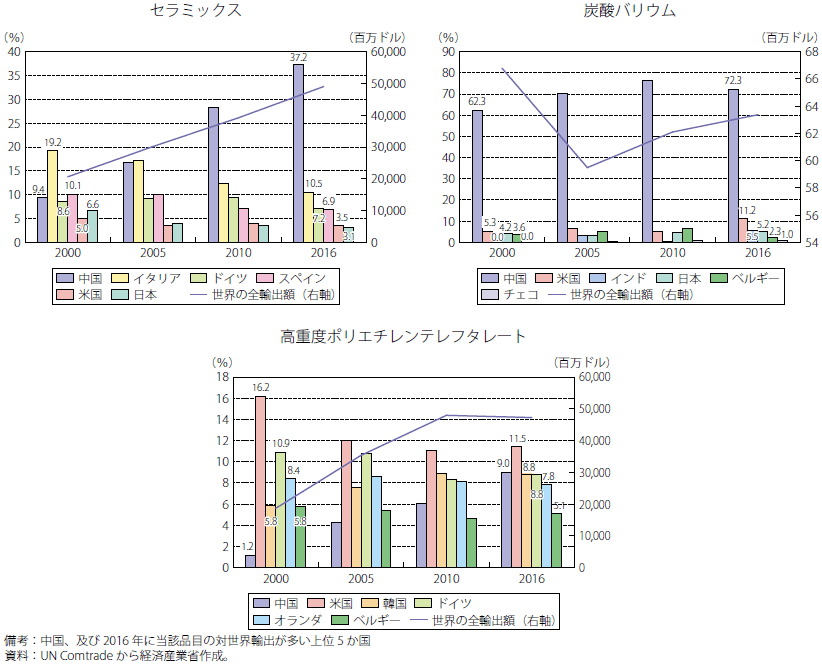
136 貿易特化係数は各産業がどれだけ輸出に特化しているかを示す指標で、貿易特化係数=貿易黒字額/貿易総額=(輸出-輸入)/(輸出+輸入)で表される。
137 1962年通商拡大法232条に基づく米国大統領布告(9704、9705)に記載された製品を集計。
138 米通商法201条に基づく緊急輸入制限。
139 欧州委員会は、2017年に公表した報告書“Commission Staff Working Document On Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defense Investigations”の中で、鉄鋼とアルミニウムに加えて、化学製品とセラミック製品の供給過剰についても懸念を示している。
(2)付加価値貿易から見た中国の貿易
かつて中国は、世界から工作機械、部品、原材料を購入して安い人件費で製品を組み立てて輸出しており、中国の輸出には外国で創出された付加価値が高い割合を占めると言われていたが、中国国内で創出された付加価値の輸出の推移について、OECDが国際産業連関表を基に算出した付加価値貿易のデータ(OECD TiVA)から見てみる。従来の貿易統計は生産物(財)を対象としているのに対し、付加価値貿易は製品やサービスができあがるまでに、どの国でいくらの価値が加わったかを推計したものである140。なお、付加価値貿易には財、サービスの両方が含まれており、本稿では産業別に分析した箇所を除き、財とサービスを含む数値を用いている。
中国の付加価値貿易は他の主要国と比べても急速に伸びており、2000年には米国の付加価値輸出の19.4%の規模しかなかった中国の付加価値輸出が2014年には87.9%となり、米国と並ぶ規模の付加価値輸出国となった(第Ⅱ-3-3-1-23図)。
第Ⅱ-3-3-1-23図 主要国の付加価値輸出141の変化
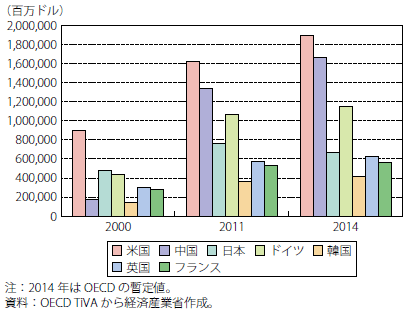
また、世界の付加価値輸出に占める割合も米国に次ぐ第2位の高さとなっており、主要先進国の割合が漸減傾向にある中、中国が先進国と比べて急速に付加価値輸出を増加させていることが分かる(第Ⅱ-3-3-1-24図)。
第Ⅱ-3-3-1-24図 主要国の世界付加価値輸出に占める割合
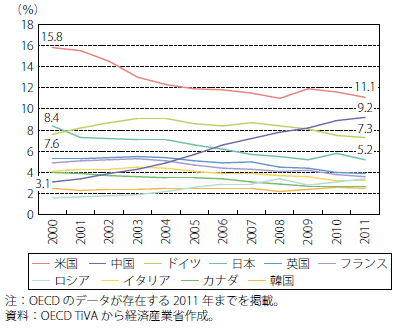
次に、付加価値ベースと通関ベースで中国の輸出全体に占める産業別の割合を見てみると、中国の輸出を牽引する産業は、繊維産業から電機・光学機器産業へと変化していることが分かる。また、中国の電気、光学機器産業の付加価値ベースでの輸出の伸びは、通関ベースの輸出の伸びを上回っている。中国国内での付加価値割合も高まっており、部品の現地調達化・製品の高付加価値化が進展していることが伺える(第Ⅱ-3-3-1-25図)。
第Ⅱ-3-3-1-25図 中国と日本の世界輸出に占める産業別輸出割合の変化
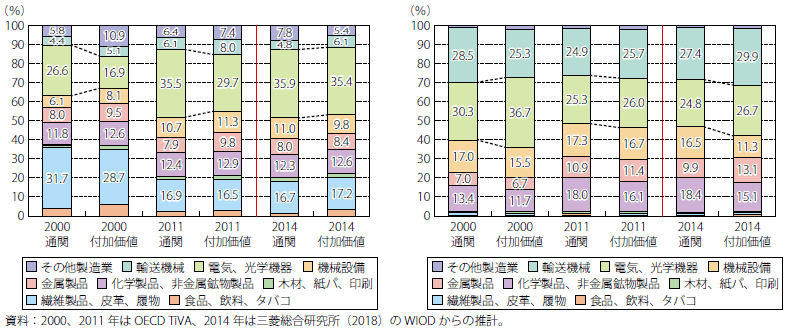
主要国の粗輸出に含まれる自国で創出された付加価値の比率を見ると、米国、日本、韓国、ドイツとも減少傾向なのに対して、中国は増加傾向にある。これは、中国が外国の付加価値を利用しなくても、自国内で付加価値を創出できるようになってきたことを意味する。具体的には、従来輸入に頼っていた部品を自前で生産可能となる、あるいは外国に依存していたサービスを国内でも行うことが可能となった等の状況の変化があったことを示唆している。逆に日本や米国等は、グローバルサプライチェーンの進展により、これまでより多くの外国創出付加価値を利用するようになっていることが伺える(第Ⅱ-3-3-1-26図)。
第Ⅱ-3-3-1-26図 各国の輸出に含まれる自国創出付加価値の比率
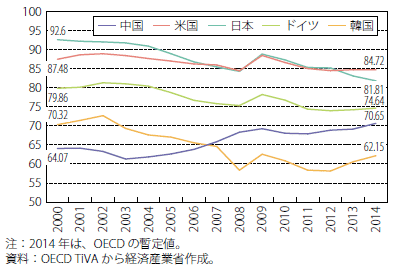
主要国の輸出に占める自国創出付加価値の割合を産業別に見ると、中国の電機・光学機器産業の付加価値比率が低いのが特徴的である。これは、貿易品目の分析でも見られたように中国は半導体や液晶パネルを他国から多く輸入しており、同産業でグローバルバリューチェーンを利用した生産が活発に行われているためだと考えられる。電機・光学機器は、現在では低めの付加価値比率であるものの、上昇基調で推移しており、今後は「中国製造2025」等で計画されている産業政策の実施や民間企業による研究開発や外国企業との協力が促進されることで、さらに上昇していく可能性があると思われる(第Ⅱ-3-3-1-27図)。
第Ⅱ-3-3-1-27図 主要国の輸出に占める自国創出付加価値の割合
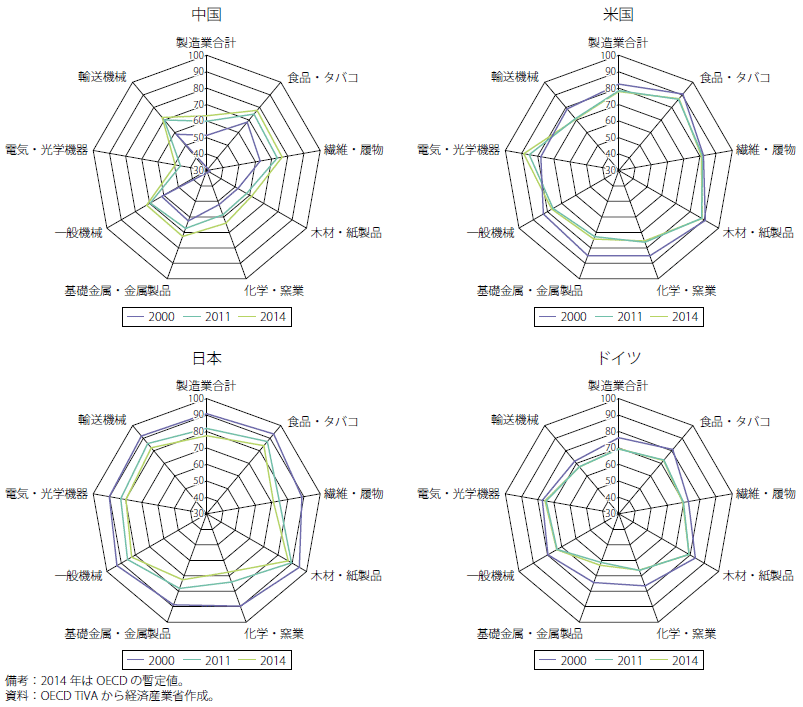
140 猪俣(2014)、広田(2017)
141 本稿では「付加価値輸出」について、OECD TiVAの“Domestic value added content of gross exports”の数値を使用。https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=75537![]()
(3)付加価値ベースと通関ベースの比較による中国の貿易内容の変化と特徴
貿易を分析する視点として比較優位に注目することは、政策的にも学術的にも欠かせない。本項では、貿易統計及び付加価値貿易統計(第Ⅱ-3-1-3-28表)に基づいて142算出した顕示比較優位(Revealed Comparative Advantage:RCA)指数143から、中国の比較優位構造の変化を分析する。
第Ⅱ-3-1-3-28表 RCA指数算出諸元
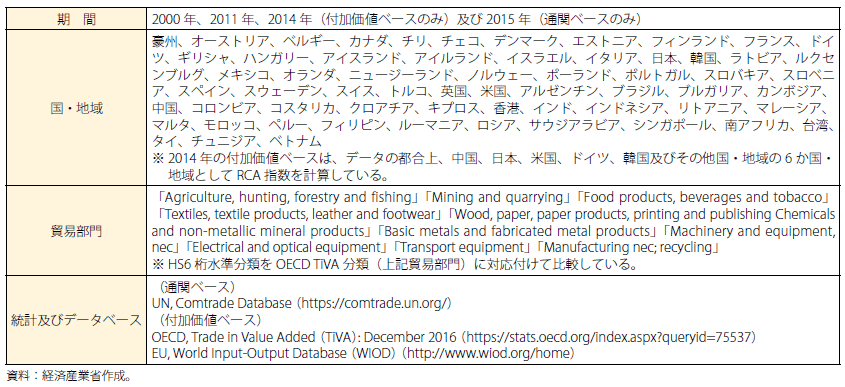
RCA指数は、比較優位を定量的に分析するために開発された指標であり、その研究者の名を冠してBalassa指数とも呼ばれている。本指数の定義式は、ある輸出部門について自国における輸出割合と世界全体における輸出割合の比率となっている144。ある部門について、国内輸出額割合が世界輸出額割合より高いということは、その部門の生産・輸出能力が相対的に高い(優位にある)ことを示唆している。このとき、RCA指数は1より大きい値になる。逆に、その部門の生産・輸出能力が相対的に低い(劣位にある)とき、RCA指数は1未満の値になる。
中国の輸出構造について、通関ベースと付加価値ベースの輸出額から算出したRCA指数に基づいて2000年、2011年及び2015年の3時点の比較から特徴を示していく。
2000年において、RCAの最高値は通関ベース、付加価値ベースともに「繊維・皮革製品・履物」であり、値はそれぞれ3.82(CC)、4.38(VA)である。通関ベースのRCAを基準にすると、第2位以降は「その他製造品(再利用含む)」(CC:2.40, VA:3.13)、「電機・光学機器」(CC:1.05, VA:0.79)と続く。
ここで注目しておきたい点は、第3位の「電機・光学機器」である。通関ベースのRCAは比較優位があるとされる1以上であるが、付加価値ベースのRCAは比較優位がないとされる1未満である。しかしながら、輸出額そのものは通関ベース、付加価値ベースともに輸出額の第2位となっている(CC:538億4,800万ドル、VA:163億7,500万ドル)。比較優位の有無が通関ベースと付加価値ベースで分かれている部門は、本部門と「基礎金属・金属製品」(CC:0.96, VA:1.06)の2部門だけである。本部門とは対照的に、後者においては通関ベースでは比較優位がなく、付加価値ベースでは比較優位があるという結果になっている。
この時点において、輸出構造上は比較優位部門(CC:3部門、VA:3部門)より比較劣位部門(CC:8部門、VA:8部門)の方が多い。また、軽工業関連部門に優位性が偏っていることがわかる。
2011年において、RCAの最高値は通関ベース、付加価値ベースともに2000年と同様、「繊維・皮革製品・履物」(CC:3.08, VA:3.89)である。第2位以下も2000年と同様に「その他製造品(再利用含む)」(CC:2.02, VA:2.64)、「電機・光学機器」(CC:1.77, VA:2.38)と続く。
2000年と比較して輸出額全体が大きく伸びていることを反映して、比較優位構造も大きく変化している。特に、「電機・光学機器」のRCAは、2000年において比較優位を持つか持たないかの境界線上であったにもかかわらず、通関ベースのRCAはさらに高くなり、付加価値ベースでは比較優位化している。本年においては比較優位の存在を十分に認められる水準にまで高まっている。
この部門以外では、「機械器具等」が2000年には比較優位のない水準(CC:0.63, VA:0.81)であったが、2011年には比較優位を持つようになっている(CC:1.80, VA:1.76)。また、比較優位化こそしていないが、「木材・紙製品・印刷出版」(CC:0.71, VA:0.55)及び「輸送機器」(CC:0.52, VA:0.78)は通関ベース、付加価値ベースともにRCAを伸ばしており、「化学・非金属鉱物製品」(CC:0.57, VA:0.72)は付加価値ベースでRCAを伸ばしている。
比較優位構造は、比較優位部門が通関ベースで4部門、付加価値ベースで5部門となっており、2000年と比べてそれぞれ1部門、2部門増えている。また、2000年と比べて、「電機・光学機器」のRCAが上昇している一方で、「繊維・皮革製品・履物」のRCAが低下している点は、軽工業部門から電気機械関連部門への比較優位上の構造変化を示唆しているものと考えられる。
2000年から2011年にかけて中国の輸出構造・比較優位構造が大きく変化していることは前述のとおりであるが、統計を入手可能な直近の状況(通関ベースは2015年、付加価値ベースは2014年)についても触れておく。
2015年において、最もRCAが高い部門は「繊維・皮革製品・履物」(CC:2.58, VA:2.57)である。以下、「その他製造品(再利用含む)」(CC:1.80, VA:1.46)、「電機・光学機器」(CC:1.60, VA:2.12)と続く。比較優位部門の数は通関ベースで4部門、付加価値ベースで4部門となっており、2011年と比べて付加価値ベースで1部門(「基礎金属・金属製品」)が比較劣位化している。
この年において特徴的な点は、2000年から比較優位の上位部門であった「繊維・皮革製品・履物」及び「その他製造品(再利用含む)」のRCAが、2011年までは付加価値ベースの値が通関ベースの値を上回っていたにもかかわらず、通関ベースが付加価値ベースを上回るようになったことである。RCA指数の示唆するところに従うならば、これらの部門においては付加価値としての比較優位と輸出額としての比較優位が逆転したということになる。この事実は、近年になって比較優位を伸ばしてきている「電機・光学機器」が2000年のRCAは付加価値ベースより通関ベースの方が高く、直近のRCAは通関ベースより付加価値ベースが高くなっていることとは対照的である。
2011年と比べてあまり大きな変化を確認することはできないが、軽工業関連部門から電気機械関連部門への比較優位のシフトが徐々に進行していることがわかる。また、比較優位部門と比較劣位部門のRCAの差が縮小してきている。このことは、RCA指数を少ない部門数で計算する場合によく観測されることであるが、我が国あるいは米国など世界輸出総額に占める1国の輸出額が大きい国に見られる特徴の一つである。これらのことから、中国は貿易額の大きさだけでなく、比較優位構造の特徴としても世界の主要国になりつつあることがわかる。
第Ⅱ-3-1-3-29図 中国RCA指数の通関ベースと付加価値ベースの比較(2000年)
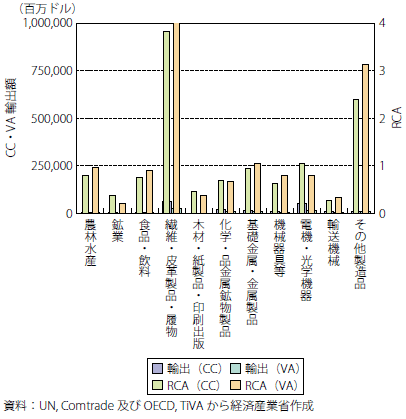
第Ⅱ-3-1-3-30図 中国RCA指数の通関ベースと付加価値ベースの比較(2011年)
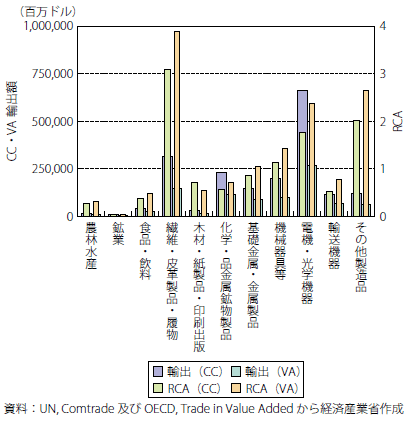
第Ⅱ-3-1-3-31図 中国RCA指数の通関ベースと付加価値ベースの比較(2015年)
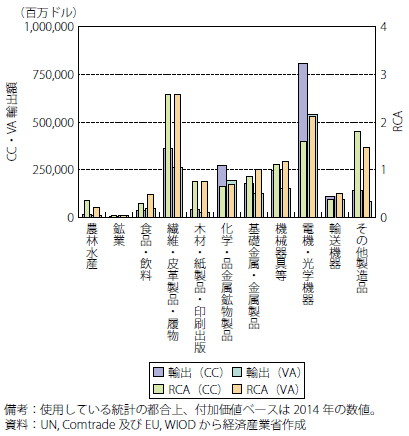
中国の輸出部門における2000年から2011年にかけた通関ベースと付加価値ベースの比較優位の変化について、RCA指数を対称変換したRSCA(Revealed Symmetric Comparative Advantage)指数145を用いて表したものが第Ⅱ-3-1-3-32図である。輸出部門を表す点が図中の右上に位置していれば、通関ベースでも付加価値ベースでも比較優位を有する部門であることを意味する。同様にして、左上に位置している場合は通関ベースで比較劣位かつ付加価値ベースで比較優位、左下に位置している場合は通関ベースでも付加価値ベースでも比較劣位、右下に位置している場合は通関ベースで比較優位かつ付加価値ベースで比較劣位である。
第Ⅱ-3-1-3-32図 中国RSCA指数の通関ベースと付加価値ベースの変化
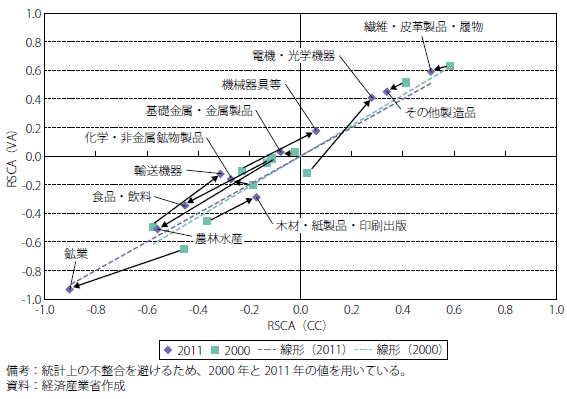
特徴的な変化として注目しておきたい部門は、「電機・光学機器」及び「機械器具等」である。前者は通関ベースでは比較優位部門が継続しているが、付加価値ベースでは比較劣位から比較優位に転換している。後者は、通関ベースでも付加価値ベースでも比較劣位だったが、いずれのベースにおいても比較優位に転換している。また、「基礎金属・金属製品」は、付加価値ベースの比較優位があるにもかかわらず、通関ベースの比較劣位が続いている。
比較劣位化した部門を確認することはできないが、比較優位部門であっても「繊維・皮革製品・履物」及び「その他製造品(再利用含む)」はRCAが低下している。RCAの低下幅は、比較劣位部門において大きくなっており、「鉱業」、「農林水産」及び「食品・飲料」の3部門は、中国の輸出部門の中でRCA変化率の下位3部門に該当する。
2011年において比較劣位にある部門であっても、RCAが低下するより上昇する傾向を見受けられる点は、構造変化の特徴として興味深い。2011年時点においては、まだ比較優位部門より比較劣位部門の方が多いが、それぞれの部門におけるRCA指数の変化の方向を考えると、遠からず比較優位部門が増えていくことが想像に難くないであろう。
142 貿易統計に基づいて計算したRCA指数を通関(Custom Clearance: CC)ベース、付加価値貿易統計に基づいて計算したRCA指数を付加価値(Value Added: VA)ベースと記述する。
143 Balassa, B. (1965).
144 RCA指数=(ある部門の輸出額/自国の輸出合計額)/(ある部門の世界輸出合計額/世界輸出合計額)。
145 RSCA指数=(RCA指数-1)/(RCA指数+1)。対称変換すると、指数の値の範囲が-1から1までになることから、国・地域間あるいは部門間を比較する際の便宜性がよくなる。Cf. Laursen, K. (1998).
(4)中国政府による輸入促進に向けた動き
上述したとおり、輸出の拡大が目立つ中国であるが、2017年から本年にかけては、輸入を促進しようとする動きが見られ始めた。2018年4月に開催されたボアオ・アジアフォーラム 2018年度年次総会において、習主席は、市場参入の大幅な緩和、魅力ある投資環境の創造、知的財権保護の強化に加えて、輸入拡大についての措置を講じると発言している。
具体的な輸入拡大措置としては、中国の国内製品では消費者ニーズに対応しきれない製品を安く輸入できるようすることで、海外流出する消費を呼び戻し内需拡大につなげる目的で、2017年12月1日から食品(乳児用粉ミルク等)、家電(電動シェーバー、電動歯ブラシ、温水洗浄便座等)、日用品(紙オムツ、魔法瓶、衣類、化粧品等)等の187品目の輸入関税を引き下げた。
他にも、イノベーションの発展や供給サイドの構造改革を支援するため需要の大きい品目の輸入奨励を目的に先進設備、基幹部品、エネルギー原材料等の948品目の関税をWTO協定の最恵国税率より低い暫定税率に2018年1月より変更した他、FTA締結国への関税引き下げなど、自国の産業構造改革や内需拡大のために昨年末から活発な対応をしている。
さらに、中国は、貿易自由化・経済グローバル化を推進し積極的な市場開放を主導し、開放型の世界経済発展を促進するためとして、同国で初めてとなる国際輸入博覧会を2018年11月に上海において開催することを発表している。
2.対外直接投資
(1)中国の対外直接投資の推移
本項では、中国の対外直接投資の推移や特徴についてみていく。
中国は、2000年以降、海外資源の獲得、中国企業の国際競争力強化などを目的に「走出去」(海外進出のための政策)を導入し、対外直接投資を推進してきた154。海外投資に関する法制度の整備・緩和を累次実施したことも功を奏し、対外直接投資は右肩上がりに増加してきており、2014年には従来の海外投資の許可制から登録制が主となる制度に移行したことで投資額が一段と増加した155。
中国の対外直接投資を残高ベースでみると、2000年から一貫して増加してきており、2017年時点では米国を除く先進諸国と同等の規模(約1兆4,820億ドル)になっている。また、フローベースでみても、2000年から2016年にかけて一貫して増加し、2015年には日本を追い抜き、米国に次ぐ世界第2位の投資国になった(第Ⅱ-3-3-2-1図)。さらに、同年初めて対外直接投資の額が対内直接投資の額を上回った。しかし、近年、不動産等への過度な投資による海外への資本流出を懸念した中国当局は、2016年11月から投資分野の制限及び事前の審査・管理体制の強化に乗り出し、その結果2017年の対外直接投資は1,246億ドルと前年比36.5%の減少となった(第Ⅱ-3-3-2-2図)。
第Ⅱ-3-3-2-1図 主要国の対外直接投資ストック(左)とフロー(右)の推移
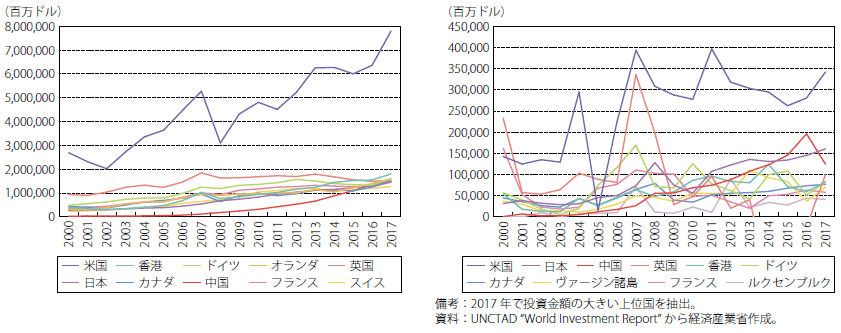
第Ⅱ-3-3-2-2図 中国の対外・対内直接投資の推移(フロー)
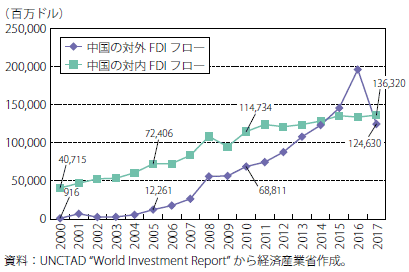
154 国際貿易投資研究所(2015)。
155 李(2016)。
中国の対外直接投資の特徴を、国・地域別及び産業別にそれぞれ概観していく。
まず、2016年の中国の対外直接投資残高を投資国・地域別にみていくと、香港が57.5%と最大の投資先となっている。その他の主要投資先については、ASEANが5.3%、EUが同5.1%、米国が4.5%、アフリカが2.9%、豪州が2.5%、ラテンアメリカ(ケイマン諸島及びヴァージン諸島を除く)が1.1%、ロシアが1.0%などとなっており、日本は0.2%と非常に少ない(第Ⅱ-3-3-2-3図)。
第Ⅱ-3-3-2-3図 中国対外直接投資残高の国別割合(2016年)
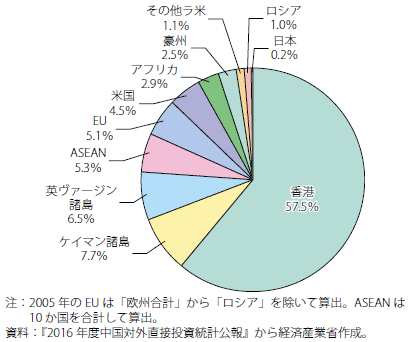
次に、2016年の中国の対外直接投資残高を産業別にみていくと、「その他サービス業」(リース・ビジネスサービスが9割を占める)が圧倒的に高い割合となっており、続いて金融業、卸・小売業、鉱業、製造業となっている(第Ⅱ-3-3-2-4図)。
第Ⅱ-3-3-2-4図 中国対外直接投資残高の産業別割合(2016年)
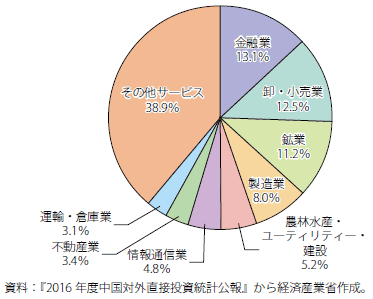
続いて、2010年から2016年にかけての中国の対外直接投資の動向を、主要国・地域別かつ産業別にみていく。
対香港の直接投資残高は、2010年から2016年にかけて3.9倍に増加した。特に大きく伸びたのは情報通信・ソフトウェア・ITサービス業で約20倍(2010年0.4%→2016年2.2%)となった。なお、対香港直接投資は以前よりリース・ビジネスサービス業向けが最大となっており、2016年には50%近い割合にまで達している。一国二制度を活用した海外からの資金調達等の中国企業の事業活動の存在が、この高い割合の背景にあると考えられる(第Ⅱ-3-3-2-5図)。
第Ⅱ-3-3-2-5図 中国の対香港投資
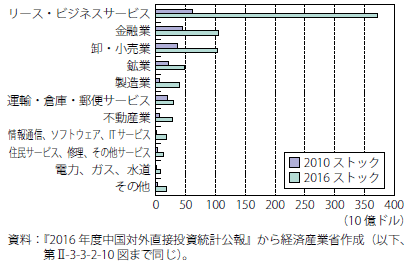
対ASEANの直接投資残高は、2010年から2016年にかけて5.0倍に増加した。2010年の対ASEAN直接投資金額で最大の割合を占めていた産業は電力・ガス・水道(19.3%)であったが、2016年には製造業(18.4%)へと変わった。中国がASEANとの間で製造業のグローバルサプライチェーンを進展させていることが伺える(第Ⅱ-3-3-2-6図)。
第Ⅱ-3-3-2-6図 中国の対ASEAN投資
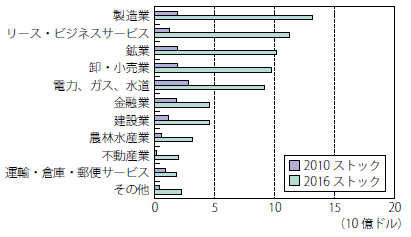
対米国の直接投資残高は、2010年から2016年にかけて12.4倍に増加し、他の国・地域と比べて突出して高い伸びとなった。特に大きく伸びたのは不動産業で71.2倍(2010年1.6%→2016年9.4%)に増加し、次いで情報通信・ソフトウェア・ITサービス業が36.8倍(同3.0%→同9.0%)となった。他にも金融業20.0倍(同10.8%→同17.3%)、学術研究・専門・技術サービス16.5倍(同5.6%→同5.0%)、リース、ビジネスサービス12.1倍(同11/8%→同11.5%)、製造業11.5倍(同27.0%→同25.1%)となっており、中国が米国の製造業やIT産業の先進技術獲得を目指して精力的に投資を行ってきたことが伺える。なお、最大の割合を占めている産業は、2010年も2016年も製造業である(第Ⅱ-3-3-2-7図)。
第Ⅱ-3-3-2-7図 中国の対米投資
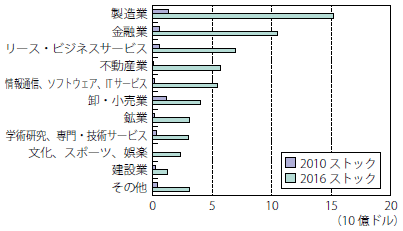
対EUの直接投資残高は、2010年から2016年にかけて5.6倍に増加した。特に大きく伸びたのは鉱業(2.9%→22.0%)であった。最大の割合を占めていた産業は、2010年のリース・ビジネスサービス(47.0%→8.0%)から2016年には製造業(24.6%→23.0%)へと変わった(第Ⅱ-3-3-2-8図)。
第Ⅱ-3-3-2-8図 中国の対EU投資
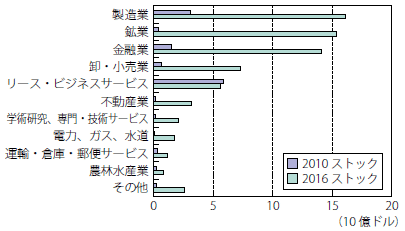
対豪州の直接投資残高は、2010年から2016年にかけて4.2倍に増加した。特に大きく伸びたのは農林水産業で31.6倍(0.3%→2.1%)、次いで不動産業が16.0倍(2010年3.3%→2016年12.34%)となった。投資金額で最大の割合を占めていた鉱業は、同期間に約82%から約57%へと全体に占める割合を下げた(第Ⅱ-3-3-2-9図)。
第Ⅱ-3-3-2-9図 中国の対豪投資
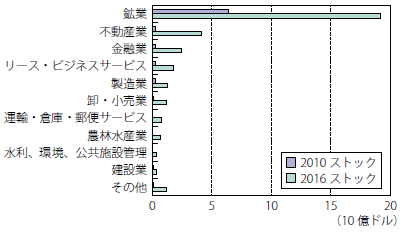
対ロシアの直接投資残高は、2010年から2016年にかけて4.5倍に増加した。特に大きく伸びたのは鉱業の22.5倍(9.9%→47.6%)で、農林水産業(26.8%→23.3%)に代わって、最大の割合を占める産業となった(第Ⅱ-3-3-2-10図)。
第Ⅱ-3-3-2-10図 中国の対露投資
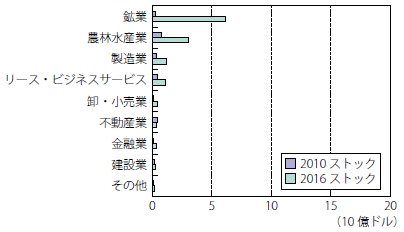
次に、中国の一帯一路関係国156への対外直接投資の動向についてみていく。2016年時点の直接投資残高は、129,414百万ドルと中国の対世界残高1,280,975百万ドルのうち10.1%を占めている。これは、5%前後の対ASEAN、EU、米国向け直接投資残高より高い割合である。
一帯一路関係国の中では、シンガポール向けが最大の割合を占め25.8%となっており、ロシア10.0%、インドネシア7.4%と続いている。地域として見るとASEANが55.3%を占め一帯一路関係国向け投資残高の過半数を占めている。また、上位20か国で一帯一路関係国向け投資残高の92.2%を占めている(第Ⅱ-3-3-2-11図)。
第Ⅱ-3-3-2-11図 一帯一路関係国に対する中国の直接投資金額(2016)
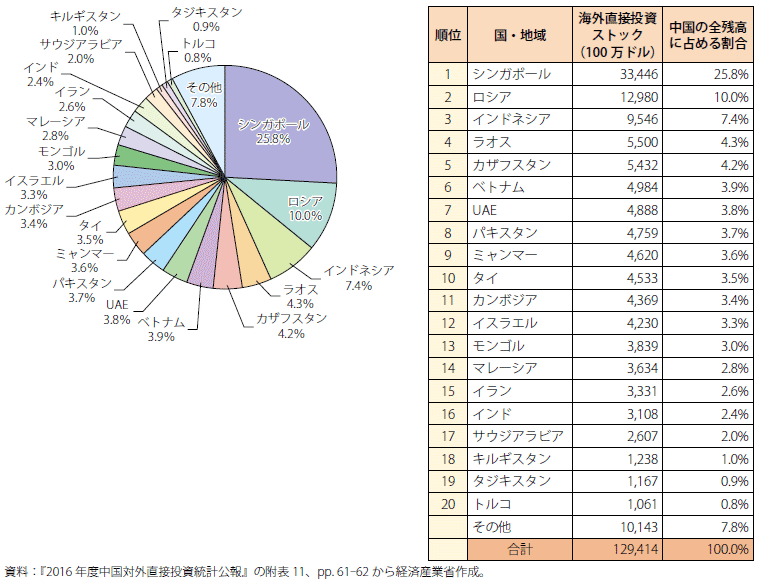
現時点では、一帯一路関係国への対外直接投資残高が中国全体の投資残高に占める割合は高くはないが、インフラプロジェクトの進展と共に、今後増加していく可能性もある。
156 『2016年度 中国対外直接投資統計公報』附表11に掲載されている63か国のうち貿易データが存在する62か国・地域。
(2)対外直接投資の実施主体の変化
次に、国有企業、非国有企業の別でみた中国の対外直接投資の実施主体の変化をみていく。
まず、国有企業、非国有企業それぞれの対外直接投資残高が対外直投資残高全体に占める割合をみてみると、当初国有企業の投資残高の占める割合が圧倒的であったが、徐々に非国営企業の投資残高の割合が拡大していることがわかる(第Ⅱ-3-3-2-12図)。
第Ⅱ-3-3-2-12図 海外直接投資残高に占める国有企業と非国有企業別の割合
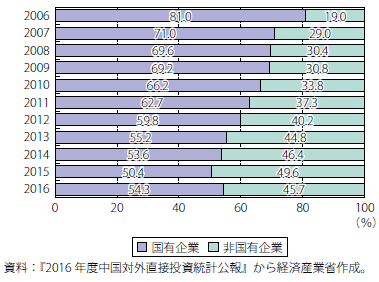
また、中国企業による対外M&A件数を実施主体別でみると、全体に占める割合において、概ね国営企業の割合が減少し、民営企業と財務投資者(ベンチャーキャピタルや投資ファンド等の投資家)の割合が増加傾向にある(第Ⅱ-3-3-2-13図)。
第Ⅱ-3-3-2-13図 対外M&A件数に占める実施主体別の割合
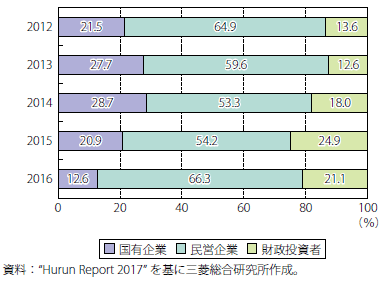
ただし、企業単位でみると、中国の対外直接投資残高の上位企業は資源・エネルギーやインフラ関係の国有企業が独占している。その多くはフォーチュン500(世界売上高上位500企業)にも含まれる大企業である。民間企業ではファーウェイ(15位)、美的集団(23位)の2社が中国の対外直接投資残高の上位30位企業の中に入っている(第Ⅱ-3-3-2-14表)。
第Ⅱ-3-3-2-14表 中国における海外直投ストック上位10社(2015)
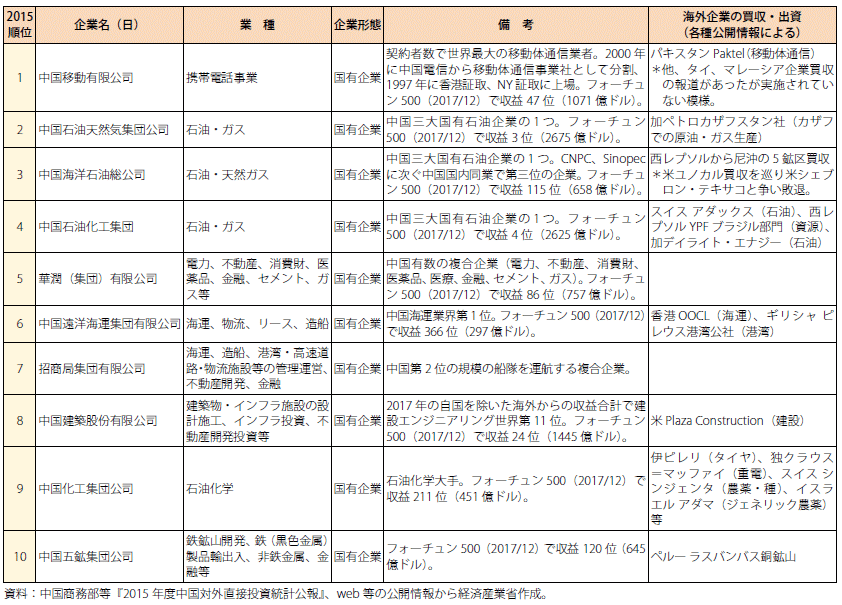
(3)欧米での積極的な企業買収
中国企業は、先端技術の獲得により自社の国際競争力を高めることなどを目的として、近年活発なクロスボーダーM&Aを実施している。そこで、本節では世界と中国のクロスボーダーM&Aの動向を見ていく。M&Aのデータは、全ての案件の金額、完了したか否かの情報が揃っているものではないため、あくまでも傾向を把握するためのデータとして用いる。
世界のクロスボーダーM&A件数を買収側企業の国籍別に見ると、中国企業によるM&Aは2000年には44件だったものが2006年以降から増加の幅が大きくなりだし、2016年には598件と約14倍になったが、2017年には中国政府による資本流出を抑制する動きで463件に減少した。世界のM&A件数に占める中国企業によるM&Aの割合も2017年に4.6%となり世界で7番目に多い国となっている。
また、M&A金額では、2000年から2017年にかけて54倍に増加し、世界のM&A金額に占める割合は12.5%まで上昇し、2017年時点で米国の23.5%に次ぐ第2位の金額となっている(第Ⅱ-3-3-2-15図)。
第Ⅱ-3-3-2-15図 世界における主要国のM&A件数、金額
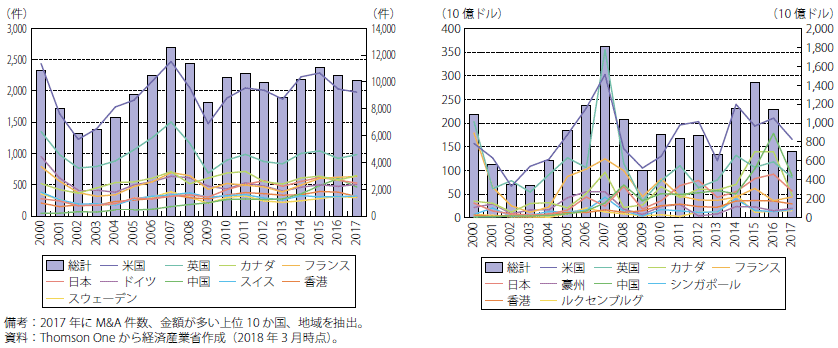
次に、中国のクロスボーダーM&A件数を地域別にみていくと、EU向け案件が2000年の4件から2017年には137件と最大の増加になった。2000年代前半は、年間20件を超えるのはアジア地域向けだけだったが、2007年以降に米国向けが、2009年以降にはEU向けのM&A件数が毎年20件を超えるようになった。また、EU向けM&A件数が占める割合は2011年に急速に高まり、2017年には全体の約30%を占めるまでに至った。EUと北米を合わせた欧米向けの割合は2011年から30%を超え、2017年には約50%を占めるまでに高まっている(第Ⅱ-3-3-2-16図)。
第Ⅱ-3-3-2-16図 中国によるクロスボーダーM&A件数の地域別推移
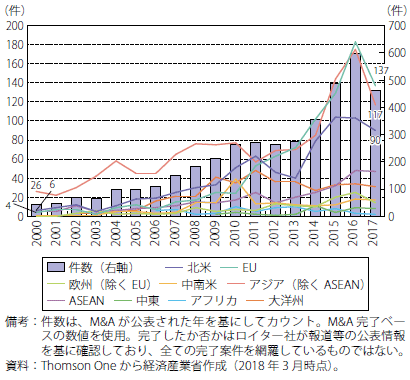
また、大洋州向けが2006年から2013年にかけて15%前後から20%近くの割合を占め、中南米向けも2008年から2010年まで7%から15%と同期間内では相対的に高い割合を占めていた。これは、豪州やブラジルをはじめとする中南米での採鉱案件の増加の影響による。
M&A件数の割合を業種157ごとに見ると、2004年以降に素材のM&A案件が急増した。2000年から2017年の素材関係M&Aの合計657件の内訳は採鉱・金属が492件で約75%と大半を占めており、そのうち豪州47.2%、カナダ14.2%と2か国で約57%を占めている。他にも2008年から2015年頃にかけてブラジルを始めとする中南米やアフリカ向けに中国が鉱物資源獲得の動きを活発化していったことが分かる。2013年以降には、工業とハイテクのM&A件数が急激に増加しており、中でも半導体、電気機器、ソフトウェアの件数が増加している。
2000年から2017年の合計件数における業種ごとの割合では素材が16.2%と最も高く、工業15.6%、金融13.1%、ハイテク13.0%と続いている(第Ⅱ-3-3-2-17図)。
第Ⅱ-3-3-2-17図 中国によるクロスボーダーM&A産業別の件数推移
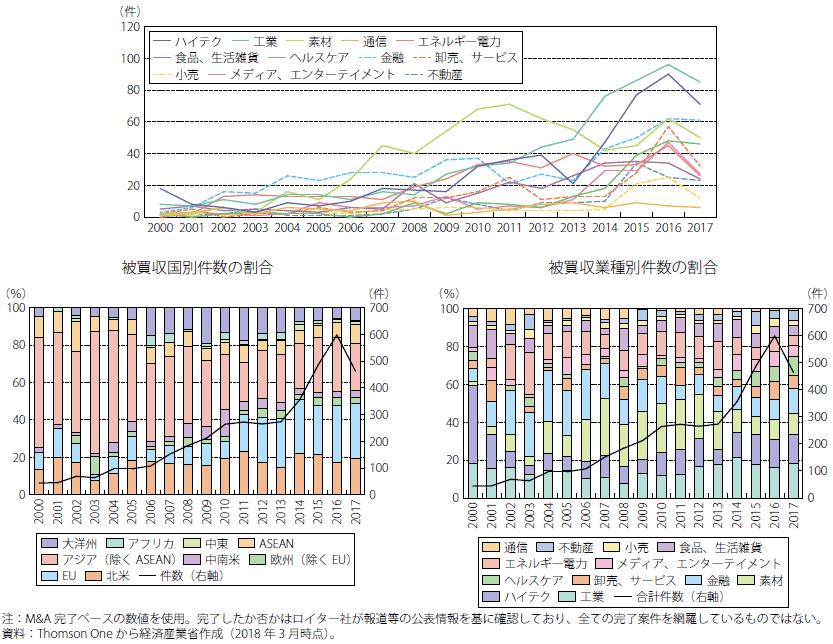
157 主な業種の内容は、ハイテク(半導体、電気機器、ソフトウェア、PC・周辺機器、Eコマース等)、工業(機械、自動車・部品、交通・運輸・インフラ、航空宇宙・軍需産業等)、素材(金属、採鉱、化学、建設資材等)となっている。
件数の多い3業種について、中国が先進国と新興・途上国のいずれに対してM&Aを主に行っているかを見てみると、エネルギー、電力は先進国と新興・途上国が拮抗していたものが、2011年以降は、カナダ、米国、豪州等先進国の石油・ガス企業に対するものが多くなった。工業・ハイテクは、米国とEUを主とした先進国向けが多く、素材は主に豪州とカナダを主とした先進国向けの金属・採鉱案件が多い(第Ⅱ-3-3-2-18図)。
第Ⅱ-3-3-2-18図 中国によるクロスボーダーM&Aの先進国、新興・途上国向けの推移
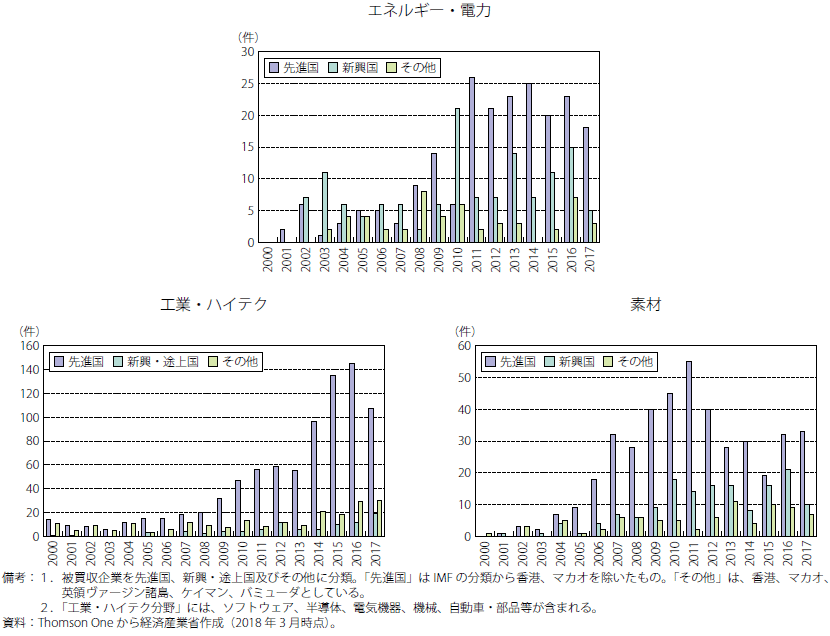
次に金額ベースでの中国M&Aの動向を見てみる。金額は欠損しているデータも多いため、必ずしも正確な実態を表しているとは言えないが、中国が関心を強く持っている地域や業種の傾向は把握できるとものと考える。中国による海外クロスボーダーM&A金額は、2000年から2017年の間において香港、米国、EUの割合が高く、件数ベースに比して米国の割合が高くなっている。2014年以降の金額急増は、米国、EU、香港向けのM&A増加が要因である。近年では米国向けの金額の割合が最も高い傾向にある(第Ⅱ-3-3-2-19図)。
第Ⅱ-3-3-2-19図 中国によるクロスボーダーM&A金額の地域別推移
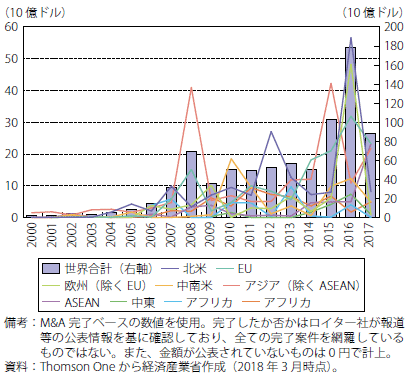
また、M&A金額の割合を業種ごとに見ると、2000年から2017年の間ではエネルギー・電力が25.2%と最も高く、素材17.4%、金融10.8%、工業9.6%と続いており、中国がこれまで資源の獲得を目的に大型M&A案件を多く実行してきたことが示唆される。エネルギー・電力以外では、素材の割合が比較的高く、同国のM&A金額が最も高かった2016年は、素材30.1%、ハイテク20.1%、工業11.4%が上位を占めていた(第Ⅱ-3-3-2-20図)。
第Ⅱ-3-3-2-20図 中国によるクロスボーダーM&A金額の産業別推移
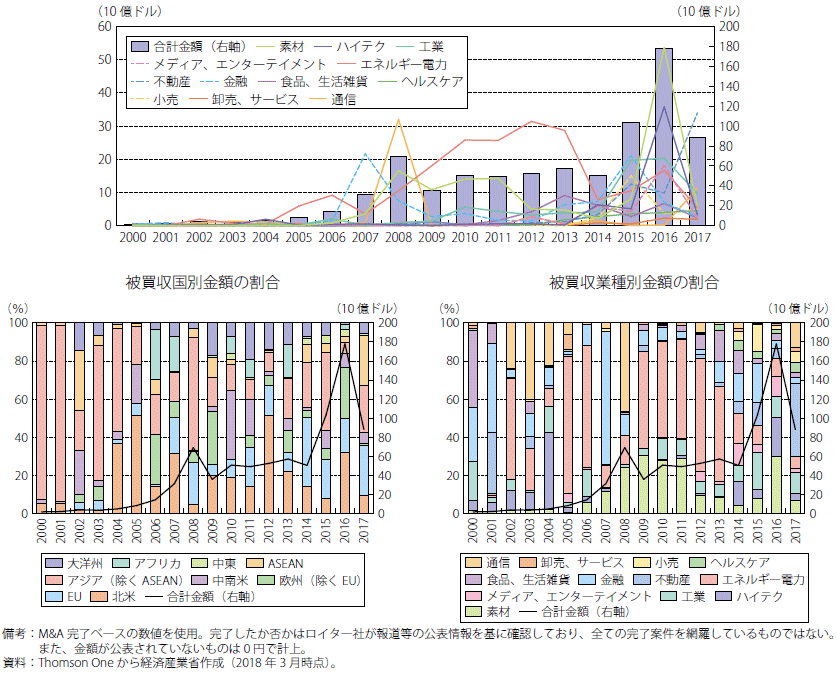
次に、特に近年、中国企業によるM&Aが増加している対米国、対EU企業買収案件の推移についてみていく。
まず、米国企業買収案件については、2013年以降、年間件数が大きく上昇しているが、2017年は減少している。産業別にみると、全期間を通じてハイテクが最大の割合を占めており、中国政府が「中国製造2025」を公表した2015年から2017年までの3年間の件数の内訳を見ると、ハイテク産業のM&A66件のうち、半導体が19件(28.8%)で最も多く、ソフトウェア12件(同18.2%)、コンピュータ・周辺機器10件(同15.2%)、びインターネットサービス10件(同15.2%)と続いている。その他、ヘルスケア、卸売・サービス、工業の件数も比較的高い割合を占めている(第Ⅱ-3-3-2-21図)。
第Ⅱ-3-3-2-21図 中国企業を最終親会社とする対米M&A件数
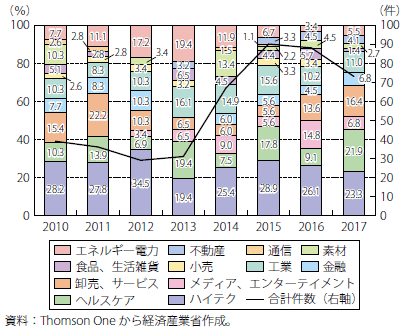
次に、EU企業買収案件についてみていくと、2016年まで件数が年々上昇傾向にあったが、2017年については減少している。産業別にみると、工業向けが全期間を通じて最大の割合を占めており、2015年から2017年までの3年間の件数の内訳を見ると、機械52件(32.9%)、自動車・自動車部品41件(25.9%)、建設・エンジニアリング28件(17.7%)となっている。その他、同期間ではハイテクも比較的高い割合を占めており、中でも半導体とソフトウェアで過半数を占めている(第Ⅱ-3-3-2-22図)。
第Ⅱ-3-3-2-22図 中国企業を最終親会社とする対EU M&A件数
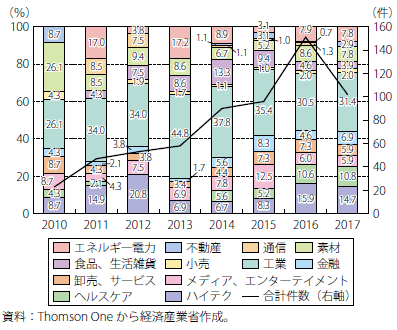
中国政府は、重点的に振興したい技術や産業における自国のイノベーション力を高める手段の一つとして、国の政策でM&Aを積極的に推進している158。
例えば、「中国製造2025」(2015年5月)では、M&Aやベンチャー投資等の海外進出支援を行うとしている。また、「国家科学技術イノベーション第13次五ヶ年計画」(2016年8月)においては、中国企業の国際化水準の向上のため、国際技術提携、企業による海外での研究センター設置、国際標準の制定への参画、クロスボーダーM&A等を奨励するとされている(第Ⅱ-3-3-2-23表)。
第Ⅱ-3-3-2-23表 中国政府の政策における重点産業・技術分野
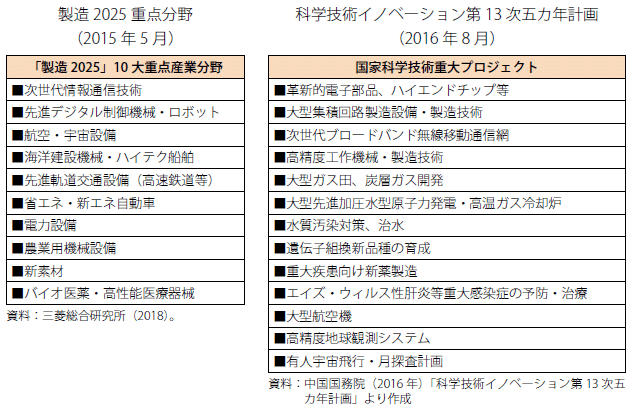
158 みずほ総合研究所(2016)。
3.主要国の反応
これまで中国の貿易及び対外直接投資の動向を見てきた。中国は貿易面でもそして対外直接投資面でも世界に占める割合を拡大させ、グローバル経済に大きな影響を及ぼす存在に変化を遂げている。ここではこうした存在感を増した中国との関係において主要国がどのような反応を示してきているか、その動向を簡単にまとめたい。既に、米国及び欧州の反応については第Ⅰ部第2章「主要国・地域の経済動向及び対外経済政策の動き」の中でもふれており、詳細については各地域についての説明を参照されたい。
まず、中国に対する世界各国からの貿易救済措置の発動状況についてみていく。WTO発足以降、1995年~2016年のAD措置の被発動件数は中国が1位(866件)であり、2位韓国(239件)、3位台湾(191件)、4位米国(177件)、5位日本(146件)以下を圧倒的に上回っている(第Ⅱ-3-3-3-1図)。直近の動きを見ると、2015年は61件、2016年は44件となっており、1995年の27件と比べると、件数が大幅に増加しており、世界各国から中国に対するAD措置の発動が増えていることがわかる(第Ⅱ-3-3-3-2図)。また、中国のAD措置被発動件数を発動国・地域別で見ると、先進国と新興・途上国の区分でみると、新興・途上国の方が中国向けAD措置の発動件数が多く、先進国の中では1位米国、2位EUとなっている159,160(第Ⅱ-3-3-3-3図)。
第Ⅱ-3-3-3-1図 各国のAD措置被発動件数
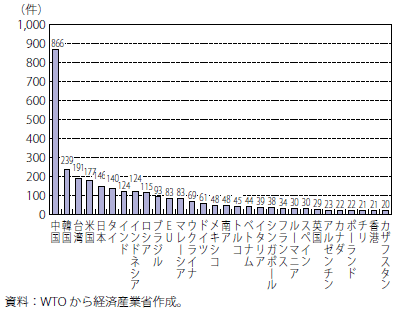
第Ⅱ-3-3-3-2図 中国のAD措置被発動件数推移
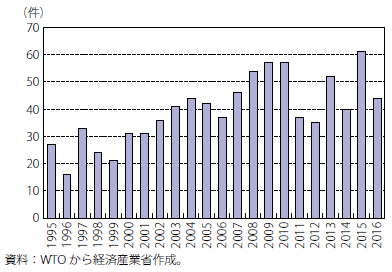
第Ⅱ-3-3-3-3図 中国向けAD措置発動件数地域別シェア(累積値)
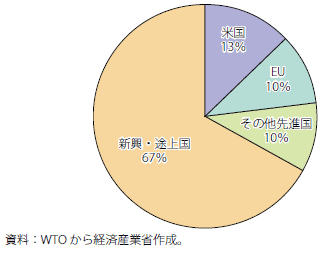
次に、米国の対中貿易や直接投資に関する措置の検討・実施状況をみていく。米国は、中国からの輸入が米国の国内産業に損害を与えているとの認識から、中国へのAD措置の実施を増加させる傾向にある。中国に対する米国のAD措置の発動件数は、年ごとにばらつきがあるが、2017年には上半期だけで8件に達している。AD措置に加え、2018年3月23日に米国は、国家安全保障の名目で、中国を含め、一部の国を除いた全世界を対象に、米国通商拡大法232条に基づく鉄鋼及びアルミニウムの輸入に対する追加関税賦課を開始した。また、2018年3月22日には、米国企業の知的財産権や技術が中国企業に移転するよう中国政府が不当に介入しているとして、特定の産品に対する25%の追加関税を含む、通商法301条に基づく中国に対する制裁措置を発動することを命ずる大統領覚書に署名した。
また、対内直接投資については、中国企業による企業買収案件が外国投資委員会(CFIUS)の審査対象とされる例が増え、大統領による買収差止命令が発動される例も出ている。また、米国議会においては、CFIUSの機能強化により対内直接投資管理を強化するための法案が、2017年11月に超党派で議会に提出されている。
続いて、EUの対中貿易や直接投資に関する措置の検討・実施状況をみていく。欧州によるAD措置の発動件数は2000年代半ば以降減少傾向にあるが、中国を対象にしたものは足元で増加している。なお、2017年12月には、AD措置のEUにおける枠組みを定めるEU規則が改正され、輸出国政府の介入により輸出国の市場価格やコストが歪曲されている場合、ダンピングの有無の判断に用いる「正常価格」の算出に、輸出国の価格やコストではなく第3国の代替価格を使用できる制度となり、本年3月には新制度に基づき中国に対してAD措置が発動されている。
また、対内直接投資については、2017年9月に欧州委員会は、域内向け外国直接投資を審査する枠組みを設立するための規則案を加盟国に提案した。また、加盟国単位でも、例えばドイツでは、対内直接投資の審査を強化するための対外経済法施行規則(AWV)改正案を、2017年7月に閣議承認した。161
159 世界全体ではインドが最大(152件)、米国(111件)、EU(91件)と続いている。
160 なお、我が国は、平成29年12月に中国産高重合度ポリエチレンテレフタレートに対して、平成30年3月に中国産炭素鋼製突合せ溶接式継手に対してAD措置を発動した。
161 日本においても、2017年に外為法を改正し、対内直接投資管理について強化を実施したところ(2017年1月1日施行)。具体的には、株式売却命令等投資後の是正措置の強化、外国投資家間の非上場株式の売買について規制対象の追加、規制対象業種の追加を行った。