

- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2020

- 白書2020(HTML版)

- 第Ⅰ部 第3章 第1節 米国
第3章 各国経済動向とリスク要因
第1節 米国
1.経済動向
(1)米国における新型コロナウイルスの感染拡大状況
米国のGDPは2009年から2019年第4四半期までの過去最長に渡る期間、前期比での拡大が続いたものの、2020年第1四半期には新型コロナウイルス感染拡大の影響により縮小に転じた。米国の新型コロナウイルスの感染拡大に伴う米国の感染者数の推移を見てみると、3月に入って以降感染が拡大し、3月27日には感染者数が約8万人に達し、中国を抜いて最も感染者の多い国となった(第I-3-1-1図)。感染拡大を受け、3月13日には国家非常事態宣言の発表、19日以降はカリフォルニア州を皮切りに連邦政府や州政府から自宅待機命令や企業への在宅勤務勧告等が行われ、4月20日時点で何らかの移動制限措置を実施した州は45州に上り、生産活動の停止や外出規制による消費活動の停滞が経済の重しとなった(第I-3-1-2図)。
第Ⅰ-3-1-1図 米国及び主要国の累積感染者数の比較
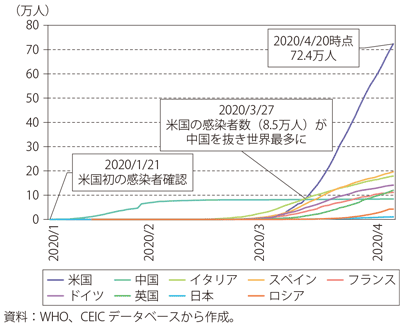
第Ⅰ-3-1-2図 米国における州別のロックダウン(都市封鎖)の状況(2020/4/20時点)
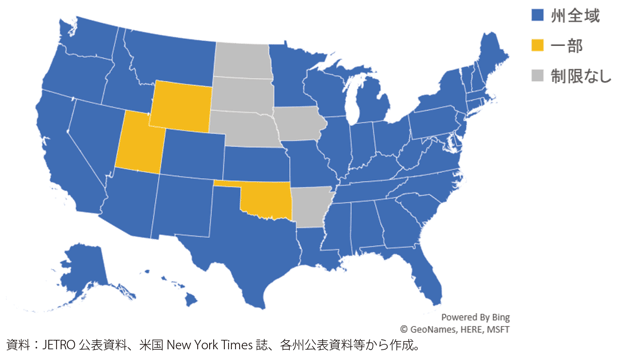
(2)実質GDP成長率
全米経済研究所(NBER)によると、これまでの景気拡大期の最長記録は1991年3月から2001年3月にかけての120か月であったが、2009年6月以降の景気拡大期は新型コロナウイルスの感染拡大前の2020年2月まで128か月間続き、米国の景気循環のデータが取得可能な1854年以降最長の景気拡大期となった37。実質GDP成長率を見ると、2020年第1四半期が新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けマイナス成長となり、また第2四半期もその影響が続くことが見込まれる。5月28日に公表された2020年第1四半期の実質GDP成長率(2次速報値)は、前期比年率-5.0%と、市場予想を下回り、世界金融危機後最大の下げ幅となった(第I-3-1-3図)。米国の実質GDP見通しについて、米国議会予算局は2020年第2四半期に前期比年率-37.7%に及ぶという試算を出すなど、第2四半期には更なる落ち込みが想定される。
第Ⅰ-3-1-3図 米国GDP需要項目別寄与度推移
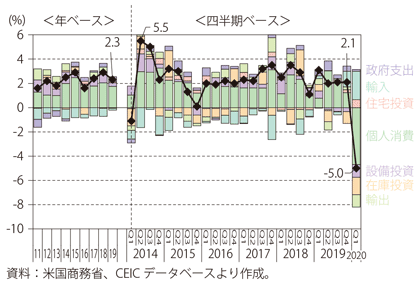
2020年第1四半期の実質GDPの主な下押し要因は、個人消費の急速な下落である。個人消費は米国GDPの3分の2を占め、2019年中はGDPの牽引役であったが、2020年第1四半期は前期比年率で-6.8%と大幅な減少となった(本節1.(4)参照)。また、個人消費以外で下押し要因となっているのは設備投資、在庫投資である。設備投資については、2019年第2四半期以降、前期比マイナスが続いており、米中貿易摩擦の激化懸念等を背景に、企業が生産の先行投資に消極的であったことが伺える。また、2019年の自動車の売上が前年比で減少したこと、ゼネラル・モーターズ社のストライキや、米大手航空機メーカーであるボーイング社の航空機の生産縮小・停止などの企業・業界特有の事情も影響している。特に、米大手航空機メーカーであるボーイング社を巡る問題では、ボーイング737MAX機のソフトウェアトラブルが多発したことを受け、2019年3月から同機の運航停止、2020年1月からは生産停止となったため、同機の生産・受注規模が大きく縮小したことが設備投資の下押し要因になっている。
また、2019年第4四半期、2020年第1四半期は、純輸出が大きくプラス寄与したが、大幅な純輸出の寄与度の拡大の背景には、2019年末にかけて米中貿易摩擦の激化により、輸出の減少を大きく上回り輸入が大幅に減少したことがあり、米国の全体の貿易規模は急速に縮小傾向にある(本節2(2)参照)。
37 NBERは遡って景気判断を行う場合もある。足下の景気拡大期間については、白書執筆時点(2020年6月時点)の情報であることに留意。
(3)雇用統計
米国の2019年末までの長期の景気拡大を可能とした要因には、堅調な労働市場、賃金上昇に支えられ、消費が好調であったことがある。雇用統計の推移を見ると、2019年の雇用者数の増加幅は月あたり平均で38、失業率は3.5%付近という約50年振りの低水準の水準で推移した。また、平均時給も前年同月比3%台の伸びを維持して堅調に増加しており、個人消費や住宅投資を下支えしていた。ただし、2020年3月以降は、新型コロナウイルス感染拡大を受けた緊急事態宣言、州・郡単位での自宅待機命令等により、経済活動も大きく制限され、雇用市場も大きく後退した。2020年4月の失業率は、14.7%にも上り、世界金融危機時の失業率(10%)を上回り、25%超となった世界恐慌時以来の最高値となった。2020年5月には、全米各地での経済活動の再開や経済対策の効果を受け、13.3%と4月から低下した(第I-3-1-4図)。また、2020年3月の雇用者数は、前月比-87万人、4月は前月比-2,069万人と大幅に減少し、4月の減少幅は第二次世界大戦後や世界金融危機後の下げ幅を超え1939年の統計開始以来最大となったものの、5月には前月比+251万人とプラスに転じた(第I-3-1-5図)。業種別の動向を見ると、3月は、全ての主要業種の雇用者数が前月比でマイナスとなった。最も下げ幅の大きかった4月は、行動制限による個人消費の低下に伴うサービス業における雇用減少が特に顕著であり、サービス部門全体で全体の8割以上を占める同1,735万人減少、とりわけ、娯楽・宿泊業は同754万人の減少となった。5月には、鉱業・林業、情報、政府部門を除く主要業種において、雇用者数が前月比プラスに転じた(第I-3-1-6表)。平均時給について見てみると、3月時点では、前年同月比3%台の伸びを維持し堅調に推移していたが、4月には低賃金労働者を中心に解雇が行われたことを背景に、前月比プラス4.7%と予想に反して大幅な伸びとなった。5月は経済活動の再開に伴い低賃金労働者の雇用が前月から回復したため、4月と比べると低下したものの、依然高い水準にある(第I-3-1-7図)。また、速報性の高い指標である米国の新規雇用保険申請件数に注目すると、2020年3月15日~6月6日の週の累計新規申請数は4,421万件に上った。この値は、5月の米国の全労働人口(約1.6億人)の約28.3%を占める。1週間の間の申請のピーク(687万件、3月22日~28日)は、世界金融危機後の申請件数のピーク(2009年3月、67万件)を大きく上回り、統計開始以降最高値となった(第I-3-1-8図)。
第Ⅰ-3-1-4図 失業率の推移
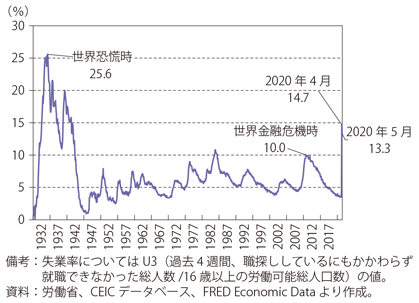
第Ⅰ-3-1-5図 雇用者数の推移(前月差)
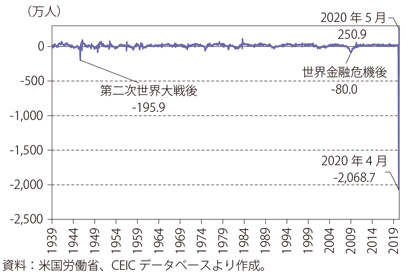
第Ⅰ-3-1-6表 米国雇用統計 業種別内訳(2020年2月~5月の変化)
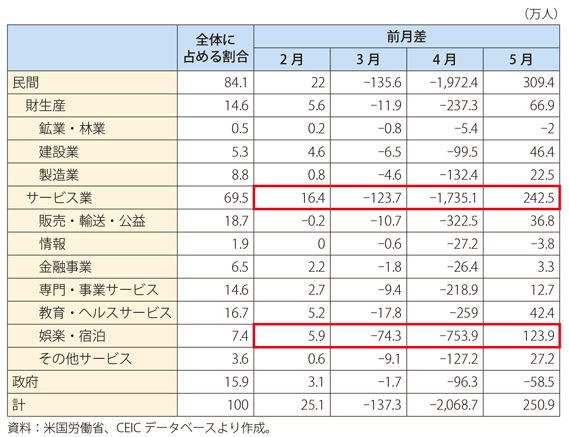
第Ⅰ-3-1-7図 平均時給の推移
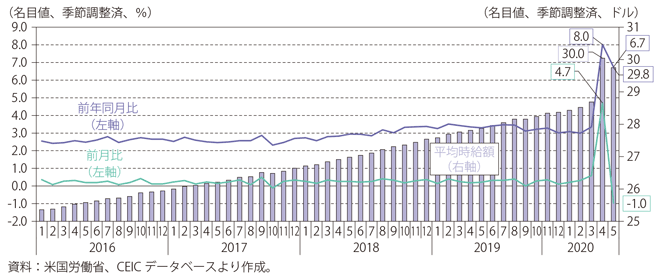
第Ⅰ-3-1-8図 新規雇用保険申請件数
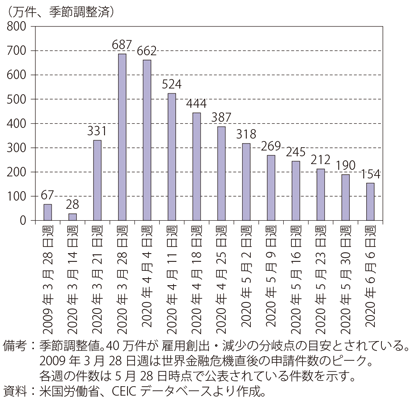
38 FRBの見解によれば、米国の雇用の巡航速度(労働人口の増加を加味した際に、米国の生産規模を保つのに十分な新規雇用者増加数)は月10万人前後の増加であり、2019年の雇用者数の増加はその水準を上回っている。なお、本統計の雇用者数においては、兼業・副業者は重複してカウントされている。
(4)個人消費・小売売上高
個人消費は米国GDPの約7割を占め、2019年は堅調な労働市場に支えられて米国経済の牽引役を果たしてきた。ただし、新型コロナウイルスの感染拡大後の3月は、前月比-7.3%と、1959年の統計開始以来最大の下げ幅となった(第I-3-1-9図)。特に、ヘルスケア、飲食・宿泊、娯楽等を中心としたサービス業の消費が大きく落ち込んだ。また、賃金上昇も好調であったことから、個人所得は堅調に推移していたが、3月に入ると失業率の急上昇等により、大きく下押しされた。業種・品目別にみると、その動向に違いが現れてきていることが分かる。企業における品目別小売売上高の動向について見てみると、特に自動車及び同部品、飲食店、衣料品店や、ガソリン販売等の売上が縮小する一方、食品・飲料、オンライン販売は増加している(第I-3-1-10図)。ガソリン販売の売上については、資源価格の変動に大きく影響を受けるが、特に2019年末以降は、OPECの協調減産に向けた協議が決裂したことなどから資源価格が急落したことも影響している(第I部第2章参照)。
第Ⅰ-3-1-9図 個人消費支出・所得の推移(前月比)
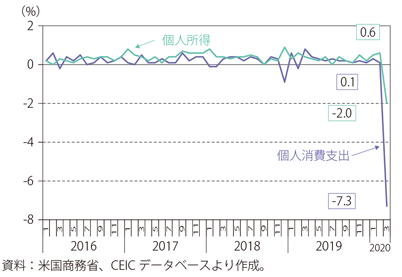
第Ⅰ-3-1-10図 小売売上高 品目別寄与度
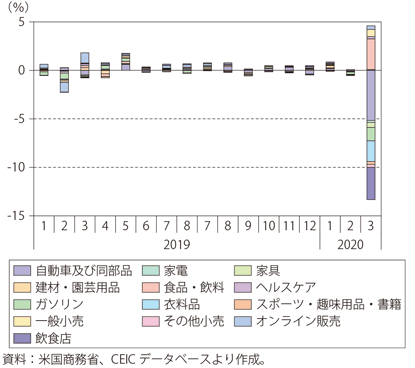
(5)鉱工業生産
米国の鉱工業生産は、製造業を中心に2019年後半に底打ちの兆しが見られたが、新型コロナウイルスの感染拡大を受け3月以降は大きく減少した(第I-3-1-11図)。
第Ⅰ-3-1-11図 鉱工業生産指数及び設備稼働率の推移
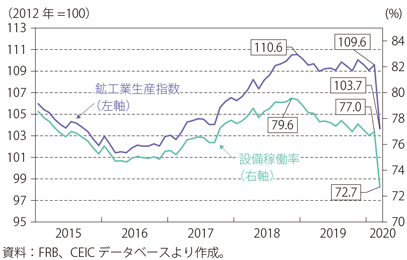
業種別では、航空機・同部品がボーイング機生産停止を受けて1月から低下しており、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあって2019年12月と比較すると約-21%と落ち込んだ他、自動車・同部品も工場の活動停止等が相次いだ影響で3月には前月比-28%と大幅に落ち込んだことが全体を下押しした。また、生産活動の状況をより先行的に表す設備稼働率についても、3月は前月比-4.2ポイントと大幅な下落となった。
(6)物価指数
長期の好景気でありながら、物価指数は目標値を下回る状況が続いている。FRBがインフレ目標の指標として注目しているPCE価格指数は、前年同月比+2%の目標値を下回る状況が2018年11月以降続いており、FRBもインフレ圧力が弱い状況が続いていることを懸念している。特に、2020年3月は、OPECによる協調減産体制が決裂した影響により原油価格が急落し、PCE価格指数も下落した。変動の大きい食品・エネルギーを除いたコア指数についても、2018年の前年同月比伸び率の通年の平均は+1.9%であったのに対し、2019年の平均は+1.6%と、前年から弱含んでいる(第I-3-1-12図)。
第Ⅰ-3-1-12図 PCE価格指数の推移(総合・コア、前年同月比)
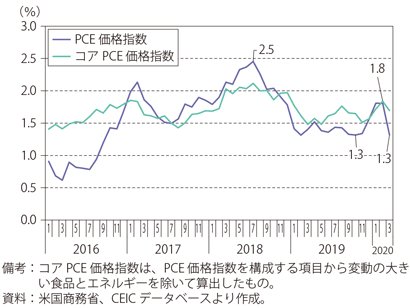
(7)住宅市場
2019年第3四半期以降、GDPを下支えした要因の一つは住宅投資である。住宅市場は、FRBの政策金利の引き下げに伴って住宅ローン金利が低水準で推移したことや、堅調な労働市場と堅調な賃金の増加に支えられる形で堅調に推移した。住宅ローン金利は、2018年末には、FRBによる利上げ(2016年12月以降2018年12月まで合計8回の利上げを実施、第I-3-1-15図参照)が開始されたことに伴い住宅ローン金利も上昇傾向にあったが、2018年末からは米中貿易摩擦の激化により長期金利が低下したことに伴い、住宅ローン金利も大幅に低下した(第I-3-1-13図)。
第Ⅰ-3-1-13図 住宅ローン金利(30年固定金利)の推移
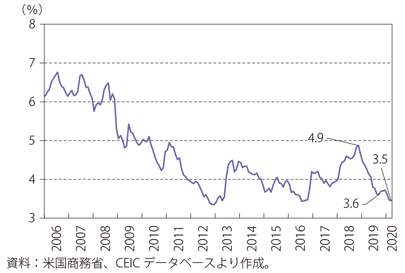
住宅価格は、資材価格や人件費の上昇から世界金融危機前を上回る水準に達している。住宅ローン金利が比較的高水準にあり、また住宅ローン控除の借入額の上限に関する税制改正が行われたこともあり、2018年から2019年半ばまでは住宅の買い渋りが生じ、新規住宅着工件数、建設許可件数も伸び悩む傾向にあった。一方、2019年半ば以降は、FRBによるフェデラル・ファンド金利(FF金利)誘導目標の引き下げに伴い、住宅ローン金利もさらに低水準となったため実質的な住宅購入コストが低く抑えられていること、平均時給と個人所得が堅調に推移していること、さらには、例年降雪の影響で冬期には住宅供給が滞るところ、2019年末~2020年初は暖冬となったことにより住宅供給が減速しなかったという一時的な要因も重なり、需要が復調し価格も再加速した(第I-3-1-14図)。2月までは前月比プラスが続いており、感染者が拡大しつつあった2月の段階でも、住宅市場は堅調であったことが伺える。感染拡大後も、米国の国家安全保障省は建設業を「必須インフラ業種」として指定し、多くの建設業者が活動を続けていることから、供給面の制約は部分的と見られる。しかし、雇用や収入の悪化から需要の低下が見込まれること、住宅市場のセンチメントには低下が見られていることから、今後の住宅市場の悪化は不可避と見られる。
第Ⅰ-3-1-14図 住宅価格指数の推移及び住宅着工・建設許可件数
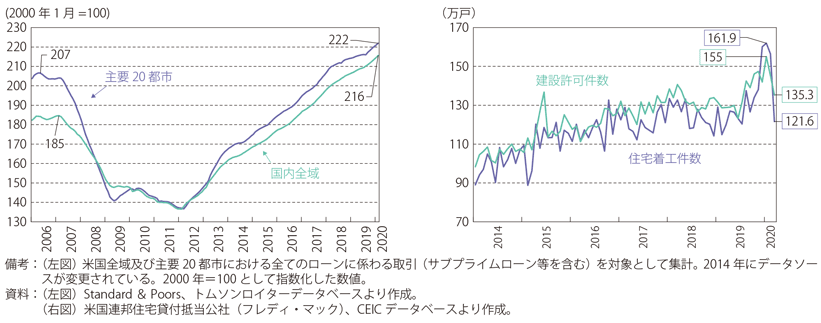
(8)金融政策
米国の金融政策を担う連邦準備理事会(Federal Researve Board : FRB)は、景気や景況感の向上を受けて2018年までに9度のフェデラル・ファンド金利(FF金利)誘導目標の引上げを実施したことにより、世界金融危機後の実質ゼロ金利状況を解消し、2.25~2.50%の水準まで引き上げた。しかし、2019年7月以降には、経済の不透明感の増大を受けた「予防的利下げ」を実施、2020年には新型コロナウイルスの感染拡大が経済にもたらすリスク懸念から、度重なる利下げや量的緩和政策等を実施し、2020年3月15日の連邦公開市場委員会(Federal Open Market Committee: FOMC)によりFF金利は再び実質ゼロ金利となった(第I-3-1-15図、第I-3-1-16図、第I-3-1-17表)。
第Ⅰ-3-1-15図 米国政策金利の推移
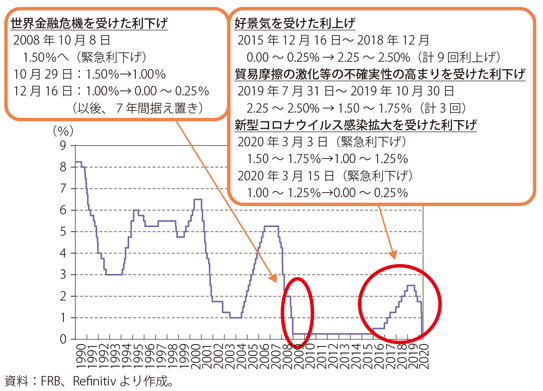
第Ⅰ-3-1-16図 FRBバランスシートの推移
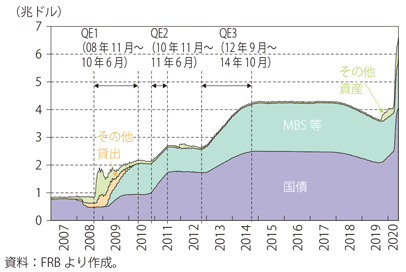
第Ⅰ-3-1-17表 FRBの新型コロナウイルス感染拡大を受けた対応
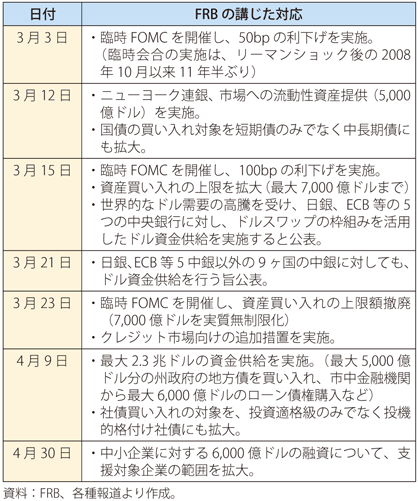
まず、新型コロナウイルス感染拡大前までのFRBの動向を振り返ると、2019年7月に開催されたFOMCにおいては、米中貿易摩擦の激化懸念から市場心理が悪化したことや、物価指数がインフレ目標(前年同月比2%)を下回る状況が2018年12月以降続いていたことを受け、約10年振りの利下げ(0.25%の利下げ)を実施し、以降10月のFOMCまで3会合連続で0.25%ずつ利下げが実施された。続く12月FOMCでは、インフレ圧力が引き続き弱いことは懸念材料であったものの、米中貿易における第一段階合意妥結の見通しが立ったことや、米中間で12月15日に発動する予定であった追加関税第4弾リストBの発動が延期になったことを受け、利下げは停止された。市場関係者の間でも、10月末のFOMCにて一旦利下げは停止との予想が大勢であった。
また、FRBはバランスシート政策も同時に実施し、債務の調整を行ってきた。2008年の世界金融危機以降、FRBは経済活動の活性化のため3度の量的緩和(図中QE1~QE3)を実施し、2014年初時点での債務残高は約4兆5,000億ドルと、2007年初時点(約8,500億ドル)の5倍以上となった。FRBは膨らんだ債務の縮小のため、2017年10月から国債の再投資額に上限を設けることにより、バランスシートの縮小を行い、調整の終了した2019年8月には3兆8,000億ドルまで縮小した。
ただし、新型コロナウイルス感染拡大後は、経済活動を抑制せざるを得なくなり、経済が大きく減速したことから、金利政策・量的緩和政策両面からの刺激策を講じざるを得なくなった。米国における感染者が出て以降初めてとなる1月29日、30日のFOMCでは、政策金利が据え置かれたものの、感染者数が増加した3月以降、FRBは臨時のFOMCを3回実施し、50bp、100bpの利下げを実施し金利は実質ゼロ金利となった。3月3日及び15日に行われた臨時FOMCにおいては、感染拡大が終息するまで現在の金利の範囲を維持することが確認された。4月28日、29日に開催されたFOMCでは、金利は据え置きとされたものの、新型コロナウイルスが中期的にもたらす経済下押し効果についても言及され、6月9日、10日に開催されたFOMCでは、2022年末まで実質ゼロ金利政策を維持する旨言及があった。市場関係者の間でも現在の実質ゼロ金利がしばらくは維持されるとの見方が大勢である。
また、国債等の買い入れによる量的緩和も順次実施し、資産額は4月30日時点で約6兆6,000億ドルと再度大幅に拡大した。さらに、経済の下押しリスクに対する懸念から、世界中でドル需要が高まったことを受け、FRBは15日に日銀、ECBを含む5中銀、21日には追加でブラジル、デンマーク等を含む9中銀に対してドルスワップの仕組みを活用したドル資金供給を実施する旨を公表した(第I-3-1-17表)。また、国内に対する信用緩和施策の一環として、特別目的事業体(SPV)を通じた社債(投資適格級・ジャンク債いずれも含む)及びコマーシャルペーパーの購入も積極的に実施した39。国債・社債・コマーシャルペーパーの購入の規模は4月末時点で1兆7,500億ドルに達し、米国の2020年度国家予算の約37%にも及ぶ異次元の規模となった。
39 米国では中央銀行が社債等の買い入れを直接行うことはできないため、新たに設立された特別目的事業体(SPV)を介した買い入れを実施している。
(9)株価
株価については、2019年初~2020年第1四半期にかけては、米中貿易摩擦をはじめとする通商交渉の動向、利下げ期待、また新型コロナウイルスの感染拡大懸念に合わせて大きく変動した。S&P500、NYダウ、NASDAQの主要3指標は、好調な米国景気、1月15日に第一段階米中通商合意が署名を迎えたことによる貿易摩擦の緩和期待により、2020年2月にいずれも史上最高値を更新した。3月以降は新型コロナウイルス感染拡大による経済活動の停滞を受け、世界同時株安が進行し、米国の株価主要3指標も軒並み下落した。S&P500においては、一定期間内の下げ幅が一定幅以上になったために取引が一時停止される「サーキットブレーカー40」が複数回発動されるなど、大幅な低下を見せた(2020年3月末現在、3/9、 3/12、3/16、3/18)。2017年1月のトランプ大統領の就任以降、株価は基本的には上昇基調にあったが、感染拡大後の下落により、就任当時の水準まで株価は下落する形となった(第I-3-1-18図)。感染拡大後、大規模な財政政策等の発表や、ロックダウン(都市封鎖)の拡大、緊急事態宣言の発出などの動きに市場は大きく反応し、市場のボラティリティ・インデックス(VIX指数)41も世界金融危機時を超える水準となった(第I-3-1-19図)。
第Ⅰ-3-1-18図 米国株価主要3指数の推移
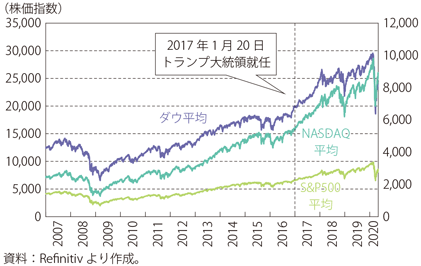
第Ⅰ-3-1-19図 S&P500種 ボラティリティ・インデックスの推移
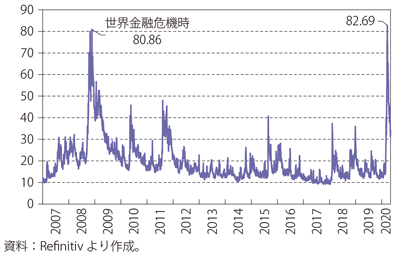
40 サーキットブレーカー制度とは、1987年に生じた米国株価の急激かつ大幅な株価暴落の教訓から、2012年以降導入された制度で、一定期間内に一定以上株価が下落した場合、取引を自動的に停止する制度である。制度開始以来、2週間の間に4回ものサーキットブレーカーが発動されたのは初めて。
41 VIX指数とは、取引価格を元に、投資家が予想する将来の株価変動の大きさを指標化した指数であり、一般に投資家の不安心理を表すと言われている。
2.通商動向
(1)貿易政策
米国の通商代表部(USTR)は、2月28日に2020年の通商政策課題及び2019年の通商政策課題(1974年通商法第163 条に基づき毎年議会に提出している通商政策に関する報告書)を提出した。USTRは、2019年の実績として、①第一段階の米中合意の締結、②米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)の締結、③日米貿易・日米デジタル貿易協定の締結、及び④EUとの航空機補助金を巡るWTO委員会での勝訴等を挙げている。前年の2019年3月に公表された報告では、課題として中国の知的財産侵害への対応やUSMCAの批准、日本との通商交渉を挙げており、一定の成果を示す形となった。また、報告書では、トランプ政権におけるこれらの通商政策の着実な実行により、米国内の格差是正、所得の向上、失業率の低減などが実現したと強調されている。2020年には、上記に挙げたようなUSMCA、中国との第一段階合意、WTO協定の着実な実現を目指すとともに、英国、EU、並びにサブサハラアフリカで初となるケニアとの2国間自由貿易協定の締結、日本との包括自由貿易協定締結に向けた更なる交渉、中国との第二段階合意締結に向けた検討、WTOの機能の見直しを目標として掲げた。
本項では、2019年の実績として上げられた事項について、2019年~2020年第1四半期の政策面における動向を概説する。
① 米中貿易摩擦
対中国の貿易摩擦に関しては、2018年中に発動された第1~3弾の追加関税措置に加えて、2019年の5月には第3弾対象品目の税率の引き上げ、9月、12月には第4弾追加関税の賦課(リストA(約1,120億ドル、9月1日に賦課)、リストB(約1,600億ドル、12月15日に賦課予定であったが、通商合意が行われたことにより賦課は延期)が実施・検討され、中国も米国の措置に報復する形で追加関税の賦課を行った(第I-3-1-20表)。特に、第4弾の追加関税については、合計で約3,000億ドル規模とこれまでの関税よりも規模が大きく、また関税賦課品目に消費財が多く含まれることから、消費者への影響も大きいとされた(第I-3-1-21図)。最終的には、12月13日に両国間で第一段階合意が行われたことによって、第4弾リストBの賦課については回避され、また過去発動分の追加関税(第4弾リストA)の税率が15%から7.5%へと半減されることとなり、市場では貿易摩擦の緩和期待が広がった。米中の第一段階通商合意においては、財・サービスの輸入を2017年比で、今後2年間の間に合計2,000億ドル(工業製品:777億ドル、農産品:320億ドル、エネルギー:524億ドル、サービス:379億ドル)増額することが目標として盛り込まれた。また、中国の輸入額規模の拡大の他、知的財産の保護の強化、中国当局による外国企業に対する技術移転の圧力の禁止、中国の金融市場に対する米国企業のアクセス制限緩和、為替レート操作の禁止とマクロ経済政策の透明性の向上、紛争解決の新たな枠組みの構築等が盛り込まれた。2020年の通商政策課題においては、第一段階合意の着実な履行とともに、第二段階合意の妥結に向け交渉を引き続き続けると言及されている。
第Ⅰ-3-1-20表 米中貿易摩擦の経緯
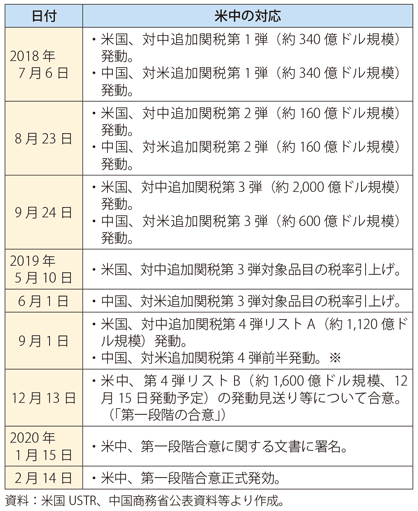
第Ⅰ-3-1-21図 対中追加関税 対象品目の財別取引額割合
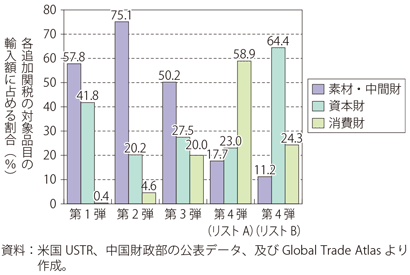
② NAFTA再交渉・USMCA の締結
米国は、NAFTAの後継となる貿易協定としてUSMCAを1月に上院にて可決後、署名した。トランプ大統領は就任当初より、NAFTAにより米国国内の労働が不当に阻害されているとしてNAFTAの再交渉を政策として掲げており、カナダ、メキシコとの協議を経て2019年12月に両国と合意、2020年1月29日にトランプ大統領による署名を迎えた。USTRは4月24日、USMCAが2020年7月1日に発効する旨を米議会に通知した。また、協定発効に向けた国内手続きを完了したことをカナダとメキシコにも通知した。
USMCAは、NAFTAにも組み込まれている自動車の原産地規則の強化、バイオ医薬品のデータ保護期間の撤廃、メキシコにおける労働法の遵守状況に関する規定、環境規制に関する監視機能の拡充などが盛り込まれている。特に、自動車産業においては、USMCAの特恵関税を適用するために必要な域内原産割合(RVC)の割合を、完成車については62.5%(現行のNAFTAにおける規定)から段階的に75%に引き上げ、また部品についてもRVCの規定を新たに設け最終的には65~75%まで引き上げると規定されている。また、コアとなる部品(スーパーコア部品:エンジン、電気自動車用バッテリーなど)は北米原産品であること、鉄鋼・アルミの北米域内調達比率(70%)の達成、労働付加価値割合の達成がなければ完成車の域内原産品認定が受けられないというルールも導入された。
今回のUSMCAの原産地規則の対象となっている自動車・自動車部品の品目の2019年の輸出入額実績をみると、輸出は2,104億ドルに対し、輸入は4,222億ドルと、輸入超過の状況である。特に、輸入について見ると、日本からの輸入は自動車では全体の19.1%(シェアはメキシコ、カナダに次いで世界第3位)、自動車部品では全体の9.5%(シェアはメキシコ、カナダ、中国に続いて世界第4位)を占め、日本の貿易においても重要な取引品目であり、日本の自動車産業への影響が及ぶものとみられる(第I-3-1-22図)。
第Ⅰ-3-1-22図 米国の自動車輸出入相手国割合(2019年実績)
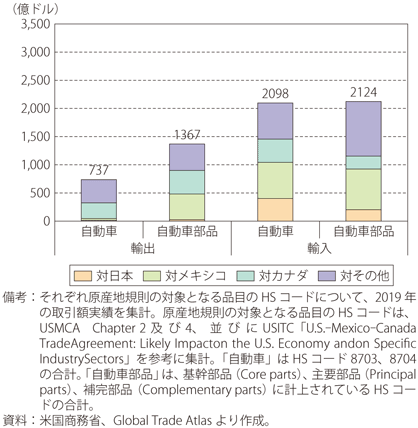
③ 日米貿易協定、日米デジタル貿易協定の締結
米国は2019年の成果の一つとして、日本との貿易協定、デジタル貿易協定の成立を挙げている。
日米貿易協定は、世界のGDPの約3割を占める日米両国の二国間貿易を強力かつ安定的で互恵的な形で拡大するために、一定の農産品と工業品の関税を撤廃または削減するものである。工業製品は、米国側で関税の撤廃・削減を行い、農産品は、日米双方でお互いの関心品目を中心に関税の撤廃・削減を行うことが定められている。
また、デジタル貿易協定については、両国間の電子的な送信(電子書籍、ビデオ、音楽等)に対する課税の禁止、内国民待遇(相手国のデジタルプロダクトを自国プロダクトと差別してはいけない)等が定められ、包括的な協定になったと報告書において指摘されている。日米貿易交渉の内容については、第3部第1章においても概説する。
④ EU内における航空機補助金を巡る問題
2004年以降、米国と欧州は互いに米大手航空機メーカーであるボーイング社(米国)及びエアバス(欧州)に対する自国製品優遇的な補助金供与がWTO協定違反に当たるとして、互いにWTO上級委員会に対する提訴を続けてきた。2018年5月には、WTOがエアバス社に対するEUからの補助金はWTO協定違反である旨を認定しており、以降米国は報復関税の実施に向けた検討を進めた。2019年10月には、対EUの報復措置を行うことがWTOから承認され、合計約75億ドルに上る輸入品目について、対EU報復関税の賦課が開始された。75億ドル規模の輸入品目に対する報復関税の認定は、これまでのWTOの査定額においても最大の規模となった。また、追加関税対象品目の中には、大型民間航空機のみならず、ワイン、チーズなどの食料品も含まれ、米欧対立の影響は航空機以外の業種にも波及している。さらに12月には、WTOが公表したEUのWTO勧告履行状況の調査において、EUからエアバスへの不当な補助金が拠出され続けていると指摘されたことを受け、2020年3月以降は、民間航空機に対する税率が10%から15%に引き上げられている。
なお、2019年3月には、WTOは米国のボーイング社に対する補助金についても、WTO協定違反にあたるとの旨の報告書を出しており、EUはそれを受け米国に対する対抗措置に出ることを表明している。ただし、欧州からは、報復関税の掛け合いは両国に利益を生まないとし、交渉を通じた解決を図るよう米国に対して呼びかけが行われており、引き続き両国間では本件を巡るやり取りが続くものとみられる。
(2)貿易動向
本節の始めに述べたように、米国GDPの推移において、純輸出は2019年第4四半期の押し上げ要因となっているが、これは主に対中国の輸入が大きく減少したことを反映したものである。実際に、貿易赤字額は2018年から2019年の間に約220億ドル縮小し、対中国の貿易赤字に限ってみれば米中貿易摩擦の激化によって約740億ドル減と大きく減少してきた(第I-3-1-23図、第I-3-1-24表)。
第Ⅰ-3-1-23図 米国の輸出入額(前年同月比)、貿易赤字額の推移
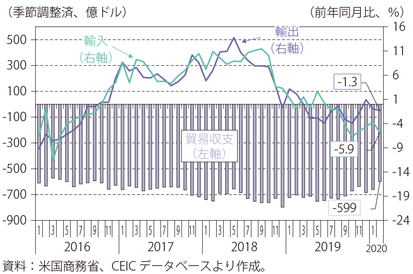
第Ⅰ-3-1-24表 貿易赤字額上位8か国の赤字額変化(2018年、2019年)
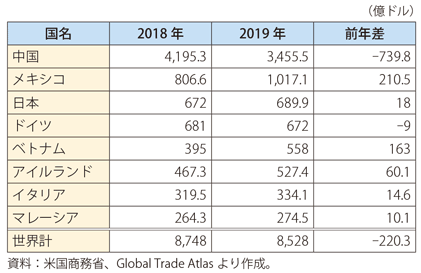
対中貿易額の推移を見ると、 特に第1~3弾の対象となっている品目の取引額は、2019年に入って以降も取引額が大きく減少していることが分かる(第I-3-1-25図)。また、2019年中はドル高基調であり、対中国のみならず米国の輸出には不利な状況であったことが伺える。
第Ⅰ-3-1-25図 対中国の輸出入額及び貿易赤字額の推移
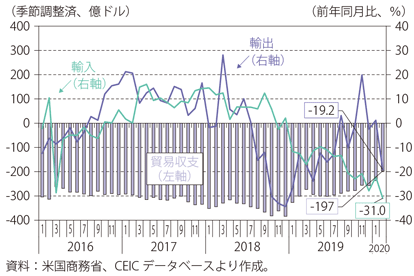
また、1月15日に署名、2月14日に正式発効した米中第一段階合意においては、前述の通り中国政府が農産品・エネルギー・工業品の対象品目の動向について、2021年末までに2017年の輸入額と比べて総額2,000億ドル規模の追加購入を行うことが盛り込まれているが、その増額規模は2019年の対中の財の取引実績(約1,300億ドル)を大きく上回っており、中国国内の需要量を超えているのではないかとの指摘もある。さらに、合意が正式発効した2月は、中国国内における新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、武漢におけるロックダウン(都市封鎖)、外出自粛措置が行われたために、中国国内の経済活動が停滞し、対象品目の対中輸出額の伸びも前年同月比マイナスとなり、目標額の達成を危ぶむ声が聞かれた(第I-3-1-26図)。
第Ⅰ-3-1-26図 米中第一段階合意の対象品目の取引額の推移
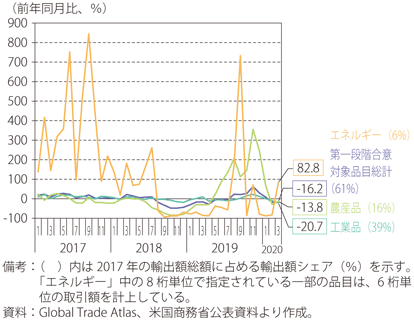
なお、新型コロナウイルスの米国内での感染拡大後は、米国内への医療物資の供給拡充のため、3月には追加関税の対象となっていた医療関係物資の関税の撤廃が行われている。
また、日米間貿易については、日米貿易協定・デジタル貿易協定が1月1日に発効した。本合意では、両国の工業品、農産品について、関税の撤廃もしくは引き下げが行われた。新型コロナウイルス感染拡大の影響によって貿易自体が縮小している(第I-3-1-27図)。
第Ⅰ-3-1-27図 対日本の輸出入額及び貿易収支の推移
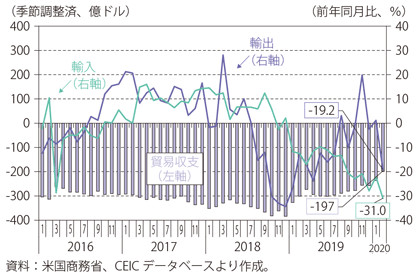
(3)国防権限法
米国の投資管理・輸出入に関する規制は、2018年8月の国防権限法において、対外投資リスク審査現代化法(FIRRMA)の成立により外国投資委員会(CFIUS)の権限が強化され、また輸出管理改革法(ECRA)の成立により輸出管理も強化されてきた。本項では、FIRRMA、ECRAそれぞれの2019年以降の動向について概観する。
① 投資管理強化
米国においては、CFIUSが安全保障の観点から対内直接投資を審査している。FIRRMAが2018年8月13日に成立し、従来審査対象となっていなかった被支配的投資に対する審査の拡大や、サイバーセキュリティへの影響、重要インフラ等が外国人に支配されることによる影響など、審査の考慮要素が多面化すること等、CFIUSの権限の強化が行われている。これらの規制は、制定後はパイロット・プログラム(暫定規則に基づくCFIUSの実験的運用)が行われていたところであるが、2020年2月13日に最終施行され、パイロット・プログラムの内容は最終規則に引き継がれる形で始動した。FIRRMAにおいては、27の業種に関連する製造・設計を行う、機微技術を保有する企業を対象としている。27の業種には、安全保障上の懸念が想起される軍事分野、航空・宇宙分野に加え、コンピュータや半導体等の電気通信分野、ナノテクノロジーやバイオテクノロジー等の先進的技術も含まれる。
審査対象として新たに追加された機微技術としては、①武器(米・国際武器取引規則ITARの規制対象であり、米・軍需品リストUSMLに掲載される製品)、②米輸出管理規則(EAR)のリスト規制対象製品であり、国際レジームに基づいて規制される汎用品等、③原子力関連製品、④特定化学剤・毒素、⑤輸出管理改革法(ECRA)における新興基盤(emerging and foundational)技術が明記された。
② 輸出管理強化
輸出管理改革法(ECRA)は2018年8月13日の国防授権法に盛り込まれる形で成立した。米国の安全保障にとって必要な「新興基盤技術」を特定し、輸出規制の対象とすることなどを定めている。あわせて、米国内で規制対象となった新興基盤技術については、国務長官が国際輸出管理レジームに輸出管理対象とする提案を行うよう義務付けている。
また、安全保障上の理由での禁輸措置の対象企業が増加している。具体的には、2018年8月以の同法成立以降、ファーウェイ、ZTE、JHICC等の企業が輸出規制の対象となる企業リスト(エンティティ・リスト)に掲載された。輸出等は、米国商務省安全保障局(BIS)の許可が必要となっており、多くの場合、全貨物についての輸出が許可されない。ただ、実際は2019年5月のファーウェイのエンティティ・リストへの掲載以降も、既にファーウェイとの取引実績のある企業や市場への影響を考慮し、既存のネットワークと機器の維持のための取引等は、期間限定で暫定包括許可(TGL:Temporary General License)が付与されている。対象期間は、幾度かの延長の末、2020年8月13日までとなっている。さらに、2019年11月には、米国連邦通信委員会において、公的な補助金を受ける米国事業者がファーウェイ、ZTE等の企業から調達を行うことを一部規制する規制が採択され、2020年3月に法律として成立した。具体的な企業、通信・サービスの概要については成立から1年以内を目処に公表されることとなっている。
