

- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2020

- 白書2020(HTML版)

- 第Ⅰ部 第3章 第2節 欧州
第2節 欧州
欧州経済は、中国を始めとする世界経済の成長の減速や米中貿易摩擦の激化、英国のEU離脱を巡る不透明性の高まり等の影響により、2018年後半以降、生産や輸出が落ち込み、主要国で成長の鈍化が続いていた。2020年2月下旬以降、新型コロナウイルス感染が欧州全体に急速に拡大し、各国で外出や移動の制限、工場や店舗の閉鎖等、感染拡大予防のための措置が実施され、経済活動に深刻な影響を与えている。
本節では、こうした情況を踏まえ、ユーロ圏及び英国経済、並びに英国のEU離脱を巡る動向について概観する。
1.ユーロ圏
(1)GDP成長率
ユーロ圏の2019年の実質GDP成長率は+1.2%と2018年の+1.9%を0.7%ポイント下回り、2017年の+2.5%から2年連続で減速し弱い回復となった。良好な雇用・所得環境や、緩和的な金融政策を背景とした堅調な個人消費や投資による内需に支えられ、緩やかな回復を続ける一方で、中国を始めとする世界経済の成長の減速や米中貿易摩擦の激化、英国のEU離脱を巡る不透明性の高まり等の影響により、2018年後半から生産や輸出が落ち込み、欧州経済のけん引役であるドイツを中心に主要国で成長の鈍化が続いた(第Ⅰ-3-2-1図、第Ⅰ-3-2-2図)。
第Ⅰ-3-2-1図 ユーロ圏のGDP成長率の推移(需要項目別寄与度)
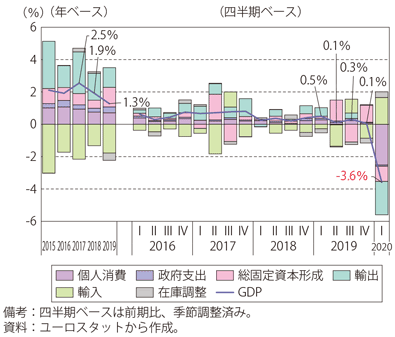
第Ⅰ-3-2-2図 ユーロ圏のGDP成長率の推移(前年比)
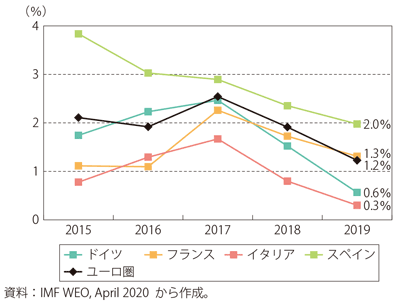
新型コロナウイルスの感染拡大が、中国やアジア地域に集中していた2020年1月から2月上旬までの時点では、欧州への影響は限定的と見られていたが、2月下旬以降、イタリアからスペイン、フランス、ドイツ、英国へと欧州全体に感染が急速に拡大し、各国で外出制限や渡航禁止措置等の移動の制限、工場や店舗等の閉鎖や国境の実質上の封鎖等の感染予防措置が実施され、さらにサプライチェーン寸断による生産停止や混乱等の影響により、消費や生産等の経済活動が前例をみない規模で悪化した。
ユーロ圏の2020年1-3月期の実質GDP成長率(季節調整済)は、前期比年率換算で-13.6%と2019年10-12月期(同+0.4%)から大きく低下し、世界金融危機時の2009年1-3月期(同-12.0%)を上回る悪化となった。各国の発表によると、フランスが同-19.7%(前期-0.4%)、イタリアが同-19.6%(同-1.0%)、ドイツが-8.6%(同-0.4%)と2期連続でマイナス成長となり、スペインが-19.4%(同+1.7%)、英国が-7.7%(同+0.1%)42といずれも大きく低下した。4月以降も経済活動が大幅に抑制された状況を踏まえると、4-6月期は更に深刻な悪化になると予想される(第Ⅰ-3-2-3図)。
第Ⅰ-3-2-3図 ユーロ圏の実質GDP成長率の推移(前期比年率)
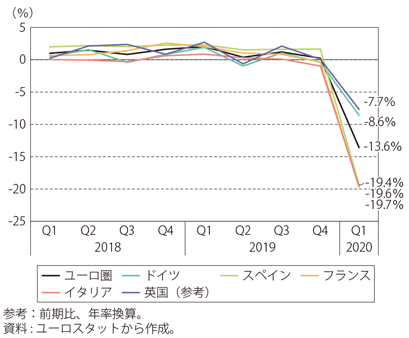
IMF43によれば、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、ユーロ圏の実質GDP成長率は2019 年+1.2%から2020 年は-7.5%と大幅に低下し、世界の主要先進国地域の中でユーロ圏が最大の打撃を受けると予想されている。IMFは2020年後半から経済活動が段階的に回復すれば2021年は+ 4.7%まで回復すると予測している44。
国別では、IMFはドイツが2020年-7.0%、2021年+5.2%、以下同様、フランスが-7.2%、+4.5%、イタリアが-9.1%、+4.8%、スペインが-8.0%、+4.3%、英国が-6.5%、+4.0%と予測しており、イタリアとスペインの落ち込み幅が他国と比べ特に大きい。
また、ユーロ圏のインフレ率は、2019年+1.2%から2020年+0.2%、2021年+1.0% と低下、失業率は2019年7.6%から2020年10.4%、2021年8.9%と、いずれも大幅な悪化を予測している(第Ⅰ-3-2-4図、第Ⅰ-3-2-5表)。
第Ⅰ-3-2-4図 IIMFによるユーロ圏の実質GDP成長率の推移と予測
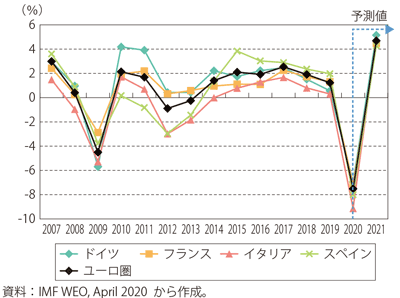
第Ⅰ-3-2-5表 IMFと欧州委員会の欧州経済の見通し
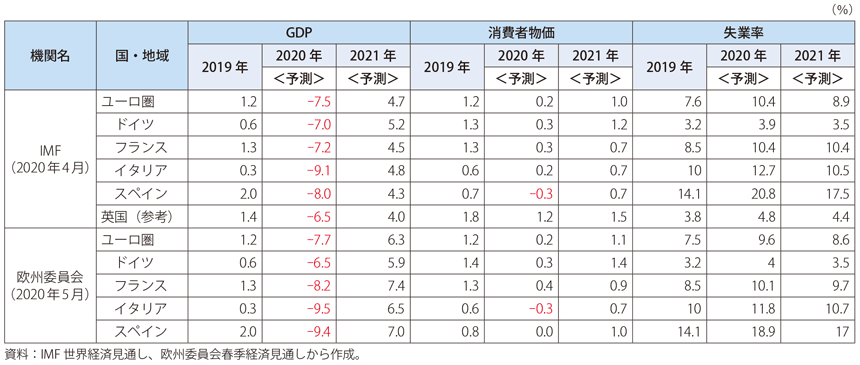
続いて欧州委員会45によると、ユーロ圏のGDP成長率は2019年+1.2%から2020年-7.7%、2021年+6.3%と予測している。国別では、ドイツが2020年-6.5%、2021年+5.9%、以下同様、フランスが-8.2%、+7.4%、イタリアが-9.5%、+6.5%、スペインが-9.4%、+7.0%と予測し、IMFの予測と同様にイタリアとスペインの落ち込み幅が大きい。2021年についてはIMFに比べ各国の回復幅が大きい。また、ユーロ圏のインフレ率は、2019年+1.2%から2020年+0.2%、2021年+1.1% に低下、失業率は2019年7.5%から2020年9.6%、2021年8.6%と大幅な悪化を予測している。景気下支えのため大規模な財政支出を実施した結果、各国の財政状況の悪化は避けられず、公的債務残高の対GDP比がユーロ圏は2019年86.0%から2020年は102.7%に増加、感染被害が大きいイタリアは2019年の134.8%から158.9%に急激に増加すると予測している(第Ⅰ-3-2-6図)。
第Ⅰ-3-2-6図 ユーロ圏の公的債務残高の推移(対GDP比)
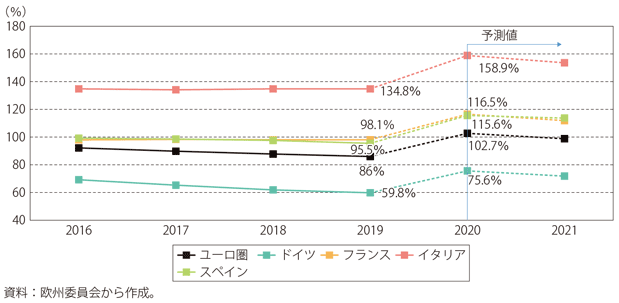
さらに、欧州中央銀行(ECB)スタッフは、新型コロナウイルスの封じ込めの期間や政策が成功するかにもよるが、2020年のGDP成長率が-5%から-12%となる可能性があるとの予測を示している46。
新型コロナウイルス感染拡大に伴う消費や生産の停滞、失業者や企業倒産の増加等、深刻な経済活動の悪化に対応するため、EU(欧州連合)及びや域内各国政府は、財政・金融対策を相次いで決定している。また、感染拡大ペースに鈍化が見られる一部の国々では、ロックダウン(都市封鎖)の解除や工場の生産や商業施設の営業の開始等、経済活動再開に向けた動きも見られているが、感染の状況は国により異なることから、第二波の発生等のリスクに十分に対応した慎重かつ段階的な実施が求められる。
42 英国はユーロ圏ではないが参考のため本項で記載している箇所がある。
43 IMF WEO, April 2020
44 IMFの基本シナリオは、4-6月期に感染がピークに達し、2020年後半にかけて徐々に収束すると想定している。2020年後半まで感染が長期化する場合や、2021年に第二波が生じる場合は、更に下押しされ、2021年もマイナス成長の可能性がある。
45 European Commission Spring 2020 Economic Forecast
46 2020年4月30日のECB理事会後の記者会見でラガルド総裁が言及。
(2)景況感
ユーロ圏の景況感について、景気先行指数である購買担当者指数(PMI)を見ると、2019年に入りユーロ圏及び主要国の製造業は悪化し、業況の改善と悪化の分岐点となる50を下回る状況が続いていたが、2019年末にやや下げ止まりの兆しをみせ、2020年に入ると回復基調を示していた。その一方、サービス業は、ほぼ50を上回る水準で推移し製造業の不振を補ってきた。しかし、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、3月、4月については製造業、サービス業ともに大きく低下し、特にサービス業の落ち込みが著しい(第Ⅰ-3-2-7図、第Ⅰ-3-2-8図、第Ⅰ-3-2-9図)。
第Ⅰ-3-2-7図 ユーロ圏のPMIの推移(製造業とサービス業)
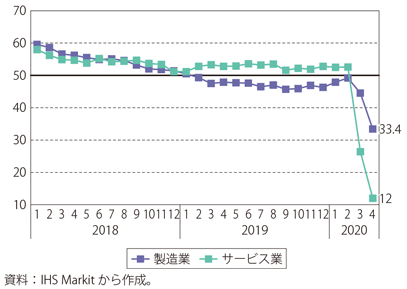
第Ⅰ-3-2-8図 ユーロ圏のPMIの推移(製造業)
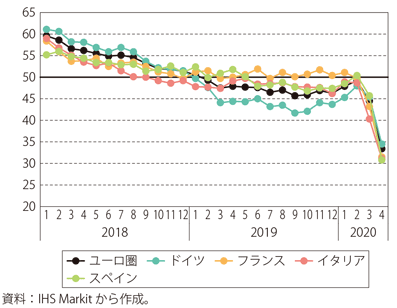
第Ⅰ-3-2-9図 ユーロ圏のPMIの推移(サービス業)
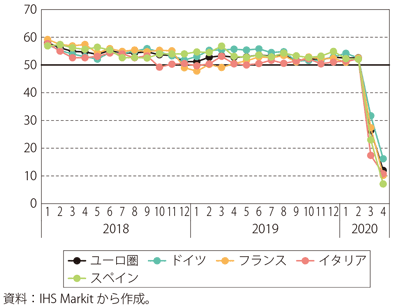
(3)鉱工業生産
ユーロ圏の鉱工業生産は、2018年以降、減産傾向が続いている。中国経済の減速に伴う需要の鈍化や欧州域内の環境規制強化等の影響により、自動車部門の調整が長期化し、欧州の生産活動全体の成長の重石となっている。2019年後半にはドイツを始めとする主要国の自動車等主要業種で一層の落ち込みが見られたが、2020年に入り回復の兆しが見られていた。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、工場の稼働停止やサプライチェーンの寸断等、生産活動に制限がかかり、3月は前月比-11.3%と大きく落ち込んだ。業種別で見ると化学・医薬品、コンピュータが増加したが、その他の業種は低下した。乗用車の生産台数を見ると3月、4月は、全ての主要国で大きく減少している(第Ⅰ-3-2-10図、第Ⅰ-3-2-11図、第Ⅰ-3-2-12図)。
第Ⅰ-3-2-10図 ユーロ圏の鉱工業生産指数の推移(国別)
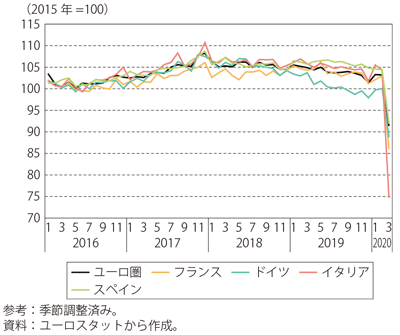
第Ⅰ-3-2-11図 ユーロ圏の鉱工業生産指数の推移(業種別)
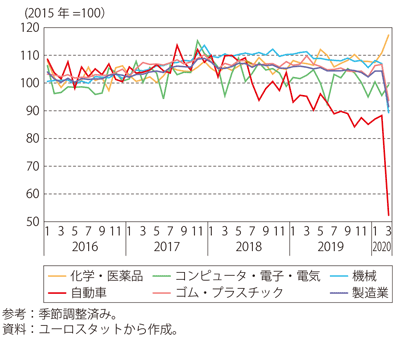
第Ⅰ-3-2-12図 ユーロ圏の乗用車生産台数の推移
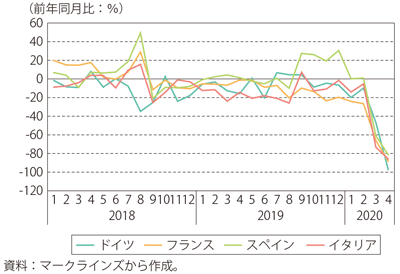
(4)小売売上高
ユーロ圏の小売売上高は、長期にわたり緩やかな増勢をみせていたが、新型コロナウイルス感染拡大に伴う店舗閉鎖や外出制限により、消費活動に制限がかかっていることから、3月には前月比-11.2%と大きく減少した。品目別では、通信販売と食料が増加した一方、衣料品、自動車燃料、コンピュータ等が低下した(第Ⅰ-3-2-13図、第Ⅰ-3-2-14図)。
第Ⅰ-3-2-13図 ユーロ圏の小売売上高指数の推移(国別)
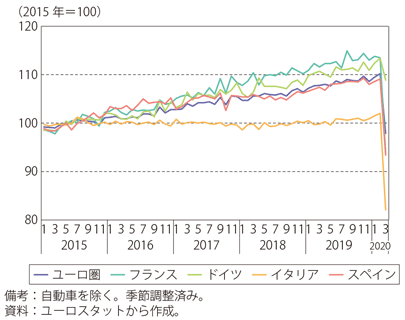
第Ⅰ-3-2-14図 ユーロ圏の小売売上高指数の推移(品目別)
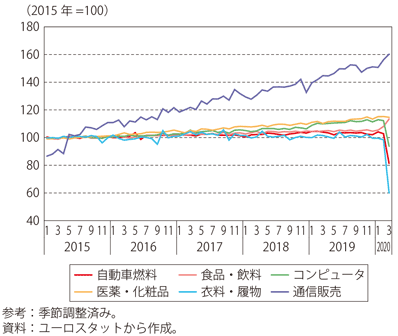
(5)消費者物価
ユーロ圏の消費者物価指数(HICP47)は、2018年11月以降、欧州中央銀行(ECB)の物価目標値48を下回り推移している。2019年後半のエネルギー価格上昇により、2019年12月から2か月連続で上昇し、物価が上向く兆候が見られていた。しかし3月になると、OPECプラス会合で原油減産強化が合意に至らなかったことでエネルギー価格が大きく下落、さらに新型コロナウイルス感染拡大により外出や移動が制限され、経済活動が低迷したため、サービス価格にも低下圧力がかかった。4月のHICPは前年同月比+0.4%(2月%+1.2%→3月+0.7%)と大きく低下している。今後も原油価格下落や感染拡大への対応による経済活動の悪化により、物価は低水準で推移すると予想される。その一方で、食料品や生活必需品の価格は買いだめや物流の停滞等による商品不足の発生等で上昇圧力がかかっている(第Ⅰ-3-2-15図)。
第Ⅰ-3-2-15図 ユーロ圏の消費者物価指数の伸び率の推移
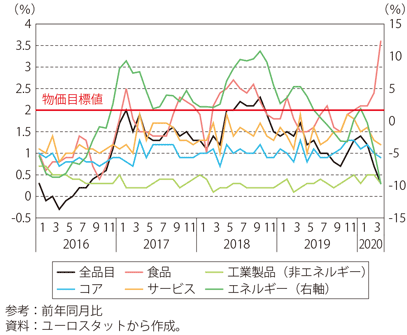
47 EU基準の消費者物価指数(HICP: Harmonized Indices of Consumer Prices)
48 現行水準(2%)もしくはそれを下回る水準。2019年7月のECB政策理事会では「18年末以降、物価上昇室が2%(前年比)を大きく下回る状況が続いていることを踏まえ、インフレ目標の対称性(symmetry)へのコミットメントを初めて明記し、物価安定の目標の達成のためには一時的に物価上昇率が2%を超えることも辞さないという姿勢を示している。」(内閣府 世界経済の潮流 2019年II)
(6)雇用
ユーロ圏の失業率は長期にわたり改善を続け、足下では2008年5月以来の低水準にある。しかし、新型コロナウイルス感染拡大の影響による生産や消費活動の制限により、今後の雇用情勢の悪化が懸念される。4月の失業率は7.3%と3月から0.2ポイント上昇した。国別では休業や労働時間の短縮により減少した賃金を補助する支援策をとったドイツ等の北部欧州と、観光等のサービス業への依存が高く、外出制限や店舗閉鎖が長期化したスペインやイタリア等の南欧諸国との間で、影響の大きさに違いが見られた。欧州委員会は2020年通年の失業率を9.6%と予測している。(第Ⅰ-3-2-16図)。
第Ⅰ-3-2-16図 ユーロ圏の失業率の推移
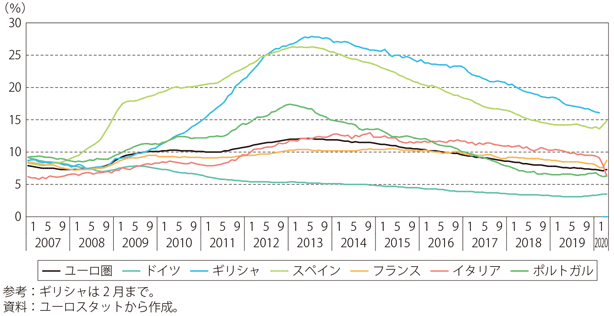
今回のコロナショックに際し、欧州委員会はEU域内企業の従業員解雇を防止するため、ドイツの「操業短縮手当」制度49をモデルとした「失業リスク緩和のための緊急支援制度(SURE)」を導入、基金を通じて1,000億ユーロの支援を可能とした(第Ⅰ-3-2-17表)。
第Ⅰ-3-2-17表 ドイツの操業短縮手当制度について
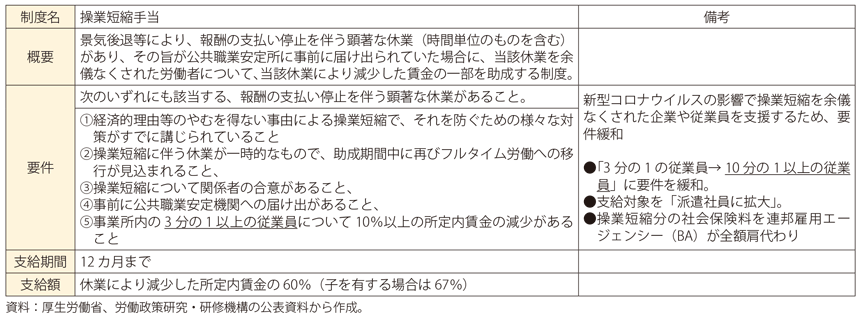
49 景気悪化により労働時間が削減された従業員の給与の一部を政府が補填し解雇を防ぐ制度。世界金融危機等の経済危機時には拡大適用され、ドイツの失業を抑制する役割を果たしてきたといわれている。
(7)貿易
2019年のユーロ圏の主要な貿易相手先(金額ベース)を割合で見ると、輸出入ともにユーロ圏内の国の合計額が全体の4割以上を占めている。域外の主要な輸出相手国は米国、英国、中国、ポーランド、スイス、輸入では中国、米国、英国、ポーランド、ロシアとなっており、輸出入ともに、米国、中国、英国が上位3位を占めている(第Ⅰ-3-2-18図、第Ⅰ-3-2-19図)。
第Ⅰ-3-2-18図 ユーロ圏の輸出相手国(2019年:輸出額割合)
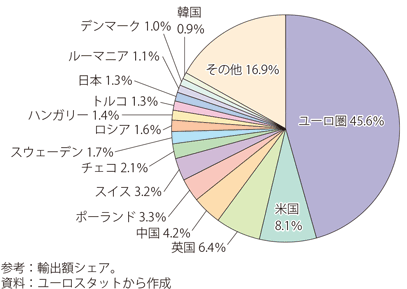
第Ⅰ-3-2-19図 ユーロ圏の輸入相手国(2019年:輸入額割合)
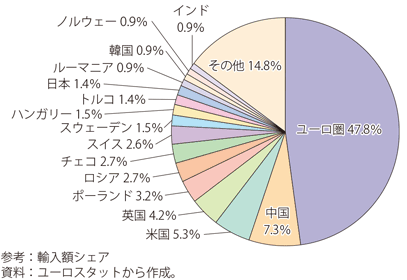
続いて、ユーロ圏の財輸出(金額ベース)の推移を見ると2017年までユーロ圏経済をけん引してきた輸出の伸びは2018年に入り減速し50、後半にやや持ち直しをみせたが再び失速している。2019年前半には当初3月末に予定されていた英国のEU離脱を控えた在庫確保のための駆け込み需要による影響で一時的な増加をみせたが、4月からはその反動で再び落ち込み、その後は低迷が続いている。
2020年3月のユーロ圏の輸出額は、コロナウイルス感染拡大の影響により、前年同月比-11%と大きく減少した。国別ではユーロ圏以外の欧州と米国、韓国等を除くほぼ全ての国がマイナスに寄与したほか、品目別51では、化学品や食品・飲料等がプラスに寄与した一方、機械・輸送機器、素材系製造品等がマイナスに寄与した。(第Ⅰ-3-2-20図、第Ⅰ-3-2-21図)。
第Ⅰ-3-2-20図 ユーロ圏の輸出額伸び率(相手国・地域別寄与度)
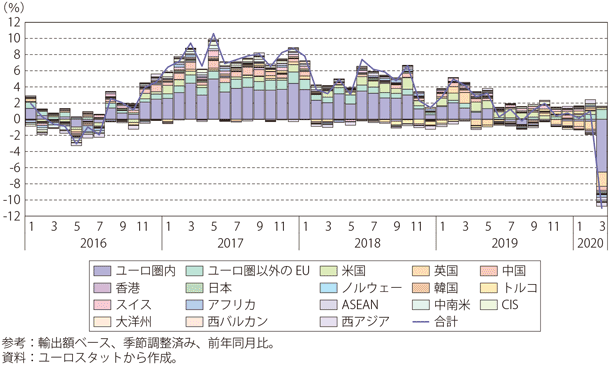
第Ⅰ-3-2-21図 ユーロ圏の輸出額伸び率の推移(ユーロ圏外向け:品目別寄与度)
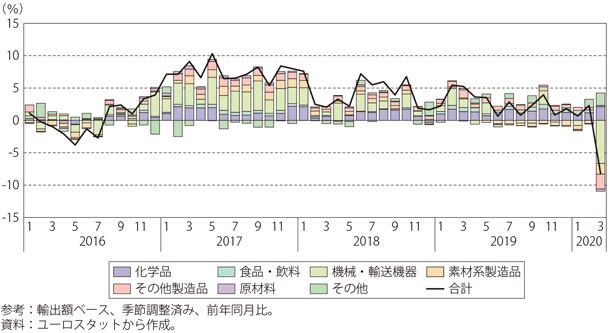
50 2018年は新興国をはじめとする世界経済の減速のほか、年初の寒波やユーロの上昇、8月以降は新燃費測定基準(WLTP)への対応の遅れによる自動車生産の落ち込み、河川の水位低下による物流が遮断され、ドイツを中心に化学品製造業が影響を受けた。
51 本項執筆時点でユーロ圏内向けのデータが入手できないため、ユーロ圏外向けのみとなっている。
(8)ECBの金融政策
欧州中央銀行(ECB)は、新型コロナウイルスの感染が拡大する以前は、成長の鈍化が続く欧州経済の下支えのため、長期にわたる緩和的な金融政策が必要であるとの見解を示すとともに、2003年以来、17年ぶりに金融政策の戦略的な見直しを開始することを決定していた52。
2020年3月2日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、ラガルド総裁は緊急声明で急速な感染の拡大は経済見通しと金融市場の機能にリスクをもたらすものであり、ECBは状況の進展と景気及び中期的なインフレ、金融政策効果の波及に及ぼす影響を注意深く見守るとし、必要かつ潜在的リスクに見合う形で「適切で的を絞った対応策を取る用意がある」と述べた。
それを受け3月12日の政策理事会では、現行の月200億ユーロ(約2兆3,000億円)ペースでの国債等の資産買い入れ(APP)に加え、2020年末までに1,200億ユーロ(約14兆円)の社債等資産の追加購入(総額3,600億ユーロ)と、中小企業等への資金供給のためTLTRO(条件付き長期資金供給オペ)の条件緩和及びLTRO(長期資金供給オペ)の導入を決定した。
さらに3月18日の臨時の政策理事会では、新型コロナウイルス感染拡大による経済悪化や金融市場の不安定化に対応するため、「パンデミック緊急購入プログラム(PEPP)」導入による量的緩和の拡大を決定し、既に拡充を決定した資産購入プログラム53に加えて、計7,500億ユーロ(約90兆円)相当の国債や社債を2020年末までに購入することとした。購入対象については、従来の国債と社債から一定の格付けのコマーシャルペーパー(CP)まで拡大したほか、国債についてもECB加盟国の出資比率(キャピタルキー)に応じて行う割り当てを緩和し、ギリシャ債についても購入対象に含める等、柔軟な運用を行うこととした。ECBは声明文で「権限の範囲内で必要なことは何でもやる」「量的緩和策の規模の拡大や構成を調整する準備はできている」と表明した。
4月20日のECB理事会では、主要政策金利を据え置き、資産購入の規模も現状維持としたが、銀行の資金繰り悪化への対応として貸出し条件付長期流動性供給オペ(TLTRO3)の条件を3月12日に続き追加で緩和し、今年6月からの一年間、最低-1%の超低金利で資金供給を行うことを決定した。また貸出し条件を設定しない新たな長期流動性供給オペ「パンデミック緊急長期流動性供給オペ(PELTROs)」の導入を決定した(第Ⅰ-3-2-22図、第Ⅰ-3-2-23図、第Ⅰ-3-2-24図、第Ⅰ-3-2-25表)。
第Ⅰ-3-2-22図 ECBの資産購入額の推移(ネット:月末時点)
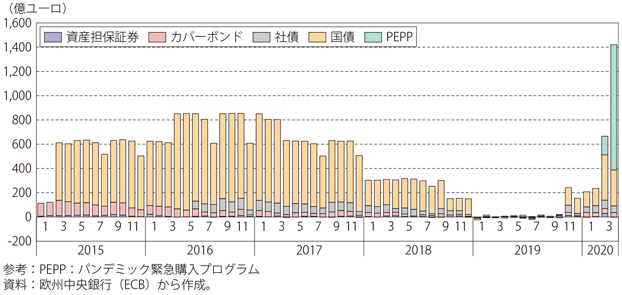
第Ⅰ-3-2-23図 ECBのバランスシート
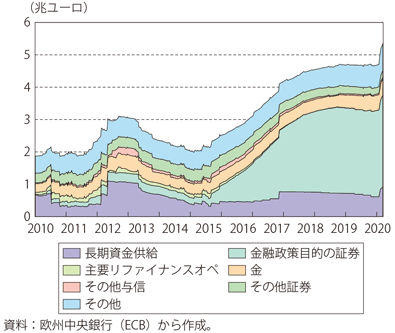
第Ⅰ-3-2-24図 ECBの主要政策金利の推移
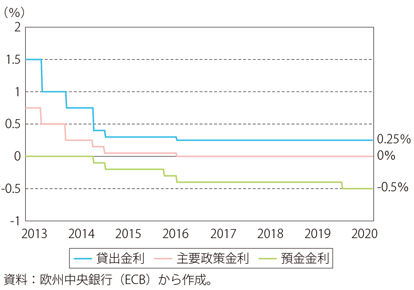
第Ⅰ-3-2-25表 ECBの新型コロナウイルス関連対策の一覧
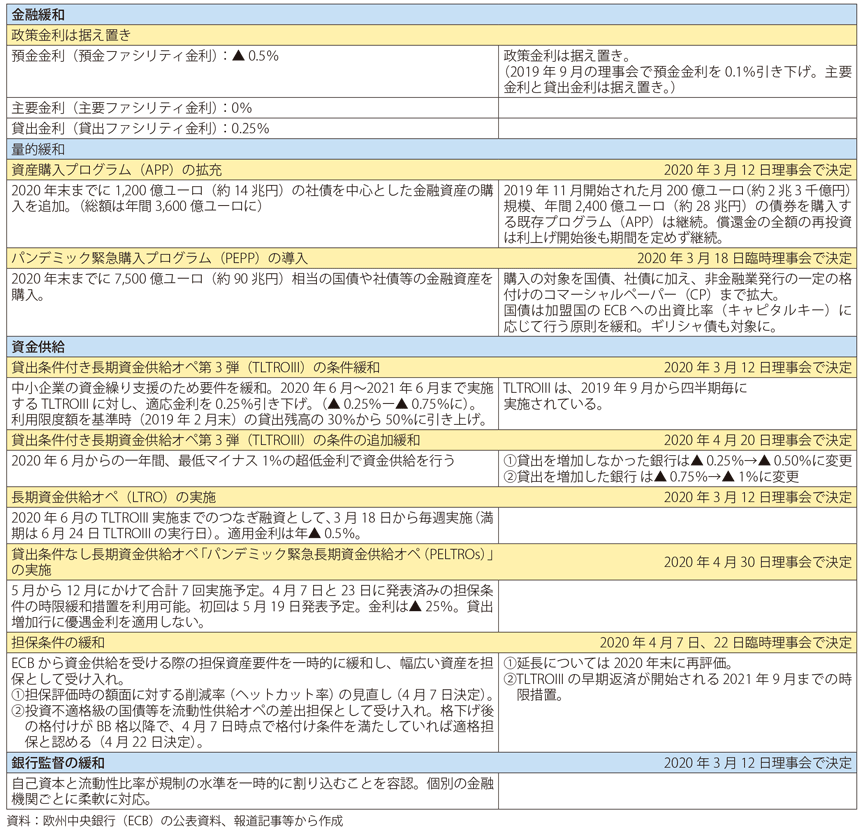
新型コロナウイルス感染拡大への対応54のため財政支出が増大し、債務返済能力の悪化が懸念されるイタリア55を始めとする南欧諸国の国債利回りの上昇は、金融市場の不安要素となっている。イタリア10年債利回りは、新型コロナウイルス感染が発生する以前は1.0%未満の水準で推移していたが、2020年3月12日のECB理事会後の記者会見で、OMT(欧州債務危機時に創設したECBの国債購入策)56の発動の有無についての記者からの質問に対し、ラガルド総裁がイタリア国債のスプレッド縮小はECBの役割ではないと答えたことが、イタリア及び周辺国の国債利回りの上昇を招き、イタリア10年債利回りは一時2.4%まで上昇した。3月18日のECBのパンデミック緊急購入プログラム(PEPP)導入の発表を受け利回りは低下したが、その後も再び高い水準が続いている(第Ⅰ-3-2-26図)。
第Ⅰ-3-2-26図 欧州主要国の10年国債利回りの推移
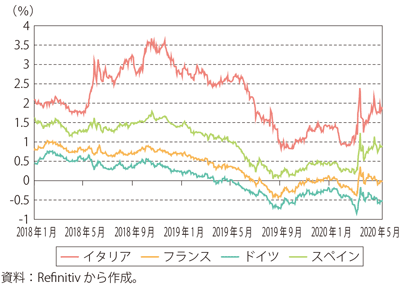
4月22日のECB緊急理事会は、適格担保基準57を緩和し今後投資不適格となる債権についても資金供給オペレーションの担保として受け入れることを発表した。イタリア国債の格付けは、4月末時点で投資適格に留まっているが、今後の格下げの可能性について視野にいれた対応とみられる58(第Ⅰ-3-2-27表)。
第Ⅰ-3-2-27表 南欧諸国の長期国債格付けの一覧
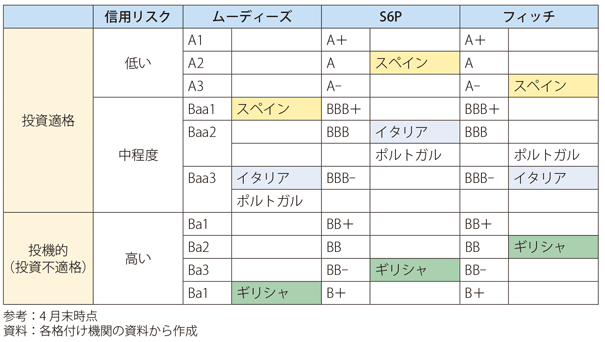
52 当初、期間については2020年末としていたが4月2日付けで2021年半ばまでに延長された。
53 2020年3月12日の理事会で、2020年末までに1,200億ユーロの社債を中心とした金融資産の追加の購入を決定し、総額を年間3,600億ユーロとした。
54 イタリアでは2月下旬から新型コロナウイルスの感染が急速に拡大し、感染者数増加が病院の受入れ能力を上回る医療崩壊の状態を招き、死者数も急増し一時危機的状況となった。
55 イタリアは2020年の財政赤字目標について当初GDP比2.2%としていたが。新型コロナウイルス感染拡大の対策でGDP比0.2%相当を講じるため、イタリア政府は財政赤字を2.5%に拡大することと、非常時としてEUの財政ルールから逸脱することに理解を求める書簡をEU宛てに送っている。またEUとして財政ルールの柔軟性を活用し、持続可能な成長目標のための協調的な財政措置を発動すべきとの意見も示した。これに対しEUはイタリアの財政措置と新型コロナウイルス感染拡大の経済への影響次第で状況が変化することに対し理解を示したといわれる。
56 OMT利用によりECBはほぼ無制限にイタリア国債を買い切ることが可能となるが、欧州安定メカニズム(ESM)による支援が条件となっており、財政再建や構造改革が要求される。
57 ECBはこれまで投資適格とされる「BBB-」以上を必要な担保条件としてきた。
58 4月28日格付会社であるフィッチ・レーティングスはイタリアの信用格付けを「BBB-」に引き下げた。
(9)欧州連合(EU)の新型コロナウイルスへの政策対応
新型コロナウイルス感染拡大の当初は、未曾有の感染拡大への対処のため、EU域内では加盟国ごとの個別の動き59が先行し、EUとして協調や連携に欠ける場面も見られた。その後、感染の拡大ペースの鈍化に伴い、EU内でも収束後の経済再建に向けた対応について検討が開始されている。加盟各国レベルでは、雇用者の所得補償や企業への資金支援、企業への融資に対する政府保証の供与等、大型の経済対策が相次いで発表されており、財政支出拡大に対処し、EUは、加盟国政府のGDP比3%相当の財政出動や同16%相当の融資保証のほか、財政規律の一時的適用除外等について合意している。
2020年4月9日のユーロ圏財務相会合(ユーログループ)は、総額5,400億ユーロ(約64兆円)規模の新型コロナウイルスへの経済対策で合意した。具体的には救済基金である欧州安定メカニズム(ESM)60の活用や、雇用の維持や中小企業の資金繰り支援のためのセーフティネットの設置が決定された(第I-3-2-28表、第Ⅰ-3-2-29図)。
第Ⅰ-3-2-28表 EUの新型コロナウイルス関連の政策対応(1)
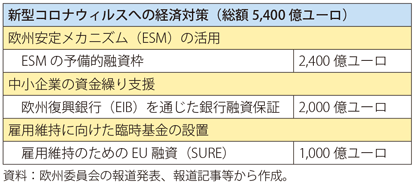
第Ⅰ-3-2-29図 EUの新型コロナウイルス関連の政策対応(2)
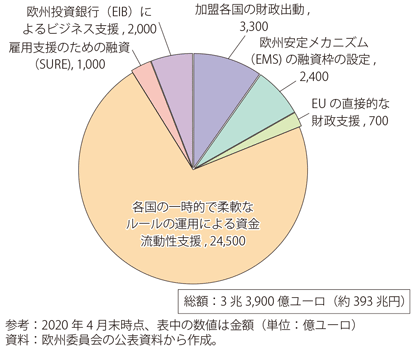
ESMの活用で合意したことで、加盟国はGDPの2%に当たる予備的な信用枠を申請することが可能となり、融資が必要な場合、ESMがその国の国債購入等を通じて支援を実施することになるが、支援を受ける国は欧州委員会による財務状況の監視が課せられる。イタリア等が無条件の活用を求めたが、規律を重視する国々との間で対立が見られ、治療、予防分野に限り無条件での利用が認められた。また一方で、感染収束後の経済再建を支援する復興基金の創設にあたり、ユーロ共同債権「コロナ債」発行による資金調達についても検討されたが、財源や規模、支援の形態等について、財政基盤が脆弱な南欧諸国と財政規律を重視する北部欧州の国々との間に対立が見られ、合意に至らず、首脳レベルの協議に持ち越された。
4月23日のEU首脳会合では、復興基金の創設に向けた準備を開始することで合意されたが、財源や規模等の詳細については折り合わず、次回以降の首脳会合での検討に持ち越され、欧州委員会は5月中に2021-2027年の中期予算と復興基金の具体案を示すことになった。欧州において債務危機が再び発生するリスクを避けるためにも、域内の加盟国間による協調と連帯が期待される。
59 感染の急拡大に対応するため、域内各国ではロックダウンに続き、国境閉鎖や一部の国(ドイツ、フランス)がマスクや手袋、防護服等の医療防具の禁輸措置をとる(その後、撤回)等、自国の保護を優先し圏内でヒトやモノの移動の自由に制限を課した。イタリアはEUに医療防具等の支援を求めたが支援が届くまで時間を要した。イタリアの世論調査では9割近くがEUの支援は不十分だったと回答している。また、感染被害は北部より南欧で深刻で、死亡者数が急増した理由として、債務危機を受けた緊縮財政の一環により、公的サービス削減で病床数が縮小したとする意見もある。
60 ESMは4,100億ユーロ規模の融資能力を持ち、資金繰りに窮した加盟国に対し国債購入等を通じて支えるEUの常設機関である。
2.英国
(1)GDP成長率
英国のGDP成長率は、2019年は+1.4%と2018年同+1.3%からわずかに回復したが、EU離脱を巡る先行きの不透明性の高まりから、個人消費の伸びの鈍化や生産や設備投資が低迷し成長は勢いを失っている61。2019年12月の総選挙で与党保守党が過半数を確保し62、2020年1月末にEU離脱が実現したことで「合意なき離脱」の混乱は回避されたが、移行期間中におけるEUとの間の自由貿易協定(FTA)締結に向けた交渉を巡る動向が新たな先行きの不透明性を高める要因となっている。
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、2020年1-3月期の実質GDP成長率は前期比-2.0%と2019年10-12月期0.0%から悪化した(第Ⅰ-3-2-30図、 第Ⅰ-3-2-31図)。
第Ⅰ-3-2-30図 英国の実質GDP成長率の推移(需要項目別寄与度)
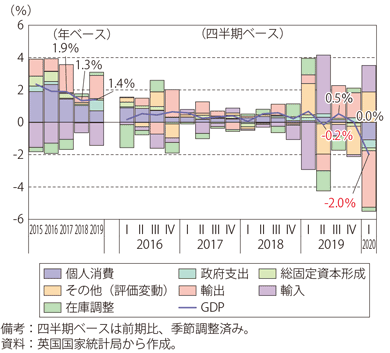
第Ⅰ-3-2-31図 英国の個人消費、総固定資本形成、輸出の推移(前期比)
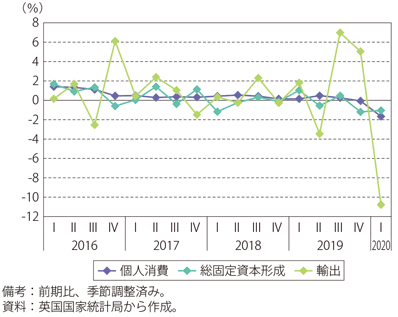
2020年2月下旬以降、新型コロナウイルスの感染が、イタリアからその周辺国、スペイン、フランス、ドイツ、そして英国へと欧州域内で急速に広がった。英国政府は大陸諸国に遅れて3月下旬になり、厳しい行動制限措置を打ち出した。英国での感染者数の増加は現在も続いており、今後の動向について注視が必要である。
英国の2020年1-3月期の実質GDP成長率は、前期比年率で-7.7%と2019年10-12月期(同+0.1%)から大きく低下した(第Ⅰ-3-2-32図)。
第Ⅰ-3-2-32図 英国のGDP成長率の推移(四半期年率換算)
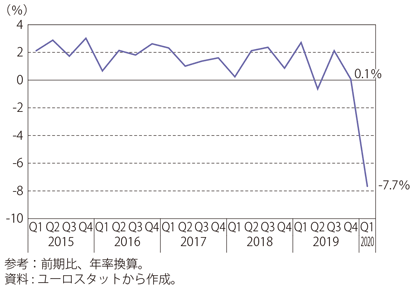
IMFは英国の実質GDP成長率は2019年の+1.4%から2020年は-6.5%と大きく低下するが、2021年には+4.0%に回復すると予測している。またイングランド銀行の経済シナリオによると、英国のGDP成長率は2019年の+1%から、2020年は-14%と約300年ぶりの歴史的収縮幅となるが、2020年後半から急速に持ち直し、2021年は+15%まで回復すると予想している。
61 2019年1-3月期は3月末に予定されていた合意なしのEU離脱に備えた在庫積み増しが成長を下支えしたが、4-6月期は緊急時対応計画の一環で、自動車メーカーが、夏季に実施していた定期修理のための工場停止を4月に前倒しで実施したことが生産を押し下げた。外需は輸出・輸入ともに減少したことから、前期比-0.1%のマイナス成長となった。7-9月期のGDP成長率は前期比+0.5%と前期のマイナス成長から回復し景気後退入りを免れたが、10-12月期の成長率は前期比0.0%とゼロ成長となった。
62 2019年12月12日の英国総選挙では、与党保守党が650議席中、365議席を確保した。
(2)景況感
景気先行指数である英国の購買担当者指数(PMI)を見ると、2019年4月に製造業が悪化し5月以降しばらく業況の改善と悪化の別れ目となる50を下回る状況が続いていたが、9月以降持ち直しをみせ、11月に再び悪化したものの、2020年に入り回復の兆しを見せていた。一方、サービス業は2018年秋以降悪化し、2019年3月には50を下回り、その後は50の水準を回復するも不安定な動きを見せたが、12月以降は上昇傾向を見せ、年明けは大きく改善していた。しかし、2020年3月と4月には、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、製造業、サービス業ともに悪化した。特にサービス業の落ち込みが大きく見られた(第Ⅰ-3-2-33図)。
第Ⅰ-3-2-33図 英国のPMIの推移(製造業とサービス業)
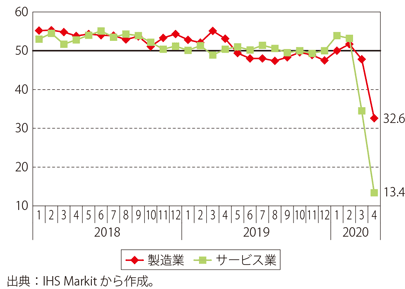
(3)生産
英国の生産は、2019年3月末に予定されていた「合意なしのEU離脱」に備えた在庫積み増しのため一時的に生産を増やしたため、その反動により4月以降は多くの業種で生産が低下した。また、自動車メーカーが緊急時対応計画の一環で、従来夏季に実施していた定期修理のための工場停止を4月に前倒しで実施したことから自動車生産が4月に大きく落ち込んだ。7月に入り回復をみせたものの、9月以降は再び低下傾向にある(第Ⅰ-3-2-34図、第Ⅰ-3-2-35図)。
第Ⅰ-3-2-34図 英国の鉱工業生産指数の推移
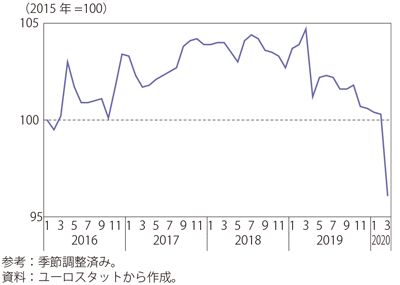
第Ⅰ-3-2-35図 英国の鉱工業生産指数の推移(業種別)
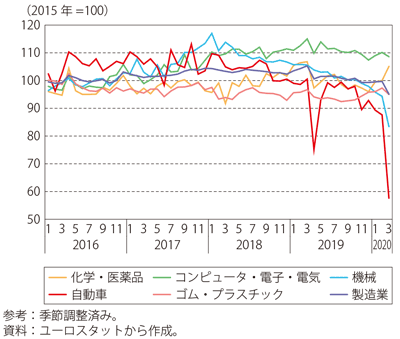
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、工場の休止や部品供給の停滞等により、生産活動に制限がかかっていることから、3月は前月比-4.2%と大きく落ち込み、品目別では、化学・薬品以外の主要な業種で低下し、特に自動車の下げ幅が大きかった。
(4)小売売上高
英国の小売売上高は堅調に推移を続けていたが、2019年後半からやや落ち込みが見られていた。新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛や禁止、商業施設の閉鎖等による影響により、消費活動が制限されたことから、3月は前月比-5.2%、4月は-18.1%と大きく低下した(第Ⅰ-3-2-36図)。
第Ⅰ-3-2-36図 英国の小売売上高指数の推移
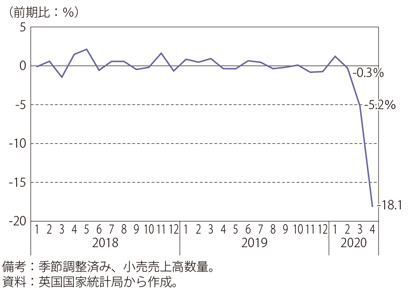
(5)物価と賃金
2016年のEU離脱を問う国民投票の後、ポンドが下落した影響で消費者物価が急上昇したため、2017年の実質賃金伸び率は低下した。2018年以降、物価は低下傾向となり、それに伴い実質賃金は上昇に転じ、その後は伸びが続いている(第Ⅰ-3-2-37図)。
第Ⅰ-3-2-37図 英国の消費者物価と賃金の伸び率の推移
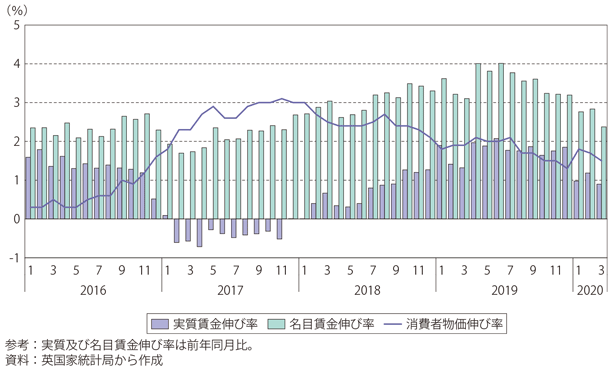
(6)雇用
英国の失業率は、2011年の8.2%をピークに低下を続け2019年は3.8%と低い水準を維持している。一方で、同年の若年者の失業率は11.2%と改善は見られるが依然高い水準にある。新型コロナウイルス拡大の影響による生産や消費活動の制限により、2020年は雇用環境の悪化が懸念される(第Ⅰ-3-2-38図)。
第Ⅰ-3-2-38図 英国の失業率の推移
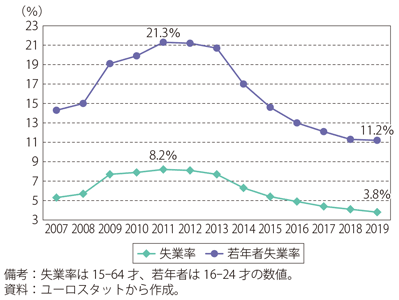
(7)貿易
2019年の英国の財貿易収支は、輸出が約3,660億ポンド(前年比-0.9%)、 輸入が約5,167億ポンド(同+6.1%)、貿易収支は約1,508億ポンド(同+28.2%)の赤字だった(第Ⅰ-3-5-39図)。
第Ⅰ-3-2-39図 英国の貿易収支の推移
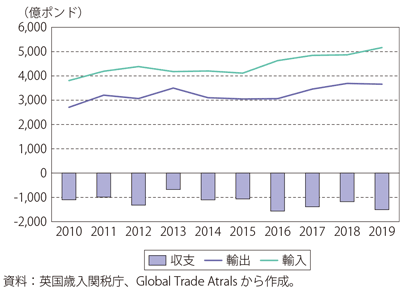
英国の主要な輸出相手国は、米国、EU(ドイツ、フランス、オランダ、アイルランド、ベルギー、スペイン、イタリア)、中国、スイス、香港、UAEとなっている。また、主要な輸出品は、一般機械、貴石・貴金属、自動車・同部品、鉱物性燃料、電気機械、医療機器等である。
2020年3月の輸出額は前年比-19.2%(2月:-9.0%)と新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け大きく落ち込み。多くの主要輸出品目がマイナスに寄与した。(第Ⅰ-3-5-40図、第Ⅰ-3-5-41図、第Ⅰ-3-5-42図)。
第Ⅰ-3-2-40図 英国の輸出相手国(2019年)
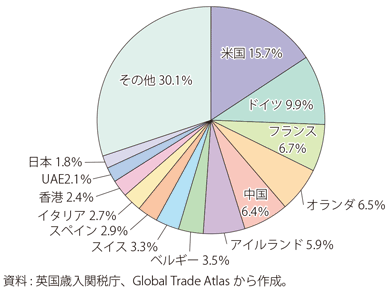
第Ⅰ-3-2-41図 英国の輸出国別の輸出額の推移
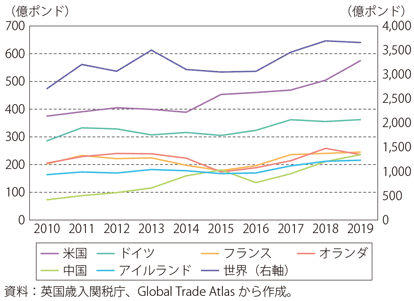
第Ⅰ-3-2-42図 英国の輸出額の推移(品目別寄与度)
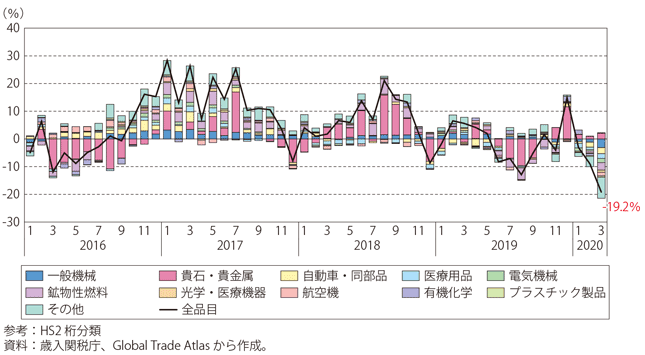
(8)海外直接投資
英国は、金融サービス、専門科学・技術サービス、卸・小売業、化学薬品、自動車産業等、様々な分野で海外からの直接投資を受け入れてきたが、英国向けの対内直接投資額は、2016年をピークに2017年から3年連続で減少している。2020年1月末にEU離脱が実現したことで合意なき離脱の混乱は回避されたが、移行期間中におけるEUとの自由貿易協定締結に向けた交渉を巡る動向が再び先行き不透明性を高め、投資が抑制される要因63となっている(第Ⅰ-3-5-43図)。
第Ⅰ-3-2-43図 英国の対内直接投資額の推移
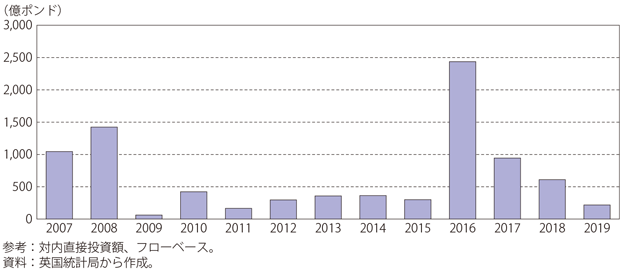
63 EU離脱により単一市場へのアクセスやシングルパスポート等の便益が失われることにより、直接投資の流入の抑制が懸念されている。
(9)イングランド銀行の金融政策
新型コロナウイルス感染拡大の英国経済への影響に対応するため、イングランド銀行(BOE)は、2020年3月11日に臨時の金融政策委員会を開催し、政策金利を年0.75%から0.5%引き下げ、年0.25%にすることを全会一致で決定した。利下げは2016年8月以来で過去最低水準となった。また、市中銀行の自己資本用件の緩和64や長期資金供給スキーム(TFSME)を通じ、中小企業向けに低金利で資金を提供する支援策を同時に発表した65。
BOEは声明文で「新型コロナウイルスによる経済への打撃の規模は極めて不透明だが、英国の経済活動は今後数ヶ月間に著しく弱まる可能性がある」と指摘。会合後の記者会見でカーニー総裁(当時)は「英国の企業と家計を支える包括的でタイムリーなパッケージ」であると語り「必要ならば、さらなる措置を講じる用意がある」と強調した。
さらに同日に英国政府が新型コロナウイルス感染拡大による景気後退リスク阻止に向けた300億ポンド(約4兆円)規模の景気支援策を盛り込んだ新年度予算を発表し、金融と財政の協調を印象付けた。
その後、BOEは、3月19日に定例の金融政策委員会を開催し、政策金利を年0.25%から更に0.15%引き下げ年0.1%にすることを全会一致で決定した。既に3月11日に決定された0.5%の利下げと合わせ合計0.65%の異例の緊急利下げとなった。さらに、国債や社債の買い入れを再開し、購入枠を2,000億ポンド(約25.6兆円)引き上げ、総額6,450億ポンドとした。また先述の長期資金供給スキーム(TFSME)の条件についても緩和した(第Ⅰ-3-2-44表、第Ⅰ-3-2-45図)。
第Ⅰ-3-2-44表 イングランド銀行の新型コロナウイルス対策の一覧
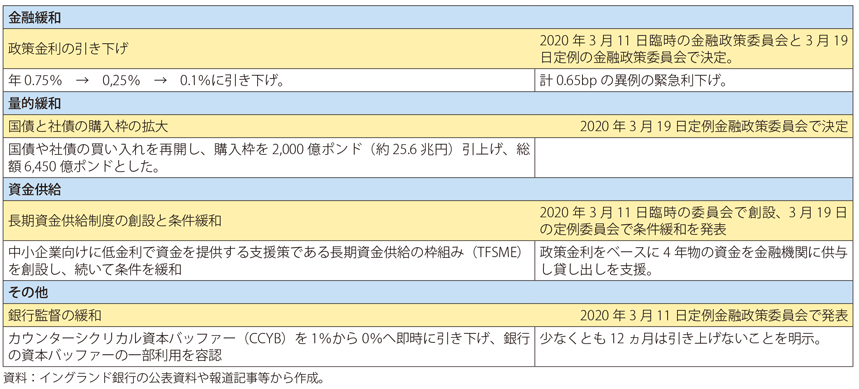
第Ⅰ-3-2-45図 イングランド銀行の政策金利の推移
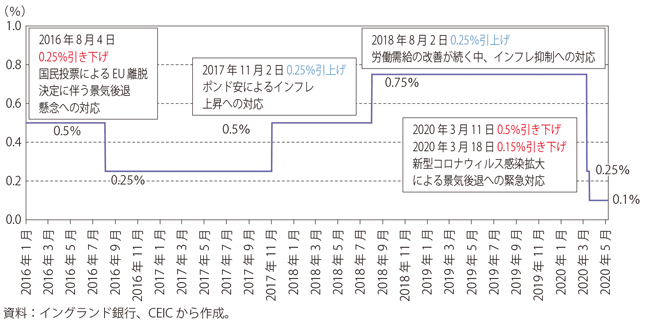
ベイリー総裁66は電話での記者会見で、市場で現金やドルを確保する動きが広がったことで「この数日間に金融環境がかなり急激に逼迫した」「この状況では経済指標を待っていられない」と述べ、新型コロナウイルス感染拡大による市場の混乱ぶりをみて判断を急いだと発言した。資産購入については、「迅速に前のめりで実施する」と強調し、市場の動きを見つつ、買い入れを果敢に進める姿勢を示した。
5月7日に開催されたBOE金融政策委員会では、政策金利を過去最低の年0.1%に、全会一致で据え置いた他、総額6,450億ポンドの国債と社債の購入枠は維持したが、9人のうち2人の委員が1,000億ポンドの増額を主張した。5月6日の時点で資産購入額は約5,285億ポンドに達しており、現在のペースで購入が進めば、7月初めに上限に達すると見込まれる。議事要旨によると「責務を果たすため、必要であれば資産購入の更なる拡大も可能」と再確認されており、次回(6月)の委員会で購入枠が見直される可能性がある。
64 カウンターシクリカル資本バッファー(CCYB)を1%から0%へ即時に引き下げ、銀行の資本バッファーの一部利用を容認する。
65 国債や社債の購入枠については維持するとした。
66 2013年から総裁を務めたカーニー氏の後任として、イングランド銀行副総裁の経験がある英国金融行動監視機構(FCA)のベイリー長官が2020年3月16日に新総裁に就任した。
(10)英国の新型コロナウイルスへの政策対応
英国では、国民健康サービス(NHS)67の医療スタッフや病床不足等、サービスの質の低下が以前から問題視されており、新型コロナウイルス感染拡大への対応に対し危機感が強かった。そのため英国政府はNHSへの負荷軽減のため、治療を受ける感染者増加のピークを遅らせる考えをとったといわれており、国民に対し外出等の自粛を求めた。一方で、国内経済への影響を懸念したことから、強制力を伴う国民の外出禁止命令やレストラン等の閉店命令、出入国規制、学校閉鎖等の措置の導入が他の欧州諸国に比べ実施が遅れた。
また、ジョンソン首相は、3月上旬の感染の初期段階においては、人口の6割を感染させ抗体を持たせることで集団免疫を付けて事態を収束させる戦略を取った。しかし、感染者や死亡者の急増により、医療崩壊を招きかねない状況となったため、宣言の数日後に方針を転換し、3月18日に学校の一斉休校、23日に罰則付きの外出制限を決定した。
さらに、ジョンソン首相自身も3月下旬にコロナウイルスに感染し、一時は集中治療室で治療を受ける等、容体が悪化したが、その後回復し4月12日に退院、療養の後、4月27日に約1ヶ月ぶりに公務に復帰した。
ジョンソン首相は復帰後の演説で、国民の外出自粛が感染拡大阻止の一助になっているとし、国民の1ヵ月にわたる外出禁止令の順守に謝意を表したが、多くの事業者や与党議員から、経済的損害を懸念する声が強まっていることを認めながらも、今はロックダウン(都市封鎖)を緩和すべき時期でないと警告した。厳しい状況は理解しており、なるべく早く経済の立て直しを図りたい一方で、「国民の今までの努力と犠牲を無駄にすることや、感染の第2 波や多数の人命の喪失、医療システムの崩壊を招く危険を冒すことは断じて避けたい」と強調した。
英国政府は3月11日に感染拡大に向けた医療機関への投資や需要急減で経営が悪化する企業向けの救済策などを盛り込んだ300億ポンドの景気対策を含む予算案を発表した。さらに同月18日には、銀行融資に対する政府保証(3,300億ポンド)の他、小売、観光、娯楽産業に対する固定資産税の免除や補助金(200億ポンド交付)等による直接支援を盛り込んだ総額3,500億ポンドの大型経済対策を決定した。感染者数が拡大する中、罰則付きの外出制限と生活必需品以外の全商店の閉店を決定した一方で、休業従業者の給与の8割(上限は従業員1人当たり月々2,500ポンド)の補償も決定した。また、6月末までの付加価値税納付分の会計年度末まで猶予や中堅企業向けの緊急融資制度の導入、中小企業向け融資制度にも追加措置を行うことを発表した。
67 患者の医療ニーズに対し公平なサービスを提供することを目的に1948年に設立され、英国の国家予算の約4分の1が投じられている。利用者の健康リスクや経済的な支払い能力にかかわらず、自己負担金額は基本的に無料で、外国人も合法的に英国に居住していると認定を受ければ、NHSのサービス利用が可能である。
3.英国のEU離脱を巡る動向
(1)現状と経緯
2020年1月31日、英国は1973年の欧州連合(EU)加盟68後、47年ぶりにEUから離脱69し、12月31日までの移行期間に入った。期間中、英国ではEUの法令が引き続き適用され、EUの単一市場、関税同盟に留まるが、移行期間中に新たな通商協定が締結されなかった国との間の貿易は、2021年1月1日よりWTOルールに基づいたものとなる。
移行期間については、EUとの間の取り決め上、一度限り1年または2年の延長が可能となっているが、延長するためには2020年6月30日までに双方の合意が必要とされている。しかし、英国のEU離脱協定法では移行期間の延長は禁じられており、ジョンソン政権は年末の「完全離脱」を表明している(第Ⅰ-3-2-46表)。
第Ⅰ-3-2-46表 英国のEU離脱の経緯
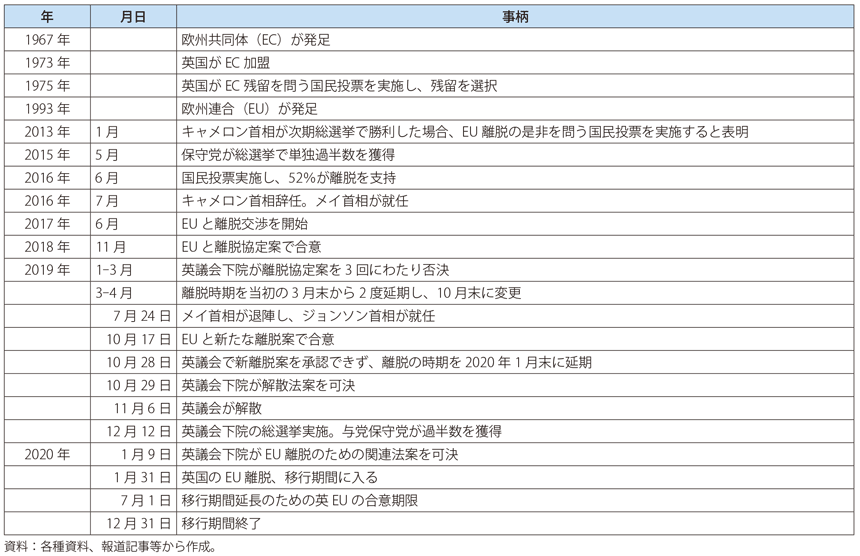
通例、通商協定交渉には、長期の年月が費やされていることから考えると、実質1年たらずの短い期間でEUとの合意は困難が予想されている。
68 当時は欧州共同体(EC)
69 英国EU諸機関の代表権を失うが、EU法の適用を受ける特殊な地位に置かれている。またこれまでどおりEUと英国双方の企業や市民の経済活動は保証されている。
(2)今後のEUの交渉日程と課題
英国とEUは「EUとの将来の関係(自由貿易協定)」の大枠を示す「政治宣言」に従い、3月2日から自由貿易協定(FTA)70の締結に向けた交渉を開始した。12月末までの移行期間中の発効を目指すが、交渉時間の不足等から期間内に協定が締結できなければ、2021年1月から原則としてWTOルールに基づき貿易を実施することになり、英国とEUの間の貿易に関税や関税手続等が発生71し、これまでの自由な貿易関係が損なわれる事態が懸念される(第Ⅰ-3-2-47表)。
第Ⅰ-3-2-47表 英国とEUの交渉に関わる日程(2020年)
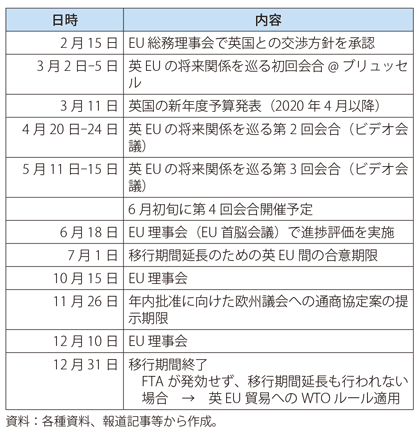
英国とEUは年内の妥協に向けて、2020年3月2~5日、ブリュッセルで・EU英国の新たなパートナーシップについての交渉の初会合を実施した。その後5月までに計5回の会合が予定されていたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、3月18日からロンドンで開催予定だった第2回会合を延期した。4月20~24日、第2回会合がビデオ会議形式で開催されたが、公正な競争環境の確保と統治、漁業の主要3分野で双方が対立し交渉に進展が得られなかったと発表された。英国とEUは今後5月と6月に1回ずつ交渉を行う予定だが、妥結の道筋は見えていない。英国側は新型コロナウイルス感染拡大を理由とした移行期間の延長はしないとの立場を堅持している。
また、4月30日、英とEU は離脱協定に基づき、アイルランド・北アイルランド国境管理を実施するための第1回「アイルランド・北アイルランドに関する特別委員会」をテレビ会議形式で開催。委員会後に英国政府は、更なる議論を深めるための作業部会での議論を継続することに合意した。
70 「自由貿易協定(FTA)を核とした刑事司法、外交や治安、国防等を含む貿易と経済協力に関する野心的、広範、柔軟なパートナーシップ」
71 世界貿易機関(WTO)が定める関税が適用された場合の関税率は自動車で10%、テレビ14%、自動車部品は3~4.5%等とされる。
(3)英国とEUの対立点と今後の交渉の行方
FTA交渉にあたり、EU側は公平な競争環境の確保が自由貿易の前提と主張し、英国がこれまで通り関税撤廃等、開かれた通商関係を望むのであれば、EUの法令や基準を従来どおり尊重するよう相互主義の原則を求めている72。一方の英国側は、通商面での高度な自由化を目指し、EUとの規制の調和は限定的な範囲に留める「カナダ型」の協定を求めており、双方の立場の違いは明確である。さらに、英国が漁業や司法協力等の分野ごとに「部分的・個別の合意」を結ぶ意向を示しているのに対し、EUは全ての分野を含む「包括的な合意」を求めている。
2020年4月24日に第二回目の交渉を終えて、バルニエEU 首席交渉官は、時間的な余裕がないにもかかわらず、英国側からの歩み寄りは見られず、英国が離脱後の移行期間の期限を 2020 年末から延長することを排除したと述べた。同氏は記者会見で「英国は交渉を巡る非常に短い日程を強いることはできない。一方で、EUにとって重要な特定分野を巡り対応したり進展させたりすることもなかった」と述べた。一方、英国首相官邸の報道官は、EUとの貿易協定交渉を成功させるには、特に漁業及び公平な競争環境の分野で、EU側の政治的な歩み寄りが必要と述べている。
また、英国のEU以外の国々との自由貿易協定交渉については、トラス英国際通商大臣は、議会宛ての声明で与党保守党が2019年の選挙公約で示した「向こう3年間で英国の自由貿易協定のカバー率を80%とする」との目標の実現に向け、EU以外の国とも通商関係の強化を目指すとの基本方針を発表している。交渉の優先国としては、米国、日本、豪州、ニュージーランドの4か国が明示されており、各国との二国間交渉が、英国の環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11)加入の足がかりになるとの見解も示している。
通商協定交渉には、交渉の開始から締結までに、数年間に渡る時間が費やされるのが通例であり、当初より、2020年末までの短期間でのEU及び他国との合意は困難との見方が強い中、新型コロナウイルスの感染拡大による経済の停滞と混乱も加わり、先行きの不透明感が更に高まっている。2020年末に向けた交渉の行方次第では、欧州を始め世界の企業活動や金融市場に与える影響が懸念される。
また、北アイルランド国境管理では、英国内における税関検査を最小限に抑え「連合王国」の一体性を維持したい英国と、北アイルランドをEU圏内への抜け穴にされることに対する強い懸念を持つEUとの間で激しい駆け引きが行われることが予想され、これが同時に進むFTA交渉へ影響を及ぼすことも懸念されている。
72 「欧州グリーンディール」や「デジタル化政策」等を含むEUの標準や規制を英国が受け入れず独自に規制緩和を進め、優位な立場を確立することに対する警戒感がある。
