

- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2020

- 白書2020(HTML版)

- 第Ⅰ部 第3章 第3節 中国
第3節 中国
1.中国のマクロ経済動向
本節では、2019年からの中国経済を概観する。2019年の中国経済は、米中貿易摩擦の影響等から減速が続き、2020年に入ると新型コロナウイルス感染拡大の影響により経済は大きく落ち込んだ。国内外の人の移動を規制したことで、生産、消費、投資、貿易、物価、雇用等の幅広い分野において停滞や悪化が見られるところ、これらの動きについて主要経済指標を追いながら分析していく。その上で、政府の対策(感染症の拡大を防ぎながら、医療品や生活必需品の供給、企業活動の再開や損失を受けた企業への補助などの支援策)を概観する。
(1)GDP
2019年の実質GDP成長率は6.1%と政府の目標(6~6.5%)は達成したものの、前年(6.6%)からは減速した(第Ⅰ-3-3-1図)。四半期別には、年初から伸び率の低下が続き、10-12月期に6四半期ぶりに一旦は下げ止まったものの、2020年1-3月期は新型コロナウイルス感染拡大による経済の停滞を受けて、前年同期比 -6.8%と、四半期ベースで統計が遡及できる1992年以降では初めてのマイナスとなった。年ベースでは文化大革命が終わった1976年以来のマイナスである。
第Ⅰ-3-3-1図 中国の実質GDP成長率(前年同期比)の推移
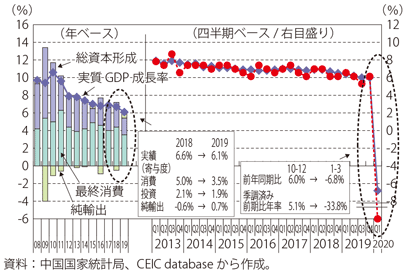
需要項目別の寄与度は、2018年から2019年への変化は、消費、投資の寄与が縮小し、純輸出は輸入が輸出以上に落ちたためプラスの寄与に転じた(第Ⅰ-3-3-2表)。2020年1-3月期は、新型コロナウイルスの関係で各項目ともマイナスに転じたが、特に消費の落ち込みが全体を大きく押し下げている。
第Ⅰ-3-3-2表 中国の実質GDP成長率の需要項目別内訳
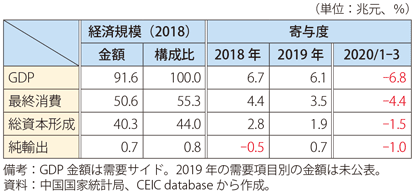
(2)工業生産
2019年の工業生産の伸び率は、月別の振れはあるものの、緩やかに低下しており、2019年全体としては前年に比べて小幅ながら鈍化した(第Ⅰ-3-3-3図)。2020年に入ると1-2月の伸びが2桁台のマイナスに転じた。月次統計で遡及できる1995年以来のマイナスであり、2008年の世界金融危機で落ち込んだ時ですら、プラスを維持したことに比べれば影響の大きさがうかがわれる。感染症の影響で春節明けから人の移動が規制され、帰郷した農民工が戻れず、また資材調達にも支障が生じて、工場の操業に影響が出たためと見られる。3月になると工場の操業が次第に再開され、食品、医薬品などの必需品や電子・通信機器等を中心に持ち直しの動きが見られ、さらに4月には主要業種の伸びはプラスに転じた(第Ⅰ-3-3-4表)。
第Ⅰ-3-3-3図 中国の工業生産の伸び率(前年同期比)の推移
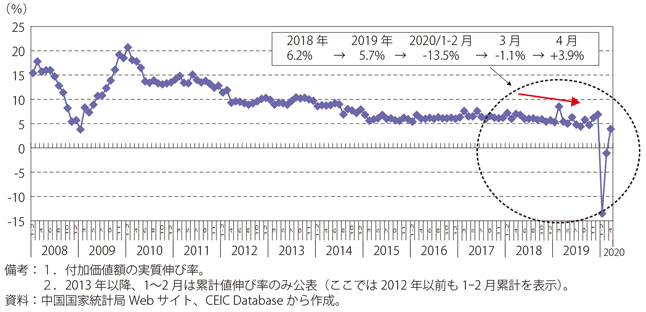
第Ⅰ-3-3-4表 中国の工業生産の伸び率(前年同期比 / 主要業種別)
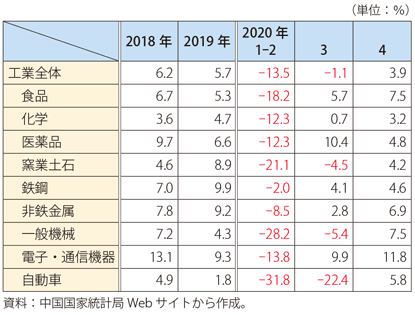
(3)小売売上高
小売売上高も2019年は減速が続いたが、2020年に入ると1-2月は感染症の影響で大幅なマイナスに転じた(第Ⅰ-3-3-5図)。これは月次統計で遡及できる1994年以来初めてのマイナスである。世界金融危機の時にも、4兆元の景気対策があったとはいえ、10%を越える伸びが続いたことに比べて落ち込みが大きい。3月、4月もマイナス幅は縮小したものの、依然としてマイナスが続いている。品目別には、生活必需品である食品はプラスが続いているが、衣類、家電、石油製品などは4月でもマイナスのままとなっている(第Ⅰ-3-3-6表)。店舗や工場の閉鎖、再開しても売上の減少などから、雇用環境や所得水準が悪化し、将来への不安と相まって購買意欲を萎縮させ、外出規制が購買活動自体を低下させたと考えられる。なお、財のネット販売は、大幅な鈍化となったものの、伸び率のプラスを維持した。これは外出が制限されたことに伴い、消費者がインターネットによる購入に移ったことが考えられる。
第Ⅰ-3-3-5図 中国の小売売上高の伸び率(前年同期比)の推移
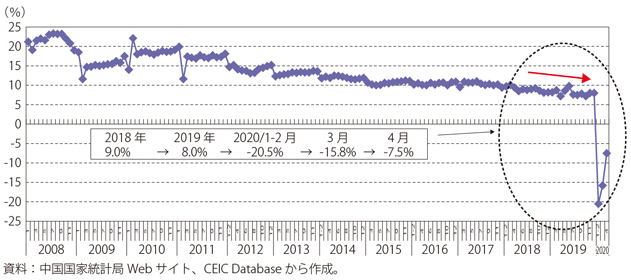
第Ⅰ-3-3-6表 中国の小売売上高の伸び率(前年同期比 / 主要品目別)
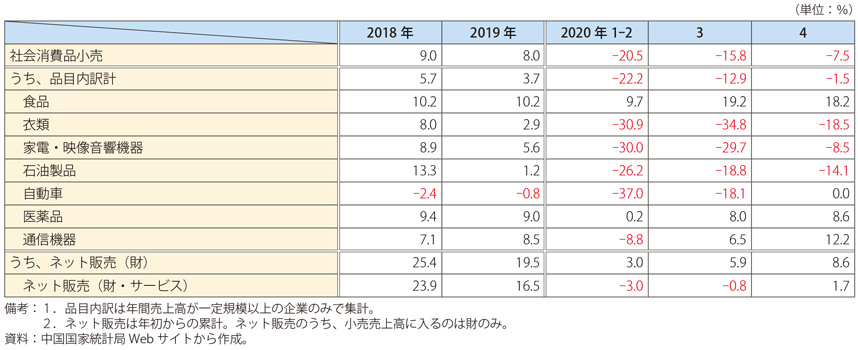
(4)固定資産投資
固定資産投資は2018年後半から2019年初めにかけて一時的に回復したものの、それ以降は減速しており、2019年全体で見れば前年より伸び率は低下した(第Ⅰ-3-3-7図)。さらに2020年1-2月は20%を越えるマイナスに見舞われ、1-3月、1-4月になってもマイナス幅は縮小したものの、2桁台のマイナスが続いている。月次統計で遡及できる1995年12月期以来、初めてのマイナスである。1-3月、1-4月はライフラインである電気・ガス・水道がプラスとなったが、製造業は総じて回復が遅れている(第Ⅰ-3-3-8表)。製造業の中では、電子・通信機器の回復が比較的早く1-4月にプラスに戻ったほか、医薬品も回復に向かっている。これまで景気支援策として利用されることの多かった電気・ガス・水道以外のインフラ投資(道路、鉄道等)も大きなマイナスを記録した。国内外の経済が停滞して投資意欲が減退するとともに、人の移動が規制されたことで、建設工事自体が滞っている。
第Ⅰ-3-3-7図 中国の固定資産投資の伸び率(前年同期比)の推移
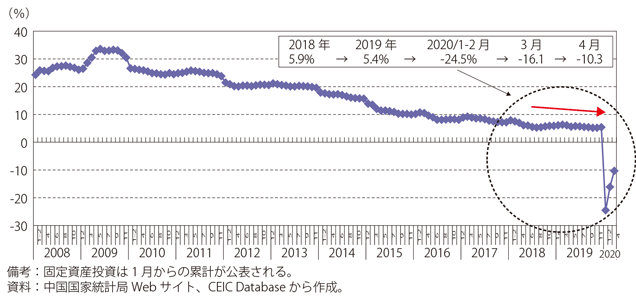
第Ⅰ-3-3-8表 中国の固定資産投資の伸び率(前年同期比 / 主要業種別)
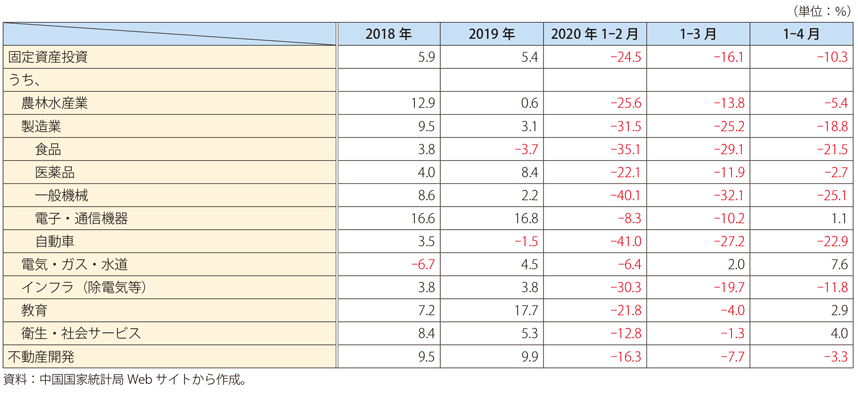
(5)貿易
貿易は米中貿易摩擦を背景に2018年末頃から急速に悪化し、2019年を通じて低調に推移した(第Ⅰ-3-3-9図)。主要国別には2019年は対米向けが輸出入ともに2桁台のマイナスに転じ全体を引き下げた(第Ⅰ-3-3-10表)。2019年末、米中間で第一段階の合意に達し、輸出入の回復が期待されたが、2020年に入ると感染症の影響が貿易にも及んだ。2020年1-2月は対世界計で輸出入ともにマイナスを記録した。特に国内に立地する工場の操業開始の遅れを反映して輸出が大きく減少した。3月は輸出のマイナス幅は縮小し、4月には国内における生産回復の動きを反映して輸出はプラスに転じたが、新型コロナウイルスが世界的な感染拡大を見せ、特に欧米先進国の需要が減退したことから、4月に欧米向け輸出はプラスに転じた国でも、総じて低い伸びにとどまっている。一方、輸入は4月に大きく減少。米国からの輸入は米中間の合意を受けて2019年末から2020年初頭まで前年比プラスとなったが、2020年3月、4月と2桁台のマイナスに転じた。
第Ⅰ-3-3-9図 中国の貿易の伸び率(前年同月比)の推移
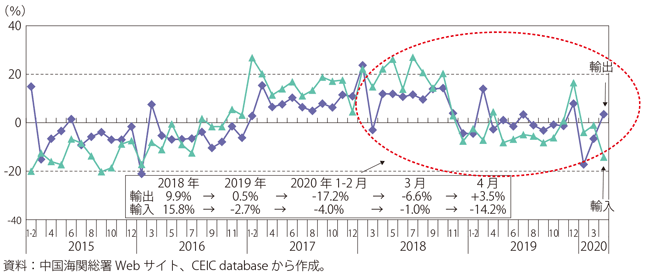
第Ⅰ-3-3-10表 中国の貿易の伸び率(前年同月比 / 主要国別)
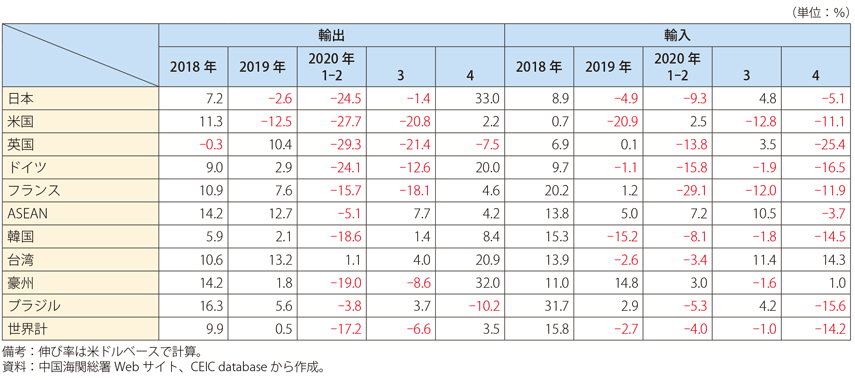
(6)物価
2019年の消費者物価は、食品・エネルギーを除くコア指数が緩やかに低下する一方で、ASF(アフリカ豚熱)や対米貿易摩擦の影響で豚肉など食品を中心に高い伸びが続き、特に2019年秋以降は消費者物価全体としては政府目標(3%前後)を上回って推移した(第Ⅰ-3-3-11図)。2020年になってからは感染症の影響による物流の停滞、品不足等の要因も加わったが、次第に伸びは低下してきている。一方、生産者物価は2019年央以降、マイナスに転じ、2020年1月に一旦プラスに戻ったものの、新型コロナウイルスの影響が顕在化した2月に再びマイナスに転じた(第Ⅰ-3-3-12図)。これは感染拡大の影響で生産が停滞し、原材料の需要が弱まった影響が指摘されている。その後は、国際的な原油価格下落の影響もあり、資源関係を中心にマイナス幅が拡大している。
第Ⅰ-3-3-11図 中国の消費者物価上昇率(前年同期比)の推移
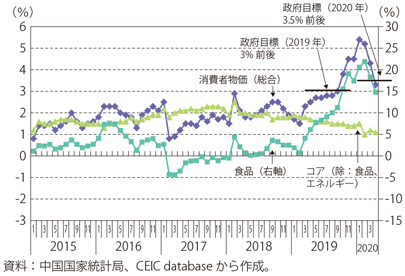
第Ⅰ-3-3-12図 中国の生産者物価上昇率(前年同期比)の推移
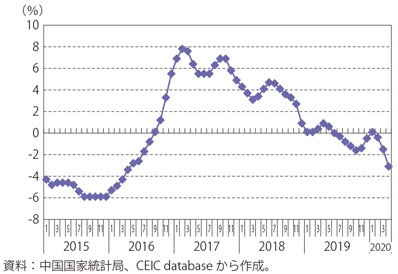
(7)雇用関係
2019年の都市部調査失業率は、政府目標(5.5%前後)は下回ったが、前年に比べて高めに推移した73(第Ⅰ-3-3-13図)。2020年に入ると2月の失業率が大きく上昇、3月、4月も2019年と比べて高く、5月の全人代で決定された2020年の政府目標(6%前後)近辺を推移している。また、都市部新規就業者数は2019年の政府目標を達成したが、2020年初頭は前年同期と比較して大きく落ち込んでいる(第Ⅰ-3-3-14図)。
第Ⅰ-3-3-13図 中国の都市部調査失業率
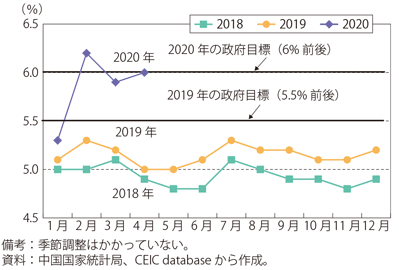
第Ⅰ-3-3-14図 中国の都市部新規就業者数(年初来累計・前年比)の推移
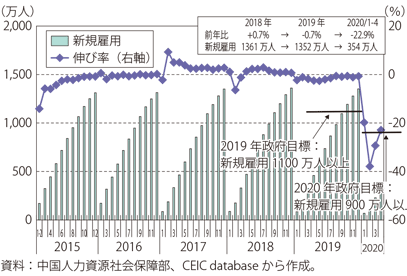
73 中国では失業率に「都市部登録失業率」と「都市部調査失業率」の2種類がある。前者はその都市に戸籍のある住民のみを対象とした失業率で、いわゆる農民工の失業は含まない。それでは実態を表していないという指摘を受けて、農民工も含めた統計として作成されるようになったのが後者。2020年5月の全国人民代表大会(略称:全人代。日本の国会に相当)は、2020年目標として、前者については5.5%前後(昨年4.5%以内)、後者については6%前後(5.5%前後)と設定した。
(8)所得
中国の1人当たり可処分所得は名目額では年々増加してきたが、2019年の名目伸び率は前年とほぼ同じ、実質伸び率ではやや鈍化した。2020年に入ると名目伸び率はほぼゼロ近傍まで低下、実質伸び率はマイナスに転じた(第Ⅰ-3-3-15図)。
第Ⅰ-3-3-15図 中国の1人当たり可処分所得(年初来累計・前年比)の推移
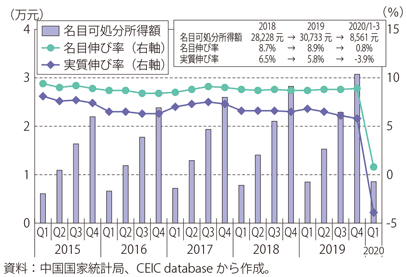
これまで見てきたように、中国経済は2019年にプラス成長ながらも減速が続き、2020年初頭は新型コロナウイルス感染拡大の影響でマイナス成長に転じた。2020年初頭の動きを月次統計で見ると、3月は1-2月期の大幅な縮小に比べれば、生産面では持ち直しの動きも見られるが、需要面では小売や投資の大幅な減少が続いている。さらに2020年初頭は貿易も減少している。このような中で雇用状況も悪化、可処分所得も低迷している。
これに対する政府の対策を次の項で見ていく。
2.政府の対策
既に第1章で横断的に各国の新型コロナウイルスに対する対策を概観したが、ここでは中国に焦点を当てて見ていく。
中国政府は感染症の広がりに対して、広範で厳格な人の移動規制をかけるとともに、医療品など不可欠な物資の優先的な供給に努め、損失を被り、資金繰りで苦境にある中小零細を始めとする企業への支援を行っている。5月の全国人民代表大会(略称:全人代、日本の国会に相当)においては、これらの施策の延長や一定の財政措置が決定された。
(1)感染症拡大防止のための人の移動制限
新型コロナウイルスによる最初の患者は湖北省の省都武漢市で発見されたが、時期的に春節に重なったため、春節による帰郷や旅行などの人の移動に伴って中国内外に感染症が拡大したとされる。今年の中国の春節休暇は1月24日(金)から30日(木)までと定められていたが、中国政府は直前の1月23日に武漢を事実上封鎖するとともに、その他の地域についても移動制限を課した74。しかし、既に武漢から出た者も多いと指摘されている。中国政府は春節休暇を2月2日(日)まで延長したが、そこからさらに1週間の延長を指示した地方政府も多い75。
中国の感染者の推移を見ると、1月末から2月にかけて増加している(第Ⅰ-3-3-16図)。3月に入る頃からは国内の感染者の増加は緩やかになる一方で、むしろ海外からの感染者の流入をより警戒するようになり、地方政府ごとに海外からの入国制限措置を導入した76。さらに中央政府は3月28日から全ての外国人の入国を禁止する措置を発動した77。
第Ⅰ-3-3-16図 中国の感染者数(累計)の推移
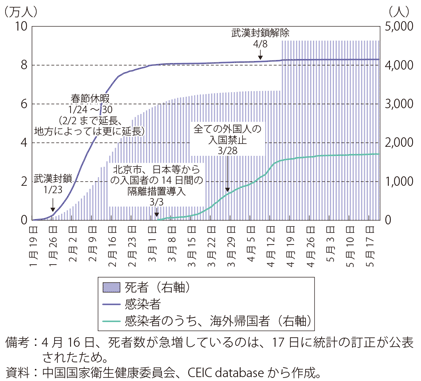
74 例えば、春節により帰郷した農民工が職場のある地域に帰る際の移動制限、地域に戻ってからの14日間の隔離措置などを実施した。また、海外への出国についても、1月27日、団体旅行を禁止するなど制限を始めた。
75 春節休暇後は徐々に企業の操業が再開されたが、移動の制限や隔離措置によって従業員の職場復帰の遅れ、資材調達が十分にできないこと、衛生管理への配慮等のため、再開までに日数を要した。また、操業しても稼働率が低い状態が続いたと伝えられる。
76 例えば、北京市は、3月3日、韓国、イタリア、イラン、日本からの入国者の14日間の隔離措置を導入した(地方政府によって対象国や実施時期に相違があるもよう)。また、中央政府は3月10日から日本に対する観光目的等での15日以内の短期入国の場合のビザ免除措置を停止した。
77 外交ビザ等の保有者を除き、これまでに発行された有効な訪中査証及び居留許可証による外国人の入国を暫定的に停止。なお、貿易や人道支援などの理由で新たにビザを申請し、認められれば入国は可能。
(2)財政・金融支援
中国政府は、医療品等の生産を支援するとともに、新型コロナウイルス感染拡大の影響で苦境にある企業に対して様々な支援策を講じている。例えば、企業の税・社会保険料を減免するとともに、リストラを抑え雇用を維持した企業への雇用保険料の還付、交通運輸業等の影響の大きかった産業の欠損金の繰越控除期限の延長などを実施している。さらに中小企業の借入れ元本・利子の返済猶予も実施している。
5月の全人代においては、これら企業の減税・社会保障負担費の減免措置や中小企業の返済猶予の期間延長の延長を決定した78。また、2020年の財政赤字を対GDP比3.6%以上(昨年は同2.8%)に設定して前年度比で1兆元増(昨年2兆7,600億元→3兆7,600億元)の支出を増やすとともに、別途、感染症対策特別国債1兆元を発行し、財政赤字・特別国債の計2兆元を用意して、全て地方政府に回すことを発表した。さらに一部、前倒し発行を認めてきた2020年の公共事業用の地方債を正式に3兆7,500億元(昨年2兆1,500億元)と決定して昨年より1兆6,000億元増額した。
金融面を見ると、中国人民銀行は春節が明ける2月3日に金融機関の営業を再開するよう指示するとともに、同日、1兆2,000億元にのぼる公開市場操作を実施して資金を供給した。その後も公開市場操作を通じて市場に十分な資金が供給されるよう配慮している79。
中国人民銀行の融資に関しては、医薬品・生活必需品等を提供する企業に対して3,000億元の特別融資枠を設定した80。これとは別に中小零細企業を含む幅広い企業の操業再開を支援するため、5,000億元の再融資・再割引枠も設定した81。さらに3月31日の国務院常務会議において、再融資・再割引枠は1兆元を追加することが決まった。この3つを合計すると1.8兆元の金融支援となる。
政策金利に関しては、企業の負担を軽減するため、2月の公開市場操作において中期貸出ファシリティ(MLF)金利、それに基づく最優遇貸出金利(LPR)1年物をそれぞれ0.1%引き下げ、再度、4月にもMLF金利、LPR1年物を更にそれぞれ0.2%引き下げた。
銀行の貸出余力を高めるため、銀行が中国人民銀行に強制的に資金を預ける比率である預金準備率についても引下げを行っている。預金準備率は景気支援のため、昨年からたびたび引き下げられてきたが、今年の3月以降は新型コロナウイルスを念頭に、中小零細企業への融資が多い銀行にターゲットを絞って引下げを実施している(第I-3-3-17表)。まず3月16日、中小零細企業への融資比率の高い銀行を対象に0.5~1.0%の預金準備率の引下げを実施した82。さらに4月3日、農民や中小零細企業への融資拡大のため、農村商業銀行や地方で営業している銀行等に対して、1.0%の預金準備率引下げを行うことを公表83。
第Ⅰ-3-3-17表 中国の預金準備率の変更
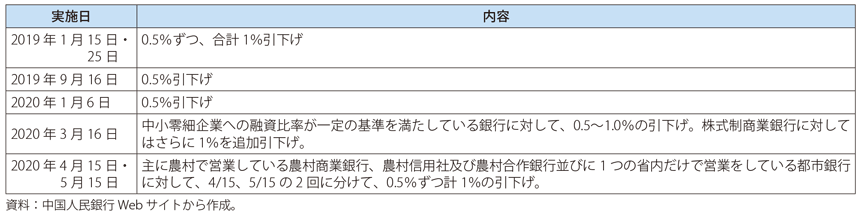
全人代では、これら預金準備率と金利引下げ等で2020年の通貨供給量と社会融資規模の伸び率を前年以上に拡大するとの方針が掲げられた。
このように全人代では、これまでの支援策の延長や一定の財政措置等が決定され、また、雇用を守っていく方針も強調された。
78 例えば、企業向け減税・社会保険料減免措置は6月末から年末まで延長。中小企業の元利払いの猶予は本年6月末から来年3月まで延長。
79 IMF資料によれば、中国政府は5月7日までに銀行システムに対して公開市場操作を通じてグロスで3.33兆元の資金供給を行っている(https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#C![]() 。2020年5月11日アクセス)。
。2020年5月11日アクセス)。
80 中国人民銀行プレス資料(2020年3月19日付け)によれば1月31日に融資枠を設置。3月13日までに中央・地方の商業銀行を介して1,821億元の融資を実行。平均金利は2.56%。50%の利子補助があるため、実際の企業負担は1.28%(国務院は必要物資生産企業への融資金利を1.6%以下に抑えることを指示)。(http://www.pbc.gov.cn/en/3688110/3688172/3991466/index.html![]() )
)
81 上記の人民銀行プレス資料によれば、3,000億元の融資枠は、対象が医療品を含む生活必需品を生産、販売、輸送する重要企業(国家発展改革委員会等がリストアップ)であるのに対して、5,000億元の再融資・再割引枠は、2,500もの地方金融機関を通じて、中小零細を含む幅広い企業や農家に対する融資や手形割引などの支援に充てることを目的としている。
82 中小零細企業への融資比率が一定の基準を満たしている銀行に対して0.5~1.0%の引下げを実施。株式制商業銀行に対してはさらに1%を追加引下げ。前者で4,000億元、後者で1,500億元、合計5,500億元の資金供給になると中国人民銀行は公表している。
83 4月3日、中国人民銀行は、主に農村で営業している農村商業銀行、農村信用社及び農村合作銀行並びに1つの省内だけで営業をしている都市銀行を対象とした預金準備率引下げを発表(なお、中国の銀行区分で「都市銀行」とは地域立脚型の銀行で日本の地銀に近い)。4月15日、5月15日の2回に分けて0.5%ずつ引き下げることで合計4,000億元の資金供給になる。同時に、4月7日から、銀行が預金準備率を超えて人民銀行に預けた場合の超過部分に係る利息の引下げ(0.72%→0.35%)を実施することも発表。これにより、銀行が人民銀行に必要以上に資金を預けるのを抑制して、資金が融資にまわりやすくする意図がある。
