

- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2020

- 白書2020(HTML版)

- 第Ⅰ部 第3章 第4節 東南アジア・南西アジア
第4節 東南アジア・南西アジア
1.東南アジア(ASEAN諸国)の経済動向
(1)GDP成長率
2019年の東南アジア(ASEAN諸国)の経済(第Ⅰ-3-4-1図、第Ⅰ-3-4-2表)は、米中貿易摩擦をめぐる世界経済の不透明感や中国経済の減速などにより、多くの国で貿易面の下押しとそれに伴う生産の減少などが見られ、2018年よりも成長のスピードが鈍化した。特に、タイやシンガポールが大きく減速した。一方、ベトナムのように米国向けの輸出を増加させたことなどで堅調に推移した国もあった。フィリピンは2019年後半、成長スピードが加速した。
第Ⅰ-3-4-1図 ASEAN各国の実質GDP成長率(原数値、前年・前年同期比)
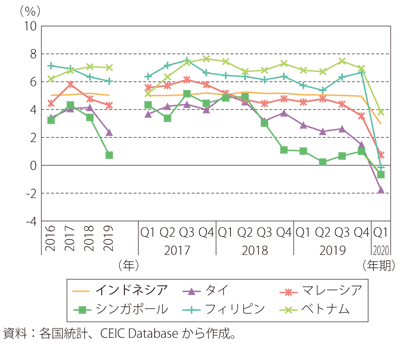
第Ⅰ-3-4-2表 ASEAN各国の実質GDP成長率(原数値、前年・前年同期比)
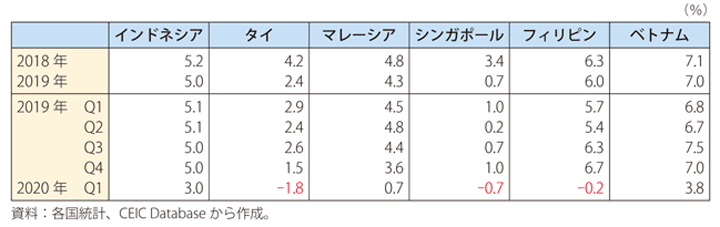
新型コロナウイルスの感染拡大の影響もあり、2020年第1四半期の各国の実質GDP成長率(原数値、前年同期比)は前期から大きく減速している。
ここでASEAN諸国のうち、インドネシア、タイ、マレーシア、シンガポール、フィリピンの実質GDP成長率について需要側、供給側の動向を概観してみよう。
<インドネシア>
インドネシアの2019年の実質GDP成長率は前年比+5.0%となり、2018年の+5.2%から減速した(第Ⅰ-3-4-3図、第Ⅰ-3-4-4図)。政府目標の+5.3%を下回った。需要側では総固定資本形成、政府消費のプラス寄与が縮小したほか、輸出、在庫変動がマイナスに転じた。供給側では製造業、鉱業等のプラス寄与が縮小した。
第Ⅰ-3-4-3図 インドネシアの実質GDP成長率(需要側)(原数値、前年・前年同期比)
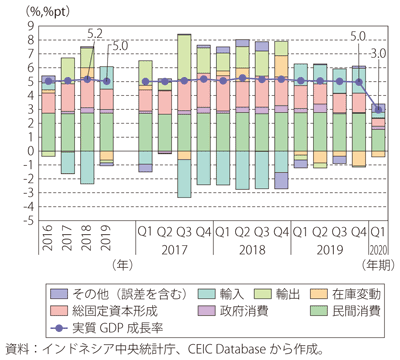
第Ⅰ-3-4-4図 インドネシアの実質GDP成長率(供給側)(原数値、前年・前年同期比)
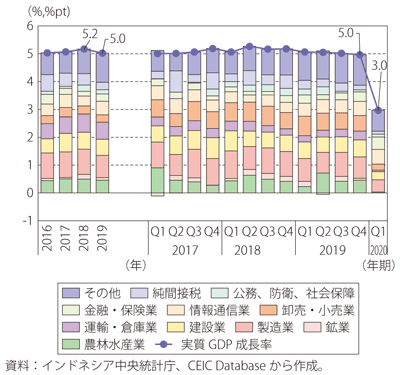
2020年第1四半期の実質GDP成長率は前年同期比+3.0%となり、前期の+5.0%から大きく減速した。需要側では特に民間消費と総固定資本形成のプラス寄与が前期から縮小した。供給側では農林水産業、卸売・小売業、製造業、建設業等のプラス寄与が前期から縮小した。
<タイ>
タイの2019年の実質GDP成長率は前年比+2.4%となり、2018年の+4.2%から大きく減速した(2014年の+1.0%以来の低い成長率)(第Ⅰ-3-4-5図、第Ⅰ-3-4-6図)。政府予測(+2.6% 2019年11月時)を下回った。輸出と在庫変動がマイナス寄与に転じたほか、民間消費や政府消費、総固定資本形成のプラス寄与が縮小した。供給側では製造業がマイナス寄与に転じた。
第Ⅰ-3-4-5図 タイの実質GDP成長率(需要側)(原数値、前年・前年同期比)
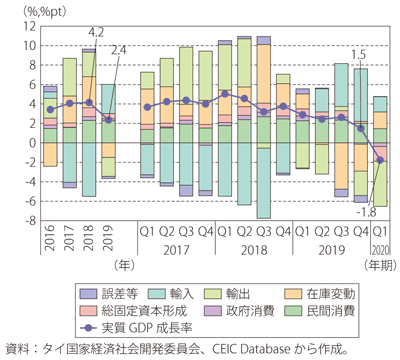
第Ⅰ-3-4-6図 タイの実質GDP成長率(供給側)(原数値、前年・前年同期比)
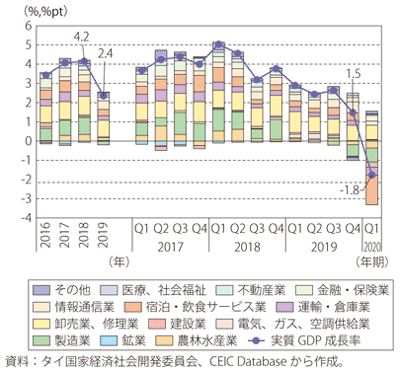
2020年第1四半期の実質GDP成長率は前年同期比-1.8%と2014年第1四半期以来、6年ぶりのマイナスとなった。需要側では、総固定資本形成がマイナス寄与に転じたほか、輸出のマイナス寄与が拡大した。供給側では、宿泊・飲食サービス業、運輸・倉庫業がマイナスに転じたほか、製造業、建設業のマイナス寄与も拡大した。
<マレーシア>
マレーシアの2019年の実質GDP成長率は前年比+4.3%となり、2018年の+4.8%から減速した(第Ⅰ-3-4-7図、第Ⅰ-3-4-8図)。需要側では輸出、総固定資本形成、在庫変動がマイナスに寄与した。供給側では鉱業が2年連続でマイナスに寄与したほか、製造業、卸売・小売業、建設業など多くの業種でプラス寄与が縮小した。
第Ⅰ-3-4-7図 マレーシアの実質GDP成長率(需要側)(原数値、前年・前年同期比)
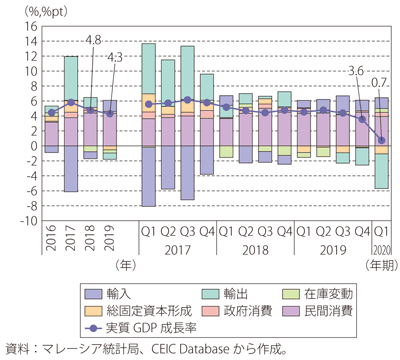
第Ⅰ-3-4-8図 マレーシアの実質GDP成長率(供給側)(原数値、前年・前年同期比)
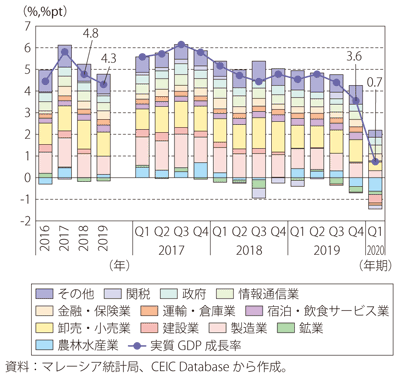
2020年第1四半期の実質GDP成長率は前年同期比+0.7%となり、前期の+3.6%から大きく減速した。特に輸出が大きくマイナスに寄与した(3期連続)ほか、総固定資本形成もマイナスに寄与した。供給側では農林水産業、建設業、鉱業などがマイナスに寄与したほか、卸売・小売業、製造業など多くの業種でプラス寄与が縮小した。
<シンガポール>
シンガポールの2019年の実質GDP成長率は前年比+0.7%となり、2018年の+3.4%から減速した(第Ⅰ-3-4-9図、第Ⅰ-3-4-10図)。需要側では輸出が、供給側では製造業、卸・小売業がマイナスに寄与した。
第Ⅰ-3-4-9図 シンガポールの実質GDP成長率(需要側)(原数値、前年・前年同期比)
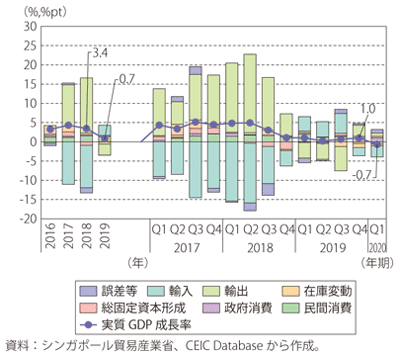
第Ⅰ-3-4-10図 シンガポールの実質GDP成長率(供給側)(原数値、前年・前年同期比)
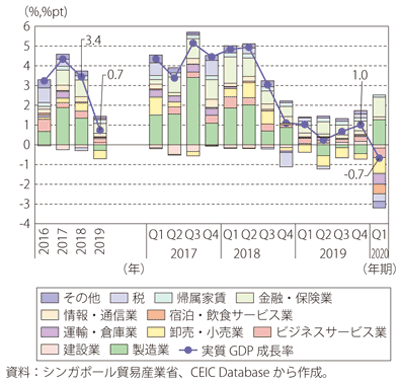
2020年第1四半期の実質GDP成長率は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、前年同期比-0.7%となった。需要側では民間消費、在庫変動が、供給側では卸売・小売業 運輸・倉庫業、宿泊・飲食サービス業等がマイナスに寄与した。
<フィリピン>
フィリピンの2019年の実質GDP成長率は前年比+6.0%となり、2018年の+6.3%から減速した(第Ⅰ-3-4-11図、第Ⅰ-3-4-12図)。需要側では輸出、総固定資本形成、政府消費のプラス寄与が縮小した。供給側では製造業、建設業などのプラス寄与が縮小した。
第Ⅰ-3-4-11図 フィリピンの実質GDP成長率(需要側)(原数値、前年・前年同期比)
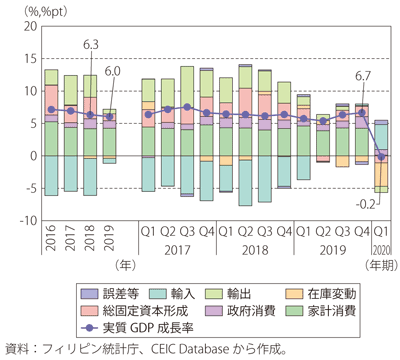
第Ⅰ-3-4-12図 フィリピンの実質GDP成長率(供給側)(原数値、前年・前年同期比)
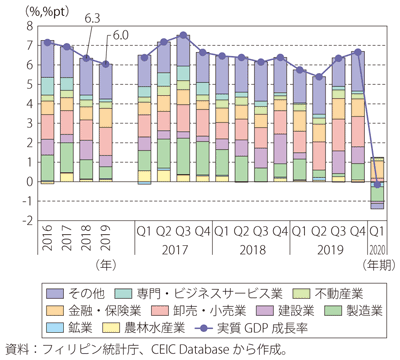
2020年第1四半期の実質GDP成長率は、前年同期比-0.2%と1998年第4四半期以来、22年ぶりのマイナスとなった84。需要側では総固定資本形成と輸出が前期のプラス寄与からマイナス寄与に転じたほか、在庫変動のマイナス寄与が拡大した。供給側では製造業、建設業がマイナス寄与に転じたほか、卸売・小売業のプラス寄与が大きく縮小した。
84 実質GDP統計は2020年4月から新基準(2018年価格)に移行しており、2000年まで遡及可能。1999年以前は旧基準のため数値の単純比較はできない。
(2)貿易(財輸出)
2019年のASEAN各国の財輸出(第Ⅰ-3-4-13図)は、インドネシア、タイ、シンガポール、マレーシアがすべての四半期85において前年比マイナスで推移するなど弱含んだ。2019年の年ベースでは特にシンガポールのマイナス幅が大きかった。ベトナムは他の諸国に比べると年間を通じて勢いがあったが、2019年第4四半期はやや減速した。フィリピンは2019年第2四半期以降、前年同期比プラスで推移し、第4四半期に拡大スピードが増した。2020年第1四半期はインドネシア、タイ、シンガポールが、プラスに転じている。
第Ⅰ-3-4-13図 ASEAN各国の財輸出(原数値・前年比・前年同期比)
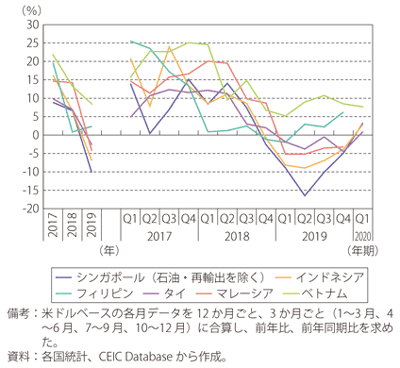
85 1-3月、4-6月、7-9月、10-12月の3か月ごとに輸出額(米ドルベース)を合算し、四半期の値とした。
<シンガポール>
2019年のシンガポールの輸出(石油と再輸出を除いた米ドルベース)を主要仕向先別に四半期ごとの動きでみると(第Ⅰ-3-4-14図)、日本、香港、ASEAN(インドネシア、タイ、マレーシアの合計)向けは年間を通じてすべての期で前年比マイナスに寄与した。中国向けは、第1、2四半期はマイナスに寄与したものの、第3、4四半期はプラスに寄与した。品目グループ別の寄与度(第Ⅰ-3-4-15図)をみると、非エレクトロニクス部門は医薬品や石油化学品の落ち込みもあり第1~第3四半期はマイナスに寄与86、エレクトロニクス部門はグローバルなエレクトロニクスの循環下降局面(ダウンサイクル)ともあいまって87、IC(集積回路)などの輸出が大きく落ち込み(第Ⅰ-3-4-16図)、すべての四半期においてマイナスに寄与した。
第Ⅰ-3-4-14図 シンガポールの輸出(米ドルベース・石油・再輸出を除く。原数値、前年同期比)における仕向先別寄与度

第Ⅰ-3-4-15図 シンガポールの輸出(米ドルベース・石油・再輸出を除く。原数値、前年同期比)における品目グループ別寄与度
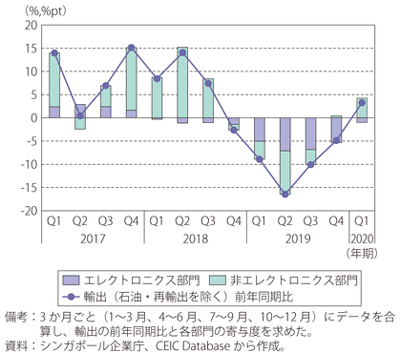
第Ⅰ-3-4-16図 シンガポールの輸出(集積回路、医薬品、石油化学製品の前年同期比)(米ドルベース)
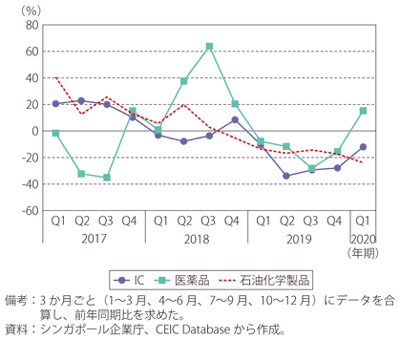
2020年第1四半期の輸出(前年同期比)は6期ぶりのプラスとなった。ASEAN(インドネシア、タイ、マレーシアの合計)や中国、香港向けはマイナスに寄与したが、日本、韓国、台湾、米国向けはプラスに寄与した。品目グループ別ではエレクトロニクス部門が引き続きマイナスに寄与したが、非エレクトロニクス部門がプラスに寄与した。非エレクトロニクス部門のうち、石油化学製品が引き続き前年割れとなっているのに対し、医薬品はプラスに転じている。
86 米ドルベース。なお、シンガポールドルベースでは第4四半期もマイナスである。
87 シンガポール企業庁「Review of 2019 Trade Performance」(2020年2月)(https://www.enterprisesg.gov.sg/-/media/esg/files/media-centre/media-releases/2020/feb-2020/review-of-2019-trade-performance.pdf?la=en![]() )
)
<ベトナム>
2019年のベトナムの輸出は年間を通じて米国向けが大きくプラスに寄与した(第Ⅰ-3-4-17図)。米国向け輸出は前年比約30%の増加となっており、特に「電話、携帯電話、部品」や、「コンピュータ、電気製品、部品」などの品目グループが大きくプラスに寄与した(第Ⅰ-3-4-18図)。輸出全体を品目グループ別にみると(第Ⅰ-3-4-19図)、「コンピュータ、電気製品、部品」が年間を通じて大きくプラスに寄与した。「電話、携帯電話、部品」は特に第2、第3四半期に大きくプラスに寄与した。
第Ⅰ-3-4-17図 ベトナムの輸出(原数値、前年同期比)における仕向先別寄与度
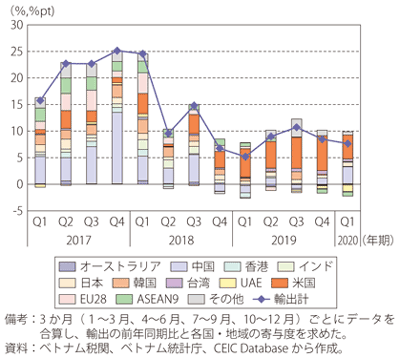
第Ⅰ-3-4-18図 2019年のベトナムの米国向け輸出増加品目グループ(寄与度順)
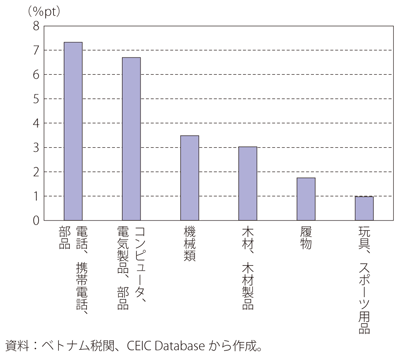
第Ⅰ-3-4-19図 ベトナムの輸出(原数値、前年同期比)における品目グループ別寄与度
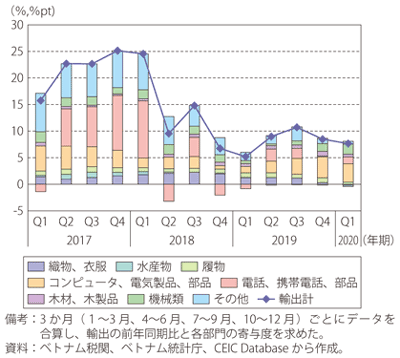
2020年第1四半期も前年同期比プラスとなった。輸出先としては中国向け、米国向けの寄与が大きい。品目グループ別では「コンピュータ、電気製品、部品」、「電話、携帯電話、部品」の寄与が大きい。
(3)対内直接投資
ASEAN各国における対内直接投資の前年比の推移(第Ⅰ-3-4-20図)をみると、2019年は特にフィリピンの伸びが大きかった。タイ、ベトナム、マレーシアも前年比プラスとなった。
第Ⅰ-3-4-20図 ASEAN各国の対内直接投資(前年比)
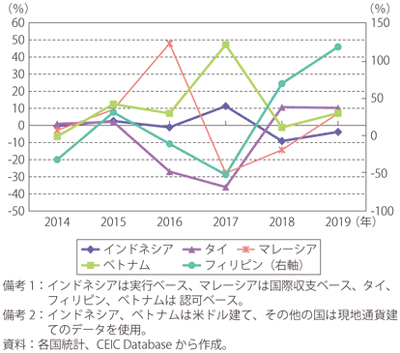
<フィリピン>
フィリピンの対内直接投資の国・地域別内訳(第Ⅰ-3-4-21図)をみると、2019年は特にシンガポールからの投資規模が大きかった(全体の約45%)。中国、韓国からの投資規模はそれぞれ全体の約23%、約11%を占めた。
第Ⅰ-3-4-21図 フィリピンの対内直接投資(国別内訳)の推移
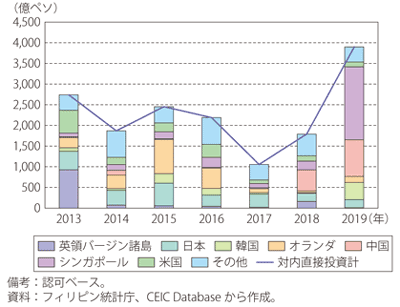
<タイ>
タイの対内直接投資(第Ⅰ-3-4-22図)においては日本からの投資規模が大きい。2018年、2019年はそれぞれ全体の約37%、約31%となっている。ただし、2010年代前半、例えば2013年には全体の約61%を占めていたのに比べるとシェアの面では半減している。2019年は中国が全体の約26%となっており、2018年の約13%から大きくシェアを伸ばしている。
第Ⅰ-3-4-22図 タイの対内直接投資(国別内訳)の推移
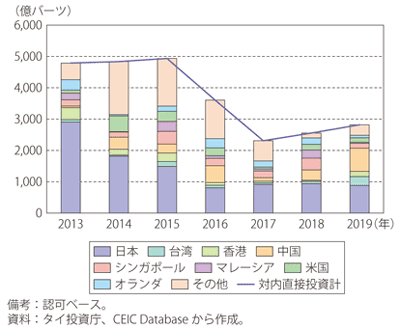
<ベトナム>
ベトナムの対内直接投資(第Ⅰ-3-4-23図)においては、韓国の投資規模が大きい。同図で示した範囲(2013年から2019年)の平均でみても、対内直接投資全体の約25%を占めている。日本の投資規模は2017年、2018年に全体の約25%を占めたが、2019年は約11%に留まった。中国、香港も近年、ベトナム向け投資を活発化させている。2019年は香港と中国を合わせて前年比+110%となり、全体に占める比率も約31%となった。
第Ⅰ-3-4-23図 ベトナムの対内直接投資(国別内訳)の推移
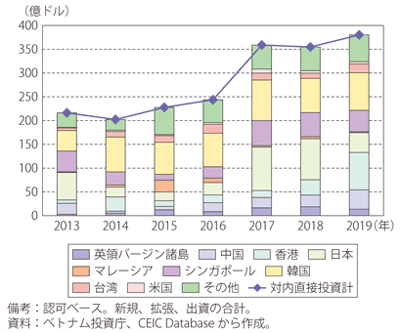
(4)鉱工業生産
ASEAN諸国の2019年の鉱工業生産指数(原数値・前年同月比)は、特にタイやフィリピンは、ほぼ年間を通じてマイナスで推移するなど弱含んだ(第Ⅰ-3-4-24図)。2020年に入り、タイは自動車などが引き続き弱い動きを示しており(第Ⅰ-3-4-25図)、フィリピンはマイナス圏から脱したものの、石油製品などが弱含んでいる(第Ⅰ-3-4-26図)。2020年3月のシンガポールは大幅にプラスとなった。特に医薬品の伸びが大きかった(第Ⅰ-3-4-27図)。
第Ⅰ-3-4-24図 ASEAN各国の鉱工業生産指数(原数値・前年同月比)
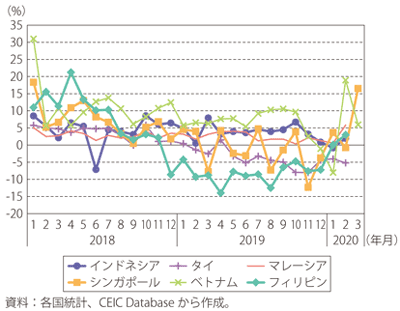
第Ⅰ-3-4-25図 タイのセクター別鉱工業生産指数(原数値・前年同月比)
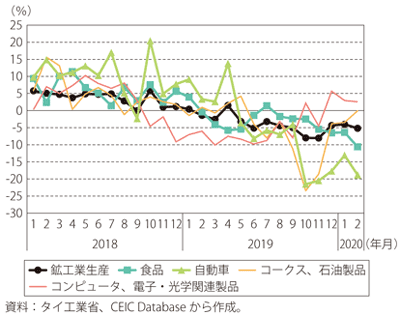
第Ⅰ-3-4-26図 フィリピンのセクター別鉱工業生産指数(原数値・前年同月比)
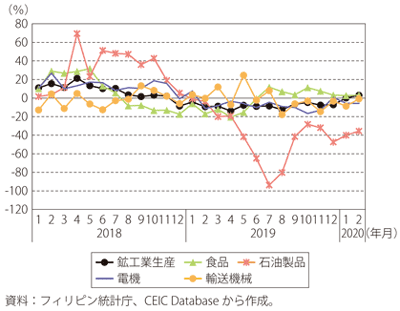
第Ⅰ-3-4-27図 シンガポールのセクター別鉱工業生産指数(原数値・前年同月比)
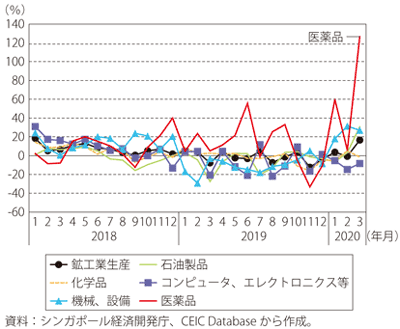
(5)消費者物価
ASEAN諸国の消費者物価上昇率(原指数・前年同月比)は、2019年を通じて、おおむね各国の物価目標88の上限を超えずに推移した(第Ⅰ-3-4-28図)。フィリピンは2018年に物品税の増税などにより急速に物価が上昇したが、2018年秋以降は物価上昇圧力が抑制され、2019年8月にはフィリピン中銀の物価目標の下限である+2%を下回った。その後、2020年初にかけて再び上昇基調に転じたが、物価目標の範囲内で推移している。ベトナムでは食料品価格の上昇を背景に2019年秋から物価が急速に上昇し、消費者物価上昇率は同年12月に+5.2%と物価目標の+4%を超え、2020年1月には+6.4%となった。その後、物価上昇スピードは鈍化し、足下(2020年3月)では+4.9%となっている(第Ⅰ-3-4-29図)。タイやマレーシア、シンガポールは、足下(同)、マイナスに転じており、マイナス幅が相対的に大きいタイ(-0.5%)では、運輸・通信部門が大きくマイナスに寄与している(第Ⅰ-3-4-30図)。
第Ⅰ-3-4-28図 ASEAN各国の消費者物価上昇率(原指数・前年同月比)
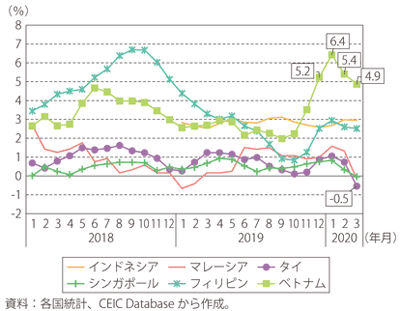
第Ⅰ-3-4-29図 ベトナムの消費者物価上昇率における内訳項目別寄与度
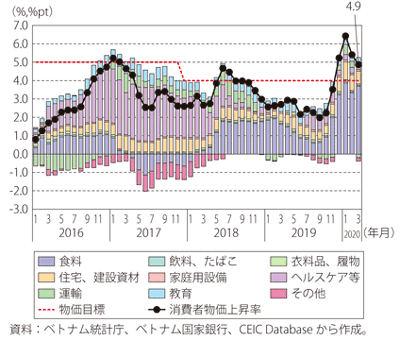
第Ⅰ-3-4-30図 タイの消費者物価上昇率における内訳項目別寄与度
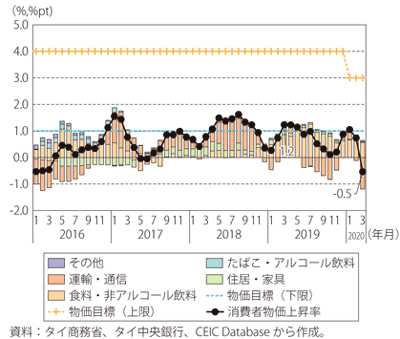
88 インドネシア(2019年は3.5±1%、2020年は3±1%。インドネシア中銀ウエブサイト(https://www.bi.go.id/en/moneter/inflasi/bi-dan-inflasi/Contents/Penetapan.aspx![]() ))、フィリピン(3±1%。フィリピン中銀ウエブサイト(http://www.bsp.gov.ph/monetary/targeting_inflation.asp#:~:text=In%20line%20with%20the%20inflation,percentage%20point%20for%202020%20%E2%80%93%202022.
))、フィリピン(3±1%。フィリピン中銀ウエブサイト(http://www.bsp.gov.ph/monetary/targeting_inflation.asp#:~:text=In%20line%20with%20the%20inflation,percentage%20point%20for%202020%20%E2%80%93%202022.![]() ))、タイ(2019年は2.5±1.5%、2020年は1~3%。タイ中銀ウエブサイト(https://www.bot.or.th/English/MonetaryPolicy/MonetPolicyKnowledge/Pages/Target.aspx
))、タイ(2019年は2.5±1.5%、2020年は1~3%。タイ中銀ウエブサイト(https://www.bot.or.th/English/MonetaryPolicy/MonetPolicyKnowledge/Pages/Target.aspx![]() ))、ベトナム(2019年は約4%、2020年は4%未満。グエン・ラン(2019)「2020年のGDP成長率目標を6.8%に、政府が社会・経済発展計画(ベトナム)」ジェトロ・ビジネス短信(2019年12月9日)(https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/12/4eba0ba7c8e05783.html
))、ベトナム(2019年は約4%、2020年は4%未満。グエン・ラン(2019)「2020年のGDP成長率目標を6.8%に、政府が社会・経済発展計画(ベトナム)」ジェトロ・ビジネス短信(2019年12月9日)(https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/12/4eba0ba7c8e05783.html![]() )、ベトナム政府ウエブサイト(http://news.chinhphu.vn/Home/NA-passes-resolution-on-socioeconomic-development-for-2020/201911/37997.vgp
)、ベトナム政府ウエブサイト(http://news.chinhphu.vn/Home/NA-passes-resolution-on-socioeconomic-development-for-2020/201911/37997.vgp![]() )。
)。
(6)政策金利
米中貿易摩擦の影響などにより、2019年のASEAN各国の経済は前年に比べ減速した。各国の中央銀行は景気下支えのため、政策金利の引下げを相次いで行った(第Ⅰ-3-4-31図)。マレーシア中央銀行(以下、中銀。他の各国についても便宜上「中銀」を用いる)が2019年5月に政策金利を25bp89引下げたほか、インドネシア中銀が7月、8月、9月、10月にそれぞれ25bp、タイ中銀が8月と11月にそれぞれ25bp、フィリピン中銀が5月、8月、9月にそれぞれ25bp、ベトナム中銀が9月に25bpの利下げを行った。シンガポール中銀(金融管理局)は為替管理を通じた金融政策を行っているが、10月にシンガポールドルの名目実効レートの政策バンドの傾き(上昇率)をやや緩やかにするとし、3年ぶりに金融緩和に転じた。
第Ⅰ-3-4-31図 ASEAN各国の政策金利
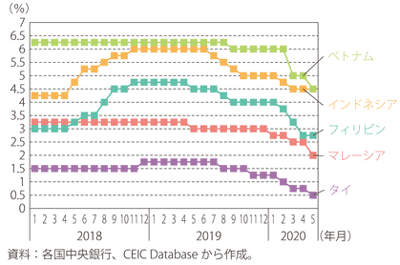
2020年に入ってからは、新型コロナウイルスの感染拡大の影響が強く懸念されたことから、各国中銀は、連続して、あるいは予想を上回る下げ幅で利下げを行っている90。マレーシアでは1月、3月にそれぞれ25bp、5月に50bp、タイ中銀が2月、3月、5月にそれぞれ25bp、フィリピン中銀が2月に25bp、3月、4月にそれぞれ50bp、インドネシア中銀が2月、3月にそれぞれ25bp、ベトナム中銀が3月に100bp、5月に50bpの政策金利引下げを決定している。シンガポール金融管理局は3月にシンガポールドルの名目実効レートの政策バンドの傾きを年率0%とすることを決定し、昨年10月の決定(「傾きをやや緩やかにする」)から更に緩和的な姿勢を強めている91。
89 bpはベーシスポイント。1bp=0.01%。
90 2020年5月20日現在。
91 シンガポールの金融政策は政策金利の上げ下げではなく為替管理(シンガポールドルの名目実効為替レート(S$NEER)の政策バンドの①傾き(slope。上昇は引締め、低下は緩和に相当)、②幅、③中心レートの設定)を通じて行われる。
(7)今後の見通し
新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、ASEAN諸国の経済は大きく下押しされることが必至であり、各国政府は2020年の経済成長について当初目標(見通し)の見直しを余儀なくされている。例えば、インドネシアは当初目標の+5.3%を+2.3%に92、タイは+2.7~+3.7%を-6.0~-5.0%に93、シンガポールは+0.5~+2.5%を-7.0~-4.0%に94、フィリピンは+6.5~+7.5%を-3.4~-2.0%に95下方修正している。マレーシアは+4.8%との目標を立てているが、4月にマレーシア中銀が-2.0 ~+0.5%との見通しを示している96。
サプライチェーンの途絶や生産活動そのものの制限による製造業への影響はもちろん、人の移動や各種活動の制限によりサービス業も大きな打撃を受けるだろう。特に経済における観光セクターの比率が高いタイなどは注意が必要である(第Ⅰ-3-4-32表)。
第Ⅰ-3-4-32表 アジア各国・地域の国際観光収入対名目GDP比(2018年・米ドルベース)
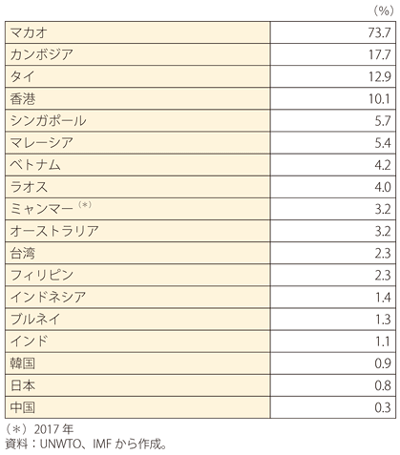
2020年4月のIMF世界経済見通しのデータを用いて、過去の金融危機時(アジア通貨危機後:1998年、世界金融危機後:2009年)と2020年のアジア各国の実質GDP成長率(見通し)を比較したものが第Ⅰ-3-4-33図である。タイはアジア通貨危機後に匹敵する下落幅を見込む。シンガポールは過去の金融危機時よりも2020年の下落幅が大きくなり、ベトナムは2020年もプラス成長を維持するが、2%台と過去と比べて大幅に低い成長率にとどまる見通しである。2020年単年では、タイの下落幅がアジア諸国の中でも特に大きい。
第Ⅰ-3-4-33図 アジア各国の経済成長率 過去の金融危機時と2020年見通しの比較
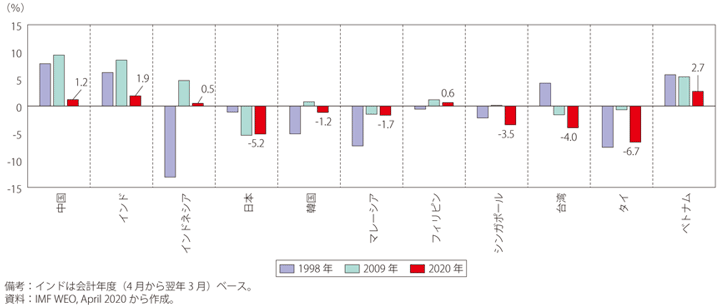
92 インドネシア政府ウエブサイト(https://setkab.go.id/en/sri-mulyani-indonesias-baseline-significantly-changes-following-covid-19-pandemic/![]() )
)
93 2020年2月と5月に下方修正している。タイ政府ウエブサイト(https://www.nesdc.go.th/nesdb_en/ewt_news.php?nid=4425&filename=index![]() )、(https://www.nesdc.go.th/nesdb_en/ewt_news.php?nid=4418&filename=index
)、(https://www.nesdc.go.th/nesdb_en/ewt_news.php?nid=4418&filename=index![]() )
)
94 2020年2月、3月、5月に下方修正している。シンガポール政府ウエブサイト(https://www.mti.gov.sg/Newsroom/Press-Releases/2020/03/Singapore-GDP-Contracted-by-2_2-Per-Cent-in-the-First-Quarter-of-2020![]() )、(https://www.mti.gov.sg/Newsroom/Press-Releases/2020/02/MTI-Downgrades-2020-GDP-Growth-Forecast-to--0_5-to-1_5-Per-Cent
)、(https://www.mti.gov.sg/Newsroom/Press-Releases/2020/02/MTI-Downgrades-2020-GDP-Growth-Forecast-to--0_5-to-1_5-Per-Cent![]() )、(https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/news/gdp1q2020.pdf
)、(https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/news/gdp1q2020.pdf![]() )
)
95 フィリピン政府ウエブサイト(http://www.neda.gov.ph/dbcc-revisits-medium-term-macroeconomic-assumptions-and-fiscal-program-amid-the-covid-19-pandemic/![]() )
)
96 マレーシア中銀ウエブサイト(https://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_press&pg=en_press&ac=5028&lang=en![]() )
)
2.南西アジア(インド)の経済動向
(1)実質GDP成長率
インドの2019年度(2019年4月~2020年3月)の実質GDP成長率は、前年度比+4.2%と前年度の+6.1%から減速した(第Ⅰ-3-4-34図)。輸出と総固定資本形成がマイナスに転じた。民間消費の寄与も縮小した。供給側の実質GVA成長率97は、+3.9%となった(第Ⅰ-3-4-35図)。サービス業、製造業のプラス寄与が縮小した。
第Ⅰ-3-4-34図 インドの実質GDP成長率と項目別寄与度(需要側)
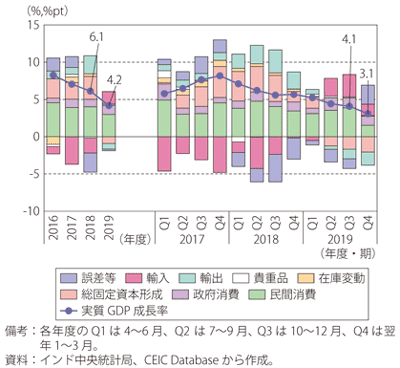
第Ⅰ-3-4-35図 インドの実質GVA成長率と項目別寄与度(供給側)
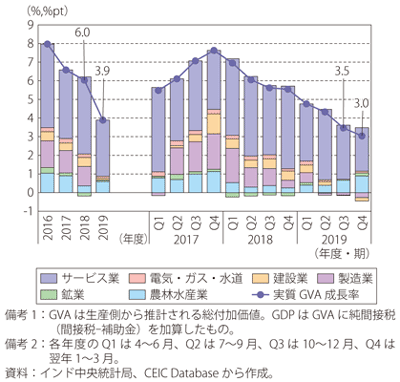
2019年度第4四半期(2020年1-3月期)の実質GDP成長率は、前年同期比+3.1%と前期の+4.1%から減速した。輸出と総固定資本形成が3期連続でマイナスに寄与した。民間消費のプラス寄与も大幅に縮小した。供給側の実質GVA成長率は、前年同期比+3.0%と前期の+3.5%から減速した。製造業、建設業がマイナスに寄与した。
97 GVA(Gross Value Added)は、生産側から推計される総付加価値。GDPはGVAに純間接税(間接税から補助金を引いたもの)を加算したもの。
(2)鉱工業生産
インドの鉱工業生産指数と内訳である製造業生産指数は2019年8月から10月にかけて弱含んだ後、同年11月以降は持ち直してきたが、2020年3月、それぞれ原指数・前年同月比-16.7%、-20.6%と大幅なマイナスとなった(第Ⅰ-3-4-36図、第Ⅰ-3-4-37図)。生産品目別では、前年同月比プラスが続いてきた金属がマイナスに転じた。自動車、トレーラー等は2018年11月以降、マイナスが続いている。
第Ⅰ-3-4-36図 インドの鉱工業生産指数前年同月比と業種別寄与度
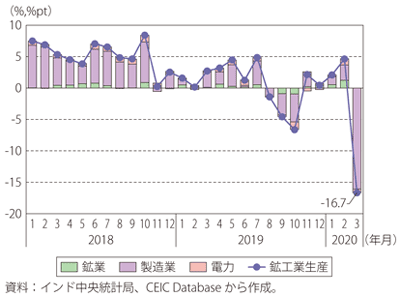
第Ⅰ-3-4-37図 インドの製造業生産指数前年同月比と業種別寄与度
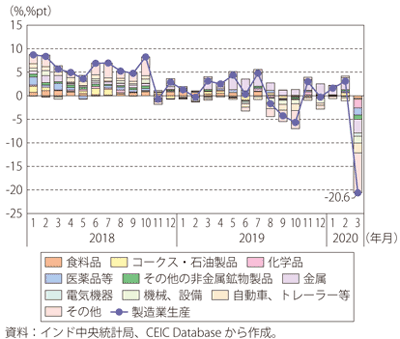
(3)自動車セクターの動向
2018年末頃から、インドの自動車セクターは弱含んでおり、国内新車販売台数は前年割れの状況が続いている(第Ⅰ-3-4-38図)。自動車セクター不振の背景としては、大手ノンバンクのデフォルト(2018年)を発端とする金融環境の悪化、自賠責保険の加入期間の延長(2018年9月)、同保険料の引上げ(2019年6月)、排ガス規制の強化(2020年4月)を見据えての買い控えなどが指摘されている98。2019年末には販売台数の前年同月比の落ち込み幅が縮小したが、足下(2020年3月)は新型コロナウイルス感染拡大にともなうロックダウンの影響もあり、大幅なマイナスとなっている。
第Ⅰ-3-4-38図 インドの国内新車販売台数と前年同月比
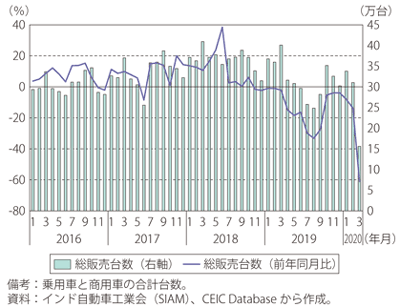
98 熊谷(2019)。
(4)消費者物価
インドの消費者物価指数(原指数)前年同月比(第Ⅰ-3-4-39図)は2019年秋頃から急速に上昇し、2019年12月、2020年1月は、インド準備銀行の物価目標(4±2%)の上限を超え、7%台となった。天候不順によるタマネギなど農産品の不作により食品価格が上昇したことなどが背景にある。2020年3月は物価目標の上限を割り込み、+5.9%となり、物価上昇スピードに一服感が出ている。
第Ⅰ-3-4-39図 インドの消費者物価上昇率(原指数・前年同月比)における内訳項目別寄与度
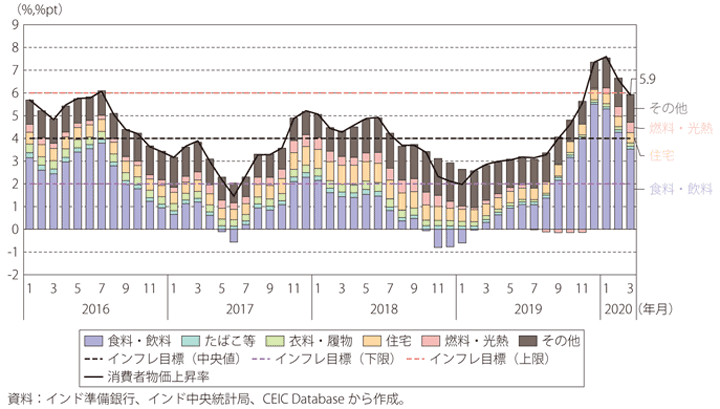
(5)政策金利
2019年のインド経済全般が力強さを欠いて推移したことから、インド準備銀行は2019年内に5回、合計で135bpの政策金利引下げを行った。2019年12月、2020年2月の会合では、急速に上昇するインフレ率を意識して政策金利を据え置いたが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による経済の下押しを警戒し、同銀は2020年3月に75bp、5月に40bpの利下げを行い、政策金利を4.0%とした(第Ⅰ-3-4-40図)。
第Ⅰ-3-4-40図 インドの政策金利の推移
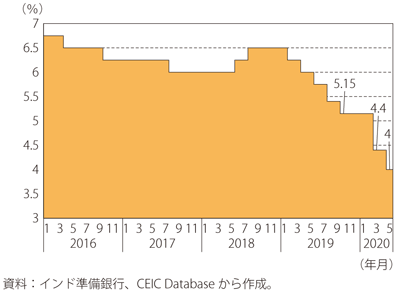
(6)経常収支
インドの経常収支(第Ⅰ-3-4-41図)は赤字が続いている。内訳では財収支の赤字額が大きい。サービス収支は黒字で、このうち9割以上がコンピュータサービスによるものである。
第Ⅰ-3-4-41図 インドの経常収支
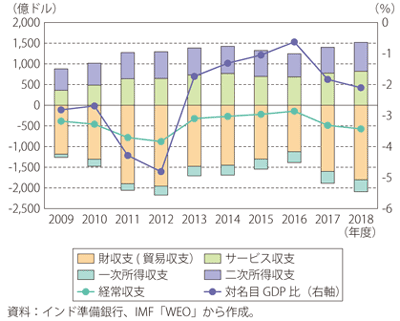
<貿易収支>
インドの貿易収支を相手国別にみると(第Ⅰ-3-4-42図)、2019年のインドの貿易赤字については、対中国を筆頭に金額の大きい順にサウジアラビア、イラク、スイスが続く。一方、貿易黒字については、対米国を筆頭に金額の大きい順にバングラデシュ、ネパール、オランダが続く。
第Ⅰ-3-4-42図 相手国別にみたインドの貿易収支(2019年)
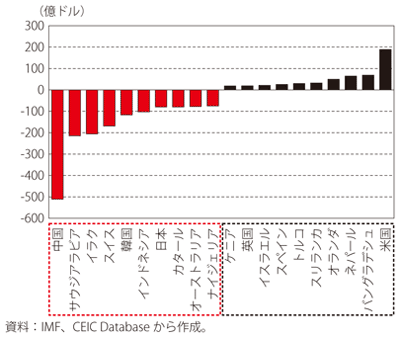
対米国、対中国の貿易収支のこれまでの推移(第Ⅰ-3-4-43図)をみると、対中赤字は2000年代後半以降、対米黒字は2010年代に急速に拡大している。2019年は対中赤字幅が前年から縮小した。
第Ⅰ-3-4-43図 相手国別にみたインドの貿易収支の推移
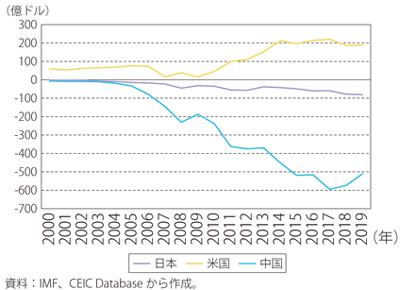
(7)対内直接投資
インドの対内直接投資は、2014年から2016年にかけて急速に拡大した。2017年、2018年には一服したが、2019年には再び拡大している(第Ⅰ-3-4-44図、第Ⅰ-3-4-45図)。
第Ⅰ-3-4-44図 インドの対内直接投資(国別)の推移
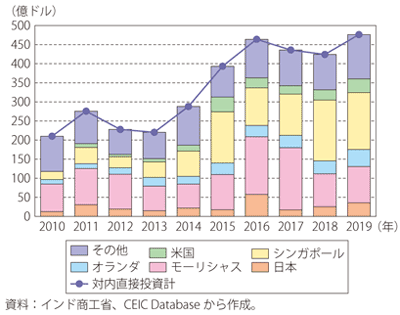
第Ⅰ-3-4-45図 インドの対内直接投資(業種別)の推移
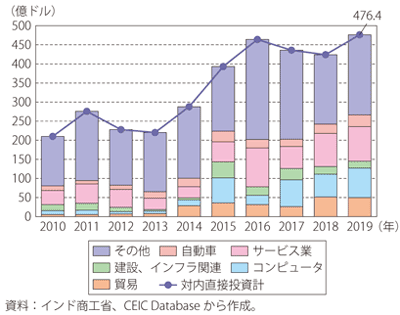
2019年における国別内訳は、シンガポールが全体の約31%、モーリシャスが約20%、オランダが約9%、米国、日本がそれぞれ約8%を占めた。
2019年における業種別内訳は、サービス業が約19%、コンピュータが約16%、貿易が約10%、自動車が約6%、建設、インフラ関連が約4%を占めた。
(8)今後の展望
2019年春に行われた連邦議会下院選挙で、モディ首相率いるインド人民党(BJP)が勝利した。同党の選挙公約99のうち経済面の目標についてみると、インドのGDPを2025年までに5兆ドル、2032年までに10兆ドルに引上げ、2030年までに世界3位の経済大国になることを目指すとしている。そのためには人口の約65%100が居住している農村の生活水準を向上させる必要があるが、公約では、2022年までに農民所得を倍増することが掲げられた。また、投資が牽引する経済を実現すべく、2024年までに100兆ルピーのインフラ投資を行うとしている。産業政策としては、投資環境のさらなる向上101を通じた対内直接投資の拡大、インダストリー4.0の実現に不可欠なAI(人工知能)や電動化といった新しい技術を意識した製造業、サービス産業の競争力強化などが盛り込まれている。
モディ政権2期目がスタートし、これらの政策の推進が期待されているところであるが、最近のインド経済は弱含んで推移しており、改革の取組を加速させることは容易ではないようである。2019年は天候不順による農産物の不作とそれに伴う農産品価格の急上昇(秋以降)に直面したほか、銀行セクターの不良債権問題やノンバンク業界の信用不安を背景とする金融環境の悪化などが消費や設備投資を下押しした。2020年に入ってから足下までは、新型コロナウイルスの感染拡大の影響が深刻化している。インド政府は3月25日から、国内全土をロックダウンとするなどの措置を講じてきたが、多くの失業者を生むなど、弊害が生じている。政府による貧困層向けの穀物類の現物配布や現金給付、低賃金労働者への賃金補助、税の減免などの経済対策パッケージやインド準備銀行による政策金利の大幅な引下げ(前述)、流動性供給や元利支払いの猶予などを内容とする各種支援策が発表されている。インド政府はロックダウンを延長する一方で、4月20日から感染拡大中心地(ホットスポット)以外の地域で制限措置の一部緩和を認めている。感染の封じ込めと経済の下支えの双方を見据えた難しい舵取りを迫られているといえよう。仮に感染拡大の勢いが止まらず、再開された経済活動が再び停止を余儀なくされる場合には、国内経済は一層強く下押しされることになる。追加の財政措置を講ずるとしても、インドの財政収支は赤字が続いていることから、財政規律とのバランスも無視できない(第Ⅰ-3-4-46図)。
第Ⅰ-3-4-46図 インドの政府予算(歳出)と財政赤字対GDP比の推移
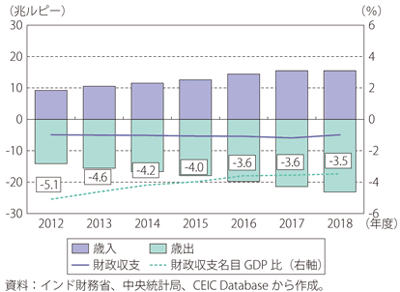
インド政府は2020年1月末時点で2020年度(2020年4月~2021年3月)のGDP成長率見通しを+6.0~+6.5 %とした102が、新型コロナウイルス感染拡大の影響のほか、銀行セクターの不良債権問題(第Ⅰ-3-4-47図)など従来からの懸案、課題も残る。IMFによれば、2020年のインドのGDP成長率は+1.9%にとどまる見通しである103。マクロ経済の動向と合わせて、通貨や株価の急速な下落など、国際金融市場の変動リスクにも注意する必要がある。
第Ⅰ-3-4-47図 インドの銀行セクターにおける不良債権比率
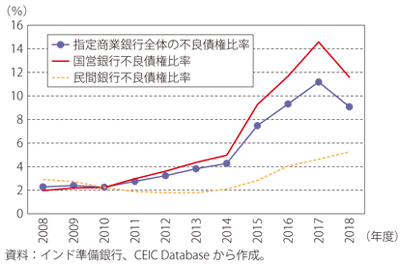
99 インド人民党2019年選挙マニフェスト(https://www.bjp.org/en/manifesto2019![]() )より。
)より。
100 国連「World Urbanization Prospects(The 2018 Revision)」のインドの都市人口比率(2020年の推計)から求めた。
101 世界銀行「Ease of Doing Business Index.」の50位以内ランクインを目指すとしている。
102 インド政府ウエブサイト(https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1601270![]() )。なお、インド準備銀行は2020年度のGDP成長率見通しを+5.5%としている(2020年4月)(https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=19439#12
)。なお、インド準備銀行は2020年度のGDP成長率見通しを+5.5%としている(2020年4月)(https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=19439#12![]() )。
)。
103 IMF「WEO」April 2020
