

- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2020

- 白書2020(HTML版)

- 第Ⅰ部 第3章 第6節 ロシア
第6節 ロシア
本節では、2019年のロシア経済を概観する。2019年のロシア経済は、世界経済の減速や資源価格の低迷等により、低成長となった。2020年に入ると、世界的に新型コロナウイルス感染拡大が広がり感染者が増加したため124、ロシアにおいても、外出や経済活動が制限された。こうした動向を踏まえ、主要経済指標を分析し、ロシア経済の抱える課題についてもみていく。
124 ロシアの感染者数は、35万人3,000人超と米国、ブラジルに次ぐ規模となった(2020年5月25日時点)。ロシアでは、3月下旬から5月11日まで、全国一斉の休業措置が行われ、薬局や食料品店などを除くほとんどの店舗や企業が休業となった。5月12日以降は、感染状況に応じて各地方の首長が制限の緩和などを決定する。
1.マクロ経済動向
(1)GDP
2019年の実質GDP成長率は、前年比+1.3%と前年の+2.5%から減速し、3年ぶりの低成長となった(第Ⅰ-3-6-1図)。前年から成長率を押し下げた主な要因は、輸出の減少である。主力輸出品目である原油の価格が、2018年に比べ下落したことが影響した。さらに、輸入が増加したことにより純輸出は-1.4%の寄与度となった。
第Ⅰ-3-6-1図 ロシアの実質GDP成長率及び需要項目別寄与度の推移
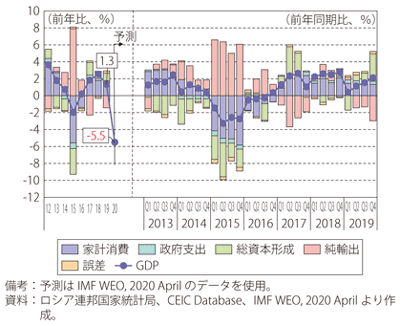
GDPの約5割を占める家計消費の伸びは前年から低下したが、他の項目に比べ最も大きくプラスに寄与した。
次に、業種別に見てみると、幅広い業種で前年より伸びが低下したことが分かる。着目すべきは、第三次産業の伸びが大きく低下したことである(+2.8%→+1.7%)。特に、宿泊・外食産業の落ち込みが目立った(+4.7%→+2.2%)。2018年はサッカーW杯がロシアで開催され、建設業や宿泊・外食産業が大きく伸びた反動もあり、今年は低下したとみられる(第Ⅰ-3-6-2表)。
第Ⅰ-3-6-2表 ロシアの業種別GDP伸び率
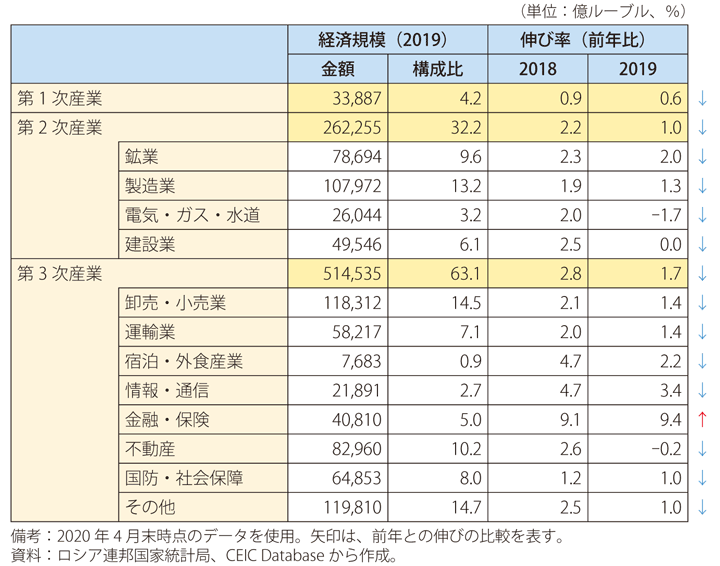
(2)為替
ロシアは世界有数の資源国であることから、ルーブル相場は原油価格に大きく左右される。ウクライナ危機125に端を発した欧米からの経済制裁や世界的な原油安を受けて2014年後半以降、ルーブルは大幅に下落した。2016年に入り、原油価格の持ち直しと共に、ルーブルも増価してきた。(第Ⅰ-3-6-3図)。しかし、2018年に入り油価が上昇する中で、初めてルーブルが減価した126。特に、米国による追加の経済制裁が実施された4月と8月にルーブルは大きく下落した。米国による制裁が緩和されたことや、原油価格も上昇したことで2019年に入り、ルーブルは持ち直した。
第Ⅰ-3-6-3図 ロシアの為替レートとWTI原油価格の推移
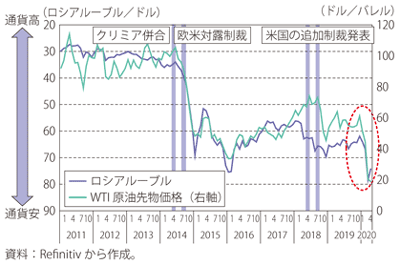
年初来の通貨の騰落率をみると、ルーブルは約2割の通貨安となっている。新型コロナウイルス感染拡大による世界経済の減速懸念に加え、原油価格が史上初めてマイナスを記録するなど原油価格の大幅な下落が影響したとみられる(第Ⅰ-3-6-4図)。
第Ⅰ-3-6-4図 新興国通貨の年初来騰落率(2020年4月30日時点)
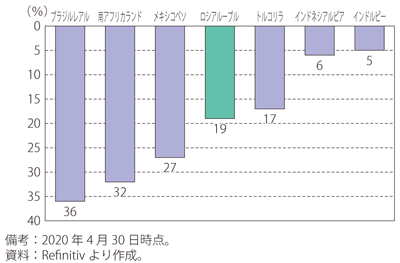
125 2013年11月、ヤヌコーヴィチ政権がEUとの連合協定の交渉プロセスの停止を決定したことにより、欧州統合支持者や政権の汚職に反対する市民による大規模反政府デモが発生。ヤヌコーヴィチ大統領のロシアへの亡命を受け、ヤツェニューク首相による新政権が発足。同年3月、クリミア自治共和国において、「共和国政府」による「住民投票」の違法な実施を受け、ロシアはクリミアを「併合」したが、ウクライナ政府はこれをロシアの武力による違法占拠とし承認しない立場を発表。その後、東部でも情勢が不安定化し、武装勢力等が地方行政府各施設を占拠したことを受け、ウクライナ政府軍と武装勢力の戦闘が開始された。外務省「ウクライナ基礎データ」(外務省Webサイト)
126 ロシアNIS調査月報2019年5月号
(3)消費
消費者物価指数は、2018年に大きく低下したが、ルーブル安に伴う輸入物価の上昇によって緩やかに上昇し同年12月には再びインフレ目標の4%を上回った。2019年に入り、一時的に5%台に達したが、9月にはインフレ目標を下回り、低下基調で推移していた。2020年に入り、足下では上昇している。(第Ⅰ-3-6-5図)。前述のとおり、ルーブルが大きく下落しており、ルーブル安が長期化する可能性もあり、輸入物価の上昇を通じてインフレが更に上振れする可能性もある。
第Ⅰ-3-6-5図 ロシアの消費者物価指数と政策金利の推移
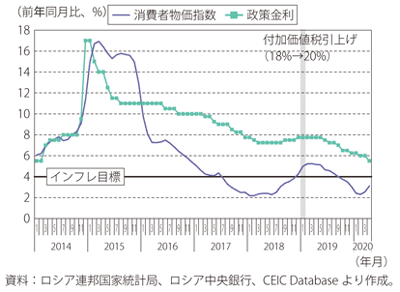
ロシア中央銀行は、米FRBの利下げ観測の高まり、インフレ圧力の後退、景気の停滞などを踏まえ2019年6月の金融政策決定会合で約1年ぶりに利下げを決定し、その後6会合連続で利下げし、2020年2月には6%となっていた。さらに、4月24日に開催された金融政策決定会合では、政策金利を0.5bp127引下げ5.5%にすると決定した。政策金利が5.5%まで引下げられたのは、2014年2月以来約6年ぶりであった。中央銀行は声明で、新型コロナウイルス感染拡大を背景に、国内の経済活動が著しく低下していること等に言及している。
次に、消費の動向を見ると、2019年9月まで小売売上高は伸び悩んでいたことが見てとれる。インフレ率が上昇したこともあり、実質賃金が弱含んでいたことが背景にある。家計消費はGDPの過半を占めていることからも、今後の動向に注視が必要である(第Ⅰ-3-6-6図)。
第Ⅰ-3-6-6図 ロシアの実質賃金と小売売上高(前年同月比)の推移
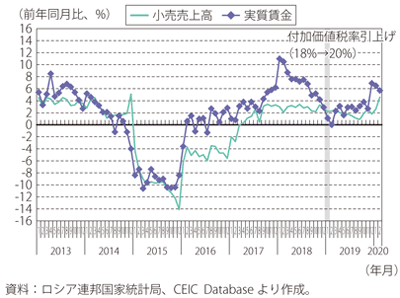
127 bpはベーシスポイント。1bp=0.01%
(4)生産
次に、鉱工業生産をみてみると、2019年の後半から増勢の鈍化が確認できる(第Ⅰ-3-6-7図)。特に、鉱業の伸びが低下している。OPECとの減産合意にもかかわらず、ロシアの2019年の原油生産量は過去最高を更新していたことから、政府の影響下にある資源企業が年末にかけて駆け込みで原油の生産にブレーキをかけた可能性があるとの見方もある。
第Ⅰ-3-6-7図 ロシアの鉱工業生産の推移(前年同月比)
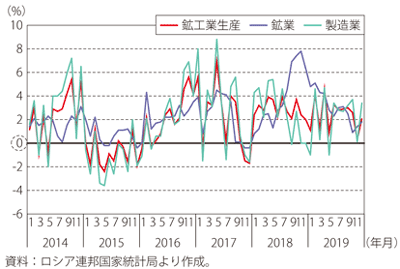
しかし、2020年3月、OPECとそれ以外の主要産油国で構成するOPECプラスは、追加減産で合意できず協議は決裂した。協調減産が3年以上に及んだ結果、ロシア石油大手会社の投資や生産の計画に制限が続いていることへの不満や減産継続による世界市場でのシェア低下への懸念があるとみられる。
その後、米国の仲介もあり、OPECとロシアは、5月~6月の原油生産量を日量1,000万バレル減らすことで合意した。過去最大規模の減産となる。
景況感をみても、製造業を中心に企業マインドは悪化する傾向が続いており、2019年5月には景気判断の分岐点である50を下回った(第Ⅰ-3-6-8図)。最大の輸出相手であるEUの景気減速などを背景に外需を取り巻く環境が厳しさを増す中、製造業PMI は11月に45.6まで低下した。その後、製造業の景況感は一時的に持ち直したが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、大幅な悪化を示している。ロシアは3月末から全国一斉の外出制限や、店舗や企業の休業が実施された。その結果、3月のサービス業の景況感は37.1と大幅に悪化。総合でも、39.5と50を大きく下回っている。さらに、4月に入り、景況感は一段と悪化し製造業が31.3、サービス業が12.2、総合でみても13.9と史上最低を記録した。
第Ⅰ-3-6-8図 ロシアの景況感の推移
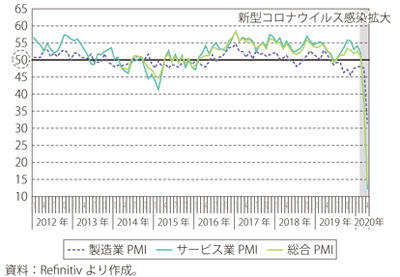
(5)貿易
ロシアは資源に依存した貿易構造であるため、資源価格の動向はロシアの貿易に大きく影響する。2019年は前年に比べ、原油価格が低下したことが影響し、輸出が前年比-6%となった。貿易収支額は約1,800億ドルと前年比約15%の減少となった(第Ⅰ-3-6-9図)。
第Ⅰ-3-6-9図 ロシアの貿易の推移
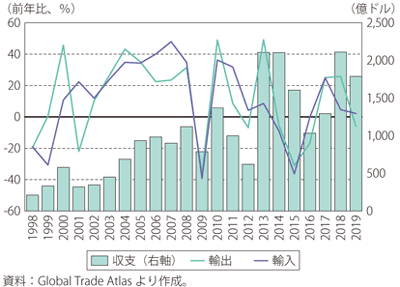
次に、主な輸出相手国を見ると、中国の存在感が高まっていることが分かる。長きに渡って、ロシアの最大輸出相手国はオランダであったが、2017年には中国が最大の輸出相手国となった。2014年のウクライナ危機以降の欧米諸国との関係悪化が、中国との関係を更に深める一つの要因となっている128。2019年には、輸出総額に占める中国向けの輸出割合が更に増加し、約13%と10年前と比べ2倍近くになっている。他方、日本向け輸出の占める割合が逓減してきており、約3%近くに留まっている129(第Ⅰ-3-6-10図)。
第Ⅰ-3-6-10図 ロシアの輸出相手国のシェアの推移
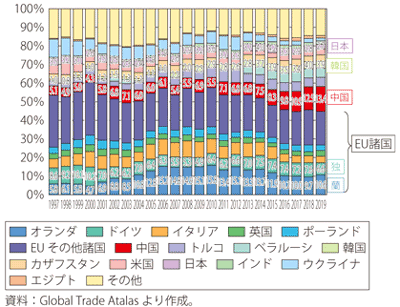
同様に、輸入相手国でみても中国の占める割合が最も多く、2019年で輸入額全体の約22%を占めている。それに比べて、ドイツや日本などは10年前と比べて、シェアが逓減してきていることがわかる130。輸出と同様、輸入においても中国との繋がりが深まってきていると言えよう(第Ⅰ-3-6-11図)。
第Ⅰ-3-6-11図 ロシアの輸入相手国のシェアの推移
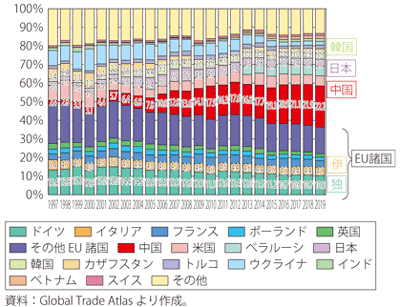
次に、最大の貿易相手国である中国との間の貿易品目を見てみる。鉱物性燃料や木材などはロシアの貿易黒字が大きい品目であり、一般機械や電気機器は貿易赤字の大きい品目である。ロシアが資源国であることもあり、中国へ資源を輸出し、中国から機械類を輸入する貿易構造となっている(第Ⅰ-3-6-12図)。
第Ⅰ-3-6-12図 ロシアの対中貿易収支の品目別内訳(2019年)
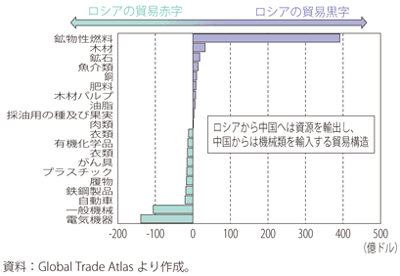
中国への最大輸出品目である鉱物性燃料の中でも、特に、原油の輸出が多い。中国への鉱物性燃料の輸出額の約8割を原油が占めている。特に、東アジア原油パイプライン(ESPO)131が全線開通した2012年以降、中国への原油輸出は大幅に増加している(第Ⅰ-3-6-13図)。
第Ⅰ-3-6-13図 ロシアの中国への鉱物性燃料の輸出の推移とシェア
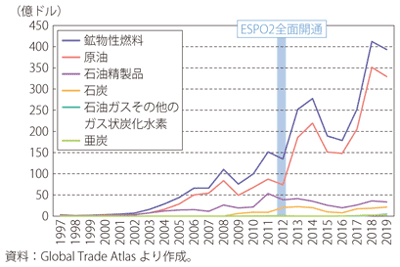
さらに、2019年12月には、ロシアと中国を結ぶ初の天然ガスパイプライン「シベリアの力」が開通した。全線が稼働する2025年には、年間380億m3の天然ガスが中国へ供給される見込みとなっている。
ロシアにとっては、極東地域の開発や市場の確保という面でも有益である。プーチン大統領は、ロシアと中国のエネルギー分野の戦略的協力を質的に新しい段階に引上げ、2国間貿易額を2024年までに2,000億ドルまで拡大させる目標の達成に近づくものと言及した132。
一方で、中国は大気汚染対策や低炭素社会の実現という観点から天然ガスの利用促進を政策的に進めている133。さらに、今回のパイプライン建設は天然ガスの供給源多角化という面でも中国にとって重要である134。現状では、ロシアから中国への天然ガスの輸出は多くないものの、今後大幅に伸びることも予想され、ロシアの中国への資源輸出は更に増加し、双方にとって貿易相手としての重要性が増していく可能性がある(第Ⅰ-3-6-14図)。
第Ⅰ-3-6-14図 ロシアの中国への鉱物性燃料の輸出割合
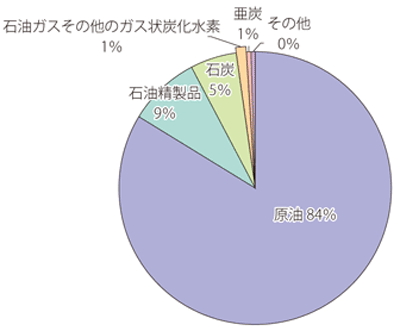
ロシアの輸出額全体に占める鉱物性燃料の割合は、約5割を占めており資源に依存した状態が続いている(第Ⅰ-3-6-15図)。ロシアは、長年、貿易構造の多角化・高度化を課題に掲げており、第3期プーチン政権の下では、2024年までに非原料・非エネルギーの輸出を2,500億ドルにまで拡大するという目標を表明している。しかし、たやすい課題ではなく、ロシアの輸出額を生産工程別の割合でみても、素材及び加工品の割合が大半を占め、部品や資本財、消費財などは依然として少ない(第Ⅰ-3-6-16図)。
第Ⅰ-3-6-15図 ロシアの輸出総額に占める資源の輸出割合
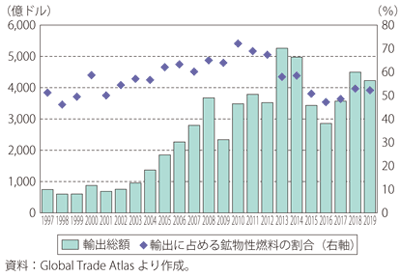
第Ⅰ-3-6-16図 ロシアの輸出(生産工程別)の推移
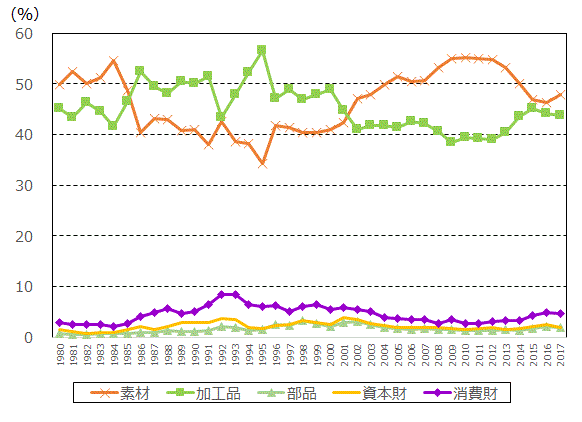
128 従前よりロシアの資源輸出の過半を占めていたのが、欧州市場であった。だが、2007年のウクライナとのガス紛争や2009年の世界金融危機などにより欧州市場への輸出拡大に限界がみえた。加えて、米国ではシェール革命が起きるなどロシアの欧米、西側重視の貿易・輸出政策は再検討を求められていたとの見方もある。下斗米(2016)
129 2019年のロシアから日本への輸出は約113億ドル(前年比-8.7%)。ロシアの輸出相手国としては12位の規模。
130 2019年のロシアの日本からの輸入は約90億ドル(前年比約+1.6%)。ロシアの輸入相手国として6位の規模。輸入相手国第2位のドイツからの輸入は約251億ドル(前年比-1.6%)。
131 東シベリア―太平洋(ESPO :East Siberia-Pacific Ocean)パイプラインは、ロシアイルクーツク州タイシェットから沿油地方のコズミノ・ターミナルまで総延長4,800キロの石油パイプライン。JOGMEC(https://oilgas-info.jogmec.go.jp/termlist/1001917/1001950.html![]() )
)
132 2019年の露中間貿易総額は約1,109億ドル(前年比+2.5%)であった。
133 JOGMEC(2019)
134 石油ガス及びその他のガス状炭化水素(HS2711)の中国への主な供給国は、豪州、トルクメニスタン、カタール、マレーシアである(2019年)。
(6)投資
先述の通り、ロシアは資源依存脱却を重要課題に掲げており、外資誘致や企業支援、イノベーションの支援などを通じて新たな産業の育成にも取り組んできた。2012年には、政府は世界銀行のビジネス環境ランキングにおけるロシアの順位を引き上げる目標を掲げ、目標達成に向けた措置をとることを大統領令で命じた。
世界銀行のビジネス環境ランキングは、企業のライフサイクル(起業から破産処理まで)に合わせて設定された項目について、ビジネスのしやすさを調査し総合評価によって各国を順位付けしている。実際に、2020年のビジネス環境ランキングでロシアのランキングは28位と他のBRICs諸国を上回り、日本よりも上位に位置しており、ビジネス環境は改善してきていると言えよう(第Ⅰ-3-6-17図)。
第Ⅰ-3-6-17図 BRICs諸国及び日本のビジネス環境
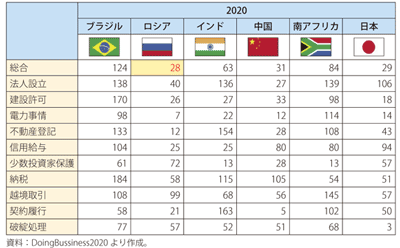
しかし、ビジネス環境が改善している一方で、対内直接投資の増加には結びついてはいない。2018年の対内直接投資額(ネット、フロー)は、約88億ドルと前年比69%減と大きく減少している。欧米による経済制裁など不確実性があることや他の新興国よりも経済成長率が低いことなどから投資先としてのリスクが小さくないことも要因として考えられる(第Ⅰ-3-6-18図)。実際、ロシアに進出している日系企業への調査によると、投資環境上のリスクについて、「不安定な政治・社会情勢」、「不安定な為替」、「行政手続きの煩雑さ(許認可など)」と回答する企業が多かった135。
第Ⅰ-3-6-18図 ロシアの対内直接投資の推移(業種別、ネット、フロー)
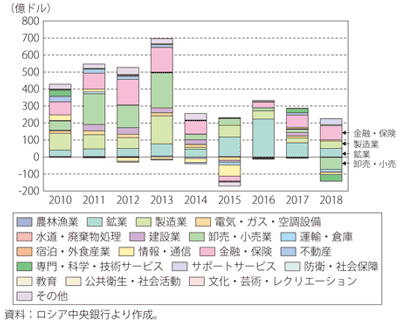
135 日本貿易振興機構(JETRO)2019年度ロシア進出日系企業実態調査
2.今後の展望とリスク要因
(1)リスク要因
① 財政状況の悪化
プーチン政権は、付加価値税率の引上げや年金給付開始年齢の引き上げなど、緊縮財政を推進してきた。背景には、ロシアの資源依存型経済や少子高齢化に伴う人口減少の課題があるとみられている。ロシアは歳入の約4~5割を石油・ガス関連収入が占め、資源価格の動向が国家の財政運営に大きな影響を与える(第Ⅰ-3-6-19図)。
第Ⅰ-3-6-19図 ロシア連邦財政(歳入)の推移
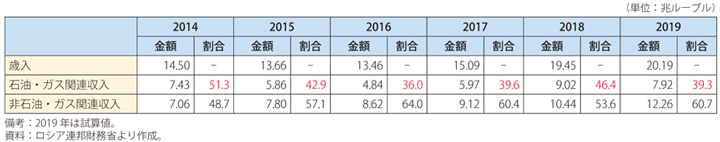
そのため、従来、ロシアは原油高の局面で上振れした税収を政府系ファンドに貯めておき、原油安の局面に備えてきた。また、ロシアは欧米諸国との国際関係も緊張しており、経済制裁が続いてきた。このような景気下押しリスクに備えるためにも、堅実な財政運営はロシアにとって重要である。従来、連邦予備基金と国民福祉基金の2つが運用されてきた。2018年初めには、この政府系ファンドのうちの1つであった予備基金が廃止され国民福祉基金に統合された。2014年以降、原油価格の下落もあり政府系ファンドの残高は縮小傾向にあったが、足下では、国民福祉基金の対GDP比は7%近くまで上昇していた(第Ⅰ-3-6-20図)。
第Ⅰ-3-6-20図 政府系ファンドの期末残高推移
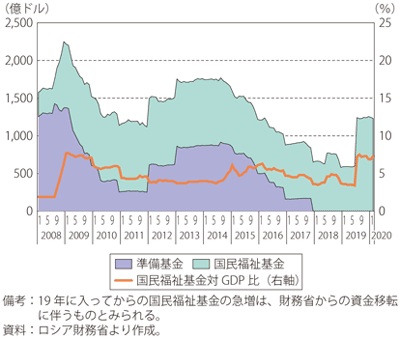
しかし、WTI原油価格がマイナスを記録したこと等による影響は大きく、シルアノフ財務相は、財政赤字が膨らむ可能性に言及し、財政赤字の埋め合わせとして、国民福祉基金を切り崩す必要があると述べた。加えて、その他の財源の確保、国債発行の必要性についても言及した。
② 家計債務の増加
先述の緊縮財政や景気低迷の影響もあり、実質可処分所得は2014年に入り低下傾向が続いていた(第Ⅰ-3-6-21図)。こうした中、不足する可処分所得を補うために家計が借入を増やしているとの指摘がある136。(第Ⅰ-3-6-22図)。
第Ⅰ-3-6-21図 ロシアの実質可処分所得伸び率の推移
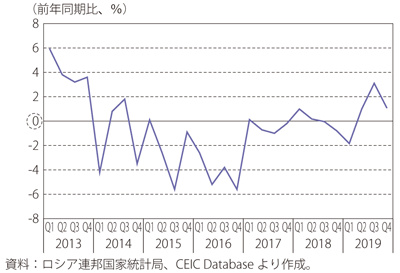
第Ⅰ-3-6-22図 ロシアの家計債務伸び率の推移
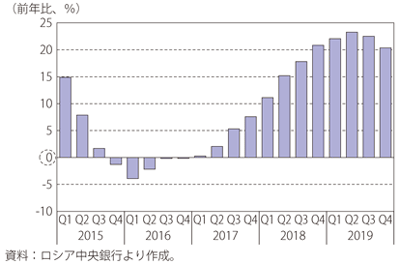
今後、予期せぬ金利上昇などによって、家計が資金繰りに悪化した場合、個人消費が悪化するリスクもある。そのため、中央銀行は家計債務を減らすため、2019年10月以降、小規模金融機関を中心に個人向けローンの与信管理を強化している。足下では、銀行の融資の厳格化などにより家計債務は減少しているものの、今後についても注視が必要である。
136 三菱UFJリサーチ&コンサルテイング(2020)
③ 人口の減少
ロシアでも日本と同様、人口減少が社会問題化している。合計特殊出生率をみても、1990年以降大幅に低下していた137(第Ⅰ-3-6-23図)。保育園の閉鎖や経済縮小による家計の育児コスト負担能力が低下したことが要因の一つとみられている138。
第Ⅰ-3-6-23図 ロシアの合計特殊出生率の推移
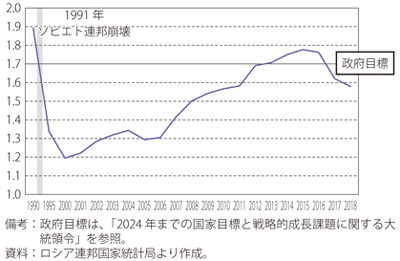
2000年代に入り、ロシアが持続的経済成長をみせるようになった後、2006年12月には育児手当等の増額が計られたとともに、「母親基金」と称する出生に対する大規模な給付制度が定められた139。2000年以降、出生率は回復してきていたものの依然として低水準に留まっている。ロシア連邦国家統計局は、ロシアの人口が2030年には1億4,300万人程度と現在の水準より約250万人減少すると予測している(第Ⅰ-3-6-24図)。
第Ⅰ-3-6-24図 ロシアの人口予測の推移
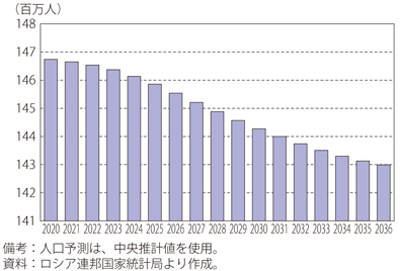
こうした状況を鑑み、2020年1月の大統領教書演説では、出生率の上昇に向け、若い家族や母子家庭に対する支援策を拡充する方針が表明された140。
137 ソビエト連邦は第二次世界大戦以降、労働力不足に直面していたことから出生を奨励していたが、1991年のソ連崩壊後、出生数を死亡数が上回る状態が続き人口の自然減が続いていた。雲和弘(2014)「ロシアの人口動態」(http://www.hit-u.ac.jp/hq-mag/research_issues/315_20181201/![]() )
)
138 雲和宏(2014)
139 「母親基金」は2人以上の子を持つ親に対し、住宅購入の費用・子どもの教育費・年金基金への積立のいずれかへの補助として、25万ルーブル(当時120万程度)を支給するものとして創設された。2007年1月1日以降に生まれた、又は縁組みされた第二子以降に関して適用。
140 具体的には、地方における保育所の拡充(2021年末までに22万5,000人の受け入れ児童数増加)、低所得家庭向けの各種手当申請手続きの改善、母親基金の受給期間の延長と受給額の引上げなどが提案された。
(2)今後の展望
新型コロナウイルスの感染拡大や原油価格の大幅な下落がロシア経済に与える影響は大きく、経済成長の下振れが避けられない状況となりつつある。
IMFによると、2020年の経済成長率は-5.5%にまで減速すると予測されている。これは2009年の金融危機後以来の落ち込みであり、1998年のロシア財政危機の際の経済成長率を下回る(第Ⅰ-3-6-25図)。
第Ⅰ-3-6-25図 ロシアの経済成長率とWTI原油価格伸び率の推移
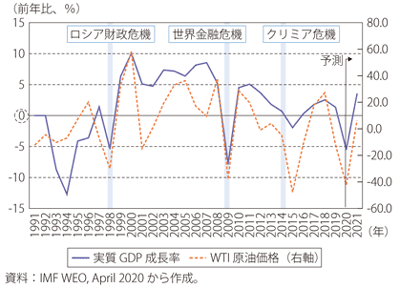
ロシア経済は資源に依存する経済構造であり、原油価格の動向に経済が大きく左右されてきた。2015年に原油価格が大きく下落した際は、-2%近くまで落ち込んだ。2020年4月には原油価格が史上初めてマイナスを記録しており、ロシア経済への更なる下押しが懸念される。
景気への悪化は、政権への不満につながりかねないことから、政府は新型コロナウイルス感染拡大による景気悪化に対しても不安を解消するため、雇用や所得の安定確保や企業支援の政策を発表し、さらに子供のいる家庭への給付や中小企業に対する付加価値税を除くすべての税の納税猶予など追加支援策も打ち出している。しかし、原油市況の低迷により、歳入減少の可能性が高まる中での積極的な財政政策は容易ではない。
加えて、世界的な経済の落ち込みによる資源需要の縮小、内需の大幅な縮小に加え、家計債務問題、人口縮小など国内の課題も少なくない。今後の先行きには注視が必要である。
