

- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2020

- 白書2020(HTML版)

- 第2部 第1章 第2節 サプライチェーンにおける集中度の高まり
第2節 サプライチェーンにおける集中度の高まり
第1節において示した通り、新型コロナウイルスの感染拡大に伴って生じたサプライチェーンの寸断については、生産体制、物流、人の移動の3点に注目することが重要である。本節ではその中で生産体制に着目する。
生産体制については、生産拠点の集中度の上昇や生産拠点の多様化が同時に進展する中で、地域や財により生産拠点の集中度の高まりが見られ、その結果、サプライチェーン途絶のリスクに直面することとなった。これは、医療用品のような緊急物資についても同様であり、生産拠点の集中が見られ、それが緊急時の需要の爆発に対応することが困難となる要因の一つであった。
さらに、地域統合により域内におけるサプライチェーンが発達してきたが、危機時においては域内のサプライチェーンであっても途絶するリスクが存在した。その一方で、自国優先も非効率につながるおそれがあり、域内・域外のサプライチェーンを精緻に把握し、経済性・効率性と供給途絶リスクへの対応力のバランスを踏まえ、強靭なサプライチェーンネットワークを構築することの重要性も示唆された。
1.世界のサプライチェーンにおける生産拠点の集中度の高まり
(1)生産拠点の集中度の上昇と生産拠点の多極化
世界においては、生産拠点の集中度の上昇と生産拠点の多極化が同時に進んでいる。その生産拠点の集中度は、物の輸入動向から把握することができる。つまり、世界や地域・国ごとの輸入動向を踏まえて、それぞれの輸入先が集中する場合には、生産拠点の集中が生じていると考えることができる。
そこで、生産拠点の集中度の高まりについて、輸入先の集中度(ハーフィンダール・ハーシュマン指数:HHI指数)を用いて評価をする3。
第Ⅱ-1-2-1図から第Ⅱ-1-2-4図において、東アジア、東南アジア、米州、欧州の輸入先の集中度を示している。これは、指数が高いほど、各地域における輸入先の集中度が高いことを示すものである。各地域の輸入先の集中度の変化に注目すると、地域内の差異も見られるものの、2000年代に集中度が低下する国が多かったが、2010年代に入ると集中度が上昇する国が多く見られる。
第Ⅱ-1-2-1図 東アジア主要国・地域の輸入先の集中・分散度合い(輸入先の国別に見たハーフィンダール・ハーシュマン指数)
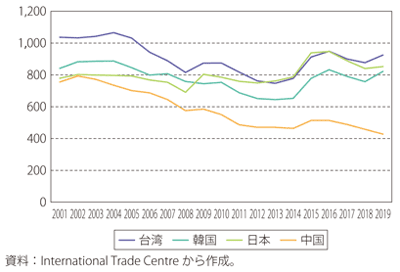
第Ⅱ-1-2-2図 東南アジア主要国の輸入先の集中・分散度合い(輸入先の国別に見たハーフィンダール・ハーシュマン指数)
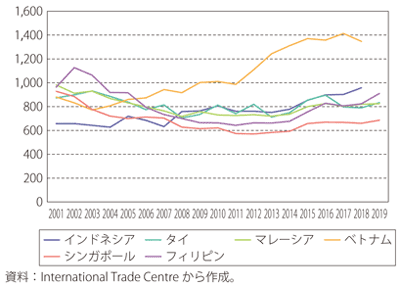
第Ⅱ-1-2-3図 米州主要国の輸入先の集中・分散度合い(輸入先の国別に見たハーフィンダール・ハーシュマン指数)
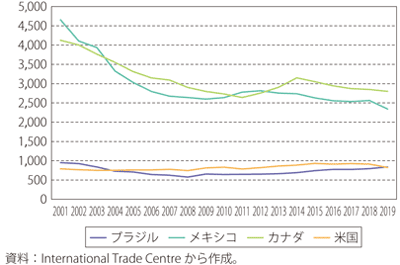
第Ⅱ-1-2-4図 欧州主要国の輸入先の集中・分散度合い(輸入先の国別に見たハーフィンダール・ハーシュマン指数)
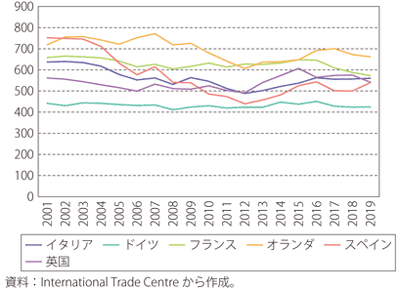
この各国の共通の動向については、2000年代以降に中国からの輸入割合の上昇を見て取ることができる(第Ⅱ-1-2-5図)。
第Ⅱ-1-2-5図 主要国の輸入に占める中国からの割合
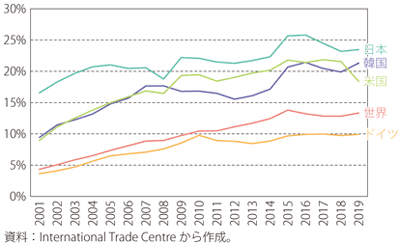
東アジアにおいては、2000年代に各国・地域において輸入先の集中度が低下傾向にあった。2010年代には中国では更に輸入先の集中度が低下したが、日本、韓国、台湾においては輸入先の集中度は上昇した。
東南アジアにおいては、2000年代にはフィリピン、マレーシア、タイ、シンガポールにおいて輸入先の集中度が低下傾向にあったものの、2010年代に入り各国の輸入先の集中度は上昇した。ベトナムでは、輸入先の集中度は2000年代半ばから上昇傾向を示した。
米州においては、カナダとメキシコの輸入先の集中度は高水準ではあるが、2000年代に大きく低下した。一方、米国の輸入先の集中度は2010年代に入り小幅に上昇した。
欧州各国における輸入先の集中度の水準はアジアや米州の多くの国・地域を下回る。2000年代にスペイン、イタリアにおいて輸入先の集中度は低下傾向であったが、2010年代に小幅に上昇した。ドイツの輸入先の集中度は欧州主要国の中で最も低い水準であり、2000年代と2010年代を通じて大きな変化を示さなかった。
この輸入先の集中度は、近隣に大国が存在する場合には水準が高くなりやすい。米国に隣接するメキシコやカナダは、米国からの輸入割合が高く、輸入先の集中度の水準が高い。その一方で、突出した大国が存在せず、単一市場として経済統合を推進してきたEUを中心とする欧州では、各国の輸入先の集中度の水準は高くない。
このため、輸入先の集中度の変化及び水準の双方を踏まえることで、集中や多様化の動向を評価することができる。
次に、地域別の輸入先の集中度の動向をそれぞれの主要な輸入先の国の動向と合わせて確認しよう。
まず欧州においては、欧州の域内における大国であるドイツやフランスでは、中国からの輸入割合が上昇しているものの、輸入先が多様であり、集中度には大きな変化は見られない。一方、欧州の周縁国においては、中国からの輸入割合が上昇する中で、ドイツやフランスからの輸入割合が低下し、輸入先の集中度は低下をしていた。ただし、イタリア、スペインなどにおいては、2015年ごろからドイツからの輸入割合が再び上昇することで輸入先の集中度が上昇してきた(第Ⅱ-1-2-6図)。
第Ⅱ-1-2-6図 欧州主要国の輸入先の集中・分散度合い(輸入先の国別に見たハーフィンダール・ハーシュマン指数)と主要輸入相手国からの輸入割合
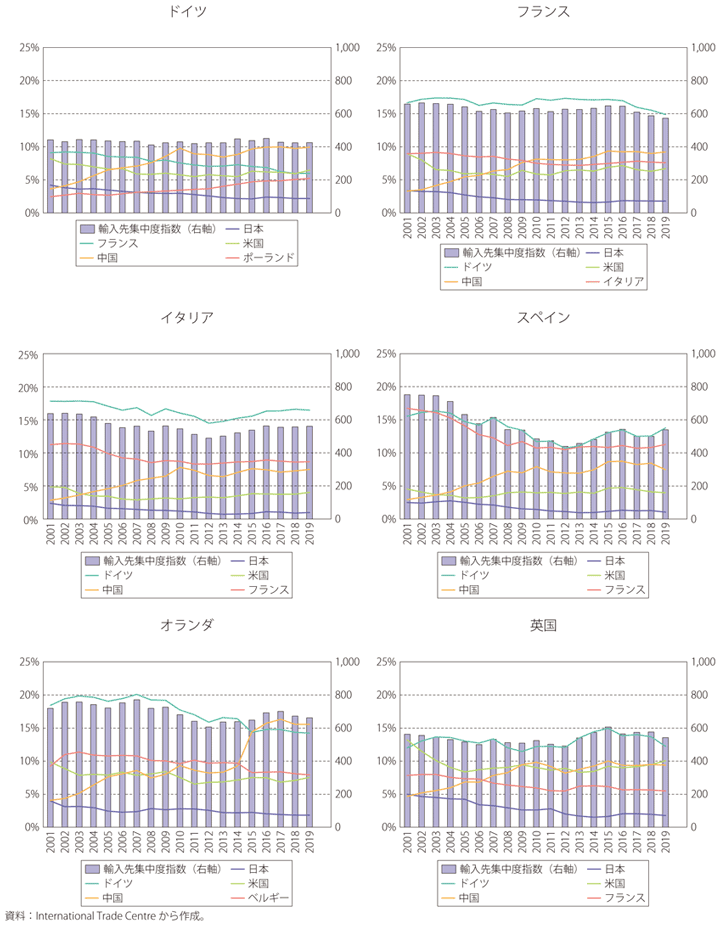
米州については、域内の大国である米国は、中国からの輸入割合が隣国であるメキシコ、カナダを上回った2008年前後から輸入先の集中度の上昇が見られる。メキシコやカナダにおいては、中国からの輸入割合が上昇することで米国からの輸入割合が低下し、輸入先の集中度の低下が見られる。ただし、メキシコやカナダは域内の大国である米国からの輸入割合が高いため、輸入先の集中度の水準は高いものとなっている(第Ⅱ-1-2-7図)。
第Ⅱ-1-2-7図 米州主要国の輸入先の集中・分散度合い(輸入先の国別に見たハーフィンダール・ハーシュマン指数)と主要輸入相手国からの輸入割合
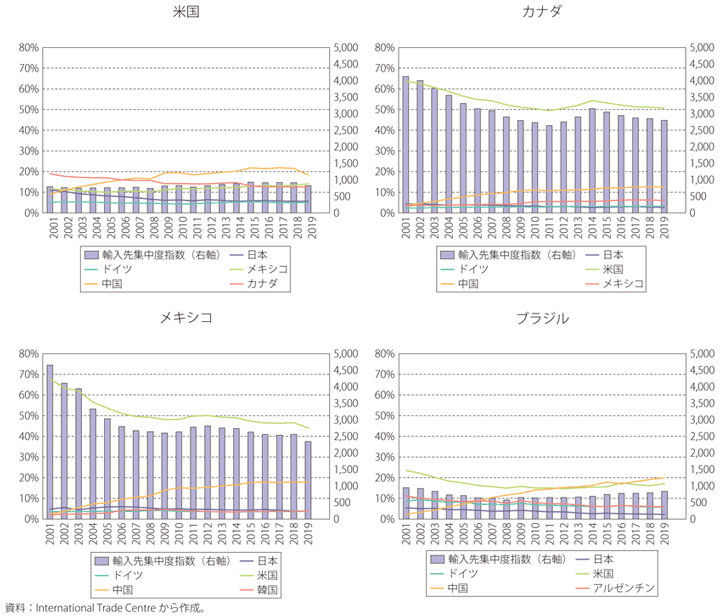
アジアの国・地域を見てみると、かつては日本からの輸入割合が高く、輸入先の集中度が高かったものの、2000年代初頭以降は中国からの輸入割合が上昇し、日本からの輸入割合が低下する中で一旦、輸入先の集中度が低下したが、その後、中国からの輸入割合が一段と上昇する中で、輸入先の集中度は上昇した(第Ⅱ-1-2-8図に東アジア、第Ⅱ-1-2-9図に東南アジアの輸入先の集中度)。
第Ⅱ-1-2-8図 東アジア主要国・地域の輸入先の集中・分散度合い(輸入先の国別に見たハーフィンダール・ハーシュマン指数)と主要輸入相手国からの輸入割合
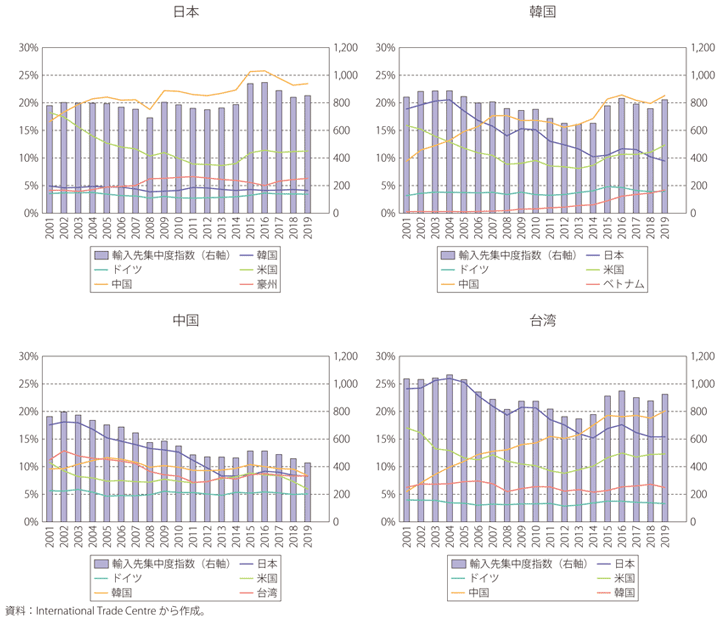
第Ⅱ-1-2-9図 東南アジア主要国の輸入先の集中・分散度合い(輸入先の国別に見たハーフィンダール・ハーシュマン指数)と主要輸入相手国からの輸入割合
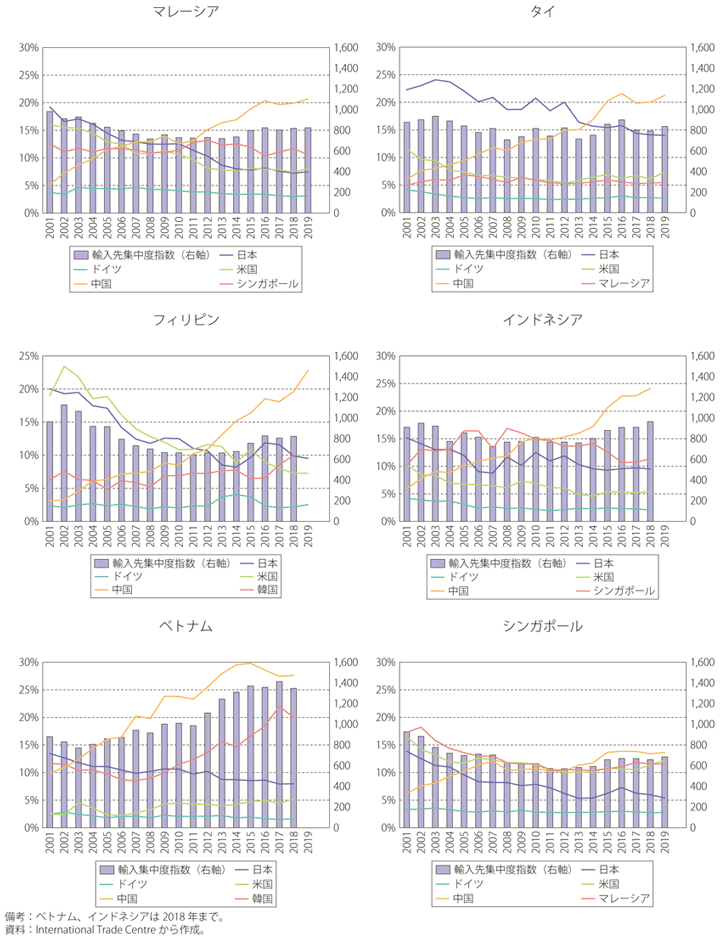
つまり、欧米においては中国からの輸入割合の上昇が地域の中心国からの輸入割合の低下をもたらした結果、輸入先の集中度の低下につながるという形での多極化が進展してきたものの、近年は中国からの輸入割合がますます上昇し、輸入先の集中度が上昇する国も見られる。また、アジアにおいては中国からの輸入割合が更に高まることによって輸入先の集中度が上昇している。
各国の輸入先に占める中国の割合と、各国の輸入先の集中・分散度合いの2005年から2019年の変化を比較すると、輸入先に占める中国の割合が世界的に高まる中で、その輸入割合が一段と上昇したアジア地域において輸入先の集中度合いが高まる状況が見られる(第Ⅱ-1-2-10図)。
第Ⅱ-1-2-10図 各国の輸入先に占める中国の割合と集中・分散度合い(輸入先の国別に見たハーフィンダール・ハーシュマン指数(2005年・2019年)
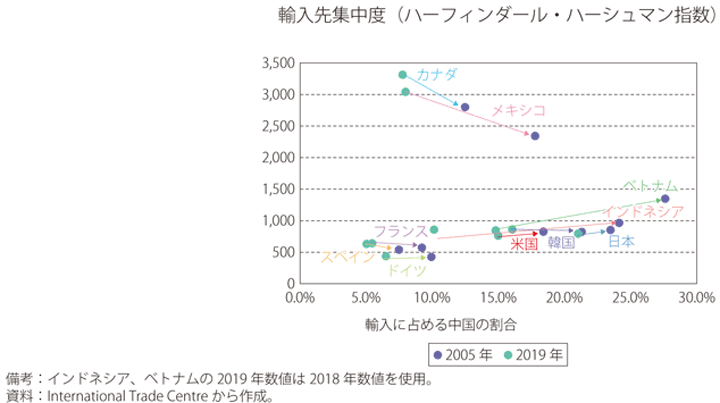
韓国、ベトナム、インドネシアにおいては、2000年代に日本や米国からの輸入の割合が低下する中で、中国からの輸入割合が上昇し、その過程で集中度指数はいったん低下した。その後、各国において2010年前後に中国からの輸入の割合が上昇する中で、輸入先の集中度が上昇した。台湾、シンガポール、タイ、マレーシアにおいても同様の傾向が見られる。
中国との貿易活動は、近隣の東アジア諸国との間で拡大してきたものの、近年は中国とASEANの間の貿易が拡大している(第Ⅱ-1-2-11図)。
第Ⅱ-1-2-11図 韓国、台湾、ASEANと中国の間の輸出入推移
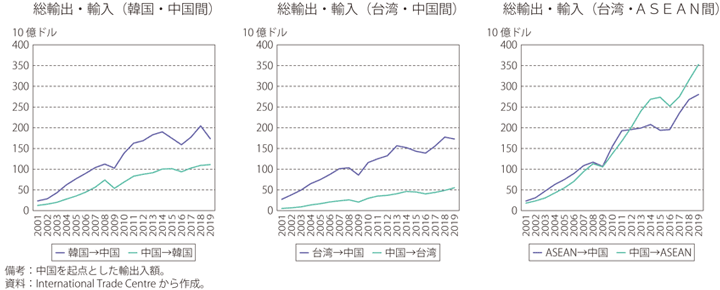
中国の輸出先に占める国・地域別の割合を比較すると、ASEANは2010年に8.8%であったが、2019年には14.4%に上昇した。一方、米国は2010年に18.0%であったが、2019年には16.8%に低下した。EUは、2010年に10.7%、2019年に11.0%と横ばいで推移した。日本は2010年に7.7%であったが、2019年に5.7%に低下した(第Ⅱ-1-2-12図左)。
次に中国の輸入先の割合を比較すると、ASEANは2010年の11.1%から2019年には13.6%に上昇した。また、EUは、2010年の12.4から2019年に13.4%に上昇したもののASEANを下回る。米国は2010年に7.4%であったが、2019年に6.0%と低下した。日本は2010年に12.8%であったが、2019年に8.3%に低下し、韓国(8.4%)、台湾(8.4%)を下回る(第Ⅱ-1-2-12図右)。
第Ⅱ-1-2-12図 中国の輸出先、輸入先の割合
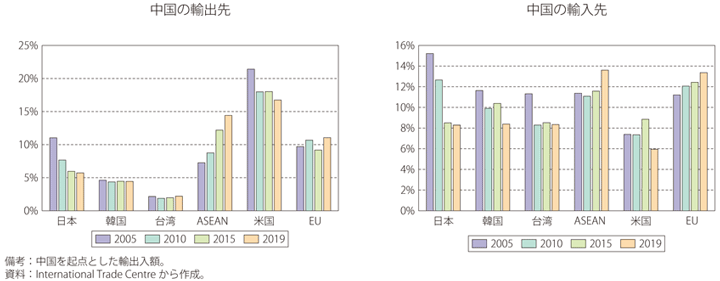
3 各国においてその輸入に占める相手国のシェアの二乗和であるハーフィンダール・ハーシュマン指数。輸入先が一国のみである場合に同指数は1万となる一方、輸入先が分散している場合に同指数は0に近づく。例えば、A国がB国から50%、C国から30%、D国から20%の輸入をしている場合、A国のHHI指数は502+302+202=3,800となる。最大値(一国のみから輸入した場合)は1002=10,000となる。
(2)産業・財別に見た集中度
次に、輸入先の集中度を産業別・財別に見てみよう。
産業別に見ると、第1節で整理したように、労働集約やすり合わせといった産業・技術の特性に応じて各国・地域における生産体制は変化するものである。その中で、IT、電子機器については国際分業による国境を越えた生産ネットワークの構築が進んでおり、中国がIT製品の最終組立拠点となり、韓国・台湾・ASEANが中間財の供給拠点となっており、世界的な集中度は上昇傾向にある。国別に見ても輸入先の集中度が上昇した国が多い(第Ⅱ-1-2-13図)。
第Ⅱ-1-2-13図 各国の電気機械、電子部品の輸入先に占める集中・分散度合い(輸入先の国別に見たハーフィンダール・ハーシュマン指数)
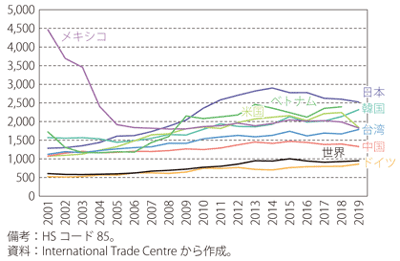
電気機械、電子部品の輸入を国ごとに見ていくと、まず日本については、輸入先の集中度が2000年代から2014年にかけて大きく上昇しており、この間に中国からの輸入割合は2001年の20.9%から2014年には51.1%に達した。一方、その後は、ベトナムやタイからの輸入の割合が上昇する中で、中国からの輸入の割合は低下し、輸入先の集中度も低下した。
韓国では、ベトナムからの輸入割合も急速に上昇した。一方、ベトナムにおいては、2010年代に入り中国からの輸入割合が低下する一方、韓国からの輸入割合が上昇する中で輸入先の集中度指数が上昇した。
中国においては、2000年代に日本からの輸出割合の低下と韓国、台湾からの輸入割合の上昇が見られる中で輸入先の集中度は安定していたものの、2010年代に入り台湾からの輸入割合が一段と上昇したことから、輸入先の集中度は上昇した。
ドイツにおいては、2000年代以降に日本からの輸入割合の低下と中国からの輸入割合の上昇が見られる中で輸入先の集中度は上昇したものの、チェコ、ハンガリー、ポーランドなどの東欧諸国からの輸入割合も2019年時点でそれぞれ5%前後存在する状況であり、多様化も進んでいることから、輸入先の集中度は他の主要国に比べて低水準となっている。
米国も、中国からの輸入割合が一段と上昇する中で輸入先の集中度が上昇した。しかし、2019年に中国からの輸入割合が大きく低下した一方でベトナムの輸入割合が上昇し、輸入先の集中度は低下した。メキシコにおいては、米国からの輸入割合が低下し、中国からの輸入割合が上昇する中で、輸入先集中度指数は2000年代に大きく低下した一方、2010年には中国からの輸入割合が安定し、マレーシア、ベトナムからの輸入割合が上昇し、輸入先集中度指数は安定して推移している。
自動車・自動車部品については、市場への近さ、複雑な生産工程の観点から各国内での地産地消が中心であるものの、自動車部品の貿易は拡大傾向にあった。生産拠点としてメキシコや中国などが存在感を増す中で、自動車部品における世界的な集中度は低下傾向にある(第Ⅱ-1-2-14図)。
第Ⅱ-1-2-14図 各国の自動車部品の輸入先に占める集中・分散度合い(輸入先の国別に見たハーフィンダール・ハーシュマン指数)
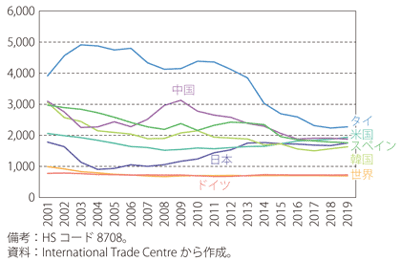
国ごとに見ていくと、日本においては、米国からの輸入割合が低下し、中国からの輸入割合が上昇する中で、輸入先の集中度が2005年から2014年にかけて上昇した。近年はタイ、ベトナムからの輸入割合が上昇することで中国からの輸入割合の上昇が止まり、輸入先集中度はほぼ一定を推移している。
中国においては、2010年以降に日本からの輸入割合が低下する中で集中度が低下した。2013年以降はドイツからの輸入割合が日本を上回る状況となっている。
韓国においては、日本からの輸入割合が低下する一方、中国からの輸入割合が上昇する中で2000年代から2010年代半ばにかけて集中度は低下した。
ドイツにおいては、フランスからの輸入割合が低下する一方、東欧からの輸入割合が上昇する中で集中度は低水準を維持している。
スペインにおいては、フランス、ドイツからの輸入割合が低下する一方、東欧からの輸入割合が徐々に上昇する中で、集中度が低下した。
米国においては、2000年代に日本からの輸入割合の低下に伴い集中度が低下したものの、2010年代に入り、メキシコからの輸入割合が上昇する中で集中度が上昇した。メキシコにおいては、高水準であった米国からの輸入割合が緩やかに低下しており、中国からの輸入割合が上昇する中で、集中度は低下傾向にある。
このように、日本と米国において自動車部品の輸入先集中度が高まりつつある一方、その他の国・地域においては自動車部品のサプライチェーンネットワークは多様化が進んでいる。自動車部品の中では、中国、ドイツ、メキシコが車輪ホイール・構成部品において世界の輸出の約5割、ブレーキ構成部品において世界の輸出の約4割を占めているように、集中度が高い状況となっている。こうした状況の下で、新型コロナウイルスの感染が拡大する中、必要な部材の調達が困難となり工場の稼働が停止する状況が各国・地域において見られた。
このように、電気機械、電子部品においては携帯電話を中心に中国の存在感が高まっており、自動車部品においても車輪ホイール・構成部品では中国の世界輸出に占める割合が高まっている(第Ⅱ-1-2-15図)。なお、自動車部品全体で見ると、中国の輸出は2019年時点で世界の輸出の8.6%を占め、世界輸出に占める割合は他の財よりも低いものの、その割合は徐々に高まりつつある。自動車部品全体においては日本と米国においては輸入の集中度が高まる一方、日本を除くアジア、米国を除く北米、そして欧州においては多様化が進んでいる。
第Ⅱ-1-2-15図 電気機械、電子部品、携帯電話、自動車部品、車輪ホイール・構成部品の世界輸出における中国の割合
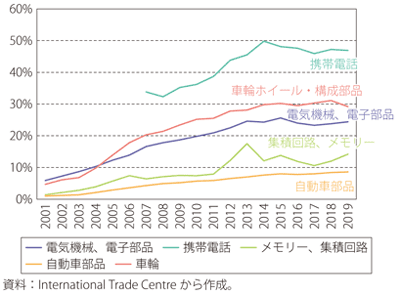
アパレルなど軽工業については、労働賃金の重要性が高いため、部分的には中国から東南アジアへの移管が見られており、アパレルにおいては中国からの世界への総輸出は横ばいに留まる中で、ASEANから世界への総輸出が拡大している(第Ⅱ-1-2-16図)。ASEANから中国へのアパレルの輸出も継続的に拡大している(第Ⅱ-1-2-17図)。
第Ⅱ-1-2-16図 アパレル、家具、おもちゃ分野における中国とASEANの総輸出額
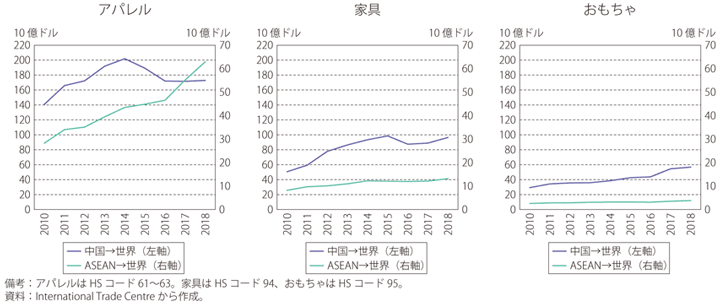
第Ⅱ-1-2-17図 アパレル、家具、おもちゃ分野におけるASEAN・中国間の貿易
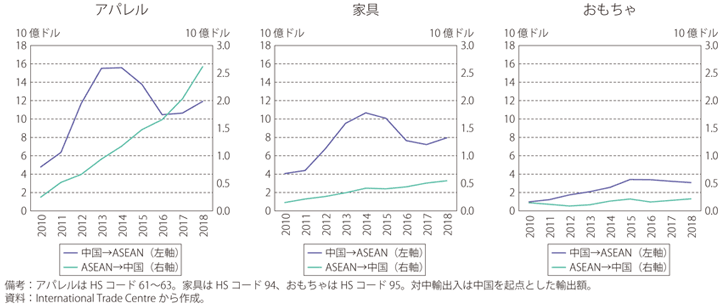
一方、中国からASEANへのアパレルの輸出は2015年から2016年にかけて減少したが、2017年以降増加した。これは、中国での生産機能を残しつつASEANに分散する動きを反映しているといえる。
また、家具分野においては、ASEANの総輸出が拡大を示す一方で、中国からの輸出は、一旦低下を示したものの再度拡大をしている。おもちゃに関しては依然として中国が一大生産地である。
おもちゃ分野においては、アパレルとは異なり、2015年以降も中国から世界への輸出が拡大を続けている。一方、ASEANから世界へのおもちゃの輸出は横ばい圏である。
このように、生産拠点が中国から東南アジアに完全に置き換わる状況とはなっておらず、繊維素材は中国から東南アジアに輸出されるなど、軽工業分野でも相互関係がより複雑になりつつある。
新型コロナウイルス感染拡大の防止という観点から重要となる医療用品や医療関連物資などについては、輸出上位の数カ国が供給の高い割合を占めることが新型コロナウイルスの感染拡大の中で明らかになった。医療用品の輸出は、ドイツ、米国、スイスの3か国で35%を占めている(第Ⅱ-1-2-18表)。また、中国、ドイツ、米国の3か国で個人用防護具の輸出の約半分を占める状況である(第Ⅱ-1-2-19図)。
第Ⅱ-1-2-18表 医療品の輸出上位10カ国
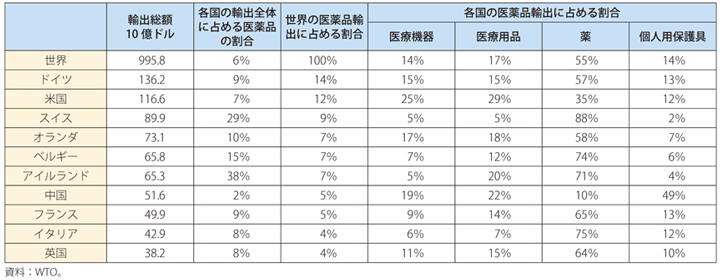
第Ⅱ-1-2-19図 個人用保護具の輸出上位10カ国
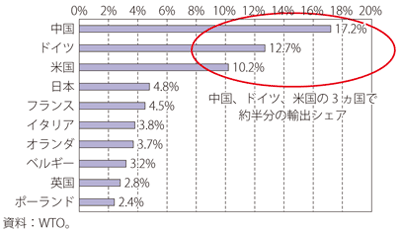
米国、EU、世界における医療用品の中国からの輸入の割合は、ゴーグルやバイザー、マスクについては中国からの輸入が各地域・国において6~7割を占め、また、他の医療用品も中国からの輸入の割合が高いものとなっている(第Ⅱ-1-2-20図)。
第Ⅱ-1-2-20図 EU、米国、世界の医療用品の輸入における中国の割合
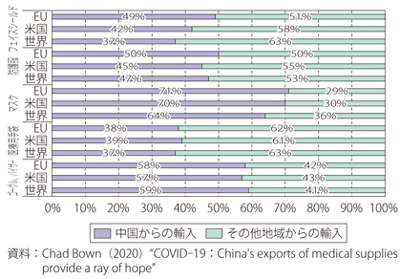
世界の輸出において中国が20%以上の割合を有する財は、HS2桁コード99分類中33分野であり、全分類の3分の1に達する。特に中国の割合が高いのは、アパレル、玩具などの軽工業、そして電気機械、電子部品などのIT製品分野である(第Ⅱ-1-2-21図)。一方、自動車、自動車部品においては、中国の輸出割合は5.0%に留まるものの、先述のように、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて自動車産業におけるサプライチェーンの寸断が顕著に見られることとなった。
第Ⅱ-1-2-21図 世界の輸出に占める中国の割合
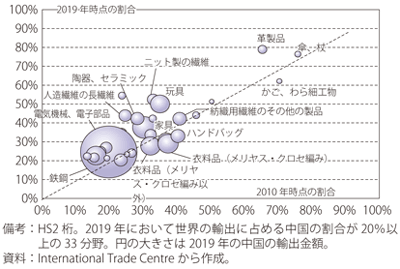
2.日本のサプライチェーンにおける生産拠点の集中度の高まり
日本のサプライチェーンにおいても、生産拠点の集中度が高まっている。特に中国への集中度が上昇している。
(1)貿易から見る集中度の高まり
日本の対中貿易は、中国がWTOに加盟した2001年以降に輸出・輸入とも大きく拡大した。特に日本の対中輸出に関しては2000年代に急速に拡大したものの、2010年代には減速し、2019年は前年比6.4%減の1,347億ドルとなった。日本における中国向けの輸出を中間財・消費財・資本財に分けると、全体に占める割合は、2000年時点で中間財が35%、消費財が9%、資本財が55%(原材料が1%)を占めていたが、2018年には中間財が23%、消費財が18%、資本財が58%(原材料が2%)を占め、投資分野が大半を占めるものの、消費財の割合も高まりつつある(第Ⅱ-1-2-22図)。
第Ⅱ-1-2-22図 日本の対中輸出の財別内訳(2000年、2018年)
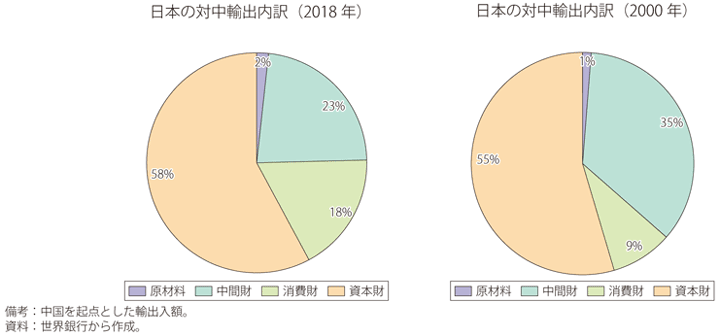
日本の対中輸入も2000年代に急速に拡大した後、2012年をピークに伸び悩むようになった。2017年以降は再拡大したものの、2019年は前年比で2.4%減少して1,693億ドルとなった。
日本における中国からの輸入を中間財・消費財・資本財に分けると、全体に占める割合は、2000年時点で中間財が12%、消費財が57%、資本財が20%(原材料が10%)を占めていたが、2018年には中間財が14%、消費財が40%、資本財が41%(原材料が4%)を占めた(第Ⅱ-1-2-23図)。
第Ⅱ-1-2-23図 日本の対中輸入の財別内訳(2000年、2018年)
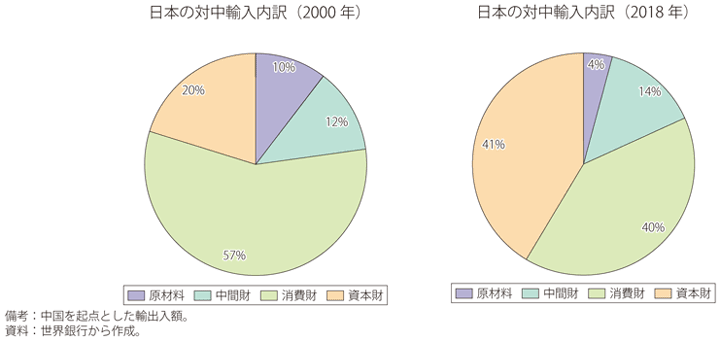
以前は日本に輸入される中国製品はアパレル、おもちゃ、家具、雑貨などの軽工業・消費財が中心であったものの、近年は消費財においても高度な技術が要求される携帯電話などの輸入が増加し、機械や部品の輸入も増加している。このような日本の中国からの輸入構成の変化は、日本の対中輸入が中国の供給サイドの変化の影響を受けていることを示している。
次に、サプライチェーンのネットワークという視点から、個別品目や産業における動向について以下で確認する。
日本企業の中国現地法人での活動も増加しており、その中で、日本への部品の輸出の増加などが見られるようになっており、自動車部品については他国からの輸入割合が高まりつつあり、新型コロナウイルスの感染拡大の中で自動車の生産が停止する事態も見られた。
自動車部品について中国との輸出入の推移を見ると、中国からの部品輸入は2010年の1,401億円から2019年に3,285億円に拡大し、日本の部品輸出に対する輸入の比率は2019年時点で50%近い水準まで上昇した4(第Ⅱ-1-2-24図)。また、電子部品を見ると集積回路についても2010年代に入ってから日本からの輸出に対する中国からの輸入比率は上昇した(第Ⅱ-1-2-25図)。一方、液晶デバイスでは、中国からの輸入が必ずしも増えていないように、部品によって事情は異なる(第Ⅱ-1-2-26図)。
第Ⅱ-1-2-24図 日本の中国に対する自動車部品の輸出入の推移
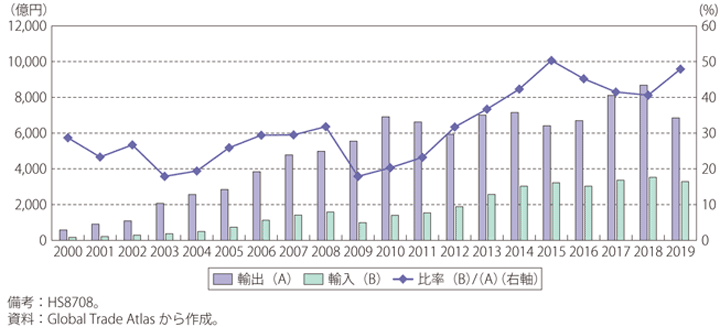
第Ⅱ-1-2-25図 日本の中国に対する集積回路の輸出入の推移
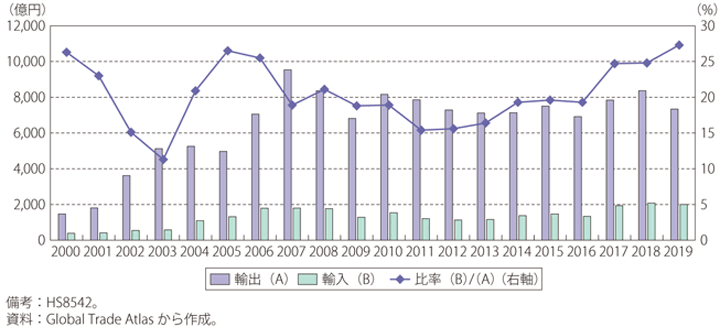
第Ⅱ-1-2-26図 日本の中国に対する液晶デバイスの輸出入の推移
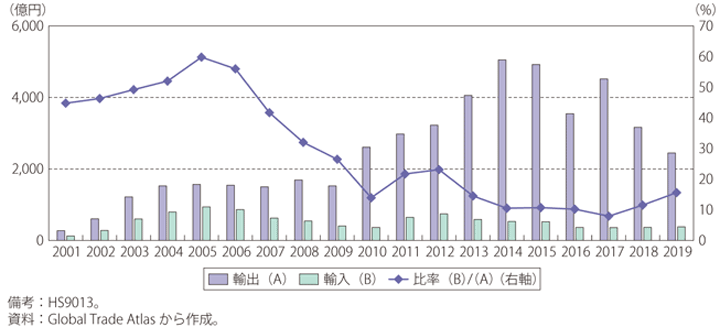
特定の品目において一国からの輸入割合の高さが目立つのは、上記品目に限らない。日本の輸入先に占める生産拠点の集中度が5割以上を占める日用品、ヘルスケア製品を第Ⅱ-1-2-27表に整理した。機械療法用機器は中国からの輸入割合が高い。整形外科用機器及び骨折治療具、免疫産品(混合したもので、投与量にしてなく、かつ、小売用の形状又は包装にしてないもの)は米国、インスリンを含有する医薬品(混合し又は混合してない物品から成る治療用又は予防用のもので、投与量にしたもの又は小売用の形状若しくは包装にしたもの)はデンマークからの輸入割合が高い。
第Ⅱ-1-2-27表 日本の輸入先に占める生産拠点の集中度が5割以上の日用品・ヘルスケア製品(2019年)
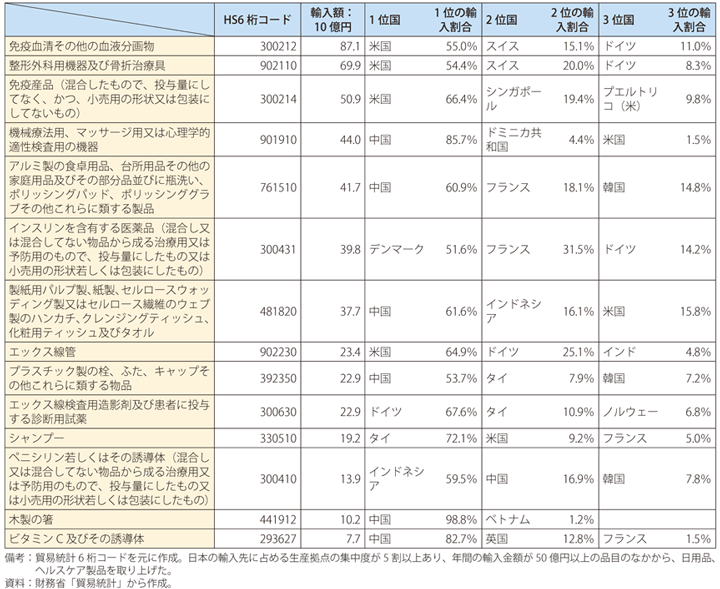
IT製品分野においては、携帯電話、携帯用の自動データ処理機械5、スイッチング機器及びルーティング機器など多くの品目において中国からの輸入割合が高い(第Ⅱ-1-2-28表)。プロセッサー、記憶素子においては台湾からの輸入割合が高いものとなっている。
第Ⅱ-1-2-28表 日本の輸入先に占める生産拠点の集中度が5割以上のIT製品、関連部材(2019年)
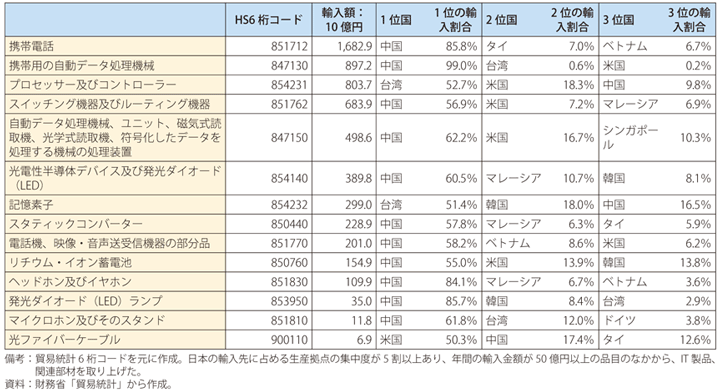
自動車分野においては、車輪は中国、バックミラーは米国、シートベルトはタイからの輸入割合が高い(第Ⅱ-1-2-29表)。
第Ⅱ-1-2-29表 日本の輸入先に占める生産拠点の集中度が5割以上の自動車、自動車部品(2019年)
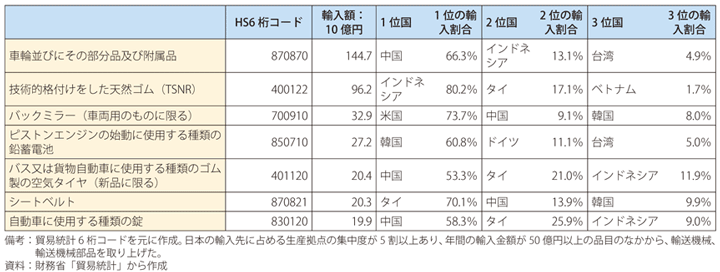
資源、ビデオゲーム、時計、衣類などでも、生産拠点の集中度が高いものが見られる(第Ⅱ-1-2-30表)。
第Ⅱ-1-2-30表 日本の輸入先に占める生産拠点の集中度が5割以上のその他の品目(2019年)
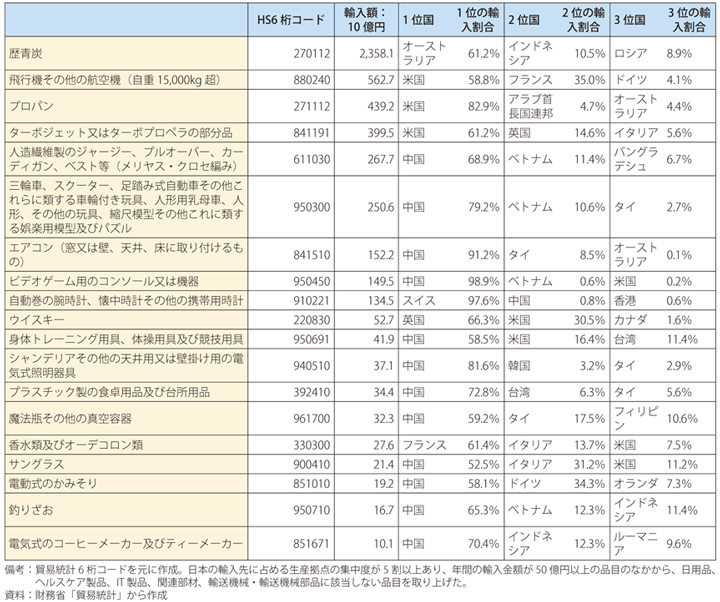
ここまでは輸入先に占める生産拠点の集中度が高い品目を見てきたが、国産品を含む総供給との比較は、産業連関表を用いて総供給と輸入を比較することにより把握することができる(第Ⅱ-1-2-31表)。
第Ⅱ-1-2-31表 日本の総供給に占める最大の輸入先国・地域からの輸入割合が高い品目(2016年)
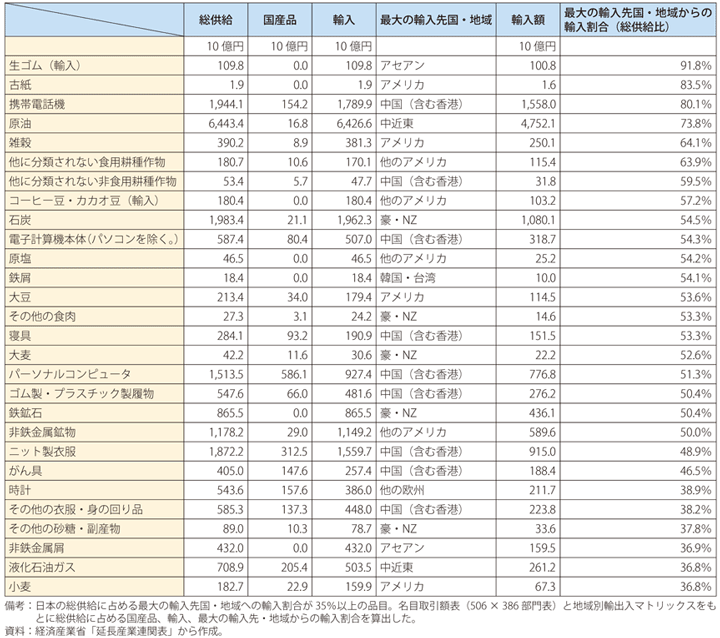
生ゴム、原油、石炭、鉄鉱石をはじめとする資源においては最大の輸入先国・地域の輸入割合が高く、雑穀、大豆、小麦など食糧分野においては米国からの輸入割合が高い。資源・食糧分野において中国からの輸入割合が高い品目は、他に分類されない非食用耕種作物で飼料を含む。
これらに加えて、中国からの輸入割合が高いのはIT製品であり、携帯電話機、電子計算機本体(パソコンを除く)、パーソナルコンピュータなど最終財が中心である。また、アパレル、寝具、がん具などの軽工業においても中国からの輸入割合が高い。
4 自動車に利用される部材は多岐にわたるが、ここでは自動車部品としてHSコード「自動車」(HS87)の下部分類である「自動車用の部品」(HS8708)を利用した。輸出入で品目構成には相違があり、日本から中国向け自動車部品輸出ではギアボックスが約7割を占め、中国からの輸入では、車輪、ブレーキ、エアバッグ、ハンドル、サスペンションが過半数となっている。
5 ラップトップパソコン、タブレットパソコンが該当する。
(2)日系現地法人の調達・販売活動と立地選択
① 製造業概観
グローバリゼーションの中で日本企業は海外展開を行っており、現地法人の活動から日本のサプライチェーンを確認することができる。そこで、以下では、中国に立地する日系現地法人の調達・販売活動に注目して分析を行う。
日本の製造業における海外生産比率は2017年度には国内全法人ベースで25.4%、海外進出企業ベースで38.7%となっている。特に輸送機械、一般機械、情報通信機械における海外生産比率が高いものとなっている。
その海外の生産拠点の中でも、企業数や売上額において中国6の存在感が2000年代に急速に高まりを見せた(第Ⅱ-1-2-32図)7。2010年代に入ってそのペースは落ち着いたものの、高い割合を維持している。こうした背景により、2020年に入り新型コロナウイルス感染が拡大する中で、日系企業の中国現地法人のサプライチェーンへの影響が見られることとなった。
第Ⅱ-1-2-32図 日系海外現地法人の立地地域別の企業数・売上額
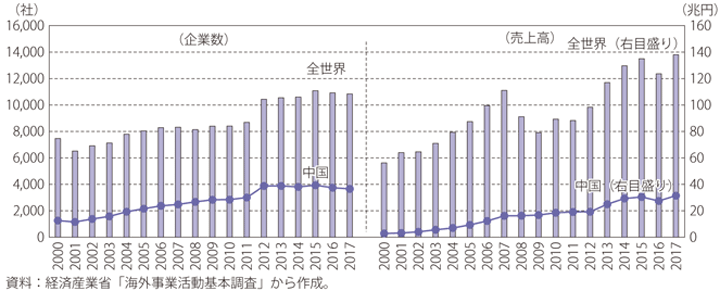
この中国も含め、世界に展開する日系製造業のサプライチェーンを確認しよう。第Ⅱ-1-2-33図は、各地域に立地する日系製造業現地法人の資材の調達先を示したものである8。中国を筆頭に、ASEAN、NIEs等のアジアに立地する日系製造業は日本との間で巨額の調達活動を行うとともに、アジア域内の第三国との間でも相互に調達を通じた結びつきが強い。その中でも中国は単独でASEAN10か国に匹敵する規模を有しており影響力が強い。図においては日本との間の販売も示しており、アジア域内からは日本に対する製品の活発な販売活動も見られる9。なお、北米、欧州に立地する日系企業も日本から調達を行っているものの、日本向けの販売は限られたものとなっている。
第Ⅱ-1-2-33図 日系現地法人(製造業)の調達活動(2017年度)
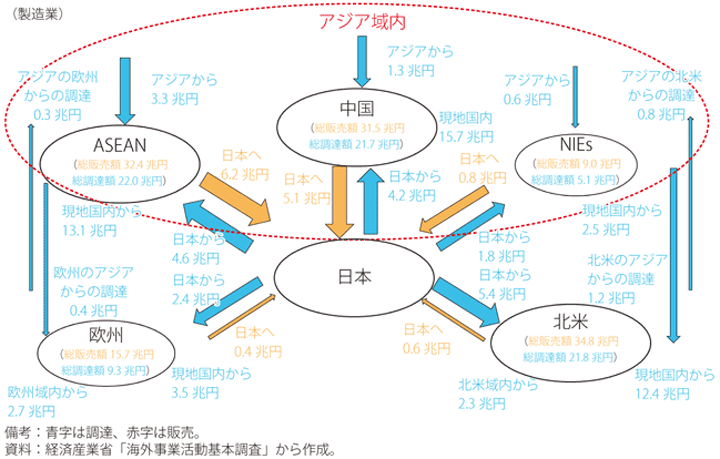
第Ⅱ-1-2-34図は、業種別に中国に立地する日系製造業の海外生産比率(横軸)、その中での中国の割合(縦軸)、在中現地法人の売上規模(円の大きさ)を示している。輸送機械及び情報通信機械の2業種が突出して海外生産比率が高く、中国現地法人の売上規模も大きいものとなっている。この2業種に焦点を当て、以下で分析を行う。
第Ⅱ-1-2-34図 日本企業の海外生産比率と中国の割合
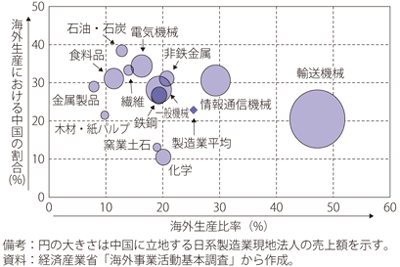
6 ここで中国とは香港を含まない中国本土を指す。以降も同様。ただし、データの関係で、一部の数字に香港を含む場合がある。
7 日系海外現地法人の分析に当たっては、経済産業省「海外事業活動基本調査」のデータを利用する。同調査は回答が義務づけられた調査ではないため、時系列推移や構造分析において誤差が生じる可能性はあるが、日系海外現地法人のデータとして貴重であることから利用する(回収率72.8% / 2018年7月調査)。
8 中国は本土のみ。ASEANは10か国ベース。NIEsは韓国、台湾、シンガポールの3か国。統計の関係でシンガポールはASEANとNIEsに重複計上されている。北米は米国及びカナダ。
9 サプライチェーン(供給網)は原材料となる資材調達の流れを意味することが多いが、ここでは日本との間の製品の販売も参考に表示した。ただし、経済産業省「海外事業活動基本調査」の統計データでは次の生産工程に使われる中間財なのか、消費・投資に使われる最終財なのか区別されていない点には注意が必要。なお、同調査は企業からのアンケート結果をもとにしているが、一部に推定が含まれている。例えば調達総額は回答が得られても、地域別内訳が記入されていない場合、回答が得られた企業のデータをもとに推定をしている。
② 輸送機械
新型コロナウイルスの感染が拡大する中で、中国に進出する日本の自動車メーカーの工場における部品不足による稼働停止や、中国から日本の工場に供給する部品の不足により日本の工場が稼働停止となる状況が見られた。
中国に立地する日系輸送機械の現地法人は総額10兆円にのぼる資材調達を行っており、現地国内のみならず、日本、アジアからも資材を輸入している(第Ⅱ-1-2-35図)。また、製品を日本へも販売しており、その中には中国に進出した日系部品メーカーが生産した部品も含まれていることが考えられる10。2020年2月に中国が全国的に行った感染症の拡大防止措置は、これらの物流の流れを停滞させ、人員の確保難と相まって工場の稼働停止の要因になったと見られる。
第Ⅱ-1-2-35図 日系現地法人(輸送機械)の調達・販売活動(2017年度)
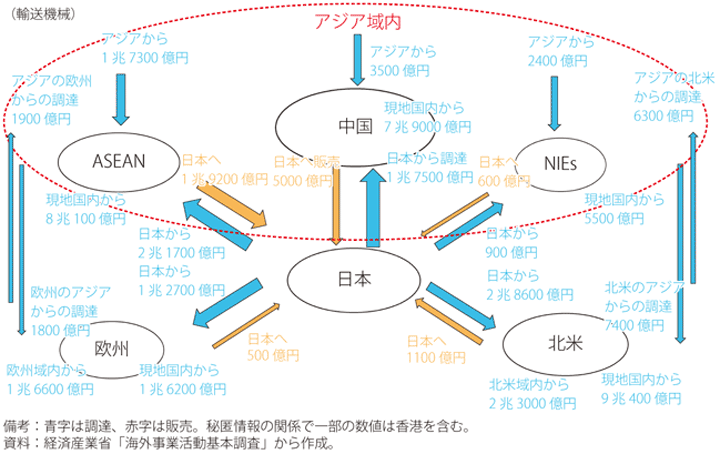
日系現地法人の調達先を詳細に見ると、総調達額の4分の3は中国国内で賄われており、現地調達が多い(第Ⅱ-1-2-36図)。輸送機械の代表的製品である自動車は、設計段階から関連会社とともに安全性など厳重な品質管理のもとに製造される「すりあわせ型」製品といわれ、部品の重量があり輸送コストがかかることも相まって、製造において組立業者の近隣に部品供給業者が立地する傾向がある。中国においても総調達額の3割弱を現地に進出した日系企業が担っている。さらに日本から約17%を調達し、残りをアジア域内等の第三国から調達する構造になっている。日本からの調達割合は必ずしも大きくはないが、主として親会社から調達するのは現地で生産していない基幹部品と考えられ、生産に不可欠であることが予想される。
第Ⅱ-1-2-36図 中国に立地する日系現地法人(輸送機械)の調達先の内訳(2017年度 / 総調達額 10.4兆円)
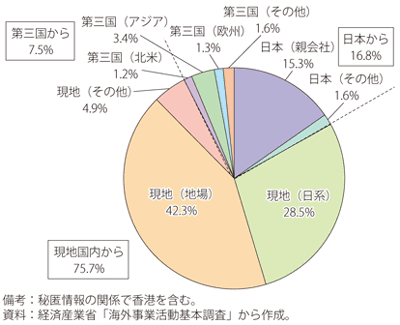
調達の推移を見ると、金額ベースでは東日本大震災のあった2011年などに一時的な減少となったことがあるものの、総調達額は増加傾向にある(第Ⅱ-1-2-37図)。調達先の地域別割合を見ると、2000年代は現地調達割合が上昇しており、地場企業の開拓とともに、日系部品供給業者の現地進出が影響していたことが考えられる。2010年代に入ってからは、現地調達比率はほぼ4分の3と横ばいとなり、そのうち、現地に進出した日系企業からの調達は3割弱で推移している。一方、日本からの調達割合は緩やかに低下しているが、全体の調達総額が増加する中で金額ベースでは一定規模を保っている。
第Ⅱ-1-2-37図 中国に立地する日系現地法人(輸送機械)の調達先の内訳
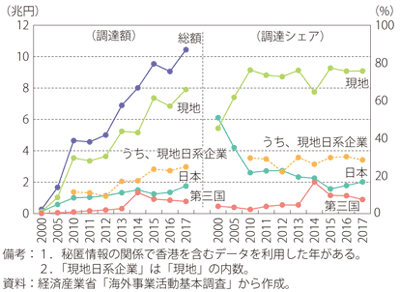
10 既に記したように、統計上は中間財と最終財の区別はされていないが、製造業企業の調達であれば生産のための資材調達が中心と考えられる。一方、販売の場合は、中間財(部品)と最終財(完成車)の両方があり得るが、後で見るように中国には多くの部品メーカーが進出しており、中国で生産した部品が日本へ輸入されていることが考えられる。
③ 情報通信機械
次に情報通信機械について分析を行う。この分野における日系海外現地法人の生産は、2000年代以降にアジア、特に中国への集中の度合いを強めている。2017年度時点で世界全体での総売上額は約13.4兆円、このうちアジアで約9.7兆円(72.9%)を占める。また、アジアの中で、中国で約4.1兆円(30.6%)、ASEANで約3.0兆円(22.2%)、NIEsで約1.9兆円(13.8%)を占める。中国の割合は2000年度の6.1%から2010年度の21.0%、2017年度には30.6%と拡大している。
第Ⅱ-1-2-38図は主要地域に立地する日系現地法人における調達・販売の結びつきを示している。日本との調達・販売の両面において1兆円を越えるのは中国だけであり、その中国に立地する日系現地法人は、アジア諸国との間で4,000億円を越える調達・販売を行っている。
第Ⅱ-1-2-38図 日系現地法人(情報通信機械)の調達・販売活動(2017年度)
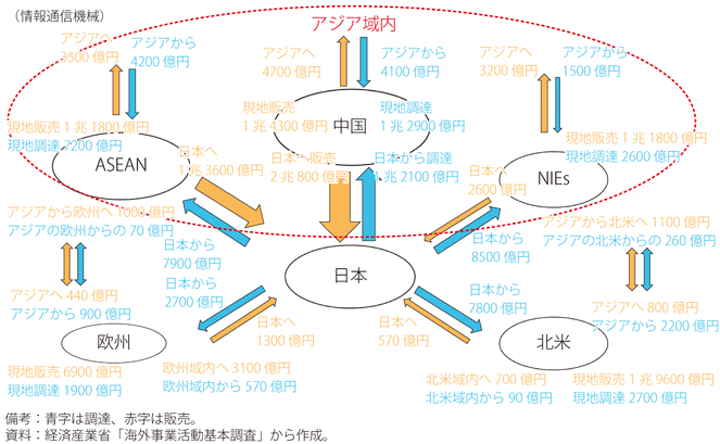
情報通信機械の日系現地法人に関しては、輸送機械と比較した特徴として、日本や第三国からの調達割合が高いことが挙げられる。この背景には、部材の重量による輸送コストの相違、輸送機械のようにすりあわせ型であるか、それとも、情報通信機械のようにモジュール型であるかなど、製品の特性による影響が考えられる。国際的な調達の割合が高いことは、サプライチェーンを通じて上流に位置する日本などへ影響が及びやすいことを示唆している。つまり、現地法人で最終製品の生産が停滞するような場合に、集積回路や画像センサーを現地法人に提供する日本国内の工場の出荷が滞る事態となりやすい。
中国に立地する日系現地法人の調達先を見ると、日本と現地国内からそれぞれ4割強、第三国(主にアジア域内)から約15%を調達している(第Ⅱ-1-2-39図)。特に日本の親会社は総調達額の約3分の1を担っており、親会社に与える影響は大きい。また、現地調達においても日系企業からの調達が半分を占めるなど、日系企業間のサプライチェーンへの影響が懸念される。
第Ⅱ-1-2-39図 中国に立地する日系現地法人(情報通信機械)の調達先の内訳(2017年度 / 総調達額 2.9兆円)
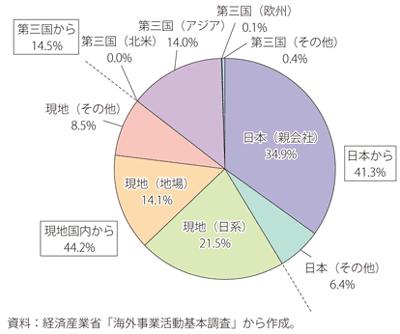
一方、販売先としては、製品の半分を日本に販売している(第Ⅱ-1-2-40図)。現地販売は売上の35%程度であるが、そのうち半分が現地の日系企業向けとなっている。この現地の日系企業向けの販売は金額ベースで約6,900億円であり、前図で見た現地日系企業からの調達額の約6,300億円と極めて近いことから、サプライチェーンに沿った現地日系企業同士での部材販売・調達が中心と考えられる。第三国向けは約14%で、主にアジア域内向けの輸出であり、北米向け、欧州向けはそれぞれ1.0%、1.6%と限られている。
第Ⅱ-1-2-40図 中国に立地する日系現地法人(情報通信機械)の販売先の内訳(2017年度 / 総販売額 4.1兆円)
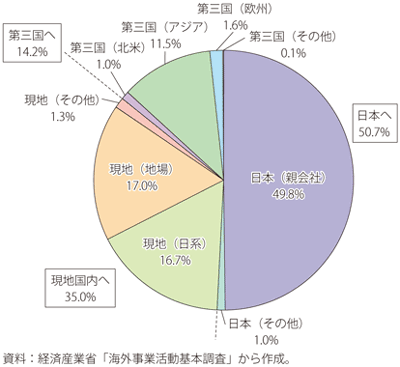
このような調達・販売活動がどのように変化してきたのかを見てみる。総調達額は、年による変動はあるものの、傾向としては増加している(第Ⅱ-1-2-41図)。調達先割合は、2010年代、現地調達比率が上昇する一方で、日本、第三国からの調達比率は低下傾向にあり、現地化が進んでいる。ただし、総調達額が増えていることから、日本からの調達も一定の規模を維持している。一方、販売先は第三国比率が長期的に低下しており、年による変動はあるものの、日本や現地向け割合が上昇している(第Ⅱ-1-2-42図)。
第Ⅱ-1-2-41図 中国に立地する日系現地法人(情報通信機械)の調達先の内訳
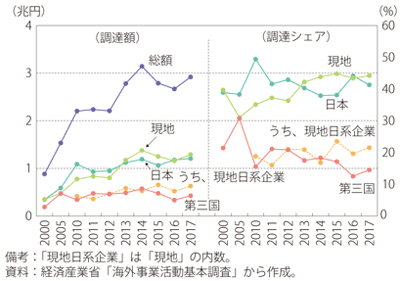
第Ⅱ-1-2-42図 中国に立地する日系現地法人(情報通信機械)の売上先の内訳
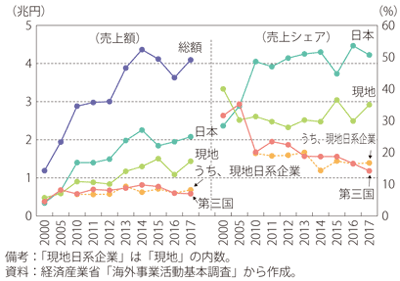
輸送機械、情報通信機械ともに、現地調達の割合が上昇しているが、その背景として、両業種とも多くの部品供給業者が現地に進出しサプライチェーンに組み込まれていることが影響していると考えられる(第Ⅱ-1-2-43図)。2017年度時点で、輸送機械は企業数ベースで立地企業の9割弱、情報通信機械は8割強が中間財を供給する企業となっている。また、これら中間財供給業者の製品は現地企業に供給されるとともに、日本に輸出されていると考えられる。
第Ⅱ-1-2-43図 中国に立地する日系現地法人に占める中間財・最終財別の生産企業の割合(輸送機械・情報通信機械)
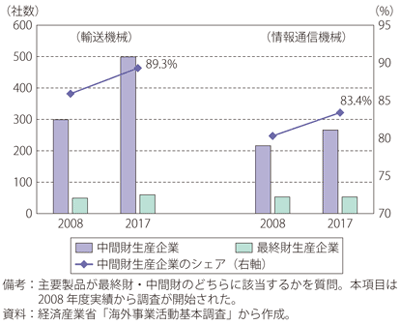
④ 配当・ロイヤリティ収入
ここまでは、サプライチェーンに沿った資材調達を見てきたが、仮に、新型コロナウイルスによる感染症のために、長期的に現地法人の活動に支障が生じることがあれば、親会社への配当金やロイヤリティにも影響が及ぶリスクがある。
世界に展開する日系製造業現地法人から親会社に支払われる配当金・ロイヤルティの推移を見ると、中国からの送金は金額ベースで拡大しており、全体に占める中国の割合も高まっている。例えば、配当金においては、2000年代初頭、中国の占める割合は1割強であったが、2017年度時点で約3割を占めている11(第Ⅱ-1-2-44図)。ロイヤルティにおいても2000年代初頭に1割にも満たなかった中国の占める割合は2017年度にやや低下したものの、約3割の水準に達している。また、ASEANに立地する日系製造業現地法人からの配当・ロイヤルティも中国に匹敵する規模に育っているものの、既に見たように中国における生産の停滞は、サプライチェーンを通じてアジアに展開する日系製造業の活動にも波及する懸念がある。
第Ⅱ-1-2-44図 日系海外製造業現地法人の配当・ロイヤリティの推移
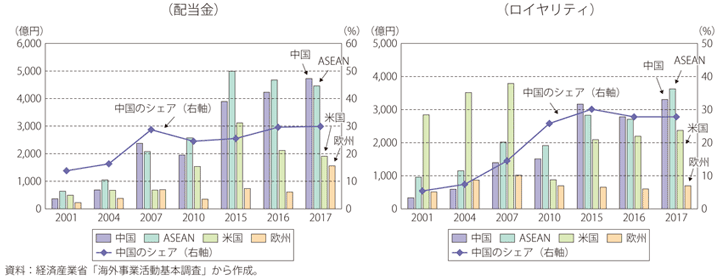
サプライチェーンが集中している場合、配当・ロイヤリティ収入においても集中が発生しやすい。特に、サプライチェーンが集中している国・地域における金融経済の環境、為替の状況、外資規制など次第で、日本の親企業における配当・ロイヤリティ収入、引いては日本の所得収支・サービス収支が上下動しやすいリスクが存在する。このため、サプライチェーンを多様化・分散化させることは、所得収支・サービス収支の安定化にも寄与する。
11 ここで配当金は日本側出資者向け支払額。日本側以外への支払いは含まない。
⑤ 日本企業の立地選択
2020年2月にJETRO(ジェトロ)が公表した「2019年度日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」(ジェトロ海外ビジネス調査)によると、今後、海外で事業拡大を図る国・地域については、「海外に拠点があり、今後さらに拡大を図る」企業のうち、中国を挙げた企業の比率が48.1%と前年度(55.4%)から後退して、2年ぶりに5割を下回った(第Ⅱ-1-2-45図)。
第Ⅱ-1-2-45図 海外で事業拡大を図る地域(日本企業)
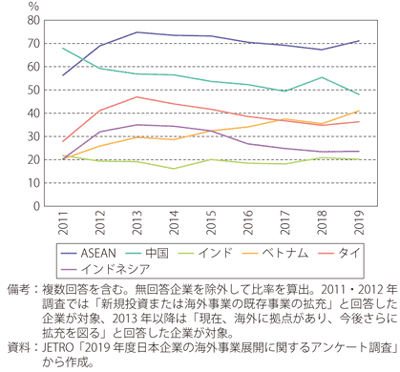
次点のベトナムは41.0%と初めて4割を超え、中国との差が縮小した。ASEAN主要6カ国合計の比率は、71.1%と6年ぶりに上昇に転じた。市場拡大への期待、輸出拠点としての役割強化に加えて、リスク回避の観点から、中国に加えてASEANで拠点を検討するといった理由が挙げられた。ASEAN主要国では、ベトナム、タイが事業の拡大を図る先の上位となる。
ASEANにおいては、情報通信機械、電子部品・デバイスをはじめ製造業、非製造業とも全般にわたり事業拡大を図るという回答の割合が上昇した。一方、中国では繊維・織物、アパレル、化学、精密機器、小売において、事業の拡大を図るという回答が低下した。
ジェトロ海外ビジネス調査においては、米中貿易摩擦など2017年以降の「保護主義的な動き」(保護貿易主義)が各社のビジネスに与えた影響についても設問を設けられており、「全体としてマイナスの影響がある」と回答した割合は20.1%と前年度比4.9%ポイント増加した。今後(2-3年程度)については、23.2%が「全体としてマイナスの影響がある」と回答した。
同調査への回答企業による「保護主義的な動き」に対応した生産移管件数(一部移管や予定含む)は計159件あり、移管先はASEANが中心となっている(第Ⅱ-1-2-46表)。移管先の国として回答が多いのはベトナム、次いでタイとなる。なお、中国への移管を実施または今後実施予定の企業も少数ながら存在している。
第Ⅱ-1-2-46表 生産移管元および移管先の国・地域(件数ベース、一部移管・予定含む)
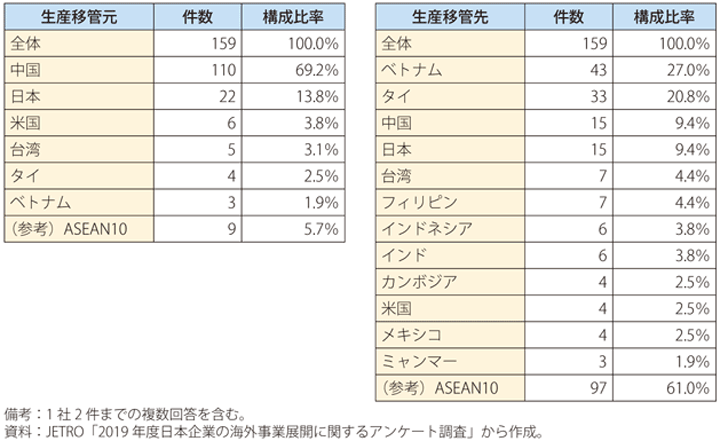
2015年に自動車部品メーカーがカンボジアに工場を建設し、2018年に新工場も建設する日本企業が見られた。2017年には大手モーターメーカーがベトナムのハノイへの投資を発表した。2019年には大手ゲームメーカーもゲーム機の生産をベトナムに一部移管した。米国IT企業もコンピューターや携帯電話の生産委託先をベトナムに部分的に切り替えると2020年2月に報じられた。
また、調達先や販売先の再編においても、ベトナム、タイへの変更が多く見られた(第Ⅱ-1-2-47表)。調達先の変更は、一般機械、自動車・自動車部品、鉄鋼、化学において割合が多く見られた。
第Ⅱ-1-2-47表 調達先の変更前および変更後の国・地域(件数ベース、一部変更・予定含む)
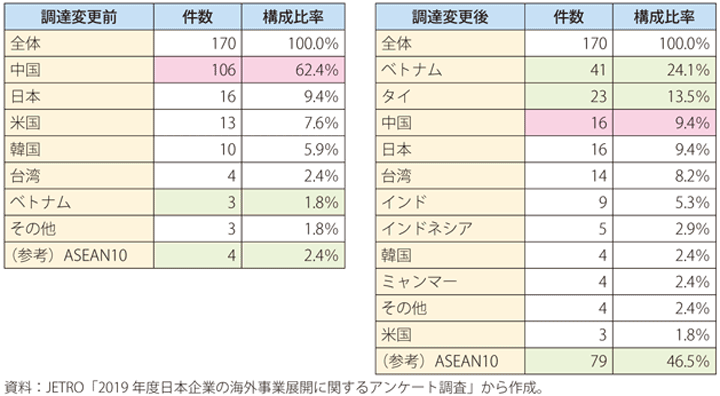
ただし、同調査では生産拠点の移管と調達先の分散化を行ったり、検討したりすると回答した企業は、それぞれ日本の海外進出企業の4~5%前後であり、必ずしも多いわけではない。
2019年6月に経済産業省が公表した「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針(グループガイドライン)」で紹介された企業の事例に、新しい地域に進出する場合に非効率を避けて拠点を一つにする一方、一つの海外子会社で異なる事業を合わせて行うように、複合的な機能を持たせるようにしているケースがある。集約と分散は必ずしもトレードオフにあるのではなく、効率性と冗長性(代替生産、調達先の多様化)が両立する多様なサプライチェーンの構築も選択肢になるものである。
3.地域統合におけるサプライチェーンネットワーク
国境を越えたサプライチェーンの構築により、世界は国際分業を発展させてきた。そのサプライチェーンの構築にあたっては、一国に閉じるものではなく、国という単位を超えた近隣諸国と密接につながったサプライチェーンも見られる。例えば、EUや北米のNAFTA、さらには日本を含むアジアは国境を越えたサプライチェーンを構築している。地域単位で見た場合の輸出入の額は、アジア、NAFTA、EUのいずれにおいても、域内の貿易が域外との貿易額を大幅に上回る(第Ⅱ-1-2-48図)。
第Ⅱ-1-2-48図 地域間と地域内の輸出入(2019年)
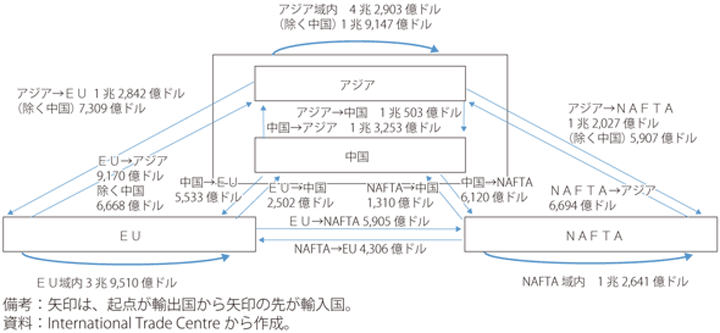
各地域でのサプライチェーンの構築が進む中で、アジアにおいては域内の輸入比率が2005年以降に拡大しており、世界貿易の拡大を上回る速度で域内貿易が拡大した。一方、EU、NAFTAにおいては、域内のサプライチェーンの構築は進んだものの、中国からの輸入が増加する中で、域内の輸入比率が低下した(第Ⅱ-1-2-49図)。電気機械、電子部品においてはアジア、中国からの輸入が増加する中で、EU、NAFTAの域内からの輸入割合が低下した。一方、アジアにおいては域内の輸入比率が上昇した。自動車、自動車部品においては、EU、NAFTA、アジアの各地域内で現地生産が進展する中、域内の輸入比率が高水準を維持しており、地域統合が域内のサプライチェーンのネットワークを強めた。
第Ⅱ-1-2-49図 EU、NAFTA、アジアにおける地域内・地域間の輸入割合
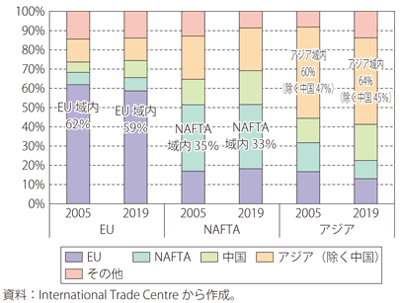
域内のサプライチェーンが発展してきた背景には、企業の最適な生産体制の構築とともに、これを後押しする経済連携の強化の流れもあった。これは企業が利益を最大化することや、経済全体として域内の成長を取り込む上で有効な手段であった。一方、今般の新型コロナウイルスの感染拡大のような危機時においては、域内サプライチェーンであっても生産工程が複雑化している中で、特定の部材の生産拠点が集中しているケースにおいては、その特定部材の生産が停止するだけで生産工程全体に影響が生じることが明らかとなった。また、医療用品や医療関連物資などについては、輸出上位の数カ国が供給の高い割合を占めることが新型コロナウイルスの感染拡大の中で明らかになった。
自国におけるサプライチェーンの冗長性の確保は、サプライチェーンが世界的に遮断される際に必要物資を確保する上で効果的と考えられる一方、自国のみであらゆる物資を確保することが可能であるわけではなく、また、自国内において災害などが生じる際に供給途絶リスクを抱えることとなる。
これらを踏まえると、域外にサプライチェーンネットワークを広げることや緊急時の供給網を確保することが有効であるとともに、域内においても更にサプライチェーンの冗長性を確保することの重要性も示唆された。
以下では、EU、NAFTA、そしてアジアにおける、地域統合としてのサプライチェーンネットワークを見ていく。
(1)EU
まず、EUの場合、単一欧州議定書やシェンゲン協定により、国境管理や加盟国間の制度の違いといった障壁が除去され、域内における労働者、商品、サービス、資本における移動の自由が確保されているという特徴がある。これはEUが経済的に統合され、単一の市場となること、さらに国境を越えたEU域内のサプライチェーンを築きやすくしたことを意味する。
EUを起点としてみた地域単位の輸出と輸入の相手先の割合を見ると、輸出と輸入のいずれにおいてもEU域内が6割前後を占めるものの、緩やかな低下傾向にある。また、NAFTAの割合は横ばい傾向にある。一方、アジア、中国からの輸入の割合は継続的に上昇しており、中でも中国からの輸入割合の上昇が顕著である(第Ⅱ-1-2-50図)。
第Ⅱ-1-2-50図 EUを起点としてみた地域単位の輸出と輸入の割合
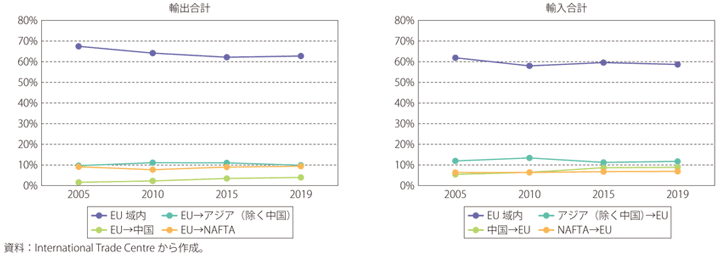
次に、EUにおける品目別地域別にみた輸入割合を見ると、一般機械、電気機械、電子部品、自動車、自動車部品、穀物、医薬品においてEU域内からの輸入割合が高いものの、紡織用繊維のその他の製品においては4割を下回る。電気機械、電子部品、紡織用繊維のその他の製品においてアジア、中国からの輸入割合が高まった(第Ⅱ-1-2-51図)。
第Ⅱ-1-2-51図 EUにおける品目別地域別にみた輸入割合
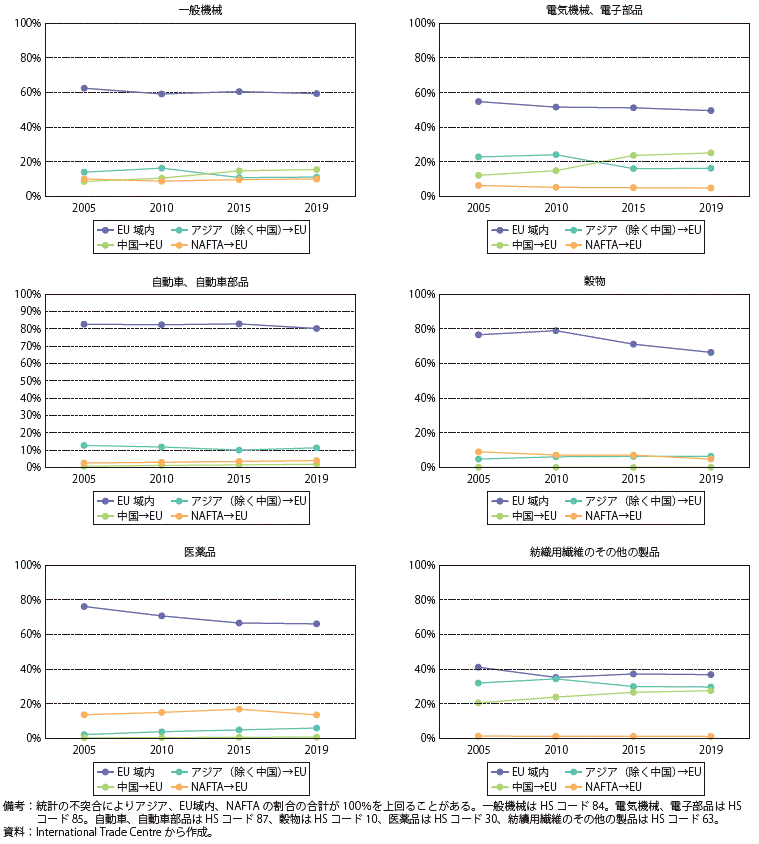
(2)北米
次にNAFTAの場合、主に貿易上の障害を取り除くものであるという性質から、EUに比べると地域統合は限定的である。他方、関税面のメリットや地理的に陸路でつながるという特徴から、域内のサプライチェーン構築を促進してきた。
NAFTAを起点としてみた地域単位の輸出と輸入の相手先の割合を見ると、輸出においてはNAFTA域内が5割前後を占めるものの、輸入においては4割を下回り、2004年以降はアジアがNAFTAを上回る割合に達し、2019年には39.8%とNAFTA(33.4%)を大きく上回る。アジアの内訳は中国が17.5%、中国以外のアジアが22.3%である。EUからの輸入の割合も2010年代に上昇し、2019年に18.2%に達した(第Ⅱ-1-2-52図)。
第Ⅱ-1-2-52図 NAFTAを起点としてみた地域単位の輸出と輸入の割合
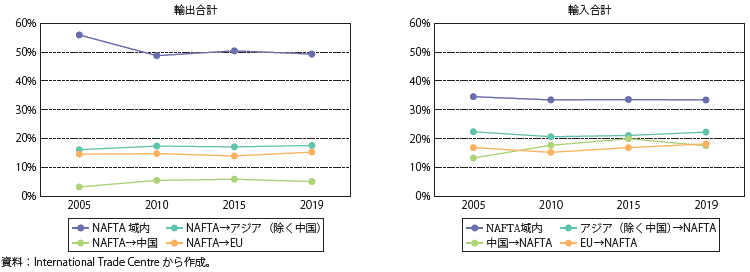
次に、NAFTAにおける品目別地域別にみた輸入割合を見ると、自動車、自動車部品、穀物においてNAFTA域内の比率が5割を上回るものの、一般機械、電気機械、医薬品、紡織用繊維のその他の製品において5割を下回る。一般機械、電気機械、電子部品、紡織用繊維のその他の製品においてはアジア、中国からの輸入割合が高まった。医薬品においては、EUからの輸入割合が高く、6割を上回る(第Ⅱ-1-2-53図)。
第Ⅱ-1-2-53図 NAFTAにおける品目別地域別にみた輸入割合
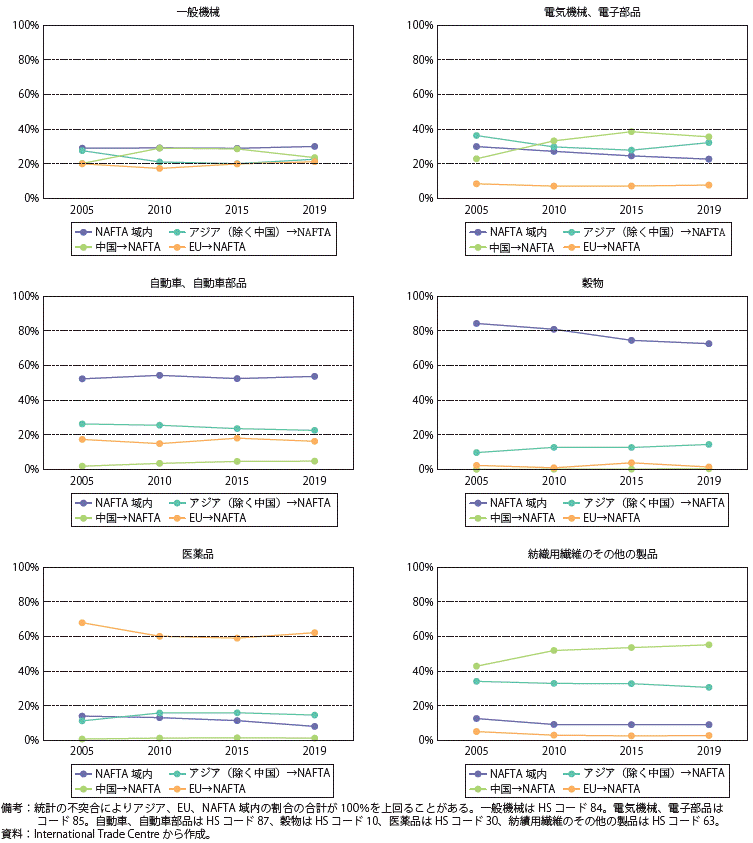
(3)アジア
アジア内のサプライチェーンの場合、ASEANを中心にした経済連携協定やTPP11協定がアジア内でのサプライチェーン構築を後押ししている一方、海を越えるという物理的な障壁が存在している。しかし、海を越えるというコスト以上に、労働コストの差が双方の国に調達コスト面や雇用の確保面という形でメリットをもたらすことがネットワーク拡大の一因ともなった。
アジアを一体としてみた地域単位の輸出と輸入の相手先の割合を見ると、輸出においてはアジア域内が56.7%と5割以上を占めるものの、43.3%は域外が占める。一方、輸入においてはアジア域内が62.4%と65%近くを占める。また、中国への輸出の割合が13.9%とアジア域内の2割強、中国からの輸入の割合が18.8%とアジア域内の3割弱をそれぞれ占める(第Ⅱ-1-2-54図)。
第Ⅱ-1-2-54図 アジアを起点としてみた地域単位の輸出と輸入の割合
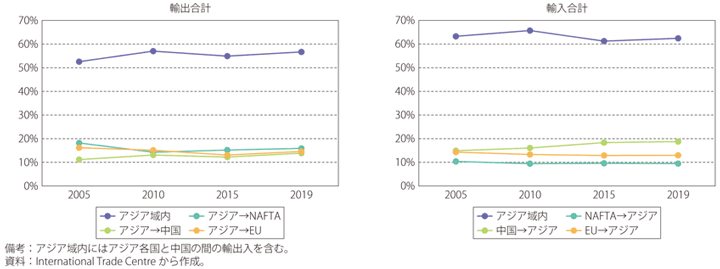
次に、アジアにおける品目別地域別にみた輸入割合を見ると、一般機械、電気機械、電子部品、自動車、自動車部品、紡織用繊維のその他の製品においてアジア域内の比率が5割を上回り、一般機械、電気機械、電子部品においてはアジア、中国からの輸入割合が高まった。一方、自動車、自動車部品と医薬品においてはEUからの輸入割合が高く、穀物においてはNAFTAからの輸入割合が高い状況が続いている(第Ⅱ-1-2-55図)。
第Ⅱ-1-2-55図 アジアにおける品目別地域別にみた輸入割合
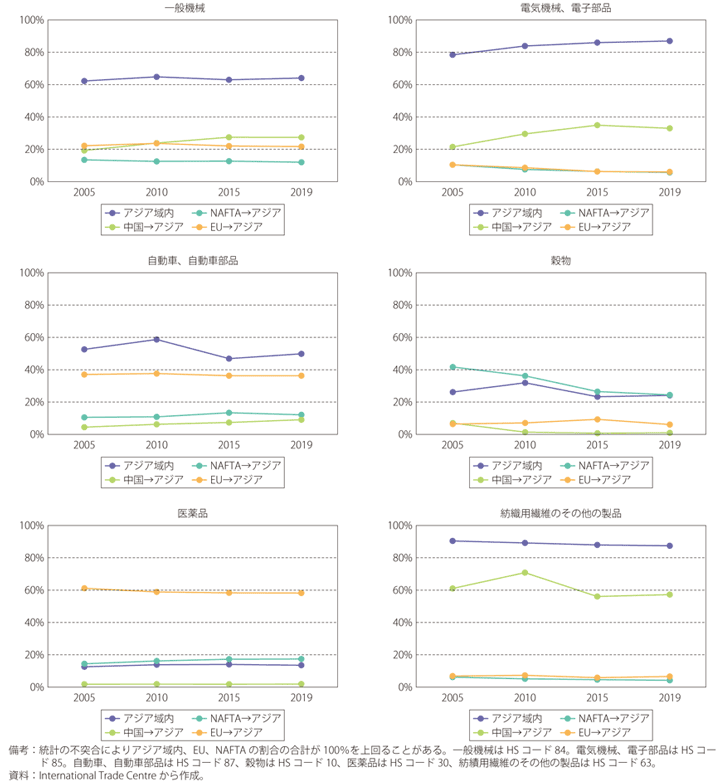
このように、域内におけるサプライチェーンが発達してきたが、新型コロナウイルスの感染拡大のような危機時においては、域内サプライチェーンであっても途絶するリスクが存在することが見られた。つまり、域内においても、サプライチェーンが配置されることが最適であるか否かは、生産体制、物流、人の移動の状況にも関係するものと言える。他方で、自国を優先するがあまり、自国の中だけにとどめることもまた非効率につながる恐れがある。
さらに、域内に留まらないサプライチェーンネットワークとしてコンピューター、電子部品、繊維製品においては、地域統合を超えて、EU、NAFTAがアジア、中国から調達する比率が高いものとなっている。また、アジア域内においても中国と中国以外のアジア域内の相互関係も強いものとなっている。新型コロナウイルスの感染拡大の中で、コンピューター、電子部品、繊維製品において域外からの物資・部品の調達が遮断される例が見られるなど、域外のサプライチェーンのリスクも顕在化した。
これらのことから、経済性・効率性と供給途絶リスクへの対応力のバランスを踏まえ、強靭なサプライチェーンネットワークを構築することの重要性が示唆されている。
