

- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2020

- 白書2020(HTML版)

- 第Ⅱ部 第1章 第3節 物流の寸断とサプライチェーン
第3節 物流の寸断とサプライチェーン
新型コロナウイルスの感染拡大に伴って渡航制限の導入や国境の封鎖が行われたことにより、陸・海・空の物流に寸断が発生した。この物流の寸断は、サプライチェーンの寸断につながり、各国の生産活動を停滞させ、その結果、貿易活動を縮小させることとなった。
物流の寸断の要因としては、まず感染の抑止のための外出制限や移動の制限が挙げられる。さらに、国境を通過する貿易においては、税関、検疫において感染の有無を確認するプロセスが導入されるなど、従来以上の時間を要する場面も存在した。物流の形態別に見れば、陸上輸送においては一部の道路・線路の封鎖、海上輸送においては一部の港湾の封鎖、航空輸送においては特に旅客機の運航数の減少が影響した。
世界の物流は、貿易量(トン)ベースでは、国際貿易の大半が海上輸送により担われている一方、貿易金額ベースでは航空運送が多く活用されている。例えば、貿易金額ベースでは、日本の場合は約4割、米国の場合は約3割が航空輸送を活用している。これは、付加価値の高い製品の生産については、国際的な分業が拡大するとともに、航空輸送の利用による運送が増加することに起因する。また、海上輸送に比べて輸送日数が短い航空輸送を用いることでジャスト・イン・タイムの生産体制の形成が促進された。
また、海上輸送や空運輸送で国境を越える前においても国境を越える後においても、トラック輸送や鉄道輸送、更に倉庫といった国内の陸上輸送を経ないと物流は完結しない。このため、経済全体で見ると物流コストの多くを占めるのは陸上輸送と倉庫である。ただし、多くの産業が様々な輸送手段を用いて資材を調達し、各産業が相互につながっていることから、陸上輸送、倉庫、海上輸送、航空輸送のいずれか一つが欠けてもサプライチェーンは混乱する。
新型コロナウイルス感染拡大の局面においては、サプライチェーンが寸断される中で、陸路や海運を回避して空輸での輸送を行うなどの代替も見られたが、それも補完的な役割にとどまるものであり、通常の物流網を維持するには至らなかった。
サプライチェーンの冗長性の観点からは、生産拠点にとどまらず、その生産拠点間を円滑につなぐことや、製品を消費地へと輸送をする物流網の把握が重要な課題として存在する。
1.新型コロナウイルス感染拡大による陸上輸送への影響
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、世界の陸上輸送は移動制限や輸送の人員不足、国境を越える検疫などにより遅延が発生することとなった。
まず2020年2月から3月にかけて、中国におけるロックダウン、高速道路の封鎖、運転手の不足などを通じて陸上輸送の停滞が見られた。国境を越える陸上輸送の停滞も発生しており、4月中旬時点でもベトナム・中国国境においてトラックが滞留する状況は継続した。
3月中旬以降には欧州、米国の各地においてもロックダウンや移動制限が行われる中で陸上輸送の遅延が見られた。欧州においては、荷物やトラック運転手の国境通過自体は認められるものの国境の検問が設けられたことにより、トラックが国境を通過する時間が長時間化した。3月上旬には平均1時間以下であった国境通過時間が、3月末には2時間超となることも見られた12(第Ⅱ-1-3-1図)。その後、国境を通過する時間は徐々に正常化に向かったものの、4月中旬時点でも、国境通過に1時間超を要する地点がポーランド国境やスイス国境において多く存在していた(第Ⅱ-1-3-2図)。
第Ⅱ-1-3-1図 欧州域内におけるトラック貨物運送の国境通過時間
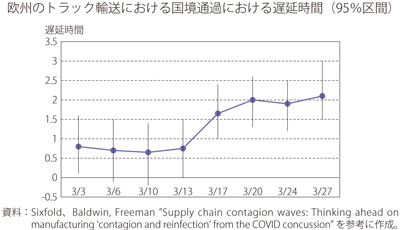
第Ⅱ-1-3-2図 欧州域内におけるトラック貨物運送の国境通過時間(3月16日時点)
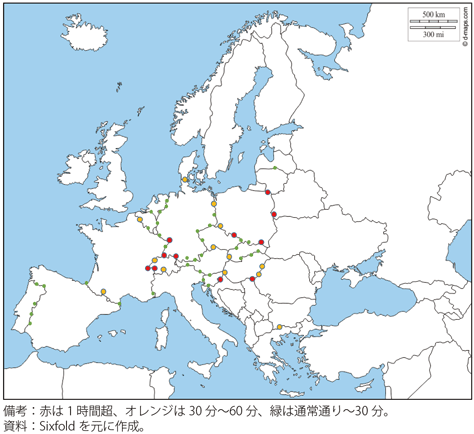
ドイツにおけるトラック貨物の走行距離数は3月後半から4月中旬にかけて減少し、4月中旬のイースター前後には前年を4割以上も下回ることとなった13。しかし、4月後半以降は、外出規制が緩やかに緩和されたことに伴い、回復に転じた(第Ⅱ-1-3-3図)。
第Ⅱ-1-3-3図 ドイツにおけるトラック貨物走行距離数
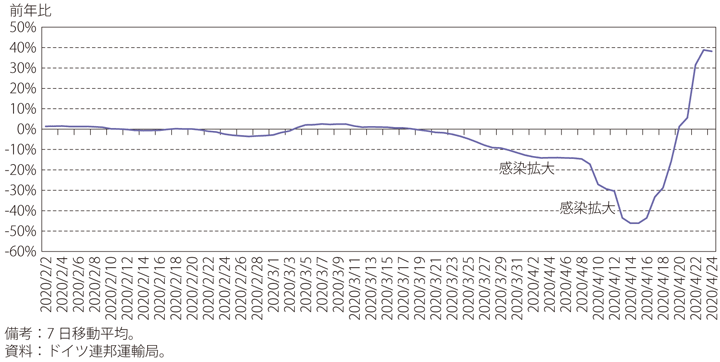
日本国内においてはオンライン消費の活性化に伴って配送需要は拡大したものの、外出自粛などに伴い経済活動が停滞することで財の運送の需要は低下し、運送業の活動の低下が見られた。電子商取引を支える宅配貨物運送業の活動指数は2月に前月比1.3%上昇し、3月に前月比3.0%上昇、4月も前月比2.2%上昇となった。一方、一般貨物自動車運送業の活動指数は2月に前月比0.4%上昇、3月に前月比0.7%上昇となったものの、4月に前月比11.2%低下した。倉庫業の活動指数は2月に前月比2.8%低下し、3月は前月比1.0%上昇、4月に前月比0.4%上昇した(第Ⅱ-1-3-4図)。このように、需要に応じて輸送の状況も影響を受けるものである。
第Ⅱ-1-3-4図 日本における陸上貨物運送業の活動指数(第3次産業活動指数)
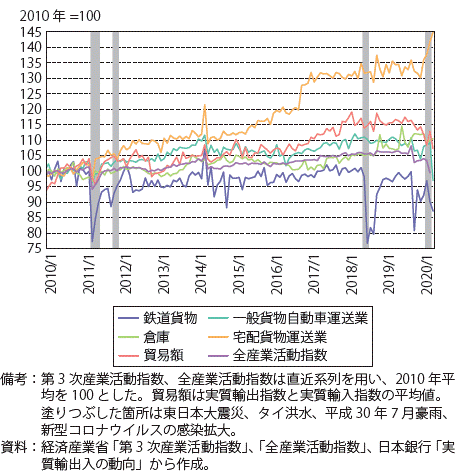
12 Baldwin and Freeman (2020)。
13 2020年4月29日付FT “European economies show early signs of post-lockdown rise in activity”。
2.新型コロナウイルス感染拡大による海上輸送への影響
世界の海上輸送は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響に伴って、需給の両面の影響を受けたことに加え、検疫強化が進められたことから海上輸送の減少や遅延が見られるようになった。また、サプライチェーン維持の観点から海運を回避し、空輸を活用することも見られた。
まず、海上輸送への影響は中国における生産の大幅な減少を受けて、中国発着のコンテナ船などの船便が減少したことに現れた。中国発の米国向けの海上コンテナ輸送量は3月には前年比で36%の減少となり、2009年2月以来の低水準を記録した14。これは、中国において生産が急減するという供給面での要因に加えて、自動車、資源、アパレルに対する需要が世界的に低迷したことも海上輸送の減少に影響を与えた。
さらに、新型コロナウイルス感染拡大への懸念から乗組員の検疫強化が進められたことも、乗組員の確保や交代が困難となったことにつながった。大型のコンテナ船やバルク船15の運行は20名以内と少人数で運行されており、大規模な感染者数が発生する事態となったクルーズ船、軍艦とは事情が異なるものの、感染拡大を防止するという動きの影響を受けたものと考えられる。なお、一部の海運会社においては、海上輸送を維持するため、乗務員の下船・交代を行わずに航行を続けるという対応を取る事例も見られた16。
検疫に時間を要することに伴い、輸送時間やコストが上昇したことから、中国でIT製品・同部品や自動車部品などを生産する企業においては、海上輸送を回避して航空輸送を行うケースも見られた。これは、一時的にはコスト増加となるものの、サプライチェーンの維持を優先した動きと見ることができる。また、中国で製造した便座を米国に輸送する際、コンテナ船での海上輸送から空輸に一時的に切り替える事例も見られた。
世界の90の港湾を対象とした4月中旬時点の調査によると、約4割の港湾においてコンテナ船とバルク船の運行が平時よりも少ない状況であった17(第Ⅱ-1-3-5図)。トラック輸送との接続に関しては、トラック輸送が停止した港湾が約1割、6~24時間の遅れが生じた港湾が約1割、6時間以内の遅延が生じた港湾が約2割、さらには生産停止に伴い船舶が荷物を積載しない状態で出港せざるを得ないケースも見られた。2020年4月の国際定期線運行数では減便数が66に上った18(第Ⅱ-1-3-6図)。
第Ⅱ-1-3-5図 世界の港湾における船舶の運行状況(平常比)に関する回答分布
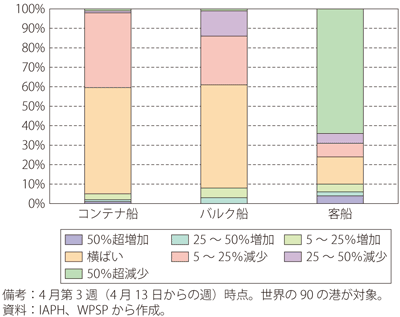
第Ⅱ-1-3-6図 2020年4月の国際定期線運行数
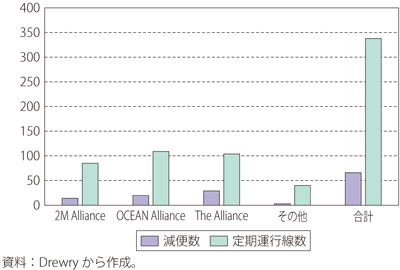
日本国内においても貿易量の減少から、外航貨物水運業活動指数は2月に前月比1.2%低下、3月に前月比2.7%上昇、4月に前月比2.9%低下となった(第Ⅱ-1-3-7図)。
第Ⅱ-1-3-7図 日本における貨物水運業の活動指数(第3次産業活動指数)
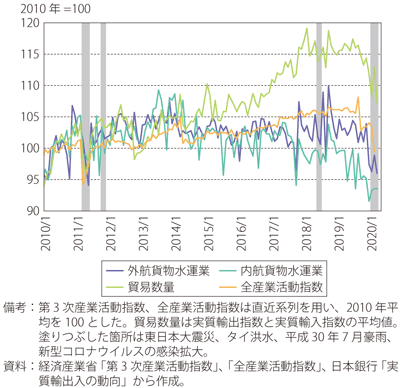
14 2020年4月10日付LNEWS “海上コンテナ輸送量/中国発米国向けがリーマン・ショック時並みに”。
15 コンテナ船は、規格化された海上コンテナにより自動車部品や衣料品などを輸送する貨物船。バルク船は、コンテナに梱包されていない鉱産物、穀物、木材などをばら積みで輸送する貨物船。
16 検疫強化の流れの中で、一部の海運会社においては1ヶ月以上に渡って交代を行わないという対応が見られた。乗務員が継続して乗船できるのは国際ルールでは最大12ヶ月とされる。
17 2020年4月16日付 IAPH-WPSP Port Economic Impact Barometer。
18 2020年4月16日付OIA Global “COVID-19: Market Updates”、2020年5月1日付 Drewry Cancelled Sailings Tracker
3.新型コロナウイルス感染拡大による航空輸送への影響
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて、3月中旬以降に世界的に旅客運行数が半減した結果、航空貨物の輸送能力の減少につながった。航空貨物の約4割は旅客機の貨物室で空輸されるため、旅客運行数が半減した結果、航空貨物輸送能力は約2割の減少となった。この結果、旅客機を用いて輸送される貨物の輸送が困難になり、航空運賃が上昇することとなった。また、移動制限や検疫強化に伴って貨物専用の旅客機の航行数自体も減少している。
世界の貿易のうち重量基準で9割強が、金額基準で7割前後を海運が担うが、付加価値の高いスマートフォン、電子部品、医薬品、医療機器は空輸されることが多い。そのため、航空貨物の輸送能力が減少しても、輸送のニーズは存在するため、運賃は上昇しやすくなる。第Ⅱ-1-3-8図に示した通り、2020年3月末には国際航空貨物量が前年比で概ね半減した19。その中で、付加価値の高い財の取引の遅延や、貨物運賃が高騰する例も見られた。特にアジア太平洋においては、運賃が3割強上昇し、欧州や北米においても運賃が2割弱上昇した(第Ⅱ-1-3-9図)20。
第Ⅱ-1-3-8図 2020年3月の国際航空貨物量
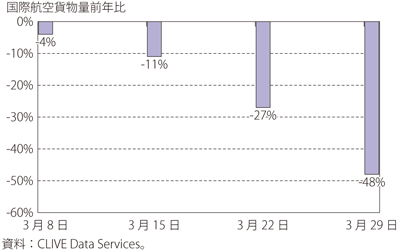
第Ⅱ-1-3-9図 2020年3月の地域別の国際航空貨物量と運賃
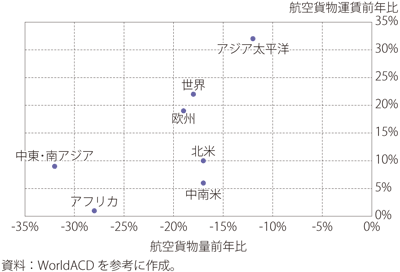
また、日本国内の輸送においても、航空貨物の減便に伴い、従来は航空輸送された農産物の種や苗がトラック輸送に一時的に切り替えられたという事例も見られた。
日本国内においては、国際航空貨物運送業の活動指数が2月に前月比4.0%上昇、3月に前月比0.3%低下、4月に前月比26.0%低下となった(第Ⅱ-1-3-10図)。
第Ⅱ-1-3-10図 日本における航空貨物運送業の活動指数(第3次産業活動指数)
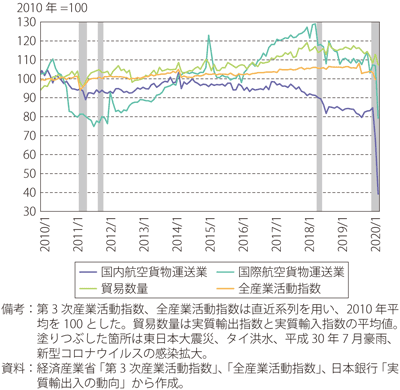
19 2020年4月1日aircargo news “CLIVE Data Services: Airfreight volumes fell 23% in March”。
20 2020年4月13日付 “March 2020: WorldACD Provisional Data – a world increasingly in lockdown, yet air cargo keeps moving”。
4.サプライチェーンにおける物流の役割
(1)各物流が有するネットワークの補完性と代替性
新型コロナウイルスの感染が拡大することにより、陸上輸送、海上輸送、航空輸送という物流において停滞が生じ、その中で、サプライチェーンの途絶が発生した。
様々な輸送手段を用いて資材の調達・製品の販売を行う中で、各産業が物流ネットワークを介して相互依存しており、陸上輸送、海上輸送、航空輸送のいずれか一つの輸送手段が欠けてもサプライチェーンは混乱することとなる21。特に、生産拠点の集中度が高まる状況においては、物流の遮断がサプライチェーンの途絶へとつながりやすい。
それぞれの物流の経路はサプライチェーンにおいて担う役割が異なっており、サプライチェーンのネットワークの中で補完性と代替性を有する。
第Ⅱ-1-3-11図は、中国からベトナムに商品をスポットで輸出する際に要する日数の事例である22。輸出においては、物流の手配、荷積みや荷下ろし、海上輸送、陸上輸送、そして通関手続き、検査などを含むプロセスが存在している。中国・ベトナム間の例では、海上輸送では輸送に有する日数が4日から5日を要するが、航空輸送に切り替えることにより輸送に係る日数自体は1日以内に短縮可能であるものの、物流の手配、荷積みや荷下ろし、陸上輸送、通関手続き、検査に要する時間はいずれの輸送手段でも必要となる。このように輸出プロセス全体を考えた中で必要な手続きは行う必要があるものの、海上輸送と航空輸送は部分的に代替関係にある。
第Ⅱ-1-3-11図 中国からベトナムに輸出する際に要する日数の事例(海上輸送)
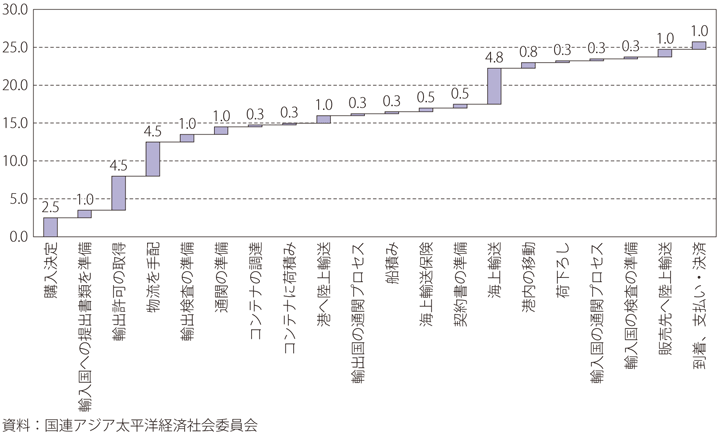
物流活動は景気との連動性も有する。第Ⅱ-1-3-12図に見るように、世界の航空貨物量と海上貨物量は、実質GDP、貿易量に連動して拡大・縮小をする傾向が見られる。また、海上貨物量は資源の取引量に連動しやすい。2000年代半ばまでは新興・途上国の高成長に伴う資源需要拡大を背景として、海上貨物量が高い伸びを示していたが、2010年代は新興・途上国の成長率が鈍化し、資源の取引量も鈍化したことから海上貨物量も低い伸びとなった。
第Ⅱ-1-3-12図 世界の航空貨物量、海上貨物量と実質GDP、貿易量(前年比)
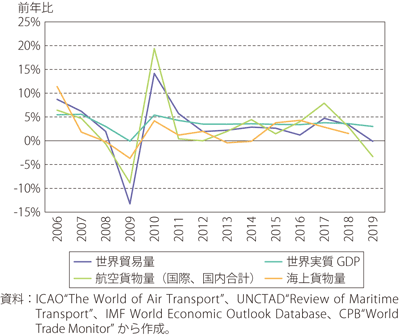
また、第Ⅱ-1-3-13図に見るように、日本の第3次産業活動指数における物流活動指数と実質GDP、貿易量の間にも連動性が見られる。航空貨物は貿易量と強く連動する傾向がある一方、トラック輸送は国内需要を反映する実質GDPと強く連動する傾向がある。
第Ⅱ-1-3-13図 日本の物流活動指数と実質GDP、貿易量(前年比)
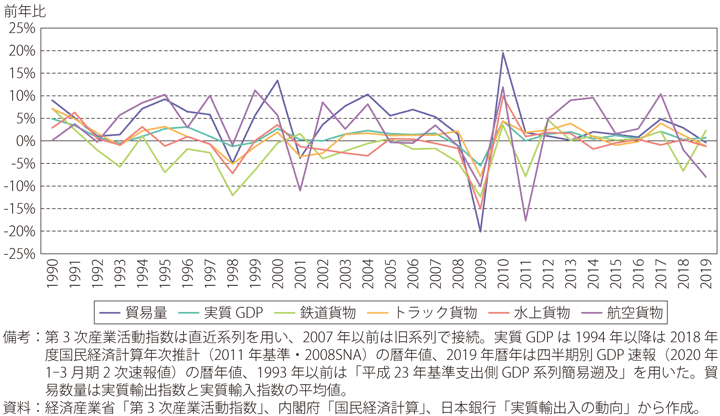
21 Diop (2020)は、幅広い物流の混乱が感染症に脆弱な国、サプライチェーンが複雑な国、都市人口比率の高い地域を中心に大きな影響を与えると整理している。
22 Duval (2015)を参考にした。
(2)各物流の補完性
日本において財の貿易活動を行う上では、海上輸送または航空輸送が不可欠である23。これに加えて、国境を通過する前段階、後段階のいずれにおいてもトラック輸送や鉄道輸送といった陸上輸送、更に倉庫での保管を経る。国内取引においても、財の特性に応じて海上輸送や航空輸送を用いるケースもあるものの、陸上輸送がより重要な役割を担う。
このように、経済活動全体における物流ネットワークの中で最も大きな割合を占めるものが陸上輸送と倉庫である。世界全体では、農林水産業・鉱業・製造業における中間投入費用全体に占める物流費の割合は4.2%に達する。このうち最も大きな要素は陸上輸送の費用であり、中間投入費用の2.7%を占める。次いで倉庫が0.7%、水上輸送が0.5%、航空輸送が0.2%、郵便が0.1%となる。
国・地域別に見ると、農林水産業・鉱業・製造業において中間投入費用に占める物流費の比率が高いのはスウェーデン(9.8%)、トルコ(8.3%)、オーストラリア(7.6%)、ブラジル(6.6%)、ノルウェー(6.3%)、インド(6.3%)である(第Ⅱ-1-3-14図)。
第Ⅱ-1-3-14図 主要国の農林水産業・鉱業・製造業における中間投入費用に占める物流費の比率
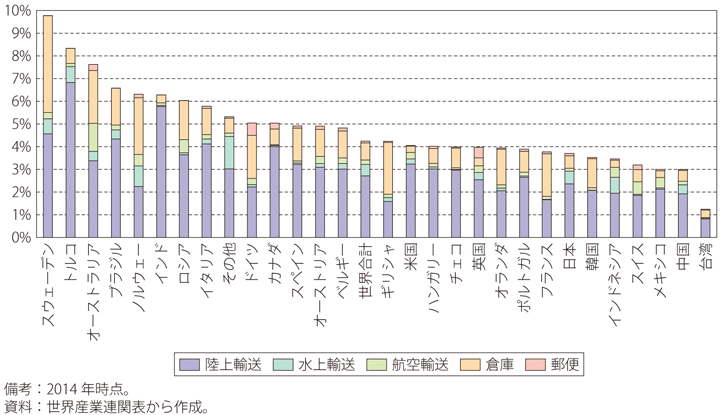
一方、農林水産業・鉱業・製造業の中間投入に占める物流の比率が低い国・地域は、台湾(1.2%)、中国(3.0%)、メキシコ(3.0%)、スイス(3.2%)、インドネシア(3.5%)、韓国(3.5%)である。
水産業の盛んな国、資源国、面積の広大な国において中間投入費用に占める物流費の比率が高く、東アジアや小国において物流の比率が低いという傾向が見られる。
世界全体における農林水産業・鉱業・製造業の各産業別に見ると、中間投入費用に占める物流費の比率が高いのは非鉄金属(6.8%)、鉱業(6.6%)、紙・パルプ(6.4%)、家具製造(6.1%)、林業(5.9%)、水産(5.3%)であり、素材産業や資源・エネルギー産業が多い。一方、中間投入費用に占める物流費の比率が低いのはコンピューター、電子部品(2.3%)、その他輸送機器(2.7%)、機械修理(3.2%)、電気機械(3.4%)、自動車、自動車部品(3.5%)である(第Ⅱ-1-3-15図)。
第Ⅱ-1-3-15図 世界の各産業における中間投入費用に占める物流費の比率(農林水産業・鉱業・製造業)
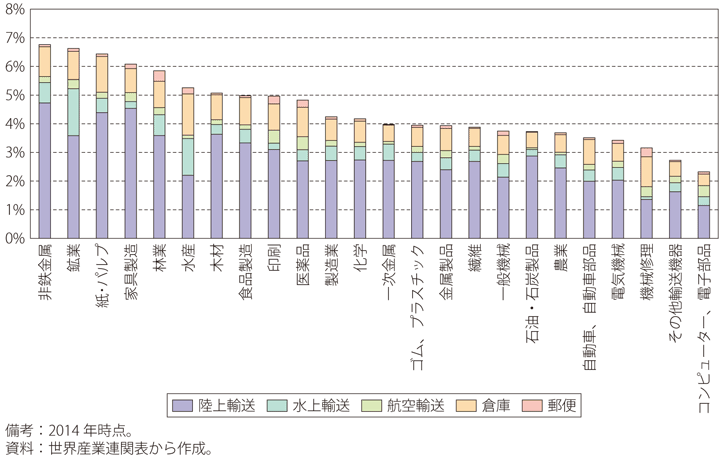
日本の農林水産業・鉱業・製造業において中間投入費用に占める物流費の比率が高いのは、非鉄金属(8.9%)、鉱業(6.7%)、印刷(6.3%)、紙・パルプ(5.9%)、農業(4.9%)、医薬品(4.9%)であり、素材産業と資源・エネルギー産業において高い点は世界と共通する。一方、中間投入費用に占める物流費の比率が低いのは自動車、自動車部品(2.3%)、コンピューター、電子部品(2.7%)、一般機械(2.9%)、電気機械(3.0%)、繊維(3.1%)である(第Ⅱ-1-3-16図)。
第Ⅱ-1-3-16図 日本の各産業における中間投入費用に占める物流費の比率(農林水産業・鉱業・製造業)
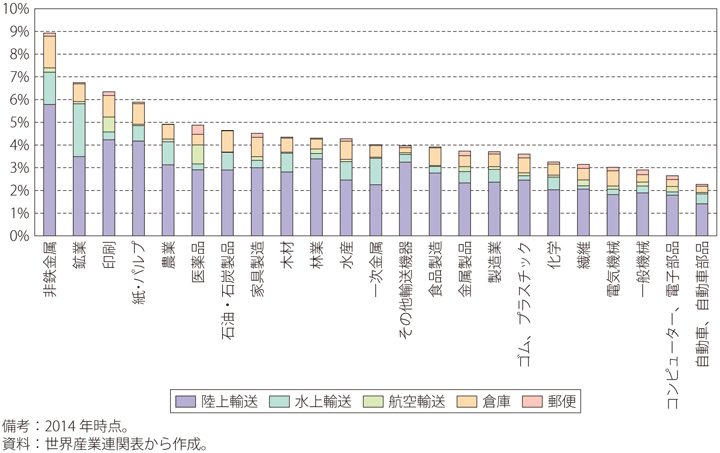
物流に伴う経済活動を評価する際には、主として、搭載する荷物の重量による評価、輸送する荷物の金額による評価の二種類が存在する。サプライチェーンを評価する上では重量、金額の双方ともに重要である。
EUにおいては、重量を基準に見た場合、国内輸送と貿易を含む全ての荷物の輸送に占める輸送手段の割合は道路(52.8%)、外航水運(30.0%)、鉄道(13.0%)、内航水運(4.1%)の順であり空輸は0.4%である(第Ⅱ-1-3-17図)。
第Ⅱ-1-3-17図 EUの荷物輸送に占める各輸送手段の割合(重量基準)
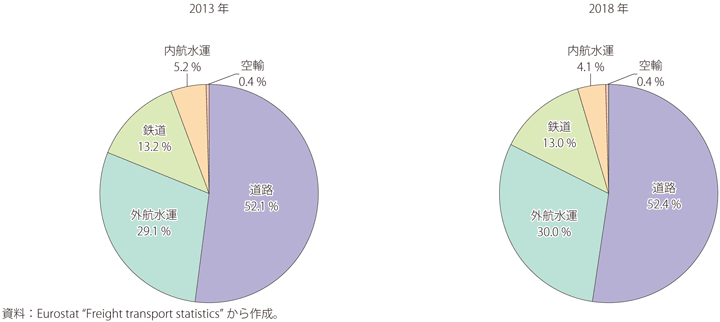
一方、EUと域外の間の貿易においては、重量を基準に見ると、外航水運(78.6%)、パイプライン(12.0%)、鉄道(3.9%)、道路(3.1%)の順に多くを占めており、空輸は0.9%に留まる(第Ⅱ-1-3-18図左)。一方、金額を基準に見ると、外航水運(50.3%)、空輸(25.5%)、鉄道(3.9%)、自走(2.4%)、パイプライン(2.3%)、道路(1.4%)の順となり、空輸が4分の1超を占める(第Ⅱ-1-3-18図右)。
第Ⅱ-1-3-18図 EUの域外貿易に占める各輸送手段の割合(左図:重量基準、右図:金額基準、2017年)
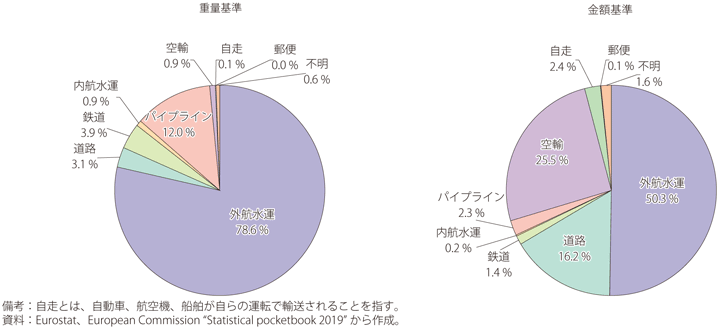
以上で見てきたように貿易量(トン)をもとに評価すると輸送の大半が海上輸送により担われている一方、貿易金額をもとに評価すると空輸の比率も大きく上昇する。貿易金額をもとにすると、日本においては約4割、米国においては約3割、EUにおいては25%強が航空輸送を活用している(第Ⅱ-1-3-19図)。
第Ⅱ-1-3-19図 各国の国際貿易における航空輸送の割合(金額基準、2017年)
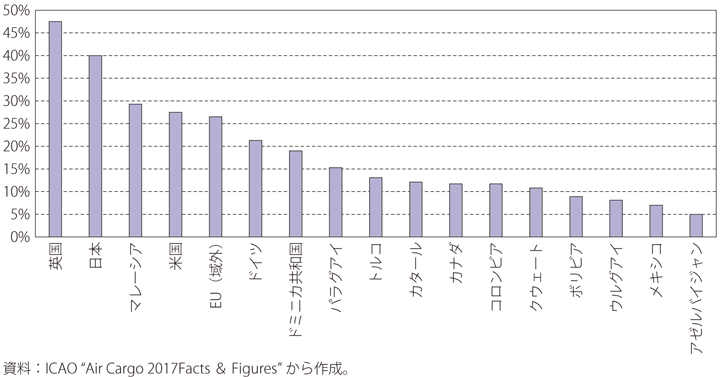
これは、付加価値の高い製品の生産にあたっては、国際的な分業が拡大していくとともに、航空輸送による運送が増加していることにも起因する。また、海上輸送に比べて輸送日数が短い航空輸送を用いることでジャスト・イン・タイムの生産体制が一段と高度化されたという側面もある。第Ⅱ部第2章第2節においては、第2のアンバンドリングに伴いジャスト・イン・タイムの生産体制が促進されたことを整理する。
日本における国内貨物輸送の分担率は、重量をもとに評価すると、トラック(91.5%)、内航海運(7.5%)、鉄道(0.9%)の順となり、トラックが9割超を占める(第Ⅱ-1-3-20図左)。これに対し、航空輸送は0.02%である。トラックの比率が高いのは、時間を問わない柔軟なサービスが可能である点、幅広い物流ニーズに対応している点、そして船舶、鉄道、航空による長距離輸送の末端輸送(ラスト・ワン・マイルともいわれる)の大半をトラックが担うことが背景にある。
一方、重量に輸送距離を乗じたトンキロに基づく分担率は、トラック(50.9%)、内航海運(43.7%)、鉄道(5.2%)、航空(0.3%)の順となる(第Ⅱ-1-3-20図右)。トンキロに基づく分担率は、2010年度前後を境に、トラックが最大の割合を維持しているものの緩やかに低下し、内航海運と鉄道が緩やかに上昇している。背景には、トラックドライバーの不足や流通業務の効率化のためのモーダルシフト24がある。内航海運は素材、資源の長距離輸送に強みがあり、トンキロ基準ではこれらの基礎素材の輸送の約8割を担う。
第Ⅱ-1-3-20図 日本における国内貨物輸送量の各交通機関分担率(重量基準:左図、重量・距離基準:右図)
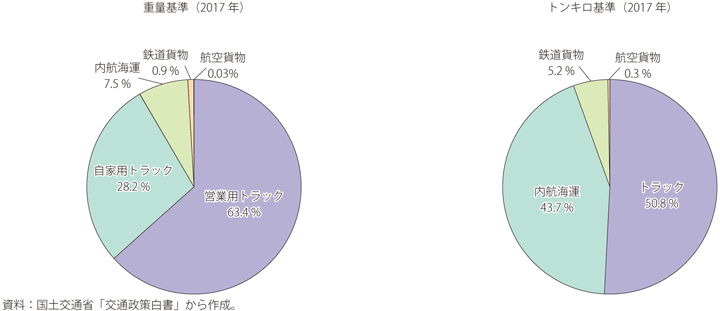
次に貿易活動における交通手段別の分担率を見ると、日本を発着する国際貨物輸送は、航空輸送と海上輸送に限られる中で、重量に基づく評価では海上輸送が全体の99.7%を占め、航空輸送の割合は0.3%である(第Ⅱ-1-3-21図右)。海上輸送は鉱物性燃料、鉄鉱石、食料品など重量の重い財を大量輸送するのに適し、重量の関係から航空輸送されることは少ない。一方、航空機は、少量または軽量で単価の高い荷物を速やかに輸送するのに適している。このように、財の特徴に応じて輸送手段は使い分けられている。この結果、貿易金額を基準に見ると、海上輸送は約6割、航空輸送が約4割を担う。
第Ⅱ-1-3-21図 日本における国際旅客(左図)と海外貿易(右図)と各交通機関分担率
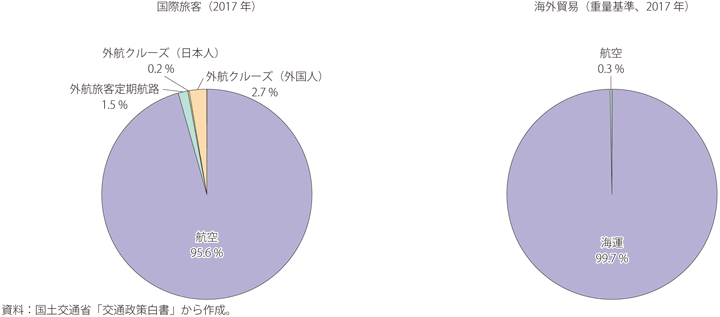
日本においては、主要地域により、貿易金額に占める航空輸送と海上輸送の比率には大きな差異が見られる。2019年の東京・大阪・名古屋における主要空港、港湾における貿易金額を比較すると、東京・横浜港においては29兆円、羽田・成田空港においては25兆円となり、海上輸送が約2割、航空輸送より大きい(第Ⅱ-1-3-22図)。一方、大阪・神戸港の貿易金額が関西空港・関西国際空港の約2倍、名古屋港の貿易金額が中部国際空港の7倍以上に達する規模であり、大きな差が見られる25。こうした差異の背景として、大阪港においては電気機器の輸出が多く、衣料品の輸入が多い点、名古屋港においては自動車の輸出が多く、化学製品と原材料の輸入が多い点が挙げられる。
第Ⅱ-1-3-22図 日本の主要空港、港湾における貿易金額(2019年)
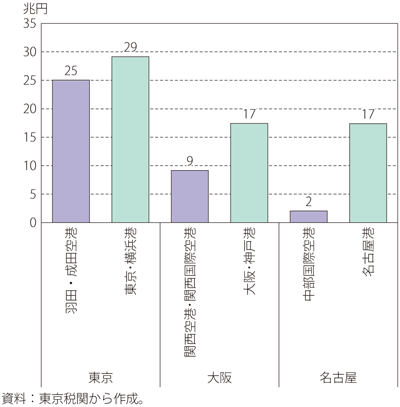
東京・横浜港と羽田・成田空港における品目別の輸出金額を比較したものが第Ⅱ-1-3-23表である。航空輸送による貿易の比率が高い品目は、半導体等電子部品(82%)、医薬品(72%)、科学光学機器(64%)、半導体等製造装置(60%)、写真用・映画用材料(56%)である。一方、自動車(0%)、原材料(2%)、紙・同製品(2%)、ゴム製品(2%)、自動車の部分品(3%)、金属加工機械(9%)においては航空輸送による貿易の比率が低く、9割以上が海上輸送によるものである。食料品(18%)、化粧品類(25%)においては、付加価値が高い品目が航空輸送されやすい傾向にある。
第Ⅱ-1-3-23表 財別の航空輸送と海上輸送の取扱金額(輸出、東京・横浜港、成田・羽田空港、2019年)
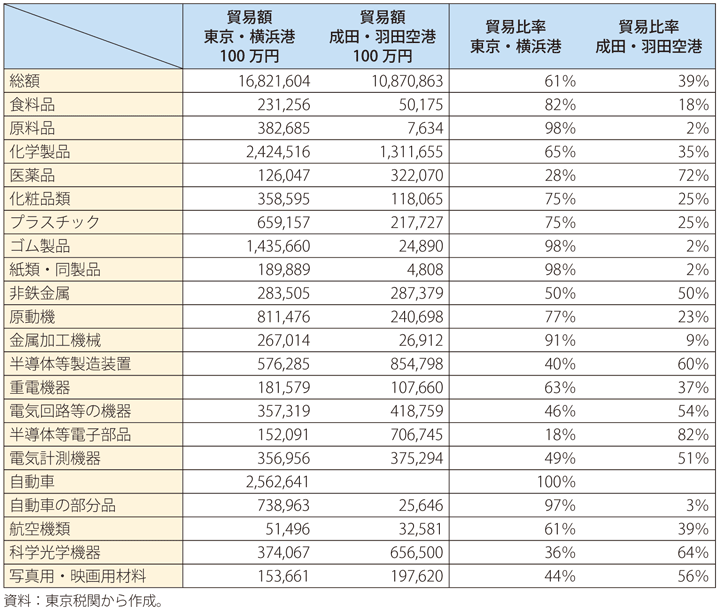
次に、東京・横浜港と羽田・成田空港における品目別の輸入金額を比較すると、第Ⅱ-1-3-24表に見るように、航空輸送による貿易の比率が高い品目は電算機類(90%)、通信機(89%)、医薬品(88%)、半導体等電子部品(88%)、事務用品(80%)である。一方、鉱物性燃料(0%)、木製品等(1%)、肉類・同調製品(1%)、食料品(4%)、紙類・同製品(5%)、家具(6%)においては航空輸送による貿易の比率が低く、95%以上が海上輸送によるものである26。他方、バッグ類(41%)、衣類・同附属品(24%)は、単価の高い品目が航空輸送される傾向にある。
第Ⅱ-1-3-24表 財別の航空輸送と海上輸送の取扱金額(輸入、東京・横浜港、成田・羽田空港、2019年)
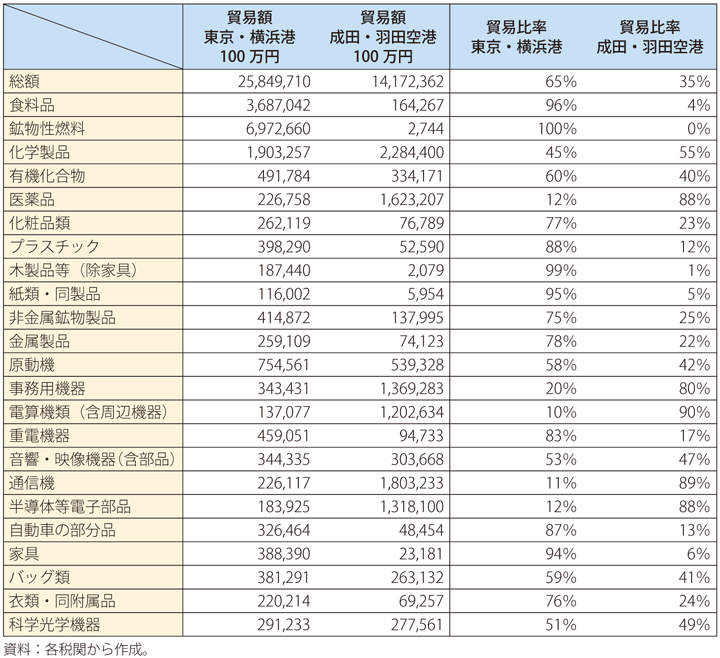
第Ⅱ-1-3-25図は、中部国際空港と名古屋港における自動車、IT製品の航空輸送による貿易比率を整理したものである。自動車の輸入に占める航空輸送の比率は0.1%であり、2019年の1年間で149台に留まる。一方、自動車の部分品の輸出入に占める航空輸送の比率は輸出において2%、輸入において9%となる。また、半導体等製造装置の輸出に占める航空輸送の比率は11%である。
第Ⅱ-1-3-25図 自動車、IT製品の空輸比率(金額基準、中部国際空港、名古屋港、2019年)
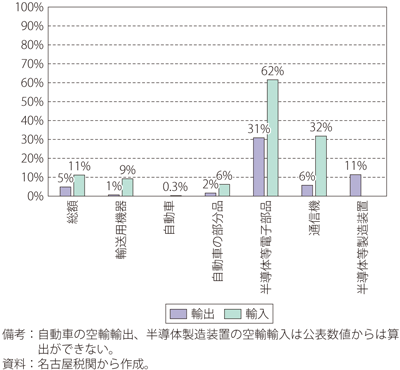
航空輸送と海上輸送の重量単価を比較すると、第Ⅱ-1-3-26表に見るように、医薬品は輸出入のいずれにおいても航空輸送の重量単価が海上輸送の重量単価を20倍から30倍も上回っており、顕著な単価の違いが存在する。原動機においても同様の傾向が見られる。自動車の輸入においては、航空輸送が1台当たり1,254万円、海上輸送が1台当たり156万円であり、ここでも8倍の差が存在する。高単価品が航空輸送されるという傾向は、ゴム製品、精油・香料及び化粧品類においても見られる。
第Ⅱ-1-3-26表 航空輸送品と海上輸送品の重量単価(中部国際空港、名古屋港、2019年)
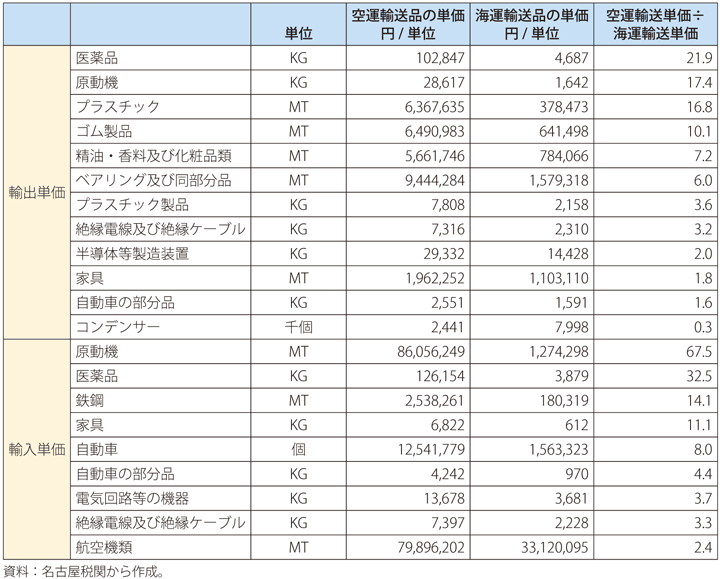
23 大陸に位置する国においては鉄道貨物輸送、トラック輸送による財の貿易も可能である
24 モーダルシフトとは、トラック等の自動車で行われている貨物輸送を環境負荷の小さい鉄道や船舶の利用へと転換することを指す。国土交通省:https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/modalshift.html![]()
25 この三地域においては、海上輸送が貿易金額の64%、航空輸送が貿易金額の36%を占める。
26 自動車の海上輸送による輸入は公表資料に掲載されていない。
(3)代替輸送経路
陸上輸送、海上輸送、航空輸送のいずれの輸送手段も欠かせないものである。国内物流においては、「ラスト・ワン・マイル」を担うトラック輸送の比率が非常に高い。貿易においては、重量を基準にした場合は海上輸送の比率が99%超と非常に高い一方、付加価値の高い財を空輸することから、貿易金額を基準にした場合は海上輸送の比率が低下し、航空輸送の比率が主要先進国において2割から4割前後と高いものである。
これまで見てきたように、各輸送手段が扱う財にはそれぞれ異なる特性があるため、輸送手段の代替可能性は財の特性や状況に応じて異なる。例えば、災害や感染症が発生するような緊急時において、海上輸送を航空輸送で代替することは、少量または軽量で付加価値の高い財、緊急性の高い物資においては可能であるものの、鉱物性燃料や自動車など重量の重い財や大量の輸送は困難であり、全てを代替することは難しい。また、感染症に伴い航空機の運航が制限される場合や減少する場合においては、航空輸送自体が限られる状況となる。
一方、航空輸送を海上輸送で代替することは、物理的には可能であるものの、アジア・米国間で1ヶ月前後から1ヶ月超、アジア・欧州間で2ヶ月前後を要するため、長距離間の輸送の場合には緊急の代替輸送手段には適しにくい。日本においては、第Ⅱ-1-3-27表に見るように、災害のたびに様々な代替輸送を実施してきたものの、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界大の物流網の混乱とその中での代替輸送は、過去の事例とは異なるものであった。このように、サプライチェーンのレジリエンシーを高めるためには、物流面の精緻な把握も重要な観点となる。
第Ⅱ-1-3-27表 災害時の代替輸送
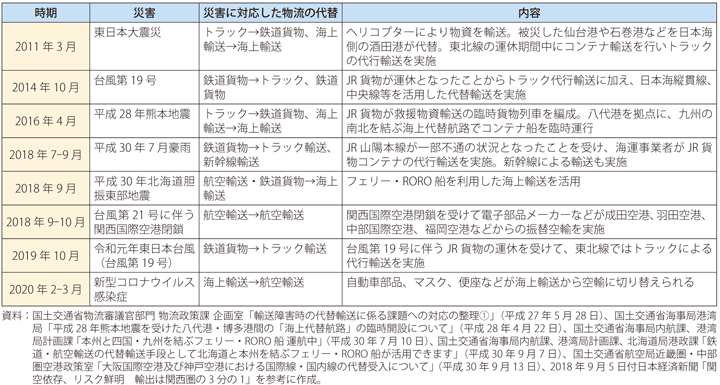
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う物流の混乱に直面する中で、日本においても海上輸送と航空輸送の間で代替の兆しも見られる。日本の輸入は2月に前年比で14%減少し、中でも中国からの輸入が前年比47%の減少と半減した。こうした中で、東京港と成田空港の輸出入を比較すると、第Ⅱ-1-3-28図右に見るように、東京港の輸入は2月に前年比で24%の減少と急減し、3月も前年比で3%の減少と減少が継続した。とりわけ、東京港における中国からの輸入は2月が前年比で54%の減少、3月が前年比で15%の減少と大幅な減少が見られた。一方、成田空港の輸入は2月に前年比で2%の増加、3月も前年比で4%の増加と東京港に比べると安定して推移している。一方で、成田空港における中国からの輸入は、2月には前年比で29%の減少となったが、3月は前年比で34%の増加となり、急回復を示した。
第Ⅱ-1-3-28図 東京港と成田・羽田空港の輸出入金額
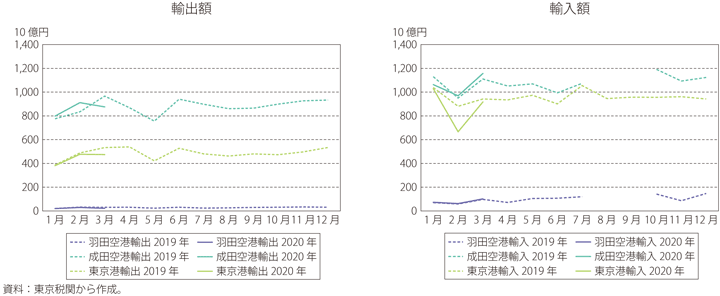
次に輸出入における航空輸送の比率が上昇した品目を第Ⅱ-1-3-29図に示している。さけ・ます、原料品、事務用機器、電算機類の部分品、通信機、がん具類においては、2月と3月に輸入に占める航空輸送の比率が2ヶ月連続で上昇した(第Ⅱ-1-3-29図右)。金属製品、自動車の部分品の輸入に占める航空輸送の比率は2月に上昇したものの、3月には低下した。輸出においては、無機化合物、半導体等製造装置、電気計測機器において輸入に占める航空輸送の比率が2ヶ月連続で高まった(第Ⅱ-1-3-29図左)。
第Ⅱ-1-3-29図 輸出入における航空輸送の比率が上昇した品目(2020年1~3月、東京港、成田・羽田空港)
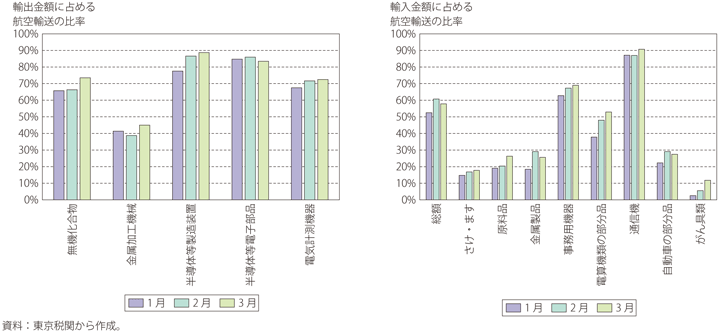
他方、輸出入における航空輸送の比率が低下した品目を第Ⅱ-1-3-30図に示した。輸出においては化粧品類、原動機、半導体等製造装置、電池、コンデンサー、事務用品において、輸入においてはアルコール飲料やICにおいて航空輸送による比率が低下することとなり、海上輸送の比率が上昇した。
第Ⅱ-1-3-30図 輸出入における航空輸送の比率が低下した品目(2020年1~3月、東京港、成田・羽田空港)
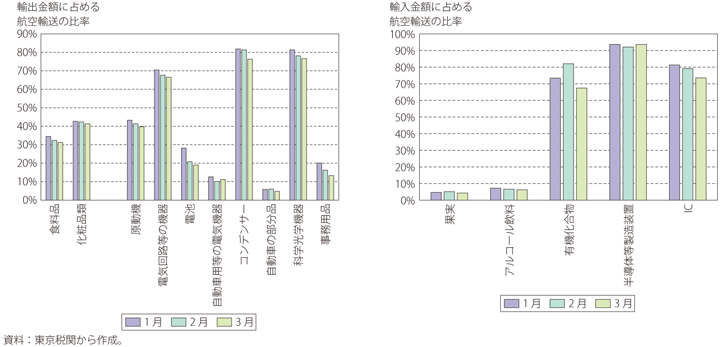
これらの変動は、輸出入業者が輸送手段を変更したという側面もあれば、いずれか一方の輸送経路が遮断されたために結果的に比率が動いたという側面もある。これらは緊急時におけて、サプライチェーンの中で物流の代替が見られた例であった。
以上で見たように、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う国境内外における物流の停滞は、国内取引と貿易活動の双方を収縮させる要因となり、貿易活動を縮小させた。特に、新型コロナウイルスの感染拡大が生じる前に、人の移動が活発であり、サプライチェーンの中で特定の財の生産拠点が集中した状態であるほど、物流が遮断されることによる影響が大きなものとなった。
こうした中で、一部の企業においては、サプライチェーンを維持するために代替手段や代替経路により輸送するケースも見られた。レジリエントなサプライチェーンの構築を今後進めていく上でも、生産拠点の集中度の高まりに対処することに加えて、安定的な物流ネットワークを維持すること、緊急時には代替輸送経路を確保することは重要となる。日本の物流企業においても、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う社会環境の変化を踏まえて、国内外の物流施設に関する統廃合、増設などの拠点の再配置、製造業の生産拠点の地域的分散と地産地消への対応、物流施設内の機械化・自動化の加速を検討し始めるという動きが見られている。
柔軟で多様な物流を国内外において確保することは、レジリエントなサプライチェーンの構築に貢献するものである。
