

- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2020

- 白書2020(HTML版)

- 第Ⅱ部 第1章 第4節 国境を越える人の移動と都市への集積
第4節 国境を越える人の移動と都市への集積
グローバリゼーションが進展する中で、国境を越えた人の交流が行われることにより世界経済は大きく発展してきた。人の交流の拡大、都市への人の集積を通じて、様々な知も同時に集積し、それが相乗効果を発揮することでイノベーションの創出や生産性の向上といった恩恵を生み出してきた。さらに、国境を越える人の移動が増加することで、国際的なビジネスが発展し、貿易や投資の活発化にもつながった。
このように人の交流の拡大はこれまで経済的な便益をもたらしてきた一方、新型コロナウイルスという感染拡大の局面においては、この自由な人の移動が世界的な感染拡大の要因ともなった。感染拡大を抑止するために世界各国において渡航制限や移動制限が課されることとなったが、これにより世界は経済活動の停滞、貿易や投資の停滞に直面している。
さらに新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、物理的なフェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションが制限されたことで、フェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションのコストの上昇という課題も生じた。これは今後の人の交流のあり方にも影響を及ぼし得るものである。
1.国境を越える人の移動の拡大や停滞がもたらす影響
(1)国境を越える人の移動の拡大と人口の都市への集中
グローバリゼーションの中で国境を越えた人の交流が進む中で、国境を超える人の移動は増加を続けてきた。
その一つである移民は増加基調にあり、過去20年間で5割ほど増加し、2019年には2.7億人に上る(第Ⅱ-1-4-1図)。世界の人口に占める移民の割合も上昇を続け、世界の人口の3.5%を上回る。その中でも特に、過去10年間の移民人口の増加については、高所得国(先進国)への移民が大部分を占めている(第Ⅱ-1-4-2図)。
第Ⅱ-1-4-1図 移民の数(ストック)と世界の人口に占める割合
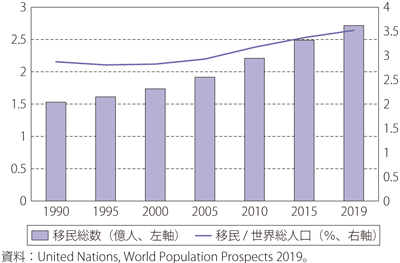
第Ⅱ-1-4-2図 移民の数(フロー)
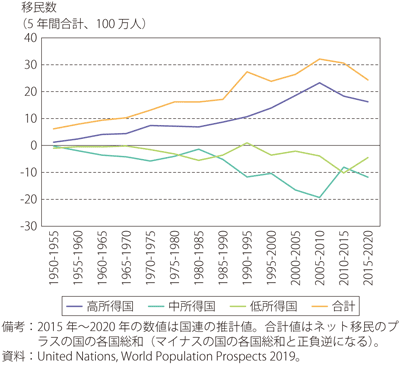
国境を越える人の交流には、観光や出張を含む旅行者もある。世界の旅行者数は増加を続け、2019年には15億人に達し、1980年の5倍を超える水準に拡大した(第Ⅱ-1-4-3図)。同期間に世界の人口は44億人から77億人と1.7倍に増加する中で、人口増加のペースを大きく上回って旅行者数は増加してきた。世界の人口比でも20%に迫り、1980年(5%強)に比べて4倍弱の水準に拡大した。
第Ⅱ-1-4-3図 国境を越える旅行者(億人)
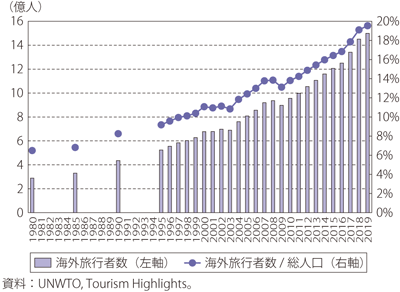
このように、国境を超える人の移動の増加の中で、人口の都市の集積が発生しており、現在、世界の人口の半数以上が都市部に居住している(第Ⅱ-1-4-4図)。
第Ⅱ-1-4-4図 世界の人口の推移
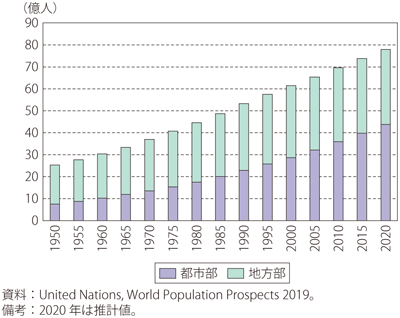
都市によって人口に占める外国人比率は異なるが、国全体よりも都市部での外国人比率が高くなり、外国人が都市部に集中する傾向がある(第Ⅱ-1-4-5表)。移住者の多くは、職を求めて外国に移住しているため、雇用機会の多い都市部において外国人比率が高くなりやすく、これは、国境を越えた人の移動に伴って都市部に人が集積をする側面の一つである。
第Ⅱ-1-4-5表 アジアの主要都市における外国人比率
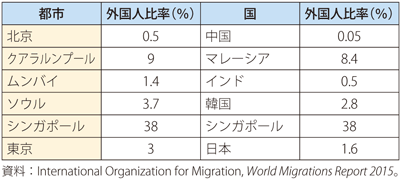
これは、都市の生産性の高さを反映したものである。都市部は地方部に比べて生産性が高く、所得水準も高い。人口の集中により多様なサービス業を営むことが可能となることで新規雇用やイノベーションの創出にもつながり、それがさらに生産性向上と所得上昇をもたらすという好循環が生じ、ますます都市への集中が生じる。
このような国境を越えた人の交流と人口の都市部への集中には、様々な要因が作用することで集積が強化されるものとなっている。例えば、イノベーション産業の地理的な集積が見られる一方、多様な人の交流がイノベーションにつながるという側面も存在する。その結果として、都市においては人の集積が加速する状況が見られる。
集積が進むほど生産性が高まる要因の一つはサービス業の生産性にある。サービス業の多くには、提供するサービスの地理的範囲が限られるため、人口密度が重要となる。人口密度が2倍になると日本においては生産性が10%上昇する27。具体的には映画館や小売店は人口密集地において効率性が高くなる。さらに創造力を要する専門サービス部門でも多様な人の交流を通じて生産性が上がる効果が見られる。
このように国境を越えた人の交流の拡大と平行して都市が人の交流の場として発展することで、イノベーション産業の企業の競争力が高まり、集積効果が発揮され、労働市場の厚みが増し、イノベーション産業のためのインフラが整い、そして、知識の伝播が促進され、経済成長が促されてきた。
27 森川 (2008)
(2)国境を越える人の移動と貿易・投資
①世界貿易と旅行者数
国境を越える人の交流が拡大する中で国境を越える経済活動も活発化され、貿易や投資が活性化してきた。これは、人の交流が拡大する中で、物や資金の交流も拡大してきたことを意味する。その要因としては、情報効果が存在する。情報効果とは、日本に来る外国人が増加すると、日本製品がその外国人の出身国内で紹介され、日本からの輸出が増加する、または、その国の製品が日本で紹介されて日本の輸入が増加するといったものである。同様に、直接投資は見知らぬ土地に対して行われるものではなく、人の移動があるからこそ促進されるものであり、人の移動の効果として直接投資が行われる。
まず、国境を越える人の交流と貿易の関係を確認しよう。1990年以降を見ると、世界のGDPに占める貿易の比率と世界人口に占める海外旅行者数の比率はともに上昇している。
世界のGDPに占める貿易の比率は1980年の38.7%から2000年に51.1%、2010年に57.1%、2018年に59.4%と上昇基調にある。また、世界人口に占める海外旅行者数の比率についても、1980年の6.5%から2000年に11.1%、2010年に13.8%、2018年に19.1%と上昇している(第Ⅱ-1-4-6図)。
第Ⅱ-1-4-6図 世界のGDPに占める貿易の比率、世界人口に占める海外旅行者数
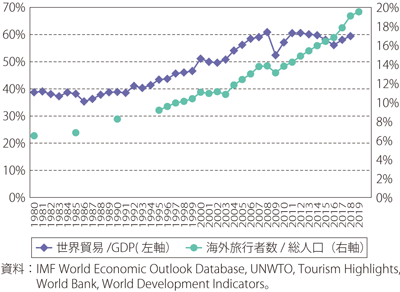
この状況に変化が見られるようになったのは2010年代である。世界のGDPに占める貿易の比率は、スロー・トレードと表現されるように伸び悩みを見せた28。これに対し、世界人口に占める海外旅行者数の比率は世界金融危機時を除いて一貫して上昇してきた(第Ⅱ-1-4-7図)。
第Ⅱ-1-4-7図 世界のGDPに占める貿易の比率と世界人口に占める海外旅行者数の相関関係
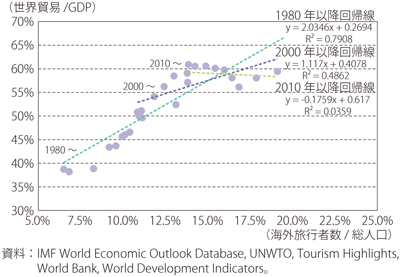
海外との人の交流を地域ごとの出入国の観点から見ると、2010年代に出入国数の伸びが輸出入ほどには鈍化しなかった要因としては、EUとアジア太平洋、新興国における出入国の増加が考えらえる。
入国においてはEU、アジア太平洋(除く中国、日本)、日本、その他地域(トルコ、インド、アラブなど)において入国者数が増加した一方、中国、EU、アジア太平洋(除く中国、日本)、その他地域(インド、アルゼンチン、ウクライナ、イスラエル)において出国が増加していた(第Ⅱ-1-4-8図)。
第Ⅱ-1-4-8図 世界の輸出入と出入国の変化率と主要国・地域の寄与度(2000年代・2010年代)
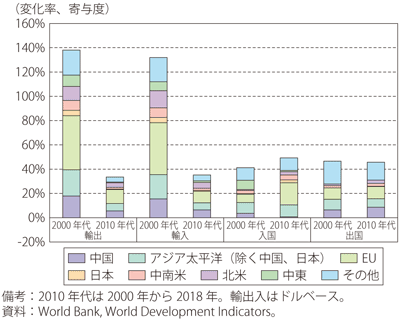
出入国の増加とは対照的に、輸出入については、EUとアジア太平洋、新興国において2000年代と比べると、2010年代は伸びが減速した。
主要国の輸出入と出入国数の動きを国別に見ると、2000年代と比べると、2010年代には貿易活動と国境を越えた移動の連動性は低下をしている。主要先進国においては、入国者数が大きく増加した一方、貿易活動は緩やかな拡大に留まった。一方、中国においては、出国者数が大きく増加したものの貿易活動は緩やかな拡大に留まり、2000年代に増加した入国者数が横ばいに転じた。
このように、世界全体で見た貿易活動と国境を越えた人の交流は2000年代半ばまで拡大し、世界金融危機後に停滞することとなった。この背景には、新興国において所得水準の上昇により旅行・貿易の双方に対する需要が増加するものの、世界では景気後退により旅行と貿易の双方に対する需要が減ったことがある。
さらに、構造的な要因として、先進国や中所得国においては、経済の成熟化とともに財よりもサービスに対する消費の比重が高まることで、貿易活動と国境を越えた移動の連動性を弱めるものとなる。
第Ⅱ-1-4-9図 主要国の輸出入と出入国数
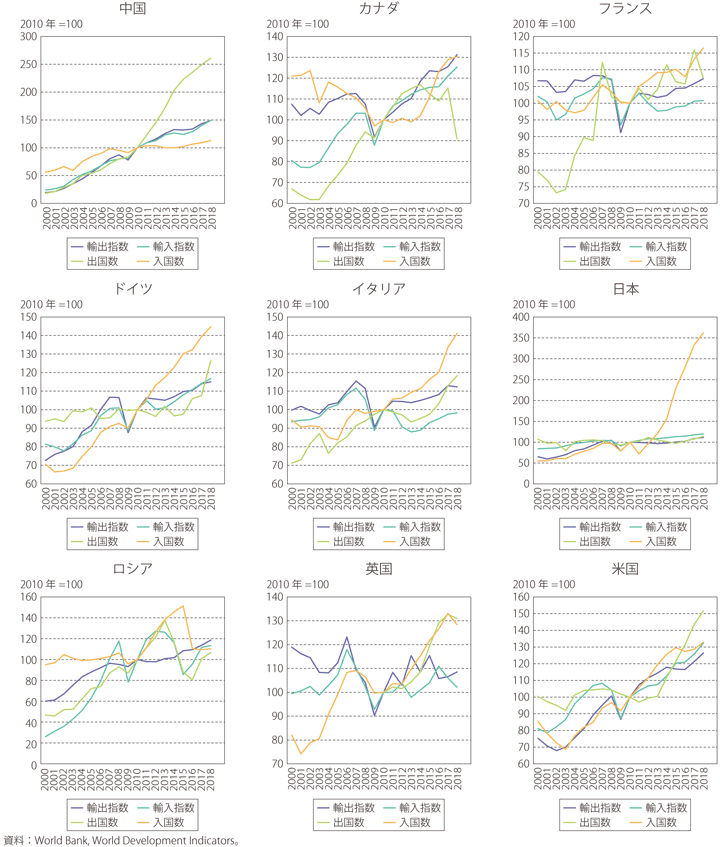
次に、国境を越える人の交流と海外直接投資の関係を見よう。人の交流の拡大と資金の交流はともに増加の傾向にあり、世界人口に占める海外旅行者数と海外直接投資残高のGDP比は、いずれも長期的に増加傾向にあった(第Ⅱ-1-4-10図)。しかし、世界人口に占める海外旅行者数と海外直接投資フローのGDP比の連動性は2010年代に入り薄れている。
第Ⅱ-1-4-10図 世界の対外直接投資のGDP比、世界人口に占める海外旅行者数
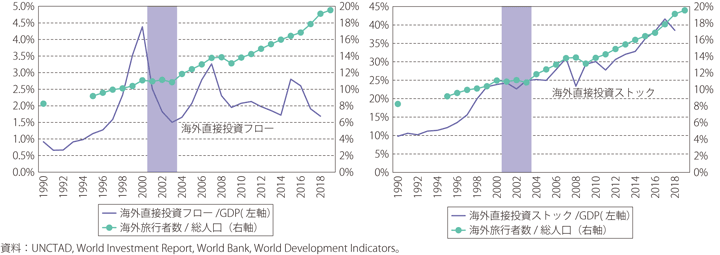
新興国・途上国を中心に、二国間の人の移動と直接投資が連動する傾向が見られる。その要因としては、企業による出張が存在する。これは、直接投資を行い、工場を立ち上げるといった場合においても、現地に人材を派遣するなどにより直接投資の実行の過程で人の交流が必要となるためである。
一方で、先進国においては、出張以外の旅行需要の拡大、ビデオ会議などによるフェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションを代替するデジタル技術の進展により、国境を越える人の交流と海外直接投資の関係は薄まりつつある。2000年代前半時点にはビデオ会議を導入する企業は少なかったが、ビデオ会議の普及が進み、出張を代替する効果が強まっている。ビデオ会議システムを提供するZoomの利用者は出張が24%減少するという効果が見られる。国際出張協会(Global Business Travel Association)によれば、出張市場と観光客数は同様の伸びを示してきたものの、新型コロナウイルスの感染拡大により2020年の出張市場は5割以上の減少が見込まれている。この出張の減少を代替したのがビデオ会議の増加であり、マイクロソフト社傘下のSkypeは1日当たりの利用者数は2020年3月には前月比で7割増加し、約4,000万人に達した。
28 一例として、 “The Global Trade Slowdown: Cyclical or Structural?” IMF working paper.
②日本と世界各国の二国間での旅行者数・在留者数と貿易・対外対内直接投資
次に、日本における国境を越えた人の交流と貿易・投資の関係を見よう。日本への訪日客数が多い国に対して、日本からの輸出額が大きい傾向が見られている(第Ⅱ-1-4-11図)。その一方、訪日客数の増加と日本への対内直接投資残高の関係は見られていない。なお、物理的な距離が近い国の間ほど貿易や観光が活発化しやすいという傾向もある29。
第Ⅱ-1-4-11図 国別の日本への訪日外客数と日本の輸出、対内直接投資(2018年)
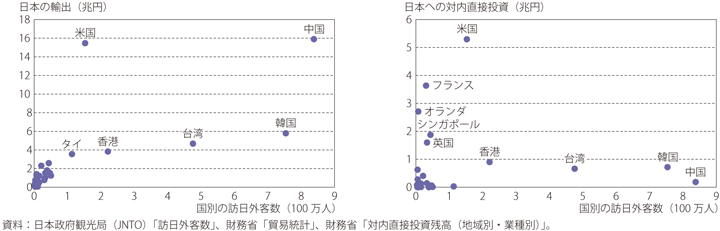
次に、国別の日本在留人数30と日本の輸出・輸入の関係を確認する。日本への在留人数が多いと日本の輸出入が大きいという関係が見られるものの、対内直接投資との関係は明確ではない(第Ⅱ-1-4-12図)。なお、観光客や貿易と同様に、在留人数も二国間の距離の影響を受ける。
第Ⅱ-1-4-12図 国別の日本在留人数と日本の輸出・輸入、対内直接投資(2018年)
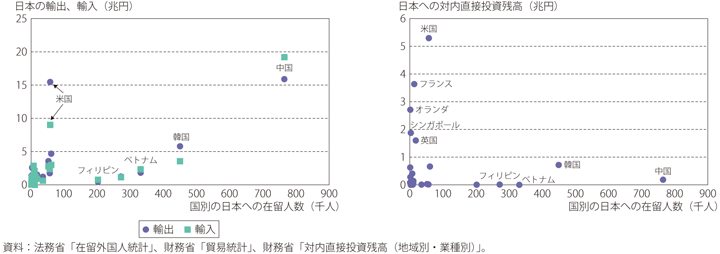
日本人による旅行や在留での海外移動と貿易(輸出・輸入)・対外直接投資との関係としては、日本からの出国者数が多いと日本の当該国への輸出、当該国からの輸入が大きいという傾向が見られるものの、対外直接投資とは明確な関係は見て取ることができない(第Ⅱ-1-4-13図)。また、第Ⅱ1-4-14図のように、国別の日本人の在留人数と日本の輸出・輸入の関係はあまり見られないものの、日本人の在留人数と日本の対外直接投資が連動する傾向も見られる。直接投資によって設立された海外の日系企業現地法人に駐在するために在留人口が増加することが一因である。つまり、日本企業の海外進出に伴い日本人の海外駐在員も増えるために、日本人の海外在留人数と対外直接投資は連動してきた。しかし、日本企業においても外国人の雇用が増え、海外現地法人の社員の大多数が現地外国人となっている31。
第Ⅱ-1-4-13図 国別の日本からの出国者数と日本の輸出入、対外直接投資(2018年)
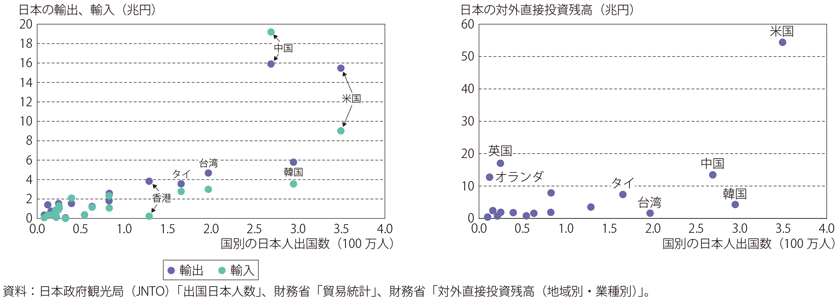
第Ⅱ-1-4-14図 国別の日本人の在留人数と日本の輸出・輸入、対外直接投資(2018年)
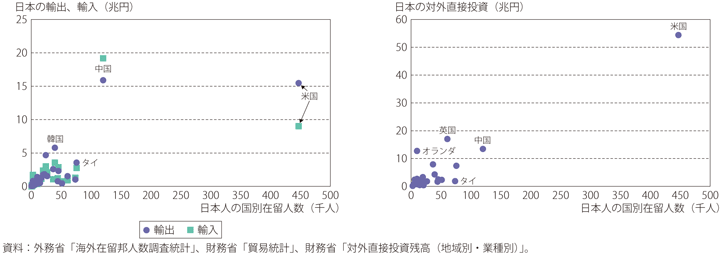
29 二国間の距離と二国間貿易の関係はAnderson and van Wincoop (2003)、二国間の距離と観光の関係はCuliuc (2016)で検証されている。
30 海外国籍を持ち、日本に在住する労働者、家族、留学生など。
31 外務省「海外在留邦人数調査統計」によると、海外に滞在している日本人の数(在留期間3カ月以上の長期滞在者と永住者)は2005年10月の101万2,547人から2017年10月には135万1,970人と34万人弱の増加となり、同期間に、日本人の民間企業従業員は21万7,315人から46万3,700万人と25万人弱の増加となった。これに対し、海外事業活動基本調査によると、日本企業の海外現地法人における常用雇用者数は2005年度の436万523人から2017年度には595万2,854人へと150万人以上増加した。このことから、現地法人では外国人の雇用の増加が進んでいることがわかる。
(3)国境を越えた人の交流の停滞と貿易・投資の停滞
このような国境を越えた人の交流の拡大が、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の要因ともなった。そこで、感染拡大を防ぐために国境を超える人の移動を制限するという措置が講じられた。
この人の移動の制限は、貿易のコストの増加を意味する。近年の貿易のコストの推移を見ると、1996年から2014年の間に世界の貿易のコストは15%前後低下しており、移動の時間や費用は低下傾向にあった32。
関税、輸送費、言語の要素が含まれる貿易コスト指数は、特に先進国間において低いものとなっている。水準を見ると、米国・カナダ間、フランス・ドイツ間において世界平均の3割強と低水準である(第Ⅱ-1-4-15図)。一方、その変化に注目すると、新興国・途上国において低下が進んできた。米国・中国間の貿易コストは1995年から2015年の間に世界の平均を約3割上回って大きく低下した。
第Ⅱ-1-4-15図 貿易コスト
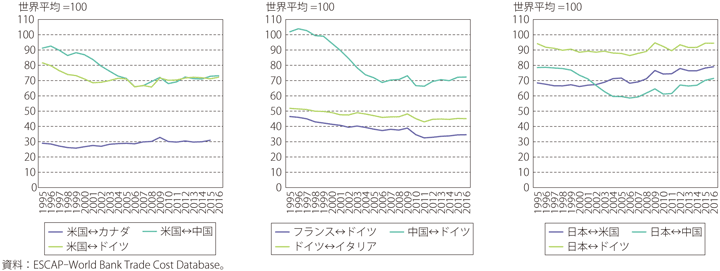
輸出に要する日数は、高所得国において、2005年の14日から2014年には12日と2日減少した。一方、中高所得国においては2005年の26日から2014年には20日と6日減少した、低所得国においては2005年の45日から2014年には37日と8日減少するなど、貿易にかかる時間の短縮は新興国・途上国において顕著に進んだ(第Ⅱ-1-4-16図)。ウルグアイにおいては、通関プロセスに要する時間が10%短くなると、輸出が3.8%増加するという関係が見られる33。
第Ⅱ-1-4-16図 輸出にかかる日数
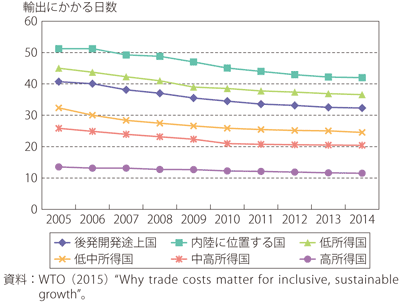
貿易コストの中で最も見えやすい要素の一つが移動時間である。中国からタイに向けて海上輸送で輸出する場合に要する日数を例にすると、20前後のプロセスを経るために合計で23日半を要する。このうち、海上輸送は5日半を要するが、陸上輸送、検疫、検査などに要する時間は18日であるように、海上輸送それ自体の時間の3倍強の長さとなる。
貿易コストに占める割合は、まず関税コストが0%から10%となっている。非関税コストについては、ICTサービスの利用に伴うコストが6%から7%、規制が6%から7%、海上輸送が16%から18%となっていることに加え、貿易手続き、非関税障壁、通貨変動リスクなどに伴うコストが全体の52%から57%を占める。また、地理的・文化的要因に伴うコストが10%から30%を占めている(第Ⅱ-1-4-17図)。このように、貿易にかかる時間、コストのいずれにおいても、大半は海上輸送や関税ではなく、検疫、検査などの手続きとなっている。
第Ⅱ-1-4-17図 貿易コストの内訳
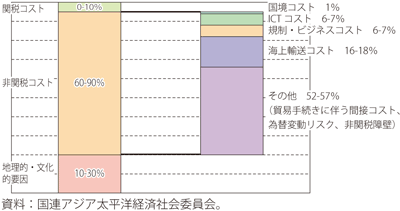
このように、貿易コストの低下が見られてきた中で、人の移動が感染を拡大させることから、人の移動の制限が見られるようになっている。その結果、前節で見た検問による輸送時間の上昇のように貿易のコストの上昇につながっている。そして、貿易や投資の大幅な停滞が生じている。
32 WTO (2018)。
33 Martinicus et al. (2015)。
2.都市における感染症の爆発的拡大
人と人との接触に伴って感染が拡大する新型コロナウイルスは、都市部において集中的に感染が拡大した。都市部においては、人口密度が高く、公共交通機関が発展し、高層ビルが乱立するように、人と人の接触が起こりやすく、新型コロナウイルスの感染が拡大した。新型コロナウイルスの感染拡大後は、社会的隔離政策が実施され、ロックダウンにより都市の機能を制限し、人と人との対面での交流の機会が限定される都市も多く見られた。
第Ⅱ-1-4-18図 米国の州ごとの新型コロナウイルス感染率と人口密度
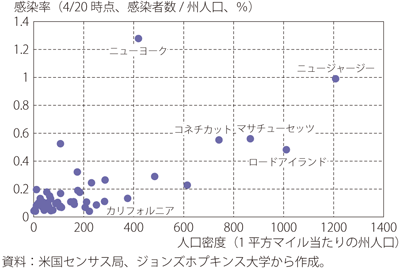
現在、世界で最も感染が拡大をしている米国においては、人口密度の高い地域ほど感染率が高い傾向が見られている。ニューヨーク州知事のアンドリュー・クオモは4月2日のツイッターにおいて、「密度が未だに高い、それは未だに非常に危険である」と述べている。
クオモ知事は同様に、ニューヨークは世界からの観光客が多い点についても要因として指摘している。このように、都市において世界の人が交流することは多くの便益をもたらすものであったが、フェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションが多く行われるが故に、新型コロナウイルス感染拡大のリスクが高いものでもあった。
第Ⅱ-1-4-19図 米国の在宅勤務とフェイス・トゥ・フェイスの業種
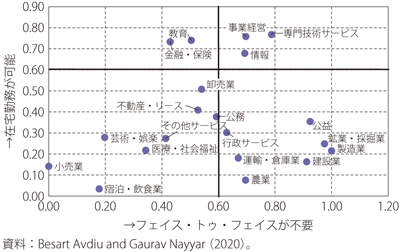
米国以外の国においても、ロンドンやパリ、ミラノといった大都市での新型コロナウイルスの感染拡大が見られている。
このような新型コロナウイルス感染拡大は、物理的なフェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションのコストを上昇させるものである。店舗の営業の制限にとどまらず、社会的距離の確保の政策を実施することで店舗への入店制限を行うことも見られる。また、顔と顔を合わせて行うビジネスについても制約が加わっている。このように、多くの産業に影響が見られている。
このフェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションの制限による影響を評価する方法として、自宅での業務による代替が可能かどうか、物理的なフェイス・トゥ・フェイスの接点が必要かという2つの基準から行うことができる。
米国シンクタンクのブルッキングス研究所の研究によれば34、在宅勤務が容易であり対面での交流がそれほど必要ではない業種がある。例えば、専門的、科学的、技術的なサービスについては自宅から提供することができ、物理的な対面でのやりとりをほとんど必要としない。一方で、宿泊業や食品サービス業、小売業は対面での交流の必要性が強く、医療も同様である。
この2つの基準の一つのみが影響する業界も見られる。製造や建設の作業は自宅で行うことはできないものの、フェイス・トゥ・フェイスは比較的限定的である。他方で、教育サービスは在宅勤務にも適するものではあるが、対面での交流も重要である。
このように、業種ごとにフェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションの必要性については異なる特徴を有している。また、在宅勤務を行うことが可能であっても、対面での交流が限定される場合には通常通りの業務遂行やサービス提供が可能であるが、生産性に悪影響を及ぼすことが考えられる。教育はWebベースのアプリケーションを使用して講義を提供できるものの、授業の質に加え、生徒が集団生活の中から人間関係を学ぶ機会の低下につながる可能性がある。
外出が可能となった場合においても、サービス業などのフェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションが重要である産業においては、消費者がレストランや店舗を訪れることに心理的な不安を有し続ける可能性がある。そのため、感染症の収束までは対面での交流を重視する産業ではコミュニケーションのコストが上昇することが考えられる。
このように、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の中で、フェイス・トゥ・フェイス・コミュニケーションのコストの上昇という課題に直面しており、その影響を今後の人の交流のあり方の進化という観点から評価することが求められている。
34 Besart Avdiu and Gaurav Nayyar (2020)“When face-to-face interactions become an occupational hazard: Jobs in the time of COVID-19.”Brookings.
