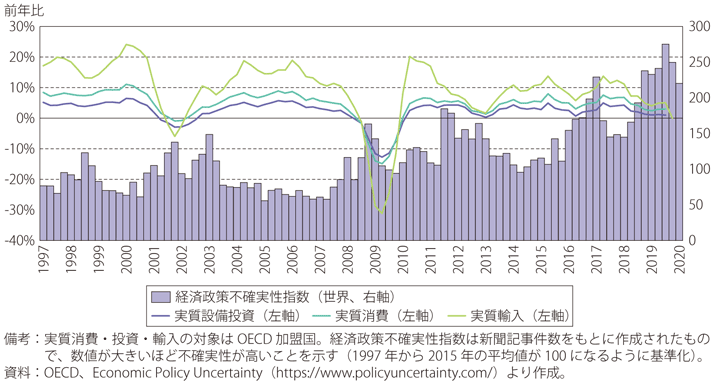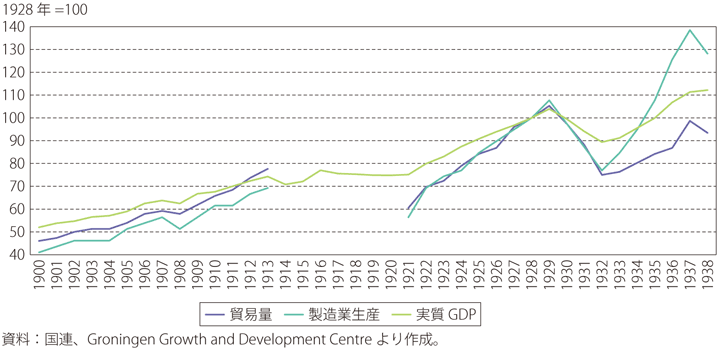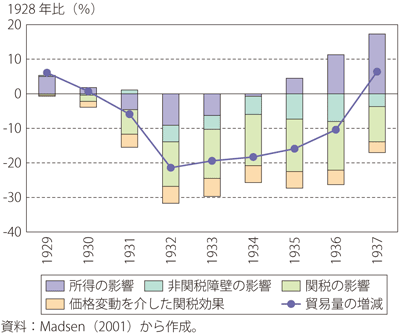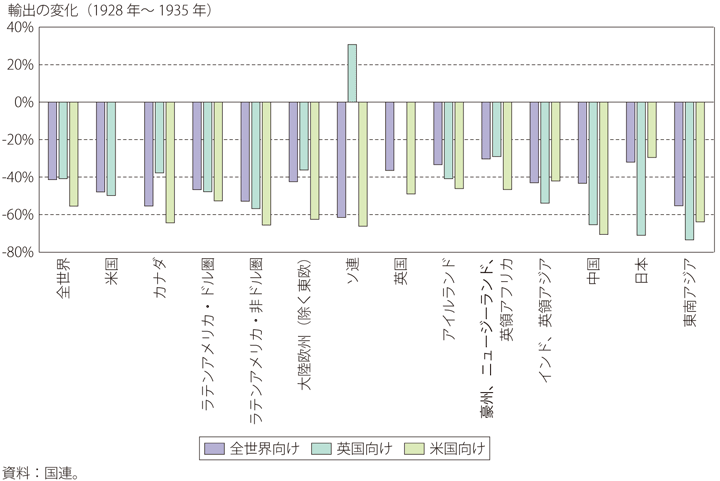- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2020

- 白書2020(HTML版)

- 第Ⅱ部 第1章 第5節 貿易制限的措置の増加
第5節 貿易制限的措置の増加
1.緊急時における自国優先策
(1)緊急時における自国優先策
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴って、感染拡大防止のために重要となるマスク、人工呼吸器、防護服等の医療関連物資の不足が各地で深刻となった。これは、第1節において確認をしたように生産拠点の集中度が高まりを見せていたことに加えて、世界各地で急速に需要が拡大をしたことによる。
その中で、各国では輸出制限・規制が見られるなど、自国の需要を満たすための動きが見られた。EUは2020年3月15日にマスクや防護服などの医療物資に対する輸出許可制度を導入した。その結果、医療用品はEU加盟国政府からの明確な許可を得た場合にのみ、非EU加盟国へ輸出できることになった。(同年5月26日失効済)その他にも、ロシアやインドネシア、タイ、インドなど世界各地でマスク等の輸出を禁止した。
米国のトランプ政権は国防生産法に基づき、自動車メーカーに対して、人工呼吸器の生産に向けた準備を開始するよう指示するなど、官民の垣根を越えて物資の生産に取り組んだ。さらに、米国では、国内でマスクが不足する中、トランプ政権は化学メーカーに対してカナダや中南米への医療用マスクN95の輸出を制限し、国防生産法に基づいて医療用マスクを米国内へ優先的に供給するよう要請した。その後、当該化学メーカーは米国に3カ月で1億6,650万枚輸入する計画を発表した。
このように緊急時において医療用品の輸出の制限や自国向けの生産拡大の動きが見られたが、輸出制限の動きは医療用品に留まらず食料にも波及している。新型コロナウイルスの感染拡大の中で、一部の国で穀物などの輸出を制限する動きが見られている。小麦粉の主要輸出国であるカザフスタンは、白糖、ジャガイモの輸出を禁止したのに加え、ニンジン、小麦粉に輸出枠を設定した。セルビアもひまわり油などの輸出を禁止した。また、世界最大の小麦輸出国のロシアは国内供給を優先し、穀物輸出量に制限を設けた。世界3位のコメの輸出国であるベトナムは、コメに輸出枠を設定した。カンボジアでも同様にコメの輸出の規制が見られた。
第Ⅱ-1-5-1表 食料の輸出制限の動き
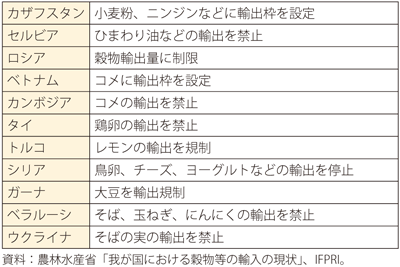
また、食料備蓄の強化の動きも見られており、世界最大のコメの生産国である中国は政府によるコメの購入量を過去最高水準まで引き上げると発表した。
このように、新型コロナウイルスの感染が世界に拡大する中で緊急時に対応するための物資については、世界的に輸出の制限や禁止が見られている。WTOが4月23日に公表した報告書によると35、世界80カ国・関税地域において新型コロナウイルスに関連する輸出の禁止又は制限が導入されている。医療物資であるフェイスマスクや防護具、手袋の輸出制限を行う地域が多く見られるが、消毒薬や医薬品、食料についても輸出の制限を行っている国が多くみられる(第Ⅱ-1-5-2図)。
第Ⅱ-1-5-2図 輸出制限の導入状況(2020年4月22日時点)
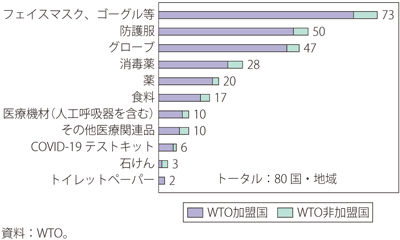
(2)物資の囲い込みとその副作用
このような物資の囲い込みは様々な副作用をもたらし得る。
まず、輸出制限により、国際的に財の価格が上昇する可能性がある。新型コロナウイルスの感染が拡大する中でマスクの価格が上昇しており、イタリアはマスクの価格を一律に設定するなど物価の上昇への対処も行われている。
食料についても世界の一部の地域では主要な主食品の価格が高騰し始めている。アフリカのウガンダでは、2020年3月中旬から4月末にかけて、主食品の価格が上昇し、トウモロコシの国内小売価格は30%上昇した(第Ⅱ-1-5-3図)。
第Ⅱ-1-5-3図 ウガンダの主食品の価格上昇率
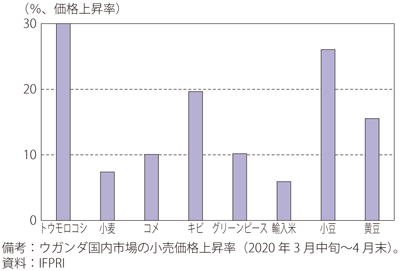
また、世界的なベンチマークであるシカゴの小麦先物は3月に高騰する状況が見られ(第Ⅱ-1-5-4図)、コメの価格も上昇している。
第Ⅱ-1-5-4図 小麦先物価格

このような食料の国際価格の上昇は、輸入に依存する国において購買力が減少することを意味し、食料を適切な価格において入手することが困難となる。また、輸出制限の導入を行った国においては、その影響により国内供給が増加することで国内価格が低下する恐れがあり、その場合には国内生産のインセンティブ低下が懸念される。
さらに、他の地域にドミノ効果を生む可能性もある。その場合、他国の対抗措置の発生や他のセクターにおいても輸出規制が導入されるリスクやサプライチェーンを通じて影響が波及することとなる。
そして、最も重要な点としては、輸出制限のように物資の囲い込みが相次ぐ場合には、必要な物資の世界での流通を阻害することがある。これは、感染が世界に拡大した状況下において、世界で感染を収束させなければ解決することのない世界的な感染症という世界規模の課題対処にあたり、世界全体に対するリスクとなるものである。第Ⅱ-1-5-5図のように、病床という基準では途上国の医療キャパシティの低さが見られるが、医療のキャパシティが十分ではないアフリカ等の途上国に物資が届かずに、世界規模で危機が収束できないリスクに直面することとなる。その場合、輸出規制のために感染状況が悪化をする国が出てくれば、その国から感染症が再度世界に拡大する可能性もあることに留意する必要がある。
第Ⅱ-1-5-5図 各国の病床数
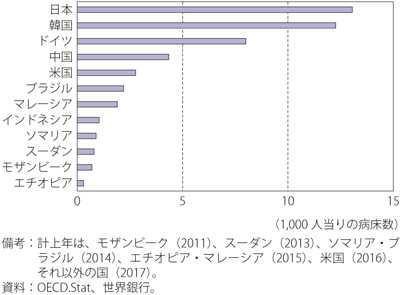
(3)輸出制限のパラドックス
輸出制限は自地域にも副作用をもたらすものともなり得る。3月15日、欧州委員会は、2019年のEU域外での売上高が121億ドルと推定される5種類の医薬品に輸出認可制限を課す法律を施行した。輸出制限の対象製品のうち、フェイスシールドの輸出が74億ドルと最も大きなものであり、次いで防護服が31億ドルであった。また、輸出額が9億ドルのマスク、4億ドルの医療用手袋、2億ドルのゴーグルとバイザーにも適用された(第Ⅱ-1-5-6図)。
第Ⅱ-1-5-6図 EUの輸出規制の対象物資
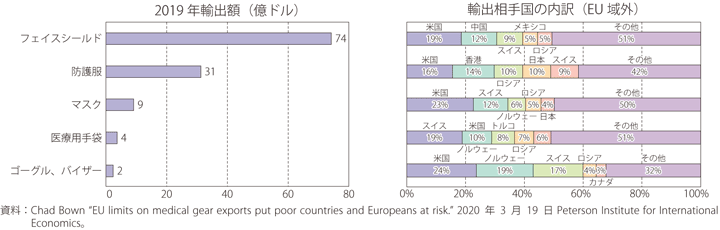
このようなEUによる輸出制限措置は、EUから米国、スイス、ノルウェー、中国、ロシアへの輸出に影響を与えただけでなく、EU自身が医療物資を輸入しにくくなる可能性があることが指摘されている36。これは、EUの医療物資のサプライチェーンが、EU国境外にまたがっているため、EU国境を複数回超えることで、必要な部品を調達することが可能となる複雑なサプライチェーンになっていることに起因する。EUの輸出規制の対象となる製品の定義が非常に広いため、部分品の輸出も制限されることとなり、結果としてEUは、自らが輸入しようとする医療物資を調達できなくなる可能性があるというものである。つまり、EUの輸出制限措置は、新型コロナウイルスとの闘いに必要なEU自身の医療物資をも危機にさらすことになり、これは輸出制限のパラドックスといえるだろう。このことから、各国が必要な物資を持続的に調達するためには、サプライチェーンを維持するための国際協調の重要性が示唆される。
輸出の禁止及び制限に係る国際協力においては、措置を実施する国の医療関連物資等の欠乏状況と、輸入国の公衆衛生等にもたらす負の影響のバランスを取る必要がある。
その中で、G20貿易・投資担当大臣は、緊急措置は的を絞り、相応かつ透明性があり、一時的なものでなければならない等強調しており、G20農業担当大臣もこれを再確認している。
新型コロナウイルス感染症の収束に向けては、緊急措置が固定化されず、世界的な協力が必要であることを意味する。
36 Chad Bown “EU limits on medical gear exports put poor countries and Europeans at risk.” 2020年3月19日 Peterson Institute for International Economics.
2.米中貿易摩擦
(1)米中貿易摩擦
米中の貿易摩擦は新型コロナウイルスの感染拡大以前に加速し、そして、2020年1月15日の第一段階の米中通商合意を経て、関税引上げが加速するとの懸念は一旦後退した(第Ⅱ-1-5-7表)。ただし、部分的に関税は引き下げられたものの、2019年までに引き上げられた関税の大部分は維持されたままである(第Ⅱ-1-5-8図)。
第Ⅱ-1-5-7表 米中貿易摩擦のタイムライン
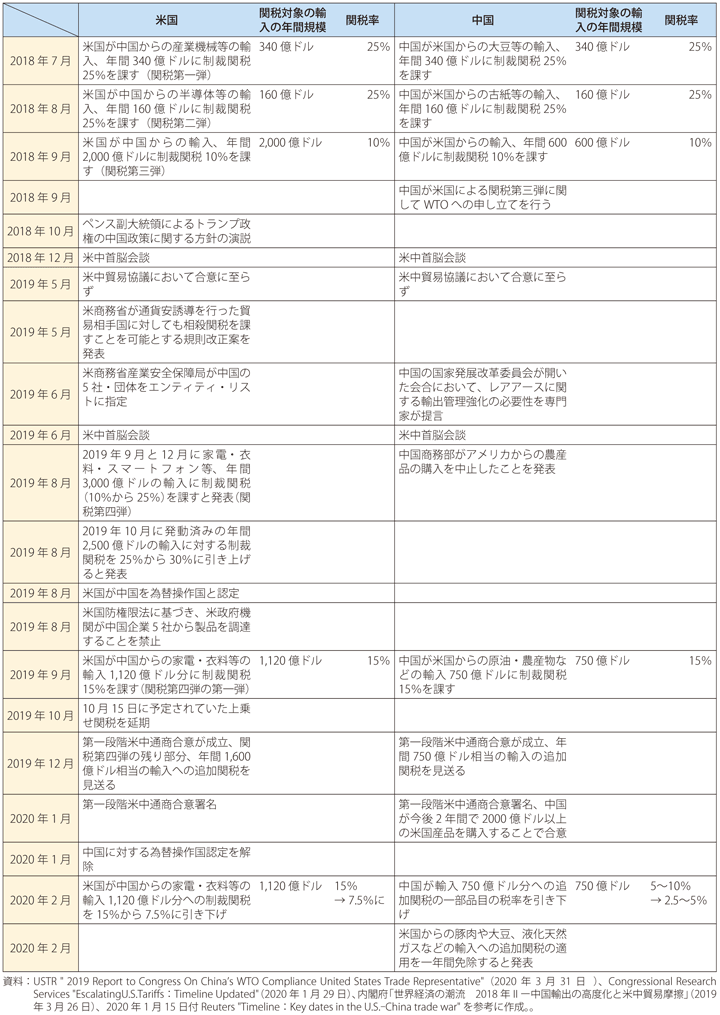
第Ⅱ-1-5-8図 米中貿易摩擦における米中の双方への平均関税率の推移
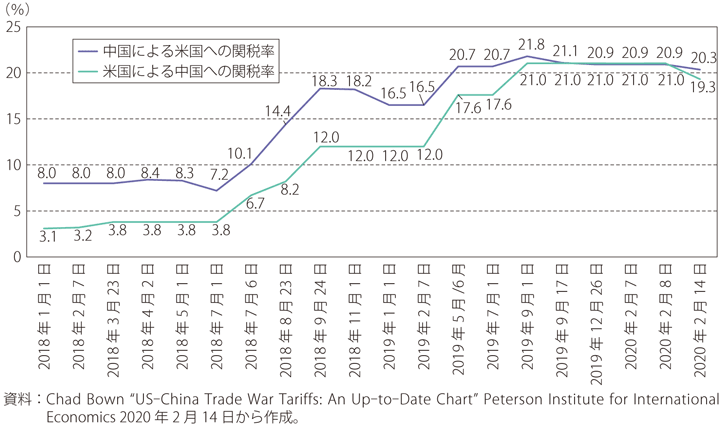
2020年1月の第一段階の米中通商合意においては、米中双方が関税を部分的に引き下げることに加えて、中国が米国からのエネルギー、農業、製造業、サービス業において、分野ごとの輸入を2020年初から2021年末の間に2017年比で2,000億ドル以上増加させることを約束した。2019年の米国の対中貿易赤字は3,456億ドルであり、合意通りに2年で2,000億ドルの米国の対中輸出増加となれば、他の条件を一定として、年間の対中貿易赤字が1,000億ドル削減される。
一方、このような管理貿易には、いくつかの懸念が存在する。まず、貿易数量の合意がなされる場合、仮に非効率な財・サービスであったとしても、その財・サービスは輸出相手国のマーケットの参入が保証されることにより、結果的に、マーケット内での競争力を高めるインセンティブが低下する。また、財・サービスが割高になることや、選択肢が減少することを通じて消費者の負担増加ともなる懸念が存在する。
管理貿易が実施される場合のもう一つの懸念は、米国以外の国からの輸入が置き換えられることである。特に、米国から中国への輸出を2017年比で2,000億ドル拡大するという約束は、中国が2,000億ドル分の輸入先を他国から米国に切り替えると読み替えることもできる。つまり、中国の市場が拡大をしない限り、他国への波及効果が懸念される。分野ごとの米国から中国への輸出の実績と合意額は第Ⅱ-1-5-9図の通りである。
第Ⅱ-1-5-9図 分野ごとの米国から中国への輸出の実績と合意額
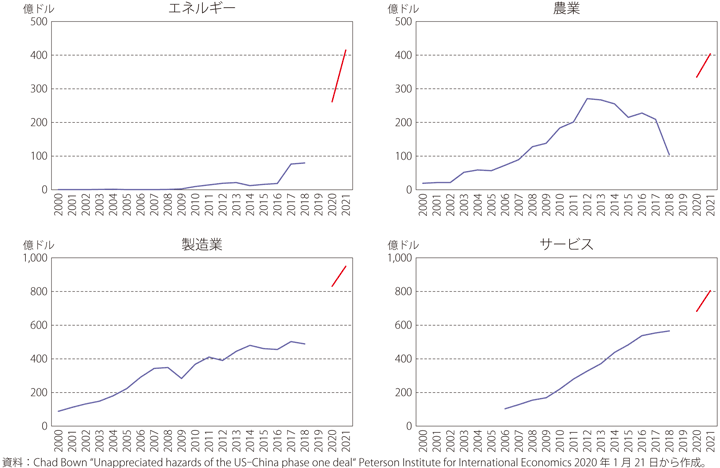
次に米中合意の対象品目の個別品目について、合意後の貿易状況を確認していく。中国の大豆の輸入に着目してみると、第Ⅱ-1-5-10図に示すとおり、2017年までは南半球のブラジルと北半球の米国それぞれからの輸入が季節性のある形で交互に行われていた。米中貿易摩擦が激化した2018年以降は米国からの大豆の輸入が減る一方、ブラジルからの大豆の輸入が季節性を上回って拡大し、米国産大豆の輸入からブラジル産大豆の輸入に置き換わっていた。その後、米中の第一段階合意に向けた歩み寄りの中で、2019年11月からは米国からの大豆の輸入が急速に拡大した。ただし、2020年に入ってからは、新型コロナウイルスの感染拡大の中、米中貿易自体が前年比で縮小をしていることもあり、今後の動向が注目される。
第Ⅱ-1-5-10図 中国の大豆の輸入(米国とブラジル)
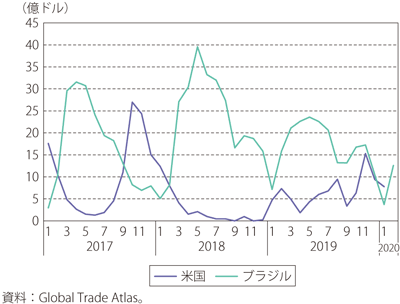
次に、2019年までの米中貿易摩擦に伴う個別品目の貿易額の変化を確認する。具体的には、米国の中国への輸出が減少した品目に関する他国の輸出による代替状況、及び米国の中国からの輸入の減少品目に関する他国からの輸入による代替状況について分析する。
まず、2019年における米国の中国への輸出である。米国の対中輸出額が減少した上位5品目は、航空機及び宇宙飛行、鉱物性燃料、ボイラー、木材、銅及びその製品である。このうち航空機及び宇宙飛行、鉱物性燃料では、米国から他国向けの輸出が増加したものの、ボイラー、木材、銅及びその製品は他国向けの輸出額も減少した(第Ⅱ-1-5-11図)。鉱物性燃料などを除けば、中国への輸出額の減少が他国への輸出の増加によって補われてはいない。米中貿易摩擦の中で米国から中国への輸出が減少したが、代替は限定的なものに留まっていた。
第Ⅱ-1-5-11図 2019年の米国の対中輸出減少項目(2018年比前年差)
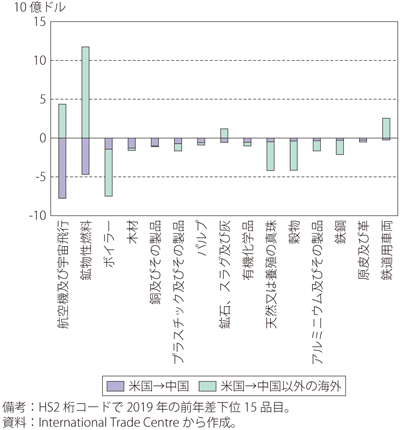
同様に、2019年の米国の中国からの輸入を見よう。2019年の米国の対中輸入額が減少した上位5品目は電気機器、ボイラー、家具・寝具、鉄道用車両、革製品である。この5品目は、いずれも中国以外の国からの輸入額が増加した(第Ⅱ-1-5-12図)。中国からの輸入の代替は一定程度行われており、東南アジアから米国への輸出の増加も見られる。ただし、電気機器、ボイラー、家具・寝具の輸入については、中国からの輸入額の減少分は他国からの輸入が増加しても、その減少分が十分に代替されているとはいえない。
第Ⅱ-1-5-12図 2019年の米国の対中輸入減少項目(2018年比前年差)
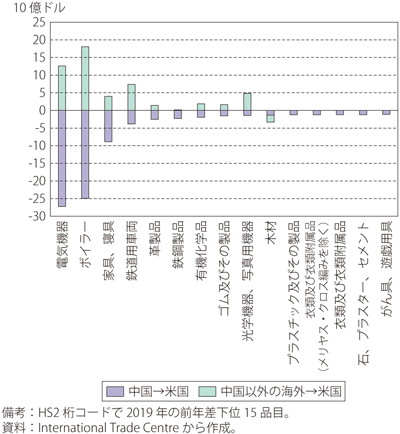
(2)米中貿易摩擦の他国への影響
貿易摩擦は、第三国にも影響が波及するものである。一部の国では米中貿易摩擦の中で、米中両国向けの貿易が拡大している。米国の2018年から2019年における相手国別の貿易額の変化率を見ると、米国の中国との貿易額は急速に縮小した一方、米国とベトナム、ベルギー、台湾等との貿易額は拡大している(第Ⅱ-1-5-13図)。
第Ⅱ-1-5-13図 米国の国別の貿易額の増減率(前年比、2018年~2019年)
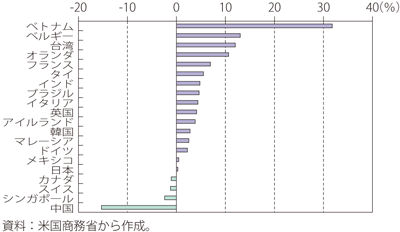
次に中国の2018年から2019年における相手国別の貿易額の変化率を見ると、マレーシア、フィリピン、ベトナム、メキシコなどにおいて東南アジア諸国との貿易額が増加している一方、米国との貿易額は大きく縮小している(第Ⅱ-1-5-14図)。
第Ⅱ-1-5-14図 中国の国別の貿易額の増減率(前年比、2018年~2019年)
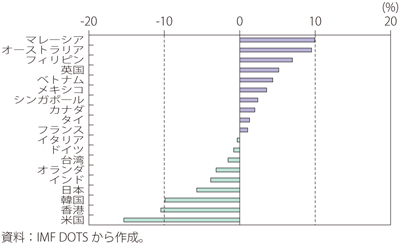
さらに米国との貿易額が2019年から増加しているASEANに注目すると、ASEANは、地域全体で見ると他の地域と同様に2018年末以降は輸出額が縮小傾向にある。ただし、個別の国では、ベトナム・カンボジア・ミャンマー等の輸出額は増加をしている。(第Ⅱ-1-5-15図、第Ⅱ-1-5-16図)。
第Ⅱ-1-5-15図 ASEANの輸出額推移
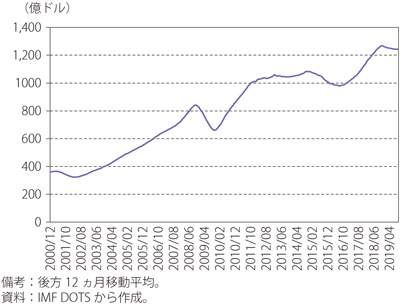
第Ⅱ-1-5-16図 ASEANの輸出額の変化(前月比寄与度)
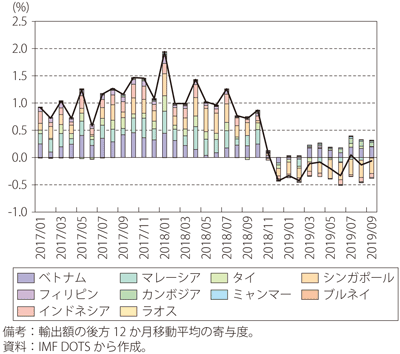
2019年にASEANから米国向けの輸出が増加した上位5品目は電気機器、家具、光学機器・写真用機器、革製品、履物である(第Ⅱ-1-5-17図)。いずれも、先に見たように中国の米国向け輸出が減少した品目である。そのため、中国とASEANの代替が生じているといえる。ただし、その代替は中国からの米国向け輸出の減少分を補うほどの規模ではない。
第Ⅱ-1-5-17図 2019年のASEANの米国向け輸出の増加項目(2018年比前年差)
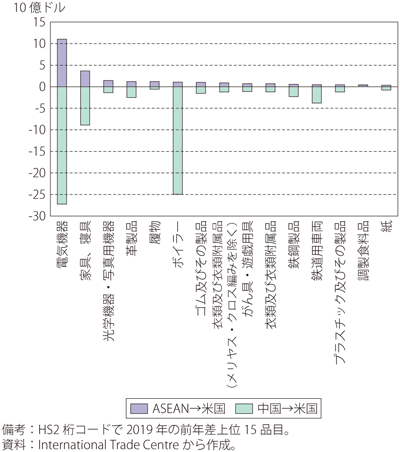
2019年にベトナムから米国向けの輸出が増加した上位5品目は電気機器、家具、ボイラー、履物、アパレル(メリヤス・クロセ編みを除く)である(第Ⅱ-1-5-18図)。電気機器では電話機・携帯電話、ダイオード・トランジスター・半導体デバイスが増加に寄与した。また、第6位はがん具・遊戯用具である。がん具・遊戯用具の中では子供用自転車・ベビーカー、ゲームが増加に寄与した。
第Ⅱ-1-5-18図 2019年のベトナムの米国向け輸出の増加項目(2018年比前年差)
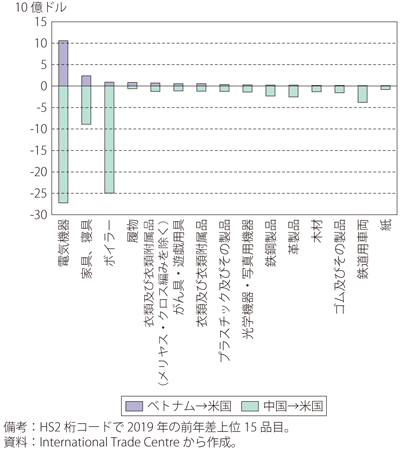
このように、米国の国別輸入において中国からの輸入が減少する中でベトナムや台湾からの輸入シェアが上昇するという変化が生じている(第Ⅱ-1-5-19図)。ただし、中国(及び香港)からの輸入の減少割合ほどにはそれらの国からの輸入は増加していない。このことは、貿易摩擦が総貿易額を縮小させる一因であることを示唆する。
第Ⅱ-1-5-19図 米国の中国及びその他アジア諸国からの輸入額の推移(前年同月差)
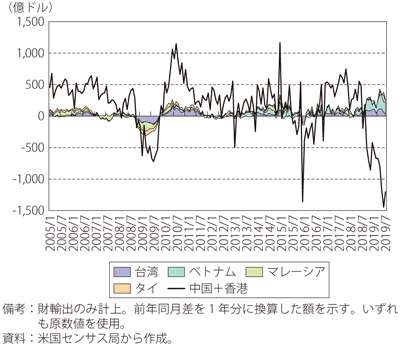
(3)米中貿易摩擦の余波、直接投資への影響
米中貿易摩擦により、貿易に留まらず投資にも影響が生じている。米中の両国間では、直接投資フローが縮小傾向を示している(第Ⅱ-1-5-20図、第Ⅱ-1-5-21図)。
第Ⅱ-1-5-20図 中国から米国への直接投資フロー(億ドル)
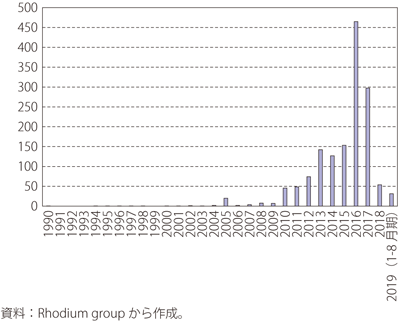
第Ⅱ-1-5-21図 米国から中国への直接投資フロー(億ドル)
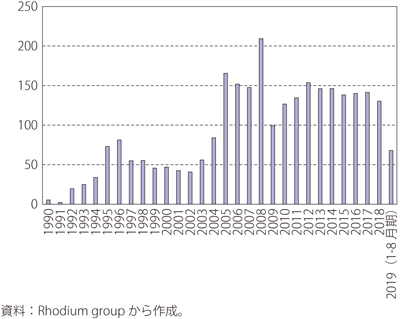
この状況下で、中国は投資先を多様化させており、米国向けの投資が縮小すると同時に周辺地域への投資を増加させている。
2019年の中国の対外直接投資フローは米国や欧州向けについては2018年に続いて減少したものの、アジア向けは堅調であった。米国・欧州向け対外直接投資フローの減少は、米国や英国、ドイツによる対内投資規制の強化に加えて、2016年以降の中国の対外投資管理強化が影響した。
2015年以降には、中国から東南アジアへの投資・建設プロジェクトの契約が増加している。米国のシンクタンクであるアメリカンエンタープライズ研究所(AEI)の提供する中国の対外投資データベース「China Global Investment Tracker」をもとに集計すると、中国のASEAN向け投資・建設プロジェクト契約は2019年に238億ドルとなっており、2018年の247億ドルから小幅に減少した(第Ⅱ-1-5-22図)。投資プロジェクトは増加したが建設プロジェクトが減少した。
第Ⅱ-1-5-22図 中国のASEAN向け投資・建設プロジェクト契約
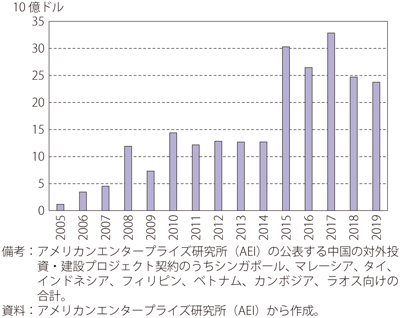
2015年以降にマレーシア、インドネシア、シンガポール向けの中国からの直接投資が急増し、2019年もインドネシア、カンボジア、フィリピン、インド向けの直接投資が増加した。2019年4月にマレーシアと中国は、中止していたマレーシア東海岸鉄道の建設を再開することで合意した。インドネシアでは、ジャカルタとバンドンを結ぶ高速鉄道計画を2015年に中国が受注し、2018年から建設を進めている。
東南アジアの中でも、ベトナムへ進出する中国企業が増加しており、香港や中国からのベトナムへの直接投資は2019年に急増した。中国からベトナムへの直接投資は828件(前年比65.6%増)、30.2億ドル(前年比75.0%)、香港からベトナムへの直接投資は428件(前年比64.0%増)、34.2億ドル(前年比75.0%増)となり、電動工具、電子機器、タイヤを中心に増加した。中国における労働コストの上昇、ベトナムの豊富な労働力に加えて、中国との地理的な近接性を背景に2015年ごろから中国によるベトナムへの直接投資は増加傾向にあり、2018年ごろからは直接投資の増加が加速した。
ベトナムにおける相対的に低い労働コスト、豊富な労働力人口を生かしてサプライチェーンを多様化する動きは、東アジア各国に共通して見られ、韓国、日本もベトナムへの投資を増加させている。
2019年の対ベトナム直接投資が最も多かった国・地域は韓国である。韓国からベトナムへの直接投資は1,594件(前年比7.6%増)、52.5億ドル(前年比12.4%減)と、前年の大型案件の反動により金額こそ減少したものの、娯楽、電子部品・デバイスなどにおいて引き続き高水準であった。韓国からベトナムへの直接投資は、当初はアパレルや靴などの労働集約産業が中心であったものの、2000年代後半以降からはエレクトロニクス産業において拡大した。
2019年の日本の対ベトナム直接投資は、655件(前年比1.9%増)、29.0億ドル(前年比65.3%)となり、韓国、香港、中国による直接投資金額を下回った。JETRO「2019年度アジア・オセアニア進出日系企業実態調査」によると、ベトナムへの生産移管が見られる中で、現地売上を増加させている日本の部材メーカーが存在する。企業向けサービスを提供する日本の人材紹介会社や建設会社においても、ベトナムにおける現地需要が増加した。一方、競争相手の企業がベトナムに進出して競争が激化するために、ベトナム国内での日本企業の売上が減少するリスク、ベトナム国内における人材、物件、部材のコストの上昇を招くリスクが懸念されている。ベトナムの地場縫製企業に米国向け縫製品の新規大型発注が入ったために、日本からの注文を受ける企業が以前よりも少なくなっているという状況も見られている37。
ベトナム以外のASEAN主要国に関しては、第Ⅱ-2-5-23表に見るように、2019年の日本の直接投資件数は、タイにおいて1位、インドネシアにおいて2位であった。
第Ⅱ-1-5-23表 ASEAN主要国の対内投資件数(単位:件、%)
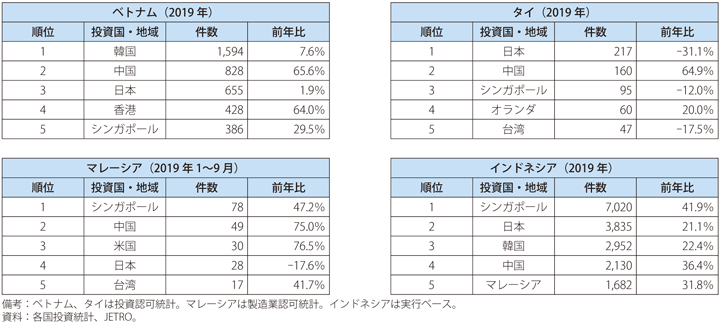
投資の変化はベンチャー投資においても見られる。第Ⅱ-1-5-24図に見るように、2019年の中国のベンチャー投資は米国向けが大きく落ち込む一方、インドネシア、ナイジェリア、イスラエル向けなどへの投資を増加させた。
第Ⅱ-1-5-24図 中国のベンチャーキャピタル投資額の変化
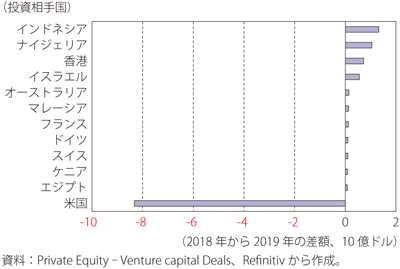
米国の地域別国際収支によると、2019年の中国向けの直接投資フロー38は61億ドルとなり、2018年の88億ドルから減少しており、2017年の152億ドルからは半分以下となっている。一方、東南アジア向けの直接投資フローは2019年に261億ドルと、2018年の494億ドルの純減と比べて大きく回復している。(第Ⅱ-1-5-25図)。東南アジア向けの直接投資フローは2009年以降に中国向けの直接投資フローを上回る水準となっており、2014年に360億ドルを記録し、2018年39を除いて高水準を維持している。
第Ⅱ-1-5-25図 米国の国別対外直接投資フロー
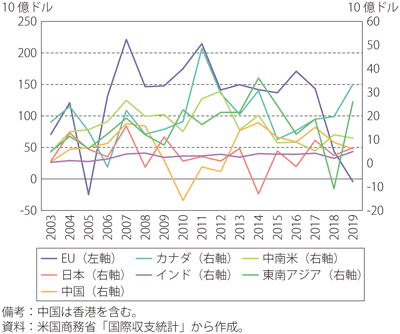
このように米中貿易摩擦の中でその影響の波及が世界に見られているが、多国間の枠組みへの不信の表れは米中貿易摩擦に限定されるものではなかった。英国のEU離脱やWTOの上級委員会の機能停止など、世界的に多国間枠組みへの不信が見られていた。
その中で新型コロナウイルスが世界的な感染拡大を見せたが、感染症への迅速な対応に対しては妨げとなっていた。米中貿易摩擦の過程で米国は中国からの医療用品の輸入に対して関税賦課を行ってきた40。CTや体温計には1974年通商法301条に基づく25%の輸入関税が課されており、輸入も縮小していた。これは、米国内で新型コロナウイルスの拡大に対して必要となる医療機器などが十分に供給されないリスクを高めるものであった。そこで、2020年3月10日、12日にトランプ政権は部分的に関税を低下させた。このような米中両国の動きは世界で物資を持続的に流通させることの重要性を改めて確認させるものでもあった。
3月30日の20カ国・地域(G20)貿易相テレビ会議において、パンデミックに対処するため、開放的な市場を維持して医療用品や医療設備などの必需品の持続的な流通を確保することで合意した。このように、世界での協調行動が求められている。
37 JETRO(2020a)。
38 香港を含む。
39 シンガポール向け直接投資フローが2018年に米国の税制変更の影響の中で-475億ドル(純減)となり、東南アジア向けがマイナスに転じた。
40 Chad Bown “Trump’s trade policy is hampering the US fight against COVID-19.” 2020年3月13日 Peterson Institute for International Economics.