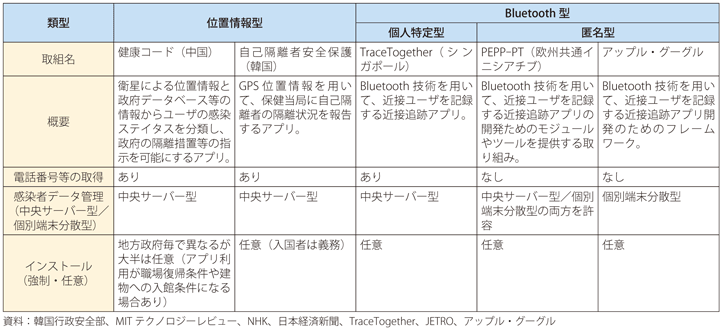- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2020

- 白書2020(HTML版)

- 第Ⅱ部 第1章 第6節 デジタル経済の拡大、コロナテックの急速な社会実装の進展
第6節 デジタル経済の拡大、コロナテックの急速な社会実装の進展
1.グローバリゼーションとデジタル経済の拡大
(1)新型コロナウイルスの感染拡大を受けたデジタル経済の急速な浸透
新型コロナウイルスの感染拡大において明らかになった世界の構造として、経済・社会のデジタル化の加速も存在している。近年のデジタル経済の拡大の延長線上にあり、感染症の拡大に伴ってフェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションが制限され、渡航制限や社会的距離の確保が導入される中において、経済・社会のデジタル化は更に進行している。
この状況は様々な経済活動に現れている。消費活動を見ると、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて外出を控える中で全体的に消費は抑制されているものの、電子商取引は各地で拡大している。中国においては、小売売上は2020年に入ってから前年比で大幅なマイナスを記録してきたが、財のインターネット販売は増加を続けており、4月には前年比で8.6%増加した。米国では4月の小売売上は前月比で16.4%減少したが、オンラインの売上は8.4%増加した。
このように、デジタルを活用した消費活動が対面の経済活動の制約を補完しており、新型コロナウイルスの感染が世界に拡大をした3月以降に電子商取引の拡大が顕著に見られる(第Ⅱ-1-6-1図)。
第Ⅱ-1-6-1図 オンライン販売による売上増加率(2020年、前年比)
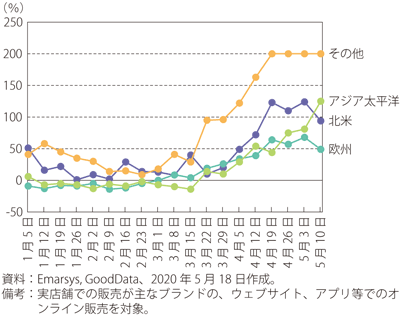
特に好調なものはITプラットフォーマーの提供するオンラインモールを用いる電子商取引であり、食料やトイレットペーパーのような必需品の需要が拡大している。アマゾンは2020年1-3月の四半期において、北米での電子商取引での売上は前年同期比で29%増の461億ドル、国外売上は18%増の191億ドルとなり、新型コロナウイルスの感染拡大の中でも売上を増加させている。中国の電子商取引JD.comにおいても、同時期に20.7%の売上増加となった。
電子商取引、貿易とパンデミックに関するWTOの分析46によると、消費者の備蓄により、消毒剤、マスクなどの医療用品、トイレットペーパーなどの生活必需品、食品などへの需要が急速に拡大したものの、電子商取引もサプライチェーンに依存するものであり、物不足が発生することとなった。このような脆弱性の存在を指摘した上で、商品やサービスの国境を越えた移動を容易にし、デジタル・デバイドを縮小し、零細・中小企業のための競争の場を平準化するための国際協力の拡大を検討することの重要性をWTOは指摘している。
新型コロナウイルスの感染拡大で加速するデジタル化は電子商取引に留まるものではない。フェイスブックは傘下のインスタグラムやワッツアップも含めて一日あたりの利用者が増加しており(第Ⅱ-1-6-2図)、マイクロソフト、グーグルも同様に世界的な外出制限の中でサービス利用が増加している。
第Ⅱ-1-6-2図 フェイスブックの一日あたりアクティブユーザー数
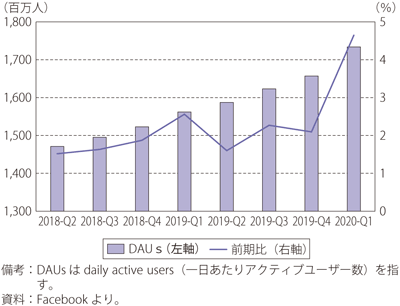
オンラインで映画などを配信するネットフリックスは新型コロナウイルスの感染拡大のあった1-3月期に自宅で過ごす消費者による需要が拡大し、ユーザー数の伸びが加速し、前期比で1,600万人ほど増加した。
ビジネスのオンライン化も促進されている。自宅から仕事を行うテレワークが普及し、様々なオンライン会議のソフトウェアの利用が拡大している。また、学校もデジタル技術を活用し、リモートでの教育も行われている。マイクロソフトのビデオ会議システムであるTeamsのユーザー数は3月11日からの1週間で1,200万人も増加した。同社のビデオ通話システムのSkypeのアクティブユーザーも急増している。さらに、同業のZoomにおいては、4月3日からの19日間で1億人のアクティブユーザーの増加が見られた。
これらは、オンライン会議の開催が増え、これまで利用しなかったユーザーの登録が増加し、会議システムは他のユーザーが利用するほどその他のユーザーが参加するというネットワーク効果が存在することから、特定のサービスへの集中が進んでいる(第Ⅱ-1-6-3図)。
第Ⅱ-1-6-3図 オンラインコミュニケーションツール(Microsoft Teams及びZoom)の利用状況
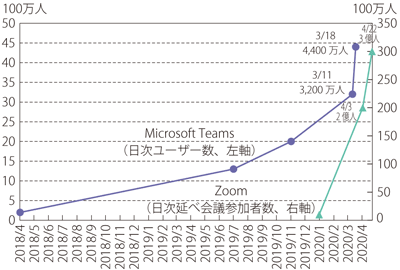
46 WTO“E-COMMERCE, TRADE AND THE COVID-19 PANDEMIC”2020年5月4日
(2)デジタル貿易の拡大
経済のデジタル化というトレンドの中で、世界ではデジタルの貿易も増加を続けてきた。ここで、デジタル貿易の現状を確認しよう。
デジタル貿易については統一的な定義が存在するわけではない。OECDは、デジタル貿易とは、基本的には国境をまたぐデータの移転を前提としたものであり、消費者、企業、政府が関わる、電子的または物理的に配送される物品やサービスの貿易にかかる電子的取引を包含するものであるとの概念を紹介している。
この定義によると、デジタル貿易は、インターネットを通じた物品の売買に加え、オンラインでのホテル予約、ライド・シェアリングや、音楽配信サービスなどオンラインプラットフォームを介して提供されるサービスなどを含むものである。
世界はオンラインプラットフォームを介して相互接続が進んでおり、世界のインターネット・プロトコル(IP)トラフィックは、経済規模と比較しても高速で増加している(第Ⅱ-1-6-4図)。このインターネットトラフィックの増大は、経済・社会のデジタル化の加速によるものであり、今後ますますの進行が予想される。
第Ⅱ-1-6-4図 インターネットトラフィックと経済規模(地域別)
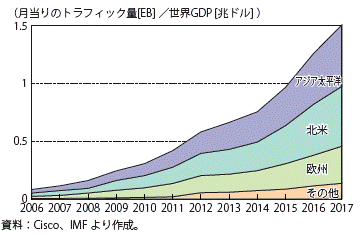
このような世界のデジタル化を背景として、電子商取引も拡大してきた。電子商取引は、膨大な選択肢を集約し、価格設定や比較を透明にすることで、国境を越えた大規模な取引を可能にしている。
UNCTADは、2017年に電子商取引は29兆ドルに達したと推計している。これは世界のGDPの36%に相当し、前年比で13%の伸びである。企業間の電子商取引は2017年に25.5兆ドルと電子商取引全体の87%を占め、企業と消費者の電子商取引は2017年に3.9兆ドルと前年比22%の増加となった。
企業と消費者の電子商取引の売上高の上位3カ国は中国、米国、英国となった。越境による企業と消費者の電子商取引の売上高は、2017年に推定4,120億ドルに達した。これは企業と消費者の売上高全体の11%に相当し、2015年の7%から増加している(第Ⅱ-1-6-5表)47。
第Ⅱ-1-6-5表 電子商取引の売上高(2017年、UNCTAD推計)
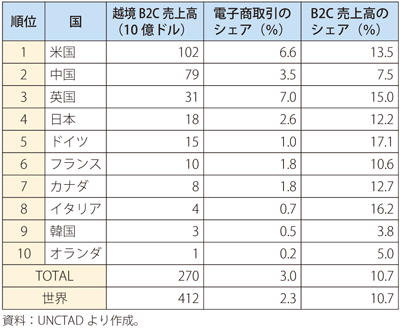
世界における電子商取引市場の拡大の背景には、インターネットの普及や携帯電話の普及が背景にある。このインターネットと携帯電話の登場は人々に国境を超えるコミュニケーションと短時間での情報収集を可能にした点において、暮らしの変化に大きなインパクトをもたらすものであった。
同時に、それらは急激なスピードで普及した。携帯電話の保有数は2000年には人口の5人に1台程度であったが、2019年には人口を上回る携帯電話保有台数となっている(第Ⅱ-1-6-6図)。そして、発展途上国の人口増加に伴い、2019年時点では、世界の携帯電話利用者全体の内80%が途上国である(第Ⅱ-1-6-7図)。アフリカにおける中国企業トランジットのように、途上国では携帯電話の機能がローカライゼーションされ、現地の所得に合わせて安価な価格で携帯電話の販売が進んでいることもあり、携帯電話の普及が進んでいることがその背景の一つとして挙げられる。
第Ⅱ-1-6-6図 全世界における携帯電話利用者数とインターネット利用者数(100人あたりの人数)の推移
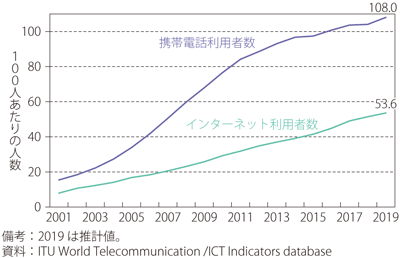
第Ⅱ-1-6-7図 途上国と先進国における携帯電話利用数の比較(2000年、2019年)
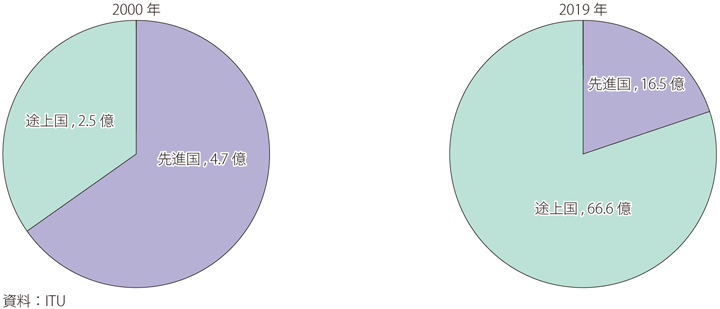
このような携帯電話による電子商取引など、デジタル技術を活用したビジネス展開は、対面での従来型のビジネスよりも大幅な利益を挙げることのできる場合がある。グローバル企業として有名な3社(アリババグループのタオバオ(中国・電子商企業)、ウォルマート(米国・スーパーマーケット)、アディダス(ドイツ、スポーツ用品店))の売上額の推移をみると、タオバオが驚異的なスピードでビジネスを拡大し、成長を遂げたことがうかがえる(第Ⅱ-1-6-8図)。
第Ⅱ-1-6-8図 デジタル技術を活用したビジネス展開(各企業の総売上高比較)
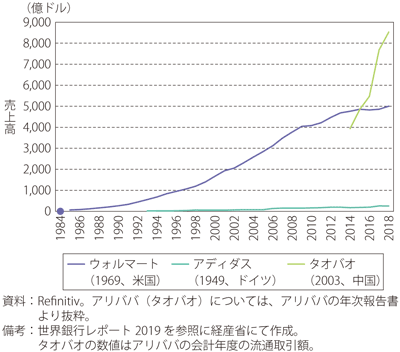
このデジタル貿易を支える基盤として、オンライン決済の手段も多様化している。クレジットカードやデビットカードにとどまらず、フィンテックの普及に伴い、多用な決済手段が提供され、それがデジタル貿易の発展につながっている。
47 UNCTAD Digital Economy Report 2019.
(3)国境をまたいで活動する巨大IT企業の存在感の高まり
デジタル経済の拡大が近年見られてきたが、デジタル経済の特徴としてネットワーク効果が存在する。ネットワーク効果は、サービスを利用する人が多いほどサービスの利便性が向上することであり、具体例としては、SNSであれば同一のSNSに多くの友人が加入するほど、各利用者は多くの友人とコミュニケーションを取ることができ、SNSの価値が高まる。
このネットワーク効果は、直接的な効果と間接的な効果に分けることができる。直接的な効果とは、同じネットワークに属する加入者が多いほど、加入者の効用(例えばSNSで投稿した人やフォローした人の満足度)が高まる効果である。間接的な効果とは、ある財・サービス(例えばハード機器)とその補完財・サービス(例えばソフトウェアや各種サービス)が密接に関係している場合に、ある財・サービスの利用が進展すればするほど、それに対応した多様な補完財・サービス(例えばSNSに付随する広告)が多く供給され、それにより利便性や効用が高まる効果である。
このネットワーク効果はグローバリゼーションによって、国境を越えて効果が働くことで、グローバルな巨大IT企業を生み出している。フェイスブックの実利用者は2008年の1億人から2019年には20億人を超えるまでに拡大をしている。これは、世界のどの国の人口よりも巨大なものであり、グローバリゼーションがあってこそ出現した状況といえるだろう。
その結果、フェイスブックの売上は、2009年の7.8億ドルから2018年には558億ドルへと72倍に拡大している。また、フェイスブックがインスタグラムを買収するなど巨大IT企業のM&Aが多く見られるが、それはサービスを超えたネットワーク効果における補完性が背景にあると考えられる(第Ⅱ-1-6-9図)。
第Ⅱ-1-6-9図 巨大テクノロジ―企業の月間ユーザー数
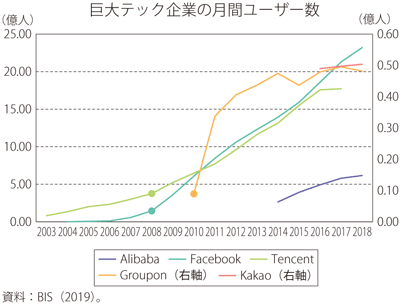
デジタル化により産業構造のレイヤー化が進展している。従来の産業は、バリューチェーン構造で捉えるのが一般的であったが、デジタル化はレイヤー構造化を促している。
バリューチェーンとは企画から製造、販売といった連鎖であるが、消費者は主に最終プレーヤーの販売に接するのみであり、消費者の選択は、販売の提供するオプションの範囲に限定される。つまり、製品の決定権は供給側に存在する。自動車であれば完成車メーカーが企画・開発と製造を担い、系列企業が部品供給、ディーラーが販売するが、消費者の選択はディーラーの提供するオプションに限定される。
それに対して、デジタル化により進展するレイヤー型の構造は、業界間にまたがるレイヤースタック(レイヤーの集まり)として構成されている。それぞれの構成要素であるレイヤーが独立して製品やサービスとして成立しているため、レイヤー型の構造では、消費者は各レイヤーに対して直接アクセスすることが潜在的に可能である。この構造のポイントは最終消費者が、レイヤーを構成する各レイヤーの製品・サービスをそれぞれ直接選択・組み合わせ可能であることにある(第Ⅱ-1-6-10図)。
第Ⅱ-1-6-10図 バリューチェーン構造とレイヤー構造
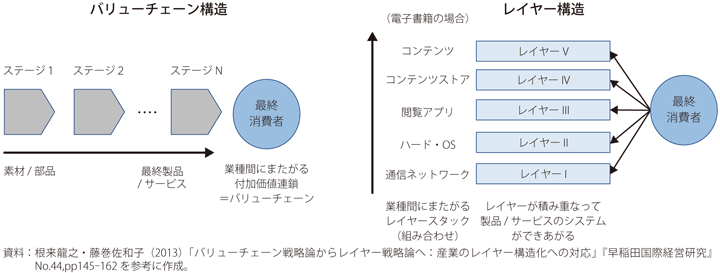
レイヤー構造化の進展は、(1)レイヤーの数が増えること、(2)各レイヤーの独立性が高まること、(3)レイヤーごとの選択肢の組み合わせの自由度が増すこと、という3つの要素で定義されており、その結果、消費者から見た選択肢が増えることとなる。電子書籍では、アプリもハードもコンテンツストアも最終消費者であり、各レイヤーの製品サービスを比較的自由に組み合わせて購入・利用することが可能である。そして、レイヤー構造化が進展することにより、レイヤーごとに存在するプラットフォーマーの影響力が増している48。
このレイヤー構造化はIT産業にとどまるものではない。従来型のバリューチェーン型の成熟した産業においても、ITの進化に伴いビッグデータの活用などが進むにつれて、モジュール化や製品のソフトウェア化が進展しつつあり、レイヤー化に向けた変化が加速する見通しとなっている49。
そして、グローバリゼーションとデジタル化の中で、競争の促進と企業の集中という両面が見られている。
グローバルに活動を行う企業は、外国企業との競争によって利ざやが低下しやすく、場合によっては国内企業の撤退や合併が発生する。グローバリゼーションに伴い企業間の競争が拡大した例が1990年代から2000年代前半の期間であった。50
しかし、近年、グローバリゼーションで競争が促される以上に、企業の集中が進む状況も見られている。企業がグローバルに市場を拡大することにより、競争力のある企業が拡大をするようになっている。つまり、国内外での競争の結果として撤退・縮小する企業が多数存在する一方、成功した国内企業がグローバルに市場を拡大する。その場合、自国の事業規模や他の企業との競争環境が変化し、自国の市場においては超巨大な企業に変貌する51。
このような集中の状況は、米国におけるスーパースター企業の増加、マークアップの上昇として顕在化している。M&Aの増加や上場企業数の減少も特徴である。代表的な巨大IT企業であるGAFAM(グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル、マイクロソフトの頭文字を取った、巨大ITサービス企業5社を表す)が、将来有望なテクノロジー企業を買収することも頻繁に行われている(第Ⅱ-1-6-11表)。その結果として、新たな巨大テクノロジー企業の台頭は進まず、他方で、巨大企業は従来の本業以外のサービスへの進出も頻繁に見られる。このように、第Ⅱ-1-6-12図の通り、デジタルサービスでは一部の企業に集中する傾向が見られる。
第Ⅱ-1-6-11表 巨大IT企業によるM&Aの件数
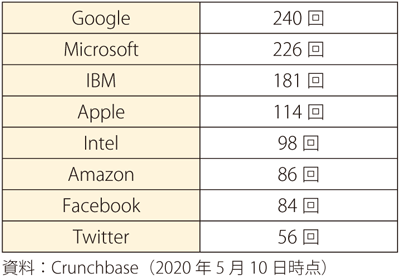
第Ⅱ-1-6-12図 世界のデジタルサービスにおけるシェア上位企業
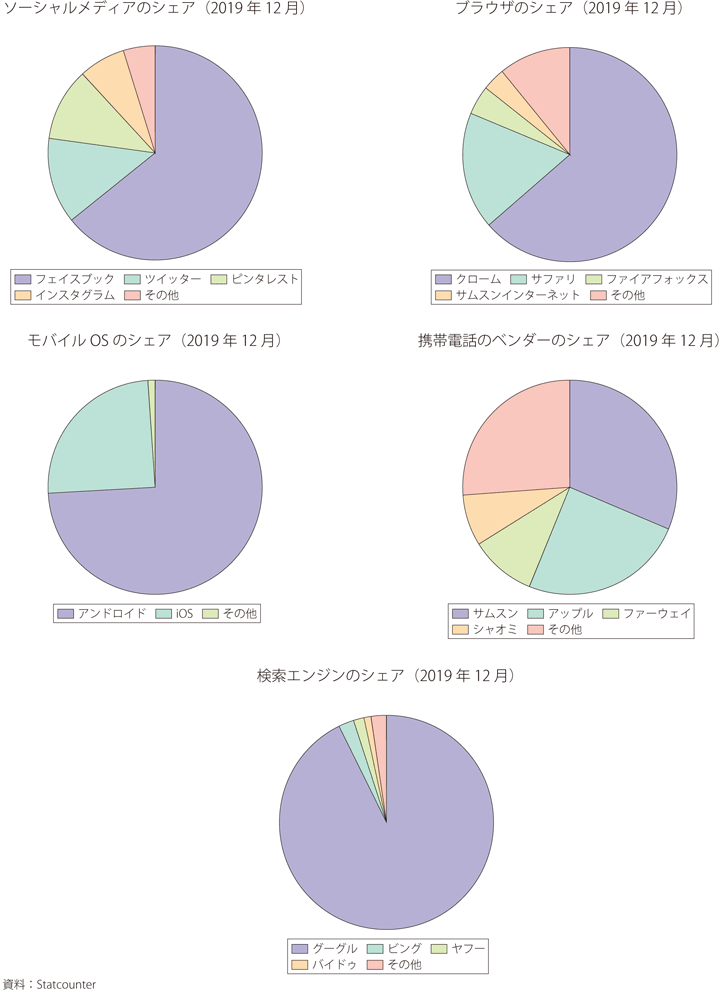
このようなトップ企業は、その売上をサーバーや回線の増強、ウェブサイトにおけるアルゴリズムの改善などに再投資し、利用者の囲い込みを強化することで集中の度合いを高めている52。インターネットサービスの利用者は、わずかな応答時間の差に敏感に反応するため、大量の設備投資によって利用者を保持しようとする。同時に利用者から得られるビッグデータの分析やAI学習を通じたソフトウェアの改良も、利用者の確保と企業の集中に大きな役割を果たしている。
このような集中はITプラットフォーマーの企業利益にも現れている。2009年から2019年の間にGAFAMの純利益は約5倍に拡大し、米国の上場企業の純利益に占めるGAFAMの純利益のシェアは6%から13%にまで拡大した(第Ⅱ-1-6-13図)。
第Ⅱ-1-6-13図 米国における巨大IT企業の時価総額・売上・純利益のシェア
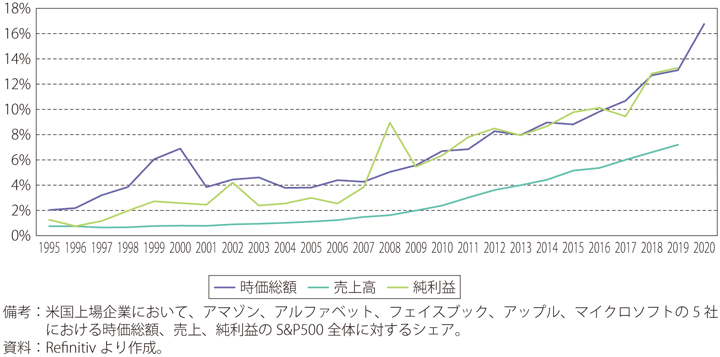
GAFAMについては、純利益や売上以上に時価総額が拡大しており、2009年末から2019年末の間に時価総額は8.5倍となった。好調な業績にも関わらず、投資の拡大ペースが遅く、純利益と投資の乖離が見られる(第Ⅱ-1-6-14図)。ただし、このテクノロジー関連の企業における特徴として、デザインやアイデアがビジネスの軸であり、工場などの有形な設備投資は相対的に低いものとなる。研究開発投資(R&D)が投資に占める比率は60%前後と高水準を維持しており、無形資産投資の割合が高い(第Ⅱ-1-6-15図)。
第Ⅱ-1-14図 米国における巨大IT企業(GAFAM)の純利益と設備投資、売上と時価総額
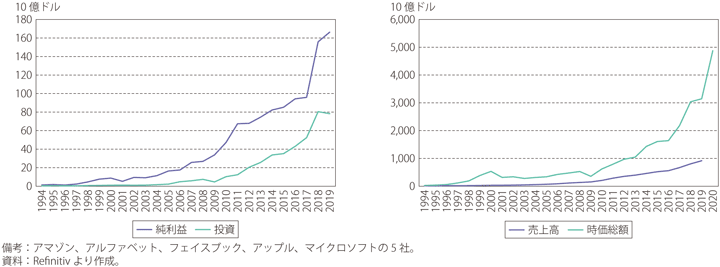
第Ⅱ-1-6-15図 米国おける巨大IT企業(GAFAM)の投資に占めるR&Dの割合
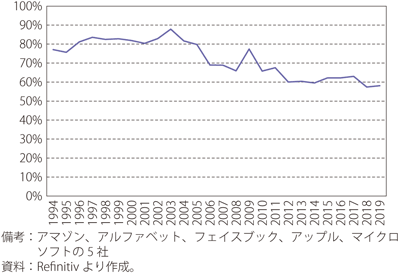
企業の集中とともに価格支配力が高まり利益率が高まることにより、経済全体における大企業の影響力が増加する。ライバルが存在しない企業は、その規模やブランド力を生かして値上げをしたとしても、代替がない場合には消費者はその値上げを受け入れざるを得ない。また、高いシェアを生かして利益率を高めた企業がブランド力などを通じて高い参入障壁を有している場合には、競争のための投資を必要としない。
そこで以下では、米国における大企業の集中度と利益率、設備投資、現預金保有の動向を中心に分析する。
米国の代表的な株価指数であるS&P500を構成する企業を対象に、米国において上場する企業の属する産業における企業の集中度を測定する指標として売上ハーフィンダール・ハーシュマン指数(15産業の中央値)を第Ⅱ-1-6-16図において示している。ハーフィンダール・ハーシュマン指数とは、各産業に属する各企業の売上シェアの二乗の合計値である。完全独占なら10000、二社が50%ずつのシェアの場合は5000、完全競争なら0となり、公正取引委員会の企業結合審査の基準の一つとしても用いられる指標である。
1990年代後半以降の米国企業の売上ハーフィンダール・ハーシュマン指数(15産業の中央値)は上昇基調にあり、2000年の225から2019年には1055と集中が進んでいる。また、企業の利益率(売上高純利益率)は、売上の集中と同様に、2000年代以降は上昇トレンドにあり、2000年の6.9%から2019年には9.8%に上昇した(第Ⅱ-1-6-16図)。
第Ⅱ-1-6-16図 米国における上場企業の集中(15産業中央値)と利益率
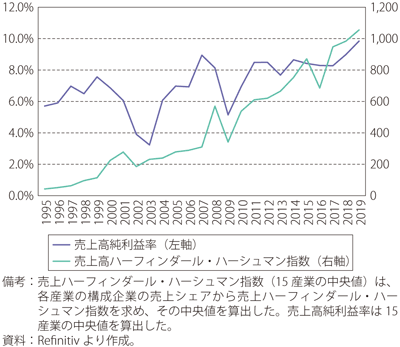
そして、2010年以降にハーフィンダール・ハーシュマン指数が上昇した産業ほど売上高純利益率の上昇も大きい(第Ⅱ-1-6-17図)。企業における集中度が上昇すると同時に利益率が上昇した産業はテクノロジー、資本財、公益、医薬などであり、集中度が低下すると同時に利益率が低下した産業は石油・石炭エネルギー、素材などである。一方、素材、小売・量販店のように、集中度が上昇しても利益率が低下するセクターも存在する。
第Ⅱ-1-6-17図 米国における上場企業の15産業別に見た売上ハーフィンダール・ハーシュマン指数と利益率の変動(2010年~2019年)
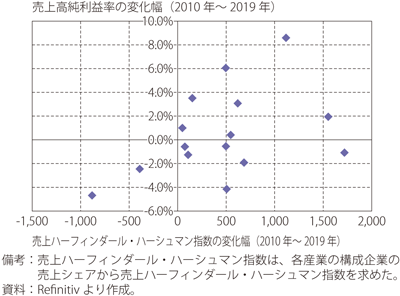
営業キャッシュフローが拡大すると、投資が増加する傾向が見られる。また、S&P500を構成する企業(除く金融)における営業キャッシュフローに対する投資の比率は60%代前半で概ね安定している。一方、GAFAMの営業キャッシュフローに対する投資の比率は50%から100%の間で比較的大きく変動している(第Ⅱ-1-6-18図)。
第Ⅱ-1-6-18図 米国における上場企業とGAFAMの営業キャッシュフローと投資
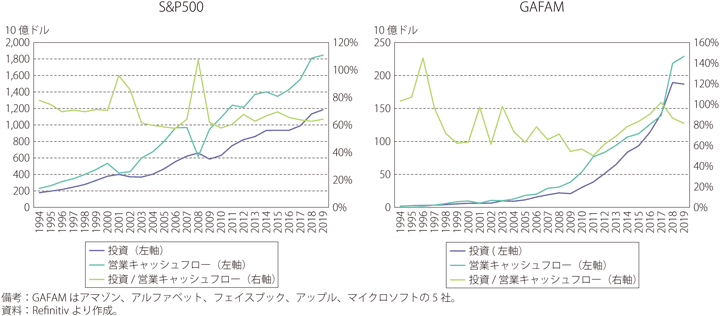
2010年代を通しての営業キャッシュフローの増減、投資の増減と現預金の増減を見ると、拡大した営業キャッシュフローが投資以外の分野、とりわけ現預金の蓄積に回っていた。2010年以降にS&P500を構成する企業(除く金融)の営業キャッシュフローは7,585億ドル拡大した。また、固定資産投資は3,729億ドルの拡大、R&D投資は1,833億ドルの拡大であった。その一方で、現預金残高は6,265億ドルの拡大と投資の増加幅を上回った。
また、GAFAMでは営業キャッシュフローは1,754億ドルの拡大、固定資産投資は680億ドルの拡大、R&D投資は887億ドルの拡大であった。その一方で、現預金残高は3,557億ドルの大幅な拡大となった(第Ⅱ-1-6-19図)。
第Ⅱ-1-6-19図 米国における上場企業とGAFAMの営業キャッシュフロー、投資と現預金(2010年~2019年)
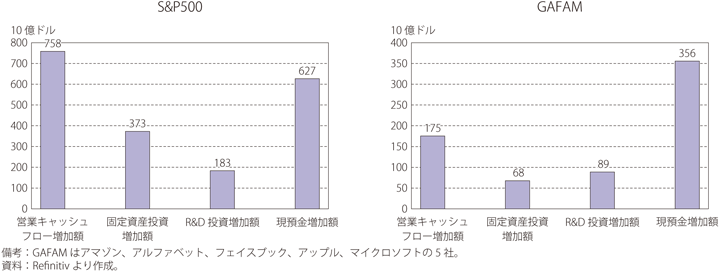
GAFAMにおける現預金保有の大きさに関しては、イノベーションや人材・無形資産への投資に回る比重が高く、工場などへの有形資産向けの投資金額が少ないために手元に資金が残りやすいことも一因である。その上、有望なスタートアップをM&Aで迅速に買収するために潤沢な現預金を手元に有することが戦略としても合理的とされる。
企業の集中度や利益率の他にも企業の利益の拡大、参入・退出の低下というダイナミズムの低下、M&Aの増加と上場企業数の減少が見られる。このように、米国において企業の集中が見られている(第Ⅱ-1-6-20図)。
第Ⅱ-1-6-20図 米国における企業の集中の動向
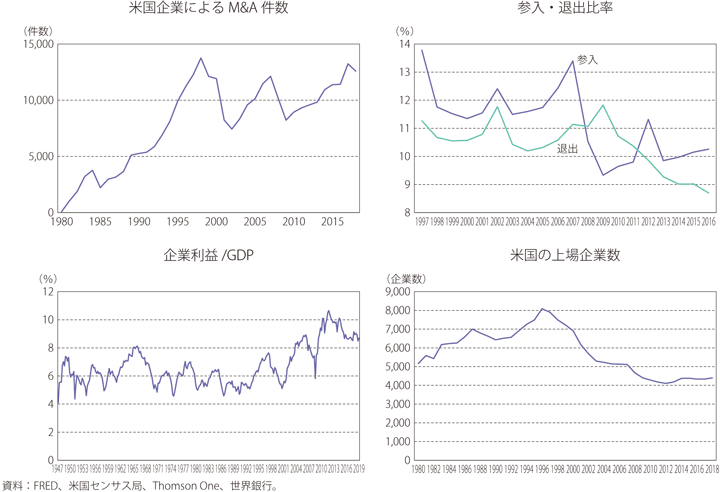
48 根来龍之・藤巻佐和子(2013)「バリューチェーン戦略論からレイヤー戦略論へ:産業のレイヤー構造化への対応」『早稲田国際経営研究』No.44,pp145-162
49 中村幹宏・根来龍之(2016)「IT化による自動車産業のレイヤー構造化 ~自動車産業における3つの「レイヤー戦略モデル」~」早稲田大学IT戦略研究所ワーキングペーパーシリーズ No.55
50 外国企業との競争によって影響を受ける産業ではマークアップが減少することが1990年代から2000年代の前半において米国で見られた(Feenstra and Weinstein, 2017)。マークアップとは、投入コストに対して販売価格に上乗せされる度合いを示すものであり、利ざやの指標となるものである。米国では1992年から2005年の間に輸入比率が上がるとともに米国企業のマークアップが約0.5%ポイント低下し、この間に米国の消費者の厚生はマークアップの低下と選択肢の増加によって約1%近く増加した。
51 Philippon (2019)
52 Matthew Hindman.2018. The Internet Trap: How the Digital Economy Builds Monopolies and Undermines Democracy Princeton University Press.
2.コロナテックの急速な社会実装の進展
新型コロナウイルスの感染拡大を契機として、対面での活動を補完するデジタルサービスや感染症の拡大防止に向けた技術革新が進展しており、その社会実装が進んでいる。これらは、コロナテックともいわれる。
(1)コロナテックの技術革新と社会実装
コロナテックの一例としては、新型コロナウイルス対策のアプリがある。例えば、中国や韓国においては、位置情報といったデータから、感染者の行動・接触情報を把握する。スマートフォンに示すアプリを開発し、中国や韓国での感染者の行動把握のほか、英国やシンガポールなどでも、ブルートゥース技術を用いて濃厚接触者を把握するアプリが導入されている。
次に、人の接触を避けるため無人化が進められている。AIを使った自動診断、健康確認によって5m以内の15人/秒の人混みから高体温者が識別可能であり、感染の疑いのある人を見つけ出す技術が実用化されている。また、ロボットやドローンを使った汚染地域での配膳、監視や消毒等が行われるなど、安全・効率的な感染症抑え込みの取り組みが進められている。中国においては、ドローンによる物資輸送は、輸送物と人員の接触を減らし医療物資の二次汚染を防ぎながら、通常の道路輸送に比べ効率を50%以上向上させていると言われる。
さらに、遠隔通信についても導入が進められている。これまでも技術的に可能であった遠隔医療、教育、テレワーク等が新型コロナウイルスの感染拡大を受け急拡大している。中国ではピークとなった2月には人口の約14億人のうち3億人がテレワークを実施したともいわれており、テレワーク支援ツールとしてテレビ通話やチャットが爆発的に普及した。アリババ集団のDingTalkはテレワーク向けのサービスとして、1,000万以上の企業や組織に採用されている。
5GやVRの導入を進める病院等も中国において見られている。新型コロナウイルスの感染の震源地であった武漢において、専門病院が建設されたが、その病院では、5Gによる映像伝送を用いた遠隔診療によって、医療者と感染者の接触を防ぎ、感染拡大を抑制する仕組みが導入された。
中国におけるイノベーションの特徴は膨大なデータを収集しそれを日々の活用により更新していくことにある。コロナテックにおいても、そのイノベーションの特徴を活かし、テクノロジーの積極的な社会実装が進められている。
台湾では、マスクと健康保険証のIDナンバーを紐づけることで、マスクの需給ひっ迫に対応した。
このような取り組みは、政府から個人への情報提供、人々の行動変容等の中長期的な感染拡大防止政策への活用が期待される一方、ITプラットフォーマーへのデータの集中が更に進む可能性が存在している。また、コロナテックにおいては、技術革新と社会実装が進展する地域での経験をもとに、他の地域へ技術を導入する動きが見られている(第Ⅱ-1-6-21表)。
第Ⅱ-1-6-21表 技術革新と社会実装の例
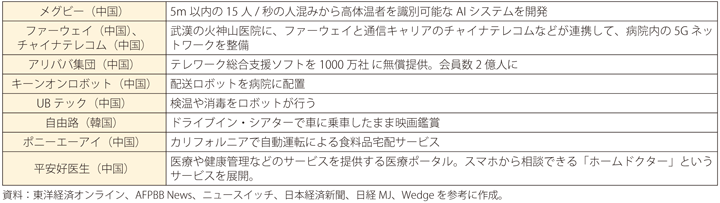
(2)新型コロナウイルスの拡散防止に向けたデジタル技術の活用
新型コロナウイルスの拡散防止に向けたデジタル技術の活用もスマートフォンのアプリやガイドラインの設定等を通じて各地で進められている。アプリ等を用いて位置データや人の接触データを収集することで、感染者や接触者の情報を把握し、個人への情報提供、人々の行動変容、中長期的な感染防止政策に活用されている。
中国では、中央・地方政府とアリババやテンセントといったITプラットフォーマーが連携して、新型コロナウイルスの感染者を検知する「健康コード」アプリが実装されている。アプリをインストールすると、最初に情報提出への同意が求められ、これに同意した後、個人情報や健康状態等を入力する。衛星による位置情報を使用することで、感染状況にかかわらずユーザはトラッキングされる。収集された情報は「健康コード」システムに保存され、政府データベース等と情報共有することで、「緑」(非感染者)、「黄」(疑似感染者)、「赤」(感染者)というステイタスでユーザを区分する。ステイタスに基づく行動制限には地域によってばらつきがあるが、「緑」の表示がなければ、公共交通機関、オフィス、商業施設、観光地の利用ができない地域も存在する。
韓国では、自己隔離者が保健当局に健康状態を報告するアプリ「自己隔離者安全保護」を行政安全部が作成した。アプリのインストールは任意であるものの、海外からの入国者には必須となる。自己隔離者は、アプリを通して保健当局に健康状態を報告し、保健当局は、アプリのGPS位置情報を通じて、自己隔離の条件に反しないように自己隔離者の位置情報を把握する。自己隔離者が隔離場所を離れた場合には、ユーザに警告メッセージが通知される。自己隔離措置の違反者が散見されたことから、行動追跡用に違反者が装着する電子リストバンド「安心バンド」を導入している。また、接触者の追跡情報は疫学調査の重要な一部とし、2015年に感染症予防法を改正し、GPS位置情報、クレジットカードの履歴や防犯カメラの映像等を用いることで個人の行動を追跡し、匿名でホームページで公開している。こうした疫学調査を支援するため、国家戦略スマートシティ研究開発プログラムの下、国土交通部がオンライン疫学調査支援システムを開発し、警察、通信会社、クレジットカード会社等の協力により、疫学調査担当者による感染者の特定やクラスター検知を迅速化している。
シンガポールでは、スマートフォンのBluetoothを使用し、利用者の接触履歴を記録するスマートフォンアプリ「TraceTogether」を政府が開発した。アプリのインストールは任意であるものの、国民の約20%にあたる110万人がインストールしている。保健当局は、感染者が発生した場合、感染者の接触者本人に直接連絡し、医療指導等を行う。
欧州では、8か国130人以上の科学者等が、欧州一般データ保護規則(GDPR)に準拠した各国の接触追跡アプリの設計・開発を支援するため、アプリ設計・開発のためのモジュールやツールを提供する取り組み「Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing(PEPP-PT)」を公表した。また、プライバシーへの配慮から、分散管理型モデル(接触データを中央サーバーに保存せず、個別端末のみで管理するモデル)を提唱するイニシアチブとして、欧州の複数の研究機関の研究者によって設計された分散型プライバシー保護接触追跡「DP-3T」が発表された。欧州委員会は4月16日に新型コロナウイルスの感染拡大対策の一環として、接触追跡を支援するためのモバイルアプリ開発のためのガイダンス「接触の追跡と警告のためのモバイルアプリの利用に関するEUツールボックス」を公表した。この中で、接触者の追跡は、危機管理の全段階、特に非エスカレーション時の封じ込め対策の一環として重要な役割を果たすとの認識を示す一方で、プライバシー及び個人の権利・自由に対する影響の大きさに鑑み、欧州共通のアプローチが必要であると強調した。ツールボックスは接触の追跡・警告用アプリの導入について加盟国に実践的な指針を示したもので、アプリが満たすべき要件として、EUのデータ保護・プライバシー関連ルールの完全な順守、アプリのインストールは任意であること等が示された。また、Bluetoothによる近接通信技術等、利用者の位置情報を用いない技術や匿名化されたデータを用いることや、感染者自身の情報を開示することなく警告し、検査や自主的な隔離を行えるようにすることも示された。
アップルとグーグルは共同で、Bluetoothを利用して、新型コロナウイルス感染者への濃厚接触可能性を検出するために、保健当局が提供するアプリがアンドロイドOSとiOSとの間で相互に機能することを可能にするアプリケーション・プログラミング・インターフェイス(API)を公開し、同機能をOSレベルで組み込む計画を発表した。両社のAPIを利用し、各国の保健当局または委託を受けたディベロッパーがアプリを開発する。アプリのインストールは任意である。なお、第Ⅱ-1-6-10図に見るように、アンドロイドOS、iOSはスマートフォンのシェアにおいて概ね100%を占める。
このように、感染拡大の防止という課題の中で、デジタル技術を活用した対策が進められている。その中で、個人情報への配慮に関しては国によって差異が見られ、プライバシーと公衆衛生のバランスという課題について議論が起こっている。(第Ⅱ-1-6-22表)。
第Ⅱ-1-6-22表 各国の新型コロナウイルスの拡散防止に向けたデジタル技術の活用