

- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2020

- 白書2020(HTML版)

- 第Ⅱ部 第1章 第7節 ドルへの集中と新興・途上国のリスク拡大
第7節 ドルへの集中と新興・途上国のリスク拡大
新型コロナウイルスの感染拡大を契機として、生産拠点の集中度の高まり、都市への集中、ITプラットフォーマーへの集中のように、多くの分野において集中が見られていたことが明らかになっている。本節では資金のドルへの集中に焦点を当てる。
ドルは世界の基軸通貨であり、ドルへの集中は長年存在してきたが、コロナショックの発生後にドルへの需要が拡大することとなり、ドルを用いる新興国や途上国における金融リスクも指摘されることとなった。その中で、資金の支払いに滞りが生じる場合には、サプライチェーンの停滞につながる恐れも存在している。
1.ドルへの集中
コロナショックにおいてドル(現金)への需要の高まりが見られた。このドルへの集中は長年見られてきたものであり、基軸通貨であるドルへの需要は経済危機時において顕在化する。近年の例としては、2007年から2008年の世界金融危機においてドル不足が見られた。米国の金融機関の破綻と各国中央銀行の協調は、マネーの集中と世界経済の相互関係を明らかにするものであった。世界金融危機の震源地であった米国から世界へと影響が波及し、いくつかの国では米国以上の経済収縮に直面することとなった。その危機の波及経路の一つとしてドル不足があり、その対処として各地で流動性供給が行われた。2020年に新型コロナウイルスの感染が世界的に拡大した際に、ドル不足は改めて生じることとなった。
ドルへの集中の要因としては取引費用の存在を挙げることができる。取引費用が存在するものは集中を促す傾向がある。同じものを用いることにより取引費用を低下させることができ、その結果、ドルへの集中が特に決済で見られている。日本では相対的に高い割合で自国通貨の円が貿易の決済通貨として使われているものの、ドルを貿易の決済通貨として用いる国が途上国を中心に多く存在している(第Ⅱ-1-7-1図)。
第Ⅱ-1-7-1図 貿易決済通貨に占めるドルの割合
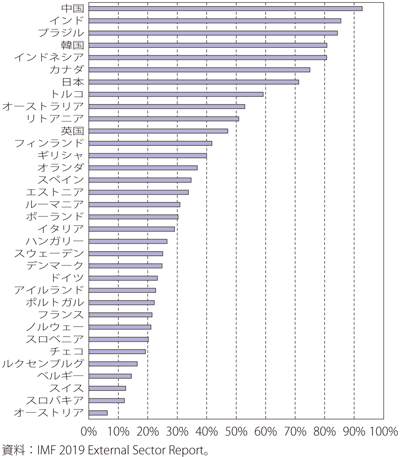
本来であれば、特定の2国間であれば、それぞれの国の通貨のレートを意識すればよい。しかし、現実に起こっていることは、ドルの利用である。例えば、韓国とブラジルであればドルで取引を行う必然性は必ずしも存在しない。為替面から見れば、それぞれの通貨のみに注目をすれば良いからである。その場合でも、主にドルを用いた取引が行われている。ドルは世界中で通じる基軸通貨であり、取引費用を減少させる。その結果として、米国を介さない場合でも、ドルが2国間の決済をつなぐという形でドルへの集中が見られている。
また、取引費用を低下させる要因としては、ドルの流動性の高さや安定性を挙げることもできる。財では供給が多いと価格が下がるが、基軸通貨に関しては、供給が多いほど流動性が確保される分だけ価値が高いものとなる53。
さらに、ドルの利用を促す要因として、新興・途上国経済の拡大も挙げることができる。新興・途上国の経済発展の中でドルの利用が進んでいるが、世界経済に占める新興・途上国の割合が現在6割前後にまで増加しており、ドルの利用が多い新興・途上国の貿易比重が高まる中で、世界全体で見たドルへの集中の傾向は高くなっている。
また、外貨準備におけるドルの比率も高いものとなっている。通貨としての安定性を有し、流動性がある通貨であれば外貨準備としての条件を満たすため、準備通貨は必ずしもドルである必要はない。しかし、米国の経済規模との比較において、ドルの外貨準備に占める割合の高さは特筆すべきものとなっている。米国の経済規模は世界経済の2割程度であるものの、ドルの外貨準備は世界の準備通貨の6割強となっている。同様に世界経済の2割程度を占めるユーロはドルを代替するほどではない(第Ⅱ-1-7-2図)。
第Ⅱ-1-7-2図 外貨準備の通貨構成
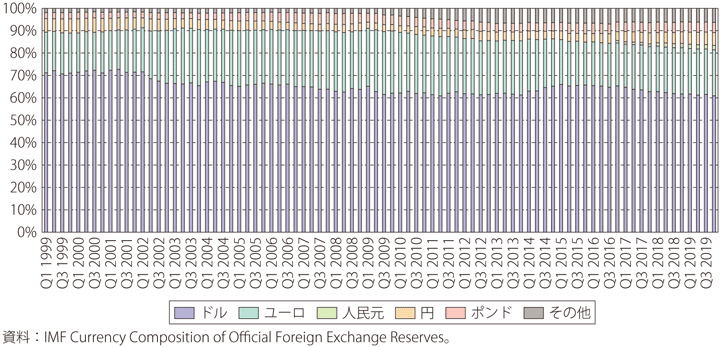
53 基軸通貨の価値と流動性の関係に関してはIlzetzki et al. (2019)、安全資産の価値と流動性の関係に関してはHabib et al. (2020)。
2.ドル集中と新興・途上国のリスク・サプライチェーンへの波及
このドルへの集中によって、米国の経済状況や金利の変化により新興・途上国の債務は大きく反応する傾向が見られる(第Ⅱ-1-7-3図)54。これは、新興・途上国の外貨建て債務のうちドル建ての比率が約3分の2となっていることによるものであり、1995年のメキシコ危機や、2013年春の米国の長期金利上昇、2018年秋の米国の長期金利上昇の後に一部の新興・途上国の債務への懸念が高まる場面が見られた。
第Ⅱ-1-7-3図 米国の政策金利変更に対する新興・途上国における対外債務の変化
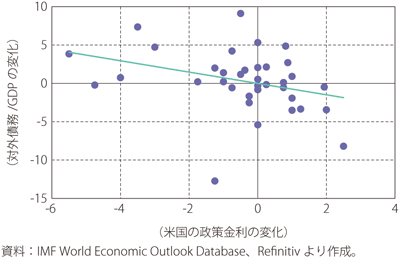
この米国の金融政策を通じた国境を越えた資金の流れは、米国の銀行ではなく主として欧州・日本など米国以外の先進国の銀行が媒介するものとなっている。このように、グローバルな金融仲介機能もドルへと集中している(第Ⅱ-1-7-4図)55。
第Ⅱ-1-7-4図 米国の政策金利とクロスボーダー銀行資金フロー
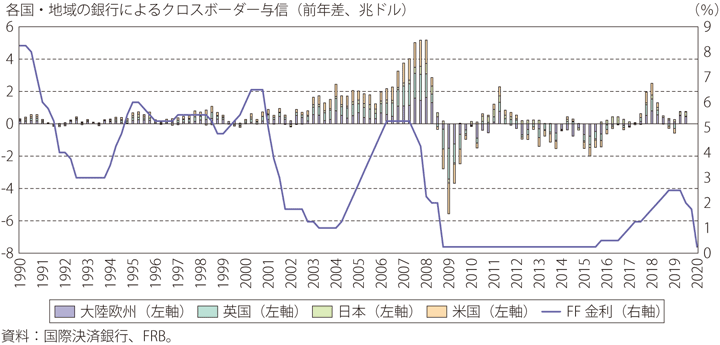
このようなドルへの集中の中で、ドルへの需要は高まり続け、他方で、世界経済が拡大を続けると、米国は対外的にドルを供給し続けることが必要となる。こうしたドルの供給という基軸通貨の役割を巡り、過去に二度、世界経済は不安定な状況に陥った。
まず、1960年代後半から1970年代初頭にかけて、金とドルの等価での兌換を維持することが困難になった末に、ニクソン・ショックが発生した。ドルと金の交換に応じられないほど米国の金の保有量が減少し、第二次世界大戦後における金とドルを中心としたブレトンウッズ体制を維持することが困難になった。
次に、2000年代の世界金融危機の以前の世界経済においては、米国が巨額の経常赤字を通じて基軸通貨であるドルの供給を行っていたところであったが、世界金融危機の発生により、これが持続不可能な構造であることが認識された。
これらの2つの例は、いずれも世界経済に大きなショックをもたらす結果となった。
そして、新型コロナウイルスの感染拡大の過程において、ドルへの集中度の高まりのリスクは改めて示された。新型コロナウイルスの感染拡大の中で世界的にドル現金の確保が見られる中、ドルの調達コストが上昇した。その結果、2020年の3月15日には、FRBと各国の中央銀行が協調し、米ドル・スワップ取極を通じた流動性供給を拡充するための協調行動が行われることとなった。
しかし、各新興国から急速に株式や債券投資が流出しており、その速度は過去の経済危機と比べても急速なものとなっている(第Ⅱ-1-7-5図)。
第Ⅱ-1-7-5図 新興国からの株式・債券投資の流出(対GDP比)
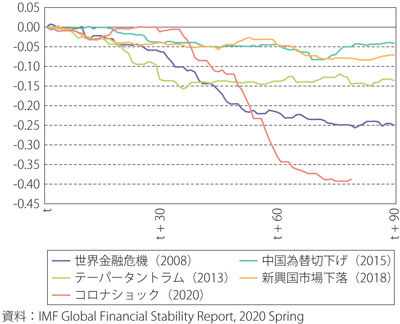
そこで、どの国・地域がドル負債を保有しているかを確認していく。国際金融協会(Institute for International Finance)によれば、アジアの新興国は香港やシンガポールを除いて外国通貨建ての負債は必ずしも大きくはなく、ラテンアメリカ諸国においてドル負債の比率が高いものとなっている(第Ⅱ-1-7-6表)。
第Ⅱ-1-7-6表 新興国の部門ごとの債務の通貨構成
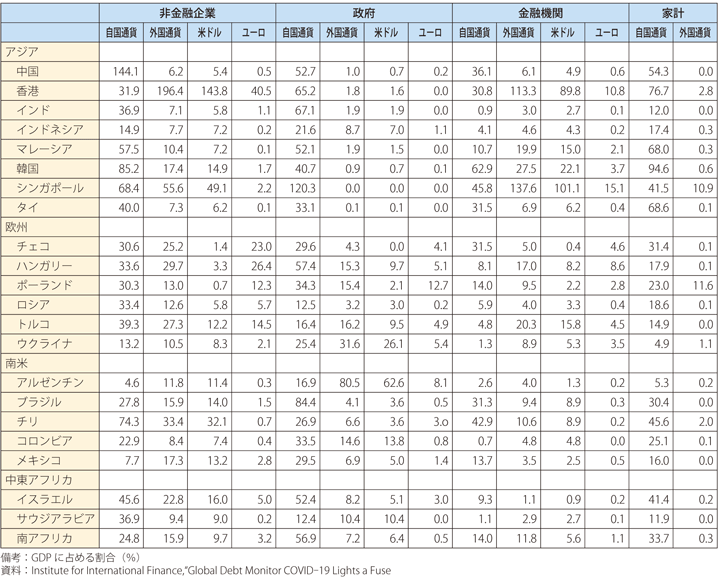
その一方で、近年アジア新興国においては、ドル建ての信用が拡大をしている(第Ⅱ-1-7-7図)。
第Ⅱ-1-7-7図 アジア各国へのドル建ての信用
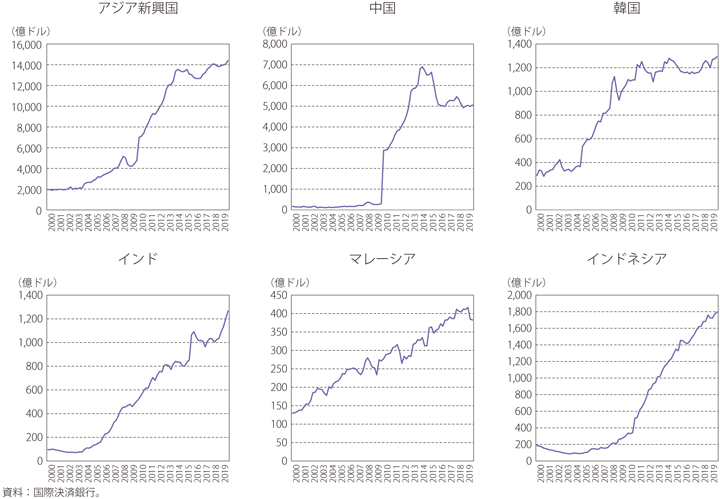
世界金融危機以前は欧州でのドル負債の増加が見られたが、現在は、ドル負債の増加は新興国や途上国で発生している。それは、概ね以下のような構造となっている(第Ⅱ-1-7-8図)56。
第Ⅱ-1-7-8図 資金の流れとバランスシート構成
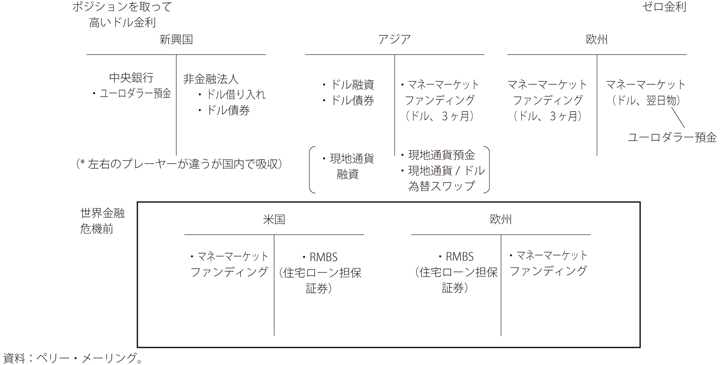
新興国の企業が、ドル建てで借り入れを行う場合には、融資はアジアなどの銀行が行う。アジアの銀行はその資金を調達するために、マネーマーケットで3ヶ月もののドルを調達するか、または自国通貨での調達を行って為替スワップでドルに交換する。そのマネーマーケットの3ヶ月ものドル融資を行うのは、欧州の銀行である。その欧州の銀行はユーロドル預金でファイナンスする。そしてユーロドル預金を行うものは、新興国の中央銀行である。
この構造は、新興国においてはドル建ての金利が高いものの、欧州ではゼロに近く、その差により、アジアの銀行もヨーロッパの銀行もマージンを取ることができるという状況から発生するものであり、近年、この構造が著しく拡大している。
その過程には米国が関与しないことに特徴がある。ドル貿易・ドル決済が増加する背景としては新興国の事業者がドル建てでの借り入れを行うことにあり、これが、世界でドル不足が発生をする要因の一つとなっている。
このような資金調達のチェーンは、サプライチェーンにも影響しうるものである。サプライチェーンは裏側から見れば、資金の支払いのチェーンでもあり、そのため、生産の停止は資金支払いの遅延にもつながるものである57。
外的な経済ショックによって生産や出荷、サービスの提供が停止した場合でも、原則として債務の返済が必要であり、サプライチェーンの停止は支払いのチェーンの停止にもつながり得る。
例えば、中国が最終組立地として日本や韓国から中間財を提供する場合において、中国から生産物が出荷されない場合には、中国の最終財の組立・販売業者は中間財の供給者への支払いの資金を得ることができず、中間財を提供する日本や韓国の企業へ支払いをすることができなくなり、結果、中間財を提供する日本や韓国の企業は資金を得ることが困難となる。このように、サプライチェーンの関連企業に影響することとなる。
新興国ではドル資金の調達が行われており、危機時には資本流出が発生する。危機時の資本流出としては短期債務に注目が集まる傾向があるが、長期債務であっても利払い費は必要となる。その利払いには営業収益が必要となるが、ドルが流入しない期間が長期化すれば、債務の利子部分の返済も困難になる。
そして、サプライチェーンが滞ることで赤字が累積すると更なる資金調達が必要となるが、それは同時に金利上昇圧力にもなり得るものである。
この観点から、2つのリスクを検討しよう。
まず、ドル支払とドル受取のミスマッチである。輸出産業を例に取ると、仕入れをドル圏の海外に依存する場合、まず仕入れをするためにドルの支払いが先に必要となる。一方、それを支払うためのドルは、輸出をした後、つまり売上の計上の後に支払い用のドルを入手することが可能となるというミスマッチが生じることとなる。第Ⅱ-1-7-9図においては、新興国の非金融法人が直面するものであり、取引が継続する場合にはこの問題が顕在化しないものの、ドルの流動性が十分に機能せず、売上が蒸発する場合には短期的な資金繰り面でドル不足に陥りやすくなっている。
さらにアジアではドル決済の比率が高く、インボイス通貨推計ではインドやインドネシアの輸入の8割がドルである58(第Ⅱ-1-7-9図)。これらの国々は、企業の売上が急速に縮小する場合にはドル不足に陥るリスクがあり、サプライチェーンにも波及し得る。
第Ⅱ-1-7-9図 各国の米国からの輸入割合とドル決済比率
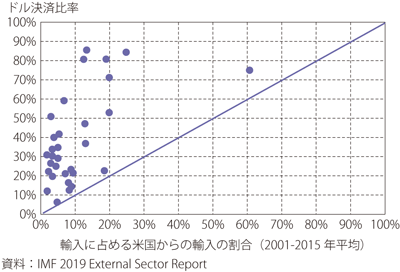
次に、サプライチェーンの裾野の広さに伴うリスクである。サプライチェーンの裾野が広いほど、一部の停止が他に波及する可能性がある。サプライチェーンの裾野の広さは付加価値と総生産額の違いから測ることができる。総生産額は総売上高でもあり、付加価値に対する総生産額の比率が高い場合にはサプライチェーンの裾野が広がっていると見ることができる。
アジア・大洋州の主要国における製造業分野の付加価値と生産額の比率をサプライチェーンの裾野の広さとして見ると、アジア各国においてはサプライチェーンの裾野が広いものとなっている(第Ⅱ-1-7-10図)。これはサプライチェーンが各国の国内に留まるものではなく、第Ⅱ部第1章第2節でみたように、アジア域内においてはIT製品を中心にサプライチェーンが広がることを示すものである。さらに、アジア各国の国境を越える取引においてはドル決済が用いられやすい(第Ⅱ-1-7-11図)。他方、最終的に組み立てられた財の多くは欧米に輸出される。
第Ⅱ-1-7-10図 サプライチェーンの裾野の広さ
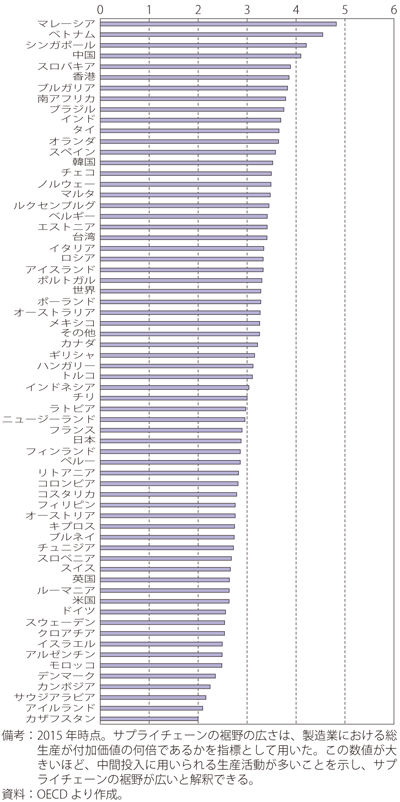
第Ⅱ-1-7-11図 アジア・大洋州主要国におけるサプライチェーンの裾野の広さとドル決済比率
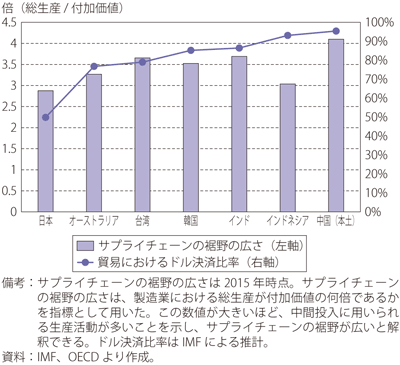
こうした状況は、アジア地域において最終財を生産し販売する川下企業が、欧米の需要蒸発に直面した場合にサプライチェーンに参画する企業に対する支払いが滞ることのリスクが大きいことを意味する。つまり、アジアにおける売上へのショックは、ドル支払いのチェーンとサプライチェーンという2つのチェーンを通じて世界にも波及しやすいものとも言える。
このように、世界的なドルへの集中の結果として、危機発生時のリスクが存在している。そして、米国が関与しない形でのドルの流通の拡大は、このようなリスクに対処するに当たっては、グローバルなシステムとの協調が重要であることを示唆するものである。
実際に、新型コロナウイルスの感染が拡大する中で、3月19日にFRBはドル流動性を融通するスワップラインの取り決めに、新たに9行の中央銀行を加え、世界的にドルの流動性を供給することを行った。また、3月31日には、海外の中央銀行が保有する米国債を利用して翌日物のドル資金の調達を可能にすることをFRBは公表した。
新型コロナウイルスの感染拡大は世界の構造を改めて明らかにするものであった。それは、グローバリゼーションと並行して、人や生産拠点、資金などが集中する経済構造が生じていることである。
グローバリゼーションは、世界をフラットなものとすることが想定されてきた。その代表的な例である「フラット化する世界」と表現されてから15年が経過する59。その想定通り、あるいはそれ以上のスピードでSNSやデジタル分野のグローバリゼーションは進んだともいえるものの、それは必ずしもフラットではなく、企業、都市、金融がそれぞれ集中することで、人や物、資金、アイデアの相互の関係が深まり、想定外のリスクに対して脆弱になるという側面もある。その結果として生じるリスクは世界規模のものであり、その対処に当たっても国際協調が重要性であることを明らかにするものであった。
54 現在では、国際金融のトリレンマではなくジレンマとも言われる。国際金融のトリレンマは、自由な資本市場、固定相場制、独立した金融政策の3つが同時に成り立つことはないことを示したものである。しかし、各国のドルへの依存が高いために変動為替相場制が米国の金融サイクルの影響を抑制するという通説は成り立ちにくい。このため、米国以外の国は自由な資本市場、独立した金融政策の2つのうちどちらか1つを断念しないといけないというジレンマに陥りやすい(Rey, 2013)。
55 Correa (2018)
56 ボストン大学のペリー・メーリングによる。
57 Zoltan Pozsar and James Sweeney (2020) “Global Money Notes #27 Covid-19 and Global Dollar Funding” Credit Swiss Economics
58 IMFの2019 External Sector Report
59 トーマス・フリードマンは2005年の著作で“The world is flat”と述べた。
