

- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2020

- 白書2020(HTML版)

- 第Ⅱ部 第1章 第1節 新型コロナウイルスの感染拡大とサプライチェーンのリスク:生産体制、物流、人の移動
第1章 コロナショックが明らかにした世界の構造
第1節 新型コロナウイルスの感染拡大とサプライチェーンのリスク:生産体制、物流、人の移動
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、当初は中国発、次いで欧米発と複数回にわたって世界中でサプライチェーンの寸断が見られた。このような新型コロナウイルスの感染拡大を発端としたサプライチェーンの寸断には、産業特性と国・地域特性が影響した。こうした産業特性と国・地域特性の双方に関連するサプライチェーンの重要な構成要素として、生産体制、物流、人の移動の三要素を挙げることができる。
本節では、これらサプライチェーンの構成要素の特性を踏まえた上で、新型コロナウイルスの感染拡大を通じて顕在化した課題を示す。その課題は従来から認識されていたサプライチェーンに関する課題の延長線上にあるものであり、新型コロナウイルスの感染拡大に際して、従来からの課題を再認識し、課題克服の機会とすることが求められる。
1.サプライチェーンの特性から見た新型コロナウイルス感染拡大前の状況と新型コロナウイルス感染拡大が与えた影響
新型コロナウイルスの感染拡大を受けたサプライチェーンの寸断は、第Ⅱ-1-1-1図に示すように、生産、物流、人の移動という多岐にわたる要因により、各地で顕在化した。
第Ⅱ-1-1-1図 新型コロナウイルスの感染拡大を受けたサプライチェーンの寸断の一例
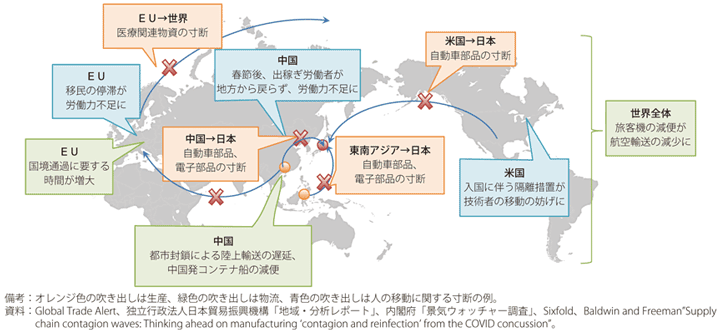
まず、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて象徴的な動きを示した財を中心に、生産体制、物流、人の移動、財・サービスの性質に即してサプライチェーンの特性を分類し、新型コロナウイルスの感染拡大前の状況と新型コロナウイルスの感染拡大の影響を整理する。
生産活動の状況を確認しよう。そのサプライチェーンの寸断や需要の減少により、日本では生産活動の停滞が見られている。日本の鉱工業生産指数は2020年3月には前月比で3.7%の低下となり、4月には前月比で9.1%の低下となった。業種別にみると、輸送機械工業、鉄鋼・非鉄金属工業、汎用・業務用機械工業の生産が2月から4月にかけて大幅に低下した(第Ⅱ-1-1-2図)。製造工業生産予測指数によると、輸送機械工業に加えて、自動車向けに供給を行う鉄鋼・非鉄金属工業において、5月に大きな前月比での低下が見込まれる一方、6月には前月比で上昇に転じることが見込まれている。
第Ⅱ-1-1-2図 日本の製造工業の生産指数(2020年2~4月実績、5・6月予測指数)
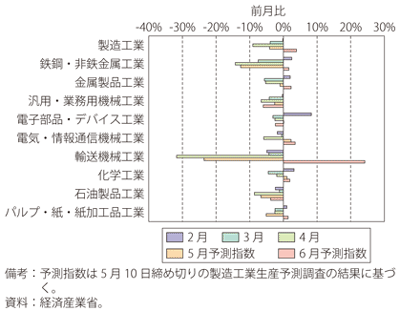
以下では、自動車、IT製品、医療用品、食糧・食品を代表例としてサプライチェーンに関する特性を順に整理していく。
(1)自動車、IT製品
第Ⅱ-1-1-3表において、自動車とIT製品のサプライチェーンに関する特性を、生産体制、物流、人の移動、財・サービスの性質に即して分類し、新型コロナウイルスの感染拡大前の状況と新型コロナウイルス感染拡大が与えた影響を整理した。
第Ⅱ-1-1-3表 自動車とIT製品のサプライチェーンの特性
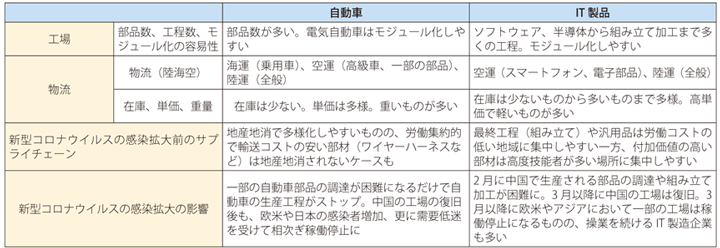
自動車の生産体制における特徴としては、労働集約的な部品(ワイヤーハーネス等)の生産拠点が集中しやすく、部品数も2~3万点と多い点が挙げられる。物流面については、重量の重さも影響して、貿易時の輸送手段として比較的時間を要する海上輸送を用いることが多い一方、在庫が少ない点が特徴である。
今般のコロナウイルスの感染拡大について生産体制から見ると、一部の生産拠点の稼働が停止することで、そこで生産する一部の部品が次の生産工程に対して供給できなくなったものである。このように一部の自動車部品の供給が滞るだけで、自動車の生産工程全体が停止しやすい。
さらに、物流面については、部材の生産が停止すると、部材の在庫があるうちはそれを用いて生産活動の維持が可能であるが、部材の輸送停止が長引いた場合は部材不足に陥り、工場が稼働停止するということが見られた。アジアと欧米間の海上輸送の場合、長ければ2ヶ月前後を要するが、自動車産業全体で見ると平均的に保有する在庫は売上の1ヶ月未満である。このため、数週間は部材の在庫を用いて生産活動の維持が可能であるが、部材が輸送されない状況が長引くとその部材を活用して生産活動を行う工場は生産の継続が難しくなる。また、部材を供給するための海上輸送、陸上輸送のいずれかの寸断・遅延によっても部材の供給は滞ることとなる。この場合、輸送コストは高くなるものの、海上輸送を航空輸送に切り替えることによってサプライチェーンの維持を重視した例も見られた。
また、電気自動車においては、部品が共通化しやすいモジュール生産が特徴であり、部品数は従来の自動車に比べて少ないものの1万点程度あることに加え、人の接触を避ける観点から出勤停止措置が取られたことも影響し、電気自動車メーカーの上海工場が一時的に稼働停止した。
次にIT製品においては、ソフトウェア、半導体から組み立て加工に至るまで多くの工程に分かれており、モジュール化しやすい点が生産体制に関する特徴である。物流に関しては、高付加価値品が多く、軽量であることから、物流の時間短縮が重視されやすく、海上輸送よりも航空輸送されることが多い。在庫に関しては少ないケースから多いケースまで混在する。委託生産方式でスマートフォンやパソコンを調達して販売する企業も米国をはじめ各国に存在しており、これは実質的に生産や在庫を持たないことと同様である。一方、受託生産する側の中国や台湾の地場企業は大規模な生産設備を有し、在庫を有する。
また、高付加価値なIT製品は資本集約的であるものの、組立・加工作業のように労働集約的な工程も存在する。こうしたサプライチェーンの特徴を持つIT製品分野においては、新型コロナウイルスの感染拡大に直面し、一部の生産拠点において組立・加工されるスマートフォン、パソコンの製品供給が滞る状況も一時的に見られた。中国での委託生産方式を早くから採り入れ、自身は在庫や生産拠点を持たない経営を行う米国のパソコンメーカーにおいては、受注から出荷までの遅延が見られた。また、中国からの部品の調達が遅れることで、日本のコピー機メーカーにおいても日本国内の生産ラインが停止する事例も見られた。
なお、自動車、IT製品のいずれにおいても、3月以降に中国の工場が復旧したが、その後、欧米や日本において労働者の感染増加を防ぐために工場の稼働が停止されるという事態も発生した。こうした中、自動車、自動車部品においては、感染者数の増加がピークアウトした後も、ロックダウン等の影響を受けた世界的な需要低迷から、減産のために工場の稼働が停止するという需要面からの影響も生じた。3月と4月の生産統計を見ると、供給ショックの影響を強く受けて大幅な生産減少となった自動車産業に対して、IT製品部門の生産は相対的に安定していたということも両者の違いである。これら自動車、IT製品に関しては、本章の第2節において詳しく整理していく。
(2)医療用品、食糧、食品
新型コロナウイルスの感染が拡大してサプライチェーンが寸断されたことで顕在化したもう一つの特徴的な事象は、医療物資の生産地である中国の工場が再稼働した後も日本の国内外において医療物資の供給不足が解消されなかった点である。
第Ⅱ-1-1-4表に整理したように、医療用品におけるサプライチェーンの特性は、部材や製品工程が少ない生産体制である点、労働集約的である点である。物流面では、高付加価値品は空輸が用いられることも多いが、汎用品は海上輸送されることが多い。マスク、防護服、消毒液は中国から世界に向けた輸出が多く、中国の生産が再稼働した後は海上輸送を空輸に切り替えて輸送するケースも見られたものの、日本を含む多くの国において品不足となる状況が続いた。これは、各国においてマスク、防護服、消毒液に対する需要が大幅に増加したことに加え、物流にも関連する規制要因として、多くの国において輸出制限が導入されたことも影響した。これらに関しては、本章の第2節と第5節において分析する。
第Ⅱ-1-1-4表 医療用品と食糧のサプライチェーンの特性
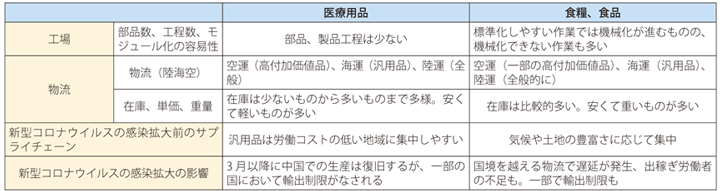
食糧分野、特に主要穀物や肉製品におけるサプライチェーンの特性は、大規模農場での機械化が進んでいるものの労働集約的な作業も多い点であり、気候や土地の豊富さに応じて生産が集中しやすい。こうした中、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて食糧の輸出に規制を設ける国も一部に見られた。また、国境を越える物流で遅延が発生したことに加え、農作業に従事する出稼ぎ労働者の人手不足が欧州では見られた。日本においては、中国製の玩具付きおもちゃ、食品トレー、キムチの調達などで遅延が見られた。新型コロナウイルスの感染拡大の影響が見られ始めた中国の春節を前にして2~3ヶ月分の在庫を確保していた食品メーカーが多くみられた。
(3)中国、欧米、アジアにおける新型コロナウイルスの感染拡大を受けた企業のサプライチェーンへの影響、企業の対応
新型コロナウイルスの感染拡大に直面して、自動車、IT製品、医療用品、食糧に加えて、それ以外の分野においても生産体制、物流、人の移動というサプライチェーンの構成要素を通じて影響が顕在化した。第Ⅱ-1-1-5表に示したように、システムキッチン、トイレを含む住設機器、電動アシスト自転車、アパレル製品、家庭用ゲーム機においても、中国の工場が稼働停止となり部材や商品の調達が遅れたことを起点に、サプライチェーンの寸断につながる状況となった。建設機械、工作機械においては中国以外の国・地域からの調達で代替するケースも見られた。
第Ⅱ-1-1-5表 中国における新型コロナウイルスの感染拡大を受けた企業のサプライチェーンへの影響、企業の対応
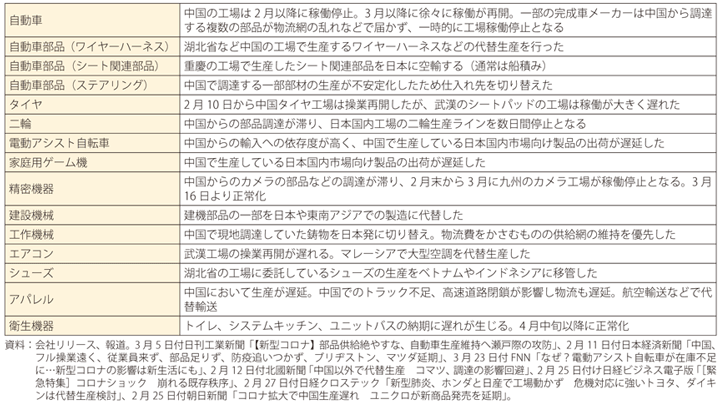
これまで見てきたように、サプライチェーンの寸断の起点となったのは工場の稼働停止だけではない。トラック不足、高速道路閉鎖が影響して物流も遅延したこともサプライチェーンの寸断につながる。こうした中、通常は中国から日本へ海上輸送されるアパレル分野では、遅延を防ぐために他の品目と同様に空輸されるケースも見られた。
第Ⅰ部第1章で整理したように、世界で感染拡大が見られる中で、供給・需要の双方へのショックが生じ、3月以降は欧米、東南アジア、インドにおいても工場の稼働停止が見られた。第Ⅱ-1-1-6表に示したように、欧米や東南アジアにおいても、中国同様に、自動車における減産が顕著に見られた。これに加えて、機械、電機機械、電子部品、航空機部品、素材、エンジニアリングなど広範な分野で生産停止や稼働低下が見られた。
第Ⅱ-1-1-6表 欧米やアジア(除く中国)における新型コロナウイルスの感染拡大を受けた企業のサプライチェーンへの影響、企業の対応
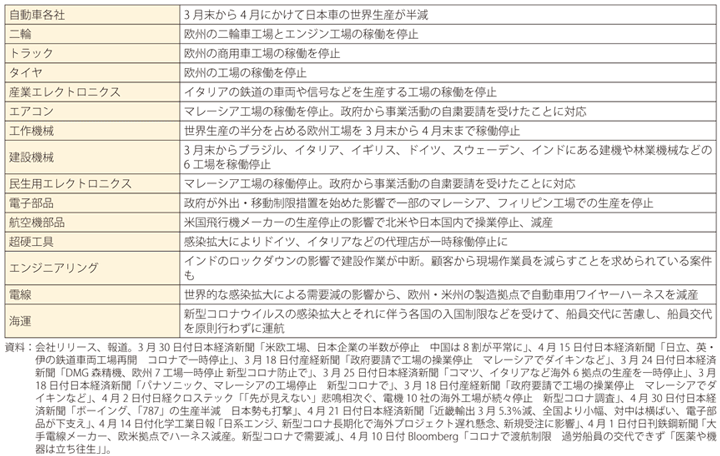
各産業によって異なるサプライチェーンの特性があることに加えて、国・地域によっては、移動制限や生産活動に対する政府の方針によっても稼働状況は影響を受けることとなった。国・地域によっては、政府が方針を定める前に労働組合の要望で操業や稼働を停止させるケースも見られた。また、海運においては船員の確保が困難な状況となることもあった。
このように、産業別に見たサプライチェーンの特性に応じて、生産拠点の集中、または、生産拠点の多様化の傾向が決定される側面もある。また、労働の観点からは、労働集約的であれば賃金に応じて生産拠点が集中しやすい。さらに、物流にかかる時間とコストも生産拠点が集中するか分散するかを左右する。これらに加えて、各国の規制、商品の寿命やサイクルにも応じて、集中や多様化の判断に影響を与える。その中で、サプライチェーンのネットワークの裾野が広く部品数が多い場合は、どの場所における生産でも、サプライチェーンが遮断されるリスクは波及しやすい。
一方で、産業特性とは別に、国・地域特性がサプライチェーンに影響する側面もある。例えば、日本におけるサプライチェーンの特徴としては、生産体制に関連して、効率的な生産体制、在庫の少なさ、海外生産比率の高さ、部品の海外からの輸入拡大が挙げられる。新型コロナウイルスの感染拡大により物流の停滞、人の移動の障害が生じると、こうした特性を有するサプライチェーンは、生産活動の停滞として影響が顕在化することとなった。
以上で整理したサプライチェーンの特性に関して、以下では、より詳細に生産体制、物流、人の移動の三点について分析を行う。
2.生産体制から見たサプライチェーンと新型コロナウイルス感染拡大の影響
生産体制について、日本の自動車産業を例に取ると、中間投入における生産拠点の集中度の高まりが明らかとなった。具体的には、自動車部品の中国からの輸入割合が上昇していたことから、日本、韓国、欧州の自動車メーカーで生産停止になるケースが見られた。
自動車部品の対中国貿易は、第Ⅱ-1-1-7図に見るように、日本と韓国のいずれにおいても中国向け輸出が中国からの輸入より大きいものの、中国からの輸入額が増加を続けていた。この点はドイツでも同様である。他方、メキシコにおいては、中国からの自動車部品の輸入が中国向けの自動車部品の輸出よりも大きくなり、2010年から2019年の間に中国からの自動車部品の輸入が4倍以上に大きく拡大した。
第Ⅱ-1-1-7図 自動車部品の対中国貿易
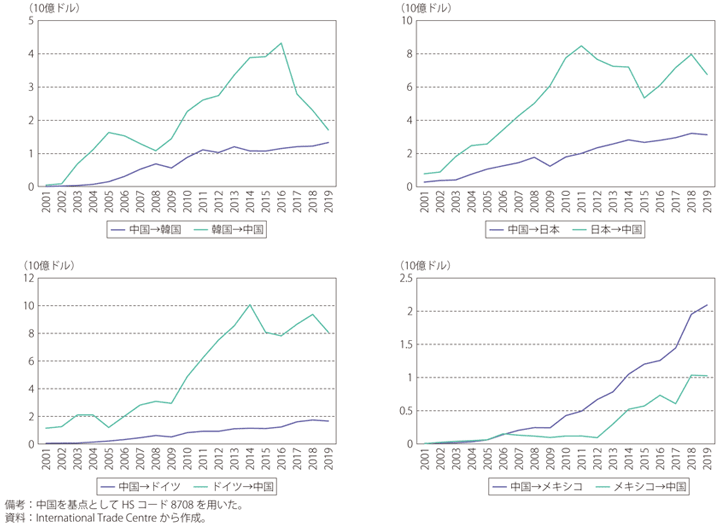
また、韓国の自動車生産においてワイヤーハーネスが調達できなくなったという例が示すように、生産工程が複雑化している中で、特定の部材の生産拠点が集中しているケースにおいては、中間投入に占める比率が小さい場合でも、その特定部材の生産が停止するだけで生産工程全体に影響が生じることが見られた。このことは、サプライチェーンの評価においては欠かせない部門を特定することが重要であることを示唆する。ワイヤーハーネスの輸出の国別の割合を見ると、第Ⅱ-1-1-8図のように、メキシコが2019年時点で19.0%と高い割合を維持している。また、中国は2001年の2.5%から2012年に11.5%に上昇し、その後は低下傾向にあるものの、2019年時点でも6.5%を占めている。ベトナムは2001年には0.5%であったものの、2000年代後半から2010年代にかけて上昇を続け、2019年に7.1%に達した。これらに次いで、ルーマニア(6.4%)、フィリピン(5.5%)における輸出割合が2019年時点では高いものとなっている。
第Ⅱ-1-1-8図 ワイヤーハーネスの輸出に占める各国の割合
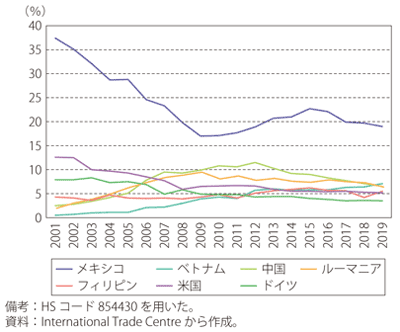
同様に、欧州においても、2月に中国からの自動車部品の供給が減少したために一部の欧州自動車メーカーが欧州の工場の稼働を停止する事態が見られた。3月以降に中国の生産が復旧を始めた後も、欧州域内での部品の調達が困難となったことから欧州の自動車の生産は停止した。欧州の自動車メーカーは欧州域内での国境を越えた生産を行っており1、ドイツの自動車メーカーでは、スペインやイタリアから部品供給を受けているが、国境の封鎖や各国での新型コロナウイルスの感染拡大に伴う生産の停止によって部品の調達が困難になり、ドイツの工場の生産に支障を来す事態となった。同様のサプライチェーンの影響は、他の自動車会社においても見られており、フランスの自動車会社でも同様の事態に直面した。
このように自動車のサプライチェーンに大きな影響をもたらしたのは、生産において欠かせない部材、物流、人の移動の遮断である。
脱脂綿、ガーゼ、包帯等においては、世界の輸出に対する中国の割合は18%と2割未満であったものの、2月以降に世界的に需要が急拡大した状況において供給が不足することとなった。そこで、天災や感染症の流行といった緊急時の需給を考慮に入れつつ、生産体制、物流、人の移動を通じたサプライチェーンへの影響を点検することは、新型コロナウイルスの感染拡大後の危機管理において重要な論点となる。
第Ⅱ-1-1-9図に見るように、スマートフォンを含む電話機において39%、パソコンにおいて40%、エアコンにおいて33%、衛生陶器を含む陶器において42%と世界輸出に占める中国の割合は高いものとなっている。第2節においては生産拠点の集中の観点から危機管理を取り上げる。
第Ⅱ-1-1-9図 各種品目における世界の輸出に占める各国の割合(2019年)
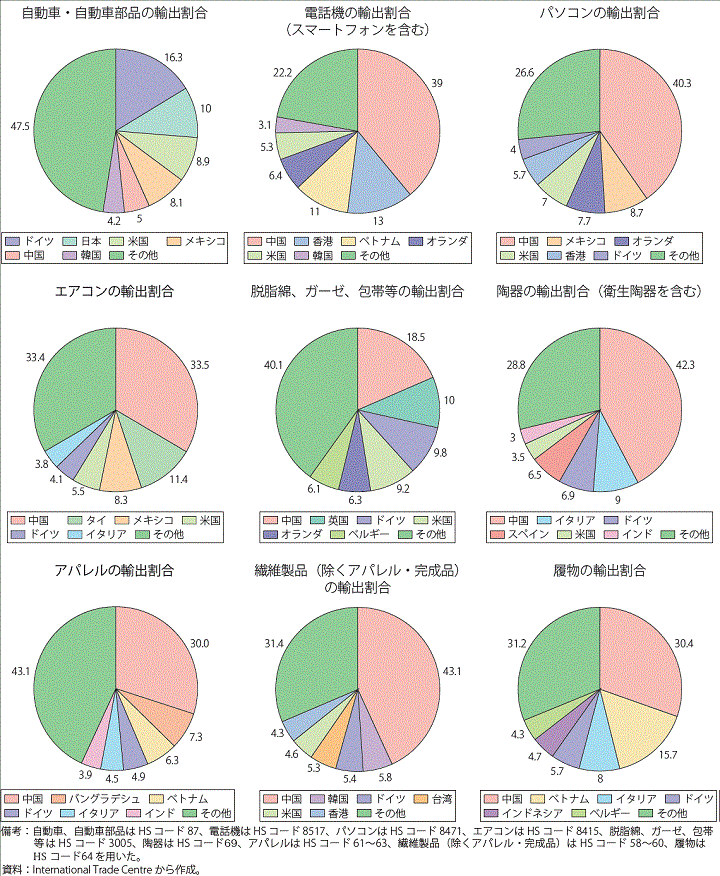
一方、電話機やパソコンにおいて世界最大の輸出国である中国は、香港経由の輸入も含むと、半導体集積回路の世界輸入の5割前後を、半導体製造装置の世界輸入の約3割を占めており、世界最大の輸入国でもある。
半導体集積回路の世界輸出の約3割は台湾が、半導体製造装置の世界輸出の約3割を日本が占めている(第Ⅱ-1-1-10図)。このように、IT製品においては、国・地域間の相互依存と、産業内貿易が極めて複雑に発展しており、この点は第2節において整理を行う。
第Ⅱ-1-1-10図 半導体集積回路、半導体製造装置における世界の輸出・輸入に占める各国の割合(2019年)
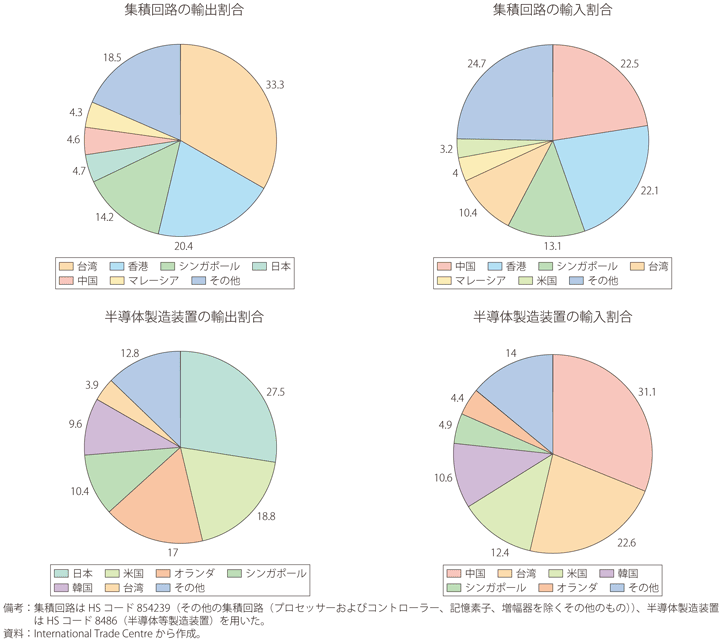
中国は世界最大の資源輸入国であり食糧輸入国でもある。中国は、第Ⅱ-1-1-11図に見るように、世界全体の銅の輸入において27%、鉱物性燃料の輸入において15%、魚介類の輸入において15%、肉の輸入において14%の輸入割合をそれぞれ有する。このように、中国の総輸入は世界の輸入総額の11%を占め、米国(14%)に次ぐ世界第二位の輸入国である。世界の輸出の13%と世界の輸入の11%を占める中国は、生産地としても消費地としても存在感を高めている(第Ⅱ-1-1-12図)。サプライチェーンは生産国・輸出国だけで成立するものではなく、消費国・輸入国も不可欠であり、相互依存の関係となっている。その相互依存の状況は局面に応じて変化するものであり、感染症の発生時においては医療用品への需要が高まり生産国・輸出国の存在感が大きなものとなる。反対に、供給過剰の場面においては購入国・輸入国の存在感が増す。第2節においては需要、供給両面からサプライチェーンの集中度を様々な角度から整理する。
第Ⅱ-1-1-11図 各種品目における世界の輸入に占める各国の割合(2019年)
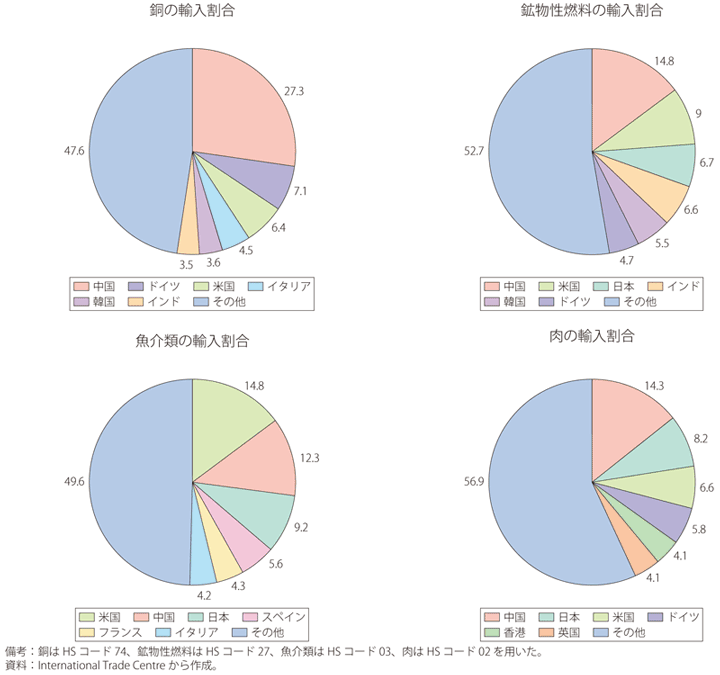
第Ⅱ-1-1-12図 世界の輸出・輸入の国別割合(2001年~2019年)
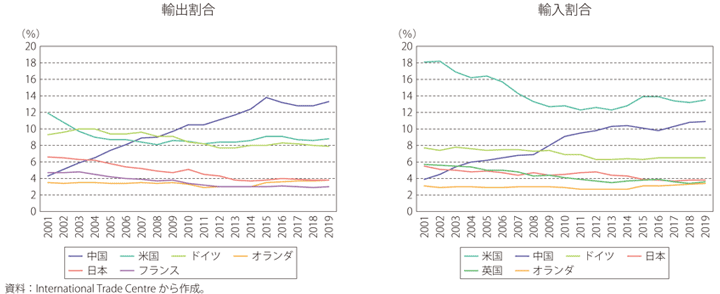
1 Financial Times “European car plants close as industry crisis deepens” 2020年3月16日
3.物流から見たサプライチェーンと新型コロナウイルスの感染拡大の影響
多くの産業が様々な輸送手段を用いて資材を調達し、各産業が相互依存していることから、陸上輸送、倉庫、海上輸送、航空輸送のいずれかが欠けてもサプライチェーンは混乱することが新型コロナウイルスの感染拡大において改めて示された。国内の物流、国境を越えた物流のいずれにおいても、物流の停滞は貿易の取引コストの増加に繋がり、貿易活動を収縮させる要因となった。
陸上輸送に関しては、本節1.で見たように、中国においては道路の封鎖やドライバー不足、欧州においては国境の検問により、トラック輸送に遅れが見られた。中国とベトナムの国境においては税関を通過するトラックが長い列を作り、国境の通過に数日を要する状況が見られた。日本においては、航空便減便による影響などから、一部の物流で遅延が見られた。
海上輸送においても、税関や検疫に時間を要することになり、輸送時間やコストが上昇した。新型コロナウイルスの感染拡大に伴いコンテナ船やバルク船の乗組員の確保が困難となるという状況も生じた上に需要の減少の影響も受け、減船も見られた。
航空貨物輸送においては、旅客機のフライトの減少に伴い付随して搭載される航空貨物の停滞が見られた。航空機が航行する場合でも、税関や検疫に時間を要することとなり、輸送時間やコストが上昇した。一方、サプライチェーンの維持を重視して、海上輸送から空輸に切り替える自動車部品やアパレルの企業も見られた。さらにマスクなど医療用具に関しても需要の高まりから空輸された例も見られた。このように、時と場合によって、空輸と海上輸送は代替する関係にある。世界の貿易のうち海上輸送は重量ベースでは9割強、金額ベースで7割前後を担っているものの、スマートフォン、電子部品、医薬品、医療機器、高級食材は付加価値が高いために空輸されることが多い。
日本においてはトラック輸送、外航海運、倉庫、港湾、内航海運、航空利用運送(旅客用飛行機での貨物輸送)の順に物流事業の荷物営業収入が多い(第Ⅱ-1-1-13表)。また、航空貨物は、航空利用運送(旅客用飛行機での貨物輸送)の売上が航空貨物(専業)よりも多いように、旅客機に搭載される航空貨物が多い。従業員数と事業者数の面では、トラック輸送が185万人の従業員、6万超の事業者と裾野が極めて広い。
第Ⅱ-1-1-13表 日本における物流事業の営業収入、従業員数、事業者数
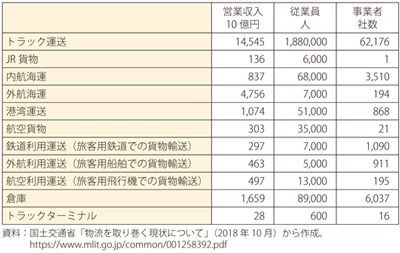
第3節においては、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた物流の停滞の現状とその背景に関する分析を行う。
4.人の移動から見たサプライチェーンと新型コロナウイルスの感染拡大の影響
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の中で国境を封鎖する国が数多く見られ、それによる人や物流の停滞はサプライチェーンに影響を与えている。先に見たように、人の移動の減少により航空機の運航が減便されたことで物流も同時に停滞した。これに加えて、人の移動の制限は生産活動に対しても影響を与えた。
中国においては、春節に伴い地方に帰省した労働者が、移動制限の影響で延期された春節期間が終了した後も都市部に戻れないために、工場の稼働再開が遅れ、再開後も稼働率の上昇に時間を要した。地方の農民戸籍のまま都市部で働く労働者は2.8億人に達する。これは中国の労働人口の3分の1に相当する。このような労働者の約半数が、新型コロナウイルスの感染が拡大する前に帰省したものの、その後に各地で移動制限が実施されたために、復帰が困難となった。中国当局によると、帰省した約1.3億人の出稼ぎ労働者のうち約6割の7,800万人が、3月初旬までに都市部に戻ってきた一方、約5,200万人は戻らなかったとされ、これは労働力人口の5~6%に相当する。
また、中国で生産が行われている米国電機メーカーのワイヤレスイヤホンのノイズキャンセリング機能のために用いられるマイクは中国の企業が供給を行っているが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により中国国内での生産停止を余儀なくされた。その際に、2019年に立ち上げていたベトナム工場におけて代替生産も含めた生産の拡大をすることはできなかった。これは、ベトナムが中国からの人の移動を制限しており、その人の移動の制限によりベトナムでの供給能力の拡大に向けた動きに支障が生じることとなった2。
欧州においては、季節労働者が不足するために春から初夏にかけての農作業に障害が生じることが懸念されている。EU主要国においては、種まきや収獲などの農作業を季節労働者に依存している。季節労働者の多くはEU域内、特に東欧からの労働者であり、ドイツにおいて30万人、イタリアにおいて25万人、フランスにおいて20万人が従事している(第Ⅱ-1-1-14図左)。こうした中、季節労働者不足の懸念の高まりから、ドイツは農業分野の季節労働者の入国を認めることに方針を変更した。また、EUの主要国は、いずれも農作業を行う自国民の大規模な採用を図っており、スペインとフランスでは、失業給付を受給しながら農業で働くことを可能とする特別措置が設けられた。
また、EUにおいては130万人から150万人が国境を越えた通勤を行っており、これは全雇用者の0.6~0.7%を占める。EU域内で国境を越えて通勤する雇用者は、新型コロナウイルスへの対策が取られる中でも移動そのものは認められる。しかし、3月中旬以降に各国が相次いで国境での検問措置を設けたことを受けて国境通過に数時間を要するようになったことで、実質的に通勤が不可能となるケースも見られた。国境を越えて通勤する労働者の人数としては、ポーランドからドイツに通勤する雇用者が13万人と最も多く、次いでフランスからルクセンブルクに出勤する雇用者数が8.8万人、ドイツからルクセンブルクに出勤する雇用者数が5.2万人、スロバキアからオーストリアに出勤する雇用者数が4.8万人、フランスからベルギーに出勤する雇用者数が4.6万人の順に多い(第Ⅱ-1-1-14図右)。
第Ⅱ-1-1-14図 EU主要国の必要とする季節農業者数、国境を通過して通勤するEUの雇用者数
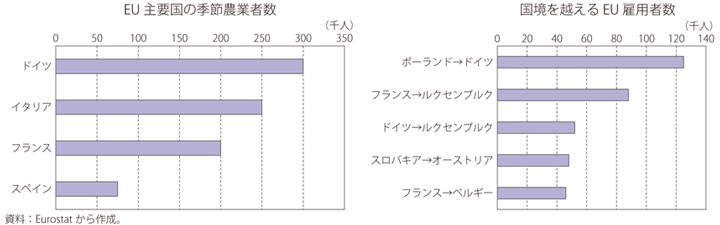
欧州委員会は、EU各国が新型コロナウイルス対策として国境管理を導入することに理解を示しつつも、一部の労働者には域内での自由な移動を保証するために3月末にガイドラインを公表した。このガイドラインにおいては、EU域内の移動が規制されるべきでない労働者として、医療関係者、保育や高齢者介護の従事者、医療関連分野の科学者、医療機器の設置に必要な人員、消防士と警察官、輸送分野の労働者、食品分野の労働者、農業季節労働者が含まれた。
国境の検問では、国境を越えて通勤する雇用者だけでなくトラックの検問も行うため、物流の遅延にも影響する。税関職員や国境を管理する職員が不足することも物流の遅延につながる。4月中旬の世界の90の港湾を対象とした調査によると、第Ⅱ-1-1-15図に見るように、約2割の港湾において港湾管理分野の人員不足が見られることとなった。
第Ⅱ-1-1-15図 世界の港湾の人員不足に関する回答報告分布
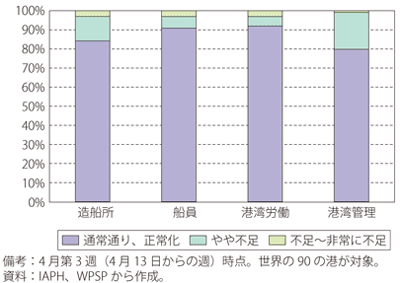
観光、移民、通勤を通じた人の移動がサプライチェーンを通じて貿易に影響を与え、更に投資にも影響を与える点に関しては第4節において整理を行う。
2 週刊ダイヤモンド2020年3月21日号 新型肺炎クライシス 電機サプライチェーンを参考にした。
5.従来からのサプライチェーンの課題を再認識して克服する機会に
新型コロナウイルスの感染拡大を機に顕在化した生産体制、物流、人の移動の寸断はサプライチェーンに大きな影響を与えることとなった。生産拠点が集中している部材・部品が供給停止となること、物流網が遮断されること、人の移動が停滞すること、これら三つのいずれか一つを契機としてサプライチェーン全体の停止に繋がるということが明らかとなった。一方、これらはいずれも従来から認識されていた課題の延長線上にあるものでもある。
中国の人件費が上昇し、米中摩擦が進展する中で日本企業は東南アジアなどへ生産拠点の多様化、分散化を進めていたものの、新型コロナウイルスの感染拡大においてサプライチェーンの寸断が見られることとなった。また、日本企業においては、2017年以降のトラック配送の値上げとドライバー不足への対応、2018年秋の非常に強い台風に伴う関西国際空港の一時閉鎖に伴う代替空輸の経験など、物流網の多様化・分散化の必要性に直面する機会は存在していたが、新型コロナウイルスの感染拡大に直面する中で、物流の遅延や寸断は広範に及び、多くの企業に影響した。そして、移動制限は生産活動や物流に大きく影響した。
このように、新型コロナウイルスの感染拡大は従来からの課題を再認識する機会となったものの、それと同時に課題を克服する機会にもなる。第Ⅱ部2章においては、情報通信技術革命の更なる進展により地理的距離を克服してバーチャルな人の移動が可能となる第3のアンバンドリングに向けた動きと国内外の動向を整理する。さらに、第Ⅱ部第3章第2節においては、レジリエント(強靭)なサプライチェーンの構築に向けた方向性を示す。
