

- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2020

- 白書2020(HTML版)

- 第Ⅱ部 第3章 第2節 レジリエントなサプライチェーンの構築、人の交流のあり方の進化
第2節 レジリエントなサプライチェーンの構築、人の交流のあり方の進化
第1章において分析を行ったように、新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、生産の停止や人の移動・物流において制限が発生し、サプライチェーンの途絶が生じた。このような事態は、世界との自由な経済活動・交流をベースとして、すり合わせに強みを持つ日本にとって逆風ともなり得るものであった。そこで、まず、新たな危機にも柔軟に対応できる強靱(レジリエント)なサプライチェーンへの変革が求められる。そのためには、物資に応じた対応、官民協力の円滑化、そして、「効率最優先」型から「臨機応変」型へのサプライチェーンの転換を検討していくことが求められる。
また、新型コロナウイルスの感染拡大はフェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションの危機であった。今後、人の対面での交流を前提としてきた様々なライフスタイルが大きく変容していくことが予想される。そこで、テクノロジーも活用しながら、人の交流のあり方を進化させることが求められる。
1.レジリエントなサプライチェーンの構築
(1)新型コロナウイルスの感染拡大によって明らかになったサプライチェーンの脆弱性
新型コロナウイルスの感染拡大で世界的にサプライチェーンの寸断が見られ、また、医療用品のような緊急物資については、需要が爆発的に拡大する中で物不足が見られた。これは、集中生産による経済性・効率性と供給途絶リスクへの対応力とのバランスを再検討する必要性を認識させるものであった。また、危機への備えや緊急時の国際協調が十分に機能しなければ、安定的な供給の確保は困難であることを示すものであった。
平時の準備と危機時の対応の重要性も明らかになった。マスクや人工呼吸器など医療関連物資の需要が爆発し、その緊急物資への需要に対しては供給が十分に追いつかない状況が見られた。その一方で、あらゆる緊急物資の需要の爆発に対応するための供給キャパシティを平時より備えることも非現実的である。そこで、平時と危機においてそれぞれに適した対応を行うことが重要となる。
以上の視点を踏まえた上で、サプライチェーンの強靭化に向けた方向性を検討する。
(2)レジリエントなサプライチェーンへ向けた方向性
そこで、レジリエントなサプライチェーンへ向けた方向性としては、3つの視点、具体的には、物資類型に応じた対応策の検討、危機時の柔軟な対応を可能とする官民連携、「効率最優先」型から「臨機応変」型へのサプライチェーンの転換が鍵となる。
①物資類型に応じた対応策の検討
まず、物資類型に応じた対応策を検討することが求められる。国境を越えたサプライチェーンの構築が進んできたが、危機時においては需要の爆発やサプライチェーンの途絶により、物不足に直面することとなった。
その一方で、効率性の極大化のみを追求する方策は維持困難であるものの、他方で、これまで構築されてきたサプライチェーンの便益を活かすことも重要である。そこで、物資類型に応じた対応が求められる。製品の用途や性質に応じてボトルネックとなる事態を想定し、その解消のためにどのような措置を講じるのか、製品の類型毎に精緻な議論が求められる(第Ⅱ-3-2-1図)。
第Ⅱ-3-2-1図 物資類型と対応策のイメージ
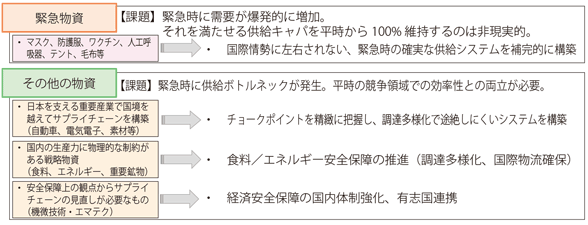
まず、マスク、防護服、ワクチン、人工呼吸器、テント、毛布等のように緊急時に需要が爆発的に増加する緊急物資については、平時から緊急時に対応する供給能力を保有することは現実的ではないため、国際情勢に左右されない緊急時の確実な供給システムを補完的に構築することが重要である。その補完として、危機発生時の柔軟な国際協調が求められる。4月17日には経済強靱性に関する日ASEAN共同イニシアティブを日本とASEANの共同で発出するなど、今後も、様々な地域と、より広範に協力を形成していくことが求められている。
次に、日本を支える重要産業で国境を越えてサプライチェーンを構築する産業物資については、緊急時に供給ボトルネックが発生することから、平時の競争領域での効率性との両立が必要である。そのためには、サプライチェーンを精緻に把握し、調達多様化で途絶しにくいシステムを構築することが重要である。
さらに、食料、エネルギーや鉱物のように国内の生産力に物理的制約がある物資については、調達多様化や国際物流確保のように食料・エネルギー安全保障の推進が重要である。
安全保障上の観点から安定的な供給確保が必要なものについては、経済安全保障の国内体制強化、有志国連携が重要であろう。
②危機時の柔軟な対応を可能とする官民連携
さらに、新型コロナウイルスの感染拡大の中で各国においては柔軟な官民連携の対応が見られた。
米国のトランプ政権は国防生産法により、民間企業に対して緊急物資の生産を要請し、EUでは、欧州製薬産業連盟と官民パートナーシップ(Innovative Medicines Initiative(IMI))への資金提供を通じて民間製薬会社による医薬品の開発を促進している。日本においても、経済産業省と厚生労働省が一体となって、経済団体等に対し、医療物資の国内増産や製造参入に向けた協力を要請している。併せて、各地域の経済産業局に窓口を設置し、医療物資の増産に向けて必要となる支援策(設備投資支援策等)を紹介することを行っている。さらに、各国の企業においても自主的に消毒薬や人工呼吸器を生産する企業が見られ、政府の要請に応じて緊急物資を生産する動きも見られた(第Ⅱ-3-2-2図)。
第Ⅱ-3-2-2図 官民連携の例
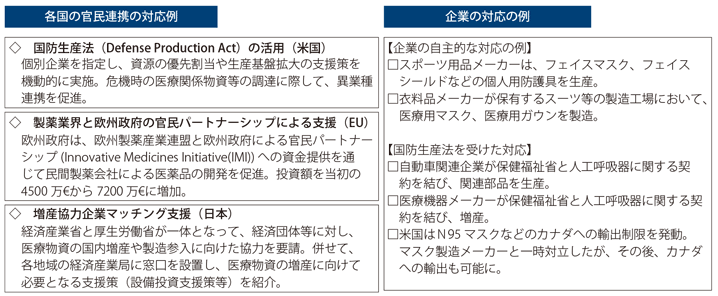
③「効率最優先」型から「臨機応変」型へのサプライチェーンの転換
サプライチェーンは効率性を追求する中で、国境をまたいだ生産体制が構築されてきた。その中で、生産体制、物流、人の移動の要素からサプライチェーンの途絶が発生した。また、緊急時には自国優先の動きも見られるなど、様々なリスクが見られた。その一方で、デジタル技術の活用など、新型コロナウイルスの感染拡大の中で、新しい動きも生まれている。
そこで、予期せぬ緊急時においても柔軟な対応を行うことができるよう、競争力と両立する方策で、サプライチェーンの強靱化を図っていくことが求められる。
その強靭なサプライチェーンの構築に向けては、サプライチェーンを精緻に把握することが重要であり、欠かせない部材の特定も求められる。
その中で、平時と緊急時において、デジタル技術も活用しながら生産体制を構築することで、効率性の向上による冗長性のカバーが期待でき、緊急時においてはサプライチェーンの途絶状況をリアルタイムで把握することも可能となる。
拠点の最適配置についても、平時には供給を多元化することによりサプライチェーンの途絶リスク低減が期待でき、緊急時には調達先の振替により、代替品を迅速・柔軟に確保することが期待できる。
(a)サプライチェーンの精緻な把握
サプライチェーンの経済性・効率性と供給途絶リスクへの対応力のバランスを踏まえ、強靭なサプライチェーンネットワークを構築するには、サプライチェーンを精緻に把握することが重要である。
サプライチェーンのネットワークは生産拠点や各国の比較優位の推移などに伴って変化するものであり、財の性質においても位置づけが異なるものである。
WTOが2019年4月に公表した報告書「Global Value Chain Development Report 2019」において、第Ⅱ-3-2-3図のとおり、世界の財・サービス全体の付加価値貿易ネットワークが示されている。日本は2000年に世界の付加価値貿易ネットワークのハブの一角を占め、東南アジアの多くの国は日本の周辺の位置していた。しかし、2017年には日本はハブではなく、中国の周辺に位置する。2017年時点ではドイツ、中国、米国が3大ハブであり、日本は東南アジアと同様に中国の周辺と位置付けられる。
第Ⅱ-3-2-3図 財・サービス全体の付加価値貿易ネットワーク(供給サイド、上段:2000年、下段:2017年)
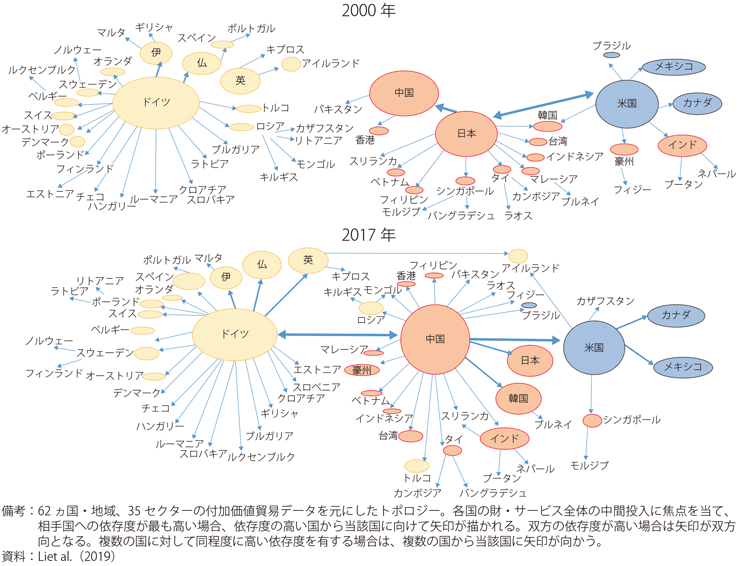
しかし、第Ⅱ-3-2-4図のように、ICT財の付加価値貿易ネットワークにおいて、日本は2017年時点でもハブである。タイ、バングラデシュ、インドネシアが日本の周辺となる一方、別のハブである台湾も日本と緊密な関係にあり、台湾の周辺国にはフィリピンが位置する。韓国もハブであるものの、日本とは距離がある一方、ベトナムと緊密な関係にある。そして中国もハブとして存在し、日本、韓国、台湾と一定の関係を有する一方、米国やドイツとも関係を有する。日本、韓国、台湾は中国を介することで米国やドイツとのつながりを有する。そこで、日本が欧米、韓国やベトナムとの間で複雑なICTの貿易取引を増加させるためには、中国は欠かせない。一方、中国がタイやバングラデシュやフィリピンとの間で複雑なICTの貿易取引を増加させるためには、日本と台湾は欠かせない。
第Ⅱ-3-2-4図 複雑なICT財の付加価値貿易ネットワーク(供給サイド、上段:2000年、下段:2017年)
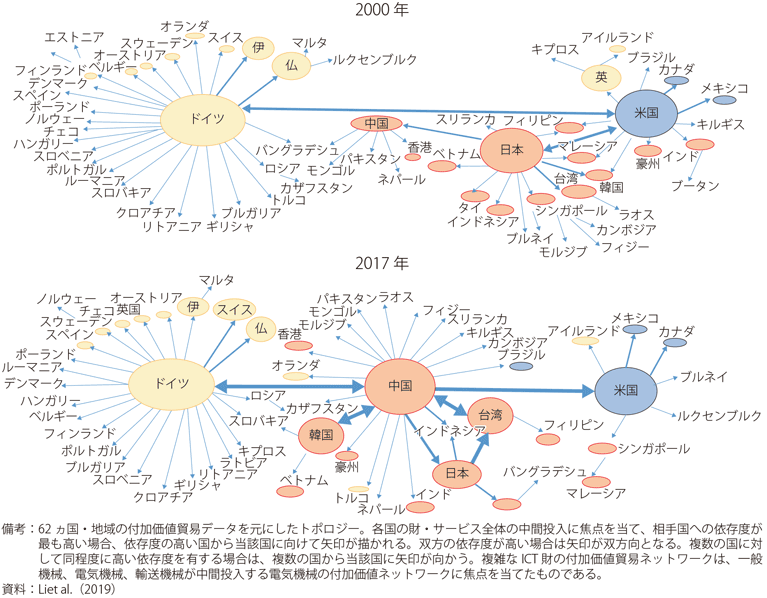
このように、日本と東アジア、東南アジアの各国・地域は、IT製品に代表されるように複雑なネットワークでつながっている。自動車においても、産業内貿易だけでなく、幅広い産業を巻き込んだ取引ネットワークが構築されている。東南アジアに生産拠点を多様化しようという動きは日本、韓国に限らず、中国の企業においても見られる。このようなサプライチェーンのネットワークを精緻に把握をした上で、サプライチェーンの経済性・効率性と供給途絶リスクへの対応力のバランスを検討することが求められる。
(b)調達の多様化
サプライチェーンの強靭性を高めるためには、調達の多様化や在庫の適正な確保も有効な戦略である。
原材料や中間財の在庫を余分に持たない、工場も複数から絞り込む、場合によっては工場も持たずに生産委託するといったリーン生産・OEM戦略は、自社の得意分野に注力し、コストを節約することで平時に高いリターンを生む。一方、感染症の拡大や自然災害といった有事の際に部品や在庫が不足し、生産停止といった事態に直面するというリスクが存在する。それに対し、在庫積み増しや生産拠点の分散化は平時のリターンを低下させる一方、有事のリスクが低下する。以下で在庫の積み増しや生産拠点の分散化の状況を確認しよう。
世界的に製造業全般が在庫を保有しない傾向が強まったのは、世界経済の安定成長が見られた世界金融危機前の時期である。その後、世界金融危機を境に、在庫率指数の上昇と低下を経験し、2010年代は世界的に製造業の在庫率は上昇基調をたどった(第Ⅱ-3-2-5図)。米国の製造業の在庫率指数は、2010年代は景気拡大が長期化する中で緩やかに拡大した。韓国と台湾の製造業の在庫率指数は2000年代半ばにかけて低下基調をたどったものの、その後は水準が上昇している。日本の製造業の在庫率指数は世界金融危機を受けて2009年に急上昇と急低下を示し、2010年代後半は上昇基調が見られた。
第Ⅱ-3-2-5図 米・日・韓国・台湾の製造業在庫率指数
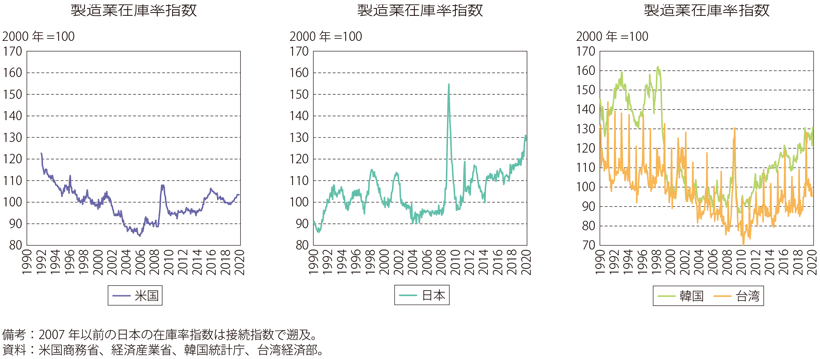
電子部品分野においては、韓国と台湾において、2000年代に見られた在庫率の低下がその後も継続し、低い水準に留まっている(第Ⅱ-3-2-6図)。一方、米国の在庫率指数は2010年代に小幅に上昇し、2015年以降は低下傾向にある。日本の在庫率指数は大幅に上昇している。
第Ⅱ-3-2-6図 米・日・韓国・台湾の電子部品在庫率指数
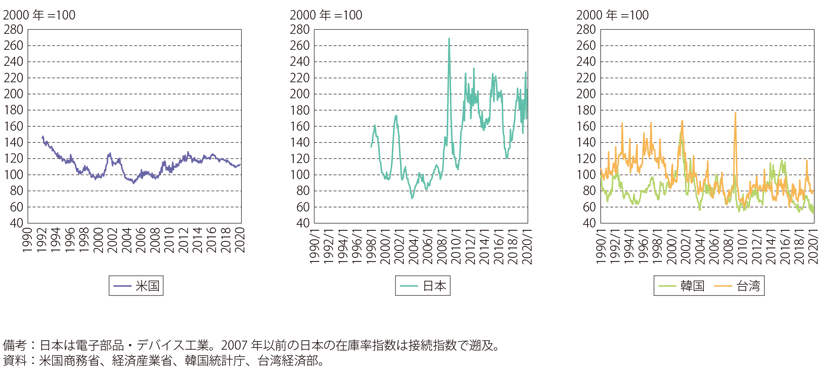
輸送機械の在庫率指数は、日本は安定して推移している一方、米国と韓国は1990年代と2000年代前半に低下した後に上昇している(第Ⅱ-3-2-7図)。
第Ⅱ-3-2-7図 米・日・韓国の輸送機械在庫率指数
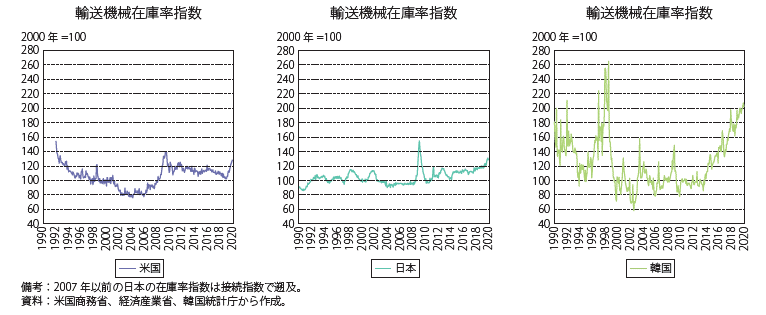
以上を踏まえると、在庫を多く保有しない状況が長年続いていた韓国や台湾の電子部品業界においては、サプライチェーンが寸断するショックが生じた際に、そのショックの影響を大きく受けやすくなっていた可能性がある。一方、2011年に東日本大震災と2011年タイ洪水という2度の大規模なサプライチェーンの寸断に直面した輸送機械においては、2011年以降に在庫を一定程度積み増すようになった。
新型コロナウイルスの感染拡大に際しても、在庫の保有率が高ければ物不足が発生しなかった可能性があるものの81、その在庫保有はコストとのトレードオフが存在し、商品の陳腐化というリスクも存在する。
2016年の熊本地震では、日本のエレクトロニクスメーカーの画像センサーの主力工場の稼働が停止したことから、デジタルカメラの生産にも影響した。この教訓により、2ヵ月で工場復旧が可能となるような在庫を保有することを含め、同様の自然災害でもサプライチェーンが遮断されないような広範なBCP計画を同社の半導体部門は策定している。これは世界シェアの高い部門での例であり、同企業において全ての部門で同様のBCP計画を有するわけではない。
在庫を保有するためには資金が必要であり、また、売れ残り時は製品価格の値下がりリスクも大きくなる。危機対応という理由で在庫を大きく積み上げるよりも、迅速に在庫や仕入れを確保できるシステムを構築する事例も見られる。例えば、米国のIT企業では、コンピューターや携帯電話の生産委託先を中国からベトナムに部分的に切り替えており、これは、分散化の事例といえる。
これに対して、日本のメーカーにおいては、生産拠点間の在庫の融通も含めたネットワークが存在する。2011年の東日本大震災を経験した結果、日本の自動車メーカーは3次・4次下請けの在庫・稼働状況を随時把握できる体制を構築している。また、エンジン制御用マイコンを代表例として基幹部品の生産が特定の一社の一工場に集中したために部品不足に直面したことを教訓として、自動車メーカーは調達先を分散させている。被災したエンジン制御用マイコンを製造するメーカーは、東日本大震災の半年後に、生産拠点の分散や外部工場による代替生産体制の拡充とともに、顧客に応じた在庫管理体制を取るようになった。
日本企業全体としては海外拠点の分散化の傾向が見られる。企業活動基本調査によれば、海外子会社・関連会社を保有する日本企業の数は2018年に5,810社と2年連続で小幅に減少した。一方、海外子会社・関連会社の数は、49,162社と増加基調が続いている(第Ⅱ-3-2-8図)。この結果、海外進出をしている企業1社あたりの海外子会社・関連会社数は2018年に8.5社となっており、2017年の8.1社に比べて拡大した(第Ⅱ-3-2-9図)。
第Ⅱ-3-2-8図 海外子会社・関連会社を保有する日本企業数、海外子会社・関連会社数
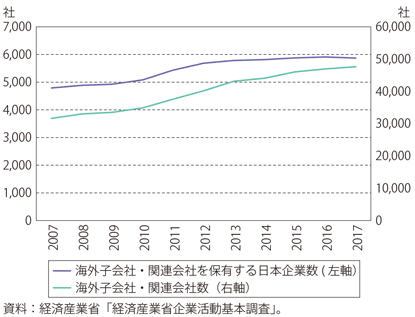
第Ⅱ-3-2-9図 海外進出をしている日本企業1社あたりの海外子会社・関連会社数
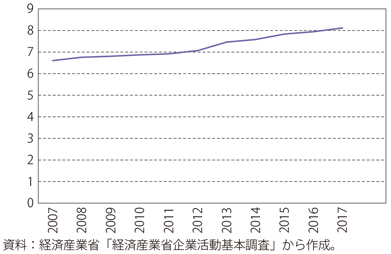
海外進出企業の数が小幅に減少している中で、海外進出企業は海外拠点の数を増加させている。2013年から2018年の海外拠点数の増減を見ると、多くの産業で海外拠点数が増加しており、業務用機械、輸送機械、化学、生産用機械、情報通信機械、電子部品・デバイスでは海外拠点数が増加した一方、革製品、木材、窯業・土石、繊維、金属製品では海外拠点数が減少している。
中国(中国本土のみ)、ASEAN4、ASEAN10における日本企業の現地法人数については、食品、化学、金属製品においては、中国の現地法人数の減少を主因としてASEAN10の現地法人数が中国(中国本土のみ)における現地法人数よりも多い(第Ⅱ-3-2-10図、第Ⅱ-3-2-11図)。電気機械、情報通信機械においては中国(中国本土のみ)の現地法人数が依然としてASEAN10の現地法人数よりも多いが、輸送機械においてはASEAN10の現地法人数が中国の現地法人数よりも多いものとなっている。
第Ⅱ-3-2-10図 日本の食品・化学・金属製品の海外現地法人数(海外事業活動基本調査)
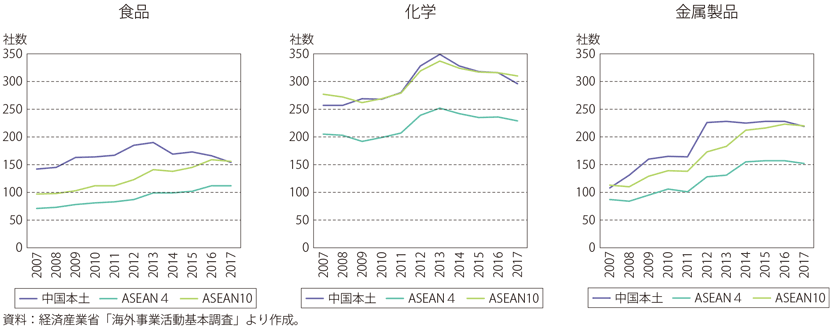
第Ⅱ-3-2-11図 日本の電気機械・情報通信機械・輸送機械の海外現地法人数(海外事業活動基本調査)
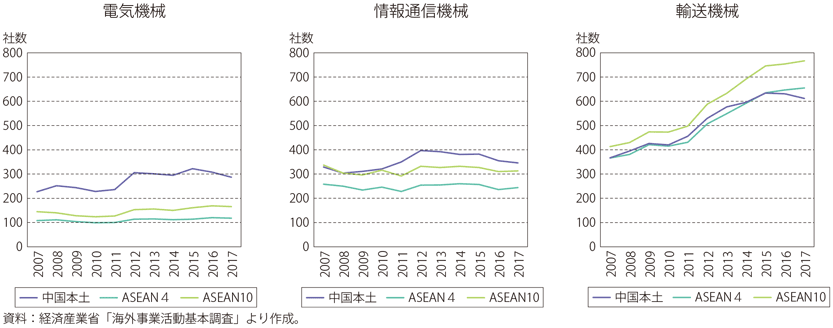
このように、日本において在庫率指数の上昇や生産拠点の多様化が産業により見られる。
上記では在庫率指数を用いたが、製造業の現場においては、在庫が1ヶ月間の出荷・売上の何ヶ月分に相当するか、すなわち在庫月数が重視されることも多い。日米の製造業においては、在庫月数は1.3ヶ月から1.4ヶ月前後と概ね同じである。ただし、産業間でのばらつきが見られる。
米国においては、民間航空機が8ヶ月超、鉱山機械において3.6ヶ月、コンピューターにおいて2.8ヶ月と在庫月数が長いものとなっている。一方で、ライトトラック、乗用車、自動車部品は1ヶ月未満と在庫月数が短い(第Ⅱ-3-2-12図)。3月後半以降に、米国の自動車工場の稼働停止が見られた要因としては、サプライチェーンの複雑さに加え、在庫月数の短さも考えられる。非耐久財においては、飲料、アパレルで在庫が多く、食品、化学、梱包用紙製品などにおいて在庫が少ない。
第Ⅱ-3-2-12図 米国製造業における在庫の売上に対する月数(2019年12月)
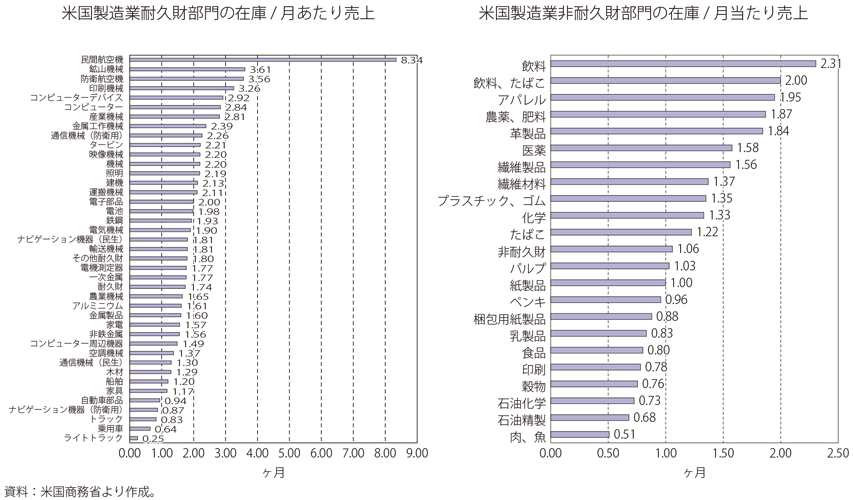
日本においても、自動車・同部品の在庫は1ヶ月の売上の約半分と他産業に比べて在庫月数が短い。また、印刷、食料品、パルプ・紙・紙加工品、情報通信機械においても在庫月数が短い。一方、化学、生産用機械、非鉄金属、繊維、鉄鋼、その他の輸送機械(航空機、船舶)においては在庫月数が長い。非製造業においては、扱う財・サービスの特性から、在庫月数は短くなる傾向があるが、小売業において在庫が売上の約1ヶ月分、建設、農林業、漁業、不動産業において在庫が売上の1ヶ月分以上存在する(第Ⅱ-3-2-13図)。
第Ⅱ-3-2-13図 日本の主要産業における在庫の売上に対する月数(2019年)
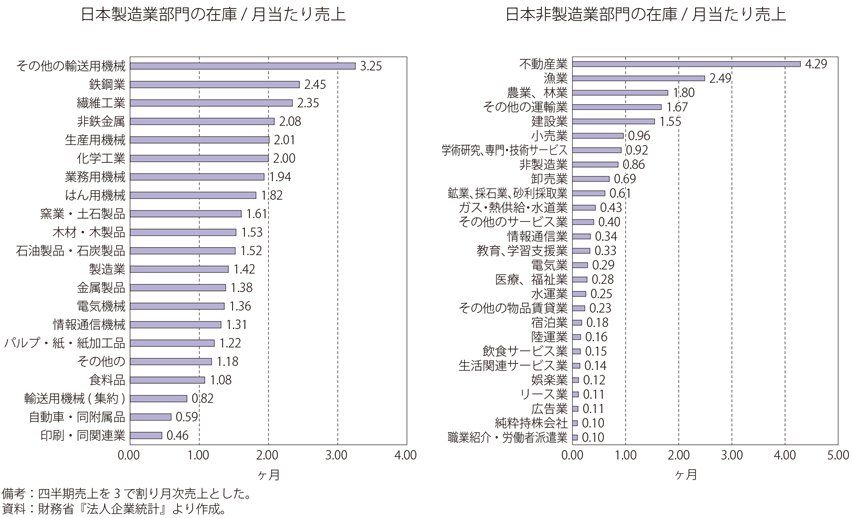
これらに加えて、サプライチェーンの多様化を進めていく上では、地方企業(ローカル)が世界市場(グローバル)と直接取引を行い、製品やサービス等の供給をしていく「グローカル成長戦略」82も重要となる。これは、サプライチェーンの多様化にも資するものであると同時に、国内における地方企業の成長にも資するものである。
さらに、緊急時における供給システムを補完的に構築することも重要であろう。新型コロナウイルスの感染拡大の過程で、マスクや人工呼吸器といった緊急物資の不足が見られた。需給バランスを速やかに把握することが困難となり、調達の遅延が見られ、市中の在庫状況が不明となった。その中で、消費者不安が生じ、買いだめ需要が発生した。
このような事態を踏まえ、デジタルの技術も活用しつつ、緊急時にも情報を正確に把握できる状況が効果的となると考えられる。それは適切な調達や在庫の管理にもつながるものであり、サプライチェーンの精緻な把握や調達の多様化を補完するものともなりえる。
81 2020年1月の米国耐久財受注統計を在庫の売上に対する日数をみると、米製造業全体の在庫は売上の1.74ヶ月分、コンピューター関連製品の在庫は売上の1.57ヶ月分、自動車の在庫は売り上げの0.65ヶ月分であった。
82 経済産業省 グローカル成長戦略研究会「グローカル成長戦略―地方の成長無くして、日本の成長なし」(2019年5月)
https://www.meti.go.jp/press/2019/05/20190515003/20190515003-2.pdf![]()
2.人の交流のあり方の進化
新型コロナウイルスの感染拡大の中で、社会の不可逆的な変化も生じている。オンラインでのコミュニケーションが増加するなど、人の交流のあり方に変化が生じている。これは、第3のアンバンドリングと通底するものである。一方で、フェイス・トゥ・フェイス・コミュニケーションにおける重要性の再認識も起こり、コミュニケーションのあり方そのものを見直す契機となっている。
(1)フェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーション:過去の感染症の経験
現在、新型コロナウイルスの感染拡大の中で、フェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションが危機を迎え、国境を越えた人の移動が低下している。各国で渡航制限が導入され、国境を越えた人の移動が停滞している。2020年1月から3月の間に、国境を越えた観光客数は8割以上減少し、航空旅客数は7割以上減少した。
感染症の流行は初めての事態ではない。1957年のアジアインフルエンザの感染の拡大時には、米国の家計の実質航空サービス支出は1957年に前年比で12.9%増加したものの、1958年には前年比で0.1%の増加と大きく減速した。1968年から1969年の香港インフルエンザの感染の拡大時には、米国の家計の実質航空サービス支出は1968年に前年比20.8%の増加、1969年に前年比18.3%の増加となった後、1970年には前年比で0.4%の増加と大きく減速した(第Ⅱ-3-2-14図)。
第Ⅱ-3-2-14図 米国家計の実質航空サービス消費の推移(暦年、月次)
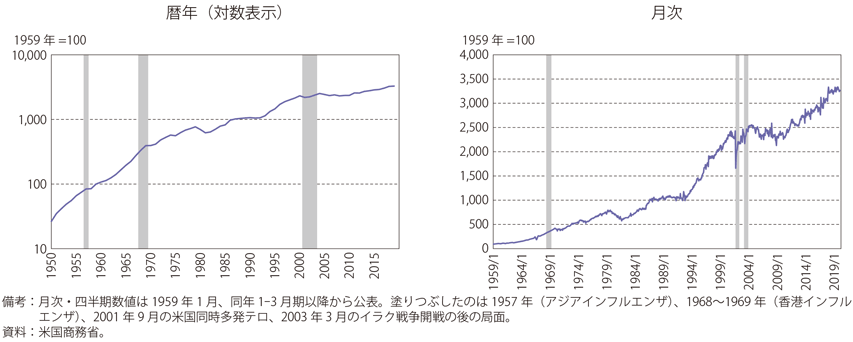
2000年代以降の感染症の事例として、2003年の重症急性呼吸器症候群(SARS)、2015年の中東呼吸器症候群(MERS)がある。これらの発生前後の東アジアのインバウンド観光客数を示したものが第Ⅱ-3-2-15図である。
第Ⅱ-3-2-15図 SARS・MERSの感染の拡大前後の東アジア各国のインバウンド観光客数
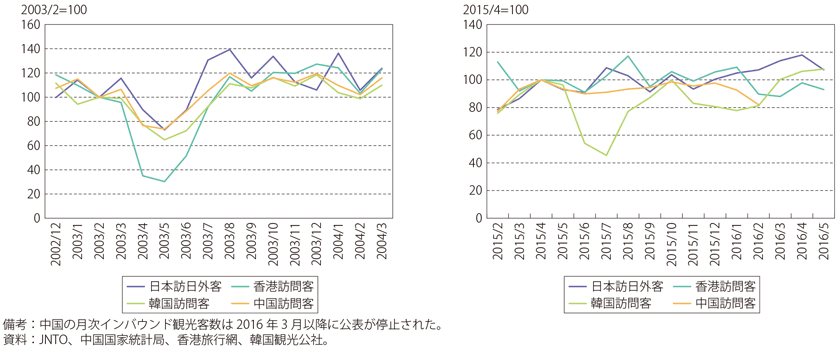
2003年春に香港と広東省を中心にSARSの感染が拡大した際には、2003年3月から5月にかけて東アジアのインバウンド観光客数が減少し、香港において67%減少した。2003年5月には韓国において35%減少、日本において27%減少、中国において26%減少と近隣国・地域への影響も見られた。同年の7月のWHOの制圧宣言の前から香港を含む東アジアのインバウンド観光客数は回復に転じ始め、同年の8月には香港のインバウンド観光客数がSARS発生前の水準を回復した。
2015年5月以降に韓国においてMERSの感染が拡大した際には、同年の4月から7月の間のインバウンド観光者数の増減は、韓国において55%減少、中国においても9%減少した。日本においては8%増加、香港においては3%増加しており、韓国からのシフトも見られた。韓国のインバウンド観光客数がMERS発生前の水準を回復したのは2016年3月である。一方で、近隣国・地域における影響は限定的であった。
以上を踏まえると、感染症の感染拡大を受けて観光客や航空旅客に対する需要が短期的に大きく減少することや、伸び率が大きく減速することはこれまで何度も見られたものの、感染症の収束とともに回復するものであった。
それでは移民についてはどのように考えることができるだろうか。大規模な感染症の流行と移民の動きについて、1918年から1919年のスペイン風邪、1957年のアジアインフルエンザ、1968年から1969年の香港インフルエンザの前後の状況を見てみよう。
第Ⅱ-3-2-16図は、19世紀後半から20世紀前半の米国、カナダ、ブラジル、アルゼンチンへの移民数(フロー、以下同様)を示している。1916年から1920年にかけての5年間の移民数は158万人となり、1911年から1915年にかけての5年間の414万人から大幅に減少した。これは移民数の減少と感染症の発生が重なることを示しているものの、1914年から第一次世界大戦が発生し、その影響が移民数の減少に寄与した。
第Ⅱ-3-2-16図 19世紀後半から20世紀前半の米国、カナダ、ブラジル、アルゼンチンへの移民数(フロー)
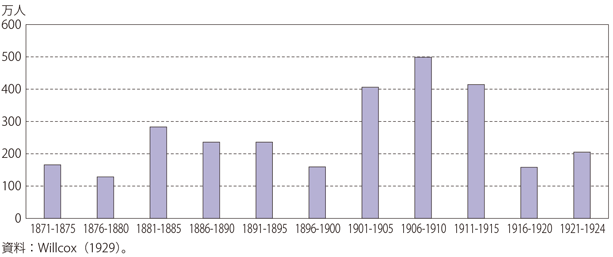
隔年の米国の移民受け入れ数では、1914年の第一次世界大戦の開戦を境に米国の移民受け入れ数が大きく減少し、1914年の122万人から1917年には4分の1の水準の30万人にまで減少し、移民受け入れのペースが鈍化した(第Ⅱ-3-2-17図)83。スペイン風邪が発生した1918年には11万人に減少し、1919年に14万人、1921年に80万人と回復した。その後、1924年の移民制限法84の施行後の1925年の移民受け入れ数は29万人と前年比で59%減少した。さらに、1929年から世界大恐慌が始まり、1930年代前半には移民受け入れ数が更に減少して10分の1の水準となった。
第Ⅱ-3-2-17図 米国の移民受け入れ数(フロー)
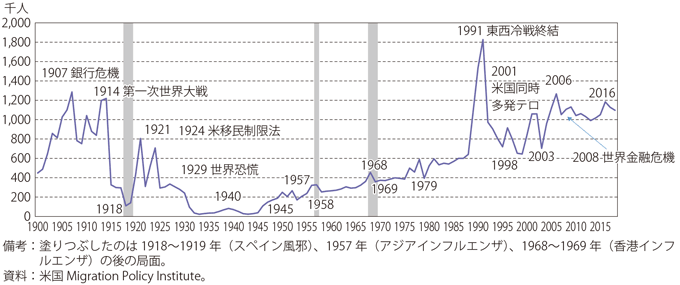
1957年のアジアインフルエンザ、1968-1969年の香港インフルエンザの流行時にも、移民数が一時的に鈍化した。米国の移民受け入れ数は1958年に前年比23%減少した。1969年にも移民受け入れ数は前年比で21%減少し、1958年同様に増加ペースが鈍化した。ただし、翌年の1959年と1970年からは移民数の伸びは再加速した。
その後、米国の移民受け入れは1970年代と1980年代を通じて緩やかに拡大し、冷戦終結に伴って1991年に大きく拡大した。2001年の同時多発テロの際も移民受け入れは拡大したものの、イラク戦争のあった2003年に前年比34%減少した。2008年の世界金融危機後はOECD加盟国全体では移民数の伸びが鈍化したものの、米国への移民数の伸びは鈍化しなかった。
このように、移民の流れを大きく抑制したのは戦争や移民規制、世界大恐慌などであり、感染症の影響は必ずしも大きなものではなく、影響は短期間に留まるものであった。
83 Keeling(2014)は1914年8月の第一次世界大戦を境に、移民に対してクォータ(割り当て)や規制が設けられるようになった点と政治的理由による亡命が増加した点を指摘している。
84 Immigration Act of 1924。日本や東欧・南欧からの移民に上限を設け、制限した。
(2)テクノロジーを活用した人の交流のあり方の進化
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により、すべての国で渡航制限が導入され、国境を越える人の移動に対して、歴史的に最も厳しい水準での制約が加えられている。WHOが「公衆衛生に関する国際緊急事態」と宣言した1月30日以降の渡航制限の状況を分析したUNWTOの調査によれば、世界中の217の目的地のうち、45%では観光客のために国境の全部または一部を閉鎖、30%では国際便の全部または一部を運休、18%では特定の出身国からの乗客や特定の目的地を通過した乗客の入国を禁止などの措置が行われている85。
国境を移動する人の移動は、高度な人材の往来によって知的な交流を促進し、また、旅行者の拡大による各国の観光産業を促進し、加えて、多くの国において移民を含めた外国人労働力の活用を可能として、2000年代以降の世界経済の発展を支える一要素となってきた。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、感染拡大防止のための各国の検疫措置の強化に伴い、当面の間は、より厳しい制約が継続的に課される可能性がある。
しかし、そうした状況のもとであっても、人の交流が生み出してきた付加価値は、状況に応じて形を変え、引き続き追求していくべきである。そのためには、リモート技術を活用してコミュニケーションのあり方を進化させるとともに、各国においても必要不可欠な人材から、検疫措置を取った上での往来再開を認める議論を早急に進めていく必要がある。
既に、海外出張のウェブ会議による代替、電子商取引(EC)や商談会のデジタル化といった新たな動きが活性化している。例えば、JETROでは、海外の主要なECサイトに特設サイト「ジャパンモール」を設置することを通じ、地域の中小企業の商品の販路開拓に取り組むとともに、「リアル」な商談会や展示会を代替するオンライン商談会の開催を進め、企業が非対面・遠隔での商談が行える環境整備を図っている。このように、国境をまたいだ電子商取引のニーズが拡大する中で、必ずしも海外に拠点を有しない地方の中堅・中小企業のビジネスチャンスが拡大することも期待され、「グローカル成長戦略」は、この視点からも重要である。
こうした方策は、国境を越えたデータの交流についてのルール作りをより強く要請するものであり、国際的なデータ流通網の構築(データ・フリー・フロー・ウィズ・トラスト、DFFT)の推進により、自由で開かれたデータ流通やデータの安全・安心を実現することが重要である。
また、ここ数年で拡大しているオンライン型の双方向サービスが一段と普及することにより、医療サービス、学習塾、スポーツなど、サービス分野において、経済活動を変革することが期待できる。
日本では移動時間に多くの時間を必要としてきたが、通勤・通学においても時間の使い方が大きく変化する余地がある。2016年の男性有業者の平日の通勤・通学時間の平均値を居住地別に見ると、全国平均が72分である。一方、埼玉県は84分、千葉県は91分、東京都は81分、神奈川県は95分と首都圏で長い。また、平日の女性有業者の通勤・通学時間の全国平均値は51分である。一方、埼玉県は55分、千葉県は61分、東京都は59分、神奈川県は65分と男性同様に首都圏において長い傾向がある。
このように、日本では、通勤・通学時間が都心を中心として長時間であることから、睡眠や余暇の時間が十分に確保されていない86。さらに、睡眠時間を増やせば生産性が上がる可能性も指摘されている87。
そこで、日本の場合では、テレワークや遠隔学習などオンラインコミュニケーションの活用により、通勤・通学時間を短縮することで、睡眠、家事などの活動時間を今以上に確保することが可能になりえる。
2018年から総務省が7月に実施しているテレワーク・デイズにおいて、2019年の集中実施日(7月24日)に、東京23区内で約25万人の通勤者が減少し、減少率は8.9%に上った。また、テレワーク・デイズ実施で得られた効果・成果として、参加者の約8割が「就労者の移動時間の短縮」を挙げた88。
2019年3月時点の国際調査に基づくと、テレワーク制度の導入を行っている企業の比率は米国において69%、英国において68%、ドイツにおいて80%、中国において51%である一方、日本においては32%と低水準にある。一方、日本人の80%が新しい雇用スタイルとしてテレワークの導入を予想しているように、実際の導入割合と期待の乖離が大きい(第Ⅱ-3-2-18図)。そこで、新型コロナウイルス感染拡大への対応として、オンラインを活用した経済活動が一段と進むことが期待される。
第Ⅱ-3-2-18図 テレワークに期待する人々の割合と導入している企業の比率(2019年3月調査)
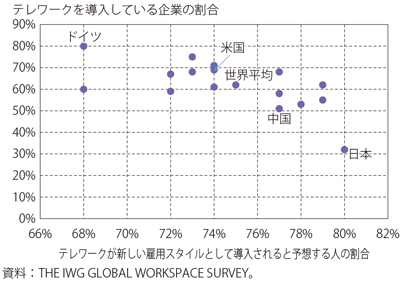
第Ⅱ-3-2-19表は、経済活動別に対面のコミュニケーション活動を整理したものである。多くの産業では対面の活動が必要な場面も多く存在する。
第Ⅱ-3-2-19表 経済活動別に見た対面のコミュニケーションの必要性
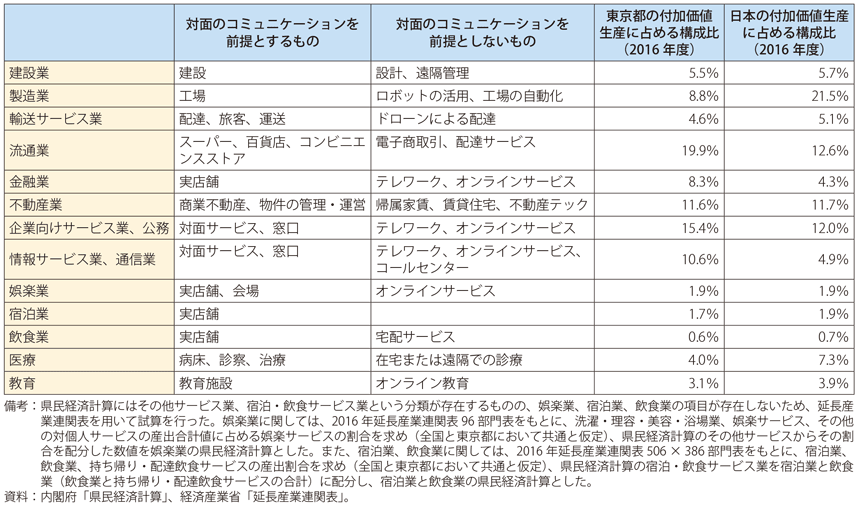
しかし、輸送サービス業においてはドローンの活用、建設業や電力・ガス・水道業においては遠隔操作、製造業においてはロボットの活用、工場の自動化などにより、対面の活動の必要性が低下することが期待される。娯楽業、不動産業においては、対面の活動を必要とする経済活動が多いものの、eスポーツに代表されるオンラインサービス、不動産テックなどが発展しつつある。
このように、電子商取引、双方向サービス、テレワークの活用により様々な社会経済活動が変化し得る。流通業においては電子商取引の活用、金融業、企業向けサービス業、公務、情報サービス業、通信業においてはテレワークの活用、オンラインサービスの提供により対面のコミュニケーションを前提とせずに経済活動を行うことが可能と考えられる。特に、東京の付加価値生産に占める流通業、金融業、企業向けサービス業、公務、情報サービス業、通信業の構成比率が日本の平均を大きく上回るように、大都市においてデジタル化技術を活用した社会変革の余地が大きいとも言える。
このように、テクノロジーの活用は新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大の中で直面するフェイス・トゥ・フェイス・コミュニケーションのコストの上昇という課題にも向き合うことを可能とするものである。
新型コロナウイルスの感染拡大の中でデジタル化の加速が見られるが、人と人の接触の制限の影響には業種により差異があるものであり、感染予防のための対面接触の制限や第3のアンバンドリングの流れにより、社会生活における不可逆的な変化が起こり、産業構造が大変容する可能性がある。今後は真に必要なフェイス・トゥ・フェイス・コミュニケーションに選別される時代となる可能性が存在しており、現在の危機を社会変革の機会と捉え、人の交流のあり方の進化につなげることが求められている。
85 UNWTO “100% OF GLOBAL DESTINATIONS NOW HAVE COVID-19 TRAVEL RESTRICTIONS, UNWTO REPORTS”
86 三島(2018)、黒田(2012)、阿部(2010)。
87 小野(2016)
88 総務省(2019)。
