

- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2020

- 白書2020(HTML版)

- 第Ⅱ部 第3章 第3節 世界の社会課題解決(SDGs)の促進に向けて
第3節 世界の社会課題解決(SDGs)の促進に向けて
第1節において、新型コロナウイルスの感染拡大の中における、国際強調の重要性を議論した。パンデミック、気候変動などの世界が国際協調により取り組むべき社会課題が存在しており、現在注目を集めている考え方がSDGs(Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標)である。国家や企業、個人といった様々な主体による協調した取り組みがますます求められる分野である。
1.SDGsと社会課題の解決
(1)SDGs策定の背景
SDGsとは、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された2016年から2030年までの17のゴール(目標)と169のターゲットからなる国際目標である。SDGsは2015年を目標としたミレニアム開発目標(Millennium Development Goals, MDGs)を補完する次の目標とされている。
SDGsの前身となったMDGsとは、世界の貧困の半減などを目指し、2015年までの達成を目指して国際社会が掲げてきた目標である89。MDGsが策定された背景として、それまでの開発協力のやり方に対する反省がある。従来は、開発途上国の経済の仕組みを市場経済メカニズムが機能するように改革することにより、開発途上国の経済発展、ひいては貧困の削減にもつながるという「構造調整政策」が国際的な開発協力の主流であった90。一方で、構造調整によって実施された諸政策により、開発途上国における貧困問題や格差が深刻化することもあり91、より直接的に貧困問題に対応する方策について国際社会の関心が高まり、2001年にMDGsがまとめられた92。
89 MDGsはミレニアム総会で採択されたミレニアム宣言と1990年代に連続して開催された会議での国際的合意を一つにまとめたもの。
90 外務省(2015)『開発協力白書(2015)』
91 高柳彰夫・大橋正明(2018)
92 外務省(2015)『開発協力白書(2015)』、高柳彰夫・大橋正明(2018)
(2)MDGsからSDGsへ
MDGsに取り組む過程において、貧困を撲滅するためには、環境問題や社会問題を解決する必要があることが理解されてきた。経済、社会、環境問題は非常に複雑に絡み合っており、統合的に問題を解決することが必要であるという認識が高まり、SDGs はその認識の元で策定された93。そのため、MDGsに比べてSDGsの対象は広範囲となっている。MDGsが途上国の貧困撲滅や教育、保健、ジェンダー平等を目標としているのに対し、SDGsは経済、社会、環境分野など広範な課題を包括的に対象としている。SDGs達成によってもたらされる、市場機会の価値は年間約12兆ドル、2030年までに世界に創出される雇用は約3億8,000万人にのぼると推計されている94。
さらに、SDGsの理念として「誰一人取り残さない(leave no one behind)」が掲げられており、途上国のみならずあらゆる国や人を対象にしている。そのため、あらゆる国や地域に応じた目標や実施方法を考える必要がある。第Ⅱ-3-3-1表において、MDGsとSDGsの違いをまとめている。
第Ⅱ-3-3-1表 MDGsとSDGsの違い
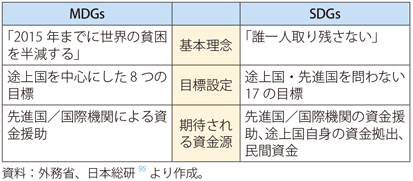
93 国連大学(2016)
94 Business&Sustainable Development Commission
95 足達英一郎、村上芽、橋爪麻紀子(2018)
(3)達成に向けた資金の不足
前述したとおり、MDGsとSDGsでは基本理念や目標設定が異なる。さらに、大きな違いとして資金調達先の多様化が挙げられる。MDGsでは、途上国の貧困削減が主な目標であったことから、主に、先進国や国際機関が資金を拠出していた。SDGsでは、先進国の政府や国際機関だけでなく、途上国自身や民間セクターからの資金が期待されている。実際に、SDGs目標17のターゲットでは「さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励、推進する」ことを掲げている。
UNCTADによると96、SDGs達成には、途上国だけで年間約3.9兆ドル必要とされているが、2014年時点では官民あわせて約1.4兆ドルの資金に留まっており、必要な額と実際の投資額の乖離は年間で約2.5兆ドルとなっている(第Ⅱ-3-3-2図)。
第Ⅱ-3-3-2図 SDGs達成にむけた資金需要と不足額の試算(途上国のみ)
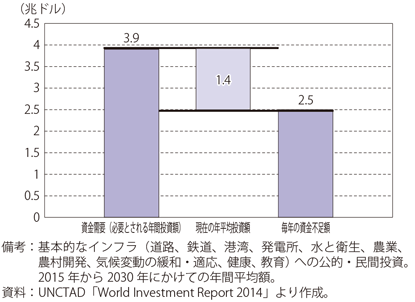
さらに、持続可能な開発ソリューション・ネットワークによると、SDGsはMDGsと異なり、開発途上国だけでなく先進国にも焦点があてられており、全ての国がSDGsを達成するためには最大でGDPの2.5%まで資金が必要であるとも言及されている。また2019年の世界銀行のレポートでは、低中所得国がSDGsに関連するインフラを整備し、世界の気温上昇を2度にまで抑えるためには2015年から2030年にかけて世界のGDPの4.5%のインフラ投資が必要であるとも述べられている。
このように、SDGsを達成するためには、膨大な資金が必要であることを様々な機関が言及している。ただし、これは、公的な資金のみで達成されるべきものではなく、民間資金の活用が肝要である。
SDGs達成に向けた資金需要と必要とされる投資額の乖離の大きさを基にポテンシャルが大きい分野を見れば、経済インフラである電力や運輸、再生エネルギー(気候変動の緩和)などの分野が大きい(第Ⅱ-3-3-3図)。また、現状の投資額に占める民間資金の割合を見れば、電力や運輸、気候変動の緩和の分野では民間資金の割合が相対的に大きい(第Ⅱ-3-3-4表)。
第Ⅱ-3-3-3図 途上国におけるSDGs主要セクターへの予想される投資額と必要とされる投資額
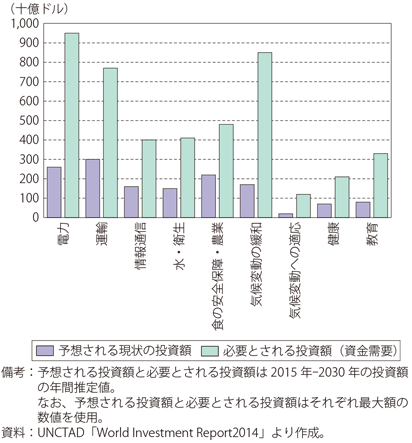
第Ⅱ-3-3-4表 現在の投資額に占める民間資金の平均割合
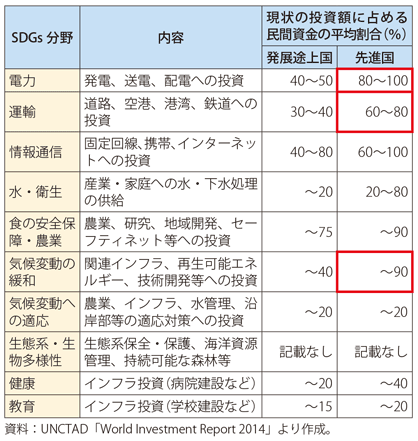
他方、民間投資家がリスク・リターンモデルを設計するのが難しい気候変動への適応分野や、公共サービスの中心である教育や医療(健康)においては、民間分野の投資は大きく進んでいない。このような分野では、民間分野とともに公的セクターが補完的に投資し合う意義は大きいといえる。
実際に、必要とされる投資額の絶対額が必ずしも大きくはない気候変動の適応分野においても、民間への期待は小さくない。気候変動対策には、CO2などの温室効果ガスの排出を抑制する「緩和策」と気候変動に対応するための「適応策」があり、両者が機能してこそ温暖化の影響を最小限に抑えられるものである。気候変動対策が社会の様々な分野に与える影響は年々拡大しており、対応する適応策へのニーズがビジネスにつながる可能性も言及されている。国連環境計画(UNEP)によると、途上国の環境適応にかかる費用は2050年時点で年間最大50兆円に達すると推定されている97。
途上国に流入する資金フローをみても、公的資金を遙かに凌ぐ民間資金が流入していることがわかる(第Ⅱ-3-3-5図)。民間部門の活動が開発途上国の経済成長を促す大きな原動力となってきている。
第Ⅱ-3-3-5図 DAC諸国による資金フロー
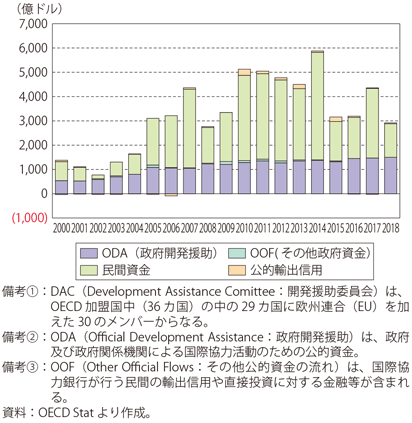
他方で、民間資金の呼び込みは肝要であるものの、現状では途上国の資金源は様々である。実際、モザンビークやカンボジアなど一部の国では、直接投資の占める割合が相対的に大きいものの、後発開発途上国98の大半にとって、依然としてODAや送金の重要性は大きい。実際、アフガニスタンやマラウィなどODA資金の占める割合が大きい国やネパールやトーゴでは送金が重要な資金源となっている(第Ⅱ-3-3-6図)。
第Ⅱ-3-3-6図 後発開発途上国への海外からの開発資金源の各国の歳入に対する比率(2017)
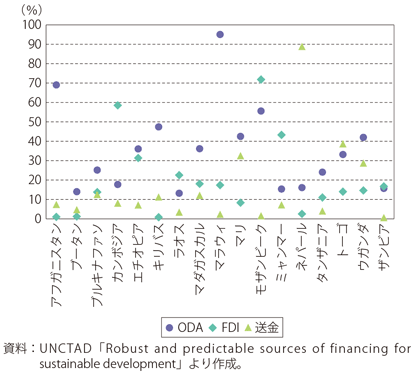
今後、後発開発途上国への投資を促進していくためには、民間が投資しやすい環境を整えるため、投資促進枠組みを導入し、実施していくことが求められるものの、実際には後発開発途上国では進んでいない現状がある(第Ⅱ-3-3-7図)。
第Ⅱ-3-3-7図 新規の投資促進・奨励の政策の数
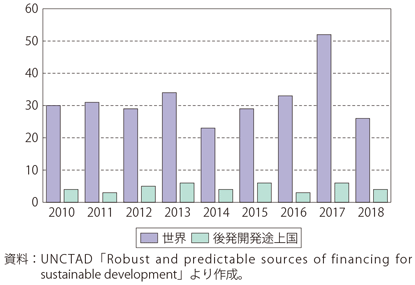
途上国に民間の投資を呼び込むためには、政府の支援や制度の整備、インセンティブの付与など投資を取り巻く環境を整備することが肝要である。また、為替リスクなど投資のリスクも事業の初期段階で包括的に理解することも重要である。
昨年、横浜で開催されたアフリカ開発会議においても、日本政府は今後3年間で約200億ドルを上回る民間投資が更に大きくなるよう後押しする考えを表明した。民間投資後押しの具体策として、日本貿易保険(NEXI)がプロジェクト融資などに貿易保険を適用する枠組みを提起している。
96 UNCTAD(2014)
97 UNEP(2016)
98 国連開発計画委員会(CDP)が認定した基準に基づき、国連経済社会理事会の審議を経て、国連総会の決議により認定された特に開発の遅れた国々。主な基準としては、一人当たりGNIやHAI(Human Assets Index)、EVI(Economic Vulnerability Index)などの基準を元に判断。
(4)期待される資金源
資金不足を担う可能性があると注目されるものの一つが、近年増加しているESG投資である。ESG投資とは、財務情報だけでなく、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)に関する取組も考慮した投資である。ESG投資は、2006年に国連が「責任投資原則(PRI)」を設立したことを契機に広がりを見せている99。ESGの要素はSDGsの各目標とも親和性が高いといえ、SDGs達成においてもESG投資は重要である。実際、日本の公的年金基金である年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)では、ESG投資とSDGsの関係について、民間企業がSDGsに取り組むことで共通価値創造(CSV:Creating Shared Value)100を実現し、企業価値の持続的な向上を図ることで、ESG投資を行う投資家の長期的な投資リターンの拡充につながるものと言及している101。
サステナブル投資を普及する世界持続的投資連合(GSIA)は、隔年ごとにGlobal Sustainable Investment Reviewを公表しており、世界のESG投資の現状をまとめている。
GSIAによると、ESG投資残高は、欧州が約14兆ドル、米国が約12兆ドルに対し、日本は約2兆2千億ドルと規模は大きくない(第Ⅱ-3-3-8表)。日本では、GPIFが2015年にPRIに署名する等により、近年では大幅な伸びを示している。実際に、運用資産全体に占めるESG投資の割合が2018年には2016年の約6倍近くとなってきている(第Ⅱ-3-3-9図)。
第Ⅱ-3-3-8表 国・地域別のESG投資残高
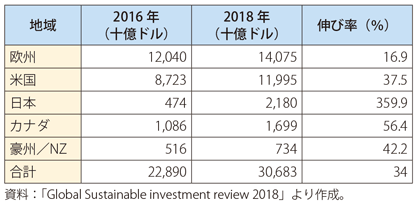
第Ⅱ-3-3-9図 運用資産全体に占めるESG投資の割合
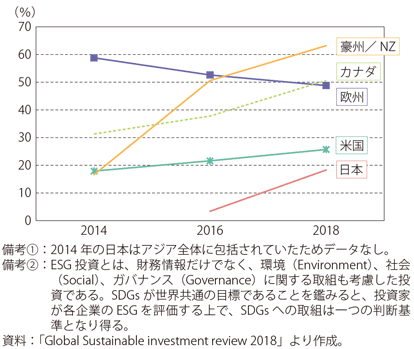
また、GSIAはESG投資を7つの投資手法に定義しており、その定義に基づいた報告をしている(第Ⅱ-3-3-10表)。国・地域別のESG投資手法を見ると、欧州では環境や社会に良い影響を与えない企業を投資対象から除外する方法、いわゆるネガティブ・スクリーニングが主な手法となっているのに対して、米国、カナダ、豪州・NZでは投資プロセスにESG要因を組み入れるESGインテグレーションがメジャーとなっている。他方、日本の場合は、エンゲージメント/議決権行使が主な手法となっている(第Ⅱ-3-3-11図)。
第Ⅱ-3-3-10表 投資手法の分類と定義
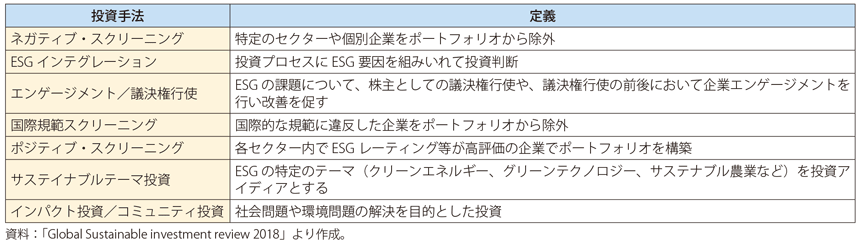
第Ⅱ-3-3-11図 国・地域別のESG投資手法
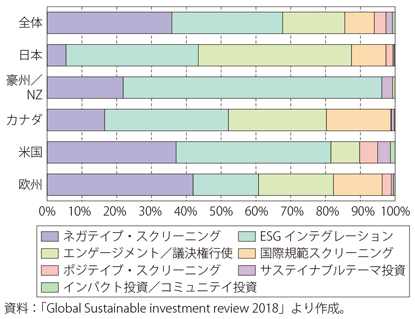
99 署名機関は2020年第2四半期時点で約3,038機関と前年比で約3割増加。
100 経済的価値を創造しながら社会的ニーズに対応することで社会的価値も創造するというアプローチ。ハーバード大学のマイケル・ポーター教授が2011年に論文にて提唱。
101 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)「ESG投資とSDGsのつながり」、2020年6月時点(GPIF Webサイト)
(5)日本の取り組みと市場の評価
経済産業省のSDGs経営/ESG投資研究会が2019年5月に公表した「SDGs経営ガイド」においては、日本企業の「SDGs経営」の優れた取組を世界に発信している。また、経済産業省は、企業と投資家の対話における共通言語として、「価値協創ガイダンス」102を策定した。価値協創ガイダンスのフレームワークとして、気候関連財務情報開示に関するガイダンス(TCFDガイダンス)103、産業保安及び製品安全における統合的開示ガイダンス、バイオメディカル産業版「価値協創出ガイダンス」、DX推進ガイドライン、ダイバーシティ2.0行動ガイドライン、CGS(コーポレートガバナンスシステム)ガイドラインの6つを掲げており、企業と投資家の建設的な対話に活用することが期待されている。SDGs経営/ESG投資研究会が2019年6月に公表した「SDGs経営/ESG投資研究会報告書」においては価値協創ガイダンスの国際展開等を通じて、SDGsを取り巻く国際的なルールメイキングに参画していくことも期待されている。
また、ESG要素の中でも投資家の注目の高い気候変動について、経済産業省は2018年8月に「グリーンファイナンスと企業の情報開示の在り方に関する『TCFD研究会』」を立ち上げ、事業会社の経営者と国内外の投資家等との「対話」を通じたTCFD提言に沿った情報開示の在り方の議論を踏まえて、2018年12月に「気候関連財務情報開示に関するガイダンス(TCFDガイダンス)」を策定した。TCFDガイダンスにおいては、TCFD提言に沿った情報開示を行うにあたっての解説に加え、主要5業種における具体的な開示ポイント・視点が示され、今後の情報開示の進め方やガイダンスの更なる拡充に向けた取組等が説明された。TCFDの提言においては、気候変動が企業活動に与える影響として、機会とリスクの両面を捉える必要があり、それらが売上・費用(損益計算書)と資産・負債(バランスシート)に与える影響を分かりやすく開示することが求められる(第Ⅱ-3-3-12図)。
第Ⅱ-3-3-12図 TCFD提言からみた気候変動の企業活動への影響
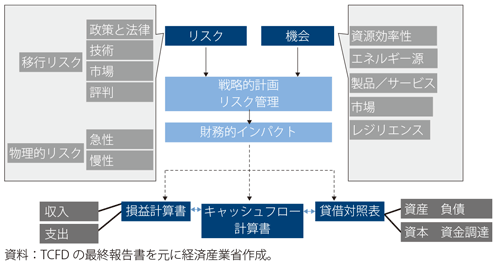
TCFDの提言に沿った日本企業の情報開示も増えつつあり、将来のシナリオ分析に基づく具体的な財務影響評価の開示も一部で始まっている。大手飲料会社においては、例えばビールの原材料である大麦の生産がオーストラリアで10~50%減少する可能性があることに加え、2030年の温室効果ガス削減目標を達成した場合には、持続可能な発展と産業革命前からの気温上昇が2℃に留まるシナリオにおいて、炭素排出コストが約47億円削減される可能性があると環境報告書で示した。大手銀行は、2050年までに洪水による与信関係費用が300億円から400億円増加するという試算を統合報告書で示した。
リスクに限らずビジネス機会とその財務影響評価を各企業も公表し始めている。大手小売・信販会社は、2050年までに気温上昇が1.5℃以下のシナリオの場合にグリーンビジネスの財務的な機会がリスクを15億円上回るという試算を統合報告書で示した。
大手アパレル製造・小売業は、取引先の縫製工場リストなどを公表し、児童虐待の防止や環境への配慮に向けた取り組みを保管する情報開示を行っている。日本の大手アパレル製造・小売業も、世界の46カ所の取引先素材工場のリストを2019年に公表した。これは第1節第1章で取り上げた貿易面でのサプライチェーンの可視化・透明化の流れとも整合的な取り組みであり、今後の進展が期待される。
また、近年大きく規模を拡大させているのが、グリーン投資104の一つであるグリーンボンド市場である(第Ⅱ-3-3-13図)。グリーンボンドとは民間企業、国際機関、国、地方公共団体等が、温暖化対策や汚染の予防・管理、生物多様性の保全、持続可能な水資源の管理等の環境プロジェクトに要する資金を調達するために使途を限定して発行される債券である。近年、世界でのグリーンボンド発行額は急増している。2019年の発行額の多い国は、アメリカ、中国、フランス、ドイツ、オランダとなっており、特に欧州の伸びが顕著であり、2018年から約74%の増加となっている105。
第Ⅱ-3-3-13図 グリーンボンド発行額の推移
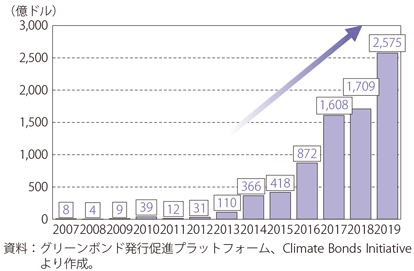
102 「価値協創出ガイダンス」とは、企業と投資家をつなぐ「共通言語」であり、企業(企業経営者)にとっては、投資家に伝えるべき情報(経営理念やビジネスモデル、戦略、ガバナンス等)を体系的・統合的に整理し、情報開示や投資家との対話の質を高める手引き。
103 気候変動の情報開示がグローバルに求められるようになった流れの中、「金融安定理事会(FSB ;Financial Stability Board)」が、気候変動に関する企業の対応を情報開示するよう促す「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD; Task Force on Climate-related Financial Disclosures)」を2015年に設置。
104 グリーン投資とは、自然資源の保全、再生可能エネルギーの生産や開発、環境配慮ビジネスの実践に係わる投資のことであり、公債や社債、環境関連産業の株式やファンド、投資信託等が含まれる。
105 Climate Bonds Initiative(2019)
2.日本としてのSDGsへの貢献
(1)日本の達成度
ドイツのベルテルスマン財団と持続可能な開発方法ネットワーク(SDSN)が共同で発表した2019年の報告書106において、2019年の世界各国におけるSDGs(持続可能な開発目標)の達成度が公表されている。1位はデンマークで2位はスウェーデンと1位から10位までを欧州や北欧の国々が独占した。欧州の国は11位~20位にも6ヵ国がランクインするなど、欧州各国のSDGsへの積極的な取組が見られる(第Ⅱ-3-3-14図)。
第Ⅱ-3-3-14図 各国のSDGs達成度合い(2019年)
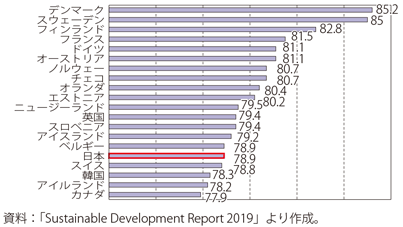
日本は15位(2018年も15位)に位置しており、アジア諸国の中では1位であった。さらに、項目別でみると、日本は、SDG1(貧困)、SDG4(教育)、SDG13(気候変動)、SDG7(エネルギー)については達成度合いが高いと評価される一方、SDG5(ジェンダー)、SDG12(生産・消費)については低いとされている(第Ⅱ-3-3-15図)。
第Ⅱ-3-3-15図 日本のSDGs達成度合い(2019年)
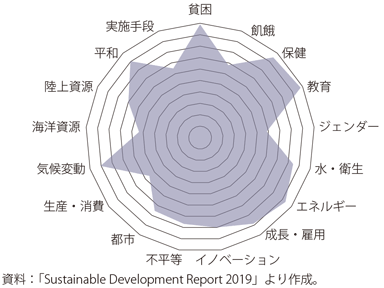
前述の通り、達成度合いの評価が高い項目として、気候変動やエネルギー分野が挙げられているが、実際、石油や天然ガスなどの資源に乏しい我が国では、エネルギー効率の向上に努めてきた。1単位の国内総生産(GDP)に対するエネルギー供給量をみると2000年以降は低下傾向にあり、エネルギー効率の改善は進展している(第Ⅱ-3-3-16図)。経済成長とエネルギー効率の改善を両立してきたと言えよう。
第Ⅱ-3-3-16図 日本の実質GDPとエネルギー効率(エネルギー供給量/実質GDP)の推移
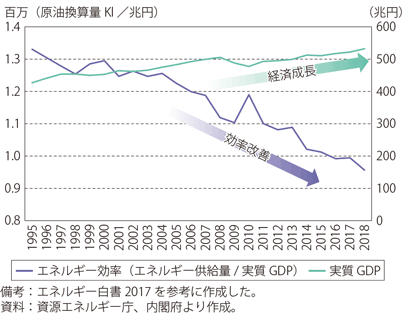
さらに、世界の二酸化炭素排出量に占める各国の割合をみると、中国の割合が最も大きく約3割近くを占めている(第Ⅱ-3-3-17図)。米国は約14%、日本は約3%となっている。また、1人当たりの二酸化炭素排出量をみると、米国の14.6トンに対し日本は8.9トンに収まっている。ただし、1990年代と比較すると他の先進国が一人当たりの二酸化炭素量の排出量を減らしているのに対し、日本は概ね横ばいで推移している。元々、排出量が少なかったことも要因の一つと考えられるが、一層の効率化が求められていくだろう。
第Ⅱ-3-3-17図 世界の二酸化炭素排出量に占める各国の割合と
1人当たりの二酸化炭素排出量 一人当たり二酸化炭素排出量の推移
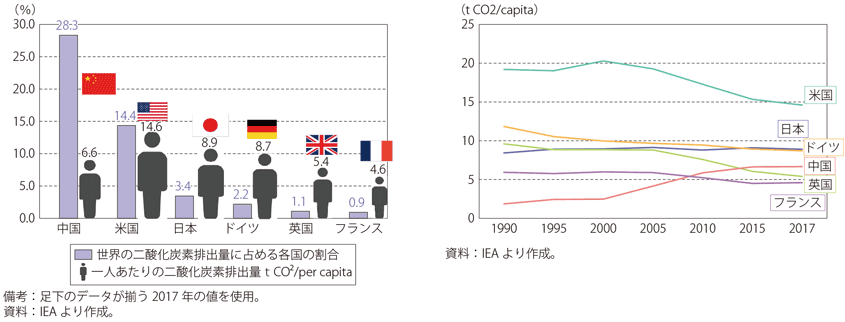
2015年にパリで開催されたCOP21では、2020年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとしてパリ協定が採択された。パリ協定は、先進国及び途上国が参加する合意となった。パリ協定では、世界共通の長期目標として2℃目標の設定や107、主要排出国を含む全ての国が削減目標を5年ごとに提出・更新することも盛り込まれた。また、我が国が提案した二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism、JCM)も含めた市場メカニズムの活用が位置づけられている(第Ⅱ-3-3-18図)。二国間クレジット制度(JCM)とは、日本の持つ低炭素技術や製品、システム、サービス、インフラを途上国に提供することで、途上国の温室効果ガスの削減などに貢献する制度である。これにより、日本は地球規模での温暖化対策に貢献するとともに、日本の温室効果ガス排出削減等への貢献を適切に評価し、削減目標の達成に活用することができる。現在、我が国はアジア、アフリカ、島嶼国、中南米及び中東の17ヵ国と署名済みである108。
第Ⅱ-3-3-18図 二国間クレジット制度の概要図
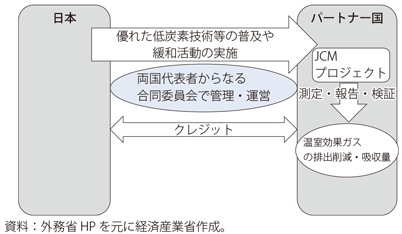
資金支援事業をみると、水力発電や太陽光発電など再生可能エネルギー技術を使用した案件が大半である(第Ⅱ-3-3-19表)。環境省が実施する事業の2019年6月までの案件数では、インドネシアが33件と最も多く、次いでタイが31件、ベトナムが23件と続く。政府は、毎年度の予算の範囲内で行う事業によって、2030年度までの累積で5,000万から1億トンCO2の国際的な排出削減・吸収量が見込まれるとしている。
第Ⅱ-3-3-19表 JCM資金支援事業案件
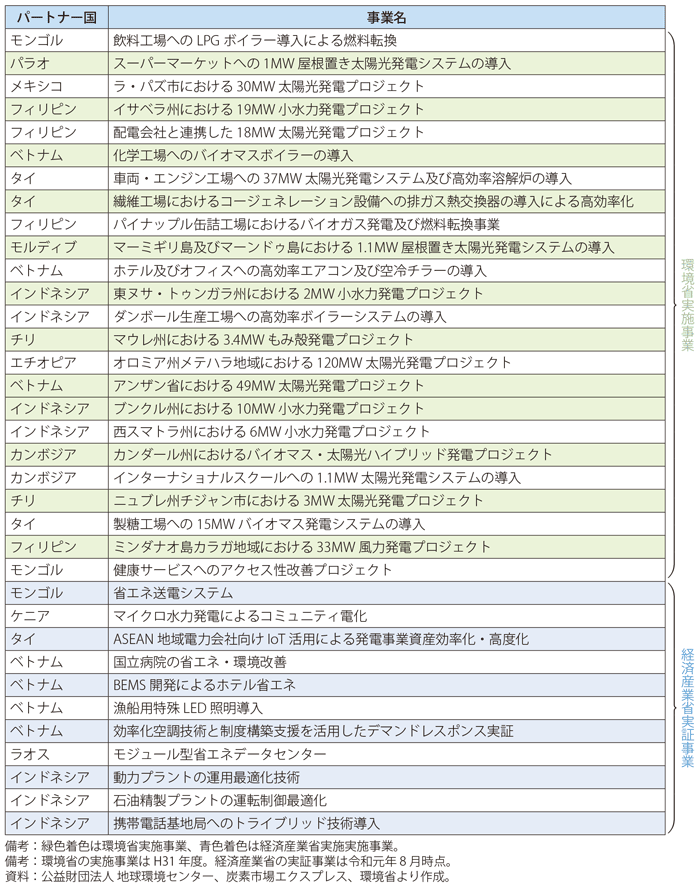
106 Sustainable Development Solutions Network (SDSN) and the Bertelsmann Stiftung. (2019)
107 許容しがたい気候変動の悪影響の回避という観点から、「産業革命後の気温上昇を2℃以内に抑える」という目安が、COP16(2010年)で合意されている(一般的に「2℃目標」と呼ばれる)。
108 2011年から開発途上国とJCMに関する協議を行っており、モンゴル、バングラデシュ、エチオピア、ケニア、モルディブ、ベトナム、ラオス、インドネシア、コスタリカ、パラオ、カンボジア、メキシコ、サウジアラビア、チリ、ミャンマー、タイ、フィリピンとJCMを構築している。
(2)期待される役割
グローバリゼーションの進展の中、我が国の持続可能性は世界の持続可能性と密接不可分である。先述したとおり、SDGsは経済・社会・環境の三側面を含むものである。2019年12月には、持続可能な開発目標(SDGs)推進本部(議長:安倍総理大臣)において、これらの相互関連性を意識して取組を推進していくことを目指して、SDGs実施指針の改定やSDGsアクションプラン2020を公表した。実施指針では、NPO/NGO、民間セクター、地方自治体、教育機関、研究機関など広範なステークホルダーとの連携を推進していくことの必要性が述べており、今後も、様々な主体が連携して社会課題の解決に向けて行動することが求められる(第Ⅱ-3-3-20表)。
第Ⅱ-3-3-20表 SDGs実施指針の取組
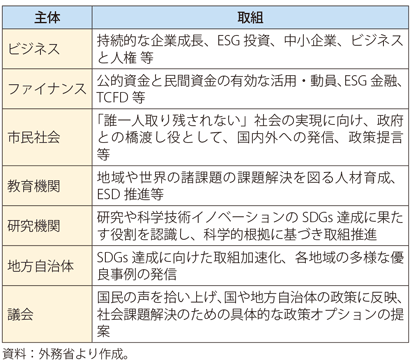
特に、上記のSDGs実施指針改訂版において「官民が連携し、企業が本業を含めた多様な取組を通じてSDGs 達成に貢献する機運を、国内外で醸成することが重要である」とされているように、SDGs達成に向けて民間企業の貢献が期待されている。例えば、関東経済産業局では、SDGs達成を通じた地域中小企業等の競争力を強化することを目的に、2018年5月、長野県との連携による地域SDGsコンソーシアム(NAGANO×KANTO地域SDGsコンソーシアム)を設置した。本コンソーシアムを通じて、有識者や産学官金の関係者と連携しながら、自治体等がSDGsに取り組む地域の中堅・中小企業等を後押しするための新たな仕組み(支援モデル)の構築や、企業・自治体への積極的な情報提供など、継続的な取組を行っている。さらに、近畿経済産業局では、2017年12月に関西で設立された「関西SDGsプラットフォーム」を母体として、ビジネスの視点からSDGs推進を目指すため、2018年3月に「関西SDGs貢献ビジネスネットワーク」を立ち上げ、各種セミナーの開催等によるノウハウの共有や企業間連携の形成を図るとともに、「関西発SDGs貢献取組事例集」の公表等を通じて個別事例の情報提供を継続的に実施している。
また、地方自治体においては、SDGsの理念に沿って、持続可能なまちづくりや地域活性化に取り組むことで、地方創生の一層の充実が図られることも期待されている。例えば、福岡県北九州市においては、2018年4月にOECDから「SDGs推進に向けた世界のモデル都市」としてアジア地域で初めて選定されるなど、世界規模で見ても先駆的な事例が見られている109。
このように、日本においては既に様々なステークホルダーがSDGsの取組を進めており、国際協調を推進しながら世界の社会的な課題の解決を実現し、世界の持続可能性を高めることが求められている。
109 北九州市「2018年4月23日報道資料」、(https://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000800982.pdf![]() )。
)。
