

- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2020

- 白書2020(HTML版)

- 第Ⅱ部 第3章 第4節 世界のデジタル化の加速における新興国との共創を通じた新事業の創出
第4節 世界のデジタル化の加速における新興国との共創を通じた新事業の創出
先進国の成長が鈍化傾向にある中、とりわけ日本は人口減少、少子高齢化が加速し、生産年齢人口の減少が急速に進み、経済成長に影を落としている。日本が今後も持続的な成長を実現するためには、成長ポテンシャルを有する新興国・途上国に積極的に関与し、日本も共に成長するというメカニズムを強化・構築していくことがこれまで以上に重要である。
第2章においてグローバリゼーションの進展の歴史、技術的な進展を振り返ってきたが、第2のアンバンドリングは日本が積極的に取り入れてきたものであった。1990年代より、日本企業は製造業中心にいち早くアジアへの積極的な投資を行い、国際分業を展開したことによりアジアと共に成長することに成功した。
そして、現在に至っては、急激なスピードで世界のデジタル経済化が進行する歴史的な転換点にいる。社会インフラが未整備の国においてはデジタル技術を活用し社会的課題を解決するような有望成長企業が台頭してきていたところに、新型コロナウイルスの感染拡大が起こった。そのような状況の中、例えばアジア新興国においては感染経路追跡アプリを民間事業者と協力して開発するといった事例や、アフリカにおいては人と人との現金の手渡しによる感染リスクを低減させるため、フィンテック企業が政府と中央銀行の支援を受ける例など、官民一体で一足飛びのデジタル化を加速させる動きが見られる。日本もその流れの中で持続可能な成長に向け、現地企業と協働しながら、社会課題を解決している事例なども見られてきている。アジアにおけるデジタル化の流れは、アジア・デジタルトランスフォーメーションと呼ばれているが、本節においては、持続可能な成長に向けた現地企業との共創の動きや、それを踏まえた長期的な視点での日本の産業戦略について見ていく。
1.デジタル化の時代におけるグローバル産業戦略の連携パートナーとしてのASEAN、インド
経済成長の長期的鈍化、GAFA、BAT110といった世界的デジタル企業を輩出できずにいる中で、世界における日本の存在感が危ぶまれている。しかし、日本は、長年蓄積してきたアジア各国との信頼関係を有しており、今後もアジア各国に積極的に関わり続けることができる環境を有している。さらに、市場の新規開拓、競争力の向上、ひいては日本の存在感の更なる向上、リスクマネジメントの観点からも、東南アジア、インドを中心としたアジアに着目する重要性が増している。
本節においては、まず、アジア新興国における各国・地域の経済規模と成長性、ビジネス環境、デジタル経済の浸透度、デジタル人材を検証することで、ASEAN、インドとの連携強化の有望性を示していく。
110 デジタル化を先導する代表的プレーヤー。米国企業のGAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)、中国企業のBAT(Baidu、Alibaba、Tencent)。
(1)経済規模と成長ポテンシャル
①GDP
世界各国のGDP額(購買力平価ベース)を2016年と2050年の2時点で比較すると、これまで世界経済を牽引してきた先進国を新興国が代替することが見込まれている。インドが米国を超える111ことのほか、ASEANの存在感が注目に値する。具体的には、2016年には8位であったインドネシアが2050年には4位になるほか、マレーシア、フィリピン、ベトナムがそれぞれ順位を大きく上げることが予測されている(第Ⅱ-3-4-1表)。
第Ⅱ-3-4-1表 GDP額(購買力平価)上位30か国(2016年と2050年の予測)
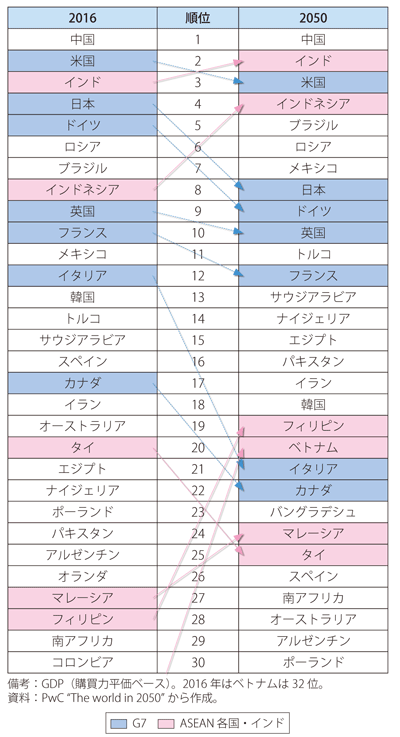
111 購買力平価ベースのGDP額は、2016年では、米国が18.6兆ドル、インドが8.7兆ドル、2050年では、米国が34.1兆ドル、インドが44.1兆ドルと予想されている。
②総人口
世界各国地域の総人口を2019年から2050年の年平均成長率で比較すると、米国以外の先進国及び地域は縮小すると予測されている。日本は年平均で-0.6%と最も縮小幅が大きいが、欧州(-0.2%)、中国(-0.1%)も同じく縮小が見込まれている。少子高齢化や人口減少は、供給面と需要面の双方に影響を及ぼすものである。一方、インドと東南アジアの総人口は、ともに年平均で0.6%の増加が予測されており、経済の拡大が期待できる(第Ⅱ-3-4-2図)。
第Ⅱ-3-4-2図 主要国・地域の総人口と年平均成長率(2019年~2050年)(予測)
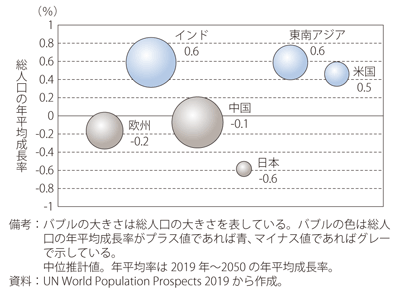
③労働力
各国の生産活動の中核となる生産年齢人口を2019年から2050年の年平均成長率で比較すると、米国以外の先進国及び地域は縮小が予測されている。生産年齢人口の縮小は総人口の縮小よりも速いペースで進み、日本は年平均-1.1%と最も縮小幅が大きいが、欧州(-0.6%)、中国(-0.6%)も同じく縮小が見込まれており、人口オーナスが進展する。一方、インドは0.6%、東南アジア0.4%と若年層の拡大が見込まれ、現在の中国に替わる世界の生産地かつ消費地となると期待される(第Ⅱ-3-4-3図)。
第Ⅱ-3-4-3図 主要国・地域の生産年齢人口と年平均成長率(2019年~2050年)(予測)
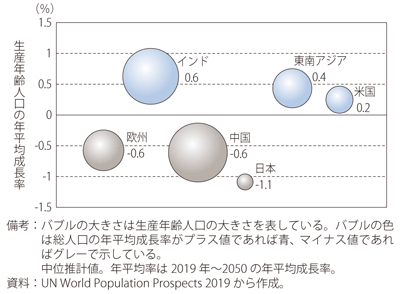
④市場
家計消費支出額を見ると、1998年から2018年の20年間で、米国は2.4倍、EU112は1.9倍、日本は1.3倍の拡大にとどまるが、ASEANは6.1倍、インドは6.0倍と大きく拡大している。中国の11.2倍には及ばないものの、ASEANやインドの人口増加や成長の伸びしろ等を踏まえると今後も市場の拡大が期待される(第Ⅱ-3-4-4図)。
第Ⅱ-3-4-4図 主要国・地域の家計消費支出額(20年の変化)
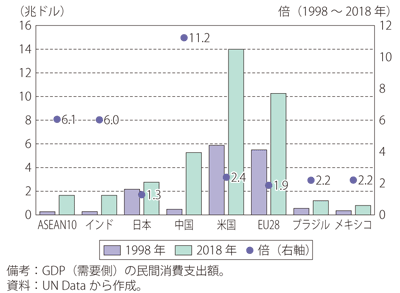
112 ここでは、EU28か国を指す。
(2)ビジネス環境整備の重要性
①世界のビジネス環境
世界銀行が発行する「ビジネス環境の現状2020」によれば、調査対象全190か国のうち、シンガポールが総合2位113であり、マレーシアが12位、タイが21位と、日本(29位)よりビジネス環境が評価されている。ASEAN10か国は成長段階に大きな差があるため、特にカンボジア、ラオス、ミャンマーといった後発国のビジネス環境は未整備ではあるものの、先発国は日本よりもビジネス環境が高いことは注目に値する。なお、当該報告書では、アジアの中でも、中国とインドが「世界で最も改善が見られた上位10か国・地域」と評価された114。今後もアジア諸国の評価は軒並み上昇すると期待できる。ビジネス環境の評価と対内直接投資には一定の相関があり、環境改善が評価された国には世界からの投資先として選ばれやすい(第Ⅱ-3-4-5表)。
第Ⅱ-3-4-5表 ビジネス環境ランキング2020
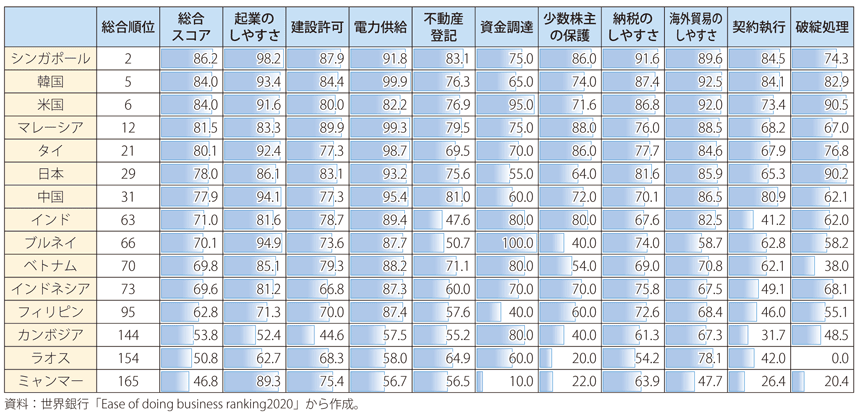
113 1位はニュージーランド。
114 中国は、調査項目である分野毎にワーキンググループをつくり、ビジネス環境改善を努めてきたこと、また、インドは、州レベルでのビジネス環境ランキングが作成され、各州間でのビジネス環境改善競争がおこったことがそれぞれの改善に大きく寄与したと指摘されている。
②日本に対する評価、期待
日本はASEANから「世界の平和・安全・繁栄・ガバナンスの貢献で最も正しい行動を取ることのできる国」と評価されている115。その他、「自由貿易のリーダーシップ」や「ルールベースの秩序、国際法のリーダーシップ」をとる国として、EUと同様、高い評価を得ている(第Ⅱ-3-4-6図)。
第Ⅱ-3-4-6図 ASEANが「世界の平和・安全・繁栄・ガバナンスへの貢献で正しい行動を取ることのできる」と考える国
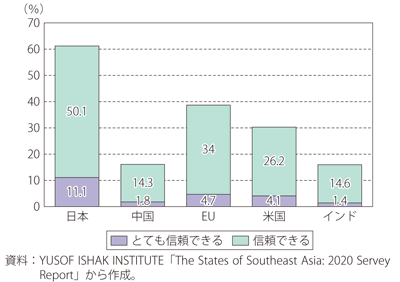
115 シンガポール政府系シンクタンクであるYUSOF ISHAK INSTITUTEがASEAN10か国を対象に行っている調査結果。ASEANの各機関が地域情勢や対話国に対してどのような認識をもっているかを調査したもの(2019年11月12日~12月1日にオンラインで実施)。なお、回答者を5つの専門分野(調査、企業/金融、公的機関、市民組織、報道)から抽出している。
2.デジタル経済の浸透
ここで成長著しいデジタル経済に視点をおくと、ASEAN6か国116のインターネット経済はGDPの5倍近い伸びで急成長している。人口の大半を占める若年層が成長を押し上げていることが背景にある。なお、名目GDPとインターネット経済(GMV)の年平均成長率を比較すると、2015年から2019年については名目GDPが6.1%、インターネット経済が33.0%であり、デジタル経済の著しい成長を見て取ることができる。なお、2015年から2025年については、名目GDPの平均成長率が6.6%と堅調に推移する一方、インターネット経済の成長率はそれを上回るペースが継続し、28.2%と予測されている(第Ⅱ-3-4-7図)。
第Ⅱ-3-4-7図 ASEAN6か国のGDPとインターネット経済(GMV)の年平均成長率の推移(予測)
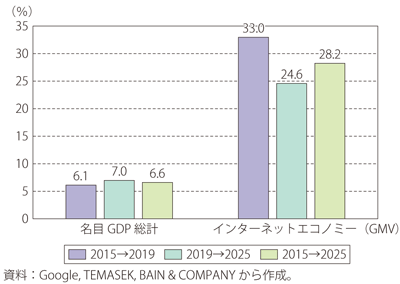
116 インドネシア、ベトナム、フィリピン、タイ、マレーシア、シンガポールの6か国
(1)拡大するインターネット経済
ASEAN6か国のインターネットユーザーは、2015年の2億6,000万人から、2019年には3億6,000万人と増加している。このうち概ね半分である1億8,000万人が、インターネット上で財やサービスの購買を行っている。つまり、市場は更に拡大をする余地を有している。
なお、ASEAN6か国のインターネット経済は急拡大しており、2019年は2015年の320億ドルから1,000億ドルに、2025年には3,000億ドルになると見込まれている117(第Ⅱ-3-4-8図)。インドについても、インターネット経済規模は2027年までに2,000億ドルに拡大することが見込まれている118。
第Ⅱ-3-4-8図 ASEAN6か国のインターネット経済(GMV)(予測)
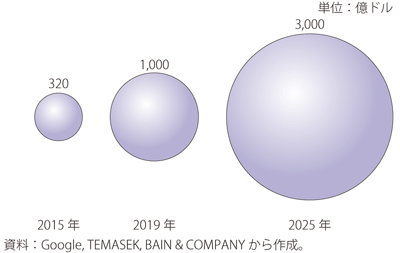
以下、ASEAN6か国の内訳を見てみよう。
2015年から2025年のインターネット経済規模の年平均成長率は、全ての国において10%を超え、とりわけ、インドネシア(32%)、ベトナム(29%)、フィリピン(27%)、タイ(24%)と高いことが分かる。
また、2025年において、インターネット経済が名目GDPに占める割合は、ベトナム(10.9%)、インドネシア(8.3%)、タイ(7.3%)と経済のデジタル化の進展が予測される。
以上から、インターネット経済はシンガポール、マレーシアのように相対的に発展度が高く一人当たりの所得も高い国より、むしろ、発展途上で一人当たり所得も低い国の方がより成長のスピードが高いことが伺える(第Ⅱ-3-4-9図)。
第Ⅱ-3-4-9図 ASEAN6か国のGDPにインターネット経済(GMV)が占める割合とインターネット経済の年平均成長率
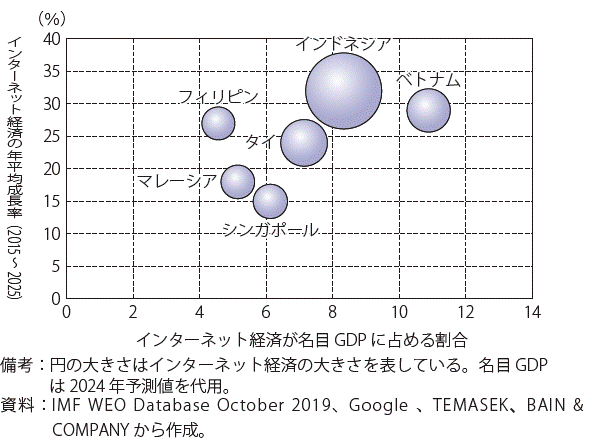
117 地場ネット通信販売、旅行予約サービス、オンラインメディア、シェアリングサービスが伸びている。
118 Ernst & Young 調査。https://economictimes.indiatimes.com/tech/ites/ey-estimates-that-digital-technologies-to-create-1-trillion-economic-value-by-2025/articleshow/71581808.cms?from=mdr![]()
(2)一足飛びのモバイル化
ASEANの新規のインターネットユーザーの多くが若年層であり、また、総ユーザーの90%が携帯電話からのアクセスであるといわれている。携帯電話の登録台数を主要国と比較してみると、中国に続きインド、ASEAN地域の携帯電話登録数が増加していることが分かる(第Ⅱ-3-4-10図)。
第Ⅱ-3-4-10図 主要国・地域の携帯電話登録台数の推移
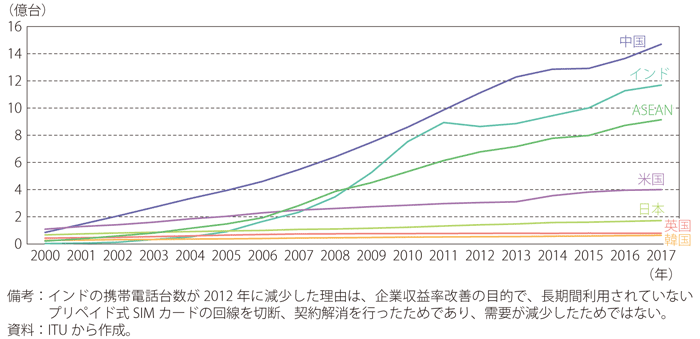
また、100人当たりの携帯電話登録数をみるとタイの180台を筆頭にベトナムが147台、シンガポールが146台とASEANメンバー国が高く、一部の国では日本よりも多く普及している(第Ⅱ-3-4-11図)。
第Ⅱ-3-4-11図 主要国・地域の携帯電話登録台数(100人当たり)
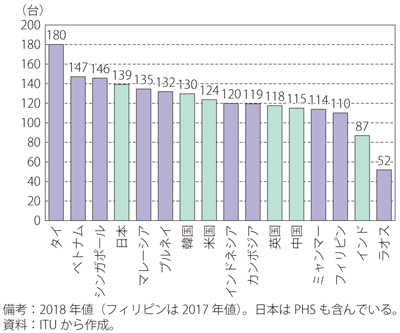
なお、携帯電話の登録数は、2000年には先進国が65.2%と過半数を占めていたが、その後先進国と途上国の割合が逆転し、2019年には途上国の占める割合が80.2%となっている。これは、固定電話より携帯電話の方がインフラ整備にコストがかからないこと、利便性や機能性が高いこと等により、先進国とは異なり、固定電話を設置する過程を経ず一足飛びに携帯電話を持ったことに起因する(第Ⅱ-3-4-12図)。既に登録台数の伸びが鈍化の様相を呈している先進国とは対照的に、インド(特に農村部)、ASEAN(特に後発国)については今後も拡大することが予想される。
第Ⅱ-3-4-12図 世界の携帯電話登録者数と先進国と途上国の割合の推移
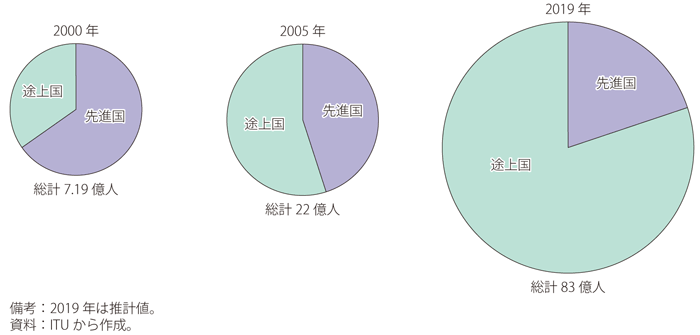
(3)生活におけるデジタルの浸透とデータフロー量の拡大
次に、携帯デバイスを通じた一日当たりのインターネット利用時間を比較すると、タイの5時間13分を筆頭に、フィリピン、インドネシア、マレーシアのASEAN4か国が世界平均(3時間14分)よりも長時間であるとされている。なお、日本はフランスと同様1時間25分と短い(第Ⅱ-3-4-13図)。
第Ⅱ-3-4-13図 世界各国の一日当たりのインターネット利用時間(携帯デバイスのみ)
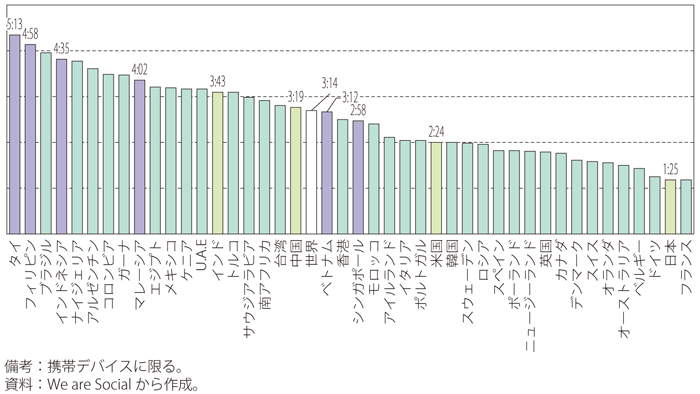
また、一日当たりソーシャルメディアの利用時間は、日本が36分であるのに対し、フィリピンが2位のブラジル(3時間34分)を大きく上回る4時間12分であることや、13才以上の人口に占めるソーシャルメディア普及率は、日本が69%であるのに対し、マレーシア、フィリピンは99%と世界最高となっている119。
これらのデータから、ASEANでは、日本と比較にならない程、人々の生活にデジタル分野が深く浸透していることを感じることができる。なお、インドも世界平均よりデジタル分野の浸透度が高いことも見てとれる。
インターネットに費やす時間の長さと利用人口の多さから、ASEANやインドにおけるデータフロー量は急速に拡大していると考えられる。
119 We Are Social調査。
(4)インドの豊富な高技能デジタル人材
急速なデジタル経済化により、世界から理系人材が必要とされている。近年、各国がSTEM教育(科学・技術・工学・数学)を重視しIT社会に適応した人材を多く産みだそうとしているが、とりわけ成功したのがインドといえよう。
同国はインフラ整備の遅れが影響し、生産拠点としては問題があったものの、もともと教育に力を入れていたことに加え、英語力、若くて豊富な人材、人件費の安さといった強みがあった。そして、90年代、米国でいわゆるIT革命が起きようとしていた頃、マイクロソフトやIBMといった米国の大企業がインドに目をつけ進出したこと、産業界120の積極的な働きかけがあったことなどがきっかけとなりIT産業が大躍進することとなった。そして90年~2000年代のIT業務のオフショアアウトソーシング(BPO事業)から、2010年以降の研究開発(R&D)、上流設計、イノベーションの供給地へと質的に業態が進化している(第Ⅱ-3-4-14図)。
第Ⅱ-3-4-14図 インドIT産業の質的業態の変化
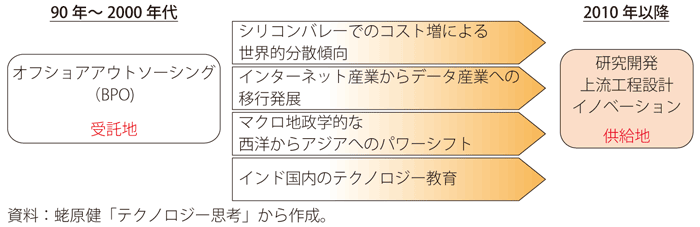
これを支えるのがインドの高等教育機関である。産学官連携重視の教育機関として、現在全国に23校を構えるインド工科大学(IIT)を始めとした大学から優秀な理系人材が輩出されている。同国には理工系大学が3,000校以上あり、毎年150万人以上が理工系大学を卒業しているとすると公表されている121。これは日本の全大学卒業者(圧倒的過半が文系122)の3倍にあたる。
参考までに、インドの高等教育機関の学校数と学生数は以下の通りである。各教育機関の定義が同一ではないこと等の理由から一概に比較はできないものの、インドと日本の高等教育を受けている学生数のボリューム感の違いを見て取ることができる(第Ⅱ-3-4-15表)。
第Ⅱ-3-4-15表 インドの高等教育機関の学校数と学生数
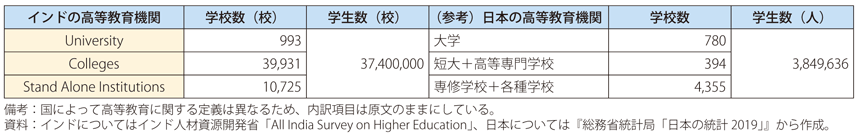
上記で人材の輩出状況をみたが、次に産業分野で働くインド人材を見てみよう。インド国内ITサービス企業の従業員数は、タタ・コンサルタンシー・サービシズが40万人、インフォシスが20万人、ウィプロが10万人であり、そのほとんどがエンジニアである。国外をみると、IBMは13万人、アクセンチュアは10万人超をインドで雇用しているが、これは米国本社よりも多く、同様の企業は他にもある。そもそも、Google、Microsoft、Adobeといったグローバル大手IT企業のCEOや創業者にはインド一世移民が多いほか、スタートアップ・エコシステムを形成するシリコンバレーにもインド人材の存在感が大きいといわれている。なお、ASEANを視点におくと、ASEANの地域拠点として選ばれることが多いシンガポールもインドの理工系人材が多いといわれている。日本は、急速なデジタル経済化に対処するためにインド理工系人材と連携することは有効と考えられる。
以上、経済規模と成長性(GDP、総人口、労働力、市場)、ビジネス環境整備の重要性、デジタル経済の浸透(データフロー量の拡大)、デジタル人材の観点でデータを見てきたが、日本が急速なデジタル経済化に対処し、長期的な成長、世界から必要とされる存在を維持するためには、東南アジア、インドと積極的に連携すべきといえよう。
120 業界団体のNASSCOMは1988年の設立当初からIT分野の強化を政府に強く要請し、政府がIT戦略を国策として推進してゆくことになった。
121 全印技術教育委員会によるデータ。
122 参考までに日本の高等学校の現状をみると、普通科約7割(80万人)・専門学科等約3割(30万人)となっている。なお普通科においては文系が約7割(50万人)と多い。多くの生徒は2年生以降、文系・理系に分かれ、特定の教科については十分に学習しない傾向にある。
3.東南アジア・インドのデジタルトランスフォーメーションの事例
ASEANやインドではデジタルコンシューマー系のスタートアップ企業が数多く現れ、企業評価額を急速に伸ばしている。これらの新興企業は、日本企業には見られないような業態で、経済基盤や社会インフラの整備、社会的課題解決につながるビジネスを展開している。ここでは具体例として、Gojek、Tokopedia、Zilingoの3社を紹介しよう。
【Gojek】
ASEANを代表するデジタル新興企業。中核のサービスはオンライン配車だが、ECサイト、輸送・配達、フードデリバリー、電子決済まで、多角的なサービスを展開。2010年に創業、2016年に企業評価額13億ドルでユニコーン企業123、2019年に100億ドルを超え東南アジアで2社目のデカコーン124となった。登録ドライバー数は10倍(2016年:20万人→2019年2月:200万人)125、アプリのダウンロード数は1億4千万を超え126、年間トランザクションは20億件に達した。
創業者は1984年にシンガポールのインドネシア人家庭に生まれたナディム・マカリム氏127。創業のきっかけは、インドネシアのバイクタクシーをテクノロジーで効率化できないかという問題意識128であった。一つの特定市場に絞り込むと値下げ競争を回避できないという考えから、一つのプラットフォームに多くのサービスを盛り込み利益を上げるビジネスモデルを採用した129。
生活のあらゆる場面で使える「スーパーアプリ」の恩恵を受けたのはユーザーのみならず、ドライバーである。貧困状況にあったバイクタクシーの運転手がGojekの運転手になることで収入の増加、生活の安定につながった。また、「スーパーアプリ」のビッグデータが、ドライバーの銀行口座開設や零細業者への低利融資といったフィナンシャル・インクルーシブ・グロースの実現につながっている130。
123 企業評価額10億ドル以上の非上場企業
124 企業評価額100億ドル以上の非上場企業
125 運輸分野における個人の財・サービスの仲介ビジネスに係る国際的な動向・問題点等に関する調査研究(2018年6月国土交通省)P22 https://www.mlit.go.jp/pri/houkoku/gaiyou/pdf/kkk148.pdf![]()
126 2019年4月時点
127 米国大学卒業後、経営コンサルタントとして従事した後、米ハーバード大学経営大学院(HBS)でMBA取得。HBSでは「ベース・オブ・ピラミッド(BoP)」と称される社会の底辺層に向けたビジネス(Business for BoP)を学んだ。なお、シンガポールで配車アプリサービスを展開するデカコーン企業Grabの創業者アンソニー・タン氏はHBSでの同級生である。
128 バイクタクシーは運賃形態が非常に不明瞭であるほか、営業区域が定められていることで、実態は、ユーザーが乗りたい時に乗れていなかった(日経アジア賞2019年5月第24回)http://www.nikkei-events.jp/asiaprizes/winner/index.html#winner01![]() 。マカリム氏はドライバーの「客待ちの待機時間が非常に長い」との話を聞き、その待機時間に別のものを運ぶことができれば、渋滞のひどいジャカルタにおいては四輪にも勝る非常に優れた輸送手段になると気づいた(KDDI総合研究所)。2010年の創業当初はコールセンターを使った配車方式だったが、2015年からスマホを使った配車や宅配、金融などのサービスを本格的に開始した(日経アジア賞2019年5月第24回)。
。マカリム氏はドライバーの「客待ちの待機時間が非常に長い」との話を聞き、その待機時間に別のものを運ぶことができれば、渋滞のひどいジャカルタにおいては四輪にも勝る非常に優れた輸送手段になると気づいた(KDDI総合研究所)。2010年の創業当初はコールセンターを使った配車方式だったが、2015年からスマホを使った配車や宅配、金融などのサービスを本格的に開始した(日経アジア賞2019年5月第24回)。
129 Go-jekの「スーパーアプリ」の考え方は、ユーザーがアクセスする最初のサービスは様々でも、プラットフォームを通じて便利と感じる他のサービスを利用してもらうことで、ユーザーの定着を図ることである。
130 KDDI総合研究所(2019年9月号)file://kvrdf99002v.ring.meti.go.jp/MShare$/OYCA4908/Downloads/KDDI-RA-201909-01-PRT.pdf![]()
【Tokopedia】
インドネシア最大手インターネット通販企業。国内の小売店の開拓を進め、約6,000万の零細事業者にAI(人工知能)などを活用した配送や金融サービスを提供。2009年に創業、10年足らずでユニコーン企業となった。企業評価額は70億ドル(約7,700億円)131に達する。総取扱高は150億ドル(約1兆6,200億円)を超える132, 133。楽天と同様、メーカーや小売店などにサイトを売り場として提供するモール(商店街)型のEC事業を展開。現在約550万の商店が出店しており、取り扱う商品数は1億5,000万点、月間アクティブユーザー数は約9,000万人に上る。
創業者は1981年にインドネシアの小さな島で生まれたウィリアム・タヌウィジャヤ氏134。創業のきっかけは、1万7,000もの島々である同国ではeコマース市場で購入した商品が届かないことがあることや個人が自由に商品販売できるプラットフォームがないという課題の解決だ。
物流の課題を克服するため、同社はGo-jekやGrabを含む11つの物流業者と提携した。出店者と購入者に配送業者を選ばせることで、配送の時間や品質を競わせた。物流業者をつなぎ合わせたことでインドネシア全土の97%をカバーできるようになった。さらに、顧客が注文した商品をできる限り顧客の所在地から近い商店から購入するよう、物流業者を誘導した135。
現在、収益構造の多角化を目指している。「誰もがテクノロジー企業になることを助けるテクノロジー企業になる」とのビジョンを掲げ、家族経営の零細事業主や農業、漁業、結婚式場など旧来型のオフラインビジネスに付きまとう非効率性をテクノロジーで変えようとしている136。
131 日本経済新聞(2019年6月)、米調査会社CB Insights(2020年4月)。ソフトバンクグループ傘下のソフトバンク・ビジョン・ファンドや中国アリババ集団などが出資している。
132 米調査会社CB Insights(2019年1月)
133 1997創業の楽天の流通総額は約3兆4,000億円(2018年12月期、日本国内)。
134 高校卒業後、生活費を稼ぐためにインターネットカフェでアルバイトをしながらジャカルタの大学に通い、大学卒業後、ソフトウェア会社を経て、モバイル関連企業で働いた。
135 注文を受けてから即日または翌日に配送する商品が65%だが、これを90~95%に高めるため、AIの活用にも取組んでいる。膨大な販売データを基にAIで需要を予測し、ある商品に関して多くの需要が発生しそうな場所の近くに前もって商品を移しておき、配送時間の短縮につなげている。
136 日経X TECH(2019年6月12日)https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00804/061000005/![]()
【Zilingo】
シンガポールを拠点137とし、ファッション・ライフスタイル用品等を提供するeコマース企業138。従来、服飾資材市場などで個別に対面で取引していた中小・零細企業に対し、同社のBtoCマーケットプレイスへの出店を通じ、消費データから需要予測を行い、最適な仕入や在庫管理、物流を提案・実施するBtoBサプライチェーンを構築していることが最大の特徴である139,140。
2015年に創業、2019年に約2.3億ドルの資金調達を行い、ユニコーン入りが目前である。
創業者は、1992年に生まれたインド人女性アンキティ・ボーズ氏141。創業のきっかけは、タイの服飾資材市場で、零細企業や個人事業主がその市場で対面取引している様子を見て、ネットの活用で彼らを支援するためとされている。
ZilingoのBtoCマーケットプレイスは出店費用を徴収せず、中小・零細事業者にとって参入障壁が低い。さらに、在庫管理システム、越境対応物流システム、売上分析、コンサルティング、テクノロジーサポートまでを「ワンストップサービス」として無料で提供する。販売手数料で収益を得るビジネスモデルが奏功し、東南アジアを中心とする17か国から5,000を超える事業者が出店している。2019年3月時点でユーザー数は700万人を突破した142。
Zilingoは2017年には欧米市場向けの新事業「ZilingoAsiaMall」を開始、順調に事業拡大しており、他国への進出も積極化している143。
137 出身地のインドではなくシンガポールに本社を置く理由は、法律や税制の面で有利で、物流やマーケティングなどの提携先を見つけやすいためと言われている。
138 GloTechTrend
139 GloTechTrend、HBS、ApparelWeb、CNBC
140 東南アジアのeコマース市場は、中国アリババ系のLazada、テンセント系のShopeeなどがこぞって参入するなど競争が激化している。Zilingoのように、BtoCマーケットプレイスで蓄積されたデータをBtoBサプライチェーンの構築に生かすビジネスモデルは、伝統的なアパレル業界の商流に変革をもたらす可能性があるほか、競争環境の中でも新興デザイナーなどが消費者と繋がり、新たな商品を生み出すエコシステム構築に貢献し得ることから注目を浴びている(GloTechTrend、CNBC)。
141 ムンバイの大学で数学と経済学を専攻。零細事業者が消費者の求める商品を理解し、適切な価格で提供し、有名ブランド、大規模なモールやオンラインショップに対抗するには、テクノロジーが不可欠だと考えていた。
142 ZilingoHP (https://zilingo.com/?landing=true![]() )、ApparelWeb (https://apparel-web.com/pickup/134782
)、ApparelWeb (https://apparel-web.com/pickup/134782![]() )
)
143 ApparelWeb
4.アジアのデジタル企業へ流入する資金
中国の成長がピークアウトし、次の成長センターはASEAN、インドに移っていくと予測されている中、ASEANやインドのスタートアップ企業へ資金が流入している。そこで、ASEANのデジタル企業向けの投資動向を見てみよう。
2019年は、投資額が前年から減少したものの、投資件数は過去最高となった。これは、ユニコーンへの投資額の減少と初期ステージの企業に対する50万ドル以下の相対的に少額投資案件が多かったことが主な要因である(第Ⅱ-3-4-16図)。
第Ⅱ-3-4-16図 ASEANデジタル企業への投資の推移(投資額・投資件数)
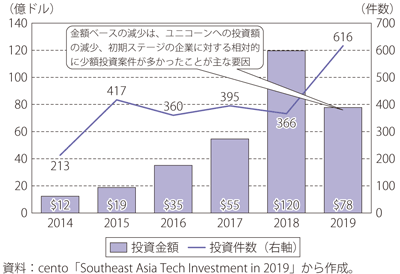
なお、直近では新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて資金調達環境の悪化が報じられており、今後の動向を丁寧に見ていくことが必要である。
ASEANデジタル企業への投資額をASEAN6の国別に見てみると、2018年以降、ベトナムのデジタル企業への投資額が急増していることが分かる。なお、投資件数はASEAN6全ての国で前年より増加しており、投資総額では減少したものの、投資は活発に行われていることが見てとれる(第Ⅱ-3-4-17図)。
第Ⅱ-3-4-17図 ASEAN各国デジタル企業への投資額の推移
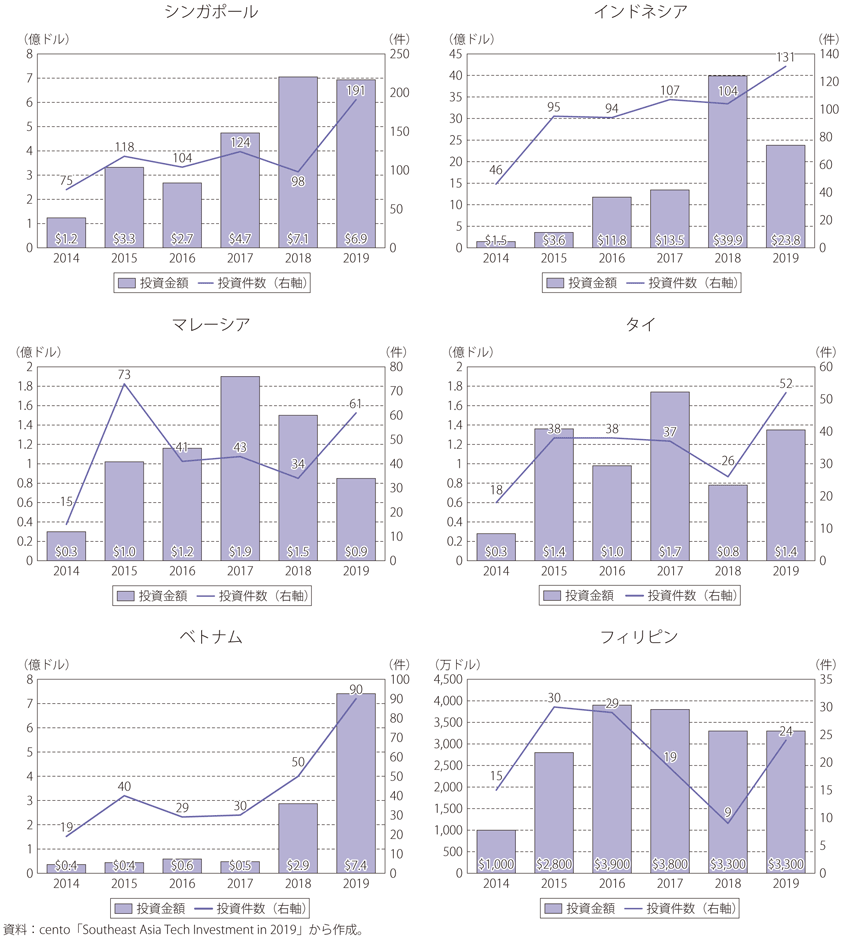
なお、各国への投資ボリューム(2014年~2019年の合計)を比較すると、金額ではインドネシアが、件数ではシンガポールが突出している(第Ⅱ-3-4-18図)。
第Ⅱ-3-4-18図 ASEAN各国デジタル企業への投資(2014年~2019年累積額)
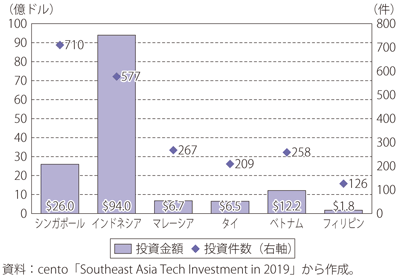
デジタル企業への投資額を分野別に見ると、2019年はマルチバーティカルといった多業種企業(例えばGrabやGojek)に対する投資額が前年からは減少したものの他分野と桁違いで1位となっている。なお、小売業、金融がそれに続いている(第Ⅱ-3-4-19表)。
第Ⅱ-3-4-19表 ASEANのデジタル企業への投資額の推移(テックの分野別)
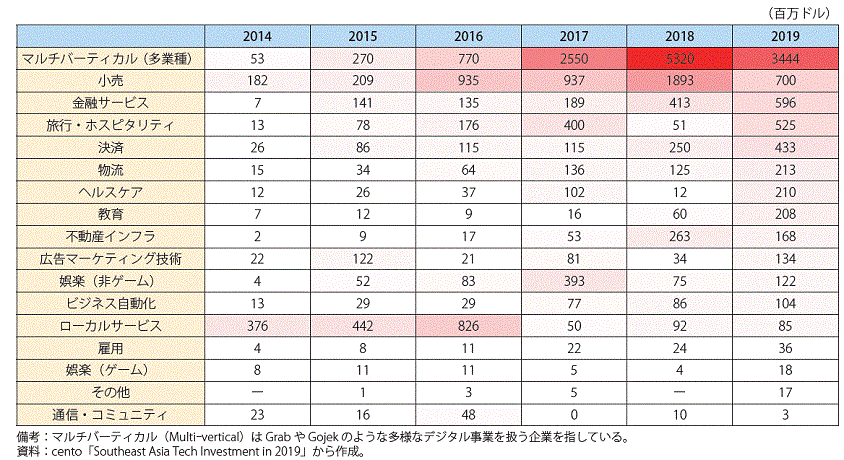
(1)中国大手インターネット企業による東南アジアEC企業の取り込み
近年、中国によるASEANデジタル企業への投資が積極的である。ここでは、2010年前後以降、東南アジアのEC市場にいち早く進出したアリババ集団、テンセント、JD.comの3社の動きを見てみよう。
アリババ集団(阿里巴巴集団、Alibaba Group Holding Limited、1999年創業)は、中国のEC最大手であり、B2Cのオンライン・ショッピングモール「Tmall.com(天猫)」は中国国内のEC市場において最大のシェアを占める。また、ECを起点に、物流、クラウドコンピューティングなど様々な分野に事業を多角化している。
テンセント(騰訊控股、Tencent Holdings Limited、1998年創業)は中国最大のソーシャルネットワーク・サービス(SNS)企業だが、それにとどまらず、オンラインメッセージサービス「Weixin」(微信)/「WeChat」を主軸に、そのプラットフォーム上でゲーム、音楽、動画、ショッピングなど多岐にわたるサービスを提供している。
JD.com(京東商城、JD.com,Inc.、1998年創業)は、アリババに次ぐ中国第2のEC企業であり、ECモールも手掛けるものの、直接販売を中心に据えている。JD.comは2014年にテンセントと業務提携するとともに、テンセントがJD.comに段階的に出資し、現在は筆頭株主となっている。テンセントからの送客など業務提携の効果から、JD.comの中国国内のEC市場におけるシェアは大幅に上昇した。
これら中国大手インターネット企業3社は、出資、買収、業務提携などを通じて東南アジアのEC事業者の資産を取り込んでいる。その背景には、中国のEC市場の成長鈍化と、東南アジアEC市場の将来性の高さの2つがある。
中国のECをはじめとするインターネット関連市場は、2006年に213億元(約3,600億円)だったが、10年後の2016年には5.3兆元(約88兆円)へ実に250倍に拡大した。ECを行う消費者の97%がアリババの「Tmall.com」を利用している。一方、スマートフォン利用者のうちテンセントの「Weixin」/「WeChat」を使う人の割合は76.5%に達しており、新規顧客の獲得が次第に難しくなりつつある。このような状況下で海外市場に目を向けるようになっている。加えて、東南アジアのEC市場は成長を続けているものの、EC化率は中国、米国、日本と比較しても低く、今後急速に拡大する余地が大きい。中国大手インターネット企業はこの点に着目しているとみられる。
(2)ASEAN政府による中国企業との連携
中国の大手インターネット企業の強みはASEANが抱える決済、物流、信頼に関わる問題を自国で克服して間もないという点である。企業内に蓄積された問題解決のためのノウハウをASEANで活用できることにある。
ASEAN各国政府も自国経済社会のデジタル化を図る144ため、中国企業と積極的に連携している。例えば、アリババの創始者を政府顧問に迎い入れたり(マレーシア、インドネシア)、同社の物流ハブを建設したり(マレーシア、タイ)、同社の研修プログラムへ閣僚を参加させる(フィリピン)などである。このようにASEANのデジタル経済において、中国の存在感は極めて大きいものになっている。
144 シンガポール「Smart Nation」、マレーシア「Digital Malaysia」、タイ「Digital Thailand」、インドネシア「Indonesia-The Digital Energy of Asia」、フィリピン「Philippine Digital Strategy」と各国スローガンを掲げてデジタル化政策を推進している。岩崎(2020)によれば、各国の狙いは異なり、シンガポールは「知識・イノベーション集約型社会の実現」、マレーシア、タイは「中所得国の罠からの脱出」、インドネシア、フィリピンは社会的課題の解決であるとしている。なお、インドは「Digital India」というスローガンのもと、デジタル化を通じて強化された知識経済社会への変革を目指している。
(3)日本企業によるASEANとの連携
こうした中、日本企業もASEANのデジタル企業との連携に乗り出している。連携分野は、Eコマース(例:オンラインマーケット)、フィンテック(例:決済ソリューション)、モビリティ(例:配車サービスなど)、最新デジタル技術(例:ビッグデータ、ロボット、ブロックチェーン等)のほか、動画配信、医療診断、広告など多岐にわたる。連携内容は、出資、資本業務提携、共同開発、実証実験、協業、買収などである。なお、参入する日本企業は、当初、新興企業が多かったが、最近では伝統的な大企業も加わるようになった。また、連携目的としては、市場の新規開拓・既存事業の強化、最新技術の獲得という調査結果がでている。
ASEANのデジタル企業が連携する目的は、企業の成長を支援してもらうためであり、資金調達がその代表例と言える。しかしながら、有望な企業には世界からのマネーが容易に集まるため、日本が連携先となる際には、資金以外のメリットが期待されている。例えば、技術獲得、顧客や取引先のネットワークの活用、日本進出の足かがりである。
5.アフリカにおけるイノベーションの潮流、社会課題解決ビジネスの勃興
次にアフリカに着目してみると、現在、アフリカにおいても、リープフロッグ型の発展によるイノベーションの潮流が生まれている。アフリカ社会もデジタル化が進んでおり、2019年時点における携帯電話の普及率はアフリカ全土で約8割(人口100人あたりの80.1人)となっており、その水準は過去10年ほどで大幅に上昇してきた(第Ⅱ-3-4-20図)。上記はアフリカ全土の平均値にあたるため国ごとの差異はあるものの、携帯電話の普及は今後も加速していくと予測されている。
第Ⅱ-3-4-20図 アフリカにおける人口100人あたりの携帯保有者数推移
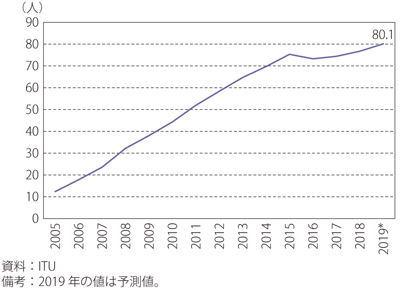
また、アフリカの市場に流通している多くのフィーチャー・フォンはインターネット接続機能を備えているため、人々は携帯電話を通じてインターネットを利用している。なお、フィーチャー・フォンだけでなく、近年、スマートフォンの普及率も高まってきており、背景としては、Transsionという中国の携帯会社が現地の需要に合った低価格で厳選した機能のみを備えた携帯電話を販売していることで、より多くの現地の人が手に入れることができるようになったことがその一因として挙げられる。2019年第4四半期では、Transsion傘下企業(Tecno、Itel、Infinix)がアフリカ全土のフィーチャー・フォン市場の70%を、スマートフォン市場の41%を占めている。145このような状況を生かし、スタートアップ企業がテクノロジーを駆使し、人々の身近な存在である携帯をうまく活用することで、現地の社会課題を解決する新しいビジネスを展開している事例が多くみられる。公衆衛生、交通インフラ、教育などの分野において、公共機関が従来担ってきた役割をボトムアップの形で、スタートアップ企業が補完している点は注目に値する。その中で、現地の政府と協議を行い、規制緩和や新しい制度を実現することで、新たなビジネス展開を可能にするスタートアップ企業も現れている。
例えば、BBOXXは、ケニアを始めとした未電化地域の農村などにおいて、太陽光発電・蓄電池等を導入する形で電力を供給している。モバイルペイメント等を利用し、支払った分だけサービスを利用できる仕組みにより生活に余裕の少ない層の利用を可能にしている。アフリカの国々では、国営の電力会社による供給が足りておらず、電化率をみても、世界が88.9%に対し、サブサハラアフリカは44.6%と非常に低い(第Ⅱ-3-4-21図)。国営の電力会社が、安定的な電力供給の機能を充分に果たすことができていない現状を補完する形で、オフグリッド146・ミニグリッド147のスタートアップが現地で活動しているのである。同じオフグリッドの分野では、日系スタートアップのWASSHAも、タンザニアなどにおいて、現地の小売店(キオスク)を介し、自社開発した太陽光充電式のLEDランタンを、所得の安定しない一般消費者に貸与する事業などを行っている。
第Ⅱ-3-4-21図 世界とサブサハラアフリカにおける電化率の推移
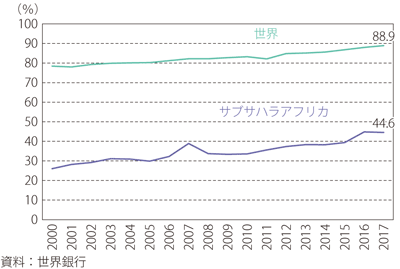
また、ヘルスケア分野においては、ナイジェリアのLifeBankが、アフリカにおいて、病院の輸血や医療物資不足により命を救うことができてない現状を解決すべく、病院に、輸血用の血液等の重要医薬品を配送するビジネスを行っている(第Ⅱ-3-4-22写真)。ナイジェリアでは、現地の交通インフラが十分に整備されていないため、交通渋滞が多く発生しているところ、バイクでの配達により、渋滞を避けたスピーディーな重要医薬品の配達を可能にしている。また、携帯アプリを活用したビジネスは、病院とLifeBankとのコミュニケーションを円滑にしており、正しい種類や量の医薬品の配達が実現している。現時点に至るまで、LifeBankは、ラゴスを中心に7,000人以上の命を救っている。なお、創業者であるTemieGiwa-Tubosun氏は、LifeBankのビジネスを通じた社会貢献が評価され、2014年にBBCが選ぶ世界の100人の女性の一人に選ばれた。
第Ⅱ-3-4-22写真 LifeBankの血液輸送バイク148

同じくヘルスケア分野において、ケニアのMydawaは、医師の処方箋を添付することで医薬品購入ができる仕組みのオンライン薬局を展開し、信頼性の高い医薬品を調達・オンライン販売を可能にした。これは、Mydawaは、ケニアで初めて、オンライン薬局として、当局よりその資格を取得したことにより実現したサービスである。Mydawaは、患者への配達も行うことで、高価かつ偽物が多い医薬品市場における課題解決を図ろうとしている。
また、ケニアの最大手通信事業者Safaricomが出資したSparkFundの支援を得て起業したSendyは、トラックやバイクを保有する配送業者と、消費財メーカー等をつなぎ、顧客までの効率的な配送を担うシステム・プラットフォームを構築している。これにより、物流市場における透明性の向上が期待される。
加えて、アフリカでは、金融や、農業、さらには既得権益の大きいエネルギー分野に至るまで、あらゆる産業でスタートアップ企業が登場し、現地の社会課題を解決するビジネスを展開することで、人々の生活を便利に、そして豊かにしていることに加え、経済社会システムの変革をももたらしている。
新型コロナウイルスが感染拡大している状況下においても、現地のスタートアップ企業は感染拡大の防止策を打ち出している。ケニアのSafaricomは、ケニヤッタ大統領と中央銀行の後押しを受け、東アフリカの主要なモバイルマネーのスタートアップ企業であるM-Pesaの手数料免除を決定した。人と人との接触や現金の手渡しによる感染リスクを避けるため、デジタルファイナンスでの取引の促進を図っている。
これらの急速な社会変容をもたらすようなイノベーションを創出し、スタートアップ企業の発展を牽引する起業家は、大きく分けて三つのタイプに分けられる。第一に、欧米人がアフリカのポテンシャルに惹かれ、また、残存する社会課題の解決を目指し起業する場合である。上述した英国のBBOXXや、2019年にニューヨーク証券取引所に上場を遂げた電子商取引(EC)サイトのJumiaなどが挙げられる。Jumiaはアフリカ版アマゾンとも呼ばれている。第二に、アフリカで育ち、欧米に渡って大学・大学院での教育や欧米企業での就労を経験した人材が、現地に戻ってスタートアップを始める場合である。上述したLifeBankが代表例として挙げられる。第三に、規模としては小さいものが多いものの、アフリカで育った若者が現地で起業する場合である。
145 IDC2020
146 電力会社からの電力供給へのアクセスが無い状態において、独自に電力を自給自足するシステム。
147 1メガワットなどの分散型電源。
148 LifeBankより提供。
6.アフリカにおけるスタートアップの成長
2019年のアフリカのスタートアップ資金調達額は、年間20億ドルと前年の11.6億ドルから約1.7倍増となった。過去5年間の推移をみると、急速な伸びを見ることができる。アフリカのスタートアップ資金調達額の伸びの要因としては、従来は、欧米の開発系の金融機関からの資金投入が多かったものの、2018年から欧米及びアフリカ所在の民間企業からの投資が増えたこと、また、2019年は中国企業による巨額の投資があったこと等が挙げられる(第Ⅱ-3-4-23図)。
第Ⅱ-3-4-23図 2015年から2019年までのアフリカのスタートアップ資金調達額149推移
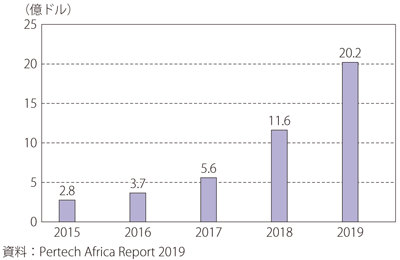
また、スタートアップ企業への投資件数も増えてきており、2019年は250ディールと前年の約1.5倍増となった(第Ⅱ-3-4-24図)。そして、2015年と2019年のラウンドのステージ別内訳をみると、シードとシリーズAの投資ラウンドが大幅に増加しており、アフリカにおけるスタートアップ企業が勃興していることが分かる(第Ⅱ-3-4-25図)。
第Ⅱ-3-4-24図 2015年から2019年までのスタートアップ投資件数
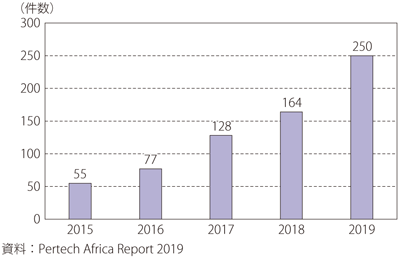
第Ⅱ-3-4-25図 2015年と2019年のステージ別スタートアップの件数の比較
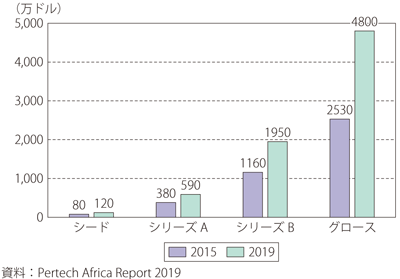
なお、2015年から2019年のステージ別の資金調達総額(第Ⅱ-3-4-26図)とラウンド毎の資金調達平均額(第Ⅱ-3-4-27図)を比較すると、グロースステージの伸びが加速しており、アフリカのおけるスタートアップの成長を牽引している。
第Ⅱ-3-4-26図 2015年と2019年の資金調達総額のステージ別スタートアップ内訳
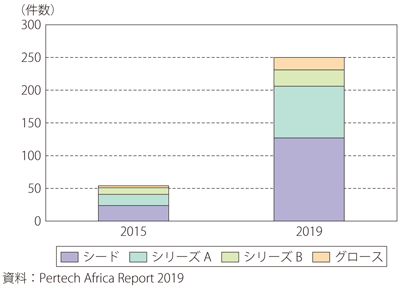
第Ⅱ-3-4-27図 2015年から2019年までのステージ別スタートアップ「資金調達額」の比較
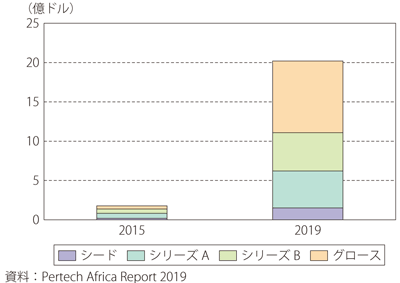
なお、2019年の資金調達額のセクター別内訳をみると、フィンテックへの投資が全体の41.4%と割合が高く、続いてオフグリッド、エンタープライズが並んで12.2%、ヘルステック9.3%となっている(第Ⅱ-3-4-28図)。アフリカでは、現地の銀行の口座を持っている人が少なく、また現地の銀行の利用は不便な点が多いため、小さな金額で資金の貸し出しや送金が可能なファイナンシャルビジネスへの注目が高まっているためと考えられる。また、世界における電子マネーサービス企業の地域別内訳をみると、世界に290の企業があるのに対し、サブサハラアフリカに144の企業がビジネス展開しており、現地におけるフィンテック分野の勃興が分かる(第Ⅱ-3-4-29図)。
第Ⅱ-3-4-28図 2019年資金調達総額のセクター別割合内訳
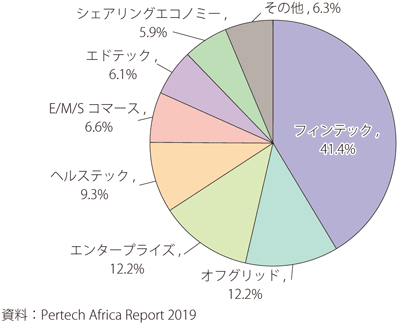
第Ⅱ-3-4-29図 世界における電子マネーサービス企業の地域別内訳(2019年)
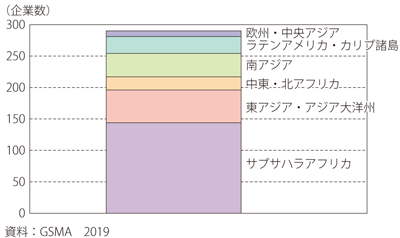
また、2019年の資金調達額を国別で比較すると、ナイジェリアとケニアがそれぞれ7.5億ドル、5.6億ドルと第3位のエジプト2.1億ドルを大きく上回る(第Ⅱ-3-4-30図)。
第Ⅱ-3-4-30図 2019年資金調達総額の国別内訳
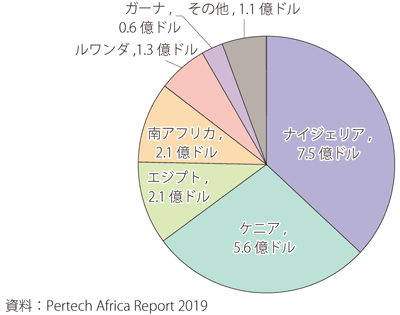
理由としては、ナイジェリアのラゴスやケニアのナイロビでは、市場の規模が大きいことに加え、スタートアップ企業に対するビジネス支援を行うインキュベーション・アクセラレーションハブが充実しており、ベンチャーキャピタルも多数存在するなど、スタートアップ・エコシステムが形成されていることが挙げられる。その背景の一つとして、シリコンバレーをはじめとする欧米に拠点を置く企業やベンチャーキャピタルが、現地事務所等の情報を通して、アフリカのスタートアップに対して巨額の投資を行っているということがある。例えば、ラゴスのCo-Creation Hub(略CCHub)という現地で有数のインキュベーションハブは、Google、Facebook、Microsoftなどを始めとした多くの企業とパートナーシップを組んで現地のスタートアップを支援するプログラムを実施した。また、Googleは2020年1月に、“Google Developer Space”と名付けてスタートアップ企業向けのハブをリニューアルし、現地の起業家やIT人材の囲い込みに一層力を入れ始めている。このような米国企業の取り組みを、欧米の教育機関における学位取得ないしは欧米企業での勤務経験を経てアフリカに戻ったベンチャーキャピタリストや起業家たちが架け橋となって支えており、現地のエコシステムの成長が加速している。
欧米企業が強い存在感を示す一方で、2019年は現地のスタートアップ・エコシステムに大きな変化が見られた。中国企業による巨額な資金投入である。各都市によって状況は異なるものの、アフリカで起業する中国人、彼らをサポートする中国人投資家や中国企業による、中国独自のエコシステムが現地で構築されており、強固なネットワークが確立されている状況となった。2018年は、資金調達額上位10位に入るディール150に中国企業が巨額な資金を投じていなかったものの、2019年はその状況が一変した。アフリカで高いシェアを誇る巨大な中国のスマホメーカーTranssionが、スマホへのアプリインストール等を通じたビジネス連携を実現するべく、Palmpayというフィンテック系のスタートアップに40億円出資した。また、中国系VCがOpayという同じくフィンテック系のスタートアップに総額120億円出資し、Opayの普及に乗る形で、ナイジェリアからケニア・ガーナ等への拡大を狙う。
上述した通り、世界中の企業からアフリカのスタートアップに対する投資が伸びていることから、将来的に、アフリカのスタートアップとのビジネスは競争率が高まっていくことが十分に考えられる。加えて、アフリカが他の地域と異なり、スタートアップ企業が重要なプレーヤーとして産業発展の過程を遂げていることからも、スタートアップ企業は将来的にアフリカの中で大企業となり得るだろう。
149 エクイティに限る。
150 Weetracker Report 2019
7.日本が目指すべき方向性と施策
(1)アジア・デジタルトランスフォーメーション(ADX)
以上で見てきたように、アジア新興国やアフリカにおいては、デジタル化を活用し、新型コロナウイルスへの対応も含めた企業の活力を見てきた。このような状況の中、まずアジア新興国に着目した日本政府の動きとしては、経済産業省に2019年9月、アジア新産業共創政策室を設置し、「アジア・デジタルトランスフォーメーション(ADX)」という構想を推進している。さらに、産業構造審議会成長戦略部会のみならず、内閣総理大臣を議長とする未来投資会議においても議論が進められている。
未来投資会議では、在来の産業政策における税・財政投融資・予算による一般的なインセンティブ措置では、狭義のガバメントリーチの外にある企業の製品開発投資やM&Aの経営決定に対し、十分な施策効果が得られなかったことに触れ、新しい産業政策の検討を旗印にしている151。その一つの切り口として、勇気ある企業数社がパイオニア的な行動を試みることで、周囲の企業に「同僚・同士効果(PeerEffect)」を及ぼし、それが雪だるま式に大きくなる「雪だるま効果(SnowBallEffect)」をもたらすことから、ADX構想はパイオニア的な企業数社を育てるプロジェクトにリソースを集中投資する。
ADX構想の基本的な視座は、大きく4つある。
まず、本政策に取り組む最大の目的は、デジタルトランスフォーメーションの加速化である。日本は、相当便利な社会になり、デジタルで構造改革を起こす起爆力が弱い。一方、新興国では、社会構造の変革がなければ生死に関わる切迫感があり、むしろ新興国の方がデジタルトランスフォーメーションを起こしやすい環境が整っている。日本の中で構造変革を起こそうとするよりも、アジアの新興国に舞台を移すことにより、デジタルトランスフォーメーションを加速化でき、それを日本の産業構造改革につなげる方が、むしろ近道ではないかということが一つ目の問題意識である。
二つ目は、日本の企業経営における問題である。日本企業は、既存ビジネスの効率化には長けているが、次なる新たなビジネスを育てていく経営ができていないとの指摘がある。そこで、上述のような新興国の環境を利用すべく、企業の人材やノウハウを出島としてアジアに出し、新しい事業を育てる組織能力、人材、その他無形資産を育む苗床とすべきである。
三つ目に、アジアのデジタルエコノミーにおけるパートナーとして、アリババやテンセントなどの中国の巨大企業が台頭しており、日本の存在感が危ぶまれているということがある。日本企業がこれまで製造拠点として進出し、築いてきた東南アジアでの良好なポジションを活かしながら、デジタルエコノミーへの参画を一気呵成に進める必要がある。
四つ目は、デジタルのルール整備についてである。昨年、G20サミットで安倍総理がDFFT(Data Free Flow with Trust)という概念を世界中に広めていく意向を表明したが、ベトナム、インドネシア、インドなどは、データローカライゼーション規制を設ける動きが顕著になってきており、東南アジア6億、インド13億の人口がどのようなデジタルルールをスタンダードとしていくのかが非常に重要な論点になっている。こうした点に働きかけるためには、その前提として、日本企業の活動がその地域で行われていなければ説得力を持たず、日本企業のデジタル活動を作る投資とルール整備を一体的に推進していかなければならない。
次に、ユニコーン企業数とユニコーン企業の価値評価額を確認する。あくまでも一時点での数であるため、このデータのみで国別順位は付けられないものの、インドは突出していることが分かる。ASEANについても日本より企業価値評価額が大きい企業が出現しており、こうした企業がインド、ASEANからは出現するが、日本からはなかなか現れないという状況が見える(第Ⅱ-3-4-31図)152。
第Ⅱ-3-4-31図 インド・ASEANのユニコーン企業数と企業価値評価額
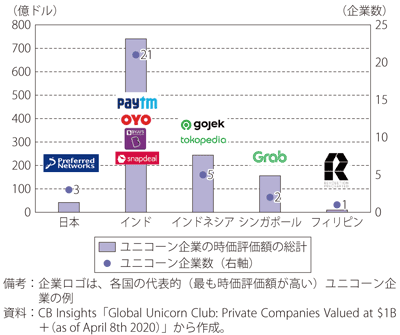
この状況を踏まえ、ADX構想では、ASEANやインドに存在する、ペインポイントといわれる深い社会課題、それをデジタルで解決したいという強い欲求、それを許す規制の緩さ、これらを日本にとってのチャンスと捉え直し、日本列島の中ではなく、アジア新興国に日本の資金・人材・技術・ノウハウを移しかえ、新しいビジネスモデルを一緒に作ることで、日本の産業構造転換につなげていくことが狙いである。
具体化の第一弾として、2019年11月、日泰企業連携プロジェクトの署名を行った。日本の大企業と現地のスタートアップとの連携事例として、例えば、豊田通商とFlareという企業の連携が挙げられる。これは、低所得者向けに車両の広告用カーラッピングサービスを提供し、車両の走行実態に応じた広告収入を還元するサービスを提供することで低所得者でも車両の購入を可能にするものである。他にも、凸版印刷とDRVRという企業との連携では、凸版印刷のID認証技術を活用し、メコン域内の物流・宅配企業向けの車両管理システムの共同開発を実施する。
日本のスタートアップ企業と現地の財閥や大手企業との連携事例もある。ウミトロンという日本のスタートアップ企業とタイ最大財閥傘下の食品子会社であるCPFOODとの連携では、CPFOODが行うエビの大規模養殖において、AIを活用した画像認識技術を活用し、適切なタイミング・量の自動エサやりを実現する。
こうした取組をアジア新興国に広めることについて、未来投資会議において議論が進められているところであるが、2019年12月には、新しい成長戦略実行計画策定に関する中間報告として、「政府では、新興国企業との連携による新事業創出を「アジアDXプロジェクト」として推進しており、(中略)JETROと在外公館とが協働し、経営層レベルのマッチングなどを行うほか、国内の大企業・既存企業が、アジア企業とともに新たなサービスや商品を試行的に開発する取組や、優秀な人材を外部に送り出す取組を支援する。こうした取組を通じ、最初のパイオニア企業数社を育てるプロジェクトを集中的に立ち上げ、「同僚・同士効果(PeerEffect)」を起こすリーディングモデルを創出する」こととしている。
こうした議論を踏まえ、「アジアDX等新規事業創造支援事業」を補正予算事業として計上したほか、日本企業が国内外問わずベンチャー企業に出資する際に所得控除を認める「オープンイノベーション促進税制」を2020年度税制改正において創設するなど、支援策の充実を通じ、アジアDXプロジェクトを加速化していく予定である。
折しも、新型コロナウイルスの感染防止に取り組む中で、ASEANなど新興国がデジタルトランスフォーメーションを一層加速化させている。例えば、シンガポール政府は感染経路追跡アプリを開発・無料配布し、タイ政府は特定国からの入国・帰国者に所在地追跡アプリのダウンロードを義務付けた。インドネシア政府は感染者の追跡監視アプリを、インド政府は感染者との接触履歴を確認できるアプリを民間事業者と協力してそれぞれ開発し、感染防止に尽力している。このように、ASEANなど新興国が欧米先進国に先行し、すばやくデジタル技術を課題解決に活用する動きを見せたことは大きく注目されるところである。
151 未来投資会議第30回(令和元年9月19日)(資料2:基礎資料)(内閣官房日本経済再生総合事務局)http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai30/siryou2.pdf![]()
152 CB Insights(https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies![]() )
)
(2)新たなビジネスポテンシャルを秘めるアフリカ
アフリカの現段階での市場規模や今後の成長性には、大きなポテンシャルがあるとはいえ、アジア新興国とは異なり、地理的にも遠く、進出している日本企業や在住する日本人の数がまだ少ないため十分な情報が手に入りづらいという大きな制約がある。また、中間層は十分に育っておらず、日本企業が自社の製品やサービスをアフリカに展開して、迅速かつ安定的に利益を上げることのできる段階にあるとはいえない。もちろん、中には自社製品・技術を現地の需要に応える形で、現地で成功を収めている日本企業がいることはいうまでもない。
アフリカ開発銀行の予測によれば、アフリカ全体の平均一人当たりGDPは、2030年に3,000ドルを超える見込みである。一人当たり3,000ドルは、四輪車が生活必需品として市場に普及するレベルであるため、2030年頃には、中間層向けビジネスモデルの展開を図ることができるようになる可能性が生まれるといえるだろう。なお、2040年には、西アフリカ以外の地域別平均では一人当たりGDPが3,000ドルを超えるため、その市場としてのポテンシャルはより一層高くなるとみることができる(第Ⅱ-3-4-32図)。
第Ⅱ-3-4-32図 アフリカにおける一人あたりGDPの比較と推移
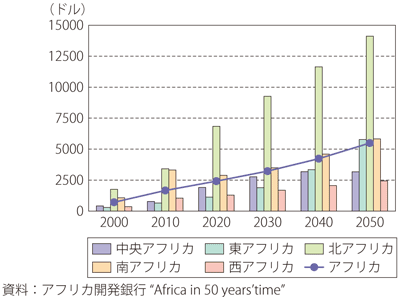
したがって、10年後のアフリカにおいては、スタートアップをはじめとする現地企業が、デジタル技術を活用したビジネスを展開し、既存の社会課題を踏まえて社会構造の変革をより進めている可能性が高い。10年後の市場開拓戦略も見据え、有望な現地スタートアップ企業への投資を通して、現地の情報収集・ネットワーク構築を図ることは有効な手段の一つであろう。既に日本企業においても、総合商社を中心に現地でビジネス展開をしているスタートアップに対して出資参画や投資をしており、新しい機会の獲得などに取り組んでいる(第Ⅱ-3-4-33表)。
第Ⅱ-3-4-33表 日本企業によるアフリカスタートアップへの出資事例
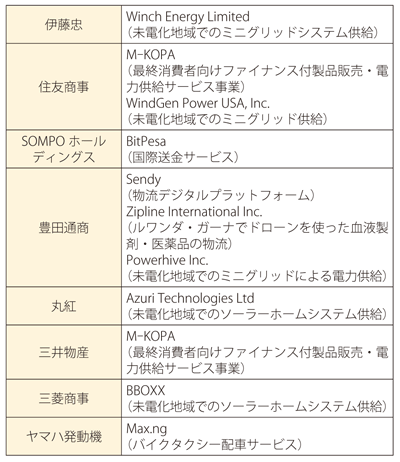
また、アフリカのスタートfアップ企業はまだアジアほど成長している企業が少ないため、現時点での投資であれば、高いポテンシャルを秘めるアフリカのスタートアップ企業に対して、アジアでの投資水準に比して少額で効果的に投資を行うことが可能であり、かつ、日本企業との将来的な協業をより一層促進するものとなり得る。現時点における情報収集と将来的な協業・パートナー探しの2つを主眼に、ビジネスモデルに親和性のある、有望な現地スタートアップ企業への投資の検討は一つの選択肢といえる。
他方、情報が限られている中で現地の有望なスタートアップ企業を探し出すことは困難であるため、現地のスタートアップ企業やベンチャーキャピタルなどと日頃より関係性を構築しているJETROの現地事務所や日系ベンチャーキャピタルからの情報やコネクションを頼ることで、投資先を選定することは一つの手段である。欧米企業や中国企業が積極的にアフリカスタートアップ企業への投資や人材育成に積極的に動く中、日本企業も先手を打って行動することが期待される。
これまで見てきたように、アジア新興国やアフリカのような社会インフラが未整備な国においては、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための対応まで含めた社会課題を解決するため、デジタル技術の社会実装を通じ、政府とベンチャー企業が協働する例や、日本企業が現地企業と協働する例などが有用な実例を見ることができた。世界がこれからも持続可能な発展を続け、新型コロナウイルス感染拡大といった課題にも活路を見いだすため、日本も官民連携しながら、こうした国々と協働を進め、世界の持続的な発展に貢献するとともに日本自体の改革につなげることが求められる。
153 各社プレスリリースより。なお、企業については五十音順。
