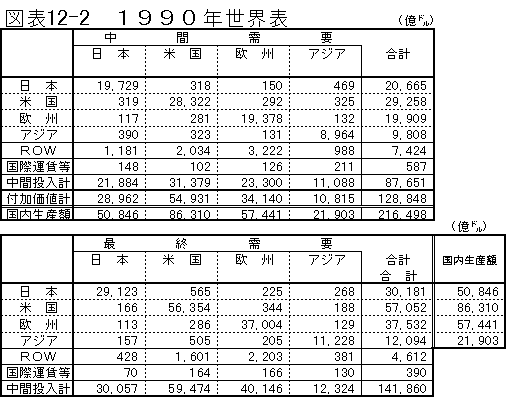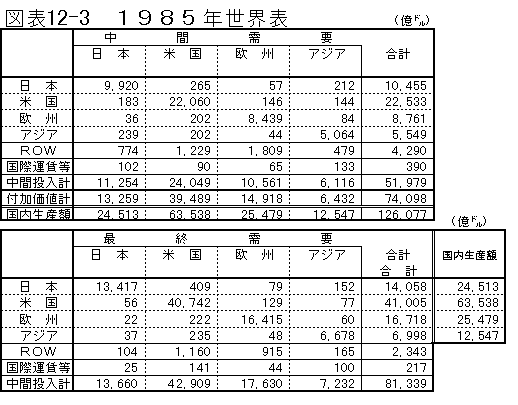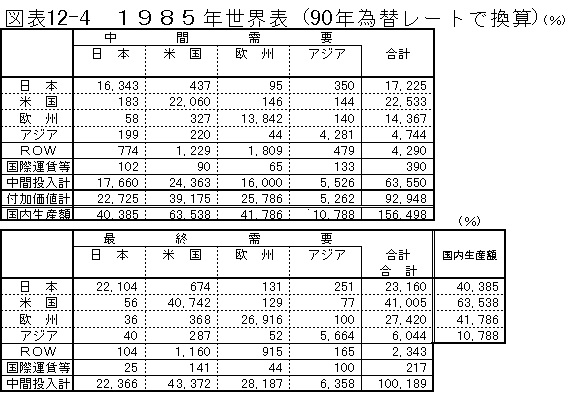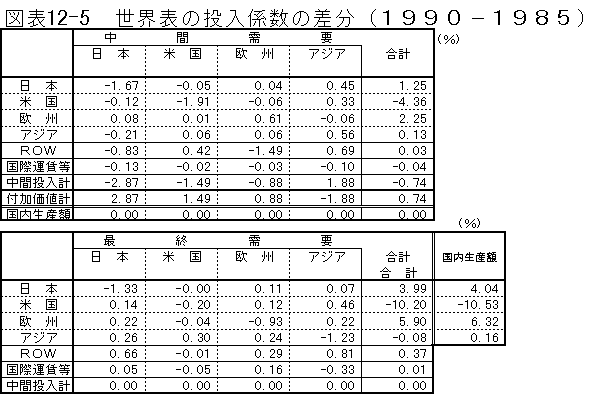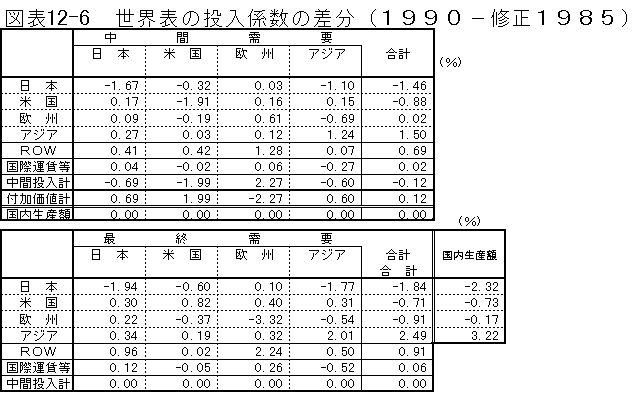- 統計

- 国際産業連関表

- 集計結果又は推計結果

- 統計表一覧

- 1990年日・米・EU・アジア多国間国際産業連関表
国際産業連関表
1990年日・米・EU・アジア多国間国際産業連関表
トピックス-2. 為替レートの変化が各国・地域の生産活動に及ぼした影響
世界表は、対象13か国の産業連関表(各国通貨建てで作成)を対米ドルレート(年平均)で換算して連結した米ドル表示の多国間産業連関表である。
世界各国の通貨は、1985年から90年にかけて変動し、日本円は85年の238.54円/ドルから90年には144.79円/ドルへと高騰している。また、欧州通貨(英国、フランス、ドイツの3か国通貨の平均)も同様に高騰しているのに対して、アジア通貨(8か国通貨の平均)はむしろこの間米ドルに対して低下している。
そこで、このような為替レートの変化が各国・地域の生産活動にどのような影響を及ぼしたか、世界表を使って簡単に分析してみた。
(1) 為替レートの変化が及ぼした影響の計測方法
1985年と90年の二つの世界表を使って、為替レートの変化が各国・地域の生産活動に及ぼした影響を計測するために、85年世界表について、90年の各国の対米ドルレートで再換算した。
換算は、ヨコ(行)方向の域内需要(中間需要+域内最終需要)と輸出は、当該国の対米ドルレートでもって換算した。これは、タテ(列)方向で言うと、各国・地域の輸入を輸出国側の為替レートで換算したことを意味している。
また、この分析では、為替レート変化が及ぼした影響のみを計測するため、4か国・地域とも1部門から成るものと見なし、4部門に統合した世界表を作成している。
(注)実際90年為替レート換算による85年表は、各国原表ベースで換算した上で、それらを連結することによって作成した。
(2) 各国・地域の生産額の増加率に見られる影響
両時点の為替レートで換算した各国・地域の名目生産額の増加率(倍)をみると、欧州は2.25倍、日本は2.07倍で2倍以上の伸びとなっているのに対し、アジアは1.75倍、米国は1.36倍の伸びである(図表12-1)。
これを為替レート変化の影響を除いた実際の生産金額(以下「85年修正生産額」)の増加率(倍)で見ると、アジアは2.03倍と伸びているのに対し、欧州は1.37倍、米国は1.36倍、日本は1.26倍の伸びであることがわかる。
これからわかるように、日本及び欧州ではともに為替レートの変化はプラスに寄与し、名目の生産額の伸びを大きくし、しかも、その寄与は修正生産額でみた増加寄与よりも大きい。これに対して、アジアでの為替レートの変化はむしろマイナスに寄与し、名目の生産額の伸び率を引き下げていることがわかる。
また、日本と欧州ではともに為替レートの変化の及ぼした影響は大きいが、為替レート変化の影響を除去すると日本の生産金額の伸び率は、欧州よりも小さかったことがわかる。
| 両年の為替レートで評価した場合(A) | 為替レートの変化の影響を除いた場合(B) | 為替レートの変化の影響 (A)/(B) | |
|---|---|---|---|
| 日本 | 2.07 | 1.260 | 1.64 |
| 米国 | 1.36 | 1.36 | 1.00 |
| 欧州 | 2.25 | 1.37 | 1.64 |
| アジア | 1.75 | 2.03 | 0.86 |
(注)米ドルの変化を基準に見ているため、米国の伸びは同率、いわゆる為替レート変化の影響はないものとみなしている。
(3) 各国・地域の投入構造変化への影響
為替レート変化の影響は、各国の交易部門を通じて各国・地域の投入係数の変化にどのように表れているか見てみよう(図表12-5,6)。
85年の為替変化の影響を除いたいわゆる各国通貨ベースによる実際的な投入係数(以下「85年修正投入係数」)と90年の投入係数の変化は輸入部門と付加価値部門に表れている。
- 日本
まず、日本について85年修正投入係数と90年投入係数による変化をみると、日本産品の投入係数は1.67ポイント低下し、代わって輸入品の投入係数が0.98ポイント上昇する、いわゆる輸入代替が見られ、これによって付加価値率が0.69ポイント上昇していることがわかる。
これを両年の名目表でみると、円高は輸入品の投入価格を低下させ、付加価値化を2.87ポイント上昇させたことがわかる。
- 米国
米国について同様に修正投入係数ベースの変化をみると、米国産品の投入係数が1.91ポイントと日本及び欧州からの輸入品の投入係数がそれぞれ0.32ポイント、0.19ポイント低下し、付加価値率が1.99ポイント上昇している。しかし、両年の名目値でみると、日本円及び欧州通貨の高騰により、これら両地域からの輸入品価格は相対的に上昇し、付加価値率は1.49ポイント上昇し、その効果は幾分相殺されたことがわかる。
- 欧州
欧州についても同様に修正投入係数ベースの変化をみると、日本・米国とは違って欧州産品及び輸入品の投入係数がともに上昇し、付加価値率が2.27ポイント低下している。しかし、両年の名目表でみると、為替レートの変化は米国及びその他世界からの輸入品の価格を低下させ、付加価値率は0.88ポイント上昇していることがわかる。
- アジア
アジアについても修正投入係数ベースの変化をみると、アジア地域産品の投入係数は上昇し、替わって日本及び欧州からの輸入品の投入係数が低下し、その結果付加価値率は0.60ポイント上昇している。これは、当該地域の経済成長を背景に工業化が進み、その中でアジア地域内での相互依存関係が深まり、アジア地域産品の投入係数が上昇したものといえる。
しかし、両年の名目表でみると、円高により、日本からの輸入品の投入係数は上昇し、米国及び欧州からの輸入品の投入係数も上昇し、付加価値率を1.88ポイント低下させた唯一地域であることがわかる。
このように各国・地域の経済は、相互依存関係を深める中で、各国の為替レートの変化は、日本、米国、欧州のように付加価値率を引き上げる方向に作用したところと、むしろ逆にアジアのように付加価値率を引き下げる方向に作用したところとがあったことがわかった。
(4) 各国・地域の域内需要構造変化への影響
次に、為替レートの変化が、各国・地域の域内最終需要(消費+投資)に及ぼした影響について、(3)と同様に見てみよう。
85年の為替変化の影響を除いたいわゆる各国通貨ベースによる実際的な投入係数(以下「85年修正投入係数」)と90年の投入係数の変化は輸入部門と付加価値部門に表れている。
- 日本
まず、日本について85年修正表と90年表によって最終需要に占める国産品と輸入品の需要割合の変化をみると(図表12-6)、日本産品の割合は1.94ポイント低下し、輸入品の割合が上昇する、いわゆる輸入代替が中間需要(投入)と同様にみられる。この変化は両年の名目表でみても変わらない。このように国内最終需要に占める輸入品の割合が高まっているということは、日本でもって1単位の最終需要が増加した場合、輸入相手国の生産を誘発する度合いが高まり、逆に、国内生産を誘発する度合いがそれだけ低下していることを意味している。
- 米国
米国についても85年修正表と90年表によって最終需要に占める米国産品と輸入品の需要割合の変化をみると、日本及び欧州からの輸入品の割合が低下し、米国産品とアジア地域からの輸入品の割合が上昇している。しかし、両年の名目表でみると、アジア通貨の対米ドルレートの低下により、アジア地域からの輸入品の割合は上昇し、米国産品と日欧からの輸入品の割合が低下している。このように米国とアジアの関係では、米国の最終需要におけるアジアの割合が上昇する中で、アジア通貨の対米レートの変化は、そのウェイトを高める方向に作用したことがわかる。
- 欧州
欧州についても85年修正表と90年表によって最終需要に占める実際的な欧州産品と輸入品の需要割合をみると、欧州産品の割合は3.32ポイント低下し、輸入品の割合が上昇している。この変化は両年の名目表でみても変わらない。
- アジア
アジアについても同様に85年修正表と90年表によって最終需要に占める実際的な国産品と輸入品の需要割合をみると、中間需要と同様に同地域においてアジア地域産品に対する需要割合が2.01ポイント上昇し、日本、欧州からの輸入品の割合は低下している。しかし、両年の名目表でみると、為替レートの変化により、むしろアジア地域産品の割合は1.24ポイント低下し、輸入品の割合が上昇していることがわかる。
このように各国・地域の域内最終需要においても為替変化の影響が表れており、特にアジア経済と米国経済に顕著に表れていることがわかる。