

- 統計

- 国際産業連関表

- 集計結果又は推計結果

- 統計表一覧

- 1990年日・米・EU・アジア多国間国際産業連関表
国際産業連関表
1990年日・米・EU・アジア多国間国際産業連関表
4-1. 米国は消費依存型、日本は投資依存型、そして欧州、アジアは外需依存型の生産構造をそれぞれ持っている。
各国・地域別の国内生産額がどのような最終需要によって誘発されているのかを各国・地域ごとに比較する。
まず、日本、米国、欧州、アジアの内需依存度を比較すると(図表4)、米国が90.8%(85年は93.0%)と最も高く、次いで日本の88.6%(85年は85.1%)、欧州の79.5%(85年は77.2%)となっており、アジアは75.1%(85年は79.7%)と最も低い。
内需依存度の内訳である消費依存度をみると、米国は61.4%と最も高く、消費依存型の生産構造になっていることがわかる。他方、その他の内需(主に投資)をみると、日本が39.9%と最も高く、その内訳として最もウェイトの高いのが投資であることを勘案すると、日本は他の3か国・地域と比べ投資依存型の生産構造であるといえる。
次に、生産誘発依存度の合計100%から内需依存度を差し引いたものが外需依存度である。この外需依存度はアジア(24.9%)、欧州(20.5%)が2割を超えている。特に欧州の外需依存度が高いのは世界表の対象地域(日米ア)以外の国への輸出による海外需要依存度が17.2%と高く、これはEU域内における英・仏・独以外の国々との貿易取引量の多さに起因していると考えられる。
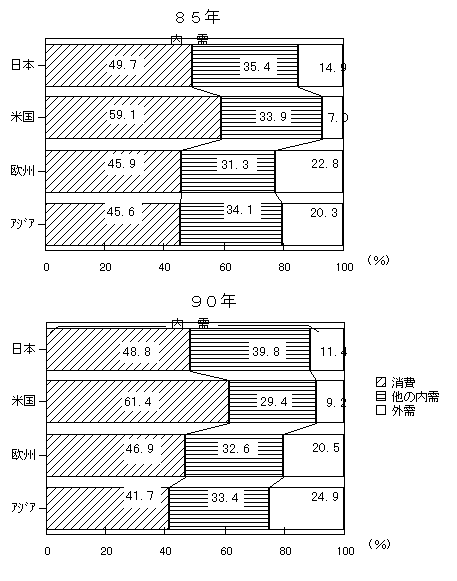
4-2. 日本に対する相手国の依存度はいずれも上昇している。逆に、日本の対欧州依存度は上昇しているものの、対米国及び対アジアへの依存度は低下。
各国の生産活動は自国の最終需要だけでなく他の3か国・地域の最終需要によっても誘発される。そこで、いま、相手国の最終需要によって誘発された国内生産額が、自国の生産額全体に占める割合を、各国の相手国に対する依存度(相互依存度)と呼ぶ。
この相互依存度をまず、日本と米欧ア各3か国・地域の間で比較してみると(図表5)、日米間では、日本の対米依存度は3.33%(85年は同5.30%)であるのに対して、米国の対日依存度は0.89%(同0.61%)、日欧間では、日本の対欧依存度は1.41%(同1.07%)であるのに対して、欧州の対日依存度は0.64%(同0.37%)、日ア間では、日本の対ア依存度は2.21%(同2.49%)であるのに対して、アジアの対日依存度は4.02%(同3.13%)となっている。
これを85年と比較すると、日本に対する相手国の依存度はいずれも上昇している。しかし逆にみると、日本の対欧州依存度は上昇しているが、対米国及び対アジアへの依存度は低下していることがわかる。
また、85年から90年の間で日本と相手国の相互依存関係の変化の方向をみると、日米間ではその水準が近づく方向に、日欧間では双方ともより依存関係を深める方向に、そして日ア間ではその水準が乖離する方向にそれぞれ変化していることが読みとれる。
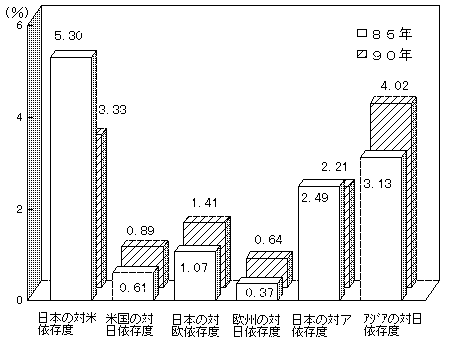
日本生産の対米依存度=(日本生産額のうち、米国の最終需要によって誘発された分/日本の生産額)×100
米国生産の対日依存度=(米国生産額のうち、日本の最終需要によって誘発された分/米国の生産額)×100
