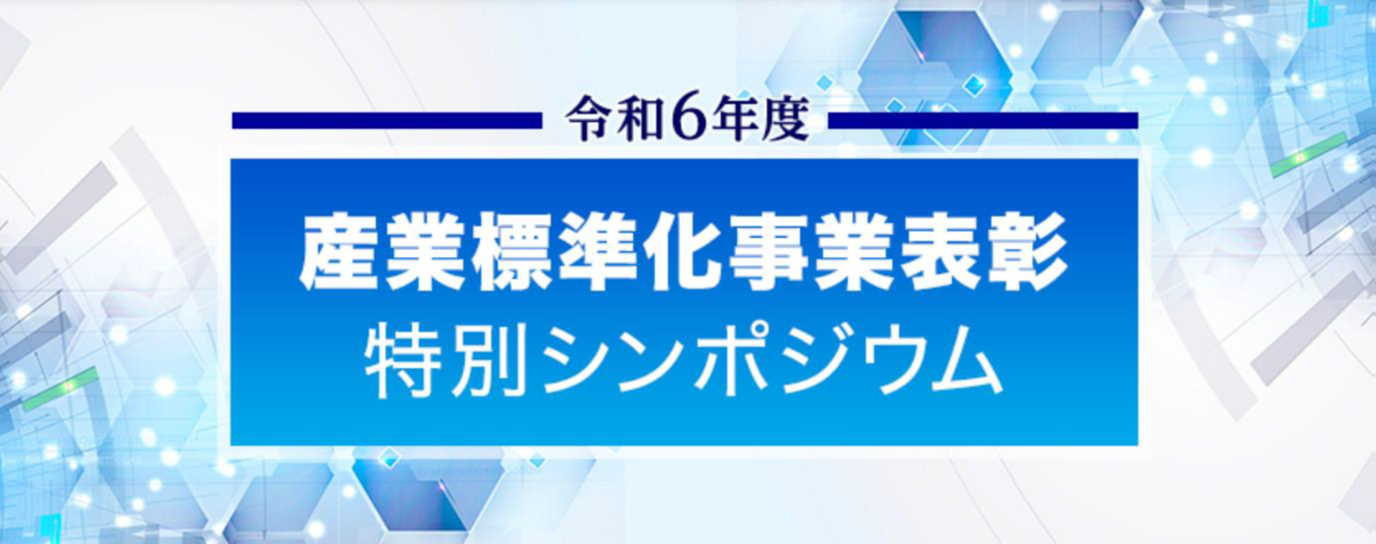
2024年10月8日(火)14:30-17:25 都市センターホテル コスモスホールにて開催。ライブ配信も同時実施。
特別講演1.「つながる時代の標準化対応」~安全・安心・便利なくらしを支えるアーキテクチャ構築をめざして~
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 齊藤 裕 氏
データとデジタルの力による変革を推進し、デジタルトランスフォーメーション(DX)のイネーブラーとして豊かな暮らしの実現を目指す、IPAの取り組みについて御紹介を頂いた後、次の点についてのお話を頂きました。
○「今、進みつつあるパラダイムシフト」
動力源やテクノロジーの進歩により、社会や産業は変化を続けている。デジタル技術とデータの活用で意思決定の時間が短縮され、AIによるシステムの自律化が行われる「デジタル革命の時代」となった今、企業のビジネスモデルも大きく変化している。
(続きはクリック)
所有と大量消費を前提に、競争で一者での大量生産を行っていた「モノ」の時代を経て、人や自然を大切に、つながり・コラボレーション・共創による価値提供を目指す「コト」の時代に移り、経営資源として投下できる「ヒト・モノ・カネ」の量から、「ヒト・マシン・
データ」により生み出す価値へと企業の差別化要因も様変わりした。その新たな戦略資源を共通化して共有し、全体最適を実現する共通
基盤としてのデジタルエコシステム構築で競争優位を確立したのがGAMA[旧GAFA]Mなどのメガプラットフォーマーであり、こ
のビジネスモデルはデジタル時代におけるオープン&クローズ戦略の体現でもある。 一例として、Appleはアプリ開発環境をエコシステ
ムのオープン領域として標準化し、世界中の企業を参画させ、より多くのユーザーへの価値提供を可能にして市場拡大する一方、クロー
ズ領域となるコア技術やデザインについては知財権を駆使して独占する、というビジネスモデルで高い収益を上げている。
○グローバル市場を席捲するメガプラットフォーマーに対抗する欧州の動き
①欧州では、データの単一市場である「欧州データ空間」の構築、およびEU圏企業のデータ共有と産業データ活用推進を目的に、サイバ
ー空間の標準化、すなわち欧州主導でのデジタルエコシステム構築を目指し、つながる相手との相互運用を可能とするアーキテクチャ
の設計・実装[民側での対応]と、他国との相互認証を可能とする標準化[主に官側での対応]を進めている。
【欧州での取り組みや事例】(詳細はクリック)
「データガバナンス法」「デジタルマーケット法」「デジタルサービス法」「データ法」の4つの法規制でEU圏企業のデータ連携とユーザー保護のための環境を整備。
データ占有で競争優位に立とうとする米中メガプラットフォーマーへの対抗軸としてのデータエコシステム構築を目指す取組みも:
Catena-X(欧州自動車産業での取り組み)→ Manufacturing-X(ドイツ製造業全体での取り組み)
②Gaia-Xなどのデータ連携基盤構築において、欧州は、スマートコントラクト(詳細はクリック)
データスペースの概念そのものの、メンバーがインセンティブとデータを共有する自立分散型組織(DAO)としての非中央集権的な連邦型による運用をおこない、データをどうマネージするかを標準化して透明性を保ち、 「上からの指示」ではなくプログラム化された「契約」である③一方G7は、法的枠組みだけで信頼性を担保できないデータの世界でのトラストをデジタル技術による物理的な標準化で担保すること
で、域内でのデータ連携基盤構築を進めながらも個人データの保護や信頼性の確保を重視する欧州とも協調し、国境を越えての「信頼性
のある自由なデータ流通[DFFT: Data Free Flow with Trust]」を実現することをめざす。【DFFTの事例】はクリック
デジタルプロダクトパスポート(DPP)→法制による義務化が進む欧州バッテリーパスポートへの対応が必要に
○「デジタルな標準化」を実現するための日本におけるアーキテクチャ設計
DFFTを国際的に強く推奨している日本でも、欧州のデジタル戦略と米メガプラットフォーマーモデルに倣い、全体最適を実現するため
のデータ連携とエコシステムの標準化(=アーキテクチャ設計)の取り組みを、産学官協働で進めている。
具体的には、System of Systemsのコンセプトにより連携を通じて一者が提供する以上の価値を創出し、産業界全体のDXを可能にする
日本型デジタルエコシステムとしてのOuranos Ecosystem(ウラノス・エコシステム)構築、および人流クライシス・物流クライシ
ス・災害激甚化という社会課題の解決をデジタル技術による国内インフラ強靭化で実現するデジタルライフラインの全国整備計画であ
る。
特別講演2.「IECでの活動について-MSB活動を中心に-」~令和6年度 内閣総理大臣表彰受賞者講演 ~
三菱電機株式会社 特任技術顧問 堤 和彦 氏
IECの概要説明、2024年12月まで議長を務められていたMSB(Market strategy Board)での活動について、そして、日本の産業界、標準化界への期待についてのお話を頂きました。
MSBは、IEC内部のシンクタンクとして、白書活動をメインとしつつ、活動の幅を広げている。発行する白書(年1回発行)は、
(続きはクリック)
IECがこれからどうあるべきを諮問する文書で、MSBの最重要成果物。メンバーは、所属する国の産業界のCTO若しくはCTO経験者で、技術及び市場を調査し、技術及び市場のトレンド領域をまとめている。
【堤氏が主導した次の2件の白書活動】 (詳細はクリック)
「Safety in the Future」(2020)-日本発の新しい「安全」の概念として世界に発信中の「Safety 2.0」の国際規格提案を行うための「地均し活動」として、ロボット
と人間の協調・協働の実現のために必要な安全規格の在り方についてとりまとめた。現在、IECでは、協調安全についてのガイドラ
インを作り始めている。
「Power semiconductors for an energy-wise society」(2023)
-電化社会を支える主要な電子部品であり、日本がまだ比較優位の立場にある“パワー半導体”について、パワー半導体の生産者側が規
格作りに参加することを目指し、“energy-wise society(パワー半導体が作り出すエネルギーを賢く使う社会)“という概念を提
案・アピールし、認知度を高め、専門家や関係者の幅広い知見を集めたパワー半導体規格開発に関するガイドライン/ロードマップが
必要性を訴えた。
○日本の産業界、標準化界への期待
・日本企業(製造業)が存続するためには、世界に通用する製品の継続的開発と持続的成長が必須。イノベーションにより始まりつつある
パラダイムシフトにのった形で優位に開発していく必要がある。
・規格も、製品個々の観点から製品が連携・システム制御する観点からの規格へ
・「ビジネスモデル」を作って世界中に早く普及することが必要。標準は、そのためのツールの1つ。(続きはクリック)
・欧米は、IEC、ISOのデジュール標準策定の議論をおこしながら、グローバルにビジネスモデルを早く普及させるために、ビジネスケース・ユースケースを踏まえた「デファクト(事実上の標準)」策定を行い、「ビジネスで勝つ標準化戦略」を推進している。
・大きな社会課題の解決という大義を掲げて、トップダウン的な規格開発の方向性を作り出していくこと、解決の実現に必要な規格開発
全体像を俯瞰する視点が必要。
・IEC/MSBへの積極的なコミットメントをお願いしたい。
・国際標準化団体は「慈善活動」しているわけではない。標準化団体の動向は他国、他社のビジネス上の思惑が反映されているという認
識をさらにしっかりと持って頂く必要がある。
特別講演2「IECでの活動について-MSB活動を中心に-」(アーカイブ動画)
経済産業省からの報告.「標準化とアカデミアとの連携について」
経済産業省 イノベーション・環境局 基準認証政策課長 有馬 伸明
アカデミアとの連携にフォーカスして、日本の標準化活動の現状と現在の政府の取組について、経済産業省から以下を報告し、戦略的標準化の更なる活用拡大に向けては、『産学官で連携した更なる取組が必要』という旨の投げかけを致しました。
○これまでの市場決定要因(価格×品質)に、市場創出要因として新たな価値軸(グリーン、デジタル、人権等)が加わり、従来からの品質確保を中心とした標準化活動(基盤的活動)に加え、経営戦略と一体となった標準化活動(戦略的活動)をこれまで以上の拡大が必要。日本の標準化活動には、①人材の確保が困難、②企業の経営戦略における位置付けの低さ、③研究開発段階からの標準化が不十分という3つの課題があることから、次の取組に、引き続き取り組む。取組の詳細はクリック
・人材の確保については、基盤的活動を維持するための人材も高齢化しており、若手も含めて人材の確保が急務。また、戦略的活動を担
う人材については、基盤的活動とは適性の異なる新たな人材層の検討から育成、さらには外部人材の利用による確保が必要。これをう
け、2024年6月「規格開発・交渉人材」の情報を検索できるデータベース標準化人材情報Directory (STANDirectory)」を公開。ま
た、8月下旬に「知財・標準化一体サポート人材(弁理士)」の情報を検索できる機能を追加。今後も、戦略人材、活用・普及人材、
アカデミア人材の情報の追加や機能拡充を図る。
・「標準化とアカデミアとの連携についての検討会」を立ち上げ、2024年4月に中間とりまとめを公表。学会連携に向けた課題につい
て、標準化活動は学術評価の対象となっていない等の現状を整理。また、学会等へ連携の働きかけや人材教育プログラムの開発・実
施。
・企業と大学等が共同で実施する研究開発について、標準化と知的財産を一体的に活用する戦略(オープン&クローズ戦略)の策定・活
用を促進するための計画認定制度を創設(令和6年産業競争力強化法改正)。2024年10月2日までに計9件を認定済。認定をうけた
者には、予算措置やNEDO、INPITからの助言などの支援措置を実施。また、政府が予算措置をしている研究開発プロジェクトでは 社会実装をプロジェクトの条件としており、GI基金という基金では、社会実装の重要なツールの1つである標準化の取組についてヒア
リングをし、研究開発段階から標準化について取りくんでいただくという取組を実施。
経済産業省からの報告「標準化とアカデミアとの連携について」(アーカイブ動画)
パネルディスカッション「標準化関係者とアカデミアとの産学サミット・ミーティング」
パネリスト :一般社団法人電気学会 会長 伏見 信也氏
サービス学会 会長 持丸 正明氏
株式会社島津製作所 専務執行役員 稲垣 史則氏
モデレーター:特定非営利活動法人横断型基幹科学技術研究団体連合 会長 椿 広計氏

経済産業省の「標準化とアカデミアとの連携についての検討会」の座長であり、標準化の専門家でもある横断型基幹科学技術研究団体連合 会長の椿様から、
背景や問題意識(詳細はクリック)
・国内外の標準化活動には、高度な専門的知見が必要となること、また、合意形成にファシリテータ(中立者)の役割を担う者が必要であること等から、昔からアカデミアの
方々が参画されており、国内委員会の委員長やISO、IEC等の国際委員会の委員長のポストについても、日本の場合は、これまでアカデミ
アの方々に担って頂いている。
・しかし、昨今ISO、IECで、AIや量子等の先端技術、経営と技術を統合したマネジメントシステムなど分野横断的な技術あるいは経営に
関する技術について、国際標準化テーマが欧州を中心に非常に多くの提案されており、これらのテーマに日本が主導的かつ積極的に関与
する観点から、企業の集合体である工業会だけでなく、アカデミア、国研、産業界も参加している「学会」が、標準化活動に積極的な参
加し、サポートするということが極めて重要となってきている。
・広義の標準化活動は、ISO、IEC、JISの原案の検討の場だけではなく、フォーラム等の民間規格も含み、「研究開発段階でのデータ収集
分析」、「知財か?標準化か?といったオープン&クローズ戦略的な分析」といったプロセスも包含するもの。
・これらプロセスを包含して、国際的に戦略的な標準化活動を行うには、学会をプラットフォームとしたアカデミアと産業界の戦略的な連
携活動が重要ではないか。また、その上で、連携や活動の主体となる人材の育成も喫緊の課題。
をご提示を頂き、
「学会での全体活動における標準化の位置づけ、その位置づけのなかで、アカデミアと産業界の役割分担は、どうあるべきか。」
に関し、パネリストの方々から、次の①から③の点について、各々の御所属(国内審議団体を引き受けられる規模の学会、会員が約500名位の規模の学会、企業)の立場の観点から御意見を頂くとともに、産学連携の新たな場としての国内学会の体制強化、学会間の連携の場の構築について、御議論頂きました。
議題1 学会における学術活動(研究)について(各学会がどういう活動をしているか?)、標準化活動との関係、標準化活動におけるア
カデミア企業との連携について
議題2 戦略的な人材の育成について、
議題3 学会をプラットフォームとしたアカデミアと産業界との連携を強化するための具体的な取組
【パネルディスカッション前半(アーカイブ動画)】
○自己照会及び各御所属の御紹介、
○議題1「学会における全体的な活動と標準化活動との関係、標準化活動にかかるアカデミア、企業の役割分担について」
○議題2「戦略的な人材育成について」、
○議題3「学会をプラットフォームとしたアカデミアと産業界との連携を強化するための具体的な方策について」、
○まとめ
【参考リンク】
- 経済産業省HP「標準化とアカデミアとの連携に関する検討会」
- 経済産業省HP「特定新需要開拓事業活動計画認定制度」
- 経済産業省HP「日本産業標準調査会基本政策部会「取りまとめ」(日本型標準加速化モデル)を公表しました。」
- 経済産業省HP「産業標準化推進月間」(※過去に行ったシンポジウム等については、こちらから)
- 経済産業省HP「表彰制度」(※令和6年度産業標準化事業表彰については、こちらから)
お問合せ先
- 産業標準化事業表彰 特別シンポジウムについて
-
イノベーション・環境局 基準認証政策課 基準認証調査広報室
電話:03-3501-1511(内線3421~3422) メール:bzl-kijun-Koho★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。
最終更新日:2025年4月21日