CONTENTS
1.諸外国における貿易救済措置の発動状況
2.日本のアンチダンピング調査事例『中華人民共和国産黒鉛電極に対する不当廉売関税の課税に関する調査開始』
3.各国の貿易政策の状況
①米国商務省がAD/CVD課税の運用を通じた貿易救済措置の執行の改善及び強化に関する最終的な規則を公表
②欧州委員会が中国における市場歪曲に関する報告書を更新
③WTOでAD委員会 会合 開催 ―2023年7月~12月期―
4.「ADの調査対象となった場合の対応」シリーズ ~第Ⅹ回 各種レビューについて~
5.貿易救済に関する論文の公表
6.相談窓口
7.FAQ
1.諸外国における貿易救済措置の発動状況
2024年3月~4月の諸外国における貿易救済措置の発動状況をお伝えします。実施状況詳細
アンチダンピング(AD)
2024年3月~4月は、以下の調査が開始されました。
補助金相殺関税(CVD)
2024年3月~4月は、以下の調査が開始されました。
2.日本のアンチダンピング調査事例
『中華人民共和国産黒鉛電極に対する不当廉売関税の課税に関する調査開始』
経済産業省及び財務省は、令和6年2月26日にSECカーボン株式会社、東海カーボン株式会社及び日本カーボン株式会社から財務大臣に提出された中華人民共和国産黒鉛電極に対する不当廉売関税の課税申請について、関係法令に基づき検討を行った結果、不当廉売関税の課税の要否に関する調査を行う必要があると認められたことから、令和6年4月24日に両省合同の調査を開始しました。▷黒鉛電極に関する調査の詳細はこちら
3.各国の貿易政策の状況
①米国商務省がAD/CVD課税の運用を通じた貿易救済措置の執行の改善及び強化に関する最終的な規則を公表
米国商務省は、1930年関税法に基づき、アンチダンピング関税及び相殺関税措置(AD/CVD) の執行及び管理を強化、改善するための最終的な規則を公表1 しました。当該改正は、2023年5月9日に米国商務省が提案した改正案2に対して寄せられた外部からの意見に一部対応するとともに、いくつかの技術的問題に対処するため改正案を修正し、最終的な改正規則に反映させたものとなっています。
改正規則では、不公正な貿易に適切に対処するために、国境を越えた補助金の相殺を禁止している現行規制である、第351.527条を廃止しています(ただし、将来的に状況が変化した際のために、留保することとしています。)。
また、特定の市場状況 (PMS:particular market situations)における相殺可能な補助金に関する規定として第351.416条を追加しています。同条においては、コストの歪みをもたらす可能性のあるPMSとして、12の状況が例示として示されています。当該例示のなかには、調査対象国の政府等が、財産 (知的財産を含む)、人権、労働、または環境保護に関する法律および政策を実施していないか、又は不十分であることがコストの歪みの原因となっている場合も含まれています。
そのほか、新たに追加した第351.529条において、政府の不作為が生産者または輸出者に利益をもたらす場合、具体的には、本来納付すべき手数料、罰金又は課徴金が放棄されたか又は徴収されない場合において、政府が当該手数料等の一部又は全部を免除したとして、金銭的貢献が存在するとみなすことを明文化したほか、いくつかの分野における手続や実務面の改訂及び明確化を実施しています。
当該改正は2024年3月25日に公表され、同年4月24日に発効しています。
1.https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-03-25/pdf/2024-05509.pd
2.https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-05-09/pdf/2023-09052.pdf
②欧州委員会が中国における市場歪曲に関する報告書を更新
2024年4月10日、欧州委員会は、「中国経済における市場歪曲に関する報告書」の最新版を公表3しました。本報告書は、2017年に公表されたものを更新したもので、最近の中国の法律、産業政策その他の動向を反映したものです。これにより、EUの産業界がダンピング輸入に関する申立てを行う際に、中国経済や市場の状況及び特定の産業分野に関する最新の情報を利用できるようになるとしています。当該報告書は、以下の点に焦点を当てています。
● 分野横断的な歪曲:資源配分、経済目標の特定における国家の役割、計画経済、国有企業の重要性に関する事項
● 生産要素の歪曲:土地、労働力、原材料、エネルギーなどの、資源の差別的配分やアクセスに関する事項
● 特定産業分野の歪曲:金融への優先的アクセスなど、国家による特定の産業分野への支援に関する事項
このうち、特定産業分野の歪曲に関して、2017年の報告書では「鉄鋼」、「アルミニウム」、「化学」及び「セラミック」の分野について言及していましたが、今回の報告書では、これらに加え「電気通信機器」、「半導体」、「鉄道」、「環境(再生可能エネルギー)」及び「新エネルギー車(NEV)」の分野について言及しています。
欧州委員会は、報告書自体、または報告書に特定の産業分野が含まれることをもって自動的に特定のダンピング率の算出方法が適用されることは無く、調査の過程で、報告書を含む利用可能なすべての証拠に基づいて、特定のセクターにおける中国の価格及びコストが歪められていることが判明した場合は、市場条件の歪みが無い第三国の価格とコストに置き換えて最終的なダンピング率を計算するものであり、利用可能な証拠に基づきケースバイケースで行われるとしています。
③WTOでAD委員会 会合 開催 ―2023年7月~12月期―
半年に一度開催されるWTOのAD委員会が2024年4月24日に開催されました4。AD委員会では、新規や改正等をしたAD法規に関する加盟国からの届出と、AD措置に関する報告を審議5しました。この会合には、日本からも特殊関税等調査室等が参加しました。会合では、2023年7月1日から12月31日までの期間を対象とする半期報告に関して、41の加盟国がこの期間に実施したAD措置を委員会に報告し、14の加盟国は同期間に新たなAD措置はなかったことを報告しました。さらに、52の加盟国は調査を実施する権限のある当局を設置しておらず、現在までAD措置を講じていない旨の報告を行いました。
議長は、措置に関する報告書を提出していない加盟国に対し、速やかに提出するよう促しました。また議長は、半期報告書を提出するにあたり、加盟国が貿易救済措置ポータルサイト6を利用していることを歓迎しました。
半期報告書に加え、WTOのAD協定は、加盟国に対し、すべての暫定措置及び確定措置について、アドホックベースで遅滞なく提出することを求めています。今回の会議では、20カ国以上からアドホック通知を受けました。
ロシアは、「AD調査における非市場経済の取扱い」と題する議題を提起しました。
次回のAD委員会の会合は、2024年10月28日の週に開催される予定です。
半期報告書に加え、WTOのAD協定は、加盟国に対し、すべての暫定措置及び確定措置について、アドホックベースで遅滞なく提出することを求めています。今回の会議では、20カ国以上からアドホック通知を受けました。
ロシアは、「AD調査における非市場経済の取扱い」と題する議題を提起しました。
次回のAD委員会の会合は、2024年10月28日の週に開催される予定です。
4. https://www.wto.org/english/news_e/news24_e/anti_25apr24_e.htm
5.委員会では通常、調査の開始、暫定的及び最終的なAD措置の適用、既存のAD措置の見直しを含めたAD措置に関する半期報告における加盟国の実施状況について審議を行います
6.貿易救済措置ポータルサイト https://trade-remedies.wto.org/en
4.「ADの調査対象となった場合の対応」シリーズ
~第Ⅹ回 各種レビューについて~
前回(第Ⅸ回)までで、調査開始前から最終決定、そして各種紛争解決の活用にいたるまで、AD調査手続の対応を時系列に沿ってご説明しました。今回はAD調査に関する最終回で、AD課税後に対象企業が直面する各種レビュー(見直し)手続について解説します。AD課税後のレビュー手続にはいくつかの種類があり、また国ごとに制度にもバリエーションがあるため、対象企業にとっては混乱を招きやすいものです。
Ⅹ.1行政レビュー(administrative review)
これは米国特有の手続で、AD税率を将来のダンピング・マージンの予測に基づいて賦課し、実際の取引履歴に基づいて最終税額を決めるという米国の制度に由来するものです。米国固有の問題とはいえ、米国の対日AD は2023年6月時点で21件あり、中国(22件)に次いで多い数です。いずれにせよ日本企業が直面する可能性の高い問題ということになりますので、この機会に概要をご紹介します。米国のAD税率の算定・賦課は、直近の調査期間のダンピング・マージンを反映して行われますが、あくまで将来のダンピング・マージンの予測に基づく仮の決定であって、課税期間中に対象業者が日々の取引について支払うAD税は、暫時預託される扱いになっています。そして、一定期間経過後に輸入実績を元に実際のダンピング・マージンが確定された後、遡及的にAD税率が確定されます。ある期間に預託されたAD税が、同期間について確定されたダンピング・マージンよりも多かった場合、差額は還付されます。逆に、預託されたAD税が同期間の実際のダンピング・マージンよりも少なかった場合、差額は追徴課税されます。このような実務をとる場合は、かかる最終的AD税額の確定及び還付の決定は、通常、利害関係者の要請から1年以内に行わなければなりません(AD協定9.3.1条)。
上記の事情のもと、AD課税開始後、直近1年間のAD税率の最終確定・還付・追徴と、向こう1年間のAD預託税率の決定のために行われるのが米国の行政レビュー(administrative review)です。課税開始から1年ごとに、利害関係者の申請に基づいて開始されます。その制度目的は上記の通りダンピング・マージンの確定であり、直近1年間の輸入実績に基づいて還付・追徴額が確定され(※実際の還付・追徴は利息を付して行います。)、次の1年間の預託額も算定されます。なお、仮にダンピング・マージンがゼロと算定されれば、翌1年間の預託額もゼロとなり、一時的にAD税の金銭的負担はなくなります。他方、損害・因果関係等他のAD課税要件の充足性についてここで争うことはできません(長期間ダンピングが行われていない場合にAD税の撤廃を求めることができる旨の規定もありますが、その適用は極めて例外的です。)。
行政レビューに参加した場合には、ダンピング・マージンの再計算に必要なデータ提出が求められるため、その対応にはそれなりのコストがかかります。ただし、元の調査におけるダンピング・マージンの計算方法が不当であると感じる場合などは、この種のレビュー対応で意見を提出することにより、AD税率を当初よりも引き下げることができる可能性もあります。他方、行政レビューに対応しない選択も可能ですが、その場合には、当初調査で賦課された関税率が課され続けることになります。
Ⅹ.2 期中レビュー(事情変更レビュー)
2つ目は、期中レビュー(事情変更レビュー)(AD協定11.2条)です。AD措置は、「損害を与えているダンピングに対処するために必要な期間及び限度においてのみ」(AD協定11.1条)発動可能とされていますが、いわばADの発動を「必要な期間及び限度」にとどめるための事後的なチェックのための制度です。
Ⅹ.2.1 一般的規律
期中レビュー(AD協定11.2条)は、AD課税期間中、調査当局がAD税の「賦課を継続することの必要性」につき見直しを行う手続です。同11.2条によれば、調査当局の職権により、又は、「見直しの必要性を裏付ける実証的な情報」を提供する利害関係者の要請により開始されます。利害関係者は、AD税の賦課継続が「ダンピングを相殺するために必要であるかないか」、AD税の早期撤廃・税率変更により「損害が存続し又は再発する可能性があるかないか」、(あるいはこれらの双方)について検討を要請できます。調査期間は、通常、12ヶ月以内で(AD協定11.4条第2文)、調査の結果、AD税を維持する正当な理由がないとされる場合は、AD税は撤廃しなければなりません(AD協定11.2条)。
Ⅹ.2.2 事情の変更(changed circumstances)
上記がAD協定上の一般的な規律ですが、実態として、調査当局が一度賦課を決定したAD課税の必要性を検討し直すというのは、AD税の税率・賦課の必要性を揺るがすような根本的な事情の変化がある場面くらいしか想定されません。また、輸出者等利害関係者としては、早期のAD課税撤廃を望むのが通常ですが、上記の通り、要請には「見直しの必要性を裏づける」証拠等が必要であり、それも多くの場合、AD課税の前提となる事情の根本的な変化を指すように思われます。このため、期中レビューは、「事情変更レビュー(changed circumstances review)」と呼ばれることもあり、その旨国内法で規定している国もあります(日本でも、関税定率法8条20項により、期中レビューは「事情の変更がある場合」に限定されています)。具体的にどのような事情が考慮され、いかなる証拠が要求されるかは調査当局次第ですが、例えば、対象輸入量が大幅に減った(対象輸出者がシェアを減らしたり、ビジネスを変更したりした等)こと、対象輸入価格が大幅に上がったこと、国内産業の状態が改善したこと、等が考えられます。しかし、上記の通り、調査当局が一度決定したAD課税を見直すインセンティブは必ずしも高くはなく、一般論として、期中見直しが開始される可能性や、見直しによりAD措置が緩和・撤廃される可能性は、いずれも低いと考えたほうがよいでしょう。
Ⅹ.3 サンセット・レビュー
Ⅹ.3.1 サンセット・レビューとは
3つ目は、サンセット・レビューです。AD課税は、一般論として「必要な期間及び限度」に限られる(AD協定11.1条)のみならず、発動後原則として5年以内に撤廃しなければならない(AD協定11.3条第1文)との規定もあります。しかし、一定の要件のもと、発動期間の延長の可否を検討するためのレビューを行うことができ、その決定によっては、延長が可能です(AD協定11.3条第2文)。AD課税の終了を俗に「sunset(日没)」と表現するため、この延長調査は課税を終了(サンセット)するか延長するかを決めるためのレビュー、ということで、一般に「サンセット・レビュー」と呼ばれます。サンセット・レビューは、その決定内容によってはAD課税期間が延長される(その際、国によっては税率も変更されうる)という、実務的影響の大きな手続です。また、サンセット・レビューを名目とした濫用的なAD延長が散見され、国際規律の観点からも議論の多い制度です。
Ⅹ.3.2 調査開始と措置の自動的な延長
サンセット・レビューは、調査当局が「自己の発意」、又は、「撤廃の日に先立つ合理的な期間内」の国内産業による要請に基づいて、「撤廃の日前に」開始されます(AD協定11.3条第2文)。なお、調査期間は、通常、12ヶ月以内ですが(AD協定11.4条第2文)、AD税は、いったんサンセット・レビューが開始されると、その結果が出るまでの間、自動的に延長されます(AD協定11.3条第3文)。つまり、AD措置の終了直前にサンセット・レビューが開始されれば、そのレビュー結果に関わらず、レビューが続く間(最大で1年)、措置は自動的に延長されることになります。国によっては、国内法でサンセット・レビューの申請期限(上記「撤廃の日に先立つ合理的な期間」)を早めに設定しているところもあります(例えば日本は「期間の末日の一年前の日まで」。関税定率法8条26項)。しかし、調査当局の「発意」すなわち職権でのレビュー開始が撤廃直前まで可能であることは変わりません。なお、米国では、サンセット・レビューは法律上自動的に開始され、最終決定から5年を経過する日の30日前までに、商務省によって公告されます。
Ⅹ.3.3 調査手続の流れ
AD協定上、証拠収集の方法等については原調査の手続規定が準用されます(AD協定11.4条第1文)。よって、例えば、サンセット・レビュー開始直後は、当初調査と同じように当局から質問状が送付されてきます。意見や反証を行う機会も与えられますので、以下で紹介する考慮要素等を踏まえて反論を準備しておきましょう。ただし、手続の詳細は各国の国内法に規定されていることから、できる限り早期に、当該国の手続を確認する(国によっては、サンセット・レビューの手続に関して、マニュアル等を公開していることがあります。)ことが重要です。例えば、米国のように、原則として、原調査に倣った360日以内の「Full review」を行うが、調査開始公告に対し回答する利害関係者が少ない場合には、「expedited review」と称する短縮した手続(公告から150日以内に完結)を実施する国もあります。
Ⅹ.3.4 延長の実体的要件と考慮要素
AD協定上のAD延長の実体要件は、AD税の撤廃が「ダンピング及び損害の存続又は再発をもたらす可能性(the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury)」(AD協定11.3条第2文)です。原調査では、ダンピング・損害・因果関係が現に存在することが要件でした(第I回参照)。しかし、このAD協定11.3条第2文の文言に照らせば、サンセット・レビューでは、「仮にAD税をレビュー終了時に撤廃した場合」という近未来の仮想事例を想定し、その場合にダンピング・損害が再発ないし存続する将来の可能性を示すことになります(日本法では、AD課税終了の場合に、損害等が「継続し、又は再発するおそれ」(関税定率法8条25項)という表現が用いられていますが、同様の意味に解されます。)。上記のような仮想事例に基づく認定をどう行うべきかは不明確であり、調査当局によっては、単なる憶測、あるいは、証拠に基づかない決めつけをもって上記存続・再発の「可能性」を認定したと称し、AD措置の延長を強行する例もしばしば見られます。この点、WTOの紛争解決先例では、仮想事例である以上、原調査のような厳密な因果関係(causal link)は要求されないものの、AD税の撤廃とダンピング・損害の再発・存続の間の何らかの結びつき(nexus)を示さなければならない、としたものがあります。日本政府もこのサンセット・レビューの規律には問題意識を持っており、韓国のサンセット・レビュー認定について、WTOに提訴したことがあります(韓国-ステンレス棒鋼(DS553))。同事件のパネル判断は、日本の主張を容れて客観的な証拠に基づく「結びつき(nexus)」の認定の重要性を強調しましたが、韓国の空(から)上訴により、未採択に終わっています。
上記の認定過程における具体的な考慮要素は事案ごとに異なりますが、各国調査当局のガイドライン等の記載を参考にすると、関連しうる事象として、下記のような点が挙げられます。
○ ダンピングの存続・再発の可能性を否定する事情
● AD課税後、ダンピング・マージンが低下したこと
● AD課税後も輸入量が不変又は増加したこと
○ 損害の存続・再発の可能性を否定する事情
● 対象輸出国における生産・輸出余力が減少したこと
● 第三国における調査対象産品に対する輸入障壁がないこと
● 他の製品の製造設備の転用可能性がないこと
● 国内同種産品を下回る価格で輸入・販売される可能性がないこと
● 国内産業の生産量、販売量、利益、市場シェア、稼働率等の低下の可能性がないこと
● キャシュフロー、在庫、故郷、賃金、成長、資本調達能力、投資に対する悪影響がないこと
Ⅹ.4 結び
今回は、AD課税後に想定されうる典型的なレビュー手続(行政レビュー/期中レビュー/サンセット・レビュー)についてご説明しました。もちろん、課税開始後に起こりうる手続はこれだけではありません。例えば、調査期間後に対象産品の輸出を始める業者について新たにダンピング・マージンを個別に決定するための追加調査(new shipper review)(AD協定9.5条)や、対象企業の迂回(circumvention)行動(対象産品を課税範囲から形式的に外す(生産拠点を他国に移す、微少な加工を加える、等)ことでAD課税を回避しようとすること)に対処するための反迂回調査(anti-circumvention investigation)等があります。具体的な手続も調査当局によって多様であり、中には、AD協定等、国際協定との整合性に疑問があるものも散見されます。不透明な調査に直面した場合、早急に詳細を現地法の弁護士に問い合わせる等の対応が重要なのはもちろんですが、国際協定との関係や、調査当局への問合せ、政府意見書の提出の可能性については経産省もご相談に応じます。次回は、これまでご説明してきたADに関する知見を前提に、類似の貿易救済制度である補助金相殺関税措置、セーフガード(緊急関税)措置、についてご説明します。
【今回のポイント】
○ 行政レビューは、米国独自の手続で、1年ごとに直近の輸出実績を元にダンピング・マージンが計算し直される。
○ 期中レビューは、事情変更に基づくAD課税の修正・終了を求めるもの。
○ サンセット・レビューは、AD課税の延長の可否を決める調査。実体要件が不明確であり、曖昧な理由による延長も多い。
5.貿易救済に関する論文の公表
貿易救済に関し、経済産業省職員による英語論文が下記2点公表されました。それぞれ、投稿先法律雑誌のウェブサイト上でも紹介されております(※ダウンロード・購読には当該雑誌のアカウントが必要です。また、あくまで執筆者個人の研究成果であり、経済産業省ないし日本政府の見解を代表するものではございません。① ADの累積に関する論考(Shohei Nishimura, 'Giving Meaning To Limitations', (2024), 58, Journal of World Trade, Issue 2, pp.
223-246)1
AD発動の際、「競争の状態」が「適当」であると調査当局が決定したこと等の要件を充足すれば、複数の輸出国からの輸入産品の
影響を累積的に(一括して)評価できるとされています(AD協定3.3条)。この場合、各輸出国の産品それぞれについて輸入国国内産
品への影響を認定する必要がないため、調査当局にとっては損害認定のハードルは下がり、結果として対象産品全体に対するAD課税決
定の比較的容易になると考えられます。条文文言は極めて簡潔・抽象的なため、調査当局によっては「競争の状態」を緻密に検討せ
ず、安易に累積が「適当」であると決定する例も多く、日本の輸出企業の海外AD対応においても問題となることがあります。
本稿は、AD協定3.3条の起草過程や関連先例を分析し、累積認定が妥当な範囲を識別するための「競争の状態」の解釈論について提
言するものです。
② セーフガード(SG)の因果関係規律に関する論考(Shohei Nishimura, 'Article: Analysis of the ‘Causal Link’ Requirement of WTO Safeguards: An ‘Unforeseen’ Solution to the Long Debates? [pre-publication]', (2024), 51, Legal Issues of Economic Integration, Issue 2 [pre-publication], pp. 1-30)2
WTOセーフガードの発動の際、WTO協定上、「輸入の増加と重大な損害・・・との間に因果関係が存在すること(‘the existence of the causal link between increased imports of the product concerned and serious injury or threat thereof’)」
立証しなければならない、とのの規定があります(セーフガード協定4.2条(b))。従来の解釈は、調査当局の認定内容・方法論につい
て争いがあり、また経済学的な観点からの批判も絡んでしばしば紛争の原因ともなってきました。
本稿は、簡単なミクロ経済学のモデルを活用し、従来の解釈論の問題点を指摘し、「causal link」についての新たな解釈論を提示す
るものです。
1.https://kluwerlawonline.com/journalarticle/Journal+of+World+Trade/58.1/TRAD2024019 2.https://kluwerlawonline.com/journalarticle/Legal+Issues+of+Economic+Integration/51.2%20[pre-publication]/LEIE2024006
6.相談窓口
経済産業省では、皆様からのアンチダンピング調査に関する個別相談を常時承っております。アンチダンピング措置は、海外からの不要な安値輸出を是正するためWTOルールにおいて認められた制度です。公平な国際競争環境が担保された中で、日本企業の皆様が事業活動を展開できるようにするためにも、アンチダンピングを事業戦略の一つとして捉えていただき、積極的に御活用いただきたいと考えております。申請に向けた検討をどのように進めればよいのか、複数の事業者による共同申請はどのようにすればよいのかなど、相談したい事項がございましたら、まずは気兼ねなく経済産業省特殊関税等調査室まで御連絡ください。
また、2023年7月から「ADの調査対象となった場合の対応」の連載を開始しておりますが、「日本企業がアンチダンピング調査の調査対象となった場合」の御相談は、経済産業省 国際経済紛争対策室まで御連絡ください。
経済産業省 貿易経済協力局 特殊関税等調査室
TEL:03-3501-1511(内線3256)
E-mail:bzl-qqfcbk@meti.go.jp
経済産業省 通商政策局 通商機構部 国際経済紛争対策室
TEL:03-3501-1511(内線 3056)
E-mail:bzl-wto-soudan@meti.go.jp
7.FAQ
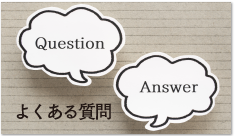
最終更新日:2025年5月30日