 |
 |
 |
 |
|
|
 |
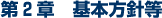 |
 |
| 2.事業者等の責務(第4条関係) |
 |
(法律)
(事業者等の責務)
第4条 工場若しくは事業場(建設工事に係るものを含む。以下同じ。)において事業を行う者及び物品の販売の事業を行う者(以下「事業者」という。)又は建設工事の発注者は、その事業又はその建設工事の発注を行うに際して原材料等の使用の合理化を行うとともに、再生資源及び再生部品を利用するよう努めなければならない。
2 事業者又は建設工事の発注者は、その事業に係る製品が長期間使用されることを促進するよう努めるとともに、その事業に係る製品が一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部若しくは一部を再生資源若しくは再生部品として利用することを促進し、又はその事業若しくはその建設工事に係る副産物の全部若しくは一部を再生資源として利用することを促進するよう努めなければならない。 |
|
| |
(趣旨)
本条においては、工場又は事業場において事業を行う者や物品販売業者、建設工事の発注者の責務を規定している。
(解説)
1.この規定では、事業者等に対して自主的努力を求めている。こうした努力を前提として、第3章以下では、さらに具体的な各種の措置を設けることにより、資源の有効な利用の促進を図ろうというものである。
2.「工場」とは、機械などを使って継続的に一定の業務として物品の製造や加工に従事する施設をいい、「事業場」とは継続的に一定の業務として物品の製造や加工以外の事業のために使用される施設をいう。いずれにおいても、そこで行われている事業活動が営利を目的としていると否とを問わない。
また、「事業場」には、建設工事に係るものを含めており、建設現場等も含まれる。
3.「建設工事に係る事業場において事業を行う者」とは、建設工事の施工者を意味しているが、建設工事において資源の有効な利用を進めるには、これら施工者のほか建設工事の発注者においても努力していくことが求められるため、「建設工事の発注者」を事業者と並べ明記したものである。
4.本条において、事業者又は建設工事の発注者の責務とされているものは、
(イ) その事業の実施やその建設工事の発注に際して原材料等の使用の合理化を行うとともに再生資源及び再生部品を利用するよう努めること
(ロ) その事業に係る製品が長期間使用されることを促進するよう努めるとともに一度使用された後等にその全部又は一部を再生資源又は再生部品として利用することを促進するよう努めること
(ハ) その事業又は建設工事に係る副産物の全部又は一部を再生資源として利用することを促進するよう努めることの3つがある。
(イ)は、直接的な効果が期待される義務である。例えば、紙製造業において古紙の原材料としての利用の拡大を図ることや複写機製造業において使用後等の駆動装置の利用の拡大を図ること、また、建設業者がコンクリートの塊等を工作物の基礎材等に利用すること、建設工事の発注者がコンクリートの塊を原料の一部として利用することを内容とする建設工事の請負契約を結ぶこと等を指している。
なお、物品の販売の事業を行う者については、再生資源を利用する可能性は比較的小さいと考えられるが、この責務は一般的努力義務であることから、販売事業者においても可能な努力を求めることとしている。
この努力を前提にして、第3章の特定省資源業種及び第4章の特定再利用業種に係る措置が設けられている。
(ロ)は、製品の長期間の使用や再生資源及び再生部品の利用の拡大を補完的に支援するものであり、具体的には、
・修理体制を充実させること
・修理のための部品を保有すること
・素材等に関して再生資源又は再生部品として利用しやすいものを選択していくこと
・分離しやすい構造への改善を図ること
・修理や再生部品としての利用を容易にするための規格化等を図ること
・分別回収のための表示を行うこと等がこれにあたる。
この努力を前提にして、第5章の指定省資源化製品に係る措置、第6章の指定再利用促進製品に係る措置が設けられている。
(ハ)は、発生する副産物の再生資源としての利用を容易にするよう努めるという義務であり、具体的には、副産物の品質の均一化を図ること等がこれにあたる。
この努力を前提にして、第9章の指定副産物に係る措置が設けられている。
(注)本条と同様の趣旨で事業者に努力を求める規定として、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第4条(エネルギー使用者の努力)、エネルギーの使用の合理化に関する法律第3条の2(エネルギー使用者の努力)が挙げられる。 |
 |
|
|
 |
| |
|
 |
|