 |
 |
 |
 |
|
|
 |
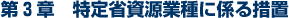 |
 |
| 2.特定省資源事業者の判断の基準となるべき事項(第10条関係) |
 |
(法律)
(特定省資源事業者の判断の基準となるべき事項)
第10条 主務大臣は、特定省資源業種に係る原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑制及び当該副産物に係る再生資源の利用を促進するため、主務省令で、副産物の発生抑制等のために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関し、工場又は事業場において特定省資源業種に属する事業を行う者(以下「特定省資源事業者」という。)の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定省資源業種に係る原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑制の状況、原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑制に関する技術水準その他の事情及び当該副産物に係る再生資源の利用の状況、再生資源の利用の促進に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3 主務大臣は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとするときは、資源の再利用の促進に係る環境の保全の観点から、環境大臣に協議しなければならない。 |
|
| |
(趣旨)
本条は、第1項で工場又は事業場において特定省資源業種に属する事業を行う者が、副産物の発生抑制等に取り組む際の目安となるべき判断の基準を主務大臣が定める旨規定し、第2項で当該判断の基準を定めるに際しての勘案事項を述べ、さらに事情の変動に応じて必要な改定をする旨規定している。また、第3項で主務大臣が当該判断の基準を定め、又は改定する場合に、環境大臣に協議するという手続を経る旨を規定している。
(解説)
1.工場又は事業場において事業を行う者は、第4条の規定(事業者の責務)により、当該事業を行うに際して、当該事業に係る原材料等の使用の合理化や副産物の全部若しくは一部を再生資源として利用することに努めなければならないこととされているが、第4条の規定は、それ自体が具体的な義務を課すものではない。一方、副産物の発生抑制等は、個々の業種ごとに努力すべき内容が大きく異なるものであるため、各業種を通じた普遍的な努力の内容を明示することは困難である。
そこで、本条では、法第2条第7項の規定に基づき政令で定める特定省資源業種に属する事業を行う者を対象に、これらの事業者の判断のよりどころとするため、どのような努力を行えばよいのかについて目安を示すこととするものである。
なお、この判断の基準は、第2項に規定するように「当該特定省資源業種に係る原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑制の状況、原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑制に関する技術水準その他の事情」及び「当該副産物に係る再生資源の利用の状況、再生資源の利用の促進に関する技術水準その他の事情」を勘案して定めることとされており、これらの事項に立脚して、主務大臣が特定省資源業種における望ましい副産物の発生抑制等とは何かを明確化するものである。
2.判断の基準と本法の他の措置との関係については、第11条の規定により主務大臣からこの判断の基準を勘案して、特定省資源事業者に対して一般的な指導及び助言が行われ、さらに第12条の規定により、主務大臣からこの判断の基準に照らして特定省資源事業者の副産物の発生抑制等の努力が著しく不十分である場合、当該特定省資源事業者に対して勧告が行われ、加えて一定の場合に、公表、命令といった措置を講ずることとしている。
この場合、判断の基準は、法的措置を実施する際の絶対的基準となるものではなく、基本的には誘導指標として総合的な判断の有力な材料となるものとして位置付けられている。このことから、判断の基準に盛り込まれる内容は、最低限遵守すべき水準のものとしてではなく、特定省資源事業者一般の漸進的な副産物の発生抑制等の努力の目安となるべき標準を示すものとなる。
また、判断の基準は、主務大臣が命令を課す場合には、命令の構成要件としての性格を帯びるものであるため主務大臣による主務省令で定めることとしている。
3.なお立法例では、事業者に対するガイドラインとして、概ね、「事業者の判断の基準となるべき事項」(エネルギーの使用の合理化に関する法律第4条)、「準則」(工場立地法第4条)、「指針」(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律5条)の3つの用法を用いている。
「準則」とは、一般的には「則るべき規則」を意味するが、工場立地法の立法例では、事業者が拠るべき明確な水準を示すものとして用いられており、同法に基づく準則では、生産施設、緑地等の敷地面積に対する比率、環境施設等の配置に関する事項について一定の明確な水準が示されている。そして、勧告等との関係においては、本則に適合している限りその事項については勧告等の規制を受けないと同時に、これに適合していない場合には原則的に規制がなされるものとされており、その意味でいわゆるミニマム・スタンダードである。
一方、本法で考えているガイドラインはミニマム・スタンダードではなく、再生資源を利用してつくられる多種多様な製品を踏まえて、具体的な努力内容を定め、それを事業者の判断の目安とし、努力を促すことで全体の水準を引き上げるという性格のものである。したがって、工場立地法の例のようにミニマム・スタンダードを意味する「準則」というガイドラインを用いることは本法の措置には適切ではない。
「指針」とは、一般には「物事を進める方針」を意味するが、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の立法例では、事業者等に誘導の方向を示すもの(ガイドライン)のうち一定の水準を示す意味合いが薄い誘導指標として用いられているが、本法で予定している措置(ガイドライン)は、それに基づき勧告、公表、命令といった措置につながるものであるため、「指針」という用語を用いることは適切ではない。
「事業者の判断の基準となるべき事項」については、エネルギーの使用の合理化に関する法律の立法例は、「事業者の判断の基準となるべき事項」を誘導指標として総合的な判断の有力な材料となるものと位置付けており、これをもとに、主務大臣は、指導助言を行うほか、努力が著しく不十分なときは勧告、計画作成の指示、計画を実施すべき旨の指示を行うこととなっており、基本的には本条の「判断の基準となるべき事項」と同じ性格のものといえる。
4.第2項の「当該特定省資源業種に係る原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑制の状況、原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑制に関する技術水準その他の事情及び当該副産物に係る再生資源の利用の状況、再生資源の利用の促進に関する技術水準その他の事情」とは、判断の基準を定める際の勘案事項を述べたものである。
「当該特定省資源業種に係る原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑制の状況」とは、量、品質、価格等の面からみた利用の状況をいい、「原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑制に関する技術水準」とは、副産物の発生の抑制に必要な各種の技術(例えば、ペーパースラッジの利用に係る新規の用途の開発)の利用可能な水準をいう。さらに、「その他の事情」とは、例えば、副産物の発生の抑制に関する技術をとりいれた対策の普及状況等をいう。
「当該副産物に係る再生資源の利用の状況」とは、量、品質、価格等の面からみた利用の状況をいい、「再生資源の利用に関する技術水準」とは、再生資源の利用に必要な各種の技術(例えば、ペーパースラッジの発生を抑制する製造方法の開発)の利用可能な水準をいう。さらに、「その他の事情」とは、例えば、再生資源の利用の促進に関する技術をとりいれた対策の普及状況等をいう。 |
 |
|
|
 |
| |