 |
 |
 |
 |
|
|
 |
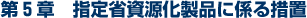 |
 |
| 1.指定省資源化製品の政令指定の要件 |
 |
(法律)
第2条 (略)
2~8 (略)
9 この法律において「指定省資源化製品」とは、製品であって、それに係る原材料等の使用の合理化、その長期間の使用の促進その他の当該製品に係る使用済物品等の発生の抑制を促進することが当該製品に係る原材料等に係る資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
10~13 (略) |
|
| |
(趣旨)
本項は、第5章に規定する措置の対象となる指定省資源化製品を定めたものである。
(解説)
1.「原材料等の使用の合理化」とは、同等の機能を有する製品における原材料等を節約することを意味する。例えば、家電製品において部品点数の削減や機能の集約化、薄肉化、軽量化などを実施すれば、同等の製品であっても使用されている原材料が削減されるなど、その使用の合理化がなされる。こうした措置を通じて製品における原材料等の使用を合理化すれば、結果として排出される使用済物品の量が削減され、廃棄物の発生を抑制することとなる。
また、部品や製品の素材を他の素材で代替することにより、小型化・軽量化が図られた場合も使用の合理化がなされたこととなる。小型化・軽量化を通じて使用済物品等の容積ベースでの発生抑制が図られることとなるからである。
2.「その長期間の使用の促進」とは、製造された製品をなるべく長期間使用する措置を事業者が実施することを意味する。製品を長期間使用するか否かは消費者の意志によるところが大きい。従って本法の義務対象となっている事業者に対しては長期間の使用の「促進」を求めることができるにとどまる。
例えば、自動車、家電製品などにおける耐久性の向上、修理容易な設計や修理体制の整備を事業者が講ずれば、消費者がこうした修理サービスを利用したり、実際に長期間使用したりすることにより、長期間使用が促進されると期待される。
3.「使用済物品等の発生の抑制」とは、事業者の実施する使用済物品等の発生抑制対策の総称である。原材料等の使用の合理化、長期間使用の促進は、使用済物品等の発生抑制対策のいわば例示として記載されるいるものであり、これら以外の対策であって、かつ使用済物品等や廃棄物の発生抑制に資するものであっても、「使用済物品等の発生抑制対策」として本法に位置づけられるものである。
例えば、洗剤などの詰替製品については、ボトル状の容器包装をスタンドパウチに変更するという、形態を大幅に変更するものであるため、「同等の機能を有する製品」における原材料等の使用の合理化とは言えない。しかしながら、プラスチックの使用量を大幅に削減し、廃棄物の発生抑制に資するものであることから、「使用済物品等の発生の抑制」対策には含まれる。
4.「原材料等に係る資源の有効な利用を図る上で特に必要なもの」とは、政策的に使用済物品等の発生の抑制の促進のための対策を事業者に義務づけることが、当該省資源化製品に係る資源としての効用を最大限に引き出す上で効果が大きいことを意味する。具体的には、指定省資源化製品に指定すべき製品は、1)使用済み等の後の排出量が多いこと、2)その資源の有用性が高いこと、3)対策の実施により使用済物品等の発生が抑制される効果が期待できること等を基準にして政令で指定されることとなる。 |
 |
|
|
 |
| |
|
 |
|