 |
 |
 |
 |
|
|
 |
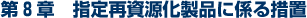 |
 |
| 1.指定再資源化製品の政令指定の要件 |
 |
(法律)
第2条 (略)
2~11 (略)
12 この法律において「指定再資源化製品」とは、製品(他の製品の部品として使用される製品を含む。)であって、それが一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された後それを当該製品(他の製品の部品として使用される製品にあっては、当該製品又は当該他の製品)の製造、加工、修理若しくは販売の事業を行う者が自主回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。以下同じ。)をすることが経済的に可能であって、その自主回収がされたものの全部又は一部の再資源化をすることが技術的及び経済的に可能であり、かつ、その再資源化をすることが当該再生資源又は再生部品の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
13 (略) |
|
| |
(趣旨)
本項は、第8章に規定する措置の対象となる指定再資源化製品を定めたものである。
(解説)
1.「製品(他の製品の部品として使用される製品を含む。)」、「当該製品(他の製品の部品として使用される製品にあっては、当該製品又は当該他の製品)」の「製品」とは、およそ製造されたものを指す概念であるため、消費者に直接販売され、消費されるものはもとより、他の製品の一部として利用されるものをも含む概念である。従って、製品との概念には、いわゆる「部品」も含むものであるが、ここでは明示的に部品を含むことを規定したものである。
部品の場合には、排出段階で部品のみを排出する消費者が太宗をしめるとは想定しにくく、むしろ製品と一体となって排出されると考えられる。本制度では、こうした実態を踏まえ、部品としての製品を指定する場合には、部品を製造する事業者のみならず、当該部品を使用した製品(「当該他の製品」)の事業者にも義務を課すことができる。
2.「自主回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。以下同じ。)」の「自主回収」とは、本来であれば回収する義務を負っているわけでない事業者が、自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。製造や販売の事業を行う者は、販路開拓を通じた流通システムを構築し、商取引慣行として消費者から使用済製品を回収する場合も見られることから、例えば、逆流通ルートなどの通常の商取引を活用した自主回収の方法が想定される。具体的には、新製品の販売の際に使用済製品の「下取り」を行う場合、使用者からの要請に応じて使用済製品を「引き取る」場合などが例として考えられる。
自主回収の対象となる使用済製品の範囲については、具体的には、製品毎の判断の基準において定めることとなる。
3.「自主回収をすることが経済的に可能」の「経済的に可能」とは、事業者のコスト負担が可能な場合であるが、経済原則に合致するもののみを限定して対象とすることを意味するのではなく、事業者の相当の努力によってはじめて可能となるようなものを念頭に置いている。
4.また、製品の製造事業者等は、当該製品の構造、再利用・再資源化可能な部品や材料、これらの資源としての有用性な部品などを熟知していることから、効率的な再資源化を実施しうる立場にある。「その自主回収がされたものの全部又は一部の再資源化をすることが技術的及び経済的に可能」の「経済的に可能」とは、こうした事業者による再資源化により得られる原材料等の価値が高く、コストが十分回収できる場合や製品価格への転嫁その他の手段により、再資源化に要するコスト負担が可能なことをいう。また、「技術的に可能」とは、回収された使用済製品を再資源化することが技術的に可能であることをいう。
なお、経済的に可能なものとは、経済原則に合致するもののみを限定して対象とすることを意味するのではなく、事業者の相当の努力によってはじめて可能となるようなものをいうのは、第3章の特定省資源業種で述べたところと同じである。
5.また、併せて「その再資源化をすることが当該再生資源又は再生部品の有効な利用を図る上で特に必要なもの」として政令で製品を指示することとなるが、具体的には1)事業者による自主的な回収・再資源化の取組だけでは十分な効果が上がらないこと2)高度な再資源化が必要であるため、市町村による再資源化が困難な製品であること等を基準に指定することとなる。 |
 |
|
|
 |
| |
|
 |
|