 |
 |
 |
 |
|
|
 |
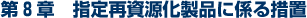 |
 |
| 3.使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定(第27条関係) |
 |
(法律)
(使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定)
第27条 指定再資源化事業者は、単独に又は共同して、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化を実施しようとするときは、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けることができる。
一 当該自主回収及び再資源化が前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に適合するものであること。
二 当該自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者が主務省令で定める基準に適合するものであること。
三 前号に規定する者が主務省令で定める基準に適合する施設を有するものであること。
四 同一の業種に属する事業を営む二以上の指定再資源化事業者の申請に係る自主回収及び再資源化にあっては、次のイ及びロに適合するものであること。
イ 当該二以上の指定再資源化事業者と当該業種に属する他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
ロ 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
2 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 自主回収及び再資源化の対象とする使用済指定再資源化製品の種類
三 自主回収及び再資源化の目標
四 自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者並びに当該自主回収及び再資源化に必要な行為の用に供する施設
五 自主回収及び再資源化の方法その他の内容に関する事項
3 主務大臣は、第一項の認定の申請に係る自主回収及び再資源化が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。 |
|
| |
(趣旨)
本条は、第8章に規定する指定再資源化事業者が、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化を実施しようとする際に、主務大臣が一定の事項に対して適合していることについて認定を行う規定である。
(解説)
1.措置の必要性
指定再資源化製品については、事業者が単独で又は共同で自主回収及び再資源化を実施しようとした場合、廃棄物の適正な処理の観点から廃棄物処理法上の規制を受ける場合が多い。また、事業者が共同で自主回収及び再資源化を実施する場合には、その方法によっては独占禁止法上の不当な取引制限及び不公正な取引方法に該当する可能性がある。
このため、本条以下の規定において、製造事業者が単独又は共同で実施する自主回収及び再資源化が判断の基準に照らし、適切であり、事業者の自主回収及び再資源化の目標を達成するために必要かつ適切である等の一定の要件を満たすものについて主務大臣が認定を行い、その円滑な実施を確保するために廃棄物処理法における配慮や独禁法の観点からの公正取引委員会との調整を図ることとするものである。
2.提出する書類
自主回収及び再資源化の実施においては、適切な再資源化が確保されているか等について審査するための基本的な条件を記載した書類が提出されることが必要である。これらの資料は、主務大臣が環境大臣及び事業所管大臣とされているため、両者に提出されなければならない。提出書類への記載事項は以下のとおりである。
1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
如何なる事業者が自主回収及び再資源化を行うこととなるかは、リサイクルの実効性や効率性を確保する上で重要な情報であり、これらの記載事項は、必要不可欠なものである。なお、ここでいう氏名や法人については、義務対象となっている事業者(例えばパソコン製造事業者など)をいう。義務者の委託を受けて事業を実施する者については、下記4)に記載されることとなる。
2) 自主回収及び再資源化の対象とする使用済指定再資源化製品の種類
自主回収の対象となる使用済指定再資源化製品を指す。また、例えば、地域的な条件などの付随事項についても付することができる(例えば、北海道地域における自社のブランドの付された製品など)。
3) 自主回収及び再資源化の目標
申請に係る自主回収及び再資源化の実施によって達成される自主回収及び再資源化の効果を指す。判断の基準に照らして妥当なものであることが認定の条件であるが(第1項)、その認定の是非は総合的に判断する。例えば、一部の地域についてのみ自主回収及び再資源化の認定を受ける必要がある事業者が存在し、こうした事業者については、全国ベースでの目標達成を行うことは不可能であっても認定を行う場合が挙げられる。
また、これらの目標については、当該自主回収及び再資源化の認定によって、確実に達成されるものでなければならない。
4) 自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者並びに当該自主回収及び再資源化に必要な行為の用に供する施設(実施者、施設)
自主回収及び再資源化に必要な行為については、指定再資源化事業者が自ら実施する場合の他に、例えば産業廃棄物処理事業者といった他の事業者が指定再資源化事業者の委託を受けて自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する場合が多いと想定される。従って、自主回収及び再資源化の認定の際には、義務対象である指定再資源化事業者のみならず、実際にこれに必要な行為を行う者やその施設についても審査する必要がある。これらを審査することを通じて、適正な自主回収及び再資源化を促進することが可能となるものである。
なお、自主回収及び再資源化に「必要な行為」とは、再資源化を行った後の残さの処分など再資源化と一体不可分の行為も含むものであり、これらの処分などを実施する者や施設についても記載することが必要である。
5) 自主回収及び再資源化の方法その他の内容に関する事項
具体的な自主回収及び再資源化の方法、目標を達成するために必要な技術や引取の対価などの内容に関する事項を記載することが必要である。
主務大臣は、認定の申請があったときは、当該自主回収及び再資源化の実施が確実であって、当該目標が判断の基準に照らして適正かつ十分であると認められるとき、かつこれらの共同で実施する事業が不当な競争制限を導かない場合には、当該自主回収及び再資源化を認定するものとした。
使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令(平成13年厚生労働省、経済産業省、環境省令第2号) |
| |
<省令>
(自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者の基準)
第1条 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号。以下「法」という。)第27条第1項第二号の主務省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当しない者であることとする。
一 当該自主回収又は再資源化を遂行するに足りる人員及び財政的基礎を有しない者
二 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
三 法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四 当該自主回収又は再資源化に必要な行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
五 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が第二号から前号までのいずれかに該当するもの
六 法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。次号において同じ。)のうちに第二号から第四号までのいずれかに該当する者のあるもの
イ 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
ロ イに掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
七 個人でその使用人のうちに第二号から第四号までのいずれかに該当する者のあるもの
(自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者の有する施設の基準)
第2条 法第27条第1項第三号の主務省令で定める基準は、当該自主回収又は再資源化に係る使用済指定再資源化製品の種類に応じ、当該使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化に適する施設であることとする。
(法第27条第2項の主務省令で定める書類)
第3条 法第27条第2項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 認定を受けようとする指定再資源化事業者が法人である場合には、その定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二 認定を受けようとする指定再資源化事業者が個人である場合には、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
三 自主回収又は再資源化に必要な行為を実施する者(以下「実施者」という。)が第1条に規定する基準に適合する旨を記載した書類
四 再資源化に必要な行為の用に供する施設の使用開始予定年月日及び当該施設において取り扱う使用済指定再資源化製品並びに当該施設が一年間に再資源化に必要な行為を実施することのできる使用済指定再資源化製品の最大数量を記載した書類
五 実施者が法第27条第2項第四号に規定する施設(運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を除く。)の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類、配置図及び付近の見取図
六 自主回収及び再資源化に必要な行為に関する料金を請求する場合にあっては、当該料金の算出の根拠に関する説明書
第4条・第5条 (略) |
|
| |
(趣旨)
本省令は、法第27条に基づき、主務大臣が使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定をする際に必要な基準及び書類を定めるものである。
(解説)
1.本省令第1条は、自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者(実施者)に関する基準を定めるものである。本条に規定する基準は、申請を行う指定再資源化事業者の他に、指定再資源化事業者の委託を受けて自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者にも適用される。
2.本省令第2条は、自主回収及び再資源化に必要な行為の用に供する施設に関する基準を定めるものである。本条に規定する基準は、申請を行う指定再資源化事業者の施設の他に、指定再資源化事業者の委託を受けて自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者の施設にも適用される。
3.本省令第3条は、法27条第2項の各号に規定する事項を記載した申請書に添付すべき書類を定めるものである。
一及び二 申請者(指定再資源化事業者)に関する基礎的な情報を補完するための書類である。
三 実施者が本省令第1条の基準に適合していることを審査するための書類である。
四 再資源化に必要な行為の用に供する施設が本省令第2条の基準に適合していることを審査するための書類である。直接に使用済指定再資源化製品の解体等の処理を行う施設(以下「再資源化拠点」という。)で処理後の使用済指定再資源化製品の一部を処理する施設(以下「二次処理施設」という)が本省令第2条の基準に適合することが明らかな場合には、本書類は、再資源化拠点のみ記載すれば事足りる。
五 実施者が、申請書に記載された施設を実際に使用できるかどうか審査するための書類である。回収に関する施設(運搬車や回収拠点など)については、本書類は不要としているが、例えば回収拠点で部品の取り外しを行うような場合には、本書類の添付が必要である。
六 自主回収及び再資源化に必要な行為に関する料金は、自主回収の実効の確保に与える影響が大きいため、その説明を求めるものである。無償又は買い取って自主回収及び再資源化を行う場合には、本書類は不要である。なお、本書類に記載した料金はいわゆる認可料金の性格を有するものではなく、この額以外の額の料金を求めることを妨げるものではない。例えば、まとまった数量を回収する際に料金を割り引くことは可能である。 |
 |
|
|
 |
| |