 |
 |
 |
 |
|
|
 |
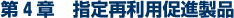 |
| |
<政令>
(指定再利用促進製品)
第4条 法第2条第10項の政令で定める製品は、別表第4の上欄に掲げるとおりとする。
(指定再利用促進事業者に係る生産量の要件)
第15条 法第23条第1項の政令で定める要件は、別表第4の上欄に掲げる指定再利用促進製品ごとにその年間の生産台数がそれぞれ同表の中欄に掲げる生産台数以上であることとする。
(指定再利用促進事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第16条 法第23条第3項の審議会等で政令で定めるものは、別表第4の上欄に掲げる指定再利用促進製品に係る指定再利用促進事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第31条 法第39条第1項第四号に定める事項についての主務大臣は、次のとおりとする。
三 別表第4の1から34まで、38から47まで及び50の項の上欄に掲げる指定再利用促進製品の製造の事業に係るものについては、経済産業大臣
四 別表第4の35から37まで、48及び49の項の上欄に掲げる指定再利用促進製品の製造の事業に係るものについては、厚生労働大臣及び経済産業大臣
五 別表第4の7の項の上欄に掲げる指定再利用促進製品の修理の事業に係るものについては、国土交通大臣 |
|
| |
| 別表第4(第4条、第15条、第16条、第31条関係) |
| 1 浴室ユニット(浴槽、給水栓、照明器具その他入浴のために必要な器具又は設備が一体として製造される製品をいい、便所又は洗面所が一体として製造されるものを含む。) |
1千台 |
産業構造審議会 |
| 2 電源装置 |
1千台 |
産業構造審議会 |
| 3 電動工具 |
1万台 |
産業構造審議会 |
| 4 誘導灯 |
1万台 |
産業構造審議会 |
| 5 火災警報設備 |
1千台 |
産業構造審議会 |
| 6 防犯警報装置 |
1万台 |
産業構造審議会 |
| 7 自動車 |
1万台 |
産業構造審議会 |
| 8 自転車(人の力を補うため電動機を用いるものに限る。以下同じ。) |
1千台 |
産業構造審議会 |
| 9 車いす(電動式のものに限る。以下同じ。) |
1千台 |
産業構造審議会 |
| 10 パーソナルコンピュータ |
1万台 |
産業構造審議会 |
| 11 プリンター |
1万台 |
産業構造審議会 |
| 12 携帯用データ収集装置 |
1万台 |
産業構造審議会 |
| 13 コードレスホン |
2千台 |
産業構造審議会 |
14 ファクシミリ装置
|
5千台 |
産業構造審議会 |
| 15 交換機 |
1千台 |
産業構造審議会 |
16 携帯電話用装置
|
1万台 |
産業構造審議会 |
| 17 MCAシステム用通信装置 |
1千台 |
産業構造審議会 |
| 18 簡易無線用通信装置 |
1千台 |
産業構造審議会 |
| 19 アマチュア用無線機 |
1千台 |
産業構造審議会 |
20 ユニット形エアコンディショナ
|
5万台 |
産業構造審議会 |
| 21 ぱちんこ遊技機 |
1万台 |
産業構造審議会 |
| 22 回胴式遊技機 |
5千台 |
産業構造審議会 |
| 23 複写機 |
1千台 |
産業構造審議会 |
| 24 テレビ受像機 |
5万台 |
産業構造審議会 |
| 25 ビデオカメラ |
1万台 |
産業構造審議会 |
| 26 ヘッドホンステレオ |
1万台 |
産業構造審議会 |
| 27 電子レンジ |
1万台 |
産業構造審議会 |
| 28 衣類乾燥機 |
1万台 |
産業構造審議会 |
| 29 電気冷蔵庫 |
5万台 |
産業構造審議会 |
| 30 電気洗濯機 |
5万台 |
産業構造審議会 |
| 31 電気掃除機 |
1万台 |
産業構造審議会 |
| 32 電気かみそり(電池式のものに限る。以下同じ。) |
1万台 |
産業構造審議会 |
| 33 電気歯ブラシ |
1万台 |
産業構造審議会 |
| 34 非常用照明器具 |
1万台 |
産業構造審議会 |
| 35 血圧計 |
1万台 |
薬事・食品衛生
審議会及び
産業構造審議会 |
| 36 医薬品注入器 |
1千台 |
薬事・食品衛生
審議会及び
産業構造審議会 |
37 電気マッサージ器
|
1万台 |
薬事・食品衛生
審議会及び
産業構造審議会 |
| 38 収納家具 |
1万台 |
産業構造審議会 |
| 39 棚 |
1万台 |
産業構造審議会 |
| 40 事務用机 |
1万台 |
産業構造審議会 |
| 41 回転いす |
2万台 |
産業構造審議会 |
42 システムキッチン(台所流し、調理用の台、食器棚その他調理のために必要な器具又は設備が一体として製造される製品をいう。)
|
5千台 |
産業構造審議会 |
| 43 石油ストーブ |
1万台 |
産業構造審議会 |
| 44 ガスこんろ |
1万台 |
産業構造審議会 |
| 45 ガス瞬間湯沸器 |
5千台 |
産業構造審議会 |
| 46 ガスバーナー付ふろがま |
1万台 |
産業構造審議会 |
| 47 給湯機 |
1万台 |
産業構造審議会 |
| 48 家庭用電気治療器 |
1万台 |
産業構造審議会 |
| 49 電気気泡発生器(浴槽用のものに限る。以下同じ。) |
1万台 |
産業構造審議会 |
| 50 電動式がん具(自動車型のものに限る。以下同じ。) |
1万台 |
産業構造審議会 |
|
| |
(趣旨)
本条は、法第2条第10項、第23条第1項及び第3項、第39条第1項第四号の規定に基づき、指定再利用促進製品及びその関連事項を定めるものである。
(解説)
1.指定の要件
法第2条第10項に基づき、指定再利用促進製品として政令指定する際の要件を以下のように設定し、具体的には別表第4の上欄に掲げる製品を指定した。
1) 製品の特性上、次のような取組により再生資源又は再生部品として利用することを促進することが可能であること。
a)再生資源又は再生部品として利用可能な材料や部品の選択等の工夫
b)取り外し容易な部品の取付け方法の採用等の工夫
c)部品の材質名の表示等の分別のための工夫
2) 資源の有効な利用を図る上で特に必要な製品であること。
a)使用済みとなった後の排出量が多い製品であること。
b)有用な資源を含む製品であること。
c)対策の実施により再生資源の利用が向上する効果が期待できること。
2.指定再利用促進製品の対象
|
|
日本標準商品分類等における範囲 |
| 1 浴室ユニット(浴槽、給水栓、照明器具その他入浴のために必要な器具又は設備が一体として製造される製品をいい、便所又は洗面所が一体として製造されるものを含む。) |
入浴のために必要な浴槽、給水栓、照明器具などが一体となっている室形の浴室をいい、便器又は洗面器などを組み込んだものを含む。主に一般の家庭やマンション、ホテルなどに供給されている製品である。日本標準商品分類では、・「サニタリー単体ユニット」(243121)のうち、「浴室ユニット」(2431211)・「サニタリー集合ユニット」(243122)のうち、「浴室・便所ユニット」(2431221)、「浴室・洗面所ユニット」(2431222)、「浴室・便所・洗面所ユニット」(2431224)・「サニタリー複合ユニット」(243123)のうち、「浴室・便所ユニット」(2431231)、「浴室・洗面所ユニット」(2431232)、「浴室・便所・洗面所ユニット」(2431234) |
| 2 電源装置 |
「無停電電源装置」(302422)及び「電源装置」(6197) |
| 3 電動工具 |
「電動工具」(3424) |
| 4 誘導灯 |
「誘導灯」(41281) |
| 5 火災警報設備 |
「火災警報設備」(4151) |
| 6 防犯警報装置 |
「防犯警報装置」(4152) |
| 7 自動車 |
「自動車及び二輪自動車(原動機付自転車を含む。)」(47) |
| 8 自転車(人の力を補うため電動機を用いるものに限る。以下同じ。) |
「その他の一般自転車」(48119)の一部 |
| 9 車いす(電動式のものに限る。以下同じ。) |
電動車いす(JIS T9203) |
| 10 パーソナルコンピュータ |
「パーソナルコンピュータ」(5212)、並びに「CRTディスプレイ装置」(521451)及び「液晶ディスプレイ装置」(521452)のうちパーソナルコンピュータ用のもの |
| 11 プリンター |
「印刷装置」(52141) |
| 12 携帯用データ収集装置 |
「データ収集装置」(521525)のうち携帯用のもの、及びPDA |
| 13 コードレスホン |
「コードレスホン」(54113) |
| 14 ファクシミリ装置 |
「ファクシミリ」(54141) |
| 15 交換機 |
「交換機」(5415) |
| 16 携帯電話用装置 |
携帯電話及びPHS |
| 17 MCAシステム用通信装置 |
「MCAシステム用通信装置」(5422132) |
| 18 簡易無線用通信装置 |
「簡易無線用通信装置」(54225) |
| 19 アマチュア用無線機 |
「アマチュア用無線機」(54296) |
| 20 ユニット形エアコンディショナ |
「ユニット形エアコンディショナ」(5622)のうち、「パッケージ用エアコンディショナ」(56222)以外のもの |
| 21 ぱちんこ遊技機 |
「ぱちんこ装置」(5772)のうち、ぱちんこホール(風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律に基づき、公安委員会から同法第2条第7号に掲げるぱちんこ屋としての営業の許可を受けている営業所)で使用されるぱちんこ遊技機(いわゆる「パチンコ台」)をいう。 |
| 22 回胴式遊技機 |
「その他類似の娯楽装置」(5779)のうち、ぱちんこホール(風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律に基づき、公安委員会から同法第2条第7号に掲げるぱちんこ屋としての営業の許可を受けている営業所)で使用される回胴式遊技機(いわゆる「パチスロ」)をいう。 |
| 23 複写機 |
「複写機」(5911)のうち、主に一般の事業所等向けに供給されている乾式間接静電式に限り、生産台数が少ないカラー複写機、A2版以上の用紙に複写が可能な構造のもの、毎分86枚以上の複写が可能な構造のもの、主に家庭用複写機として製造されている毎分16枚以上の複写が不可能な構造のものを除外したものをいう。 |
| 24 テレビ受像機 |
「テレビ受像機(付加機能付きのものを含む。)」(6011) |
| 25 ビデオカメラ |
「ビデオカメラ(放送用を除く。)」(6013)、デジタルカメラ |
| 26 ヘッドホンステレオ |
「ヘッドホンステレオ」(60212及び60222)、ヘッドホンステレオCDプレーヤ、ヘッドホンステレオMDプレーヤ、半導体オーディオ等 |
| 27 電子レンジ |
「電子レンジ」(60433) |
| 28 衣類乾燥機 |
「衣類乾燥機(業務用は除く。)」(60491) |
| 29 電気冷蔵庫 |
「電気冷蔵庫(冷凍庫と一体のものを含む。)」(6051) |
| 30 電気洗濯機 |
「電気洗濯機(業務用を除く。)」(607) |
| 31 電気掃除機 |
「電気掃除機」(608) |
| 32 電気かみそり(電池式のものに限る。以下同じ。) |
「電気かみそり(電池式)」(60971) |
| 33 電気歯ブラシ |
「電気歯ブラシ」(60974) |
| 34 非常用照明器具 |
「非常用白熱灯器具」(622117及び622124)、及び「非常用螢光灯器具」(622222) |
| 35 血圧計 |
「血圧計」(66212) |
| 36 医薬品注入器 |
「医薬品注入器」(66433) |
| 37 電気マッサージ器 |
「マッサージ器」(66646)のうち電動式のもの及び「家庭用電気マッサージ器」(865111) |
| 38 収納家具 |
天板、地板、棚板、戸、フラップ、巻戸、引出しなどの幾つかの主要構成部材の組合せによって構成され、筐体(枠体)が金属製のもので、主に企業や官公庁などのオフィスなどで、物品収納などに用いられる収納家具である。また、収納家具は収納する物品が戸などによって六面が覆われる構造のものであり、その構造によって箱形構造収納家具とファイリングキャビネットに分類される。 |
| 39 棚 |
支柱、棚板、棚板支持具などの主要構成部材の組合せによって構成され、支柱(枠体)が金属製のもので、主に企業や官公庁などのオフィスや書庫、倉庫、図書館などで、事務用品、業務用品及び図書等の収納・保管などに用いられる一面以上が開放された構造のものをいう。 |
| 40 事務用机 |
甲板、そで、脚、引出し部などの幾つかの主要構成部材の組合せによって構成され、甲板(天板)を支えている部分が金属製のもので、主に企業や官公庁などのオフィスなどで使用される机である。また、事務用机は構造によって両そで机、片そで机、わき机、平机に分類される。 |
| 41 回転いす |
座面、背もたれ、ひじ部、脚部などの幾つかの主要構成部材の組合せによって構成され、座面、背もたれを支える部分が金属製の回転いすで、主に企業や官公庁などのオフィスなどで使用される執務用回転いす、会議用回転いすである。また、座面高さ調整式のものも含む。 |
| 42 システムキッチン(台所流し、調理用の台、食器棚その他調理のために必要な器具又は設備が一体として製造される製品をいう。) |
調理のために必要な台所流し(シンク)、調理用の台、食器棚などが有機的に結合された台所設備をいい、主に一般の家庭に供給されている製品である。 |
| 43 石油ストーブ |
「開放式であってしん式放射形石油ストーブ」(84212111)及び「気化式であって強制対流式石油ストーブ」(84212122) |
| 44 ガスこんろ |
「ガスグリル付こんろ」(843116) |
| 45 ガス瞬間湯沸器 |
「先止め式ガス瞬間湯沸器(給湯配管のできるもの)」(845112) |
| 46 ガスバーナー付ふろがま |
「給湯付ガスふろがま」(845143) |
| 47 給湯機 |
「石油小形給湯機」(84521) |
| 48 家庭用電気治療器 |
「家庭用電気治療器」(86521) |
| 49 電気気泡発生器(浴槽用のものに限る。以下同じ。) |
「家庭用超音波気泡浴装置」(865131)及び「家庭用気泡浴装置」(865132) |
| 50 電動式がん具(自動車型のものに限る。以下同じ。) |
「電動式がん具(自動車、電車、汽車等)」(89515)のうち自動車型のもの |
|
| |
| 3.政令第15条に定める要件に該当する指定再利用促進事業者の範囲(勧告・命令等の対象)は法第23条に基づく勧告・公表・命令の対象となる事業者の要件を定めるものである。これらの要件に該当する指定再利用促進事業者の生産量は、我が国における指定再利用促進製品の生産量全体の9割以上を占め、政策効果としては十分である。 |
| |
<政令>
第27条 主務大臣は、法第37条第2項の規定により、指定再利用促進事業者に対し、その製造に係る指定再利用促進製品に係る業務の状況につき、次の事項に関し報告させることができる。
一 当該指定再利用促進製品の種類及び数量その他当該指定再利用促進製品の製造の業務に関する事項
二 当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進のための構造の改善その他再生資源又は再生部品の利用の促進に関する事項
2 主務大臣は、法第37条第2項の規定により、その職員に、指定再利用促進事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造に係る指定再利用促進製品、当該指定再利用促進製品の製造のための設備及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。 |
|
| |
(趣旨)
本条は、第37条第2項の規定に基づく指定再利用促進製品に係る報告徴収又は立入検査を行う際の、報告又は検査の内容を規定したものである。
(解説)
1.法第37条第2項の規定においては、指定再利用促進事業者に対する報告徴収及び立入検査を政令で定めるところにより行うことができるものとされている。
2.具体的な報告内容については、以下のような内容が想定される。
(1) 当該指定再利用促進製品の種類及び数量その他当該指定再利用促進製品の製造の業務に関する事項
製品の種類・数量、製造工程の状況等
(2) 当該指定再利用促進に係る再生資源又は再生部品の利用の促進のための構造の改善その他再生資源又は再生部品の利用の促進に関する事項
製品構造・部品の材料・分別の容易化等の工夫の状況、再生資源又は再生部品の利用の促進に資する技術開発の状況等
浴室ユニットの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(経済産業省令第76号) |
| |
<省令>
(原材料の工夫)
第1条 浴室ユニット(浴槽、給水栓、照明器具その他入浴のために必要な器具又は設備が一体として製造される製品をいい、便所又は洗面所が一体として製造されるものを含む。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、浴室ユニットに係る再生資源の利用を促進するため、浴槽、防水パンその他の浴室ユニットの部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置を講ずるものとする。
(構造の工夫)
第2条 事業者は、浴室ユニットに係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減、複数の部品を一体として取り付けることその他の部品等の取り外しの容易化、小型のねじの採用による部品等の破砕の容易化、回収及び運搬が容易な大きさに解体することが可能な構造の採用その他の措置により、浴室ユニットの処理を容易にするものとする。
(分別のための工夫)
第3条 事業者は、浴室ユニットに係る再生資源の利用を促進するため、重量が百グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫を行うことにより、浴室ユニットに係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。
(処理に係る安全性の確保)
第4条 事業者は、浴室ユニットに係る再生資源の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
(安全性等の配慮)
第5条 事業者は、前各条の規定に即して浴室ユニットに係る再生資源の利用を促進する際には、浴室ユニットの安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
(技術の向上)
第6条 事業者は、浴室ユニットに係る再生資源の利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。
(事前評価)
第7条 事業者は、浴室ユニットの設計に際して、浴室ユニットに係る再生資源の利用を促進するため、第1条から第4条までの規定に即して、あらかじめ浴室ユニットの評価を行うものとする。
2 事業者は、前項の評価を行うため、浴室ユニットの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3 事業者は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
(情報の提供)
第8条 事業者は、浴室ユニットの構造、部品等の取り外し方法、部品等の材質名その他の浴室ユニットに係る再生資源の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。
(包装材の工夫)
第9条 事業者は、浴室ユニットに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が容易な原材料又は再生資源を利用した原材料を使用するものとする。
2 事業者は、浴室ユニットに係る包装材の再生資源としての利用を促進するため、浴室ユニットに係る包装について、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が可能な包装材を他の包装材から分離することが容易な構造の採用、回収及び運搬が容易な構造の採用その他の措置を講ずるものとする。 |
|
| |
(趣旨)
法第21条に基づき、政令第4条の規定により指定した浴室ユニットの製造の事業を行う者についての判断基準を示すものである。
(解説)
この省令において「製造の事業を行う者(事業者)」とは、製品の組立・加工を最終的に行い製品を市場に供給する事業者(アセンブラー)のことをいう。ただし、材料の加工、部品の組立といった物理的な製造行為は行わないものの自らの商標を付して製品を市場に供給する事業者(ブランドオーナー)が併存する場合は、どちらが製造事業者に該当するかは当該判断の基準による取組に関する影響力、製品の企画・設計に関する支配及び指示の状況、自己の商標の使用等についてを総合的に評価し判断するものである。
省令第1条は、製造事業者が製品の設計・製造段階において、製品に使用する原材料を工夫することにより、使用済みとなった製品に係る再生資源の利用を促進することを目的に、必要な各種の措置を規定している。「再生資源としての利用が可能な原材料の使用」とは、リサイクルをすることが技術的かつ経済的に可能であって、リサイクルがし易い原材料を浴槽、防水パン等の部品に使用することを意味している。「原材料の種類数の削減」とは、リサイクルをする上では、製品又はその部品等に使用する原材料の種類数が少ないほどリサイクルが容易となることから、部品等に使用する素材をリサイクルがし易い原材料に統一化することなどを意味している。「再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減」とは、異種の材料を複合化させることはリサイクルの阻害になる懸念があるため、可能な限りこのような材料の複合化を避けることを意味している。
省令第2条は、製造事業者が製品の設計・製造段階において、製品の構造を工夫することにより、使用済みとなった製品に係る再生資源の利用を促進することを目的に、必要な各種の措置を規定している。
省令第2条に掲げる「ねじの数量の削減」とは、部品等の取り外しなど分解を容易にすることを目的に、従来のねじの取り付け位置の見直しを行い、ねじの使用の合理化を行うことや、部品等の結合部分をねじを使わないはめ込み構造(スナップフィット方式)にすることなどを意味している。「複数の部品を一体として取り付けること」とは、従来では個々の部品等で構成されていたユニットを、一体として成型して1つの部品等に集約化・統合化することを意味している。この措置は、一般に結合箇所数の低減につながり分解の容易化に寄与するものである。また、集約化された部品等の素材の統一化が同時に図られれば、ユニット単位でのリサイクルが可能となりリサイクル性の向上にも大きく寄与するものである。
なお、設計・製造段階における再生資源の利用の促進に向けた取組は、各製造事業者の創意工夫により促進されるべき取組である。そのため、第1条から第3条においては具体的な部品名や措置内容を示しているが、これらは取組の余地があると想定される代表的なものの例示であり、これらの取組に限定するという趣旨ではない。その他の取組であっても再生資源の利用の促進に資する有効な措置であれば、その措置に取り組むことにより本規定を満たすこととなる。第1条に掲げる「その他の措置を講ずるものとする。」や第2条に掲げる「その他の措置により、」等は、そうした趣旨を踏まえて規定されたものである。
省令第4条は、製品が使用済みとなった後の処理に係る安全性を確保するため、製品に使用する原材料の毒性やその他の特性に配慮することを規定している。なお、本条においては、環境負荷の原因となりうる有害物質の使用の削減を行うことも含まれる。
省令第5条は、第1条から第4条までの規定に基づいて、製造事業者が再生資源又は再生部品の利用の促進に資する取組を行う際には、製品が本来持つべき安全性や耐久性等の機能が損なわれないように配慮することが必要な旨を規定している。
省令第7条の「事前評価」とは、製造事業者が製品の設計・製造段階において、当該製品の生産、使用、廃棄、リサイクル等の各段階における、第1条から第4条までの規定に関することを事前に評価し、必要に応じて製品設計や生産方法等の変更を行うことをいう(いわゆる製品アセスメント)。
省令第8条の「情報の提供」に係る規定は、消費者や修理事業者に対して、使用済みとなった製品に係る再生資源の利用を促進するために、必要な限度における情報の提供を行うことを趣旨としている。
自動車の製造又は修理の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(経済産業省、国土交通省令第1号) |
| |
<省令>
(原材料の工夫)
第1条 自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、自動車に係る再生資源の利用を促進するため、バンパー、内装その他の自動車の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置を講ずるものとする。
2 製造事業者は、自動車に係る再生部品の利用を促進するため、エンジン、バンパーその他の自動車の部品等への腐食するおそれが少ない原材料の使用その他の措置を講ずるものとする。
(構造の工夫)
第2条 製造事業者は、自動車に係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減その他の部品等の取り外しの容易化その他の措置により、自動車の処理を容易にするものとする。
2 製造事業者は、自動車に係る再生部品の利用を促進するため、エンジン、バンパーその他の自動車の部品等について、取り外す際に損傷するおそれが少ない構造及び腐食するおそれが少ない構造の採用その他の措置を講ずるものとする。
(分別のための工夫)
第3条 製造事業者は、自動車に係る再生資源の利用を促進するため、重量が百グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫を行うことにより、自動車に係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。
(処理に係る安全性の確保)
第4条 製造事業者は、自動車に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
(安全性等の配慮)
第5条 製造事業者は、前各条の規定に即して自動車に係る再生資源又は再生部品の利用を促進する際には、自動車の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
(部品等の交換の工夫)
第6条 自動車の修理の事業を行う者(以下「修理事業者」という。)は、自動車に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、自動車の部品等の交換に当たっては、再生資源又は再生部品としての利用が可能な部品等の使用及び再生部品の使用に努めるとともに、交換された使用済みの部品等を当該部品等に表示された材質名により分別するものとする。
(技術の向上)
第7条 製造事業者及び修理事業者は、自動車に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、必要な技術の向上(習得を含む。)を図るものとする。
(事前評価)
第8条 製造事業者は、自動車の設計に際して、自動車に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、第1条から第4条までの規定に即して、あらかじめ自動車の評価を行うものとする。
2 製造事業者は、前項の評価を行うため、自動車の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3 製造事業者は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
(情報の提供)
第9条 製造事業者は、自動車の構造、部品等の取り外し方法、部品等の材質名その他の自動車に係る再生資源又は再生部品の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。
2 修理事業者は、自動車の修理に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、自動車の構造、部品等の取り外し方法、部品等の材質名の表示等に関し、製造事業者が配慮すべき事項について、必要に応じて当該製造事業者に対して情報の提供を行うものとする。 |
|
| |
(趣旨)
法第21条に基づき、政令第4条の規定により指定した自動車の製造又は修理の事業を行う者についての判断基準を示すものである。
(解説)
省令第1条の「製造の事業を行う者(事業者)」及び第9条の「情報の提供」の基本的な考え方については、指定省資源化製品の判断の基準となるべき事項を定める省令における規定の考え方と同様である。
省令第1条は、製造事業者が製品の設計・製造段階において、製品に使用する原材料を工夫することにより、使用済みとなった製品に係る再生資源又は再生部品の利用を促進することを目的に、必要な各種の措置を規定している。
省令第1条第1項に掲げる「再生資源としての利用が可能な原材料の使用」とは、リサイクルをすることが技術的かつ経済的に可能であって、リサイクルがし易い原材料をバンパー、内装等の部品に使用することを意味している。「原材料の種類数の削減」とは、リサイクルをする上では、製品又はその部品等に使用する原材料の種類数が少ないほどリサイクルが容易となることから、部品等に使用する素材をリサイクルがし易い原材料に統一化することなどを意味している。「再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減」とは、異種の材料を複合化させることはリサイクルの阻害になる懸念があるため、可能な限りこのような材料の複合化を避けることを意味している。
省令第2条は、製造事業者が製品の設計・製造段階において、製品の構造を工夫することにより、使用済みとなった製品に係る再生資源又は再生部品の利用を促進することを目的に、必要な各種の措置を規定している。
省令第2条第1項に掲げる「ねじの数量の削減」とは、部品等の取り外しなど分解を容易にすることを目的に、従来のねじの取り付け位置の見直しを行い、ねじの使用の合理化を行うことや、部品等の結合部分をねじを使わないはめ込み構造(スナップフィット方式)にすることなどを意味している。
なお、設計・製造段階における再生資源又は再生部品の利用の促進に向けた取組は、各製造事業者の創意工夫により促進されるべき取組である。そのため、第1条から第3条においては具体的な部品名や措置内容を示しているが、これらは取組の余地があると想定される代表的なものの例示であり、これらの取組に限定するという趣旨ではない。その他の取組であっても再生資源又は再生部品の利用の促進に資する有効な措置であれば、その措置に取り組むことにより本規定を満たすこととなる。第1条に掲げる「その他の措置を講ずるものとする。」や第2条に掲げる「その他の措置により、」等は、そうした趣旨を踏まえて規定されたものである。
省令第4条は、製品が使用済みとなった後の処理に係る安全性を確保するため、製品に使用する原材料の毒性やその他の特性に配慮することを規定している。なお、本条においては、環境負荷の原因となりうる有害物質の使用の削減を行うことも含まれる。
省令第5条は、第1条から第4条までの規定に基づいて、製造事業者が再生資源又は再生部品の利用の促進に資する取組を行う際には、製品が本来持つべき安全性や耐久性等の機能が損なわれないように配慮することが必要な旨を規定している。
省令第8条の「事前評価」とは、製造事業者が製品の設計・製造段階において、当該製品の生産、使用、廃棄、リサイクル等の各段階における、第1条から第4条までの規定に関することを事前に評価し、必要に応じて製品設計や生産方法等の変更を行うことをいう(いわゆる製品アセスメント)。
パーソナルコンピュータの製造の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成13年経済産業省令第77号) |
| |
<省令>
(原材料の工夫)
第1条 パーソナルコンピュータ(その表示装置であってブラウン管式又は液晶式のものを含む。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、パーソナルコンピュータに係る再生資源の利用を促進するため、ブラウン管、筐体その他のパーソナルコンピュータの部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、めっきをした合成樹脂製の部品等の数の削減その他の措置を講ずるものとする。
2 事業者は、パーソナルコンピュータに係る再生部品の利用を促進するため、ブラウン管、筐体その他のパーソナルコンピュータの部品等への汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料の使用その他の措置を講ずるものとする。
(構造の工夫)
第2条 事業者は、パーソナルコンピュータに係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減、複数の部品を一体として取り付けることその他の部品等の取り外しの容易化、回収及び運搬の容易化その他の措置により、パーソナルコンピュータの処理を容易にするものとする。
2 事業者は、パーソナルコンピュータに使用される密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池(電気量が234キロクーロン以下のものに限る。)、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池をいい、機器の記憶保持用のものを除く。以下同じ。)の再生資源としての利用を促進するため、はんだ付けによらない密閉形蓄電池の取付け方法の採用、密閉形蓄電池の取り外しが消費者にとって容易である構造の採用その他の構造の工夫を行うものとする。
3 事業者は、パーソナルコンピュータに係る再生部品の利用を促進するため、主記憶装置、磁気ディスク装置その他の部品等について、取り外す際に損傷するおそれが少ない構造及び汚れるおそれが少ない構造又は清掃が容易な構造の採用、寿命の明確化その他の措置を講ずるものとする。
(分別のための工夫)
第3条 事業者は、パーソナルコンピュータに係る再生資源の利用を促進するため、重量が25グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫を行うことにより、パーソナルコンピュータに係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。
2 事業者は、パーソナルコンピュータに使用される密閉形蓄電池の再生資源としての利用を促進するため、当該機器が密閉形蓄電池を使用する機器である旨その他の密閉形蓄電池の再生資源としての利用の促進に係る事項のパーソナルコンピュータ及びそれに付属する取扱説明書その他の物品への表示又は記載を行うものとする。
(処理に係る安全性の確保)
第4条 事業者は、パーソナルコンピュータに係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
(安全性等の配慮)
第5条 事業者は、前各条の規定に即してパーソナルコンピュータに係る再生資源又は再生部品の利用を促進する際には、パーソナルコンピュータの安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
(技術の向上)
第6条 事業者は、パーソナルコンピュータに係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。
(事前評価)
第7条 事業者は、パーソナルコンピュータの設計に際して、パーソナルコンピュータに係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、第1条から第4条までの規定に即して、あらかじめパーソナルコンピュータの評価を行うものとする。
2 事業者は、前項の評価を行うため、パーソナルコンピュータの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3 事業者は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
(情報の提供)
第8条 事業者は、パーソナルコンピュータの構造、使用される密閉形蓄電池その他の部品等の取り外し方法、部品等の材質名その他のパーソナルコンピュータに係る再生資源又は再生部品の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。
(包装材の工夫)
第9条 事業者は、パーソナルコンピュータに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が容易な原材料又は再生資源を利用した原材料を使用するものとする。
2 事業者は、パーソナルコンピュータに係る包装材の再生資源としての利用を促進するため、パーソナルコンピュータに係る包装について、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が可能な包装材を他の包装材から分離することが容易な構造の採用、回収及び運搬が容易な構造の採用その他の措置を講ずるものとする。 |
|
| |
(趣旨)
法第21条に基づき、政令第4条の規定により指定したパーソナルコンピュータの製造の事業を行う者についての判断基準を示すものである。
(解説)
省令第1条の「製造の事業を行う者(事業者)」及び第8条の「情報の提供」の基本的な考え方については、指定省資源化製品の判断の基準となるべき事項を定める省令における規定の考え方と同様である。
省令第1条は、製造事業者が製品の設計・製造段階において、製品に使用する原材料を工夫することにより、使用済みとなった製品に係る再生資源又は再生部品の利用を促進することを目的に、必要な各種の措置を規定している。
省令第1条第1項に掲げる「再生資源としての利用が可能な原材料の使用」とは、リサイクルをすることが技術的かつ経済的に可能であって、リサイクルがし易い原材料をブラウン管、筐体等の部品に使用することを意味している。「原材料の種類数の削減」とは、リサイクルをする上では、製品又はその部品等に使用する原材料の種類数が少ないほどリサイクルが容易となることから、部品等に使用する素材をリサイクルがし易い原材料に統一化することなどを意味している。「めっきをした合成樹脂製の部品等の数の削減」とは、装飾的外観を得るために金属をめっきするなど、異種の材料を複合化させることは合成樹脂のリサイクルの阻害になる懸念があるため、可能な限りこのような材料の複合化を避けることを意味している。
省令第2条は、製造事業者が製品の設計・製造段階において、製品の構造を工夫することにより、使用済みとなった製品に係る再生資源又は再生部品の利用を促進することを目的に、必要な各種の措置を規定している。
省令第2条第1項に掲げる「ねじの数量の削減」とは、部品等の取り外しなど分解を容易にすることを目的に、従来のねじの取り付け位置の見直しを行い、ねじの使用の合理化を行うことや、部品等の結合部分をねじを使わないはめ込み構造(スナップフィット方式)にすることなどを意味している。「複数の部品を一体として取り付けること」とは、従来では個々の部品等で構成されていたユニットを、一体として成型して1つの部品等に集約化・統合化することを意味している。この措置は、一般に結合箇所数の低減につながり分解の容易化に寄与するものである。また、集約化された部品等の素材の統一化が同時に図られれば、ユニット単位でのリサイクルが可能となりリサイクル性の向上にも大きく寄与するものである。
なお、設計・製造段階における再生資源又は再生部品の利用の促進に向けた取組は、各製造事業者の創意工夫により促進されるべき取組である。そのため、第1条から第3条においては具体的な部品名や措置内容を示しているが、これらは取組の余地があると想定される代表的なものの例示であり、これらの取組に限定するという趣旨ではない。その他の取組であっても再生資源又は再生部品の利用の促進に資する有効な措置であれば、その措置に取り組むことにより本規定を満たすこととなる。第1条に掲げる「その他の措置を講ずるものとする。」や第2条に掲げる「その他の措置により、」等は、そうした趣旨を踏まえて規定されたものである。
省令第4条は、製品が使用済みとなった後の処理に係る安全性を確保するため、製品に使用する原材料の毒性やその他の特性に配慮することを規定している。なお、本条においては、環境負荷の原因となりうる有害物質の使用の削減を行うことも含まれる。
省令第5条は、第1条から第4条までの規定に基づいて、製造事業者が再生資源又は再生部品の利用の促進に資する取組を行う際には、製品が本来持つべき安全性や耐久性等の機能が損なわれないように配慮することが必要な旨を規定している。
省令第7条の「事前評価」とは、製造事業者が製品の設計・製造段階において、当該製品の生産、使用、廃棄、リサイクル等の各段階における、第1条から第4条までの規定に関することを事前に評価し、必要に応じて製品設計や生産方法等の変更を行うことをいう(いわゆる製品アセスメント)。
<参考>
パソコンの事前評価を行うに当たっては、(社)電子情報技術産業協会が作成した「情報処理機器の環境設計アセスメントガイドライン」を参照されたい。
ぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(経済産業省令第79号) |
| |
<省令>
(原材料の工夫)
第1条 ぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、ぱちんこ遊技機に係る再生資源の利用を促進するため、遊技盤、遊技球の受け皿その他のぱちんこ遊技機の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、めっきをした合成樹脂製の部品等の数の削減その他の措置を講ずるものとする。
2 事業者は、ぱちんこ遊技機に係る再生部品の利用を促進するため、液晶表示装置、遊技盤の枠その他のぱちんこ遊技機の部品等への汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料の使用その他の措置を講ずるものとする。
(構造の工夫)
第2条 事業者は、ぱちんこ遊技機に係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減、複数の部品を一体として取り付けることその他の部品等の取り外しの容易化その他の措置により、ぱちんこ遊技機の処理を容易にするものとする。
2 事業者は、ぱちんこ遊技機に係る再生部品の利用を促進するため、液晶表示装置、遊技盤の枠その他のぱちんこ遊技機の部品等について、取り外す際に損傷するおそれが少ない構造及び汚れるおそれが少ない構造又は清掃が容易な構造の採用、寿命の明確化その他の措置を講ずるものとする。
(分別のための工夫)
第3条 事業者は、ぱちんこ遊技機に係る再生資源の利用を促進するため、重量が百グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫を行うことにより、ぱちんこ遊技機に係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。
(処理に係る安全性の確保)
第4条 事業者は、ぱちんこ遊技機に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
(安全性等の配慮)
第5条 事業者は、前各条の規定に即してぱちんこ遊技機に係る再生資源又は再生部品の利用を促進する際には、ぱちんこ遊技機の安全性及び耐久性、不正の防止その他の必要な事情に配慮するものとする。
(技術の向上)
第6条 事業者は、ぱちんこ遊技機に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。
(事前評価)
第7条 事業者は、ぱちんこ遊技機の設計に際して、ぱちんこ遊技機に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、第1条から第4条までの規定に即して、あらかじめぱちんこ遊技機の評価を行うものとする。
2 事業者は、前項の評価を行うため、ぱちんこ遊技機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3 事業者は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
(情報の提供)
第8条 事業者は、ぱちんこ遊技機の構造、部品等の取り外し方法、部品等の材質名その他のぱちんこ遊技機に係る再生資源又は再生部品の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。
(包装材の工夫)
第9条 事業者は、ぱちんこ遊技機に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が容易な原材料又は再生資源を利用した原材料を使用するものとする。
2 事業者は、ぱちんこ遊技機に係る包装材の再生資源としての利用を促進するため、ぱちんこ遊技機に係る包装について、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が可能な包装材を他の包装材から分離することが容易な構造の採用、回収及び運搬が容易な構造の採用その他の措置を講ずるものとする。 |
|
| |
(趣旨)
法第21条に基づき、政令第4条の規定により指定したぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者についての判断基準を示すものである。
(解説)
省令第1条の「製造の事業を行う者(事業者)」及び第8条の「情報の提供」の基本的な考え方については、指定省資源化製品の判断の基準となるべき事項を定める省令における規定の考え方と同様である。
省令第1条は、製造事業者が製品の設計・製造段階において、製品に使用する原材料を工夫することにより、使用済みとなった製品に係る再生資源又は再生部品の利用を促進することを目的に、必要な各種の措置を規定している。
省令第1条第1項に掲げる「再生資源としての利用が可能な原材料の使用」とは、リサイクルをすることが技術的かつ経済的に可能であって、リサイクルがし易い原材料を遊技盤、遊技球の受け皿等の部品に使用することを意味している。「原材料の種類数の削減」とは、リサイクルをする上では、製品又はその部品等に使用する原材料の種類数が少ないほどリサイクルが容易となることから、部品等に使用する素材をリサイクルがし易い原材料に統一化することなどを意味している。「めっきをした合成樹脂製の部品等の数の削減」とは、装飾的外観を得るために金属をめっきするなど、異種の材料を複合化させることは合成樹脂のリサイクルの阻害になる懸念があるため、可能な限りこのような材料の複合化を避けることを意味している。
省令第2条は、製造事業者が製品の設計・製造段階において、製品の構造を工夫することにより、使用済みとなった製品に係る再生資源又は再生部品の利用を促進することを目的に、必要な各種の措置を規定している。
省令第2条第1項に掲げる「ねじの数量の削減」とは、部品等の取り外しなど分解を容易にすることを目的に、従来のねじの取り付け位置の見直しを行い、ねじの使用の合理化を行うことや、部品等の結合部分をねじを使わないはめ込み構造(スナップフィット方式)にすることなどを意味している。
なお、設計・製造段階における再生資源又は再生部品の利用の促進に向けた取組は、各製造事業者の創意工夫により促進されるべき取組である。そのため、第1条から第3条においては具体的な部品名や措置内容を示しているが、これらは取組の余地があると想定される代表的なものの例示であり、これらの取組に限定するという趣旨ではない。その他の取組であっても再生資源又は再生部品の利用の促進に資する有効な措置であれば、その措置に取り組むことにより本規定を満たすこととなる。第1条に掲げる「その他の措置を講ずるものとする。」や第2条に掲げる「その他の措置により、」等は、そうした趣旨を踏まえて規定されたものである。
省令第4条は、製品が使用済みとなった後の処理に係る安全性を確保するため、製品に使用する原材料の毒性やその他の特性に配慮することを規定している。なお、本条においては、環境負荷の原因となりうる有害物質の使用の削減を行うことも含まれる。
省令第5条は、第1条から第4条までの規定に基づいて、製造事業者が再生資源又は再生部品の利用の促進に資する取組を行う際には、製品が本来持つべき安全性や耐久性等の機能が損なわれないように配慮することが必要な旨を規定している。
省令第7条の「事前評価」とは、製造事業者が製品の設計・製造段階において、当該製品の生産、使用、廃棄、リサイクル等の各段階における、第1条から第4条までの規定に関することを事前に評価し、必要に応じて製品設計や生産方法等の変更を行うことをいう(いわゆる製品アセスメント)。
「回胴式遊技機の製造の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」についても使用済製品の違いはあるものの、基本的な考え方は同じである。
複写機の製造の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(経済産業省令第81号) |
| |
<省令>
(原材料の工夫)
第1条 複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機及び資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第2の4の項の上欄に規定する複写機に関する省令(平成13年経済産業省令第50号)第1条で定めるものを除く。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置への汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料の使用その他の措置を講ずるものとする。
(構造の工夫)
第2条 事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置を講ずるものとする。
2 事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、複写機の駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置について、取り外す際に損傷するおそれが少ない構造及び汚れるおそれが少ない構造又は清掃が容易な構造の採用、寿命の明確化その他の措置を講ずるものとする。
(処理に係る安全性の確保)
第3条 事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
(安全性等の配慮)
第4条 事業者は、前3条の規定に即して複写機に係る再生部品の利用を促進する際には、複写機の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
(技術の向上)
第5条 事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。
(事前評価)
第6条 事業者は、複写機の設計に際して、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、第1条から第3条までの規定に即して、あらかじめ複写機の評価を行うものとする。
2 事業者は、前項の評価を行うため、複写機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3 事業者は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
(情報の提供)
第7条 事業者は、複写機の構造、部品の取り外し方法その他の複写機に係る再生部品の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。 |
|
| |
(趣旨)
法第21条に基づき、政令第4条の規定により指定した複写機の製造の事業を行う者についての判断基準を示すものである。
(解説)
この省令において「製造の事業を行う者(事業者)」とは、製品の組立・加工を最終的に行い製品を市場に供給する事業者(アセンブラー)のことをいう。ただし、材料の加工、部品の組立といった物理的な製造行為は行わないものの自らの商標を付して製品を市場に供給する事業者(ブランドオーナー)が併存する場合は、どちらが製造事業者に該当するかは当該判断の基準による取組に関する影響力、製品の企画・設計に関する支配及び指示の状況、自己の商標の使用等についてを総合的に評価し判断するものである。「再生部品」の基本的考え方は、特定再利用業種の複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき省令における規定の考え方と同様である。
省令第1条及び第2条は、製造事業者が製品の設計・製造段階において、製品に使用する原材料や構造を工夫することにより、使用済みとなった製品に係る再生部品の利用を促進することを目的に、必要な措置を規定している。
なお、設計・製造段階における再生資源又は再生部品の利用の促進に向けた取組は、各製造事業者の創意工夫により促進されるべき取組である。そのため、第1条及び第2条においては具体的な措置内容を示しているが、これらは取組の余地があると想定される代表的なものの例示であり、これらの取組に限定するという趣旨ではない。その他の取組であっても再生部品の利用の促進に資する有効な措置であれば、その措置に取り組むことにより本規定を満たすこととなる。第1条及び第2条に掲げる「その他の措置を講ずるものとする。」は、そうした趣旨を踏まえて規定されたものである。
省令第3条は、製品が使用済みとなった後の処理に係る安全性を確保するため、製品に使用する原材料の毒性やその他の特性に配慮することを規定している。なお、本条においては、環境負荷の原因となりうる有害物質の使用の削減を行うことも含まれる。
省令第4条は、第1条から第3条までの規定に基づいて、製造事業者が再生部品の利用の促進に資する取組を行う際には、製品が本来持つべき安全性や耐久性等の機能が損なわれないように配慮することが必要な旨を規定している。
省令第6条の「事前評価」とは、製造事業者が製品の設計・製造段階において、当該製品の生産、使用、廃棄、リサイクル等の各段階における、第1条から第4条までの規定に関することを事前に評価し、必要に応じて製品設計や生産方法等の変更を行うことをいう(いわゆる製品アセスメント)。
省令第7条の「情報の提供」に係る規定は、消費者や修理事業者に対して、使用済みとなった製品に係る再生部品の利用を促進するために、必要な限度における情報の提供を行うことを趣旨としている。
テレビ受像機の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(経済産業省令第82号) |
| |
<省令>
(原材料の工夫)
第1条 テレビ受像機の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、テレビ受像機に係る再生資源の利用を促進するため、ブラウン管、筐体その他のテレビ受像機の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置を講ずるものとする。
(構造の工夫)
第2条 事業者は、テレビ受像機に係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減その他の部品等の取り外しの容易化、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置により、テレビ受像機の処理を容易にするものとする。
(分別のための工夫)
第3条 事業者は、テレビ受像機に係る再生資源の利用を促進するため、重量が百グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫を行うことにより、テレビ受像機に係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。
(処理に係る安全性の確保)
第4条 事業者は、テレビ受像機に係る再生資源の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
(安全性等の配慮)
第5条 事業者は、前各条の規定に即してテレビ受像機に係る再生資源の利用を促進する際には、テレビ受像機の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
(技術の向上)
第6条 事業者は、テレビ受像機に係る再生資源の利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。
(事前評価)
第7条 事業者は、テレビ受像機の設計に際して、テレビ受像機に係る再生資源の利用を促進するため、第1条から第4条までの規定に即して、あらかじめテレビ受像機の評価を行うものとする。
2 事業者は、前項の評価を行うため、テレビ受像機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3 事業者は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
(情報の提供)
第8条 事業者は、テレビ受像機の構造、部品等の取り外し方法、部品等の材質名その他のテレビ受像機に係る再生資源の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。
(包装材の工夫)
第9条 事業者は、テレビ受像機に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が容易な原材料又は再生資源を利用した原材料を使用するものとする。
2 事業者は、テレビ受像機に係る包装材の再生資源としての利用を促進するため、テレビ受像機に係る包装について、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が可能な包装材を他の包装材から分離することが容易な構造の採用、回収及び運搬が容易な構造の採用その他の措置を講ずるものとする。 |
|
| |
(趣旨)
法第21条に基づき、政令第4条の規定により指定したテレビ受像機の製造又は修理の事業を行う者についての判断基準を示すものである。
(解説)
省令第1条の「製造の事業を行う者(事業者)」及び第8条の「情報の提供」の基本的な考え方については、指定省資源化製品の判断の基準となるべき事項を定める省令における規定の考え方と同様である。
省令第1条は、製造事業者が製品の設計・製造段階において、製品に使用する原材料を工夫することにより、使用済みとなった製品に係る再生資源の利用を促進することを目的に、必要な各種の措置を規定している。
省令第1条に掲げる「再生資源としての利用が可能な原材料の使用」とは、リサイクルをすることが技術的かつ経済的に可能であって、リサイクルがし易い原材料をブラウン管、筐体等の部品に使用することを意味している。「原材料の種類数の削減」とは、リサイクルをする上では、製品又はその部品等に使用する原材料の種類数が少ないほどリサイクルが容易となることから、部品等に使用する素材をリサイクルがし易い原材料に統一化することなどを意味している。「再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減」とは、異種の材料を複合化させることはリサイクルの阻害になる懸念があるため、可能な限りこのような材料の複合化を避けることを意味している。
省令第2条は、製造事業者が製品の設計・製造段階において、製品の構造を工夫することにより、使用済みとなった製品に係る再生資源の利用を促進することを目的に、必要な各種の措置を規定している。
省令第2条に掲げる「ねじの数量の削減」とは、部品等の取り外しなど分解を容易にすることを目的に、従来のねじの取り付け位置の見直しを行い、ねじの使用の合理化を行うことや、部品等の結合部分をねじを使わないはめ込み構造(スナップフィット方式)にすることなどを意味している。
なお、設計・製造段階における再生資源又は再生部品の利用の促進に向けた取組は、各製造事業者の創意工夫により促進されるべき取組である。そのため、第1条から第3条においては具体的な部品名や措置内容を示しているが、これらは取組の余地があると想定される代表的なものの例示であり、これらの取組に限定するという趣旨ではない。その他の取組であっても再生資源の利用の促進に資する有効な措置であれば、その措置に取り組むことにより本規定を満たすこととなる。第1条に掲げる「その他の措置を講ずるものとする。」や第2条に掲げる「その他の措置により、」等は、そうした趣旨を踏まえて規定されたものである。
省令第4条は、製品が使用済みとなった後の処理に係る安全性を確保するため、製品に使用する原材料の毒性やその他の特性に配慮することを規定している。なお、本条においては、環境負荷の原因となりうる有害物質の使用の削減を行うことも含まれる。
省令第5条は、第1条から第4条までの規定に基づいて、製造事業者が再生資源又は再生部品の利用の促進に資する取組を行う際には、製品が本来持つべき安全性や耐久性等の機能が損なわれないように配慮することが必要な旨を規定している。
省令第7条の「事前評価」とは、製造事業者が製品の設計・製造段階において、当該製品の生産、使用、廃棄、リサイクル等の各段階における、第1条から第4条までの規定に関することを事前に評価し、必要に応じて製品設計や生産方法等の変更を行うことをいう(いわゆる製品アセスメント)。
「ユニット形エアコンディショナの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」、「電子レンジの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」、「衣類乾燥機の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」、「電気冷蔵庫の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」及び「電気洗濯機の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」についても使用済製品の違いはあるものの、基本的な考え方は同じである。
事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(経済産業省令第89号) |
| |
<省令>
(原材料の工夫)
第1条 事務用机(金属製のものに限る。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、事務用机に係る再生資源の利用を促進するため、甲板、脚部その他の事務用机の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置を講ずるものとする。
(構造の工夫)
第2条 事業者は、事務用机に係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減、再生資源としての利用が可能な原材料の部品等を他の原材料の部品等から分離することが容易な接合方法の採用その他の部品等の取り外しの容易化、回収及び運搬の容易化その他の措置により、事務用机の処理を容易にするものとする。
(分別のための工夫)
第3条 事業者は、事務用机に係る再生資源の利用を促進するため、重量が百グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫を行うことにより、事務用机に係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。
(処理に係る安全性の確保)
第4条 事業者は、事務用机に係る再生資源の利用を促進するため、原材料及び構造の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
(安全性等の配慮)
第5条 事業者は、前各条の規定に即して事務用机に係る再生資源の利用を促進する際には、事務用机の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
(技術の向上)
第6条 事業者は、事務用机に係る再生資源の利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。
(事前評価)
第7条 事業者は、事務用机の設計に際して、事務用机に係る再生資源の利用を促進するため、第1条から第4条までの規定に即して、あらかじめ事務用机の評価を行うものとする。
2 事業者は、前項の評価を行うため、事務用机の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3 事業者は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
(情報の提供)
第8条 事業者は、事務用机の構造、部品等の取り外し方法、部品等の材質名その他の事務用机に係る再生資源の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。
(包装材の工夫)
第9条 事業者は、事務用机に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が容易な原材料又は再生資源を利用した原材料を使用するものとする。
2 事業者は、事務用机に係る包装材の再生資源としての利用を促進するため、事務用机に係る包装について、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が可能な包装材を他の包装材から分離することが容易な構造の採用、回収及び運搬が容易な構造の採用その他の措置を講ずるものとする。 |
|
| |
(趣旨)
法第21条に基づき、政令第4条の規定により指定した事務用机の製造の事業を行う者についての判断基準を示すものである。
(解説)
省令第1条の「製造の事業を行う者(事業者)」及び第8条の「情報の提供」の基本的な考え方については、指定省資源化製品の判断の基準となるべき事項を定める省令における規定の考え方と同様である。
省令第1条は、製造事業者が製品の設計・製造段階において、製品に使用する原材料を工夫することにより、使用済みとなった製品に係る再生資源の利用を促進することを目的に、必要な各種の措置を規定している。
省令第1条に掲げる「再生資源としての利用が可能な原材料の使用」とは、リサイクルをすることが技術的かつ経済的に可能であって、リサイクルがし易い原材料を甲板、脚部等の部品に使用することを意味している。「原材料の種類数の削減」とは、リサイクルをする上では、製品又はその部品等に使用する原材料の種類数が少ないほどリサイクルが容易となることから、部品等に使用する素材をリサイクルがし易い原材料に統一化することなどを意味している。「再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減」とは、異種の材料を複合化させることはリサイクルの阻害になる懸念があるため、可能な限りこのような材料の複合化を避けることを意味している。
省令第2条は、製造事業者が製品の設計・製造段階において、製品の構造を工夫することにより、使用済みとなった製品に係る再生資源の利用を促進することを目的に、必要な各種の措置を規定している。
省令第2条に掲げる「ねじの数量の削減」とは、部品等の取り外しなど分解を容易にすることを目的に、従来のねじの取り付け位置の見直しを行い、ねじの使用の合理化を行うことや、部品等の結合部分をねじを使わないはめ込み構造(スナップフィット方式)にすることなどを意味している。
なお、設計・製造段階における再生資源又は再生部品の利用の促進に向けた取組は、各製造事業者の創意工夫により促進されるべき取組である。そのため、第1条から第3条においては具体的な部品名や措置内容を示しているが、これらは取組の余地があると想定される代表的なものの例示であり、これらの取組に限定するという趣旨ではない。その他の取組であっても再生資源の利用の促進に資する有効な措置であれば、その措置に取り組むことにより本規定を満たすこととなる。第1条に掲げる「その他の措置を講ずるものとする。」や第2条に掲げる「その他の措置により、」等は、そうした趣旨を踏まえて規定されたものである。
省令第4条は、製品が使用済みとなった後の処理に係る安全性を確保するため、製品に使用する原材料及び構造の特性に配慮することを規定している。
省令第5条は、第1条から第4条までの規定に基づいて、製造事業者が再生資源又は再生部品の利用の促進に資する取組を行う際には、製品が本来持つべき安全性や耐久性等の機能が損なわれないように配慮することが必要な旨を規定している。
省令第7条の「事前評価」とは、製造事業者が製品の設計・製造段階において、当該製品の生産、使用、廃棄、リサイクル等の各段階における、第1条から第4条までの規定に関することを事前に評価し、必要に応じて製品設計や生産方法等の変更を行うことをいう(いわゆる製品アセスメント)。
「収納家具の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」、「棚の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」及び「回転いすの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」についても使用済製品の違いはあるものの、基本的な考え方は同じである。」
システムキッチンの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(経済産業省令第91号) |
| |
<省令>
(原材料の工夫)
第1条 システムキッチン(台所流し、調理用の台、食器棚その他調理のために必要な器具又は設備が一体として製造される製品をいう。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、システムキッチンに係る再生資源の利用を促進するため、調理用の台、食器棚その他のシステムキッチンの部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置を講ずるものとする。
(構造の工夫)
第2条 事業者は、システムキッチンに係る再生資源の利用を促進するため、ステンレス鋼製の部品等を他の原材料の部品等から分離することが容易な接合方法の採用その他の部品等の取り外しの容易化、回収及び運搬が容易な大きさに解体することが可能な構造の採用その他の措置により、システムキッチンの処理を容易にするものとする。
(分別のための工夫)
第3条 事業者は、システムキッチンに係る再生資源の利用を促進するため、重量が百グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫を行うことにより、システムキッチンに係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。
(処理に係る安全性の確保)
第4条 事業者は、システムキッチンに係る再生資源の利用を促進するため、原材料及び構造の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
(安全性等の配慮)
第5条 事業者は、前各条の規定に即してシステムキッチンに係る再生資源の利用を促進する際には、システムキッチンの安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
(技術の向上)
第6条 事業者は、システムキッチンに係る再生資源の利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。
(事前評価)
第7条 事業者は、システムキッチンの設計に際して、システムキッチンに係る再生資源の利用を促進するため、第1条から第4条までの規定に即して、あらかじめシステムキッチンの評価を行うものとする。
2 事業者は、前項の評価を行うため、システムキッチンの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3 事業者は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
(情報の提供)
第8条 事業者は、システムキッチンの構造、部品等の取り外し方法、部品等の材質名その他のシステムキッチンに係る再生資源の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。
(包装材の工夫)
第9条 事業者は、システムキッチンに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が容易な原材料又は再生資源を利用した原材料を使用するものとする。
2 事業者は、システムキッチンに係る包装材の再生資源としての利用を促進するため、システムキッチンに係る包装について、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が可能な包装材を他の包装材から分離することが容易な構造の採用、回収及び運搬が容易な構造の採用その他の措置を講ずるものとする。 |
|
| |
(趣旨)
法第21条に基づき、政令第4条の規定により指定したシステムキッチンの製造の事業を行う者についての判断基準を示すものである。
(解説)
この省令において「製造の事業を行う者(事業者)」とは、製品の組立・加工を最終的に行い製品を市場に供給する事業者(アセンブラー)のことをいう。ただし、材料の加工、部品の組立といった物理的な製造行為は行わないものの自らの商標を付して製品を市場に供給する事業者(ブランドオーナー)が併存する場合は、どちらが製造事業者に該当するかは当該判断の基準による取組に関する影響力、製品の企画・設計に関する支配及び指示の状況、自己の商標の使用等についてを総合的に評価し判断するものである。
省令第1条は、製造事業者が製品の設計・製造段階において、製品に使用する原材料を工夫することにより、使用済みとなった製品に係る再生資源の利用を促進することを目的に、必要な各種の措置を規定している。「再生資源としての利用が可能な原材料の使用」とは、リサイクルをすることが技術的かつ経済的に可能であって、リサイクルがし易い原材料を調理用の台、食器棚等の部品等に使用することを意味している。「原材料の種類数の削減」とは、リサイクルをする上では、製品又はその部品等に使用する原材料の種類数が少ないほどリサイクルが容易となることから、部品等に使用する素材をリサイクルがし易い原材料に統一化することなどを意味している。「再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減」とは、異種の材料を複合化させることはリサイクルの阻害になる懸念があるため、可能な限りこのような材料の複合化を避けることを意味している。
省令第2条は、製造事業者が製品の設計・製造段階において、製品の構造を工夫することにより、使用済みとなった製品に係る再生資源の利用を促進することを目的に、必要な各種の措置を規定している。
省令第2条に掲げる「ステンレス鋼製の部品等を他の原材料の部品等から分離することが容易な接合方法」とは、部品等の取り外しなど分解を容易にすることを目的に、従来の接合方法の見直しを行い、部品等の結合部分をねじを使わないはめ込み構造(スナップフィット方式)にすることなどを意味している。
なお、設計・製造段階における再生資源の利用の促進に向けた取組は、各製造事業者の創意工夫により促進されるべき取組である。そのため、第1条から第3条においては具体的な部品名や措置内容を示しているが、これらは取組の余地があると想定される代表的なものの例示であり、これらの取組に限定するという趣旨ではない。その他の取組であっても再生資源の利用の促進に資する有効な措置であれば、その措置に取り組むことにより本規定を満たすこととなる。第1条に掲げる「その他の措置を講ずるものとする。」や第2条に掲げる「その他の措置により、」等は、そうした趣旨を踏まえて規定されたものである。
省令第4条は、製品が使用済みとなった後の処理に係る安全性を確保するため、製品に使用する原材料及び構造の特性に配慮することを規定している。
省令第5条は、第1条から第4条までの規定に基づいて、製造事業者が再生資源又は再生部品の利用の促進に資する取組を行う際には、製品が本来持つべき安全性や耐久性等の機能が損なわれないように配慮することが必要な旨を規定している。
省令第7条の「事前評価」とは、製造事業者が製品の設計・製造段階において、当該製品の生産、使用、廃棄、リサイクル等の各段階における、第1条から第4条までの規定に関することを事前に評価し、必要に応じて製品設計や生産方法等の変更を行うことをいう(いわゆる製品アセスメント)。
省令第8条の「情報の提供」に係る規定は、消費者や修理事業者に対して、使用済みとなった製品に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するために、必要な限度における情報の提供を行うことを趣旨としている。
石油ストーブ等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(経済産業省令第92号) |
| |
<省令>
(原材料の工夫)
第1条 石油ストーブ等(石油ストーブ(密閉燃焼式のもの及び資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第3の15の項の上欄に規定する石油ストーブに関する省令(平成13年経済産業省令第51号)で定めるものを除く。)、ガスこんろ(グリル付きのものに限る。)、ガス瞬間湯沸器(先止め式のものに限る。)、ガスバーナー付ふろがま(給湯部を有するものに限る。)又は給湯機(石油を燃料とするものに限る。)をいう。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、石油ストーブ等に係る再生資源の利用を促進するため、燃焼装置、筐体その他の石油ストーブ等の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置を講ずるものとする。
(構造の工夫)
第2条 事業者は、石油ストーブ等に係る再生資源の利用を促進するため、ねじの種類数の削減その他の部品等の取り外しの容易化、回収及び運搬の容易化その他の措置により、石油ストーブ等の処理を容易にするものとする。
(分別のための工夫)
第3条 事業者は、石油ストーブ等に係る再生資源の利用を促進するため、重量が百グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫を行うことにより、石油ストーブ等に係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。
(処理に係る安全性の確保)
第4条 事業者は、石油ストーブ等に係る再生資源の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
(安全性等の配慮)
第5条 事業者は、前各条の規定に即して石油ストーブ等に係る再生資源の利用を促進する際には、石油ストーブ等の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
(技術の向上)
第6条 事業者は、石油ストーブ等に係る再生資源の利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。
(事前評価)
第7条 事業者は、石油ストーブ等の設計に際して、石油ストーブ等に係る再生資源の利用を促進するため、第1条から第4条までの規定に即して、あらかじめ石油ストーブ等の評価を行うものとする。
2 事業者は、前項の評価を行うため、石油ストーブ等の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3 事業者は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
(情報の提供)
第8条 事業者は、石油ストーブ等の構造、部品等の取り外し方法、部品等の材質名その他の石油ストーブ等に係る再生資源の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。
(包装材の工夫)
第9条 事業者は、石油ストーブ等に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が容易な原材料又は再生資源を利用した原材料を使用するものとする。
2 事業者は、石油ストーブ等に係る包装材の再生資源としての利用を促進するため、石油ストーブ等に係る包装について、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が可能な包装材を他の包装材から分離することが容易な構造の採用、回収及び運搬が容易な構造の採用その他の措置を講ずるものとする。 |
|
| |
(趣旨)
法第21条に基づき、政令第4条の規定により指定した石油ストーブ、ガスこんろ、ガス瞬間湯沸器、ガスバーナー付ふろがま及び給湯機の製造の事業を行う者についての判断基準を示すものである。
(解説)
省令第1条の「製造の事業を行う者(事業者)」及び第8条の「情報の提供」の基本的な考え方については、指定省資源化製品の判断の基準となるべき事項を定める省令における規定の考え方と同様である。
省令第1条は、製造事業者が製品の設計・製造段階において、製品に使用する原材料を工夫することにより、使用済みとなった製品に係る再生資源の利用を促進することを目的に、必要な各種の措置を規定している。
省令第1条に掲げる「再生資源としての利用が可能な原材料の使用」とは、リサイクルをすることが技術的かつ経済的に可能であって、リサイクルがし易い原材料を燃焼装置、筐体等の部品に使用することを意味している。「再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減」とは、異種の材料を複合化させることはリサイクルの阻害になる懸念があるため、可能な限りこのような材料の複合化を避けることを意味している。
省令第2条は、製造事業者が製品の設計・製造段階において、製品の構造を工夫することにより、使用済みとなった製品に係る再生資源の利用を促進することを目的に、必要な各種の措置を規定している。
省令第2条に掲げる「ねじの数量の削減」とは、部品等の取り外しなど分解を容易にすることを目的に、従来のねじの取り付け位置の見直しを行い、ねじの使用の合理化を行うことや、部品等の結合部分をねじを使わないはめ込み構造(スナップフィット方式)にすることなどを意味している。
なお、設計・製造段階における再生資源の利用の促進に向けた取組は、各製造事業者の創意工夫により促進されるべき取組である。そのため、第1条から第3条においては具体的な部品名や措置内容を示しているが、これらは取組の余地があると想定される代表的なものの例示であり、これらの取組に限定するという趣旨ではない。その他の取組であっても再生資源の利用の促進に資する有効な措置であれば、その措置に取り組むことにより本規定を満たすこととなる。第1条に掲げる「その他の措置を講ずるものとする。」や第2条に掲げる「その他の措置により、」等は、そうした趣旨を踏まえて規定されたものである。
省令第4条は、製品が使用済みとなった後の処理に係る安全性を確保するため、製品に使用する原材料の毒性やその他の特性に配慮することを規定している。なお、本条においては、環境負荷の原因となりうる有害物質の使用の削減を行うことも含まれる。
省令第5条は、第1条から第4条までの規定に基づいて、製造事業者が再生資源又は再生部品の利用の促進に資する取組を行う際には、製品が本来持つべき安全性や耐久性等の機能が損なわれないように配慮することが必要な旨を規定している。
省令第7条の「事前評価」とは、製造事業者が製品の設計・製造段階において、当該製品の生産、使用、廃棄、リサイクル等の各段階における、第1条から第4条までの規定に関することを事前に評価し、必要に応じて製品設計や生産方法等の変更を行うことをいう(いわゆる製品アセスメント)。
電源装置等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(経済産業省令第93号) |
| |
<省令>
(構造の工夫)
第1条 電源装置等(電源装置、電動工具、誘導灯、火災警報設備、防犯警報装置、自転車(人の力を補うため電動機を用いるものに限る。)、車いす(電動式のものに限る。)、プリンター、携帯用データ収集装置、コードレスホン、ファクシミリ装置、交換機、携帯電話用装置、MCAシステム用通信装置、簡易無線用通信装置、アマチュア用無線機、ビデオカメラ、ヘッドホンステレオ、電気掃除機、電気かみそり(電池式のものに限る。)、電気歯ブラシ、非常用照明器具又は電動式がん具(自動車型のものに限る。)をいう。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、電源装置等に使用される密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池(電気量が234キロクーロン以下のものに限る。)、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池をいい、機器の記憶保持用のものを除く。以下同じ。)の再生資源としての利用を促進するため、はんだ付けによらない密閉形蓄電池の取付け方法の採用、密閉形蓄電池の取り外しが消費者又は当該電源装置等の保守点検の事業を行う者にとって容易である構造の採用その他の構造の工夫を行うものとする。
(再生資源の利用の促進のための表示等)
第2条 事業者は、電源装置等に使用される密閉形蓄電池の再生資源としての利用を促進するため、当該機器が密閉形蓄電池を使用する機器である旨その他の密閉形蓄電池の再生資源としての利用の促進に係る事項の電源装置等及びそれに付属する取扱説明書その他の物品への表示又は記載を行うものとする。
(安全性等の配慮)
第3条 事業者は、前二条の規定に即して電源装置等に使用される密閉形蓄電池の再生資源としての利用を促進する際には電源装置等の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
(技術の向上)
第4条 事業者は、電源装置等に使用される密閉形蓄電池の再生資源としての利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。
(事前評価)
第5条 事業者は、電源装置等の設計に際して、電源装置等に使用される密閉形蓄電池の再生資源としての利用を促進するため、第1条及び第2条の規定に即して、あらかじめ電源装置等の評価を行うものとする。
2 事業者は、前項の評価を行うため、電源装置等の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めることとする。
3 事業者は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
(情報の提供)
第6条 事業者は、電源装置等の構造、使用される密閉形蓄電池の取り外し方法その他の電源装置等に使用される密閉形蓄電池の再生資源としての利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。 |
|
| |
(趣旨)
法第21条に基づき、政令第4条の規定により指定した電源装置等の製造の事業を行う者についての判断基準を示すものである。
(解説)
本省令は、対象の製品が小形二次電池の使用機器であることに着目して、小形二次電池の再生資源としての利用を促進するための判断の基準を示している。
本省令において「事業者」(製造の事業を行う者)とは、製品の組立・加工を最終的に行い製品を市場に供給する事業者(アセンブラー)のことをいう。ただし、材料の加工、部品の組立といった物理的な製造行為は行わないものの自らの商標を付せて製品を市場に供給する事業者(ブランドオーナー)が併存する場合は、どちらが製造事業者に該当するかは当該判断の基準による取組に関する影響力、製品の企画・設計に関する支配及び指示の状況、自己の商標の使用等についてを総合的に評価し判断するものである。
本省令において、「機器の記憶保持用のものを除く」としているのは、機器の記憶保持用として使用される小形二次電池は、1)その性質上データ保持のため接続が常に保たれることが求められるため、構造上機器の中心部に位置することが多く、かつ比較的外れにくい構造とする必要があること、2)機器あたりの使用量、全体の使用量とも少ないことから、回収・リサイクルに配慮した設計を求めることが技術的又は経済的に過大な負担を強いることになる恐れがあることによる。
本省令第1条の規定は、小形二次電池の取り外しを容易にするなど、小形二次電池の再生資源としての利用を促進するための構造の工夫を求めるものである。主として一般消費者が使用する機器については、消費者にとって取り外しが容易な構造となっている必要がある。他方、一般消費者による取り外しが想定されず、機器の保守・点検事業者、工事業者、サービス業者などによる取り外しが予定されている機器については、これらの事業者にとって取り外しが容易な構造であればよい。
本省令第2条の規定は、機器本体、取扱説明書その他機器に付属する物品に、小形二次電池の再生資源としての利用を促進するための事項を明記することを求めるものである。この表示又は記載については、特に様式を定めていないが、例えば機器本体への表示は、指定表示製品に係る様式(メビウス・ループとNi-Cdなどの文字の表示)を準用することが、また取扱説明書への記載事項は、小形二次電池が使用されていること、回収・リサイクルの必要性、問い合わせ先などが考えられる。
本省令第3条は、第1条及び第2条の規定に基づいて、製造事業者が密閉形蓄電池の再生資源としての利用を促進する際には、製品が従来持つべき安全性や耐久性等の機能が損なわれないように配慮することが必要な旨を規定している。
本省令第5条の「事前評価」とは、製造事業者が製品の設計段階において、当該製品の生産、使用、廃棄等の各段階における、第1条及び第2条の規定に関することを事前に評価し、必要に応じて製品設計や生産方法等の変更を行うことをいう(いわゆる製品アセスメント)。
省令第6条の「情報の提供」に係る規定は、消費者や機器の保守・点検事業者、工事業者、サービス業者等に対して、密閉形蓄電池の再生資源としての利用を促進するために必要な限度において、電源装置等の構造、使用される密閉形蓄電池の取り外し方法などの情報の提供を行うことを趣旨としている。
「血圧計等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」についても密閉形畜電池使用機器製品の違いはあるものの、基本的考え方は上記の解説と同様である。 |
 |
|
|
 |
| |