 |
 |
 |
 |
|
|
 |
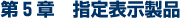 |
| |
<政令>
(指定表示製品)
第5条 法第2条第11項の政令で定める製品は、別表第5の上欄に掲げるとおりとする。
(勧告の対象から除かれる指定表示事業者)
第17条 法第25条第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
二 常時使用する従業員の数が5人以下の会社及び個人であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの
三 常時使用する従業員の数が20人以下の組合等(農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会をいう。次号において同じ。)であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
四 常時使用する従業員の数が5人以下の組合等であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの
五 常時使用する従業員の数が20人以下の民法法人等(民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人、酒造組合、酒販組合、酒造組合連合会、酒販組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合中央会、学校法人、私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の規定により設立された法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、中小企業団体中央会、商工会議所、商工会及び都道府県商工会連合会をいう。)
2 法第25条第1項の政令で定める収入金額は、当該法人又は個人がその事業年度(その期間が1年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後1年ごとに区分した各期間)に行うすべての事業の収入金額の総額とする。
3 法第25条第1項の政令で定める要件は、収入金額が2億4千万円(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行う者にあっては、7千万円)以下であることとする。
(指定表示事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第18条 法第25条第3項の審議会等で政令で定めるものは、別表第5の上欄に掲げる指定表示製品に係る同表の中欄に掲げる指定表示事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第31条 法第39条第1項第4号に定める事項についての主務大臣は、次のとおりとする。
一~五 (略)
六 別表第5の1及び7の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造の事業及び当該指定表示製品であって、輸入されたものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣
七 別表第5の2及び4の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造の事業に係るものについては、農林水産大臣及び経済産業大臣
八 別表第5の2及び4の項の上欄に掲げる指定表示製品であって、輸入されたものの販売の事業に係るものについては、農林水産大臣
九 別表第5の3及び5の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造の事業に係るものについては、財務大臣及び経済産業大臣
十 別表第5の3及び5の項の上欄に掲げる指定表示製品であって、輸入されたものの販売の事業に係るものについては、財務大臣
十一 別表第5の6の項の上欄に掲げる指定表示製品のうち同項の中欄第1号に規定する特定容器包装の製造の事業に係るものについては、経済産業大臣
十二 別表第5の6の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造をその事業の用に供するために発注する事業者(以下「製造発注事業者」という。)が行う事業(同項の中欄第2号及び第3号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品であって輸入されたものの販売の事業に係るものについては、財務大臣
十三 別表第5の6の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造発注事業者が行う事業(同項の中欄第4号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品であって輸入されたものの販売の事業に係るものについては、厚生労働大臣
十四 別表第5の6の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造発注事業者が行う事業(同項の中欄第5号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品であって輸入されたものの販売の事業に係るものについては、農林水産大臣
十五 別表第5の6の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造発注事業者が行う事業(同項の中欄第6号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品であって輸入されたものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣 |
|
| |
| 別表第5(第5条、第18条、第31条関係) |
| 1 塩化ビニル製建設資材(硬質塩化ビニル製の管、雨どい及び窓枠並びに塩化ビニル製の床材及び壁紙をいう。以下この項において同じ。) |
塩化ビニル製建設資材を製造する事業者及び自ら輸入した塩化ビニル製建設資材を販売する事業者 |
産業構造審議会 |
| 2 鋼製又はアルミニウム製の缶(内容積が七リットル未満のものに限る。以下単に「缶」という。)であって、飲料(酒類を除く。以下単に「飲料」という。)が充てんされたもの |
1 缶を製造する事業者 |
産業構造審議会 |
| 2 缶に飲料を充てんする事業者及び飲料が充てんされた缶であって自ら輸入したものを販売する事業者 |
食料・農業・農村政策審議会 |
| 3 缶であって、酒類が充てんされたもの |
1 缶を製造する事業者 |
産業構造審議会 |
| 2 缶に酒類を充てんする事業者及び酒類が充てんされた缶であって自ら輸入したものを販売する事業者 |
国税審議会 |
| 4 ポリエチレンテレフタレート製の容器(内容積が150ミリリットル以上のものに限る。以下「ポリエチレンテレフタレート製容器」という。)であって、飲料又はしょうゆが充てんされたもの |
1 ポリエチレンテレフタレート製容器を製造する事業者 |
産業構造審議会 |
| 2 ポリエチレンテレフタレート製容器に飲料又はしょうゆを充てんする事業者及び飲料又はしょうゆが充てんされたポリエチレンテレフタレート製容器であって自ら輸入したものを販売する事業者 |
食料・農業・農村政策審議会 |
| 5 ポリエチレンテレフタレート製容器であって、酒類が充てんされたもの |
1 ポリエチレンテレフタレート製容器を製造する事業者 |
産業構造審議会 |
| 2 ポリエチレンテレフタレート製容器に酒類を充てんする事業者及び酒類が充てんされたポリエチレンテレフタレート製容器であって自ら輸入したものを販売する事業者 |
国税審議会 |
| 6 特定容器包装(容器包装(商品の容器及び包装であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいう。)のうち、主として紙製のもの又は主としてプラスチック製のものをいい、飲料、しょうゆ又は酒類を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製容器その他主務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。) |
1 特定容器包装(商品の容器であるものとして経済産業省令で定めるものに限る。)を製造する事業者 |
産業構造審議会 |
| 2 その事業(たばこ事業又は塩事業に限る。以下この号において同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者 |
財政制度等審議会 |
| 3 その事業(酒類業に限る。以下この号において同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者 |
国税審議会 |
| 4 その事業(厚生労働大臣の所管に属する事業に限る。以下この号において同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者 |
薬事・食品衛生審議会 |
| 5 その事業(農林水産大臣の所管に属する事業に限る。以下この号において同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者 |
食料・農業・農村政策審議会 |
| 6 その事業(経済産業大臣の所管に属する事業に限る。以下この号において同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者 |
産業構造審議会 |
| 7 密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池(電気量が234キロクーロン以下のものに限る。以下同じ。)、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池(輸入されるものにあっては、プラスチックその他の物質を用いて被覆したものに限り、機器の部分品として輸入されるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。) |
密閉形蓄電池を製造する事業者及び自ら輸入した密閉形蓄電池を販売する事業者 |
産業構造審議会 |
|
| |
(趣旨)
本条は、法第2条第11項、第25条第1項及び第3項、第39条第1項第四号の規定に基づき、指定表示製品及びその関連事項を定めるものである。
(解説)
1.指定の要件
法第2条第11項に基づき、指定表示製品として政令指定する際の要件を以下のように設定し、具体的には別表第5の上欄に掲げる製品を指定した。
a)使用済みとなった後の排出量が多い製品であること(排出量の観点)
b)有用な資源を含む製品であること(有用資源の観点)
c)回収体制等が整備されており、識別を容易にする表示を付することによって分別回収が促進されることが期待できること(効果の観点)
2.指定表示製品、対象事業者の範囲
(1) 塩化ビニル製建設資材
1) 対象製品
政令第5条の規定で定める「塩化ビニル製建設資材(硬質塩化ビニル製の管、雨どい及び窓枠並びに塩化ビニル製の床材及び壁紙をいう。)」とは、それぞれ以下のとおりである。
a)硬質塩化ビニル製の管
建設資材として利用される硬質塩化ビニル製の管をいう。
b)硬質塩化ビニル製の雨どい
建設資材として利用される硬質塩化ビニル製の雨どいをいう。
c)硬質塩化ビニル製の窓枠
建設資材として利用され、主に塩化ビニルで構成される窓枠をいい、室内側のみが硬質塩化ビニルで構成される窓枠を含む。
d)塩化ビニル製の床材
建設資材として利用される塩化ビニル製の床をいう。
e)塩化ビニル製の壁紙
建設資材として利用される塩化ビニル製の壁紙をいう。
2) 対象事業者
塩化ビニル製建設資材の製造事業者及び輸入販売事業者
(2) 飲料が充てんされた鋼製又はアルミニウム製の缶
1) 対象製品
政令別表第5の2の項で定める「缶」とは、日本標準商品分類に掲げる「金属製飲料用缶」(2515)及び「アルミニウム製飲料用缶」(2516)をいう。
2) 対象事業者
缶の製造事業者、缶に飲料を充てんする事業者及び飲料が充てんされた缶の輸入販売事業者(関係する表示の標準となるべき事項を定める省令を参照)
(3) 酒類が充てんされた鋼製又はアルミニウム製の缶
1) 対象製品
(2) 1)に同じ。
2) 対象事業者
缶の製造事業者、缶に酒類を充てんする事業者及び酒類が充てんされた缶の輸入販売事業者(関係する表示の標準となるべき事項を定める省令を参照)
(4) 飲料、しょうゆが充てんされたポリエチレンテレフタレート製の容器
1) 対象製品
ポリエチレンテレフタレート製の容器のうち、内容積が150ミリリットル以上のもの(以下「ポリエチレンテレフタレート製容器」という)。
2) 対象事業者
ポリエチレンテレフタレート製容器の製造事業者、ポリエチレンテレフタレート製容器に飲料、しょうゆを充てんする事業者及び飲料、しょうゆが充てんされたポリエチレンテレフタレート製容器の輸入販売事業者(関係する表示の標準となるべき事項を定める省令を参照)
(5) 酒類が充てんされたポリエチレンテレフタレート製の容器
1) 対象製品
(4) 1)に同じ。
2) 対象事業者
ポリエチレンテレフタレート製容器の製造事業者、ポリエチレンテレフタレート製容器に酒類を充てんする事業者及び酒類が充てんされたポリエチレンテレフタレート製容器の輸入販売事業者(関係する表示の標準となるべき事項を定める省令を参照)
(6) 特定容器包装
1) 対象製品
基本的に紙製・プラスチック製の容器包装を規定する。
政令第5条(別表第5の6の項の上欄)に規定する「商品の容器及び包装」とは、商品に係る容器及び包装に限定するものであり、役務の提供に係るもの(例:クリーニングの袋)は含まない。また、「当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるもの」とは、例えば化粧品の外箱や、デパートの紙袋等を言う。なお、商品の一部であるものや、商品が費消された場合又は分離された場合に不要とはならないもの(例:紅茶等のティーバッグ、テニスラケットのケース、コンパクト・ディスクのプラスチックケース)は含まない。
また、別途指定表示製品として定める「飲料、しょうゆ又は酒類を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製容器」や技術的な観点から表示を付すことが困難なものについて別に主務省令で定めるものを対象から除外する。
2) 対象事業者
特定容器包装の製造事業者(「容器省令」第一号又は第二号に掲げる容器を製造する事業者)、事業の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装を付した商品の輸入販売事業者が表示の義務を負う。(関係する「特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令」を参照)
政令第5条(別表第5の6の項の中欄第2号から6号まで)に規定する「その事業の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者」とは例としてピザの箱の製造を発注するデリバリーピザ店、紙袋や包装紙の製造を発注する菓子メーカー、食品用発泡トレーを発注するスーパーなどが挙げられる。また、カタログ等を参考に容器包装の仕入発注する事業者も当該事業者に当てはまる。容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)上における特定容器(包装)を利用する特定容器(包装)利用事業者の多くが該当する。
なお、販売促進のため、商品製造事業者から酒類等の小売事業者に配布されたレジ袋に関して、当該レジ袋を利用した小売事業者は「特定容器包装の製造を発注する事業者」に該当せず、レジ袋の製造を発注した事業者(商品製造事業者)が該当する。
(7) 密閉形蓄電池
1) 対象製品
政令第5条(別表第五の七の項)で規定する「密閉形蓄電池」とは、以下の蓄電池をいう。
[1]密閉形鉛蓄電池(電気量が234キロクーロン以下のものに限る。)
「密閉形」とは、以下の要件を満たしているものであり、「密閉形鉛蓄電池」とは、日本工業規格に掲げる「小形シール鉛蓄電池」(JIS C8702-1,2,3)及び同等の方式の規格外品、並びに「据置鉛蓄電池」(JIS C8704-2)の一部及び相当品がこれに該当する。
i.蓄電池内部において正極板から発生する酸素を負極板で反応吸収させ、負極板を化学的に放電状態として水素の発生を抑え、補水を必要としない機能を持つこと
ii.規定された使用状態で漏液しない密閉構造であること
iii.安全弁(制御弁)を備えていること
「電気量が234キロクーロン以下のもの」は、定格容量20時間率に換算すると、65Ah以下のものに相当する。
[2]密閉形アルカリ蓄電池
「密閉形アルカリ蓄電池」とは、密閉形のアルカリ蓄電池をいい、日本工業規格に掲げる「密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池」(JIS C8705)及び「密閉形ニッケル・水素蓄電池」(JIS C8708)並びにこれらの相当品がこれに該当する。
[3]リチウム蓄電池
「リチウム蓄電池」とは、日本工業規格に掲げる「リチウム二次電池」(JIS C8711)及び同等の方式の規格外品(代表例:いわゆるリチウムイオン二次電池)をいう。
本政令において、「プラスチックその他の物質を用いて被覆したものに限る」としているのは、プラスチックその他の物質を用いて被覆していない密閉形蓄電池(素電池)は、国内においてプラスチックその他の物質を用いて被覆された後に、最終的な製品として市場に供給されるため、最終的な製品として市場に供給する事業者(アセンブラー又はブランドオーナー)に表示を求めるものとしたことによる。また、「機器の部分品として輸入されるものを除く」としているのは、機器の部分品として輸入される密閉形蓄電池は、通常機器に内蔵されていることから、表示を求めることが経済的に過大な負担を強いることになる恐れがあることによる。
2) 対象事業者
密閉形蓄電池の製造事業者及び輸入販売事業者(関係する表示の標準となるべき事項を定める省令を参照)
3.勧告の対象から除かれる指定表示事業者
法律第25条において主務大臣は、指定表示事業者に対しその表示事項を表示せずに、また遵守事項を遵守しない場合に勧告をすることができる旨が規定されているが、政令第17条ではその勧告の対象から除外される小規模な事業者の規模要件が規定されている。 |
| |
<政令>
第28条 主務大臣は、法第37条第2項の規定により、指定表示事業者に対し、その製造又は販売に係る指定表示製品に係る業務の状況につき、次の事項に関し報告させることができる。
一 当該指定表示製品の種類及び数量その他当該指定表示製品の製造又は販売の業務に関する事項
二 当該指定表示製品に係る表示事項の表示の状況及び遵守事項の遵守の状況
2 主務大臣は、法第37条第2項の規定により、その職員に、指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造又は販売に係る指定表示製品、当該指定表示製品の製造のための設備及び当該指定表示製品に係る表示事項の表示のための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。 |
|
| |
(趣旨)
本条は、第37条第2項の規定に基づく指定表示製品に係る報告徴収又は立入検査を行う際の、報告又は検査の内容を規定したものである。
(解説)
1.法第37条第2項の規定において、指定表示事業者に対する報告徴収及び立入検査は、政令で定めるところにより行うことができるものとされている。本条はこれを受けて定められたものである。
2.具体的な報告内容については、以下のような内容が想定される。
(1) 当該指定表示製品の種類及び数量その他当該指定表示製品の製造又は販売の業務に関する事項
製品の種類・数量、製造工程の状況等
(2) 当該指定表示製品に係る表示事項の表示の状況及び遵守事項の遵守の状況
表示された製品の種類別の数量、製品の種類別の遵守状況等
塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令(経済産業省令第94号) |
| |
<省令>
(表示事項)
第1条 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第24条第1項の主務省令で定める同項第1号に掲げる事項は、塩化ビニル製建設資材(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成3年政令第327号)別表第5の1の項の上欄に規定する塩化ビニル製建設資材をいう。以下同じ。)について、当該塩化ビニル製建設資材の材質に関する事項とする。
(遵守事項)
第2条 法第24条第1項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、塩化ビニル製建設資材を製造する事業者及び自ら輸入した塩化ビニル製建設資材を販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。
一 別表の上欄の指定表示製品の区分ごとに、別記様式に基づき、それぞれ、同表の中欄に定める大きさ以上の大きさの文字及び記号を用いて、同表の下欄に定める表示の方法により、表示をすること。
二 表示を構成する文字及び記号は、塩化ビニル製建設資材の模様及び色彩と比較して容易に識別できること。
三 第一号に規定する表示に装飾を施すに当たっては、前号に反しないものとすること。
附 則
(施行期日)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年3月31日までに製造され、又は輸入された塩化ビニル製建設資材については、法第25条、第37条第2項及び第42条から第44条までの規定は、適用しない。 |
|
| |
| (別表(第2条関係) |
| 指定表示製品の区分 |
文字及び記号の大きさ |
表示の方法 |
| 1 硬質塩化ビニル製の管 |
硬質塩化ビニル製の管の外径が80ミリメートル未満のものについては、14ポイント(日本工業規格Z8305に規定するポイントをいう。以下同じ。)硬質塩化ビニル製の管の外径が80ミリメートル以上のものについては20ポイント |
その表面に、長さ1メートルごとに、1箇所以上、印刷し、ラベルをはり、又は刻印すること。 |
| 2 硬質塩化ビニル製の雨どい |
10ポイント |
その表面に、長さ1メートルごとに、1箇所以上、印刷し、ラベルをはり、又は刻印すること。 |
| 3 硬質塩化ビニル製の窓枠 |
10ポイント |
その表面に、1箇所以上、印刷し、ラベルをはり、又は刻印すること。 |
| 4 塩化ビニル製の床材 |
20ポイント |
シート状のものについては、その表面に、居室、廊下その他の区画ごとに、一箇所以上、ラベルをはり、若しくは刻印すること、又はその裏面に、面積一平方メートルごとに、一箇所以上、印刷し、若しくは刻印すること。タイル状のものについては、その表面に、居室、廊下その他の区画ごとに、一箇所以上、ラベルをはり、若しくは刻印すること、又はその裏面に、一箇所以上、印刷し、若しくは刻印すること。 |
| 5 塩化ビニル製の壁紙 |
20ポイント |
その裏面に、面積1平方メートルごとに、1箇所以上、印刷し、又はラベルをはること。 |
|
| |
(趣旨)
法第24条に基づき、政令第5条の規定により指定した塩化ビニル製建設資材(硬質塩化ビニル製の管、雨どい及び窓枠並びに塩化ビニル製の床材及び壁紙)についての表示の標準となるべき事項を規定したものである。
(解説)
1.本省令において、「塩化ビニル製建設資材を製造する事業者」とは、製品の組立・加工を最終的に行い製品を市場に供給する事業者(アセンブラー)のことをいう。ただし、材料の加工、部品の組立といった物理的な製造行為は行わないものの自らの商標を付せて製品を市場に供給する事業者(ブランドオーナー)が併存する場合は、どちらが製造事業者に該当するかは当該判断の基準による取組に関する影響力、製品の企画・設計に関する支配及び指示の状況、自己の商標の使用等についてを総合的に評価し判断するものである。また、「自ら輸入した塩化ビニル製建設資材を販売する事業者」とは、製品を輸入して市場に供給する事業者のことをいい、単に輸入事務を代行する事業者は含まない。
2.本省令第2条は、塩化ビニル製建設資材を製造する事業者及自ら輸入した塩化ビニル製建設資材を販売する事業者についての遵守事項を定めている。
(1) 塩化ビニル製建設資材の製品ごとに定められている表示方法で、定める様式に基づき表示をすること。
(2) 表示を構成する文字及び記号は、製品の模様及び色彩と比較して容易に識別できるようにすること。
鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令(平成3年大蔵省、農林水産省、通商産業省令第1号) |
| |
<省令>
(表示事項)
第1条 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第24条第1項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項は、鋼製又はアルミニウム製の缶(内容積が7リットル未満のものに限る。以下単に「缶」という。)であって、飲料(酒類を含む。以下同じ。)が充てんされたものについて、当該缶の材質に関する事項とする。
(遵守事項)
第2条 法第24条第1項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、缶を製造する事業者及び缶に飲料を充てんする事業者並びに飲料が充てんされた缶であって、自ら輸入したものを販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。
一 別表の上欄の指定表示製品の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、缶の胴に、1箇所以上、印刷し、又はラベルをはることにより、表示をすること。
二 表示を構成する文字及び記号は、缶の全体の模様及び色彩と比較して鮮明であり、かつ、容易に識別できること。
三 第一号に規定する表示に装飾を施すに当たっては、前号に反しないものとすること。
附 則
1 (略)
(表示の特例)
2 第2条第一号の規定にかからわず、缶であって、飲料が充てんされたものの製造又は販売の数量が少ないため、缶の胴に表示をすることが困難な場合にあっては、当分の間、様式1及び様式3中「17mm」とあるのは「10mm」と、「10mm」とあるのは「6mm」と、「14ポイント」とあるのは「10ポイント」と、様式2及び様式4中「20mm」とあるのは「10mm」と、「12mm」とあるのは「6mm」と、「16ポイント」とあるのは「10ポイント」と読み替えて、缶の胴以外の部分に表示をすることができる。
3 (略) |
|
| |
(趣旨)
法第24条に基づき、政令第5条の規定により指定した鋼製又はアルミニウム製の缶であって飲料が充てんされたものの表示の基準を示すものである。
(解説)
1.本省令第1条において、内容量が7リットル未満のものに限ったのは、これ以外の金属缶については、専ら業務用に使用され、材質も関係者にとってはよく知られており、一定の回収ルートを通じて再生利用されていることから、本法に基づき表示の義務を新たに課す必要がないためである。
2.本省令第2条において、表示箇所の数は「1箇所以上」と規定しているが、基本的には、2箇所の表示を缶胴の対局に位置するよう行うことが望ましい。
3.本省令第2条において、ラベルをはることにより表示を行う場合には、缶が分別されるまで当該ラベルが容易にはがれることのないような方法で行う必要がある。
4.本省令附則は、製造又は販売の数量が少ないため、缶の胴に表示をすることが困難な場合について、表示の特例を定めるものである。例えば外国市場向けに海外で製造された缶入り飲料を少量輸入するといった場合においては、本法により義務づけられる表示をラベルにより行うこととなるが、この場合において、ラベルを缶胴に貼付することとした場合には、缶をひとつずつ箱から取り出した上で行わなければならず、コストの大幅増をもたらすことから、結果的に外国製品にとっての輸入障壁となる恐れがある。
このため、本条では、一定の場合について、缶の胴以外の部分、すなわち、缶底部分への表示を特例として認めることとした。その際、缶底の面積には限界があること、また、本法以外にも表示義務を課す法律があることから、表示の大きさについても特例を認めることとしている。
ポリエチレンレテフタレート製の容器であって、飲料又はしょうゆが充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令(平成5年大蔵省、農林水産省、通商産業省令第1号) |
| |
<省令>
(表示事項)
第1条 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第24条第1項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項は、ポリエチレンテレフタレート製の容器(内容積が150ミリリットル以上のものに限る。以下単に「容器」という。)であって、飲料(酒類を含む。以下同じ。)又はしょうゆが充てんされたものについて、当該容器の材質に関する事項とする。
(遵守事項)
第2条 法第24条第1項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、容器を製造する事業者及び容器に飲料又はしょうゆを充てんする事業者並びに飲料又はしょうゆが充てんされた容器であって、自ら輸入したものを販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。
一 別表の上欄の指定表示製品の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、容器の底部又は側部に、1箇所以上、刻印し、かつ、容器の側部に、1箇所以上、印刷し、又はラベルをはることにより、表示をすること。ただし、飲料又はしょうゆが充てんされた容器であって、自ら輸入したものを販売する事業者については刻印による表示を要しない。
二 表示を構成する数字、文字及び記号は、容器の全体の模様及び色彩と比較して鮮明であり、かつ、容易に識別できること。
三 第一号に規定する表示に装飾を施すに当たっては、前号に反しないものとすること。 |
|
| |
(趣旨)
法第24条に基づき、政令第5条の規定により指定したポリエチレンテレフタレート製の容器であって飲料又はしょうゆが充てんされたものの表示の基準を示すものである。
(解説)
本省令第2条において、飲料又はしょうゆが充てんされた容器であって、自ら輸入したものを販売する事業者については、事業者への過度の負担となることを避けるため、刻印による表示は免除されている。ただし、この場合であっても、印刷し、又はラベルをはることにより表示をする必要はある。
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第5の6の項の上欄に規定する特定容器包装に関する省令(平成13年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第1号) |
| |
<省令>
(定義)
第1条 この省令において「紙製容器包装等」とは、主として紙製の容器包装(主として段ボール製の容器包装又は主として紙製の容器であって飲料若しくは酒類を充てんするためのもの(原材料としてアルミニウムが利用されているものを除く。)を除く。)又は主としてプラスチック製の容器包装(飲料、しょうゆ又は酒類を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器を除く。)をいう。
2 この省令において「無地の容器包装」とは、その事業(財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣の所管に属するものに限る。以下同じ。)の用に供するために容器包装の製造を発注する事業者が当該事業の用に供する時、又は容器包装に入れられ若しくは容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者がその販売をする時に、その表面に印刷がされていない又はラベルがはられていない容器包装(その製造工程に、刻印をすることが可能な成形の工程を含むものを除く。)をいう。
3 この省令において「表示不可能容器包装」とは、特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令(平成13年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第2号)別表第2の上欄の指定表示製品の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、その表面に印刷し、ラベルをはり又は刻印することにより表示をすることが、素材上、構造上その他やむを得ない理由により不可能な容器包装をいう。
4 この省令において「関連容器包装」とは、容器包装に入れられ若しくは容器包装で包まれた商品を入れ又は包む当該容器包装以外の容器(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第5の2から5までの項の上欄に掲げる指定表示製品を構成する容器に限る。)又は紙製容器包装等をいう。
(令別表第5の6の項の上欄の主務省令で定める容器包装)
第2条 令別表第5の6の項の上欄の主務省令で定める容器包装は、次のとおりとする。
一 事業者が専らその事業活動に伴い費消する商品を入れ又は包むための容器包装
二 主として段ボール製の容器包装
三 主として紙製の容器であって飲料又は酒類を充てんするためのもの(原材料としてアルミニウムが利用されているものを除く。)
四 飲料、しょうゆ又は酒類を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器(内容積が150ミリリットル未満のものに限る。)
五 無地の容器包装又は表示不可能容器包装である紙製容器包装等(当該紙製容器包装等の関連容器包装がある場合にあっては、当該関連容器包装のすべてが、無地の容器包装(紙製容器包装等に限る。)又は表示不可能容器包装であるものに限る。)
六 紙製容器包装等(印刷又は刻印がなされているものに限り、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第5の6の項の中欄第1号に規定する特定容器包装を定める省令(平成13年経済産業省令第52号。)第一号及び第二号に掲げる容器を除く。)であって、小売販売(消費者に対する販売をいう。)を業として行う者が販売する時に商品を入れ又は包むもの(特定の商品を入れ又は包むために製造されるものを除く。)のうち、その表面積が1,300平方センチメートル以下であるもの
七 紙製容器包装等に入れられ又は紙製容器包装等で包まれた商品であって、自ら輸入したものを販売する事業者(外国において自ら当該紙製容器包装等を製造する者若しくはその製造を発注する者又はこれらの者に直接若しくは間接に当該紙製容器包装等の素材、構造、自己の商標の使用等に関する指示を行う者を除く。)の販売に係る当該紙製容器包装等又は当該紙製容器包装等に入れられ若しくは当該紙製容器包装等で包まれた商品を入れ若しくは包む当該紙製容器包装等以外の容器包装の表面に、印刷し、ラベルをはり又は刻印することにより日本語が表示されていないもの
附 則
この省令は、平成13年4月1日から施行する。 |
|
| |
(趣旨)
法第24条に基づき、政令第5条の規定により指定した特定容器包装(紙製・プラスチック製の容器包装)のうち、表示義務の対象外とするものを定めるものである。本省令第1条では必要な定義を、本省令第2条では表示義務の対象外の容器包装を具体的に規定している。
(解説)
1.本省令第1条第1項中「紙製容器包装等」とは、1)段ボール製の容器包装、2)アルミニウムが利用されていない飲料又は酒類用の紙製パック及び3)飲料、しょうゆ又は酒類を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製容器を除いた特定容器包装(紙製・プラスチック製の容器包装)をいう。
2.本省令第1条第2項中「無地の容器包装」とは、容器包装の利用及び輸入販売段階で、容器包装の表面に印刷又はラベルが施されないもので、容器包装の製造工程に、刻印をすることが可能な成形の工程を有さない容器包装をいう。
なお、以下のものについては、その製造段階において、商品の容器包装として利用されることが明らかでないことから、識別表示を付すことが適当でないため、本省令第1条第2項中の「その表面に印刷がされていない又はラベルがはられていない容器包装(その製造工程に、刻印をすることが可能な成形の工程を含むものを除く。)」に該当するものとして取り扱う。
1) 商品の容器包装以外にも使用される汎用品を用いて加工した容器包装
例えば、花屋が、文房具店などで取り扱われている消費者向けの「商品」としての全面水玉模様の汎用包装紙を購入し、新たにその包装紙に印刷又はラベルを施さず、刻印が可能な成形工程を経ないで、販売する花を包む場合。
2) 市販品を転用した容器包装
例えば、菓子製造事業者が、市販品の全面ストライプ模様の付いたプラスチック製コップを購入し、そのプラスチック製コップに新たに印刷又はラベルを施さず、刻印が可能な成形工程を経ないで、菓子を詰める容器包装に転用した場合。
3.本省令第1条第4項中「関連容器包装」とは、特定容器包装が付されたものと同一の商品に付した別の容器包装であり、政令第5条(別表第5の上欄)で規定され、指定表示製品となっている。
1) 飲料又は酒類が充てんされた鋼製又はアルミニウム製の缶
2) 飲料、しょうゆ又は酒類が充てんされたポリエチレンテレフタレート製の容器
3) 本省令第1条第1項に規定する「紙製容器包装等」の容器包装をいう。
第2条では、紙製容器包装等のうち、技術的な観点等から表示の義務の対象外とするものを定めている。
1.本省令第2条第一号は、専ら事業活動によって費消される容器包装を指し、表示義務の対象外となる。一部でも消費者向けに販売される商品等の容器包装である場合は表示義務の対象となる。
2.本省令第2条第三号は、アルミニウムが利用されていない飲料又は酒類用の紙製パックを指し、表示義務の対象外となる。アルミニウムが利用されている飲料又は酒類用の紙製パックについては表示義務の対象となる。
3.本省令第2条第五号は、無地の容器包装又は表示不可能容器包装を指し、表示義務の対象外となる。ただし、関連容器包装がある場合は、その全てが、無地の容器包装である紙製容器包装等、又は表示不可能容器包装である場合が該当する。関連容器包装に無地でない紙製容器包装等であってかつ表示が可能な容器包装が含まれる場合は表示の義務対象となる。
4.本省令第2条第六号は、百貨店等の小売販売を業として行う事業者が消費者に対して販売する時に商品を包む包装のうち、その表面積が1,300cm2以下であるものをいい、表示義務の対象外となる。ただし、特定の商品を包むために専用に製造された包装は表示の義務対象となる。
5.本省令第2条第七号は、輸入販売事業者が、自ら外国で当該商品の紙製容器包装等の製造又は製造の発注を行っていない場合、また他の事業者に対して当該商品の素材、構造、自己の商標の使用等に関する指示を行っていない場合であって、かつ、当該紙製容器包装等又はその同一の商品を入れる又は包む別の容器包装に日本語の表示がされていないものを表示義務の対象外とするものである。
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第5の6の項の中欄第1号に規定する特定容器包装を定める省令(平成13年経済産業省令第52号) |
| |
<省令>
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第5の6の項の中欄第1号に規定する特定容器包装のうち商品の容器であるものとして経済産業省令で定めるものは、次に掲げる商品の容器とする。
一 特定容器包装(商品の容器であるものに限る。)のうち主として紙製のものであって、次に掲げるもの
イ 箱及びケース
ロ カップ形の容器及びコップ
ハ 皿
ニ 袋
ホ イからニまでに掲げるものに準ずる構造、形状を有する容器
ヘ 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの
ト 容器に入れられた商品の保護又は固定のために、加工、当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器
二 特定容器包装(商品の容器であるものに限る。)のうち主としてプラスチック製のものであって、次に掲げるもの
イ 箱及びケース
ロ 瓶
ハ たる及びおけ
ニ カップ形の容器及びコップ
ホ 皿
ヘ くぼみを有するシート状の容器
ト チューブ状の容器
チ 袋
リ イからチまでに掲げるものに準ずる構造、形状を有する容器
ヌ 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの
ル 容器に入れられた商品の保護又は固定のために、加工、当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器
附 則
この省令は、平成13年4月1日から施行する。 |
|
| |
(趣旨)
法第24条に基づき、政令第5条の規定により指定した特定容器包装のうち、製造事業者に表示義務がかかる容器について規定したものである。
特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令(平成13年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第2号) |
| |
<省令>
(表示事項)
第1条 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第24条第1項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項は、特定容器包装(容器包装(商品の容器及び包装であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいう。)のうち、主として紙製のもの又は主としてプラスチック製のものをいい、飲料、しょうゆ又は酒類を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製容器及び資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第5の6の項の上欄に規定する特定容器包装に関する省令(平成13年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第1号。以下「特定容器包装省令」という。)第2条に規定するものを除く。以下同じ。)について、当該特定容器包装の材質に関する事項とする。
(遵守事項)
第2条 法第24条第1項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、別表第1の上欄に掲げる者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
附 則
(施行期日)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる特定容器包装については、法第25条、第37条第2項及び第42条から第44条までの規定は、適用しない。
一 平成15年3月31日までに製造された特定容器包装
二 特定容器包装に入れられ又は特定容器包装で包まれた商品(平成15年3月31日までに輸入されたものに限る。)を入れ又は包んだ当該特定容器包装 |
|
| |
| 別表第1(第2条関係) |
| 1 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第5の6の項の中欄第1号に規定する特定容器包装を定める省令(平成13年経済産業省令第52号。以下「容器省令」という。)第一号又は第二号に掲げる容器を製造する事業者(収益事業を行う者に限る。以下同じ。)及びその事業(財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣の所管に属する事業に限る。以下同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者 |
1 別表第2の上欄の指定表示製品の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、特定容器包装の表面に、1箇所以上、印刷し、ラベルをはり又は刻印することにより、表示をすること。 |
| 2 特定容器包装と同時に廃棄されると認められる一体容器包装(特定容器包装に入れられ又は特定容器包装で包まれた商品を入れ又は包む当該特定容器包装以外の容器包装をいう。以下同じ。)がある場合であって、当該一体容器包装の表面に、1箇所以上、印刷し、ラベルをはり又は刻印することにより別表第2の上欄の指定表示製品の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づく表示をするとともに、当該表示に当該特定容器包装の役割名(当該特定容器包装に係る商品の容器包装全体における当該特定容器包装を示すふた、内袋その他の部分の名称をいう。以下同じ。)を併記するときは、前号の規定にかかわらず、同号の表示を省略することができること。 |
| 3 無地の容器包装(特定容器包装省令第1条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)である特定容器包装又は第1号の表示をすることが素材上、構造上その他やむを得ない理由により不可能な特定容器包装については、当該特定容器包装の一体容器包装がある場合であって、当該一体容器包装の表面に、1箇所以上、印刷し、ラベルをはり又は刻印することにより別表第2の上欄の指定表示製品の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づく表示をするとともに、当該表示に当該特定容器包装の役割名を併記するときは、同号の規定にかかわらず、同号の表示を省略することができること。この場合において、当該特定容器包装と同時に廃棄されると認められる一体容器包装があるときは、他の一体容器包装に優先して当該一体容器包装の表面に表示及び併記をしなければならない。 |
| 4 表示を構成する文字及び記号は、特定容器包装全体の模様及び色彩と比較して鮮明であり、かつ、容易に識別できること。 |
| 5 第1号から第3号までの規定による表示又は併記に装飾を施すに当たっては、前号に反しないものとすること。 |
| 2 特定容器包装に入れられ又は特定容器包装で包まれた商品であって、自ら輸入したものを販売する事業者(外国において自ら当該特定容器包装を製造する者若しくはその製造を発注する者又はこれらの者に直接若しくは間接に当該特定容器包装の素材、構造、自己の商標の使用等に関する指示を行う者に限る。) |
1 別表第2の上欄の指定表示製品の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、特定容器包装の表面に、1箇所以上、印刷し、ラベルをはり又は刻印することにより、表示をすること。 |
| 2 特定容器包装と同時に廃棄されると認められる一体容器包装がある場合であって、当該一体容器包装の表面に、1箇所以上、印刷し、ラベルをはり又は刻印することにより別表第2の上欄の指定表示製品の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づく表示をするとともに、当該表示に当該特定容器包装の役割名を併記するときは、前号の規定にかかわらず、同号の表示を省略することができること。 |
| 3 無地の容器包装である特定容器包装又は第1号の表示をすることが素材上、構造上その他やむを得ない理由により不可能な特定容器包装については、当該特定容器包装の一体容器包装がある場合であって、当該一体容器包装の表面に、1箇所以上、印刷し、ラベルをはり又は刻印することにより別表第2の上欄の指定表示製品の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づく表示をするとともに、当該表示に当該特定容器包装の役割名を併記するときは、同号の規定にかかわらず、同号の表示を省略することができること。この場合において、当該特定容器包装と同時に廃棄されると認められる一体容器包装があるときは、他の一体容器包装に優先して当該一体容器包装の表面に表示及び併記をしなければならない。 |
| 4 表示を構成する文字及び記号は、特定容器包装全体の模様及び色彩と比較して鮮明であり、かつ、容易に識別できること。 |
| 5 第1号から第3号までの規定による表示又は併記に装飾を施すに当たっては、前号に反しないものとすること。 |
| 3 特定容器包装又は当該特定容器包装の一体容器包装の表面に、印刷し、ラベルをはり又は刻印することにより日本語が表示されている場合における当該特定容器包装に係る商品であって、自ら輸入したものを販売する事業者(外国において自ら当該特定容器包装を製造する者若しくはその製造を発注する者又はこれらの者に直接若しくは間接に当該特定容器包装の素材、構造、自己の商標の使用等に関する指示を行う者を除く。) |
1 1箇所以上、印刷し、ラベルをはり又は刻印することにより日本語が表示されている特定容器包装若しくは当該特定容器包装の一体容器包装の表面に、別表第2の上欄の指定表示製品の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、1箇所以上、印刷し、ラベルをはり又は刻印することにより、表示をすること。ただし、当該表示をされる容器包装が、当該特定容器包装の一体容器包装である場合は、当該一体容器包装の表面に、1箇所以上、印刷し、ラベルをはり又は刻印することにより、当該表示に当該特定容器包装の役割名を併記しなければならない。 |
| 2 表示を構成する文字及び記号は、特定容器包装全体の模様及び色彩と比較して鮮明であり、かつ、容易に識別できること。 |
| 3 第1号に規定する表示に装飾を施すに当たっては、前号に反しないものとすること。 |
|
| |
(趣旨)
法第24条に基づき、政令第5条の規定により指定した特定容器包装についての表示の標準となるべき事項を規定したものである。
(解説)
1.本省令別表第1の1の項は、特定容器包装のうちの容器の製造事業者及びその特定容器包装の製造発注事業者についての遵守事項を定めている。
(1) 定める様式に基づき、特定容器包装の表面に表示をすること。「表面」とは、商品に容器包装を付した状態での外側の面をいう。
(2) 特定容器包装と同時に廃棄される別の容器包装(鋼製又はアルミニウム製の缶、ポリエチレンテレフタレート製容器、主として紙製の容器包装、主としてプラスチック製の容器包装、主として段ボール製の容器包装、木箱等)がある場合であって、当該別の容器包装の表面に表示及び部位の名称を併記するときは、当該特定容器包装自体への表示を省略することができる。
(3) 特定容器包装のうち、無地の容器包装又は表示が不可能な容器包装については、同一の商品に係る当該容器包装とは別の容器包装の表面に表示及び部位の名称を併記する場合は当該特定容器包装自体への表示を省略することができる。この場合に、同時に廃棄される別の容器包装がある場合にあっては、その別の容器包装にそれ以外の別の容器包装に対して優先して表示をすること。
2.別表第1の2の項は、特定容器包装に入れられ又は包まれた商品の輸入販売事業者(外国で自ら当該特定容器包装を製造している者若しくは製造発注をしている者又はこれらの者に直接、間接に当該特定容器包装の素材、構造等について指示をしている者に限る。)についての遵守事項を定めている。
(1) 定める様式に基づき、特定容器包装の表面に表示をすること。
(2) 特定容器包装と同時に廃棄される別の容器包装がある場合であって、当該別の容器包装の表面に表示及び部位の名称を併記するときは、当該特定容器包装自体への表示を省略することができる。
(3) 特定容器包装のうち、無地の容器包装又は表示が不可能な容器包装については、同一の商品に係る当該容器包装とは別の容器包装の表面に表示及び部位の名称を併記する場合は当該特定容器包装自体への表示を省略することができる。この場合に、同時に廃棄される別の容器包装がある場合にあっては、その別の容器包装にそれ以外の別の容器包装に対して優先して表示をすること。
3.別表第1の3の項は、特定容器包装又は特定容器包装が付されているものと同一の商品に付した別の容器包装に日本語が表示されている場合の当該特定容器包装に入れ又は包む商品の輸入販売事業者(外国で自ら当該特定容器包装を製造している者、若しくは製造発注をしている者又はこれらの者に直接、間接に当該特定容器包装の素材、構造等について指示をしている者を除く。)についての遵守事項を定めている。
定める様式に基づき、特定容器包装又は特定容器包装が付されているものと同一の商品を入れた別の容器包装の表面に表示をすること。ただし、特定容器包装が付されているものと同一の商品を入れた別の容器包装に表示する場合はその部位の名称を併記すること。
密閉形蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令(平成5年6月30日経済産業省令第33号) |
| |
<省令>
(表示事項)
第1条 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第24条第1項の主務省令で定める同項第1号に掲げる事項は、密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池(電気量が234キロクーロン以下のものに限る。以下同じ。)、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池(リチウムイオン蓄電池に限る。以下同じ。)をいう。以下同じ。)について、当該密閉形蓄電池の極板の材質に関する事項とする。
(遵守事項)
第2条 法第24条第1項の主務省令で定める同項第2号に掲げる事項は、密閉形蓄電池を製造する事業者及び自ら輸入した密閉形蓄電池(プラスチックその他の物質を用いて被覆したものに限る。)を販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。
一 別表の上欄の指定表示製品の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、文字及び記号を、プラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形蓄電池にあっては、その表面に、一箇所以上、印刷し、又はラベルをはることにより、その他の密閉形蓄電池にあっては、その表面に、一箇所以上、印刷し、ラベルをはり、又は刻印することにより、表示をすること。
二 表示を構成する文字及び記号は、密閉形蓄電池の全体の模様及び色彩と比較して鮮明であり、かつ、容易に識別できること。
三 表示を構成する文字及び記号は隣接していること。
四 第1号に規定する表示に装飾を施すに当たっては、第2号に反しないものとすること。
附 則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 (省略)
附 則(平成13年3月28日経済産業省令第95号)
(施行期日)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年3月31日までに製造され、又は輸入された密閉形鉛蓄電池、密閉形アルカリ蓄電池(密閉形ニッケル・水素蓄電池に限る。)又はリチウム蓄電池については、法第25条、第37条第2項及び第42条から第44条までの規定は、適用しない。 |
|
| |
| 別表(第2条関係) |
| 指定表示製品の区分 |
様式 |
| プラスチックその他の物質を用いて被覆されない密閉形鉛蓄電池及びプラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形鉛蓄電池であって高さが10ミリメートル未満のもの |
様式1 |
| プラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形鉛蓄電池であって高さが10ミリメートル以上のもの |
様式2 |
| プラスチックその他の物質を用いて被覆されない密閉形アルカリ蓄電池(密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池に限る。以下この項及び次項において同じ。)及びプラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形アルカリ蓄電池であって高さが10ミリメートル未満のもの |
様式3 |
| プラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形アルカリ蓄電池であって高さが10ミリメートル以上のもの |
様式4 |
| プラスチックその他の物質を用いて被覆されない密閉形アルカリ蓄電池(密閉形ニッケル・水素蓄電池に限る。以下この項及び次項において同じ。)及びプラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形アルカリ蓄電池であって高さが10ミリメートル未満のもの |
様式5 |
| プラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形アルカリ蓄電池であって高さが10ミリメートル以上のもの |
様式6 |
| プラスチックその他の物質を用いて被覆されないリチウム蓄電池及びプラスチックその他の物質を用いて被覆したリチウム蓄電池であって高さが10ミリメートル未満のもの |
様式7 |
| プラスチックその他の物質を用いて被覆したリチウム蓄電池であって高さが10ミリメートル以上のもの |
様式8 |
|
| |
(趣旨)
法第24条に基づき、政令第5条の規定により指定した密閉形蓄電池についての表示の標準となるべき事項を規定したものである。
(解説)
1.本省令において「密閉形蓄電池を製造する事業者」とは、製品の組立・加工を最終的に行い製品を市場に供給する事業者(アセンブラー)のことをいう。ただし、材料の加工、部品の組立といった物理的な製造行為は行わないものの自らの商標を付せて製品を市場に供給する事業者(ブランドオーナー)が併存する場合は、どちらが製造事業者に該当するかは当該判断の基準による取組に関する影響力、製品の企画・設計に関する支配及び指示の状況、自己の商標の使用等についてを総合的に評価し判断するものである。また、「自ら輸入した密閉形蓄電池を販売する事業者」とは、製品を輸入して市場に供給する事業者のことをいい、単に輸入事務を代行する事業者は含まない。
2.本省令第2条は、密閉形蓄電池を製造する事業者及び自ら輸入した密閉形蓄電池を販売する事業者についての遵守事項を定めている。
(1) 密閉形蓄電池の種類ごとに定める様式に基づき、密閉形蓄電池の表面に表示をすること。
(2) 表示を構成する文字及び記号は、鮮明かつ容易に識別できるようにすること。なお、表示を行うに当たっては、(社)電池工業会が作成した「小形充電式電池の識別表示ガイドライン」を参照されたい。 |
| |
 |
|
|
 |
| |