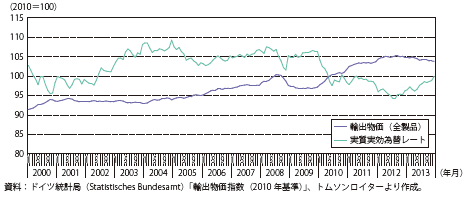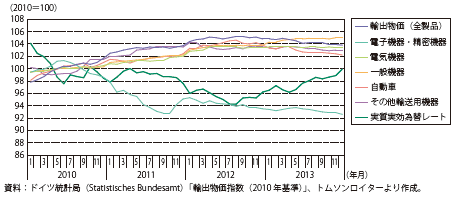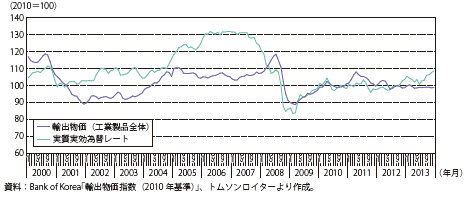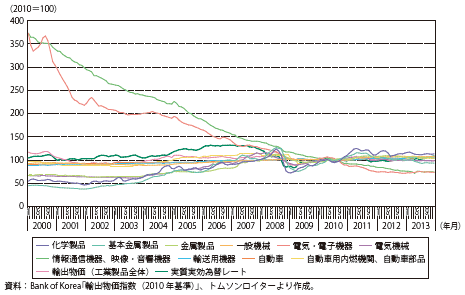- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2014

- 白書2014(HTML版)

- 第1部 第2章 第3節 為替動向と企業行動及び輸出数量への影響
第3節 為替動向と企業行動及び輸出数量への影響
ここでは、為替動向と生産拠点や輸出価格に関する企業行動、輸出数量への影響について見ていく。
1.為替動向と生産拠点に関する企業行動
まず、為替動向と生産拠点に関する企業行動の関係について見ていく。
「為替変動に対する企業の価格設定行動等についての調査分析」(2014)によると、2008年半ばからの円高方向への動きの中、国内の設備投資を抑制した企業、国内生産・輸出採算が合わなくなったため海外生産シフトを進めた企業は、輸送用機器や電気機器などで多くなっている(第Ⅰ-2-3-1図)。
第Ⅰ-2-3-1図 経営戦略への影響(2008年半ば以降(為替は円高方向に推移))
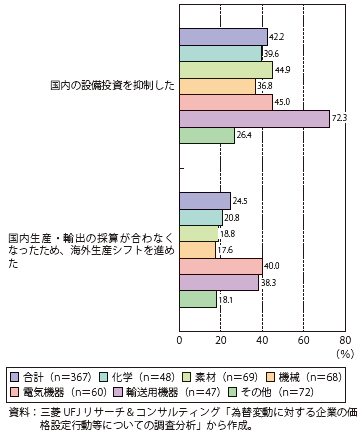
2012年11月以降円安方向に推移する中、国内の生産設備投資計画を変更していない企業の割合は82.6%、拡充・増強した企業は10.9%となっている。一方、海外の生産設備投資計画に関しては、海外に生産拠点を持つ企業の約4分の3が変更せず、約4分の1が拡充・増強している。輸送用機器で拡充・増強している企業の割合が大きい(第Ⅰ-2-3-2図、第Ⅰ-2-3-3図)。
第Ⅰ-2-3-2図 国内生産設備への影響(2012年11月以降(為替は円安方向に推移))
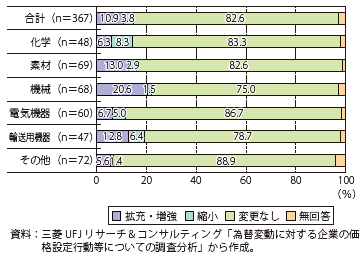
第Ⅰ-2-3-3図 海外生産設備への影響(2012年11月以降(為替は円安方向に推移))
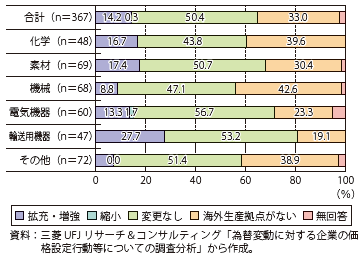
円安方向へ推移する中においても海外の生産設備投資計画を拡充または変更しない上位の理由としては、「海外需要の伸びが期待できる」点や「為替変動に企業業績が左右される事のないように、現地生産・現地販売を進めている」点となっている。業種別に見ると、電気機器や輸送用機器は「為替変動に企業業績が左右される事のないように、現地生産・現地販売を進めている」点を他業種に比べ多く理由としてあげている一方で、化学は「人口減少によって国内市場の縮小が見込まれるため、為替変動に関わらず海外シフトを進めている」点を理由としてあげている割合が他の理由よりも多くなっている(第Ⅰ-2-3-4図)。
第Ⅰ-2-3-4図 円安方向に推移する中でも海外生産設備投資計画を拡充または変更しない理由(複数回答、上位3つ)
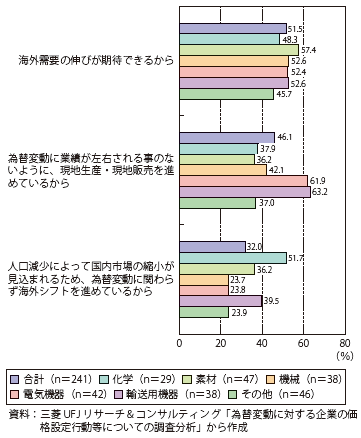
2.為替動向と輸出価格に関する企業行動
次に、為替動向と輸出価格に関する企業行動の関係について見ていく。
2000年代の為替動向と輸出物価(契約通貨ベース)の推移を見てみると、2005年から2007年、2012年末から2013年にかけて為替が円安方向に動く中で、輸出物価はやや低下の動きも見られるがその動きは小さい。また、2008年半ば以降円高方向に推移する中においても、輸出物価は余り上昇していない。このように、円安・円高のいずれの方向に推移しても、輸出物価は為替動向に連動した変化を余り見せていない。(第Ⅰ-2-3-5図)。
第Ⅰ-2-3-5図 実質実効為替レートと輸出物価(全製品・契約通貨ベース)の動き
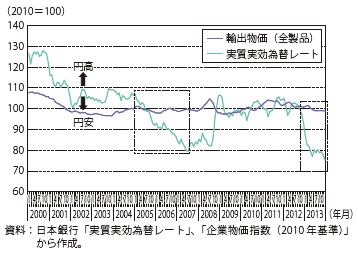
2000年代の品目別輸出物価(契約通貨ベース)の推移を見ても、為替動向と連動して変化する傾向はほとんど見られない。電気・電子機器については、世界的な市場価格低下の動きに伴って、輸出価格が低下している動きが見られる(第Ⅰ-2-3-6図)。
第Ⅰ-2-3-6図 実質実効為替レートと輸出物価(品目別・契約通貨ベース)の動き
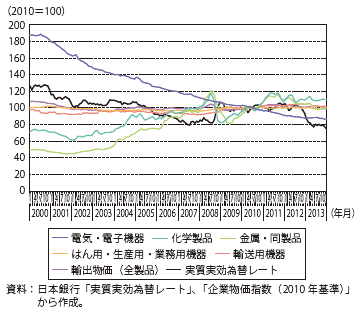
2012年から2013年にかけての動きについて、更に細分化した品目別で見ても、自動車用内燃機関・自動車部品、金属・同製品、情報通信機器等では、2013年の円安方向への動きに伴い輸出物価がやや低下しているが、現時点では多くの品目では為替動向と連動した価格変化の動きは見られない(第Ⅰ-2-3-7図)。
第Ⅰ-2-3-7図 実質実効為替レートと輸出物価(品目別・契約通貨ベース)の動き(2012年~2013年)
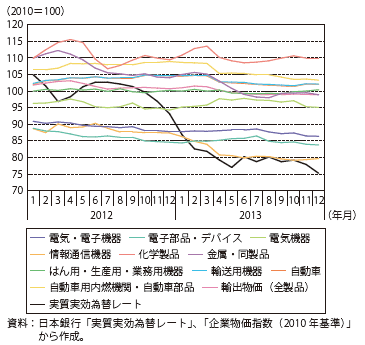
次にアンケート結果に基づき企業行動を見ていくと、2008年半ば以降、円高方向に推移する中で、全産業ベースで輸出価格を引き上げた企業は11.6%、輸出価格をほとんど変えなかった企業は71.6%となっている(第Ⅰ-2-3-8図)。
第Ⅰ-2-3-8図 主要輸出製品の契約通貨建て輸出価格の改定(2008年半ばから2010年末(為替は円高方向に推移))

2008年半ば以降、円高方向に推移する中、輸出価格の改定を行わなかった理由としては、化学や素材では、「競合他社との価格競争が厳しく、輸出価格を引き上げると売上の減少が見込まれた」点を理由としている割合が高く、輸送用機器や機械では、「価格改定は製品のモデルチェンジ等のタイミングで行っている」点を理由としている割合も高くなっている(第Ⅰ-2-3-9図)。
第Ⅰ-2-3-9図 輸出価格の改定を行わなかった理由(2008年半ばから2010年末(為替は円高方向に推移))
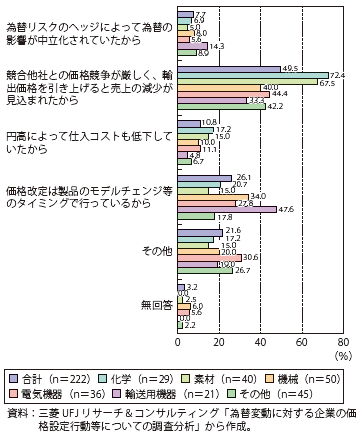
2012年11月以降の円安方向に推移する中、企業規模、輸出額によらず企業数でみると、現在までのところ輸出価格を引き下げた企業は全産業で見ると11.0%、輸出価格をほとんど改定していない企業は78.1%となっている。この円安方向への動きが見られる中、輸出価格改定を行っていない企業のうち87.2%が現時点では、輸出価格を引き下げる予定はないとしている(第Ⅰ-2-3-10図、第Ⅰ-2-3-11図)。
第Ⅰ-2-3-10図 主要輸出製品の契約通貨建て輸出価格の改定(2012年11月以降(為替は円安方向に推移))
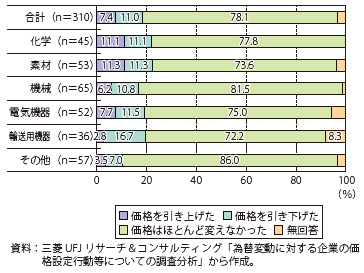
第Ⅰ-2-3-11図 輸出価格の改定を行っていない企業の今後の輸出価格改定方針(2012年11月以降(為替は円安方向に推移))
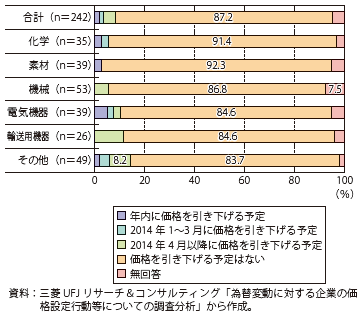
円安方向に推移する中、輸出価格を引き下げる予定がない理由としては、全産業で見ると、現時点では「価格を引き下げても売上増加が見込めない」、「価格改定は製品のモデルチェンジ等の際に行っているが当面はその予定がない」等が多くなっている。業種別に見ると、輸送用機器では、「価格改定は製品のモデルチェンジ等の際に行っているが当面はその予定がない」点を理由にしている割合が高く、「価格を引き下げても売上増加が見込めない」点を理由としている割合は他業種に比べ低い。これに対して、化学や素材では、「価格改定は製品のモデルチェンジ等の際に行っているが当面はその予定がない」点を理由としている割合は相対的に低く、「価格を引き下げても売上増加が見込めない」点や「価格を引き下げると燃料価格上昇等のコスト上昇分を吸収できない」点を理由としている割合が高くなっている(第Ⅰ-2-3-12図)。一方で、今後為替の安定や世界経済の動向次第では価格を引き下げる企業が増加する可能性もある。
第Ⅰ-2-3-12図 輸出価格の引き下げを行う予定がない理由(2012年11月以降(為替は円安方向に推移))
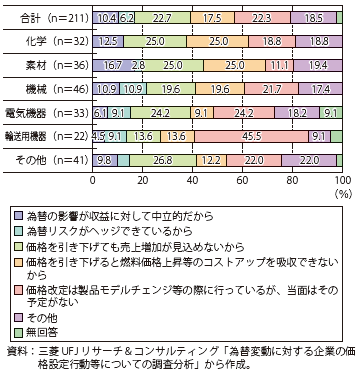
3.為替動向に伴う企業の輸出数量の変化
ここでは為替動向に伴う企業の輸出数量の変化についてアンケート結果に基づき見ていく。
まず、2008年半ば以降円高方向に推移する中、「輸出数量はほとんど変わらなかった」としている企業が全産業で見ると45.2%、「減少している」としている企業は33.5%となっている。業種別に見ると、機械では、「減少した」としている企業の割合が46.2%と高く、「ほとんど変わらなかった」としている企業の割合の35.4%を上回っている。一方、化学では、「増加した」としている企業の割合が「減少した」としている企業の割合を唯一上回っている(第Ⅰ-2-3-13図)。
第Ⅰ-2-3-13図 主要輸出製品の輸出数量の変化(2008年半ばから2010年末(為替は円高方向に推移))
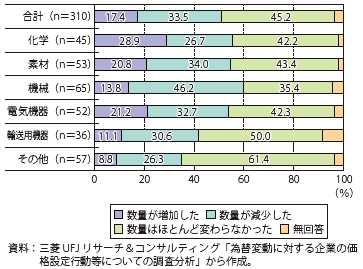
「減少した」理由として、全産業で見ると「リーマン・ショックによる海外需要の減少」としている企業が最も多く、「円高による価格競争力の低下」としている企業が次いで多くなっている。輸送用機器では「円高による価格競争力の低下」を理由としている企業が特に多くなっている(第Ⅰ-2-3-14図)。
第Ⅰ-2-3-14図 輸出数量減少の理由(2008年半ばから2010年末(為替は円高方向に推移))
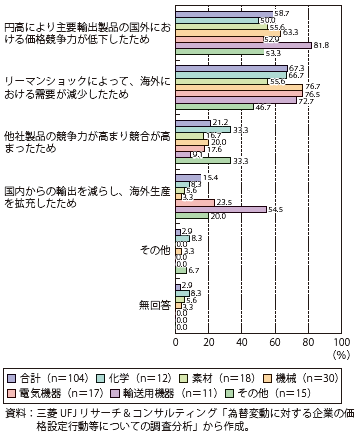
次に、2012年11月以降、円安方向へ推移する中、「輸出数量はほとんど変わらなかった」としている企業が全産業で見ると56.5%、「増加した」としている企業は31.9%となっている。業種別に見ると、化学では「増加した」としている企業の割合が37.8%と最も高い一方、輸送用機器では「増加した」としている企業の割合は27.8%となっている。また、素材では、「増加した」としている企業の割合が高い一方、「減少した」としている企業の割合も他の業種に比べ高くなっている(第Ⅰ-2-3-15図)。
第Ⅰ-2-3-15図 主要輸出製品の輸出数量の変化(2012年11月以降(為替は円安方向に推移))
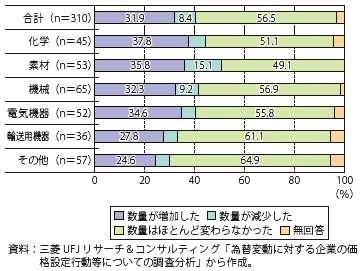
「増加した」理由として、全産業で見ると、「海外需要の増加」としている企業が最も多く、「円建ての輸出価格は引き下げていないが、円安により現地価格が下がったため」としている企業が次いで多くなっている。「契約通貨建ての輸出価格を引き下げることにより競争力が高まったため」としている企業は、総じて先の2つの理由よりも少なくなっている(第Ⅰ-2-3-16図)。
第Ⅰ-2-3-16図 輸出数量増加の理由(2012年11月以降(為替は円安方向に推移))
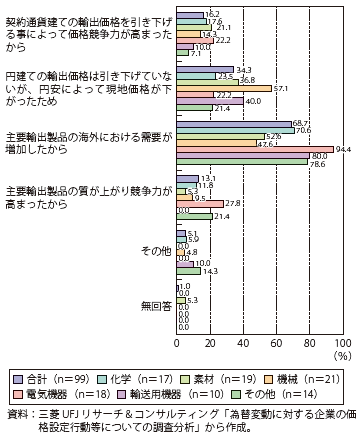
以上、為替動向と生産拠点や輸出価格に関する企業行動の関係、輸出数量への影響について見てきた。
為替動向と生産拠点や輸出価格に関する企業行動との間には現時点では余り強い連動性は見られなかった。企業は海外需要の動向や為替水準の安定性を注視している可能性がある。他方、輸出数量への影響については、為替水準にかかわらず、海外における需要動向の影響を指摘する企業が多くなっているが、円高方向に推移する中での輸出数量の減少に関しては、円高の影響により価格競争力が低下したこと、また、円安方向に推移する中での輸出数量の一定の増加に関しては、円建ての輸出価格は引き下げていないが円安方向への動きによって現地価格が下がっていることを指摘する企業が比較的多くなっている。