第1節 世界経済との連結性を強化する経済連携(EPA/FTA)
1.経済連携(EPA/FTA)の効果1
経済連携の推進は、国内に立地する輸出企業にとっては、関税削減等を通じた輸出競争力の維持又は強化の面で意義があり、他方で、外国に拠点を設置する等の投資をする又はサービスを提供する企業にとっては、海外で事業を展開しやすい環境が整備されるという点で意義がある。
例えば、輸出の面では、関税削減によって日本からの輸出品の競争力を高められる。例えば、メキシコでは乗用車に20%、マレーシアではエアコンに30%、インドネシアではブルドーザーに10%の関税が課されているが、EPAを利用した場合、これらの関税がゼロになる。また、複数国・地域間で結ばれる広域のEPAでは、EPAごとにバラバラに決められている要件・手続を統一し、企業が地域内でのEPAをより使いやすくするメリットがある。例えば、EPAを利用して関税削減の恩恵を受けるために必要な要件・手続(原産地規則と呼ばれる)を地域内で統一することは、企業の事務コストを削減し、EPAの活用対象国を広げやすくする効果がある。このほかにも、広域のEPAのメリットとして、地域内の複数国で生産された製品に対してEPAを使いやすくなること、地域内の物流拠点(ハブ)に貨物を集約し、物流拠点からの分割輸送を可能となること等が挙げられる。
海外で事業を行う企業に対しては、投資財産の保護、海外事業で得た利益に対する日本への送金の自由を確保、現地労働者の雇用義務等の規制を制限・禁止、民間企業同士で交わされる技術移転契約への政府の介入規制等の約束を政府同士で行うことにより、海外投資の安定性を高めている。
また、外国でのサービス業の展開に関しては、外資の出資制限や拠点設置要求等の禁止、パブリックコメント等による手続の透明性確保等、日本企業が海外で安心して事業を行うためのルールを定めている。
この他にも、我が国のEPAでは、締約国のビジネス環境を改善するための枠組みとして、「ビジネス環境の整備に関する委員会2」の設置に係る規定を設けている。「ビジネス環境の整備に関する委員会」では、政府代表者に加え、民間企業代表者も参加して、外国に進出している日本企業が抱えるビジネス上の様々な問題点について、相手国政府関係者と直接議論することができる。これまでの「ビジネス環境の整備に関する委員会」の成果として、メキシコでは模倣品取締りのためのホットライン設置に合意し、マレーシアでは治安向上のためパトロールの強化や監視カメラの増設等を実現してきている。なお、最近の「ビジネス環境の整備に関する委員会」での成果についてはコラム13に記載している。
1 EPA(経済連携協定)/FTA(自由貿易協定)とは、物品関税の削減・撤廃、サービス貿易の自由化、投資環境の整備、ビジネス環境の向上に関する協議の場の設置等を規定し、幅広い経済関係の強化を目的とする二国間又は多国間の国際協定をいう。
近年のFTA の中には投資環境整備等のEPA の要素を含むものもあり(例:韓米FTA)、EPA とFTA の区別は厳密なものではない。また、EU は旧植民地とのFTA をEPA と称しており、日本とは少し意味合いの異なる用語法となっている。
2 日メキシコEPAでは「ビジネス環境整備委員会」、日スイスEPAでは「経済連携緊密化小委員会」、日ペルーEPAでは「ビジネス環境の整備に関する小委員会」等、規定されるEPAごとに呼称が異なる。本白書では総称として、「ビジネス環境の整備に関する委員会」と表記する。
2.経済連携(EPA/FTA)を巡る全般的な動向
1990年代以降、国際経済環境や各国の開発戦略の変化により地域統合の動きが加速し、EPA/FTAの締結数が年々増加してきている。その背景としては、①欧米諸国が経済的関係の深い近隣諸国との間で貿易・投資の自由化・円滑化等による経済連携を図る動きを活発化させたこと(例:米国及びECがそれぞれNAFTA(1994年発効)及びEU(1993年発足)への取組を加速させる等)、②NIEsやASEANがいち早く経済開放を推し進めることにより高成長を果たす中、チリ・メキシコ・ペルー等の新興国が貿易・投資の自由化や市場メカニズムの導入へと経済政策を転換させ、その中でEPA/FTAを活用する戦略を採ったこと、さらに、③2000年代後半以降、WTOドーハ・ラウンド交渉が停滞する中、世界の主要国が貿易・投資の拡大のために積極的にEPA/FTAを結ぶようになったこと等が挙げられる。GATT第24条等に基づく地域貿易協定(RTA)3の通報件数は、1990年には27件に満たなかったが、2014年1月時点で583件まで増加している4。
3 地域貿易協定(Regional Trade Agreement):EPA/FTAや関税同盟を含む特定の国・地域の間での貿易の自由化等を約束する協定の総称。
4 WTOウェブサイト(http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm)参照。![]()
3.アジア太平洋地域の経済統合と世界のFTA動向
東アジア・アジア太平洋地域では、2002年に日本がシンガポールとのEPAを発効させたことを受けて、FTAを結ぶ動きが活発化した。2000年代後半にかけてシンガポール、マレーシア、韓国、中国等が東アジア地域内外の国・地域との間で多くのFTAを発効させた。
ASEANにおいては、2010年、ASEAN原加盟国6か国(インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、ブルネイ)の間で関税が原則撤廃されるとともに、物品分野については全ての「ASEAN+1」のFTAが発効し、東アジア地域のFTAが新しい段階に進んだと言われる。「ASEAN+1」のFTAとは、ASEANと周辺6か国(日本、中国、韓国、インド、豪州、NZ)が個別に結んだFTAであり、ASEANをハブとして東アジアにFTA網が張り巡らされた形となった。
こうしたFTA網の整備も手伝って、東アジア地域、あるいは最終消費地も加えてアジア太平洋地域では、工程間分業、生産拠点の集約化及び最適配置は相応に進展してきている(第Ⅲ-1-1-1図)が、広域経済連携によって更に統一的なスケジュールで関税を削減し、ビジネス活動に関する様々なルールを共通化することができれば、企業がこの地域全体にまたがるサプライチェーンの高度化に取り組むことを一層後押しすることとなる。
第Ⅲ-1-1-1図 東アジア地域におけるサプライチェーンの実態
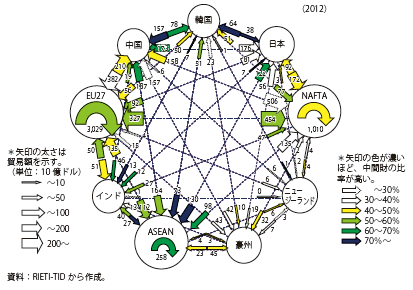
特に、アジア太平洋地域では、APEC参加国・地域の間で、FTAAP(エフタープ)(アジア太平洋自由貿易圏)の実現が目指されており、そのための道筋として、TPP(環太平洋パートナーシップ)、RCEP(アールセップ)(東アジア地域包括的経済連携)、日中韓FTA等の広域経済連携の取組が同時に進行している(第Ⅲ-1-1-2図)。
第Ⅲ-1-1-2図 FTAAPへの道筋
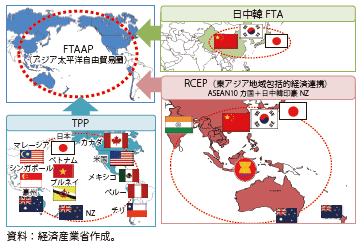
2013年3月には日中韓FTA、2013年5月にはRCEPについてそれぞれ交渉が開始され、米国とEUとの間でも2013年7月にTTIP(ティーティップ)(環大西洋貿易投資パートナーシップ)交渉が開始した。2014年5月現在、北米、欧州、アジア太平洋の各地域をつなぐ様々な経済連携の取組が同時並行で進行している(第Ⅲ-1-1-3図)。これらの取組が相互に刺激し合うことで高い相乗効果を生み、先進国間でも高いレベルのEPA/FTAの締結が進むことで世界全体の貿易投資に関するルール作りが進むことが期待されている。
第Ⅲ-1-1-3図 世界のFTA動向
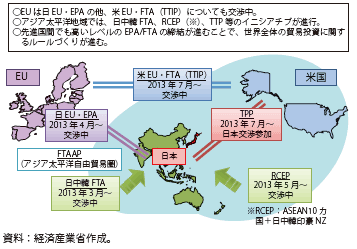
4.日本のEPA取組状況
我が国はこれまで、13の国・地域との間でEPAを発効させてきており、2014年4月に日豪EPAが大筋合意に至った。また、現在その他に4か国・6地域(TPP、RCEP、AJCEPサービス貿易章・投資章、日中韓FTA、日EU・EPA、日モンゴルEPA、日カナダEPA、日コロンビアEPA、日韓EPA(交渉中断中)、日GCC・FTA(GCC側がFTA一般について見直し中))との間で交渉会合が行われている。2010年10月より交渉が行われていたAJCEPのサービス貿易章・投資章の交渉は2013年12月にルール部分について実質合意に至った。さらに、2014年1月に日トルコEPAにつき、交渉を開始することで合意がなされた(第Ⅲ-1-1-4図、第Ⅲ-1-1-5図)。
第Ⅲ-1-1-4図 日本のEPA交渉の歴史
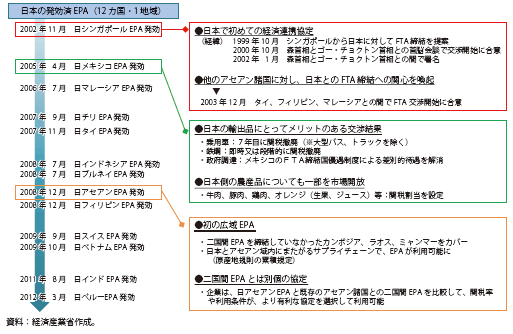
第Ⅲ-1-1-5図 日本のEPA取組状況
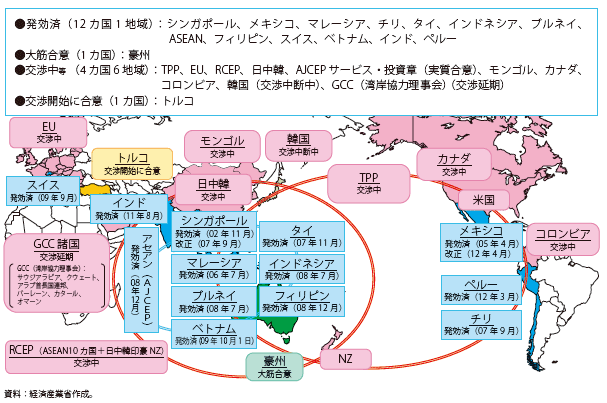
第Ⅲ-1-1-6図 EPA交渉の状況
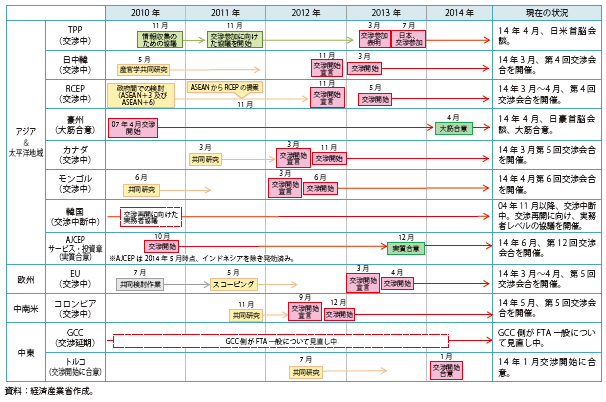
第Ⅲ-1-1-7図 各国のFTAカバー率比較
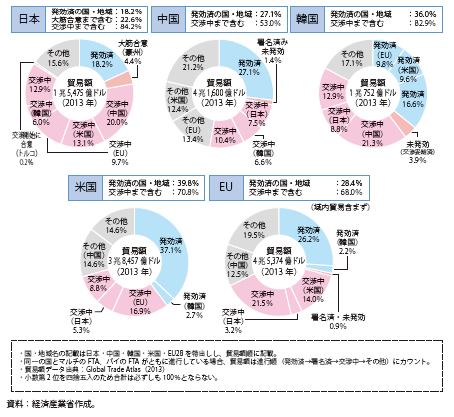
- Excel形式のファイル(日本)はこちら

- Excel形式のファイル(中国)はこちら

- Excel形式のファイル(韓国)はこちら

- Excel形式のファイル(米国)はこちら

- Excel形式のファイル(EU)はこちら

自由貿易の拡大、経済連携の推進は、日本の通商政策の柱であり、特にこれからは、TPP、RCEP、日中韓FTA、日EU・EPA等の広域的EPAを推進し、世界に「経済連携の網」を張り巡らせることで、アジア太平洋地域の成長や大市場を取り込んでいくことが、日本の成長にとって不可欠といえる。
「日本再興戦略(平成25年6月14日閣議決定)」においても、「FTA比率(貿易額に占めるFTA相手国の割合)を現在の19%から、2018年までに70%に高める」ことを決定しており、引き続き交渉を進めているところである。
以下、現在の我が国の経済連携の取組状況について、(1)大市場国・地域との経済連携、(2)その他の経済連携の取組に分けて紹介する。
(1)大市場国・地域との経済連携
【TPP(環太平洋パートナーシップ)】(交渉中)
①TPP交渉の経緯
2005年、シンガポール、NZ、チリ、ブルネイの4か国は環太平洋戦略的経済連携協定(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement、通称P4協定)に署名し、2006年に発効した。2010年3月、上記4か国に米国、豪州、ペルー、ベトナムを加えた8か国で環太平洋パートナーシップ(Trans-Pacific Partnership)協定交渉が開始した。
その後さらにマレーシア(2010年10月)、メキシコ(2012年10月)、カナダ(2012年10月)が交渉に参加し、日本は2013年7月に交渉に参加した。2014年5月現在、計12か国が交渉に参加している。
2013年3月には、シンガポールで第16回交渉会合、5月にペルーで第17回交渉会合、7月にマレーシアで第18回会合、8月にブルネイで第19回交渉会合が開催された。
同年10月、インドネシア・バリにてAPEC首脳会合が開催された。この際、TPP交渉参加12か国の首脳会合及び閣僚会合が開催され、首脳声明及び貿易閣僚による首脳への報告書が発表された。首脳声明では、「年内に妥結することを目的に、これから交渉官は残された困難な課題の解決に取り組むべきであることに合意した。」との発表がなされた。
その後、11月に米国ソルトレイクシティで行われた首席交渉官会合での議論を経て、12月、2月にシンガポールでTPP閣僚会合が開催され、2月の閣僚会合において「共同プレス声明 TPP閣僚会合」(第Ⅲ-1-1-8図)が発表された。
第Ⅲ-1-1-8図 TPPシンガポール閣僚会合 結果報告
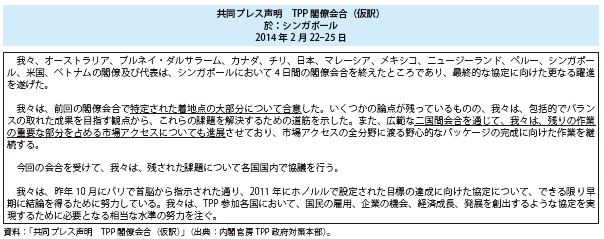
②TPPの交渉分野について
TPPはアジア太平洋地域において、21世紀型の新たな経済統合ルールの土台を作り上げていく野心的な試みである。高いレベルの関税削減・撤廃だけではなく、第Ⅲ-1-1-9図の21の分野5のような、サービス、投資、知的財産、金融サービス、電子商取引、環境、競争政策等、幅広い分野で新たなルールを構築することで、成長著しいアジア太平洋地域全体に大きなバリュー・チェーンを作り出すことができるものと期待される。
第Ⅲ-1-1-9図 TPP交渉で扱われる分野
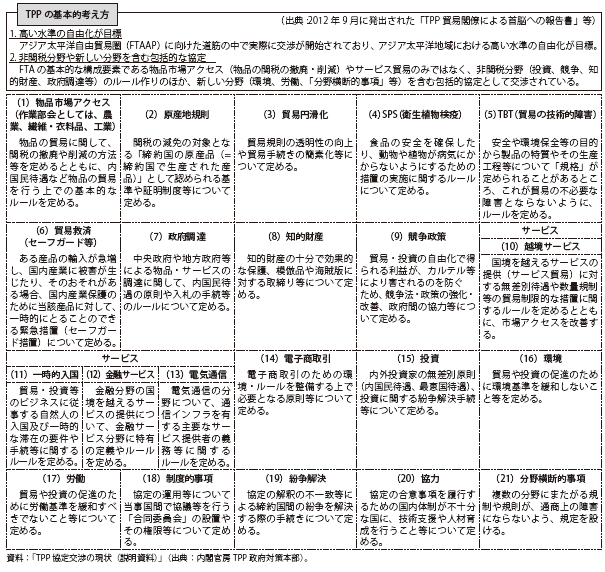
5 USTR等のプレスリリースでは、「29章」と呼ぶことがある。ただし、部会や交渉分野の数え方は、交渉会合によっても異なり、協定の章立てがこのとおりになるとは限らない。
③我が国の交渉参加について
我が国のTPP交渉参加については、2013年2月に行われた日米首脳会談において、安倍総理とオバマ大統領との間で、1)日本には一定の農産品、米国には一定の工業製品というように、両国ともに二国間貿易上のセンシティビティが存在すること、2)最終的な結果は交渉の中で決まっていくものであること、3)TPP交渉参加に際し、一方的に全ての関税を撤廃することをあらかじめ約束することは求められないこと、の三点について明示的に確認され、「日米の共同声明」(第Ⅲ-1-1-10図)を発出した。
第Ⅲ-1-1-10図 日米の共同声明(2月22日付)
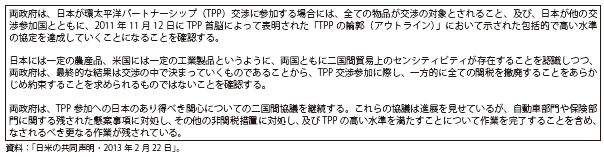
このような動きも踏まえて、3月15日に安倍総理は記者会見を行い、日本としてTPP交渉に参加する決断を表明し、その旨関係国に通知した。
さらに、4月12日には、米国との交渉参加に向けた協議が成功裡に終了したことが確認された。(「日米協議の合意の概要」(第Ⅲ-1-1-11図)参照)
第Ⅲ-1-1-11図 日米協議の合意の概要(4月12日付)(内閣官房TPP政府対策本部)
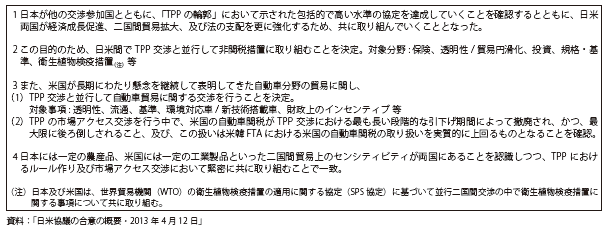
④日本のTPP交渉参加以降の取組について
日本は、2013年3月に安倍総理からTPP交渉への参加表明を行い、交渉参加国全てとの二国間協議ののち、7月にマレーシアで行われた交渉会合から正式に参加した。日本は12か国中最後に交渉に参加をする形となったが、これまで交渉の進展に大きな役割を果たしてきた。
2014年2月に開催されたシンガポールでの閣僚会合では、ルール分野において多くの進展が見られ、市場アクセスについても、物品のほか、サービス、投資、政府調達など全般にわたって精力的に交渉が行われた。日米間では甘利TPP担当大臣とフロマン米国通商代表が二度にわたり会談を行い、日米間の懸案の解決へ向け、事務レベルで引き続き折衝を続けることとなった。(「TPPシンガポール閣僚会合 結果概要」(第Ⅲ-1-1-12)、参照)
第Ⅲ-1-1-12図 TPPシンガポール閣僚会合 結果概要
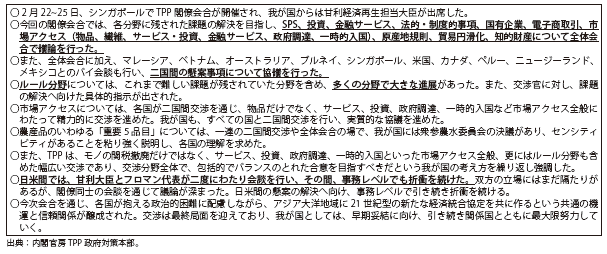
2014年3月、オランダ・ハーグにおいて、安倍総理とオバマ大統領が会談を行った際、TPP交渉を加速化させることで一致したことを踏まえ、日本と米国は両国間の残された課題について集中的に交渉を行った。
日米両国は4月だけで40時間近く閣僚(甘利大臣・フロマン代表)間で交渉を行い、オバマ大統領が国賓として訪日した際に行われた、4月24日の日米首脳会談前後も閣僚同士で協議を行った。
その結果、TPPに関する二国間の重要な議題について前進する道筋を特定するとともに、今後、日米が協力してTPPを早期妥結へ導くことが重要であるという認識のもと、全てのTPP交渉参加国に対し、協定を妥結するために必要な措置をとるために可能な限り早期に行動するよう呼びかけることとなった(「日米共同声明」(第Ⅲ-1-1-13図)、参照)
第Ⅲ-1-1-13図 日米共同声明/U.S.-Japan Joint Statement〈TPP部分抜粋/原文・仮訳〉
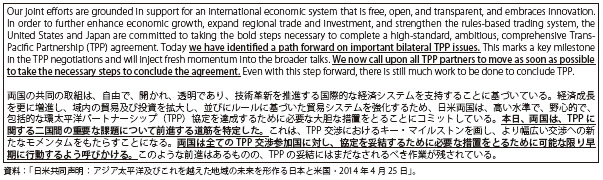
【RCEP(アールセップ)(Regional Comprehensive Economic Partnership:東アジア地域包括的経済連携)】(交渉中)
RCEPは、世界全体の人口の約半分、GDPの約3割を占める広域経済圏を創設するものであり、最終的にはFTAAP(アジア太平洋自由貿易圏)の実現に寄与する重要な地域的取り組みの一つである。
東アジア地域では、既に高度なサプライチェーンが構築されているが、この地域内におけるさらなる貿易・投資の自由化は、地域経済統合の深化に重要な役割を果たす。
この地域全体を覆う広域EPAが実現すれば、企業は最適な生産配分・立地戦略を実現した生産ネットワークを構築することが可能となり、東アジア地域における産業の国際競争力の強化につながることが期待される。また、ルールの統一化や手続の簡素化によってEPAを活用する企業の負担軽減が図られる。
2012年11月のASEAN関連首脳会議において、「RCEP交渉の基本指針及び目的」(以下、「基本指針」)が16か国(ASEAN10か国及び日本、中国、韓国、インド、豪州、NZ)の首脳によって承認され、RCEPの交渉立ち上げが宣言された。
基本方針には、物品貿易・サービス貿易・投資以外に、知的財産・競争・経済技術協力・紛争解決及びその他事項を交渉分野とすること、2015年末までの妥結を目指すことが盛り込まれている。第1回RCEP交渉会合は、2013年5月に開催され、高級実務者による全体会合に加えて物品貿易、サービス貿易及び投資に関する各作業部会が開催された。
直近では、3月31日~4月4日に第4回交渉会合が中国・南寧にて開催された。物品貿易、サービス貿易、投資、競争、知的財産、経済技術協力に関する各作業部会(WG:ワーキンググループ)等が開催されるとともに、新たにSTRACAP (Standards Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures:任意規格、強制規格及び適合性評価手続)、SPS(Sanitary and phytosanitary measures:衛生植物検疫措置)のサブWGの立ち上げに合意がなされるなど、着実に議論が進展している。
東アジアの成長を取り込み、我が国産業の国際展開を後押しするものとなるべく、包括的で高いレベルの協定を目指し、2015年末の交渉完了との目標に向け、迅速かつ精力的に交渉を進めているところである(RCEP参加の意義(第Ⅲ-1-1-14図)、参照)。
第Ⅲ-1-1-14図 東アジア地域のサプライチェーンネットワークの統合

第Ⅲ-1-1-15図 RCEPの経緯と予定
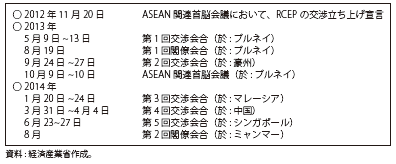
第Ⅲ-1-1-16図 日中韓FTAの経緯と予定・現在FTA交渉の協議対象となっている分野(15分野)
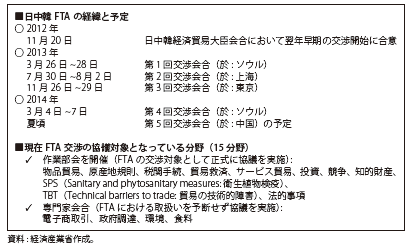
【日中韓FTA】(交渉中)
日中韓三か国は、世界における主要な経済プレイヤーであり、三か国のGDP及び貿易額は、世界全体のGDP及び貿易額の約2割を占める。日中韓FTAは、三か国間の貿易・投資を促進するのみならず、FTAAP (アジア太平洋自由貿易圏)の実現にも寄与するものである。
民間共同研究(2003年~2009年)、産官学共同研究(2010年~2011年)を経て、2012年5月の第5回日中韓サミットにて三か国首脳が日中韓FTAの年内交渉開始につき一致、同年11月の東アジアサミットの際に開催された日中韓経済貿易大臣会合において交渉開始が宣言された。翌2013年3月以降、計4回の交渉会合を開催し、物品貿易、サービス貿易、投資、競争、知的財産等の広範な分野について議論が行われている。
2014年3月に韓国・ソウルで開催された第4回交渉会合では、物品市場アクセス関税の交渉方式(モダリティ)について活発に議論が行われるとともに、多くの分野において条文案に基づく交渉が開始され、協定に盛り込むべき要素等について議論が深まるなど、着実に議論が進展している。引き続き、包括的かつ高いレベルの協定を目指し精力的に交渉を進めていく。
【日EU・EPA】(交渉中)
日本とEUは、世界人口の1割、貿易額の2割、GDPの3割を占める重要な経済的パートナーであり、日EU・EPAは、日EU間の貿易投資を拡大し、我が国の経済成長をもたらすとともに、世界の貿易・投資のルール作りに寄与するものといえる。
EUは元来、GATT/WTOを中心とする多角的な貿易交渉を通じた貿易投資自由化を重視しており、FTAについては近隣諸国や旧植民地国を中心として、政治的枠組みの構築を目指す連合協定の一部や、既存の特恵貿易に関する協定を発展的に改組する形で締結していた。しかし、2001年に立ち上がったWTO・ドーハ・ラウンド(DDA)交渉が長引き、また新興国の台頭に伴い世界の経済環境が変化していることから、欧州委員会は、2006年10月に「新通商戦略:グローバルヨーロッパ(Global Europe: Competing in the World)」を発表し、WTOが引き続き世界の通商制度における重要なプラットフォームであることを念頭に置きつつ、FTAを通じ、欧州企業にとっての市場アクセスの確保・非関税障壁の改善等の利益を確保する方針を打ち出した。優先的にFTAを締結する対象国は、①市場潜在力(経済規模と成長性)、②EUの輸出利益に対する保護水準(相手国の市場の閉鎖性や関税水準及び非関税措置に加えて、EUの競争相手国とのFTA締結状況等)を総合的に勘案して判断されており、ASEAN、韓国、南米南部共同市場(メルコスール、2000年から交渉開始)をFTA締結の優先国・地域として、また、インド、ロシア、GCC(湾岸協力理事会)(1990年から交渉中)をFTAの交渉対象候補国として特定した。この戦略に基づき、2007年4月のEU閣僚理事会で、欧州委員会に対し、韓国、ASEAN、インドとのFTA交渉権限を付与する決定が採択され、同年に交渉が開始された6。韓国とのFTAについては、2009年10月に仮署名し、2011年7月に暫定発効に至った。さらに近年、先進国であるカナダとのCETA(包括的経済貿易協定)に基本合意しており(2013年10月)、米国ともTTIP(環大西洋貿易投資パートナーシップ)交渉を2013年7月に交渉を開始するなど、先進国とも通商関係強化に向けた動きをみせている。
こうした中、日EU・EPAについては、2009年5月の日EU定期首脳協議において日EU経済の統合の強化に協力する意図が表明され、翌2010年4月の日EU定期首脳協議では、「合同ハイレベル・グループ」を設置し、日EU経済関係の包括的な強化・統合に向けた「共同検討作業」を開始することに合意した。合同ハイレベル・グループにおける幅広い分野での作業の結果を踏まえ、2011年5月の日EU定期首脳協議において、交渉のためのプロセスの開始についての合意がなされ、日本政府と欧州委員会との間で、交渉の「範囲(scope)」及び「野心(ambition)のレベル」を定める「スコーピング作業」を実施することとなった。
スコーピング作業は2012年5月に実質的に終了し、同年11月29日のEU外務理事会において、欧州委員会が加盟国より交渉権限(マンデート)を取得した。マンデート取得に当たり、欧州委員会は加盟国との関係で「交渉開始1年後の見直し」(レビュー)を課され、交渉開始後1年で日本側の取組状況について加盟国に報告・協議し、十分な成果があるか否かを評価することとなった。マンデートの取得を受け、2013年3月に行われた日EU電話首脳会談において、日EUのEPA/FTA及び戦略的パートナーシップ協定(SPA)の交渉開始に合意し、2013年4月の交渉開始以降、2014年5月現在までの間、5回の交渉会合が開催された。2014年3月31日~4月4日に東京で行われた第5回交渉会合では、物品貿易、サービス貿易、投資、知的財産権、非関税措置、政府調達等の各分野について議論がなされ、物品貿易の市場アクセスについてはオファーの交換が行われる等、着実な進展が見られている。
また2013年11月に続き、2014年5月にブリュッセルで日EU定期首脳協議が開催され、日EU両首脳は、包括的かつ高いレベルの日EU・EPAの早期締結の重要性を確認した。(日EU定期首脳協議・共同プレス声明(第Ⅲ-1-1-17図)、参照)
第Ⅲ-1-1-17図 日EU定期首脳協議・共同プレス声明
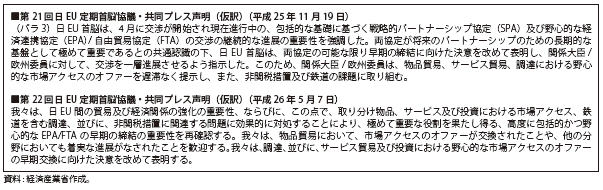
第Ⅲ-1-1-18図 日EU・EPAの経緯と今後の予定
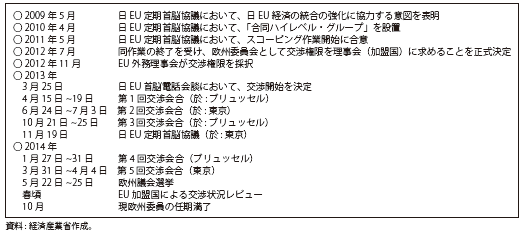
また、ブリュッセル訪問前に安倍総理が欧州6か国を訪欧した際、「2015年中の大筋合意を日本政府としては目指したい」旨様々な機会で言及したところ、欧州各国及びEUの首脳との間で交渉の早期締結の重要性について一致した。
日EU・EPA早期締結に対しては産業界からの期待も強く、2013年11月と2014年5月の日EU定期首脳協議前には、欧州企業を含む多数の団体が交渉を支持する声明を発表した。2014年4月には、日欧産業界が双方の経済成長を促進するための会合である日・EUビジネス・ラウンドテーブル(BRT)年次会合を開催し、可能な限り早期に日EU・EPAを締結することへの要請と、そのために全力で支援する決意を表明した内容の提言書を採択し、日EU両政府に提出した。
2014年5月現在、EU側は交渉開始1年後の「見直し」を行っており、交渉継続が決定されれば、早期締結に向け速やかに次回交渉会合を実施することとなる。
6 JETRO調査レポート(2009)「EUのFTA戦略及び主要FTAの交渉動向」ブリュッセル・センター、海外調査部欧州課 http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000067/0906R3.pdf![]()
(2)その他の経済連携の取組
【日豪EPA】(大筋合意)
2007年4月に第1回交渉会合が開催された本EPA交渉は、2012年6月までに16回の交渉会合を実施するとともに、その後も閣僚折衝や実務協議を継続してきた。2014年4月7日、安倍総理とアボット首相は首脳会談を行い、日豪EPA交渉の大筋合意を確認した。今後、両国は可能な限り早期の署名に向けて迅速に作業を進めていく。
豪州は、これまで日本が締結した二国間EPAのパートナーとして最大の貿易相手国。本EPAは、貿易、投資、知的財産、競争、政府調達等、幅広い分野を含む包括的協定であり、アジア太平洋地域のルール作りに資するものと考えられる。(「日豪経済連携協定の大筋合意について」(第Ⅲ-1-1-19図)参照)
第Ⅲ-1-1-19図 日豪経済連携協定の大筋合意について
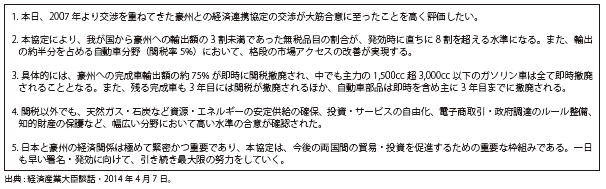
【日・ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定 サービス・投資章】(実質合意)
ASEAN全体とのEPAである日・ASEAN包括的経済連携(AJCEP)は、2004年11月の首脳間での合意に基づき2005年4月より交渉を開始し、2008年4月14日に各国持ち回りでの署名を経て、2014年5月時点でインドネシアを除くすべての参加国との間で発効している。AJCEPは、日本とASEANを1つのエリアとして、人口7.4億人、経済規模8兆3千億ドル(2012年)の自由な経済圏を制度化するものであり、日本とASEAN双方の経済活性化促進の観点から、非常に重要な意義がある。
2010年10月より交渉が行われていたAJCEPのサービス貿易章・投資章については3年にわたる交渉を経てルール部分について実質合意に至り、2013年12月の日ASEAN特別首脳会議において同成果は各国首脳に歓迎された。
今後は残された技術的論点の調整や、サービス分野の市場アクセス交渉を行っていく。
【日韓EPA】(交渉中断中)
韓国とのEPA交渉は2003年12月に交渉を開始したものの、2004年11月の第6回交渉会合を最後に事実上中断している。2008年2月の福田総理(当時)と李明博大統領(当時)との日韓首脳会談の合意を受け、交渉再開に向けた実務協議が開催されてきた。また、2011年10月に野田総理(当時)と李明博大統領(当時)の間で行われた日韓首脳会談において、交渉再開に必要な実務的作業の本格的実施につき合意し、実務協議が行われてきたが、現在まで交渉再開には至っていない。
【日GCC・FTA】(交渉延期)
バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦からなるGCC(湾岸協力理事会)諸国とのFTAについては、2006年9月に交渉が開始され、2009年3月までに2回の正式会合と4回の中間会合が実施された。しかし同年7月に、GCC側の要請により交渉が延期されており、現在、我が国は交渉再開に向けて働きかけを行っている。
この地域は、我が国の原油輸入量全体の約77%(2013年)を占め、また我が国からの総輸出額も2兆円に達する(2013年)。さらに、人口増加に伴う大規模なインフラ整備の需要があり、各国による、官民一体となった売り込みが積極的に展開されている。貿易・投資拡大及び我が国のエネルギー安全保障の観点に加えて、同諸国との間で経済関係を含めた友好的な関係を形成・維持することが重要である。
【日モンゴルEPA】(交渉中)
日モンゴルEPA交渉は、2010年1月に行われた政府間の実務レベル協議において、官民共同研究を立ち上げることが決定され、日モンゴル両国首脳にEPAの早期の交渉開始を提言する内容の共同研究最終報告書が2011年3月に完成した。同報告書を受け、2012年3月の日モンゴル首脳会談において、互恵的かつ相互補完的な経済関係の構築に向けて、日モンゴルEPA交渉を開始することで一致した。
第1回交渉会合が2012年6月に行われ、最近では2014年4月に第6回交渉会合が開催された。直近の会合では、総則・最終規定、物品貿易、投資、サービス、知的財産、電子商取引、原産地規則、税関手続、競争、協力、紛争解決、SPS(衛生植物検疫措置)、TBT(貿易の技術的障害)等の分野につき議論が行われ、進展が見られた。
日モンゴルEPAが締結されればモンゴルにとって初めてのEPA/FTAとなり(2014年5月現在、モンゴルはいずれの国ともEPA/FTAを締結していない)、両国間の政治的・経済的つながりの強化に資するだけでなく、2010年11月の日本・モンゴル共同声明に掲げる「戦略的パートナーシップ」の構築に向けた重要なステップとなる。
【日カナダEPA】(交渉中)
カナダは、シェールガスなど我が国の新たなエネルギー・鉱物資源の調達先として着目されている。資源の安定確保の観点に加え、カナダからのエネルギー供給は、他国・地域の海域を経由しないことから、エネルギー安全保障上有利であり、カナダとの経済関係の深化は大きな意義がある。
日カナダEPA交渉については、2011年3月から2012年1月までに4回の共同研究が開催され、共同研究報告書が作成された。同共同研究の報告書をうけ、2012年3月の日加首脳会談において、両国の実質的な経済的利益に道を開く二国間EPAの交渉を開始することで一致した。第1回交渉会合は2012年11月に行われ、最近では2014年3月に第5回交渉会合が開催された。
直近の会合では、サービス貿易、投資、知的財産、鉱物・エネルギー資源・食料等の分野につき有意義な議論が行われた。
【日コロンビアEPA】(交渉中)
コロンビアは、高い成長率(今後5年間で平均4%強)が見込まれる人口4,800万人の市場であり、EPAを通じた貿易・投資環境の改善により輸出入拡大が期待される。コロンビアは、中南米諸国とのFTAに加え、米国、EU、カナダとも既にFTAを発効済みである他、韓国のFTAにも署名済みである。
2011年9月の日コロンビア首脳会談において日コロンビアEPAの共同研究立ち上げが合意されたことを受け共同研究が開始し、2012年7月に報告書がとりまとめられ、あり得べきEPAは両国に多大なる利益をもたらすであろうことが明らかになった。共同研究報告書を受けて2012年9月に行われた日コロンビア首脳会談にて、両国はEPA交渉を開催することで一致した。
第1回交渉は2012年12月に開催され、最近では2014年5月に第5回交渉会合が開催された。第5回交渉会合では、物品貿易、協力、政府調達、SPS(衛生植物検疫)、TBT(貿易に関する技術的障害)等の幅広い分野について議論が行われ、進展が見られた。
【日トルコEPA】(交渉開始に合意)
トルコは高い成長率(今後5年で平均5%強)が見込まれる人口7,500万人の魅力的な市場を持つ。貿易・投資環境の改善による輸出入拡大が期待され、我が国企業の関心は高い。トルコは、EU・トルコ関税同盟の締結等、EUとの間で特に強い通商上の結びつきを形成しているほか、中東アフリカ諸国や、近年ではチリや韓国との間でFTAを発効済みである。
トルコと我が国は2012年7月に第1回日・トルコ貿易・投資閣僚会合を開催し、日トルコEPAの共同研究を立ち上げることにつき合意した。これを受けて、同年11月に第1回、2013年2月に第2回の共同研究が開催され同年7月に日本・トルコの両政府にEPA交渉開始を提言する共同研究報告書が発表された。
共同研究報告書を受けて、2014年1月に行われた日トルコ首脳会談にて、両国はEPA交渉を開始することで一致した。今後、スコーピングを経て、正式に交渉を開始する予定である。
5.「EPAのライフサイクル」
以上、現在交渉中、交渉開始に合意したEPA/FTAを紹介したが、グローバルに展開するビジネスの要請に応えるには、このような新たな協定締結に向けた取組に加えて、EPA/FTAの円滑な利用促進、既存EPAの内容の改善(再交渉)も重要である。
現在、我が国の発効済みEPAにおいては企業による活用も浸透し始め、「活用・運用段階」にあるといえる。
今後、政府のみならずJETRO7、日本商工会議所8、業界団体等による積極的なEPAの普及啓蒙・利活用率の向上・着実な執行、「ビジネス環境の整備に関する委員会」等の場を通じた両国政府・民間企業代表者を交えた協議9、EPAの利活用実態やニーズを踏まえた協定見直し10等、いわば「EPAのライフサイクル」にわたって、EPAの質を高めていくことが非常に重要であると言える。
なお、発効済みEPA/FTAを活用した企業の事例は第4節で特集した。
7 EPA利活用相談(日本企業の方)https://www.jetro.go.jp/services/advice/![]() 、EPAアドバイザー等海外進出企業の支援サービス(在海外企業の方) https://www.jetro.go.jp/services/advisor/
、EPAアドバイザー等海外進出企業の支援サービス(在海外企業の方) https://www.jetro.go.jp/services/advisor/![]()
8 特定原産地証明書の指定発給機関 http://www.jcci.or.jp/international/certificates-of-origin/![]()
9 ビジネス環境の整備に関する委員会 http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/about/business.html![]()
10 日シンガポールEPAは2002年発効、2007年改正。日メキシコEPAは2005年発効、2012年改正。
