第5節 世界・地域規模でのルール形成に向けた取組
経済連携協定に加え、WTO、APECや個別分野での有志国によるルール形成とその遵守も、貿易環境の整備に不可欠な取組である。
1.多角的自由貿易体制としての世界貿易機関(WTO)
1948年に発足したGATT締約国は過去8度にわたり多角的交渉を行い、自由かつ公正な貿易ルールの策定を目指してきた。数次のラウンド交渉27を経て、次第に関税削減が実現され、関税以外の貿易関連ルールも整備された。1993年のウルグアイ・ラウンド妥結後はGATTを発展的に改組してWTO(世界貿易機関)が設立された。
WTOは、それまでGATTが担ってきたラウンド交渉を通じた物品貿易に係る関税及び非関税障壁の削減や予見可能性を高めるための通商ルールの強化・充実に加え、規律範囲を拡大し、新たにサービス貿易、知的所有権の貿易的側面についても対象としている。また、紛争処理機能を抜本的に強化し、GATTに比べて、対象範囲が拡大し実効性も向上している。
2001年に開始されたドーハ・ラウンド交渉に関しては、2011年12月に行われた第8回WTO定期閣僚会議(MC8)において、交渉対象全分野28の一括合意が当面困難であることを認め、「新たなアプローチ」を見いだす必要性を共有し、進展が可能な分野で議論を進めることが合意された。その後の交渉を通じて、貿易円滑化、農業の一部、開発が進展可能な分野であるとの共通認識が形成され、2013年12月にインドネシア・バリで開催された第9回WTO定期閣僚会議(MC9)において精力的な交渉の結果、バリ・パッケージとして合意された。
ラウンド交渉以外でも、WTO協定(ルール)の執行を図る紛争解決手続が有効に機能しており、新興国を含め、紛争解決手続の活用が増加している。また、リーマンショックに端を発する世界的な経済危機以降、一部の国では自国産業支援や雇用確保を名目とした措置や鉱物資源の輸出規制といった保護主義的措置が導入されたが、我が国は、WTO紛争解決手続を積極的に活用し、こうした措置の是正を求めてきている。
本節では、現行WTO協定の執行、ドーハ・ラウンド交渉の状況、保護主義の抑止及びラウンド外の取組としてITA(情報技術協定)拡大交渉、新サービス貿易協定、環境物品交渉、政府調達協定改正に向けた取組を概観する。
27 1960年に開始された第5回交渉(ディロン・ラウンド)以降、多角的交渉は「○○ラウンド」と呼ばれる。
28 第1表ドーハ・ラウンド一括受諾の交渉項目と主要論点参照
(1)現行WTO協定(ルール)の執行
WTO協定は、自由かつ公正な貿易ルールを策定すると同時に、加盟国・地域間に通商摩擦・紛争が生じた際に、ルールの解釈・適用を通じてその解決を図る紛争解決手続に係る規律を備えている。WTO上の手続は、問題措置の是正勧告のみならず、勧告が履行されない場合に対抗措置を発動するための手続を備えていることから、他の国際紛争処理手続と比較して実効性は高い。WTO協定に違反する諸外国・地域の法令や措置の是正を求めることは、我が国の不利益を解消するのみならず、協定の実効性を担保するためにも重要である。また、通商摩擦をいたずらに政治問題化させないためにも、WTO協定が規定する権利・義務に基づいて主張・対処することが必要である。
こうした方針のもと、我が国は二国間交渉のほか、WTO紛争解決手続の活用によりWTO協定に違反する各国の政策・措置についてその是正を要求している。WTOでは、紛争解決手続が大幅に強化された結果、GATT時代と比べ紛争解決のための通商ルールを加盟国が積極的に活用しており、紛争解決手続に基づく協議要請件数が著しく増加している。1995年のWTO発足以来、WTO紛争解決手続が用いられた案件は474件(2014年4月11日現在)に上っている。こうした中、我が国が当事国として協議を要請した案件は19件あり、第三国としても多くの案件に参加している。
(2)紛争解決手続に付託して解決を図っている事案
我が国は、WTO協定に違反する外国政府等の政策・措置について、二国間交渉やWTO紛争解決手続等、あらゆる機会を通じてその是正を図っている。我が国が当事国としてWTO紛争解決手続に付託し、解決を図っている最近の事例は以下のとおりである。
①中国の原材料輸出規制への対応
中国政府は、多くの原材料品目について輸出規制(①輸出税の賦課、②輸出数量の制限、③最低輸出価格の設定)を行っている。各国は、中国の輸出規制措置が、GATT(関税と貿易に関する一般協定)及び中国のWTO加盟議定書に整合的でないとして、WTOの委員会や二国間協議の場で累次の是正を求めてきた。これに対し、中国政府からは、輸出規制措置の目的は、環境への配慮及び有限天然資源の保存であり、GATT第20条に整合的であるとの回答がなされたが、措置を正当化する加盟議定書上の根拠等について、詳細な説明は行われてこなかった。
2009年6月、米国及びEUは、ボーキサイト、コークス、蛍石等の原材料9品目に対する輸出規制措置がWTO協定に整合的でないとして協議要請を行ったが、協議による解決に至らなかったため、同年12月にパネルが設置された(我が国は第三国参加)。2011年7月には、中国の輸出規制措置はWTO協定に整合的でないとするパネル報告書が公表された。同年8月に中国は上訴したが、2012年1月にパネルの判断をおおむね支持する上級委員会報告書が公表された。これにより、中国は、協定整合的でないと判断された輸出規制措置の是正が求められ、2012年末が履行期限とされた。中国政府は、2013年1月以降、ボーキサイト、コークス、蛍石、マグネシウム、マンガン、シリコンメタルの6品目の輸出税を撤廃し、黄リン、亜鉛については加盟議定書で定められている範囲内の税率へと変更された。加えて、ボーキサイト、コークス、蛍石、シリコンカーバイド、亜鉛については輸出数量制限を撤廃するなど、勧告を履行している。
2012年3月、我が国は、米国及びEUとともに、中国のレアアース、タングステン及びモリブデンに対する輸出規制措置(輸出税、輸出数量制限、貿易権の制限等)について、WTO協議要請を行い、2012年4月に協議を実施した。しかし、協議による解決に至らなかったため、同年6月、三か国がパネル設置要求を行い、同年7月にパネルが設置された。その後、2014年3月26日、パネルは報告書を公表し、中国の輸出規制について、GATT第11条(輸出数量制限の禁止)及び中国のWTO加盟議定書第11条第3項(輸出税の禁止)、WTO加盟議定書第5条第1項(貿易権の制限)等に違反するとの我が国、米国、EUの主張を全面的に認めた。本パネルの判断は、重要資源であるレアアース等の安定供給の確保のみならず、一部の資源国の保護主義的な動きを牽制する観点からも意義深く、我が国は、中国が本パネルの判断に従い、早期に輸出規制措置を是正するよう強く求めていく。
②カナダ・オンタリオ州の電力固定価格買取制度に係るローカルコンテント要求
カナダ・オンタリオ州は、再生可能エネルギーの普及を図るため、2009年5月に再生可能エネルギーの電力の固定価格買取制度(Feed in Tariff(FIT))を創設。同制度では、発電事業者等が固定価格買取制度に参入する際の条件として、組立てや原材料の調達等一定割合以上の付加価値が同州内で付加された太陽光・風力発電設備を使用することが義務化された(ローカルコンテント要求)。こうした措置は、内国民待遇義務を定めるGATT第3条、貿易に関連する投資措置に関する協定(TRIMs)第2条違反に該当する。
我が国は、現地領事館等を通じてオンタリオ州政府に懸念を伝える他、カナダ連邦政府に対してもハイレベルでの働きかけを行う等、二国間の協議による解決を探ってきたが、カナダ側より前向きな回答が得られなかったため、2010年9月、カナダに対してWTO上の二国間協議要請を行った。その後、2011年6月にパネル設置要請を行い、7月にパネルが設置され、2012年3月及び5月にパネル会合が開催された。2012年12月、パネルは最終報告書を公表し、WTO協定に基づき、買取条件におけるローカルコンテント要求を撤廃すべきという我が国の主張をおおむね認め、カナダがGATT第3条及びTRIMs第2条等に違反して不当な州産品優遇を行っているとの判断を示した。この認定に基づき、パネルはカナダに対し、GATT及びTRIMs違反とされた措置をWTO協定に整合させるように勧告した。その後、2013年2月にパネル判断を不服としてカナダが上訴し、同年5月、上級委員会が最終報告書を公表した。同報告書はパネルの結論を支持し、我が国の勝訴が確定している。
上級委員会による勧告を受け、カナダは、履行期間を10か月(2014年3月24日まで)とすることで日本と合意した。2013年8月、オンタリオ州政府は履行に向けた中間的な措置として、ローカルコンテント比率を、小規模風力発電事業については50%から20%に、小規模太陽光発電事業については60%から19~28%に引き下げるエネルギー大臣指示を公表した。現在、ローカルコンテント要求を撤廃する改正法案がオンタリオ州議会で審議されている。
③アルゼンチンの非自動輸入ライセンス制度の導入・拡大
アルゼンチン政府は、2008年11月、金属製品(エレベータなど)について輸入事業者・輸出事業者・輸入物品の価格、数量などの情報を添えた申請を義務づける非自動輸入ライセンス制度を導入した。その後、同制度の対象品目を拡大し、対象品目は約600品目に達している。加えて、輸入事業者に対する輸出入均衡要求(例えば、1ドルの輸入を行う条件として、1ドルの輸出を求める措置)を実施。さらに、2012年2月には、追加的な輸入許可制度として事前宣誓供述制度を導入し、輸入者はあらゆる輸入品について事前に歳入庁に申請を行うことが必要となった。2013年1月には、非自動輸入ライセンス制度が撤廃されたが、その他の措置(事前輸入宣誓供述制度、輸出入均衡要求など)は依然として存続している。
これらの輸入制限的措置は、GATT第11条の「数量制限の一般的廃止」に抵触する可能性がある。
我が国は、産業界による改善要望も踏まえ、2012年8月、米国及びメキシコとともに二国間協議を要請し、同年9月に協議を実施したが、満足のいく解決を得られなかったことから、同年12月、米国・EUとともにパネル設置要請を行い、2013年1月にパネルが設置され、現在係争中である。
④中国の日本製ステンレス継目無鋼管に対するAD(アンチ・ダンピング)措置
2011年9月、中国政府は中国国内企業からの申請を受けて、日本、EUからの高性能ステンレス継目無鋼管の輸入に対するAD調査を開始した。2012年11月、中国政府は、当該産品の輸入について、ダンピングの事実、国内産業の損害及びこれらの因果関係があるとしてAD税を賦課する最終決定を行った。
本措置は、最終決定の公告における事実の記載が不十分であるなど調査手続に瑕疵があると考えられるほか、ダンピングによる国内産業への損害の認定等においても瑕疵があると考えられ、AD協定に違反する可能性がある。
このため、我が国は、2011年秋、2012年春及び秋のWTO・AD委員会において、日本から輸出される当該製品のほとんど全ては、超々臨界圧の石炭火力発電所のボイラ等に使用される高付加価値製品であり、中国製品とは競合しないため、中国国内産業に損害を与えないと指摘するとともに、当該日本製品の中国国内ユーザー側の意見も踏まえて適切な決定がなされることを強く要望する旨伝えた。その後も中国政府に対し、日本製品の調査対象からの除外を求めて働きかけを行うなど対話による解決を図ってきたが、解決に至らなかったため、2012年12月、我が国は、中国に対してWTO協定に基づく二国間協議要請を行い、2013年1月に協議を実施した(EUが第三国参加)。協議結果を踏まえ、4月にパネル設置を要請し、5月にパネルが設置された。また、同年6月にはEUが本件についてWTO協議要請を行い、同年8月にパネル設置を要請し、同月、パネルが設置された。現在、日・EUの要請に基づくパネルが係争中である。
⑤ロシアの自動車廃車税
ロシア政府は、2012年9月1日から、自動車に対する廃車税(リサイクル税)を導入し、自動車の輸入者及びロシア国内生産者に廃車税の支払を義務づけた。廃棄物の安全処理義務を引き受けたロシア国内生産者は廃車税の支払を免除されるが、関税同盟諸国(ロシア、カザフスタン及びベラルーシ)の領域内で製造された部品の使用等が免除の要件とされた。また、一定の条件を満たす関税同盟諸国からの輸入車については廃車税が不適用とされた。
廃車税免除の余地を国産車のみに認め、関税同盟諸国に対して不適用とし、輸入車への免除の可能性が排除されている点等が、内国民待遇義務(GATT第3条)に違反する可能性があったことから、我が国は、2012年6月以降、経済産業大臣及び外務大臣をはじめとするハイレベルより、ロシア経済発展大臣や第一副首相等に対し懸念表明を行った。また、WTO物品理事会において、米国・EUとともに懸念を表明した。
こうした申入れを受けて、2013年4月、ロシア政府は、廃車税制度をWTO整合的なものとするため、同制度を改正する法案(国内生産者や関税同盟国に対する免除制度を廃止し、すべての企業に廃車税を支払うことを義務付け)を公表した。しかし、同年6月、当初施行日は7月1日とされていた同法案の審議を秋に延期することを発表したことを受け、同年7月、EU及び我が国がそれぞれWTO協議を要請し、EUは7月、我が国は8月にロシアとの協議を実施した。こうした制度是正の要求の後、2013年10月に廃車税制度の改正法がロシア議会で可決され、2014年1月1日に施行された。
本改正により、①一定の条件を満たすロシア国内生産者に対する免税制度、②関税同盟諸国からの輸入車に対する免税制度が廃止され、内外差別及び特定国優遇の要素は基本的に是正された。今後、我が国企業が内外差別的な扱いを受けることのないよう、引き続き、改正法及び関連実施規則等の施行・運用状況を注視していく。
⑥ウクライナの自動車セーフガード措置
2011年7月、ウクライナ経済発展・貿易省は、2008年から2010年を調査対象期間とした輸入乗用車(排気量1,000cc~1,500cc及び1,500cc~2,200ccの乗用車)に対するセーフガード調査を開始し、2012年4月にセーフガード措置(追加関税の賦課)を発動すべきとする提案を行った。しかし、調査対象期間中のウクライナの乗用車輸入台数は大幅な減少傾向を示している等、多くの点でWTOセーフガード協定の措置発動要件を満たすかについて強い疑義があったため、我が国は、2011年10月及び2012年4月に、WTOセーフガード委員会においてEUとともに懸念を表明した。また、公聴会への参加や、二国間協議の実施、ウクライナ経済発展・貿易大臣宛書簡の発出等を通じて懸念を表明しつつ、措置の発動を控えるよう要請を行った。
しかしながら、2013年3月、ウクライナ政府は「30日後から3年間、排気量1,000cc~1,500ccの輸入乗用車に対して6.46%、排気量1,500cc~2,200ccの輸入乗用車に対して12.95%の追加関税を課す」旨のセーフガード発動決定を公表し、同年4月に課税が開始された。これを受け、我が国は、閣僚レベルでの申入れを始め、二国間及びWTOの関連委員会において、措置撤回に向けての累次にわたる働きかけを行ったが、状況が改善されなかったため、2013年10月、WTO協定に基づく二国間協議を要請した。同年11月及び2014年1月にウクライナとの協議を実施したが、満足のいく解決策が得られなかったことから、2014年2月、パネル設置要請を行い、同年3月にパネルが設置された。今後、引き続きウクライナ側の動きを注視しつつ、WTO紛争解決手続を通じて本件の解決を目指していく。
(3)ドーハ・ラウンド交渉(多角的交渉の推進)
①ドーハ・ラウンド交渉の特徴・経緯
2001年にカタールのドーハで行われた第4回WTO定期閣僚会議において立ち上げが宣言されたドーハ開発アジェンダ(以下「ドーハ・ラウンド」)は、産品の貿易自由化のみならず、サービス貿易、アンチ・ダンピングなどの貿易ルール、環境、途上国問題も含んでおり、グローバリゼーションやIT化が進んだ新たな時代の要請に対応した幅広い分野を扱っていることが特徴である。日本にとって本ラウンドの推進は、①他の先進国及び主要途上国の関税を削減する、②我が国サービス産業の海外市場への参入を容易にする、③通商ルール強化により予見可能性を高め、通商紛争を予防する、④加盟国・地域の国内構造改革を推進するきっかけとなる、等の意義がある。
ラウンド交渉は、経済発展段階や利益・関心の異なる加盟国・地域間での合意を目指すという、複雑かつ困難なものである。先のウルグアイ・ラウンドでは8年間の歳月をかけ、一進一退を繰り返しつつ、関係者の粘り強い交渉により合意が達成された。ドーハ・ラウンドは、2008年7月の閣僚会合の決裂以後、先進国と新興途上国の対立により交渉が停滞し、2011年12月の第8回定期閣僚会議では、議長総括における「政治ガイダンスの要素」として、ドーハ・ラウンドについて、近い将来の一括受諾の見通しがないことを認めつつも、「新たなアプローチ」を見いだす必要性を共有し、進展が可能な分野で、先行合意を含め議論を進めることが合意された(第Ⅲ-1-5-1表)。
第Ⅲ-1-5-1表 ドーハ・ラウンド 一括受諾の交渉項目と主要論点
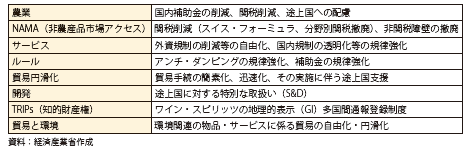
その後、非公式閣僚会議等を通じて、貿易円滑化、農業の一部、開発が進展可能な分野であると特定され、APEC閣僚・首脳会議等を通じて、同3分野からなる2013年12月の第9回定期閣僚会議の成果(バリ・パッケージ)へのコミットメントが繰り返し確認された。
②第9回定期閣僚会議
2013年9月のアゼベド新事務局長就任以降、第9回定期閣僚会議の成功を目指し、10月末までのバリ・パッケージ妥結を目標に交渉が加速された。3分野のうち、政治的対立が比較的少ない開発については進展が見られたものの、多くの論点が残る貿易円滑化と、食料安全保障目的の公的備蓄提案を巡る米国とインドの対立を抱える農業については交渉が難航した。アゼベド事務局長は交渉期限を順次延長し、交渉を続けたものの、11月26日の一般理事会において、最終合意を目前にしながら合意に至らず、今後の対応について加盟国間で議論してほしいと報告し、交渉妥結しないまま第9回定期閣僚会議に突入した。
第9回定期閣僚会議の開会後も、インドが食料安全保障目的の公的備蓄の取扱いについて恒久的な解決が必要であると強く主張するなど自国の立場を堅持したため、バリ・パッケージの成立が危ぶまれたが、米国とインドの間の水面下での交渉が続けられ最終的には両国間で合意に至った。バリ・パッケージの最終合意案に対して反自由化を主張する一部の国による強固な反対も見られたが、アゼベド事務局長の精力的な調整によって全会一致で合意に至った(第Ⅲ-1-5-2表)。
第Ⅲ-1-5-2表 バリ・パッケージの合意内容
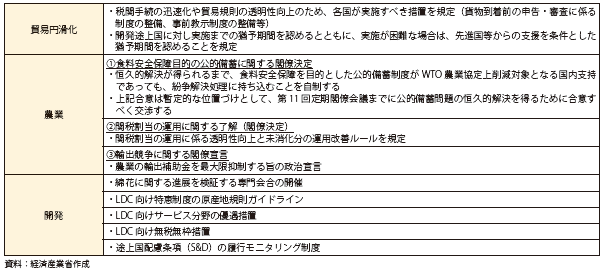
第9回定期閣僚会議で合意された貿易円滑化は、税関手続の簡素化及び透明化を通じて我が国企業のグローバルな活動を支えるものであると同時に、協定が締結されれば1995年のWTO設立以来初の全加盟国による協定となる。第9回定期閣僚会議は、13年間続くドーハ・ラウンド交渉において画期的な成果をあげ、WTOの交渉機能の信認維持に大きく貢献した(第Ⅲ-1-5-3図)。
第Ⅲ-1-5-3図 ドーハ・ラウンド交渉の経緯
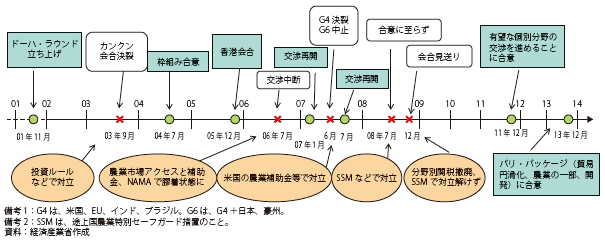
第9回定期閣僚会議では、バリ・パッケージに加え、12か月以内に今後のドーハ・ラウンドの残された課題についての作業計画を策定することについても合意した。2014年1月25日にスイス・ダボスで開催されたスイス主催WTO非公式閣僚会合では、今後のWTO交渉の進め方について議論が開始された。作業計画について、アゼベド事務局長から、分野間の相互関連性を考慮すること、プロセスの透明性及び包括性が重要であること、実現可能性と野心のバランスに注意を払うべきこと等について発言があった。現在、今後のWTO交渉について加盟国間で議論されており、我が国は、WTOによる多角的貿易体制の維持・強化に向けて、今後のWTO交渉の議論でも積極的に貢献していく。
(4)保護主義の抑止
2008年9月のリーマンショックに端を発する世界的な経済危機が発生して以降、自国産業支援や雇用確保を目的とした保護主義的措置の導入を求める政治的圧力が各国で高まった29。そうした国内の圧力を受けて保護主義に陥る国があると、他国の追随や報復などの連鎖を招き、世界全体に保護主義が蔓延し、世界貿易・経済に悪影響を及ぼすことが懸念された。そうした中で、多角的貿易体制を体現するWTOは保護主義を抑止し、自由貿易体制の維持に重要な役割を果たしている。
2013年12月に公表されたG20諸国・投資措置に関する報告書(第10版)では、調査期間中にG20諸国が新たに導入した保護主義的措置は前期比で増加しており、G20諸国が保護主義に対抗する努力を強化するよう訴えている。こうした報告書は、各国の貿易措置の監視を強化し、保護主義的措置の拡散を防止する効果が期待される。
また、G20やAPECの場では保護主義抑止を求める国際的な高いレベルの政治宣言がなされてきた。加盟国はWTO協定を遵守する義務を負うが、政治合意により協定以上のコミットが表明されるという意義がある。
G20、APECにおける保護主義抑止の政治宣言については、保護主義抑止の実効性を高めるため、2つの大きな要素が存在する。一つは、「スタンドスティル(現状維持)」のコミットメントであり、新たな保護主義的措置を今以上に実施しないことを約束している。もう一つは、既に導入された保護主義的措置を是正すること、すなわち、「ロールバック」のコミットメントである30。2013年9月のG20サンクトペテルブルグ・サミットでは、「ロールバック」のコミットメントを確認するとともに、「スタンドスティル」約束の2016年末までの延長に合意した。
29 『通商白書2009』第2章第3節参照
30 2012年のG20ロスカボス・サミットでも、カンヌ・サミットにおけるスタンドスティル及びロールバックのコミットメントが再確認された。(2012年6月G20カンヌ・サミット首脳宣言)
(5)ITA拡大交渉
①拡大交渉の背景
ITA(情報技術協定)は、IT製品144品目(HS6桁ベース:附属書A31掲載品目のみ)について、ITA参加国の当該品目の譲許税率を撤廃する取決めである。1996年12月のシンガポールWTO定期閣僚会議の際に日米EU韓など29か国で合意し、1997年に発効した。それ以降、中国、インド、タイなど参加国数が拡大し、2014年2月現在、78か国・地域(ただしメキシコ、ブラジル等中南米の主要国や南アフリカ等は未参加)が協定に参加している。これらの国のITA対象物品の世界貿易総額に占める割合は97%以上となっており、ITAは世界貿易総額の約15%(4.8兆ドル(2011年))の関税撤廃に貢献している。主な対象品目は、半導体、コンピュータ、通信機器、半導体製造装置等である。
現行協定の発効から16年が経過し、その間の技術進歩を受け、現行協定の品目リスト拡大と品目リストの対象範囲の明確化に対する各国産業界からの期待が高まっている。
ITA拡大交渉は、具体的には、技術進歩により高機能化、デジタル化している医療機器やデジタルビデオカメラ、高機能化・多機能化した新型集積回路等を新たにITA協定の対象とする品目リストの拡大や、範囲を巡って過去にWTOの紛争解決手続に付託されたこともある、ITAの対象等(現行協定の附属書Bから附属書Aへの移行を含む)の明確化を目的としている。
31 ITA対象品目のリストは、附属書A(対象品目がHSによって特定されている品目)と、附属書B(関税分類にかかわらず対象とされる品目リスト)で構成されている。
②拡大交渉立ち上げまでの経緯
2011年3月に、日米韓台等、17か国39業界団体(その後、同年5月に18か国41団体)がITA拡大を要請する共同声明を発表。これを受け、ITAの主要参加国(日米中韓台など)がほぼ全て参加するAPECで、日米が連携してWTOでのITA拡大交渉に向けた機運の醸成を開始した。具体的には、2011年11月のAPECホノルル首脳会議で、「APECエコノミーが品目及びメンバーシップ拡大に向けた交渉開始にリーダーシップを発揮していく」旨に合意した。
このAPEC首脳宣言を受けて、日米連携の下、2012年前半の交渉開始を目指して協定参加国間の意見調整を行ってきた。他方で、交渉立ち上げの最終局面まで、EUが関税交渉と非関税障壁交渉をリンクさせてITA拡大交渉を行うべきと強く主張し、ドーハ・ラウンドが停滞する中、産業界の期待に応え、WTOが迅速に結果を出すためには、関税交渉に集中すべきと主張する日米等各国との間で協議が続いた。日米は、各国と連携してEUに対して働きかけを行い、最終的には関税交渉と非関税障壁交渉を切り離すことでEUも合意し、交渉立ち上げの道筋ができた。
2012年5月には、日米等が共同で拡大交渉の開始を呼びかけるコンセプトペーパーをWTOに提出し、5月14日にジュネーブのWTO事務局で開催されたITA15周年記念シンポジウムの翌日に開催されたITA委員会公式会合で、ITA拡大及びそのための作業を開始していくことに各国の強い支持があり、実質的な交渉が開始された。
③拡大交渉の現状
2012年5月末以降、月に1回の頻度で日米EU韓台マレーシア等の関心国による交渉会合がジュネーブで開催され、関心国の要望品目を積み上げ、整理した「品目候補リスト」の作成が進んだ。
2012年秋以降の交渉会合からは、フィリピン、シンガポール、そしてIT製品の最大の貿易国である中国が参加し、「品目候補リスト」の絞り込みが行われるとともに、各国のセンシティブ品目に関する議論も行われた。しかしながら、2013年7月の交渉会合において、中国の広範なセンシティブ品目リストに大きな改善が見られなかったことから、7月の交渉会合は中断されることになった。
その後、APEC等の場を活用して、各国ハイレベルで中国に対する働きかけを続けた結果、2013年10月から交渉が再開された。
交渉再開後、2013年11月の交渉会合において、各国が妥結に向けて譲歩する中、中国等が多くのセンシティブ品目を維持し続けたこと等から、妥結に至らなかった。現在、早期の交渉再開を目指し、各国間で調整が行われている。
2014年2月現在、現行ITA対象品目の世界貿易額の90%以上をカバーする55か国・地域(内、EUは28か国)がITA拡大交渉に参加している。
(6)新サービス貿易協定の検討
1995年のGATS発効から長期間が経過し、この間にインターネットの普及をはじめとする技術革新の影響を受け、サービスの提供・消費の実態が大きく変化してきていることを背景に、WTOにおいても状況変化に対応した約束表の改訂や新たなルールの策定が求められてきた。しかしながら、ドーハ・ラウンドが膠着し、急速な進展が見込めない状況となり、各国はFTA/EPAの締結等を通じてサービス貿易の自由化を推進してきた。
こうした中、2011年12月に開催された第8回WTO閣僚会議では、①途上国が強く支持するドーハ開発アジェンダは打ち切らない一方、②一括妥結は当面実現不可能であることを認め、部分合意、先行合意等の可能な成果を積み上げる「新たなアプローチ」を試みることで一致した。
これを受け、2012年初頭から、「新たなアプローチ」の一環として、有志国・地域によるサービス貿易自由化を目的とした新たな協定の策定に関する議論が開始された。2012年7月5日には、交渉のモメンタムの維持・拡大、有志国・地域以外の国々に対する透明性の確保と議論への参加の奨励を目的として、それまでの約半年間の議論で方向性の一致したものを取りまとめたメディア・リリース「サービス貿易交渉の進展」が公表された。日本を含む有志国・地域は、自由化の約束方法、新たなルールなど、21世紀にふさわしい新たなサービス貿易協定に向けた議論を重ね、2013年6月には、本格的な交渉段階に移ったことを確認する共同発表を行った32。2014年3月末現在のメンバーは、23か国・地域(日、米、EU、豪州、カナダ、韓国、香港、台湾、パキスタン、イスラエル、トルコ、メキシコ、チリ、コロンビア、ペルー、コスタリカ、パナマ、ニュージーランド、ノルウェー、スイス、アイスランド、パラグアイ及びリヒテンシュタイン)である。
(7)環境物品交渉
①議論の背景
2001年のドーハ閣僚宣言において、「環境関連物品及びサービスに係る関税及び非関税障壁の撤廃及び削減」に関する交渉の立ち上げと、貿易と環境に関する委員会特別会合(Committee on Trade and Environment Special Session)の設置が盛り込まれ、これを受けて、CTESSにおいて関税削減・撤廃の対象となる環境物品リストに関する議論が行われてきた。
その後、ドーハ・ラウンド交渉が停滞する中で、APECに場を移して環境物品の関税削減・撤廃が議論された。2011年11月のAPECホノルル首脳会議で、2015年末までに対象物品の実行関税率を5%以下に削減する旨合意され、2012年9月のAPECウラジオストク首脳会議で、その対象品目として54品目に合意した。
②現状
APECにおいて環境物品54品目の関税削減が合意されたことも受け、2012年11月より、ジュネーブにおいて、環境物品自由化推進国で形成する「環境フレンズ」国(日本、米国、EU、韓国、台湾、シンガポール、カナダ、豪州、ニュージーランド、スイス、ノルウェー)で、WTOでの今後の環境物品自由化交渉の進め方についての議論が開始された。
2013年6月には、米国が「気候変動に関する大統領行動計画(the President’s Climate Action Plan)」を発表。その中で、APEC環境物品リストを基に、WTOにおいて、太陽光、風力、水力、地熱などクリーンエネルギー技術を含んだ環境物品の貿易自由化に向けた交渉を立ち上げること、今後1年間で当該品目の世界貿易シェアの90%を占める国の参加を目指すこと等に言及した。
その後、2013年10月のAPECバリ首脳会議において、APEC環境物品リストを基にWTOで前進する機会を探求する旨合意したことも受け、ジュネーブにおける議論が加速した。そして、2014年1月に、ダボスのWTO非公式閣僚会合の開催にあわせて、米国が主導して、有志国14か国・地域(日本、米国、EU、中国、韓国、台湾、香港、シンガポール、カナダ、豪州、ニュージーランド、スイス、ノルウェー、コスタリカ)が、WTO環境物品交渉の立ち上げに向けた声明を発表した。具体的には、APECバリ首脳宣言を歓迎し、地球環境保護及び多角的貿易体制の強化のため、WTOにおいてAPEC環境物品リストを出発点にグリーン成長に資する品目を幅広く追加するとともに、その最終的な関税撤廃を模索するという内容となっている。
我が国としては、日本企業の競争力強化、地球環境問題への貢献、交渉の場としてのWTOの再活性化という観点から、本交渉の推進に、関係国と連携しつつ積極的に取り組んでいく。
(8)政府調達協定
1994年に作成され、1996年に発効した政府調達協定は、協定発効から3年以内に新たな交渉を行うことが規定されていたことから、1997年から政府調達委員会において、ⅰ)協定の改善・手続の簡素化、ⅱ)開放的な調達を阻害する差別的な措置及び慣行の撤廃、ⅲ)協定の適用範囲(調達機関等)の拡大の3つを主な見直しの内容とする政府調達協定の改正交渉が開始された。
ⅰ)については、2006年12月に改正条文案に関する暫定合意が成立した。
ⅱ)及びⅲ)については、2004年7月に協定加盟国間で合意したモダリティ(交渉の枠組み)に基づき、協定加盟国間で提出されたリクエスト(他の協定加盟国に対する協定の適用範囲拡大の要求)及びオファー(自国の適用範囲拡大に係る提案)に基づいた二国間交渉が継続的に行われた。協定加盟国間の見解の相違を埋めるのは容易ではなく、長年にわたり合意を達成することができなかったが、2011年12月15日に第8回WTO定期閣僚会議に先立ち開催されたWTO政府調達閣僚会議において、14年間続いた交渉が実質的妥結に至り、2012年3月30日、政府調達委員会において協定改正議定書が正式に採択された。交渉の妥結により、各国が政府調達の対象とする機関を拡充するなど調達の範囲を拡大し、更なる政府調達市場が創出されることになった。例えば、日本は国際開放する物品・サービスの調達の基準額の引下げなど、米国は連邦政府の10機関を新たに国際調達の対象に追加、韓国は中央政府機関10機関及び地下鉄などを新たに国際調達に追加した。WTO事務局によれば、協定改正により、年間800億から1,000億ドル規模の新たな政府調達市場が創出されると推計されている。また、協定条文も改訂され、加盟交渉中及び実施の過程における開発途上国に対するS&D(特別のかつ異なる待遇)の提供など開発途上国の加盟を促進するための条項等が導入された。この改正の背景には、改正前の政府調達協定加盟国のほとんどが先進国であり、潜在的に大きな政府調達市場を有する開発途上国の加盟促進が重要な課題の1つである点が挙げられる。また、電子的手段の利用の奨励等、より効率的な手続を行うための規定も整備され、これらにより外国の政府調達への参加が容易になることが期待される。
政府調達協定改正議定書の発効のためには政府調達協定加盟国の3分の2が受諾しなければならない。2014年3月7日にこの要件を満たす10か国目の国(イスラエル)が改正議定書を受託し、WTO事務局へ寄託したため、その後30日目の日に当たる4月6日に改正議定書は発効した。我が国については、2013年12月3日に改正議定書の締結のための国会承認を得たのち、改正協定の実施のための国内法令等の改正作業を進め、2014年3月17日にWTO事務局へ受諾書を寄託、その後30日目の日に当たる4月16日に改正協定が発効した。改正議定書の発効により、我が国の供給者等が参入できる他国の政府調達の範囲が拡大するとともに、我が国自身の調達をより効率的かつ機動的に行うことが可能となる。
2.APECを通じた地域経済統合の推進と経済成長の促進
APECは、日本と豪州が主導して1989年に創設した、アジア太平洋地域における地域協力の枠組みであり、現在21の国・地域が参加している。
中長期的な目標としては、1994年にインドネシアのボゴールにて開催された首脳会議において、先進エコノミーは2010年(途上エコノミーは2020年)までに自由で開かれた貿易・投資を達成することが目標として掲げられている(ボゴール目標。なお、2010年のフォローアップにより、先進エコノミーについても、引き続き2020年までに自由で開かれた貿易・投資の達成を目指すこととされている)。
さらに、APECは、アジア太平洋地域の貿易・投資の自由化・円滑化だけではなく、世界の貿易・投資ルールの策定に大きな影響を及ぼしてきた。例えば、1996年のWTO閣僚会議における情報技術協定(Information Technology Agreement:ITA)の合意に際しては、APECとしても、直前に開催された首脳会議においてIT製品の関税撤廃を目指すことに合意し、WTOにおける合意を後押しするなど、大きな貢献を果たしている。
また、2006年のハノイAPEC首脳会議では、長期展望としてのアジア太平洋自由貿易圏(FTAAP)を含む、地域経済統合を促進する方法及び手段について更なる研究を実施することで合意し、それ以降、APECにおける地域経済統合に関する議論が急速に進展することとなった。
(1)最近の動き
①2010年(議長エコノミー:日本)
2010年には、我が国はAPEC議長エコノミーとして、首脳会議や閣僚級の会合から専門家レベルの会合に至るまで一連の会合を主催し、その成果として「緊密な共同体」、「強い共同体」、「安全な共同体」を目指す「横浜ビジョン」がまとめられた。
その中で、2010年時点においてボゴール目標の達成に向けた顕著な進展を遂げたことを報告するとともに、2020年のボゴール目標達成に向けて地域経済統合の取組を今後とも推進していくことが確認された。
また、FTAAPの実現に向けて具体的な手段をとることとされ、ASEAN+3、ASEAN+6及び環太平洋パートナーシップ(TPP)協定などの現在進行している地域的な取組を基礎として更に発展させることにより、包括的な自由貿易協定として追求していくことに合意した。さらに、FTAAPの実現の過程において、APECは、FTAAPに含まれるべき「次世代型」の貿易・投資の問題を規定・整理し、対処することに重要な役割を果たすことにより、FTAAPの育ての親(インキュベーター)として、貢献することとされた(「FTAAPへの道筋」)。
その他、世界の成長センターであるアジア太平洋地域の成長をより確たるものとするため、「均衡ある成長」や「あまねく広がる成長」、「持続可能な成長」、「革新的成長」、「安全な成長」の5つの成長を達成することを目的とする、長期的かつ包括的な「APEC首脳の成長戦略」を策定した。
②2011年(議長エコノミー:米国)、2012年(議長エコノミー:ロシア)、2013年(議長エコノミー:インドネシア)
2011年から2013年までのAPECでは、地域経済統合の推進やグリーン成長の促進、コネクティビティの促進など、「横浜ビジョン」や「成長戦略」の実現に向けた具体的な議論が進められた。
まず、地域経済統合の推進については、FTAAPの実現に向けて、次世代貿易・投資課題に対処しつつ、域内の貿易・投資の自由化・円滑化及び地域経済統合に向けて努力していくことが確認された。FTAAPに含まれるべき次世代貿易・投資課題については、2011年に(1)効果的、無差別かつ市場主導のイノベーション政策の推進(イノベーションと貿易)、(2)中小企業のグローバル生産網への参加強化、(3)グローバル・サプライチェーンを課題として選定し、(1)及び(2)について共通原則を策定したほか、2012年には、上記3つの課題について議論を深化させるとともに、新たな課題として、(4)FTAの透明性を選定、RTA/FTAの透明性に関するAPECモデル章を策定した。
また、グリーン成長については、2012年の首脳会議で、グリーン成長及び持続可能な開発に直接的かつ積極的に貢献する「APEC環境物品リスト」(太陽光発電パネル、風力発電設備を始めとする54品目から構成)に合意し、2011年のAPEC首脳会議における合意(ホノルル宣言)に従い、各エコノミーにおける実行関税率が、2015年末までに5%以下に引き下げられることとなった。環境物品の関税引下げは、WTOの場でも2001年のドーハ・ラウンドの立ち上げ以降、「貿易と環境」の検討の一環として議論が行われてきたが、現在に至るまで具体的な合意に至れていない困難な課題である。APECとWTOにおける議論とでは対象とする品目や削減目標等が異なるものの、APECで合意できたことは、APECが域内の貿易・投資の自由化推進に果たす役割を実証する顕著な成果であると言える。なお、APECでの合意が、WTOにおける環境物品貿易自由化への取組に新たな弾みを与えている。
コネクティビティの促進については、2013年、インドネシア議長のもと、優先課題の一つとして掲げられ、①インフラ開発・投資の促進を始めとした「物理的連結性」、②APEC構造改革新戦略の進展や国境を越えた教育の推進等を含む「制度的連結性」、③学生・研究者等ビジネス関係者の移動円滑化等を内容とする「人と人との連結性」について重点的に議論がなされ、成長の軸を連結するための青写真(blueprint)を描くとともに、それぞれの取組を加速していくこととなった。特に、物理的連結性に関しては、APEC・PPP(官民連携)専門家アドバイザリー・パネル、試験的PPPセンターの設置や、インフラ開発・投資におけるライフサイクルコストの重視などを内容とする「インフラ開発・投資に関する複数年計画」が策定され、これを通じて物理的インフラの開発・維持・刷新において協力していくこととなっている。なお、我が国としても、このような取組を具体的に進めていくべく、本年、インフラ開発・投資に関する人材育成のセミナーを開催することを提案し、歓迎されている。
第Ⅲ-1-5-4図 2013年APECにおける閣僚会議・首脳会議の模様

第Ⅲ-1-5-5図 APECにおける最近の議論の動向
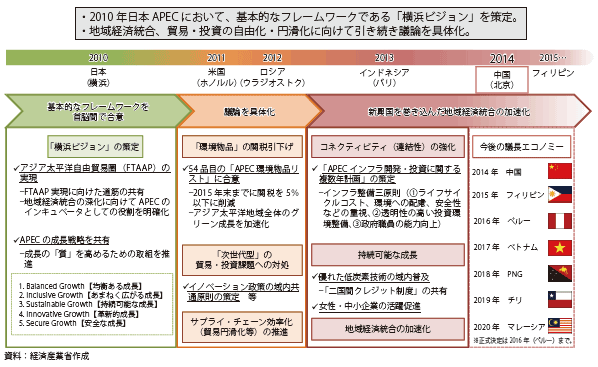
(2)今後の展望
2014年は、中国が議長を務め、「アジア太平洋パートナーシップを通じた未来の形成(Shaping the Future through Asia-Pacific Partnership)」をテーマに、(1)地域経済統合の進展、(2)創造的な発展、経済改革及び成長の促進、(3)包括的な連結性及びインフラ開発の強化、の3つの優先課題の下に議論を行っており、その成果が、11月に北京で開催されるAPEC首脳会議・閣僚会議においてとりまとめられる。
我が国としては、2010年の「横浜ビジョン」を基礎とした議論の流れを着実に引き継ぎつつ、サービス貿易の自由化やインフラ開発・投資の促進等に係る具体的な取組を進め、アジア太平洋地域の貿易・投資の自由化・円滑化を促していくことで、同地域の地域経済統合の推進と更なる発展に取り組んでいく。その上で、この地域の力強い成長力、インフラなどの旺盛な需要や巨大な中間層の購買力を取り込むことで、我が国に豊かさと活力をもたらすような通商政策を実現していく。
3.規制協力における世界の動向
世界経済のグローバル化が進展し、グローバル・バリュー・チェーンの重要性が認識されている中、国際的な通商政策の論点として、関税の撤廃・削減に加え、非関税措置の撤廃・調和を通じた「behind the border」(各国国内規制)に係るコスト削減をいかに進めていくかについて関心が高まっている。このような動きは今後の非関税措置における世界のルール形成に繋がるものである。
これまでも欧米産業界は、5~10年先の自社製品投入円滑化の観点から規制導入に係る働きかけを自国政府に行っており、米国政府やEUはそのような活動を支援し、規制導入を行っている。こうした動きを加速化させるものとして、米EU間での「環大西洋貿易投資パートナーシップ(T-TIP)」交渉において「規制協力」が産業分野ごとに議論されており、米欧産業界は協調して米EU間での実現可能性を検証し、双方の交渉担当者、規制当局等に対して積極的な政策提言を実施している。また、マルチの場では、通商政策の観点から「国際規制協力」の効果等に係る体系的な分析がこれまでなかったことから、OECDにおいては本年2月に開催したワークショップで議論が正に始まった段階である。
我が国でも、現在交渉中の日EU・EPAにおいて「規制協力」に係る議論を行っており、並行して本年4月に開催した日EU産業政策対話において「規制協力」に係る議論を開始している。今後、本分野における世界の動向を見つつ、我が国としても取り組んでいく必要がある。
