第4節 EPA/FTAの利用状況と利用促進のための情報提供について
我が国のEPA締結国との貿易額は2割弱であるが、現在交渉中の対象国を含めれば8割を超える。今後、既存のEPAについては、即時に関税が撤廃されなかった品目についても段階的な関税低減が進み24、一方で現在交渉中のEPA/FTAが締結されれば、EPA/FTAによる潜在的な関税節減メリットは増大していくと考えられる。このことを念頭におき、より幅広いユーザーがEPA/FTAを円滑に利用できるよう、現在の利用状況を分析し、利用促進のための情報提供の在り方について考察する。
EPAの経済上のメリットとして、1)WTOより進んだ貿易の自由化や、WTOでは扱われない分野でのルール作り、2)貿易の投資、自由化を進め、日本企業が海外に進出するための環境を整備し、両国の経済を活性化すること、3)資源、エネルギー、食料等の安定的輸入の確保や輸入先の多角化が挙げられる。それでは我が国企業が実際に認識しているEPA/FTAのメリットはどのようなものか。アンケート調査によれば、EPA/FTAのメリットを認識しているとする回答数のうち、相手国の関税撤廃による輸出競争力の強化が最も多く、続いて日本の関税撤廃による調達コストの低減が多かった。また外資規制の緩和や事業環境の整備、日系企業の事業拡大による売上げ増といった、関税減免と異なり数値的に把握が難しいメリットも認識されていることは注目に値する(第Ⅲ-1-4-1図)。
第Ⅲ-1-4-1図 我が国企業が認識しているEPA/FTAのメリット(複数回答)
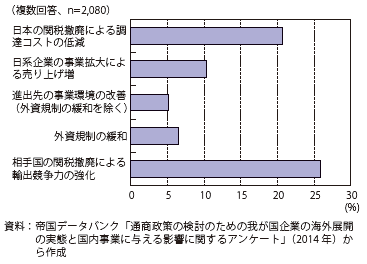
24 一例として、日本・フィリピンEPAに基づいて、従来日本からの輸出の際に10%から30%の税率で課されていた18品目の自動車部品の関税等が撤廃された。(Executive Order 147, Office of the President of the Philippines, 2014/2/13)
このように我が国企業に最大のメリットと認識されているEPAの優遇税率について、利用はどの程度広がっているかを確認する。2002年にシンガポールとのEPAが発効して以来、EPAの優遇税率を利用するために必要な原産地証明書発給件数は、EPA締結国数が増えるに従って増加している(第Ⅲ-1-4-2表、第Ⅲ-1-4-3図)。発給件数で上位を占めるのは、タイ(2013年度約6万6千件)インドネシア(2013年度約4万1千件)、インド(2013年度約2万6千件)であり、おおむね我が国からの輸出額が多い国となっている。(第Ⅲ-1-4-4図)。
第Ⅲ-1-4-2表 我が国の二国間EPA締結国、履行期間終了時の関税撤廃品目割合(品目ベース)
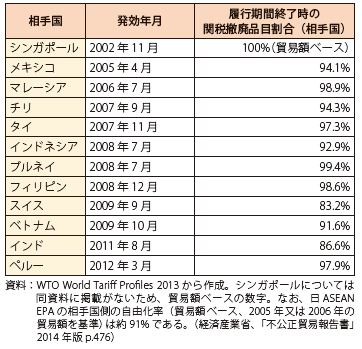
第Ⅲ-1-4-3図 EPA発効国への輸出額推移
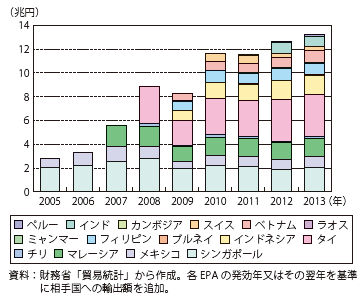
第Ⅲ-1-4-4図 適用EPA別原産地証明書の発給件数
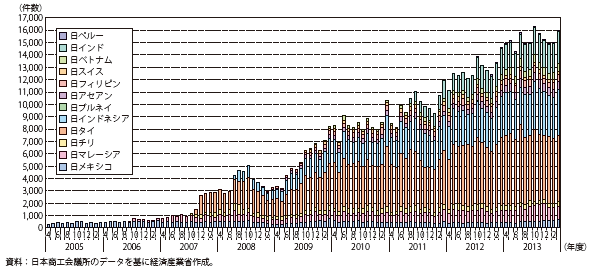
JETROによるジェトロ・メンバーズを対象としたアンケート調査においても、輸出又は輸入に際してEPAの優遇税率を利用していると回答する企業の割合は年々増加している(第Ⅲ-1-4-5図)。
第Ⅲ-1-4-5図 EPA/FTAを利用している企業の割合
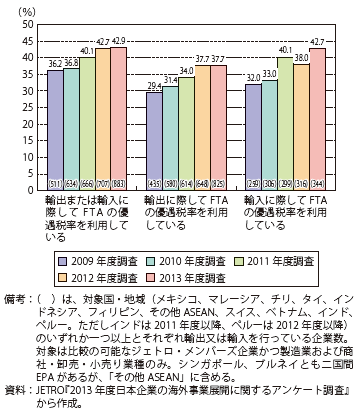
EPAの利用状況を企業単位で包括的に把握する統計はないものの、これらのデータを総合的に考えれば、我が国においてEPA/FTAのメリットを受ける企業の層は拡大していると言えよう。
続いて、規模別・業種別の利用状況について見ていく。特定原産地証明書取得のための登録事業所数は年々増加しており、中小企業の割合も上昇している(第Ⅲ-1-4-6図、第Ⅲ-1-4-7図)。中小企業の事業所の方が大企業のそれよりも多いことを考えれば、大企業に比べて中小企業の事業所単位でみた利用率は低いといえる。これは一般に大企業の方が中小企業に比べ貿易量が多いことに加え、中小企業の方が、EPA/FTAに基づく優遇税率の適用を受けるための事務的負担と関税節減のメリットをより厳しく判断すること等の理由が考えられる。なお、原産地証明書申請のための書類作成状況については、中小企業のうちの業種間及び中規模企業と小規模企業の間において、自社で作成するか取引先が作成したもののみ利用しているかについて大きな差はなかった。(第Ⅲ-1-4-8図)品目別の発給件数を見ると、輸出先国により違いはあるものの、おおむね我が国の主要輸出品目である鉄鋼、機械、電気、自動車・同部品等において件数が多い。(第Ⅲ-1-4-9図、第Ⅲ-1-4-10図、第Ⅲ-1-4-11図、第Ⅲ-1-4-12図)
第Ⅲ-1-4-6図 原産地証明書取得のための登録事業所数(地域別)
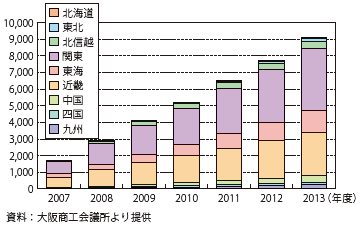
第Ⅲ-1-4-7図 原産地証明書取得のための登録事業所数(中小企業のみ)及び中小企業比率
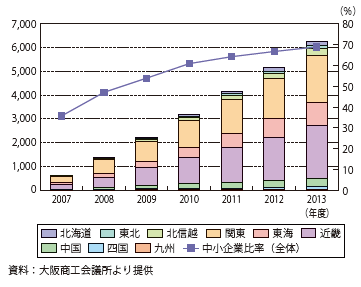
第Ⅲ-1-4-8図 中小企業の原産地証明書申請のための書類作成状況
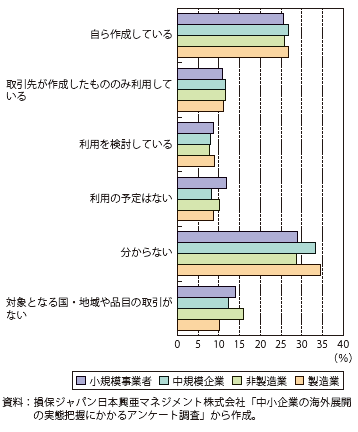
第Ⅲ-1-4-9図 品目別の原産地証明書発給件数(全協定)
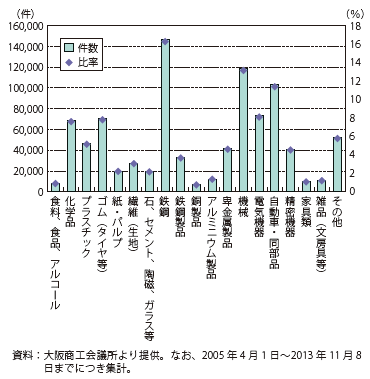
第Ⅲ-1-4-10図 品目別の原産地証明書発給件数(日マレーシアEPA)
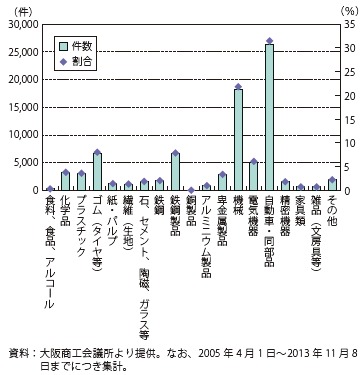
第Ⅲ-1-4-11図 品目別の原産地証明書発給件数(日タイEPA)
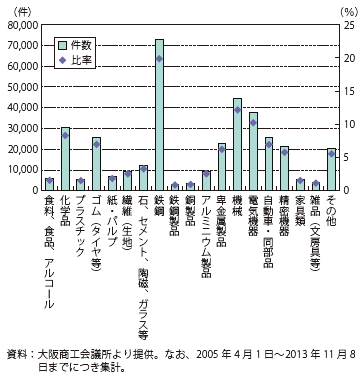
第Ⅲ-1-4-12図 品目別の原産地証明書発給件数(日インドネシアEPA)
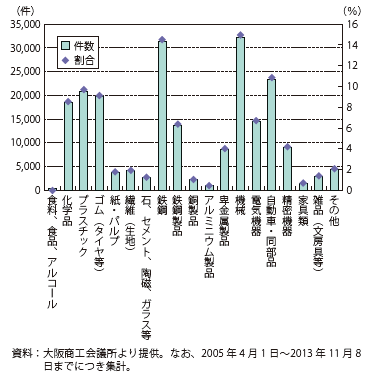
第Ⅲ-1-4-13図は、EPA/FTA優遇税率利用までのプロセス(以下「フローチャート」という。)の概略である。ここに示されるよう、自社の輸出先国と我が国の間にEPA/FTAが締結されているだけではEPA/FTAは利用可能ではなく、輸出品目がEPA/FTA優遇税率の対象であり、原産地規則を満たす場合にのみ利用可能となる。さらに、利用には一定のコストがかかるため、企業は利用のためのコストとメリットを勘案の上で利用することになる。
第Ⅲ-1-4-13図 EPA/FTA優遇税率利用までのプロセス概略(フローチャート)
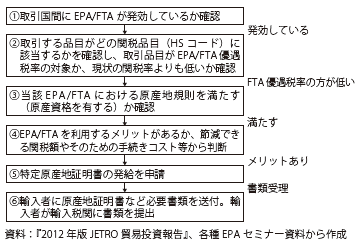
これまで、EPA/FTAの利用率が高くない理由として、フローチャート④のコストメリットの判断が着目されてきた。実際に、JETROが実施したアンケートにおいても、EPA/FTA利用上の問題点として、原産地証明の取得に関する手間や事務的負担が指摘されている(第Ⅲ-1-4-14図)。また、2008年のJETROのアンケート調査では「FTA利用に及ぶ関税差」という質問に対し、差が5~7%にのぼると全体の約3分の2が利用に及ぶという結果がでている(2012年『JETRO貿易投資報告』64頁)。つまり、企業の規模や輸出品目の特性等による違いはあると考えられるが、関税節減メリットが5%以上あることが一つの目安と認識されている。なお、厳しい原産地規則がEPA/FTAの利用を阻害するとの指摘は、他国においてもなされている25。
第Ⅲ-1-4-14図 EPA/FTA利用上の問題点(複数回答)
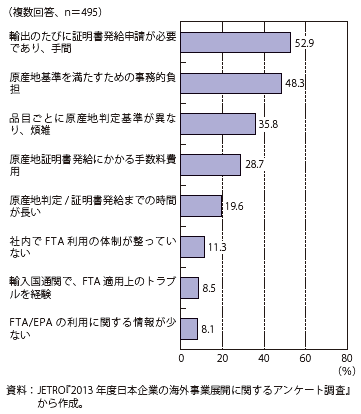
25 Intaravitak, Mudkum and Panpheng, “Rules of Origin and Utilization of Free Trade Agreements: An Econometric Analysis”, TDRI Quarterly Review, Vol. 26, No. 3.
一方で、EPA/FTAに関する情報を十分に知らないことや情報を入手するのに手間がかかることにより、潜在的なユーザーが利用していないという可能性も指摘できる。アンケート調査によれば、大企業と中小企業、製造業と非製造業を問わず、現在の情報提供の在り方で十分という意見も3割弱あるものの、どのようなホームページで情報提供がなされているかわからないと回答している(第Ⅲ-1-4-15図)。
第Ⅲ-1-4-15図 EPA/FTAの情報提供についての意見(複数回答)
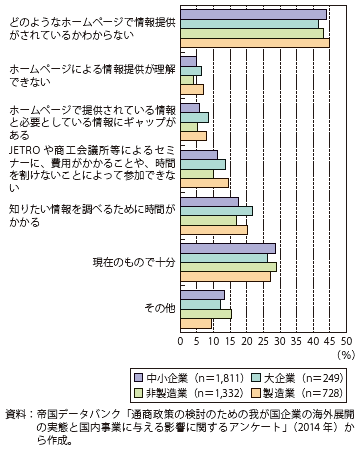
さらに、EPA/FTAの利用を検討するために必要な情報としては、EPA/FTAの締結国と対象品目、関税節減額といった先のフローチャートの①段階及び②段階の情報が多くを占めた(第Ⅲ-1-4-16図)。中小企業庁実施のアンケートにおいても同様の結果となっている(第Ⅲ-1-4-17図)。このことは、実際にEPA/FTAの利用のメリットを勘案するに至っていない潜在的利用者が一定程度存在することを示唆する。その他必要と挙げられた情報には、実際の他社の利用事例という回答も1割程度あった(第Ⅲ-1-4-16図)。日本政府の関係省庁やJETRO、商工会議所等のホームページで情報提供がなされ、一定程度参照されていることから(第Ⅲ-1-4-18図)、今後さらなる閲覧促進の取組が期待されるとともに、諸外国で行われているような、成功事例などより具体的なメリットを認識できるような情報を提供することも効果的と考えられる(第Ⅲ-1-4-19表)。
第Ⅲ-1-4-16図 EPA/FTAの利用検討に必要な情報(複数回答)
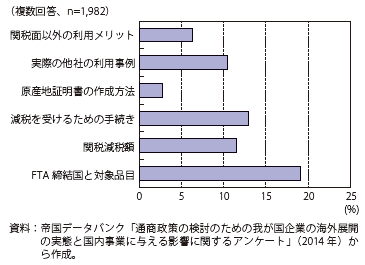
第Ⅲ-1-4-17図 EPA/FTAの利用検討に必要な情報(中小企業のみ、複数回答)
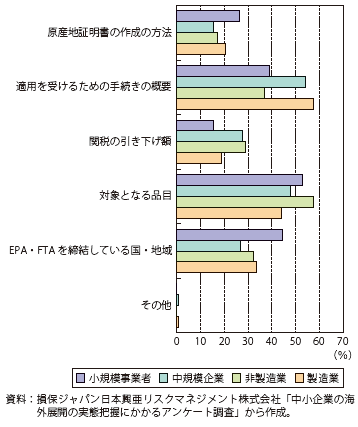
第Ⅲ-1-4-18図 EPA/FTA利用のために参照したホームページ(複数回答)
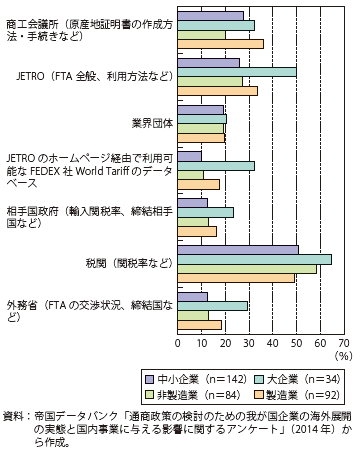
第Ⅲ-1-4-19表 諸外国で行われているEPA/FTA利用促進のための情報提供
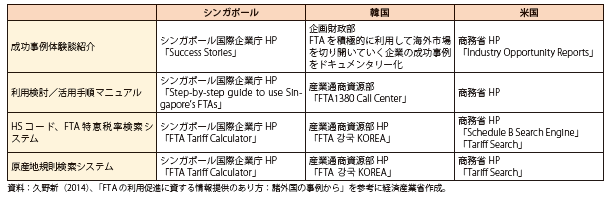
次に、EPA/FTAの利用促進のためには、既に利用している企業の利用開始のきっかけやどのような部署が担当しているか等を把握することが参考になると考えられるため、EPA/FTAを利用している企業の実態を確認する。利用開始のきっかけについて、規模別、業種別の違いがあるかを見ていくと、大企業や製造業は、中小企業や非製造業に比べ、JETROや商工会議所等のセミナーやアドバイスの割合が高いと言える。輸出先の要請(日系、外国企業)や社内からの提案については、業種別、規模別に見て大きな差は見られない(第Ⅲ-1-4-20図)。
第Ⅲ-1-4-20図 EPA/FTA特恵税率利用開始のきっかけ(複数回答)
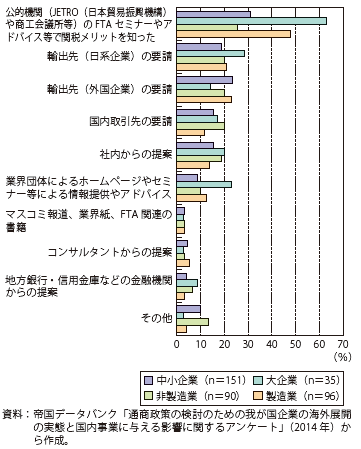
続いて、EPA/FTAを担当する部署について見ていく。利用に関する検討・提案を行う部署は、規模・業種別を問わず自社の割合が高く、続いて現地法人となった。規模別の特徴としては、大企業の方が中小企業に比べ、統括部門よりも、自社(事業部)や現地法人(生産・調達拠点)において提案を行っている割合が高いことが指摘できる(第Ⅲ-1-4-21図)。
第Ⅲ-1-4-21図 EPA/FTAの利用検討を行っている部署(複数回答)
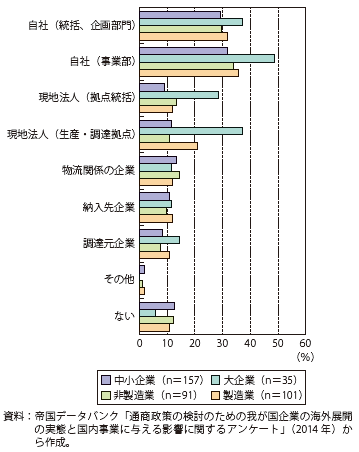
原産地証明書取得のための書類を作成している部署については、情報の入手しやすさを反映しておおむね自社の事業部や現地法人(生産・調達拠点)の割合が高かった(第Ⅲ-1-4-22図)。
第Ⅲ-1-4-22図 原産地証明書取得のための書類を作成している部署(複数回答)
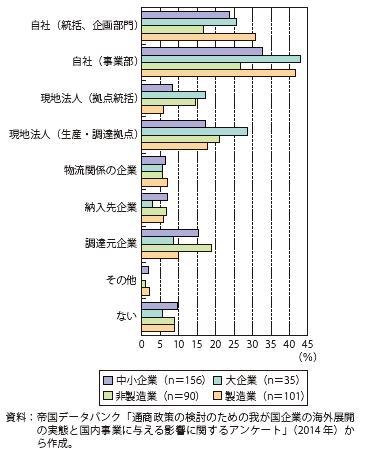
最後に、EPA/FTAを積極的に活用している企業について、EPA/FTAを利用し始めたきっかけや、円滑に利用するための工夫、及び業界団体による業種特性を踏まえた情報提供の取組を紹介する。
1.三ツ星ベルト株式会社
三ツ星ベルト株式会社は伝動ベルト及び関連機器(自動車向け、OA機器向け等)や搬送ベルト及びシステムの製造及び販売等を主力事業とし、アジアを中心に12の海外拠点を有する、資本金81億5,025万円、従業員数710人(グループ連結4,400人)の企業である。
①EPA/FTAを利用し始めたきっかけ、利用しているEPA/FTA
三ツ星ベルトは約5年前に生産・販売を行っているタイの現地法人からEPAの特恵関税を活用して日本から製品(ベルト等)を輸入したいとの依頼があり、日タイEPAを活用したことが、EPA/FTAの特恵税率を利用し始めたきっかけである。その後インドネシア、シンガポール、ベトナムと日本との間のEPAを現地法人の生産拠点向けに日本から原材料や製品(ベルト等)を輸出する際に活用するようになった。さらには、ASEAN間でのFTA(例:タイからシンガポールやベトナムへの製品輸出時)やACFTA(例:中国からインドネシアへの製品輸出時)といった第三国間FTAも活用している。
②利用に際しての苦労や解決方法、利用に伴うメリット
三ツ星ベルトにおいては、現在2名の社員がHSコードの管理や原産地証明書の取得のための書類作成、書類保存等EPA/FTAを利用するに当たって必要な事務手続に従事している26。EPA/FTAを利用し始めた当初は、原産品判定を受けるに当たり作る書類が多い事、HSコードを調べて製品がどの原産地基準に該当するのか調べる事等が特に苦労する点であった。また輸出製品がどのHSコードに該当するのかについて輸出国税関と輸入国税関との間で判断の違いがあったため、数か月後に原産品判定をし直すなどのトラブルも発生した。現在は、事務手続を行う社員に様々なノウハウが蓄積され、また技術担当の部署や輸入サイドの現地法人と密に相談を行いながら事務作業を進める等の対策をすることにより、事務的な負担はある程度減少している。しかしそのノウハウが個人に蓄積されており、社内の後任者に引継ぎや共有をすることが困難であることが課題とされている。
EPA/FTAの特恵関税を利用することによる三ツ星ベルトへのメリットとしては、輸入者からのコストダウンの要請に応えることができ他社との価格競争に有利である点や利益率プラスに作用している点があげられる。
26 日本と各国間のEPAについて。第3国間については現地法人のスタッフが対応。
第Ⅲ-1-4-23図 製品の写真
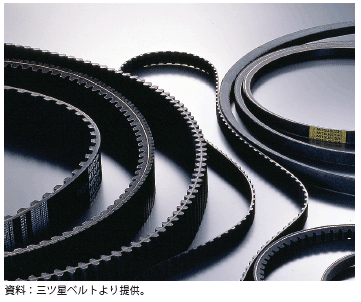
2.株式会社ダイフク
株式会社ダイフクは一般生産・流通向け、半導体・液晶生産ライン向け、自動車生産ライン向け、エアポート向けの搬送・保管・仕分システムの製造・販売を主力事業とし、グループとしてアジアを中心に20か国に海外拠点・現地法人を有する、資本金80億2,400万円、従業員数2,284人(グループ連結7,376人、2014年4月1日現在)の企業である。
①EPA/FTAを利用し始めたきっかけ、利用しているEPA/FTA
ダイフクのEPA/FTA利用は、2010年に、マレーシアの現地法人からの提案により、日本からの製品の輸出に日マレーシアEPAを利用したのが始まりである。その結果、グループの利益に還元することができたため、現地法人があり日本とEPAを締結している他の国との間でも活用しようとしたものの、申請手続における社内作業の増加の懸念等があり、なかなか拡大できなかった。
しかし、現地顧客(主に日系企業)からのEPA利用の要望がきっかけとなって、現在ではマレーシアのほかにタイ、インドネシアと日本との間のEPAを活用している。さらに、現在はACFTAを日本、中国、ASEAN各国との3国間貿易で活用している。例えば、日本本社とマレーシアの顧客の間で売買契約が成立し、製品の一部を中国の現地法人で製作してマレーシアの顧客に直送する場合、中国からの直送出荷品に関してACFTAで認められているリインボイスを活用している(第Ⅲ-1-4-24図)。
第Ⅲ-1-4-24図 3国間貿易でのACFTAの活用
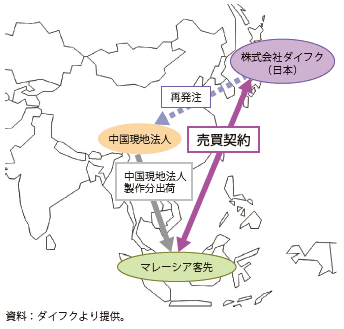
②利用に際しての苦労・問題点や解決方法、利用に伴うメリット
ダイフクにおいては、EPA/FTAの利用に当たり原産資格割合の試算は各事業部門が行い、原産地証明書の取得のための書類の作成、書類保存等の各種手続は、国際業務部がとりまとめている。
利用に際して発生した問題点は、まず製品が基本的にオーダーメードであり製品ごとに部品が異なるため、各製品について原産品判定申請が必要であること。さらに製品を構成する部品数が多いため、原産資格割合の試算に労力がかかることが言える。この問題点を解決するために、全ての購入部品を基本的に非原産とし、その部分の原産率試算業務をなくすことで短時間で原産資格を立証している。
また、製品全体(システム)として出荷すれば原産地基準をクリアし関税がかからないにもかかわらず、製品のサイズ等の事情により、部分ごとにパーシャルに出荷せざるを得ない。それに伴いHSコードが変化し、原産地基準をクリアできず関税がかかるようになってしまうという点があげられる。これに対しては取引先企業や現地法人等と協力して、輸出先国の税関と事前調整等を行っている。EPA/FTAを利用する最大メリットは、顧客の価格ニーズに対応することを可能とした点であると考えられる。
3.ダイヤモンド電機株式会社
ダイヤモンド電機株式会社は自動車機器(点火機器、電装機器)及び電子機器の製造及び販売等を主力事業とし、アジアを中心に10の海外拠点を有する、資本金21億9,000万円、従業員数(2013年3月末時点)936人(グループ連結2,164人)の企業である。
①EPA/FTAを利用し始めたきっかけ、利用しているEPA/FTA
ダイヤモンド電機が最初にEPA/FTAを利用したのは、2012年にインドの現地製造子会社からの要請に伴い、原材料(樹脂)を日本からインドへ輸出する際に日インドEPAを利用したケースである。その後、第三国間EPA/FTAを含め多くのEPA/FTAを活用している。タイの現地子会社立ち上げ時にEPA/FTA利用拡大の要請が現地子会社側よりあり、ASEANインドFTA(イグニッションコイルのインドからタイへの輸出時)、日タイEPA(コントローラー等の日本からタイへの輸出時)、韓国ASEAN FTA(イグニッションコイル部材の韓国からタイへの輸出時)を活用するようになり、また、インドネシアの現地子会社立ち上げ時にも同様の要請が現地子会社側よりあり、日インドネシアEPA、ASEAN間でのFTA、ASEANインドFTA(イグニッションコイルのタイ・インドからインドネシアへの輸出時等)を活用するようになった。
②利用に際しての苦労・問題点や解決方法、利用に伴うメリット
ダイヤモンド電機においては、EPA/FTA活用に際して、HSコードの管理及び原産地認定基準の対応を2名、システム登録や原産地証明書の取得を2名でそれぞれ他の業務と並行している。第3国間のEPA/FTA利用に際しての同様の事務手続は、基本的には適切なHSコードを適用しているか等を本社がしっかりとチェックをしつつ、現地法人が行っている。同社にとってのEPA/FTA利用に際しての苦労・問題点は主に4つあげられる。1点目は製品がどのHSコードに該当するのか輸出国・輸入国税関との間で確定させるのに労力がかかる点である。時に輸出国税関と輸入国税関との間で製品がどのHSコードに該当するのかの判断が異なり、トラブルが発生することもある。これを解決するために各国税関への事前教示、HSコードの照会、社内OJTでノウハウを蓄積するなどしている。2点目は現地通関業者を説得するために製品のHSコードを海外子会社にあらかじめしっかりと説明しておく必要がある点である。これをスムーズに行うために、海外子会社に対して、事前教示リストを提示し、また関税率表の解説や技術者説明書の共有等を行っている。3点目はあらゆるEPA/FTAを効率よく活用するためには自社で製作している製品はどのHSコードに該当し、関税率は各国間でどれくらいになっているのか逐一チェックしておく必要がある点である。そのために、国別・部品別に関税率がどうなっているのかデータベースを作成している。4点目は購入部材を利用し製品を輸出する際に付加価値基準をしっかりとクリアさせるようにする点である。構成部材データ(部品明細リスト)やその他費用(加工賃、物流費等)を事前に入手し試算を行うことにより、基準をクリアできず特恵関税を活用できないということにならないよう対策をうっている。
このように現在様々な問題点に対し解決策を打ち出しEPA/FTAを活用することにより、収益の改善や、顧客の獲得に成功している。
第Ⅲ-1-4-25表 ダイヤモンド電機の活用しているEPA/FTA一覧
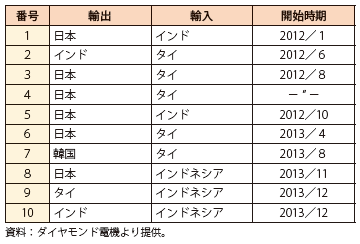
4.パナソニック株式会社
パナソニック株式会社は、電子部品、民生用家電、車載用機器、住宅設備など幅広い電子電気機器を製造・販売する総合エレクトロニクスメーカーである。多くの海外拠点を有し、資本金2,587億円、従業員数はグループ連結で約27万人である。
①EPA/FTAを利用し始めたきっかけ、利用しているEPA/FTA
パナソニックの事業部門では、EPA/FTAを積極的に活用している。ASEANにおけるFTAや北米におけるNAFTA等の地域自由貿易協定の利用経験があり、2000年代後半以降、日本がASEAN諸国や中南米とEPA/FTAを締結するようになってからは、それら二国間EPAも活用している。最近では、中国やASEAN拠点から東アジア域内や域外への輸出の際にもFTAを利用するなど活用は多岐に及んでいる。
②利用に際しての苦労・問題点や解決方法、利用に伴うメリット
パナソニックは、新規にEPA/FTAを活用しようとする事業部門に対しては、本社関連部門が支援を行っており、渉外部門において、EPA/FTAに関する情報提供を行っているほか、EPA/FTA利用のための問い合わせ窓口を設けている。輸出品目が多様であることから、本社関連部門、事業部門及びその海外拠点との間で情報共有を図るために、社内のイントラネットの整備やメールによる情報提供などに力を入れている。
社内からの問い合わせ状況から、EPA/FTA活用時の問題点としては、①EPA/FTA関税率やFTA原産地規則を調べるのに手間と時間がかかること、②輸入国と輸出国でHSコードが異なりEPA/FTA活用が困難な場合があること、③受発注が第3国を経由するビジネスで、EPA/FTAの活用が困難な場合があること、などが認識されている。(第Ⅲ-1-4-26表)このような問題はすぐには解決が困難だが、EPA/FTAを活用するためのコストとメリットを検討しながら、メリットがより大きいと判断される場合には即座に活用できる体制を整えておくことを基本的方針としている。
第Ⅲ-1-4-26表 EPA/FTAごとに異なる原産地規則の例
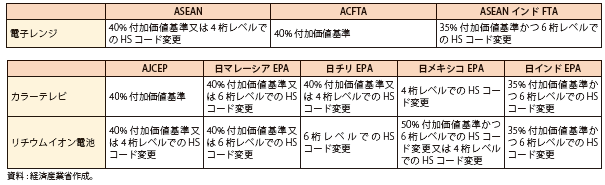
5.日本鉄鋼連盟
業界団体の中には、会員企業向けに充実した情報提供を行っている団体もある。例えば、一般社団法人日本鉄鋼連盟の会員専用ホームページでは、EPAを利用した輸出手続を行う際に必要となる情報(原産地規則や適用されるEPA税率等の確認、現行のMFN税率とEPA税率の比較)及び、原産地規則とはどのようなルールなのか、簡潔に解説する資料等を掲載している。
具体例を挙げれば、上記ホームページの画面上で日本の「輸出相手国」を選択すると、当該国とのEPA(例えばタイの場合は日・タイEPAとAJCEP)において決定しているEPA税率の譲許スケジュール表が確認できる。また、原産地規則についても、EPAごとに一覧表の閲覧が可能となっている。さらに、第三国間のFTAについても、ATIGA(ASEAN物品貿易協定)、AKFTA、ACFTA等の協定別に、協定文本体やその他関連情報等へのリンクが掲載されている。
本節では、我が国企業によるEPA/FTA利用促進という観点から、利用状況等を分析した。アンケート調査からは、既存の政府や関係機関による情報提供は、一定程度参照されてはいるものの、さらなる認知向上の余地があること、EPA/FTAをまだ利用していない企業にとっては、具体的な他社の利用事例などが検討開始のきっかけになる可能性が示唆された。また、EPA/FTAを積極的に活用している企業事例は、様々な情報を利用し、それぞれの会社に合う方法でEPA/FTA利用のために必要となるノウハウを、属人的なノウハウにとどめず、形式知化する努力を行っていることを明らかにしている。今後、EPA/FTAに関して提供されている情報(ホームページなど)の認知が進むことや、より多様な情報が提供されることによりEPA/FTAの利用のためのコストが低減し、EPA/FTAの利用促進につながることが期待される。
