第1節 我が国の対外収支動向
1.貿易収支の動向
(1)貿易収支動向の概観
まず、「輸出する力」を表す貿易収支の動向を様々な視点から見ていく。我が国の貿易収支は2011年に赤字に転じ、その後も年々赤字幅を拡大している。2014年の貿易収支は-12兆8,161億円と過去最大の赤字となった(財務省「貿易統計」ベース)。しかしながら、その拡大幅(前年差)を見てみると、2012年に4.4兆円、2013年に4.5兆円であったものが、2014年には1.3兆円となり、赤字拡大幅は限定的となっている1(第Ⅰ-1-1-1-1図)。
第Ⅰ-1-1-1-1図 貿易収支の推移
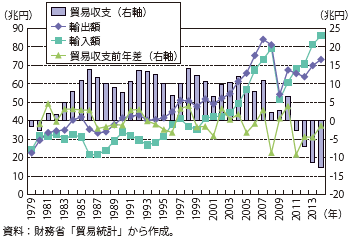
輸出入額の動きを見てみると、輸出入額ともに増加しているが、その増加率は輸入額の方が大きい。輸出額は一般機械や電気機器、輸送用機器等の輸出増を背景に、前年比4.8%増の73兆930億円となった(2年連続の増加)。一方、輸入額は電気機器や一般機械、原料別製品等の輸入増を背景に、前年比5.7%増の85兆9,091億円と過去最大の輸入額となった(5年連続の増加)。
直近の状況を月次で見てみると、貿易赤字幅は縮小傾向にある。2014年1月以降の貿易収支(季節調整値)を月次で見てみると、2014年初には、4月の消費税率引上げを前にした駆け込み需要の影響等により、1月には1.8兆円、3月には1.9兆円の赤字を計上していた。しかし、4月から11月までの期間は0.9兆円程度の赤字でほぼ横ばいに推移し、12月以降は赤字幅縮小基調で推移しており、2015年3月には49カ月ぶりの黒字となった(第Ⅰ-1-1-1-2図)。なお、1月と2月の数値に変動が見られるのは、春節(旧暦の正月)の影響が出ているものと考えられる(コラム1参照)。
第Ⅰ-1-1-1-2図 貿易収支の推移(季節調整値、2014年1月~2015年3月)
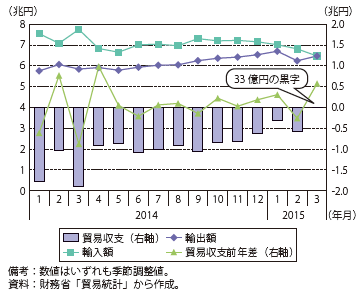
1 本項の数値は、2014年以前は確定値、2015年3月以前の輸出は確報値、2015年2月以前の輸入は確報値、2015年3月の輸入は9桁速報値を使用。
(2)相手国・地域別、品目別の貿易動向
国・地域別に見ると、2014年の最大の輸出相手国は米国(13.6兆円)、最大の輸入相手国は中国(19.2兆円)であったが、輸出入額の和である貿易額で見ると中国が最大の相手国(32.6兆円)となった(第Ⅰ-1-1-1-3表、第Ⅰ-1-1-1-4図、第Ⅰ-1-1-1-5図)。
第Ⅰ-1-1-1-3表 我が国の貿易額(相手国・地域別)
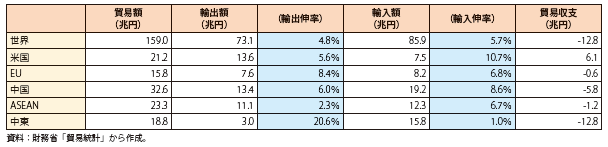
第Ⅰ-1-1-1-4図 主要国・地域別の輸出額の推移
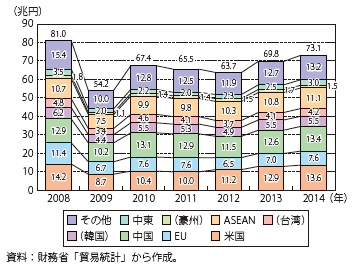
※棒グラフのデータは凡例の順に並んでいる
第Ⅰ-1-1-1-5図 主要国・地域別の輸入額の推移
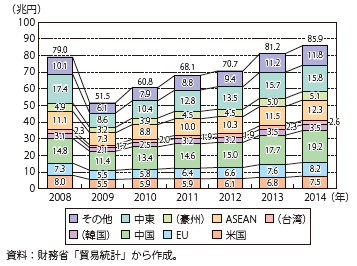
※棒グラフのデータは凡例の順に並んでいる
対米国貿易は、6兆1,066億円の黒字となった。輸出額は、自動車の輸出が大きく落ち込んだものの、原動機や鉄鋼等の輸出が増加したことにより、前年比で5.6%増加した(13兆6,493億円)。一方輸入額は、穀物類や液化石油ガス、原動機等の輸入増加により、前年比で10.7%増加した(7兆5,427億円)。
対EU貿易は、5,835億円の赤字となった。輸出額は、自動車等の輸出増加により、前年比で8.4%増加した(7兆5,853億円)。一方輸入額は、自動車や肉類、液化天然ガス等の輸入増加により、前年比で6.8%増加となり(8兆1,688億円)、対EU貿易としては過去最高の輸入額となった。
対中国貿易は、5兆7,950億円の赤字となった。輸出額は、科学光学機器や自動車等の輸出増加により、前年比で6.0%増加した(13兆3,815億円)。一方輸入額は、半導体等電子部品や通信機等の輸入増加により、前年比で8.6%増加し(19兆1,765億円)、対中国貿易としては、輸出入額ともに過去最高額となった。
対ASEAN貿易は、1兆1,720億円の赤字となった。輸出額は、自動車の部品等の輸出が落ち込んだものの、半導体等電子部品等の輸出増加により、前年比で2.3%増加した(11兆800億円)。一方輸入額は、原油及び粗油等の輸入が減少したものの、衣類・同付属品や非鉄金属鉱等の輸入増加により、前年比6.7%増加した(12兆2,520億円)。
対中東貿易は、12兆8,384億円の赤字となった。輸出額は、自動車等の輸出増加により、前年比で20.6%増加した(2兆9,875億円)。一方輸入額は、原油及び粗油等の輸入が減少したものの、液化天然ガスや石油製品等の輸入増加により、前年比で1.0%増加した(15兆8,260億円)。
次に主要品目別に見ると、輸出は、一般機械(前年比+6.4%)、電気機器(同+5.0%)、輸送用機器(同+3.5%)が特に大きな伸びを見せた。概況品ベースで見ると、自動車が大きく牽引した形である。輸入は、一般機械(前年比+13.3%)、原料別製品(同+12.0%)、電気機器(同+11.9%)を中心に全ての品目で伸びが見られた。概況品ベースで見ると、液化天然ガスが特に大きな伸びを見せた(第Ⅰ-1-1-1-6表、第Ⅰ-1-1-1-7図、第Ⅰ-1-1-1-8図)。
第Ⅰ-1-1-1-6表 我が国の品目別輸出入額
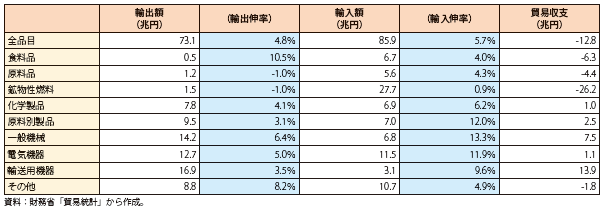
第Ⅰ-1-1-1-7図 主要品目別の輸出額の推移
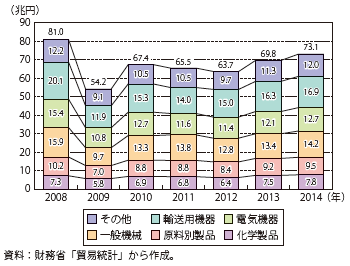
※棒グラフのデータは凡例の順に並んでいる
第Ⅰ-1-1-1-8図 主要品目別の輸入額の推移
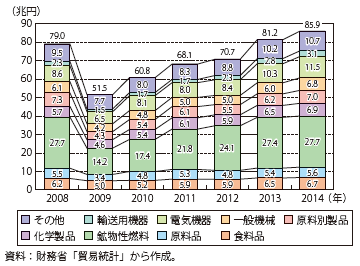
※棒グラフのデータは凡例の順に並んでいる
最後に貿易相手国・地域別の主要商品ごとの輸出額増減寄与度(前年比)を見ると、輸出に関しては、主に中東向け輸送用機器(輸出総額前年比寄与度0.44%)、米国向け一般機械(同0.39%)、中国向け電気機器(同0.34%)、EU向け輸送用機器(同0.32%)等の増加が輸出額増加に寄与している。同様に輸入に関しては、主に中国からの電気機器(輸入総額前年比寄与度0.30%)、ASEANからの電気機器(同0.24%)、米国からの食料品(同0.24%)、EUからの一般機械(同0.23%)等の増加が輸入額増加に寄与している(第Ⅰ-1-1-1-9表、第Ⅰ-1-1-1-10表)。
第Ⅰ-1-1-1-9表 貿易相手国・地域別の輸出額増減寄与度
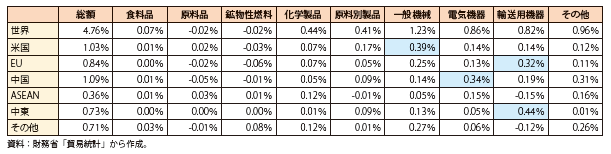
第Ⅰ-1-1-1-10表 貿易相手国・地域別の輸入額増減寄与度
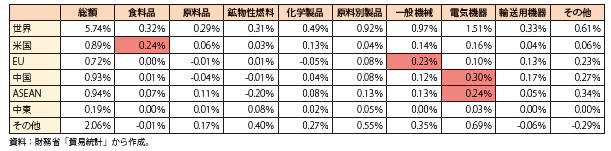
(3)数量・価格要因から見た貿易動向
2014年の貿易収支は、2013年に比べ1.3兆円貿易赤字が拡大した。この貿易収支の差を輸出数量要因、輸出価格要因、輸入数量要因、輸入価格要因の4つの要因に分解する2と、2014年の貿易赤字の最大の要因は輸入価格の上昇であることが分かる(第Ⅰ-1-1-1-11図)。
第Ⅰ-1-1-1-11図 貿易収支前年差の要因分解
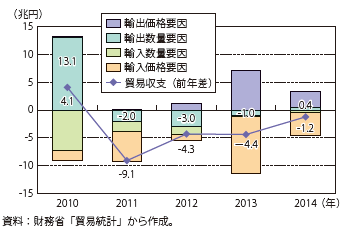
※棒グラフのデータは凡例の順に並んでいる
各要因の影響を見ていくと、輸出価格の上昇(前年差で黒字方向に2.9兆円寄与)と輸出数量の増加(同0.4兆円寄与)が黒字方向へ寄与(同3.3兆円寄与)し、輸入価格の上昇(前年差で赤字方向に4.1兆円寄与)と輸入数量の増加(同0.4兆円寄与)が赤字方向へ寄与(同4.5兆円寄与)していることがわかる。なお、輸出数量の増加、つまり為替の影響や名目上の価格上昇の影響等を除いた実質的な輸出の増加、が見られたのは、2010年以来4年ぶりとなる。
直近の状況を季節調整値で見てみると、2013年度中(2013年第2四半期から2014年第1四半期まで)は、輸入価格の上昇が一貫して貿易収支の赤字幅拡大に寄与していたことがわかる。さらに、2013年半ば以降は、消費税率引上げ前の駆け込み消費に向けた輸入数量の増加もあり、貿易収支赤字幅は拡大が続いた。この間、輸出価格は上昇し貿易収支の赤字幅を一定程度縮小させる要因になったものの、輸出数量の増加は見られなかった(第Ⅰ-1-1-1-12図)。
第Ⅰ-1-1-1-12図 貿易収支(季節調整値)前期差の要因分解
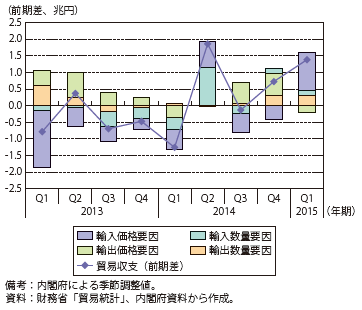
※棒グラフの上からの順番は以下の通り。
2013年 輸出価格要因・輸出数量要因・輸入数量要因・輸入価格要因
2014年 Q1 輸出数量要因・輸出価格要因・輸入数量要因・輸入価格要因
2014年 Q2
輸入価格要因・輸入数量要因
2014年 Q3 輸出価格要因・輸出数量要因・輸入数量要因・輸入価格要因
2014年 Q4
輸入数量要因・輸出価格要因・輸出数量要因・輸入価格要因
2015年 Q1
輸入価格要因・輸入数量要因・輸出数量要因・輸出価格要因
2014年4月の消費税率引上げ後は、国内個人消費が駆け込み需要の反動により大幅に減少した。こうした動きに伴い、輸入数量も大きく減少し、貿易収支赤字幅は消費税率引上げ前に比べて縮小することとなった。
2014年10-12月期以降は、輸出数量が緩やかに増加に向かっており、貿易収支赤字幅の縮小に寄与している。為替の円安方向での推移に伴い、輸出価格が上昇することも貿易収支の赤字幅縮小に寄与している。
2 本章における要因分解では、前年(同期)の各指数の数値に前年(同期)比伸び率を乗じて各要因を算出している。グラフによっては近似誤差が大きくなっている場合があるが、その補正は行っていない。
(4)輸入額に見る原油価格下落の影響
2014年後半から始まった原油価格の下落が、我が国の輸入に与えた影響について見てみる。原粗油や液化天然ガス(以下、LNG)に代表される鉱物性燃料は、2011年以降輸入総額の30%以上となるなど、我が国の輸入において特に大きな割合を占めている。原粗油とLNGの年間輸入額について見てみると、2013年と比較して2014年は、原粗油は3,714億円減少(前年比2.6%減)しているのに対し、LNGは7,919億円増加(前年比11.2%増)していることが分かる(第Ⅰ-1-1-1-13図)。
第Ⅰ-1-1-1-13図 鉱物性燃料輸入額及び輸入総額の推移
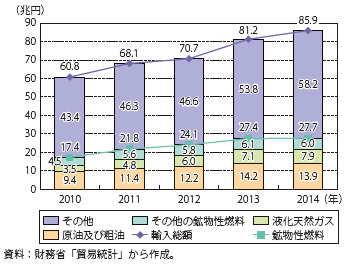
※棒グラフのデータは凡例の順に並んでいる
輸入増加額の前年同期差を四半期ベースで見てみると、2014年後半から国際的な原油価格の下落が始まったことを受け、特に2014年第4四半期から原粗油の輸入額が大きく減少している。同様にLNGの輸入額について見てみると、定常的に増加していたが、2015年第1四半期に減少に転じていることが分かる(第Ⅰ-1-1-1-14図、第Ⅰ-1-1-1-15図)。
第Ⅰ-1-1-1-14図 鉱物性燃料輸入額前年同期差の推移
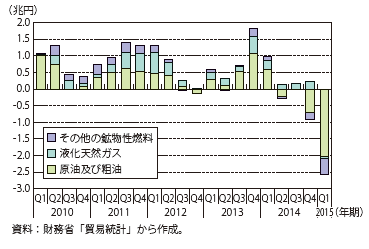
※棒グラフの上からの順番は以下の通り。
2010年Q1:(鉱物性燃料・液化天然ガスは確認できない)・原油及び粗油
2010年Q2:鉱物性燃料・液化天然ガス・原油及び粗油
2010年Q3:鉱物性燃料・液化天然ガス
2010年Q4~2012年Q2:鉱物性燃料・液化天然ガス・原油及び粗油
2012年Q3:液化天然ガス・原油及び粗油・鉱物性燃料
2012年Q4:(鉱物性燃料・液化天然ガスは確認できない)・原油及び粗油
2013年Q1:鉱物性燃料・液化天然ガス・原油及び粗油
2013年Q2:液化天然ガス・原油及び粗油・鉱物性燃料
2013年Q3~2014年Q1:鉱物性燃料・液化天然ガス・原油及び粗油
2014年Q2:液化天然ガス・原油及び粗油・鉱物性燃料
2014年Q3:液化天然ガス
2014年Q4:液化天然ガス・原油及び粗油・鉱物性燃料
2015年Q1:原油及び粗油・液化天然ガス・鉱物性燃料
第Ⅰ-1-1-1-15図 原油の国際価格の推移
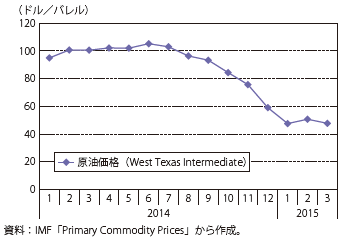
原粗油とLNG、それぞれの数量、価格、金額の伸び率を四半期で見てみると、原油安の影響が大きかったことが分かる(第Ⅰ-1-1-1-16表、第Ⅰ-1-1-1-17図、第Ⅰ-1-1-1-18表)。原粗油は第1四半期には数量、価格ともに前年同期比プラスであったものの、第2四半期には数量がマイナスとなり、第4四半期には原油安の影響を受けて価格もマイナスとなった。2015年第1四半期には、価格が前年同期比-41.9%の大幅なマイナスとなったことが大きく影響し、輸入金額は伸び率で前年同期比-48.6%、実数値で前年同期差-2兆144億円の輸入額減少を記録した。原粗油輸入額前年同期差を要因分解すると、価格下落による輸入額減少幅は1.5兆円超と試算できる。
第Ⅰ-1-1-1-16表 原粗油の輸入に関する前年同期との比較(2014年)
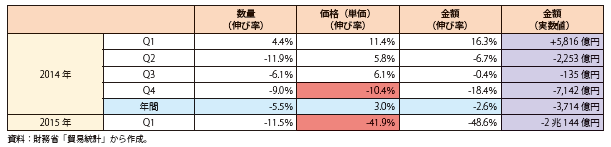
第Ⅰ-1-1-1-17図 原粗油輸入額前年同期差の要因分解
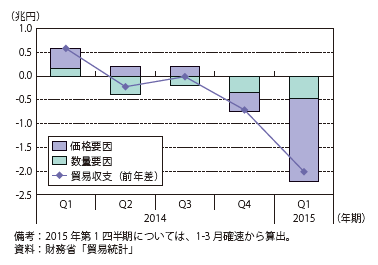
※棒グラフの上からの順番は以下の通り。
2014年Q1:価格要因・数量要因
2014年Q2:価格要因・数量要因
2014年Q3:価格要因・数量要因
2014年Q4:数量要因・価格要因
2015年Q1:数量要因・価格要因
第Ⅰ-1-1-1-18表 液化天然ガス(LNG)の輸入に関する前年同期との比較(2014年)
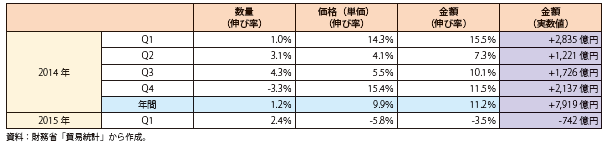
一方、LNGは2014年の年間では数量が前年比+1.2%、価格が前年比+9.9%の伸びとなり、輸入金額は伸び率で前年比+11.2%、実数値で前年同期差+7,919億円の輸入増となった。また、2015年第1四半期には、価格が前年同期比-5.8%のマイナスとなったことを受け、輸入金額は伸び率で前年同期比-3.5%、実数値で前年同期差-742億円の輸入額減少を記録した。
(5)まとめ
「輸出する力」を見る出発点として、2014年の貿易動向を概観した。2014年は輸出数量の前年比増や、原粗油の輸入額減少等により、収支では赤字縮小傾向が見られた。「輸出する力」を見るには、輸出の変動が何に影響されているかを見る必要がある。また、世界のどの市場において伸びているか、またどのような品目で競合していたり、輸出を伸ばしているかを見る必要がある。これらの分析については第Ⅱ部第1章第1節で行う。
2.サービス収支の動向
貿易収支に続き、その他の経常収支項目についても順次見ていく。サービス収支とは、各種サービスの取引に係る収支を計上するもので、「輸送収支」「旅行収支」「その他サービス収支」の3つに大別される。なお、「その他サービス収支」には、ロイヤリティ等を計上する「知的財産権等使用料」や「建設」、「通信・コンピュータ・情報サービス」等が含まれる(第Ⅰ-1-1-2-1図)。
第Ⅰ-1-1-2-1図 サービス収支の内訳
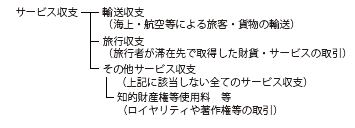
我が国のサービス収支は、赤字で推移してきたが、近年その赤字幅は縮小しつつあり、2014年は、-3兆801億円と過去3番目に小さい赤字額となった(第Ⅰ-1-1-2-2図)。その要因として、旅行収支の赤字幅縮小と知的財産権等使用料収支の黒字幅拡大等が挙げられ、それぞれ過去最小の赤字額、過去最大の黒字額を記録した。
第Ⅰ-1-1-2-2図 サービス収支の推移
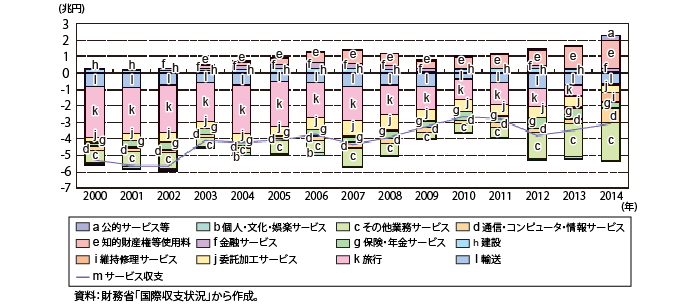
旅行収支の赤字は2000年代前半にはサービス収支赤字の半分に相当したが、近年その赤字幅は縮小しつつある(第Ⅰ-1-1-2-3図)。旅行収支の赤字が縮小している主な要因としては、訪日外国人の増加が挙げられ、2014年の年間訪日外国人数は1,341万人と過去最高を記録している。旅行を通したヒトの呼び込みは、「呼びこむ力」を表すものとして、第Ⅱ部第1章第2節でより詳しく分析する。
第Ⅰ-1-1-2-3図 旅行収支、訪日外客数、出国日本人数の推移
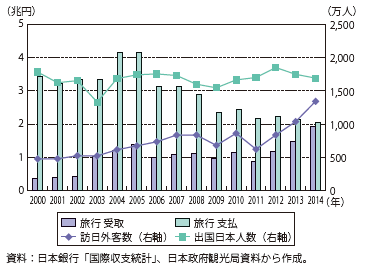
※各年左側の縦棒が旅行受取、右側が旅行支払である
知的財産権等使用料収支は、2003年に黒字に転じてからその黒字幅を拡大してきており、2014年は1兆6,973億円と過去最大の黒字となった(第Ⅰ-1-1-2-4図)。その要因としては、産業財産権等使用料(ロイヤリティ等)の受取増加が挙げられ、その額は2014年には前年比27.4%増の3.7兆円で過去最大となっている。一方、著作権等使用料(ソフトウェア等の使用権料等)の収支はその赤字幅を拡大させている。知的財産権等使用料は「外で稼ぐ力」を表すものとして、第Ⅱ部第1章第3節の我が国の海外現地法人の分析の中でより詳しく検証する。
第Ⅰ-1-1-2-4図 産業財産権等使用料・著作権等使用料(受取・支払)の推移
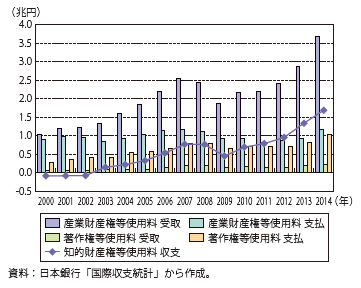
※各年の縦棒は産業財産権等使用料受取・産業財産権等使用料支払・著作権等使用料受取・著作権等使用料支払の順に並んでいる
3.第一次所得収支の動向
第一次所得収支とは、直接投資や証券投資等に係る収益を計上するもので、「雇用者報酬」「投資収益」「その他第一次所得収支」の3つに大別される。「投資収益」は、海外現地法人からの還流や内部留保が計上される「直接投資収益」のほか、「証券投資収益」と「その他投資収益」が含まれている(第Ⅰ-1-1-3-1図)。
第Ⅰ-1-1-3-1図 第一次所得収支の内訳
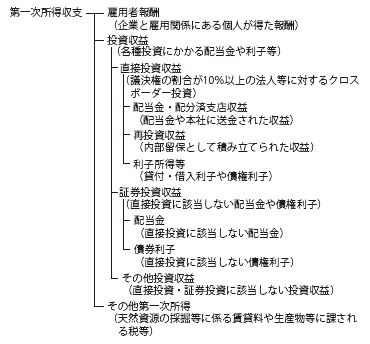
第一次所得収支は黒字で推移してきており、2014年は18兆1,203億円と過去最大の黒字となった。その主な要因としては直接投資収益と証券投資収益の黒字幅拡大が挙げられる(第Ⅰ-1-1-3-2図)。
第Ⅰ-1-1-3-2図 第一次所得収支の推移
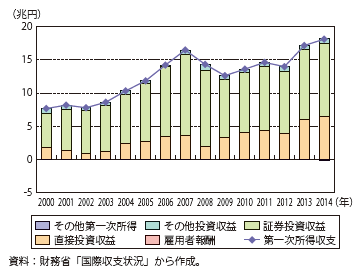
※棒グラフの上からの順番は以下の通り。
その他投資収益・証券投資収益・直接投資収益
第一次所得収支の推移を見てみると、2008年からの世界経済危機と2011年に発生した東日本大震災の影響を受けて落ち込みが見られたものの、基本的には一貫して増加基調を維持しており、直近では、2013年、2014年と2年連続で過去最大の黒字を記録した。これは対外投資残高の増加に伴う、直接投資収益と証券投資収益双方の受取の増加によるもので、直接投資収益は2014年に6兆5,477億円と過去最大の黒字となり、証券投資収益は10兆9,896億円と過去3番目の大きさの黒字となった(第Ⅰ-1-1-3-3図)。
第Ⅰ-1-1-3-3図 対外投資残高及び投資収益の推移
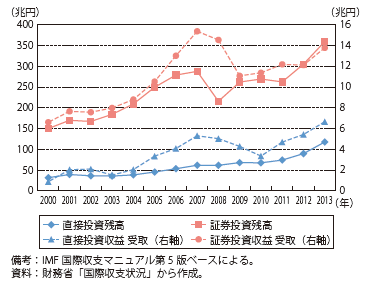
直接投資収益の黒字幅拡大の主な要因としては、配当金・配分済支店収益の受取増加が挙げられる(第Ⅰ-1-1-3-4図)。また、証券投資の黒字幅拡大の主な要因としては、債券利子(中長期債)の受取増加が挙げられる(第Ⅰ-1-1-3-5図)。
第Ⅰ-1-1-3-4図 直接投資収益の推移(2000年~2014年)
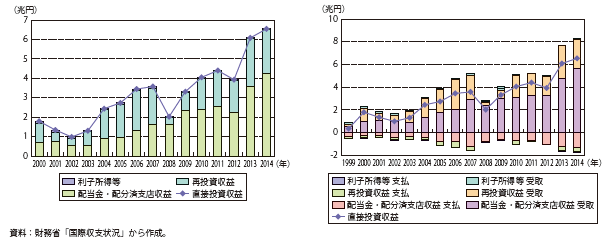
第Ⅰ-1-1-3-5図 証券投資収益の推移(2000年~2014年)
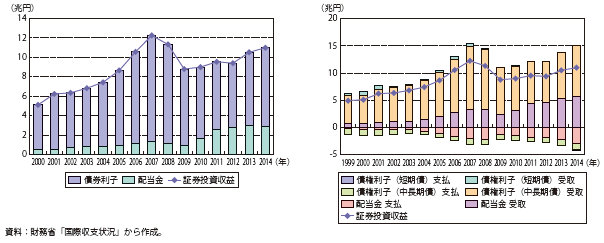
我が国の直接投資収益と証券投資収益について、双方とも黒字幅が拡大していることが確認できたが、その収益率は国際的に見てどのような水準にあるのだろうか。主要国との比較を行う。比較対象国は、GDP上位国である米国、英国、フランス、ドイツ、中国に、近隣国として韓国を加えた6カ国とし、2005年から2013年までの各国の対外投資残高と収益率をドルベースで比較する。
まず主要国の対外直接投資残高を見ると、世界経済危機の際に米国を始めとする一部の国において落ち込みが見られたものの、各国ともおおむね増加傾向にある。米国の残高が他国に比べ突出して多く、その増加幅も他国を上回っている。日本も緩やかな増加傾向にはあるが、相対的に低い水準にとどまっている(第Ⅰ-1-1-3-6図)。
第Ⅰ-1-1-3-6図 各国の直接投資残高の推移
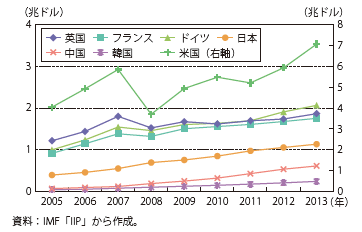
その上で各国の直接投資収益率を見てみると、2011年以降は全体的に低下傾向にあることが分かる。特に英国と米国の下げ幅は大きく、2013年には、2011年比でそれぞれ3.5%と2.6%の低下となっている。2013年時点の収益率の水準を見ると、日本はドイツ、中国、フランスよりも高い水準にあるが、米国、韓国よりも低い水準となっている(第Ⅰ-1-1-3-7図)。
第Ⅰ-1-1-3-7図 各国の直接投資収益率の推移
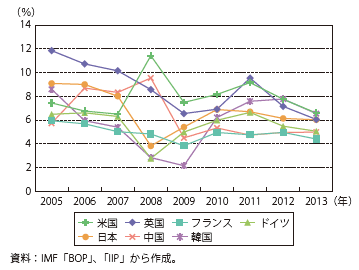
次に、対外証券投資についても同様に比較を行う。但し、中国と韓国はその他の国と比較して残高が小さいため、対外証券投資に関しては比較対象から除くこととする。
対外証券投資残高を見ると、世界経済危機の際に落ち込んだものの、各国ともおおむね増加傾向にある。対外直接投資と同様、米国の残高が他国に比べ突出して多く、その増加幅も他国を上回っている。日本は、米国、英国に次ぐ水準となっている(第Ⅰ-1-1-3-8図)。
第Ⅰ-1-1-3-8図 各国の証券投資残高の推移
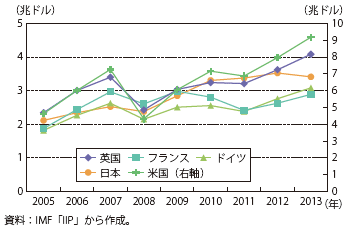
対外証券投資収益率を見ると、直接投資収益率と同様に、2011年以降は全体のトレンドとして低下傾向にあることが分かる。特にドイツと英国の下げ幅は大きく、2013年には2011年比でそれぞれ1.2%と0.8%の低下となっている。また、比較対象の5か国の中で収益率を比較すると、日本は2005年以降最も高い水準を維持している(第Ⅰ-1-1-3-9図)。
第Ⅰ-1-1-3-9図 各国の証券投資収益率の推移
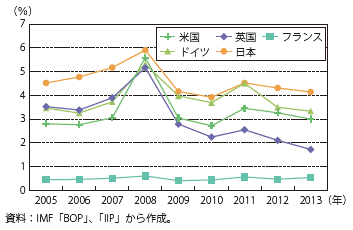
ここまで、第一次所得収支の動向を見てきたが、特に直接投資収益に含まれる配当金・配分済支店収益等の受取の動向は、「外で稼ぐ力」を表すものとして、第Ⅱ部第1章第3節における我が国海外現地法人の分析の中でより詳しく検証する。
