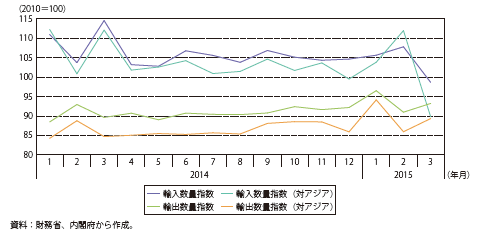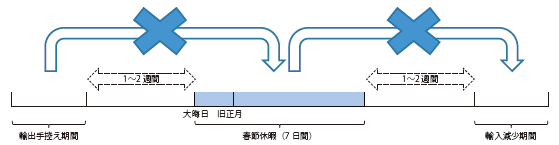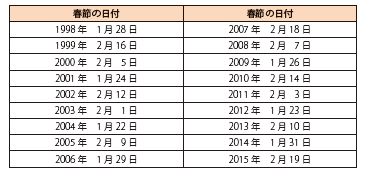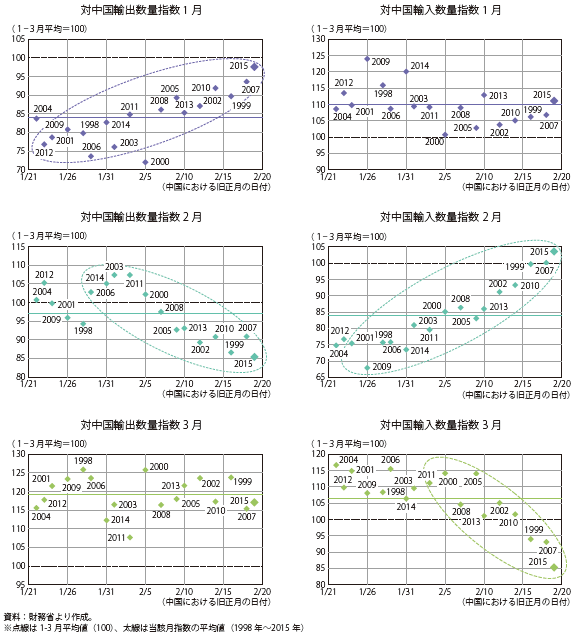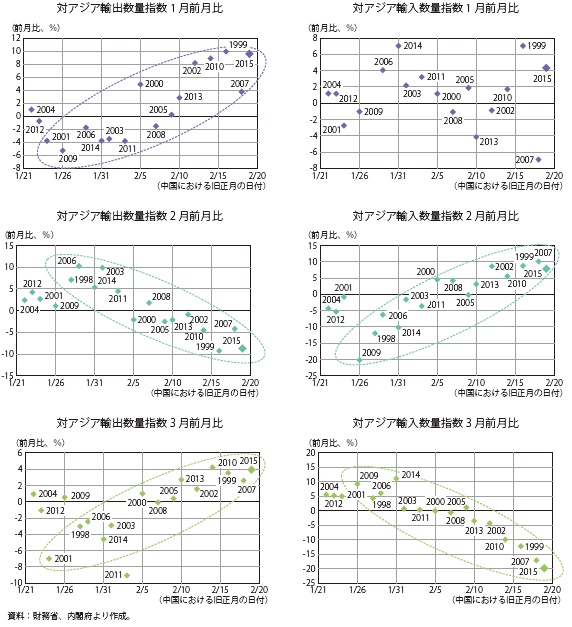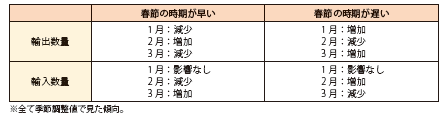第2節 経常収支構造の国際比較
1.我が国の経常収支の動向
前節では、我が国の経常収支の項目別動向を見たが、本節では経常収支全体を俯瞰するとともに、我が国と主要国とで特徴に相違が見られるのか比較してみる。
まず、我が国の経常収支は、2014年には、2兆6,458億円の黒字と比較可能な1985年以降最小となり、4年連続で黒字幅を縮小させた(第Ⅰ-1-2-1-1図)。2000年以降の動向を見てみると、2001年から増加していた経常収支は2007年に24兆9,490億円と過去最高の黒字を記録したが、2008年のリーマン・ショックに端を発した世界経済危機の影響により、2008年、2009年と2年連続で経常収支黒字幅の縮小が見られた。その後、2010年に一度黒字幅を拡大したものの、2011年の東日本大震災の影響による鉱物性燃料輸入の大幅な増加による貿易収支の赤字転化とともに黒字幅が縮小し続けている。このように、近年の経常収支の黒字幅の縮小は主として貿易収支の赤字化によるものである。
第Ⅰ-1-2-1-1図 経常収支の推移(2000年~2014年)
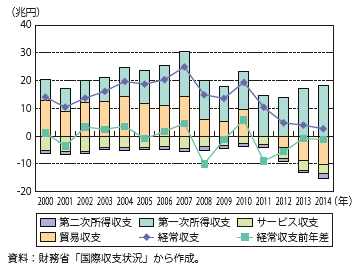
また、2014年1月以降の動きを月次(季節調整値)で見てみると、2014年初めは、4月の消費税引上げを前にした駆け込み需要が貿易収支赤字幅の拡大圧力となり、経常収支が赤字となっていたが、4月以降は貿易収支の赤字幅が縮小したことで経常収支が黒字転化し、7月、8月は赤字となったものの、2015年3月まで7か月連続の黒字となっている(第Ⅰ-1-2-1-2図)。また、2015年1月には貿易収支が2011年9月以来40か月ぶりに黒字(財務省「国際収支状況」の貿易収支ベース3)となるなど改善基調が見られる。2月には一時的に再度赤字転化しているが、春節(旧暦の正月)の影響によるものと考えられる(コラム1参照)。
第Ⅰ-1-2-1-2図 常収支の推移(季節調整値、2014年1月~2015年3月)
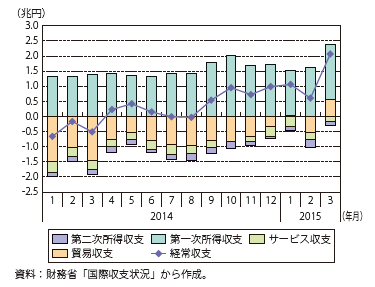
3 「貿易統計」の貿易収支と「国際収支状況」の貿易収支は異なるが、これは計上方法が異なることに起因するものであり、「貿易統計」の方が輸入額が大きく計上されるため、貿易赤字額が大きくなる傾向にある。
2.主要国の経常収支構造
(1)主要国における経常収支と貿易収支との関係
次に、我が国の経常収支構造を念頭に、主要国と比較してみる。比較対象国は、GDP上位国である米国、英国、フランス、ドイツ、中国に、近隣国として韓国を加えた6カ国とし、2005年から2013年までの各国の対外投資残高と収益率をドルベースで比較し、各国の対外的稼ぎ方とその変化を明らかにする。
経常収支と貿易収支との関係について、各国の貿易収支と経常収支の対GDP比の推移を見ると、多くの国が45度線と平行の方向での推移をしたことが分かる。対象とした国において経常収支に対する貿易収支の影響が大きいことを示している。また、移動距離を見ると、比較対象国の半数程度がリーマン・ショックのあった2008年からその翌年の2009年にかけて最も大きく移動していることが分かる。全比較対象国の2008年から2009年にかけての推移を見ると、米国、英国、フランスは、輸入額減少によって、貿易収支対GDP比がプラス方向へ推移したが、ドイツと中国はマイナス方向へ推移している。日本の場合は、2008年から2009年にかけての変化はほとんどないもの、2011年以降、東日本大震災に起因した輸入額増加によって貿易収支対GDP比がマイナス方向へ推移している(第Ⅰ-1-2-2-1図)。
第Ⅰ-1-2-2-1図 各国の貿易収支対GDP比と経常収支対GDP比の推移(2005年~2013年)
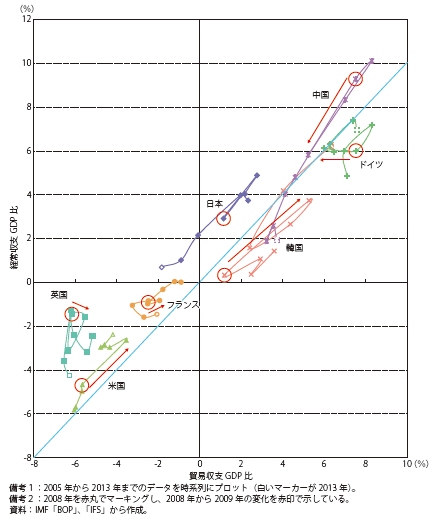
(2)主要国の経常収支の動向
次に各国の経常収支構造について推移を見ていく。
各国の経常収支構造を比較すると、貿易収支の黒字・赤字によって大きく2つの型に分けられることが分かる。まず、第1のグループは、貿易収支と第一次所得収支が黒字で、サービス収支が赤字の国であり、日本(2000年代)、ドイツ、韓国(2010年代)がこれに含まれる(第Ⅰ-1-2-2-2図、第Ⅰ-1-2-2-6図、第Ⅰ-1-2-2-8図)。これらの国は、大幅な貿易黒字により経常収支でも黒字となっている。第2のグループは、貿易収支が赤字で、サービス収支と第一次所得収支が黒字の国であり、米国、英国(2000年代)、フランスがこれに含まれる(第Ⅰ-1-2-2-3図、第Ⅰ-1-2-2-4図、第Ⅰ-1-2-2-5図)。これらの国は、サービス収支と第一次所得収支が黒字であるものの、大きな貿易赤字幅を補いきれず経常収支では赤字となっている。
第Ⅰ-1-2-2-2図 日本の経常収支の推移
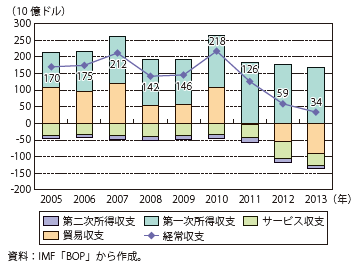
第Ⅰ-1-2-2-3図 米国の経常収支の推移
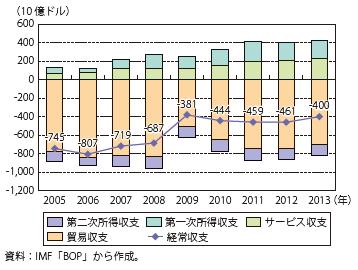
第Ⅰ-1-2-2-4図 英国の経常収支の推移

第Ⅰ-1-2-2-5図 フランスの経常収支の推移
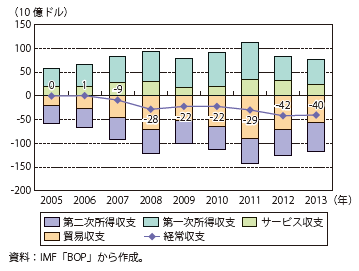
第Ⅰ-1-2-2-6図 ドイツの経常収支の推移
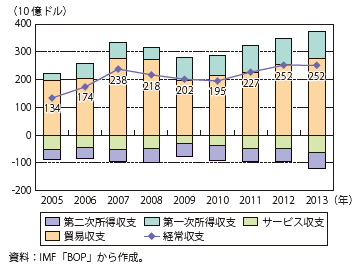
第Ⅰ-1-2-2-7図 中国の経常収支の推移
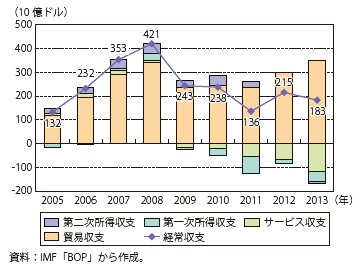
第Ⅰ-1-2-2-8図 韓国の経常収支の推移
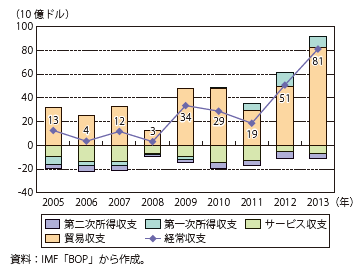
時系列で見ると、2005年以降の変化の中で特徴的な点として、2008年のリーマン・ショック前後の変化が挙げられる。それまでは米国が大幅な経常赤字を計上し、中国等は経常黒字を続けるいわゆるグローバル・インバランスと言われる状態が続いていた。しかし、リーマン・ショック後は、米国は貿易赤字縮小により経常赤字を縮小し、中国は貿易黒字縮小により経常黒字を縮小している。
上記のほかに、今回取り上げている国のうちその経常収支構造に興味深い変化があったのが、英国、中国、韓国である。英国は第一次所得収支の赤字転化、中国は第一次所得収支とサービス収支の赤字幅拡大、韓国は第一次所得収支の黒字化が見られた。以下、3か国の経常収支構造の変化について、もう少し詳しく見ていく。
(3)経常収支構造に変化が見られた国
(英国)
英国の第一次所得収支は2008年をピークに黒字幅が縮小しており、2012年にほぼ収支均衡、2013年には赤字に転化している。
第一次所得収支を分解してみると、2008年頃から証券投資収益の赤字幅が拡大し、直接投資収益も2011年をピークに減少してきているのが分かる。これらの内訳を受取と支払に分解すると、直接投資収益においては再投資収益の受取減少が、証券投資収益においては中長期債の債券利子の受取減少と配当金の支払増加が要因となっていることが分かる(第Ⅰ-1-2-2-9図、第Ⅰ-1-2-2-10図、第Ⅰ-1-2-2-11図)。
第Ⅰ-1-2-2-9図 英国の第一次所得収支の推移
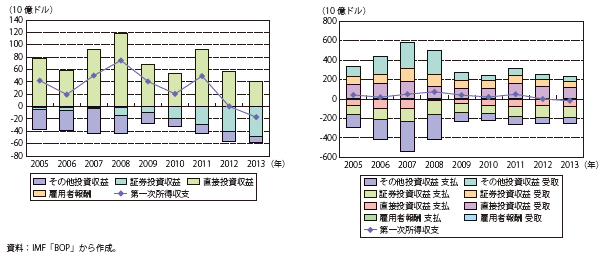
第Ⅰ-1-2-2-10図 英国の直接投資収益の推移
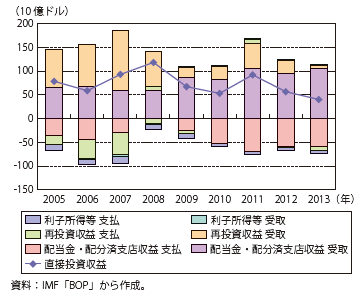
第Ⅰ-1-2-2-11図 英国の証券投資収益の推移
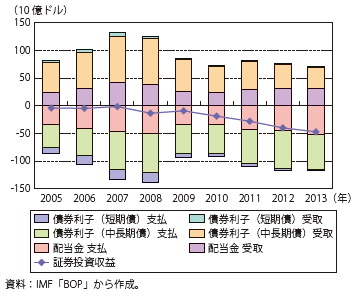
(中国)
中国の第一次所得収支は2007年に一旦黒字化したものの、2009年に赤字転化し、赤字幅が拡大してきている。
第一次所得収支の赤字幅拡大は直接投資収益の赤字幅拡大によるものである。配当金・配分済支店収益と再投資収益の両方の支払が増加傾向にあるように見えるが、特に再投資収益の支払は2009年からその拡大を加速し、2011年にピークを迎えた後、2012年以降落ち着きを見せている(第Ⅰ-1-2-2-12図、第Ⅰ-1-2-2-13図)。
第Ⅰ-1-2-2-12図 中国の第一次所得収支の推移
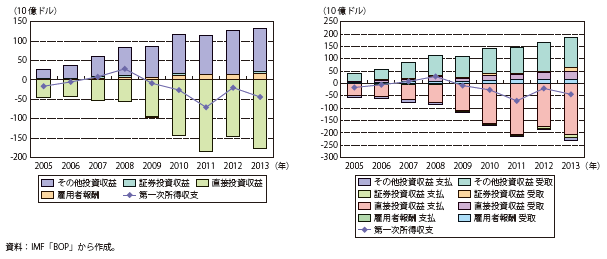
第Ⅰ-1-2-2-13図 中国の直接投資収益の推移
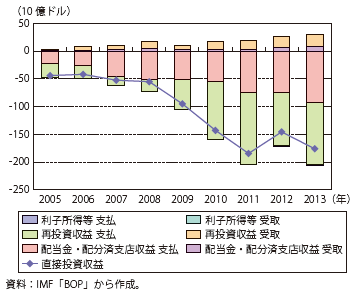
また、サービス収支が2009年以降、赤字に転化して赤字幅を拡大させている。その内訳を見ると、輸送収支と旅行収支の赤字幅が拡大している。それぞれ輸送収支は海上輸送(貨物)の支払増加が、旅行収支は支払の増加が赤字幅拡大の主因となっている(第Ⅰ-1-2-2-14図、第Ⅰ-1-2-2-15図、第Ⅰ-1-2-2-16図)。
第Ⅰ-1-2-2-14図 中国のサービス収支の推移
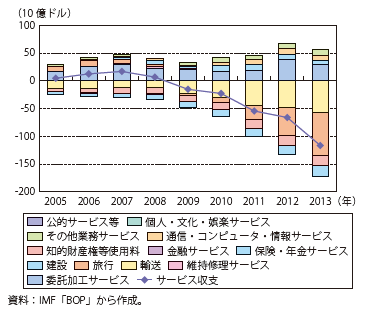
第Ⅰ-1-2-2-15図 中国の輸送収支の推移
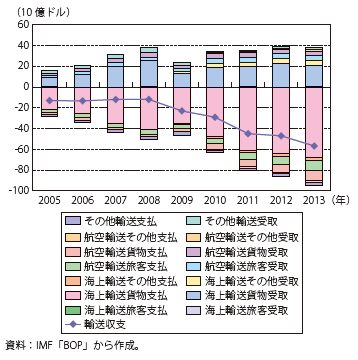
第Ⅰ-1-2-2-16図 中国の旅行収支の推移
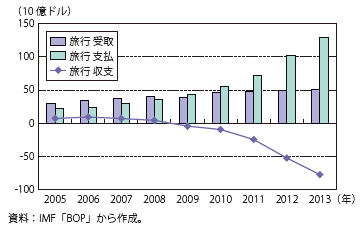
(韓国)
韓国は2010年に第一次所得収支が黒字転化した。
主因は直接投資収益の黒字化である。さらに直接投資収益の内訳を見ると、再投資収益及び配当金・配分済支店収益の支払は余り変わらないものの、受取が大きく増加している(第Ⅰ-1-2-2-17図、第Ⅰ-1-2-2-18図)。
第Ⅰ-1-2-2-17図 韓国の第一次所得収支の推移
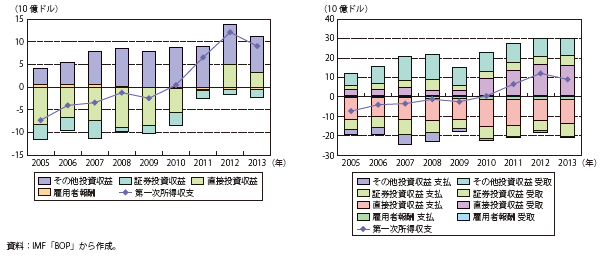
第Ⅰ-1-2-2-18図 韓国の直接投資収益の推移
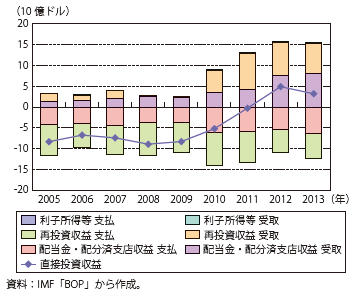
(4)まとめ
ここまで見てきたように、各国の経常収支構造を比較すると、貿易収支の状況によって大きく2つの型に分けられる。第1のグループは、貿易収支黒字を背景に経常収支も黒字となっているもので、日本(2000年代)、ドイツ、韓国(2010年代)がこれに含まれる。そして第2のグループは、大幅な貿易収支赤字により経常収支も赤字となっているもので、米国、英国(2000年代)、フランスがこれに含まれる。
しかし、経常収支構造は不変のものではなく、英国(第一次所得収支の赤字転化)や中国(サービス収支と第一次所得収支の赤字転化)、韓国(第一次所得収支の黒字転化)において、経常収支構造の変化が見られた。また、日本の経常収支についても、貿易収支赤字の拡大に伴って経常収支の黒字幅が縮小傾向にあることから、対外的な稼ぎ方についての問題意識が高まったところである。
対外的な稼ぎ方という観点からは、特に「輸出する力」を表すものとしての貿易収支、「外で稼ぐ力」を表すものとしての第一次所得収支が着目されることが多い。しかし、その場合には、収支ではなく輸出額や受取を見ることがより適切であると考えられることから、ここでは輸出額と第一次所得収支受取を取り上げ、各国の稼ぎ方のバランスを見ていく。
主要国の稼ぎ方のバランスを比較するため、輸出額と直接投資収益受取の対GDP比の関係を見てみると、各国が異なる稼ぎ方をしていることが分かる(第Ⅰ-1-3-1-19図)。既に見てきたことと考え合わせると、輸出が各国の稼ぎに対して大きな影響を持つ一方で、直接投資収益でも稼ぐ体制を取っている国が存在することを示している。
第Ⅰ-1-2-2-19図 各国の輸出額対GDP比と直接投資収益受取対GDP比の推移(2005年~2013年)
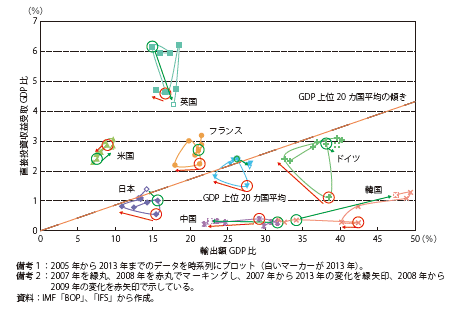
世界GDPの約80%を占めるGDP上位20か国の平均と比較すると、日本とフランス、ドイツの稼ぎ方はGDP上位20か国平均と近いが、米国と英国は相対的に直接投資収益受取からの稼ぎが多く、中国と韓国は相対的に輸出からの稼ぎが多いことが分かる。
また、各国の稼ぎ方のバランスを時系列で見てみると、リーマン・ショックの発生した2008年前後で動きが見られることが分かる。まず2007年から2008年にかけて、日本、英国、ドイツ、フランスでは直接投資収益受取対GDP比が減少し、次に2008年から2009年にかけては、世界経済危機の影響によりいずれの国も輸出額対GDP比を減少させている。しかしながら、世界経済危機発生前の2007年と足下の2013年とを比較すると、ほとんどの国においては輸出額対GDP比と直接投資収益受取対GDP比の双方において水準の変化は小さい。
英国、中国、韓国の3か国では、これらの水準の一方若しくは双方において大きな変化が見られる。英国は、世界経済危機によって2008年に直接投資収益受取対GDP比の水準を減少させたまま定着し、稼ぎ方のバランスにおける直接投資収益受取の比重が小さくなった。2011年に一度2007年の水準まで回復させたものの、2012年以降は2008年の水準に戻っている。中国は、世界経済危機の影響により輸出額対GDP比が減少し、2008年以降その水準で定着している。しかし、中国はかつてより直接投資収益受取対GDP比の水準が低いため、輸出額対GDP比が減少しても、稼ぎ方のバランス(原点と各点を結んだ直線の傾き)においては大きな変化は見られない。韓国は2008年以降に輸出額対GDP比が増加し、2010年以降には直接投資収益受取対GDP比も増加しており、2011年以降は両指標とも一定の水準で定着している。これにより、稼ぎ方のバランスにおける輸出の比重は依然大きいものの、2013年には2007年と比較し相対的に直接投資収益受取の比重が大きくなった。
ここでは「輸出する力」の例として輸出額対GDP比を、「外で稼ぐ力」の例として直接投資収益受取対GDP比を取り上げ、それらの水準の動きを見たが、第Ⅱ部以降、「輸出する力」と「外で稼ぐ力」に、我が国の成長力を高めるための「呼びこむ力」を加えた3つの力について、詳細な分析を行っていく。