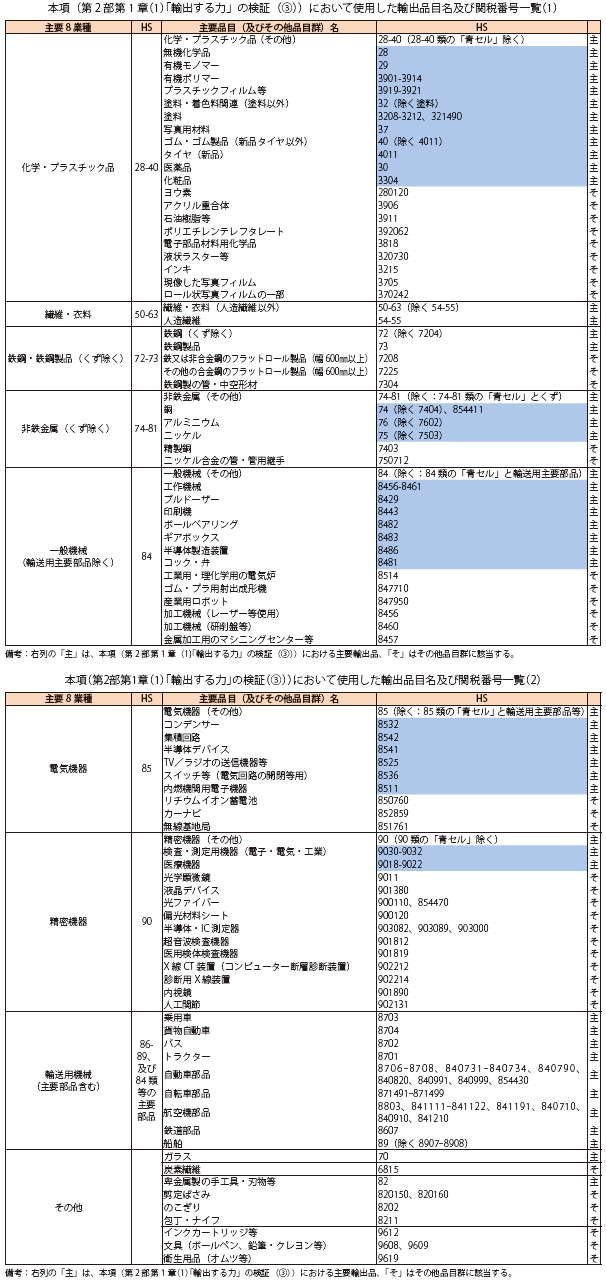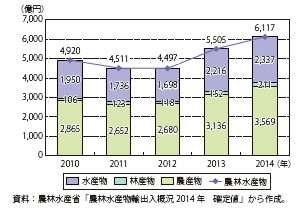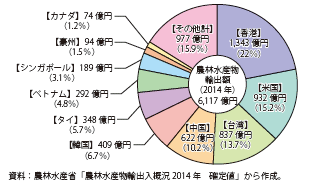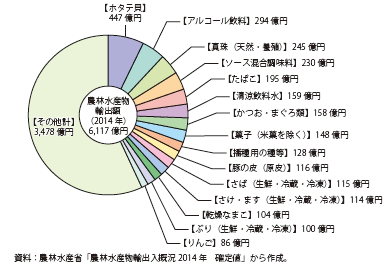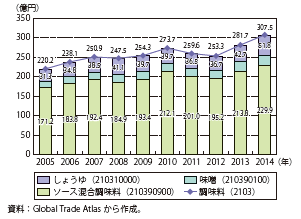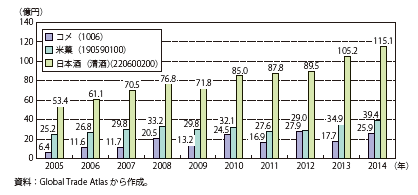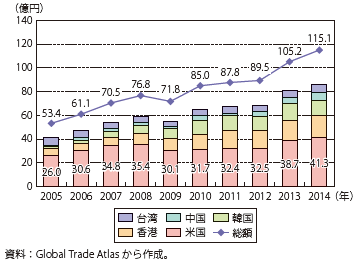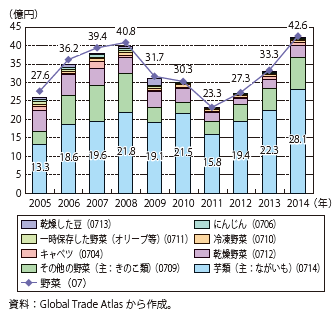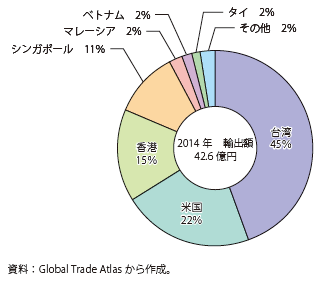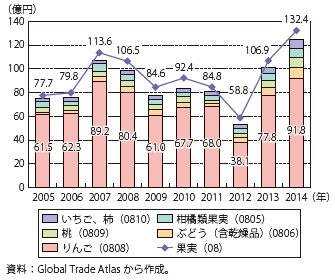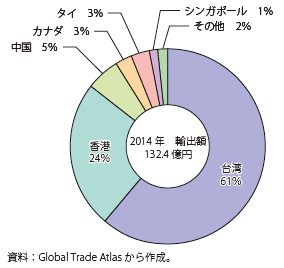- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2015

- 白書2015(HTML版)

- 第2部 第1章 第1節 「輸出する力」の検証
第1章 対外的稼ぎ方に見る日本の競争力
第1節 「輸出する力」の検証
1.我が国財輸出の変動要因分析
第1部第1章では、我が国貿易収支が2011年以降赤字を計上し続けていること、2014年に入り輸出数量が増加に転じ、貿易収支の赤字拡大にもようやく歯止めがかかりつつあることなどを紹介した。
以下では、こうした近年の我が国の貿易動向を踏まえ、これまでの我が国の財輸出における数量面での変動が、どのような要因に基づくものであったのかを明らかにする。
(1)価格競争力と輸出数量
第Ⅱ-1-1-1-1図は、2000年以降の我が国の相対輸出価格(対世界及び対先進国、ドルベース、前年同期比)と円の実質実効為替レート(前年同期比)の推移を比較したものである。
第Ⅱ-1-1-1-1図 実質実効為替レートと相対輸出価格の推移
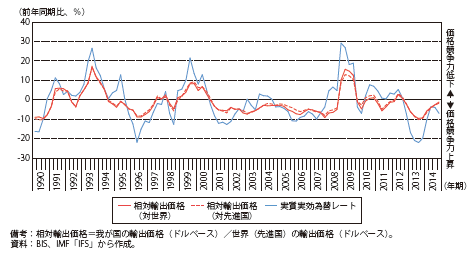
ここで、相対輸出価格は、我が国の輸出価格(ドルベース)と世界の輸出価格(ドルベース)の比率であり、その上昇は輸出財の価格競争力の低下を表し、逆に、その低下は輸出財の価格競争力の向上を表す1。
実質実効為替レートは、一国の輸出財の潜在的な価格競争力を示す指標である。
対外競争力を測る上では、単に名目為替レートの動きだけでなく、各国の製品価格の変動を考慮に入れた実質為替レートを用いる方が望ましい。また、グローバル市場全体での競争関係を見るためには、単一通貨ではなく、複数通貨の動きを考慮した実効為替レートを用いる必要がある。実質実効為替レートはこの両点を勘案しているため、円ドル・レートといった単一通貨の名目為替レートよりも対外競争力を適切に表している2。
そして、相手国との物価上昇率に差がなければ、為替レートの増価によって実質実効為替レートは上昇する。この場合、当該国の輸出財の潜在的な価格競争力は低下していると言うことができる。逆に、為替レートが減価すれば、実質実効為替レートは低下する。この場合は、当該国の輸出財の潜在的な価格競争力は高まっていると言うことができる。
ここで言う潜在的とは、企業が現地での販売価格を改定するまでは実際の価格競争力は変化しないということを指す。以下では、こうした企業の価格設定行動と為替レートの関係を詳しく見てみる。
一般に、実質実効為替レートが上昇している局面では、現地での販売価格を引き上げない限り利益の減少は避けられなくなる。これは、為替レートが円高方向へ動くと、現地での販売価格の円換算価値が減少するためである。この収益悪化の影響を緩和するには、現地での販売価格を引き上げる必要がある3。したがって、実質実効為替レートが上昇している局面では、現地での販売価格を引き上げる企業が増えること(当該国における価格競争力の低下)が想定される。
逆に、実質実効為替レートが低下している局面では、それまでの利益水準を維持しつつ現地での販売価格を引き下げる余地が生ずる。したがって、実質実効為替レートの低下局面では現地での販売価格を引き下げる企業が増えること(当該国における価格競争力の上昇)が想定される。
世界及び先進国の輸出価格については、より原油など国際商品価格の影響を受けるなど分析上の限界はあるが、図を見ると、我が国の実質実効為替レートの動きは、おおむね、相対輸出価格の動きに沿っている。
そして、他の要因が一定ならば、潜在的な価格競争力)の向上(実質実効為替レートの低下)を背景として、企業が現地での販売価格を引き下げることで初めて、現地での販売数量が増加に転じ、その結果、我が国からの輸出数量も増加する。
ただし、2009年の円高方向へ動いていた時期や2013年の円安方向へ動いていた時期など為替レートが大きく変動した時期には、両者の乖離が一時的に大きくなっていることも見て取れる。その要因としては、為替市場における投機的取引の存在に加えて、近年、輸出企業による価格設定行動が多様化していることが考えられる。
例えば、為替レートが円安方向に推移していても、多くの輸出企業が輸出数量よりも利益を確保しようとして現地での販売価格を引き下げないような場合には、実質実効為替レートの動きに比べ輸出価格の変化幅は小さくなる。逆に、円高方向へ推移する局面において、多くの企業が輸出数量の維持を優先して現地での販売価格を引き上げないような場合も同様である。実際、第Ⅱ-1-1-1-2図を見ると、2005年から2007年、2012年末から2013年にかけて実質実効為替レートが円安方向に動く中で、契約通貨建ての輸出物価指数はやや低下も見られるがその動きは小さい。また、2008年半ば以降円高方向に推移する中においても、輸出物価はあまり上昇していない。
第Ⅱ-1-1-1-2図 実質実効為替レートと輸出物価指数
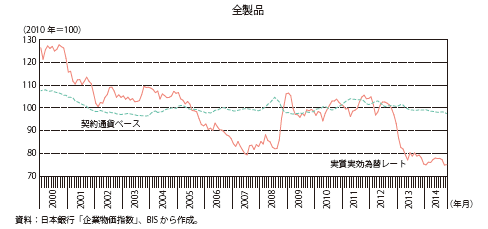
さらに、企業の価格設定行動は、輸出する財の種類によっても大きく異なる。
第Ⅱ-1-1-1-3図は、実質実効為替レートと財別の輸出物価指数(契約通貨ベース)の動きを比較したものである。これを見ると、電気・電子機械では、国際的な価格競争の激化を背景に、実質実効為替レートの動きとは無関係に、契約通貨ベースの輸出物価は下落し続けている。対照的に繊維品は、すう勢的な輸出製品の高価格帯へのシフトを背景に、契約通貨ベースの輸出物価は上昇傾向にある。化学品は、むしろ原料である原油価格の動きに連動していることが分かる。自動車などの輸送用機械では、2010年頃までは、実質実効為替レートとおおむね連動していたが、東日本大震災のあった2011年以降は、その関係がやや崩れてきているように見える。
第Ⅱ-1-1-1-3図 実質実効為替レートと輸出物価指数

- Excel形式のファイル(電機・電子機器)はこちら

- Excel形式のファイル(輸送用機械)はこちら

- Excel形式のファイル(繊維品)はこちら

- Excel形式のファイル(化学品)はこちら

- Excel形式のファイル(化学品)はこちら

また、これら以外にも、近年、海外進出する企業が増加したことで、海外子会社向けの輸出が増えていることもその要因として挙げられる。こうしたいわゆる企業内取引における価格設定行動は、一般的な輸出取引におけるそれとは大きく異なっている可能性がある。
そこで、第Ⅱ-1-1-1-4図を見てみよう。ここでは、我が国における輸出数量(2010年=100)と円の実質実効為替レート(2010年=100)の推移を比較している。
第Ⅱ-1-1-1-4図 実質実効為替レートと我が国輸出数量の推移
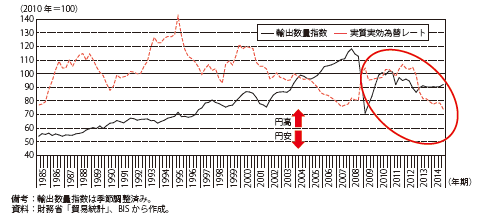
これを見ると、2000年頃から2007年頃までは、実質実効為替レートが下落を続ける中、輸出数量は増加し続けていることが分かる。
しかしながら、米国においてサブプライムローン問題が顕在化した2007年央頃から実質実効為替レートは大幅な上昇に転じ、その後は、2012年末まで高水準を維持している。この間、我が国の輸出数量は、リーマン・ショック前の水準に回復できずに足踏み状態を続けている。2012年末以降、実質実効為替レートはようやく大幅な低下に転じたものの、我が国の輸出数量は増加に転じず、おおむね横ばいの動きを続けている。
一般的には、為替レートが変化してから企業が輸出価格を改定するまでには一定の時間を要する4。加えて、企業が輸出価格を改定し、それが現地販売価格に反映され、販売数量に変化が生じるまでにも一定の時間を要するものと考えられる。したがって、実質実効為替レートが下落してから、価格改定を通じて、その効果が輸出数量の変化に現れるまでには相当の時間を要するであろうと考えられる5。今回は、実質実効為替レートが大幅な下落に転じてから既に2年強が経過しており、今後の輸出数量の動向が注目される。
では、なぜ、価格競争力が向上しているにもかかわらず、輸出数量は低迷を続けているのだろうか。以下では、こうした企業の価格設定行動のほかにも、輸出数量を左右する要因がないか考察する。
1 本来ならば、契約通貨ベースでの相対輸出価格を用いるべきであるが、データの制約から、ここではドルベースでの相対輸出価格を用いている。なお、日本の場合、輸出額の約4割が円建て決済であり、ドルベースの輸出価格の算定に当たって、ドル円レートの変動の影響を直接受ける点に留意が必要。
2 伊藤ほか(2011)より。
3 内閣府(2004)第3章第2節。
4 例えば、伊藤ほか(2010)では、我が国輸出企業215社へのアンケートを行い、為替変動を販売価格に反映させる頻度については、回答企業137社のうち約8割の企業が1年以内に価格改定を行っているとする結果を得ている。
5 このうち、為替レートが円安方向に推移している場合は、「Jカーブ効果」と呼ばれる。
(2)海外需要と輸出数量
まず、輸出数量の動向に影響を与えうる他の要因として、最初に挙げなければならないのは、海外需要の動向である。通常、海外需要を表す指標としては、各国の実質GDP(ドルベース)の合計値が用いられることが多い。ただし、我が国輸出産業から見た海外需要の動向を把握するためには、財輸出の相手国別の構成を考慮する必要がある。第Ⅱ-1-1-1-5図は、我が国輸出に占める米国向け、欧州(EU28)向け及び中国向け輸出の割合の推移を見たものである。米国向け輸出が占める割合は約20%と最も高く、次いで、中国向け輸出が約19%を占める。欧州向け輸出は約12%である。これら3か国地域で、我が国輸出の半分を占めている。2008年のリーマン・ショック以降、欧州向け輸出のシェアが長期的な低下傾向にある中、米国向け輸出のシェアが2012年以降拡大傾向にあること、中国向け輸出のシェアは2008年以降横ばいを続けていることなどが見て取れる。
第Ⅱ-1-1-1-5図 我が国の相手国・地域別輸出の推移
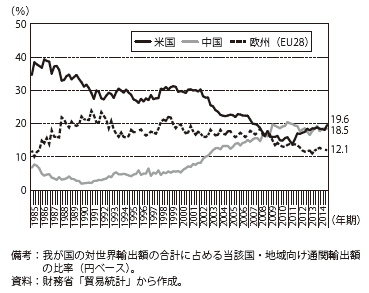
第Ⅱ-1-1-1-6図は、各国向け通関輸出額をウェイトに我が国の主要輸出相手国26か国・地域6の実質GDP(ドルベース)を加重平均したものである。これを見ると、過去、主要輸出相手国の実質GDPの伸びにおおむね沿うように推移してきた我が国の輸出数量は、2011年以降、主要輸出相手国の実質GDPの伸びを大きく下回って推移していることが分かる。この結果は、最近の我が国輸出数量の低迷が、海外需要を原因とするものではないことを示唆している。
第Ⅱ-1-1-1-6図 海外実質GDPと我が国輸出数量の推移
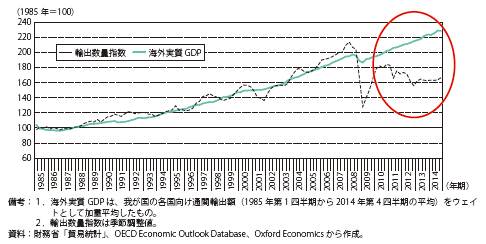
6 26か国・地域の内訳は、米国、英国、ベルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、カナダ、フィンランド、ポルトガル、スペイン、オーストラリア、ニュージーランド、メキシコ、韓国、台湾、インド、インドネシア、シンガポール、マレーシア、フィリピン、タイ、中国(香港を含む)である。これら26カ国・地域で我が国輸出総額の約87%(1985年~2014年の平均)を占める。
(3)高付加価値化と輸出数量
輸出財の「高付加価値化」も輸出数量の動きに大きな影響を与える要因の一つである。
ここでは、まず、輸出財の高付加価値化の定義を輸出物価指数7との関係で整理する。
一般に、輸出物価指数の作成過程では、調査対象となる製品を固定し、個々の製品の質的変化や品目構成の変化も除外した上で、指数が作成される。したがって、物価指数の基準時点以降に、輸出財の高付加価値化、すなわち、個別輸出品目の高付加価値化や輸出に占める高付加価値品のシェア拡大が生じても、これらの変化は輸出物価指数には反映されない。
ここで、「個別輸出品目の高付加価値化」とは、例えば、乗用車を例に取ると、輸出される普通乗用車の価格帯がより排気量の大きい車種にシフトすることである。輸出物価指数では、特定の車種(排気量)の乗用車を調査対象として特定し、その価格変化を追跡し「普通乗用車」の物価指数として公表する。したがって、普通乗用車の価格帯の中心がより排気量の大きい車種にシフトして輸出される普通乗用車の平均輸出価格が上昇しても、普通乗用車の輸出物価指数には反映されない。
「高付加価値品のシェア拡大」とは、例えば、「乗用車」という物価指数が普通乗用車と大型乗用車という2つのサブカテゴリーで構成されている場合に、大型乗用車の輸出シェアが拡大するようなケースである。輸出物価指数では、サブカテゴリーの構成比は基準時点のもので固定するため、このようなケースで乗用車全体の平均輸出価格が上昇しても、乗用車の輸出物価指数には反映されない。
したがって、輸出財の高付加価値化は、輸出物価指数では捕捉されない「価格の上昇」と考えることができる。
そして、輸出数量との関係では、高付加価値化が進展すれば、輸出物価が一定でも、輸出数量は増えにくくなるのである。実際、我が国の輸出財の高付加価値化は着実に進んでおり、我が国の財輸出は構造的に輸出数量が増えにくい体質になっていると言えよう(第Ⅱ-1-1-1-7図)。
第Ⅱ-1-1-1-7図 財輸出の高付加価値化
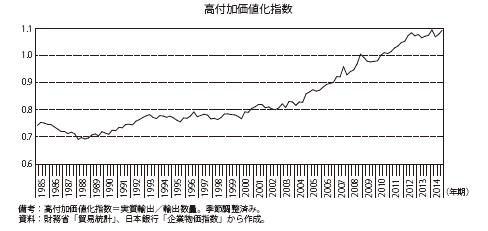
第Ⅱ-1-1-1-8図は、こうした我が国輸出財の高付加価値化の動き(前年比)を「個別輸出品目の高付加価値化(品目高級化要因)」と「輸出に占める高付加価値品のシェア拡大(品目構成高度化要因)」の2つに分解したものである。
第Ⅱ-1-1-1-8図 高付加価値化指数の変動要因分解
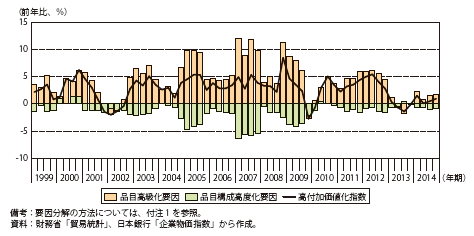
これを見ると、品目高級化要因が恒常的に高付加価値化に寄与する一方、品目構成高度化要因は、品目構成の低付加価値化を通じて、高付加価値化とは逆の方向に寄与する傾向が見て取れる。
通常、価格が低下した品目に対する需要は増加するため、品目構成の高度化によって高付加価値化を推し進めることは容易ではない。実際、図を見ると、2004年末から2009年にかけての我が国輸出産業は、輸出品目の高付加価値化を推し進めながらも、そのシェアを高めることができず、低付加価値品の生産拡大を同時に行っていたことが見て取れる。
しかしながら、2010年以降は、輸出品目の高付加価値化が引き続き進展する中、それまで断続的に見られた品目構成の低付加価値化の動きがほぼ消滅してしまっている。2010年以降、低付加価値品の生産拡大の動きが大きく後退していることが示唆される。さらに、2013年以降は、輸出品目の高付加価値化も大きく減速しており、我が国輸出財の高付加価値化の動きは足踏み状態が続いている。
7 輸出物価指数は、日本銀行によってラスパイレス式の固定ウェイト方式で作成されている。
(4)輸出財生産能力と輸出数量
輸出財の生産能力も、輸出数量の動向に影響を与えうる重要な要因である。特に、近年、経済のグローバル化を背景に、我が国製造業の海外展開が急速に進む中、生産設備の海外移転による国内生産基盤の空洞化が懸念されていることは周知のとおりである。
国内生産基盤の縮小が進めば、縮小した生産能力が足かせとなり、将来、海外需要が拡大してもその機会を捉えて我が国の輸出を増やすことは困難となる。したがって、国内生産能力は、我が国の「輸出する力」の基盤となるべき最も重要な要素と言える。
一般に、他の条件が一定ならば、一国の輸出数量は、国内の輸出財の生産能力の大きさに比例する8。そこで、以下では、この輸出財の生産能力と輸出数量の関係を見てみる。
まず、国内向けと輸出向けを合計した我が国製造業の国内生産能力全体の推移を見てみよう(第Ⅱ-1-1-1-9図)。製造業全体では、それまで上昇を続けていた生産能力が1997年頃を境に低下傾向に転じていることが分かる。生産能力の低下は2004年頃まで続くが、2005年に入り再び上昇に転じ、2008年まで上昇傾向が続く。リーマン・ショック後の2009年以降、生産能力は再度低下に転じ、その後は足下の2014年まで低下傾向が続いている。
第Ⅱ-1-1-1-9図 業種別国内生産能力指数(輸出+内需)
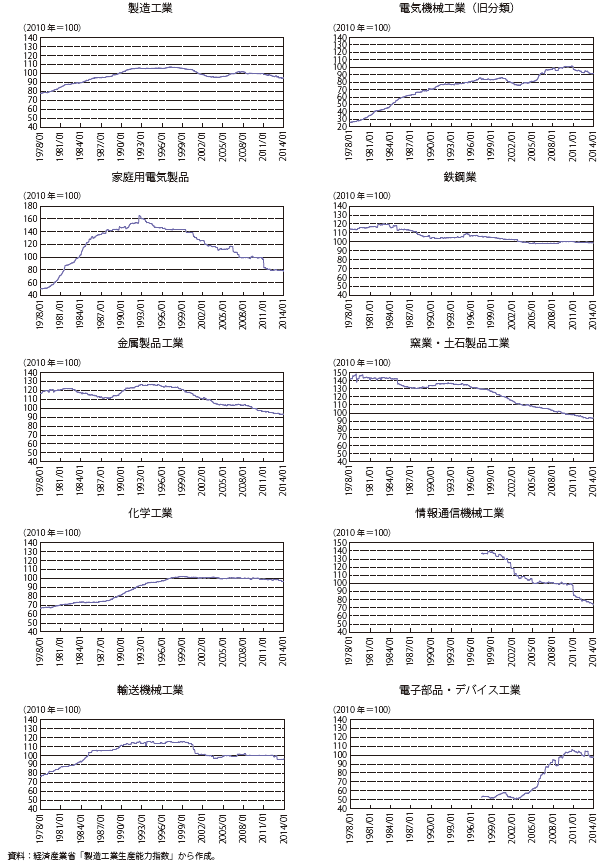
- Excel形式のファイル(製造工業)はこちら

- Excel形式のファイル(電気機械工業)はこちら

- Excel形式のファイル(家庭用電気製品)はこちら

- Excel形式のファイル(鉄鋼業)はこちら

- Excel形式のファイル(金属製品工業)はこちら

- Excel形式のファイル(窯業・土石製品工業)はこちら

- Excel形式のファイル(化学工業)はこちら

- Excel形式のファイル(情報通信機械工業)はこちら

- Excel形式のファイル(輸送機械工業)はこちら

- Excel形式のファイル(電子部品・デバイス工業)はこちら

次に、個別業種ごとの生産能力の動きを見てみよう。電気機械工業(旧分類)9の生産能力は、2001年のITバブル崩壊後の回復過程にあったが、2011年の震災後、再度低下に転じている。とりわけ、新興諸国などとの厳しい競争に直面している家庭用電気製品などの分野では、1990年代後半以降長期間にわたる急速な生産能力の低下が続いている。鉄鋼、金属製品、窯業・土石製品、化学などといった素材系産業においても、長期間にわたる低下傾向が続いている。我が国輸出産業の中核である輸送機械工業においても、2000年から2004年にかけて大幅な生産能力の低下が起きている。その後、生産能力は横ばいで推移していたが、2013年以降、再び低下に転じている。また、これまで一貫して拡大を続けていた電子部品・デバイスの生産能力も、2011年頃をピークに以後は低下傾向に転じている。
このように、国内生産能力全体の動向は、近年、いずれの業種においても、ほぼ例外なく低下傾向をたどっていることが分かる。
次に、産業別の輸出比率の動きを見てみよう。
第Ⅱ-1-1-1-10図は素材系及び加工・組立型の各産業の輸出比率の推移である。
第Ⅱ-1-1-1-10図 産業別輸出比率の推移
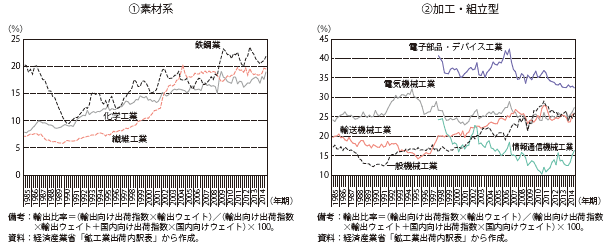
これを見ると、多くの産業で、近年、輸出比率は上昇傾向にあることが分かる。輸出比率は、繊維工業等素材系産業ではおおむね1990年代から、加工・組立型産業のうち輸送機械や一般機械では、これよりやや遅く2000年代に入ってから、それぞれ上昇が始まっている。ただし、2008年頃からは両者ともその動きは停滞が続いている。加工・組立型産業のうち、情報通信機械工業では、輸出比率は長期的な低下傾向にあったが、2011年以降上昇に転じている。
他方、電子部品・デバイス工業では、2007年以降輸出比率は急速に低下し続けている。また、電気機械工業では2000年代以降おおむね横ばいで推移している。
なお、足下の2014年の動きを見ると、電子部品・デバイス工業など一部の産業を除き、素材系を含む多くの産業で輸出比率は上昇に転じていることが見て取れる。特に、情報通信機械工業では大幅な上昇が見られる。
一般に、輸出財生産能力の動きと輸出向け出荷の動きは比例すると考えられるから、国内生産能力全体が低下傾向にあっても、輸出比率(輸出向け出荷/(輸出向け出荷+国内向け出荷))が上昇している場合には、輸出財生産能力は拡大しているはずである。
そこで、以下では、これら国内生産能力と輸出比率の情報を用いて、我が国全体の輸出財の生産能力の動きを試算してみる。
輸出財生産能力を直接調べた統計はないので、ここでは、我が国輸出産業の輸出財生産能力に係る代理指標として、経済産業省「製造工業生産能力指数」の国内生産能力に、同じく経済産業省の「鉱工業出荷内訳表」から得た輸出比率(輸出向け出荷/(国内及び輸出向け出荷))を乗じたものを用いた10。
第Ⅱ-1-1-1-11図がその試算結果である。これを見ると、内需財の生産能力が1990年代後半以降長期的低下傾向を続ける中、輸出財の生産能力は、リーマン・ショックによる一時的な低下を経て2011年初め頃まで上昇傾向を続けていたことが分かる。
第Ⅱ-1-1-1-11図 輸出財生産能力の推移
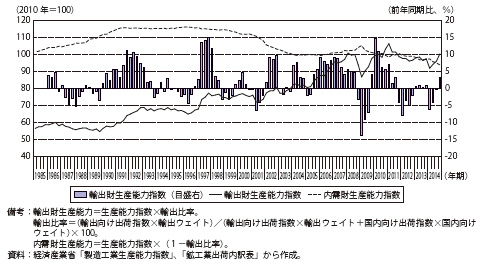
この間、我が国の輸出財の生産能力は、1990年代半ば頃まで横ばいで推移した後、好調な米国経済や円安方向への動きなどを背景に、1996年央頃から急速な上昇に転じている。当時、円レートは1995年央頃から円安方向へ推移しているから、輸出財の生産能力が上昇に転ずるまでには約1年を要したことになる。
その後、輸出財生産能力はおおむね横ばいで推移したが、ITバブル崩壊後の2002年に入り再び上昇に転ずる。この時も、円レートは2001年初め頃から円安基調に転じているから、輸出財の生産能力が上昇に転ずるまでには、やはり約1年を要したことになる。円安基調はその後も2007年央頃まで続き、その間、輸出財の生産能力も上昇傾向にあった。
2011年以降、輸出財生産能力は2度の大きな下落を経験している。
最初の下落は、リーマン・ショックからおよそ3年が経過した2011年第4四半期から始まり、2012年第4四半期までの5四半期続いている。2度目の下落は、2014年第1四半期から2014年第3四半期にかけての3四半期である(ただし、2014年第3四半期は前年比-0.4%とほぼ横ばいなので、実質的な下落期間は2四半期である)。
この間、2007年央頃から始まった円高方向への推移はその後2012年末頃まで続くから、前者はリーマン・ショック後の長引く円高方向への推移の中及び震災を受けて我が国のエネルギー情勢が大きく変化した中で生じている。さらに、前年比で見た下落が1年以上にわたり続いたこと、下落後も指数水準が下落前の水準に回復していないことなどから11、本格的な輸出財生産能力の削減が行われたことがうかがえる。
他方、後者は、2012年末以降に円レートが円安方向へ推移してから生じていること、下落がわずか2四半期で終了していること、最初の下落から3四半期後の2014年第4四半期には早くも下落前の水準を大きく超えていることなどから、本格的な輸出財生産能力の削減が行われたとは考えにくい。むしろ、何らかの特殊要因によって輸出財生産能力が一時的に下落したことが強く示唆される。
では、当時、どのような特殊要因が生じていたのであろうか。
2014年4月には消費税率の引上げが実施されており、同年第1四半期には駆け込み需要が発生している。
実際、2012年第2四半期から下落を続けていた我が国製造業の実稼働率12は、消費税率引上げ前年の2013年に入り上昇に転じている。2012年第4四半期には74.6%だった実稼働率は、消費税率引上げ直前の2014年第1四半期には84.9%とリーマン・ショックのあった2008年第3四半期以来の高水準に達している。そして、消費税率引上げ直後の同年第3四半期には再び78.6%まで低下している(第Ⅱ-1-1-1-12図)。
第Ⅱ-1-1-1-12図 消費税率引上げ前後の実稼働率、輸出及び国内向け出荷の推移
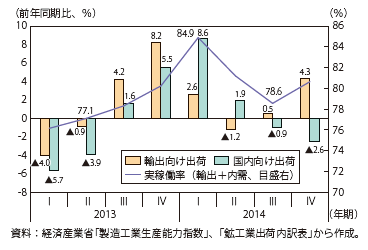
この間、輸出向け出荷の伸びは、2014年第1四半期に前年同期比2.6%まで大きく減速した後、同年第2四半期には同-1.2%と減少に転じたが、同年第3四半期には再び増加に転じ、同年第4四半期には同4.3%の大幅な増加を記録している。
他方、国内向け出荷は、2013年第4四半期と2014年第1四半期に大幅な伸びを示した後、同年第3四半期には再び下落に転じている。企業が、駆け込み需要に対応するため、国内の生産能力の一部を一時的に輸出向けから内需向けへと振り替えていたことが強く示唆される13。
このように、2011年以降の2つの大きな輸出財生産能力の低下局面は、その性格が全く異なったものであった可能性が高い。
最後に足下の動きを見てみよう。2014年後半から輸出財の生産能力は再び増加に転じている。そして同年第4四半期には、リーマン・ショック前の水準にまで回復している。内需財の生産能力が引き続き低下を続けていることが懸念されるが、輸出財の生産能力については、海外需要の回復や為替レートの安定化などといった最近の輸出環境の好転を背景に、我が国輸出産業が、再び、国内の生産能力の強化に注力し始めたことが示唆される動きである。
こうして得られた輸出財の生産能力の動きを輸出数量の動きと比較してみると、両者の動きはよく連動していることが分かる。ただし、リーマン・ショック前後など一部、輸出数量が短期的に大きく変動している時期には、両者が大きく乖離していることも見て取れる(第Ⅱ-1-1-1-13図)。
第Ⅱ-1-1-1-13図 輸出財生産能力と輸出数量の推移
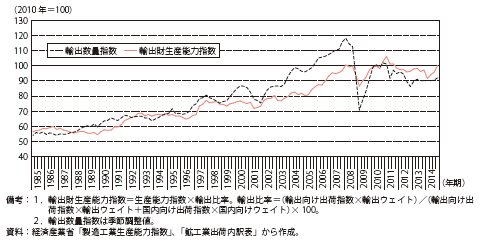
この輸出数量の短期的な変動を引き起こす要因として重要なものが、次に紹介する海外での在庫投資である。
8 例えば、Goldstein, M and Mohsin S. Khan (1978), pp 276。
9 ここでいう「電気機械工業」は、鉱工業指数の旧分類を指しており、鉱工業指数の現行の22年基準分類の「電気機械工業」、「情報通信機械工業」及び「電子部品・デバイス工業」を合算したものである。
10 ただし、ここでは生産設備の稼働率の問題が考慮されていない。出荷データから得られた生産能力には、景気動向と連動して短期的に変動する稼働率の影響が含まれてしまっている。すなわち、この場合、輸出財生産能力の低下ではなく、輸出財生産能力の稼働率の低下によって輸出向け出荷が減少する場合も、輸出財生産能力の低下としてとらえられてしまう。したがって、以下で試算する輸出財生産能力には稼働率の変動の影響が含まれていることに留意する必要がある。
また、近年、単独の生産ラインで輸出向け製品と国内向け製品の両方を生産する生産方式、いわゆる「混流生産方式」が、国内の自動車産業や一般機械産業を中心に広く普及している。こうした生産方式の変革は、企業が需要動向に応じて機動的に既存の生産能力を輸出向けまたは内需向けに使い分けることを可能にする。
したがって、出荷データを用いて用途別に推計された生産能力の動きを評価するにあたっては、関連する他の経済統計や、その背景となっているさまざまな経済事象を併せて注意深く観察する必要がある。
11 下落直前の輸出財生産能力指数は101.2(2011年第3四半期)である。その後の指数水準は、2014年第4四半期現在、これを下回って推移している。
12 公表されている基準時(2010年)における実稼働率水準に稼働率指数を乗じることによって推計。
13 日本銀行(2014)においても、自動車関連の実質輸出について、国内販売の大幅増に伴う供給制約などが、一時的な下押し要因となっていたことを報告している。なお、企業による駆け込み需要への対応(増産)は、自動車産業を中心に、生産が需要に追いつけなかったため、2014年4月の消費税率引上げ以降も続いたことは、2014年8月の産業構造審議会製造産業分科会(第2回)においても報告されている。
(5)海外在庫投資と輸出数量
一般に企業は、景気拡張期には在庫を積み増すために生産や輸出を増加させ、景気後退期には過剰在庫を削減するために生産や輸出を抑制または停止する。
その結果、現実には、在庫積増しや在庫調整といった企業による在庫投資は、景気循環の過程で生産や輸出を平準化させず、むしろその変動を増幅する役割を果たしている14。
今回は、我が国輸出産業による海外在庫投資の代理変数として、我が国主要輸出相手国のGDPを構成する需要項目の一つである「在庫増減額」の名目GDP比を用いた(第Ⅱ-1-1-1-14図)。これによって、海外での在庫投資に伴う我が国輸出数量の短期的な変動の多くの部分を説明することが可能となる。
第Ⅱ-1-1-1-14図 海外在庫投資の推移
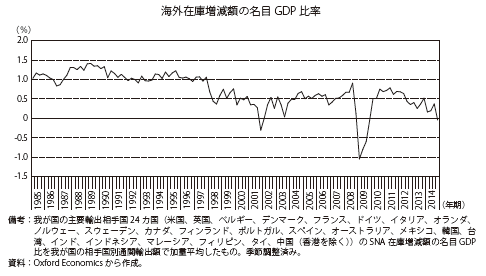
実際、図を見ると、ITバブル崩壊後の2001年から2002年にかけて、及び、リーマン・ショック後の2008年から2009年にかけて、企業は急激な海外在庫の調整と積み増しを1年間という短期間に行っていたことが見て取れる。そして、このように在庫投資が大きく変動するとき、輸出数量も短期間で急激な変動を示すことになる。
なお、2012年以降の海外在庫投資の動きを見ると、海外需要全体に大きな変化が見られないにもかかわらず、減少傾向にある。2014年第4四半期には、-0.2%とリーマン・ショック以来のマイナスとなっている。そこで、海外在庫投資の動きを輸出相手国別に見てみると、米国、中国及びインドネシアなどでは好調な国内経済動向を背景に在庫の積み増しが続く一方、韓国、タイ、フィリピン、台湾などアジア諸国の一部及びEU諸国などでは、2012年頃から在庫調整の動きが強まっている(第Ⅱ-1-1-1-15図)。特に、足下の2014年第4四半期には韓国の在庫投資が大きく減少していることが見て取れる。
第Ⅱ-1-1-1-15図 輸出相手国別の海外在庫投資
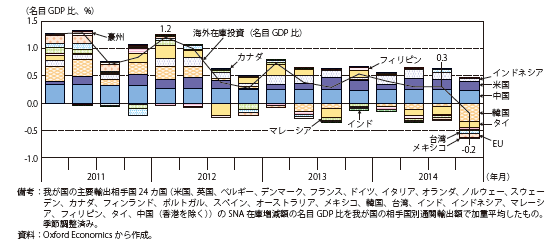
14 例えば、経済企画庁(1992)第2章第5節では、在庫投資の特性について次のように記述している。「現実に在庫投資は拡大期に増え、後退期に減ることによって、景気循環の過程で生産を平準化せず、むしろその変動を増幅する役割を果たしている。このことは、在庫がバッファーとして機能する上で、ある程度需要水準に比例した適正な在庫量が存在し、需要の変動とともに在庫が変動することを示している。」
(6)輸出数量関数の推計と変動要因分解
以上、我が国の輸出数量の動きと深く関わっているとみられる5つの要因、すなわち価格競争力、海外需要、高付加価値化、輸出財の生産能力及び海外在庫投資について、その特性や輸出数量との関係について詳しく見てきた。
以下では、これら5つの要因を全て用いて、我が国の輸出数量関数の推計を試みる。また、その推計結果を用いて、輸出数量の変動要因分解も行い、それぞれの要因が我が国輸出数量の変動にどの程度の影響を与えているのかを示す15。
第Ⅱ-1-1-1-16図は、輸出数量関数の推計値と実績値を比較したものである。
第Ⅱ-1-1-1-16図 輸出数量(季節調整前)の推計値と実績値
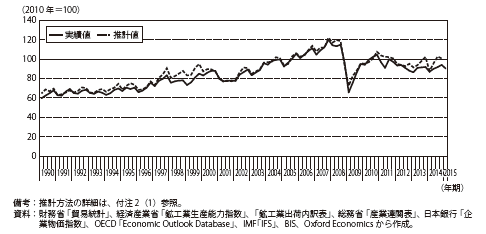
これを見ると、推計値は、2001年のITバブル崩壊前後や2008年のリーマン・ショック前後の大きな実績値の変動をよく捉えていることが見て取れる16。
第Ⅱ-1-1-1-17図は、輸出関数の推計によって得られた推計値を用いて、輸出数量の変動(前年比)を価格競争力、海外需要、高付加価値化、輸出財の生産能力及び海外在庫投資の5つの要因に分解したものである。
第Ⅱ-1-1-1-17図 輸出数量(季節調整前)の変動要因分解
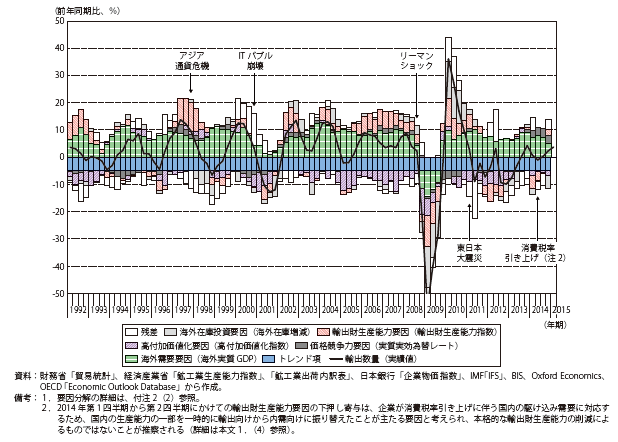
はじめに、各要因と輸出数量の関係について概観してみよう。
まず、海外在庫投資要因は、事前に想定されたとおり、1997年から1998年にかけてのアジア通貨危機の際や2001年のITバブル崩壊後、2008年のリーマン・ショック直後など海外需要が短期間に大きく変動した際の激しい輸出数量変動の多くを説明していることが見て取れる。
しかしながら、2012年以降の海外在庫投資の動きを見ると、海外需要に大きな変動が見られないにもかかわらず、多くの期間でマイナス寄与を示すようになっている。これは、1.(5)で見たように、我が国の主要な輸出先の一つである韓国等のアジア諸国やEU諸国の一部で2012年以降在庫投資の抑制や削減が行われているためである。
次に、価格競争力要因を表す実質実効為替レートを見てみよう。実質実効為替レートは、およそ4四半期(1年)のタイムラグを伴って輸出数量に影響を与えている。既に見たように、円レートは1995年央頃から円安方向へ推移しているが、それから約1年を経過した96年第4四半期から実質実効為替レートが輸出数量に対する上押し要因として現れているのが見て取れる。次に円レートが円安方向へ推移している2001年初めも、同様に、その約1年後の2002年第1四半期から輸出数量に対する上押し要因として現れているのが見て取れる。足下の2012年末以降の円安方向へ推移する中においても、その約1年後の2013年末以降その効果が現れ始めている。
逆に、1993年、1999年~2000年あるいは2008年以降の円高方向へ推移した局面では、円レートが円高方向へ推移しはじめた約1年後に実質実効為替レートが輸出数量に対する下押し要因となって現れているのが見て取れる。
海外需要要因を表す海外実質GDPの動きを見てみると、リーマン・ショック直後の2008年第4四半期以降の1年間を除き、推計期間全体を通じて安定的に輸出数量に対する上押し要因となっていることが分かる。
他方、高付加価値化要因を表す高付加価値化指数は、我が国輸出財の高付加価値化の流れを反映して、多くの期間で輸出数量に対する下押し要因となっている。ただし、足下の2013年以降は、輸出数量に対するマイナス寄与がやや小さくなっている。これは、1.(3)で見たように、2013年以降我が国輸出財の高付加価値化の動きが足踏み状態となっているためである。
輸出財生産能力要因を表す輸出財生産能力指数は、2008年のリーマン・ショックまでは、ITバブルの崩壊やリーマン・ショックなど海外需要が大きく落ち込んだ際に一時的な下押し要因となっているが、それらの時期を除けば、低付加価値品の生産拡大を背景に、恒常的に輸出数量に対する上押し要因となっていたことが見て取れる。
しかしながら、リーマン・ショック後は、海外需要に大きな落ち込みが生じていないにもかかわらず、低付加価値品の生産拡大の後退を背景に、輸出数量に対する上押しが見られなくなり、2011年末から2012年第4四半期にかけては輸出数量に対する下押し要因となっている17。
以上の結果から、リーマン・ショック以前の2002年から2008年までの我が国の輸出数量の順調な拡大は、海外在庫投資による短期的な影響を除けば、海外需要の伸びと低付加価値品を中心とする輸出財の生産能力の拡大による輸出数量の上押しが、高付加価値化の進展による下押し圧力を恒常的に上回ることで実現していたことが分かる18。
他方、2011年以降の我が国輸出数量の低迷は、好調な海外需要と円レートの円安方向への推移を背景とする価格競争力の要因による輸出数量の上押しが、輸出財の高付加価値化、2011年末から2012年まで続いた輸出財生産能力の削減、消費税率引上げへの対応による輸出財生産能力の一時的な低下及び2012年以降拡大傾向にある海外での在庫調整の進展による下押し圧力を上回ることができなかったためであることが分かる。
15 具体的な推計方法と推計結果、要因分解の詳細については、付注2を参照。
16 ただし、2011年以降の実績値の動きに対しては、推計値がやや上ぶれしている。このことは、今回の輸出数量関数で用いた5つの要因以外に、2011年以降、何らかの構造的な要因が新たに生じていることを示唆している。例えば、海外生産の拡大による国内生産の代替などといった動きが想定されるが、期間が短く推計に必要なデータ数が十分に確保できないため、今回の推計では分析を見送っている。
17 2014年にも輸出財生産能力は下押し要因となっているが、これは、1.(4)で見たとおり、生産能力の本格的な削減ではなく、消費税率引上げ前の駆け込み需要対応による一時的なものであった可能性が高い。
18 ただし、2005年は、一時的に高付加価値化要因の下押し圧力が海外需要要因と輸出財生産能力要因の上押し圧力を上回ったため、輸出数量の前年比はマイナスとなった。
(7)まとめ
米国を中心に引き続き好調な海外需要、消費税率引上げ対応による一時的な落ち込みからの回復が進む輸出財生産能力、円レートの円安方向への推移によって向上しつつある価格競争力などを背景に、我が国の輸出数量は足下の2014年第4四半期には前年比で増加に転じている。
しかしながら、既に見たとおり、高付加価値化の進展によって我が国の財輸出は構造的に数量が増えにくい体質となっている。加えて、リーマン・ショック後は、それまで輸出財生産能力の拡大をけん引していたと見られる低付加価値品の生産拡大の動きも大きく後退してしまっている。
したがって、経済のグローバル化が急速に進む中、我が国が今後とも一定程度の輸出数量の伸びを維持していくためには、輸出財の高付加価値化を引き続き推し進めるとともに、輸出財の生産能力を維持・拡大していくことが不可欠であると考えられる。そして、輸出財生産能力の維持・拡大は、今後、我が国輸出産業が高付加価値品のシェア拡大を実現することができるかどうかが鍵となるであろう。
2.「輸出する力」の国際比較概観
本項では、「輸出する力」について、日本の輸出力を検証する。
足下で見ると、日本の輸出数量はようやく上昇の兆しが確認できる。しかし、世界及び日本の輸出数量指数を見ると、新興国、米国はリーマン・ショック以前の水準を上回り上昇傾向で推移しているのに対して、日本はリーマン・ショック以前よりも低い水準で軟調に推移している(第Ⅱ-1-1-2-1図)。
第Ⅱ-1-1-2-1図 世界及び日本の輸出数量指数の推移
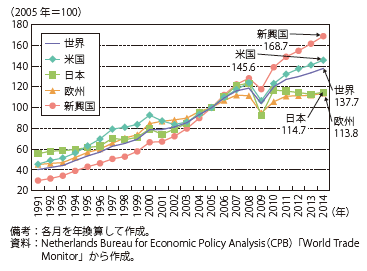
本項では日本の輸出について、生産工程別に貿易財の国際比較を行い、その特徴を概観する。そして、日本の貿易品について貿易統計(財務省)を用いて、主要業種別に輸出額の伸び率、個別品目を中心に各国・地域の輸入額に占める割合(輸入額シェア)を見ることで日本の輸出力を検証する。
(1)世界貿易と生産工程別貿易財の国際比較
世界貿易の推移と世界貿易における日本の輸出動向を確認するとともに、生産工程別に貿易財の国際比較を行い、その特徴を概観する。
①世界貿易(輸出額)の推移
世界貿易を輸出額の推移で見ると、2000年以降、高い伸びが見られる(第Ⅱ-1-1-2-2図)。世界貿易(輸出額)の伸び率を見ると、1991年~2000年の90年代の伸び率が年率6.3%であったのに対して、2001年~2010年の2000年代では9.0%へと急激な伸びが見られた。足下2011年~2013年の2010年代では6.9%と、その伸びは鈍化したものの、90年代を上回る水準を維持している。また2000年代の伸びは先進国以上に新興国の伸びが世界貿易の拡大をけん引していたことが分かる(第Ⅱ-1-1-2-3表)。
第Ⅱ-1-1-2-2図 世界貿易(輸出額)の推移
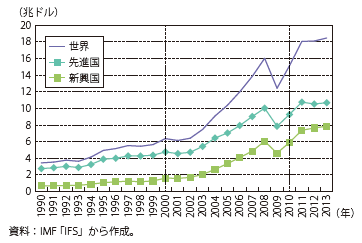
第Ⅱ-1-1-2-3表 世界貿易(輸出額)の伸び率
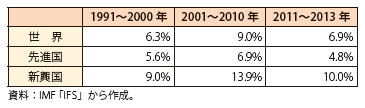
②主要輸出国・地域の輸出額と世界輸出に占める輸出額割合
主要輸出国・地域19の輸出額の推移を見ると、2000年代後半以降、各国・地域とも上昇傾向で推移しており、特に中国の輸出額が急増している。日本の輸出額は1990年代にアジア諸国を上回っていたものの、2000年代に入り輸出額が伸び悩んでいる(第Ⅱ-1-1-2-4図)。
第Ⅱ-1-1-2-4図 主要輸出国・地域の輸出額の推移
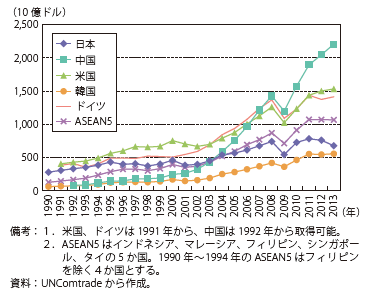
世界輸出額に占める主要輸出国・地域の輸出額割合の推移を見ると、多くの国・地域が低下傾向にある中、中国の輸出額割合が増加している(第Ⅱ-1-1-2-5図)。
第Ⅱ-1-1-2-5図 世界輸出に占める主要輸出国・地域の輸出額割合の推移
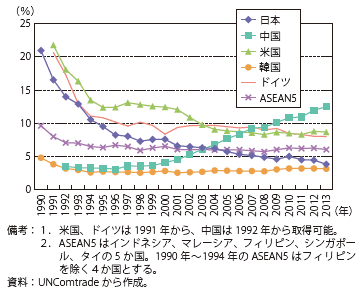
19 ここでは2014年時点の対世界輸出上位国(中国、米国、ドイツ、日本)に韓国、ASEAN5を加えた国・地域とする。
③生産工程別貿易財の輸出動向
次に、貿易財を生産工程別(第Ⅱ-1-1-2-6図)に整理し、国際比較を行うとともに、その推移を確認する20。
第Ⅱ-1-1-2-6図 生産工程別貿易財分類
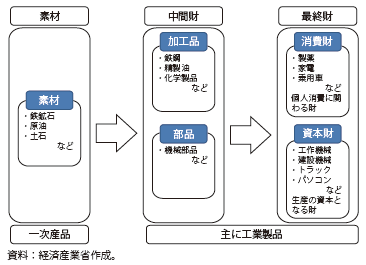
世界貿易(輸出額)の生産工程別貿易財の推移を見ると、全ての貿易財は2000年代に入り増加傾向で推移している。リーマン・ショックの影響により2009年に一旦は落ち込んだものの、その後は緩やかに回復している。素材は2000年代後半以降、徐々に増加傾向にあり、1990年から2013年で6.8倍(4,129億ドルから27,980億ドル)、中間財は、1990年から2013年で5.3倍(14,908億ドルから79,506億ドル)、最終財は、1990年から2013年で4.5倍(13,275億ドルから60,111億ドル)まで増加している(第Ⅱ-1-1-2-7図)。世界貿易(輸出額)に占める割合の推移を見ると、中間財は5割近傍で推移しているのに対して、最終財は1999年をピークに低下傾向にあり、現在はおよそ3割台まで低下している(第Ⅱ-1-1-2-8図)。
第Ⅱ-1-1-2-7図 世界貿易(輸出額)の生産工程別貿易財の推移
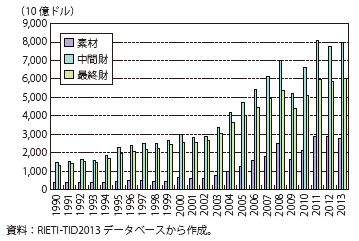
第Ⅱ-1-1-2-8図 世界貿易(輸出額)に占める生産工程別貿易財割合の推移
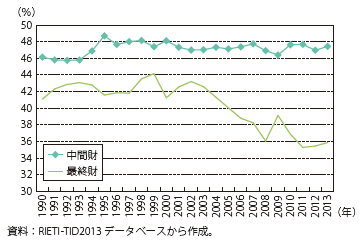
20 ここでは生産分業を念頭に、貿易を生産工程別の財(素材、中間財(加工品及び部品)、最終財(資本財及び消費財))に分けて分析を行う。その基礎データとしては、独立行政法人 経済産業省研究所RIETI-TID2013を用いる。
a)最終財の国際比較
次に、主要輸出国・地域21の最終財(消費財及び資本財)輸出額の推移を見ると、2013年では中国が12,113億ドル、ドイツが6,129億ドル、米国が5,166億ドルである。特に中国からの輸出額が急増しており、1990年から2013年で22.1倍になっている。日本は2008年まで増加傾向で推移していたものの、リーマン・ショックの影響により2009年に大きく落ち込んだ。その後、一旦は回復したものの、2011年以降再び低下傾向に転じており、2013年には2,998億ドルにまで低下している(第Ⅱ-1-1-2-9図)。
第Ⅱ-1-1-2-9図 主要輸出国・地域の最終財輸出額の推移
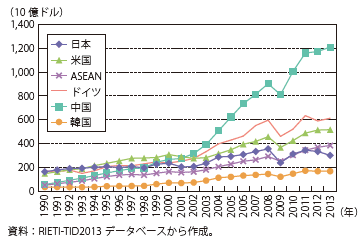
21 ここではRIETI-TIDの地域区分に従い、主要輸出国・地域を日本、米国、ASEAN、ドイツ、中国、韓国とする。ASEANはブルネイ、カンボジア、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの8か国。ただし、データの制約上、一部の国・年については統計が入手できない場合もある。特に記載がない限り、RIETI-TIDのデータを利用する集計の場合は以降も同じとする。
b)中間財の国際比較
次に、主要輸出国・地域の中間財(加工品及び部品)輸出額の推移を見ると、2013年は中国が8,185億ドル、米国が7,860億ドル、ドイツが6,607億ドル輸出している。特に中国の輸出額は1990年から2013年で36.2倍に増加している。日本は最終財と同様の動きを見せており、2008年まで緩やかに上昇していたものの、2009年にはリーマン・ショックの影響により低下した。その後、一旦は回復したものの、2011年をピークに再び低下傾向にあり、2013年には4,513億ドルにまで低下している(第Ⅱ-1-1-2-10図)。
第Ⅱ-1-1-2-10図 主要輸出国・地域の中間財輸出額の推移
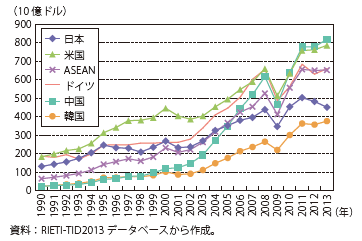
c)日本の生産工程別貿易財輸出額と主要輸出先別推移
日本の生産工程別貿易財の輸出額の推移を見ると、中間財である加工品、部品の輸出額が最も大きく、日本は中間財が輸出の主力となっていることが分かる。また、最終財のうち資本財はリーマン・ショックの影響を受け2009年に大きく落ち込んだ後、一旦は回復したものの、2011年をピークに再び低下傾向にある。消費財も資本財と同様に2009年に大きく落ち込んだものの、2010年に僅かに回復し、その後、横ばいで推移している(第Ⅱ-1-1-2-11図)。
第Ⅱ-1-1-2-11図 日本の生産工程別貿易財輸出額の推移
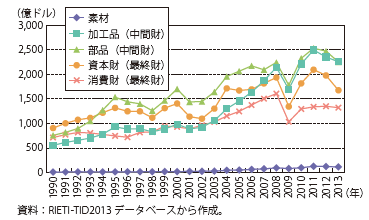
次に、日本からの輸出先別に生産工程別貿易財の輸出額の推移を見る。加工品(中間財)は、1990年から2013年で中国向けが15.0倍(36.3億ドルから544.1億ドル)、部品(中間財)は、1990年から2013年で中国向けが30.3倍(16.3億ドルから492.6億ドル)へと大きく増加している。資本財(最終財)及び消費財(最終財)は、日本の最大輸出相手国である米国向けの輸出額が大きい。また、2000年以降中国向けが増加傾向にあり、1990年から2013年で資本財(最終財)は13.3倍(28.1億ドルから374億ドル)、消費財(最終財)は18.1倍(6.0億ドルから107.9億ドル)と中間財同様に大きく増加している。日本は最終財以上に中間財を中国、ASEANへ輸出していることから、日本のサプライチェーンがアジアを中心に展開されている構図が見てとれる(第Ⅱ-1-1-2-12図)。
第Ⅱ-1-1-2-12図 輸出先別に見た日本の生産工程別貿易財輸出額の推移
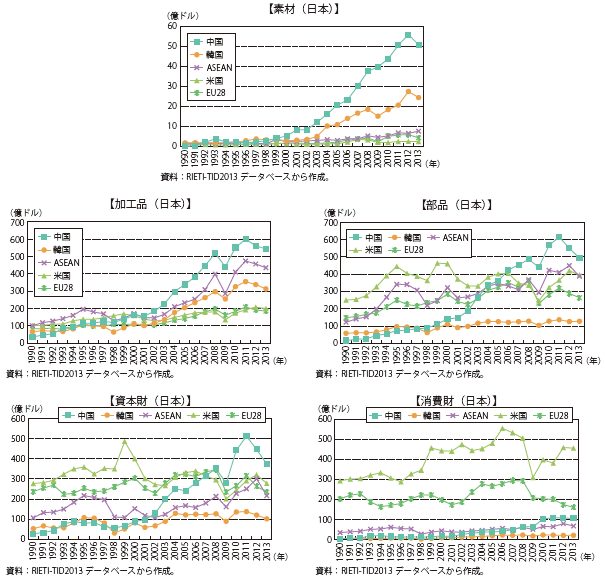
- Excel形式のファイル(素材(日本))はこちら

- Excel形式のファイル(加工品(日本))はこちら

- Excel形式のファイル(部品(日本))はこちら

- Excel形式のファイル(資本財(日本))はこちら

- Excel形式のファイル(消費財(日本))はこちら

日本の生産工程別貿易財の推移を見ると、資本財(最終財)が2011年をピークに低下傾向にあり、中国向け、EU28向け、韓国向けが低下している。特にEU28向けでは2009年にリーマン・ショックの影響により落ち込んだものの、その後、リーマン・ショック以前の水準には戻らず、軟調に推移している。
最終財(資本財及び消費財)について、日本と米国のEU28向け輸出額の推移を見ると、米国はEU28向けの最終財輸出が増加傾向であるのに対して、日本は1990年代からほぼ横ばいで推移している。また、日本と米国のEU28向け輸出を最終財(資本財及び消費財)別に比較すると、日本は資本財が横ばい、消費財が緩やかな低下傾向にあるのに対して、米国は資本財、消費財共に増加傾向にある(第Ⅱ-1-1-2-13図)。
第Ⅱ-1-1-2-13図 日本、米国のEU28向け最終財輸出額の推移
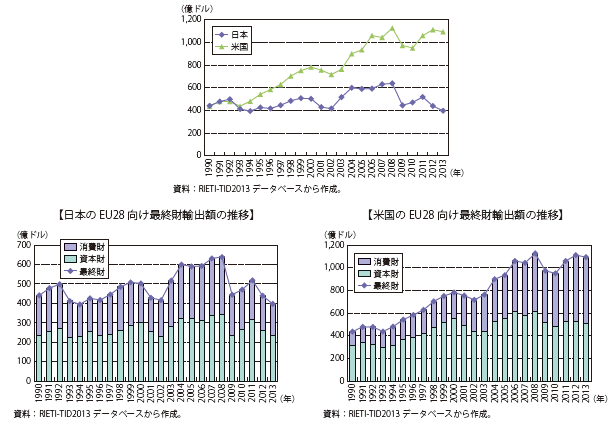
次に、日本と同様に主要輸出国からの生産工程別貿易財輸出について見る。
米国は中間財(加工品及び部品)の輸出額が最終財(資本財及び消費財)の輸出額を上回っている。特に、加工品(中間財)の輸出額は2000年代以降、増加傾向にあり、2009年にはリーマン・ショックの影響で一旦は落ち込んだものの、2010年以降、再び増加している。また、部品(中間財)の輸出額も加工品に次いで高い水準にある。また、素材に含まれる原油や天然ガスなどの資源の輸出にも強みを持つことから、素材の輸出額も堅調に推移している(第Ⅱ-1-1-2-14図)。
第Ⅱ-1-1-2-14図 米国の生産工程別貿易財輸出額の推移
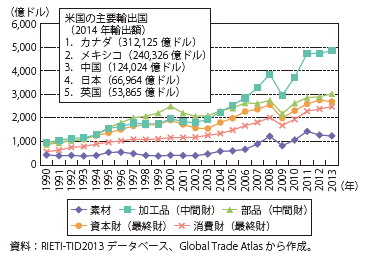
輸出先別に見ると、中間財(加工品及び部品)、最終財(資本財及び消費財)はEU向け、中国向け、ASEAN向けの輸出額が増加している。特に中国向けの部品(中間財)は1990年から2013年で36.7倍(8.1億ドルから295.7億ドル)、消費財(最終財)は39.1倍(4.2億ドルから166.1億ドル)と大きく増加している(第Ⅱ-1-1-2-15図)。
第Ⅱ-1-1-2-15図 輸出先別に見た米国の生産工程別貿易財輸出額の推移
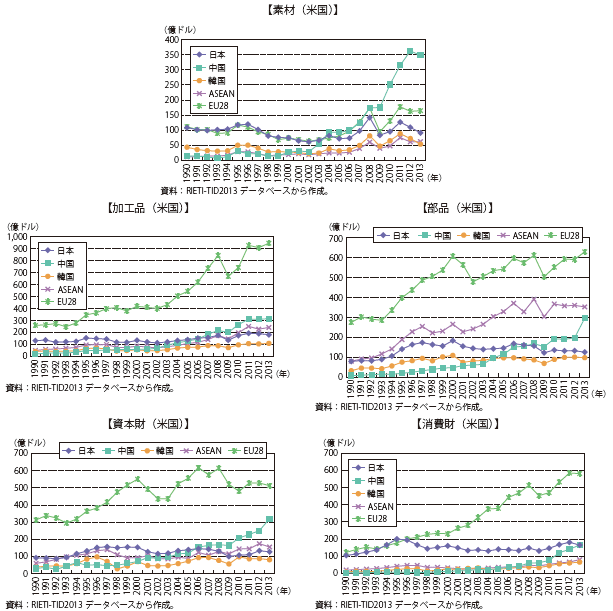
- Excel形式のファイル(素材(米国))はこちら

- Excel形式のファイル(加工品(米国))はこちら

- Excel形式のファイル(部品(米国))はこちら

- Excel形式のファイル(資本財(米国))はこちら

- Excel形式のファイル(消費財(米国))はこちら

ドイツは多くの貿易財の輸出額が増加傾向にあり、リーマン・ショック前を上回る水準で推移している。ドイツは日本と同様に素材の輸出額が少ないものの、加工品(中間財)、消費財(最終財)の輸出額が大きい(第Ⅱ-1-1-2-16図)。
第Ⅱ-1-1-2-16図 ドイツの生産工程別貿易財輸出額の推移
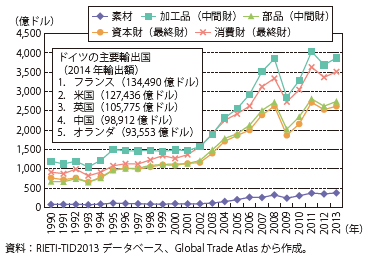
輸出先別に見ると、米国向けとEU域内、中国向けの輸出が増加しており、特に中国向けの部品(中間財)は1990年から2013年で55.2倍(5.0億ドルから277.1億ドル)、消費財(最終財)は60.7倍(3.0億ドルから179.8億ドル)と大きく増加している(第Ⅱ-1-1-2-17図)。
第Ⅱ-1-1-2-17図 輸出先別に見たドイツの生産工程別貿易財輸出額の推移
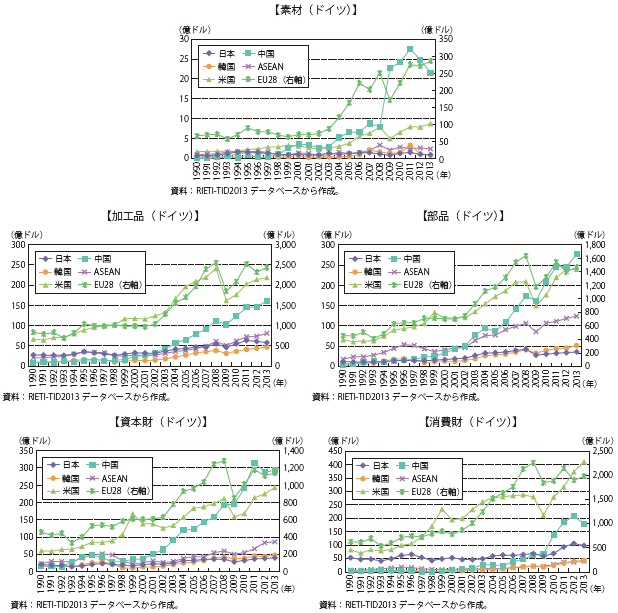
- Excel形式のファイル(素材(ドイツ))はこちら

- Excel形式のファイル(加工品(ドイツ))はこちら

- Excel形式のファイル(部品(ドイツ))はこちら

- Excel形式のファイル(資本財(ドイツ))はこちら

- Excel形式のファイル(消費財(ドイツ))はこちら

次に、中国について見ると、中国は最終財(資本財及び消費財)の輸出額が急増している。リーマン・ショックの影響を受け、2009年に落ち込みがみられたものの、その後は急速に輸出額を伸ばしている(第Ⅱ-1-1-2-18図)。
第Ⅱ-1-1-2-18図 中国の生産工程別貿易財輸出額の推移
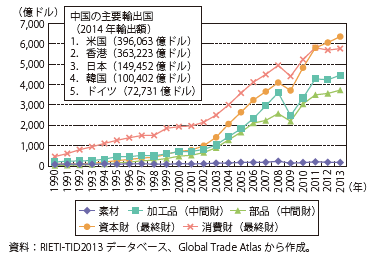
輸出先別に見ると、部品(中間財)は、ASEAN向けが1990年から2013年で256.0倍(1.7億ドルから446.5億ドル)、日本向けが1990年から2013年で223.7倍(1.2億ドルから267.8億ドル)と大きく増加している。資本財(最終財)は日本向けが1990年から2013年で172.3倍(2.7億ドルから461.2億ドル)、ASEAN向けが1990年から2013年で120.7倍(4.1億ドルから497.5億ドル)と大きく増加している(第Ⅱ-1-1-2-19図)。
第Ⅱ-1-1-2-19図 輸出先別に見た中国の生産工程別貿易財輸出額の推移
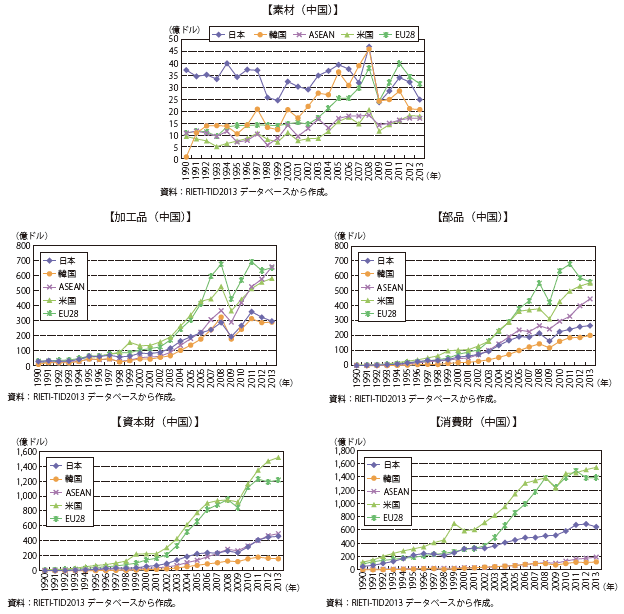
- Excel形式のファイル(素材(中国))はこちら

- Excel形式のファイル(加工品(中国))はこちら

- Excel形式のファイル(部品(中国))はこちら

- Excel形式のファイル(資本財(中国))はこちら

- Excel形式のファイル(消費財(中国))はこちら

ASEANについて見ると、特に加工品(中間財)、部品(中間財)の輸出額が増加している(第Ⅱ-1-1-2-20図)。
第Ⅱ-1-1-2-20図 ASEANの生産工程別貿易財輸出額の推移
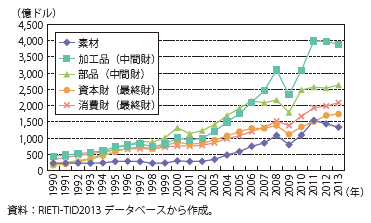
輸出先別に見ると、中国向けの加工品(中間財)及び部品(中間財)が増加傾向にある。中国向け加工品(中間財)は1990年から2013年で32.8倍(17.6億ドルから577.5億ドル)、部品(中間財)は1990年から2013年で289.9倍(2.2億ドルから637.7億ドル)と大きく増加している。日本向けの素材輸出も増加しており、2000年代後半以降100億ドルを上回る水準で推移している(第Ⅱ-1-1-2-21図)。
第Ⅱ-1-1-2-21図 輸出先別に見たASEANの生産工程別貿易財輸出額の推移
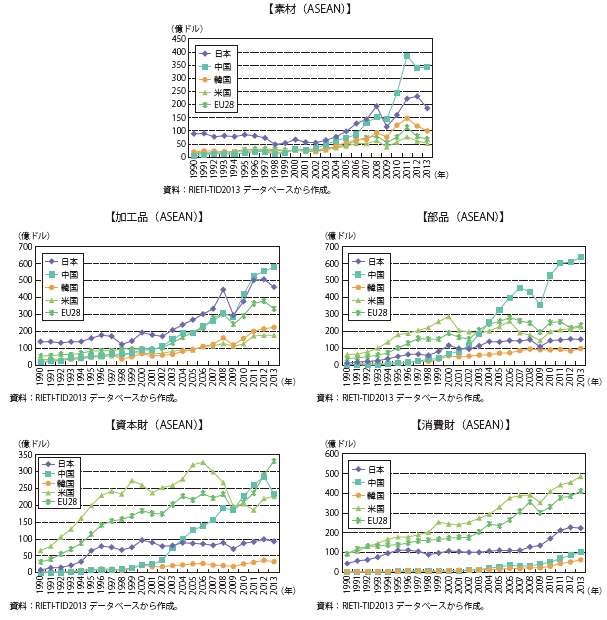
- Excel形式のファイル(素材(ASEAN))はこちら

- Excel形式のファイル(加工品(ASEAN))はこちら

- Excel形式のファイル(部品(ASEAN))はこちら

- Excel形式のファイル(資本財(ASEAN))はこちら

- Excel形式のファイル(消費財(ASEAN))はこちら

④世界貿易と財別輸出動向のまとめ
世界貿易(輸出額)を見ると、先進国が伸び悩む中、新興国が世界貿易(輸出額)の伸びをけん引しており、特に、中国からの輸出額の増加が顕著である。日本は先進国の中でも輸出額が低く、足下で見ると2011年をピークに低下傾向にある。
世界貿易(輸出額)を生産工程別貿易財別に見ると、最終財、中間財、素材と全ての貿易財で輸出額は増加傾向にある。しかし、その世界貿易に占める割合の推移をみると1990年代から中間財は横ばいで推移しているのに対して、最終財は2000年代以降、低下傾向にある。
主要輸出国別に生産工程別貿易財の推移を見ると、中国、米国、ドイツでは最終財、中間財の輸出額が増加傾向にある。日本は中間財の輸出額が最終財の輸出額を上回り、比較的高付加価値な中間財を中国などの組立拠点へ供給する輸出構造となっていることがうかがえる。また、日本の輸出を生産工程貿易財別に見ると、最終財が他国と比べても低調に推移していることが日本の輸出額が伸び悩む一因であると考えられる。
日本は最終財よりも中間財が主力となっているのに対して、米国、ドイツは共に中間財、最終財の両財の輸出額を伸ばしている。特に日本はEU28向けの最終財輸出が低下傾向にあり、米国と比べて見ても、消費財(最終財)輸出が伸び悩んでいることが分かる。
以下では、日本からの輸出に強みを持つ製品を明らかにするため、主要業種別に伸び率比較、個別品目を中心に各国・地域での輸入額シェアを確認し、日本の輸出力を検証する。
(2)日本の輸出力の検証
①日本の主要輸出先
日本の主要輸出先は、米国、中国である。これまで米国が日本の最大輸出先国であったが、2012年以降、米国、中国の両国への輸出額はほぼ同規模で推移している。日本からASEAN10への輸出額は微増しており、米国、中国に続く主要輸出先として、日本において重要な位置を占める。また、EU28への輸出はリーマン・ショック以降、減少しており、その水準はリーマン・ショック以前よりも回復せず横ばいで推移している(第Ⅱ-1-1-2-22図)。
第Ⅱ-1-1-2-22図 日本の主要輸出先(上位6か国)
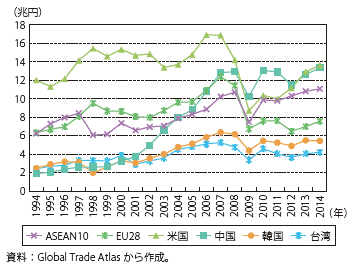
②日本の主要業種別輸出額の推移
次に、貿易統計(HSコード22)から日本の主要業種別に輸出額(円ベース)の推移と割合を見ると、「自動車」、「一般機械」、「電気機器」は日本の輸出をけん引する主要業種であり、堅調に推移している。また、「化学・プラスチック製品」の輸出も徐々に増加傾向にあり、足下では輸出額の15%を占めている(第Ⅱ-1-1-2-23図)。
第Ⅱ-1-1-2-23図 日本の主要業種別に見た輸出額の推移と主要業種割合(2014年)
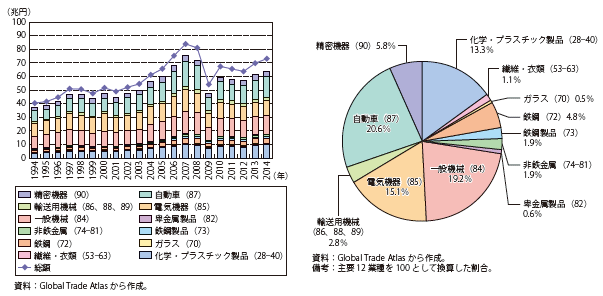
22 分類名の括弧はHSコードを指す。特に記載がない限り、本項以下の分類名、品目名の括弧もHSコードを指す。
③日本の主要輸出先に対する主要輸出品目
日本の主要輸出先に対する主要輸出品目(各国上位10品目)を見ると(第Ⅱ-1-1-2-24図)、中国、台湾、韓国、ASEANのアジア地域においては、「一般機械」、「電気機器」、「自動車」、「鉄鋼」が上位を占める。日本の最大輸出先である米国へは、「一般機械」、「電気機器」、「精密機器」の他、「自動車」や「航空機」といった輸送機械の輸出が上位を占める。EU28でも他国と同様に「一般機械」、「電気機器」、「自動車」、「精密機器」が輸出の上位を占めている。
第Ⅱ-1-1-2-24図 日本から各国・地域に対する主要輸出品目
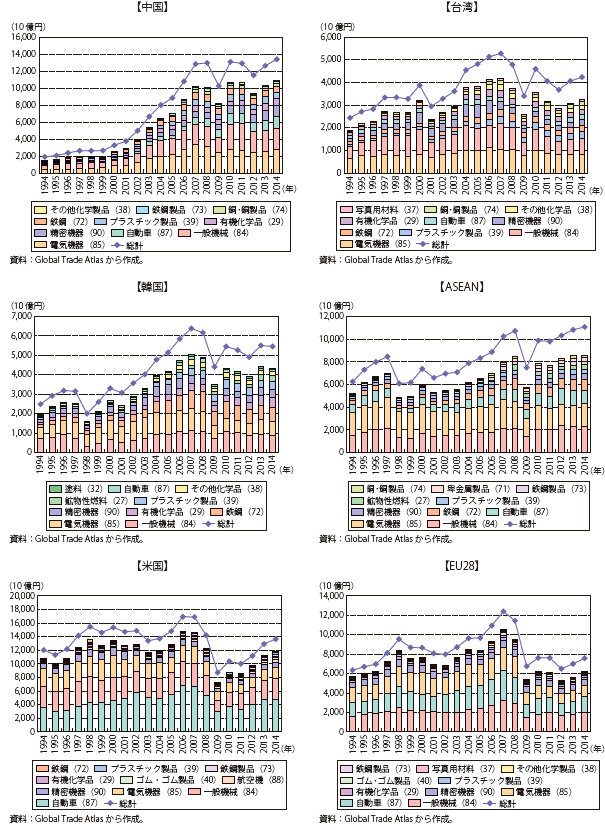
- Excel形式のファイル(中国)はこちら

- Excel形式のファイル(台湾)はこちら

- Excel形式のファイル(韓国)はこちら

- Excel形式のファイル(ASEAN)はこちら

- Excel形式のファイル(米国)はこちら

- Excel形式のファイル(EU28)はこちら

④日本輸出の伸び率比較
次に、主要産業別に世界輸出額の伸び率と日本輸出額の伸び率についての比較を行う。世界輸出額の伸び率を縦軸、日本輸出額の伸び率を横軸に取り比較すると、世界輸出額の伸び率に比して日本輸出額が伸びている業種はないことが分かる。
セクター別23に動きを見てみると、「素材関連セクター24(赤バブル)」は世界輸出額の伸びに対して、日本輸出額の伸びが比較的近い水準にある。また、「機械セクター25(青バブル)」の輸出額は大きいものの、世界輸出額の伸びに比して日本輸出額の伸びは低く、世界輸出額が4~8%の伸びであるのに対して、日本は-2~2%程度の伸びにとどまっている。「輸送用機械セクター26(オレンジバブル)」は世界輸出額の伸びが6~8%なのに対して、日本は3~5%程度である(第Ⅱ-1-1-2-25図)。
第Ⅱ-1-1-2-25図 世界と日本の主要業種別輸出額の伸び率
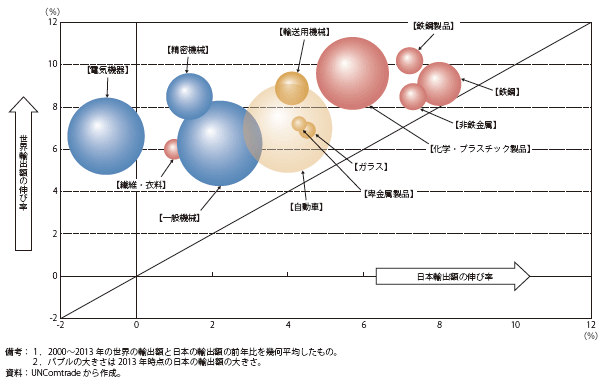
a)素材関連セクター伸び率
次に、各セクター別に中分類について世界と日本の輸出額の伸び率を見てみる。
「素材関連セクター」に関して中分類を見ると、「プラスチックフィルム等」は日本の輸出額の伸びが世界輸出額の伸びを上回っている。また、「鉄鋼」、「プラスチック製品」、「有機モノマー」は、世界の伸び率と近い水準にあり、かつ輸出額も大きい(第Ⅱ-1-1-2-26図)。
第Ⅱ-1-1-2-26図 素材関連セクター伸び率
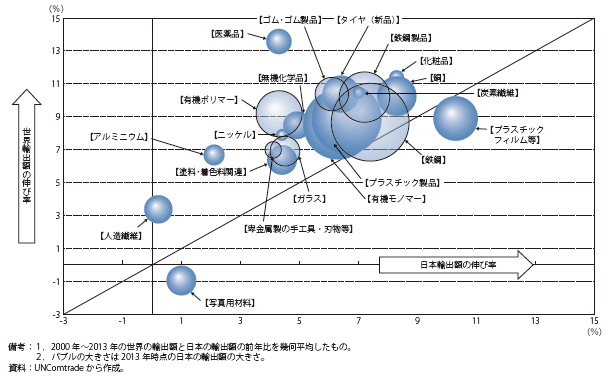
第Ⅱ-1-1-2-27表 素材関連セクター中分類品目表
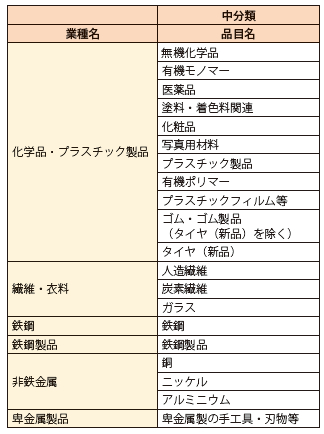
~化粧品の輸出~
近年、輸出が増加している化粧品について日本からの輸出額を見ると、化粧品の7~8割を「化粧下地、クリーム化粧品等」が占める(第Ⅱ-1-1-2-28図)。主要輸出先を見ると、台湾、香港、中国等のアジア諸国が上位を占める(第Ⅱ-1-1-2-29図)。
第Ⅱ-1-1-2-28図 日本の化粧品における品目別輸出額の推移
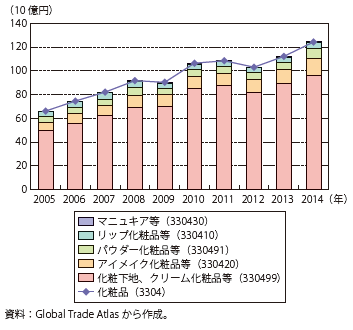
第Ⅱ-1-1-2-29図 日本の化粧品における主要輸出先(上位5か国)
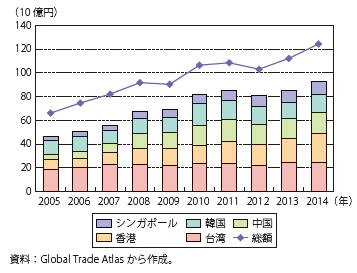
b)機械セクター伸び率
「機械セクター」に関して中分類を見ると、世界輸出額の伸びを上回る品目はないものの、「印刷機」や「ブルドーザー」、「内燃機関用の電子機器」は世界、日本共に輸出が伸びている品目である。機械類、機械部品の輸出は、日本の技術力が世界的にも評価されており、世界需要の動きを捉えながら輸出を伸ばしていることが分かる(第Ⅱ-1-1-2-30図)。
第Ⅱ-1-1-2-30図 機械セクター伸び率
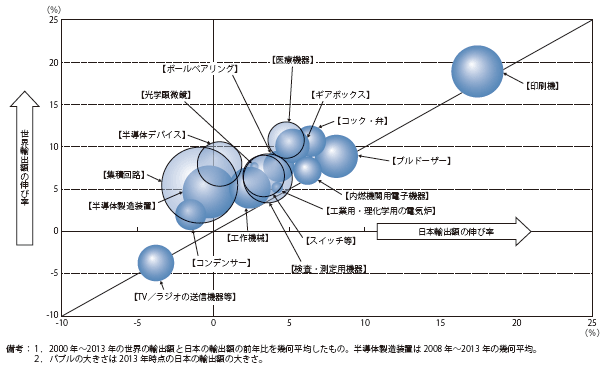
第Ⅱ-1-1-2-31表 機械セクター中分類品目表
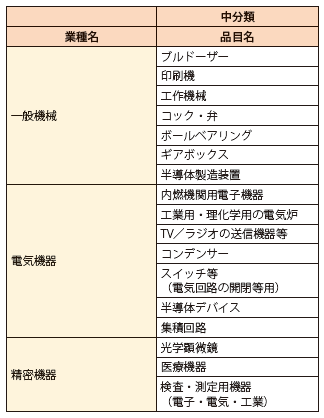
c)輸送用機械セクター伸び率
輸送用機械セクターに関して見る。「バス」、「船舶部品」、米国やEUを中心に市場拡大も見込まれる「航空機部品」は、輸出額は小さいものの、日本輸出額の伸びが世界の輸出額伸びを上回っている。また「乗用車」、「自動車部品」の輸出額は大きいものの、日本輸出額の伸びが世界輸出額の伸びを下回っている(第Ⅱ-1-1-2-32図)。
第Ⅱ-1-1-2-32図 輸送用機械セクター伸び率
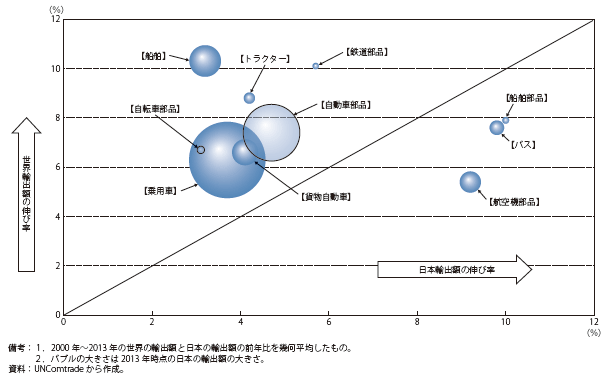
第Ⅱ-1-1-2-33表 輸送用機械セクター中分類品目表

~航空機部品の輸出~
日本からの航空機部品についての輸出額を見ると8,216億円(2014年)で、「航空機部品」と「航空機用エンジン部品」が増加傾向にある。2005年から2014年で「航空機部品」は3.6倍、「航空機用エンジン部品」は2倍に増加している(第Ⅱ-1-1-2-34図)。主要輸出先を見ると、米国向けの輸出が8割程度を占めている(第Ⅱ-1-1-2-35図)。
第Ⅱ-1-1-2-34図 日本の航空機部品における輸出額の推移
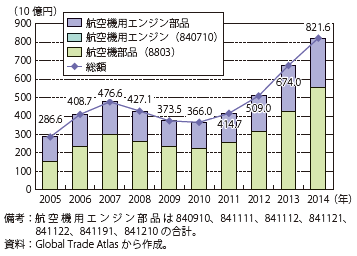
第Ⅱ-1-1-2-35図 日本の航空機部品における主要輸出先(上位3か国)
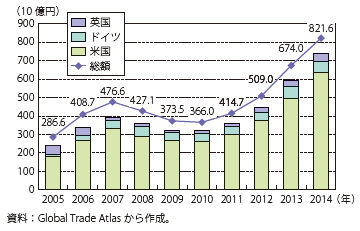
23 各セクター分類の詳細は各セクターの対象品目表を参照。
24 「素材関連セクター」は「化学・プラスチック製品(28-40)」、「繊維・衣料(53-63)」、「鉄鋼(72)」、「鉄鋼製品(73)」、「非鉄金属(74-81)(除:くず)」を指す。
25 「機械セクター」は「一般機械(84)」、「電気機器(85)」、「精密機器(90)」を指す。
26 「輸送機械セクター」は「自動車(87)」、「輸送用機械(自動車を除く)(86、88、89)」を指す。
⑤各国・地域に占める日本からの輸入割合~輸入額シェア~
各国・地域に占める日本からの輸入割合の推移を見ると、日本の主要輸出先における日本からの輸入割合は低下傾向にある。国別に見ると、2014年時点で日本からの輸入割合が最も高いのは台湾であり、台湾の輸入のうち15.3%が日本からの輸入である。次いで、韓国(10.2%)、ASEAN5(9.0%)、中国(8.3%)とアジア諸国が上位を占める。また、日本の最大輸出先である米国での輸入額シェアは5.7%である(第Ⅱ-1-1-2-36図)。
第Ⅱ-1-1-2-36図 各国・地域に占める日本からの輸入割合~輸入額シェア~
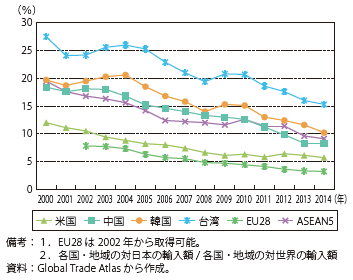
a)素材関連セクターの輸入額シェア
次に、各セクターの細分類(個別品目)27を中心に各国・地域に占める日本からの輸入額シェア(2011年~2014年平均28)を見る。素材関連セクターを見ると、多くの個別品目が、韓国で高い輸入額シェアを有する。特にプラスチック製品の「プラスチックフィルム等」が75%であり、そこに含まれる個別品目の「ポリエチレンテレフタレート」が81%と極めて輸入額シェアが高い。また「塗料」、「インキ」や日用品の「剪定ばさみ」や「のこぎり」も韓国、台湾で過半数以上の輸入額シェアを有する。日用品産業は近年の消費者のライフスタイルや消費者の購買意識の変化、またアジア諸国からの安価な輸入品の増加など、総じて地場産業にとっては厳しい状況が続いているものの、韓国、台湾、中国を中心に日本の優れた製品が評価されていることがうかがえる29(第Ⅱ-1-1-2-37図)。
第Ⅱ-1-1-2-37図 各国・地域に占める日本からの輸入額シェア~素材関連セクター~(2011年~2014年平均)
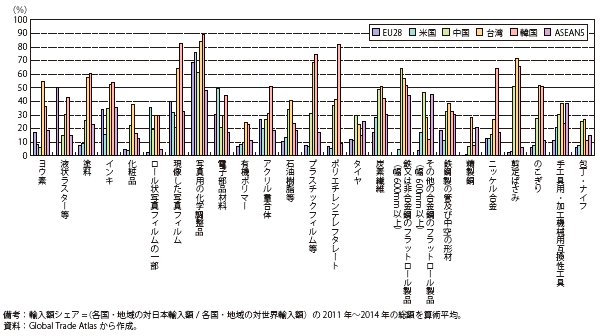
b)機械セクターの輸入額シェア
機械セクターの輸入額シェアを見ると、日本の一般機械の中でも「ブルドーザー」、「産業用ロボット」、「金属加工用のマシニングセンター等30」が多くの国・地域で50%以上の輸入額シェアを有する。
「産業用ロボット」については、ロボット技術の高度化によって医療品工場などのクリーンルームにおける作業などの適用分野の広がりや自動車工場での溶接やハンドリング用途など、更なる高度化が期待される。また、「金属加工用のマシニングセンター等」は、数値制御で自動操作できることから、高品質の製品を安定的に製造できるため、工作機械の中でも主要な製品である。これらの機械製品は最先端研究を行う先進国やアジアを中心とした新興国の成長などの需要の広がりによって、更なる輸出が期待される。
精密機器の個別品目である「偏光材料シート31」は米国(87.5%)、韓国(81.3%)で80%以上、「光学顕微鏡」は台湾(49.6%)、韓国(46.3%)などのアジアを中心におよそ50%程度の輸入額シェアを有している(第Ⅱ-1-1-2-38図)。
第Ⅱ-1-1-2-38図 各国・地域に占める日本からの輸入額シェア~機械セクター~(2011年~2014年平均)
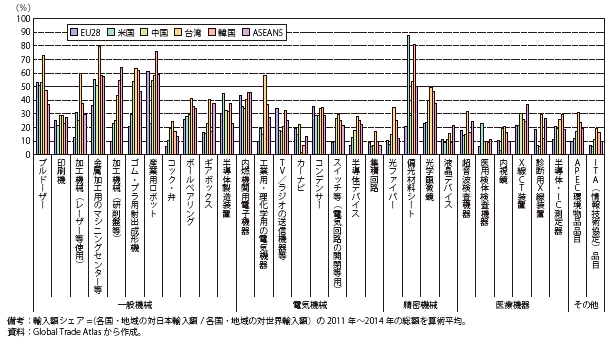
c)輸送用機械セクターの輸入額シェア
輸送用機械セクターの輸入額シェアを見ると、日本は、台湾の輸入のうち「バス」(84.4%)、「鉄道部品」(83.3%)、「船舶部品」(55.6%)、「船舶」(48.8%)、「自動車部品」(46.1%)が高い輸入額シェアを有している。
ASEAN5の輸入では「バス」が52.4%、「自動車部品」(46.4%)、「船舶部品」(42.6%)の輸入額シェアを有している。
輸送用機械セクターに関してみれば、日本は、「バス」、「鉄道部品」、「船舶部品」などの交通インフラに関する品目、「自動車部品」、「貨物自動車」などの道路用車両に関する品目をアジア諸国中心に輸出し、高い輸入額シェアを獲得している(第Ⅱ-1-1-2-39図)。
第Ⅱ-1-1-2-39図 各国・地域に占める日本からの輸入額シェア~輸送用機械セクター~(2011年~2014年平均)
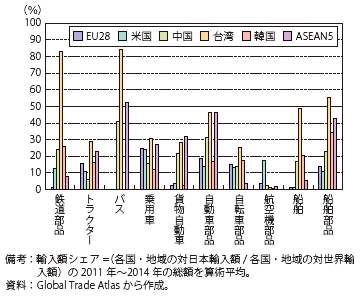
d)その他の輸入額シェア
その他の輸入額シェアを見ると、中国(57.7%)、台湾(57.8%)で「衛生用品」が50%以上の輸入額シェアを有している。また、「ボールペン等」は多機能性やアイデアのある製品が消費者の購買意欲を高めており、近年、欧米での人気が高まっている(第Ⅱ-1-1-2-40図)。
第Ⅱ-1-1-2-40図 各国・地域に占める日本からの輸入額シェア~その他~(2011年~2014年平均)
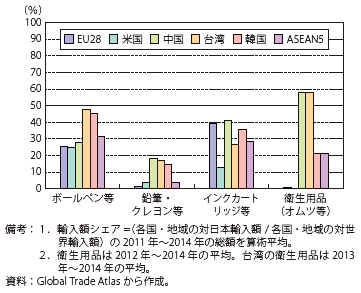
27 各セクター細分類の詳細は各セクターの対象品目表を参照。
28 日本の輸出はリーマン・ショックの影響により、2009年に大きく落ち込んだが、2010年には一旦回復した。しかし、2011年に震災の影響により再び落ち込んだことから、本項での輸入割合(輸入額シェア)は2011年~2014年までの平均を見ている。
29 数量と単価を見ても、数量増加、単価上昇が確認できる。詳細は第Ⅱ部第1章第1節3.品目別に見た「輸出する力」を参照。
30 マシニングセンターは自動で金属加工を行うことができる機械である。
31 偏光材料シートは主に液晶ディスプレイに用いられている。
⑥伸び率、輸入額シェアのまとめ
a)素材関連セクター
素材関連セクターは、「写真用材料32」、「プラスチックフィルム等」が日本輸出額の伸びが世界輸出額の伸び率を上回っている。
「プラスチックフィルム等」の輸入額シェアを見ると、韓国(74.4%)、台湾(68.4%)のシェアを有しており、「ブラスチックフィルム等」の個別品目である「ポリエチレンテレフタレート」を見ると、韓国で81.6%と高い輸入額シェアを有している。
また世界輸出額の伸び率を上回らないものの、「卑金属の手工具・刃物等」の個別品目である日用品の「剪定ばさみ」、「のこぎり」は中国、台湾、韓国のアジア諸国を中心に輸入額シェアを有している(第Ⅱ-1-1-2-41表)。
第Ⅱ-1-1-2-41表 素材関連セクターのまとめ
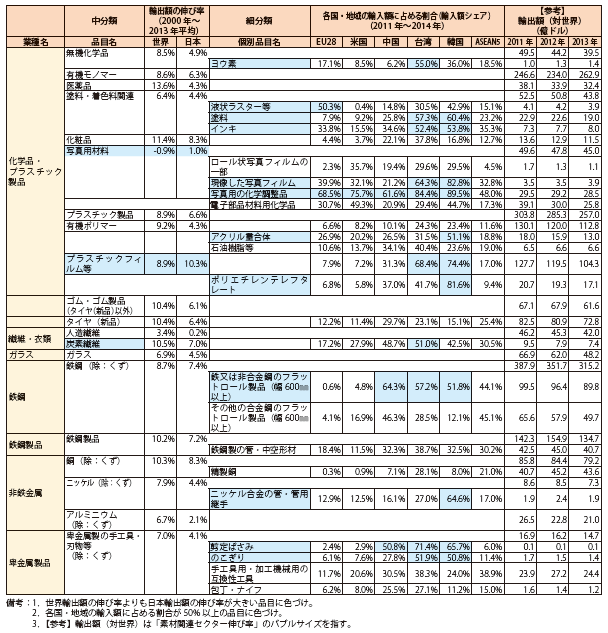
32 「写真用材料」の主要輸出品目について輸入額シェアを見ると、「写真用の化学調整品」がASEAN5を除く他の市場全てで過半数以上、「現像した写真フィルム」も台湾、韓国で過半数以上のシェアを有する。しかし、写真用材料はデジタル化の進展により市場が縮小傾向にある。
b)機械セクター
「機械セクター」は、日本輸出額の伸びが世界輸出額の伸びを上回る品目はないものの、「ブルドーザー」や「印刷機」の伸び率差は1%程度であり、世界と日本の伸び率はほぼ近い水準となっている。
輸入額シェアを見ると、「ブルドーザー」は韓国、ASEAN5を除く各国・地域でシェアを有し、特に台湾では73.2%のシェアを有している。「ゴム・プラスチック用射出成形機」や「産業用ロボット」はアジア諸国を中心に5~7割程度のシェアを有している。また、工作機械の個別品目である「金属加工用のマシニングセンター等」はEU28を除く各国・地域でシェアを獲得しており、特に台湾で79.3%の高い輸入額シェアを有している。
精密機器の個別品目である「偏光材料シート」について見ると、米国(87.5%)、韓国(81.3%)、台湾(53.8%)の輸入額シェアを有しており、特に米国、韓国では8割を超えるシェアを有している。また、「光学顕微鏡」は台湾(49.6%)、韓国(46.3%)でおよそ50%の輸入額シェアを有していることから、光学部品はアジア中心に輸入額シェアを有していることが分かる(第Ⅱ-1-1-2-42表)。
第Ⅱ-1-1-2-42表 機械セクターのまとめ
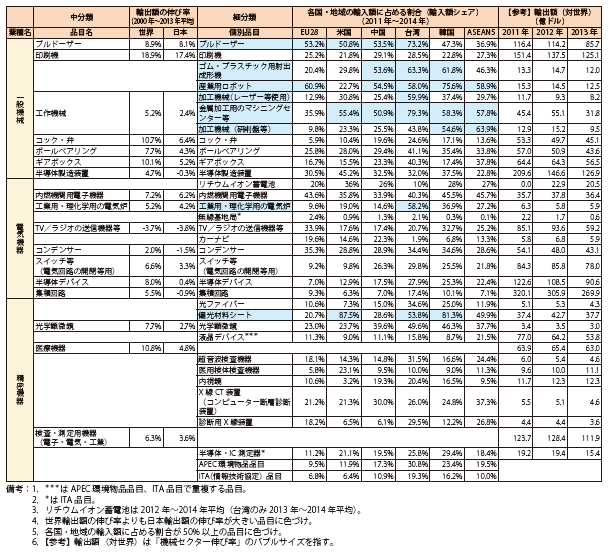
c)輸送用機械セクター
輸送用機械セクターを見ると、日本輸出額の伸びが世界輸出額の伸びを上回っているのは、「バス」、「航空機部品」、「船舶部品」である。輸入額シェアを見ると、「バス」は台湾(84.4%)、ASEAN5(52.4%)でシェアが高い。「航空機部品」は米国の輸入額シェアが最も高く17.2%を有する。また、台湾では「鉄道部品」(83.3%)、「船舶部品」(55.6%)が高い輸入額シェアを有している(第Ⅱ-1-1-2-43表)。
第Ⅱ-1-1-2-43表 輸送用機械セクターのまとめ
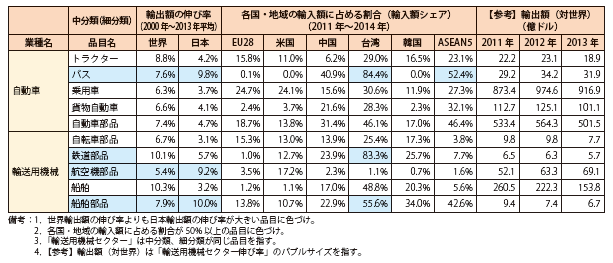
第Ⅱ-1-1-2-44表 素材関連セクターの対象品目表
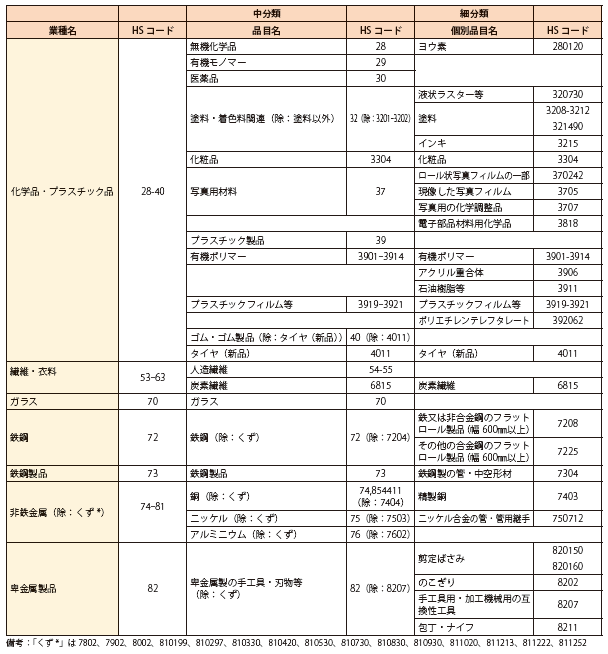
第Ⅱ-1-1-2-45表 機械セクターの対象品目表
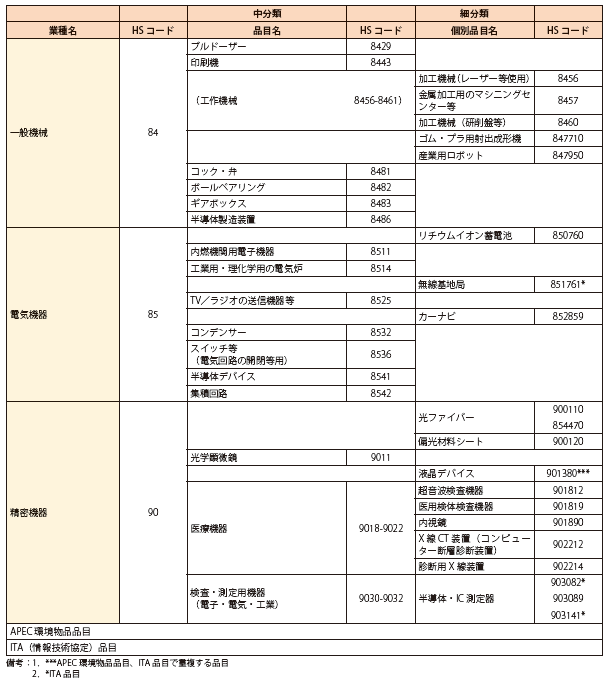
第Ⅱ-1-1-2-46表 輸送用機械セクターの対象品目表
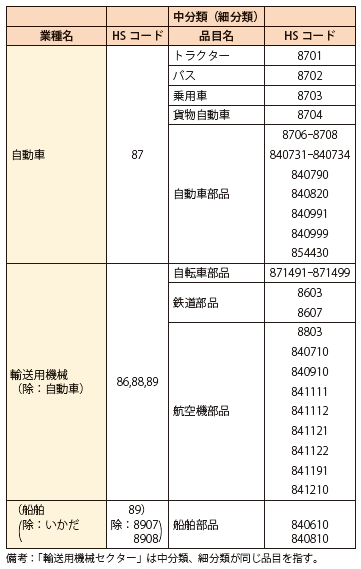
第Ⅱ-1-1-2-47表 その他の対象品目表
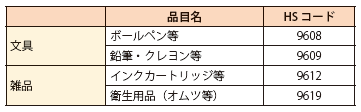
3.品目別に見た「輸出する力」
前段までに、日本と世界の主な輸出品目に関する動向を確認した。しかし、輸出額全体で見ることに加えて、細分化した品目の状況(輸出額、単価、数量とその伸びなど)を詳細に検討することで、日本の製造業の輸出力をより具体的に把握することが可能であろう。
そこで、各国比較が可能な範囲で最も細分化した関税番号であるHS6桁単位で、日本を中心とした輸出動向を見ていくこととする。
(1)輸出額増加品目(各国比較)
はじめに、主要国の輸出総額の中で、輸出額が増加しているHS6桁単位の品目(以下、HS6桁の品目を「品目」とする)がどの程度のシェアを占めているのかを比較してみる。なお、主要国としては、我が国の輸出競合相手国として、米国、英国、ドイツ、フランス、中国、韓国を取り上げることとする。
輸出額が増加している品目の抽出方法は、第Ⅱ-1-1-3-1図のとおりとする。
第Ⅱ-1-1-3-1図 輸出額増加品目の割合に関する各国比較(手法)37
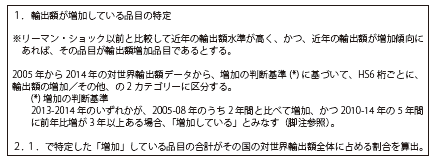
37 なお、具体的な基準については、直近の2014年の輸出額が2008年を上回るというような単純化したものも考えられるが、詳細な品目におりた場合は、長期的な傾向とは別に、受注生産の場合など個別事情によって単年の輸出額が増減することも少なくない。そこで、ここではそういった統計の不安定性を回避するため、複数年にわたってみていくこととして、図に示す方法を採用した。
輸出額が増加傾向にある品目が輸出額全体に占める割合を見ると、日本が40%台にとどまるのに対し、ドイツ、米国、韓国、英国、中国は70%を超えている(第Ⅱ-1-1-3-2図)。近年の日本の輸出が他国に比べて伸び悩んでいることからすれば、日本の輸出額が増加している品目シェアが低いことは当然ではある。しかし、輸出額が増加している品目シェアと輸出額の全体の伸びの傾向は、必ずしも一致しておらず、輸出額が増加している品目シェアが高いにも関わらず輸出額の伸びが低い国も見られる(第Ⅱ-1-1-3-3図)。
第Ⅱ-1-1-3-2図 輸出額が増加傾向の品目が輸出額全体に占める割合(2014)
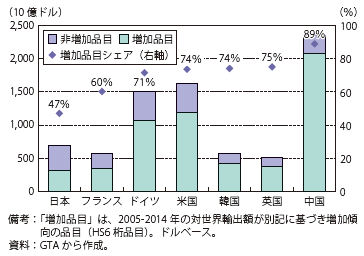
第Ⅱ-1-1-3-3図 対世界輸出額の伸び率比較

そこで、輸出額が増加している品目と非増加品目の輸出額の伸びを比較してみる。まず、輸出額が増加している品目の2005年から2014年の輸出額の伸びは、中国と韓国が群を抜いて高い(第Ⅱ-1-1-3-4図)。非増加品目の輸出額の伸びは、英国とフランスのマイナス幅が大きいことがわかる。日本とドイツを比較すると、輸出額が増加している品目の輸出額伸び率は日本の方が高く、非増加品目の輸出額の伸び率の減少幅は日本の方が小さい。それにも関わらず、ドイツの方が全体での輸出額の伸びが大きいのは、先に見たように、輸出額が増加している品目シェアが大きいという点にある。
第Ⅱ-1-1-3-4図 輸出額が増加している品目と非増加品目の輸出額伸び率(2011-14年/2005-08年)
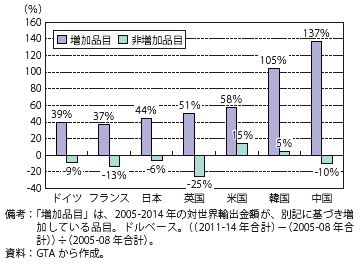
一方、ドイツと英国を比較すると、両国の輸出額が増加している品目シェア(第Ⅱ-1-1-3-2図)と輸出額の伸び(第Ⅱ-1-1-3-3図)は近い水準にあるが、輸出額が増加している品目と非増加品目の輸出額の伸びの傾向は大きく異なっている。これは、両国において、伸びている品目とそうでない品目の種類や状況の違いが影響していると考えられる。
次に、各国はどのような業種において、輸出額増加品目のシェアが高いのか見てみる(第Ⅱ-1-1-3-5図)。ここでは、主要業種として、化学・プラスチック、繊維・衣料、鉄鋼・鉄鋼製品、非鉄金属、一般機械、電気機器、精密機器、輸送用機械の8業種に焦点を当てる38。
第Ⅱ-1-1-3-5図 主要国の輸出における輸出額増加品目のシェア(主要8業種)
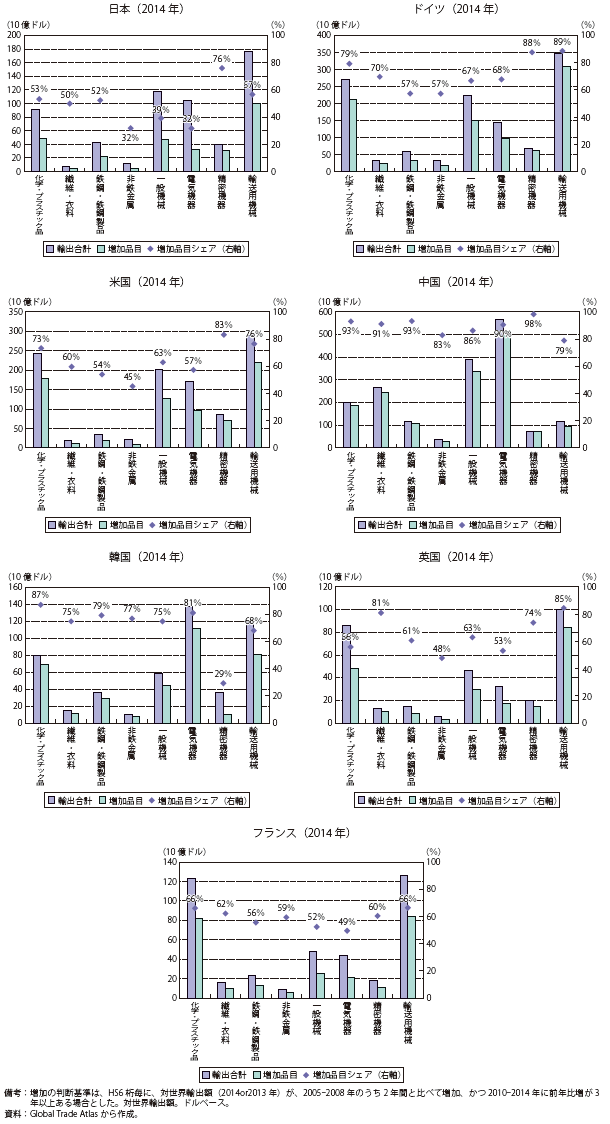
- Excel形式のファイル(日本(2014年))はこちら

- Excel形式のファイル(ドイツ(2014年))はこちら

- Excel形式のファイル(米国(2014年))はこちら

- Excel形式のファイル(中国(2014年))はこちら

- Excel形式のファイル(韓国(2014年))はこちら

- Excel形式のファイル(英国(2014年))はこちら

- Excel形式のファイル(フランス(2014年))はこちら

まず、日本は、輸送用機械と精密機器を除き、輸出額が増加している品目シェアが3~5割にとどまる。一方、中国とドイツはどの業種でも輸出額が増加している品目の割合が高く、日本との差が顕著である。米国は一部に輸出額が増加している品目シェアが低いものがみられるものの、規模の大きい輸送用機械、一般機械、化学・プラスチック品の業種では、いずれも輸出額が増加している品目シェアが60%を上回っている。英国は、規模が最も大きい輸送用機械で輸出額が増加している品目シェアが8割を超える一方、規模の大きい化学・プラスチック品や電気機器で、同割合が5割強と、差が大きいことが特徴的である。
38 本項における「主要8業種」の内容及び対象とする関税番号については、第Ⅱ-1-1-3-67図を参照。また、鉄鋼・鉄鋼製品及び非鉄金属については、「くず」を含まない。また、輸送用主要部品は「輸送用機械」に含まれ、「一般機械」等には含まれない。
(2)輸出数量と単価(各国比較)
(1)で確認した輸出額は、為替の影響による増減も含んだものであったが、以下((2)(3)(5))では、為替の影響を排除するため輸出数量を確認する。同時に、日本からの輸出品が高付加価値化している可能性が指摘されていることから、輸出単価の動向も確認する。また、数量の動向と単価の動向を合わせて見ることにより、輸出額が伸びているものが、数量の増加によるものなのか、単価の上昇によるものなのか、あるいはその両方によるものなのか、といったことを明らかにできると考える。また、それにより各国の強みや特徴も確認していく。なお、本項における数量と単価の動向の分析方法は、第Ⅱ-1-1-3-6図のとおりとする。
第Ⅱ-1-1-3-6図 数量×単価分析(計算方法)
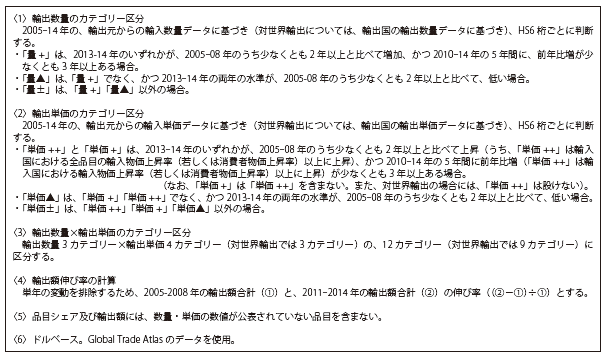
第Ⅱ-1-1-3-7図 (参考)数量×単価分析の一覧表の見方
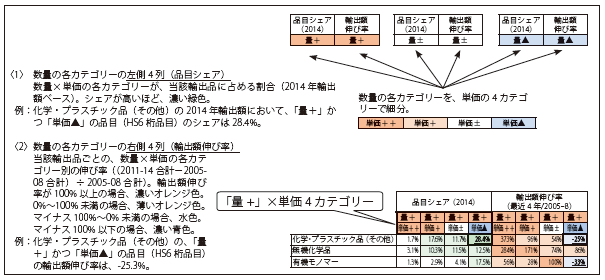
はじめに、対世界輸出の合計額について、各国の数量・単価動向を比較する。
第Ⅱ-1-1-3-8表のとおり、日本は、数量増加の品目シェアと、単価上昇の品目シェアが、今回確認した主要国の中で最も低い。また、数量と単価を合わせて見ると、数量増加かつ単価上昇(「量+単価+」)カテゴリーの品目シェアが最も高いのは、中国、韓国、ドイツの順であった。
第Ⅱ-1-1-3-8表 数量・単価動向(主要国の対世界輸出)
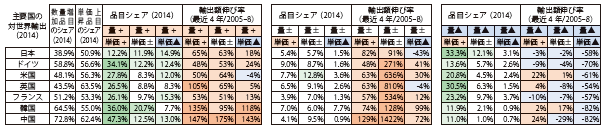
他方、数量が減少していても単価が上昇することで輸出額の伸びが期待できる場合もあることから、数量減少かつ単価上昇(「量▲単価+」)カテゴリーの品目シェアを確認すると、日本の同カテゴリー割合は、各国の中で最も高く33%であったが、同カテゴリーの輸出額の伸びはマイナスであった。同カテゴリー割合が比較的大きく輸出額の伸びがプラスである国は、英国(品目シェア31%、伸び4%)、米国(同21%、22%)であった。
次に、市場別に比較する。
日本の数量増加品目のシェアは、中国市場(第Ⅱ-1-1-3-9表)とEU市場(第Ⅱ-1-1-3-11表)では3割程度と低いが、米国市場(第Ⅱ-1-1-3-10表)では4割強とやや高まる。日本の単価上昇の品目シェアを見ると、米国市場では6割強と高く、ドイツと英国を上回っている。
第Ⅱ-1-1-3-9表 数量・単価動向(主要国の対中国輸出)
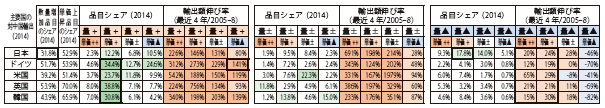
第Ⅱ-1-1-3-10表 数量・単価動向(主要国の対米国輸出)
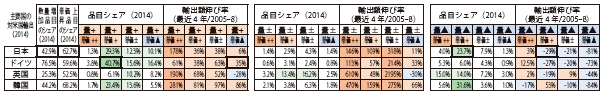
第Ⅱ-1-1-3-11表 数量・単価動向(主要国の対EU輸出)
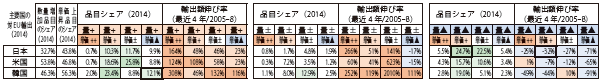
数量と単価を合わせて見ると、日本の、数量増加かつ単価上昇(「量+単価+」)、数量増加かつ単価大幅上昇(「量+単価++」)の両カテゴリーの品目シェアは、中国市場とEU市場では他国に比べ顕著に低い。その分、数量減少かつ単価上昇(「量▲単価+」)、数量減少かつ単価大幅上昇(「量▲単価++」)の両カテゴリーの品目シェアが高いが、両カテゴリーの輸出額の伸び率を見ると、中国市場を除いてマイナスとなっている。
ドイツは、対中国輸出、対米国輸出の双方で、数量増加かつ単価上昇(「量+単価+」)カテゴリーの品目シェアが高い。また、ドイツは、対中国輸出、対米国輸出の双方で、数量減少(「量▲」)カテゴリーの品目シェアが他国と比べて最も小さい。特に対米国市場では、数量増加かつ単価上昇(「量+単価+」)、数量増加かつ単価大幅上昇(「量+単価++」)の両カテゴリーの品目シェアが他国に比べ最も高い。ドイツ企業の多くが、価格競争によらずに売上を伸ばすことに成功していることを示唆していると言える。一方、ドイツは数量増加かつ単価低下(「量+単価▲」)カテゴリーの品目シェアも他国に比べて高く、しかも同カテゴリーの輸出額の伸びが大きいことから、価格の引き下げによるビジネスもうまく行っていることがわかる。
(3)日本の輸出数量と単価動向(主要業種及び主要輸出品別)
以上より、日本は全体的に、輸出数量が増加している品目の割合が他国に比べて低く、また、輸出数量が減少している場合には、単価が上昇していても輸出額が伸びていない品目が多いことが分かった。
それでは、全体ではなく分野別に見ると、どのような傾向が読み取れるであろうか。以下では、主な輸出業種や主な輸出品目等について数量と単価の分析を行い、日本の製造業の輸出力を概観する。
まず、主要8業種39を見てみよう。数量が増加している品目シェアが高い(同シェア50%以上の)業種が、鉄鋼・鉄鋼製品、繊維・衣料、化学・プラスチック品、精密機器である。またこれらの業種では、数量が増加している品目の輸出額の伸び率も高い(第Ⅱ-1-1-3-12図)。
第Ⅱ-1-1-3-12図 数量増加の品目シェアと伸び(日本の対世界輸出:主要8業種)
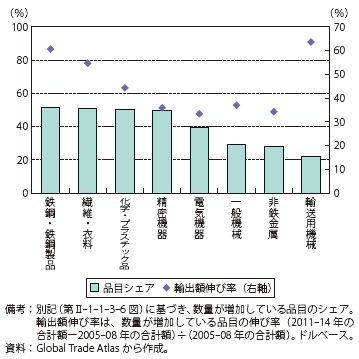
次に、単価が上昇している品目シェアが高い(50%以上)業種を挙げてみると、その中で、輸送用機械、精密機器、繊維・衣料、化学・プラスチック品では、単価が上昇している品目の輸出額の伸び率も高い(第Ⅱ-1-1-3-13図)。一般機械は、単価が上昇している品目シェアが高いものの、その輸出額の伸び率は低い。一方、電気機器は、単価が上昇している品目の輸出額が減少していることが分かる。
第Ⅱ-1-1-3-13図 単価上昇の品目シェアと伸び(日本の対世界輸出:主要8業種)
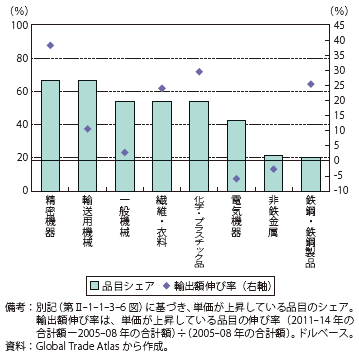
数量と単価を合わせて見ると、数量増加かつ単価上昇(「量+単価+」)カテゴリーの品目シェアが、他と比べて大きい業種は、化学・プラスチック品、繊維・衣料、精密機器である(第Ⅱ-1-1-3-14表)。数量減少かつ単価上昇(「量▲単価+」)カテゴリーの品目シェアが、他の業種と比べて大きい業種主要8業種は、一般機械、精密機器、輸送用機械である。そのうち一般機械は、同カテゴリーの品目の輸出額の伸び率がマイナスとなっている。
第Ⅱ-1-1-3-14表 数量・単価動向(日本の対世界輸出:主要8業種)
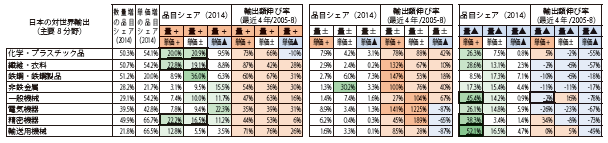
39 鉄鋼・鉄鋼製品及び非鉄金属については、「くず」を含まない。また、輸送用主要部品は「輸送用機械」に含まれ、「一般機械」等には含まれない。なお、本項における「主要8業種」の内容及び対象とする関税番号については、第Ⅱ-1-1-3-67図を参照。
①素材関連セクター
素材関連セクターの主要輸出品の状況を確認する。数量増加の品目シェアが高く(同シェア50%以上)、その輸出額の伸びが大きい(同伸び率50%以上)ものは、化粧品、ガラス、ゴム・ゴム製品(新品タイヤ以外)、有機モノマー、鉄鋼、人造繊維である(第Ⅱ-1-1-3-15図)。
第Ⅱ-1-1-3-15図 数量増加の品目シェアと伸び(日本の対世界輸出:素材関連セクター)

単価上昇カテゴリーを見ると、全体的に輸出額の伸びが低く、同カテゴリーの品目の輸出額の伸びが50%以上であるのは、ゴム・ゴム製品、タイヤ(新品)、化粧品にとどまる(第Ⅱ-1-1-3-16図)。
第Ⅱ-1-1-3-16図 単価上昇の品目シェアと伸び(日本の対世界輸出:素材関連セクター)

数量増加かつ単価上昇(量+単価+)カテゴリーの品目シェアが比較的大きい(同シェア20%以上)ものは、ゴム・ゴム製品、人造繊維、タイヤ(新品)、有機モノマーである(第Ⅱ-1-1-3-17図)。
第Ⅱ-1-1-3-17図 数量・単価とも増加の品目シェアと伸び(日本の対世界輸出:素材関連セクター)
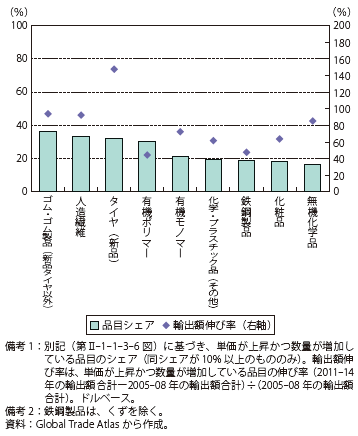
一方、数量減少かつ単価上昇カテゴリーの品目シェアが10%以上の主要輸出品の状況は第Ⅱ-1-1-3-18図のとおりである。塗料などが数量減少かつ単価上昇の品目の輸出額を伸ばしている。
第Ⅱ-1-1-3-18図 数量減少・単価上昇の品目シェアと伸び(日本の対世界輸出:素材関連セクター)
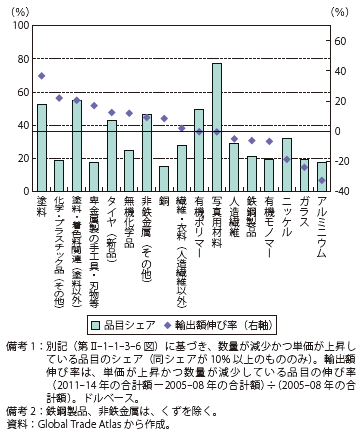
第Ⅱ-1-1-3-19表 数量・単価動向(日本の対世界輸出:素材関連セクター)
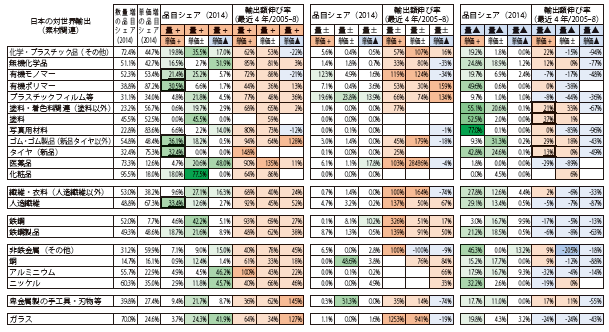
②機械関連セクター
機械関連セクターの主要輸出品で、数量増の品目シェアが高く(同シェア50%以上)、その輸出額の伸びが大きい(同伸び率50%以上)ものは、航空機部品、工作機械、自動車部品、コック・弁である(第Ⅱ-1-1-3-20図)。
第Ⅱ-1-1-3-20図 数量増加の品目シェアと伸び(日本の対世界輸出:機械関連セクター)
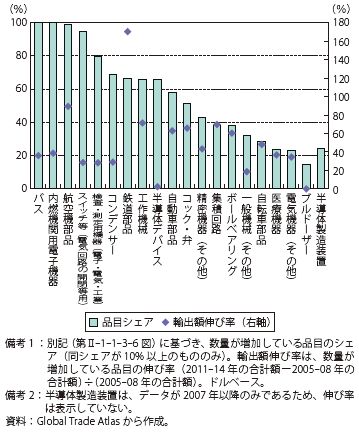
単価上昇カテゴリー割合について見ると、全体的に同カテゴリーに含まれる品目の輸出額の伸びは低いが、鉄道部品と集積回路は、同カテゴリーの品目の輸出額の伸びが高い(同伸び率50%以上)(第Ⅱ-1-1-3-21図)。
第Ⅱ-1-1-3-21図 単価上昇の品目シェアと伸び(日本の対世界輸出:機械関連セクター)
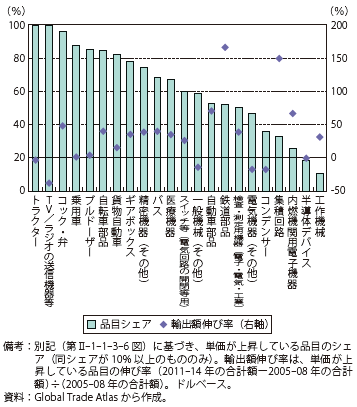
また、数量増加かつ単価上昇(量+単価+)カテゴリーの品目シェアが高い(20%以上)ものは、バス、スイッチ等(電気回路開閉等用)、鉄道部品、コック・弁、自動車部品等である(第Ⅱ-1-1-3-22図)。
第Ⅱ-1-1-3-22図 数量・単価とも増加の品目シェアと伸び(日本の対世界輸出:機械関連セクター)
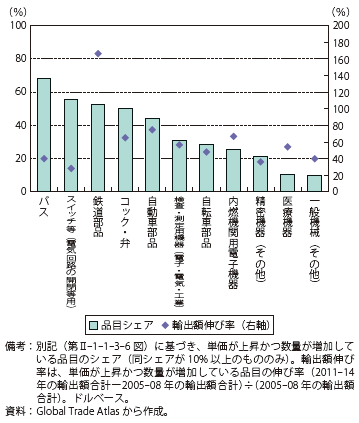
一方、数量減少かつ単価上昇(量▲単価+)だが、その輸出額が伸びている品目を多く含む主要輸出品としては、精密機器等が挙げられる(第Ⅱ-1-1-3-23図)。
第Ⅱ-1-1-3-23図 数量減少・単価上昇の品目シェアと伸び(日本の対世界輸出:機械関連セクター)
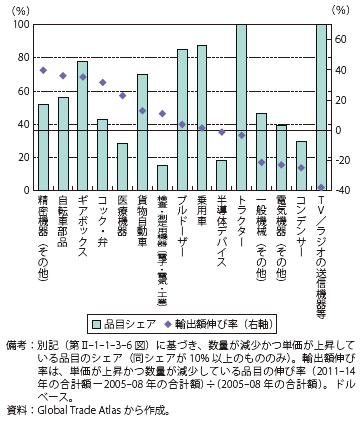
③その他品目群40
次に、既に紹介した素材や機械関連の主要輸出品の内訳となるものや、その他規模が小さいものなどの中でも、興味深いと思われるものを見ていく。例えば、数量・単価がともに増加し、その輸出額の伸びも高い品目を含むものが見られる。スマートフォン等に使用される偏光材料シート、日本企業が高い世界シェアを有する石油樹脂やアクリル重合体、職人の高い技術が生きる刃物類、細かな仕様や使い心地で評価が高いボールペン等の文具類等が該当する。(第Ⅱ-1-1-3-25図)
第Ⅱ-1-1-3-24表 数量・単価動向(日本の対世界輸出:機械関連セクター)
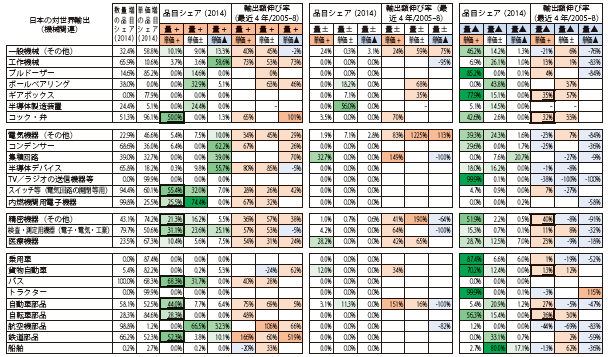
第Ⅱ-1-1-3-25図 数量・単価とも増加の品目シェアと伸び(日本の対世界輸出:その他品目群)
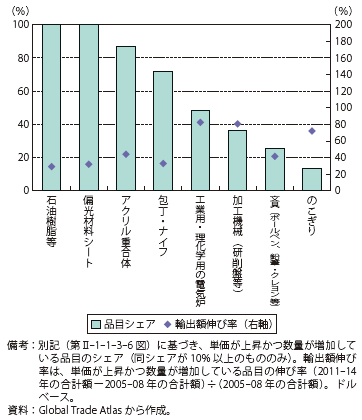
一方、数量が減少していても、単価が上昇することにより輸出額が伸びている品目を多く含むその他品目群も見られる。液晶デバイス等が該当する。(第Ⅱ-1-1-3-26図)
第Ⅱ-1-1-3-26図 数量減少・単価上昇の品目シェアと伸び(日本の対世界輸出:その他品目群)
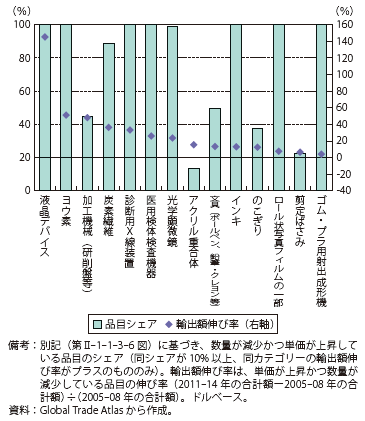
第Ⅱ-1-1-3-27表 数量・単価動向(日本の対世界輸出:その他品目群)
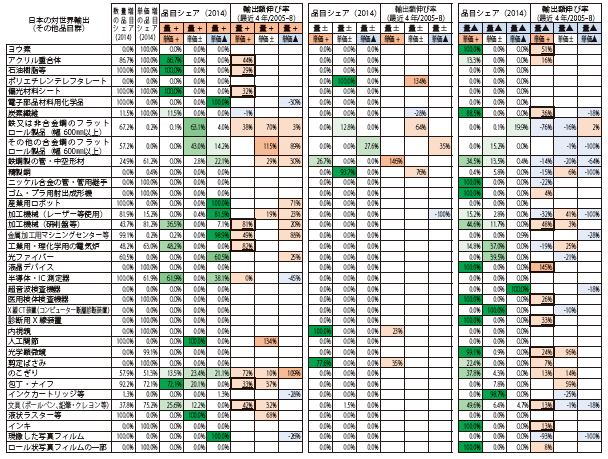
40 本項では、主要輸出品とは別に、規模が小さくても日本の輸出が比較的好調なものや、日本の輸出シェアが大きいもの、また今後伸びが期待できそうなものなどについて、「その他品目群」として分析対象としている(それらのうちの一部は、主要輸出品に包含される場合もある)。なお、こうした「その他品目群」は、それが包含するHS6桁番号の数が少ないものが多く、数量・単価動向のカテゴリー別の品目シェアが、100%や0%等、極端な数値になる場合が多いことに留意。
(4)世界単価との比較
(2)および(3)では、日本からの輸出は、数量の増減に関わらず、単価の上昇によって輸出額が伸びている品目(ゴム・ゴム製品、塗料、鉄道部品、ギアボックス等)が見られること確認できた。しかし、単価の上昇傾向だけでは、世界の平均単価と比べて日本の輸出単価がどの水準にあるのか明らかでない。また、第1章(1)①では、日本の輸出は全体的に高付加価値化の傾向が見られることが確認されている。そこで、以下では、品目ごとに世界単価との比較を行い、世界単価よりも単価が高い輸出額の動向や、輸出割合の変化等から、日本の輸出における高付加価値化の現状を確認する。比較の方法は第Ⅱ-1-1-3-28図のとおりとする。
第Ⅱ-1-1-3-28図 世界単価との比較(計算方法)
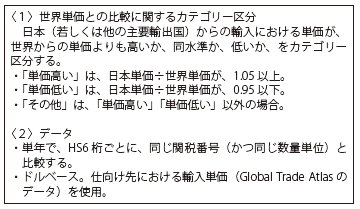
はじめに、輸出額合計で、2005年から2014年までの変化を市場別に確認する。
日本の中国向け及び米国向け輸出においては、合計輸出額は減少していないものの、「単価高い」カテゴリーの品目シェアは低下しており、同割合が高いドイツとの差が開いている(第Ⅱ-1-1-3-29図)。
第Ⅱ-1-1-3-29図 品目構造(対世界単価比別)の各国比較
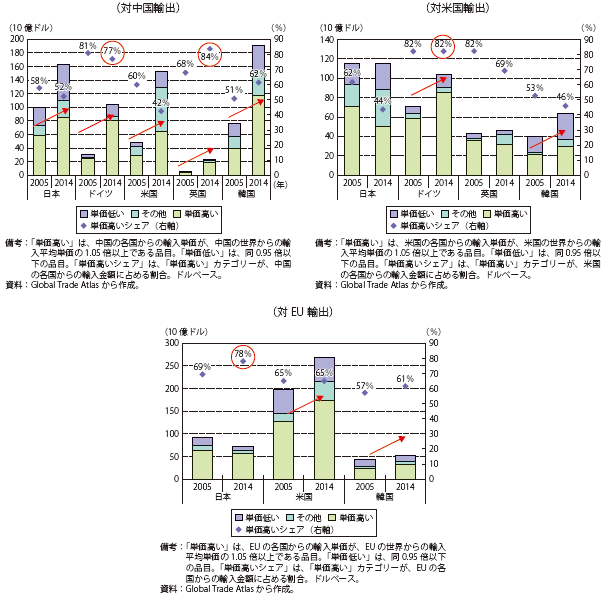
第Ⅱ-1-1-3-30図 (参考)数量×単価分析(対ドイツ・米国比較)の一覧表の見方
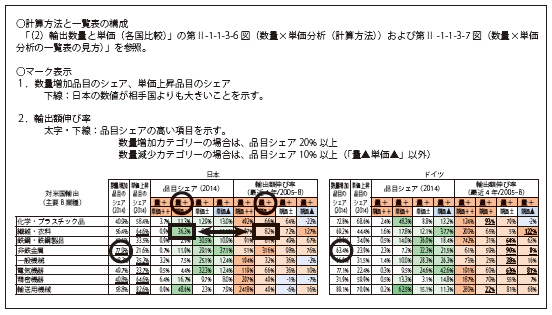
一方、EU向け輸出においては、合計輸出額は減少しているものの、「単価高い」カテゴリーの品目シェアは上昇しており、2014年には78%と、米国および韓国を上回っている。
また、「単価高い」カテゴリーの品目輸出額は、今回確認した主要国の多くで増加しているが、日本の米国向けとEU向け輸出においては減少している。
日本の輸出単価(ドルベース)は、輸出価格の約4割を占める円建て決済部分が名目為替レートの影響を直接受けることもあり、2013年以降の円安方向への動きによって低下している点に留意する必要がある一方、契約通貨建ての輸出物価指数についても、2013年以降、原油などの国際商品価格の下落の影響もあり、品目によっては価格が低下していることなど、輸出者による価格の引き下げが生じている可能性が指摘できる。
次項((5))では、市場別、また品目ごとに、世界単価との比較についても見ていくこととする。
(5)市場別の日本の輸出動向
次に、世界貿易における主な市場である中国向け輸出、米国向け輸出、及びEU向け輸出において、主要輸出国であり、かつ工業品の輸出内容が日本と比較的似ているドイツ、あるいは米国と日本を比較する(中国向け及び米国向けについては、ドイツと、EU向けについては米国と比較する)。合わせて、仕向け先による日本の輸出動向の違いについても見ていくこととする。
比較は、(2)(3)で行った数量と単価動向、および(4)世界単価との比較によって行う。
①中国向け輸出(日本、ドイツ)
日本とドイツの中国向け輸出を、主要8業種で比較する。
まず、双方の数量増加カテゴリーで比較する(第Ⅱ-1-1-3-31表)。ドイツは数量増加の品目シェアがどの業種でも日本を上回っている。また数量と単価を合わせて見ると、数量増加かつ単価上昇(「量+単価+」)カテゴリー割合が高い業種は、ドイツが日本よりも多い。また、ドイツは、日本より数量増加かつ単価低下(「量+単価▲」)カテゴリーの品目シェアが高い業種が多く、また同カテゴリーの輸出額の伸びが全体的に高い。
第Ⅱ-1-1-3-31表 数量・単価動向(対中国輸出、主要8業種、数量増加カテゴリー)
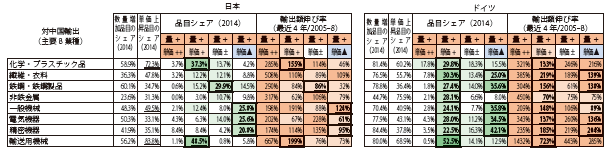
次に、数量減少カテゴリーを見てみよう(第Ⅱ-1-1-3-32表)。日本の数量減少カテゴリーの品目シェアは、主要8業種の全ての業種でドイツよりも大きい。しかし、数量と単価を合わせて見ると、数量減少かつ単価上昇(「数量▲単価+」)、数量減少かつ単価大幅上昇(「数量▲単価++」)の両カテゴリーにおいて、精密機器や一般機械等で、輸出額の伸び率がプラスとなっている。
第Ⅱ-1-1-3-32表 数量・単価動向(対中国輸出、主要8業種、数量減少カテゴリー)
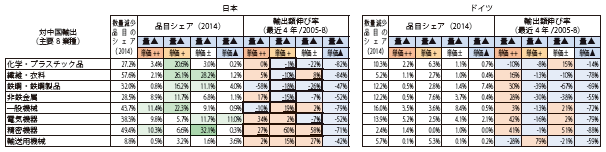
さらに世界単価と比較すると、世界単価よりも日本からの輸出単価が高い(「単価高い」)カテゴリーの輸出額は、鉄鋼・鉄鋼製品がやや減少している他は、増加、若しくは変動していないかのいずれかである。なお、主に「単価低い」あるいは「その他」のカテゴリーの輸出額が大きく増加している業種もある(鉄鋼・鉄鋼製品、非鉄金属、一般機械)(第Ⅱ-1-1-3-33図、第Ⅱ-1-1-3-34表)。
第Ⅱ-1-1-3-33図 日本の対中輸出の品目構造(対世界単価比別)
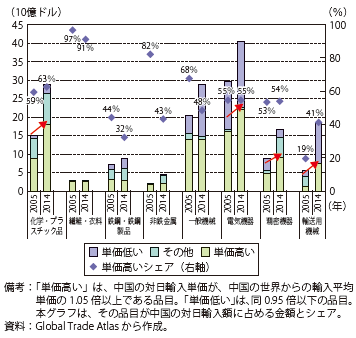
第Ⅱ-1-1-3-34表 対世界単価比別カテゴリーの動向一覧(日本の対中輸出)
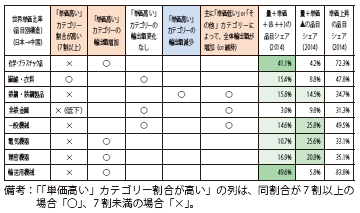
〈対中輸出:参考1〉セクター別主要輸出品等~数量・単価比較(日本、ドイツ)
素材関連セクター
素材関連セクターの主要輸出品について、数量増加(「量+」)カテゴリーの品目を見ると、日本は多くが単価上昇カテゴリー(「量+単価+」若しくは「量+単価++」)にある(第Ⅱ-1-1-3-35表)。一方ドイツは、単価上昇カテゴリー(「量+単価+」若しくは「量+単価++」)に加えて、単価が低下している(「量+単価▲」)カテゴリーの品目シェアが高い主要輸出品が多い。
第Ⅱ-1-1-3-35表 数量・単価動向(対中国輸出、素材関連)
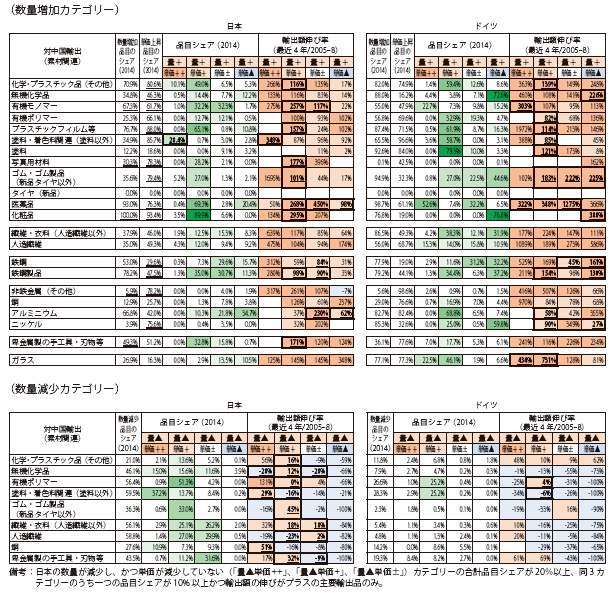
数量増加(「量+」)カテゴリーについて両国の輸出額の伸びを比較すると、一部で、日本がドイツを上回る主要輸出品もみられる(プラスチックフィルム等、塗料・着色料関連(塗料以外)、アルミニウム等)41。
一方、数量減少かつ単価上昇(「量▲単価+」)カテゴリーの品目の輸出額が伸びている主要輸出品も見られる(日本:銅、ゴム・ゴム製品、塗料・着色料関連(塗料以外)等)。
〈機械関連セクター〉
機械関連セクターを主要輸出品別にみると、日本の数量増加カテゴリー(「量+」)の品目シェアは、そのうちの単価減少(「量+単価▲」)カテゴリーの品目シェアが高い主要輸出品が、素材関連セクターよりも多い(第Ⅱ-1-1-3-36表)。一方、数量増加かつ単価が大幅に上昇(「量+単価++」)している品目を多く含む主要輸出品も一部にみられる(検査・測定用機器(電子・電気・工業)、自転車部品、鉄道部品)。
第Ⅱ-1-1-3-36表 数量・単価動向(対中国輸出、機械関連)
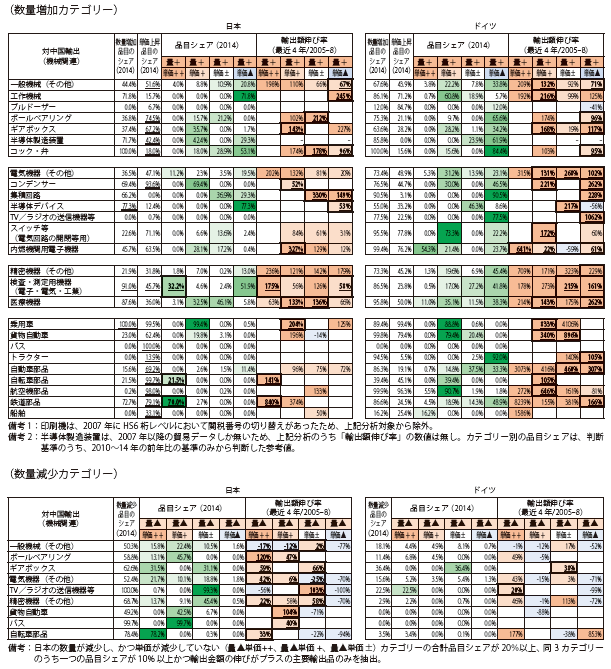
ドイツの「量+」カテゴリーは、日本と同様に「量+単価+」若しくは「量+単価++」)」、と「量+単価▲」に広がっている。「量+」カテゴリーにおいて両国の輸出額の伸びを比較すると、一部で、日本がドイツを上回る主要輸出品もみられる(工作機械、ボールベアリング、コック・弁、自転車部品、鉄道部品)。
また、数量減少かつ単価上昇(「量▲単価+」若しくは「量▲単価++」)カテゴリーの品目の輸出額が伸びている主要輸出品も見られる(ボールベアリング、貨物自動車等)。
〈その他品目群42〉
また、既に紹介した素材や機械関連の主要輸出品の内訳となるものや、その他規模が小さいものなどの中でも、興味深いと思われるものを見ていくと、例えば、数量が増加している(「量+」)カテゴリーの品目シェアが高いものが多い(第Ⅱ-1-1-3-37表)。単価動向のカテゴリーでは特に偏りがみられず、単価減少かつ数量増加(「量+単価▲」)カテゴリーの品目が輸出額を伸ばしているその他品目群も見られる(電子部品材料用化学品、産業用ロボット、金属加工用マシニングセンター等、医用検体検査機器)。
第Ⅱ-1-1-3-37表 数量・単価動向(対中国輸出、その他品目群)
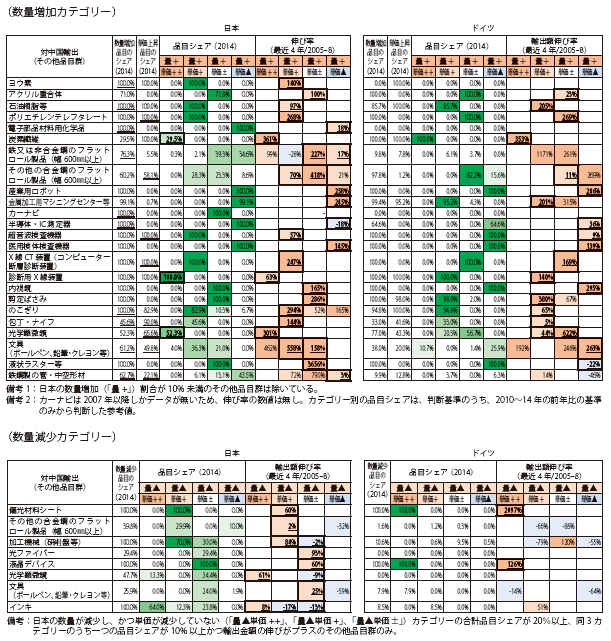
一方、数量が減少していても単価の上昇により輸出額が伸びている品目を含むその他品目群も見られる(偏光材料シート、加工機械(研削盤等)等)。
41 数量・単価動向の数量増加カテゴリーのうち、日本とドイツの品目シェアが20%以上のカテゴリーの輸出額の伸び率を比較したもの。
42 その他品目群については、本項Ⅱ-1-1-3(3)③の脚注を参照。
〈対中輸出:参考2〉セクター別主要輸出品等~対世界単価比較
世界単価と比較すると、日本の輸出単価が世界単価よりも高い(「単価高い」)カテゴリーの輸出額が増加している主要輸出品(及びその他品目群)が多い(プラスチックフィルム等、精密機器、コック・弁、スイッチ等(電気回路の開閉等用)、検査・測定用機器(電気・電子・工業)、自動車部品、ポリエチレンテレフタレート、内視鏡等)(第Ⅱ-1-1-3-38図)。
第Ⅱ-1-1-3-38図 日本の対中輸出の品目構造(対世界単価比別:主要輸出品等)
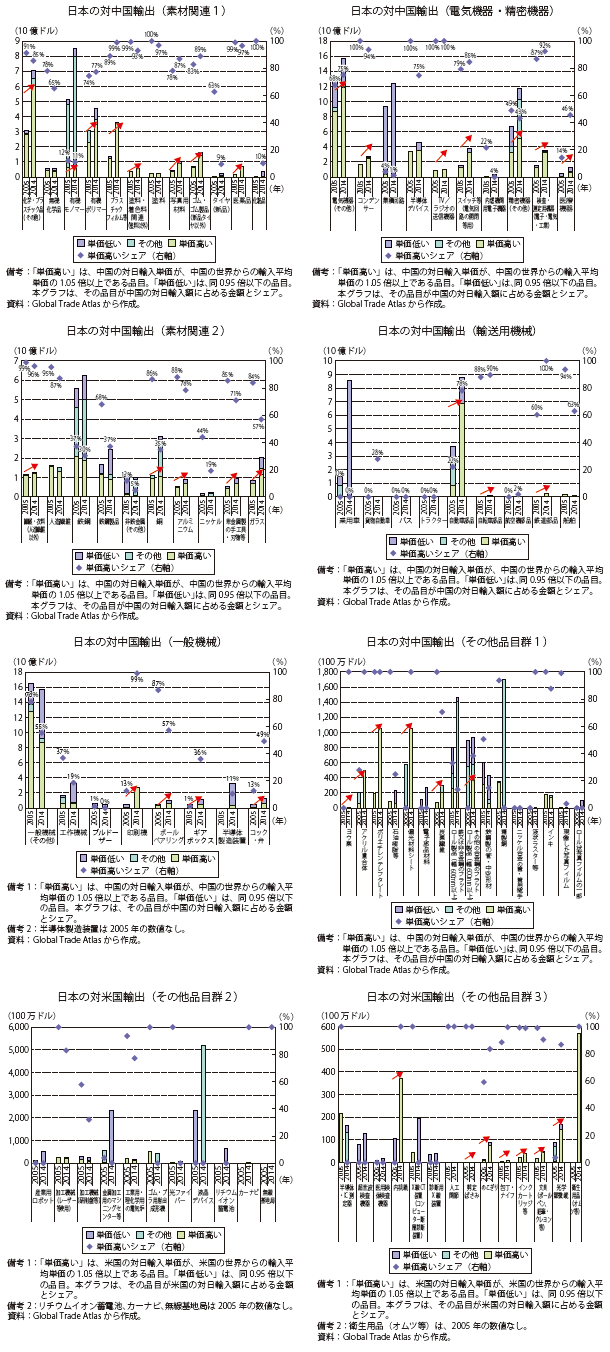
- Excel形式のファイル(日本の対中国輸出(素材関連1))はこちら

- Excel形式のファイル(日本の対中国輸出(電気機器・精密機器))はこちら

- Excel形式のファイル(日本の対中国輸出(素材関連2)はこちら

- Excel形式のファイル(日本の対中国輸出(輸送用機械))はこちら

- Excel形式のファイル(日本の対中国輸出(一般機械))はこちら

- Excel形式のファイル(日本の対中国輸出(その他品目群1))はこちら

- Excel形式のファイル(日本の対米国輸出(その他品目群2))はこちら

- Excel形式のファイル(日本の対米国輸出(その他品目群3))はこちら

一方、「単価高い」カテゴリーの輸出額が増加していない主要輸出品(及びその他品目群)のうち、一部は、主に日本の輸出単価が世界単価よりも低い(「単価低い」)、若しくは世界単価と同水準(「その他」)カテゴリーの輸出額の増加によって、全体の輸出額が増加している(有機モノマー、鉄鋼、集積回路、金属加工用マシニングセンター等、鉄または合金のフラットロール製品(幅600mm以上)等)。
なお、世界単価より「高い」カテゴリーの品目の輸出額が増加している主要輸出品(及びその他品目群)を見ると、〈対中輸出:参考1〉で確認した数量・単価比較において、数量が増加かつ単価が上昇(「量+単価+」若しくは「量+単価++」)しているカテゴリーの品目シェアが高いものが多い(プラスチックフィルム等、医薬品、コンデンサー、鉄道部品等)(第Ⅱ-1-1-3-39表)。価格競争によらない形で輸出額が増加している可能性が示唆される。
第Ⅱ-1-1-3-39表 世界単価より「高い」カテゴリーの輸出額が増加している主要輸出品等(対中国輸出)
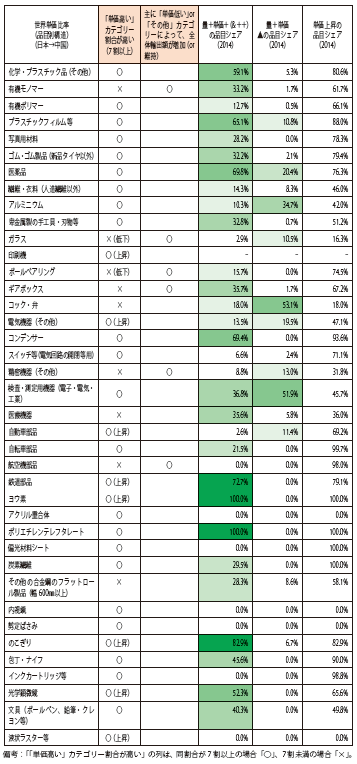
一方、世界単価より「低い」若しくは同水準(「その他」)のカテゴリーによって全体の輸出額が増加している主要輸出品(及びその他品目群)も多い(第Ⅱ-1-1-3-40表)。それらの多くは、数量が増加かつ単価が低下(「量+単価▲」)しているカテゴリーの品目シェアが高い。
第Ⅱ-1-1-3-40表 世界単価より「低い」「同水準」のカテゴリーにより、全体の輸出額が増加している主要輸出品等(対中国輸出)
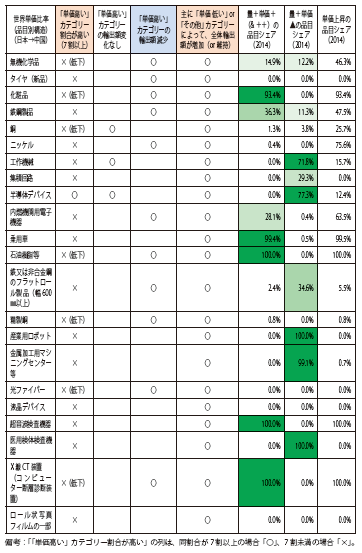
ただし、世界単価より「低い」若しくは同水準(「その他」)のカテゴリーによって全体の輸出額が増加している主要輸出品(及びその他品目群)のうちの一部には、単価上昇の品目シェアが高いもの(化粧品、乗用車等)も見られる。単価が上昇傾向にあるにも関わらず、世界単価より「高い」カテゴリーではなく、「低い」若しくは同水準(「その他」)のカテゴリーが増加している要因としては、他国からの単価が高い製品の輸入増加などが影響し、日本の単価が相対的に低下している可能性が考えられる。
②米国向け輸出(日本、ドイツ)
次に、日本とドイツの米国向け輸出を、主要8業種で比較する。
まず、双方の数量増加カテゴリーで比較する(第Ⅱ-1-1-3-41表)。数量増加の品目シェアは、多くの業種でドイツが日本を上回っているが、非鉄金属と精密機器では日本がドイツを上回っている。
第Ⅱ-1-1-3-41表 数量・単価動向(対米国輸出、主要8業種、数量増加カテゴリー)
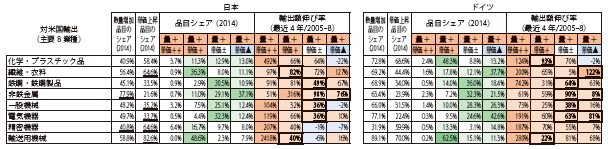
また、数量と単価の動向を合わせて見ると、数量増加かつ単価上昇(「量+単価+」)カテゴリーの品目シェアは、両国とも輸送用機械において高い。また、ドイツは化学・プラスチック品、日本は繊維・衣料において高い。
また、ドイツは、日本よりも数量増加かつ単価低下(「量+単価▲」)カテゴリーの品目シェアが高い業種が多いが、化学・プラスチック品を除いて、同カテゴリーの輸出額が伸びている。
数量減少の品目シェアは、主要8業種では、非鉄金属を除く全ての業種で日本がドイツよりも大きい(第Ⅱ-1-1-3-42表)。また、数量減少かつ単価上昇(「量▲単価++」若しくは「量▲単価++」)カテゴリーでは、日本は、鉄鋼・鉄鋼製品や精密機器の一部において、輸出額の伸び率がプラスとなっている。特に精密機器では、単価が大幅に上昇している(「量▲単価++」)カテゴリーの品目シェアが高く、同カテゴリーの輸出額の伸び率も高い。
第Ⅱ-1-1-3-42表 数量・単価動向(対米国輸出、主要8業種、数量減少カテゴリー)
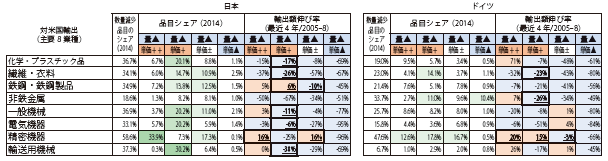
次に、世界単価と比較すると、日本からの輸出単価が世界単価よりも高い(「単価高い」)カテゴリーの輸出額が増加している業種は、鉄鋼・鉄鋼製品、および非鉄金属にとどまる(第Ⅱ-1-1-3-43図、第Ⅱ-1-1-3-44表)。一方、「単価高い」カテゴリーではなく、世界単価よりも低い(「単価低い」)若しくは同水準(「その他」)のカテゴリーによって、全体の輸出額を増加若しくは維持している業種もある(一般機械、輸送用機械)。
第Ⅱ-1-1-3-43図 日本の対米輸出の品目構造(対世界単価比別)
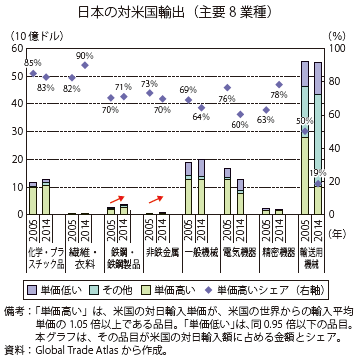
第Ⅱ-1-1-3-44表 対世界単価比別カテゴリーの動向一覧(日本の対米輸出)
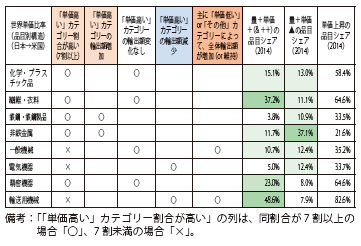
〈対米輸出:参考1〉セクター別主要輸出品等~数量・単価比較(日本、ドイツ)
素材関連セクター
素材関連セクターの主要輸出品について、数量増加カテゴリーを見ると、日本の単価動向に偏りはみられない(第Ⅱ-1-1-3-45表)。一方ドイツは、特に化学品関連において、単価上昇(「量+単価+」)カテゴリーの品目シェアが大きい主要輸出品が多い。
第Ⅱ-1-1-3-45表 数量・単価動向(対米国輸出、素材関連)
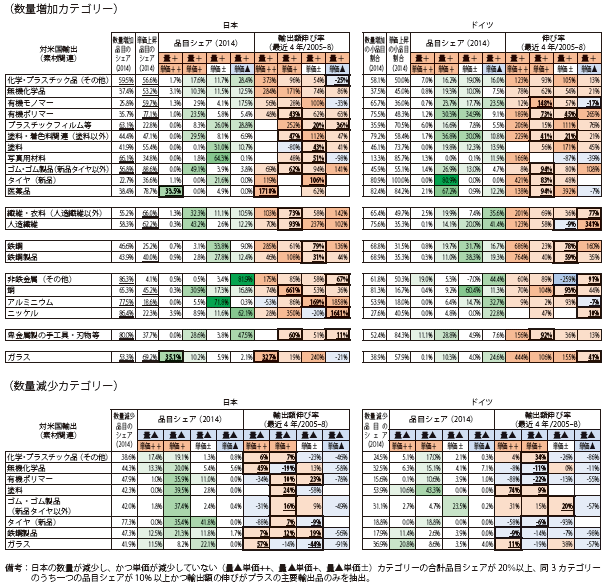
数量増加分について、主な単価動向カテゴリーで両国の輸出額の伸びを比較すると、化学品関連ではドイツが日本を上回る主要輸出品が多いが、日本がドイツを上回っている主要輸出品も見られる(塗料・着色料関連(塗料以外)、タイヤ(新品)、医薬品、鉄鋼、銅、アルミニウム、ニッケル、ガラス)43。中でも医薬品とガラスは、単価が大幅に上昇している(「量+単価++」)カテゴリーの品目シェアが高く、同カテゴリーの品目の輸出額の伸びが大きい。
一方、数量が減少していても単価の上昇(「量▲単価+」若しくは「量▲単価++」)により輸出額が伸びている品目を多く含む主要輸出品も見られる(塗料等)。
43 数量・単価動向の数量増加カテゴリーのうち、日本とドイツの品目シェアが20%以上のカテゴリーの輸出額の伸び率を比較したもの。
機械関連セクター
機械関連セクターの主要輸出品について、数量増加カテゴリーを見ると、一般機械と電気機器では、日本は「量+単価±」(単価動向が「上昇」「低下」以外)であるカテゴリーの品目シェアが高いものが多い(第Ⅱ-1-1-3-46表)。ドイツは、「量+単価±」だけでなく、「量+単価▲」(単価減少)カテゴリーの品目シェアが大きい主要輸出品も多い。
第Ⅱ-1-1-3-46表 数量・単価動向(対米国輸出、機械関連)
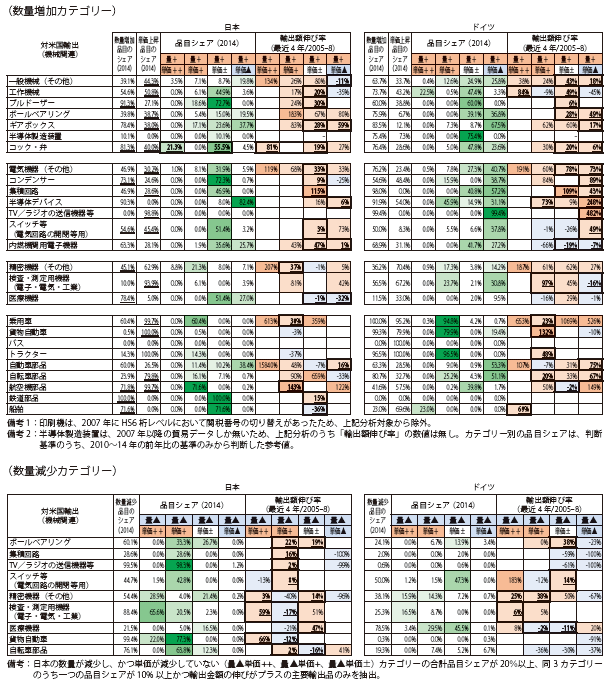
自動車関連(乗用車、貨物自動車、トラクター、自動車部品)では、両国の単価動向にあまり違いは見られない(なお、貨物自動車とトラクターは、両国の数量動向の違いが顕著である(ドイツは増加、日本は減少))。
数量増加分について、主な単価動向カテゴリーで両国の品目輸出額の伸びを比較すると、日本がドイツを上回っている主要輸出品も見られる(ブルドーザー、ギアボックス、コック・弁、集積回路、内燃機関用電子機器、乗用車、航空機部品)44。中でもコック・弁は、単価が大幅に上昇(「量+単価++」)しているカテゴリーの品目シェアが大きく、同カテゴリーの品目の輸出額の伸びも大きい。
一方、数量が減少していても単価の上昇により輸出額が伸びている品目の割合が大きい主要輸出品も見られる(日本:検査・測定用機器(電子・電気・工業)、貨物自動車等)。
44 数量・単価動向の数量増加カテゴリーのうち、日本とドイツの品目シェアが20%以上のカテゴリーの輸出額の伸び率を比較したもの。
その他品目群 45
また、既に紹介した素材や機械関連の主要輸出品の内訳となるものや、その他規模が小さいものなどの中でも、興味深いと思われるものを見ていくと、例えば、数量増加カテゴリーを見ると、日本は「量+単価±」(上昇でも低下でもない)と「量+単価▲」(単価減少)が多い(第Ⅱ-1-1-3-47表)。「量+単価▲」では、同カテゴリーの品目の輸出額が減少しているものと増加しているものが見られるが、後者としては、偏光材料シート、炭素繊維、医用検体検査機器、包丁・ナイフが挙げられる。
第Ⅱ-1-1-3-47表 数量・単価動向(対米国輸出、その他品目群)
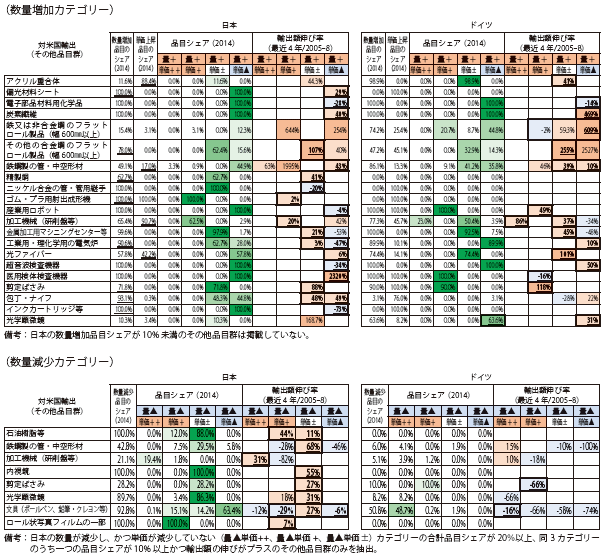
一方、数量が減少していても単価の上昇により輸出額が伸びている品目シェアが大きいその他品目群も見られる(加工機械(研削盤等))。
ドイツは、単価動向のカテゴリーに特に偏りは見られないが、「量+単価+」カテゴリーの品目シェアが大きいその他品目群が日本よりやや多い。
45 その他品目群については、本項Ⅱ-1-1-3(3)③の脚注を参照。
〈対米輸出:参考2〉セクター別主要輸出品等~対世界単価比較
世界単価と比較すると、日本の輸出単価が世界単価よりも高い(「単価高い」)カテゴリーの品目輸出額が増加している主要輸出品(及びその他品目群)が、素材関連セクターを中心に見られる(ゴム・ゴム製品(新品タイヤ以外)、鉄鋼製品、集積回路、航空機部品、金属加工用マシニングセンター等、アクリル重合体等)(第Ⅱ-1-1-3-48図)。
第Ⅱ-1-1-3-48図 日本の対米輸出の品目構造(対世界単価比別:主要輸出品等)
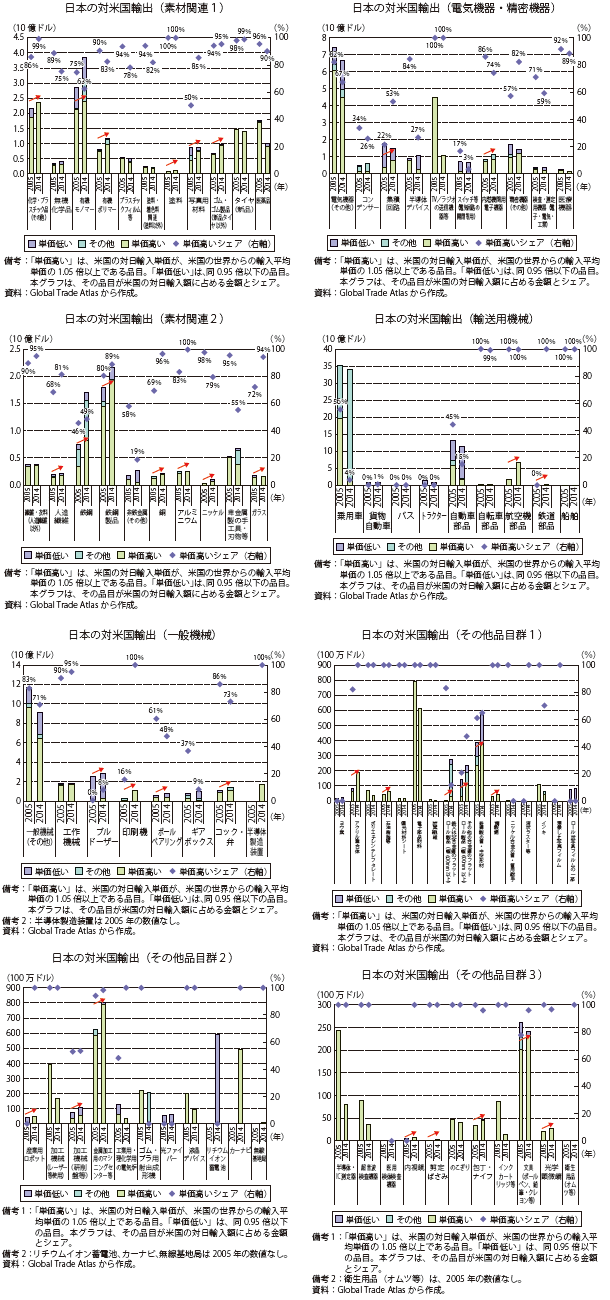
- Excel形式のファイル(日本の対米国輸出(素材関連1))はこちら

- Excel形式のファイル(日本の対米国輸出(電気機器・精密機器))はこちら

- Excel形式のファイル(日本の対米国輸出(素材関連2))はこちら

- Excel形式のファイル(日本の対米国輸出(輸送用機械))はこちら

- Excel形式のファイル(日本の対米国輸出(一般機械))はこちら

- Excel形式のファイル(日本の対米国輸出(その他品目群1))はこちら

- Excel形式のファイル(日本の対米国輸出(その他品目群2))はこちら

- Excel形式のファイル(日本の対米国輸出(その他品目群3))はこちら

一方、「単価高い」カテゴリーの品目の輸出額は増加せず、日本の輸出単価が世界単価よりも低い(「単価低い」)もしくは世界単価と同水準(「その他」)のカテゴリーの品目輸出額の増加によって、全体の輸出額が増加(若しくは維持)している主要輸出品(及びその他品目群)も見られる(非鉄金属(その他)、半導体デバイス、ギアボックス、乗用車等46)。
世界単価より「高い」カテゴリーの品目の輸出額が増加している主要輸出品(及びその他品目群)のうち、一部は、〈対米輸出:参考1〉で確認した数量・単価比較において、数量増加かつ単価上昇(「量+単価+(若しくは「量+単価++」)」)の品目シェアが高い(ゴム・ゴム製品、人造繊維、ガラス、航空機部品等)。価格競争によらない形で輸出額が増加している可能性が示唆される(第Ⅱ-1-1-3-49表)。
第Ⅱ-1-1-3-49表 世界単価より「高い」カテゴリーの輸出額が増加している主要輸出品等(対米国輸出)
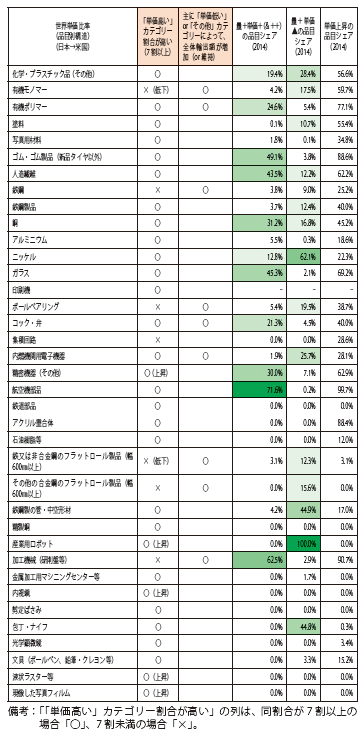
一方、世界単価より「低い」若しくは同水準(「その他」)のカテゴリーの品目の輸出額の増加によって全体の輸出額が増加している主要輸出品(及びその他品目群)も、各セクターに見られる(第Ⅱ-1-1-3-50表)。なお、これらのうちゴム・プラスチック用射出成型機と乗用車は、単価上昇の品目シェアが高く、また単価が世界単価と同水準である(「その他」)品目の輸出額が増加している。単価が上昇傾向にあるにも関わらず、世界単価より「高い」カテゴリーではなく、「低い」若しくは同水準(「その他」)のカテゴリーが増加している要因としては、他国からの単価が高い製品の輸入増加や円安方向への推移が影響して、日本の輸出単価が相対的に低下した可能性が考えられる。
第Ⅱ-1-1-3-50表 世界単価より「低い」「同水準」のカテゴリーにより全体の輸出額が増加している主要輸出品等(対米国輸出)
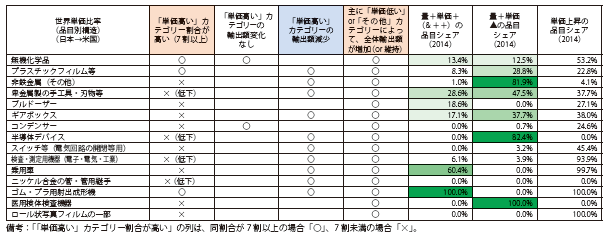
46 乗用車は、特に2014年に「その他」カテゴリー割合が上昇していることから、円安方向への動きの影響が生じている可能性がある。加えて、HS6桁ごとの比較を行っていることが影響している可能性にも留意が必要(乗用車は、関税分類が他の業種よりも細分化されているため、他の多くの主要輸出品と異なり、全体に占める高付加価値品の比重の増加は、関税番号の異なる品目の増加となる場合がある。高付加価値品における世界単価との比較では、日本は「単価高い」ではなく「その他」カテゴリーに区分される場合があり、結果として、「単価高い」割合の低下となる。なお、乗用車のうち主なHS6桁品目の輸出単価は、ほぼ世界単価と一致して推移し、HS4桁では、世界単価と比較して上昇傾向となっている)。
③EU向け輸出(日本、米国)
次に、日本と米国のEU向け輸出を、主要8業種で比較する。
まず、双方の数量増加カテゴリーで比較する(第Ⅱ-1-1-3-51表)。米国は数量増加の品目シェアが、多くの業種で日本を上回っている。特に、化学・プラスチック品、鉄鋼・鉄鋼製品、非鉄金属、輸送用機械では、米国が日本を大きく上回っていることがわかる。一方、精密機器では日本が米国を上回っている。
第Ⅱ-1-1-3-51表 数量・単価動向(対EU輸出、主要8業種、数量増加カテゴリー)
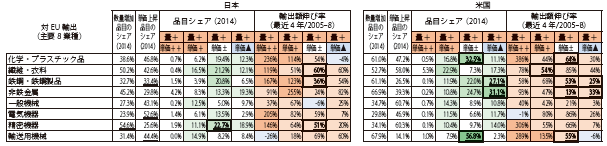
次に、数量と単価を合わせて見ると、数量増加かつ単価上昇(「量+単価+」若しくは「量+単価++」)カテゴリーの品目シェアは、両国とも高くない(同カテゴリーの品目シェアが最も高い業種は、両国ともに繊維・衣料であるが、日本は約17%、米国が約28%にとどまる)。一方、数量増加かつ単価減少(「量+単価▲」)カテゴリーの品目シェアは、非鉄金属と一般機械において、米国が30%前後と比較的高い。
数量減少カテゴリーの品目シェアは、主要8業種では、精密機器を除き日本が米国よりも高い(第Ⅱ-1-1-3-52表)。また、数量減少かつ単価上昇(「量▲単価++」若しくは「量▲単価++」)カテゴリーの品目では、ほとんどの業種で日本の輸出額の伸びがマイナスとなっている。
第Ⅱ-1-1-3-52表 数量・単価動向(対EU輸出、主要8業種、数量減少カテゴリー)
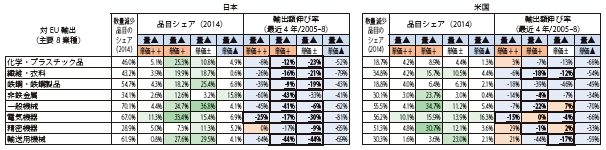
次に世界単価と比較すると、日本からの輸出単価が高い(「単価高い」)カテゴリーの品目の輸出額については、増加している業種(化学・プラスチック品、鉄鋼・鉄鋼製品、非鉄金属、一般機械)と、減少している業種(電気機器、精密機器、輸送用機械)がある(第Ⅱ-1-1-3-53図、第Ⅱ-1-1-3-54表)。なお、一般機械においては、日本からの輸出単価が低い(「単価低い」)品目の輸出額が減少する一方で、「単価高い」品目の輸出額が増加している。
第Ⅱ-1-1-3-53図 日本の対EU輸出の品目構造(対世界単価比別)
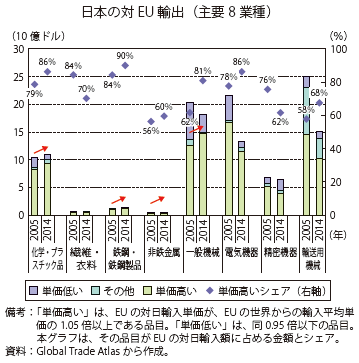
第Ⅱ-1-1-3-54表 対世界単価比別カテゴリーの動向一覧(日本の対EU輸出)
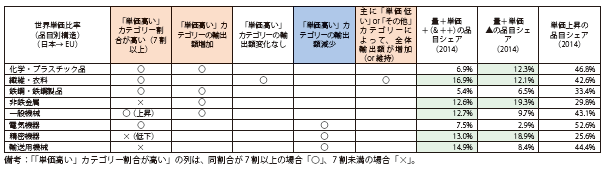
なお、第Ⅱ-1-1-3-55図を見ると、米国は、一般機械を除き、全ての業種で「単価高い」カテゴリーの品目の輸出額が増加している。
第Ⅱ-1-1-3-55図 米国の対EU輸出の品目構造(対世界単価比別)
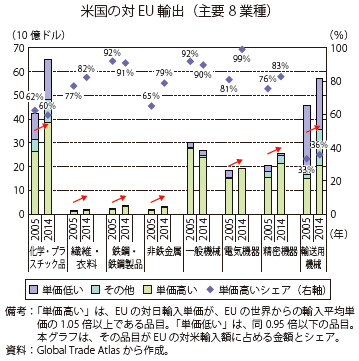
〈対EU輸出:参考1〉セクター別主要輸出品等~数量・単価比較(日本、米国)
素材関連セクター
素材関連セクターの主要輸出品について、数量増加カテゴリーを見ると、日本は、単価上昇カテゴリー(「量+単価+」若しくは「量+単価++」)の品目シェアが高いものが少ないが、一部に単価が大幅に上昇(「量+単価++」)している品目シェアが高い主要輸出品も見られる(塗料、非鉄金属)(第Ⅱ-1-1-3-56表)。なお、米国は、数量増加かつ単価上昇(量+単価+)の品目シェアが大きい主要輸出品が、日本よりも多い。
第Ⅱ-1-1-3-56表 数量・単価動向(対EU輸出、素材関連)
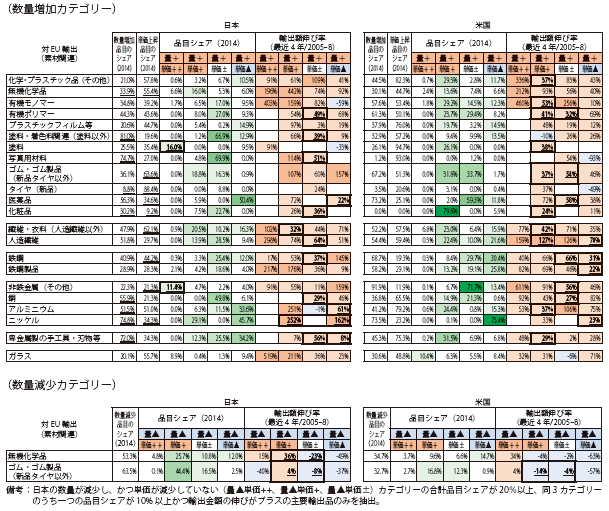
数量増加分について、両国の品目輸出額の伸びを比較すると、日本が米国を上回る品目も見られる(有機ポリマー、化粧品、銅、アルミニウム、ニッケル等)47。特にニッケルは、「量+単価+」と「量+単価▲」の両カテゴリーで、輸出額の伸びが大きい。
一方、数量が減少していても単価の上昇(「量▲単価+」)により輸出額を伸ばしている品目を多く含む主要輸出品も見られる(日本:無機化学品等)。
47 数量・単価動向の数量増加カテゴリーのうち、日本と米国の品目シェアが20%以上のカテゴリーの輸出額の伸び率を比較したもの。
機械関連セクター
機械関連セクターの主要輸出品について、数量増加カテゴリーを見ると、日本、米国ともに、一部を除き数量増加の品目シェアが低く、「量+単価+」カテゴリーと「量+単価▲」カテゴリーに広がっている(第Ⅱ-1-1-3-57表)。
第Ⅱ-1-1-3-57表 数量・単価動向(対EU輸出、機械関連)
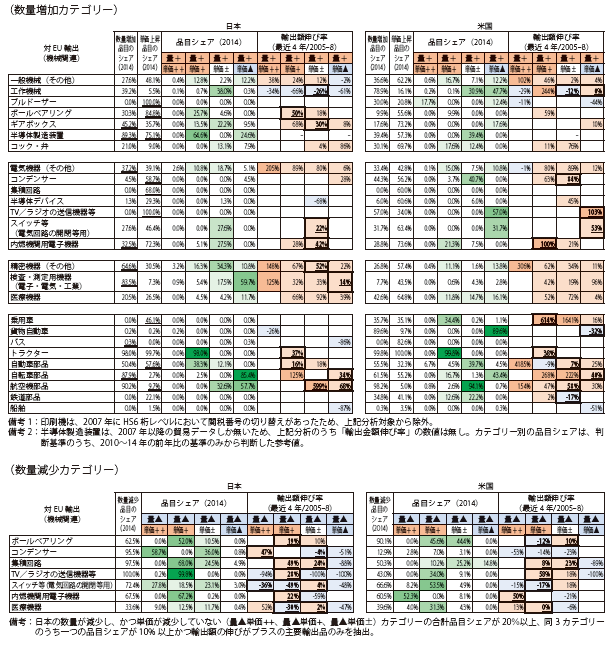
数量増加カテゴリーについて、両国の品目の輸出額の伸びを比較すると、日本が米国を上回っているものも一部見られる(自動車部品、航空機部品)。
一方で、数量が減少していても単価の上昇によって輸出額を伸ばしている品目を多く含む主要輸出品も見られる(日本:コンデンサー、集積回路、TV/ラジオの送信機器等、内燃機関用電子機器、ボールベアリング等)。
その他品目群 48
また、既に紹介した素材や機械関連の主要輸出品の内訳となるものや、その他規模が小さいものなどの中でも、興味深いと思われるものを見ていく。例えば、数量増加カテゴリーを見ると、日本は、単価減少(「量+単価▲」)カテゴリーの品目シェアが高いものが多いが、一部に「量+単価+」カテゴリーの品目を多く含むものもある(産業用ロボット、診断用X線装置、文具(ボールペン、鉛筆・クレヨン等))(第Ⅱ-1-1-3-58表)。
第Ⅱ-1-1-3-58表 数量・単価動向(対EU輸出、その他品目群)
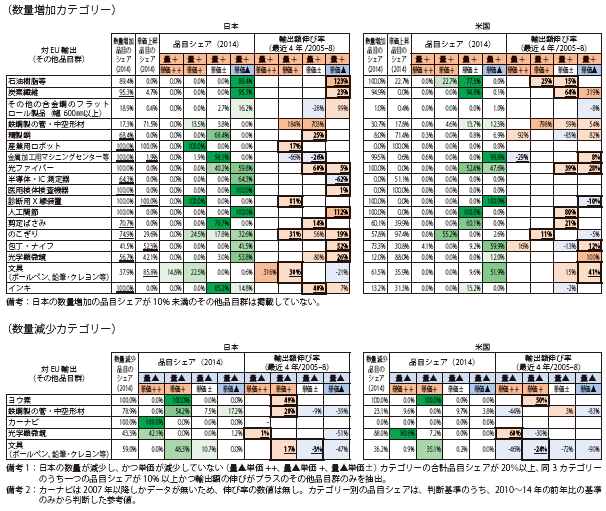
数量増加分について単価動向カテゴリー別に両国の輸出金額の伸びを比較すると、日本が米国を上回っているものも見られる(石油樹脂、人工関節、のこぎり、包丁・ナイフ等)。
一方、数量が減少していても単価の上昇によって輸出額を伸ばしている品目を多く含むその他品目群も見られる(ヨウ素、文具(ボールペン、鉛筆・クレヨン等)等)。
48 その他品目群については、本項Ⅱ-1-1-3(3)③の脚注を参照。
〈対EU輸出:参考2〉セクター別主要輸出品等~対世界単価比較
世界単価と比較すると、日本の輸出単価が世界単価よりも高い(「単価高い」)カテゴリーの品目輸出額が増加している主要輸出品(及びその他品目群)が、一部に見られる(有機ポリマー、鉄鋼、工作機械、集積回路、航空機部品、光ファイバー、内視鏡等)(第Ⅱ-1-1-3-59図)。
第Ⅱ-1-1-3-59図 日本の対EU輸出の品目構造(対世界単価比別:主要輸出品等)
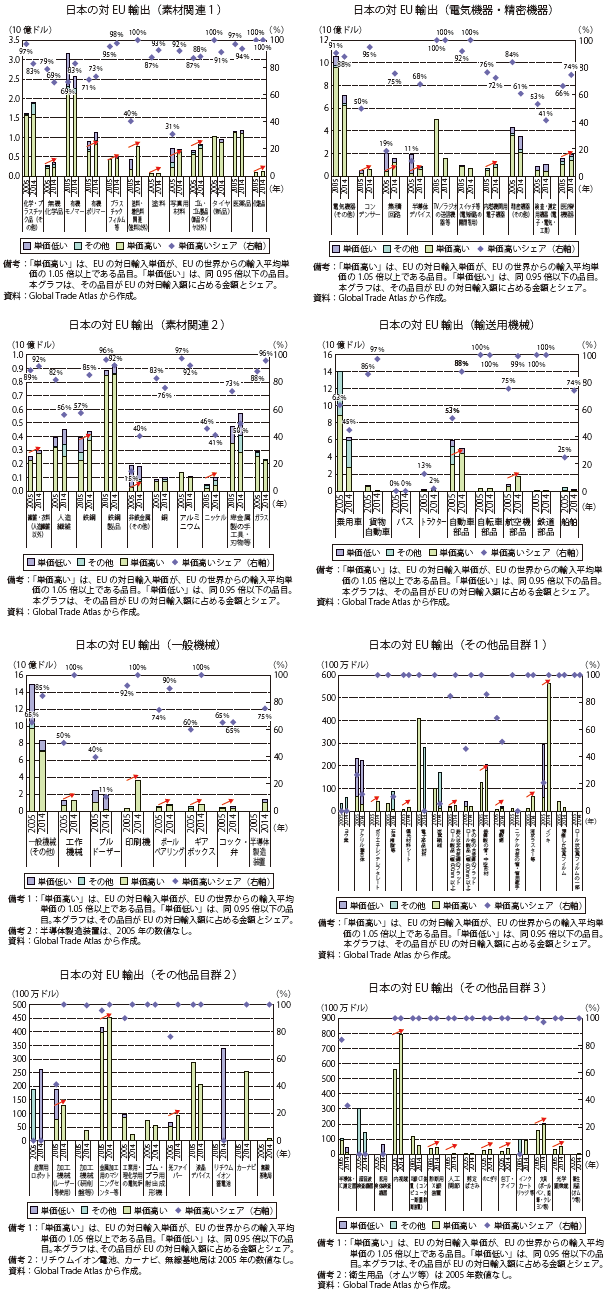
- Excel形式のファイル(日本の対EU 輸出(素材関連1))はこちら

- Excel形式のファイル(日本の対EU 輸出(電気機器・精密機器))はこちら

- Excel形式のファイル(日本の対EU 輸出(素材関連2))はこちら

- Excel形式のファイル(日本の対EU 輸出(輸送用機械))はこちら

- Excel形式のファイル(日本の対EU 輸出(一般機械))はこちら

- Excel形式のファイル(日本の対EU 輸出(その他品目群1))はこちら

- Excel形式のファイル(日本の対EU 輸出(その他品目群2))はこちら

- Excel形式のファイル(日本の対EU 輸出(その他品目群3))はこちら

一方、「単価高い」カテゴリーの品目輸出額が増加していない主要輸出品(及びその他品目群)のうち、主に日本の輸出単価が世界単価よりも低い(「単価低い」)もしくは世界単価と同水準(「その他」)カテゴリーの増加によって、全体の輸出額が増加(若しくは維持)しているものも、少ないながら見られる(人造繊維、卑金属製の手工具・刃物等、産業用ロボット、医用検体検査機器等)。
なお、世界単価より「高い」カテゴリーの輸出額が増加している主要輸出品(及びその他品目群)のうち、数量・単価比較における数量増加かつ単価上昇(「量+単価+(若しくは「量+単価++」)」)カテゴリーの品目シェアが高いものとして、自動車部品、ボールベアリング、診断用X線装置、文具(ボールペン、鉛筆・クレヨン等)等が挙げられる(第Ⅱ-1-1-3-60表)。欧州の内需が伸び悩む一方で、価格競争によらないビジネスが行われていることが示唆される。
第Ⅱ-1-1-3-60表 世界単価より「高い」カテゴリーの輸出額が増加している主要輸出品等(対EU輸出)
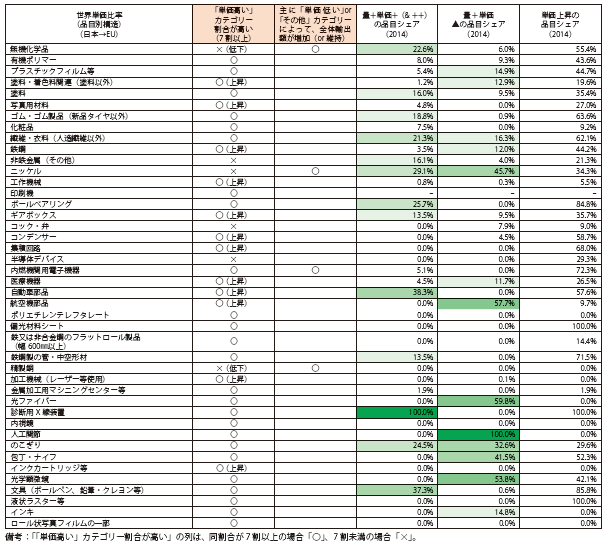
一方、世界単価より「低い」若しくは「同水準」のカテゴリーによって全体の輸出額が増加している主要輸出品(及びその他品目群)も見られる(第Ⅱ-1-1-3-61表)。なお、これらのうち、産業用ロボット等は、単価上昇の品目シェアが高く、また単価が世界単価より低いカテゴリーの輸出額が増加している。単価が上昇傾向にあるにも関わらず、世界単価より「高い」カテゴリーではなく、「低い」若しくは同水準(「その他」)のカテゴリーが増加している要因としては、他国からの単価が高い輸入品の増加や円安方向への動きが影響し、相対的に日本の輸出単価が低下した可能性が考えられる。
第Ⅱ-1-1-3-61表 世界単価より「低い」「同水準」のカテゴリーにより全体の輸出額が増加している主要輸出品等(対EU輸出)
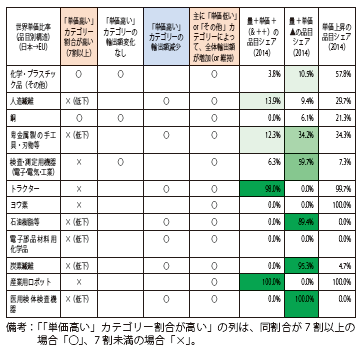
④市場別の日本の輸出動向(まとめ)
日本は、主要3市場(米国、EU、中国)において、数量が増加している品目シェアが、ドイツ及び米国を下回る主要輸出品が多い。
しかし、単価が上昇傾向にある品目が輸出額を伸ばしているという例が各セクターで見られたほか、数量と単価の動向で品目を区分すると、主要輸出品(及びその他品目群)に含まれる一部の品目において、日本の輸出額の伸びがドイツや米国を上回るものも見られた。
また、世界単価よりも単価が高いカテゴリーについて見ると、主要8業種のうち、化学・プラスチック品及び鉄鋼・鉄鋼製品は、欧州債務危機を背景に需要が低迷するEUにおいても、堅調に輸出額が増加しており、価格競争によらず、差別化した製品によって需要が獲得できているケースが多いことが示唆される。一方、電気機器が輸出額を伸ばしている市場は、今回確認した中では中国のみであり、米国とEUにおいては、世界単価よりも単価が高いカテゴリーであっても、輸出額が減少している。
なお、各業種の内訳である主要輸出品等を確認すると、世界単価よりも単価が高いカテゴリーの輸出額が増加している主要輸出品が、全ての業種において見られた。
例えば、化学・プラスチック品関連の主要輸出品の多くは、EUと中国を中心に、主に世界単価よりも高いカテゴリーで輸出額を伸ばしている。なお、医薬品については、中国と米国において、数量および単価の上昇によって大きく輸出額を伸ばしている品目シェアが高い。
なお、品目の輸出額の伸びがドイツ(中国向け輸出、米国向け輸出)若しくは米国(EU向け輸出)を上回る主要輸出品としては、プラスチックフィルム等(以上、中国向け輸出)、アルミニウム、ニッケル、ガラス(以上、米国向け輸出)、銅、アルミニウム(以上、EU向け輸出)などが確認できた49。
一般機械関連では、印刷機械は、主要3市場全てにおいて、世界単価よりも単価が高いカテゴリーで輸出額を大きく伸ばしている。また、工作機械の中でも、その他品目群で取り上げた金属加工用のマシニングセンター等は、米国とEUでは世界単価よりも高いカテゴリーで、中国では世界単価よりも低いカテゴリーで、いずれも輸出額を伸ばしている。
品目の輸出額の伸びがドイツ(中国向け輸出、米国向け輸出)若しくは米国(EU向け輸出)を上回る主要輸出品としては、工作機械(中国向け輸出)、ブルドーザー(米国向け輸出)などが確認できた。
引き続き需要の拡大が見込まれるIT関連では、集積回路が、EUと米国において、世界単価よりも単価が高いカテゴリーの輸出額を伸ばし、中国においては、世界単価よりも単価が低いカテゴリーで、数量の増加により輸出額を伸ばしている。また、スイッチ等(電気回路の開閉等用)や検査・測定用機器(電子・電気・工業)、偏光材料シートが、中国において、世界単価よりも単価が高いカテゴリーで輸出額を伸ばしている。
医療機器関連では、中国と、また少子高齢化が進むEUにおいて輸出額が伸びており、中でも内視鏡は、世界単価よりも高いカテゴリーで輸出額が大きく伸びている。
品目の輸出額の伸びがドイツ(中国向け輸出、米国向け輸出)若しくは米国(EU向け輸出)を上回る主要輸出品としては、超音波検査機器、X線CT装置(コンピューター断層診断装置)(以上、中国向け)、医用検体検査機器(中国、米国向け)、診断用X線装置、人工関節(以上、EU向け)などが確認できた。
輸送用機械関連のうち、乗用車は、中国と米国においては、数量増加かつ単価上昇(「量+単価+」)の品目シェアが高い。対世界単価比率で見ると、中国では世界単価より低いカテゴリーによって全体の輸出額が大きく伸びている。
自動車部品は、中国において、世界単価より高いカテゴリーによって大きく輸出額が伸びている。EUにおいては、世界単価より高いカテゴリーのみ輸出額が増加し、全体では減少している。米国では、単価上昇カテゴリーの品目シェアが低く、世界単価比で単価が高いカテゴリーも含めた輸出額全体が減少している。
また、自転車部品と航空機部品は、中国と米国では単価上昇の品目シェアが高い一方、EUでは単価上昇の品目シェアは非常に小さく、数量の増加により輸出額を伸ばしている。
品目の輸出額の伸びがドイツ(中国向け輸出、米国向け輸出)若しくは米国(EU向け輸出)を上回る主要輸出品としては、鉄道部品(中国向け)、航空機部品(米国向け)などが確認できた。
更に、職人の技術力を活かした刃物や工具について日本の製品の評価が海外で高まる中、卑金属製の手工具・刃物等は各市場で輸出額を伸ばしている。またその中に含まれる、のこぎり、包丁・ナイフ、剪定ばさみ等は、世界単価より高いカテゴリーで輸出を拡大している。
49 数量・単価動向の数量増加カテゴリーのうち、日本とドイツ(あるいは米国)の品目シェアが20%以上のカテゴリーの輸出額の伸び率を比較したもの。
(6)主要国の輸入額増加品目に占める各国割合
ここまでに、日本の輸出は主要国に比べて伸びが低い業種が多いものの、品目や市場によって状況が大きく異なっており、中には日本の輸出額の伸びが他の主要な輸出国を上回る品目が見られることなどを確認した。
ただし、そのような比較的堅調に輸出できている品目とは、「主要輸出品」や「その他品目群」のうちの一部分に限定されていることが多いことも確認した。
そこで、世界需要の高まりに日本がどの程度対応できているのかを確認するため、主要市場で輸入が増加している品目を抽出し、その各国別シェアを見ることとする。確認の方法は第Ⅱ-1-1-3-62図のとおりとする。
第Ⅱ-1-1-3-62図 主要国の輸入額増加品目に占める各国シェア分析(計算方法)
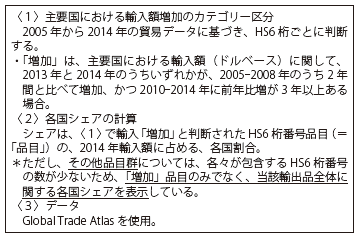
①中国の輸入額増加品目に占める各国割合
まず、中国の輸入額増加品目について、日本からの輸入額が占める割合は、主要8業種では1~2割程度である(第Ⅱ-1-1-3-63図)。各セクターの主要輸出品を見ると、中国の輸入額の伸びが高い輸送用機械関連や電気機器関連、医薬品については、日本の比率はあまり高くない。伸びが高い場合には、他国も積極的に市場を取りに来るため、相対的に日本のシェアが低下している可能性がある。
第Ⅱ-1-1-3-63図 中国の輸入額増加品目に関する各国割合
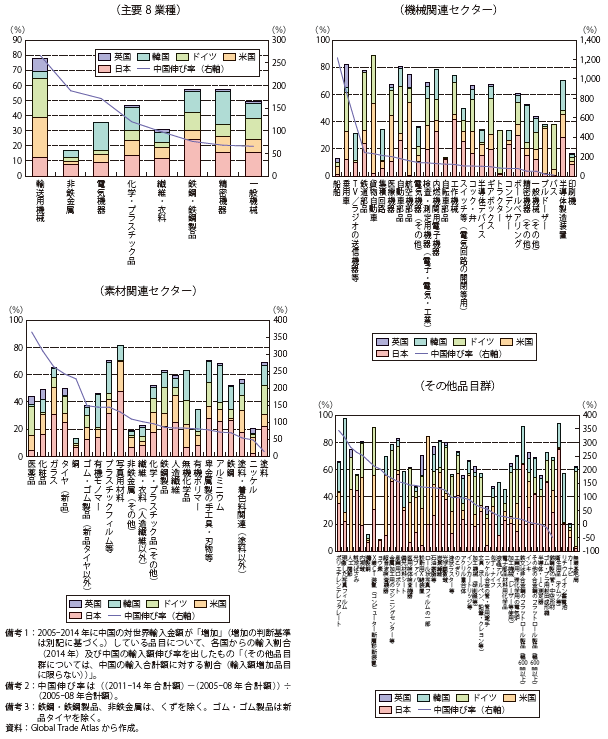
- Excel形式のファイル(主要8業種)はこちら

- Excel形式のファイル(機械関連セクター)はこちら

- Excel形式のファイル(素材関連セクター)はこちら

- Excel形式のファイル(その他品目群)はこちら

なお、その他品目群50では、機能性化学品が含まれている可能性があるポリエチレンテレフタレート、剪定ばさみ、医療用のX線CT装置、工作機械のうち金属加工用マシニングセンター等、産業用ロボット、スマートフォン等に使用される偏光材料シート、炭素繊維、光学顕微鏡、のこぎり、ボールペン・鉛筆等の文具類で、日本のシェアが高い。
②米国の輸入額増加品目に占める各国割合
米国の輸入額増加品目における日本のシェアは、主要8業種を見ると、最も高い輸送用機械が約15%であり、1割に満たない業種も見られる(第Ⅱ-1-1-3-64図)。全体的に、米国の輸入額の伸びが高い主要輸出品(医薬品、集積回路、人工関節等)については、日本のシェアは低い。
第Ⅱ-1-1-3-64図 米国の輸入増加品目に関する各国割合
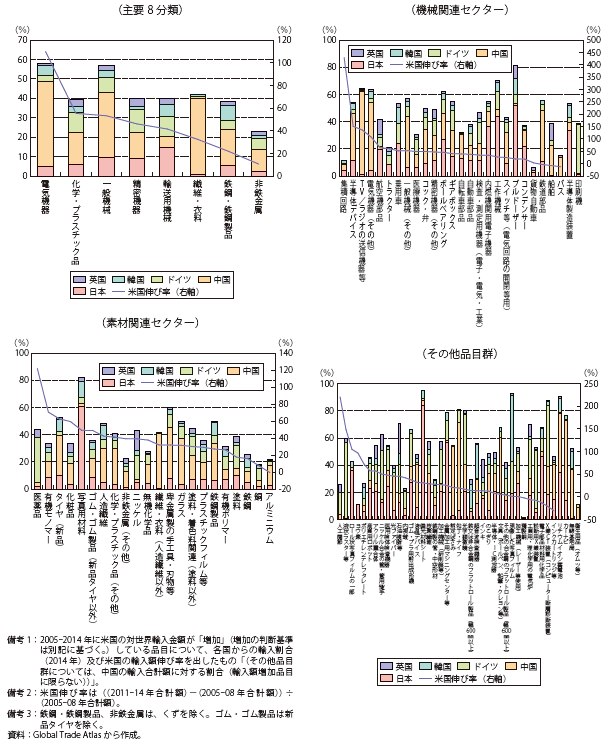
- Excel形式のファイル(主要8業種)はこちら

- Excel形式のファイル(機械関連セクター)はこちら

- Excel形式のファイル(素材関連セクター)はこちら

- Excel形式のファイル(その他品目群)はこちら

一方、機械関連セクターでは、全体的に日本のシェアが高く、特にブルドーザー、工作機械、内燃機関用電子機器では3割以上を占める。
その他品目群では、日本のシェアが高いものが多く、特に偏光材料シート、マシニングセンター、電子部品材料用化学品、リチウムイオン蓄電池は3割以上と高い。
③EUの輸入額増加品目に占める各国割合
EUの輸入額増加品目における日本の比率は、主要8業種を見ると、最も高い精密機器が約10%であり、他は更に低い(第Ⅱ-1-1-3-65図)。主要輸出品を見ると、機械関連セクターでは、一部に日本のシェアが高いものが見られる(内燃機関用電子機器、コンデンサー、工作機械)
第Ⅱ-1-1-3-65図 EUの輸入額増加品目に関する各国割合
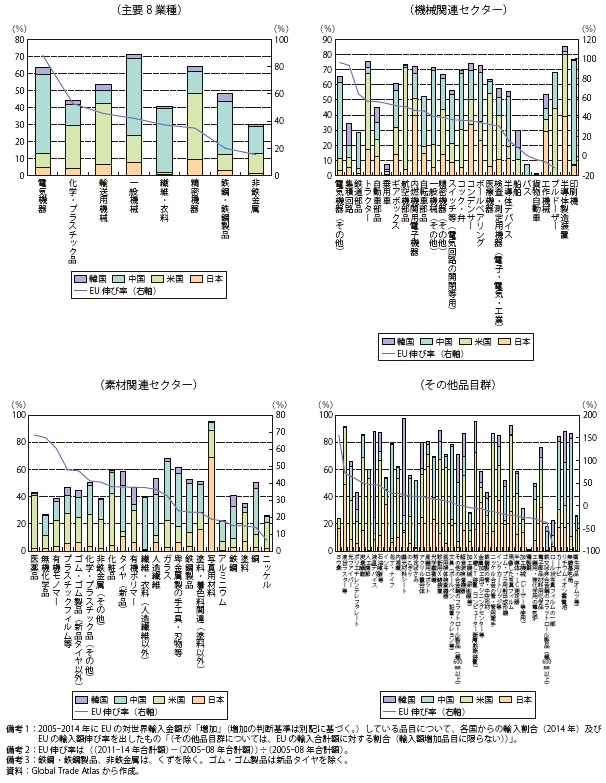
- Excel形式のファイル(主要8業種)はこちら

- Excel形式のファイル(機械関連セクター)はこちら

- Excel形式のファイル(素材関連セクター)はこちら

- Excel形式のファイル(その他品目群)はこちら

その他品目群では、日本のシェアが高いものも多い(産業用ロボット、金属加工用マシニングセンター等、電子部品材料用化学品等)。
④タイの輸入額増加品目に占める各国割合
タイの輸入額増加品目に占める日本のシェアは高い(第Ⅱ-1-1-3-66図)。主要8業種を見ると、最も低い繊維・衣料が約1割であり、最も高い鉄鋼・鉄鋼製品では約4割となっている。主要輸出品ごとに見ても、素材関連セクター、機械関連セクターともに、日本のシェアが高いものが多く見られる(卑金属製の手工具・刃物等、鉄鋼、ニッケル、写真用材料、ブルドーザー、自動車部品、内燃機関用電子機器、工作機械、ギアボックス、半導体デバイス、ボールベアリング等)。
第Ⅱ-1-1-3-66図 タイの輸入額増加品目に関する各国割合
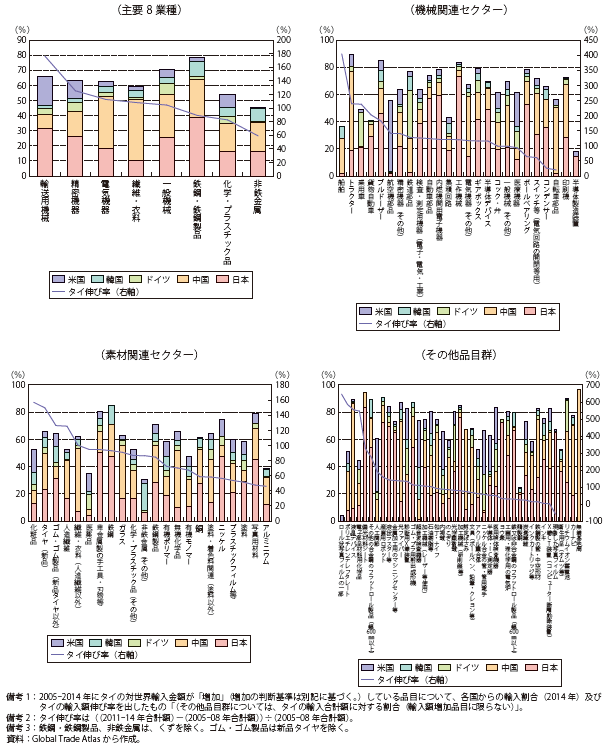
- Excel形式のファイル(主要8業種)はこちら

- Excel形式のファイル(機械関連セクター)はこちら

- Excel形式のファイル(素材関連セクター)はこちら

- Excel形式のファイル(その他品目群)はこちら

その他品目群でも、日本のシェアが高い品目が多い(偏光材料シート、産業用ロボット、金属加工用マシニングセンター等、加工機械(研削盤等)、ヨウ素、鉄または非合金鋼のフラットロール製品(幅600mm以上)等)。
⑤主要国の輸入額増加品目に占める各国割合(まとめ)
本項では、輸出品の中でも、主要市場(中国、米国、EU、タイ)において輸入額が増加している品目を抽出し、その合計輸入額に占める各国シェアを確認した51。その結果、そうした輸入額増加品目の輸入額に占める日本のシェアが比較的高い主要輸出品(及びその他品目群)が、機械関連セクターを中心に多く見られた。
例えば、IT関連の主要輸出品およびその他品目群は、各市場において輸入額の伸びが高いものが多い。その中で産業用ロボット(その他品目群)は、今回確認した市場のうち、米国を除く3市場において、日本のシェアが5割を超え、偏光材料シート(その他品目群)は、米国とタイにおいて8割を超える。また半導体製造装置の輸入額増加品目では、タイを除く3市場において、日本のシェアが3割を超えている。
他にも、4市場全てにおいて、輸入額増加品目の輸入額に占める日本の割合が2割を超える主要輸出品(及びその他品目群)が確認できた(工作機械、内燃機関用電子機器、写真用材料、ボールベアリング、コンデンサー、光学顕微鏡(その他品目群))。
さらに、市場を区切って米国とEU市場のみを見ると、日本のシェアが両市場で2割近くを占めるその他品目群が、化学品と雑貨で見られた(吸水性樹脂等を含むアクリル重合体(その他品目群)、電子部品材料用化学品、細かな仕様や使い心地で評価が高いボールペンや鉛筆・クレヨン等の文具(その他品目群))。
50 その他品目群については、包含するHS6桁番号の数が少ないものが多いため、輸入額増加品目のみでなく、輸入額全体に関する各国シェアを使用している。
51 その他品目群については、包含するHS6桁番号の数が少ないものが多いため、輸入額増加品目のみでなく、輸入額全体に関する各国シェアを使用している。
(7)品目別に見た「輸出する力」(まとめ)
日本の輸出額は、全体で見ると他国に比べて伸びが弱い。
しかし、(3)で見たように、数量と単価の動向ごとにカテゴリー区分して、丁寧に見ていくと、中には、他の主要国に比べて日本の輸出額の伸びが高い品目を含む主要輸出品等が存在する。また、(6)で見たように、市場において輸入額が増加している品目に限ってみると、既に日本が高いシェアを占めている主要輸出品等は多く存在している。
先進国を中心とした少子高齢化や、製造業におけるデジタル化や素材の軽量化を背景に、IT関連製品、炭素繊維、産業用ロボット、医療機器等は、今後の需要拡大が見込まれる業種であり、各国の輸入額の伸びも高いものが多い。また、特に日本の製品に対する需要が高まっているような品目も見られる。さらに、新興国において富裕層を中心に所得が上昇する中、付加価値の高い製品に対する需要が高まっていることが指摘されている。日本は、こうした世界における需要の高まりをうまくキャッチしていくことが必要である。
なお、(2)において他の主要な輸出国の動向を見たが、それによると、多くの国では単価が高い品目の輸出額が増加傾向にあり、価格競争によらずに輸出を拡大している可能性が高いことが確認できた。また、日本の輸出についても、単価が世界に比べて高い品目は、輸出が堅調である場合が多いことも確認できた。
単価の高いものであっても、その技術力によって差別化した製品であれば、適切な販路の開拓等によって引き続き輸出を確保していくことが可能なケースが多いが、上記のデータはその表れであると言える。
日本は、新興国の輸出競争力向上を背景に、コストの引下げを重視しがちであると指摘されることが多いが、世界の需要の高まりをキャッチし、また日本の技術力を活かして、製造業のあらゆる分野において、付加価値の高い製品の製造をより重視することが、日本からの輸出を将来にわたり確保していくことに繋がるのではないだろうか。
第Ⅱ-1-1-3-67表 輸出品目名及び関税番号一覧