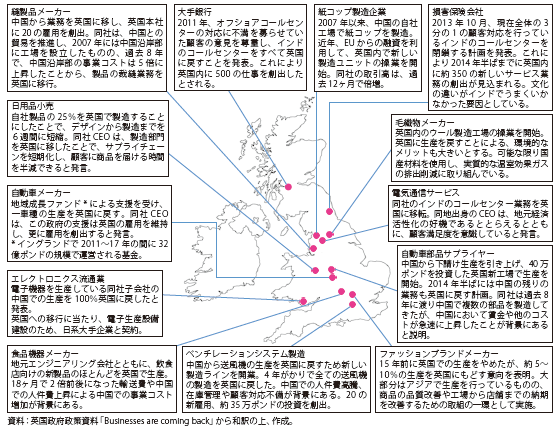第2節 「呼びこむ力」の検証
本節では、「ヒト」や「企業」を呼び込む力の向上が、わが国の成長およびグローバルな稼ぐ力の向上につながるとの問題意識から、「ヒト」については旅行客の訪日、消費の動向及びその背景を、「企業」については外資系企業の立地選択について分析する。
1.「ヒト」の呼び込み
(1)増加する訪日外国人旅行客数
2014年の訪日外国人旅行客数は1,341万人(前年比29.4%増)となり過去最高を記録した。これまで過去最高であった2013年の1,036万人を大きく上回る結果である。特にアジアからの訪日が多く、2014年の訪日外国人のうち80.7%がアジアからの訪日であり、上位10か国・地域のうち、7カ国・地域がアジアの国・地域であった。伸び率で見てもアジアの国々が上位を占めている。伸び率が特に大きかった国は、中国(前年比83.3%増)、フィリピン(同70.0%増)、ベトナム(同47.1%増)、タイ(同45.0%増)、マレーシア(同41.4%増)となっている(第Ⅱ-1-2-1-1図)。
第Ⅱ-1-2-1-1図 訪日外国人旅行客数の推移
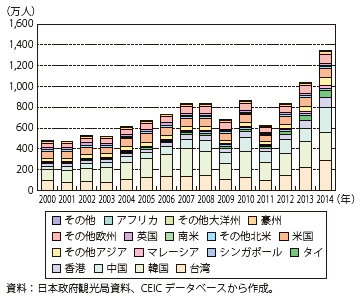
ここで世界に目を転じてみると、世界の旅行者数はリーマン・ショック後の2009年にいったん前年比減となったものの増加傾向にある(第Ⅱ-1-2-1-2図)。日本を訪れる外国人旅行者数は2013年時点で世界第23位と決して高くない水準にあるが、主要国の国際旅行者数の伸び率では、2012年、2013年ともに1位であり世界の旅行者に占める割合も上昇傾向となっている(第Ⅱ-1-2-1-3図、第Ⅱ-1-2-1-4図)。旅行者数の増加に伴い、旅行に伴う支出は世界規模では1.3兆ドル(世界GDPの9%)に達している。日本の名目GDPに占める旅行収支受取額の割合は必ずしも高くはないものの、わずかながら上昇している(第Ⅱ-1-2-1-5表)。
第Ⅱ-1-2-1-2図 世界の旅行者数と訪日旅行者の割合
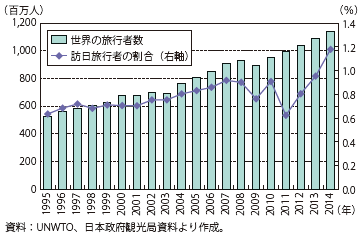
第Ⅱ-1-2-1-3図 各国の国際旅行者数
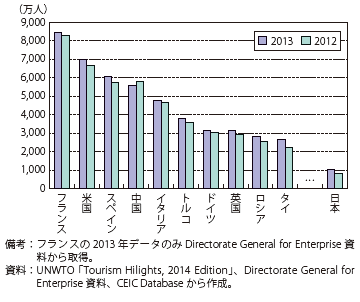
第Ⅱ-1-2-1-4図 国際旅行者数の伸び率
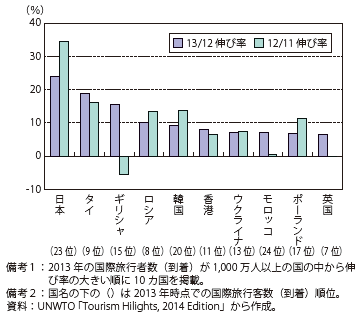
第Ⅱ-1-2-1-5表 名目GDPに占める旅行収支受取額の国際比較(2010-2013年)
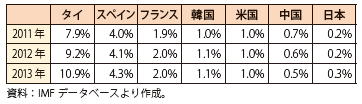
(2)旅行者を呼び込むための環境整備
旅行者を呼び込むために様々な政策がとられてきたが、前述の外国人旅行者の増加に寄与したと思われる主な背景として、積極的な訪日プロモーション、航空ネットワークの拡充や魅力ある観光地域づくり等が挙げられる。加えて、外国人旅行者を呼び込むための制度整備も影響を与えていると見られている。ビザ発給にかかる手続の簡素化又は要件の緩和、並びに免除といった旅行推進策もその一つであり、本節ではこの点に焦点をあてて観察したい。近年旅行者数が増加傾向にあるアジアの国・地域に対して、我が国はビザ要件の緩和を行っており、一定の効果があったと考えられる。以下、東アジア各国・地域、中国、一部のASEAN諸国について、2000年以降のビザ要件緩和前後での訪日者数の推移を見ていく。
まず、東アジアの国・地域を見てみよう。2014年の訪日外国人旅行者の国・地域別順位で、上位3位を占めるのが台湾(283万人、21.1%)、韓国(276万人、20.5%)、中国(241万人、18.0%)で、これら3カ国・地域だけで全体の約6割を占めている。これら3カ国・地域に対しては、2004年に香港向けに、2005年に台湾と韓国向けにビザが免除されたことにより、訪日旅行者数の伸びの加速が見られた。その後、リーマン・ショック後の2009年と東日本大震災のあった2011年に訪日客数の減少が見られたが、2012年末から為替が円安方向に推移したことが追い風となり、ビザ免除を実施した時期よりも急激に訪日客数が伸びている(第Ⅱ-1-2-1-6図、第Ⅱ-1-2-1-7表)。
第Ⅱ-1-2-1-6図 東アジア各国・地域からの訪日客の推移
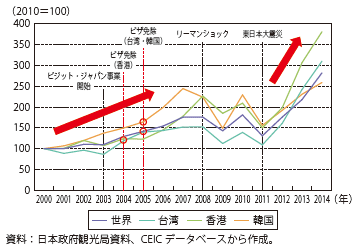
第Ⅱ-1-2-1-7表 東アジアの国・地域向けのビザの緩和
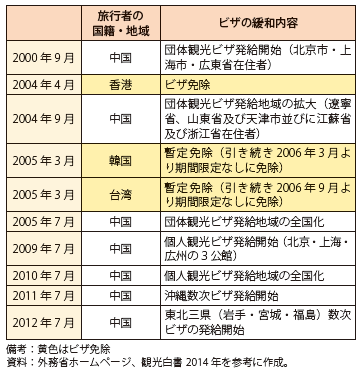
次に中国について見てみると、同国の所得水準の上昇を背景に、個人観光ビザの発給が中国からの訪日旅行客増加に大きく寄与したことが分かる。2000年以降の推移を見ると、中国からの訪日旅行客数は、従来より全世界からの訪日旅行客数の伸びを上回るペースで増加していたが、まず2003年のビジット・ジャパン事業開始を受け、翌年より増加幅が拡大し、リーマン・ショックの翌年である2009年にも小幅ながら増加を維持した。続いて、2009年の個人観光ビザ発給開始により、翌年の2010年には急激な伸びを見せ、2011年には東日本大震災の影響により、落ち込んだものの、翌2012年には2010年とほぼ同水準にまで回復した。2013年には再度前年比減となったが2014年には109万人増(同83.3%)となった(第Ⅱ-1-2-1-8図)。
第Ⅱ-1-2-1-8図 中国人訪日客数の推移
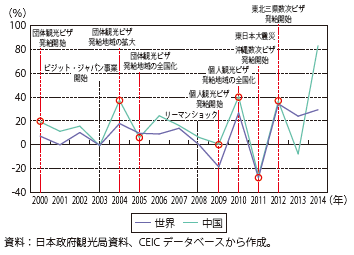
最後にASEAN諸国について見てみると、ビザの緩和と為替の円安方向への推移が重なり、訪日外国人旅行客数増加に大きな影響を及ぼしていることが分かった。我が国は2013年後半に一部のASEAN諸国に対してビザの緩和を行っている。具体的には、2013年7月にはタイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、ベトナム向けに、11月にはカンボジア、ラオス、ミャンマー向けにビザの緩和を行った。これらのうち一部の国々に対しては、2012年にもビザを緩和しており、そこに為替の円安方向へ推移が重なり、2013年にはいずれの国もリーマン・ショックのあった2008年以前の伸び率以上の伸び率を記録している(第Ⅱ-1-2-1-9図、第Ⅱ-1-2-1-10表、第Ⅱ-1-2-1-11図)。
第Ⅱ-1-2-1-9図 一部のASEAN諸国からの訪日客数の推移
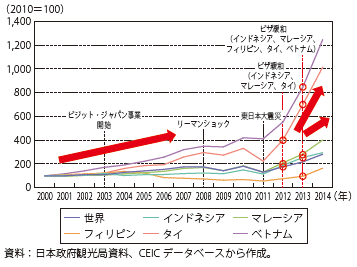
第Ⅱ-1-2-1-10表 一部のASEAN諸国向けのビザの緩和
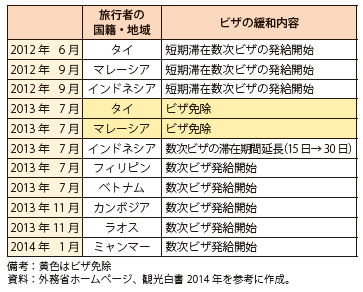
第Ⅱ-1-2-1-11図 各国通貨と円の名目為替レートの推移
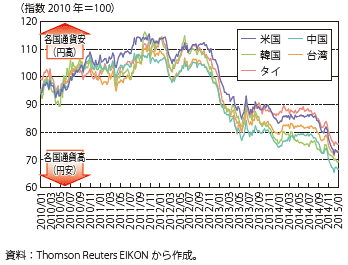
(3)訪日外国人の消費動向と地域への広がり
訪日外国人旅行客数が過去最高を記録したのと並行して、2014年の訪日外国人旅行客の消費金額は2兆円を超え、前年比では5,000億円の増加となり、過去最高額を記録した。百貨店における外国人観光客向けの売上は、外国人旅行客数の増加幅以上に増加しているなど、訪日外国人旅行客の増加が日本経済に与える影響は、急速に拡大傾向にあると言えよう(第Ⅱ-1-2-1-12図)。
第Ⅱ-1-2-1-12図 百貨店における外国人観光客向け売上高の推移
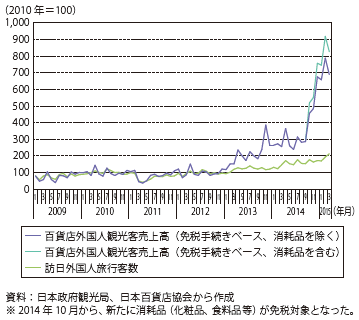
内閣府「景気ウォッチャー調査(2015年3月)」を見ても、外国人観光客の増加を指摘するコメントが増加しつつある。観光業や宿泊業、小売業などを中心として、北海道から沖縄に至る幅広い地域で、外国人観光客の増加が経済の押し上げに寄与している模様である。
商店街(北海道)「外国人観光客の入込は春節後も順調に推移しており、好調が続いている。」
金融業(北海道)「外国人観光客の大幅増加により、土産品メーカーは好調である。」
旅行代理店(北関東)「外国人来訪者の増加が目立ってきている。」
飲食業(北陸)「県外からの客、外国人の客、どちらも家族旅行が多く、1卓あたりの注文点数も増えている。」
百貨店(近畿)「前年は消費税増税前の駆け込み需要があったため、今月は減収の見通しであるが、外国人客向けの売上の急増で、前年比での落ち込みの約半分はカバーできる。」
テーマパーク(中国)「天候に恵まれ、一般の来園者が増えた。外国人観光客も増えている。」
都市型ホテル(中国)「宿泊部門は外国人客数が依然として好調を継続している。」
観光旅館組合(九州)「円安の影響で外国人観光客が多い。」
レンタカー(沖縄)「特に外国人観光客の利用が伸びている。」
では、具体的にどのような地域で、どのような形で、外国人旅行客は消費活動を行っているのだろうか。旅行消費のうち、具体的に消費金額が判明する「日本滞在中の費目別支出52」を確認してみよう。
まず、2014年の「日本滞在中の費目別支出」で捕捉される旅行消費金額は約1.72兆円である。このうち、買い物が7,391億円と最も大きく、宿泊料金(4,413億円)、飲食費(3,397億円)、交通費(1,624億円)と続く53。次に、変化幅を見ると、2014年に4,800億円(前年比+38.6%)増加した旅行消費金額のうち、2,587億円が買物代である(前年比+53.8%)。次に、飲食費(1,059億円、同+45.3%)、宿泊料金(566億円、同+14.7%)、交通費(468億円、同+40.5%)となる(第Ⅱ-1-2-1-13表)。
第Ⅱ-1-2-1-13表 日本滞在中の費目別支出
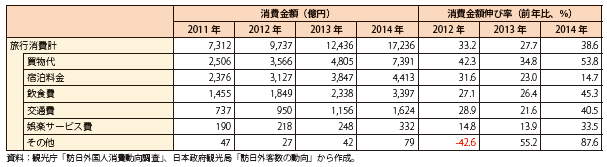
買物代は、旅行消費に占める割合が高いだけでなく、増加率も最も大きい。足下の旅行消費増加は、買物代の増加がかなりの部分を占めているといえる。飲食費、交通費に関しても、外国人旅行客の増加率よりも大きく消費金額が伸びており、一人当たりの消費単価が上昇傾向にあると言える。宿泊料金は、増加率が他の項目と比べて低いが、同時にパッケージツアーの利用率が高まっている54ことを考慮すれば、必ずしも消費単価が下がっていることを意味しないため、注意が必要である。
旅行消費金額増加の大部分を占める買物代であるが、さらに細かく見ていくと、2014年には「化粧品、医薬品」の消費金額が大きく伸びている(前年差+825億円、前年比+90.2%)55。2014年10月以降、免税対象品目が化粧品を含む消耗品まで拡大されたことが、この背景にあると考えられよう。
この後、「服(和服以外)・かばん・靴」(前年差+551億円、前年比+51.9%)、「電気製品」(前年差+372億円、前年比+100.7%)、「カメラ・ビデオカメラ・時計」(前年差+292億円、前年比+54.2%)と続く。これらの製品に関しては、為替の円安方向への推移により、割安感が増したことに加え、日本で販売されているものは品質がよく、模造品などが混じっていないという、日本に対する信頼の高さなどが販売増加につながったと指摘する声もある。増加幅は小さいが、「マンガ・アニメ・キャラクター関連商品」(前年差+76億円、前年比+75.7%)の伸び率の大きさからは、日本のコンテンツが諸外国にも評価されていることを表していることが読み取れる。このようにファッション、食、コンテンツなどの消費金額の伸びは、総じてクールジャパン戦略の成果の一端と捉えることが出来よう(第Ⅱ-1-2-1-14表)。
第Ⅱ-1-2-1-14表 日本滞在中の買物支出費目
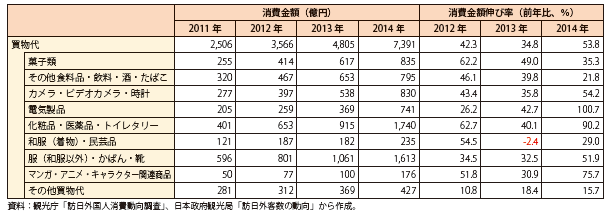
地域別の外国人旅行客支出動向を見てみよう。訪日外国人消費動向調査には、「主な宿泊地での支出額」を尋ねる調査項目があり、外国人旅行客が訪れた地域ごとの消費金額がある程度把握できる。さらに、観光庁の「宿泊旅行統計調査」という統計からは、外国人旅行客の宿泊人数を把握することが出来る。これらを組み合わせることで、宿泊地別の支出金額を大まかながら推計することが可能である。
まず、地域別56の外国人旅行客数の動向を見てみよう。外国人旅行客の累積宿泊日数で比較すると、最も外国人旅行客数が多い地域はやはり関東地方である。ビジネス向けの訪日客も含んでいることなどから、やはり東京での宿泊日数は他県と比べて群を抜いて大きく、日本全体の外国人観光客の1/3程度は東京で宿泊している。関東地方の次は、近畿地方、北海道、九州、中部、沖縄と続く。近畿地方では大阪、京都の宿泊数が全体の中心である。北海道、沖縄などは、特に近年の旅行客数の伸びが著しい。2014年の日本全体の外国人延べ宿泊日数は2011年対比+143%であるが、北海道は+155%と全体を上回っている。さらに、沖縄に関しては+312%と実に4倍となっている。九州では、地理的な距離の近い韓国や台湾からの旅行客が多く、中部地方は大きな国際空港を有することや、関東と関西の間に位置することで、ツアーに組み込まれることが多いことなどが宿泊者数の増加につながっているものとみられる(第Ⅱ-1-2-1-15表)。
第Ⅱ-1-2-1-15表 地域別の外国人旅行客数
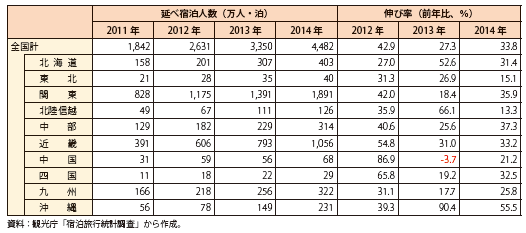
次に、地域別の外国人累積宿泊日数を元に、地域別訪日外国人旅行客数を推計し、訪日外国人消費動向調査における「主な宿泊地での支出額」を掛け合わせることで、地域別の外国人観光客支出金額を作成したものが、第Ⅱ-1-2-1-16表である。
第Ⅱ-1-2-1-16表 地域別の外国人旅行客支出金額(推計)
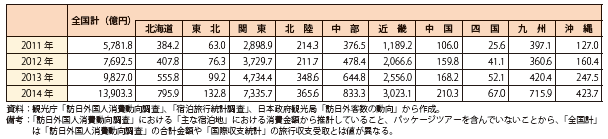
地域別の支出額が判明する金額57を積み上げると、2014年の外国人旅行客消費金額は約1.39兆円となり、「日本滞在中の支出」約1.72兆円のうち約8割程度は捕捉出来ている。また、パッケージツアー旅行代金を含む旅行消費金額約2兆円との対比でも、7割程度を把握できている。
地域別の支出金額は、地域別の外国人累積宿泊日数で見たものと概ね傾向は一致している。関東地方が全体の半分以上を占め、次に近畿、中部、北海道、九州、沖縄の順に続く。ただし、地域ごとに経済規模は異なるため、外国人旅行客の増加が地域に及ぼしている影響は、金額の大小のみでは測れない。そこで、地域別の名目GRP(域内総生産)対比で外国人旅行客消費額を見たものが、第Ⅱ-1-2-1-17図である。
第Ⅱ-1-2-1-17図 地域別名目GRPに対する外国人旅行客消費額
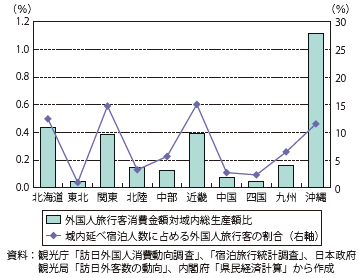
このように見ると、外国人旅行客数、外国人旅行客消費金額の大きい関東、近畿地方だけでなく、北海道と沖縄においても、外国人旅行客増加のインパクトが大きいことが見て取れる。また、外国人旅行客数増加のインパクトが大きい地域では、域内の延べ宿泊人数に占める外国人旅行客の割合が高い。外国人旅行客に魅力を伝えることに成功し、域内への呼び込みに成功した地域ほど、経済の押し上げ効果が大きいといえる。
52 「日本滞在中の費目別支出」は、旅行消費金額のうち、パッケージツアー旅行代金を含まない。ただし、実際にはパッケージツアー旅行には、国内旅館・ホテルの宿泊料や交通料、飲食料、国内航空機関の運賃などが含まれていることから、「日本滞在中の費目別支出」は、外国人観光客が支出し、日本国内に「落ちる」金額の一部を捉えられていない。
53 品目別の支出金額は、外国人観光客数×購入率×購入者単価によって求めた。
54 訪日外国人消費動向調査によると、パッケージツアー購入率は2012年に28.1%、2013年に30.4%、2014年に34.1%と徐々に上昇傾向にある。
55 2013年までは「化粧品・医薬品・トイレタリー」という区分での調査であったが、2014年第1四半期からは「化粧品・香水」と「医薬品・健康グッズ・トイレタリー」に調査内容が分けられた。ここでは、両項目を加えた数値と、2013年までの「化粧品・医薬品・トイレタリー」を比較している。
56 ここでは、訪日外国人消費動向調査、宿泊旅行統計調査の区分に従い、国土交通省の運輸局別の地域区分を用いている。
57 主な宿泊地別の支出金額は、費目別支出額、あるいは1人1泊あたりの支出額のみが公表されている。今回は、費目別支出額を地域別外国人観光客数×地域別購入率×地域別購入者単価によって推計し、積み上げることで地域別の支出額を推計した。地域別外国人観光客数は、外国人観光客数を、宿泊旅行統計調査の地域別延べ宿泊人数で按分する形で推計した。
(4)まとめ
本節では、外国人旅行客が増加している背景にある政策及び国内に広がりをもった消費動向を明らかにした。近隣アジア諸国の所得水準の上昇が予想される中、クールジャパン、ビジットジャパンの連携など日本の魅力を多角的にアピールすることが国内の幅広い地域への訪日旅行客数の増加につながると期待される。
2.グローバル企業の立地選択から考える「呼び込む力」
前項では外国人旅行者の増加、その背景にある政策や消費動向の分析を通じて我が国の「ヒト」を呼び込む力が向上していることを見てきた。本項では我が国の「企業」を呼び込む力について、グローバル企業の立地選択も参考にしつつ検証を進めていく。
まず企業の立地選択がどのような視点で行われているかについてのこれまでの理論を確認する。次に、グローバル企業のビジネス機能別拠点の実際の立地状況、立地に際して考慮される要件などを通して、グローバル企業の立地選択の在り方を概観する。続いて、日本の事業環境や日本ならではの優位性にも触れつつ、日本の「呼び込む力」向上のための課題を整理する。
(1)企業の立地選択における立地競争力の位置づけ
ここでは企業が立地先を検討、選択する際、どのような立地環境に着目しているのかに焦点を当て、幾つかの理論を確認する。
ダニング(Dunning)(1998)は、1970年代と1990年代の多国籍企業(Multinational enterprises)の立地行動に影響を与える要因の変化を整理している。彼によれば1970年代の企業の立地選択においては、天然資源の価格や利用可能性、製造費、輸送費、原材料費や賃金コスト等が重視されていたのに対し、1990年代に入ると知識経済の進展に対応するため、知識を保持した熟練労働者や専門人材の利用可能性、知識集約部門ユーザーへの近接性、また自社が持っている資産との相乗効果が見込める資産の利用可能性といった要因が重視されるようになってきているとされている。一般的なコスト要因重視からより先端技術や知識等の戦略資産58の獲得、利用を重視する方向へと企業行動が変化してきていることがうかがえる。
ポーター(Porter)(1998、邦訳1999)は、天然資源の有無、労働コスト、資本コスト等の要因は経済のグローバル化の中でその意義を失い、知識が社会・経済の発展を駆動する現在のような知識基盤型社会では、知識、情報を効率的に活用し、イノベーションを誘発して企業を成長させる環境59が、立地競争力において大きな役割を果たすようになってきたとしている。更にポーター&リブキン(Porter and Rivkin)(2012)は、企業の立地選択は今や「国の競争力を測る投票である」と表現する。彼らは、企業が事業展開する国・地域を選ぶ際には、グローバル市場の中で自社の業務や機能が最良のパフォーマンスを発揮することができる事業環境を整えている国・地域を選択するとし、このようにして「選ばれる国」には競争優位(立地競争力)があると唱えている。そして、自国の立地競争力を維持するために採るべき行動として、自国の核となる強みを守る、事業環境の弱点に対処するために事業環境整備を不断なく行う等、幾つかの方向性を提示している60。
高橋(2011)は、多国籍企業の立地に関する代表的な既存の理論を検証した上で、多国籍企業は、自社の持つ優位性を効果的に発揮できる場所や新しい戦略資産を活用できる場所に戦略的重要性の高い海外子会社の立地を集中させるため、そのような海外子会社の立地先には、立地の持つ魅力61が必要になるとしている。つまり、優位性を活用して、事業コスト(取引コスト、研究開発コストや生産コスト)を上回る便益が得られるからこそ、その国に立地すると述べている。
これらの理論から、企業の立地選択は、従来見られる事業コスト等の一般的な事業環境の優位性を求めて行われる他、近年は、立地することで戦略資産を活用し、企業の競争優位の向上を可能にする環境を求めるといった二つの視点があることが示唆される。
このことを選ばれる側の国・地域の視点から見ると、企業を誘致したい場合には、自身の事業環境の弱点に対処するために、税制改革や企業設立にかかる制度の見直しなど、一般的な事業環境整備を不断なく行うこと、更に自国の核となる強みを維持・強化するとともに、イノベーションにより新たな強みを創出し続けることで、投資企業が立地国・地域において相乗効果を生み、競争優位を向上できる環境を作っていくこと、の二つの視点が必要であると言い換えることができよう。
上記で見たとおり、企業の立地選択は、①一般的な事業環境の優位性を求めて行われる他、②戦略資産を活用し、そこに立地することで競争優位を向上させることができる環境を求める視点の二つに大別できる。
そこでグローバル企業がビジネス機能拠点を選択する際の立地要因を整理する上で、この二つの方向からの視点を設定する。
①第Ⅱ-1-2-2-1表の横軸である「国(立地先)が持つ一般的な事業環境の優位性」の視点
第Ⅱ-1-2-2-1表 グローバル企業の立地選択における視点(イメージ)
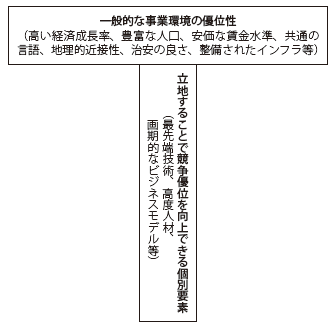
立地国の経済成長率、事業コスト、地理的位置、インフラの整備状況、共通言語等、その国で事業を行う際の一般的な事業環境が持つ優位性の視点である(以下、「一般的な事業環境の優位性」とする)。
②第Ⅱ-1-2-2-1表の縦軸である「当該国に立地することで競争優位を向上できる個別要素」の視点
例えば「卓越した技術力」「質のいい企業集積の存在」や、「高度な技能を持ち、企業の戦略資産をいかせる人的資本」、「新規性、独創性の高いビジネスモデルの存在」等、投資側が持つ資産をいかし、更に競争優位を向上させるための各要素の視点である(以下、「個別要素」とする)。
以下、グローバル企業の立地拠点、日本の持つ魅力と課題を検討していく上で、上記の二つの視点を念頭に状況を見ていくこととする。
58 小島(2012)によると、戦略資産とは、企業レベルでも事業レベルでも事業戦略を策定する際に必要となるもので、その企業にしかなく、他社は持ち得ないという独自性があり、それが事業能力を競争優位源泉(企業の事業が市場で競争優位を持つために必要なもの)に高めるものとしている。
59 Porter, M. (1998)(竹内弘高訳(1999))は、一定の分野で相互に関連する企業、大学、研究機関、自治体等が集積し、互いの協調(連携)及び競争関係を通じて、イノベーションを誘発する状態である「クラスター」の在り方が立地競争力において大きな役割を果たすようになってきたと指摘している。
60 Porter, M. and Rivkin, J.(2012)によると、企業の立地先になると、雇用確保、投資、税収、経済発展が期待できることから、どの国も「選ばれる国」になるために事業環境整備や誘致政策に積極的に取り組んでいるとしている。その中で「選ばれる国」になる(立地競争力を保持する)ためには、税制改革等、事業環境の弱点に対処するため事業環境整備を不断なく行う、またその国が持つ「核となる強み」を守る(例えば米国では新しいアイデアを創造し商業化する力がそれに当たるとされている)等、幾つかの視点が挙げられている。
61 高橋(2011)は立地の持つ魅力の一例として、有効なクラスターの存在を挙げ、うまく機能している魅力的なクラスターは、イノベーション創出や生産性向上効果に優れており、多国籍企業の投資を引き付けると述べている。
(2)他国グローバル企業の立地拠点
ここではグローバル企業における実際のビジネス機能拠点の設置状況を具体的に見ていく。
経済産業省委託調査62において、欧米アジアの主要グローバル企業54社(日系企業は除く)63のビジネス機能拠点の設置動向につき、公表資料を基にしたデスクトップ調査及び立地の際に重視している要件につき、10社程度のヒアリング調査を行った。
対象には「R & D」「地域統括」「マーケティング」「調達・購買」「生産」「物流」「販売」「アフターサービス」「バックオフィス・ITサービス」の9つのビジネス機能を設定したが、企業側にとって立地選択は、重要な経営戦略の一つであり、公表資料のみならず、ヒアリング調査においても入手できる情報が制限されていたことから、評価に足る結果を得ることは困難であった。
そのため以下では限定的ではあるが、実際の拠点設置の状況につき比較的情報が得られた「R & D」「生産」「地域統括」の各機能を中心に見ていくこととする64。
62 デロイト・トーマツ・コンサルティング株式会社(2015)。
63 ここでは他国グローバル企業の動向を探り、日本への立地可能性について考えることを目的としているため、対象企業から日系企業は除いている。また対象企業は、連結売上高上位かつ海外売上高比率が20%以上などグローバルでの営業実績に加え、拠点の設置場所・機能についての情報公開度合いなどを勘案して、選定を行った。
64 「販売」機能については一定の情報が得られたものの、需要のあるところに拠点を設置していると見られ、全世界に分散し、特段の傾向が見られなかったことからここでは触れない。
①R & D機能・生産機能
(a)設置の方針・重視される要件
ヒアリング調査にて、企業から出された各ビジネス機能拠点の設置方針は第Ⅱ-1-2-2-2表のとおりである。主なところでは、R & D拠点については、「コア技術は本社や売上げ規模の大きな市場に集約」、「現地対応のための応用R & Dは需要地に近接分散」、「重視する要件としては人材、言語、コスト」などの方向性が見られた。また生産拠点については、「地産地消が原則」「労働集約的な製品は低コスト国に集約」「高付加価値なものは自社工場等に集約」などの傾向が示された。
第Ⅱ-1-2-2-2表 R&D及び生産拠点の設置方針
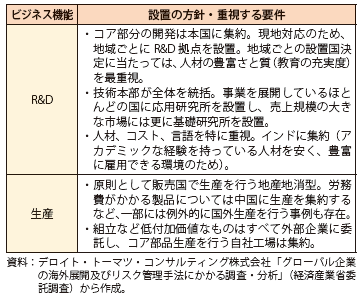
(b)実際の設置状況
調査対象企業を「総合電機(重電中心)」、「食品、日用品等の一般消費財」、「自動車」、「化学」、「製薬」、「情報通信(ハイテク)」、「総合電機(家電中心)」の7業種に分類し、拠点分布の特徴を基に「分散型」、「集中型」、「中間型」の3類型65に分けて見ていくと状況は以下のとおりである。
取扱い製品が幅広く、求められるものにその文化的な特異性、地域による嗜好(しこう)や特徴が出る業種が多く、現地のニーズを取り入れ、カスタマイズしていく必要性が高いことから、拠点は他の業種と比較すると分散して設置される傾向にある。
i)食品、日用品等の一般消費財
〈R & D拠点〉
巨大市場を抱える米国への設置が最多となっているが、それ以外の国・地域にも比較的分散して設置されている(第Ⅱ-1-2-2-3表)。文化的な特異性、地域の嗜好(しこう)やニーズをくみ取り、カスタマイズするための応用R & Dの現地化も進んでいると見られる。
第Ⅱ-1-2-2-3表 グローバル企業(一般消費財)の拠点設置状況
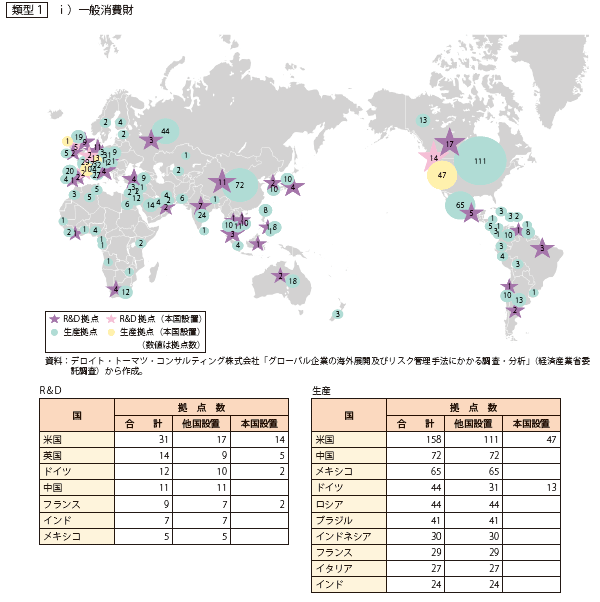
〈生産拠点〉
立地の視点としては需要地域への近接性が重視される。生産拠点は、巨大市場である米国、続いて中国への設置が多いが、それ以外の国・地域にも多数の拠点が細かく設置されており、原則として地産地消で対応している様子がうかがえる(第Ⅱ-1-2-2-3表)。
65 ビジネス機能拠点の分布状況は、視覚的に捉えやすい分散と集中の傾向で類型化を行う。分布状況の背景にはコスト等の一般的な事業環境の優位性と高度な技術力、画期的なビジネスモデル等の個別要素とのバランスで立地選択がなされているとの視点が含まれると考えられる。
全世界で比較的同一の製品・サービスを提供している産業が多く含まれる。R & D拠点、生産拠点ともに少数の拠点に集約され、各国には販売拠点のみ設置される傾向が見られる。
i)製薬
〈R & D拠点、生産拠点〉
立地の視点としては、高い技術力や製薬産業をめぐる制度・法規制等の状況が考えられる。医療、ライフサイエンス分野で高度な技術水準を保持している米国にR & D拠点、生産拠点ともに集中して設置されている。また、英国、スイス、フランス、ドイツ等、欧州先進国にも両拠点の設置が多く、欧米に集中していることがうかがえる。一方、低価格の後発(ジェネリック)医薬品の主な生産拠点であるインド等へのコスト優位の立地も見られる(第Ⅱ-1-2-2-4表)。
第Ⅱ-1-2-2-4表 グローバル企業(製薬)の拠点設置状況
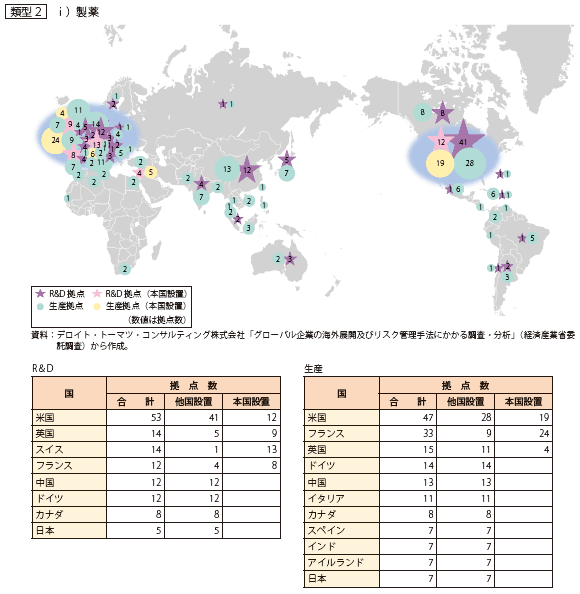
ⅱ)情報通信(ハイテク)
〈R & D拠点〉
立地の視点としては、高度技術、IT人材、情報の集積等、一般的な事業環境の優位性より個別要素重視と見られ、米国企業による本国設置が圧倒的に多い。また本国設置を除くと「中東のシリコンバレー」であるイスラエルに集まっていることが分かる66。また、高度な技術分野の知識を持っている人材を安く、豊富に雇用できる環境であるインドや中国にも多くの設置が見られる(第Ⅱ-1-2-2-5表)。
第Ⅱ-1-2-2-5表 グローバル企業(情報通信)の拠点設置状況
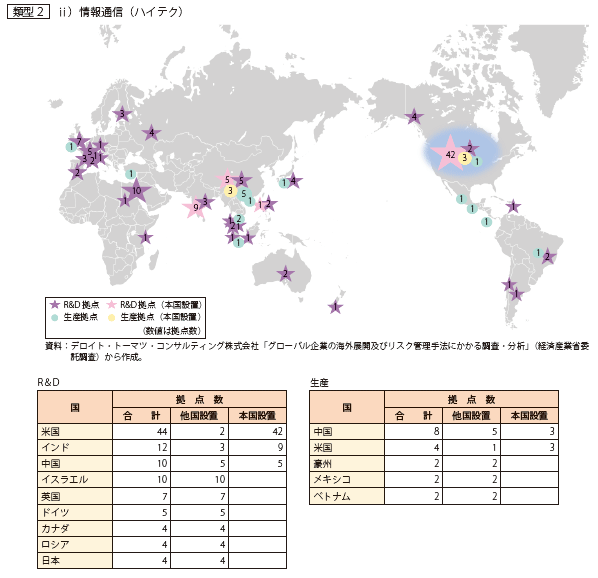
66 イスラエルについては第2章第2節「2.イスラエル」参照。
〈生産拠点〉
中国に拠点が多く、高付加価値部品の生産拠点は高い技術(個別要素)を持った国に、また組立てなどは主にコスト視点からの立地選択が行われていると考えられ、集約化の傾向が見られる(第Ⅱ-1-2-2-5表)。
ⅲ)総合電機(家電中心)
〈R & D拠点〉
一定の技術力を保持している先進国への設置が多いが、大需要地である中国、インドへの設置も見られる(第Ⅱ-1-2-2-6表)。
第Ⅱ-1-2-2-6表 グローバル企業(総合電機 家電中心)の拠点設置状況
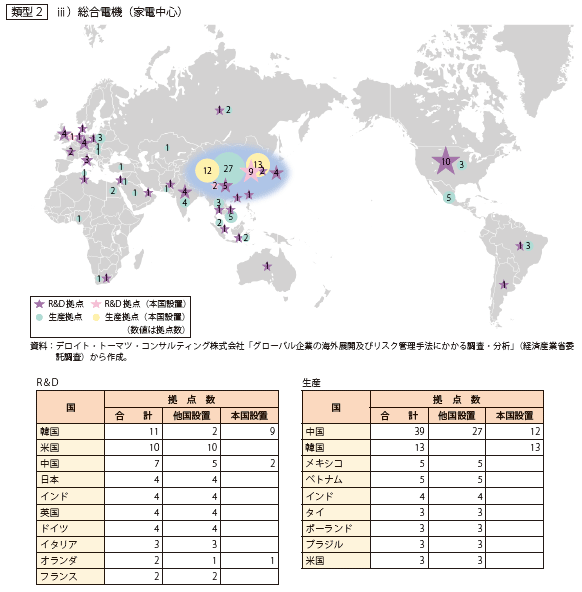
〈生産拠点〉
最適地生産が行われており、中国への設置が圧倒的に多く、続いてメキシコ、ベトナム、タイ等の新興国への設置が多く見られる(第Ⅱ-1-2-2-6表)。事業コストが立地選択の大きな要因となっており、日本においても足下の事業環境の改善を受け、一部の日本企業が生産拠点を国内に回帰させる動きも出ている67。
67 経済産業省、厚生労働省、文部科学省(2015)第1部第1章第2節「2. 事業環境の変化に対応した国内拠点の在り方」参照。
求められる製品・サービスの地域差は大きいものの、基礎技術・素材は共有化されている部分が多く、基礎研究や高付加価値品の生産拠点は個別要素の視点での立地から集約傾向、一方、応用研究や製品の組立て等は分散傾向が見られる産業である。
ⅰ)総合電機(重電中心)
〈R & D拠点〉
米国、ドイツなどの先進国への設置が多いが、それ以外の地域にも比較的分散して設置されている(第Ⅱ-1-2-2-7表)。高度な基礎技術、素材などが多いことから、R & Dは高い技術力を持った一部の国に集中している。それに加えて地域特性に合わせた展開を行うための応用R & Dがある程度分散して設置されていると見られる。
〈生産拠点〉
米国、フランス(他国設置分は2か所)、英国等、先進国への設置が多い。高機能製品の生産は技術の観点から、組立て等は事業コストの視点からの設置がなされていると考えられる(第Ⅱ-1-2-2-7表)。
第Ⅱ-1-2-2-7表 グローバル企業(総合電機 重電)の拠点設置状況
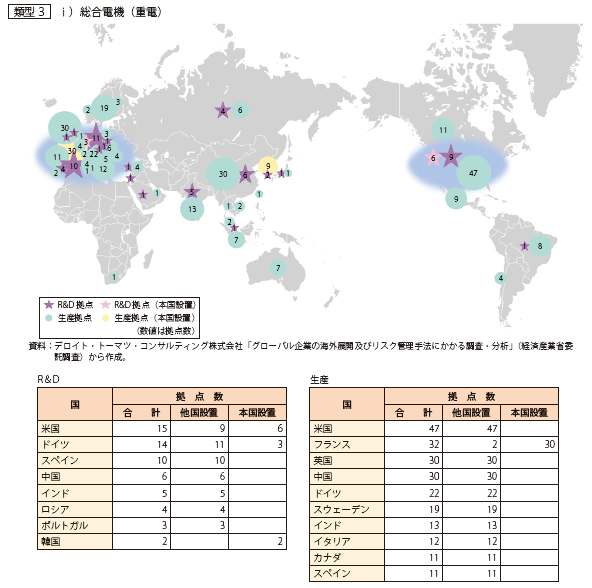
ⅱ)自動車
〈R & D拠点、生産拠点〉
いずれも自動車の市場が大きい、ドイツ、米国、中国に集中して設置されている。特に米国、ドイツは自国企業による設置が多く見られる68。自動車産業は、好まれる製品の地域差も大きく、関税対応や事業コストなどの観点から、地産地消が進んでいるものの、大規模市場で生産し、輸出対応するような最適地生産も進んでいる業種である(第Ⅱ-1-2-2-8表)。
第Ⅱ-1-2-2-8表 グローバル企業(自動車)の拠点設置状況
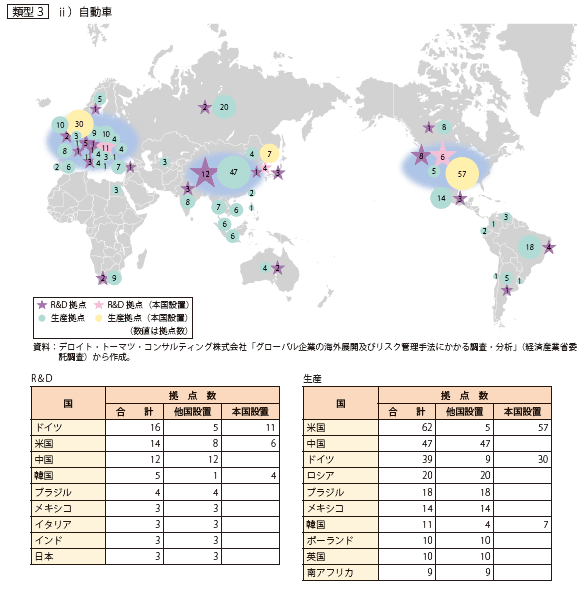
68 自動車産業については、日本の技術力が高く評価されている分野であり、R & D、生産拠点ともに日系企業による自国(日本)への立地が多くなされているが、ここでは他国のグローバル企業の設置動向を探る目的により、調査対象から日系企業を除いている。
ⅲ)化学
〈R & D拠点〉
米国が最多であるが、本国設置を除けば中国、日本、インドへの設置も多い(第Ⅱ-1-2-2-9表)。機能性化学産業69については、日本が競争力を保持している分野であり、その厚い技術基盤とすり合わせ能力といった個別要素を要因とするR & D拠点の立地がなされていることがうかがえる。
第Ⅱ-1-2-2-9表 グローバル企業(化学)の拠点設置状況
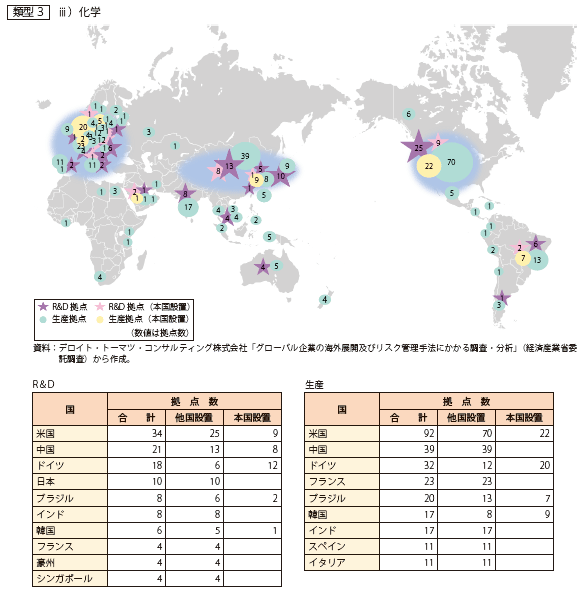
〈生産拠点〉
生産拠点は米国、中国に集中しているが、ドイツ、フランスにも多く設置されている(第Ⅱ-1-2-2-9表)。米国は近年、非在来型エネルギー革命を背景としたエネルギーコストの低下も求心力となっていると思われる。
②地域統括拠点
次に、地域統括拠点について整理する。
(a)設置の方針・重視される要件
ビジネス機能ごとに地域内の複数国を統一して指揮・管理する機能は保持している、また機能ごとの地域責任者が地域統括機能を果たしているなど、機能自体は存在するものの、法人形態の拠点という形はとらないとする方針も見られた。また、日本に対しては、中国と並び市場規模が大きいため、日本から他アジアを統括するというよりも、一国で一つの市場と捉えているとの方針が比較的多く出された。さらに拠点を設置する場合は、地域全体へのアクセスに優れている国、またシンガポールなど地域拠点への税の優遇措置70を採用している国に行うとの回答もあった(第Ⅱ-1-2-2-10表)。
第Ⅱ-1-2-2-10表 地域統括拠点の設置方針
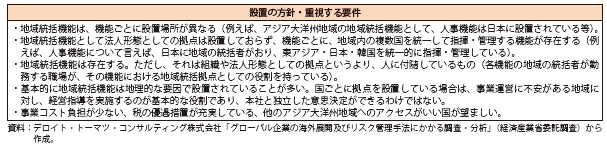
地域統括拠点は、あるビジネス機能拠点が兼ねている場合が多く、法人形態の拠点として設置する場合は、一般的な事業環境の優位性(税等のコスト要因、地理的要因等)が重視される傾向があると考えられる。
(b)実際の設置状況
地域統括拠点は、アジア大洋州地域ではシンガポールへの設置が圧倒的に多く、続いて中国に多いとの結果となった。米州地域では米国が最多であり、また欧州、中東及びアフリカ地域ではアラブ首長国連邦(UAE)、オランダ、ドイツ、スイスに設置している場合が多いとの結果が得られた(第Ⅱ-1-2-2-11表)。
第Ⅱ-1-2-2-11表 グローバル企業(全業種)の地域統括拠点設置状況
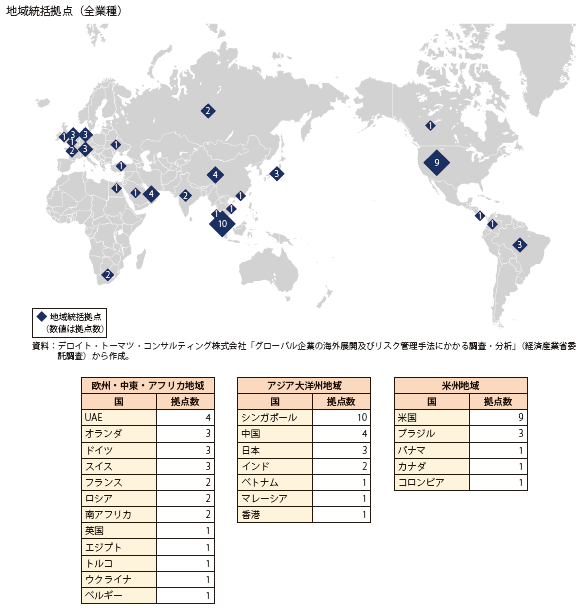
69 経済産業省(2013a)では「すり合わせにおいて、顧客ですら気づいていない潜在的な課題に対し、独自技術により材料に特殊な機能を持たせることで解決策を提案し、顧客の製品の付加価値向上を実現する化学産業」とされている。
70 シンガポールではアジア太平洋地域の統括拠点をシンガポールに置き、政府の認定を受けた企業に対して、税を軽減するインセンティブが実施されている。
③その他機能(物流機能、バックオフィス機能など)
以下、参考までにその他機能(物流機能、バックオフィス機能など)についても立地方針につき得られた情報を整理しておく(第Ⅱ-1-2-2-12表)71。
第Ⅱ-1-2-2-12表 その他機能拠点の設置方針
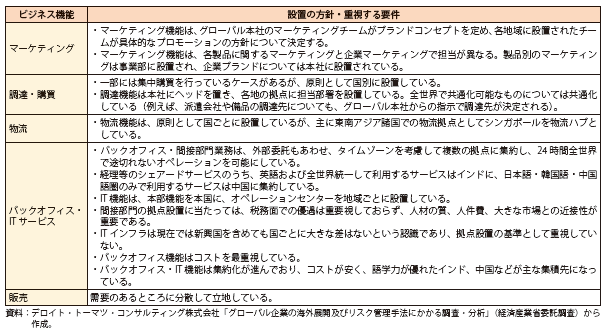
例えばバックオフィス機能は、地域や業種特性による差がほとんどなく、そもそも集約化される傾向にある機能であるが、その立地に当たっては、タイムゾーンを含む地理的要因、言語、コストなど、一般的な事業環境における優位性の視点が重視されていると見られる。また物流拠点も、国ごとの設置を基本にしながら、ハブ拠点への集約化も図られているが、ハブ拠点の立地に当たり、事業コスト、輸送インフラの整備状況、地理的アクセス等、一般的な事業環境における優位性が重視されていることがうかがえる。
71 評価に足る十分な情報を得られていないことには留意が必要である。
④グローバル企業の立地選択(まとめ)
以上見てきたように、グローバル企業のビジネス機能拠点は、機能や産業ごとに分布の傾向に特徴がある。グローバル企業は、一般的な事業環境の優位性及び個別要素(事業コスト、需要、規制要因、技術力、産業集積の状況など)を勘案しながら、ビジネス機能のみならず産業特性も踏まえて、戦略的に立地していることがうかがえる。
これを「選ばれる国」側の観点から見ると、我が国においては、新興国との事業コストの差が明らかな上に、近年の新興国の事業環境整備を受け、一般的な事業環境の優位性のみで、企業を呼び込むことは困難になっている。もちろん先進国においても一般的な事業環境の魅力がなければ企業を呼び込むことはできないが、高度な技術力・イノベーション力やハイレベル企業の集積等の個別要素の魅力・強みを国内に維持し、更に伸ばすことで勝負していくことが必要性であろう。
また、我が国においては「日本再興戦略」の中で「健康長寿産業」を戦略的分野の一つとして位置づけ、本産業の発展、強化に向けた政策が推進されている。2014年11月に再生医療分野の規制緩和72がなされたことを受け、複数の外資系企業が日本でのR & Dや我が国企業との提携等を検討しているとの報道もなされており73、今後我が国へR & Dを始めとするビジネスの参入が期待されている。適切な規制緩和により呼び込む力が高められることが示唆される。
72 2014年11月25日に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」が施行され、従来の医薬品、医療機器とは別に、「再生医療等製品」の分類が新たに設けられることとなった。その中で均質でない再生医療等製品については、有効性が推定され、安全性が認められれば、条件及び期限付で早期に承認される仕組みが導入された。また同時に「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」も施行され、再生医療に使う細胞の培養加工について、医療機関から企業への外部委託が可能となった。
73 日本経済新聞「再生医療薬、日本で開発」2015年1月26日より。
(3)日本の魅力と課題
ここでは、これまで述べてきたグローバル企業の立地行動にかかる理論、他国グローバル企業の実際の立地状況も踏まえ、日本の立地競争力、企業を呼び込む力について検証する。
まず、日本で事業を行う他国グローバル企業の声から、日本の魅力と課題を抽出する。次に、国際競争力指標を用いて、日本の総合的な事業環境の評価を整理する。続いて、日本の個別要素としての魅力と課題を各種指標、アンケート調査等を踏まえ考察することとする。
①日本で事業を行う他国グローバル企業の見方
日本に進出している他国グローバル企業約30社に「投資先としての日本に対する見方」につき、アンケート又はヒアリング調査74を行った結果を見てみる。
アンケート調査は、①市場の将来性、②参入規制の厳しさ、③技術力(研究開発力、製造技術等)、④産業集積の度合い、⑤規制の度合い(環境、労務等)、⑥人材の質(人材の気質、能力等)、⑦多言語による公共サービスの提供、⑧各種コスト、⑨優遇措置の充実度、の9項目につき4段階(1~4、数値が高い方がポジティブな見方)で日本を評価するよう設定した。その回答結果(第Ⅱ-1-2-2-13図)とヒアリング調査で出された企業からの指摘事項(第Ⅱ-1-2-2-14表)は以下のとおりである。
第Ⅱ-1-2-2-13図 他国グローバル企業による日本の評価
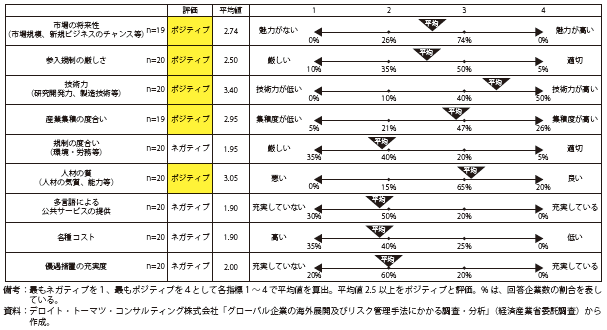
第Ⅱ-1-2-2-14表 他国グローバル企業による「投資先としての日本」の評価
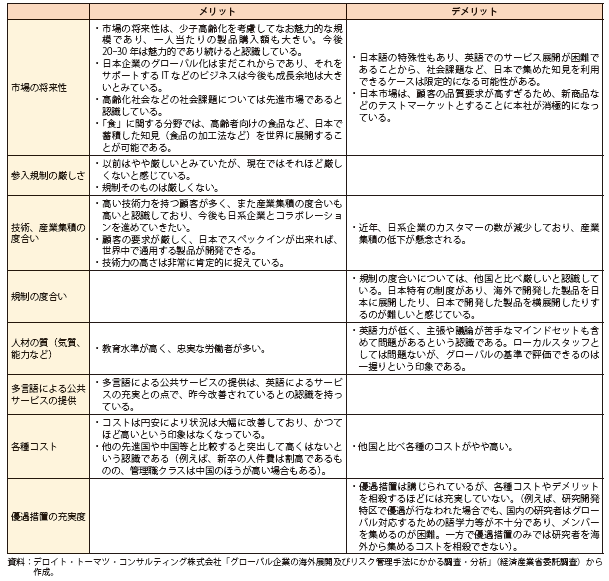
アンケート回答企業数が少ないことには留意が必要だが、他国グローバル企業が日本の魅力としてポジティブにとらえている項目として、「技術力」(平均値3.40)や「人材の質」(同3.05)、「産業集積の度合い」(同2.95)が挙げられる。また、将来の人口予測との関係から否定的な声も聞かれがちな「市場の将来性」(同2.74)についても、「魅力がない」と回答した企業はなく、比較的ポジティブにとらえられている。また、「参入規制の厳しさ」(同2.50)についても、参入規制そのものは厳しくない、以前に比べて改善しているとの声が出されている。
一方、「規制の度合い」(同1.95)、「多言語による公共サービスの提供」(同1.90)、「各種コスト」(同1.90)、「優遇措置の充実度」(同2.00)についてはネガティブな見方が多いとの結果が出された。ヒアリング調査においても「規制の度合い」については、「他国と比較して非常に厳しく、日本市場特有の制度・慣行等がある」との指摘がなされている75。しかしながら「多言語による公共サービスの提供」、「各種コスト」のように、アンケート調査ではネガティブな評価が出されているものの、ヒアリング調査では、近年改善しているとのポジティブな声が寄せられているものもあり、実際に日本で活動を行うグローバル企業が、日本の事業環境の改善を実感していることがうかがえる。
74 前述の経済産業省委託調査による。
75 内閣府(2014)において、日本特有の制度・慣行等(例えば日本独自の基準が要求される等)、様々な規制が企業活動を制約しているとする同様の指摘が外国企業等よりなされており、日本企業の低い収益性の背景の一つとして挙げられている。
②国際競争力指標から見た日本の現状
ここでは「国際競争力指標」を用いて、客観的な視点での我が国の評価を見ていく。一般的によく知られている、世界経済フォーラム(WEF: World Economic Forum)が発表している「国際競争力レポート」(Global Competitiveness Report)(以下、「WEFランキング」とする)と国際経営開発研究所(IMD: International Institute for Management Development)が発表している「世界競争力年鑑」(World Competitiveness Yearbook)(以下、「IMDランキング」とする)によるランキングを使用する。
WEF ランキング(2014-2015年)は144か国・地域を評価対象としており、評価項目数は111、そして国際競争力を「国の生産性のレベルを決定する諸要素」と定義している。他方IMDランキング(2014年)は60か国・地域を評価対象としており、評価項目数は338、そして国際競争力を「企業の力(競争力)を保つ環境を創出・維持する力」として捉えている76。この国際競争力指標は評価項目として、マクロ経済指標や法人税率のような一般的事業環境の優位性に関する項目と、企業集積、高度人材の存在やイノベーション力のような個別要素に関する項目が両方含まれている77。
WEFランキングの推移を見ると、日本は2012-2013年の10位を底に、2013-2014年9位、2014-2015年6位と足下で2年連続改善している。また、IMDランキングでも、日本の順位は2012年の27位から2013年24位、2014年21位と足下で2年連続上昇している(第Ⅱ-1-2-2-15図)。両者の順位は異なっているものの、我が国の国際競争力が改善している様子がうかがえる。
第Ⅱ-1-2-2-15図 国際競争力ランキングの各国推移(左:WEF、右:IMD)
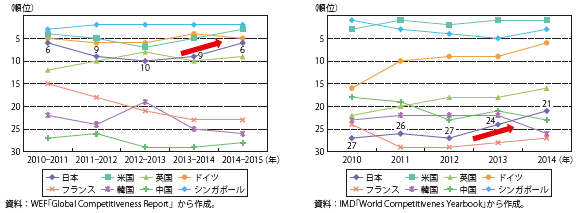
同時に、外国企業から見たアジアの投資先の関心度調査(第Ⅱ-1-2-2-16表)においても、日本がR & D拠点や販売拠点で1位に選ばれる等、投資先としての日本の魅力も向上していることが分かる。
第Ⅱ-1-2-2-16表 外国企業から見たビジネス機能拠点として最も魅力的なアジアの国・地域(R&D、地域統括、販売拠点)
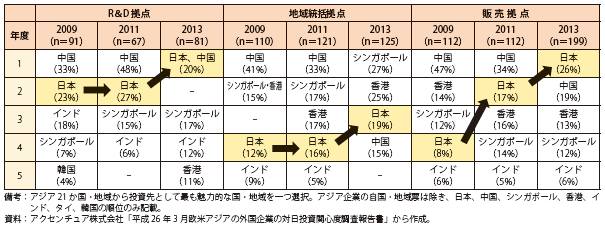
国際競争力ランキングの個別評価項目を見てみると、WEFランキングでは、日本は「ローカルサプライヤーの質、量」など、主に個別要素の項目からなる「ビジネス洗練度」が1位を継続しており、強みを持っていることが分かる。さらに足下で「制度」「インフラ整備」などを始めとする一般的な事業環境の優位性の観点が多く含まれる項目での改善も見られる。また、IMDランキングでは大項目である4部門のうち「政府の効率性」「ビジネスの効率性」及び「インフラ」の3部門で2012年以降順位を上げており、その下位評価項目においては、2年連続で順位が上昇している項目が20項目中12項目に及んでいる(第Ⅱ-1-2-2-17表)。しかしながら、IMDランキングにおける「基礎的インフラ」の評価項目の一つである「産業用電力コスト」については、2010年も45位と低位であったものの、2013年52位、2014年50位と近年では更に順位を落としており、我が国の国際競争力の低下圧力となっている。
第Ⅱ-1-2-2-17表 国際競争力ランキング個別項目順位の推移(左:WEF、右:IMD)
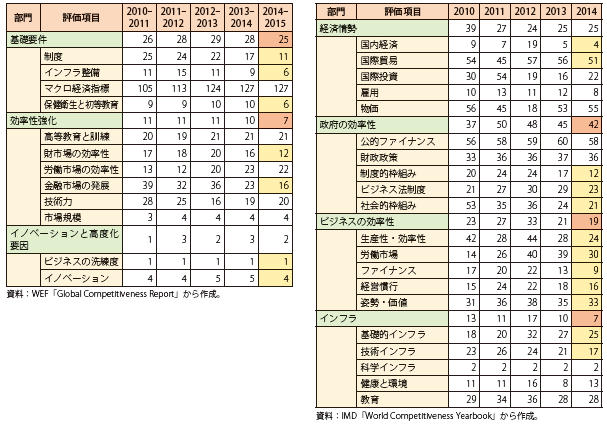
我が国の国際競争力ランキングは改善しているものの、各国政府も我が国と同様に事業環境整備等を通じて、立地競争力の強化を図っていることから、それに劣らないスピードで、引き続き対応、改善していくことが重要である。
日本のような先進国にとって個別要素の魅力が重要であることは言うまでもないが、一般的な事業環境の優位性が立地選択に与える影響も小さくないことが、昨今の事象からも確認される(コラム3)。
76 定義については小針(2013)の表現を引用した。小針は同ランキングの違いになどについても詳しくまとめている。
77 国際競争力については、その定義に加えて、各々の評価項目や基準が明確でないとの指摘もあるものの、内閣府(2004)「国の競争力は、世界市場に対して魅力のある財・サービス等の製品を提供し長期的に国民生活水準を向上していくような環境を国内の産業、企業に提供できるかどうかにかかっている。・・・国の競争力とは企業、産業レベルでの高い国際競争力を実現するような環境を提供しているかという点に依存し、これらが国全体としての高い付加価値生産性、生活水準の実現につながっていると考えられる。」との記述がよく整理されていると思われる。
③日本特有の魅力、強み
以上、国際競争力指標を整理し、我が国の国際競争力が改善している様子を見てきた。ここからは、アンケート調査で日本の魅力としてポジティブな評価がなされた「技術力」「産業集積の度合い」「人材の質」「市場の将来性」に焦点をあて、企業から出された指摘や各種指標を整理しながら、我が国の持つ魅力・強みとそれを更に伸ばすための課題について見ていく。
(a)技術力・産業集積の度合いについて
ヒアリング調査の中で、我が国企業の持つ高い技術力を評価する声や、そのような企業の集積が厚いことを肯定的に捉えている企業が多く見られた(前掲第Ⅱ-1-2-2-14表)。この「技術力」や「産業集積の度合い」は日本ならではの強みと認知されており、この個別要素を狙って投資を行う企業が少なくないことが示唆される。
実際に投資企業と我が国企業がお互いに持っている技術力をいかして共同でイノベーションを起こし、競争力のある製品を開発、世界に展開している例も見られる(コラム4)。
〈産業集積の度合い〉
産業集積を評価する声が出される一方、「ビジネスパートナーとして技術を持った日系企業が減っており、産業集積の低下を感じる」との厳しい見方も同時に示された。そこでWEFランキングの個別評価項目を使って、我が国の「産業集積力」及び「企業の持つ技術力」の評価を行う84。ここでは「産業集積」の力を①ローカルサプライヤーの量、②ローカルサプライヤーの質、③産業クラスター開発の状況、④バリューチェーンにおける存在感、⑤最新技術の利用、⑥地域競争の激しさの6項目で評価している。
2014年の日本、ドイツ、英国、米国を比較すると、日本は「最新技術の利用」において、米国、英国に後れをとっており、また「産業クラスター開発の状況」において、ドイツ、米国をやや下回るものの、全体的に見て、産業集積力は他国と比較して悪くないように見える。しかしながら、日本の状況を2006年と2014年の時系列で比較してみると、6項目中4項目で悪化が見られ、中でも、ローカルのサプライヤーの質と量の項目は共に水準の低下がうかがえる。「技術を持った日系企業のカスタマーが減っている」という企業の声を裏付ける結果とも言えよう(第Ⅱ-1-2-2-18図、第Ⅱ-1-2-2-19図)。
第Ⅱ-1-2-2-18図 産業集積関連指標の各国比較(2014年)
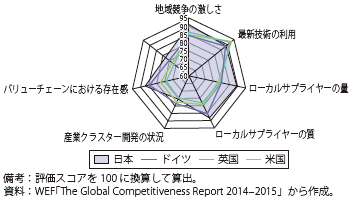
第Ⅱ-1-2-2-19図 日本における産業集積関連指標の推移(2006年、2014年)
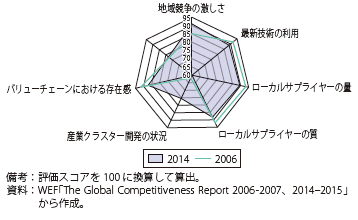
〈技術力〉
続いて、「企業の持つ技術力」について①イノベーション力、②製品・プロセスの差別化、③生産プロセスの洗練度、④企業による研究開発投資、⑤知的財産権保護の5項目で評価する。
2014年の日本、ドイツ、英国、米国を比較すると日本は技術力の評価は全般的に高いことが分かる。ただし「イノベーション力」だけは米国、ドイツに後れをとっており、更に日本を2006年と2014年の時系列で比較してみても、イノベーション力が低下していると評価されている(第Ⅱ-1-2-2-20図、第Ⅱ-1-2-2-21図)。イノベーションは競争力の源泉とも言えるものであり、成長戦略の最重要課題として取組が進められているところではあるが、企業を呼び込む力の向上のためにも、イノベーション力の引上げが求められる。
第Ⅱ-1-2-2-20図 技術力関連指標の各国比較(2014年)
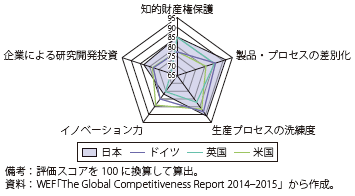
第Ⅱ-1-2-2-21図 日本における技術力関連指標の推移(2006年、2014年)
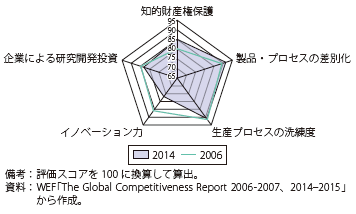
そこでイノベーション力に焦点を当てて見ていく。コーネル大学、インシアード経営大学院及び世界知的所有権機関(WIPO)が共同で発表している「技術革新力ランキング」は社会において適切にイノベーションが行われているかを捉えることを目的としている。我が国は2007年以降、順位を下げていたが、2013年22位、2014年は21位と2012年の25位を底に足下で改善している(第Ⅱ-1-2-2-22図)。
第Ⅱ-1-2-2-22図 世界技術革新力ランキングの各国推移
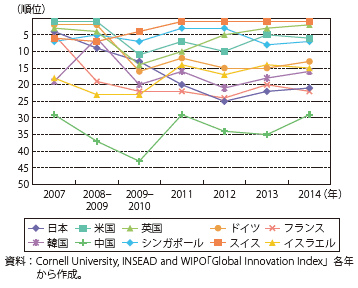
本指標の総合ランキングは、イノベーション活動を具現化する経済要素の観点であるインプット指標「制度」、「人的資本と研究」、「インフラ(社会基盤)」、「市場洗練度」、「ビジネス洗練度」と、イノベーション活動の結果であるアウトプット指標「知識・技術のアウトプット」、「創造的なアウトプット」の7分類からなる。
日本を見ると、インプットの項目である「研究開発」は6位と比較的高評価である。他方アウトプットでは「知識・技術のアウトプット」は12位とさほど悪くないが、「創造的アウトプット」は46位と弱く、中でも「無形資産の創造」は99位と低評価である。その中の下位評価項目である「ICTが新しいビジネスモデルを創出しているか」は2012年52位、2013年26位、2014年19位であり、「ICTが新しい組織モデルを創出しているか」の項目は2012年40位、2013年49位、2014年35位と改善傾向は見られるものの、更なる改善の余地も大いに残されていることが分かる(第Ⅱ-1-2-2-23表)。米国、ドイツに見られるように(第2章第1節参照)、自国の強みやイノベーション力をいかしたビジネスモデルの構築が、様々な生産要素、資本を引きつける磁力として重視されるようになっている昨今、日本において、ICTを通じた新しいビジネスモデル、新しい組織モデルを創出する力の向上が急務であることが示唆される。
第Ⅱ-1-2-2-23表 世界技術革新力ランキングの日本の評価
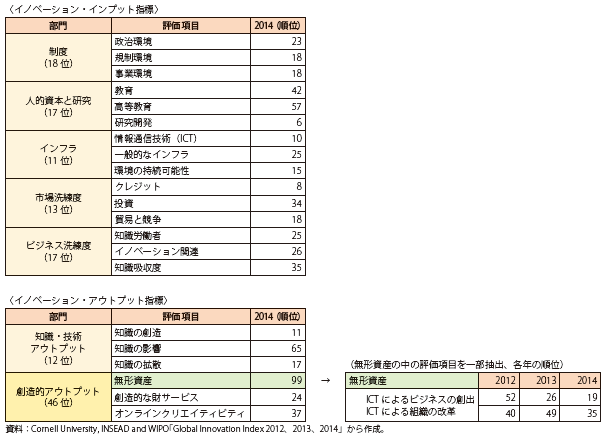
〈技術をビジネスに結びつける力〉
日本はR & Dに強みがあり、知識、技術のアウトプットは12位と比較的評価がなされているものの、創造的なアウトプットが弱く、ICTを使って新しいビジネスを創り出していくところに課題があることが示唆された。ビジネス創出の観点につき、IMDの個別指標を見てみる。
IMDでは「知識移転(企業と大学間で知識の移転がうまく行われているか、産学連携)」の評価項目の上位カテゴリーが、2004年から2014年の間に「教育」から「科学インフラ」に変更されており、産学連携が実践的なビジネスインフラとしての観点で捉えられるようになっている。しかし日本が比較的高い順位に位置する「科学インフラ」の中で、本項目は2004年23位、2014年24位と低評価となっている。
また、2004年から2014年の間に「公的、民間部門のベンチャー企業が技術開発を支えているか」との観点からの新項目が「技術インフラ」分野に追加される等、ベンチャー企業の存在が、技術、ビジネスを支えるためのインフラ基盤として重要性を増していることがうかがえる。この項目でも日本は2014年27位と改善の余地がある(第Ⅱ-1-2-2-24表)。
第Ⅱ-1-2-2-24表 IMDによる科学・技術インフラの評価(2004年、2014年)
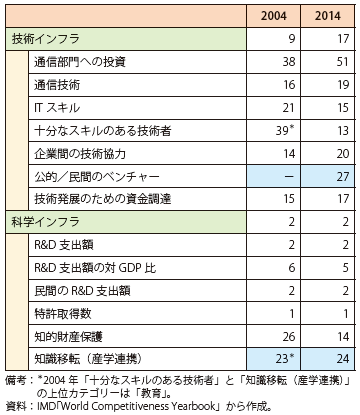
我が国は開廃業率が低く、ベンチャー企業が少ない、また市場経済において産業の新陳代謝が促されていない等の指摘85がこれまでもなされている。第Ⅱ-1-2-2-25図によると、2014年の18歳~64歳の人口に占める起業活動者86の割合は日本は3.8%と他国と比較してかなり低水準である。本割合は発表元87によると、各国の起業活動の活発さを表す代表的な指標とされており、我が国の起業活動が非常に低迷していることが見てとれる。
第Ⅱ-1-2-2-25図 起業活動者が18歳~64歳人口に占める割合の国際比較
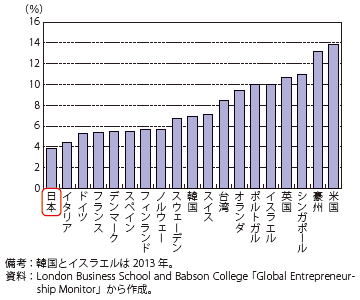
第Ⅱ-1-2-2-26図はその背景の一因と考えられるものである。いずれも18歳~64歳のうち、縦軸が「起業に必要な技術・知識を保持していると認識している割合」、横軸が「起業の機会があると認識しながらも、失敗に対する恐れから起業を躊躇(ちゅうちょ)するとした割合」、そしてバブルの大きさが「起業の機会に恵まれていると認識している割合」を示している。つまり、グラフの右下に行くほど、起業の知識・技術がないと認識しており、失敗を恐れる割合が高く、バブルが小さいほど、起業機会に恵まれていないと感じていることを表している。
第Ⅱ-1-2-2-26図 起業行動調査の国際比較
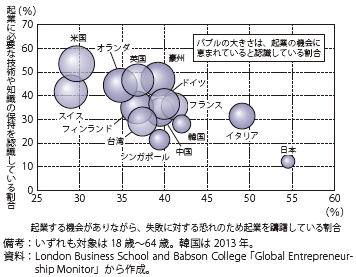
他国と比較して、日本は起業に必要な技術、知識を持っていないと感じており、かつ失敗を恐れる傾向から起業に踏み切れない割合が高い結果が見てとれる。特に米国とは起業をめぐるマインドセットが対極に位置していていることが分かる。日本のR & Dに対する支出額は国際的に見ても大きく、高い技術水準が評価されているにもかかわらず、それをビジネスとして効率的に活用できていないとの見方が示唆される88。
グローバル企業は、新しいビジネスモデルの創出を目指し、常にその種になる新しい技術やアイデアを求めており、それは日本への立地を検討する場合も同様である。特に米国企業の多くは、低コスト、低リスクでかつスピード感もあるとの認識から、積極的に社外の技術やアイデア、人材などの資源を有効活用するオープン・イノベーションを推進しており、ベンチャー企業の買収等を通じて、新技術やアイデアの事業化、ビジネスモデルの構築を図る傾向にある89。また新しいビジネスが次々と生まれ、それを目指した企業が世界中から集まってくることで、我が国においてもイノベーションが起こり、更にビジネスが拡大していく好循環も期待される。日本の呼び込む力を高めるためには、新陳代謝を高めるべく、新しい企業を次々に生み出していく環境整備が必要であることが示唆される90。
84 各評価対象項目の抽出については、経済産業省、厚生労働省、文部科学省(2013)及び株式会社三菱総合研究所(2013)の考え方を参考にした。
85 経済産業省中小企業庁(2014)での分析を始め、国際比較における我が国の開廃業率の低さは、これまでも幾度となく指摘されている。
86 起業活動者とは、起業における「誕生期」(独立・社内を問わず、新ビジネスを始めるための準備を行っており、まだ当該事業から報酬を受け取っていない又は受け取っている場合は3か月未満の人)と「乳幼児期」(既に起業しており、当該事業から報酬を受け取っている期間が3か月以上3.5年未満の人)と定義されている。
87 London Business School and Babson College “Global Entrepreneurship Monitor.”
88 高橋他(2013)は、日本の起業活動が不活発な原因は、起業態度を有しないグループが圧倒的多数を占めていることであり、起業態度を有しているグループにおける起業活動はむしろ活発であると指摘している。つまり日本においては、起業態度に働きかける政策、具体的には、身近な起業活動を知る機会を増やす、起業家というキャリアとしての選択肢を分かりやすく示す、起業家として必要な経験や能力を獲得させる、そして起業活動の経済社会における役割を教える等の起業家教育が効果的であると述べている。
89 McGrath, R.(2013)(鬼澤忍訳(2014))によると、デジタル革命、グロバリゼーションなどを背景に、業界が刻々と変化している昨今、持続する競争優位を持てる企業はなく、常に新しい戦略的取組を打ち出し、短期間の優位性を同時並行的に確立し活用していく必要があるとされており、外部資源の活用もそのための有効な戦略の一つとして挙げられている。
(b)人材の質
企業から出された、「教育水準が高く忠実な労働者が多い」との「人材の質」に対するポジティブな視点は、我が国の一般的な事業環境の優位性の一つと位置づけられよう。IMDの項目から見ると(第Ⅱ-1-2-2-27表)、我が国は識字率(1位)やPISA91の結果(5位)による評価が高く、日本人が高い教育水準を背景とした労働者であることが分かる。その一方で、国際経験を持ったシニアマネージャーの存在(59位)、海外への留学者数(52位)や英語の堪能さ(60位)といった国際感覚を養った人材という観点から見ると、非常に低評価にある。「英語力が低く、主張や議論が苦手であり、現地スタッフとしては問題ないが、グローバルの基準で評価できるのは一握りという印象である」といった企業のネガティブな見方が裏付けられた結果である。
第Ⅱ-1-2-2-27表 IMDによる人材関連項目の評価(2014年)
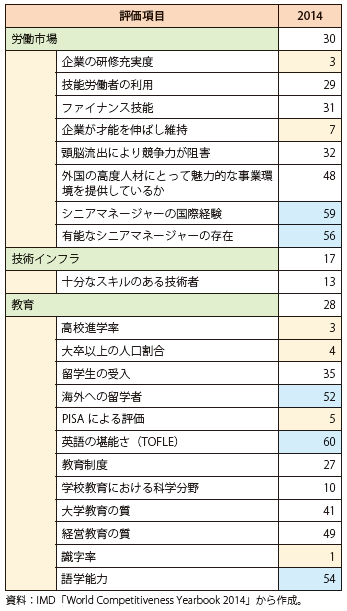
外資系企業調査(第Ⅱ-1-2-2-28図、第Ⅱ-1-2-2-29図)でも、我が国で事業展開する上での阻害要因に対する外資系企業の見方として「人材確保の難しさ」が上位から4番目に挙げられており、「人材確保の難しさ」の理由として、「英語でのビジネスの困難性」が「給与水準の高さ」とほぼ並んで大きな阻害要因となっている。日本が保持する個別要素の魅力が、外国語に堪能な人材が不足しているという一般的な事業環境に関わる点で劣位にあるため、十分にいかされていない懸念がなされる。
第Ⅱ-1-2-2-28図 日本で事業を展開する上での阻害要因
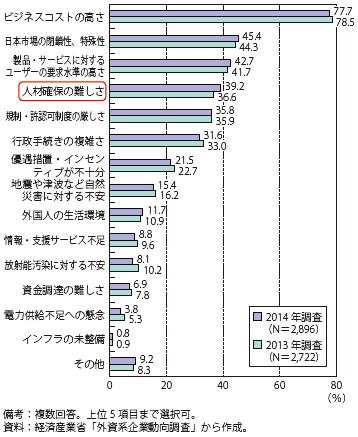
第Ⅱ-1-2-2-29図 人材確保上の阻害要因
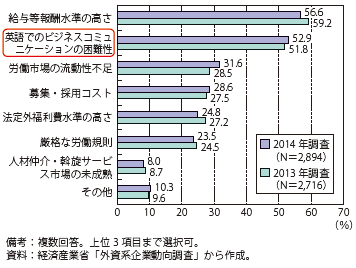
また、人材を一般的な事業環境の優位性の視点のみではなく、個別要素の観点で見ると、高度な専門技術・知識を身につけた人材(例えば高度IT人材等。以下「専門技術人材」とする)などは、呼び込む力の源泉となり得ると考えられる。例えば、インドには高い技術力を持ちながら、英語でコミュニケーションができ、コスト競争力もある厚い人材層が存在するが、一般的な事業環境の優位性と個別要素の強みが兼ね備わることで、グローバル企業がインドへのR & D拠点設置を加速させている背景となっている92。
一方、日本では博士課程卒業者93の割合がOECD主要国の中でも低位であり、専門技術人材の育成が不足している懸念がなされる(第Ⅱ-1-2-2-30図)。また、我が国の博士号取得者の就職先を見てみると、主要国の中で企業(Business enterprise)に就職する人の割合が低いことから、ビジネスの場における専門技術人材が少なく、イノベーションの創出・活用の基盤として活用されていない可能性も考えられる(第Ⅱ-1-2-2-31図)。
第Ⅱ-1-2-2-30図 博士課程卒業者割合の国際比較(2012年)
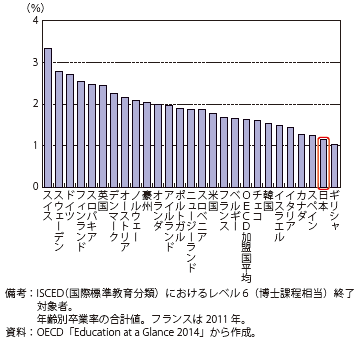
第Ⅱ-1-2-2-31図 博士号取得者の分野別就職先
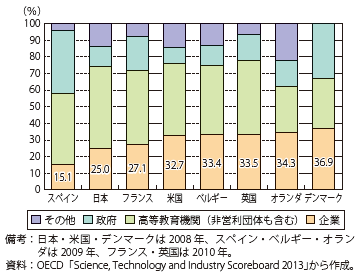
対内直接投資と専門技術人材94との関係については第Ⅱ-1-2-2-32図に見られるように、就業者数に占める専門技術人材の割合が大きいほど、対内直接投資のフロー額の対GDP比が大きい傾向が見られる95。日本においては、全就業者に占める専門技術人材の割合が他主要国と比較して低位にあり、高度な専門性を持った人材を育成、活用していくことも企業の呼び込み促進の方策として、重要であることが示唆される。
第Ⅱ-1-2-2-32図 対内直接投資フローの対名目GDP比と専門技術人材比率の関係
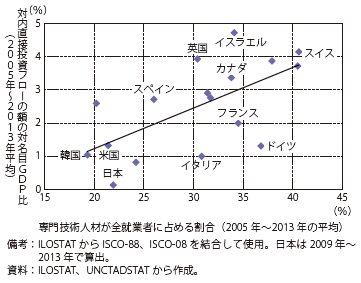
外国語教育に一層注力するとともに、知識基盤社会を多様に支える専門性の高い人材を育成していく、加えて海外の優れた人材を積極的に受け入れるための制度を一層周知・活用していくことも必要であろう。これらの点では、既に政策として推進している「グローバル人材」96の育成や、高度人材ポイント制を活用して、グローバルな高度人材の獲得競争に力を入れていくことが求められる。また同時に我が国ではIMDランキングの個別評価(前掲第Ⅱ-1-2-2-27表)で「外国の高度人材にとって魅力的な事業環境を提供しているか」との項目が48位と低位にあることから、事業環境自体を魅力あるものにしていくことも望まれる。
90 OECD(2013)においても、活力のある新規企業は雇用創出とイノベーションの重要な源であり、新規企業がマーケットに参入し成長するための環境を創り出すことが、日本にとって重要な課題であると指摘されている。
91 Programme for International Student Assessmentのこと。OECD加盟国を中心に3年ごとに実施される15歳児の学習到達度調査であり、主に読解力・数的能力・科学的能力などを測定する。
92 独立行政法人日本貿易振興機構(2014)によると、多国籍企業によるインド国内のR & D拠点数は2001年~2012年で約4倍に増加している。その要因として、英語能力や技術力が高い人的資源が豊富であること、コスト競争力があること、また潜在力の高い市場における事業機会の拡大を期待できること等を挙げている。
93 文部科学省、科学技術・学術審議会、人材委員会(2015)にて、博士号取得者は「広い教養と深い専門知識を持ち、かつ社会的課題の解決にその知識を活用できる人材として、その重要性が更に高まっている」とされ、その育成・確保、活躍促進が提言されている。
94 ここではILOSTATデータのISCO-88とISCO-08の「2. Professionalsと3. Technicians and associate professionals」を専門技術人材として算出。この分類の中には、科学技術分野の専門家のみならず、経営管理の専門技術人材なども含まれる。
95 服部、舘(2015)や内閣府(2008)のように、知識資本モデルを用いた推計結果から、日本への直接投資の水準が低い理由を他の先進国と比較して「専門技術及び管理者の比率が低いこと」と「投資コスト(投資先国の投資障壁)が高いこと」である可能性を指摘した実証研究結果も報告されている。さらに服部、舘は、日本の対内直接投資残高倍増のためには、日本の労働市場、教育制度改革を更に推し進める必要があると述べている。
96 文部科学省、産学連携によるグローバル人材育成推進会議(2011)では「世界的な競争と共生が進む現代社会において、日本人としてのアイデンティティを持ちながら、広い視野に立って培われる教養と専門性、異なる言語、文化、価値を乗り越えて関係を構築するためのコミュニケーション能力と協調性、新しい価値を創造する能力、次世代までも視野に入れた社会貢献の意識などを持った人間」とされている。
(c)日本「市場」が持つ魅力
2010年は1億2,806万人であった日本の人口は、2015年は1億2,660万人、2025年には1億2,066万人と徐々に減少が見込まれている上に97、近隣には成長市場である中国、ASEANを控え、一般的には市場に対する魅力がないと見なされがちである。
しかしながら上述したように、日本の「市場の将来性」について、ポジティブな見方をしているグローバル企業も多い(前掲第Ⅱ-1-2-2-13図、第Ⅱ-1-2-2-14表)。その具体的な声をまとめると、「一人当たりの購買力が高い」「高くてもよいものは購入する質の高い消費者が存在する」「洗練された消費者により高度化された市場が形成されており、そこへの参入によって自社の製品の競争力を向上させることが可能」「超高齢社会などの社会課題については先進市場」と、日本市場の特性を「強み」と評価している企業も多い。
富裕層98に限ってみれば、日本一国で2025年時点でもASEAN6、南アジアに遜色ない規模の層が存在する。こうした強みを認識し、少子化対策、マクロ経済パフォーマンスの更なる改善等に臨むことは、企業を呼び込む力向上の点からも必要とされよう(第Ⅱ-1-2-2-33図)。
第Ⅱ-1-2-2-33図 日本とアジア主要国の富裕層人口推計
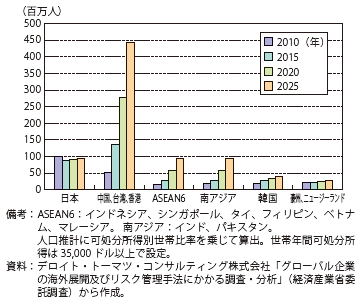
また、上記の見方に対し「日本市場は、顧客の品質要求が高すぎるため、新商品などのテストマーケットとすることに本社が消極的になっている」といったネガティブな指摘も見られたものの、要求水準の高い顧客の存在(洗練された消費者の存在)を利用して製品価値を高め、その世界展開により成功を収めている企業(コラム5)や、世界最速の高齢化社会、エネルギー制約など、弱みともとれる我が国の社会課題にビジネスチャンスを見いだし、積極的な取組を行っている企業(コラム6)も存在している。
日本の「市場」の特性に着目した強み・魅力を世界に発信していくことも必要である。
97 2010年は国勢調査結果、その他は国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口」(2012年1月推計)(出生中位、死亡中位)による。
98 富裕層は経済産業省(2013b)を参考に「世帯年間可処分所得35,000ドル以上」で設定。
99 高齢世代(シルバー)の生活の質を高め、幸せな輝かしい人生(ゴールド)を送れるようにしようとする同社の中長期戦略。
(4)まとめ
我が国は現在、「世界で一番ビジネスがしやすい国」を目指し、積極的な事業環境整備に取り組んでおり、足下の国際競争力ランキングにおいても改善が見られている。引き続きスピード感を持って立地競争力強化を推進し、更なる改善の継続を図っていくことが求められる。
我が国の「企業を呼び込む力」をグローバル企業の視点から検証すると、その高度な技術力、それら技術を持つ企業の集積等、個別要素の魅力が高く評価されており、R & D拠点や高機能品の生産拠点といった高い技術力を要するビジネス機能拠点の呼び込みに適した力を保持していると言えよう。2014年12月、米国グローバル企業による我が国への自国以外初のR & D拠点設置の発表や、2014年秋に実施された再生医療分野の規制緩和を受けて、外資系企業が我が国への進出を検討しているとの報道がなされていることから鑑みると、我が国の高い技術力を更に伸ばすことや、効果的な規制緩和等の政策が呼び込む力を高めることを示唆している。
他方、高い技術力の評価の裏で、我が国のイノベーションの創出力やその活用等においてはむしろ懸念される状況にあり、昨今、米国やドイツに見られるような自国の強みや革新的技術を基にした画期的なビジネスモデルの構築に積極的に取り組んでいる他先進国の潮流に乗り遅れているのではないだろうか。卓越した技術力、人材、購買力といった外国企業から見た我が国の強みを最大限いかし、更に伸ばすとともに、新しいビジネスが次々と生まれ、それを目指した企業が世界中から集まってくることで、新たなイノベーションが起こり、更にビジネスが拡大していくような仕組み作りを早急に行っていくことが必要である。持続可能な立地競争力の確立は、事業コストの引下げに加えて、それ以外の事業環境面での強みを確固たるものとし、いかにうまく活用するかによって決まると言っても過言ではないであろう。
また、企業を呼び込む力は、新たな領域へと広がりを見せていることにも留意が必要である。例えば、エストニアでは、ICチップを搭載した国民IDカード等の利用を通じて、行政サービスのみならず、幅広い民間サービスを受けられる電子化を実現している。同国では、現在、官民合わせて約3,000ものサービスがデータ管理基盤であるプラットフォーム上で提供されており、このようなデータプラットフォームの存在が、企業のビジネスチャンスとなり、呼び込む力になっているとの見方もできる。さらに世界で初めて「e-Residency(電子居住)」を開始し、非在住の外国人にもIDカードの配布を行うことで、世界中どこからでも銀行口座の開設や納税オンラインなどの電子サービスへのアクセスが可能となり、居住していなくても同国で起業、会社運営が行える仕組みを創設した。この仕組みは起業家を呼び込む力となり、そこで様々なイノベーションが起こり、そこからまた新たなビジネスモデルが誕生するとの好循環も期待されている。IT化の進展に伴い、従来では予想もしづらかった領域まで、ビジネスのプラットフォームと認識されるに至っている。企業を呼び込む力をめぐる国際競争が一層の広がりを見せていることの証左であろう。
これらのビジネスモデルを可能にするイノベーションの創出、活用力と並んで重要と考えられる人材の質を見ると、我が国ではビジネスを英語で行う力に乏しい人材が多く、技術力などの強み、魅力が国際ビジネスの場で十分にいかされていない可能性がある。さらに呼び込む力に必要とされている専門性の高い人材層が薄いことも懸念される。近年、高度人材の獲得競争は激しくなっており、我が国もこの競争に乗り遅れることなく、高度人材の育成とともに、高度人材ポイント制を活用して、呼び込む力の強化を図っていくことが喫緊の課題であると言える。