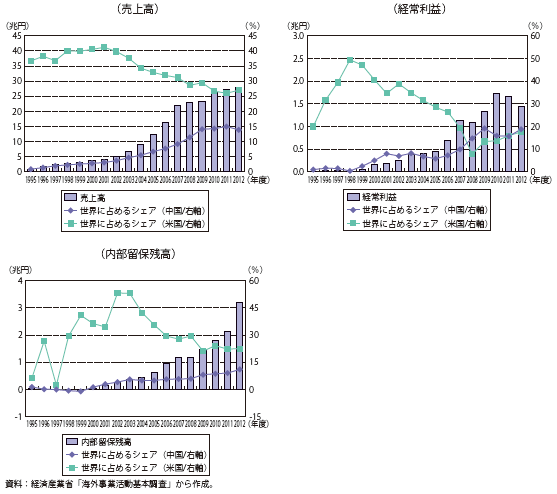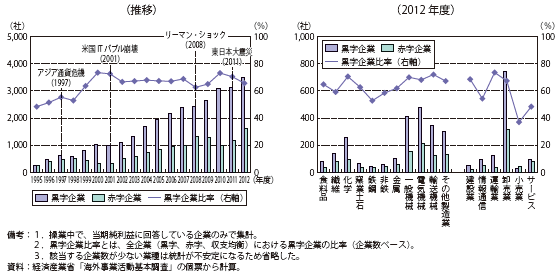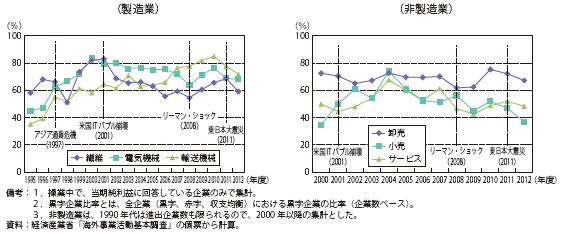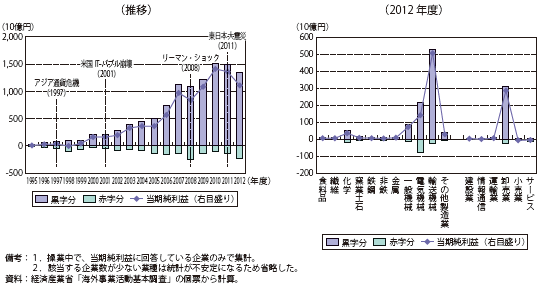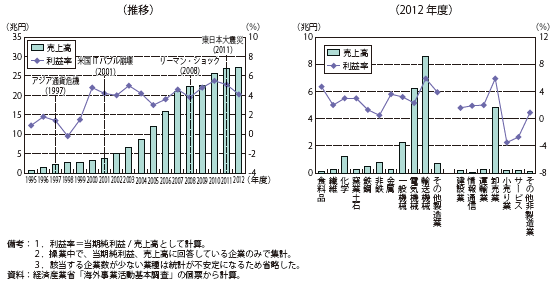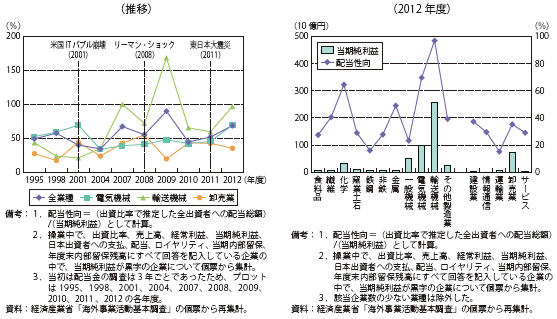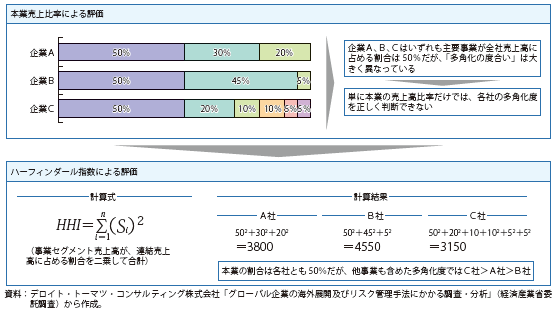第3節 「外で稼ぐ力」の検証
1.海外での「稼ぎ方」の変化と実態
(1)日本企業の事業活動拠点
①国内に立地している企業と海外現地法人
我が国企業の海外展開のもと、日本企業はどこで製品・サービスを売り、どこで利益を稼いでいるのだろうか。事業活動における国内拠点と海外拠点の重みの変化を見てみる。
我が国企業を国内に立地している企業と海外現地法人に分けて、事業活動の基本である売上について動向を見ると、2000年代、少なくともリーマン・ショックまでどちらも売上額を拡大している。しかし、国内に立地している企業に対する海外現地法人の比率(以下では「海外比率」と表記)は緩やかに上昇している(第Ⅱ-1-3-1-1図)100,101,102,103。リーマン・ショック後、海外比率は一時的に低下したものの、再び上昇する兆しを見せている。
第Ⅱ-1-3-1-1図 国内に立地している企業と海外現地法人の売上高の推移
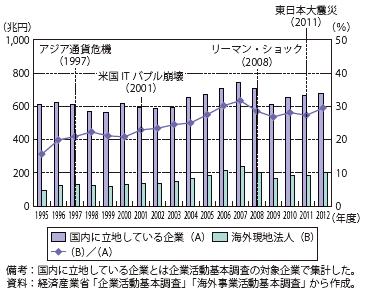
経常利益の推移を見ると、売上と同様に、国内に立地している企業、海外現地法人ともに利益額を拡大しているが、2000年代、海外現地法人の方が急速に拡大しているため、海外比率は上昇している(第Ⅱ-1-3-1-2図)。この傾向はリーマン・ショック後も続いていたが、東日本大震災後は落ち込んだ。
第Ⅱ-1-3-1-2図 国内に立地している企業と海外現地法人の経常利益の推移
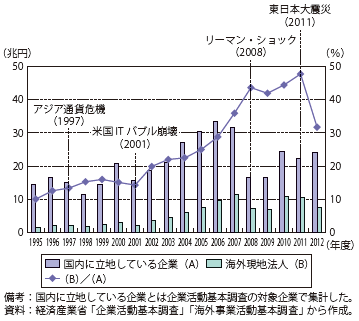
利益の蓄積である内部留保残高を見ても、2000年代、リーマン・ショックまで国内に立地している企業、海外現地法人ともに増加したが、上昇のペースは海外現地法人の方が早く、海外比率は急速に上昇している(第Ⅱ-1-3-1-3図)。
第Ⅱ-1-3-1-3図 国内に立地している企業と海外現地法人の内部留保残高の推移
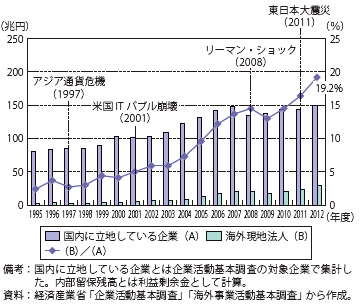
これまで見てきた、売上、経常利益、内部留保残高の海外比率は、1995~2012年度の間に、売上で2倍、経常利益で3倍、内部留保残高では8倍に拡大している。特に、利益や内部留保残高において、海外で利益を稼ぎ蓄積する傾向が強まってきている(第Ⅱ-1-3-1-4図)。
第Ⅱ-1-3-1-4表 海外現地法人の国内に立地している企業に対する比率
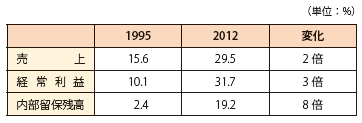
100 国内に立地している企業には、海外現地法人を有する企業及び有しない企業の両者を含む。国内に立地している企業は経済産業省「企業活動基本調査」、海外現地法人は「海外事業活動基本調査」を利用した。両統計とも企業の連結決算でなく単体決算で集計されており、子会社との連結分を除いた本社企業単体の動向を分析することができる。その調査対象企業には、業種、規模、出資比率等に相違はあるものの、両統計を比較して時系列の変化を見ることが出来る。
101 「企業活動基本調査」の調査対象は、国内に立地している、製造業、卸売業、小売業、一部のサービス業等に属する、従業員50人以上かつ資本金3,000万円以上の会社。「海外事業活動基本調査」の調査対象は、海外に現地法人を有する、金融業、保険業、不動産業以外の日本企業。この場合の海外現地法人は日本側出資比率が10%以上の外国法人(子会社)等を指す。本社企業に対して、調査書類を配付し、本社企業及び現地法人両方についてのデータを回収する。本社への発送数8,662社、回収6,615社で回収率は76.4%(2012年度実績に関する調査)。
102 同じ期間に日本企業の海外展開が進行し、海外現地法人は企業数ベースでも増加しており、海外比率は12.4%から18.6%に上昇している。
103 本節において「企業活動基本調査」、「海外事業活動基本調査」とも最新である2012年度までの実績を利用する。一部のデータについて2013年度速報が公表されたものもあるが、個票を含めた大半のデータが2012年度実績までしか利用できないためである。
②国内に立地している企業における相違
次に、国内に立地している企業の中で、海外に展開している企業、ここでは海外現地法人を有している企業(仮に「海外進出企業」)とそれ以外の企業に分けて、業績に相違があるかを見てみる104,105。まず、売上については両者とも緩やかに拡大しており、明らかな相違はないように見える(第Ⅱ-1-3-1-5図)。
第Ⅱ-1-3-1-5図 国内に立地する企業のうち、海外進出企業とそれ以外の企業(売上高)
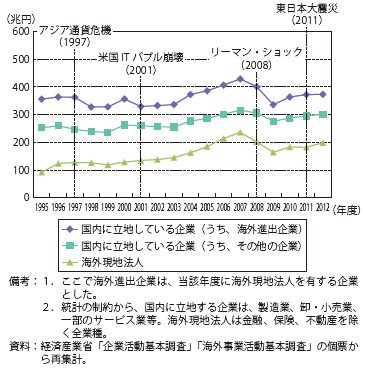
しかし、経常利益を見ると、リーマン・ショックまでの2000年代、海外進出企業の利益額の拡大が著しい一方、その他の国内に立地している企業の利益は拡大しているものの、緩やかなペースにとどまっている(第Ⅱ-1-3-1-6図)。ただし、リーマン・ショック後は海外進出企業の利益額は一旦大きく低下し、2012年度時点で回復に向かっているところである。
第Ⅱ-1-3-1-6図 国内に立地する企業のうち、海外進出企業とそれ以外の企業(経常利益)
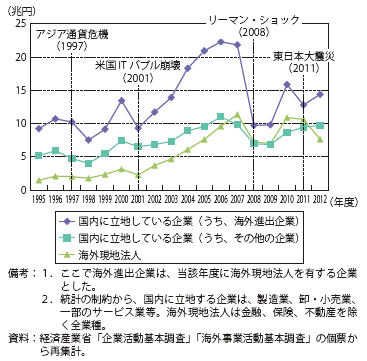
このような経常利益の差が広がった背景のひとつとして、主要な業種構成の相違が考えられる。海外進出企業は、輸送機械、化学、一般機械、電気機械等の製造業を中心に、経常利益を急速に拡大したが、その他の国内に立地している企業は、卸売業、小売業、サービス業、ソフト・情報処理等の非製造業を中心に経常利益が拡大している(第Ⅱ-1-3-1-7図)。
第Ⅱ-1-3-1-7図 主要業種別経常利益の推移
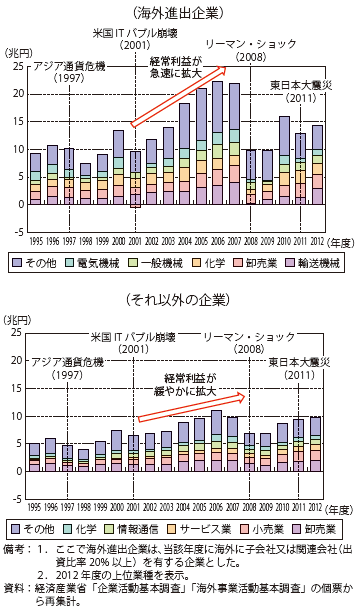
このような経常利益の拡大の下で、利益の蓄積としての内部留保残高も、海外進出企業の方がその他の国内に立地している企業よりも高水準で推移している(第Ⅱ-1-3-1-8図)。
第Ⅱ-1-3-1-8図 国内に立地する企業のうち、海外進出企業とそれ以外の企業(内部留保残高)
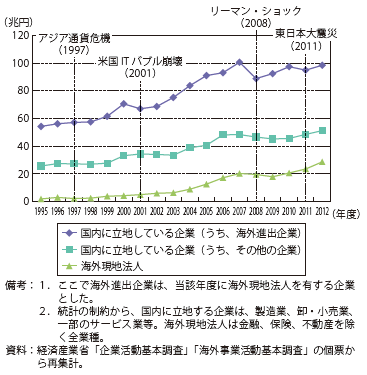
104 海外進出企業とは、国内に立地する企業のうち、当該年に海外に現地法人を有する企業。具体的には、「企業活動基本調査」において、海外に子会社(出資比率50%~)又は関連会社(同20%~50%)を有する企業を集計。なお、「海外事業活動基本調査」では、日本側出資比率10%以上を対象としているため、両統計で多少のずれが生じる。
105 海外に現地法人を有していなくとも、直接・間接に輸出に携わり海外ビジネスに関係する企業も存在するが、ここでは便宜的に海外現地法人を有するかどうかで海外進出の程度を分けた。多国籍企業の例と言える。
③海外における展開
それでは、我が国の海外現地法人は、どの国に展開しているのか、あるいはどの業種が事業を拡大しているかを見てみる。2000年代初頭、海外現地法人の立地国としては、米国が売上、経常利益、内部留保残高のいずれの面から見ても圧倒的に大きかったが、中国を始めとするアジア新興国・地域等が次第に存在感を増してきている(第Ⅱ-1-3-1-9図、第Ⅱ-1-3-1-10図第Ⅱ-1-3-1-11図)。特に、リーマン・ショック後、米国に立地する海外現地法人の業績が悪化し、売上高も低下したが、経常利益はそれ以上に落ち込みが大きく、中国に立地する海外現地法人の経常利益が米国のそれを上回ることとなった。ただし、過去からの利益の蓄積である内部留保残高は、依然として米国が大きく、中国、タイ、豪州、ブラジル等はほぼ同額で推移している。中国は売上で米国に迫ってきているものの、内部留保残高については依然としてその差は大きい。
第Ⅱ-1-3-1-9図 日系海外現地法人の売上高(立地国・地域別)
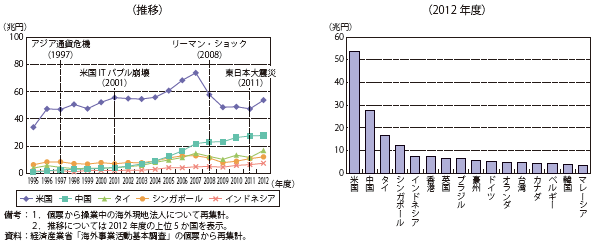
第Ⅱ-1-3-1-10図 日系海外現地法人の経常利益(立地国・地域別)
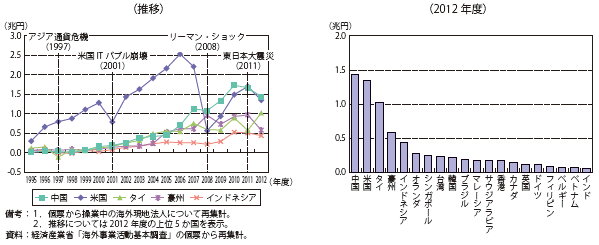
第Ⅱ-1-3-1-11図 日系海外現地法人の内部留保残高(立地国・地域別)
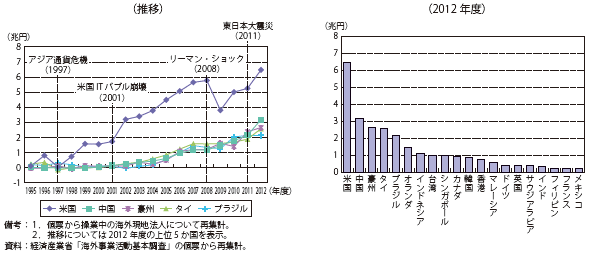
2012年度時点の売上、経常利益、内部留保の上位国・地域を見ると、米国を筆頭に、アジアの中国、タイ、シンガポール、インドネシア等のアセアン、韓国、台湾、香港、豪州等が上位に並び、欧州では、オランダ、英国等、中南米ではブラジル等が日系海外現地法人企業の主要な展開先に挙げられる。
海外現地法人の業種別動向を見てみる。まず、製造業については、売上高で電気機械及び輸送機械の2業種が圧倒的に大きかったが、2000年代、リーマン・ショックまで、電気機械が緩やかな伸びにとどまる中で、輸送機械が急速に拡大した106(第Ⅱ-1-3-1-12図)。また、化学、一般機械等も緩やかに拡大してきた。2008年のリーマン・ショックでは各業種とも売上高の減少を余儀なくされたが、その後緩やかな回復に向かっている。経常利益も基本的に同様の傾向が見られ、輸送機械が大きいが、化学の存在も大きく、電気機械を上回って推移している(第Ⅱ-1-3-1-13図)。内部留保残高の場合もほぼ同じ傾向となっている(第Ⅱ-1-3-1-14図)。非製造業に目を向けると、卸売業が売上高、経常利益、内部留保ともに圧倒的に大きいが、売上高を見ると、小売業、運輸業、サービス業、情報通信業等が、規模はまだ小さいものの、緩やかに拡大している。鉱業はやや特殊で、売上高は卸売業を下回るものの、経常利益はリーマン・ショックまでに卸売業とほぼ同水準にまで急拡大し、リーマン・ショック後は急減少している。2012年度の内部留保残高は、製造業4割、非製造業6割と非製造業の方が大きく、製造業の中では、輸送機械が大きく、一般機械、化学、電気機械が続いている。非製造業では、卸売業が大きく、鉱業、サービスが続いている(第Ⅱ-1-3-1-15図)。
第Ⅱ-1-3-1-12図 日系海外現地法人の売上高の推移(主要業種別)
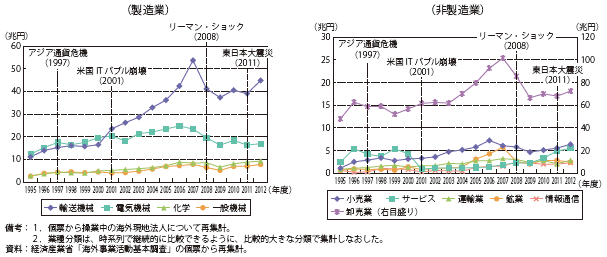
第Ⅱ-1-3-1-13図 日系海外現地法人の経常利益の推移(主要業種別)
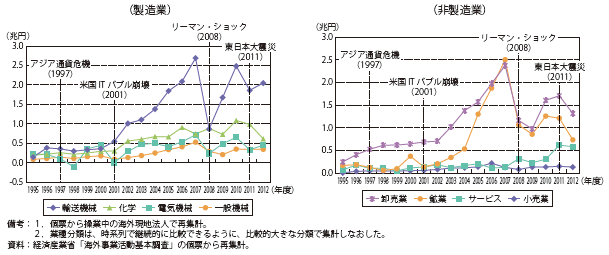
第Ⅱ-1-3-1-14図 日系海外現地法人の内部留保残高の推移(主要業種別)
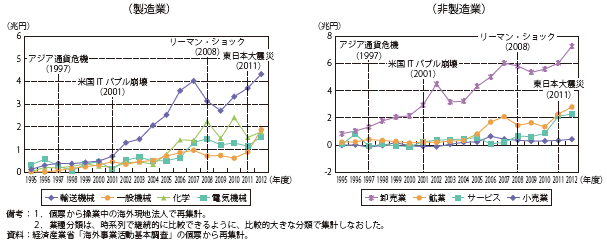
第Ⅱ-1-3-1-15図 日系海外現地法人の内部留保残高(業種別/2012年度)
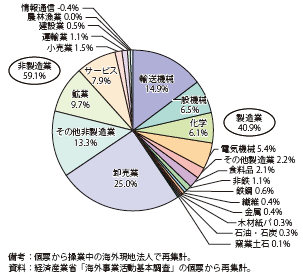
ここで海外現地法人の業種について、日本にある本社と異なることがある点には注意が必要である。例えば、日本国内では製造業を営んでいる企業が、海外に製造業の企業だけでなく、日本からの完成品の輸入販売、製品の保守・点検等のメンテナンス、現地市場に適合した商品開発のための研究開発等を行う現地法人を設立することがある107。これは国内でも起こり得ることで、いわゆる製造業のサービス化の例とも言えるが、このような場合、本社と海外現地法人の業種が一致せずに、対応関係が見えにくくなる。特に本節では、海外現地法人から本社への配当・ロイヤリティの分析を行うため、本社の連結決算に表れる業種別の動向と相違が生じるおそれもある。そこで、本社の業種区分で集計した結果も参考に併記しておく。
海外現地法人の売上高、経常利益、内部留保残高を日本にある本社企業の業種区分で再集計したのが第Ⅱ-1-3-1-16図~第Ⅱ-1-3-1-19図である。本社の業種区分で集計した方が、輸送機械、電気機械、一般機械等の製造業売上高は増額となり、卸売、小売、サービス業等の非製造業は減額となっている(第Ⅱ-1-3-1-16図)。これは製造業が海外展開する際に、流通やサービス関係にも手を広げていることを示唆している。
第Ⅱ-1-3-1-16図 日系海外現地法人の売上高の推移(本社の業種別)
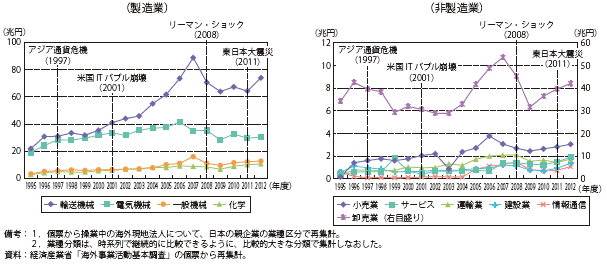
経常利益も同様に、輸送機械、電気機械、一般機械等は増額となり、小売、サービス業等は減額となっている(第Ⅱ-1-3-1-17図)。ただし、卸売業の経常利益は2000年代半ば以降増額している。
第Ⅱ-1-3-1-17図 日系海外現地法人の経常利益の推移(本社の業種別)

内部留保についても同様の傾向が見られる(第Ⅱ-1-3-1-18図)。2012年度末の内部留保残高は、現地法人の業種別には、製造業4割、非製造業6割であったが、本社企業の業種別には、製造業6割以上、非製造業4割以下と逆転する(第Ⅱ-1-3-1-19図)。
第Ⅱ-1-3-1-18図 日系海外現地法人の内部留保残高の推移(本社の業種別)
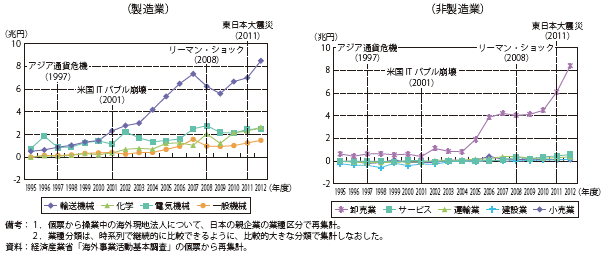
第Ⅱ-1-3-1-19図 日系海外現地法人の内部留保残高(本社の業種別/2012年度)

本社企業、現地法人の業種別の関係を分かりやすく表示したのが第Ⅱ-1-3-1-20図である。本節では海外での利益に関心が高いので、特に2012年度の経常利益について表示した。縦軸は現地法人の業種別経常利益、横軸は本社企業の業種別に見た経常利益が表示されている。本社企業と同じ業種に属する現地法人の経常利益が大きいものの、本社とは異なる業種の現地法人の利益も少なくない。特に、現地法人の卸売業の場合、本社企業も卸売業であるものは全体の半分以下であり、むしろ輸送機械、一般機械、電気機械等の占める割合が大きい。一方、本社が卸売業の場合、様々な分野の現地法人を設立しており、特に鉱業分野での利益が大きい。
第Ⅱ-1-3-1-20表 日系海外現地法人の経常利益(本社企業・現地法人の業種別 / 2012年度)

106 「海外事業活動基本調査」における業種区分は調査年によって改定されることがある。ここでは、時系列で統計を継続的に見ることができるように、便宜的に比較的大きな括りで業種区分を設定して個票から再集計した。製造業は13業種(食料品、繊維、木材紙パ、化学、石油・石炭、窯業土石、鉄鋼、非鉄、金属、一般機械、電気、輸送機械、その他製造)、非製造業は9業種(農林漁業、鉱業、建設、情報通信、運輸、卸売業、小売業、サービス、その他非製造)とした。このため、最新の調査で、はん用機械、生産用機械、業務用機械と分かれているのは「一般機械」、電気機械、情報通信機械は「電気機械」として集計した。
107 一つの現地法人が複数の業種にまたがる事業を行う場合も、業種別に複数の現地法人を設立する場合もある。1社で複数の事業を行う場合、統計上は便宜的に最も売上高の大きな業種を当該企業の業種としている。
④その他
これまで、売上、経常利益、内部留保を見てきたが、他の項目についても見ておく。まず、雇用関係では、従業員数は国内、海外ともに増加しているが、海外現地法人が国内に立地している企業を上回るペースで増加しているため海外比率は上昇している(第Ⅱ-1-3-1-21図)。国内に立地している企業の中では、海外現地法人を有しない企業が従業者を拡大している。海外進出企業も、リーマン・ショック等の際には従業員減少を余儀なくされているが、傾向としては緩やかなペースながら従業者を拡大している。
第Ⅱ-1-3-1-21図 国内に立地している企業と海外現地法人の従業員数の推移
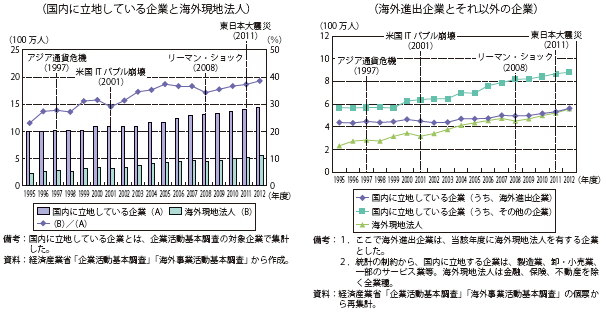
企業が支払っている給与総額は、国内に立地している企業は2000年代ほぼ横ばいなのに対して、海外現地法人は従業者数増加等のため給与総額は増加している(第Ⅱ-1-3-1-22図)。国内に立地している企業の中では、海外現地法人を有しない企業は長期的にほぼ横ばいで推移している。海外進出企業は2004年をピークにやや低下してきたが、リーマン・ショック後は反転している。海外現地法人は、日本との賃金水準に相違があるため給与総額としては低いが、従業者数の増加等を背景に緩やかに増加している。
第Ⅱ-1-3-1-22図 国内に立地している企業と海外現地法人の給与総額の推移
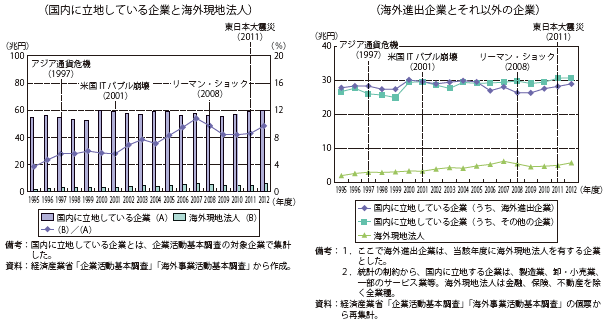
それでは海外現地法人は海外のどこで従業者を増やしているかを見ると、中国における従業者数が急速に拡大している(第Ⅱ-1-3-1-23図)。一方、給与総額については、給与水準の相違から米国が圧倒的に大きい。ただし、中国が従業者数、給与水準の上昇を背景に給与総額を上昇させている。
第Ⅱ-1-3-1-23図 海外現地法人の立地国別の従業者数・給与総額の推移
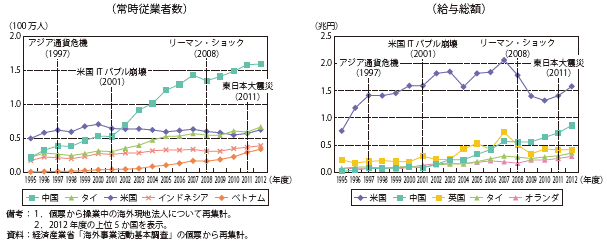
研究開発については、依然として国内に立地している企業の比率が高く、その中でも特に製造業を中心とした海外進出企業が圧倒的な割合を占めている(第Ⅱ-1-3-1-24図)。しかし、海外現地法人における研究開発支出も着実に拡大してきている。立地国としては、米国が大きいが、中国、韓国等が拡大してきている(第Ⅱ-1-3-1-25図)。
第Ⅱ-1-3-1-24図 国内に立地している企業と海外現地法人の研究開発の推移
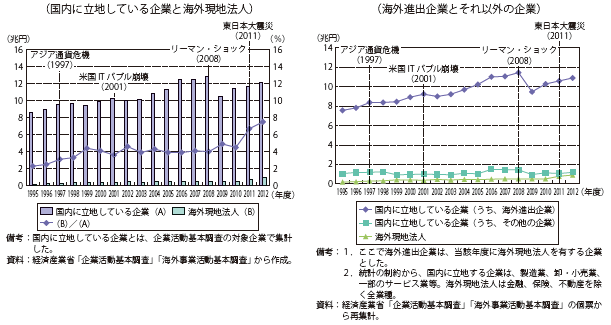
第Ⅱ-1-3-1-25図 海外現地法人の立地国別の研究開発の推移
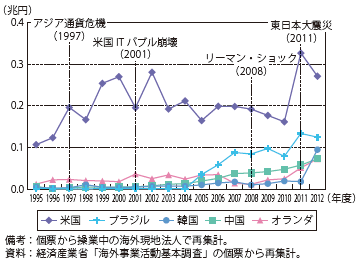
(2)日本企業の収益構造の変化
①輸出、配当金、ロイヤリティの推移
それでは、このように海外で稼ぐ比重が高まる中で、国内に立地している企業はどう稼いでいるのかを考えてみる。特に、海外現地法人を有する企業は、本社企業と海外現地法人との関係をどう活用しているのかに着目してみる。
日本に立地している本社企業の収益を海外現地法人の側から見ると、①日本からの資材調達(日本の輸出)、②日本向け配当金支払(国際収支の所得収支の一項目)、③日本向けロイヤリティ支払(サービス収支の一項目)等に分けることができる108。リーマン・ショック等の経済的なショックの際に一時的な減少はあるものの、いずれも金額ベースで増加してきている109(第Ⅱ-1-3-1-26図)。一方、3者の比率を見ると、依然として日本からの資材調達が大きな割合を占めており、海外現地法人が事業を展開するに当たって、日本からの基幹部品等の供給が重要な役割を果たしていることを示唆している。しかし、配当金、ロイヤリティの比率も拡大し、世界で稼ぐ傾向も顕著になってきている110。
第Ⅱ-1-3-1-26図 海外現地法人(製造業)の日本との取引

108 日本にある企業の側から見れば、海外現地法人以外の相手との取引もあるが、ここでは海外現地法人を設立して海外展開したことの影響に着目して分析する。また、国・業種別の相違、企業の規模、売上、利益等の企業要因との関係も分析する。
109 資材調達額については、統計の関係で親会社を含めた日本からの調達総額でプロットしてある。その中で親会社からの調達額は約9割(2012年度)を占める。
110 本節では、国別・業種別に企業の売上、利益、配当、ロイヤリティ等の動きを見るため、経済産業省「海外事業活動基本調査」のデータをもとに分析していく。「海外事業活動基本調査」と「国際収支統計」とは、統計の定義や対象が異なるため、ずれが生じることがある。例えば、配当金の場合、「国際収支統計」は全業種を対象としているが「海外事業活動基本調査」では対象外業種(金融、保険、不動産)があり、調査に回答義務がないこともあって必ずしも全配当金を網羅しているわけではない。その一方で、「国際収支統計」では、国別、業種別内訳が公表されていない(再投資収益等を含む直接投資収益ならば国別に公表されている)が、「海外事業活動基本調査」を利用すれば分析が可能である。ロイヤリティについては、「海外事業活動基本調査」は外国企業からの受取は含まれていないが、業種別内訳が公表されている。また、「海外事業活動基本調査」は企業の会計年度で集計されており、実際に配当・ロイヤリティの送金がなされて「国際収支統計」に表れるまでにはタイムラグがある点にも注意が必要である。
(3)海外収益の日本への還流
これまで、海外現地法人が利益を拡大し、その海外現地法人との取引において、資材調達に比べて配当やロイヤリティの比重が次第に拡大していることを見てきた。ここでは、配当、ロイヤリティに焦点を当てて動向を分析していく。その中で、海外現地法人の利益のどの程度が日本に還流しているのかも見ていく。
まず、日本出資者向け支払総額を概観した上で、配当とロイヤリティを分けて動向を見る。次に、利益を挙げることができているかどうかという利益状況を確認した上で、我が国への配当性向等を考察する。さらに配当を実施している企業の特徴も併せて考察することとする。
①日本側出資者向け支払の推移
まず、日本側出資者向け支払(配当金、ロイヤリティ等の合計)の推移を見ると堅調に拡大している。内訳では2000年代中頃まではロイヤリティが多く、それ以降は配当金が上回って推移している(第Ⅱ-1-3-1-27図)。立地国・地域別には、支払総額で、米国が圧倒的であったが、2000年代に中国が急速に拡大し、リーマン・ショックで急減した米国に迫っているほか、タイも堅調に拡大している(第Ⅱ-1-3-1-28図)。2012年度で見ると、これら米国、中国、タイ3国が上位を占めるとともに、第4位のオランダを除くと、第5位以下はシンガポール、インドネシア、台湾、香港と続き、アジアで稼ぐ傾向が表れている(第Ⅱ-1-3-1-29図)。なお、欧州からの支払はオランダ(第4位)に集約される傾向が見られ、ドイツ(第16位)、英国(第18位)からの直接の支払は意外に少ない。
第Ⅱ-1-3-1-27図 日系海外現地法人の日本側出資者向け支払の推移
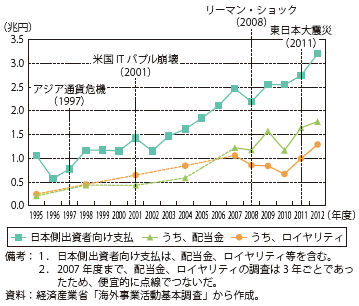
第Ⅱ-1-3-1-28図 日系海外現地法人の日本側出資者向け支払の推移(立地国別)
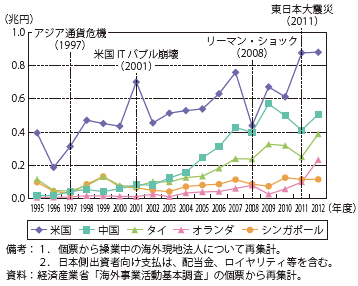
第Ⅱ-1-3-1-29図 日系海外現地法人の日本側出資者向け支払(立地国・地域別 / 2012年度)
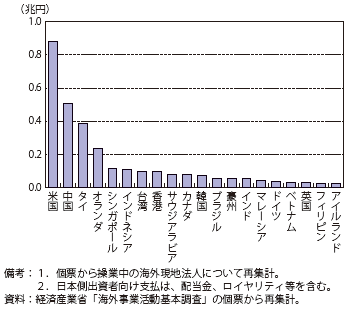
業種別には、製造業では、輸送機械がリーマン・ショック、東日本大震災等で一時的に落ち込んだものの、増加傾向で推移している111(第Ⅱ-1-3-1-30図)。電気機械も緩やかに増加してきたが、リーマン・ショック後は減少している。化学は最近伸びている。非製造業の中では、卸売業が大きく、運輸、建設、小売等もリーマン・ショック等で低下を経験しながらも伸びてきている。サービス業も着実に伸びている。2012年度で見れば、製造業では輸送機械が稼ぎ頭で、化学、電気機械と続く。非製造業では、卸売業が大きい(第Ⅱ-1-3-1-31図)。
第Ⅱ-1-3-1-30図 日系海外現地法人の日本側出資者向け支払の推移(本社の業種別)
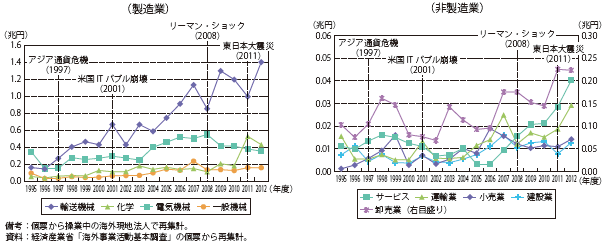
第Ⅱ-1-3-1-31図 日系海外現地法人の日本側出資者向け支払(業種別 / 2012年度)
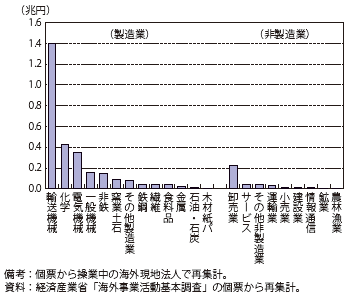
111 業種については、配当、ロイヤリティを受け取る本社企業との関係に焦点をおいて、本社企業の業種で集計した。これ以降、本節においては特に記載がない限り、本社企業の業種で集計する。既に述べたように現地法人の業種で集計した場合、本社との関係が見えにくくなることや、特にロイヤリティについて、複数の業種にまたがる現地法人の製造部門で利用されている特許料支払が非製造業から支払われているように見えることがある等のためである。
②配当とロイヤリティ
日本側出資者向け支払いを、その内訳である配当金とロイヤリティに分けて見ていく112。同じ日本側出資者向け支払でも、配当金とロイヤリティでは性格が異なる。配当金は企業が利益を計上したときに、その利益の中から出資者に対して支払をするもので、配当の実施、配当額は事業実績との関係で決定される。利益が出なければ配当の実施は難しいし、利益額が多いほど配当額も大きくなることが予想される。
これに対して、ロイヤリティは、技術やブランド等の対価として支払われるもので、あらかじめ支払額等の条件が契約で決められている。もし、契約でロイヤリティが生産数量当たりの料率で決められていれば、支払額は利益の有無に関係なく決定される。その意味で、ロイヤリティは会計の側から見れば、資材調達と同様に経費の一部に含まれ、利益動向によって影響を受ける配当金とは性格が異なる。
(配当金)
立地国別に配当金の推移を見ると、かつては米国が首位だったが、中国が売上高、経常利益の拡大を背景に2000年代半ば以降に拡大して、リーマン・ショック後には米国に匹敵する水準となっている(第Ⅱ-1-3-1-32図)。ただし、年による変動が大きい点には注意が必要である。また、タイも配当金を伸ばしてきている。2012年度は、中国、米国、タイが大きく、欧州のオランダが続いている(第Ⅱ-1-3-1-33図)。業種別には、2012年度の場合、製造業が全体の約8割を占め、特に輸送機械が大きく、化学、電気機械が続く(第Ⅱ-1-3-1-34図)。非製造業の中では卸売業が比較的大きい。
第Ⅱ-1-3-1-32図 日系海外現地法人の日本側出資者向け配当金の推移(立地国別)
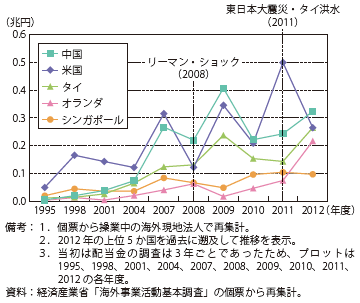
第Ⅱ-1-3-1-33図 日系海外現地法人の日本側出資者向け配当金(立地国・地域別/2012年度)
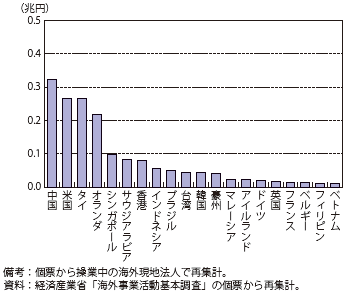
第Ⅱ-1-3-1-34図 日系海外現地法人の日本側出資者向け配当金(本社の業種別/2012年度)
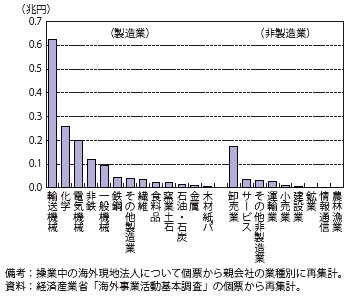
112 日本出資者向け支払には、正確には、配当金、ロイヤリティの他に、親会社からの貸付に対する利子等が含まれるが、「海外事業活動基本調査」では、利子等は明確な金額が調査されていないことや配当・ロイヤリティに比べて金額的に少ないと見られることから、ここでは配当金とロイヤリティに焦点をおいて分析する。
(ロイヤリティ)
ロイヤリティについては、国別に見ると、米国が圧倒的に大きく、リーマン・ショック後の落ち込み時を除けば、他国を大きく引き離している(第Ⅱ-1-3-1-35図)。2012年度の場合、中国、タイ、カナダと続く(第Ⅱ-1-3-1-36図)。また、業種別には、2012年度の場合、製造業が全体の9割以上を占め、特に輸送機械が大きく、化学、電気機械、窯業土石、一般機械が続く(第Ⅱ-1-3-1-37図)。非製造業の中では卸売業が比較的大きい。
第Ⅱ-1-3-1-35図 日系海外現地法人の日本側出資者向けロイヤリティの推移(立地国別)
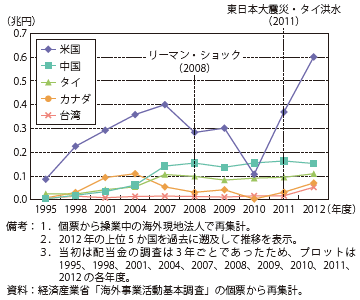
第Ⅱ-1-3-1-36図 日系海外現地法人の日本側出資者向けロイヤリティ(立地国・地域別/2012年度)
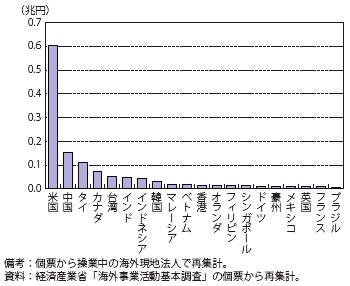
第Ⅱ-1-3-1-37図 日系海外現地法人の日本側出資者向けロイヤリティ(業種別/2012年度)
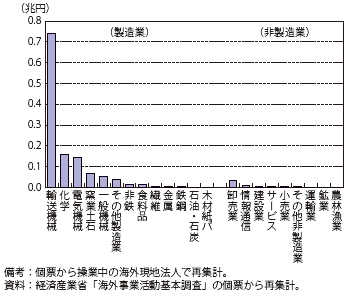
(国別パターン)
配当金とロイヤリティのどちらがより多いかというバランスについては、立地国によってパターンが異なっている。米国、カナダ、インドはロイヤリティ、中国、タイ等は配当金を中心に支払が行われている(第Ⅱ-1-3-1-38図)113。このような傾向は、米国、中国、タイの推移を時系列で見ても同様であった(第Ⅱ-1-3-1-39図)。
第Ⅱ-1-3-1-38図 日系海外現地法人の日本側出資者向け配当・ロイヤリティ(2012年度)
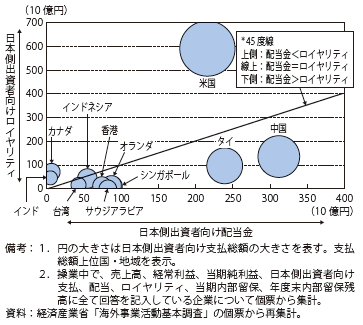
第Ⅱ-1-3-1-39図 日系海外現地法人の日本側出資者向け配当・ロイヤリティの推移
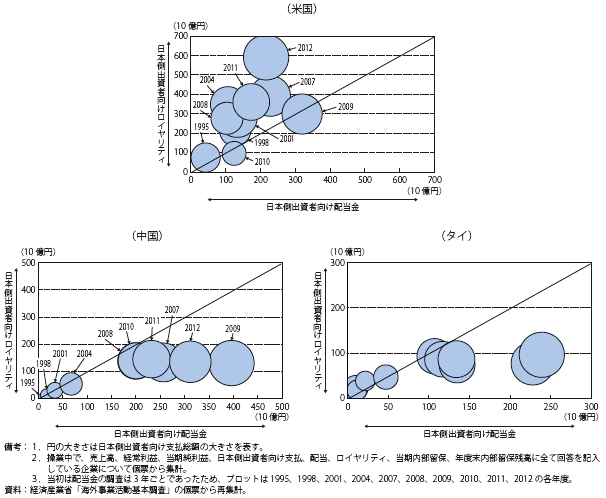
各国の業種内訳を見ると、米国の場合、輸送機械のロイヤリティが極めて大きく、次いで化学、電気機械、一般機械が続いている(第Ⅱ-1-3-1-40図)。一方、中国の場合、電気機械は配当金・ロイヤリティがほぼ同水準であるものの、輸送機械は配当金が中心となっている。タイでも大きなウェイトを占める輸送機械が配当金中心となっている。立地国による特徴の背景としては、同じ業種でも製品のスペックが異なることや税率の相違114等が考えられる。
第Ⅱ-1-3-1-40図 米国、中国、タイの配当・ロイヤリティの業種別相違
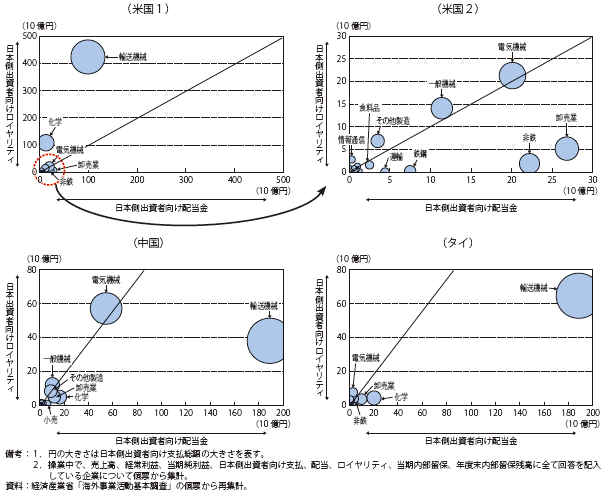
また、最近、ロイヤリティの伸び悩みが見られるが、その理由としては、技術進歩に伴う既存技術の陳腐化や現地調達の拡大に伴う本社技術に頼る度合いの低下等が指摘できる。
113 ここまでは、売上、利益、配当金等の項目ごとに当該項目に回答を記入した企業で集計してきた。この方法は可能な限り多くの回答を利用し実態に近い集計ができる一方で、項目ごとに集計している回答企業が異なるため、項目間の関係を見ようとする場合には祖語が生じるおそれがある。これ以降は、企業の事業実績との関係を分析していくため、原則として、操業中であり、売上、経常利益、当期純利益、日本側出資者向け支払、配当、ロイヤリティ、内部留保、内部留保残高に全て回答を記入している企業で集計する。
114 配当金、ロイヤリティの送金は課税対象で、租税条約の適用が受けられ、その税率は米国の場合、配当金免税~10%(持株割合による)、ロイヤリティ免税、中国の場合、配当金10%、ロイヤリティ10%となっている。。
③海外現地法人の利益率
(全体的動向)
利益の還流を考えるに当たっては、そもそも利益を上げていることが前提となる。そこで、まず利益を上げられているかどうか、利益額や利益率の推移を見て、その上で利益の還流を考えることにする。売上高に対する利益率を見ると、2000年代は上昇傾向にあった(第Ⅱ-1-3-1-41図)。リーマン・ショック時に低下したものの、その後は回復に向かい、東日本大震災後の2011年度に再び低下した。このような基本的な動向は経常利益率で見ても、当期純利益率で見ても同様である115。
第Ⅱ-1-3-1-41図 日系海外現地法人の売上高及び利益の推移
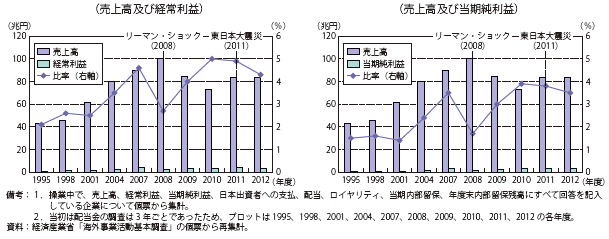
(主要国別の動向)
主要国別に売上と利益の動きを平面に表示したのが第Ⅱ-1-3-1-42図である。横軸が売上、縦軸が利益、原点との傾きが利益率を表す。もし、売上・利益が順調に拡大していれば右上に推移し、原点からまっすぐな直線上に移動していれば利益率も安定していることを意味する。これを見ると、中国、タイは、リーマン・ショックまでおおむね安定的に右上がりに推移し、ショック時には純利益が減少したものの、その後は回復に向かった。ただし、東日本大震災後の2011年度は、国内外のサプライチェーンの寸断の影響から低調であった。これに対して、米国は、2007年度のサブプライム問題の顕在化で売上、利益とも減少し、さらに2008年度のリーマン・ショック時には当期純利益が大きく減少した。その後、利益が回復していくが売上が萎縮して推移している。世界全体で見ても、2000年代は右上がりに拡大していったが、リーマンショック前後に落ち込んでいる様子がうかがえる。
第Ⅱ-1-3-1-42図 日系海外現地法人の売上高と当期純利益の推移(主要国別)
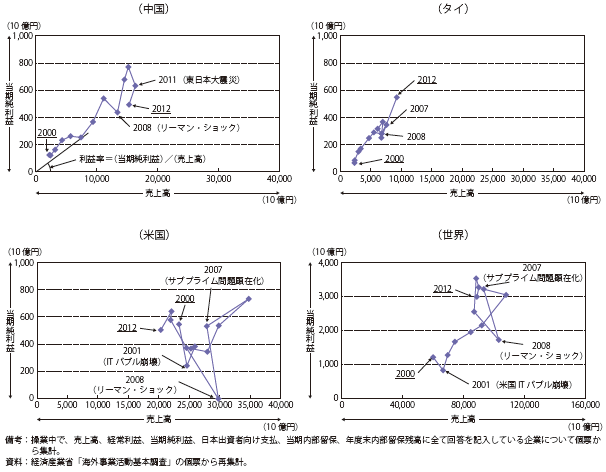
(企業の黒字・赤字)
ここまで、国全体の利益率を見てきた。その際に、一国の利益額を計算するに当たって、その国に立地する全企業の利益額を合計してきたが、海外現地法人の中には黒字を計上している企業だけでなく赤字計上の企業も存在する。どのくらいの企業が黒字を計上しているかを見ておく。企業数ベースで黒字企業の割合は、リーマン・ショック等で低下したものの、2000年代、緩やかに上昇してきており、2012年度は約7割の企業が黒字を計上している(第Ⅱ-1-3-1-43図)。
第Ⅱ-1-3-1-43図 日系海外現地法人の当期純利益(黒字・赤字企業別)の推移
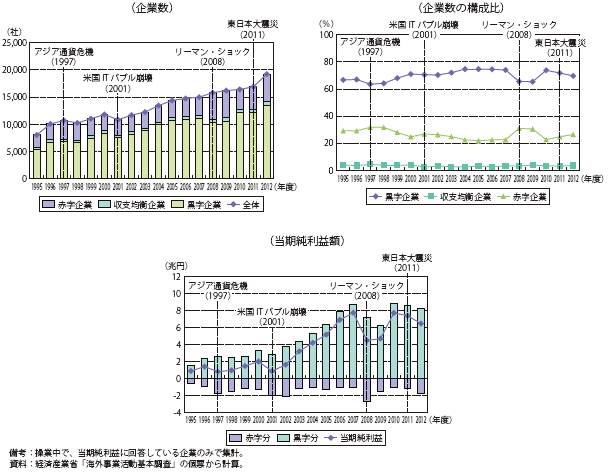
金額ベースでは、毎年ある程度の赤字が計上されているが、黒字額と相殺した当期純利益は拡大してきた。ただし、リーマン・ショック後等に低下している点は企業数ベースと同じである。
国・地域別に見ると、2012年度は、タイ、台湾は黒字企業の比率が約8割と高くなっている(第Ⅱ-1-3-1-44図)。立地企業数の多い中国は黒字企業も多い一方で赤字企業も多く見られる。金額ベースでは、米国、中国は赤字分が多いものの、黒字分で相殺されて大きな当期純利益を計上している。
第Ⅱ-1-3-1-44図 日系海外現地法人の当期純利益の状況(2012年度)
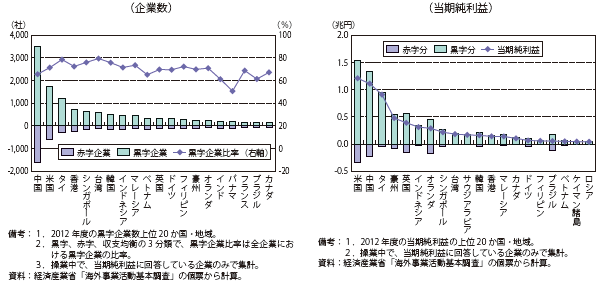
115 利益を表す指標としては、営業利益、経常利益、当期純利益等がある。それぞれ特徴があり、営業利益は売上高から売上原価、販売費・一般管理費等のコストを引いた本業で稼いだ利益。経常利益は営業利益に受取利息・借入利息等を加減した利益。当期純利益は更に特別損益、税金を引いて最終的に企業に残った利益。ここまでは企業の事業全体の利益として経常利益を見てきたが、利益の還流で着目する配当金の原資となるのは当期純利益なので、これ以降、本節の中では当期純利益を中心に見ていく。なお、日本の親会社について、現地法人からの配当受入れ前の利益を見るのであれば営業利益が適している。
④配当性向
日本側出資者向け支払の売上や利益に対する比率を見ていこう。売上に対する比率を見たのが第Ⅱ-1-3-1-45図である。支払総額の対売上比はリーマン・ショック後に低下したが緩やかに上昇している。内訳はロイヤリティの比率がほぼ横ばいで推移する中、配当金が緩やかに上昇している116。純利益の対売上高比がリーマン・ショック後に急落したことに比べれば比較的穏やかな推移となっている。その意味では、日本経済に対して安全弁となっているとの見方もできる。なお、ロイヤリティの対売上比がほぼ横ばいであることは、ロイヤリティは、利益というよりも、売上高を基準に設定されている可能性が高い。
第Ⅱ-1-3-1-45図 日系海外現地法人の売上高に対する日本側出資者向け支払の推移
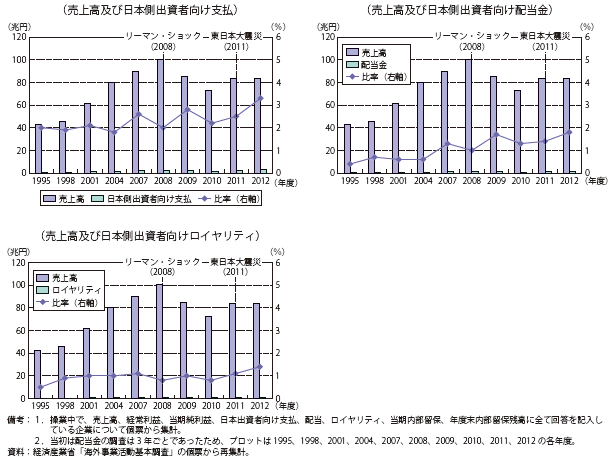
- Excel形式のファイル(売上高及び日本側出資者向け支払)はこちら

- Excel形式のファイル(売上高及び日本側出資者向け配当金)はこちら

- Excel形式のファイル(売上高及び日本側出資者向けロイヤリティ)はこちら

次に純利益との比率を見てみる。リーマン・ショック時に純利益は大きく減額したが、日本側出資者向け支払はあまり減額せず、むしろ日本側出資者向け支払比率は上昇している(第Ⅱ-1-3-1-46図)。配当金については、長期的には純利益の約4割強を中心に変動しており、純利益の急減に対しては出資者への影響が緩和されるように動いているように見える。なお、ロイヤリティは純利益に対して低下しており、先に見たように売上高を基準に設定されている可能性が高い。
第Ⅱ-1-3-1-46図 日系海外現地法人の純利益に対する日本側出資者向け支払の推移
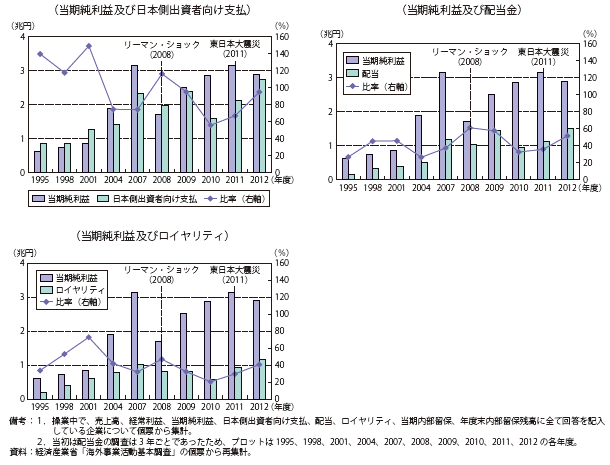
ここからは、日本への利益の還流という観点から、配当金に焦点を絞って分析していく。その際に、配当性向は、黒字利益を計上している企業について、出資比率を使って日本側持分を考慮しながら集計する117。このようにして主要国に立地する日系海外現地法人の利益率、配当性向をプロットしたのが第Ⅱ-1-3-1-47図である。グラフの横軸は利益率、縦軸は配当性向、円の大きさは日本側出資者への配当金を表す。
第Ⅱ-1-3-1-47図 日系海外現地法人の国別利益率・配当性向(2012年度)

グラフからは、日本側出資者向け配当金については、中国、米国、タイが突出して大きいことが分かる。利益率については、おおむね新興国の方が高い傾向がある。例えば、タイの利益率は米国を大きく上回っている。ただし、中国については、米国の利益率よりはやや高いものの、タイ等の他のアジア新興国に比べれば低い水準にとどまっている。
配当性向については、立地国によってかなりばらつきがあるが、最近配当金が拡大してきている中国の配当性向は米国に匹敵する水準になっている。
当期純利益は年ごとに大きく変動することから、配当性向も変動が大きい可能性が考えられる。そこで、配当額の大きい米国、中国、タイの配当性向を年別に計算してみると、年によって大きく変動している(第Ⅱ-1-3-1-48図)。いずれの国でも、2009年度が最高となっているのは共通で、2012年度については3国の中で中国が最も配当性向が高く、タイ、米国の順となっている。2011年度は、タイ、中国、米国の順であった。
第Ⅱ-1-3-1-48図 日系海外現地法人の利益率・配当性向の推移
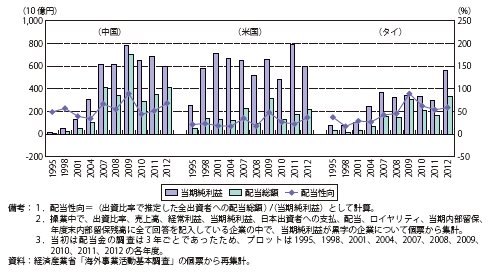
116 ここでは、単純に日本出資者向け配当金を売上高で除して比率を計算している。次に出てくる純利益に対する比率も同様。これに対して、海外現地法人の出資比率で補正して計算する方法は後のパートで記載する。
117 これまでは、単純に配当金合計を利益合計で除していたが、本来、海外現地法人は100%出資とは限らない。利益額全体が日本側持分に相当するわけではなく、海外現地法人ごとに出資比率が異なる点も勘案しなければならない。しかし、海外事業活動基本調査では日本側出資者向け配当金しか調査対象になっていないため、個々の企業ごとに日本側出資比率を使って全出資者に対する配当総額を推定した。これを当該国・地域別に合計し、当期純利益の合計額で除して配当性向を計算した。また、一部に当期純利益が赤字でも配当を行う企業も存在するが、利益のどの程度が日本に還流しているかを見るとの観点から、利益を計上している黒字企業だけで配当性向を計算した。なお、すでに述べたように集計は、操業中であり、売上額、当期純利益、配当金等の一連の質問に全て回答している企業のみで行った。
⑤配当企業のプロフィール
それでは、どのような企業が配当を行っているかについて、2012年度における立地国、業種、利益率、出資比率等の企業属性ごとの分布を見ていく118。
まず、2012年度は海外現地法人の約3割の企業が配当を実施している。立地国・地域別にみると、企業数では、中国、米国、タイが多いが、配当を実施した企業の比率(「配当企業比率」と表す)は、台湾、韓国、シンガポール、タイ、香港の順となっている(第Ⅱ-1-3-1-49図)。業種別には、製造業では電気機械の配当企業比率が製造業のほぼ平均に当たる。石油・石炭は企業数は少ないものの、配当企業比率が約6割と高く、他にも化学、輸送機械等が製造業平均を上回っている。非製造業では、卸売業、運輸業が非製造業平均を上回っており、小売業、サービス業は平均よりも低い(第Ⅱ-1-3-1-50図)。
第Ⅱ-1-3-1-49図 日系海外現地法人の中で配当を行っている企業(2012年度/立地国・地域)
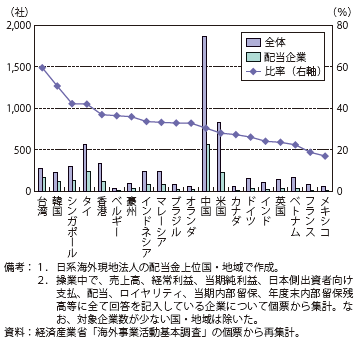
第Ⅱ-1-3-1-50図 日系海外現地法人の中で配当を行っている企業(2012年度/業種)
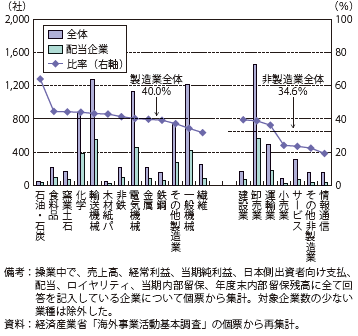
企業の利益率との関係を見ると、配当企業比率は、概ね、純利益率とともに上昇するが、純利益率10~15%の層以上は頭打ちとなっている(第Ⅱ-1-3-1-51図)。これは利益率がある程度高い方が配当を実施しやすいということと、利益率が高いからといって必ずしも配当するとは限らず、企業は利益率以外の要因も勘案していることがうかがえる。
第Ⅱ-1-3-1-51図 日系海外現地法人の中で配当を行っている企業(2012年度/純利益率)
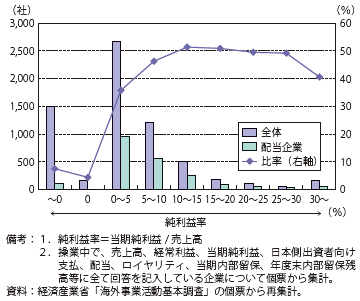
日本側出資比率別に見ると、親会社のコントロールが効く高い出資比率の層は配当企業比率が低い(第Ⅱ-1-3-1-52図)。特に日本側100%出資の層が最も低く、資金を手元に置く傾向が見られる。これは合弁のパートナー側から利益の配分を求められる等の理由が考えられる。
第Ⅱ-1-3-1-52図 日系海外現地法人の中で配当を行っている企業(2012年度/出資比率)
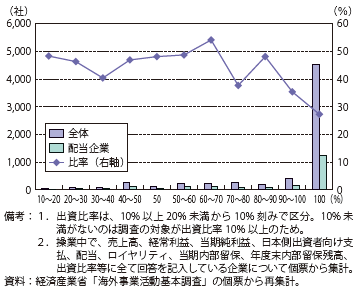
操業年数との関係を見ると、配当企業比率は操業年数とともに上昇し、10年を過ぎる頃からほぼ4割前後と一定となっている(第Ⅱ-1-3-1-53図)。これは、企業が安定して配当を行えるよう成長するためには、経営ノウハウを蓄積し、従業員や現地関係者との信頼関係を構築するなど組織的、財政的基盤を固めるために年数がかかるためと考えられる。また、一定年数を超えると現地に資金を残す選択を行っていることも示唆される。
第Ⅱ-1-3-1-53図 日系海外現地法人の中で配当を行っている企業(2012年度/操業年数)
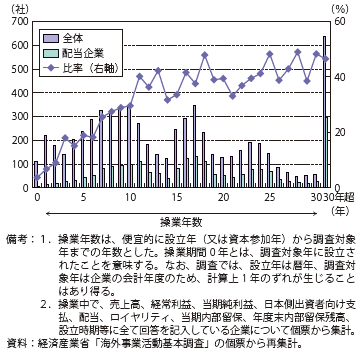
内部留保残高別に見ると、配当企業比率は、おおむね内部留保残高とともに上昇する(第Ⅱ-1-3-1-54図)。現地法人が十分な蓄積を有している場合には、本社に利益を配分していることがうかがえる。
第Ⅱ-1-3-1-54図 日系海外現地法人の中で配当を行っている企業(2012年度/内部留保残高)
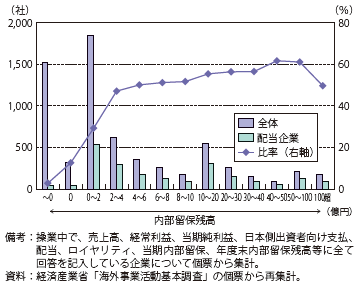
設備投資や研究開発については、まったく設備投資や研究開発をしない層よりは、適度に実施する企業の方が配当企業比率は高いが、ある程度を超えると配当企業比率はむしろ低下する(第Ⅱ-1-3-1-55図、第Ⅱ-1-3-1-56図)。これは、企業戦略として、配当に回すよりも、現地のビジネスチャンスを活かすために投資を実行するという現地での資金需要に応じた結果と推測される。
第Ⅱ-1-3-1-55図 日系海外現地法人の中で配当を行っている企業(2012年度/設備投資比率)
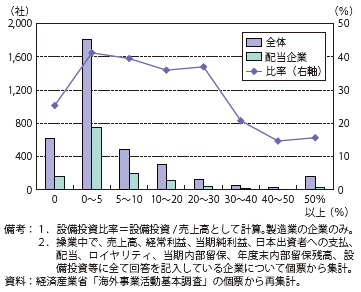
第Ⅱ-1-3-1-56図 日系海外現地法人の中で配当を行っている企業(2012年度/研究開発費比率)
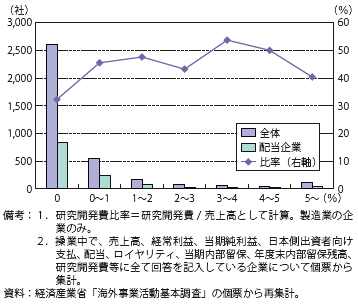
(中国と米国)
それでは、個別国の例を見てみよう。最近配当額が拡大している中国の配当企業のプロフィールは、他国、例えば米国と比べて大きな相違があるのだろうか。中国と米国に立地する日系海外現地法人の主要な項目について図示したのが、それぞれ第Ⅱ-1-3-1-57図、第Ⅱ-1-3-1-58図である。まず、中国については、これまで見てきた配当企業比率の傾向がおおむね同様に見ることができる(第Ⅱ-1-3-1-57図)。
第Ⅱ-1-3-1-57図 日系海外現地法人の中で配当を行っている企業(2012年度/中国)
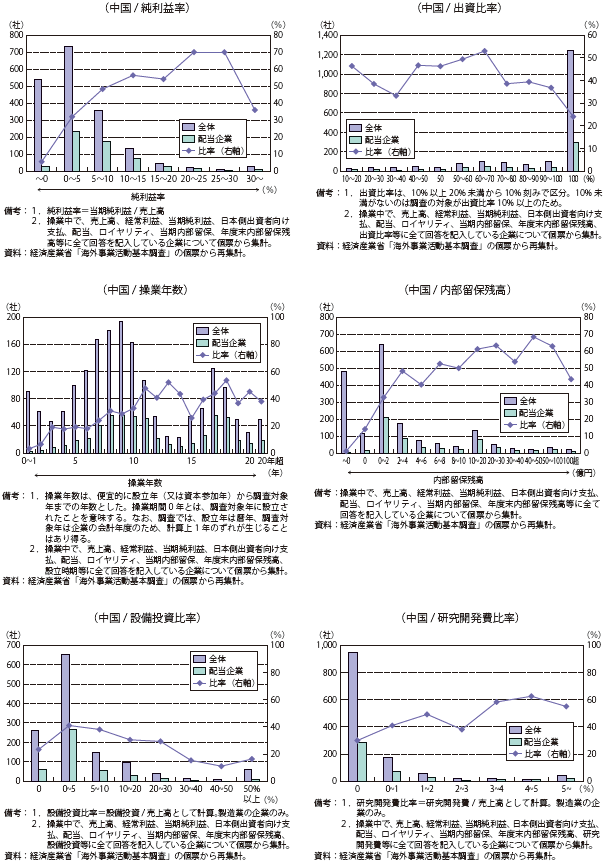
- Excel形式のファイル(中国/純利益率)はこちら

- Excel形式のファイル(中国/出資比率)はこちら

- Excel形式のファイル(中国/操業年数)はこちら

- Excel形式のファイル(中国/内部留保残高)はこちら

- Excel形式のファイル(中国/設備投資比率)はこちら

- Excel形式のファイル(中国/研究開発費比率)はこちら

米国においても、これまで見てきた世界全体や中国の傾向から大きく異なるわけではない(第Ⅱ-1-3-1-58図)。両国とも、設備投資は全く実施しないよりは、実施した場合の方が配当企業比率は高いが、ある程度を過ぎると急速に低下するという傾向は似ている。
第Ⅱ-1-3-1-58図 日系海外現地法人の中で配当を行っている企業(2012年度/米国)
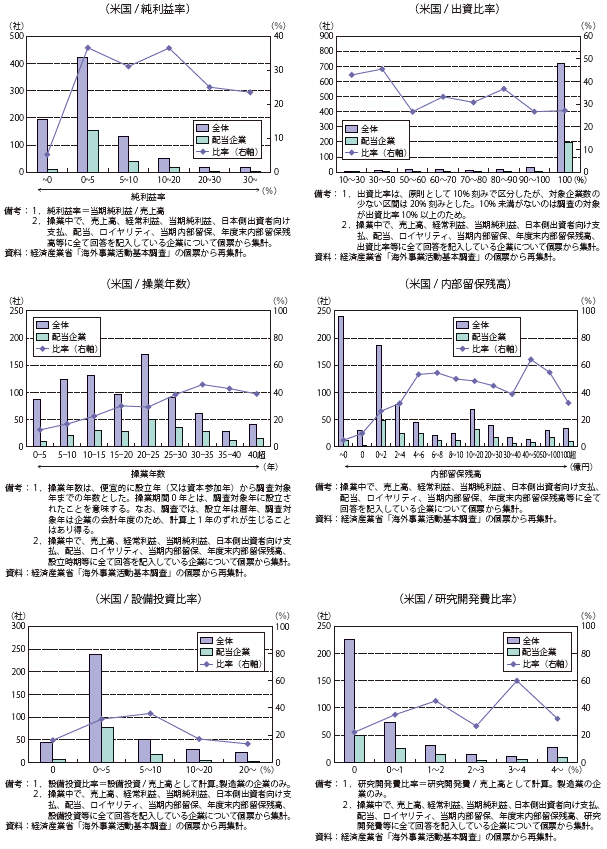
- Excel形式のファイル(米国/純利益率)はこちら

- Excel形式のファイル(米国/出資比率)はこちら

- Excel形式のファイル(米国/操業年数)はこちら

- Excel形式のファイル(米国/内部留保残高)はこちら

- Excel形式のファイル(米国/設備投資比率)はこちら

- Excel形式のファイル(米国/研究開発費比率)はこちら

(配当企業と非配当企業の相違)
既に見たように利益率が高いほど配当企業比率は上昇するが、ある程度以上の利益率では頭打ちになることも分かった。それでは利益率が高いのに配当しない企業とはどのような企業であろうか。また、同じ利益率でも配当する企業としない企業の差はどこにあるのであろうか。これまでは企業の属性を単独に見てきたが、利益率の階層ごとに配当企業と非配当企業で属性に相違があるのかを見てみる。同じ純利益率ごとに配当企業と非配当企業の平均を比較すると、いくつかの属性について傾向がうかがえる。例えば、出資比率の場合、利益率のすべての階層において、配当企業の平均は非配当企業に比べて、出資比率が低い(第Ⅱ-1-3-1-59図)。同様に見ていくと、配当企業は、同じ利益率でも、操業年数が長く、内部留保残高は大きく、設備投資比率は低い。特に、配当企業比率が純利益率10~15%で頭打ちとなるのは、これより上の層では、設備投資が旺盛な割に、内部留保残高が少ないこと等が影響していることが考えられる。
第Ⅱ-1-3-1-59図 純利益率別の配当・非配当企業の相違(2012年度)
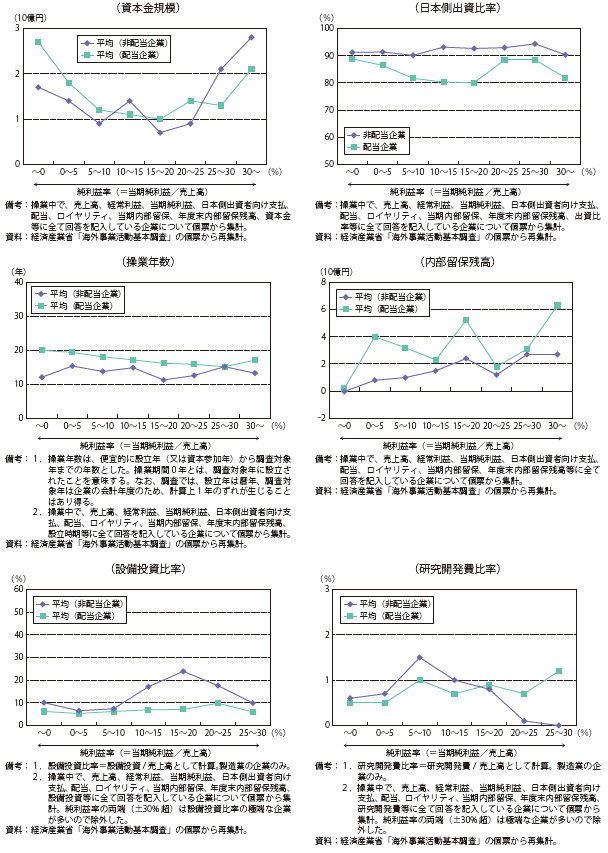
- Excel形式のファイル(資本金規模)はこちら

- Excel形式のファイル(日本側出資比率)はこちら

- Excel形式のファイル(操業年数)はこちら

- Excel形式のファイル(内部留保残高)はこちら

- Excel形式のファイル(設備投資比率)はこちら

- Excel形式のファイル(研究開発費比率)はこちら

海外現地法人が配当を実施するかどうか影響を与える要因について、試みに回帰分析を行ってみた119(第Ⅱ-1-3-1-60図)。その結果とこれまで見てきたことを考え合わせると、個々の企業が配当を行うかどうかについては、純利益が計上されれば自動的に配当されるというわけではなく、企業の置かれた状況に合わせて決定されていることがうかがわれる。例えば、純利益率が高く、内部留保残高比率が高い企業は配当を行う可能性は高い。日本側出資比率が低い場合は、配当を実施する可能性が高くなる傾向が見られる。操業年数が若い企業は配当を控える可能性が高く、設備投資比率が高い場合も、配当実施可能性が低い。また、親会社の事情も関係すると見られ、親会社の企業規模が小さい場合や営業利益率が低い場合は、配当を実施して本社企業に送金する可能性が高まる。
第Ⅱ-1-3-1-60表 回帰分析試算
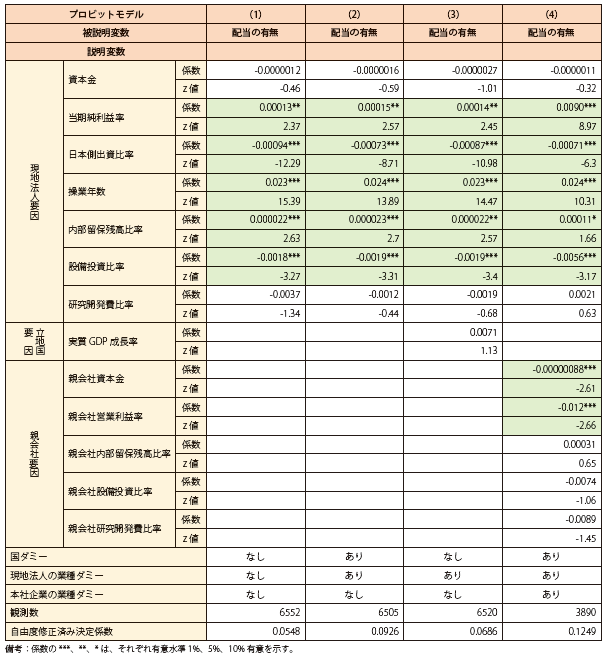
118 企業数ベースで分析を行う。集計の対象としたのは、2012年度、操業中で、売上高、経常利益、当期純利益、日本側出資者向け支払、配当金、ロイヤリティ、当期内部留保、年度末内部留保残高、出資比率、設立年、設備投資、研究開発等に全て回答している海外現地法人約6,500社。
119 2通りの手法で試算した。第2-1-3-59図で見たような傾向は特定の国・業種によって偏りがある可能性がある。そこで、1つ目の手法は、国・業種をコントロールした上でも、現地企業の属性ごとに配当企業と非配当企業で統計的に有意な差があるかどうかを検証した。被説明変数を企業属性(例えば、出資比率)、説明変数を配当企業かどうかのダミー変数とする線形モデル(最小二乗法で推定)で、国ダミー、業種ダミーを加えても配当の有無は統計的に有意に影響するかどうか。その試算結果は、国、業種をコントロールした上で、操業年数、内部留保残高は係数が正で有意(1%水準)、出資比率は係数負で有意(1%水準)とグラフで観察した結果と整合的であった。資本金規模は係数が正、設備投資比率、研究開発比率は係が負と、グラフと整合的であったが有意とはならなかった。そして意外なことに純利益率は係数が正だが有意とはならなかった。
そこで、2つ目は、単独の要因だけではなく、様々な要因が影響して配当の有無が決定されていると仮定して、どの要因が統計上有意に影響しているかを調べた。被説明変数を配当企業かどうかという質的変数、説明変数を現地法人、立地国、親企業に係る諸要因とするプロビットモデルで推定した。試算結果は第2-1-3-60図に示した。
なお、分析の対象サンプルは原則として第2-1-3-59図にあるような2012年度に一連の項目に回答した企業とした。親企業の属性データについては、海外事業活動基本調査と企業活動基本調査のデータを、独立行政法人経済産業研究所から提供いただいたコンバーターによって個票レベルでリンクして利用した。このため、親企業属性も含めた分析については個票レベルでリンクができたサンプルに限られる。
⑥配当性向の分析
ここからは、配当をしている企業に焦点を当てて、個々の企業の配当性向や、配当性向に影響を与える要因について考察する120。考えられる要因として、①現地法人の要因、②立地国の要因、③親会社の要因を順に見ていく。
まず、日系海外現地法人の平均配当性向121の推移を見ると、たびたびの経済ショックにより、低迷することはあるが、傾向としては緩やかに上昇の動きが見られる(第Ⅱ-1-3-1-61図)。
第Ⅱ-1-3-1-61図 平均配当性向の推移
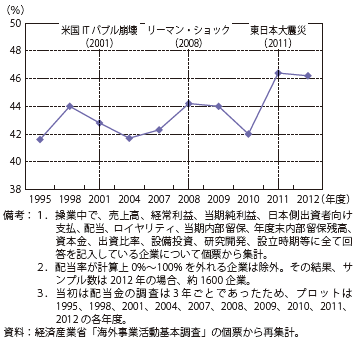
①現地法人の要因
配当を実施している企業の、企業属性(例えば、資本金)の階層別に、平均配当性向(個々の企業の配当性向の単純平均)やシェア(企業数ベース、配当金額ベース)をプロットしたのが、第Ⅱ-1-3-1-62図から第Ⅱ-1-3-1-67図である。
まず、資本金規模については、平均配当性向は1-3億円の階層が最も低く、むしろ両端では高くなっている(第Ⅱ-1-3-1-62図)。また、配当企業の構成では、企業数ベースで比較的小規模な企業のシェアも高いが、配当金額ベースでは、100億円超の企業が大きなシェアを占めている。
第Ⅱ-1-3-1-62図 配当企業分布と平均配当性向(2012年度)
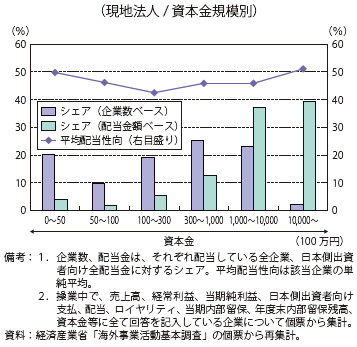
内部留保残高比率(内部留保残高/売上高)については、残高比率の比較的低い層では、残高比率が高いほど配当性向は下がり、ある一定の残高比率を超える層ではほぼ横ばいとなっている(第Ⅱ-1-3-1-63図)。これは、配当性向が高い結果、内部留保が蓄積しにくいとも考えられる。
第Ⅱ-1-3-1-63図 配当企業分布と平均配当性向(2012年度)
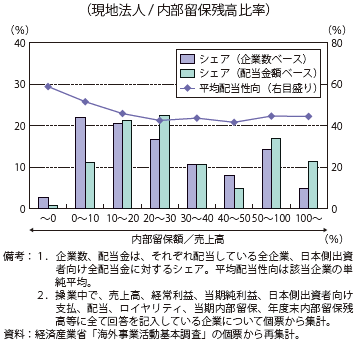
②立地国・地域の要因
2012年度の企業の平均配当性向は、パナマ、台湾、フィリピン等が高い(第Ⅱ-1-3-1-64図)。一方、中国の平均配当性向は、米国、タイよりも高くなっている。
第Ⅱ-1-3-1-64図 配当企業分布と平均配当性向(2012年度)
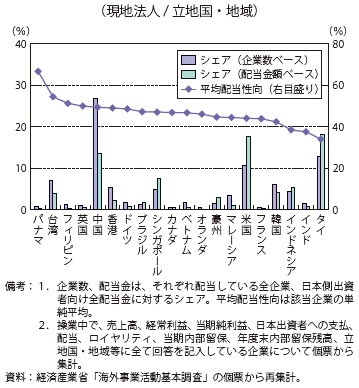
配当性向は立地国の実質GDP成長率が高くなるほど低下する傾向が見られる(第Ⅱ-1-3-1-65図)。一般に、立地国の経済成長率は、高い方がビジネスチャンスに恵まれることが期待できる。そのために現地に利益を留めようとする動きともとれる。ただし、成長率7~8%の層の配当性向が高く、中国の影響が考えられる。
第Ⅱ-1-3-1-65図 配当企業分布と平均配当性向(2012年度)
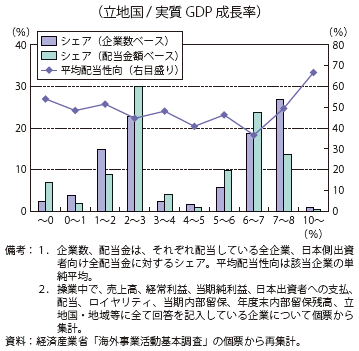
③親企業の要因
親企業の財務基盤の安定性等が海外現地法人の配当性向に影響を与えていることが考えられる。親会社の企業規模については、資本金規模が大きな層の方が配当性向が高いようにも見えるが、0~50百万円の層でもある程度の配当性向を有していることから必ずしもはっきりしない(第Ⅱ-1-3-1-66図)。
第Ⅱ-1-3-1-66図 配当企業分布と平均配当性向(2012年度)
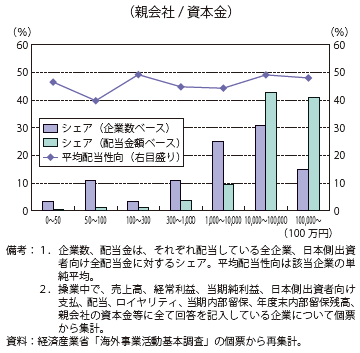
親会社の営業利益率(営業利益/売上高)122が高い場合に、配当性向は低くなる傾向が見られる(第Ⅱ-1-3-1-67図)。
第Ⅱ-1-3-1-67図 配当企業分布と平均配当性向(2012年度)
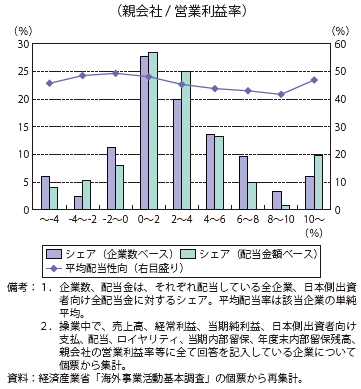
内部留保残高比率(内部留保残高/売上高)が一定水準に達するまでは、配当性向は内部留保残高比率が高いほど低下する(第Ⅱ-1-3-1-68図)。ただし、30%を超えるとあまり変わらなくなる。
第Ⅱ-1-3-1-68図 配当企業分布と平均配当性向(2012年度)
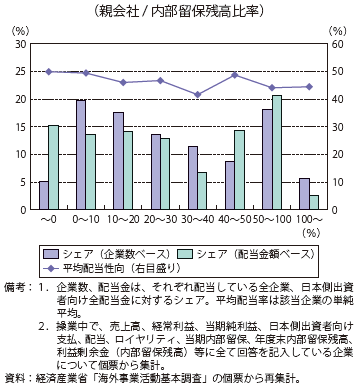
120 実際には、赤字でも配当する場合や当期純利益を超えて配当するケースも見受けられる。前年度からの繰越利益を利用していると思われるが、ここでは標準的な場合について分析するものとして、配当性向が0~100%の企業に限定し0%以下や100%を超えるデータは除外した。
121 ここでは、個別企業の行動を分析することを念頭に、平均配当性向も個別企業の配当性向の単純平均をとっている。
122 営業利益率は、支払利子、受取利子、海外現地法人からの配当金が算入される前の利益率。
⑦日本の出資金に対する配当金・ロイヤリティ
これまでは、配当性向を見てきたが、日本の出資額に対する配当の比率はどうであろうか。主要国別に日系海外現地法人について集計してみると、中国は2011、2012年度、やや低下したものの、ほぼ世界平均を上回って推移していることが分かる(第Ⅱ-1-3-1-69図)。米国と比較すると、常に米国を上回って推移している。
第Ⅱ-1-3-1-69図 日本の出資額に対する配当金比率の推移(主要国)
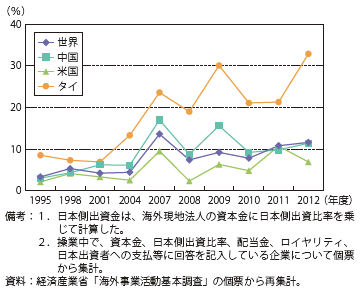
また、2012年度の業種別の状況を見ると、世界合計では、輸送機械、電気機械、一般機械、化学、卸売業の出資額が多く、このうち、輸送機械、化学、卸売業で、出資額に対する配当金の比率も相対的に高い(第Ⅱ-1-3-1-70図)。中国でもおおむね同様の傾向が見られる。なお、タイの配当金比率が高いのは、輸送機械の出資額・配当額がともに大きく、全体を引き上げている結果である。
第Ⅱ-1-3-1-70図 日本の出資額に対する配当金比率(主要国・業種 / 2012年度)
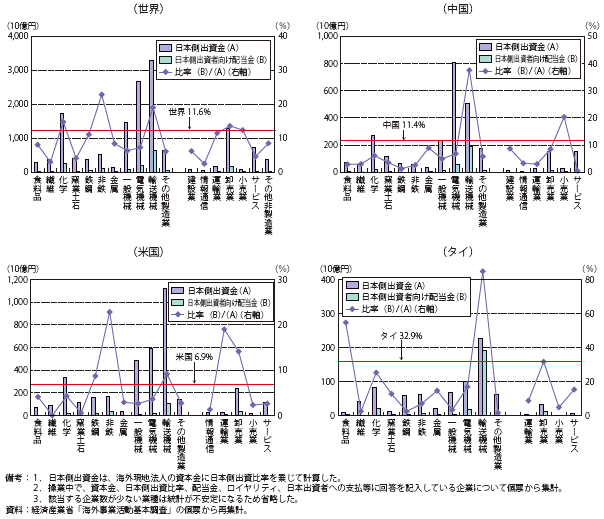
出資額の上位国から順に並べてみると、欧州のオランダ、英国等も出資額は大きい(第Ⅱ-1-3-1-71図)。しかし、欧州の場合は、オランダからの配当金比率が高い一方で、英国等の比率が低く、オランダに集約されている可能性がある。
第Ⅱ-1-3-1-71図 日本の出資額に対する配当金比率(2012年度)
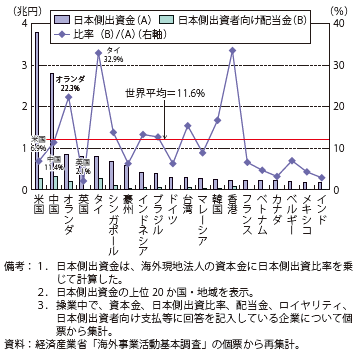
さらに、配当だけでなく、ロイヤリティ等123も含めた日本出資者への支払総額について、日本の出資額に対する比率を見てみる。中国、米国、タイとも比率は上昇するが、上昇の程度はロイヤリティ等収入の大きさに影響される。2000年代半ば以降、中国は世界平均を上回ってきたが、2011、2012年度はやや下回っている(第Ⅱ-1-3-1-72図)。ロイヤリティ収入の多い米国は、2011、2012年度は世界平均や中国を上回っている。
第Ⅱ-1-3-1-72図 日本の出資額に対する支払額(配当、ロイヤリティ等)の比率の推移(主要国)
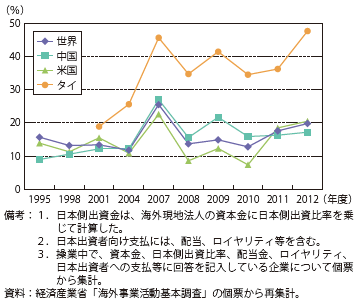
各国の業種別の状況を見ると、中国の中では、輸送機械が日本の出資額、出資者向け支払額、支払比率とも高い(第Ⅱ-1-3-1-73図)。電気機械は、出資額は大きいものの、支払比率はほぼ平均に近い水準となっている。米国、タイでも、輸送機械の出資額、支払額、支払比率は高くなっている。
第Ⅱ-1-3-1-73図 日本の出資額に対する支払額(配当、ロイヤリティ等)の比率(主要国・業種 / 2012年度)
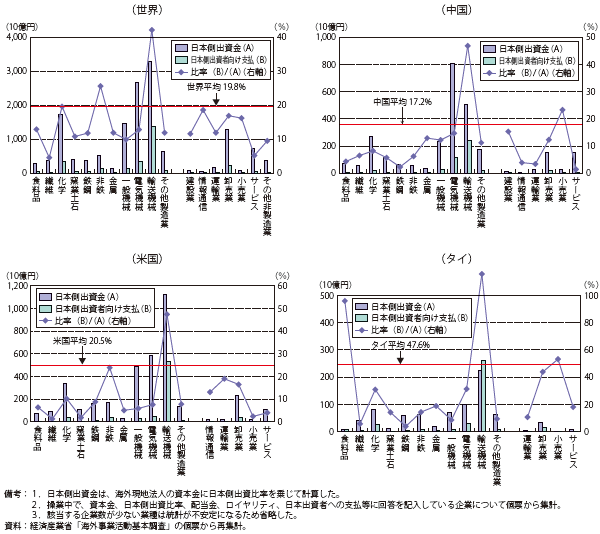
その他の日本出資額の大きな国を見ると、欧州のオランダは世界平均を上回っているものの、その差はわずかでありロイヤリティ収入は少ないことがうかがわれる(第Ⅱ-1-3-1-74図)。反対に、配当金に比べてロイヤリティの多いカナダ、インドは世界平均を上回っている。
第Ⅱ-1-3-1-74図 日本の出資額に対する支払額(配当、ロイヤリティ等)の比率(2012年度)
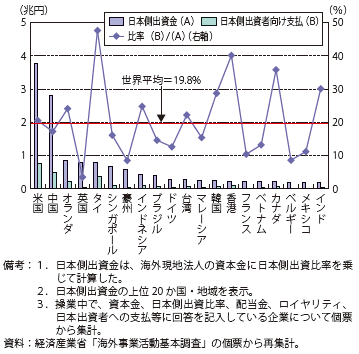
123 日本出資者向け支払には、配当金、ロイヤリティの他に、親会社からの貸付に対する利子が含まれる。
⑧まとめ
本節では、まず、日本企業がどこで稼いでいるかを確認した。その結果、海外で利益を稼ぎ、蓄積する傾向が強まっていることが分かった。海外の展開先としては、かつては米国が圧倒的であったが、中国、タイ等のアジア諸国・地域も台頭してきている。業種としては、輸送機械、電気機械、化学、卸売業等が中心で、特に輸送機械が拡大している。
次に、日系現地法人が海外に展開する中で、国内に立地している企業の稼ぎ方は、どう変化してきているのかを見た。海外現地法人に対する資材の供給(国際収支の輸出)とともに、配当金(第一次所得収支)、ロイヤリティ収入(サービス収支)が金額ベースで拡大してきている。その比率は、依然として資材供給が大きな割合を占めており、海外現地法人が事業を展開するに当たって、日本からの基幹部品等の供給が重要な役割を果たしていることを示唆している。しかし、配当金、ロイヤリティの比率も拡大し、世界で稼ぐ傾向も顕著になってきている。
さらに海外で稼いだ利益が日本に還流してきているのかを考察した。海外現地法人の日本出資者向け支払額は、米国、中国、タイ等を中心に、配当金、ロイヤリティともに拡大している。日系企業の事業活動が拡大している中国については、当期純利益に対する配当性向が米国を上回り、日本側出資額に対する配当金比率もほぼ世界平均並みとなっている。
企業の配当行動を考察すると、利益率が高い方が配当しやすいのは事実としても、その他の様々な要因を考慮して配当の決定をしていることがうかがわれた。特に日本側出資比率が高く日本側のコントロールが高い場合には、配当を実施せずに利益を現地に留める企業も少なくない。
また、配当金とロイヤリティは性格が異なり、米国、カナダ、インド等はロイヤリティ中心、中国、タイ等は配当中心に日本向け支払がなされている。
これらの分析から示唆されることは、企業は配当という形で利益を日本に還流させる場合も、現地に留めおいて現地でのビジネスに活用する場合もあるが、その経営判断が自由に行えるような環境が確保されていることが重要であり、さらに、企業活動のグローバル化が進む中で、成長のための資金が日本に再度投下されるためには、日本の立地競争力を一層向上させていく必要があるということである。
2.グローバル企業の財務分析
本節では、日本及び海外の主要なグローバル企業の稼ぎ方の特徴について、財務データを基に比較、分析していく。
(1)前提条件、分析内容及び留意事項
①前提条件、分析内容
本分析では、2006年度から2013年度128の8年分の財務データをもとに、連結売上高(以下、本節において「売上高」という。)129が直近12か月における売上高の上位500社、また、海外売上高比率が20%以上等を前提として357社を抽出した(第Ⅱ-1-3-2-1図)。この企業群を主要なグローバル企業と位置づけ、その稼ぎ方について、次の観点から分析する。
第Ⅱ-1-3-2-1図 分析対象企業群の絞り込み
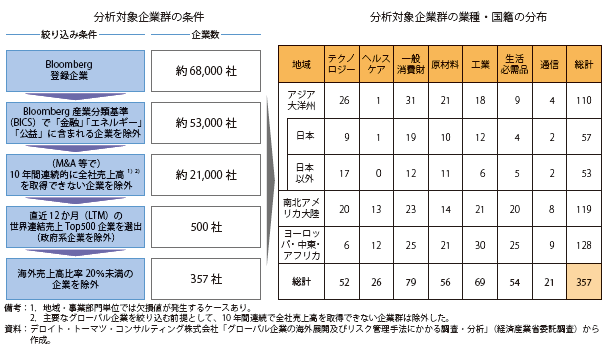
まず、全体的な売上・利益の傾向について、分析対象の財務データ全体を用いて分析する。
次に、主要なグローバル企業を本社所在地別に「日系企業(本社が日本に所在)」「米系企業(本社が南北アメリカ大陸に所在)」「欧州系企業(本社がヨーロッパ・中東・アフリカに所在)」「アジア系企業(本社が日本を除くアジア大洋州に所在)」と分類した上で、それぞれのグローバル企業群の成長性・収益性の特徴を分析する。分析に当たっては、売上高、営業利益、営業利益率とこれらの成長性を分析対象項目とし、これについて、事業の多角化度といった成長性・収益性に影響を与える経営指標130、企業が活動する地域との関係を確認する。
128 決算月が6月以前の企業は、決算月の前年を会計年度とし(例えば、2014年3月期決算の場合は、「2013年度」と定義)、決算月が7月以降の企業は、決算月を含む年を会計年度としている(例えば、2013年12月期決算の場合は、「2013年度」と定義)。
129 売上高はすべて在外子会社の売り上げを含めた連結売上高で分析している。
130 設立からの年数、売上規模、多角化度、R&D投資額との関係を分析する。
②留意事項
地域や業種情報については、財務データの提供元であるBloomberg社が定義している区分を採用している131。なお、地域別の分析においては、企業の情報開示状況の制約から第Ⅱ-1-3-2-1図で挙げた企業の全事業部門は対象としておらず、原則として2006年度から2013年度の8期連続で売上高132が取得できる地域別データのみを対象とした。
また、国営企業が多数を占める等分析を歪める可能性のある業種(「金融」、「エネルギー」、「公益」)に含まれる企業を除外していること、企業による情報開示状況の制約から、分析対象数がごく少数になるケースがあること、対象企業を売上高の大きなグローバル企業に絞っているため、ニッチ分野で高収益を上げている企業や自国内を中心に高い収益を上げている企業は分析対象外となっていることが挙げられる。
また、本分析において、企業ごとの指標を合算する際には以下の方法に沿って行っている。
・売上高年平均成長率:各国企業の売上高を単純合算し、分析期間内(2006-2013年度)の年平均成長率を算出。
・売上高営業利益率:各国企業の営業利益率を単純平均して算出。
131 地域はアジア大洋州、南北アメリカ大陸、ヨーロッパ・中東・アフリカの3分類を、事業部門はBICS Level 1(Sectors)10分類およびLevel 2(Industry Group)49分類を使用。具体的には付表2参照。
132 地域別の営業利益は大半の企業が公開していないため分析は行っていない。
(2)グローバル企業の稼ぎ方の全体的な傾向
まず、分析対象とする主要企業(357社)全体133について、成長性の観点から売上高の推移、次に、収益性の観点から営業利益・売上高営業利益率の推移を見ていく。
①売上高の推移
分析対象企業全体の売上高を見ると、2006-2013年度の分析対象期間内に約8.9兆ドルから12.9兆ドルへ、年平均成長率5.5%で成長している。地域別にはアジア大洋州地域が2.0兆ドルから3.3兆ドル(年平均成長率7.3%)と最も成長し、全体の成長を牽引している134。事業部門別には、コンピュータやこれを構成する回路や装置などのハードウェア、プログラムなどのソフトウェアとこれに関連するサービスを含む「テクノロジー」(年平均成長率6.4%)、食品等の製造、販売サービスを含む「生活必需品」(年平均成長率6.2%)が他を上回る成長となっている(第Ⅱ-1-3-2-2図)。
第Ⅱ-1-3-2-2図 分析対象企業全体の売上高推移(地域別・事業部門別)
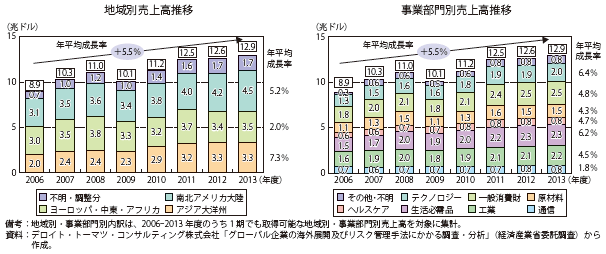
なお、同期間内における世界の名目GDPの平均伸び率は5.8%であり、本分析で取り上げた企業群全体では世界のGDPとほぼ同じペースで成長したと言える。
133 ここでは対象企業全体の動向を俯瞰するため、2006-2013年度のうち1期でも取得可能なデータを対象に集計している。このため、これ以外の分析と数値は必ずしも一致しない。
134 企業が情報を公開していない、または本分析での地域分類に一致しない場合があるため、3地域売上高の合計は総売上高に一致しない。
②営業利益・売上高営業利益率の推移
分析対象企業全体の営業利益を見ると、2006-2013年度の分析対象期間内に約0.9兆ドルから1.3兆ドルへ、年平均成長率5.6%で成長した。一方、売上高営業利益率の平均は、11.2%から10.4%に低下している(第Ⅱ-1-3-2-3図)。事業部門別には、医薬品や医療機器等の製造・関連サービスを含む「ヘルスケア」と「生活必需品」が安定的に高収益である一方、「工業」は低収益のまま推移している。「テクノロジー」や「原材料」は売上高営業利益率の変動が激しく、「通信」は2006年以降、急速に収益性を回復している(第Ⅱ-1-3-2-4図)。
第Ⅱ-1-3-2-3図 分析対象企業全体の営業利益・売上高営業利益率推移
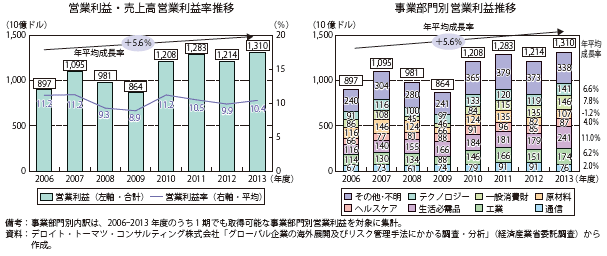
第Ⅱ-1-3-2-4図 売上高営業利益率推移(事業部門別)
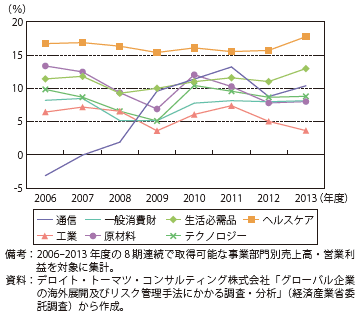
以上より、対象企業全体で見ると、売上高の成長性の観点では、地域別にはアジア大洋州地域が、事業部門別には「テクノロジー」、「生活必需品」が牽引している。また、収益性の観点では、「ヘルスケア」、「生活必需品」が安定的に高収益を維持していることが読み取れる。
(3)各グローバル企業における稼ぎ方の違い
次に、本社所在地ごとの各グローバル企業群の成長性・収益性の特徴について、以下の観点135から分析していく。
①全社的な経営指標から見た稼ぎ方の違い:売上高年平均成長率(成長性)・売上高営業利益率(収益性)、設立・再編後年数分布と成長性・収益性、多角化度の分布と成長性・収益性、R&D投資額
②地域別の稼ぎ方の違い:成長性、地域別シェア
135 地域別の観点での分析においては、(1)②で述べたように、企業による情報開示状況の制約から、分析対象数がごく少数になるケースがあることに留意が必要である。
①全社的な経営指標から見た稼ぎ方の違い
(a)成長性・収益性
売上高及び営業利益については、アジア大洋州地域の高い成長を背景に、同地域に本社が所在するアジア系企業が最も高い成長(売上高年平均成長率11.2%136、営業利益年平均成長率10.1%)を示している。売上高営業利益率については、2013年度で見ると米国系(売上高年平均成長率13.2%)が最も高く、欧州系(同10.9%)がこれに次いでいる。日系企業は、特に売上高営業利益率が米系・欧州系の約半分(同6.6%)にとどまるなど、いずれにおいても各企業群中、最も低い値となっている(第Ⅱ-1-3-2-5図)。
第Ⅱ-1-3-2-5 図 売上高成長率、営業利益成長率、売上高営業利益率の比較
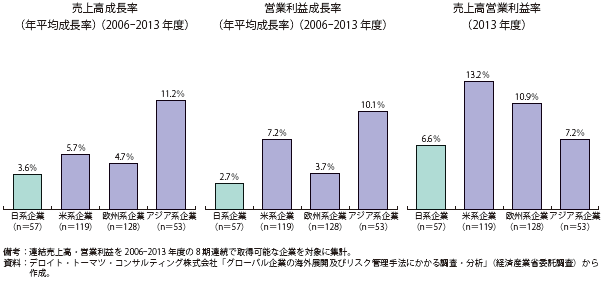
136 企業が情報を公開していない、または本分析での地域分類に一致しない場合があるため、地域別の売上高平均成長率・平均営業利益率と企業単位の売上高平均成長率・平均営業利益率は一致しない。
(b)設立・再編からの年数の分布と成長性・収益性
ベンチャー企業等の新規設立や、既存企業の合併・事業譲渡といった企業再編により改めて企業設立の登記が行われてからの年数137(本節において「設立・再編後年数」という。)と成長性・収益性の関係については、日系以外の企業では設立・再編後年数が50年以下の企業が多く、かつ、これらの企業では売上高年平均成長率、売上高営業利益率も高い傾向にある。一方、日系企業については、設立・再編後年数が51~80年の企業数が集中的に多いが、設立・再編後年数50年以下の企業は少ない。また、特に設立・再編後年数が20年未満の企業では、日系企業のみ売上高年平均成長率及び売上高営業利益率が著しく低い(第Ⅱ-1-3-2-6図)。
第Ⅱ-1-3-2-6図 設立・再編後年数の分布と成長性・収益性の関係
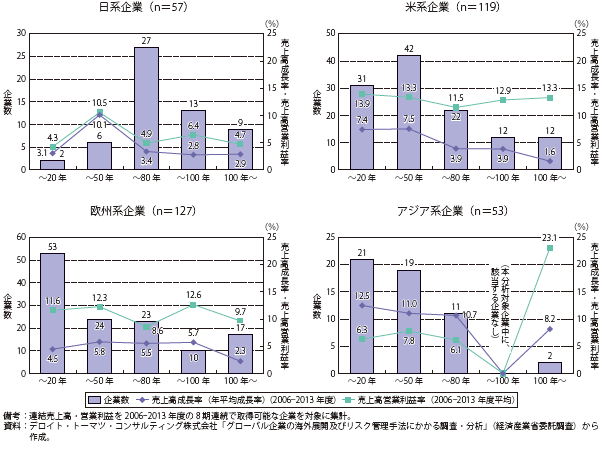
137 財務データの提供元であるBloomberg社によれば、各社のアニュアルレポート等に記載されている法人登録の年を「設立年」としており、創業した年とは異なる。企業が新規設立した年のほか、既存企業の合併や事業譲渡といった企業再編により改めて登記が行われた年等も「設立年」に含まれている。
(c)多角化度の推移、分布と成長性・収益性
ここでは各企業の「多角化度」について、事業の集中度を評価するハーフィンダール指数(HHI)138を算出し、各企業群内における多角化度の違いと、成長性・収益性との関係を分析していく139。
まず、多角化度の推移を見ると、アジア系企業を除き、全体的に近年やや専業的になる傾向が見られるが、日系企業のみ多角的な状態が継続している。また、日系企業の特徴として、多角的な企業と専業的な企業に二極化していることが挙げられる(第Ⅱ-1-3-2-7図)。
第Ⅱ-1-3-2-7図 多角化度の推移及び多角化度別企業数分布
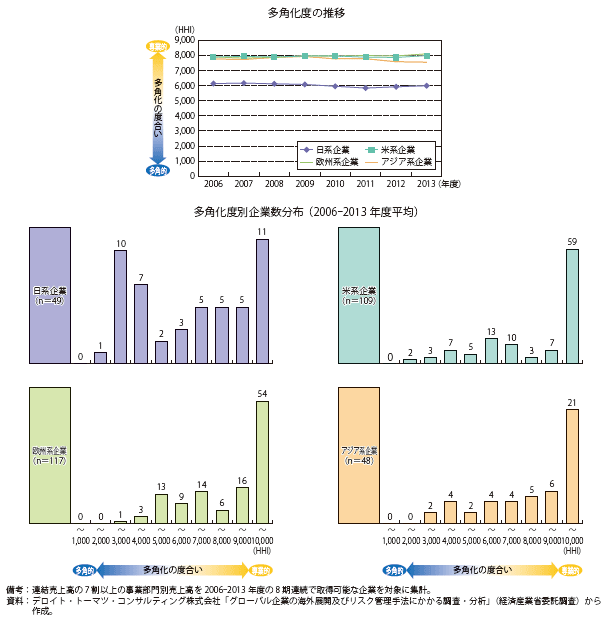
- Excel形式のファイル(多角化度の推移)はこちら

- Excel形式のファイル(日系企業)はこちら

- Excel形式のファイル(米企業)はこちら

- Excel形式のファイル(欧州系企業)はこちら

- Excel形式のファイル(アジア系企業)はこちら

次に、各企業群内で多角化度の高低によって企業を区分140し比較した場合、日系企業は多角的な企業の売上高の成長性、収益性がともに低い(売上高年平均成長率2.9%、売上高営業利益率5.1%)。
米系企業は成長性の違いはほとんど見られないが、多角的な企業の営業利益が伸びており、収益性を高めている(売上高営業利益率13.3%)。
欧州系企業は専業的な企業が売上高を伸ばしており(売上高年平均成長率5.0%)、収益性も高い(売上高営業利益率12.1%)。
アジア系企業は専業的な企業における売上高の成長性が極めて高い一方(売上高年平均成長率14.6%)、収益性は多角的な企業が上回っている(売上高営業利益率8.9%)(第Ⅱ-1-3-2-8図)。
第Ⅱ-1-3-2-8図 事業の成長性・収益性と多角化度の関係分析
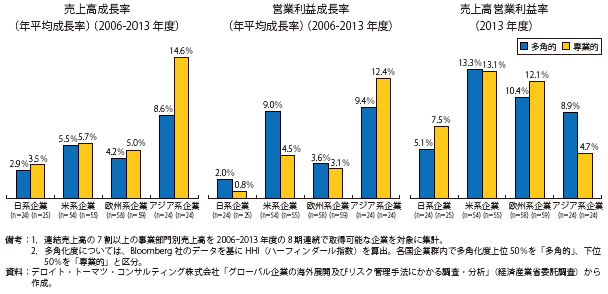
多角化度における企業数の分布を踏まえると、日系企業は多角的な企業が相対的に多く、これらの企業の成長性・収益性の低さが、日系企業全体に影響している可能性が考えられる。
そこで、多角的な企業の成長性・収益性の低さの要因を、事業部門ごとの収益性の構成比から見ると141、日系企業の事業の91%が売上高営業利益率10%未満(2006-2013年度平均)であり、米系企業(28%)、欧州系企業(66%)、アジア系企業(59%)と比較しても明らかに高い水準となっていたことがわかる(第Ⅱ-1-3-2-9図)。
第Ⅱ-1-3-2-9図 事業部門における収益性分布(2006-2013年度平均)
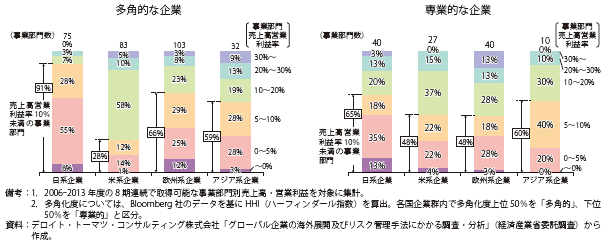
このことから、多角的な日系企業が抱える事業の多くが低収益となっており、これが日系企業全体の成長性・収益性を押し下げている要因の一つであることが示唆される。一方、他国企業群を見ると、特に米系の多角的な企業においては、売上高営業利益率10%以上の事業部門が7割以上を占め、多角化企業の収益性の高さを示している。
専業的な企業についても、米系、欧州系企業の事業部門における収益性が高いが、売上高営業利益率10%未満(同上)の事業部門の割合はいずれの企業においても半数~半数強の範囲にあり、多角的な企業で見られるような大きな差異は見られない。よって、日系企業のうち専業的な企業については、収益性において他国企業群とそれほど遜色のない事業を展開していることが伺える。
さらに、多角化度と売上規模の大小によって企業を区分142し、成長性・収益性を比較した。その結果、全体的な傾向としては、成長性は、売上規模にかかわらず専業的な企業群ほど高くなっており、収益性は、売上規模が大きい大規模企業においては多角的な企業群、売上規模が小さい小規模企業では専業的な企業群の収益性が高くなっている。
特に収益性の観点から各グローバル企業群を比較すると、日系の大規模企業については、全体的な傾向に反して、多角的な企業群の収益性が専業的な企業群と比較して低くなっている。なお、日系の小規模企業については、全体的な傾向と同様、専業的な企業群の収益性が高い。米系、欧州系企業を見ると、全体的な傾向と同じく、大規模で多角的な企業群と小規模で専業的な企業群の収益性が高くなっている(第Ⅱ-1-3-2-10図)。
第Ⅱ-1-3-2-10図 多角化度と企業規模による成長性・収益性の変化
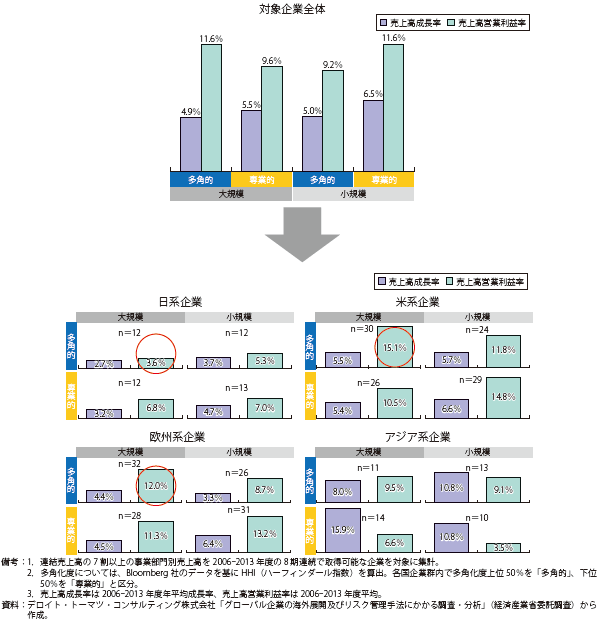
- Excel形式のファイル(対象企業全体)はこちら

- Excel形式のファイル(日系企業)はこちら

- Excel形式のファイル(米系企業)はこちら

- Excel形式のファイル(欧州系企業)はこちら

- Excel形式のファイル(アジア系企業)はこちら

売上規模の拡大や多角化によって、複数の事業間の相乗効果によって全体の利益率がいっそう高まることが期待されるが、本分析からは、対象企業数の限定もあるものの、日系大規模企業は規模の経済性や多角化のメリットを十分に得られていないことが示唆される。
138 本分析では、各企業の公表する事業をBICS (Bloomberg Industry Classification System)Level 2(Industry Group)49分類に再編したものをもとに、事業毎の売上高合計額に占める割合からHHIを算出して評価した。HHIについてはコラム8参照。
139 ここでは、多角化度を正確に把握するため、連結売上高の7割以上の事業構成比を取得可能な企業のみを対象とした。なお、第Ⅱ-1-3-2-9図は、事業部門別に分析を行う観点から、本条件を課さずに分析を行っている。
140 各国企業群において、2006~2013年度平均のHHIで多角化度上位50%を「多角的」、下位50%を「専業的」と区分した。このため、多角的な企業グループ、専業的な企業グループそれぞれに含まれる企業の多角化度については、各国企業群によって違いがある点に注意が必要である。
141 多角化度の分析に当たっては、多角化度を正確に把握するため、連結売上高の7割以上の事業構成比を取得可能な企業のみを対象としているが、本分析は、事業部門別に分析を行う観点から、本条件を課さずに分析を行っている。
142 2013年度売上高で上位50%を大規模企業、下位50%を小規模企業と区分した。
(d)R&D投資額
R&D投資は、企業の生産性を向上させる要因であるイノベーション活動の代表的な要素とされている。本分析対象企業のうち、R&D投資額が得られるものについて、売上高に対するR&D投資額の推移を見ると、米系企業、次いで欧州系企業は対象期間を通じて高い。日系企業は、アジア系企業よりは高いものの、欧州系企業よりは低い水準で推移している(第Ⅱ-1-3-2-11図)。
第Ⅱ-1-3-2-11図 R&D投資額(対売上高比)

R&D投資が収益に与える影響の評価については様々な手法があるが、ここでは、対象期間(2006-2013年度)内に限定し、R&D投資1ドルあたりの営業利益(同年度内平均)をもってR&D投資の効率性を評価する143。これによれば、日系企業のR&D投資1ドル当たりの営業利益(1.07ドル)は米系(2.44ドル)、欧州系(2.24ドル)の半分以下であり、日系企業のR&D投資効率が他の企業群から劣後している状況が読み取れる(第Ⅱ-1-3-2-12図)。
第Ⅱ-1-3-2-12図 R&D投資1ドルあたり営業利益(2006-2013年度平均)
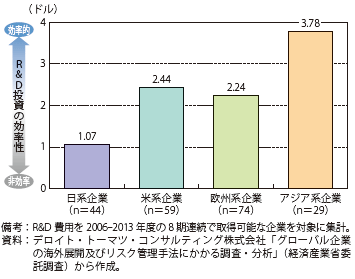
なお、R&D投資の効率性は業種によって異なる可能性があることから、産業構成の異なる各国の企業群同士を簡単に比較することは難しいものの、(c)での分析と同様に、各企業群内で多角化度の高低によって企業を区分し、R&D投資の効率性を評価した。その結果、他の企業群では、多角化度の高低によるR&D投資1ドルあたり営業利益について、大きな差異は見られなかった一方、日系企業では、多角化度上位企業で0.97ドル、下位企業1.51ドルと約1.5倍の差が生じていた(第Ⅱ-1-3-2-13図)。このことは、多角的な日系企業では複数の事業にR&D投資が分散し、有効な投資につながっていない可能性を示唆している。
第Ⅱ-1-3-2-13図 多角化度とR&D投資1ドルあたり営業利益(2006-2013年度平均)
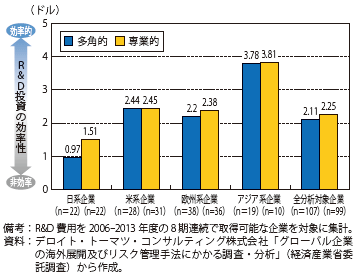
143 R&D投資額は、サービス業の企業を除外している。また、データを公開していない企業は含まれていない。
②地域別の稼ぎ方の違い
(a)地域別売上高から見た成長性
(2)①でみてきたように、本分析対象企業全体における地域別の売上高の傾向としてはアジア大洋州地域が最も成長し、全体の成長を牽引している。
地域別に本分析対象企業群の売上高の成長性を見ると、日系企業は全地域において売上高年平均成長率が他国企業に劣後している。特に、本社所在地を含む地域であり、かつ市場規模が拡大しているアジア大洋州地域において、日系企業の売上高年平均成長率は3.6%と極めて低い。これに対し、米系企業(同11.2%)、欧州系企業(同10.1%)及びアジア系企業(同8.5%)は、いずれも市場規模が拡大するアジア大洋州地域の成長を取り込んでいることがうかがえる。なお、日系企業は南北アメリカ大陸地域でも売上高年平均成長率が低水準であり(1.3%)、ヨーロッパ・中東・アフリカ地域においては日系企業のみマイナス成長に陥っている(第Ⅱ-1-3-2-14図)。
第Ⅱ-1-3-2-14図 地域別の売上高成長率比較(年平均成長率)(2006-2013年度)
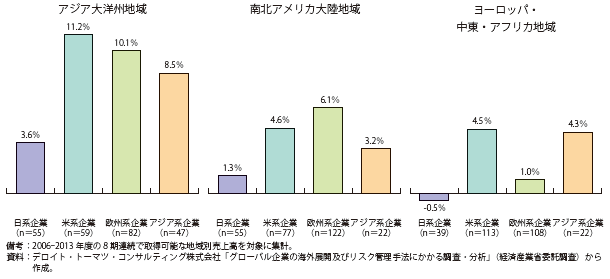
(b)地域別売上高の企業群別シェア
地域別に本分析対象企業群の売上高シェアを見ると、日系企業は全地域においてそのシェアを落としている。特にアジア大洋州地域において、引き続き最大のシェアは持つものの(40%)、成長性は最も低く(3.6%)、市場シェアを他国企業に奪われている状況にある。一方、米系、欧州系企業はそれぞれの本社所在地を含む地域での高いシェアを維持しつつ、成長市場であるアジア大洋州地域でのシェアを拡大している(第Ⅱ-1-3-2-15図)。
第Ⅱ-1-3-2-15図 地域別の売上高推移
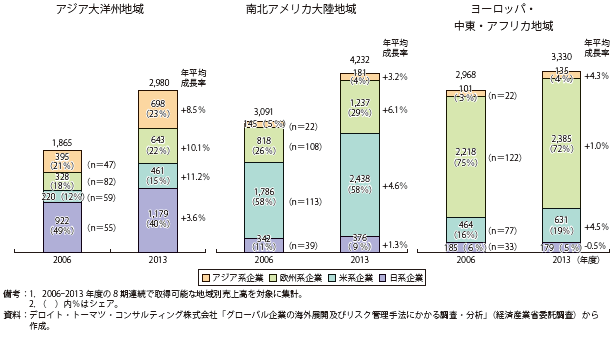
(c)各企業群別の地域別売上高シェア
分析対象企業群別に各地域における売上高シェアを見ると、いずれの企業群とも、それぞれの本社所在地を含む地域での売上が最も高くなっている。また、すべての企業群で、売上高全体に占めるアジア大洋州地域の売上高の割合が上昇しており、アジア大洋州市場の重要性が増していることがうかがわれる(第Ⅱ-1-3-2-16図)。
第Ⅱ-1-3-2-16図 各企業群別の地域別売上高推移
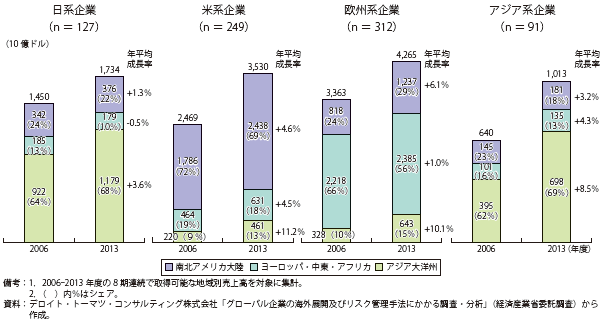
(d)アジア大洋州地域における日本と日本以外の地域の比較
(a)で見たように、日系企業は全地域において、売上高年平均成長率が企業群中最も低く、とりわけアジア大洋州地域での成長性において、大きく劣後している。このため、日系企業はアジア大洋州地域において最大のシェアを持つものの、そのシェアを他国企業に奪われている状況にある。
ここでは、日系企業全体の低成長の一因とも考えられるアジア大洋州地域での低成長について、日本と日本以外のアジア大洋州地域とに細分化し、本地域内での成長性を詳しく見ていく144。
日本と日本以外のアジア大洋州地域での売上比率を見ると、日系企業は、売上高のおよそ67%を日本市場で上げており、この割合は他国企業の3~5倍にのぼっている。
次に、日本と日本以外のアジア大洋州地域での売上高の成長性を見ると、日系企業の売上高年平均成長率(日本市場1.8%、日本以外のアジア大洋州市場7.2%)は、日本と日本以外のアジア大洋州地域の双方で、他国企業のいずれと比較しても半分以下に留まっている(第Ⅱ-1-3-2-17図)。
第Ⅱ-1-3-2-17図 アジア大洋州地域に占める日本での売上高の影響
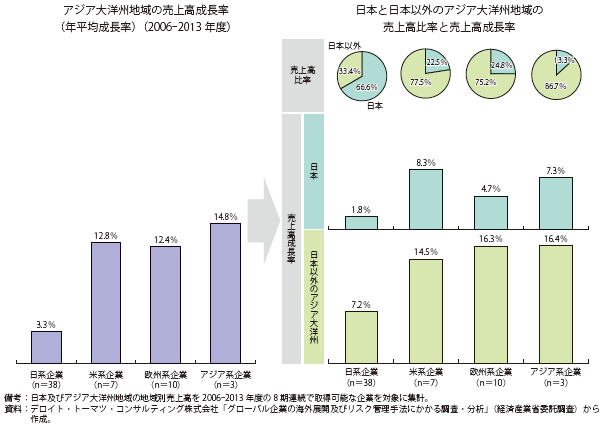
以上より、日系企業は市場自体の成長性が低い日本での売上比率が高いことに加え、日本及び日本以外のアジア大洋州市場のいずれの成長性でも他の企業群に劣後しており、日系企業が低成長となる一因となっていることが考えられる。
144 ここでの分析は、日本と日本以外のアジア大洋州地域のそれぞれの財務情報を公開している企業のみが対象であり、(a)~(c)までの売上高年平均成長率とは値が一致しない。
(4)まとめ
以上の分析より、主要なグローバル企業について得られたそれぞれの特徴は以下のようにまとめられる。
特に、限られた対象数という条件はあるものの、日系企業において、事業が専業的な企業では比較的海外企業に互しているが、多角的な企業において成長性、収益性が低いという結果となった。これについては、多角化による複数の事業間の相乗効果というメリットを十分得られておらず、逆に、リソースが分散し、高成長、高収益へと転換するための十分な投資が困難となっている可能性、また、自社の競争優位を軸としたポートフォリオの見直しがスピーディに行われていないことから、競争力を失っている可能性が示唆される。
一方、米系、欧州系の企業においては、事業ポートフォリオを柔軟に組み替えながら、規模の経済や多角化を高収益につなげ、独占的な地位を確立している大企業や、新成長分野での活動を展開する新興企業の存在が、企業群全体の成長性、収益性を高めていると考えられる。
①日系企業
・他地域の企業と比べ、全体的に低成長・低収益。主要企業内に新規設立・再編後50年以内の企業が少ない。特に多角的な企業で低収益。
・売上高に対するR&D投資比率が欧米系と比較して低い。
・全地域において低成長。特にアジア大洋州地域においてシェアを減少させている。
②米系企業
・最も高収益。主要企業内に新規設立・再編後50年以内の企業が多く、成長性も高い。特に大規模で多角的な企業と小規模で専業的な企業において、成長性・収益性とも高い。
・売上高に対するR&D投資比率が最高。
・地域別ではアジア大洋州、ヨーロッパ・中東・アフリカ地域で最も成長。
③欧州系企業
・米系に次ぐ高収益。主要企業内に新規設立・再編後50年以内の企業が多い。小規模で専業的な企業において、成長性・収益性が高い。
・売上高に対するR&D投資比率が米系に次いで高い。
・地域別ではアジア大洋州、南北アメリカ大陸地域で成長。
④アジア系企業
・成長性が極めて高い。主要企業内に新規設立・再編後50年以内の企業が多い。専業的な企業の成長率が極めて高く、多角的な企業は収益性が高い。
・売上高に対するR&D投資比率は最低だが、R&D投資1ドル当たりの営業利益は最高。
・地域別ではアジア大洋州地域で成長。