第2節 イノベーション力の強化のために
1.国際競争力ランキングから見る各国・地域のイノベーション力
世界経済フォーラム(WEF)の国際競争力ランキングで「総合」及び「イノベーション」について見てみると、スイス、シンガポール、フィンランド、イスラエル、台湾といった、日本と比べて国土が狭く、人口も少ない国や地域が数多くみられる(第Ⅱ-2-2-1-1表)。
第Ⅱ-2-2-1-1表 国際競争力ランキング(World Economic Forum)
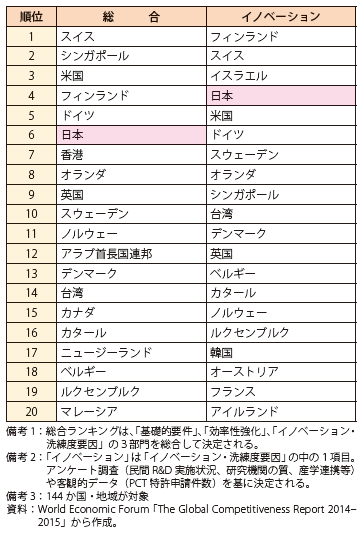
概して、このような国や地域は、「国土が狭い」、「人口が少ない」、「国内市場の規模が小さい」、「資源に乏しい」等といった制約により、「製造業よりもサービス業」、「労働集約型産業よりも知識集約型産業」、「海外市場指向」、「人材を重要な資源と考え教育に注力」というような傾向が見られる。
イノベーションを成長の源泉として位置づけることは世界的な潮流であり、イノベーションを先駆的かつ効率的に生み出すことは日本が国際競争に勝ち抜くための必要な条件であると言える220。2015年1月に産業競争力会議で決定された「成長戦略進化のための今後の検討方針」の中でも、ますます激化する国際競争の中で、日本経済が競争力を保つためには、未来社会を見据えた変革が不可欠であり、変革を引き起こすイノベーション創出力を強化することが重要であると唱われている。
本節では、上述のような制約を克服してイノベーションを生み出し、国際的な競争力の獲得に成功した国や地域、具体的には、イスラエル、スイス、台湾の事例を調査し、イノベーションを生み出した背景やそれを支える政府の支援策、エコシステム等について紹介する。これにより、日本がイノベーション力の向上を通じて立地拠点としての魅力を更に高め、海外からの人材、技術、資金等を呼び込む力を獲得するための方向につき示唆を得る。
220 中鉢良治(2015)「イノベーション生むには産学官の信頼関係構築を」日本経済新聞、経済教室。
2.イスラエル
イスラエルは1990年代以降、ハイテク技術に注力した国づくりを積極的に進め、その創造的な技術開発力により、急速な発展を遂げた。テルアビブ、エルサレム、ハイファ、ベエルシェバの4都市を結ぶ地帯には、ハイテク企業が集積し、「中東のシリコンバレー」、「第2のシリコンバレー」とも呼ばれている(第Ⅱ-2-2-2-1図)。
第Ⅱ-2-2-2-1図 イスラエルのハイテク企業の集積がみられる4都市
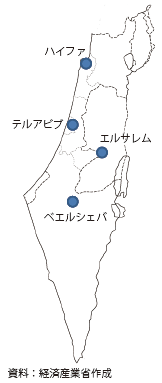
イスラエルの国土の面積は日本の四国程度であり、1948年の建国当時は約60万人だった人口は、持続的なイノベーションと移民政策により、2014年には約818万人221までに増加した。2014年の名目GDPは、約3,038億ドルと世界第37位、一人あたり名目GDPは36,991ドルと世界第25位に成長した222。
また、イスラエルには、世界のトップクラスのグローバル企業が多数進出しており、先述の4都市に研究開発拠点(以下R & D拠点)や製造拠点が集積している。現在、イスラエルにR & D拠点を置く海外企業は約250社、雇用者数は約5万人である223。また、イスラエルは、「Start-up Nation(スタートアップ国家)」とも呼ばれるほど、毎年、数多くのハイテク関連のベンチャー企業を輩出している。
221 イスラエル中央統計局。
222 IMF “WEO April 2015”
223 イスラエル経済省(2014-2015)“Israel Innovation Landscape and OCS activity”より。
(1)スタートアップ国家
イスラエルにおけるハイテク企業への投資額は、毎年10億ドルを超える水準で推移している。そのうち海外投資家の割合が増加しており、2013年では約76%を占めている(第Ⅱ-2-2-2-2図)。
第Ⅱ-2-2-2-2図 イスラエルのハイテク企業への投資額の推移
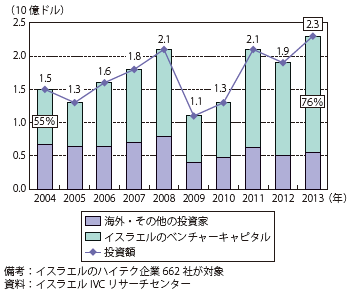
イスラエルは、自国市場の規模が限られていることから、起業家は初めから海外展開を意識した技術開発を進めるとともに、その多くは比較的早い段階で、国内外の企業によるM & A(合併・買収)によるイグジットを目標とする(第Ⅱ-2-2-2-3図)。イスラエルにおいては、世界的なグローバル企業等が、自らの事業分野を拡大し、新たな技術や優秀な人材を獲得する手段として、積極的なベンチャー企業のM & Aが行われている(第Ⅱ-2-2-2-4図)。また、この他のイグジットの手段として、IPO(新規株式公開)を目指す起業家もおり(第Ⅱ-2-2-2-5図)、ハイテク企業銘柄の割合が高い米国の株式市場のナスダック(NASDAQ)への上場企業数は、イスラエルは、米国、カナダ、中国に次ぎ世界第4位となっている(第Ⅱ-2-2-2-6図)。イグジットしたハイテク企業の取引額を部門別にみると、2014年では、ソフトウェアが28.3%、通信が20.5%、半導体が20.4%となっている(第Ⅱ-2-2-2-7図)。
第Ⅱ-2-2-2-3図 イスラエルのスタートアップ企業の設立数と操業状況の推移
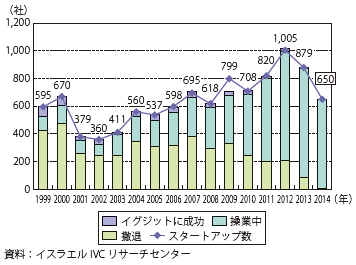
第Ⅱ-2-2-2-4図 イスラエルのハイテク企業の合併・買収(M&A)の推移
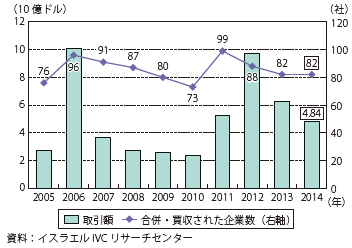
第Ⅱ-2-2-2-5図 イスラエルのハイテク企業の新規株式公開(IPO)の推移
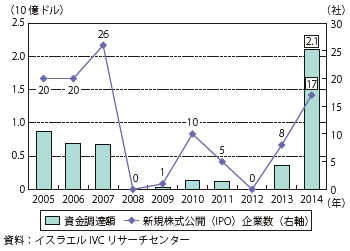
第Ⅱ-2-2-2-6図 国別のナスダック上場企業数の比較
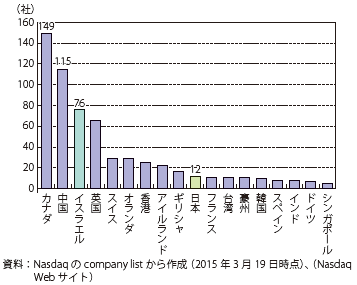
第Ⅱ-2-2-2-7図 イスラエルでイグジットしたハイテク企業の部門別構成比(2014年:取引額ベース)
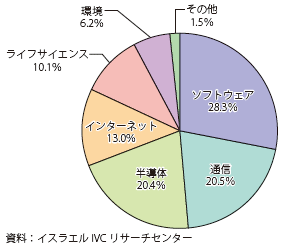
M & AやIPOにより成功を収めた起業家には、再び新たなアイデアや技術で起業を目指すシリアルアントレプレナーになる者、売却で得た資金を元にエンゼル投資家やベンチャーキャピタル(VC)になる者、またメンター(指導者、助言者)になる等して、イスラエルのベンチャー投資や起業家育成の立場に転向する者もおり、後に続く起業家達を支援する循環が存在する。
これまで、日本企業は必ずしもイスラエルとの協業に積極的であったと言えず、直近のイスラエルへの日本の進出企業数は14社程度に留まっている224。しかし、近年、イスラエルのハイテク技術獲得のため、欧米のみならず中国、韓国等の新興国企業によるイスラエルのベンチャー企業の買収や、イスラエル国内へのR & D拠点の設立が相次いでいる(第Ⅱ-2-2-2-8図)。それに伴い、日本企業にも次第に動きが見られるようになっている。
第Ⅱ-2-2-2-8図 イスラエル企業を買収した企業の国及び地域別構成比(2014年:企業数)
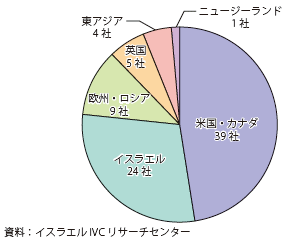
224 東洋経済新報社(2015)『海外進出企業総覧(国別編)2015年版』から日系現地法人数を取得。
(2)イスラエルの技術の特徴
周辺諸国との緊張関係から、イスラエルでは国防関連の軍事技術が発達したため、イスラエルのハイテク技術は、軍事技術の民間への転用が多いことが特徴である。国防軍(IDF)の技術開発は多岐の分野に渡り、そのレベルは非常に高い。また、イスラエルでは男女ともに18歳から兵役義務があり、有能な理工系の学生は、軍の研究開発部門に配属され、最先端の軍事技術に触れることになる。また、旧ソ連崩壊時に、ロシアから大量に流入した優秀なユダヤ系の科学者や技術者も、イスラエルの研究開発を担う人材として活躍してきた(第Ⅱ-2-2-2-9表)。
第Ⅱ-2-2-2-9表 イスラエル発の先進技術の例
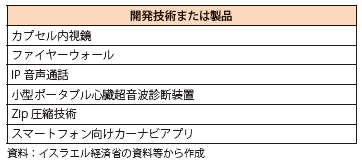
「イスラエルのハイテク産業が、直面している政治・外交・経済環境のなかで成長していくためには、国内で製造し、それを輸出するより、ソフト開発に特化する、あるいは既存の工業製品とは発想の違う製品を製品することで、既存の市場で一定の成果を上げた後、グローバルな企業に買収され、その傘下に入るほうが、効果的ではある。しかし、イスラエルには、国際的に知られるような工業製品のブランドがほとんど育っていない状況で、ハイテク・ベンチャー企業の繁栄だけでは、確保できる雇用者数に限界があることから、平行して国内の製造業を育成していく必要がある」との見方もある225。
225 中島勇(2014)。
(3)人材の充実
イスラエルは「人こそが国の宝であり、経済の原動力」と考え、幼少の頃から教育に熱心で、大学教育は世界のトップレベルにある。人口に占める科学者の割合も高く、量・質ともに高いレベルを誇っている。イスラエルには、現在8つの公式な総合大学があるが、中でもイスラエル第3の都市ハイファにあるテクニオン・イスラエル工科大学は、イスラエルの起業家の約7割を輩出しており226、ハイファの南東に位置するイスラエル最大のビジネスパークには、世界トップクラスのグローバル企業のR & D施設が集積し、産学連携も積極的に行われている。
226 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター(2010)「科学技術・イノベーション動向報告~イスラエル2010年版」より。
(4)イノベーションを生むエコシステム
イスラエルには、創造的なアイデアに基づく革新的な技術やスタートアップを次々と生み出し、育てるユニークなエコシステムが存在する。イスラエルのエコシステムは、イスラエル特有の起業家精神に富む文化に加え、政府の支援や経験豊かなベンチャーキャピタル・コミュニティーにより支えられている(第Ⅱ-2-2-2-10図)。
第Ⅱ-2-2-2-10図 イスラエルのハイテク技術・スタートアップを生むエコシステム
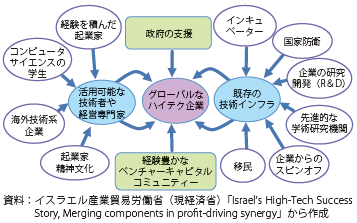
(5)政府によるイノベーション支援
イスラエルでは、経済省傘下のOffice of the Chief Scientist(以下OCS)が、スタートアップや産学連携支援を実施している。
①スタートアップ支援
「テクノロジロジカル・インキュベーターズ・プログラム」227は、リスクが高い革新的な技術アイデアを持つ企業のスタートアップを支援する。政府が積極的にリスクを負担することで、マイノリティー分野の研究開発の促進やベンチャーキャピタルを含む民間部門の投資機会を創出する他、研究機関から産業への技術移転や起業家精神の醸成も行う。
約2-3年のインキュベーション期間に、一社あたり57-86万ドルを助成を行う。うちプロジェクト総額の15%については、民間インキュベーターがベンチャーキャピタル等の出資者を取りまとめて調達し、残り85%について、政府が助成しリスクを政府が引き受ける。政府分については、事業が成功した場合のみ、収益の3-5%をロイヤリティーとして利息分と一緒に返済する。一方、民間インキュベーターは、その企業の50%までの株式を取得することができる。
現在、イスラエルには約20の民間インキュベーターがあり、そこから約160社が事業支援を受けている。インキュベーターは、有望な企業を見つけると、OCSに申請を行い、OCSは契約している専門家等と協議の上、融資の可否を決定する。融資の返済期限は6-7年で、企業はこの間、技術開発に専念ができるため、有力なベンチャー企業が育ちやすいといわれている。
本プログラムの成果により、毎年70-80社のスタートアップ企業が生まれており、1991年の開始から2013年までに約1,900社に対して約7億3千万ドルを出資した。約1,600社がこのプログラムを卒業し、うち約60%が民間投資家から出資を受けることに成功し、獲得した投資総額は40億ドルを越えている。
227 「Technological Incubator Program」(イスラエル経済省 Office of the Chief Scientist Webサイト)より。
②産学連携支援
「MAGNETプログラム」は、産業界と大学研究機関等からなる研究開発コンソーシアム形成を奨励し、先進的なハイテク製品やプロセスを生み出すことを目的としている。OCSは承認案件の研究開発費の66%を助成する。商品化への成功を成果としないため、ロイヤリティーの返済義務は生じない。また、本スキームにより開発された技術の特許権は開発者に帰属する228。外国企業も貢献の方法によりコンソーシアムに参加可能な場合もある229。これまでにカプセル内視鏡といった年間2,000万ドル規模の売上を達成する技術開発につながった事例がある230。
228 「イスラエル 研究開発促進のための優遇措置」(JETRO Webサイト)より。
229 「MAGNET -The Development of Technological Infrastructure for the Industry」(イスラエル経済省 Webサイト)より。
230 「イスラエルの産学連携の仕組み」(CP & C Japan Partners Webサイト)より。
3.スイス
スイスは、人口808万人(2013年)233で国土の面積は日本の九州程度である。西ヨーロッパの中心に位置し、四方をドイツ、フランス、イタリア、オーストリア、リヒテンシュタインの5か国に囲まれた26の州(カントン)からなる連邦国家である。主な公用語は、ドイツ語、フランス語、イタリア語であるが、ビジネスでは英語が広く使用されている。
世界有数の最裕福国としても知られ、2014年の名目GDPは約7,120億ドルで世界第20位、1人当たり名目GDPは87,475ドルで世界第4位で日本の約2.4倍である234。
スイスは、各種の国際競争力、イノベーションランキングで常に上位の評価を受けていることで知られている。世界経済フォーラム(WEF)の国際競争力ランキングでは、2009年以来、「総合」で第1位をキープしている他、直近の2014-15年版では、「イノベーション・ビジネスの洗練度」の部門でも第1位を獲得している。また、個別項目でも「全般的なインフラの質の高さ」、「教育制度の質の高さ」、「研究・訓練サービスの有用性」、「労使の協力関係」「才能ある人材を惹きつける力・引き留める力」等で第1位を獲得している。
国内総研究開発支出の対GDP比は約3%(2012年)で、欧州の中ではフィンランド、スウェーデン等に次ぐ水準であり、そのうちの約7割が製薬会社を中心とする民間部門からのものである。また、公的部門の研究開発支出は、大学や公的研究機関の基礎研究分野に手厚い。
スイスの代表的な産業は、精密機械、医薬・化学・バイオ、医療機器、金融、食品、医薬品、観光等であるが、特に時計に代表される精密機械や、「スイス銀行」と呼ばれるプライベートバンク機能で競争力を持つ金融業、チョコレートやチーズ等の名産物で知られる食品業等がある。スイスの主要産業の特徴は、高い品質とブランド力により高付加価値の製品やサービスを生みだし、国際的に競争優位を築いている点である。
また、スイスには、1,000社を越える世界トップクラスのグローバル企業が本社や地域統括本部を置いており、2003年から2011年までに300社以上がスイスに本社または地域統括拠点を移転したと言われている235。しかし、産業構造全体を見てみると、企業総数の99.8%、雇用数の約7割を中小企業(従業者数250人未満)が担っており、その約7割が家族経営企業と言われている(第Ⅱ-2-2-3-1図)。
第Ⅱ-2-2-3-1図 スイスの企業数と雇用者数(2012年:従業者規模別構成比)
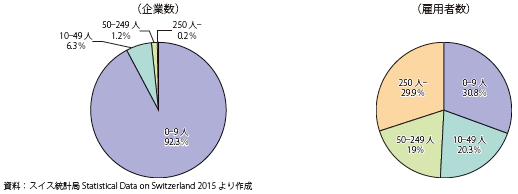
スイスは国内市場が小さく、需要の多くが国外にあるが、スイスとEUの間では一部の農産品等を除き、ほぼ完全な自由貿易関係にあり、中小企業にとっても欧州市場への参入が容易となっている。そのため、「スイス企業の国外事業は、企業自体の規模と余り関係なく、中小企業の3分の1は国外の企業と関係がある」との調査結果がある236。また、「スイスと日本の最大の違いは、スイス企業の多くの顧客は国外産業であり、資本関係のない企業であることだ。日本のように親企業から孫企業までピラミッド構造が国内で成立することはまれで、スイス企業は自ら新しい販路を国外に開拓することを求められている」237という見方もある。
233 United Nations, World Population Prospects
234 IMF “WEO April 2015”
235 「経営コンサルティングファーム、アーサー・D・リトル社の分析によると、2003年から2011年半ばまでに300社以上がスイスに本社または欧州統括本部を移転しました。こうした企業のうち53%は米国から、31%は欧州から、そしてアジアからは11%が移転して来ています。」スイス貿易振興会(2012)『事業展開ハンドブック ビジネス拠点としてのスイス』より。
236 「2010年スイス国際企業調査(Swiss International Enterpreneurship Survey 2010)」
フリブール経済大学バルトエッガー教授が実施したアンケート調査でスイス全土の625社を対象。
237 江藤学(2014)。
(1)グローバル企業の事業拠点
スイスは、特に企業の本社機能を設置する国として好まれており、1,000社を越えるグローバル企業がスイスに本社や地域統括本部を置いていることは先述のとおりである。スイスを選択する理由としては、「安定した政治経済」、「豊富な優れた人材」、「整備されたインフラ」、「欧州主要都市へのアクセスの良さ」、「企業経営に協力的な労働環境」、「優れた生活環境」等に加え、「低い税率」、「安全性」、「世界有数の研究機関の存在」等が挙げられている238。現在、スイスに進出している日本企業数は約150社239となっており、欧州本社や欧州における販売拠点を置く企業が多い。
238 スイス大使館スイス外国企業誘致局(2015)『スイスのビジネス投資環境』より。
239 同上
(2)産業クラスター
スイスでは、各地に多くの産業クラスターが形成されている。世界的に知られるスイス大手製薬会社の波及効果により、バーゼルとその周辺に製薬・化学・バイオテクノロジーのクラスターが誕生し、大手製薬会社とバイオベンチャーとのアライアンスやM & Aが活発である。機械、電子、金属工業は、スイス最大の産業部門であり、代表的な大手企業はほぼ全ての州に拠点を置いているが、特にチューリッヒ、ティチーノ、ライン峡谷、スイス中央部で成長を遂げている。また、時計産業は、歴史的背景があるジュネーブからシャフハウゼンに至るジュラ地方の「時計メーカーベルト地帯」にクラスターを形成しており、専門のノウハウを持つ熟練労働力に引き寄せられ、同様の技術を必要とする異業種企業もこの地に集まってきている。情報通信技術については、チューリッヒ湖コンスタンス地方にある連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZ)とその研究施設、及びチューリッヒ大学周辺に、米国を代表するIT関連のグローバル企業がR & D拠点を設置している240(第Ⅱ-2-2-3-2表)。
第Ⅱ-2-2-3-2表 スイスの主要産業クラスター
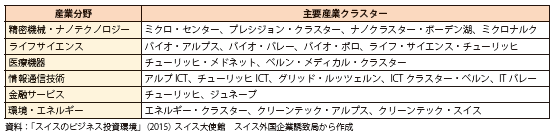
240 スイス貿易振興会(2014)『事業展開ハンドブック ビジネス拠点としてのスイス』より。
(3)教育制度・優れた人材の育成
スイスには、高度な職業訓練や大学教育を受け、幅広い語学スキルを持ち、国際経験を積んだ人材が多いと言われている。
①職業訓練制度
高校入学時に大学進学を目指す進学コースと職業訓練の2つのコースに分かれるが、約7割が職業訓練コースに進む。職業訓練コースでは、週1~2日学校で授業を受け、残り3~4日は協力企業で研修を受ける。学校の授業では語学教育が重視され、国民の英語力は高い。職業訓練コースを選択する理由は、大卒に比べて就業機会に恵まれ、給与格差もないためである。職業訓練修了者が応用科学大学に進学し、学士や修士課程に行くことも可能である。この他国に例をみない独特な職業訓練コースがスイス国民に高い職能を与え、国の生産性を高めている。また論理的な知識と実践的な技能取得の組み合わせ(dual education system)が、起業家精神の育成にも役立っている。
②大学教育
スイス国民の国内の大学への進学率は2割程度である。うち、スイスの大学に進学するものは7割程度で、残りは米国やドイツ等の国外に留学する。大学進学率の低さは、OECD諸国の中でもトルコとともに最下位だが、特に問題視はされていない。
スイスの大学は、学部・修士課程の約半数、博士課程の7割以上が外国人留学生、教官の6割以上を外国人が占めており、海外からの優秀な人材を獲得する機関としての役割が強い。スイスの国立大学は、連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZ)と連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)の二校のみであるが、両校ともにヨーロッパ大陸におけるトップレベルの大学として高い評価を受けている。ノーベル物理学賞を受賞したアインシュタインは、チューリッヒ校の卒業生である。また、この2大学の他に、チューリッヒ大学、ベルン大学、ジュネーブ大学等の10の州立大学、スイス内の7地域に応用科学大学がある。
(4)企業誘致策
スイスでの企業誘致は、連邦政府と州の二段階で実施されている。連邦機関のスイス外国企業誘致局が最初の窓口となり、投資家を適切な州当局に紹介し、その後は各州の経済開発局が引き継ぎ、具体的な立地の提案や地域内の行政機関や自治体と連携し組織的なサポートを行う。連邦レベルと州・地方自治体レベルでの優遇措置があり、多くは設立後10年以内をめどに法人税の全額または、一部免税などが行われる241。こうした優遇措置の他にも、企業誘致のための土地整備や道路・インフラ整備、様々な支援策の提供により、各州が競って企業誘致を展開している。
「重要な点は、スイスの各州が国外からの誘致をねらっているのは、本社あるいは研究所など、各国外国企業の中枢となる組織であるということだ。(中略)スイスは日本以上の高人件費社会であり、工場などの生産組織の誘致にはスイス側も移転を考え国外企業側も魅力を感じていない。本社や研究所の場合、組織だけでなく、そこで働く労働者の多くも国外から移転してくることになるため、雇用の創出効果は大きくないが、高い給与を獲得できる雇用の創出ができることが、スイスにとって重要なねらいなのである。さらに、国外の大企業の本社幹部や研究者と言った高水準の人材がスイスに移動してくることは、スイスの生産性向上に対してもさまざまな効果をもたらす。(中略)このように、スイスによる国外企業の本社誘致は、税収や雇用の創出といった意味だけでなく、優秀な人材のスイス国内への勧誘という意味も持っている。」との見解がある242。
241 「スイス 外資に関する奨励」(JETRO Webサイト)より。
242 江藤学(2014)。
(5)連邦政府によるイノベーション支援
スイスにおいてイノベーション支援を担うのは、スイス国立科学財団(SNSF:Swiss National Science Foundation、以下SNSF)と技術革新委員会(CTI:Commission for Technology and Innovation、以下CTI)である。SNSFは基礎研究や国家として重要な研究、国際共同研究を支援し、特に若手研究者の育成に尽力しており、その原資は連邦政府予算と民間からの寄付となっている。一方、CTIは、「科学から市場へScience to Market」を設立理念とし、研究部門と産業部門の間に存在する「デスバレー(死の谷)」243を乗り越え、応用研究の成果を速やかに市場に投入するための産学協同プロジェクトに尽力しており、60年以上にわたり、応用研究開発プロジェクトへの資金提供の他、中小企業・ベンチャー起業支援、知識・技術移転支援等を通じ、産業と大学・研究機関との橋渡し役として、スイスのイノベーションを促進してきた(第Ⅱ-2-2-3-3図)。CTIではボトムアップの原則が採用されており、政府から大学・研究機関に対する助成金に上限を設け、支援するのはその人件費のみとし、プロジェクト参加企業に50%以上を負担させる義務を課している。プロジェクトの革新性と市場化の可能性を考慮の上、助成が決定される(第Ⅱ-2-2-3-4図)。
第Ⅱ-2-2-3-3図 スイスのイノベーションの創出過程におけるデスバレー克服のイメージ
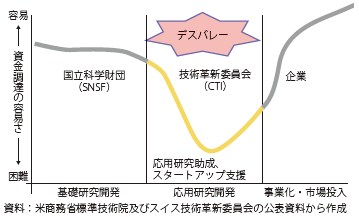
第Ⅱ-2-2-3-4図 スイスの研究助成のスキーム図
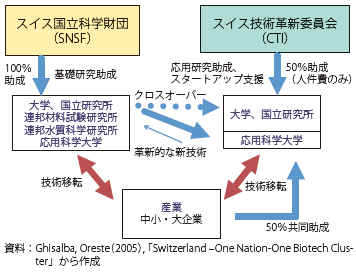
また、CTIの「ベンチャーラボ」事業は、将来有望な起業家を対象に、カスタマイズされた研修モジュールを通じて、ビジネスのアイデアを実現し、新たな会社を設立するための手段や方法を提供する。若手起業家は、専門的な指導を要請することもできる。本支援は、市場性が高い知識集約型の技術系企業に対し提供される。
CTIの「知識・技術移転サポート(KTT:Knowledge and Technology Transfer)」は、同一地域内の大学と産業界の知識及び技術移転を強化する事業で、専門家により運営されているNTNs(National Thematic Networks)が中小企業や大学が契約書を作成したり、プロジェクトを進展させるための実践的なサポートを行う。
243 デスバレー(死の谷)とは、基礎研究が応用研究に、また、研究開発の結果が事業化に活かせない状況あるいはその難関・障壁を指す。
4.台湾
台湾は、九州と同程度の面積を有し、人口は約2,337万人(2013年)である244。2014年の名目GDPは約5,295億ドルと世界第26位、一人当たり名目GDPは22,598ドルと世界第37位である245。
主要な産業は、電子・電気機械、鉄鋼金属製品、精密機器、プラスチック製品等となっている。2013年は、日本は台湾の輸入相手国・地域として第1位である一方、輸出相手国・地域としては第5位となっており、主な輸出先は中国、香港、米国、シンガポール、日本の順となっている。
台湾は、情報機器と集積回路等のエレクトロニクス産業で世界トップレベルを占めている。地場の中小企業が経済活動の主体となっており、企業数の99.7%、雇用者数の約7割を中小企業(従業者数200人未満)が占めている(第Ⅱ-2-2-4-1図)。
第Ⅱ-2-2-4-1図 台湾の企業数と雇用者数(2011年:従業者規模別構成比)
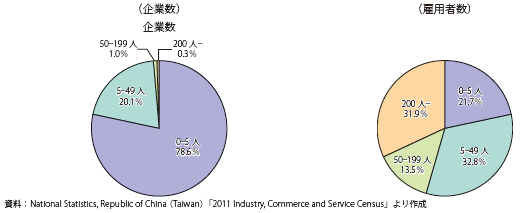
台湾は旺盛な起業家精神と活発な創業活動により、こうした中小企業を中心とした産業の成長を支えてきた。国内市場が小さいことから、海外での展開を目指している。また、起業の資金調達方法は株式資本によるところが大きい。台湾の株式市場における個人投資家の割合は約7割と言われており、旺盛な投資意欲がベンチャー企業への新規投資を資金面でサポートしている246。また、政府レベルでも様々な基金が設置されており、例えば工業技術研究院(ITRI Industrial Technology Research Institute、以下ITRI)からのスピンオフ企業の株式をITRIや行政院国家発展基金等が保有することでキャピタルゲインを得、この資金が次の技術開発や産業育成に活用されている247。
244 外務省「国・地域 台湾基礎データ」(外務省Webサイト)より。
245 IMF “WEO April 2015”
246 台湾の証券市場には、集中取引市場である台湾証券取引所(TWSE)と店頭市場である中華民国証券店頭売買センター(別名グレタイ証券市場:GTSM)がある。後者が成長企業向けで、日本のJASDAQやマザーズに相当する。アジアの新興市場では韓国のコスダック市場(Kosdaq)に次ぐ2番目の規模である。
247 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター(2014)。
(1)台湾のイノベーション力の評価
インフラ、とりわけハイテク分野における製造業の産業クラスターの質が高く評価されている。先述の世界経済フォーラム(WEF)の国際競争力ランキングにおいても、台湾はインフラ整備で世界第11位、クラスターの発展状況で世界第2位の高評価を受けている(2014-15年版)。
これは、1972年に政府主導で建設された新竹サイエンスパークが、台湾のハイテク産業のクラスター形成に大きく貢献し、パークに隣接して立地するITRIが、台湾のハイテク産業の発展や起業に大きく貢献していることが大きい。
(2)政府によるイノベーション支援
工業技術研究院(ITRI)は、1973年に経済部傘下に非営利組織として設立された研究機関で、基礎研究、応用研究、技術開発、商業化に至るまで幅広い領域をカバーし、特に応用研究と技術開発に活動の重点を置く。またITRIは、産業界と連携し、事業化に向けた共同研究、技術移転、コンサルティングサービス等も実施し、地場の中小企業を対象とする技術移転と研究者の起業を促すことで、先端技術のインキュベーションセンター、人材育成センターとしての機能も果たしている。
組織は、研究開発部門とサービス部門に大別される。研究開発部門は、電子・光電、情報通信、機械システム、クラウド・コンピューティング、材料化学、グリーンエネルギー・環境等を対象とした15の研究所・センターから成る。また、サービス部門は、技術移転、商業化・産業サービス、戦略企画、マーケティング・コミュニケーション、国際センター等の10部門から成っている248。
ITRIの事業化支援は、技術的側面のみならず、施設や設備の提供、ベンチャーキャピタル、マーケティング、事業性評価など、研究成果を事業化する上で必要なあらゆる機能をサービス部門が提供しているところが特徴的である。
また、ITRIは1996年に開設した「オープンラボ・インキュベーションセンター」により、ベンチャー創出のためのプラットフォームを形成している。現在の本施設への入居状況は70企業、1,006名であり(2014年)、ITRIと共同研究を実施する外国企業も入居可能で、日本企業も数社入居している。
ITRIが2014年までに創業支援を行った企業は260社(うちスピンオフ企業は103社)を超え、払込資本額は634億台湾ドル(約2,473億円)249となった。ITRIで技術開発を行った研究者が、自ら創業・スピンオフして創設者になるケースも多く、グローバルな企業に発展したスピンオフ企業としては、世界最大級の半導体製造専門のファウンダリーメーカーがよく知られており、新竹サイエンスパーク内に本部を置いている。
2015年時点の職員数は5,631人(博士:1,336人、修士3,051人、学士1,244人)であり、2万人を越えるITRI出身の産業界人材(うちCEOが70名超)によるネットワークがITRIの産業連携や人材育成をサポートしている。また、2012年の特許出願件数は2,190件、承認件数は1,715件(累積取得件数は、22,311件)となっている。産業連携の実績としては、2014年の技術支援相談件数が15,086件、技術移転(ライセンス)数は626件であった。
また2013年の総業務収入は184億台湾ドル(約718億円)で、その内訳は、民間及び公的資金による研究開発事業費が約90億台湾ドル(約351億円)、産業・技術サービス収入が84億台湾ドル(約328億円)、技術移転収入が約9億ドル(約35億円)となっている。ITRIのように多くの資金を外部から獲得している公的研究機関は世界的にも珍しいと言われている。
ITRIの取組みは、米国大統領科学技術諮問会議の「先進的な製造業におけるアメリカのリーダーシップを確保するための大統領への報告書」(2011年5月)250の中で、ドイツのフランホーファー研究機構と並び、製造業におけるリーダーシップ発揮のために、イノベーションや研究開発に積極的に取り組む国々の事例として取り挙げられている。
248 台湾工業技術研究院(ITRI)Webサイトより。
249 台湾ドル=3.9円で換算(2015年4月30日時点)
250 The U.S. Executive Office of the President, President’s Council of Advisors on Science and Technology (2011), “Report to the President on Ensuring American Leadership in Advanced Manufacturing”, p. 7
(3)ハイテク産業クラスター
1980年代に入り、それまで主流だった繊維や食品といった軽工業製品が国際競争力を失い、台湾は労働集約型から資本技術集約型へと産業構造の転換を迫られることになった。このような状況の下、工業技術の研究開発を促進する目的で台北市の西南約70kmの新竹市郊外に「新竹サイエンスパーク(新竹科学工業園区)」が設立された。奨励するのは、電子・コンピュータ関連、精密機器、バイオ等のハイテク・高付加価値産業に限定し、単にインフラの整備だけでなく、研究開発の推進、人材の育成及び確保、優遇税制等の政策もパッケージとして推進してきた251。
サイエンスパーク内の企業は、台湾清華大学、台湾交通大学等の近隣大学やITRIから共同研究開発や技術移転、人材育成等、技術・人材の両面の提供を受けている252。
新竹サイエンスパークは、設立からこれまでの30年余り、台湾経済の発展に大きく貢献してきており、現在パーク内には、半導体、光電子工学等の分野の481社(2013年)が立地し、敷地周辺にも拡大を続けている。また、また新竹サイエンスパーク以外にも1995年に南部サイエンスパーク、2003年に中部サイエンスパークが設立されている(第Ⅱ-2-2-4-2表)。
第Ⅱ-2-2-4-2表 新竹サイエンスパークの発展の推移
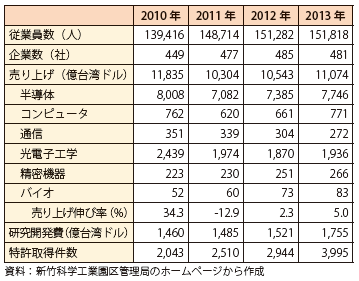
251 成清正和(2002)。
252 成清正和(2002)。
5.まとめ
これまで見てきた、国の規模としては小さくとも高いイノベーション力を誇る3つの国・地域の特徴は、以下のようにまとめられる。
(1)イスラエル:革新的な技術やスタートアップ企業を次々に生み出すことに成功。
・ハイテク企業が、海外投資家から多くの資本を調達。
・世界規模のグローバル企業のR & D拠点が国内に立地。
・政府が、起業の初期段階のリスクを積極的にとることで、スタートアップを支援。
(2)スイス:ハイレベルの企業や人材を海外から呼び込むことで、生産性を向上。
・世界規模のグローバル企業の本社や地域統括本部が国内に立地。
・優秀な留学生や給与水準が高い外国人労働者の受け入れと独自の教育システムによる高度人材の育成。
・連邦政府が、産業と大学・研究機関との橋渡し役として応用研究成果を速やかに市場に投入するための産学協同研究、スタートアップ、技術移転を支援。
(3)台湾:政府主導で優秀なハイテク人材に就業や起業等の機会を拡大。
・起業家精神に富む優秀な国内の理工系学生を研究機関やサイエンスパーク内の企業に受け入れ。
・政府が、半導体・エレクトロニクス産業に、資金等を重点的に投資し、政府機関傘下の非営利機関が事業化に向けた共同研究、技術移転、コンサルティング・サービスを実施。
これらの国や地域は、コスト競争力には頼れない現状下で、自国・地域の強みを見極め、効果的な政府等の支援も背景に、独自のシステムや事業環境に磨きをかけることによって、グローバルな競争の中で「イノベーション立国」としての地位を確立し、その評価を高めている。このような充実したイノベーション環境に世界中から企業や資金が集まり、新たなビジネスモデルや技術が生み出され、それが更なる「呼び込む力」となって、イノベーション環境を益々向上させるという好循環が見られるのではないだろうか。第1章第2節2.において、企業を「呼びこむ力」について検討した際、日本の事業環境の魅力・強みについての検証を行ったが、日本特有の魅力や強みを見極め、それらを最大限に活かしていくことが、魅力あるイノベーション環境を日本に創り出すための課題であることを、これらの国・地域の事例は示唆しているといえよう。
