第3節 グローバル経営力の強化のために
前章での検討を踏まえ、本節ではグローバルな競争が激化し、海外事業の割合が拡大する中で必要になってくる企業経営上の課題について検討する。
1.日本企業のグローバル化とその意味
まず、日本企業のグローバル化について見ていこう。日本企業の海外事業割合の拡大については、第1章第3節で詳しく述べたことから、ここでは、日本企業の海外事業活動は世界においてどのようなウエイトを占めているかを概観する。
世界の直接投資残高を見ると、先進国で9割近くを占め、日本の割合は2.3%である(第Ⅱ-2-3-1-1図)。日本の経済規模が世界第3位であることを考えれば相対的に高い割合ではない。一方で、対外直接投資のフローを見ると、日本のシェアは増加しつつある(第Ⅱ-2-3-1-2図)。近年、企業の海外事業拡大は、グリーンフィールド投資のみならず、既存事業の買収であるM&Aというかたちでも行われており、日本企業のM&Aの積極化はしばしば指摘されている。わが国のM&A動向について見ると、リーマン・ショック後に世界全体ではクロスボーダーM&Aの金額が減少する中、日本企業によるクロスボーダーM&Aの割合は増加している(第Ⅱ-2-3-1-3図)。日本企業のグローバルな活動は世界経済の中でそのシェアを増加しつつあると言える。
このような企業活動のグローバル化は、競争力の維持・強化という面もある。経営者に対するアンケートにおいて、10年後にも競争力を持つために日本企業が取り組む必要がある課題についてという質問に対し、グローバル化への対応という回答の割合は年々高まっている傾向がみられる(第Ⅱ-2-3-1-4図)。日本企業を対象とした実証分析においても、企業が海外進出の程度を高めることによる収益力向上への寄与を肯定するものもある253。
第Ⅱ-2-3-1-1図 世界の対外直接投資残高(2013年)
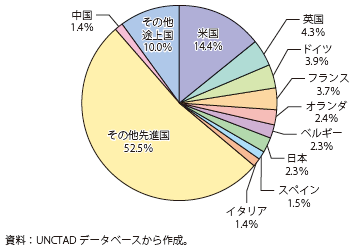
第Ⅱ-2-3-1-2図 世界の直接投資フローと日本のシェア(1990年-2013年)
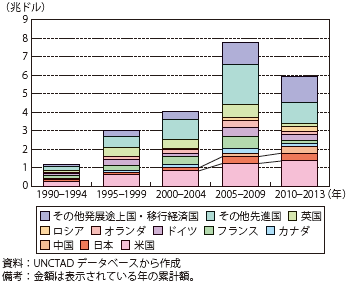
第Ⅱ-2-3-1-3図 世界のクロスボーダーM&Aと日本のシェア(1990年-2013年)
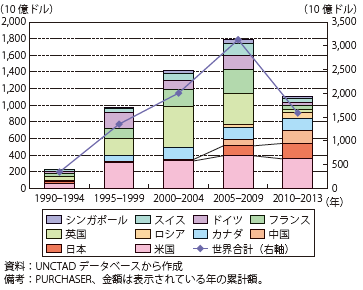
第Ⅱ-2-3-1-4図 10年後にも競争力を持つために日本企業が取り組む必要がある課題(複数回答、重要なものから5つ以内)
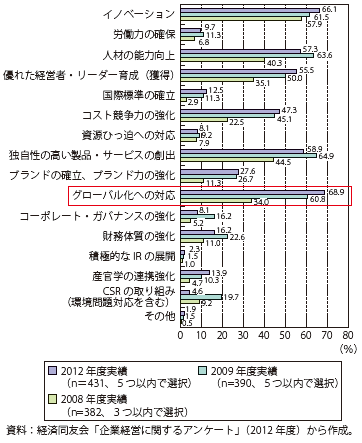
253 近藤、中浜、一瀬(2014)
2.適切なリスクをとる前提となるリスクマネジメント
これまで見てきた企業活動のグローバル化についての近年の変化は次のようにまとめられる。第一に、既に海外に事業拠点を置いている企業には、事業活動における海外比率の拡大やM&Aなどによるスピーディな海外市場の獲得などというかたちでのグローバル化の深化が見られる。これと並行して、企業規模を問わず、安価な労働力といったコスト面での理由よりも、よりマーケットを獲得することを理由とする海外事業の開始や拡大がなされるようになっている(第Ⅱ-2-3-2-1図)。第二に、生産や販売のグローバル化のみならず、研究開発についても海外で行う割合が高まるなど(第1章第3節)、海外事業活動の幅も拡大している。
第Ⅱ-2-3-2-1図 投資決定のポイント(大企業、中堅企業、中小企業)
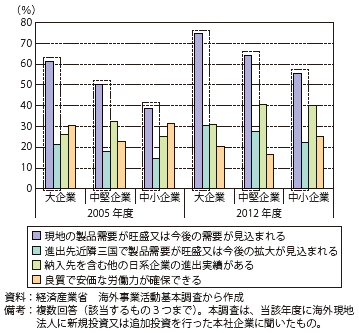
企業活動がグローバル化する際には、国内事業とは異なるリスクマネジメントが必要となる。まず、海外進出段階においては、そもそも海外に進出するかどうか、また立地国・地域の選定においてビジネス上その他のリスクが勘案される。続いて、グローバル活動を深化させる過程においては、海外拠点のマネジメント方法、親子会社間での情報共有体制や世界規模での人事などについて見直しが必要になってくると考えられる。同時に、国内とは異なるリスクから受ける事業活動全体へのインパクトも増大していくことが想定される。加えて、より競争の激しい市場において収益性を高めていくためには、適切にリスクをとる必要があるところ、そのためには精度の高いリスクマネジメントが欠かせない254。
グローバル企業のリスク認識は、必ずしも国内と海外を分けたものではないが(第Ⅱ-2-3-2-2表)、以下では海外拠点を設置し、拡大していく際に切り離すことのできない様々なリスクとその管理の態様について、アンケート調査等をもとに実態を示し課題を明らかにしていく。なお、ここではリスクマネジメントを「リスクを全社的視点で合理的かつ最適な方法で管理してリターンを最大化することで、企業価値を高める活動」と定義する255。
第Ⅱ-2-3-2-2表 グローバル企業上級経営者のリスク認識
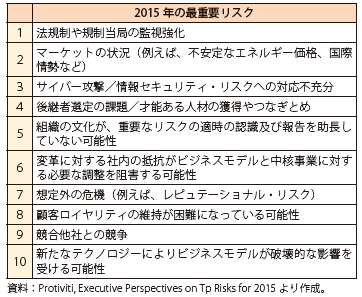
254 「持続的成長への競争力とインセンティブ~企業と投資家の望ましい関係構築~」プロジェクト(伊藤レポート)、平成26年8月、14頁。
255 経済産業省経済産業政策局産業資金課編(2005)、『先進企業から学ぶ事業リスクマネジメント実践テキスト―企業価値の向上を目指して』、財団法人経済産業調査会。
(1)リスク管理体制
まず、リスク管理体制についてみていこう。会社法及び同法施行規則において、コンプライアンスや損失の危険の管理に関する規程その他の体制の整備が求められており、有価証券報告書におけるリスクについての記載や統合報告書(又はCSRレポート)等におけるコンプライアンスやリスク管理体制等の説明など、企業のリスク管理体制についての情報は一定程度開示されている。しかし、具体的な管理体制の開示は企業によってばらつきがある。そこで、経済産業省の委託調査で海外売上高比率20%以上の日本の主要上場企業に対しアンケート調査を行い、補足的にヒアリング調査も実施した。以下では特に明記しない場合には、アンケートは先の委託調査によるアンケートを指す。
まず、リスクマネジメントに関する体制整備として明確なものに、リスクマネジメント部門の設置が挙げられる。比較的規模の小さい企業も含めて調査を行っている東京海上日動リスクコンサルティング株式会社のアンケート(2013年実施)によると256、2年前の同様の調査と比較して、リスクマネジメント部門の設置は、従業員1,000人以上の規模において専任部署が増加し、1,000人未満の部署においても兼任ではあるが設置の割合が増えるなど、体制の整備が進んでいる傾向がうかがわれる(第Ⅱ-2-3-2-3図)。ヒアリング調査によっても、米国におけるサーベンス・オクスレー法対応といったコンプライアンス対応の要請や、東日本大震災やタイにおける洪水等の経験から事業継続計画(BCP)を整備する必要性の認識が高まるなど、日本企業のリスクに対する意識は以前よりも高まっているとの指摘があった。
第Ⅱ-2-3-2-3図 リスクマネジメント部署の設置状況(2013年、2011年)
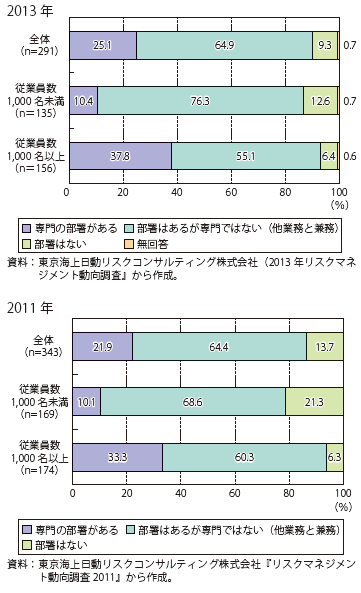
次に、対応しているリスクについて見ていく。リスクマネジメント部門が対応しているリスクについては、アンケートによると、想定されうる幅広いリスクに対して、リスクマネジメント部門において対応しているとの回答が大半を占めた(第Ⅱ-2-3-2-4図)。なお、個別のコメントの中には、事業リスクは事業部門が見るといった役割分担があるとの回答も見られた。海外売上高比率別に見ると、海外売上高比率が高い企業ほど多くのリスクに対応している傾向が見られた。また、リスクマネジメント部門が設置されている組織については、全体的には本社のみに設置している会社の割合が高いが、地域統括拠点にも設置している割合が高く、地域統括拠点もリスクマネジメントに重要な役割を果たしていることがわかる(第Ⅱ-2-3-2-5図)。グローバル全体でリスクマネジメント部門に所属している人数規模については、専任者、兼任者共に分散している(第Ⅱ-2-3-2-6図)。
第Ⅱ-2-3-2-4図 リスクマネジメント部門において対応しているリスク
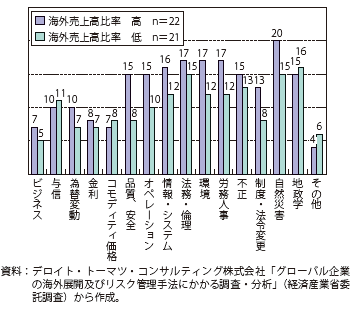
第Ⅱ-2-3-2-5図 リスクマネジメント部門が設置されている組織
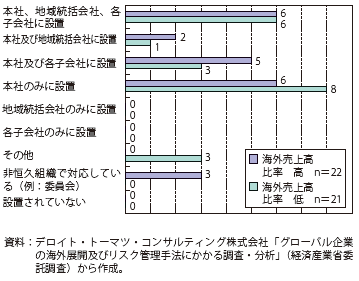
第Ⅱ-2-3-2-6図 グローバル全体でリスクマネジメント部門に所属している人数の規模
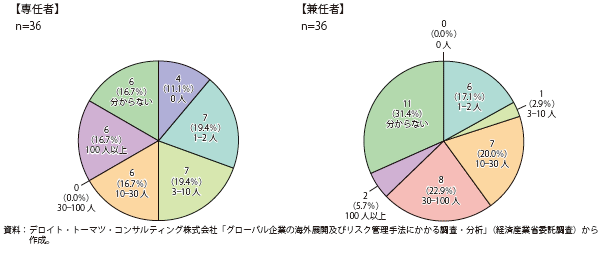
リスクを適切に管理することによって企業価値を高めるという観点からは、事業を拡大するに際して、どのようなリスクを重視しているかについてもみていく必要がある。市場規模や販売シェアといったビジネスに直結するリスクに加えて、政情・経済不安や法令変更リスクといった、特に海外事業において顕著に見られるリスクについても重視されていることがわかった(第Ⅱ-2-3-2-7図)。
第Ⅱ-2-3-2-7図 ビジネスの拡大にあたって重視しているリスク
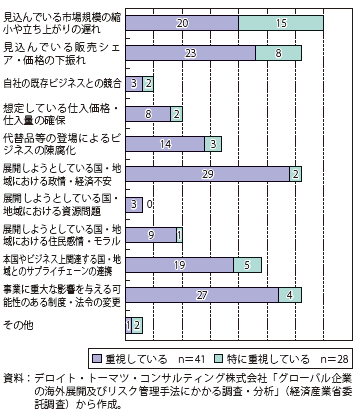
256 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社、『2013リスクマネジメント動向調査―事業継続の取組みの深化と戦略リスクへの挑戦』。
(2)課題
このようにリスク管理体制が進みつつあることがうかがわれる一方で、一定の課題も明らかになった。一つには、本社と海外子会社間でのリスクに対する意識の違いである。東京海上日動社のインドネシア、タイ、中国の日系子会社を対象とした調査によると、リスクマネジメントを推進する上で特に大きな障害・課題と感じる要素につき、他の回答と比べ割合としては高くないものの、「日本本社との間でリスク認識のずれがある」という回答割合が一定程度を占めている257(第Ⅱ-2-3-2-8図)。
第Ⅱ-2-3-2-8図 リスクマネジメントを推進する上で特に大きな障害・課題と感じる要素
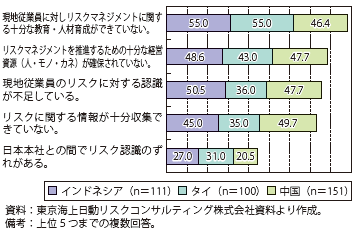
さらに、本社側を対象としたアンケートでは、リスクマネジメント部門が実効性を持って管理できている範囲についてという問いに対し、日本国内においては小規模子会社まで含めて管理できていると回答した企業が4割以上あるのに対し、海外の拠点やM&Aで取得した子会社については、管理できていないという回答が一定程度あった上、小規模子会社まで含めて管理できていると回答した企業は少なかった(第Ⅱ-2-3-2-9図)。同様の傾向は、オペレーショナルリスク及び自然災害リスクの管理状況に対する回答においても見られた(第Ⅱ-2-3-2-10表)。なお、リスクマネジメント部門が実効性を持って管理できている範囲について、補足的に行ったアンケート及び追加的なヒアリングによると、外資系企業においては、海外拠点についても小規模子会社を含めて管理できているという回答割合が高かった。
第Ⅱ-2-3-2-9図 リスクマネジメント部門が実効性を持って管理できている範囲
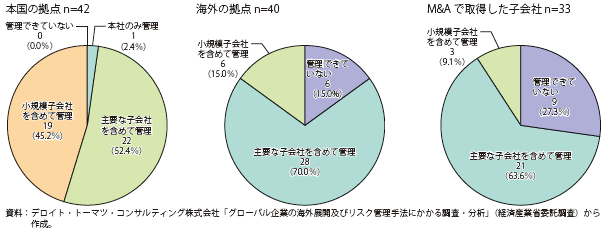
第Ⅱ-2-3-2-10表 リスクマネジメント実施状況(オペレーショナルリスク、自然災害リスク)
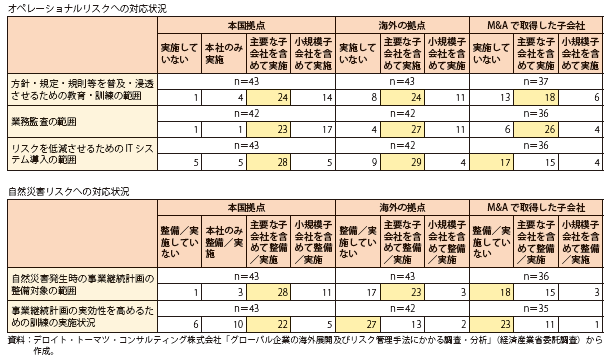
子会社の規模等によるこのようなリスク管理体制の違いはなぜ生まれるのだろうか。リスク管理を、会社の総資産への一定程度以上のインパクトを有するものという考え方によって行うのであれば、小規模会社のリスク管理の優先順位が下がることは想定されるが、M&A等で取得した子会社についてはそうはいえない。ヒアリング調査においては、M&A等で取得した子会社のリスク管理体制が本社と同等又は本社よりも優れている場合などに、必ずしも本社と同一のルールを適用しないことがあるという回答があった。
加えて、リスクマネジメントの組織間における役割分担についての課題も存在している。ヒアリング調査等においては、リスクマネジメント部で管理するべきリスクと事業部サイドで管理するべきリスクの役割分担や、海外法人の独立性を維持することとグループとして統一的な管理を行うことの両立について課題とする意見が出された。関連して、別の調査では、日系企業のアジア統括会社の悩みとして「基本的に事業部縦割りの会社であるので、事業部に横串を指すような統括会社機能は何をどこまでやるべきなのか悩んでいる」、「日本の本社にも同様の機能が残ってしまっているので、レポートラインが二重になり各現地法人から「どちらを向いたらよいのか」という苦情が発生している」といった課題も指摘されている258。
最後に、リスクを適切に管理することによって企業価値を高めるという観点からは、いかにして「攻め」のリスクをとっていくかという点も指摘できる。そこで、国内事業及び海外事業における収益目標(ハードルレート)の設定方法について聞いたところ、どちらの事業においても資本コストをベースに設定するとの回答が多いが、国内に比べて海外事業の方が、カントリーリスクやさらにバッファーを加えた収益目標を設定するという、より厳しい収益目標を課している傾向が見られた(第Ⅱ-2-3-2-11図)。
第Ⅱ-2-3-2-11図 国内及び海外事業における収益目標(ハードルレート)の設定方法
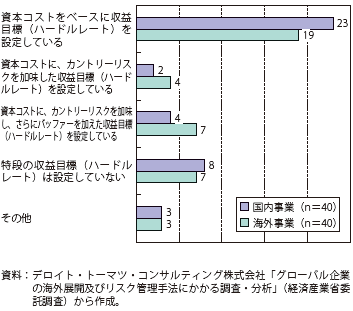
257 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社(2014)、リスクマネジメント最前線2014 №33「リスクマネジメントにおける本社と海外拠点の連携のあり方~海外拠点リスクマネジメント動向調査 調査結果~」
258 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社(2014)、リスクマネジメント最前線2014 №28、「アジア地域統括会社に求められるリスク管理」参照。
(3)地政学リスクへの対応状況
世界経済フォーラム(WEF)が企業経営者、学術関係者等に毎年実施しているアンケートによれば、近年の地政学的緊張の高まりを反映して、リスクの1位に「国家間紛争」が挙げられた(第Ⅱ-2-3-2-12表)。地政学リスクを含む広い意味での政治的リスクへの対応方法としては、①進出する国・地域の選定にあたってリスクをより慎重に判断する、②進出の際に合弁形態をとることによりリスクを低減する、③保険等の金融的手段により、リスクを低減する又は損失が顕在化したときの事業全体へのインパクト低減する、④事業分野や進出する国・地域を分散することにより、リスクが顕在化したときの事業全体へのインパクトを低減する、⑤相手国の政策上、自社の企業活動が重要な位置づけとなるような事業を展開することによりリスクを低減する等の方法が考えられる259。日本企業の海外法人の多くは米国やアジア地域に立地しており、その際には従業員の生命等が危険にさらされるリスクはそれほど高くないと判断されている可能性が高い。ヒアリング調査においても「地政学リスク」への対応については、一定程度安全性が確認される場所に進出するとの回答が多く得られた。
第Ⅱ-2-3-2-12表 懸念されるグローバルリスク
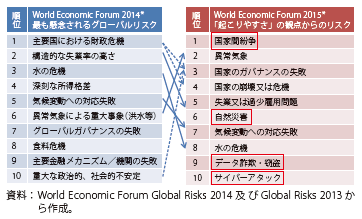
その一方で、上述のWEFのアンケート調査等は、従来よりも広い地域において地政学リスクが顕在化するというリスク認識を示唆している可能性もある。ここでは、仮に従来よりも地政学リスクが広い範囲で顕在化した場合には、より幅広い企業においてその対応が必要になるのではないかとの問題意識に立ち、日本企業の地政学リスクへの対応状況についてアンケート調査を元にみていく。
地政学リスクのマネジメントとしては、まず情報収集等によるリスクの察知が必要となる。アンケート調査の回答につき、海外売上高の低い企業と高い企業を比較すると、海外売上高の低い企業の方が外部専門家との契約や外部機関の作成した指数を利用する傾向が高かった。海外売上高の高い企業は、地政学リスクへの対応も含めてある程度自社で分析を行っていることが示唆される(第Ⅱ-2-3-2-13図)。
第Ⅱ-2-3-2-13図 地政学のリスクマネジメント(事前の情報収集)
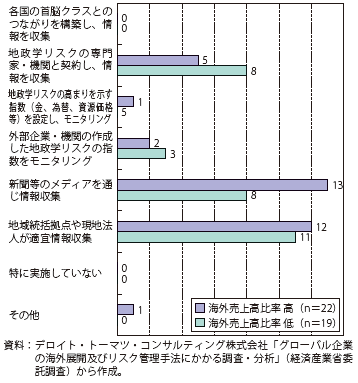
一方で、リスクの評価方法については、行っていないという対応も一定程度あるが、全体として定性的な評価方法の割合が高く、一部に定量的な評価を行っている例が見られた(第Ⅱ-2-3-2-14図)。ヒアリング調査においても、地政学リスクの数量的評価については困難とする見解が複数出された。
第Ⅱ-2-3-2-14図 地政学のリスクマネジメント(リスクの分析・評価)
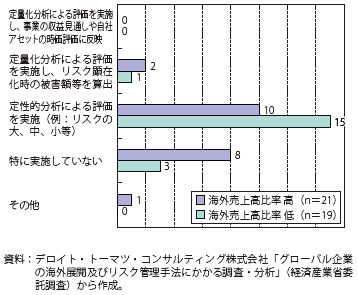
分析結果の情報の共有については、経営陣、リスクマネジメント部のみで共有するとする回答割合が高かった(第Ⅱ-2-3-2-15図)。その他の対応方法として、事業を継続できる体制の構築は、8割弱の企業が国内又は国外にて体制を構築していると回答したが、実践的な訓練については半数以上が実施していないという回答となった。保険・金融派生商品についてのヘッジは実施している企業としていない企業で回答が分かれた(第Ⅱ-2-3-2-16表)。
第Ⅱ-2-3-2-15図 地政学のリスクマネジメント(分析結果の情報共有)
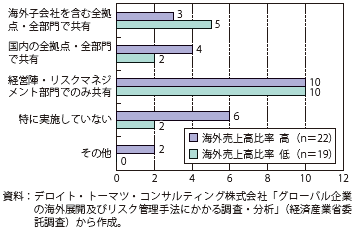
第Ⅱ-2-3-2-16表 地政学リスクへの対処方法
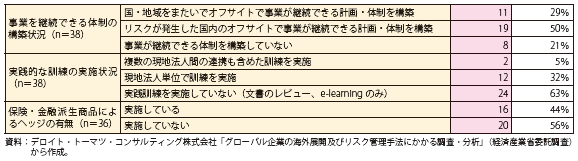
なお、対応を行っていない企業に対して、その理由を聞いたところ、リソース不足やコントロール不可能なリスクであるために対応するメリットがない等の回答が得られた。地政学リスクが顕在化した場合のインパクトは大きいものの、リスクの発生そのものを予防することが困難であることや、どの程度のリソースを割くことが適切であるかの判断が困難であること等が、リスクマネジメント上の課題であるといえる。
259 イアン・ブレマー(2014)、「保護主義化する世界で戦う8つのルール」、Diamond Harvard Business Review, Wells and Ahmed (2007), Making Foreign Investment Safe, Oxford University Press。
(4)まとめ
日本のグローバル企業については、リスクマネジメントに対する認識及び取組の充実が進みつつある状況がうかがえた。企業ごとのリスクマネジメントの充実度の差は、リスクの認定をどの程度きめ細かに(リスクの種類及び判断のタイミング)行うか、組織間の役割分担における曖昧さを減らしているかという点に現れているのではないか。
地政学リスクについては、企業のリスク管理を補助する観点から、政府等には情報提供のさらなる充実と迅速化が期待される。また、企業サイドにおいて、どの程度のコストをかけるべきかの判断が難しいものについては、ベストプラクティスや平均的な水準を知ることが、自社においてどの程度のコストをかけるかの判断においても役立つと考えられる。
3.経営のグローバル化とダイバーシティ
企業活動のグローバル化の進展により、人事マネジメントのグローバル化対応も必要となっている。「競争優位を構築するための経営戦略」としてのダイバーシティ経営は、①優秀な人材を獲得し、②多様化する顧客ニーズを的確に捉え、新たな収益機会を取り込むためのイノベーションを生み出すこと、③急激な環境変化に柔軟かつ能動的に対応し、リスクをビジネス上の機会として捉え機動的に対処すること、④国内外の投資家からも、「持続可能性」(サステナビリティ)のある投資家として信頼されること、等の要請に対応するために必要である260。ダイバーシティの企業経営上のメリットを指摘する分析は数多く発表されている(第Ⅱ-2-3-3-1表)。ダイバーシティの要請は、グローバルに経済活動を深化させている企業においてより強いと考えられ、世界的に人材獲得競争が激化していく中で、ダイバーシティ経営は喫緊の課題といえる。2012年に実施された経済同友会のアンケート調査によると、「グローバルな経営環境の激しい変化によって、企業に必要な人材の変化のサイクルが短期化される中、常にベストな人材で会社を満たすために必要なこと」という質問に対して、「人材育成」の次に、「人材多様性の向上」とする回答が多かった。グローバル化への対応としてのダイバーシティの必要性は広く認識されているといえよう(第Ⅱ-2-3-3-2図)。
第Ⅱ-2-3-3-1表 ダイバーシティの効果についての定量的分析

第Ⅱ-2-3-3-2図 グローバル経営環境の激しい変化によって、企業に必要な人材の変化のサイクルが短期化される中、常にベストな人材で会社を満たすために必要なこと(重要なもの3つ以内)
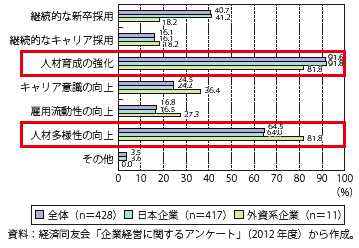
政府においても、ダイバーシティの試金石ともいえる女性の活躍推進を最重要課題に掲げ、「2020年に、指導的地位に占める女性の割合:30%」を目標に様々な課題に取り組んでいる。
以下では、日本企業のダイバーシティ経営の現状と課題について検討する。
260 経済産業省(平成27年3月)『ダイバーシティ経営企業100選 ベストプラクティス集』、3頁。
(1)女性の登用状況
それでは、日本企業におけるダイバーシティの現状はどのようなものであろうか。まず、ダイバーシティの一要素である女性の登用状況から見ていく。日本は、就業者に占める女性の比率は国際的にみて低くはないものの、管理的職業に従事する女性の割合は、11.3%(2014年)と低い水準に留まる(第Ⅱ-2-3-3-3図)。女性CEOや執行役員についても、グローバル企業を対象とした調査によれば、他国に比べて依然として低い水準である(第Ⅱ-2-3-3-4図)。
第Ⅱ-2-3-3-3図 管理職に占める女性比率の国際比較
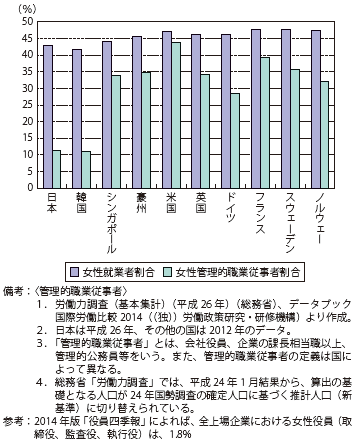
第Ⅱ-2-3-3-4図 グローバル3,000社の執行役員/CEOの女性比率
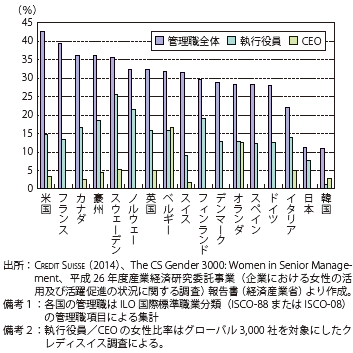
女性の登用が進まない又は管理職候補となる女性の人材プールが拡大しにくい原因の一つとして、長時間労働を指摘する見解もある261。慣行としての長時間労働は、管理職的立場になることを目指す女性のみならず、様々なキャリアプランを持つ女性全般にとって、能力を十分に発揮する仕事を行うにあたっての障害となっている。成長戦略としての女性の活躍推進の観点から、政府及び企業においては積極的な取組がなされているところであるが、省庁と企業の双方で、伝統的男女間の分業構造を前提にした雇用慣行をも変えていく積極的な取組が求められる。
261 産業競争力会議実行実現点検会合第12回(平成27年2月13日)小室淑恵議員提出資料において引用されている山口一男氏「女性の活躍推進と長時間労働との関係について」参照。
(2)外国人材の登用状況
次に、ダイバーシティのもう一つの要素である外国人材の登用状況についてみてみる。創業40年以上の大企業を中心に200件以上の回答がなされた経済同友会のアンケート(2014年10月-11月実施)によると、人数ベースでは、社外取締役や執行役員層で外国人人材の登用割合が高く、また、単体(親会社)本社における外国人材の有無についての回答からは、部長級、課長級においても一定の登用がなされているが、全体としては低い水準に留まっている(第Ⅱ-2-3-3-5表)262。現地法人の経営職に占める母国人比率についての国際的な調査を見ても、外国人材のさらなる登用の余地があると考えられる263。
第Ⅱ-2-3-3-5図 外国人人材の登用状況
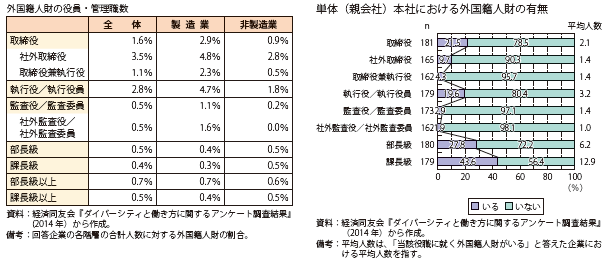
外国人材の登用を拡大し、組織のダイバーシティを高めるための一つの方策としては、留学生の採用拡大が考えられる264。それでは、日本における留学生の就職希望や採用の状況はどのようになっているだろうか。以下では、企業(上場企業及び非上場企業のうち従業員数上位企業を対象)、外国人社員及び留学生を対象に行った経済産業省委託調査によるアンケート調査を元に課題を明らかにしていく。
まず、留学生の内定状況について見てみると、卒業後に就職を予定している者の中で、日本で就職予定と回答した留学生は6割いるものの、その内の学部4年生と修士2年生で回答時点(2015年3月上旬)において内定をもらえた学生は約5割に留まっている(第Ⅱ-2-3-3-6図)。日本で就職を希望していながら、就職できていない留学生が一定数存在することがうかがえる。
第Ⅱ-2-3-3-6図 留学生の就職活動及び内定取得の状況
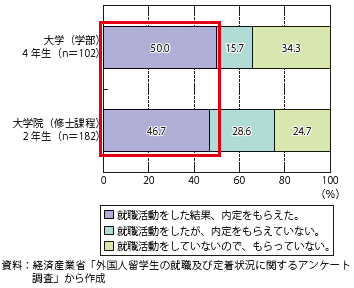
次に、企業が留学生を採用する目的に対する回答から、企業側の意識について確認してみよう。外国人留学生の採用理由として、「国籍にかかわらず選考を行ったため」、及び「社内の多様性を高め、職場を活性化するため」という理由が、ほぼ同じ回答割合となっており、企業側のダイバーシティに対する意欲の高さがうかがわれる(第Ⅱ-2-3-3-7図)。
第Ⅱ-2-3-3-7図 外国人留学生の採用理由(従業員規模別、複数回答)

また、企業の採用方法については、日本人学生と区別無く採用しているとする回答が多く、国籍にかかわらず優秀な人材を採用するという意識が表れていると考えられる(第Ⅱ-2-3-3-8図)。
第Ⅱ-2-3-3-8図 外国人留学生の採用方法(留学生の採用理由別)
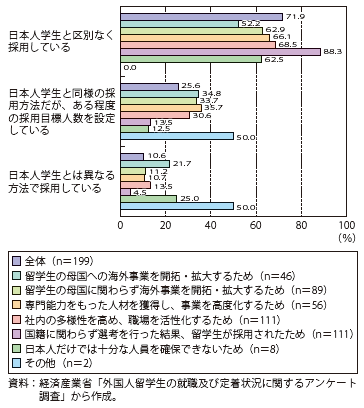
しかし、入社後の業務の中で、日本語能力も含めて、日本人学生と同様の水準を期待するあまり、外国人材ならではの強みが薄れる懸念も見られる。同調査で、ヒアリングを行った企業からも、ダイバーシティを高めることを目的に留学生を採用しているが、就職後数年経つと日本人と同質化しているとのコメントがあった。
一方で、留学生が就職活動中に困ったことについての回答からは、様々な課題があることが分かった。アンケートの回答には、留学生向けの求人が少ないことや、日本語への対応が困難であることが挙げられている(第Ⅱ-2-3-3-9図)。これに対して、英語による採用・選考を実施している企業は1割にとどまっているという結果であった(第Ⅱ-2-3-3-10図)。
第Ⅱ-2-3-3-9図 留学生が日本での就職活動中に困ったこと(複数回答)
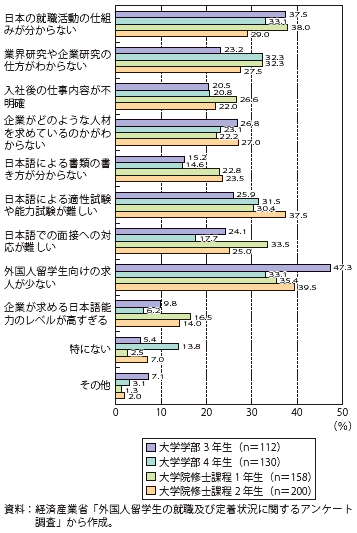
第Ⅱ-2-3-3-10図 英語による採用・選考活動の実施状況(企業)
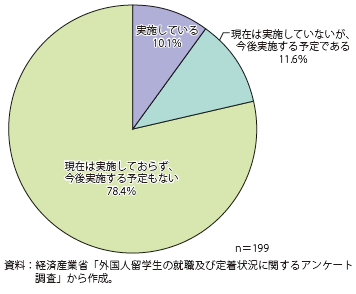
さらに、就職後の定着のための取組については、外国人社員も重視している「会社が将来のキャリアパスを明示する」については、既に実施している企業が半数に留まる一方、1、2年以内に実施すると回答した企業が24%存在し、キャリアパスの明示を課題としながらも、なかなか手がつけられていないことを示唆するものとなっている(第Ⅱ-2-3-3-11図、第Ⅱ-2-3-3-12図)。また、外国人社員定着のために重要だと思う取組について、企業と社員の双方に聞いた設問への回答を見ると、特に「外国人の経営幹部への登用」と「長時間残業の見直し」については企業と社員の間の認識のギャップが顕著となっている(第Ⅱ-2-3-3-12図)。
第Ⅱ-2-3-3-11図 外国人社員の定着のための取組の実施状況
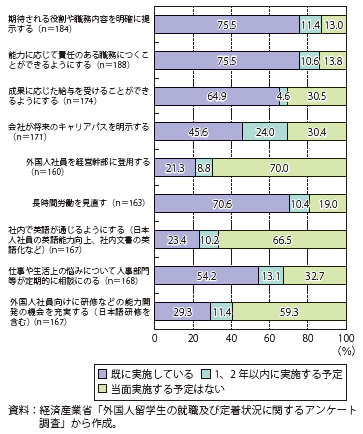
第Ⅱ-2-3-3-12図 外国人社員定着のために重要だと思う取組(企業・社員)
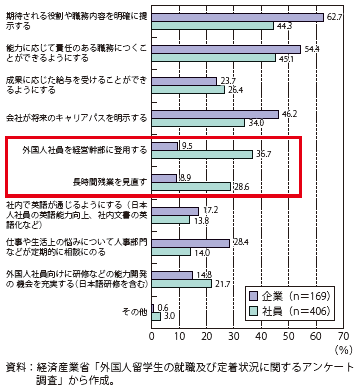
262 経済同友会(2014)『ダイバーシティと働き方に関するアンケート調査結果』
263 Harzing (2001), “Who’s in charge? An empirical study of executive staffing practices in foreign subsidiaries”, Human Resource Management, Vol 20, no. 2, pp. 139-158.においては、公表資料を基に、現地法人の経営職に占める親会社国籍の者の割合を公表データ等で明らかにしている。
264 政府においては、外国人留学生の受け入れを2020年までに30万人とする「留学生30万人計画」を発表して取り組んでいるところである。
(3)まとめ
日本企業がグローバル経営力を向上させる上でダイバーシティを進めていくことは急務である。日本政府は、成長戦略としての女性の活躍推進や、高度人材獲得のための環境整備等を通して、ダイバーシティ経営を後押しする政策を進めている。経済産業省としては、「ダイバーシティ経営企業100選」や東京証券取引所との共同の取組である「なでしこ銘柄」など、ダイバーシティや女性の活躍推進に優れた企業を表彰、選定することにより企業のダイバーシティ経営を後押ししている。加えて、外国人材獲得の観点からは、留学生の日本企業への就職や定着が重要であることから、2013年10月に一般社団法人留学生支援ネットワークが設立され、全国の国公立大学等の参加のもと、ビジネス日本語講座や就職活動に必要な情報、企業からの求人情報などを提供している265。
このような取組を背景に内なるグローバル化やダイバーシティが進むことで、日本企業が「稼ぐ力」を強化し、厳しさを増すグローバルな競争環境の中で優位に立つことを期待したい。
265 詳細については、一般社団法人留学生支援ネットワークのホームページ http://www.issn.or.jp![]() 参照。
参照。
