第5節 新しいルール形成に向けた取組
1.規制協力における世界の動向
(1)背景
世界経済のグローバル化が進展し、グローバル・バリュー・チェーンの重要性が認識されている中、国際的な通商政策の論点として、関税の撤廃・削減に加え、非関税措置の撤廃・調和を通じた「behind the border」(各国国内規制)に係るコスト削減をいかに進めていくかについて関心が高まっている。また、グローバル企業は、政府と連携し、自社の強みを基礎とした国際的な標準・規制作りを通じて、「地球規模課題の解決」と「市場獲得」を中長期戦略として取り組んでいる。
このような動きは非関税措置における将来の世界のルール形成に繋がるものであり、バイ、マルチといった様々な場で「規制協力」の議論が進められている。
(2)世界の動向
①米国―EU
これまでも欧米産業界は、5~10年先の自社製品投入円滑化の観点から規制導入に係る働きかけを自国政府に行っており、米国政府やEUはそのような活動を支援し、規制導入を行っている。
具体的には、米国EU間の規制問題に関する対話の場として、2005年以降、官民合同のフォーラムとして「Transatlantic Business Council」が毎年開催されている。2013年4月の会合では、70以上の製造業等の産業界が参加し、自動車等の規制協力の具体的分野の設定、「両方の市場で一度のテスト」原則の採用、国際標準の採用等の提言が行われた。この動きの一環として、米国エネルギー省(DOE)とEU共同研究センター(JRC)との間でSmart Grid Interoperability Centerを設置し、電気自動車の試験方法、標準化等の協力を進めている。
また、2013年7月に交渉が開始された「環大西洋貿易投資パートナーシップ(T-TIP)」交渉においても「規制協力」が産業分野ごとに議論されており、米欧産業界は協調して米EU間での実現可能性を検証し、規制当局に双方の交渉担当者、規制当局等に対して積極的な政策提言を行っている。EUは、2014年5月、5分野(自動車、化学、化粧品、医薬品、繊維・医療分野)における「規制協力」のポジションペーパーを公表し、このほかにも医療機器、農薬、ICT、エンジニアリングについて議論されている。また、2015年2月には、米国商工会議所が「T-TIPにおける規制調和・規制協力」に係る文書を公表し、米国とEUの規制当局間が規制同等性評価等を通じて協力することを提言している。
②EU―カナダ
2002年12月の日EUカナダ首脳協議の合意を踏まえ、2004年に「規制協力」に係る対話枠組(フレームワーク)を構築。化学、電気・電子機器、食品、自動車、木材製品、たばこ等の様々な分野で議論が継続されている。
また、批准に向けた手続きが進められているEU・カナダFTA(CETA)(2009年10月交渉開始、2014年9月交渉終了)においては、規制協力章において「規制協力フォーラム(RCF)」の設置が規定されており、必要に応じて民間事業者等関係者と協議を行うことが可能である旨規定されている。
③EU―韓国
2011年7月に暫定発効されたEU・韓国FTAにおいては、自動車、医薬品・医療機器及び化学の3分野に関するワーキンググループが設置され、これまで2回開催されている(2012年4月、2013年9月)。自動車では排ガス規制、UNECE(国連欧州経済委員会)規制と国内規制の互換性、医薬品・医療機器では医薬品の品質テスト等、化学では双方のREACH等の議論が行われている。
また、2013年11月のEU韓国首脳協議の合意を踏まえ設置された「ハイレベル産業政策対話」では、2014年9月の第1回会合において、規制協力、中小企業支援協力、イノベーション、技術協力等が議論されている。
④マルチでの議論
OECDでは、規制協力について、かねてから規制政策委員会で議論されてきたところ、2014年2月に「貿易と国際規制協力」というテーマのワークショップが開催されたことを皮切りに、同年10月から、貿易委員会においても、貿易の文脈における国際規制協力の効果等について本格的な議論が開始された。
また、スイス・ジュネーブに拠点を置くICTSD(International Center for Trade and Sustainable Development)と世界経済フォーラム(WEF)が共催する枠組みであるE15において、産業界もオブザーバーとして参加し、通商交渉専門家による「規制制度調和に関するタスクフォース」が設置された。2015年末のWTO閣僚会合と2016年初頭のダボス会議までに2025年の世界貿易システムに関する提言を発出することを目標としている。
(3)我が国の取組
現在交渉中の日EU・EPAでは、先進国同士での高いレベルの貿易投資ルール作りを目指しており、従来の関税撤廃・削減等に加え、互いの貿易投資に影響のある国内での措置についても議論を行っている。日EU・EPAの早期締結は、日EU間の規制協力に資するものである。
また、後述する「ルール形成戦略」の先行的事例として、我が国ではEUとの規制協力の議論を進めている。具体的には、日EUの官民が政策策定の初期段階から連携し、規制の相違を小さくしようとする取組として、経済産業省と欧州委員会域内市場・産業・起業・中小企業総局は、2014年4月の日EU産業政策対話において、「日EU規制協力」の具体的議論を進めることに合意した。この合意を受け、規制当局の専門家間において、自動車、化学、ロボット、紛争鉱物といった分野での議論が進展し、2015年3月の同対話において、12分野13項目に係る「日EU規制協力に関する共同文書」がとりまとめられた31。同年3月、日本経団連においても「日EU規制協力に関する提言」32が公表された。今後も官民一体となった規制協力の取組を進めていくことが重要である。
日EU規制協力に関する共同文書(概要)
- 生活支援ロボット普及に向け、製品認証の運用の統一を図るため政策対話を深める。
- 化学物質のリスク評価や製品中化学物質の情報伝達スキームに関し意見交換。
- 国連GHS分類におけるガスの燃焼性基準の見直しについて意見交換。
- R110(天然ガス自動車に関する国連規則)の改正及び水素・燃料電池自動車のGTR(世界技術規則)のフェーズ2に関し日EU産業政策対話・自動車WGにおいて議論を実施。他の新たな分野における協力を探求。
- EU紛争鉱物規制の適切な対応について意見交換。
- 併せて、エコデザイン政策、建材の省エネ性能、資源効率政策、医療機器、FLMs(Forced Localization Measures)、製造業におけるITの活用、個人情報保護規制分野への対応についても協力を深めていく。
2.ルール形成戦略
現在、国際社会においては、新興国の台頭及び西欧諸国の退潮と、非政府主体の台頭及び主権国家の相対化、という二つの現象が共に進行している。すなわち、急速な経済成長を背景として中国・インドを始めとする新興国の影響力が増大するとともに、国際社会における先進諸国の影響力が相対的に低下している。併せて、国際社会における多国籍企業やNGOといった非政府主体の影響力が増してきており、主権国家が基本構成要素である国際政治社会の構造に対して少なからぬインパクトを与えている。
これら二つの現象の主要原因は、戦後のGATT・IMF体制によって基盤が築かれた経済のグローバル化、世界市場の統合の深化であろう。GATT・IMF体制、及びGATTの後継であるWTOにおける累次の貿易自由化の努力、そして地域レベルや二国間で積極的に進められた自由貿易協定(FTA)や経済連携協定(EPA)に向けた交渉、更には各国の自主的な貿易投資自由化措置等を通じて、世界経済の相互連結性が飛躍的に向上し、この新たな環境を効果的に捉えた主要途上国は、新興国として経済力そして国際政治力を大幅に飛躍させた。また、多くの途上国においては、貧困問題を軽減することに成功した。一方で、経済成長以外の問題、例えば環境、人権、労働、といった社会問題の重要性が相対的に高まり、経済発展の持続可能性や包摂性といったいわば「質重視」の経済発展の重要性が叫ばれるようになっている。ポスト2015開発アジェンダや「ビジネスと人権」といったイシューを巡る国連を中心とする国際社会での活発な議論は、その一例である。これらの社会問題は、対応を誤ると、高度にグローバル化された世界経済の健全な運営を損なうリスクがあり、従って、これらは同時に経済問題でもある。
以上に述べた「質重視」の経済発展という考え方に寄り添う形で、国際政治経済に関連する諸政策は調整される必要があり、通商政策もその例に漏れない。「ルール形成戦略」は、上記の新たな国際環境に即応する形で考案され実施される「新思考の通商政策」である。国際的規模で見出される社会課題の解決、地球規模の「共通善」実現に向けて、様々な制度構築・ルール形成を行い、真の意味でグローバル化の「果実」を出来るだけ多くの世界市民が享受出来るように我が国も力を尽くすための通商政策である。
なお、従来より環境・省エネ等各種の社会課題を製品・技術・サービスを通じて解決してきた経験を持つ我が国は、このような国際情勢の変化に対応することができる大きな潜在力を有している。しかしながら、こうした我が国の製品・サービス等が普及するためには、その優れた社会課題解決力が適切に評価される必要があり、各国市場においてこのような適切な評価がなされる制度枠組みを作ることが極めて重要となる。ところが、国際的なルール形成は、各種の課題を発見し、概念・理念を通じてこれを定式化し把握するところから始まることが多く、仮にこうした議論の初期段階から関与することができなかった場合には、ルール形成の過程に実質的に参加することは出来ない。その場合、我が国が社会課題の解決に貢献できる技術や製品を有していたとしても、既に作られたルールを所与のものとせざるをえないため、その強みを十分に発揮できない可能性がある。したがって、こうした事態を避けるために、我が国は、政府・企業の双方が、課題設定やコンセプト構築などの制度設計の初期の段階から議論により積極的に参画し、自らの製品・技術・サービスが適切に評価されるような制度や仕組みを構築する必要がある。これらのルール形成を通じて、共通善の実現と併せて、我が国の製品・サービスの持てる「非価格競争力」が評価される市場を創出し、以て、新興国も参入し激化しつつあるグローバル市場での競争において、我が国が相応の位置を確保していくことが出来ることにもなる。以上の観点から、「ルール形成戦略」においては、日本企業の「社会課題解決力」が適切に評価されるような制度や仕組みを国際的に作るため、アジェンダ設定やコンセプト構築といった議論の初期段階からグローバルルールの策定にこれまで以上に能動的に参画することが求められている。
このような「ルール形成」の視点は、様々な分野、様々な形態の「ルール」、様々な場に関連してくる。ここでは、1.「高齢化問題」、2-1.「水問題」、2-2.「合併処理浄化槽」、3.「食糧問題」、4.「代替フロン」を事例としてとりあげる。
(1)高齢化問題
我が国の高齢化率は、2014年10月1日時点で26.0%33であり、2005年以降、世界最高水準となっている。長年にわたって様々な高齢化対策に取り組んできた我が国の経験及び知見を生かし、今後我が国と同等かそれ以上の速度で急速に高齢化が進展する新興国34に対して、新たな国際協力の可能性を追求する。
とりわけ我が国の介護システムは、高齢者の介護を社会全体で支え合う介護保険をベースに発展してきた経緯をもつ。我が国が開発してきた介護サービスや福祉用具・機器、介護人材の育成等に関する情報提供を頻繁に行うとともに、アジア諸国への各種制度の導入の働きかけ、ISO35やIEC36で議論されている介護福祉関連分野(自立生活支援(AAL:Active Assisted Living)等)の標準化の議論にも幅広く参画していく。
第Ⅲ-1-5-2-1図 高齢化率の動向予測
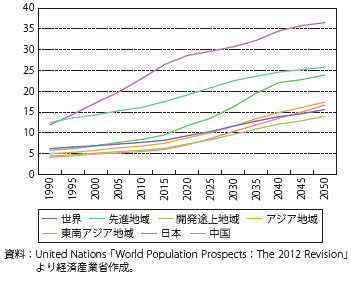
33 総務省統計局「人口推計」
34 例えば中国では、2012年末時点で高齢化率が既に9.4%に達しており、2005年以降、毎年、年0.2~0.4%の増加を見せている(出典:中国人民共和国国家統計局「中国年間統計2013」)。
35 国際標準化機構。電気分野を除く工業分野の国際的な標準である国際規格を策定するための民間の非政府組織。
36 国際電気標準会議。電気工学、電子工学、および関連した技術を扱う国際的な標準化団体。
(2-1)水問題
水資源に乏しい地域では、毎日の飲料水の確保は死活問題である。無収水率37や浄水技術、水道料金制度等様々な要因があるものの、十分な上水を得ることができない地域が局地的に存在している。その中で、欧米の多国籍企業やNGOの間で使用水量を可視化する動きが見られる。2014年7月下旬に、ISOにおいて、ある製品や組織、事業が水に関してどれだけの環境影響を与えたかを評価する「ウォーター・フットプリント(WFP)」に係る国際標準、ISO14046が策定、公表された。
37 漏水や盗水等などの原因により、浄水場から配水したのに料金が徴収できない割合。
(2-2)日本の生活排水処理システムの国際展開
新興国では現在、水質汚染が深刻化しており、その解決のためには適切な生活排水処理システムの導入が不可欠である。これに寄与すべく、これまでも下水道や浄化槽など日本で発展してきた生活排水処理システムの国際普及や国際基準化に向けた取組を進めてきたところである。このような取組の更なる推進に向け、本年8月にフィリピンのセブ市で予定するAPEC(アジア太平洋経済協力)高級実務者会合において、水に係る官民対話を日本政府の主催により開催し、水質汚染に対する取組の重要性をAPEC域内で共有する。セブ市は屈指のリゾート地である一方で、急速な経済発展を遂げたため、下水整備や住民の意識が都市の発展に追いついておらず、水質汚染が進んでいる。これを改善するため、セブ市は2012年に横浜市と「持続可能な都市の発展に向けた技術協力に関する覚え書き」を作成しており、水を含めた都市課題の解決に向けた取組は既に始まっている。このように、水質汚染に対する意識の高いセブ市を皮切りとして、日本の優れた排水処理設備・ノウハウが適切に評価されるような規制・標準等のAPEC地域への導入を目指す(第Ⅲ-1-5-2-2図、第Ⅲ-1-5-2-3表)。
第Ⅲ-1-5-2-2図 合併処理浄化槽の構造例
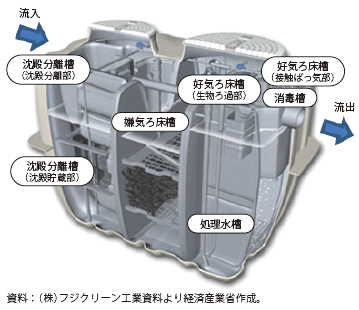
第Ⅲ-1-5-2-3表 生活排水水質規制例(ベトナム、インドネシア)(2011年8月現在)
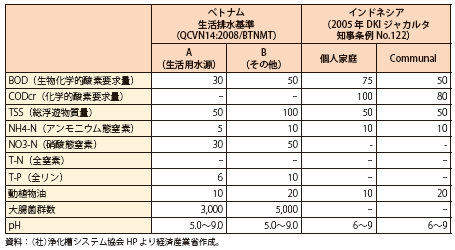
(3)食料問題
世界では、農業生産から消費に至るフードバリューチェーン全体で、世界の生産量の3分の1にあたる約13億トンの食料が毎年廃棄38されている。その一方で、アフリカなどの途上国を中心に8億500万人もの飢餓人口が存在する39。特定の地域で食料が廃棄されることは、別の地域における当該食料品の入手可能性や価格に影響を及ぼす恐れがあるほか、経済的損失、水・エネルギー等資源の過剰消費、温室効果ガスの排出を始めとする環境への無用な負荷を与えている。このような状況に対して、例えばEUは食品ロスの発生を2025年までに30%削減する方針40を打ち出しているほか、大手流通業者が食品ロス削減に貢献する企業の表彰を開始するなど、欧州諸国を中心に積極的な取組がみられる。我が国でも、食品ロス削減に向けた消費者の意識改革、3分の1ルール41と呼ばれる商慣習の緩和に向けた取組に加えて、鮮度保持効果のある食品梱包技術や冷蔵物流等の我が国が誇る製品・技術が適切に評価されるようなルール形成を進めていく。
38 FAO「What Causes Hunger?」
39 FAO(国連食糧計画)「The State of Food Insecurity in the World」
40 欧州委員会「Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe」(2014)
41 食品業界の商習慣で、製造日から賞味期限までの期間を3等分して納品期限や販売期限を設定するというもの。例えば、賞味期限が6か月の場合、製造者・卸売業者は製造日から2か月目までに小売店に納品し、小売店は製造日から4か月目までに消費者に販売する。
(4)代替フロン
モントリオール議定書42での国際的議論を経て、CFC43・HCFC44からHFC45へと、オゾン層保護のため、エアコン冷媒ガスの代替フロンへの転換が進められているが、代替フロンにも種々あり、その中でも地球温暖化係数(GWP)46の低いものが普及するよう政策的に促すことが必要である。他方、こうした冷媒ガスについて、燃焼性に関して過剰規制となっているとの指摘がある。すなわち、GWPが相対的に低いガスであっても、燃え広がりにくいため危険性が低いにも拘わらず、化学品の国際分類(GHS47およびTDG48)では可燃性については着火濃度のみを基準にしているため、「強燃性」に区分されてしまっている。このため、これを参照する各国の輸送・貯蔵の安全基準が過剰規制となっている現状がある。エアコン冷媒の燃焼速度については既にISOの安全分類も発行されており、GHSの燃焼性基準を改正し、燃焼濃度に加えて燃焼速度も加味した区分とすることにより、GWPの低いガスを強燃性ではなく「可燃性」へと適切に変更し、温暖化係数の低い冷媒ガスの適切な普及を図る(第Ⅲ-1-5-2-4図)。
第Ⅲ-1-5-2-4図 極めて引火性の高いガスのラベル(左:GHS、右:TDG)

上記の分野に限らず、今後もこのような「ルール形成」の視点を経営に取り入れることが、日本企業が今後の世界市場を生き残るための重要なカギの一つである。より具体的に言えば、世界の政策・ルール動向に敏感であること、制度形成を経営戦略に位置づけることの重要性を認識し、最適な内部体制を構築すること、国ごとの事情や政策体系に応じた効果的なアプローチをすること、などが必要とされる。一方で、企業だけでは活動に限界があり、政府によるアプローチも不可欠である。「ルール形成」の重要性を啓発するとともに、フェーズに応じて外国政府を含む多様なアクターへの働きかけを行い、我が国の企業活動を後押ししていく。
42 ウィーン条約(オゾン層の保護のためのウィーン条約)に基づき、オゾン層を破壊するおそれのある物質を指定し、これらの物質の製造、消費および貿易を規制することを目的とし、1987年にカナダで採択された議定書。特定フロン、ハロン、四塩化炭素などは、先進国では1996年までに全廃(開発途上国は2015年まで)、その他の代替フロンも先進国は、2020年までに全廃(開発途上国は原則的に2030年まで)することが求められた。
43 クロロフルオロカーボン。特定フロン。モントリオール議定書において、先進国では1996年までに、開発途上国では2015年までに全廃することが決定されている。
44 ハイドロクロロフルオロカーボン。モントリオール議定書において、先進国では2020年までに、開発途上国では2030年までに生産が中止されることが定められている
45 ハイドロフルオロカーボン。京都議定書が指定する削減対象物質(温室効果ガス)の一つである。
46 二酸化炭素を基準に、その気体の大気中における濃度あたりの温室効果の100年間の強さを比較して表したもの。
47 化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals)。全化学品を対象に危険性を分類し(爆発性、可燃性、急性毒性、発がん性、オゾン層有害性など)、危険有害性や取扱い方法について表示を定める国連の枠組み。輸送・貯蔵・建築・労働安全等の各国規制の国際基準となっている。
48 国連危険物輸送勧告(UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods)。国際的な危険物の輸送における安全性を確保するため、国連の専門家委員会が2年ごとに出している勧告。労働安全、消費者保護、貯蔵、環境保護等の各国規制の一貫性を確保することを目的とする。
