第1節 我が国の現況の貿易投資の課題
本節では、我が国の国際収支の動向を概観し、我が国の対外経済関係の特徴を考察する。2014年に過去最小の経常黒字、過去最大の貿易赤字となった我が国の経常収支であるが、2015年の動向を見ると、サービス輸出や第一次所得が牽引することにより、16.4兆円の黒字と大幅に黒字を拡大させた。本節では、我が国の財貿易、サービス貿易、対外直接投資の動向からそれぞれ成長の中心の変化を考察する。
1.我が国の対外収支の現状
はじめに、近年の我が国の経常収支の動向を見ていく。
我が国の2015年の経常収支受取額は対前年比5.1%増の126兆円となり、世界経済危機前の水準を超過し過去最高となった1。支払額は対前年比▲5.5%の110兆円と減少した結果、収支は16.4兆円の黒字と前年から12.5兆円の大幅増となった(第Ⅱ-1-1-1図、第Ⅱ-1-1-2図)。
第Ⅱ-1-1-1図 経常収支受取額の推移
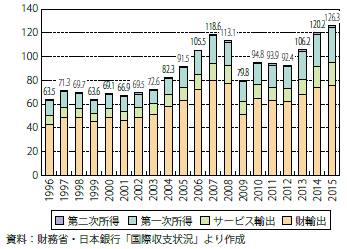
第Ⅱ-1-1-2図 経常収支支払額の推移
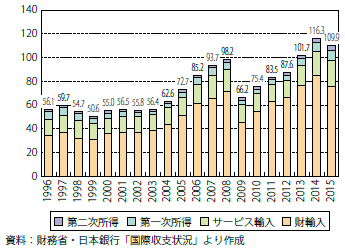
受取額の約6割を占める財輸出は75.3兆円と世界経済危機以降過去最高であったが、成長の中心は投資に対する収益等を示す第一次所得(対前年比5.1%増に対する寄与:1.9%)やサービス輸出(同1.9%)に移りつつある2,3。また過剰生産能力や資源価格の下落など、第1部で概観したような世界経済全体の動きによる影響も受けている(第Ⅱ-1-1-3図)。
第Ⅱ-1-1-3図 経常収支受取額及び成長寄与の構成比(2015)
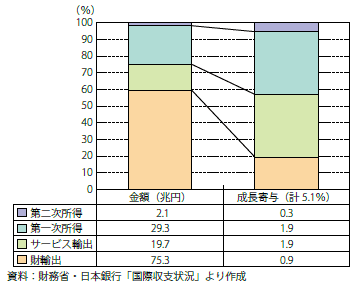
各トピックスに対する詳細な分析は次節以降に譲ることとし、本節では近年の経常収支を概観する4。
1 財務省「国際収支状況」確報値
2 財輸出による寄与は経常収支の伸び5.1%に対して1.0%に留まっている。なお第二次所得による寄与は0.3%であった。
3 通商白書2015では我が国の対外的な稼ぎ方を「輸出する力」、ヒトや企業を「呼び込む力」、海外展開することによる「外で稼ぐ力」という切り口(「3つの力」)から明らかにし、対外経済政策への示唆を提示した。詳細な分析結果は、同白書第2部を参照されたい。
4 我が国の対外収支のそれぞれの項目については、本白書の第2部における各章で取り上げていく。サービス収支の動向に関しては第2部第2章第1節、旅行収支の動向については第2部第2章第2節、我が国の地域における財貿易の在り方については第2部第3章第1節についてそれぞれ解説している。
(1)米国・輸送機器依存が深まる財輸出
2015年の財輸出は対前年比3.45%増の75兆6千億円(通関統計ベース5)と世界経済危機以降では最高額となったが、中国市場の変化に十分適応できておらず、国別では対米輸出、品目別では輸送用機器への依存度が高まっている。
2010年以降の伸び率である2.33%を寄与度により分解すると、国・地域別では米国(1.37%)・アジアNIEs(0.13%)・EU(0.10%)・中国(0.04%)・その他(0.68%)と米国向け輸出による寄与が圧倒的に高い。品目別では輸送用機器(0.8%)・一般機械(0.3%)・電気機器(0.2%)などと、自動車をはじめとする輸送用機器による寄与が極めて大きい。特に両者がクロスする「米国向け輸送用機器」による寄与は0.61%と集中度合いが高いことが見受けられる(第Ⅱ-1-1-4図、第Ⅱ-1-1-5図、第Ⅱ-1-1-6表)。
第Ⅱ-1-1-4図 2015年の輸出相手国シェアと輸出増加率に対する国・地域別寄与

第Ⅱ-1-1-5図 2015年の輸出品目シェアと輸出増加率に対する品目別寄与
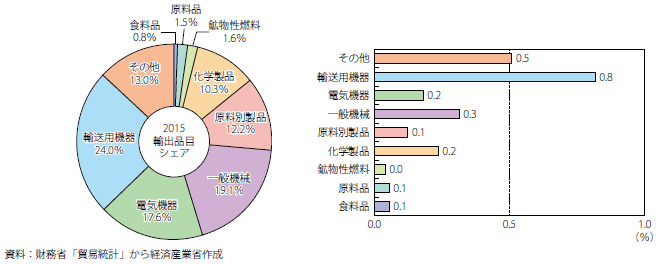
第Ⅱ-1-1-6表 輸出伸び率に対する国別・品目別寄与
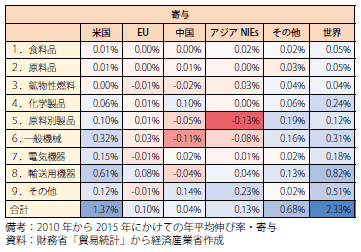
このような特定カテゴリーへの集中は国内の輸出元地域・業種についても観察される。
国内製造業による直接輸出額6の伸び率を見てみると、2010年から2014年にかけて、北海道(21.3%)や北陸(12.7%)などにおいて伸び率が高かった(第Ⅱ-1-1-7図)。
第Ⅱ-1-1-7図 地域別製造業輸出の年平均伸び率(2010-2014)
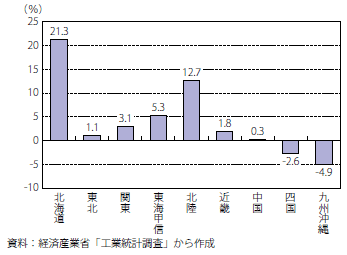
他方、2014年の製造業による直接輸出額の国内地域別のシェアを見れば、東海甲信(32.7%)・関東(22.6%)・近畿(18.6%)が高くなっているほか、2010年から2014年の間における年平均成長率2.6%のうち、地域別では「東海甲信地域」、業種別では「輸送用機械器具製造業」による寄与が大きく、両者がクロスする「東海甲信地域の輸送用機械器具製造業」による寄与は1.48%である7(第Ⅱ-1-1-8図、第Ⅱ-1-1-9図、第Ⅱ-1-1-10表)。
第Ⅱ-1-1-8図 我が国の輸出の地域別シェア(2014)
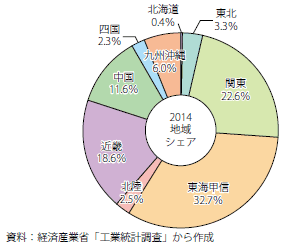
第Ⅱ-1-1-9図 我が国の輸出伸び率寄与の地域別シェア(2010→2014)
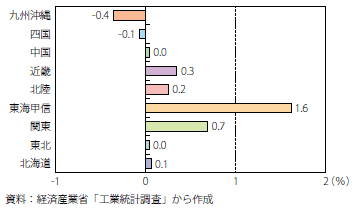
第Ⅱ-1-1-10表 製造業の輸出増加率に対する地域別・業種別寄与(2010→2014)
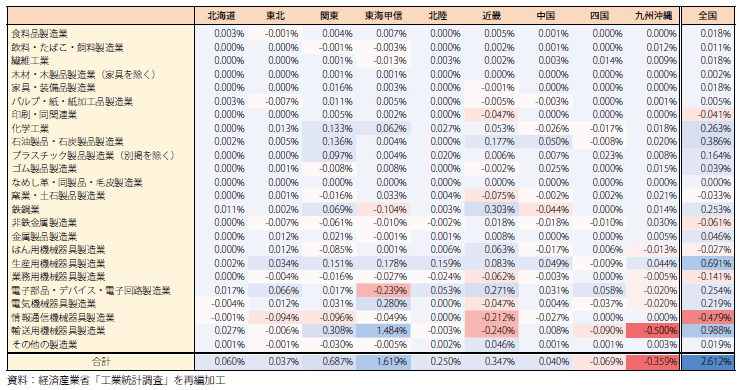
一方、2015年の財輸入は対前年比▲8.7%の78.5兆円となっている。背景には2014年後半からの原油価格下落があり、輸入額の23.2%のシェアを占める鉱物性燃料は対前年比▲34.2%と大幅に減少した。
中国などにおける過剰生産能力の影響も見受けられる。鉄鋼については、輸出数量は対前年比▲1.0%の下落に留まるものの、単価下落により金額は同▲7.3%と大幅に減少した。建設用・鉱山用機械など機械類の輸出額も対前年比▲3.6%と減少しているほか、輸入面でも、鉄鉱石は輸入数量・輸入金額ともに減少している。
他方、新興国の所得向上等を受け、農林水産物輸出は7,452億円(対前年比+21.8%)と過去最高となった。
そもそも、我が国は、少子高齢化で共通する欧州主要国と比較してもGDPに占める財・サービス輸出の割合が低い。我が国と同じく経常黒字国であるドイツ・中国より少ないことに加え、ドイツについては、EU域内との貿易を除いたとしても、我が国の方が対GDP比が小さい(第Ⅱ-1-1-11図、第Ⅱ-1-1-12図)。
第Ⅱ-1-1-11図 日中独の財サービス輸出入対GDP比
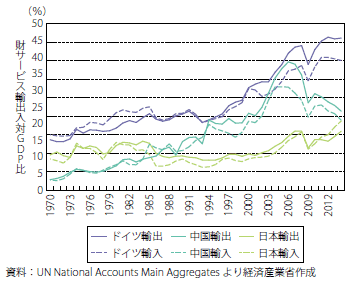
第Ⅱ-1-1-12図 欧州各国の輸出(対GDP比)(EU域外のみ)推移
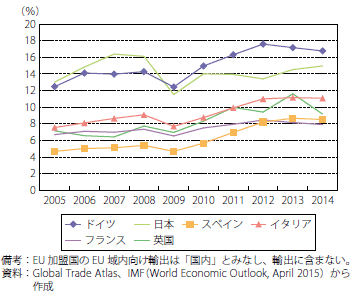
5 貿易統計と国際収支状況では、費目の計上方法の差異から財貿易の輸出入額が異なる。具体的には、①貿易統計の輸入額には運賃・保険料等が計上されているが、国際収支状況ではこれらはサービス収支に計上される。また②貿易統計では、税関(関税境界)を通過した貨物を計上しており、国際収支状況では、税関を通過したか否かにかかわらず、居住者と非居住者との間において所有権が移転した貨物を計上している。(詳細は財務省ウェブサイト参照)
6 経済産業省「工業統計」から作成。工業統計では各事業所からの直接輸出額が記載されており、個票レベルで集計することにより都道府県ごとの直接輸出金額を把握することが可能。ただし、製造業のみが対象となっていること、従業員が3人以下の事業所が除かれること、速報性が低いなど、業務統計である貿易統計や国際収支状況と比較するとデメリットもある。
7 このほか、地域からの輸出動向については、第2部第3章第1節において分析を行った。
(2)中国の消費へのシフトと我が国の対中輸出
我が国は貿易投資の面で中国との結びつきを強めてきた。これまで多くの我が国企業が中国に現地法人を設立し、我が国からの対中輸出も欧米を最終需要地とする国際的生産分業(グローバル・バリューチェーン)の一環として、現地法人向けの中間財(鉄鋼・化学品等の部材、電子関係を中心とする機械部品等)や資本財(工作機械、建設機械等)を中心に拡大してきた(第Ⅱ-1-1-13図、第Ⅱ-1-1-14図)。
第Ⅱ-1-1-13図 日系海外現地法人の企業数・売上げの推移
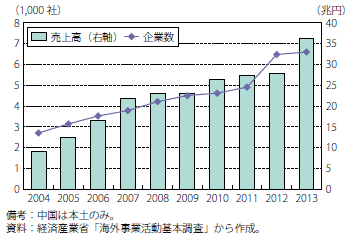
第Ⅱ-1-1-14図 日本の財別の対中輸出
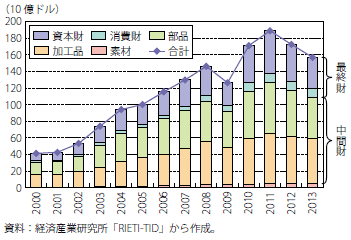
しかし、これまで見てきたように人件費の上昇等を背景に中国の製造拠点としての位置付けは変化しつつある。日系製造業現地法人の現地調達率上昇や中国政府の投資から消費への転換という方針を考えれば、これまでのような中間財、資本財輸出は伸び悩んでいくことも考えられる。中国に立地する日系現地法人の業種を見ると、情報通信機械、電気機械、鉄鋼、化学等の輸出をにらんだ製造業が多い(第Ⅱ-1-1-15図)。一方、非製造業については、卸売業のみが突出しており、堅調な消費からの受益が大きいと見られる小売業やサービス業などの進出が少ない。仮に、中国政府が目指すように、投資から消費にシフトした場合、このような日系現地法人の業種構成は、拡大する中国市場の取り込みに不利に働く懸念がある。また、本社立地場所を見ると、沿海部中心の立地となっている(第Ⅱ- 1-1-16図)。
第Ⅱ-1-1-15図 在中日系現地法人(2013年)
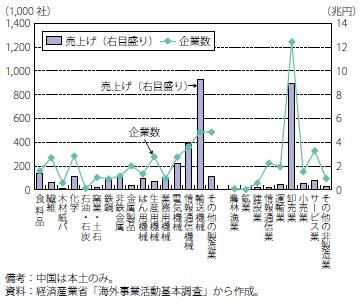
第Ⅱ-1-1-16図 日系現地法人の立地状況(2013年度)
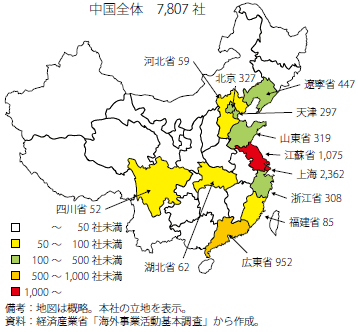
今後の中国ビジネスの行方を考える上での参考として、最近の中国の品目別の輸入動向を2つの側面から見てみる。1つ目は輸入額の多い主要品目で、2つ目は、たとえ現在の輸入額は大きくなくとも、最近高い伸び率を示している品目の動向である。
まず、輸入額の大きな主要品目としては、電気機械などの機械類、鉱物性燃料などの資源、化学品等が多く、このうち、機械類や化学品については、我が国が大きなシェアを占めている(第Ⅱ-1-1-17表)。なお、この分野では、韓国、台湾との競合も激しい。次に伸び率の高い品目を見ると、所得水準の向上を反映して、食の安全・高度化の関連品(肉類、飼料を含む穀物、粉ミルク、ワイン、コーヒー等)、美術品、化粧品など生活を楽しむための品目が目につく(第Ⅱ-1-1-18表)。また、高齢化の影響と思われる医療用品(主として医薬品)の伸びも高い。しかし、これら品目の輸入における我が国のシェアは、香水・化粧品は高いものの、多くの品目では必ずしも拡大する市場を取り込めていない懸念がある8。なお、消費財の中でも、衣類、履き物の輸入相手国を見ると、新興国とともにイタリアが大きなシェアを占めており、日用品の中でも、高級品を求める動きも出てきていると見られる。
第Ⅱ-1-1-17表 中国の主要輸入品(輸入額上位品目)
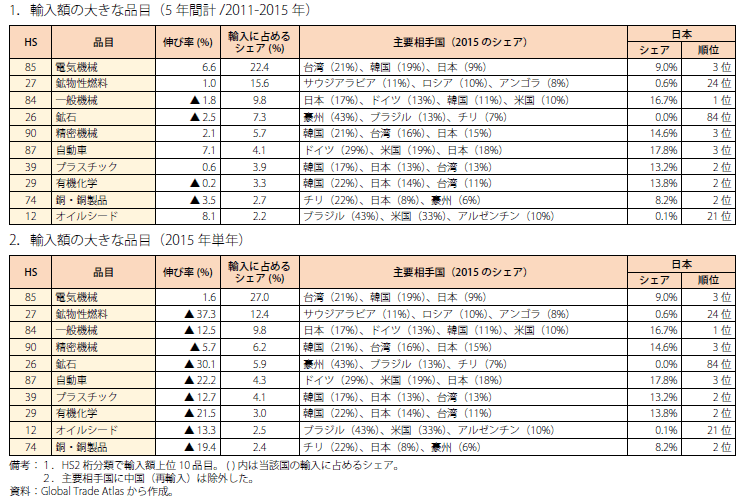
第Ⅱ-1-1-18表 中国の輸入品(伸び率の上位品目)
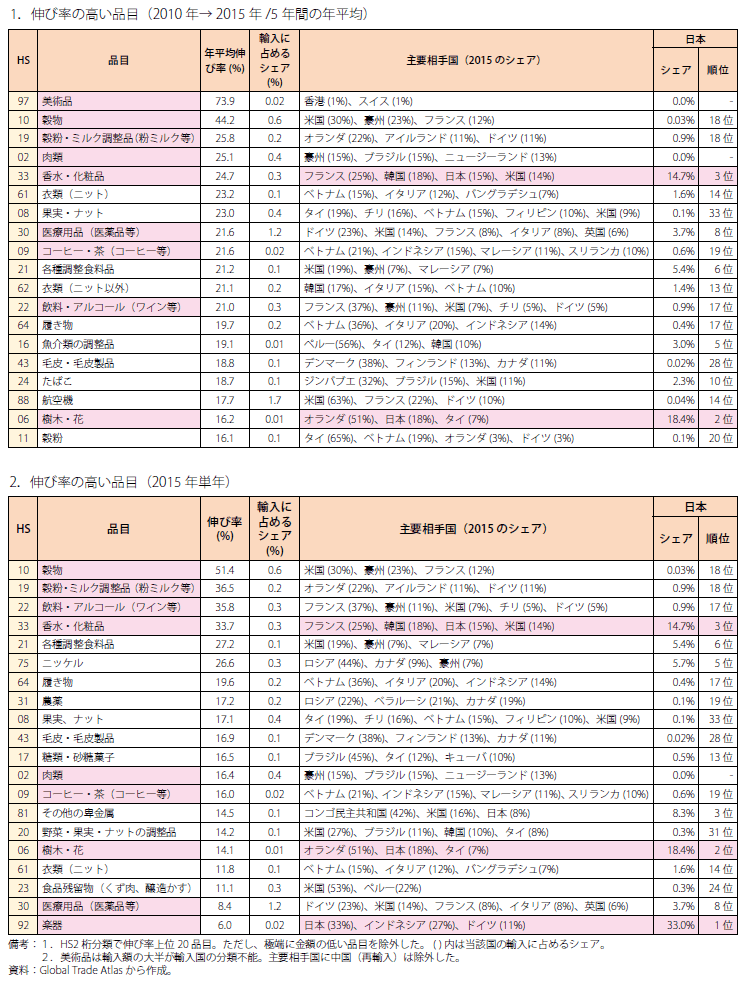
中国の財別輸入の傾向を見ると、所得水準の上昇や「投資から消費への転換」等を背景に、現時点での水準は低いものの、消費財が着実にシェアを伸ばしている(第Ⅱ-1-1-19図)。
第Ⅱ-1-1-19図 中国の輸入における財別シェアの推移
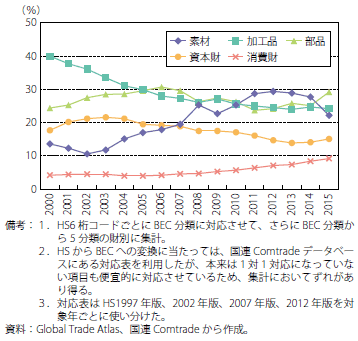
それでは、我が国を始めとした主要国の対中輸出(中国側から見た輸入)はどうなっているのかを見ていく。中国の国別輸入は、主要国が2014年まで金額を伸ばしている中で、我が国は2011年をピークに減少している(第Ⅱ-1-1-20図)。我が国の場合、東日本大震災等の影響はあるものの、その他の要因、例えば他の国は高い伸び率を示している消費財をうまく取り込んでいるなど品目構成の影響はないのだろうか。
第Ⅱ-1-1-20図 中国の国別輸入額の推移
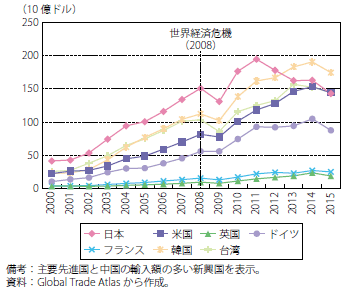
中国の主要相手国別の輸入品構成と伸び率の動向を概観する。第Ⅱ-1-1-21図は、中国の我が国からの輸入をプロットしたもので、横軸は2008年時点の品目構成(シェアの高い主要10品目を表示)、縦軸は2008年から2015年までの年平均成長率を示している。世界経済危機後の我が国からの伸び率を見ると、精密機械、自動車、プラスチック、有機化学品等が伸びている一方で、シェアの最も高い電気機械、一般機械、鉄鋼等は不調だった。それに対して、米国は、幅広い品目で伸びており、特に精密機械、航空機、自動車の伸びが高い(第Ⅱ-1-1-22図)。ドイツは自動車、精密機械が伸びているほか、医療用品の高い伸びが目立つ。その他のフランス、英国、イタリアも、それぞれ相違はあるものの、機械類のほか、医療用品、飲料・酒類、香水・化粧品、衣類、毛織物など消費財関係も大きなシェアを持ち、伸びていることが見て取れる。新興国では、韓国が、鉱物性燃料、鉄鋼が落ち込む一方、電気機械、一般機械等が伸びており、台湾は全体の4割近くを占める電気機械が全体を牽引している。
第Ⅱ-1-1-21図 中国の日本からの輸入品構成と伸び率
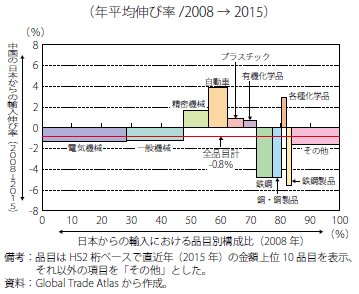
第Ⅱ-1-1-22図 中国の主要国からの輸入品構成と伸び率
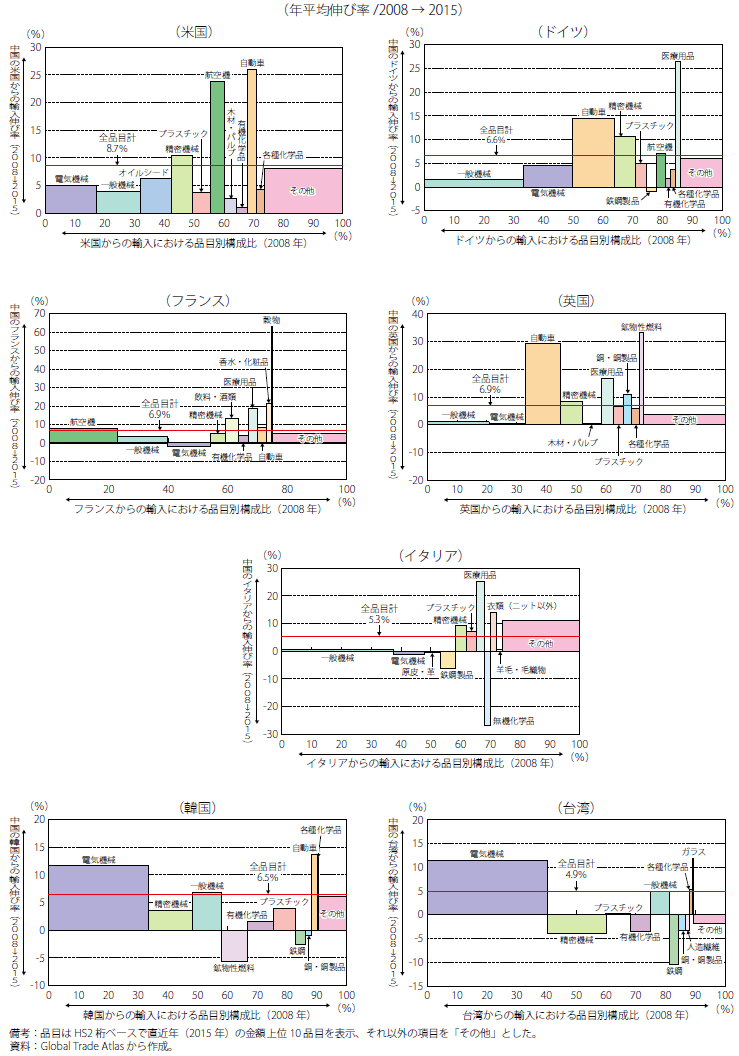
- Excel形式のファイル(米国)はこちら

- Excel形式のファイル(ドイツ)はこちら

- Excel形式のファイル(フランス)はこちら

- Excel形式のファイル(英国)はこちら

- Excel形式のファイル(イタリア)はこちら

- Excel形式のファイル(韓国)はこちら

- Excel形式のファイル(台湾)はこちら

我が国が機械、金属、化学品に集中しているのに対して、他の先進国は比較的幅広い品目、特に欧州諸国は消費財もカバーしている。もし、中国の消費財の着実な輸入拡大が続いていくとすれば、我が国の品目構成は不利に働くことが懸念される。
このように考えてくると、現在の中間財・資本財を中心とした貿易投資の在り方は、徐々に、転換を迫られる可能性がある。我が国としては、中国の構造改革の行方を見据えながら、拡大する消費財市場も取り込んでいけるよう対応していくことが重要といえる。
8 日系現地法人が現地生産によって供給している場合もあり得るが、ここでは、輸入品の分析をしており、現地生産は分析に入れていない。
(3)訪日観光客の増加により改善が進むサービス収支
新興国の構造変化や産業のサービス化による影響を受け、サービス輸出は19.7兆円(対前年比+13.9%)、訪日客は1974万人(同+47.1%)といずれも過去最高に達した。サービス収支は前年比+1.5兆円と赤字幅を縮小し、比較可能な平成8年以降で過去最少の赤字となっている(第Ⅱ-1-1-23図)。
第Ⅱ-1-1-23図 我が国のサービス輸出入額の推移(兆円)
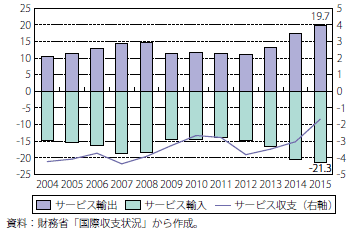
大きな伸びとなった我が国のサービス収支であるが、世界全体の伸びからは相当遅れている。例えば過去10年間における世界全体のサービス貿易の伸び(年平均7.2%)に対する我が国の寄与(同0.2%)は極めて小さく、特に付加価値の高い対ビジネスサービス輸出が遅れている傾向にある(第Ⅱ-1-1-24図、第Ⅱ-1-1-25図)。
第Ⅱ-1-1-24図 世界の財・サービス輸出の推移
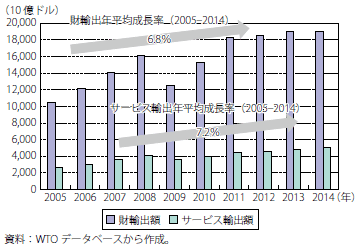
第Ⅱ-1-1-25図 主要国の「専門業務サービス」輸出伸び率と項目別寄与度(2010-2014年)
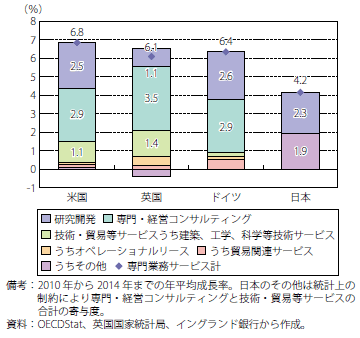
サービス収支、旅行収支の動向に関しては、第2部第2章を参照されたい。
(4)まとめ
以上のように、我が国の対外経済関係を国際収支の状況から見てみると、財貿易では、米国向け輸出や自動車といった輸送用機器の輸出に依存していること、中国への輸出は機械、金属、化学品に集中しており、消費財など新たな需要の取りこぼしを生む可能性があることがわかった。サービス収支は、旅行収支の改善に依存している。これらは、我が国の対外経済動向が特定の分野への依存を高めている可能性を示しており、幅広い分野においてグローバル化した稼ぎ方の構築が求められている。
2.対外経済関係深化の必要性と我が国の現状
企業の生産性と海外進出は密接な関係にあることが様々な研究で示されている9。本項では、生産性と海外進出に関するこれまでの研究を概観するとともに、貿易・対外直接投資の対GDP比の国際比較を通じて、我が国の現状を分析する。
9 海外市場進出による企業の生産性向上に果たす役割については、通商白書2013において詳細に分析がなされていることから、参照ありたい。
(1)企業の海外進出と生産性に関するこれまでの議論
まず、同一産業内における企業の異質性に着目した新しい貿易理論からは、海外市場に製品を供給するためには、進出形態ごとに固定費用10が異なり、それは国内への供給<輸出による供給<対外直接投資による順で高くなるとしている。その上で、各形態で市場に海外市場に参入するためには、その固定費用を上回る利潤を上げるための生産性が必要であり、結果として輸出や対外直接投資に従事する海外市場進出企業の生産性が非海外市場進出企業より高くなることが予測される(第Ⅱ-1-1-26図)11。
第Ⅱ-1-1-26図 生産性と企業の海外市場進出のモデル
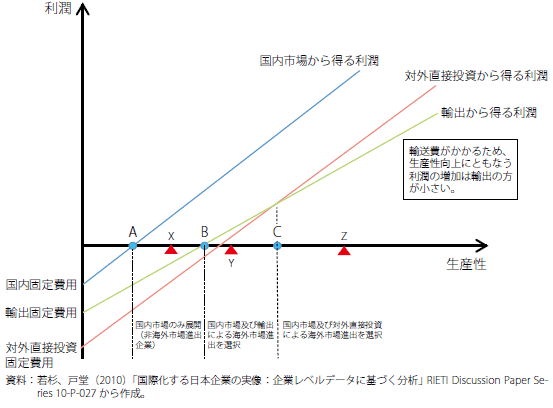
一方、輸出については、海外需要の取込みにより規模の経済をより有効に働かせる効果のみならず、企業に海外の新しい知識や技術に接触する機会を提供することで、海外市場の要求に対応して技術・品質水準の向上努力を行うことや、技術を吸収しイノベーションにつなげることなどを通じて、事後的に生産性を向上させる、いわゆる「輸出の学習効果」の存在も指摘されているところである12。
経済連携協定の効果も生産性の上昇に負うところが大きい。内閣官房TPP政府対策本部が試算した「TPP協定の経済効果分析13」においても、TPPによる貿易・投資の拡大によって、生産性が上昇し、労働供給と資本ストックが増加することで、真に「強い経済」が実現することになるとされている。具体的には、TPPが経済を動かす内生的な成長メカニズムとしては、「①輸出入拡大→貿易開放度上昇→生産性上昇」、「②生産性上昇→実質賃金率上昇→労働供給増」、「③実質所得増→貯蓄・投資増→資本ストック増→生産力拡大」の3つが挙げられている。
10 具体的には、国内事業を行うときにかかる固定費用に加え、輸出時には輸出に必要とされる現地での情報収集費などを含むマーケティング費用、販売・流通サービスの構築費などを含んだ固定費用がかかる。また、対外直接投資時には輸出時に必要な固定費用に加えて、現地法人を設立し、維持する費用などが大きくかかることが想定される。
11 例えば、対外直接投資残高対GDP比の推移において生産性がXにある企業は、国内市場では利潤を得られるが、輸出や対外直接投資を通じた海外市場では利潤が出ないため、国内市場のみに供給する非海外市場進出企業となる。また、生産性がYにある企業は、自社の利潤最大化のため国内供給に加え、海外市場への供給を行うが、対外直接投資より利潤の高い輸出を選択し、輸出企業となる。一方、生産性がZにある企業は、輸出より利潤の高い対外直接投資を選択し、対外直接投資企業となる。
12 対外直接投資による学習効果に関連して、現在、多くの我が国企業が先進的な技術の吸収を目的にシリコンバレーやその周辺部に進出している。同地域に進出する我が国企業数は調査を開始した1992年以降で過去最大となっている。その具体的な様態や現地ヒアリングに基づく課題については、本章第2節において分析をしているため、参照ありたい。
13 2015年12月24日公表
(2)欧州主要国と比較して伸びが弱い財サービスの輸出
次に、財サービス貿易の対GDP比率の国際比較により、我が国の現状を確認する。
我が国からの輸出の対GDP比(輸出比率)は、近年やや増加傾向にあるものの、他のOECD主要国と比較して財・サービスともに低い水準にとどまっている。
韓国やドイツは財輸出の対GDP比が約4割と高い水準にあり、ドイツについては、EU域外への輸出に限定してもなお我が国よりも輸出比率が高い(第Ⅱ- 1-1-27図)。
第Ⅱ-1-1-27図 我が国と欧州主要国の財輸出対GDP比
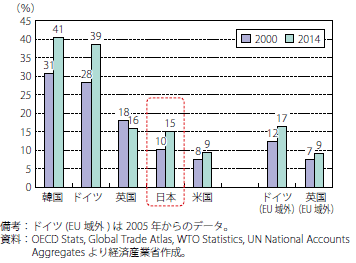
第1部第3章2.において分析したとおり、近年の増加が著しいサービス貿易についても、欧州主要国と比較して我が国の対GDP比率は低い水準にある。サービス輸出の対GDP比はイギリスにおいて高く、ドイツの財輸出と同様、EU域外への輸出に限定しても我が国よりも輸出比率が高い(第Ⅱ-1-1-28図)。
第Ⅱ-1-1-28図 サービス輸出額の対GDP比
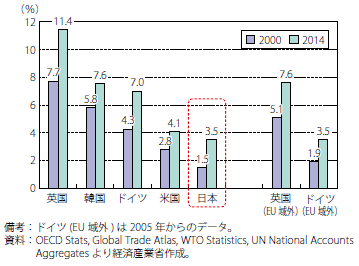
2000年以降、ドイツや韓国をはじめOECD主要国の多くが、輸出の拡大を通じて経済成長を図っているのに対して、我が国は、輸出比率が低い水準にとどまっている(第Ⅱ-1-1-29図)。
第Ⅱ-1-1-29図 サービス輸出額の対GDP比
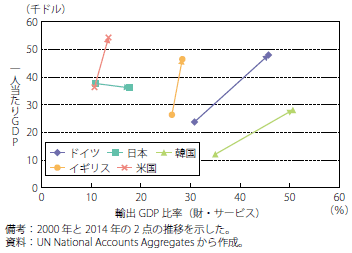
(3)対外投資が遅れる非製造業
次に、我が国の直接投資の動向を主要国と比較する。
主要国の直接投資残高の対GDP比を比較すると、欧米先進国は対外直接投資・対内直接投資ともに90年代以降急速に伸びているのに対し、我が国では対外直接投資がやや伸びているものの、対外・対内ともに低い伸びにとどまっている(第Ⅱ-1-1-30図)。
第Ⅱ-1-1-30図 主要国の対内・対外直接投資対GDP比
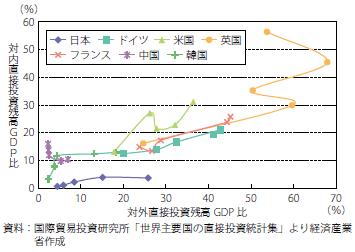
我が国の業種別・対外直接投資残高対GDP比を他主要国と比較すると、製造業については13.4%(2013年)と他主要国とほぼ同じ水準(米国3.7%、英国9.7%、フランス13.0%、ドイツ11.3%)であるのに対し、非製造業は15.6%(2013年)と極めて低い水準(英国39.1%、フランス32.5%、ドイツ32.0%、米国22.8%)にあり、前述のサービス貿易と同様に、非製造業の海外展開は他国に比べて低い水準にあると言える(第Ⅱ-1-1-31図)。
第Ⅱ-1-1-31図 対外直接投資残高対GDP比の推移
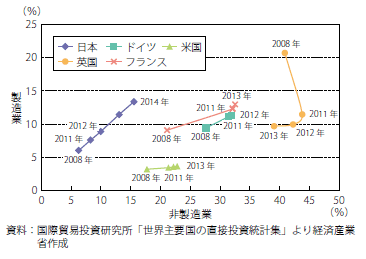
(4)まとめ
以上、生産性の向上による経済成長のためには、海外との経済関係を深化させることが必要である一方、我が国においては、財サービス貿易・対内外直接投資ともに欧州主要国と比較して対GDP比が低いことが確認された。次節では対外経済関係の深まりとイノベーションの関係を人材面に焦点を当てて分析するとともに、第2章及び第3章では、観光を始めとするサービス貿易、中堅・中小企業の輸出拡大をはじめとする地域からの輸出拡大などの各論について分析を行う。
