第2節 高度人材の確保とイノベーションの創出
我が国の対外経済関係は特定の地域、品目、相手国へ集中している傾向が見られている。裾野をより拡大するためには、世界の新たなフロンティアの潮流をとらえるとともに、それを踏まえた我が国企業による挑戦が必要となると考えられる。
また、情報通信技術の発展に伴った新たな産業構造のプラットフォーム化が進んでおり、今後のイノベーションを通じた経済成長の軸のひとつとなることが予想される。その際、経営戦略と並んで重要であるのは、イノベーションを担う「人材」であり、優秀な高度人材14、特にIT人材の争奪戦は国境を超えて激しさを増していると言われている。
本節では、上記のような我が国における高度人材確保の状況と課題について紹介し、我が国産業の裾野を拡大すべくイノベーション(技術革新)の必要性について検討する。その後、人材の国際移動とイノベーションの関係性について考察し、我が国対外経済関係の裾野拡大のための示唆を得る。
14 本節においては、「高度人材」は専門的な技術や知識を習得した人材を指し、日本人、外国人の両方を含むとする。他方、外国人の高度人材のみを指す場合は、「高度外国人材」とする。
1.我が国産業における高度人材の確保
ここでは、我が国産業が世界の新たな変化に対応すべく、イノベーションの創出に貢献する高度人材の確保状況や課題について検討する。
高度人材を増加させるには、海外から高度外国人材の呼び込みを促進させるパターンと、我が国の優秀な高度人材を国内に留めて定着させるパターンの2つが考えられる。本項では、「(1)高度外国人材の動向と呼び込みの強化」において高度外国人材が国境を超え、我が国へ定着することを促すための課題を考察し、「(2)国境を超えてニーズが高まるIT人材の確保とその課題」では、プラットフォームビジネスといった世界の新たなフロンティアに挑戦すべく、イノベーション創出に貢献する可能性が指摘されているIT分野の高度人材に着目し、こうした人材を確保するための課題を考察する。
(1)高度外国人材の動向と呼び込みの強化
前述のとおり、我が国における高度人材の必要性が高まっており、こうした人材の確保が課題となっている。その中でも高度外国人材15は、我が国企業の海外戦略に貢献するとともに、我が国の人材との交流によって新たなイノベーションのきっかけになるとの指摘があり、我が国でも高度な専門知識や技術を習得している外国人材の呼び込みを促進し、世界の質の高い人材を確保することが重要視されている16。
本項では我が国における高度外国人材の現状を把握すべく、世界の主要国との比較を交えて現状を概観する。この際、我が国の高等教育機関における留学生の呼び込みについても考察する。高等教育機関における留学生は、一定の知識が保証されていることに加え、日本語を習得しやすく、我が国の文化への理解があることから、定着を促しやすいと考えられる。そのため、留学生の受け入れおよび定着を促進することは、我が国における高度外国人材を増加させる可能性が高いと考えられる。
15 「高度外国人材」に関しては、世界各国で様々な定義を用いている。我が国の高度人材ポイント制度では「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」と定義しており、一定の学力に加え特別な専門知識を有していることが必要とされる。また、世界共通の定義が設定されていないことから、国際比較の際は高等教育機関修了者の値を用いて比較している。
16 2000年代前半から、産業界より外国人材の受け入れ促進に関する要望の声が大きくなった。日本経済団体連合会による「活力と魅力溢れる日本をめざして」(2003)や、日本商工会議所の「外国人労働者の受け入れのあり方に関する報告書」(2008)等において、外国人材、とくに高度外国人材に関する呼び込みの重要性について指摘されている。さらに2015年6月30日に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2015」では、優秀な外国人材の受け入れ、特に「海外の最新の知見と国内トップレベルの知見の融合によるイノベーションを促進する観点から」IT人材の受け入れに重点を置くべきとされた。
①我が国における高度外国人材の動向
(a)高度外国人材の呼び込みと定着の動向
我が国の高度外国人材について、他国との比較を行いつつその動向を見てみる。
高度外国人材の定義は各国によって異なるが、多くは「高等教育修了程度」を要件のひとつとしている。OECDでは高度外国人材の国際比較を行う際、「高等教育終了程度(ICED5以上)」という基準を用いているため、ここではそれに沿った比較を行う。
第Ⅱ-1-2-1図は、主要国の高等教育修了者の流入に関し、各国の人口比の推移を示している。言語のハードルが低い英語圏である米国や英国には、人材が集中する傾向にある一方、非英語圏であるドイツやフランスにおいても増加がみられている。これらの国と比較し、同じ非英語圏である我が国は低水準にとどまっていることが分かる。
第Ⅱ-1-2-1図(再掲) 高等教育修了者の流入人口の推移(対人口比)
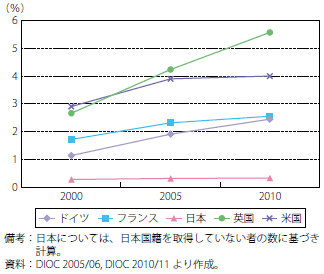
(b)留学生の呼び込みと定着の動向
次に高度外国人材の卵とも言える留学生の呼び込み状況をみると、米国や英国といった英語圏の人気が高く、主要な留学先とされている。ドイツやフランスといった非英語圏も、高度外国人材の呼び込みと同様高い水準にあるほか、中国や韓国でも受け入れ数に増加が見られている。我が国について見ると、我が国への留学生数も緩やかな増加傾向にあるものの、フランスやドイツに及ばない水準である(第Ⅱ-1-2-2図)。
第Ⅱ-1-2-2図 主要国の留学生受け入れ人数の推移
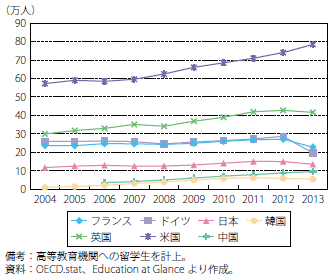
次に、我が国の大学への留学生のうち、卒業後に我が国へ就職した者の割合をみると、世界経済危機直後の2009年度の卒業生(2010年3月卒業者)では約22%まで落ち込んだが、2013年度の卒業生(2014年3月卒業者)の数値では約28%に上昇し、我が国企業における採用ニーズが回復していることが伺える(第Ⅱ-1-2-3図)。他方、就職率のピークであった2006年度の約46%からは低くとどまっている。
第Ⅱ-1-2-3図 就職率の推移
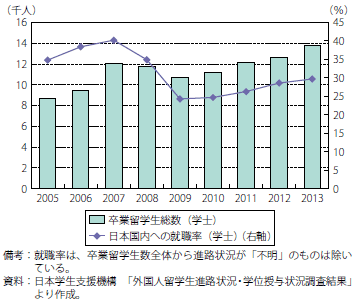
我が国の大学への留学生に対して行われたアンケートにおいて、彼らの進路について問うと、「日本における就職を希望」と回答したのは全体70.1%に及んだ。本調査が開始された2005年と比較すると、「出身国における就職」や「第3国での就職」への希望は減少傾向にあり、我が国における就職の希望が高まっていることが伺える。前段において、我が国企業における外国人材の採用が増加している傾向を示したが、我が国での就職を望む人材はそれを大きく上回っており、優秀な人材が取りこぼされている可能性が示唆される(第Ⅱ-1-2-4図)。
第Ⅱ-1-2-4図 留学生の卒業後の希望進路(就職分野)
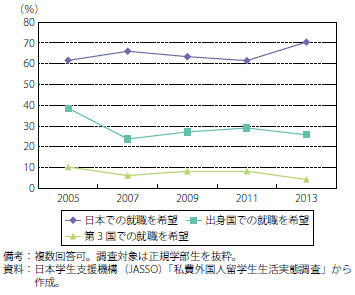
②呼び込む力の向上のために検討すべき要因
以上の現状から、高度外国人材および留学生の呼び込みに関し、我が国の水準は他の主要国に比べ低いことがわかった。さらに留学生の定着について見れば、定着人数の上昇傾向は見られるものの、留学生の我が国への就職率は微増にとどまっており、世界経済危機前の水準には達していない。留学生の我が国企業への就職意欲を鑑みても、優秀な人材を取りこぼしている可能性が考えられる。このような低い水準にとどまっている要因については、様々な理由が検討されてきたが17、本項では、我が国における在留資格制度、我が国企業における企業体制の在り方、そして我が国企業が求める理系人材の呼び込みが不足しているという3点について検討したい。
17 平成27年度経済産業省委託調査「平成27年度アジア産業基盤強化等事業(「内なる国際化を進めるための調査研究」)」では、高度外国人材および留学生の定着に関する課題や対応策について、我が国企業や外国人材へのヒアリングを交え議論している。そのなかで、上記のような要因の他に、生活環境における要因等についても検討している。
(a)在留資格制度
2012年、我が国では「高度人材ポイント制」として、高度外国人材の年収や学歴等によってポイントを付し、様々な優遇措置を講ずる在留制度を整備した。目的は高度外国人材18の受入れの促進であるが、制度利用者が微増にとどまり、制度の改善が求められた。2013年に年収要件等を見直したほか、イノベーション支援措置を受ける企業のうち中小企業にはポイントを加えるなど、企業への配慮も盛り込まれた。さらに、2015年には高度人材に特化した在留資格「高度専門職」が創設され、「高度専門職1号」で3年間在留した高度外国人材は、「永住者」と同様に在留期間が無期限の「高度専門職2号」へ移行できることとした。
同制度の利用者は2015年12月で累計4,300名となっており、2017年末までに5000名の利用を目指している。
また、他国の高度外国人材受入れ政策を見てみると、ドイツでは「EUブルーカード」と呼ばれる在留資格制度が実施されており、永住権が取得しやすく高度人材や留学生の受入れを促進していると言われている19。
このような状況のなか、我が国では、世界最速級の「日本版高度外国人材グリーンカード」の創設など諸外国以上に魅力的な入国・在留管理制度を整備するとともに、高度人材ポイント制の利用促進、日本での就労希望者(留学生、ODA等による高度人材育成事業対象校の海外学生、JETプログラム終了者等)と採用意欲の高い企業側のマッチング支援、就労する外国人の子供の教育環境を含む生活環境整備を進めることにより、高度外国人材の受入れを拡大する20。一方、我が国の高度人材ポイント制に関しては、一定の条件を満たせば親の帯同が認められるなど、他国よりも優遇措置を強化した側面もあり、アピールすべき措置の積極的な広報が求められる21(第Ⅱ-1-2-5表)。
第Ⅱ-1-2-5表 各国の高度外国人材呼び込み制度
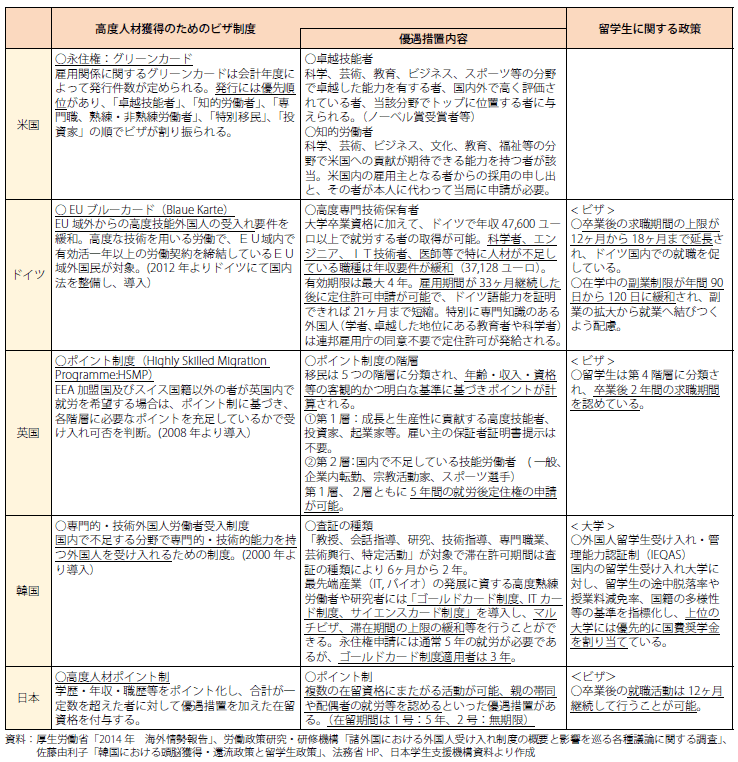
18 我が国のポイント制における高度外国人材は「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされています。(平成21年5月29日高度人材受入推進会議報告書)とされる。
19 詳細は、本書の「第2部第3章第2節(3)ドイツにおける高度人材の活用」を参照されたい。
20 経済財政諮問会議(第7回)(平成28年4月25日)資料参照。
21 第6次出入国管理政策懇談会 外国人受け入れ問題検討分科会(第2回)(平成25年5月1日)資料参照。
(b)我が国における労働環境に対する負のイメージ
我が国への高度外国人材の定着において重要なことのひとつが、彼らの労働環境についてである。ここでは、我が国で「働くこと」に関する課題について見てみる。
我が国において我が国企業へのフルタイム勤務経験のある外国人へのアンケート調査によると、我が国への居住に対するイメージは81.7%が魅力的であると答えているのに対し、我が国における労働を魅力的ととらえるのは21.1%にとどまる。さらに、この原因となる要素を尋ねると、「長時間労働」といった項目のなかに「遅い昇進」や「評価システムの不透明さ」といった、日本企業特有の人事システムへの不満がみられている(第Ⅱ-1-2-6図、第Ⅱ-1-2-7図)。
第Ⅱ-1-2-6図 日本における居住と労働のイメージ
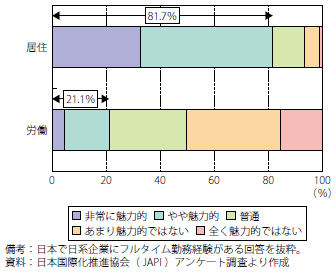
第Ⅱ-1-2-7図 日本における就職の不満
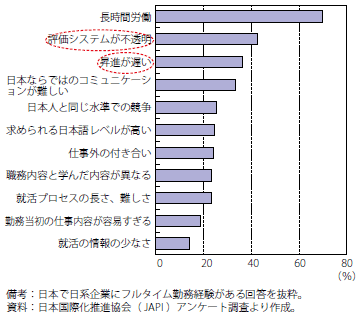
また、同アンケート調査に項目は設けられていなかったものの、自由回答では、昇給の遅さ等にも触れている回答が見られた。我が国および欧州主要国の平均賃金について、29歳以下の若年層の平均賃金(従業員10人以上の企業)を100としたとき、英国やドイツでは早期から昇給する傾向が見られた(第Ⅱ-1-2-8図)。
第Ⅱ-1-2-8図 日本および欧州主要国の年齢別平均賃金
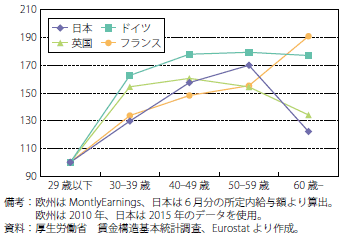
(c)企業が求める人材の不足
次に、我が国企業の求める人材を適切に国内に呼び込めているのかについて検討する。
第Ⅱ-1-2-9図、第Ⅱ-1-2-10図は、我が国の高等教育機関における留学生の国籍別、専攻別の割合(2013年)を示している。専攻別に見ると、人文科学(21%)と社会科学(38%)で約6割を占めており、理学(2%)や工学、建築学(17%)といった理系分野は2割程度となっていることがわかった。また、国籍別に見てみると、92.2%がアジア地域出身の学生であり、次いで欧州(3.4%)、北米(2.1%)の順である。アジア地域出身者については、中国出身が全体の約65.3%と最も多い(第Ⅱ-1-2-9図、第Ⅱ-1-2-10図)。
第Ⅱ-1-2-9図 我が国における留学生の構成比【国籍別】
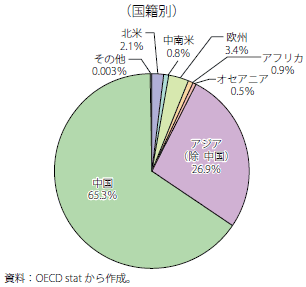
第Ⅱ-1-2-10図 我が国における留学生の構成比【専攻別】
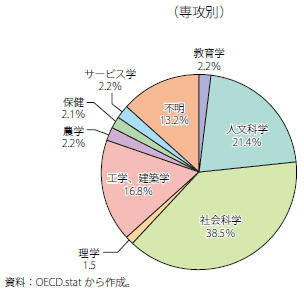
第Ⅱ-1-2-9図の傾向をみると、我が国への留学生の多くが中国出身であることがわかるが、中国人留学生はどのような国に留学しているのか、中国人帰国留学生白書22をもとに紹介する。それによると、学部レベルでは韓国・英国・米国、修士課程では英国・米国・豪州の人気が高いが、博士課程では、米国と並んで我が国への留学生が多いことが分かる。本調査は留学後中国に帰国した者に対する調査であるため、留学先や第三国で就職した者もいることを勘案する必要があるが、参考になるであろう。なお、中国では1990年代以降、海外留学した中国人学生の帰国、就業を促す政策が取り組まれており23、現在では中国人留学生のうち、約79.9%が海外留学後に帰国している。
中国に例えられるように、各国における高度人材の確保は、国外に留学した自国の学生の呼び込みにも及んでいる。このような留学生の帰国は、我が国への定着にも影響を及ぼす可能性が考えられ、留学生定着のための一層の取組が求められる(第Ⅱ-1-2-11図、第Ⅱ- 1-2-12図、第Ⅱ-1-2-13図)。
第Ⅱ-1-2-11図 中国人留学生の渡航先(学部生等)
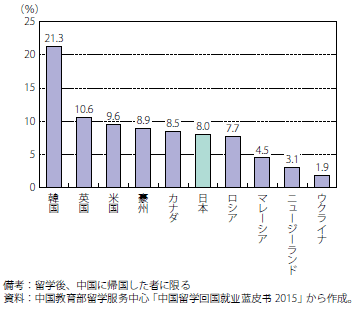
第Ⅱ-1-2-12図 中国人留学生の渡航先(修士課程)
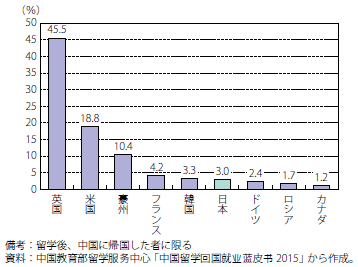
第Ⅱ-1-2-13図 中国人留学生の渡航先(博士課程)
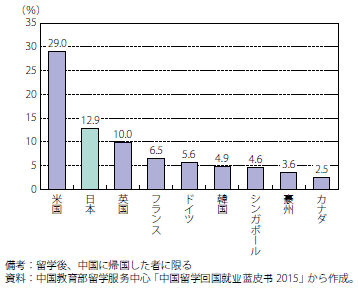
次に、専攻別から考えられる要因について検討する。我が国企業の留学生の採用動向をみると、国内の大学・大学院(文系)の留学生の新卒採用を行うとする企業は32.7%、国内の大学・大学院(理系)の留学生の新卒採用を行うとする企業は34.0%であり、やや理系人材の需要が高く、需要の高い理系人材の呼び込み促進が望まれる(第Ⅱ-1-2-14図)。
第Ⅱ-1-2-14図 企業の外国人材の採用ルート
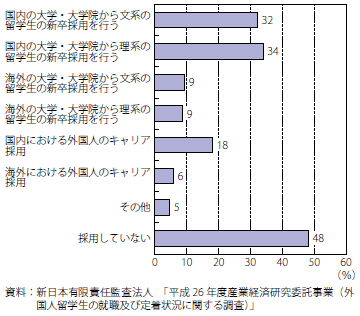
22 中国教育部 中国人帰国留学生白書(http://www.moe.edu.cn/jyb_xwfb/xw_fbh/moe_2069/xwfbh_2016n/xwfb_160325_01/160325_sfcl01/201603/t20160325_235214.html![]() )を参照。中国教育部により発表されており、中国人留学生の留学、帰国、就業等に関して議論されている。
)を参照。中国教育部により発表されており、中国人留学生の留学、帰国、就業等に関して議論されている。
23 許海珠「中国の人材政策―留学政策を中心―」
③まとめ
本項では、我が国における高度外国人材の呼び込みや定着が低水準であることや、呼び込む上で阻害要因となっているであろう3点を紹介した。
第1節で述べたように、我が国を訪れる外国人は増加傾向にあり、本項で見た留学生数等も増加傾向にある。一見、人材のグローバル化が進んでいると思われるが、世界の水準を見れば、我が国の人材のグローバル化状況は低水準にあり、のばすべき余地はあると考えられる。我が国企業の国際競争力やイノベーション力が求められる中、高度外国人材を呼び込む力を向上させるべく、高度外国人材にとって定着しやすい労働環境作りや制度改革など、官民一体となった取組みが望まれる。
次項では、イノベーション力の強化のためのIT人材の確保について検討する。本項の3つ目の要因で示したように、我が国における理系人材の需要は高く、我が国産業を支える人材の確保が求められる中、その課題について考察したい。
(2)国境を超えてニーズが高まるIT人材の確保とその課題
第1章で見てきたように、進化する情報通信技術を活用し、世界の新たなフロンティアであるデジタルプラットフォームビジネスはじめ様々な革新的なビジネスをグローバルに展開し、我が国ビジネスの裾野を拡大するにあたり、これを可能とする人材の必要性が高まり続けている。一方で、国内ではITとビジネスを結びつけたり、実際に高度なプログラムを組み立てることのできるエンジニア、技術者の不足が指摘されている。以下では、この需要が高まるIT人材に焦点を当て、我が国でこのような人材を集積させるため、国内雇用環境の評価や、先端IT技術の集積地であるシリコンバレーに進出する我が国企業の取組みから得られる課題を見ていく。
①国際的に高まるIT人材の需要
IoT、ビッグデータ、人工知能といった、近年進化する情報通信技術を活用し、デジタルプラットフォームビジネスはじめとした、新たなビジネスをグローバルに展開するためには、高度なプログラムを構築するIT人材の存在が必要不可欠となっている。Mckinsey社の調査によれば、これらの人材は、世界的に競争力の高いIT企業が集積する米国に特に集中しており、これに加えて近年ではサービス化に向けて経済構造を変換する中国でも大きくその数を伸ばしている(第Ⅱ- 1-2-15図)。
第Ⅱ-1-2-15図 データ分析の才能を有する人材の推移
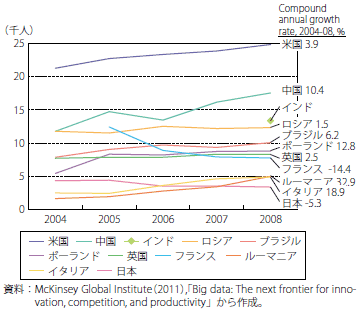
一方、米国でも、高度なスキルを持つIT人材の不足が指摘されており、人材不足を背景とした賃金の高騰も指摘されている24。デジタルビジネスに必要不可欠なIT人材等の確保のためにはM&Aも活用されており、特に革新的な独自の技術を持つ人材を有する企業が高額で買収される事例が世界的に増加している(第Ⅱ-1-2-16表)。
第Ⅱ-1-2-16表 Googleの買収企業
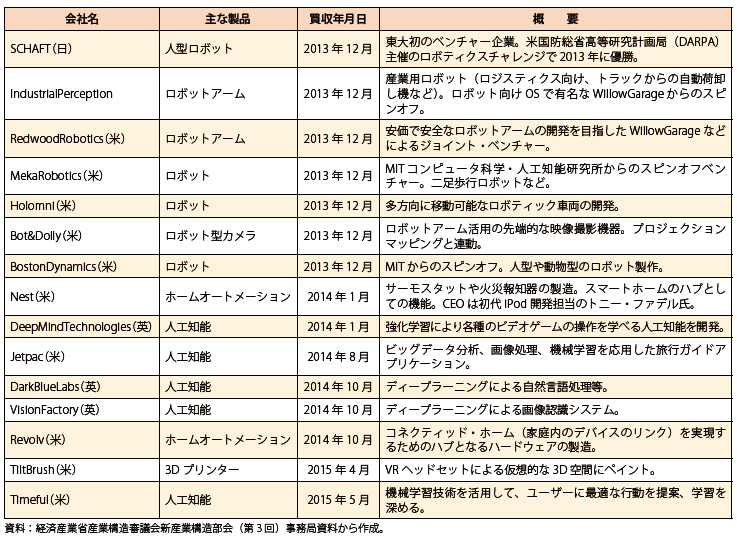
24 Federal Reserve Board(2015)。
②我が国でも高まるIT人材へのニーズと課題
日本国内でも、ITのユーザー企業、IT企業共にIT人材への量的不足感は高い。
「IT人材白書2015」によると、IT人材の量的過不足感についてのアンケートでは、製造業等のユーザー企業のみならず、IT企業そのものでも9割前後の企業がIT人材が不足しているとしている(第Ⅱ-1-2-17図)。
第Ⅱ-1-2-17図 IT人材の「量」に対する過不足感
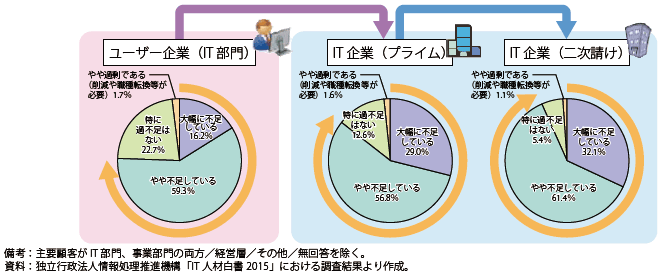
更に、プラットフォームビジネスの展開に欠かせないと考えられる、ITとビジネスが融合した領域において、イノベーションを創出し、新事業や新サービスを生み出すことができる人材(「IT融合人材」)については、必要性の認知度も過半数に届かず、確保状況も低調な状態となっている(第Ⅱ-1-2-18図)。
第Ⅱ-1-2-18図 IT企業・ユーザー企業のIT融合人材の必要性と確保状況
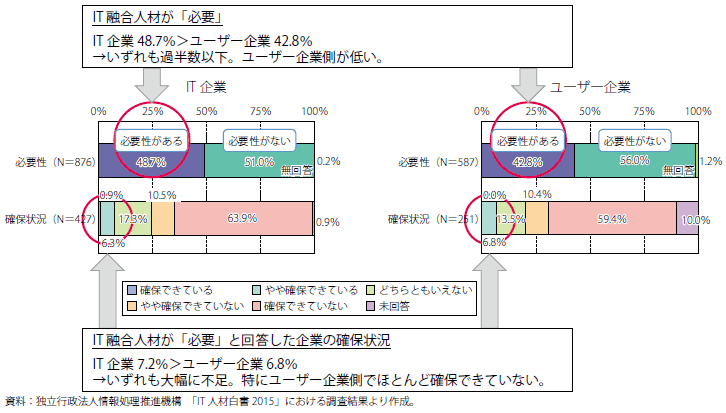
以下では、国際的に需要が高まるITエンジニアを国内に呼び込むための要素としての観点から、ITエンジニアがおかれている雇用環境について、我が国の他、米国、インド、中国等のIT技術者に対し経済産業省が実施した委託調査におけるアンケート25をもとに比較する。
まず、IT先進国として考えられる米国、インド、中国及び日本に居住するITエンジニアについて、どのような雇用環境に重きを置いているかを見るため、転職時に重視する理由を見てみると、共通して最も高いのは「給与」となっている。それ以外の項目については、日本のITエンジニアのみ、傾向が異なるものの、米国、インド、中国のITエンジニアにおいては、「給与」以外にも、「地位・役職・責任の重さ」、「企業の将来性」、「仕事のやりがい」や「スキルアップ」等において、2~4割程度の評価を得ている(第Ⅱ-1-2-19図)。
第Ⅱ-1-2-19図 転職時に重視すること
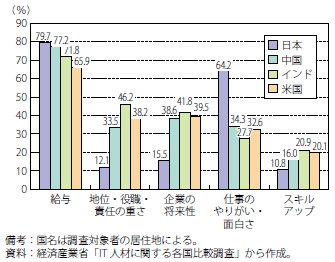
次に、実際の雇用環境への評価を確認するため、ITエンジニアの仕事や職場環境に対する満足度を米国と比較すると、米国は多くの項目で50%前後の満足度となっているのに対し、我が国はすべての項目において著しく満足度が低い状態となっている26(第Ⅱ-1-2-20図)。
第Ⅱ-1-2-20図 現在の仕事や職場環境に対する満足度
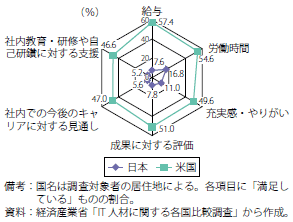
ITエンジニアの雇用環境に対する判断項目のうち、まず「給与」に関して調査対象者の役職のクラス別に給与水準の分布を見ると、「経営層・役員クラス及び部長クラス」、「一般社員クラス」共に、米国の給与水準が、比較的分散しつつも全体として高くなっている。また、インドは全体的な給与水準は低いものの、高い給与を得るITエンジニアも一定程度存在するという特徴が見られる。一方、我が国は一定の給与水準への偏りが他国より大きく(我が国の経営層・役員クラス及び部長クラスで900~1,500万円程度、一般社員クラスで300~500万程度)、中国、インドの最頻値は上回るものの、米国よりは低い水準に集中している傾向にある(第Ⅱ-1-2-21図)。
第Ⅱ-1-2-21図 調査対象者の年収の分布
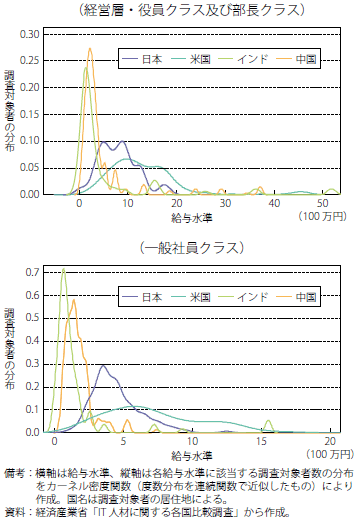
また、「社内での今後のキャリアに対する見通し」に関連して、自らの将来のキャリアパスを見通す参考となりうるITエンジニアの役職を見ると、米国等では4~5割程度が経営層・役職クラスや部長クラスなど、広範囲の事業に対して責任を負うポジションに配置されているのに対し、我が国においては、ほぼ半数が一般社員クラスレベルであり、経営層等上層クラスの配置は1割程度に止まる(第Ⅱ-1-2-22図)。
第Ⅱ-1-2-22図 調査対象者の現在の役職
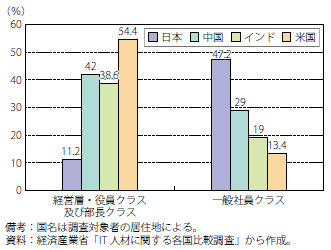
このように、我が国におけるITエンジニアの雇用環境のうち、各国のITエンジニアが重視する度合いの高い「給与」や「地位・役職・責任の重さ」に関する項目で、条件が劣後している。
この結果から、我が国のITエンジニアは、他のIT先進国と比較して処遇の水準が低く、その結果として仕事に対する満足度も全体的に低い、すなわち仕事自体の魅力が低い状況にあることが読み取れる。こうした事態が、新事業・新サービスを生み出せるような優秀な人材である「IT融合人材」の不足を引き起こし、ひいては、競争力のある製品・サービスの創出をも阻んでいるものと考えられる。
次に、「成果に対する評価」については、モチベーションを高め、仕事のやりがいにつながると考えられるが、ITエンジニアが職場から評価されていると感じている点について見てみると、我が国は多くの項目で割合が低い。特に、米国では、生産性の高さや、顧客に対する貢献度といった、それぞれの職務のクオリティに対して評価されていると考えら得るが、我が国においては、それら以上に上司からの信頼度といった、組織の一員として重要度が高いと考えられる項目が評価されていることが示唆される(第Ⅱ-1-2-23図)。
第Ⅱ-1-2-23図 職場から評価されていると感じる点
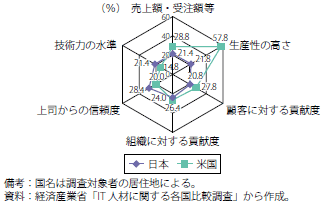
最後に、「社内教育・研修や自己研鑽に対する支援」については、雇用者がさらなるスキルアップができるかどうかについて、業務の内容そのものと並んで大きな要素と考えられる。
そもそも研修への参加については、雇用者側におけるそのニーズの高さによるところではあり、ITエンジニア、努力や勉強の必要性の認識を「よくあてはまる」に限定し、研修への参加頻度との相関を見ると、正の相関関係となっており、特に、米国、インドなどのITエンジニアで必要性の認識と参加頻度がともに高くなっている27(第Ⅱ-1-2-24図)。
第Ⅱ-1-2-24図 研修への参加頻度に関係する要素(必要性の認識)
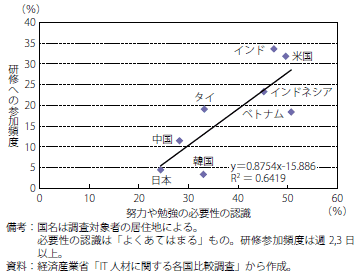
一方、実際の研修への参加に際しては、労働時間の制約も実体上発生すると考えられることから、これを推測しうる項目として、「労働時間の満足度」と研修への参加頻度との相関を見ると、同様に正の相関関係となっており、かつ、米国、インドなどのITエンジニアにおいて、労働時間の満足度と研修への参加頻度が高くなっている。これに対し、日本は中国、韓国よりもさらに低位に位置しており、雇用環境と合わせてスキルアップの機会も劣後していることが考えられる(第Ⅱ-1-2-25図)。
第Ⅱ-1-2-25図 研修への参加頻度に関係する要素(労働時間満足度)
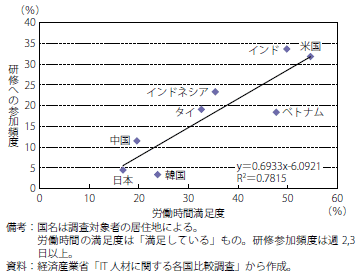
このような雇用環境の現状に対して、呼び込まれる人材側のニーズとして、米国、インド、中国及び日本のエンジニアの海外進出したい理由を見てみると、「給与」への評価は同様に高いものの、「スキルアップ」や「仕事のやりがい・面白さ」といった項目で評価が高くなっている(第Ⅱ-1-2-26図)。
第Ⅱ-1-2-26図 海外進出したい理由
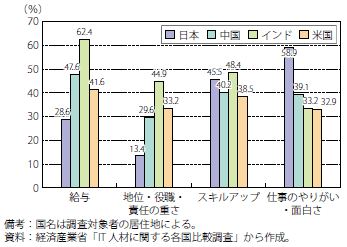
また、希望する転職対象国としては、有力IT企業が多く集積し、これまで見てきた雇用環境でも評価の高い米国が最も高い。我が国については、インドネシア等の東南アジアからの評価は高いものの、中国、米国及びインドネシアの技術者の希望転職国としては、ドイツよりも劣ったレベルに位置するという結果となっている(第Ⅱ-1-2-27図)。
第Ⅱ-1-2-27図 海外進出したい国
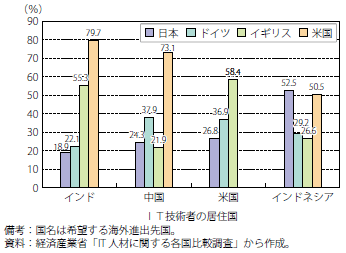
25 平成28年経済産業省委託調査「IT人材に関する各国比較調査」。
26 引用したアンケートでは、第Ⅱ-1-2-20図に引用した項目の他、「職場の雰囲気」や「仕事の内容」等、10の項目について、「満足している」「どちらかといえば満足している」「どちらかと言えば満足していない」「満足していない」の4回答からの選択となっている。
27 なお、自己研鑽の必要性は、雇用者が求められるスキルのレベルや、その動機付けを促す管理体制等、様々な要因にも影響されると考えられる。
③人材・技術を求めてシリコンバレーに進出する我が国企業の動向と課題
IoT、AIやロボティクスといった新たな技術の発展・浸透に際し、その既存産業に与える影響が大きくなる一方、既存産業の企業にとって、新技術への対応は自社内に従来保有する組織的な能力や資産だけで対応することが難しい場面も多い。このため、イノベーションの分野で先行する既存企業の中では、求める技術やこれを生み出す人材の獲得のため、外部企業との提携や買収を通じた外部技術の取り込みや集積地への進出に力を入れている。
特に、上記のような先進的技術は、世界的に競争力の高いIT企業が集積するシリコンバレーなど世界の一部の地域に偏在することから、同地域を巡る企業の動きが活発になっている。
代表的な既存の産業領域の産業である自動車産業においても、コネクテッドカーや自動運転の実現に向けた新技術の必要性の高まりを背景に、企業の拠点シフトが進んでおり、研究開発機能の集積地として、米国における同産業の一大集積地であったデトロイトから、シリコンバレーへと世界各国の企業が集積しつつある(第Ⅱ-1-2-28図)。
第Ⅱ-1-2-28図 自動車の新たな集積地“シリコンバレー”
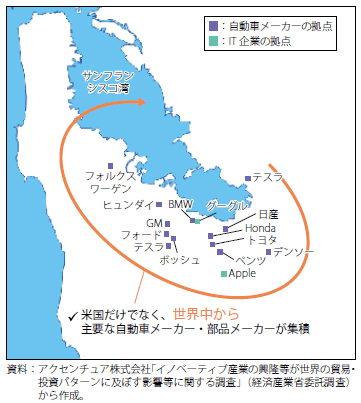
このような背景のもと、我が国企業においても、シリコンバレーに進出する企業が増えており、北加日本商工会議所とジェトロ・サンフランシスコが共同で実施した調査28によると、シリコンバレーやサンフランシスコを含む米国ベイエリアに進出する日系企業数は、2014年にはジェトロの調査開始後最多の水準となっている(第Ⅱ-1-2-29図)。
第Ⅱ-1-2-29図 ベイエリアにおける日本企業数
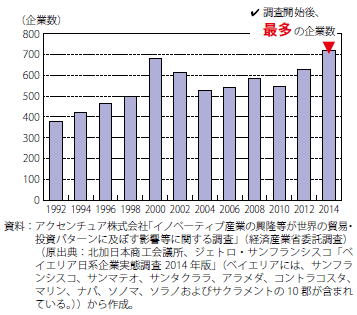
このような新たなイノベーションの創出を目指した技術のキャッチアップのためのアプローチとしては、現地企業の提携・買収による技術・人材の取り込み、現地での採用活動による人材の獲得、現地への社員の送り込みによる人材育成の3つに大別できる(第Ⅱ-1-2-30図)。
第Ⅱ-1-2-30図 海外技術取り込みのアプローチ
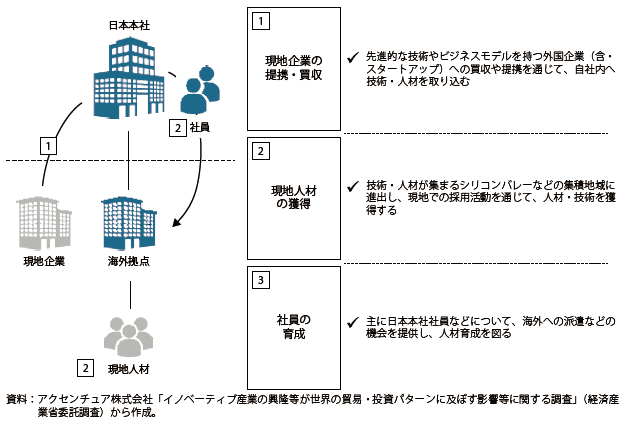
一方、シリコンバレーに進出した我が国内外の企業、及び現地の企業、大学、研究機関などへのヒアリングを通じて、経済産業省が実施した委託調査29によれば、我が国企業はシリコンバレーなどの海外のテクノロジーの先進地から技術・人材を取り込む上で、様々な課題に直面している。
まず海外に進出した企業は、現地で十分に認知されておらず、海外の優秀な人材などを取り込めない「認知」の壁がある。特に現地企業の買収・提携を目指した我が国企業にとって、現地で知られていないことは交渉の進展を妨げる要素になりうる。
また、企業の認知が進んでいた場合でも、その企業がどのような実績を有するのか、どのようなテーマ・体制で研究開発を行っているかなどを十分に訴求できておらず、関心を持ってもらえない「関心」の壁がある。優秀な現地のエンジニアの中には、入社後に誰と何ができるのか、などを重視するケースも少なくない。
加えて、「行動」の壁も海外へ進出した企業の前に立ちはだかっている。例えば、意思決定権が十分に現地法人に与えられておらず、交渉に時間がかかってしまうことで買収交渉が進まないケースや、採用にあたっても十分な報酬を提供できずに断念せざるを得ないケースなどがある(第Ⅱ-1-2-31図)。
第Ⅱ-1-2-31図 日系企業が海外からの技術取り込みを図る上で抱える課題
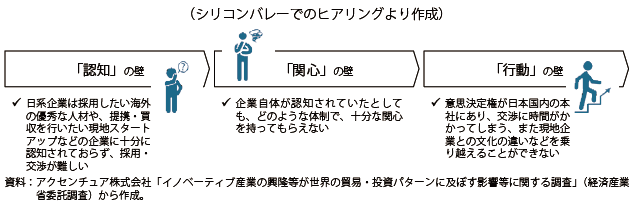
これらの課題を解消し、技術のキャッチアップを円滑・迅速に獲得するため、我が国企業各社では様々な取組が行われ始めている。例えば、先進的なテクノロジーを持つ現地企業の提携・買収や優秀な現地人材の採用を実現するため、進出先においては、現地経営層としてその分野に実績のある人物を配し、現地オフィスにおける迅速な意思決定を可能とするガバナンスを与えることが挙げられる。これに対応する本社側においても、本社経営層及び本社現場側で現地の意思決定をサポートし、提供される情報を活用することがポイントとなっている。
また、外部からの技術を取り込むことと並行して、社内人材の育成にも取り組むことが求められるが、海外の現地オフィスへの派遣や、オンラインプラットフォーム上での擬似的体験を通じて、我が国内の社員に海外のビジネスや技術を活用できるバックグラウンドを構築することが重要と考えられている(第Ⅱ-1-2-32図、第Ⅱ-1-2-33図)。
第Ⅱ-1-2-32図 提携・買収/現地採用に関するポイント
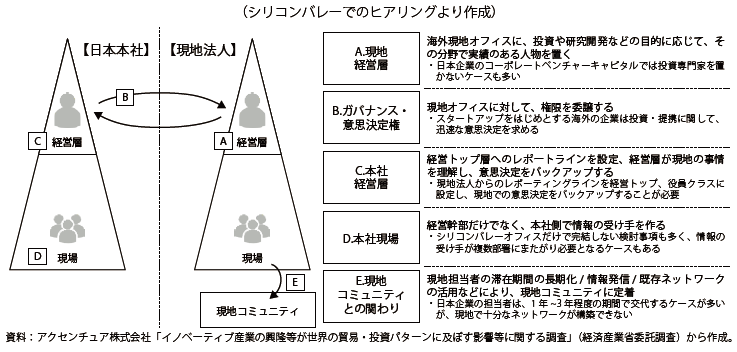
第Ⅱ-1-2-33図 社員の育成に関するポイント
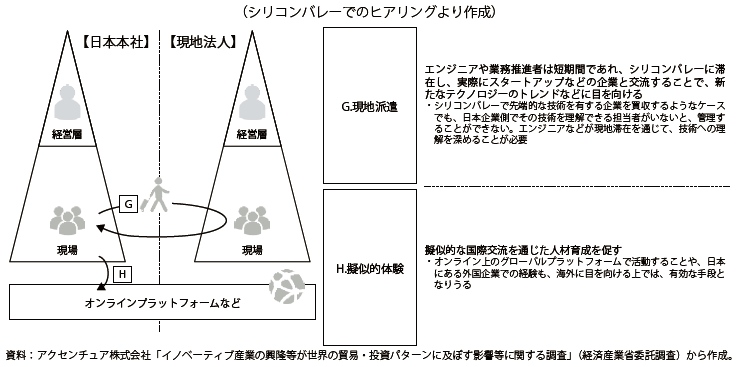
28 北加日本商工会議所、ジェトロ・サンフランシスコ「ベイエリア日系企業実態調査 2014年版」から作成。なお、同調査では、①我が国企業が 10%以上出資(間接出資を含む)している現地法人、②我が国に本社のある企業の支店・駐在員事務所、③日本人が設立し運営している日本人設立企業を対象とし、ベイエリアには、サンフランシスコ、サンマテオ、サンタクララ、アラメダ、コントラコスタ、マリン、ナパ、ソノマ、ソラノおよびサクラメントの 10 郡が含まれている。
29 アクセンチュア株式会社(2016)。
④まとめ
②で見てきたアンケート結果を踏まえると、我が国においては人材不足の問題を抱える中、国内IT人材は仕事のやりがい、給与、地位やスキルアップ等、IT人材が重視する面での処遇が低く、仕事自体の魅力が乏しい状況から、諦めて現状に安住する者が多いと考えられる。このような魅力の乏しい労働環境は、新たな人材の呼び込みを阻むのみならず、やりがいを求める一部のエンジニア層の海外への転職を引き起こし、新事業・新サービスを生み出せるような優秀な人材である「IT融合人材」の不足、ひいては競争力のある製品・サービスの創出を阻んでいるものと考えられる。
特に、優秀なIT人材が自らのキャリアプランを考える際は、給与水準に加え、自分のスキルを高めるインセンティブが強く働く傾向にあると言われている。その結果、データを多く保有・活用できる環境が整った企業や、既に優れたエンジニアが集まっている企業に人材が集中する傾向があり、米国を始めとする競争力の高いIT企業に各国の優秀なエンジニアが集中するという状態が加速化している。
これに対し、我が国において、ITエンジニアという世界的に需要が高まっている人材を確保するためには、給与や役職、評価基準や人材育成投資等において多くの課題があると考えられる。新たなテクノロジーによりイノベーションを生み出す人材を獲得するため、先行する日本企業の取組を踏まえ、企業や人材が活躍しうる多様な環境整備を早急に構築する必要性が高まっていることが示唆される。
2.イノベーションと高度人材の獲得
(1)産業別の生産性動向
第1部で見たように、我が国のこれまでの全要素生産性(以下「TFP」という。)の伸びは、米国・ドイツと比較して最も低かった。他方、TFPの伸びは業種によって大きく異なることも事実である。
第Ⅱ-1-2-34図及び第Ⅱ-1-2-35図は、各国のTFPの伸びを業種別に見たものである。
第Ⅱ-1-2-34図 TFP(業種別)の推移(1)
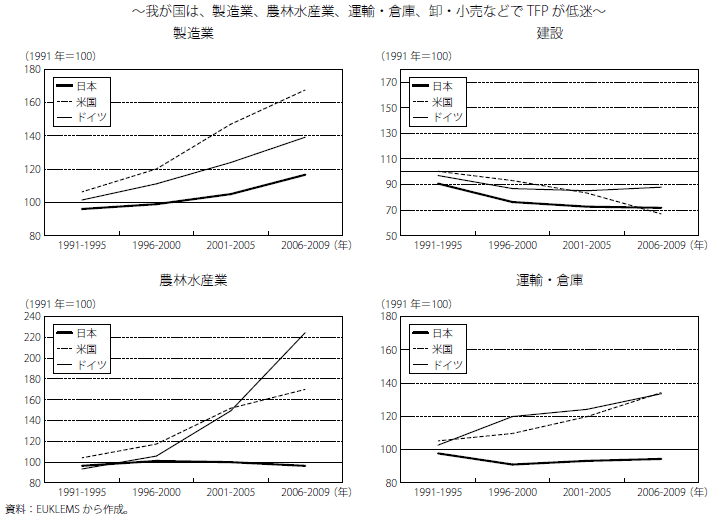
第Ⅱ-1-2-35図 TFP(業種別)の推移(2)
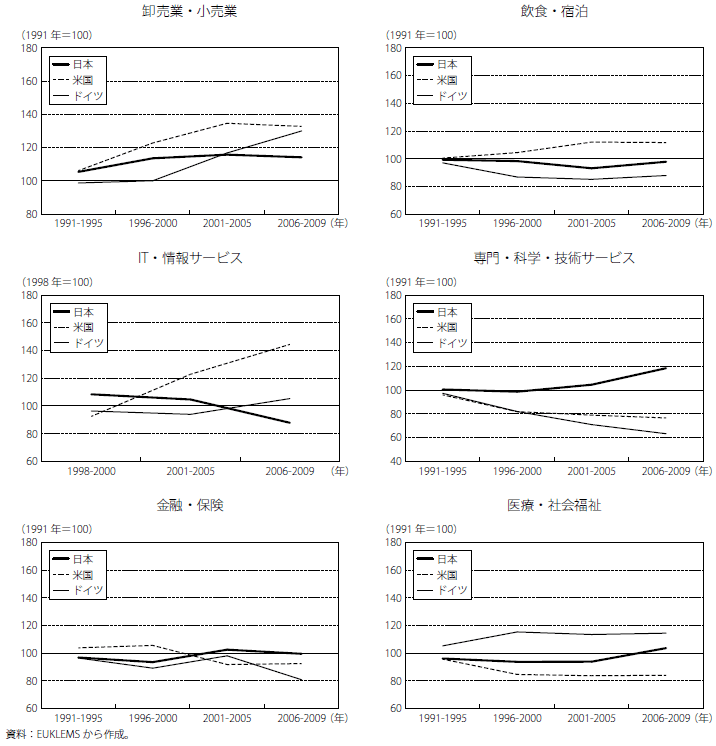
- Excel形式のファイル(卸売業・小売業)はこちら

- Excel形式のファイル(飲食・宿泊)はこちら

- Excel形式のファイル(IT・情報サービス)はこちら

- Excel形式のファイル(専門・科学・技術サービス)はこちら

- Excel形式のファイル(金融・保険)はこちら

- Excel形式のファイル(医療・社会福祉)はこちら

これらを見ると、我が国は、製造業、農林水産業、運輸・倉庫、卸・小売業などでTFPの伸びが米国、ドイツを大きく下回っている。我が国製造業のTFPは90年代後半以降持続的な伸びを続けているものの、そのペースは米国やドイツを大きく下回っている。農林水産、運輸・倉庫、卸・小売業などでは、90年後半代以降TFPはほとんど横ばいのままである。他方、専門・科学・技術サービスなどでは、逆に、我が国のTFPの伸びが米国やドイツを上回っている。
では、こうした産業間におけるTFP伸び率のばらつきを踏まえた場合、今後、我が国の経済成長をけん引するためには、産業界としてどのような方策を採ることが望ましいのであろうか。
急速な少子高齢化が進む我が国では、今後、国内の財・サービス市場の飛躍的な拡大は見通しづらい。そのような環境の中で、例えば、TFPの高い産業は、その高い競争力を活用して、製品・サービスの輸出拡大を通じた生産・雇用の拡大を目指すことによって、我が国の経済成長に大きく貢献することが出来る。他方、TFPの低い産業は、技術革新(以下「イノベーション」という。)の実現を通じて、TFPの底上げを行わなくてはならない(第Ⅱ-1-2-36図)。
第Ⅱ-1-2-36図 高生産性産業の伸張と低生産性産業の底上げ
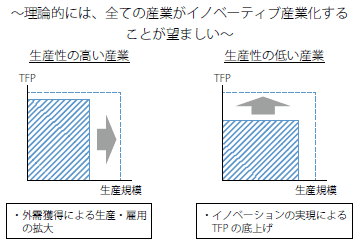
前者の高生産性産業による市場拡大の実現は比較的容易と考えられるが、後者の低生産性産業によるTFPの底上げは容易なことではない。
企業がTFPを高めるためには、イノベーションが欠かせない。イノベーションの実現によって、新製品・新サービスの市場投入が可能となれば、企業は新しい市場を獲得できる可能性がある。生産技術の革新によって、生産コストの大幅な削減が実現すれば、製品・サービスの競争力は飛躍的に向上するはずである。
(2)国境を超えたTFP向上の波及に必要な条件
企業がTFPを高めるためには、イノベーションが欠かせない。イノベーションの実現によって、新製品・新サービスの市場投入が可能となれば、企業は新しい市場を獲得できる可能性がある。生産技術の革新によって、生産コストの大幅な削減が実現すれば、製品・サービスの競争力は飛躍的に向上するはずである。
では、国境を越えたTFP向上の波及にとって必要な条件とはどのようなものなのであろうか。
一般にイノベーションとは、既存の知識をベースに、そこに新たな知識を加えることで、新しい価値を創造するプロセスを指す。
過去のイノベーションの成果でもある既存の知識には、公知のものもあれば、知財としての権利が付与されているものもある。前者は、文献やインターネットなどを経由して無償で活用することができるが、後者を自身の研究開発あるいは生産活動に活用しようとする場合、企業はその使用権を購入する(技術ライセンシングを受ける)必要がある。
さらに、こうして得た外部の知識を吸収し、そこに新たな知識を加え新しい価値を生み出すためには、優れた技術者の存在が欠かせない。
そして、近年では、こうした技術ライセンシングや優れた技術者の確保が国境を越えて行われることが当たり前になってきている。
そこで、以下では、こうした国境を越えた知識伝搬とイノベーションとの関係について見ていく。そして、外部の知識を取り入れることに積極的な企業ほど、また、外国人技術者の受入れに積極的な企業ほどイノベーションを実現していることを示す。
まず、知識伝搬の経路について整理する。第Ⅱ-1-2-37表は、伝搬経路ごとにその具体例と、伝搬媒体の関係を示したものである。
第Ⅱ-1-2-37表 国境を越えた知識伝搬の経路
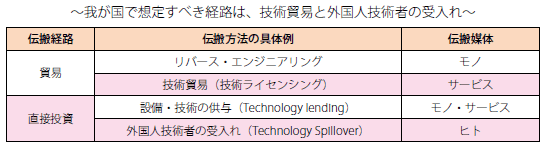
企業によるイノベーションを念頭に置いた場合、伝搬経路にはおもに貿易と直接投資の2種類が想定される30。このうち貿易については、輸入した外国製品を分解することでその製造技術を得ようとするリバースエンジニアリングと、海外の技術の使用権を金銭で購入する技術ライセンシングの2つの経路が考えられる。これらのうち、我が国のような先進国の企業が一般的に選択する経路は後者であろう。これらが貿易、すなわちモノまたはサービスの取引を媒体にした国際的な知識伝搬の経路の例である。
また、直接投資によっても知識は伝搬する。この場合、具体的な経路としては、設備・技術の供与(Technology lending)と外国人技術者の受入れ(Technology spillover)の2種類がある。前者は、投資国が生産設備やその運転方法などといったモノやサービスを被投資国に供与して生産を行わせるものである。この場合、被投資国の生産者は単なる生産設備のオペレーターとしてしか位置づけられないから、生産設備や運転方法に体化された様々な知識の伝搬は生じない。
他方、これとは対照的に、外国投資を受け入れる際に、生産設備や運転方法だけでなく外国人技術者も受け入れる場合は、様々な知識の伝搬が期待できる。例えば、技術者同士のFace to faceのコミュニケーションを通じて、形式知(公知の知識や技術ライセンシング)では得られないような知識(暗黙知)を得ることが可能となるだろう。特に我が国のような先進国の企業が外国投資を受け入れるような場合、その中心は、こうした外国人技術者の雇用を通じて、海外のイノベーションの成果を確実に取り込んでいくことが、自身のTFP向上にとって重要になると考えられる。
30 実際には、これら以外にも、開発援助や大学等の研究交流、移民の帰国などといった経路が想定されるが、ここでは扱わない。
①技術貿易とイノベーション
第Ⅱ-1-2-38図はOECD諸国の特許等使用料(受取及び支払)の名目GDP比の推移を見たものである。これを見ると、1990年代以降、世界の技術貿易の規模は急速に拡大していることが見て取れる。経済の急速なグローバル化を背景に、国境を越えた知識の取引(伝搬)が世界規模で活発化していることがうかがえる。
第Ⅱ-1-2-38図 世界の技術貿易の推移
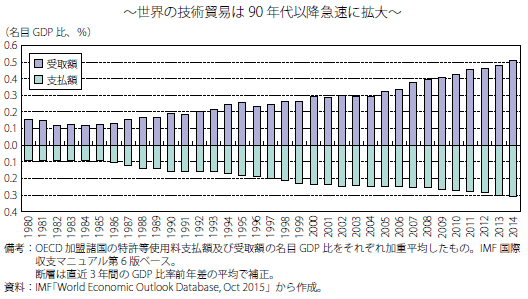
またGDPに占める比率が急速に高まっていることは、一国の経済活動における外国知識の重要性が高まってきていることも表している。
次に、我が国製造業の技術貿易の実態を見てみよう。第Ⅱ-1-2-39図は、総務省「科学技術研究調査」の製造業19業種について、親子会社間技術貿易(以下「企業内技術貿易」という。)と親子会社以外との技術貿易(以下「企業外技術貿易」という。)の2つに分けて見たものである。
第Ⅱ-1-2-39図 我が国製造業の技術貿易の現状①
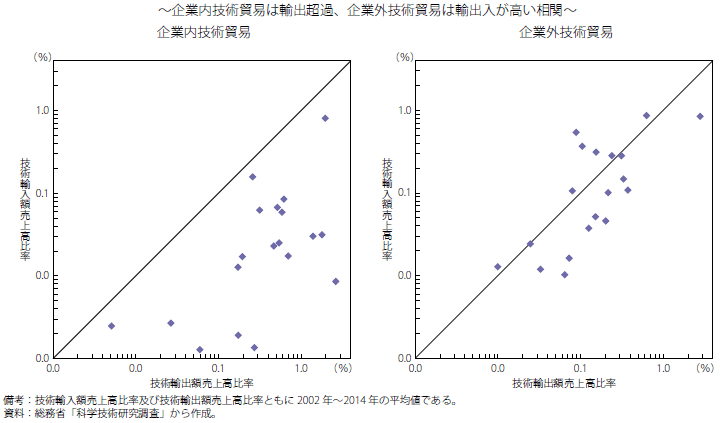
まず、企業内技術貿易を見ると、19業種すべてが45度線の下に位置しており、輸出超過であることを示している。これは、我が国の対内直接投資が極めて少ないことから、我が国で活動する多国籍企業の大半が日系の多国籍企業であることに起因する。すなわち、我が国企業の海外進出目的の多くが海外生産拠点の設置であり、国内の親会社から生産拠点である海外子会社への生産技術の移転が活発に行われていることがその背景にあると考えられる。
他方、企業外技術貿易を見ると、おおむね各業種とも45度線付近に分布しており、活発な企業外技術貿易が行われていることがうかがえる。
では、具体的にどのような業種で企業外技術貿易が活発に行われているのであろうか。第Ⅱ-1-2-40図は、製造業19業種の企業外技術貿易(売上高比率)の推移を2002年~2006年及び2007年~2012年の2期間について見たものである。
第Ⅱ-1-2-40図 我が国製造業の技術貿易の現状②
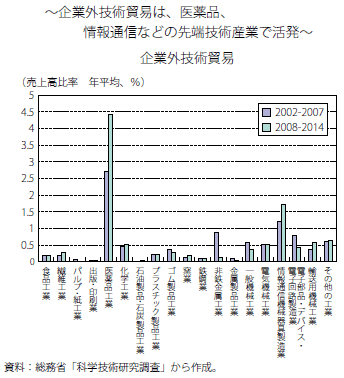
これを見ると、医薬品工業を始め、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業など我が国の代表的な先端技術産業において、高い水準で企業外技術貿易が行われていることが分かる。とりわけ研究開発が活発に行われている医薬品工業では突出して高い水準となっている。
さらに、これらの先端技術産業のTFP上昇率を見ると(第Ⅱ-1-2-41図)、いずれも他の業種と比べ相対的に高いTFP上昇率を実現していることが分かる。
第Ⅱ-1-2-41図 我が国製造業のTFP
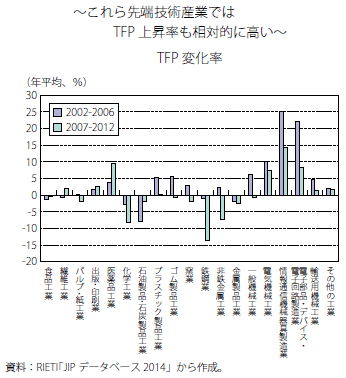
第Ⅱ-1-2-42図は、総務省「科学技術研究調査」の製造業19業種について、企業外技術貿易とTFPの関係を見たものである。
第Ⅱ-1-2-42図 企業外技術貿易とTFPには密接な関係がある
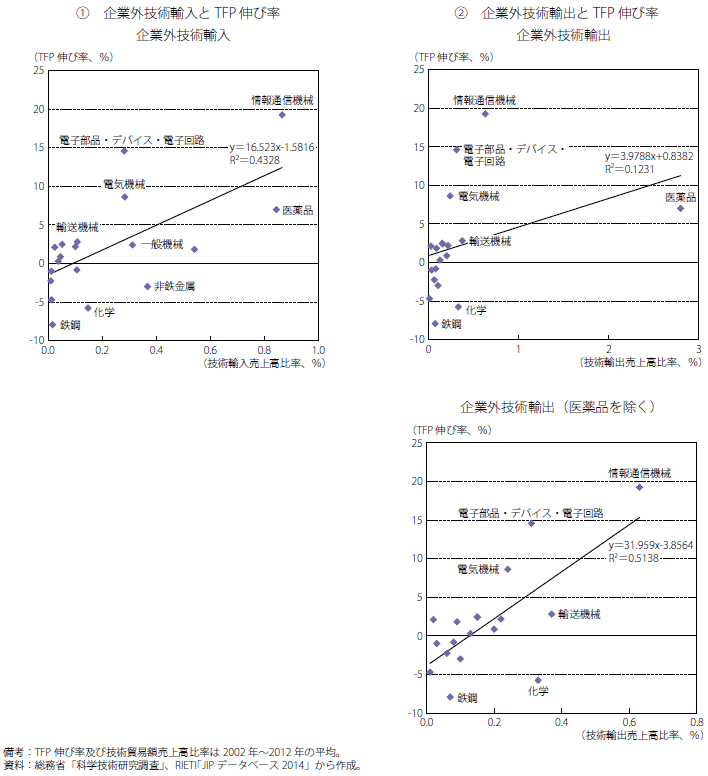
まず、企業外技術輸入額の売上高比率とTFP上昇率の関係を見ると、両者の間には密接な関係があることが分かる。TFP上昇率が高く競争力のある業種ほど、多くの技術を外部企業から取り込んでいることが見て取れる。
他方、企業外技術輸出額の売上高比率とTFP上昇率の関係を見ると、企業外技術輸出の水準が突出して高い医薬品工業を除くと、高い正の相関を示すことから、技術輸入と同様、TFP上昇率が高く競争力のある業種ほど、多くの技術を外部企業に供給していることが見て取れる。
②技術者の国際移動とイノベーション
次に、技術者の国際移動とイノベーションの関係について見ていく。
技術者の国境を越えた移動とイノベーションの関係については、米国を中心にこれまでにも数多くの実証研究が行われてきている。
こうした実証研究は、外国の技術者を受け入れることで、技術者同士のコミュニケーションが深まり、公知の技術や技術輸入では得られなかったような暗黙知の獲得が可能となったり、知識の吸収がより確固たるものになったりする結果、当該国のイノベーションを促進する効果があるという想定に基づいている。
そして、これらの研究において一般的にイノベーションの進展度合いを表す指標としてよく使われているのが特許申請件数である。これは容易に入手が可能である。
他方、技術者の移動に関するデータは我が国を含め先進国であってもその入手は難しい。唯一、米国だけが技術者の出国時期・出国先、出国目的及び米国内の出発地などといった詳細な渡航情報が入手できる。
Hovhannisyan et al(2012)は、被説明変数に34か国の対米特許申請件数を、説明変数に米国技術者の出国データを用いている。その際、米国技術者の出国数は、出発地の州または郡のパテント・ストックのGDP比で加重したものを用いている。これによって、例えば、イノベーションが活発なカリフォルニア州の技術者とイノベーションが不活発なネブラスカ州の技術者では渡航先の国のイノベーションに与える影響度合いが異なるといった状況を再現することができるとしている。
さらに、Hovhannisyan et al(2012)では、技術者の移動に関するデータに加えて、一般的にイノベーションに影響を与えるとされている自国の研究開発費支出などいくつかのマクロ変数も同時に加えて推計を行っている31。
その推計結果を見ると(第Ⅱ-1-2-43図)、米国からの商用旅行者数は、他のマクロ変数の有無とは関係なく、常に有意に正の値を維持している。事前の想定どおり、海外技術者との交流は自国のイノベーションにプラスの効果を有していることが確認できる。
第Ⅱ-1-2-43表 人材の国際移動とイノベーション 推計結果
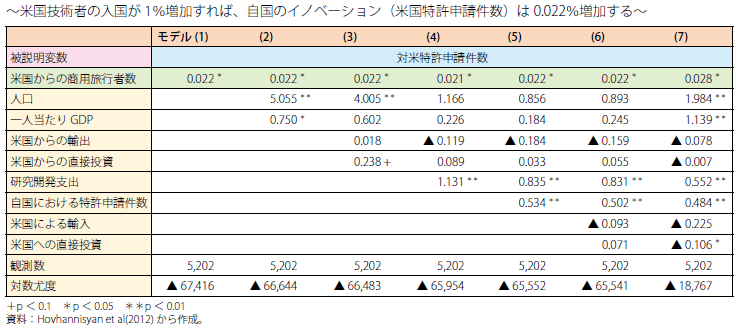
31 マクロ変数は、自国の人口、一人当たりGDP、米国から自国への輸出及び直接投資、自国の研究開発費支出、自国内での特許申請件数、自国から米国への輸出及び直接投資である。
(3)まとめ
以上、人口減少下の我が国にとって、イノベーションを通じたTFP向上が強く求められること、技術輸入や海外からの技術者の受入れがTFPの向上にとって一定の効果を持つことなどを示してきた。
他方、現実の我が国の技術者の受入れ状況を見てみると、極めて低調である。第Ⅱ-1-2-44図は商用の短期滞在者について、我が国と米国及び中国を比較したものであるが、我が国の滞在者数は極めて低い水準で低迷していることが分かる。米国の滞在者数は我が国のおよそ6倍、中国も最近低下傾向にあるものの、我が国の5倍近い水準である。
第Ⅱ-1-2-44図 我が国、米国及び中国の短期滞在者数の推移
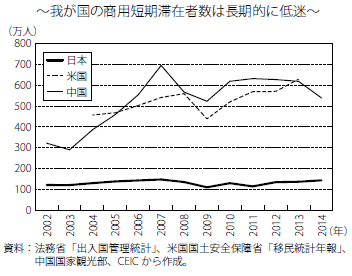
また、大学在学者以上の海外高度人材の移住者数がOECD加盟国の移住者数全体に占める割合を見ても、我が国はわずか1.5%と極めて低く、米国の41%に遠く及ばない(第Ⅱ-1-2-45図)。高度人材の多くが米国に集中していることが見て取れる。
第Ⅱ-1-2-45図 OECD諸国における移住者のシェア(全学歴及び高度人材)
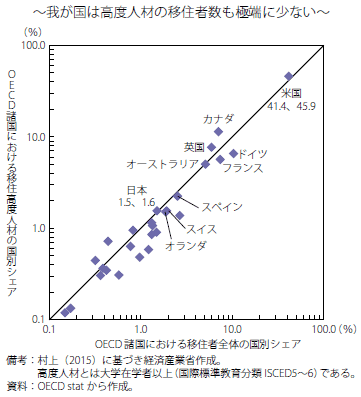
このように我が国が、短期滞在でも移住でも海外高度人材の受入れが低調な背景には、高度人材に対しても日本語能力や日本的雇用慣行への適合を求めていることなどの問題が指摘されているが32、今後は、こうした慣行を改め、海外高度人材の受入れの増加と定着を積極的に進めていかなければならない。
32 例えば、労働政策・研究機構(2013)141頁。
