

- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2017

- 白書2017(HTML版)

- 第1部 第1章 第3節 世界の主要国・地域別対外経済関係
第3節 世界の主要国・地域別対外経済関係
第1節では、IMF、WTO等の国際機関の論考から見る世界経済動向を紹介し、特に前節では2016年の世界経済に影響を与えた資源価格の動向に関し説明を行なった。本節では、更に貿易と経常収支の観点から、世界の主要国・地域の対外経済関係を考察していく。
1.世界貿易の動向
(1)概観
近年の世界における貿易の動向について概観していく。2016年の世界の財貿易額は31兆9,128億ドルで前年比▲3.8%と2年連続で減少した。貿易額の伸び率の推移を見ると、2008年以前は毎年前年比+10%を越える成長を続けていたことがわかる。しかし、世界経済危機が起こった後、大きく貿易額が落ち込んだ反動で一時的に高い伸び率を見せたものの、2012年以降その伸び率は大きく鈍化し、2015年には遂にマイナス転化した(第Ⅰ-1-3-1-1図)。
第Ⅰ-1-3-1-1図 主要国・地域別の財貿易額と伸び率の推移
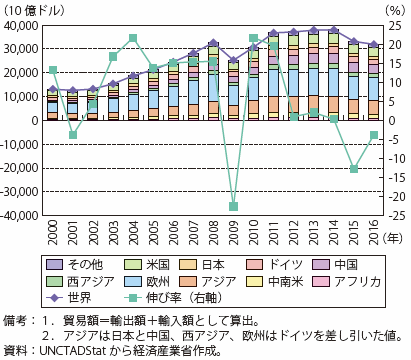
近年、このような世界貿易の縮小が、国際機関等、世界の論檀において指摘されている。一例を挙げれば、第1節でも述べたように、世界の貿易量の伸び率が実質GDP成長率を長期間下回って推移していることが各機関で取り上げられている13。2007年以前は実質GDP伸び率の約2倍の伸び率で推移していたが、2012年に貿易量の伸び率が実質GDP伸び率を下回って以降、その状態が5年間にわたって継続していることが取り上げられている(第Ⅰ-1-3-1-2図)。本状況をIMF、WTO等の国際機関はスロー・トレード13と呼び、本論点に関する論考が多数出されている。
第Ⅰ-1-3-1-2図 世界の実質GDP、輸入量の伸び率推移
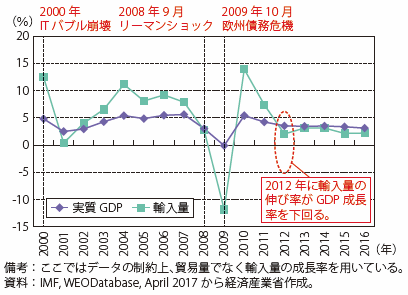
「スロー・トレード」とは貿易量に言及した議論であるが、本節では貿易額に焦点を絞って、近年の世界的な貿易縮小要因を考察していく。
13 「スロー・トレード」は、2014年12月にIMFが発行する雑誌「Finace & Development」の記事から提唱された。記事によれば、「スロー・トレード」とは、実質GDP成長率を貿易量の伸び率が下回ることであるが、明確な定義等は定まっていない。
(2)貿易額の拡大鈍化の要因
世界の貿易額の伸び率鈍化の要因として、①世界的な経済成長率の鈍化、②2011年以降の原油価格の下落、③新興国の中間財国内生産化の三点を考察していく。
①世界的な経済成長率の鈍化
貿易額の伸び率鈍化の要因として、世界的な経済成長率の鈍化があげられる。世界の実質GDP成長率を見ると、世界経済危機が起こった2008年以前は前年比+5%を超える上昇傾向であった。しかし、2009年以降、新興国・途上国地域を中心に世界の実質GDP成長率は鈍化している。OECDによれば14、2016年に至るまでの過去5年間、世界経済は低成長の罠に陥っている。さらに、成長率の継続的な低下は、将来の成長期待の重石となっており、経常的な支出及び潜在成長を低下させ、主要新興市場における投資の不振、賃金の伸び悩み、経済活動の停滞等を引き起こすとの指摘がある。上記に加え、需要と供給の減少もあいまって、各国・地域の貿易量を減少させ、貿易額が減少したと考えられる(第Ⅰ-1-3-1-3図)。
第Ⅰ-1-3-1-3図 世界のGDP成長率と主要国・地域別寄与度の推移(購買力平価ベース)
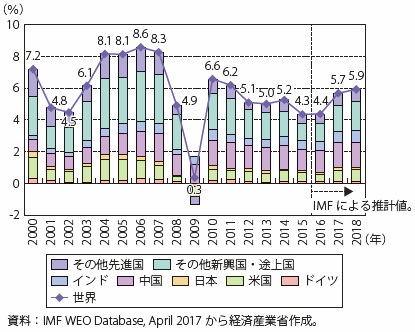
14 OECD「Economic Outlook100(2016年11月)」を参考に記載。
②資源価格低下に伴う貿易額下落
次に、資源価格下落の観点から貿易額の伸び率鈍化の原因を考察していく。貿易額を詳細に見ると、2012年以降、伸び率が鈍化している財貿易額の中でも、特に原油を含む資源貿易額の伸び率が大きく低下している(第Ⅰ-1-3-1-4図)。2014年の資源貿易額は前年比▲6.4%の伸びであったところ、2015年では同▲38.0%の伸びとなった。これは、世界経済危機の影響を受けた2009年並みの下げ幅であり、この低下を受け、財貿易額全体も2015年には同▲11.3%と伸び率が縮小した(第Ⅰ-1-3-1-4図)。
第Ⅰ-1-3-1-4図 財・サービス、資源貿易額の推移
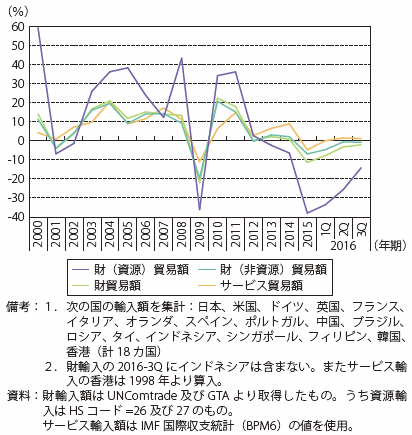
財別で貿易額の伸び率を寄与度分解すると、輸入額全体が同▲3.4%の伸び率であるところ、資源を含む素材は同▲2.6%と8割近くの寄与を占めており、2012年から2015年にかけて大きく輸入額全体を下押しした品目であることがわかる(第Ⅰ-1-3-1-5図)。
第Ⅰ-1-3-1-5図 輸入額成長率の財別輸入額寄与度の推移(世界)
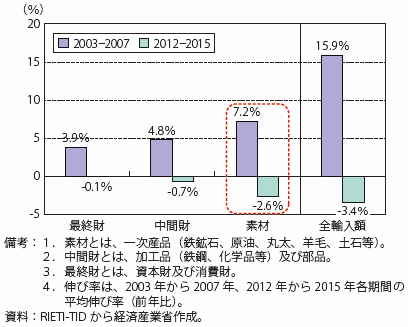
資源貿易額減少の主な要因としては、価格下落の影響が大きいと考えられる。前節で述べた原油だけでなく、石炭や鉄鉱石といった資源の価格も2011年比で2014年から2016年初頭にかけて大きく下落し、現在(2017年3月時点)は低水準で推移している。IMFでは、資源価格下落の要因として、資源の供給過剰及び中国のリバランスと成長への懸念をあげている。
また、2011年と比較すると、前述したように低水準ではあるが、2016年以降、主な資源価格は上昇傾向となっている(第Ⅰ-1-3-1-6図、第Ⅰ-1-3-1-7図)。
第Ⅰ-1-3-1-6図 主要コモデティ価格の推移
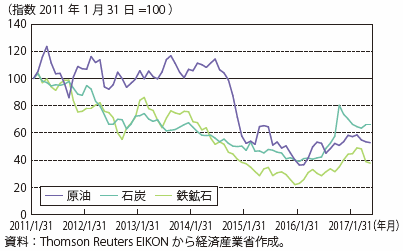
第Ⅰ-1-3-1-7図 WTI原油先物価格の推移
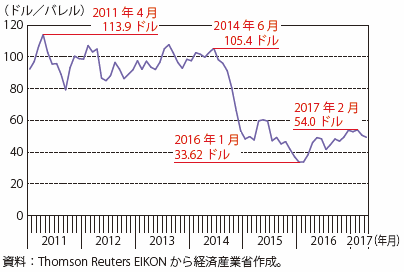
③中間財の国内生産化
財貿易の中で、グローバル・バリュー・チェーン(以下、GVC)の動向と世界の貿易額の関係について見ていく。IMFによれば15、世界で大きく財貿易額が拡大した要因の一つに、GVCの構築による中間財貿易の拡大があげられている。GVCとは、「製造業などにおける生産工程が内外に分散していく国際的な分業体制のこと16」を指す。国際的な生産分業により世界の財貿易額の半分近くを占める中間財の輸出入が活発になることで、大きく貿易額が増加した。GVCの拡大は、特に1990年代から2000年代初頭にかけて顕著であった。東アジア地域では、中間財の輸入割合が64.6%(2015年時点)を占めており、NAFTA(域内中間財輸出比率47.0%)、EU28(同49.8%)等の地域より大幅に高いことから、GVCの構築がより進んでいると考えられる17(第Ⅰ-1-3-1-8図、第Ⅰ-1-3-1-9図)。
第Ⅰ-1-3-1-8図 世界における輸入額の財別シェア(世界、2015年)
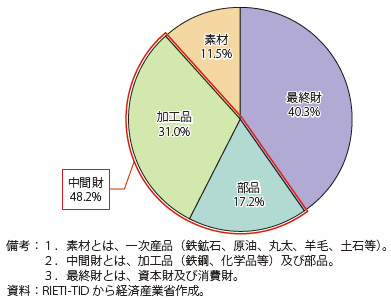
第Ⅰ-1-3-1-9図 域内貿易の財別輸出比率の推移
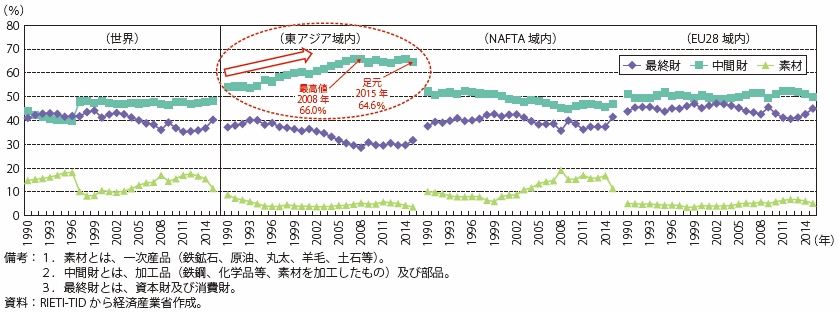
しかし、近年ではこの域内貿易における中間財輸出割合の拡大が鈍化している(第Ⅰ-1-3-1-9図)。このことから世界の貿易額の伸び鈍化の一因として、世界のGVC拡大の一服による中間財貿易の鈍化が影響を与えていると考えられる。
前述したようにGVCの構築が他地域より進んでいると考えられる東アジアについて、2012年以降の東アジアの財別輸入額の推移を見ると、2003年から2007年までは中間財が年平均16.7%伸びることにより輸入額全体を牽引していた。しかし、2008年9月に起こった世界経済危機の影響から2009年に輸入額が急落して以降、2012年から中間財輸入額の伸び率は鈍化しており、2015年は同▲15.4%の伸びと大きく落ち込んだ(第Ⅰ-1-3-1-10図)。
第Ⅰ-1-3-1-10図 財別輸入額成長率の推移(東アジア)
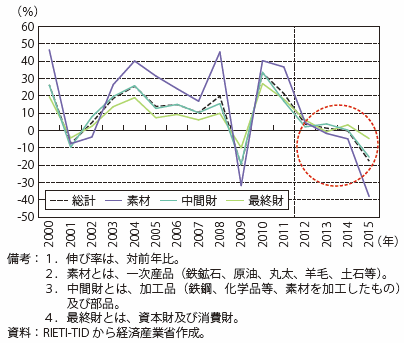
中間財輸入額の推移傾向から、現地のGVCの現状を考察していく。一つの目安として、主要な品目別に輸出総額に対する中間財輸入比率を見ると、中国、ASEAN域ともに電気機械、一般機械、精密機械の三品目全てにおいて中間財輸入比率が年々減少していることがわかる。中国やASEAN域では、我が国を含む先進国との加工貿易が盛んであった。しかし、技術進歩等によりこれまで輸入していた中間財を国内で生産することが可能になり、中間財輸入が減少したとの指摘がある18(第Ⅰ-1-3-1-11図)。なお、東アジアに立地する日系企業の動向を見ると、中国とASEAN419に立地する日系製造業の現地法人は、2005年以降、それぞれ現地から中間財を調達する割合が年々高まっており、2015年時点では調達物の半分以上を現地で賄っている。この点からも、新興国の中間財国内生産化による貿易額の伸び率鈍化の一端が伺える。
第Ⅰ-1-3-1-11図 財別輸出に対する中間財輸入の比率(品目別)
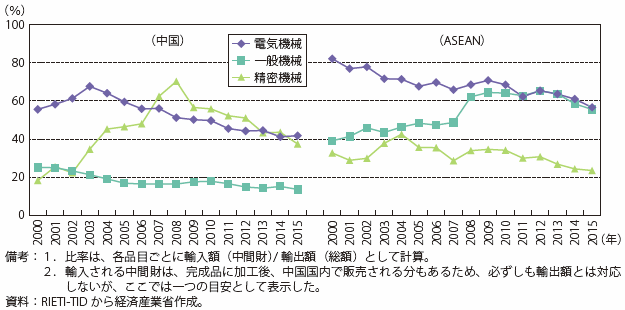
15 IMF「What’s Behind the Slowdown?」
16 経済産業省「平成23年度総合研究調査 グローバル・バリュー・チェーン分析に関する調査研究」株式会社 三菱総合研究所より引用。
17 JETRO「東アジアの貿易構造と国際価値連鎖 モノの貿易から「価値」の貿易へ」(2011年)を参照。
18 IDE-JETRO、「東アジアの貿易構造と国際価値連鎖 モノの貿易から「価値」の貿易へ」(2011年10月)を参考。
19 ASEAN4とは、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピンを指す。
2.世界の経常収支動向とその背景
前項においては、足下の貿易動向を中心に世界の経済関係を見てきた。本項ではさらに詳しく世界の経済関係を見るために第一次所得収支、サービス収支等を含んだ経常収支を概観していく。
(1)経常収支の不均衡
2000年代初頭の主要国・地域の経常収支の推移を見ると、経常黒字・赤字は大幅に拡大傾向であった。しかし2008年9月に発生した世界経済危機の影響を受け、それまで不安定に拡大を続けていた経常黒字・赤字は2009年にそれぞれ一挙に縮小することとなった。しかし2010年以降、黒字・赤字は再び緩やかな拡大傾向となっている(第Ⅰ-1-3-2-1図)。
第Ⅰ-1-3-2-1図 主要国・地域別経常収支の推移
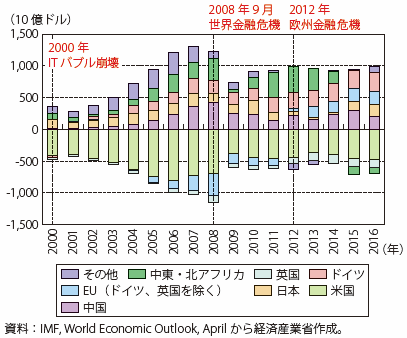
詳しく見ていくと、黒字額はユーロ圏、日本、中国が、赤字額は米国がそれぞれ拡大を牽引している。ユーロ圏内では、2000年代前半に赤字国となっていたイタリア、スペイン、ポルトガル等の国が世界経済危機以降、欧州債務危機を経て黒字国へと変化している20。黒字化の主因としては、財政再建を進めたことに加え、一次産品価格の低下、ユーロ安、当該国の経済停滞等が指摘されるが、域内全体で黒字額が大きく拡大している。また、主要な産油国を含む中東・北アフリカ地域が、2015年以降、二年連続で経常収支が赤字化している。赤字化の主な要因は、原油価格の大幅な下落が原因と考えられるが、石油産業以外の産業の乏しい中東地域においてこの赤字が恒常化した場合、金融収支の動向等によって、経済が不安定化するリスクに注意が必要である。
20 IMF「2016 EXTERNAL SECTOR REPORT」
(2)主要国・地域の経常収支構造とその変化
主要国の経常収支の変化を見ていく。
まず、米国では2000年代初めにかけて、貿易赤字額の拡大により年々経常収支の赤字額を拡大させていた。しかし2007年以降、急激にサービス収支、第一次所得収支の黒字額が拡大し、経常収支赤字額の拡大に歯止めをかけた。サブプライムローン問題、世界経済危機等の経済危機の影響から、2007年、2009年と一時的に貿易収支の赤字額が縮小したものの、サービス収支、第一次所得収支の黒字額が更に拡大し、経常収支赤字額の拡大を抑制している(第Ⅰ-1-3-2-2図、第Ⅰ-1-3-2-3図)。
第Ⅰ-1-3-2-2図 経常収支の項目別推移(米国)
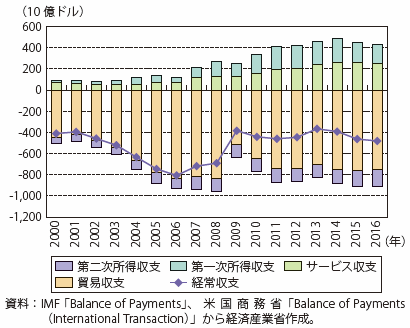
第Ⅰ-1-3-2-3図 第一次所得収支の主要項目別推移(米国)
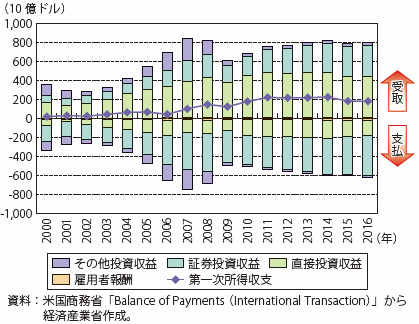
サービス収支では、特に、旅行(教育を含む全目的)、知的財産権等使用料、金融サービス収支が黒字額拡大を牽引し、第一次所得収支では直接投資収益内の再投資収益、証券投資収益内の配当金受取が黒字額を拡大させている(第Ⅰ-1-3-2-4図)。
第Ⅰ-1-3-2-4図 サービス収支の項目別推移(米国)
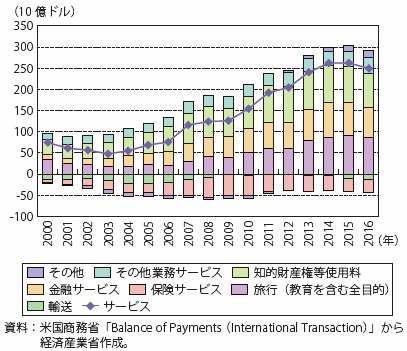
次にEUの経常収支の推移を見ていく。EU域内の主要国・地域別に経常収支を分解すると、ドイツの経常黒字額が2,934億ドル、英国の経常赤字額が1,145億ドルと特に額が大きい。EU全体の経常収支額に対する割合でも、ドイツの経常黒字額は75.5%、英国の経常赤字額は29.4%を占めており、EU全体の経常収支への影響力が強いことがわかる。そこで、本項ではドイツと英国の経常収支に関して概観していく(第Ⅰ- 1-3-2-5図)。
第Ⅰ-1-3-2-5図 EU域内の主要国別経常収支額(2016年)
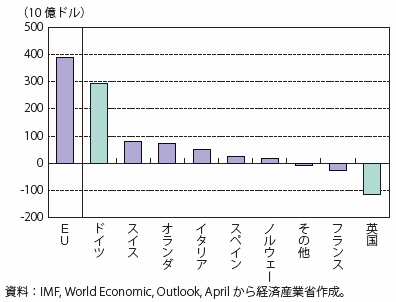
ドイツの経常収支を見ると、2016年のドイツの経常収支は前年比+14億ユーロ21で2,614億ユーロの黒字となり3年連続で黒字額が拡大した。黒字額拡大の主な要因は、貿易収支が2,717億ユーロと同+105億ユーロ拡大したことである。
長期的な推移を見ると、ドイツにおける経常収支の構造変化は経常収支が黒字転化した2002年と第一次所得収支が黒字転化した2004年に起こったと考えられる。2002年は貿易収支の黒字額が大きく拡大したことで、経常収支を黒字転化させた。また2004年には直接投資収益の黒字転化により、第一次所得収支全体が黒字転化し、さらに経常収支を拡大させた。その後は2008年以降、世界経済危機の影響から貿易収支が縮小し一時的に経常収支の黒字額が縮小したものの、2011年以降、更に貿易収支の黒字額は拡大し経常収支を押し上げている。ドイツの経常収支構造は、直近約20年間で経常収支全体、または第一次所得収支が一時的に赤字推移することはあったが、長期的に、貿易収支に加え、第一次所得収支により稼ぐ構造となっている(第Ⅰ-1-3-2-6図)。
第Ⅰ-1-3-2-6図 経常収支の項目別推移(ドイツ)
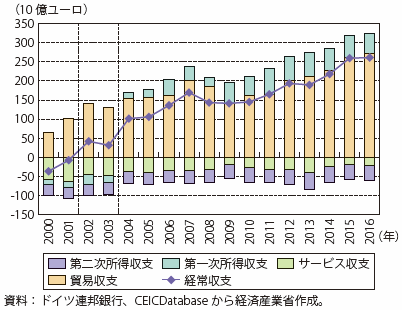
21 各国別で経常収支を概観する際は、為替変動の影響を排除するため現地通貨にて記載した。
次に、英国の経常収支を概観していく。2016年の経常収支は845億ポンドで前年比▲43億ポンドと2年ぶりに赤字額が拡大した。赤字額拡大の主な要因は、1,341億ポンドで同▲143億ポンドと拡大した貿易収支赤字である。なお、同赤字額の拡大も2年ぶりである。
英国の経常収支は米国と同じく恒常的に大幅な貿易赤字を抱えている一方で、サービス収支の黒字額が拡大を続けており、貿易による赤字額を補填する形となっている。サービス収支と第一次所得収支は2000年代初頭から急激に黒字額の拡大を始め、サービス収支では英国の主要産業の一つである金融とその他業務サービスが、第一次所得収支では直接投資収益が黒字額拡大の牽引役となった(第Ⅰ-1-3-2-7図、第Ⅰ-1-3-2-8図)。
第Ⅰ-1-3-2-7図 経常収支の項目別推移(英国)
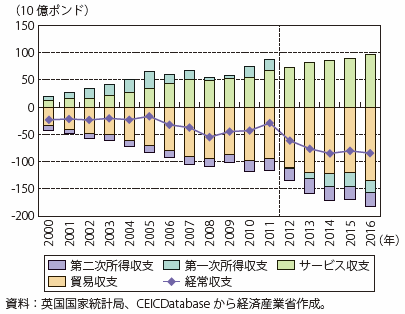
第Ⅰ-1-3-2-8図 サービス収支の項目別推移(英国)
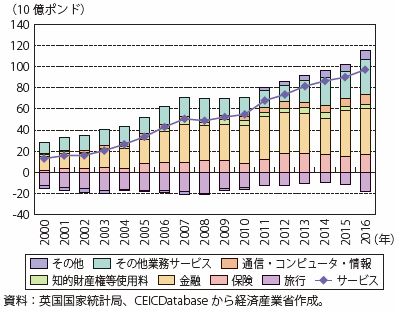
前述した世界経済危機の始期である2008年に、第一次所得収支内の直接投資収益の黒字額縮小から第一次所得収支が縮小。その後一時的に回復を見せたものの、2011年をピークに直接投資収益の受取は急激に下落し、2009年以降の証券投資収益の赤字額拡大も加わったことで、2012年より第一次所得収支は赤字転化した(第Ⅰ-1-3-2-9図)。さらに直接投資収益を業種別に分解すると、主要産業である「金融・保険」からの収益割合が高いことがわかる。もともと縮小傾向であった金融産業への対内直接投資が減少した結果、受取が減少し第一次所得収支の赤字転化へ繋がった可能性がある。英国では2016年6月23日にEU離脱国民投票が行なわれ、英国のEU離脱、いわゆるBrexitが決定されたところであるが、2011年には既にBrexitに対する懸念が囁かれていた。このことから、Brexitによる英国の金融ハブ機能縮小に対する懸念も投資の減少の要因であったとの指摘もある(第Ⅰ-1-3-2-10図、第Ⅰ-1-3-2-11図、第Ⅰ-1-3-2-12図)。
第Ⅰ-1-3-2-9図 第一次所得収支の項目別推移(英国)
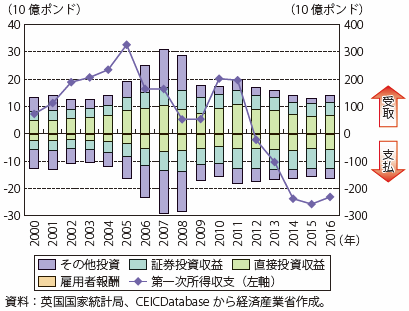
第Ⅰ-1-3-2-10図 金融セクターからの直接投資収益の主要国別推移
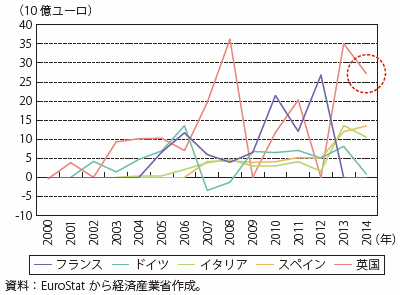
第Ⅰ-1-3-2-11図 対外直接投資収益の投資業種別割合(英国、2014年)
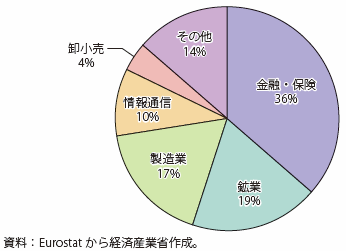
第Ⅰ-1-3-2-12図 金融セクターの対GDP比の推移(主要国別)
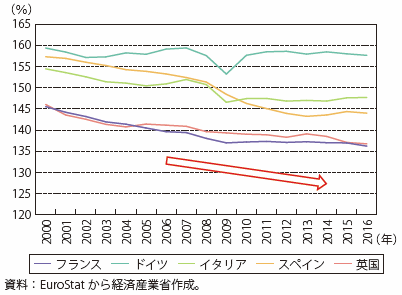
次に中国の経常収支の構造に関して俯瞰していく。
世界第2位の経済大国である中国の経常収支を見ると、2016年は1,964億ドルの黒字であり、同▲1,078億ドルで黒字額が縮小した。黒字額縮小の主な要因は、貿易収支の黒字額が同▲821億ドルと縮小したことに加え、サービス収支の赤字額が同▲258億ドルと拡大したことである。
足元では多少縮小したが、中国の経常収支黒字を牽引しているものは貿易収支であり、直近の約20年の間、モノで稼ぐ構造に変化はない。一方、2009年以降、サービス収支の赤字額が急速に拡大しており経常収支黒字額の拡大のペースが緩やかになっている(第Ⅰ-1-3-2-13図)。
第Ⅰ-1-3-2-13図 経常収支の項目別推移(中国)
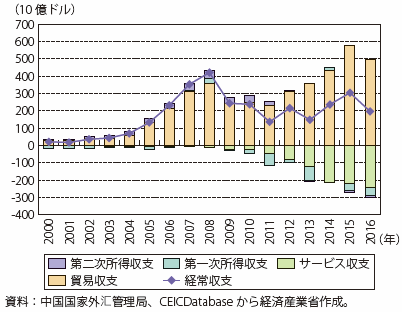
(3)国際収支発展段階説からみる経常収支の推移
前項まで、主要国の経常収支構造を概観してきた。本項では、主要国の収支構造を経験的な経常収支の段階変遷に基づき比較していく。
国際収支発展段階説とは、各国の経常収支構造を、①債権国(第一次所得収支がプラス)か債務国(第一次所得収支がマイナス)か、②資本輸入国(金融収支がプラス)か資本輸出国(金融収支がマイナス)か、という2つの基準を主に用い、経常収支の推移段階によって6段階に分けたものである(第Ⅰ-1-3-2-14表)。
第Ⅰ-1-3-2-14表 国際収支発展段階説
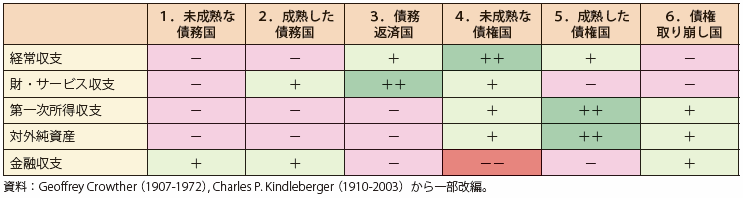
この仮説に前項で概観した国々をあてはめると、米国が「6.債権取り崩し国」、我が国とドイツが「4.未成熟な債権国」、中国が「3.債務返済国」、英国が「1.未成熟な債務国」となる。英国に関しては、現在の第一次所得収支の赤字推移が一時的なものであるとするならば、米国と同じく「6.債権取り崩し国」に該当する。すると先進国であれば、経常収支の推移段階は基本的に進んだ段階に位置していることがわかる(第Ⅰ-1-3-2-15表)。
第Ⅰ-1-3-2-15表 国際収支発展段階説による各国の分布
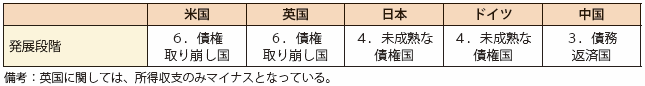
この仮説によれば、我が国は今後、①人口の高齢化と賃金の上昇から国の競争力が低下し、結果として貿易収支が赤字転化するが、②第一次所得収支の大幅な黒字を背景に、経常収支は黒字を保つ、という経緯を辿り、「5.成熟した債権国」に移行していく。我が国は長期間「4.未成熟な債権国」に位置しているが、1990年代と比較すると実際に貿易収支は大幅に縮小している。一方で、第一次所得収支は増加しており、「5.成熟した債権国」の経常収支の稼ぎ方に近づいている傾向がある(第Ⅰ-1-3-2-16図)。
第Ⅰ-1-3-2-16図 経常収支平均額の項目別推移(日本)
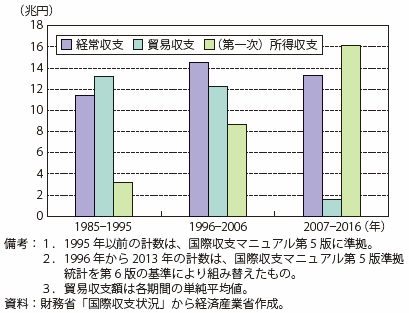
一方で、国際収支発展段階説は米国の経常収支等の推移に則り、経験則的に唱えられた仮説であるため、必ずしもこの経路に従って全ての国・地域が発展していくわけではない。したがって、我が国は我が国に適合した方法によってインクルーシブな成長を達成していくべきである。
(4)財・サービス収支と経済成長率の関係
ここまで、主要国別に経常収支の推移を概観した。本項では主要国の経済成長率が経常収支、とりわけ財・サービス貿易収支とどのような関係性を持つかについて考察していく。
①収支と経済成長率の関係
まず、財・サービス収支名目GDP比と名目GDP成長率の関係性を見ていく。第Ⅰ-1-3-2-17表は、名目GDP成長率を三段階に分け、2015年時点で財・サービス貿易収支の高赤字から高黒字まで4つに分けてクロスさせ、12分類とした。名目GDP成長率が高いか、財・サービス収支の名目GDP比が高いかに関わらず、それぞれの要素をもった国が各カテゴリーに分散していることがわかる。例えば、成長率が8%以上である高成長国を比較しても、名目GDP比5.3%の財・サービス貿易赤字を抱えているインドがあれば、名目GDP比2.8%の財・サービス貿易黒字を持つ中国のような国も存在する。この点から、大幅な財・サービス貿易赤字額を計上している国が、必ずしも低成長に陥るとは限らないことがわかる(第Ⅰ-1-3-2-17図)。
第Ⅰ-1-3-2-17表 主要国における名目GDP成長率と財・サービス貿易収支額の関係(2010-2015)
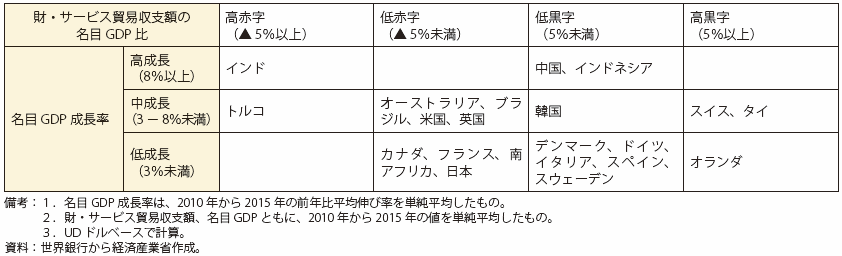
また、先進国で見ればイタリアのように財・サービス貿易収支黒字国であっても低成長となっている国が存在する一方で、米国、英国のように財・サービス貿易収支赤字国であっても中成長となっている国が存在する。以上のことから、財・サービス収支が黒字か赤字かと経済成長率の伸びは関連性が薄いことがわかる。
加えて、財・サービス貿易収支の名目GDP比と名目GDP成長率を各国ごとにプロットした散布図からも、財・サービス貿易収支額と名目GDP成長率との相関性は低いと考えられる。つまり、財・サービス貿易収支の赤字額が減少すれば、経済状態が改善するという訳ではない。経済理論においても、財・サービス貿易収支額はGDP成長率とは関係は弱いとされており、実際の数字からも見て取れる(第Ⅰ-1-3-2-18図)。
第Ⅰ-1-3-2-18図 財・サービス貿易収支名目GDP比と名目GDP成長率の各国分布
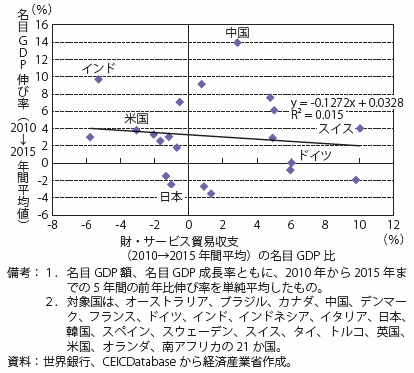
②貿易額の変化と経済成長率の関係
次に、収支額ではなく、財・サービス貿易額22と名目GDP成長率の相関性を見る。第Ⅰ-1-3-2-19図は財・サービス貿易額増加分の名目GDP比と名目GDP成長率を各国ごとにプロットしたものである。我が国では2011年に発生した東日本大震災以降、輸出額、輸入額ともに縮小したことで貿易額増分の名目GDP比は▲1.7%となっており、加えて名目GDP成長率も▲2.5%とマイナスになっている。前述のとおり名目GDP成長率の高い中国やインドを見てみると、貿易額増分の名目GDP比はそれぞれ+13.5%、+6.6%とプラスの値を示していることがわかる。その他の国の分布を見ても、財・サービス貿易額増分の名目GDP比が高いほど名目GDP成長率も高い傾向が見て取れ、経済成長率との関係では、収支額より貿易額の増加が比較的高い相関性を持つと考えられる(第Ⅰ-1-3-2-19図)。
第Ⅰ-1-3-2-19図 財・サービス貿易増加額名目GDP比と名目GDP成長率の各国分布
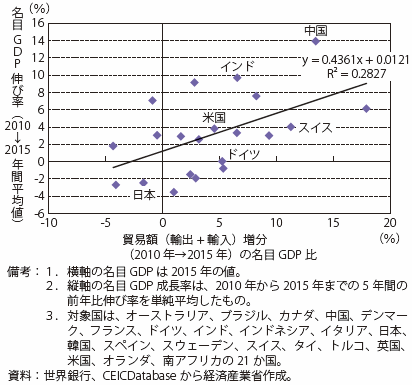
つまり、輸出と輸入の両方を拡大させることが、経済の活性化に寄与するという関係が見て取れる。
22 財・サービス輸出額と財・サービス輸入額を足したもの。
