

- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2017

- 白書2017(HTML版)

- 第1部 第2章 第1節 米国
第2章 欧米経済動向
第1節 米国
1.マクロ経済動向
米国は、世界経済危機による景気後退を経た後、7年以上にわたり景気回復を続けている。以下、2016年~2017年足下までの米国経済の動向につき、主要経済指標をもとに概観する。
(1)GDP
2016年の実質GDP成長率は前年比1.6%増と、2015年の2.6%増からはやや鈍化した。需要項目別寄与度を見ると、GDPの約7割を占める個人消費は引き続き堅調に伸びたものの、設備投資が7年ぶりにマイナスに寄与したほか、在庫投資の落ち込みが目立った(第Ⅰ-2-1-1-1図)。
第Ⅰ-2-1-1-1図 米国の実質GDP成長率(前期比年率)
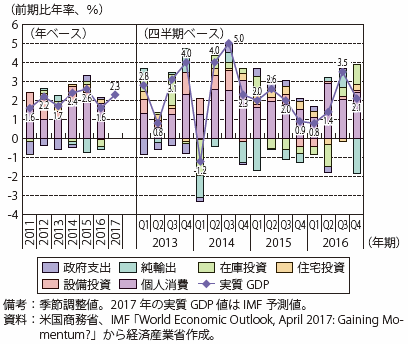
四半期ごとの推移を見ると、第1四半期は年率換算で前期比0.8%増と鈍化したものの、第2四半期以降は好調な個人消費を中心に持ち直している。第3四半期は大豆輸出の急増などを背景に前期比年率3.5%増となったが、第4四半期はその反動による輸出減少などにより2.1%増へ減速した。弱さが指摘されてきた設備投資は、第1四半期は前期比マイナスとなったものの、第2四半期以降は前期比0.9%~1.4%増で推移している。設備投資全体の5割弱を占める機器設備投資の低迷が続いていることが背景にあるが、3割強を占める知的財産投資は比較的堅調に拡大している。米国経済は緩やかな拡大基調にあり、IMFの見通しによれば、2017年のGDP成長率は前期比年率2.3%増まで回復することが見込まれている。
(2)個人消費
2016年の個人消費は、堅調な雇用などを背景に底堅く推移し、実質個人消費支出の伸びは年後半にかけて緩やかに上昇した(第Ⅰ-2-1-1-2図)。家計における個人消費の6割以上はサービスに関する消費が占めており、特に住居費・公益費(2016年:18%)、ヘルスケア(同17%)への支出が多いが、2016年の伸び率を見ると、娯楽用品(前年比10%増)、家具・住宅設備(同7%増)、ヘルスケア(同5%増)の伸びが高かった。
第Ⅰ-2-1-1-2図 米国の実質個人消費、実質可処分所得及び貯蓄率
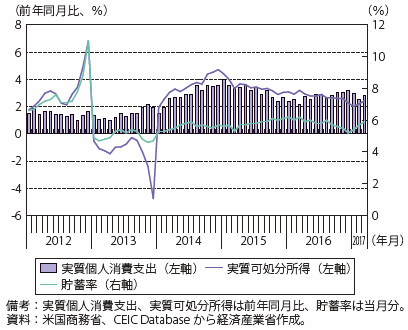
また、インフレ率として注目される個人消費支出(PCE)価格指数は、エネルギー価格及び輸入価格の下落による影響などから2015年は低迷したが、2016年は1月に前年比+1.1%まで上昇した後、年後半に再び急上昇し、2017年2月には連邦準備制度理事会(以下、FRBという)のインフレ目標23を上回る前年比+2.1%まで回復した(第Ⅰ-2-1-1-3図)。トランプ新政権の経済政策への期待などから、消費者マインドは2016年秋以降改善基調にあるが、消費者物価の上昇による個人消費への影響など、今後の動向に注視が必要である。
第Ⅰ-2-1-1-3図 米国のPCE価格指数、コアPCE価格指数
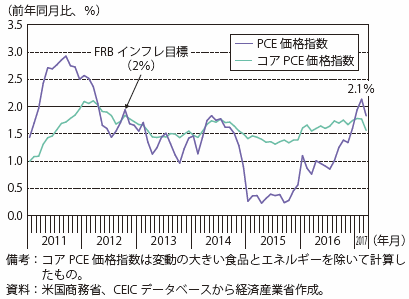
23 FRBは個人消費支出価格指数(PCEデフレータ)前年比+2%を長期のインフレの目標としている。
(3)雇用環境
月間の非農業部門就業者数の伸びは2016年5月に前月比4.3万人増と大きく落ち込んだものの、その後勢いを取り戻し、2016年の平均では1か月あたり18.7万人増のペースで増加した(第Ⅰ-2-1-1-4図)。2015年の平均(1か月あたり22.6万人増)に比べると若干減速しているが、FRBイエレン議長が、失業率を長期的に安定させることができる雇用増加の水準を1か月あたり7.5万人~12.5万人としている24ことを踏まえると、2016年はこれを十分に上回るペースで就業者数が増加したといえる。
第Ⅰ-2-1-1-4図 米国の非農業部門就業者数と失業率
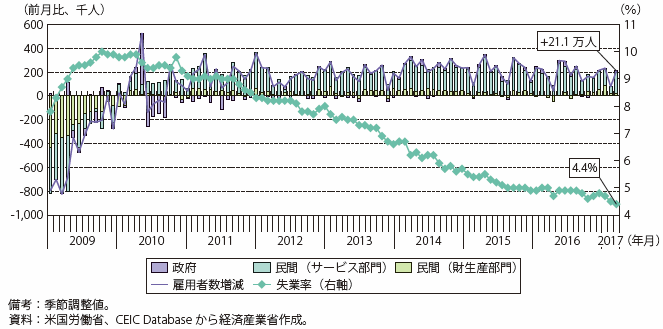
失業率は、今回の景気回復期に入ってから一貫して改善を続けており、2016年平均では4.9%、2017年4月は4.4%であった。これは、前回の景気拡大期の後半に並ぶ低水準であり、足下ではFRBによる長期見通し(4.7%)25を下回っている。一方、フルタイムで働く意思があるが経済的理由からやむなくパートタイム職に就いている人等を加えた広義の失業率(U-6)は2016年平均で9.6%となっており、前回の景気拡大期に比べると若干高止まりしているが、これについては、産業構造的要因、人口動態的要因などから正常な水準が世界経済危機前よりも上がっている可能性があるとの指摘もある26。
24 Janet L. Yellen “The Economic Outlook and the Conduct of monetary Policy”、2017年1月19日、FRB Webサイト
25 連邦公開市場委員会(FOMC)経済見通し(2017年3月)中央値による。
26 Golden(2016)によれば、非自発的パートタイム労働者が増加している要因として、パートタイム職をより多く活用しているサービス業の成長という産業構造的要因、自発的にパートタイム職に就く若年齢層の減少という人口動態的要因、フルタイム職に比べてパートタイム職は雇用コストが低いために雇用主側がパートタイム職をより求めるという制度的要因などが指摘されている。FRBイエレン議長は、広義の失業率(U-6)に関しても、世界経済危機後に起きた急激な悪化はほぼ解消したと述べている(Janet L. Yellen “The Economic Outlook and the Conduct of monetary Policy”、2017年1月19日、FRB Webサイト)。
(4)金融政策
FRBは世界経済危機を契機にフェデラルファンド金利(以下、FF金利という)の誘導目標を事実上のゼロ金利(0%~0.25%)まで引き下げていたが、2015年12月、FRBは7年間にわたったゼロ金利政策を解除し、FF金利誘導目標を0.25%~0.50%へ引き上げた。この時点で公表された連邦公開市場委員会(以下、FOMCという)参加者による見通しでは、2016年末までに4回の金利引上げが予想されていた27が、金利の引上げは見送りが続いた。これについては、年前半の雇用関連指標及びGDP成長率の落ち込み、エネルギー価格及び輸入価格の下落の影響などによるインフレの停滞、英国のEU離脱にかかる国民投票による金融市場の混乱のリスクなどが背景との見方がある。
2016年は、12月のFOMCにおいて1年ぶりにFF金利誘導目標を0.50%~0.75%へ引き上げることが決定された。労働市場は力強さを増し、経済活動は緩やかなペースで拡大しているとの認識が示された。また、インフレ率はいまだ目標の2%に達していないものの、エネルギーや輸入価格の過去の下落による一時的な影響が消え、労働市場が力強さを増せば、中期的に2%へ上昇していくと判断された。
2017年3月に行われたFOMCでは、FF金利誘導目標が0.75%~1.0%へと再び引き上げられた。併せて発表された経済見通しでは、2017年の実質GDP成長率は2.1%、失業率は4.5%、インフレ率及びコアインフレ率28は1.9%とされ、経済活動が引き続き緩やかに拡大する中で労働市場は力強さを増し、インフレ率は中期的に2%程度で安定するとの見通しが示された。雇用が堅調に伸び、インフレ率が2%の目標へ向かって回復する中で、現時点では2017年末までに更に2回の利上げが見込まれている(第Ⅰ-2-1-1-5図、第Ⅰ-2-1-1-6表)。
第Ⅰ-2-1-1-5図 FF金利の推移
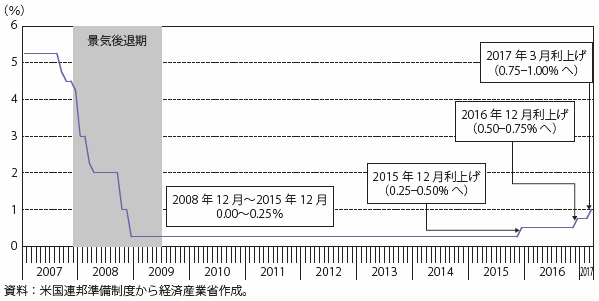
第Ⅰ-2-1-1-6表 FOMC参加者による米国経済見通し(2017年3月時点)
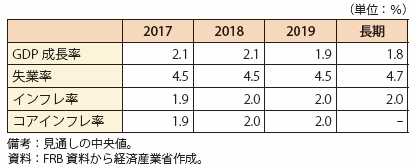
また、世界経済危機に対応するために実施された大規模な量的緩和政策29によって連邦準備制度は多額の国債や住宅ローン担保証券(MBS)等を保有しており(第Ⅰ-2-1-1-7図)、現在は償還期限を迎えた債権については再投資を行うことでバランスシートの規模を一定に保っているが、経済が回復を続ける中で、バランスシート縮小に向けた再投資政策の変更に関する議論が始められている。2017年3月に行われたFOMCにおいては、大半の参加者が再投資政策の変更は年後半に適切になる可能性が高いと判断した。バランスシート政策の変更の具体的な内容や時期については、経済状況等を踏まえ、今後議論が本格化していくと考えられる。
第Ⅰ-2-1-1-7図 FRBの資産構成
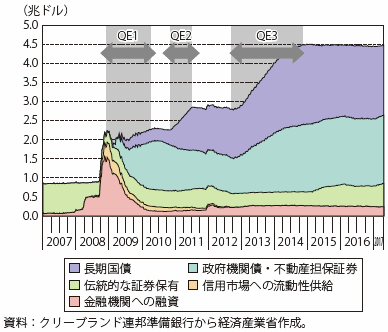
27 見通しの中央値による。1回あたり0.25%の引上げとした場合、年末までに4回の利上げが予想されていた。
28 食品、エネルギーを除いた個人消費支出(PCE)価格指数。
29 FRBが国債や証券などを買い入れ、市場に潤沢に資金を供給し、景気回復を誘導する政策。世界経済危機後の2008年12月~2010年3月(第1弾:QE1)、2010年11月~2011年6月(第2弾:QE2)、2012年9月~2014年10月(第3弾:QE3)の合計3回にわたって行われた。
(5)国際収支
米国の経常収支は貿易収支の赤字により長年赤字で推移しており、世界経済危機直前にはGDP比6%弱まで赤字幅が拡大した。世界経済危機後は赤字が大幅に縮小し、09年以降はおおむね横ばいで推移している。2016年の経常収支は4,812億ドルの赤字となり、前年から赤字幅が3.9%拡大した。名目GDP比では2.6%の赤字と前年から横ばいだった(第Ⅰ-2-1-1-8図)。
第Ⅰ-2-1-1-8図 米国の経常収支
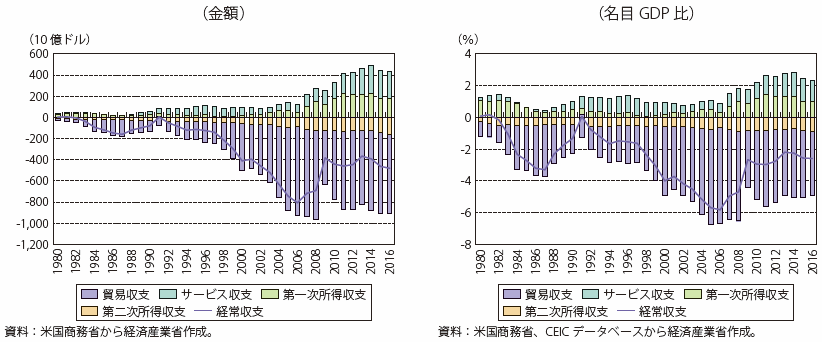
①貿易・サービス収支
貿易収支、サービス収支を主要分野別に見てみると、貿易収支はほぼ全ての分野で赤字が続いている。ただし、シェールオイルの開発により原油生産量が増加したことなどを背景に、石油が含まれる「工業資材・原材料」の赤字額は近年減少している。2016年は輸出が1兆4,597億ドル、輸入が2兆2,096億ドル、貿易赤字は7,499億ドルとなった。前年より輸出が506億ドル、輸入が633億ドルそれぞれ減少したことにより、前年に比べ赤字額が1.7%減少した(第Ⅰ-2-1-1-9図)。
第Ⅰ-2-1-1-9図 米国の貿易収支
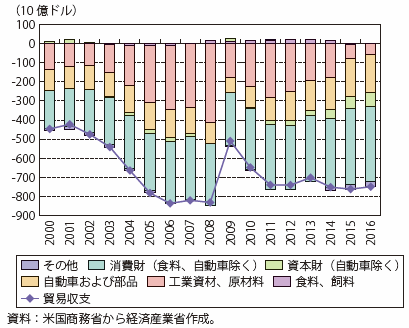
サービス収支は「保険」、「輸送」、「通信・コンピュータ・情報」分野を除いて黒字で推移している。「知的財産権等使用料」、「金融」、「旅行」等の伸びにより、収支全体の黒字も拡大基調となっており、2006年から2016年の10年間でサービス収支の黒字は3倍以上拡大した。2016年は輸出が7,524億ドル、輸入が5,030億ドル、黒字額は2,494億ドルとなった。前年に比べ輸出が16億ドル増加した一方で、輸入も144億ドル増加したため、黒字額は4.9%減少した(第Ⅰ-2-1-1-10図)。
第Ⅰ-2-1-1-10図 米国のサービス収支
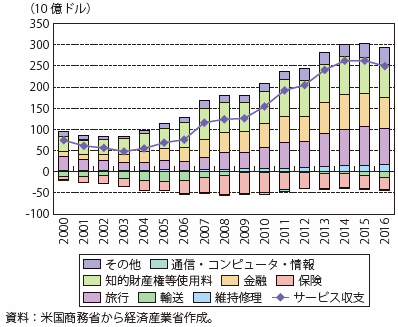
②第一次所得収支
第一次所得収支は、直接投資収益の収支黒字額の増加及び証券投資収益の収支赤字額の減少を受け、2000年代前半に比べて黒字額が拡大している。特に直接投資収益の収支黒字額の増加が黒字幅の拡大に大きく寄与しており、対外直接投資の活発化、海外子会社の高い収益力等が背景にあると考えられる。2016年の第一次所得収支は前年からほぼ横ばいの1,806億ドル(前年比1%減)となった(第Ⅰ-2-1-1-11図)。対外直接投資残高は2000年から2015年の間に約4倍に増加しており、特に欧州地域への投資の増加が全体を牽引している。アフリカ地域への投資は、金額は小さいものの増加率は最も高かった。(第Ⅰ-2-1-1-12図)。
第Ⅰ-2-1-1-11図 米国の第一次所得収支
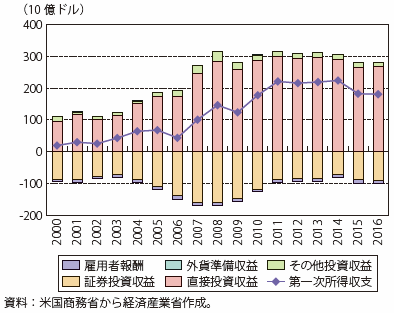
第Ⅰ-2-1-1-12図 米国の対外直接投資残高
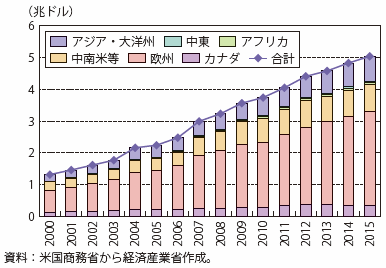
③金融収支
米国の金融収支は長年負債超過で推移しており、海外から米国証券市場への資金流入が多い。2016年については4,284億ドルの負債超過となり、前年から大幅に負債超過額が増加した(第Ⅰ-2-1-1-13図)。証券投資のうち債権については2009年を除き負債超過で推移しており、中でも米国債が含まれる長期債が証券投資における資金流入額の大部分を占めている。国債利回りは2016年半ばを底に、秋以降上昇傾向にあり、比較的高い利回りを維持する米国債への投資は今後も持続的に行われていくと予想される。
第Ⅰ-2-1-1-13図 米国の金融収支
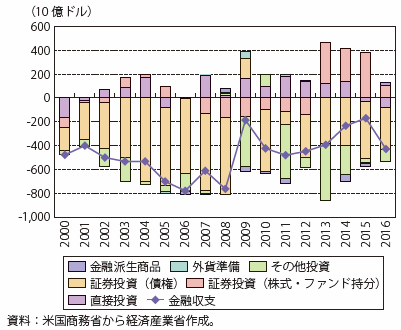
(6)地域経済
米国経済は全体的には緩やかな拡大基調にあるものの、地域及び州によって多少のばらつきがある。
2016年の州別実質GDP成長率30を見ると、マイナスとなったのは50州のうち5州(アラスカ州、ニューメキシコ州、ノースダコタ州、オクラホマ州、ワイオミング州)であった。4つの地域別(北東部、中西部、南部、西部)に見ると、北東部は全体的に堅調に成長し、中西部では多くの州が相対的に高い伸びを示したが、西部は成長率が高い州とマイナスにとどまる州が混在する結果となった(第Ⅰ-2-1-1-14表)。
第Ⅰ-2-1-1-14表 米国の州別実質GDP成長率(2015~2016年)
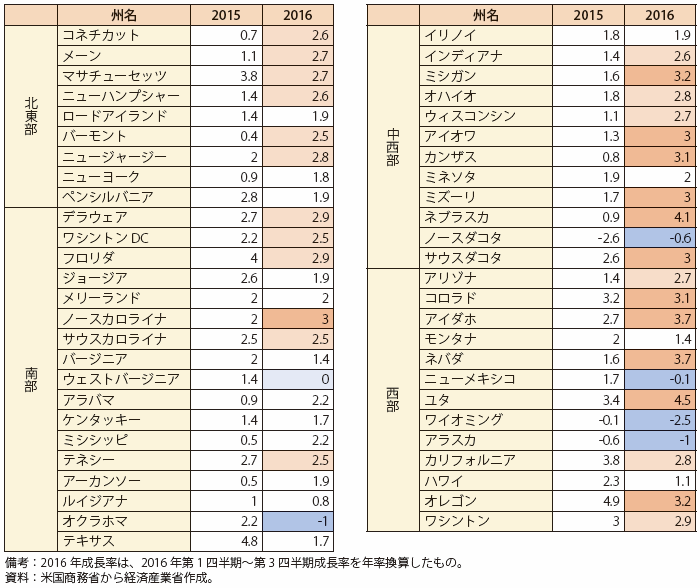
次に州別の個人所得31を見てみると、北東部は従来所得の高い地域だが、2016年においても1人あたり所得の上位1位~5位の州は北東部に位置している。他方、前年からの州別個人所得の増加率については、西部及び南部大西洋側の州が上位となった。最も増加率が高かったのは西部に位置するネバダ州で、前年比5.9%の伸びを示したほか、2位のユタ州では5.6%、3位のフロリダ州では4.9%の増加が見られた。2016年は大半の州で所得が増加したが、50州のうち3州(アラスカ州、ノースダコタ州、ワイオミング州)では所得が減少した(第Ⅰ-2-1-1-15図)。
第Ⅰ-2-1-1-15図 米国の州別個人所得
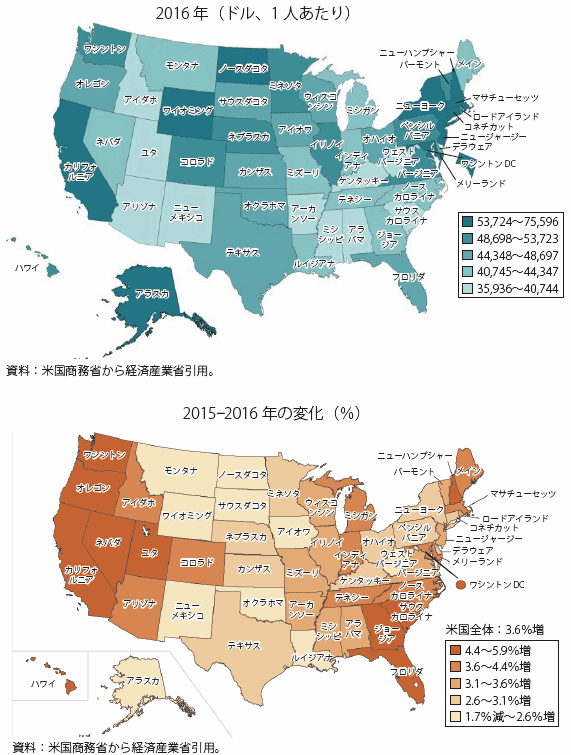
失業率については米国全体でおおむね改善傾向にあり、2016年は41州で低下又は横ばいとなったが、9州では上昇が見られた。地域別では中西部地域が最も失業率が低く(4.7%)、西部地域が最も高かった(5.1%)が、前年からの低下幅は反対に西部地域が最も大きく(0.6%ポイント減)、中西部地域が最も小さかった(0.1%ポイント減)。
州別では、北東部のニューハンプシャー州及び中西部のサウスダコタ州が2.8%と最も低く、西部のニューメキシコ州が6.7%と最も高かった。前年比では、北東部マサチューセッツ州及び南部サウスカロライナ州で1.2%ポイント減と大きく低下した一方で、西部ワイオミング州では1.1%ポイント上昇した(第Ⅰ-2-1-1-16図)。
第Ⅰ-2-1-1-16図 米国の州別失業率
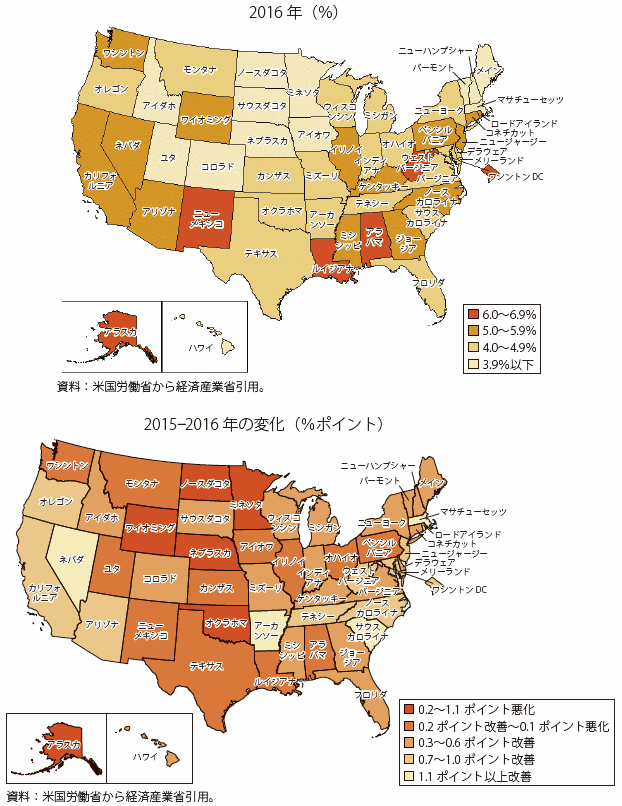
2016年、米国内で実質GDP成長率が最も低く、1人あたり所得及び失業率が最も減少・悪化したワイオミング州には石炭をはじめとする天然資源が豊富に存在しており、産業別GDP(2015年、民間部門)の30%を鉱業が占めている。同州における同産業の成長率は近年の資源価格の変動等の影響により2015年第1四半期以降マイナスで推移していることから、所得及び雇用に影響が見られた可能性が考えられる。また、アラスカ州及びノースダコタ州でもGDP成長率がマイナスとなり、所得の低下及び失業率の悪化が見られたが、これらの州も鉱業が主要産業となっているため、資源価格動向が州経済へ影響を及ぼした要因の一つとして示唆される32。
30 2016年第1四半期~第3四半期の成長率を年率換算したもの。
31 純収入、財産所得及び社会保障・年金等の受取の合計。2016年の値は速報値。
32 2015年の産業別実質GDPにおいては、アラスカ州では31%、ノースダコタ州では17%を鉱業が占めており、それぞれ民間部門で最大となっている。
2.大統領選挙概要及び背景
2016年11月に行われた大統領選挙は、共和党ドナルド・トランプ氏が民主党ヒラリー・クリントン氏を破り、第45代米国大統領に選出された。事前の支持率予想ではクリントン氏の勝利を予想する声も大きかったが、接戦州の多くを制したトランプ氏が大統領への就任を決めた。また、同日行われた連邦議会選挙においては、上下両院において共和党が過半数を占める議席を獲得した。
トランプ氏は「米国を再び偉大に」とのスローガンを掲げ、不法移民への対応厳格化、税制改革、通商政策の見直し、医療保険制度改革等の公約を掲げて大統領選を戦った。通商政策の見直しには環太平洋パートナーシップ(以下、TPPという)協定からの離脱や北米自由貿易協定(以下、NAFTAという)の見直しも含まれており、大統領就任直後にこれらを実行に移すための指示が通商代表部に出されるなどの動きが見られた33。
大統領選挙後に行われた出口調査34では、全体の半数以上(52%)の人々が米国の最重要課題として「経済」を挙げ、その数は2位の「テロリズム」(18%)、3位の「移民」(13%)、同3位の「外交」(13%)と回答した人々を大きく上回った。トランプ氏の支持者に限って見ても最多回答は「経済」となっていることからも、支持者を問わず、米国民全体で経済が最重要課題であると捉えられていたことが分かる(第Ⅰ-2-1-2-1図)。
第Ⅰ-2-1-2-1図 出口調査結果(米国の最重要課題)
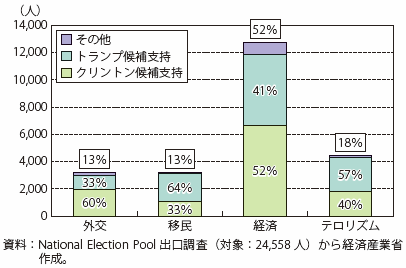
一方、国際的な貿易の影響については「米国から雇用を奪う」と考える人が最も多く(42%)、「米国の雇用を生み出す」と回答した人はそれを下回った(39%)。本質問については支持者による差が現れており、クリントン氏支持者の多くがグローバル貿易を肯定的に捉えていたのに対し、トランプ氏支持者の多くがグローバル貿易についてネガティブなイメージを持っていたことが分かる。なお、貿易が「雇用に影響しない」と回答した投票者は全体の1割程度だった(第Ⅰ-2-1-2-2図)35。
第Ⅰ-2-1-2-2図 出口調査結果(国際的な貿易の影響)
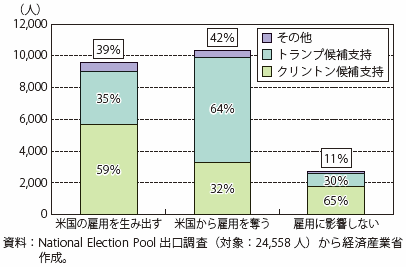
33 2017年1月23日、TPP協定からの離脱と二国間交渉の追求をUSTRに指示する大統領覚書に署名した。
34 National Election Pool(ABCニュース、AP通信、CBSニュース、CNN、Foxニュース、NBCニュースから成る)による。対象は24558名。(CNN “Exit polls 2016”、2016年11月23日、CNN webサイト)
35 Gallupが1,035名の成人を対象に2017年2月に行った調査では、72%が貿易は経済成長のための好機会だと回答し、23%が貿易は経済への脅威だと回答。また、経済的好機だと回答した人は民主党員の80%、共和党員の66%だった。(Gallup “In US, record-high 72% see foreign trade as opportunity”、2017年2月16日、Gallup Webサイト)
3.米国における格差の拡大と産業構造の変化
(1)所得格差の拡大
米国の2015年の実質家計所得(中央値)は前年比5.2%増となり、前回の景気後退以降の最高値を記録したが、過去最高の1999年及び景気後退直前の2007年の所得には届いていない(第Ⅰ-2-1-3-1図)。
第Ⅰ-2-1-3-1図 米国の実質家計所得(中央値)の推移
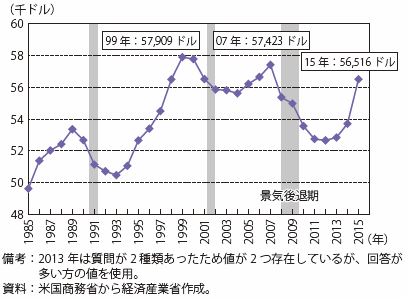
実質家計所得の伸び方を5つの階層別に見てみると、今回の景気回復局面(2010年~2015年)は、2014~2015年の急激な所得水準の上昇を受け、前回の景気回復局面(2002~2007年)に比べて全体的に増加率が高い。しかし、階層により増加率は大きく異なっており、最も所得が低い下位20%の階層(第1分位)の所得は4.2%、中間に当たる階層(第3分位)は6.3%、最も所得が高い上位20%の階層(第5分位)は9.9%の増加となり、高所得層ほど所得の伸び率が高いことが分かる(第Ⅰ-2-1-3-2図)。
第Ⅰ-2-1-3-2図 米国の所得階層別の実質家計所得の伸び
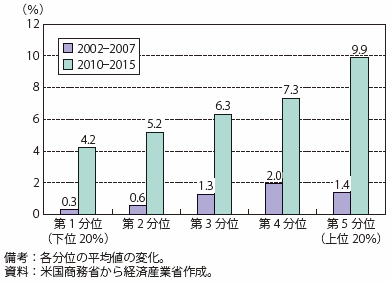
また、中間所得層36の割合が減少しているとの指摘もある。ピュー・リサーチ・センターの調査によれば、2015年、中間所得層に当たる成人の数は1億2080万人となった一方で、低所得層と高所得層を合わせた人数は1億2130万人となった37。これにより、1971年には成人の61%を占めていた中間所得層は、2015年には約50%まで減少したとされている。過去40年間以上、中間所得層の比率は徐々に縮小を続けているが、低所得層は25%から29%へ、高所得層は14%から21%へ拡大した(第Ⅰ-2-1-3-3図)。
第Ⅰ-2-1-3-3図 米国の中間所得層の割合
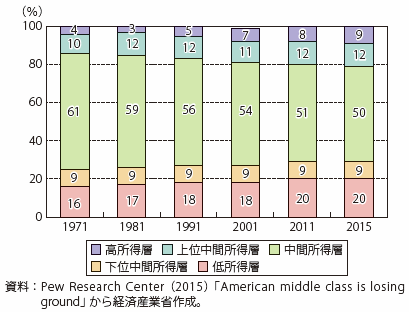
これらの結果、近年指摘されている低所得層と高所得層の二極化が一層進んでおり、国全体としては所得が伸びているものの、景気回復の実感に乏しい人々が一部に残されていることが考えられる。
36 ピュー・リサーチ・センターは、世帯規模別の年間世帯所得の中央値の3分の2から2倍の所得がある家庭を中間所得層と定義している。2014年は、3人家族の場合で約4万2000~約12万6000ドル、4人家族の場合で約4万8000ドル~14万5000ドルが中間所得層とされる。
37 Pew Research Center (2015)
(2)所得格差の背景
この所得格差の背景について、2016年版通商白書では、米国では職業間に大きな賃金格差があり、近年、賃金水準が中程度の職業従事者が減少している一方で、賃金水準が相対的に低い職業及び相対的に高い職業の従事者の数が増加しているという雇用構造の変化を指摘している38。職種別就業者数と賃金水準の最新のデータを見ても、生産工程従事者の賃金を事務従事者の賃金が上回ったことを除けば構造的な変化は見られず、最も賃金水準の高い専門的職業従事者と最も低いサービス職業従事者の数が更に増加しており、雇用構造は一層二極化したことが分かる(第Ⅰ-2-1-3-4図)。
第Ⅰ-2-1-3-4図 米国の職種別就業者数の変化と賃金水準
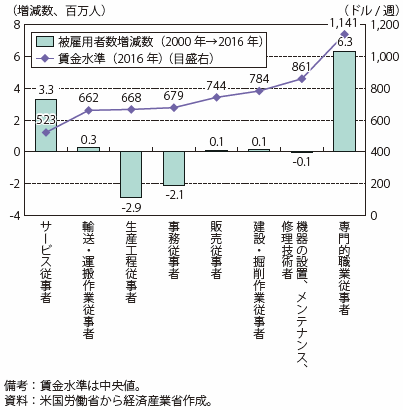
これに加え、主要業種別の就業者数の増減及び賃金水準を見てみると、米国では業種間でも大きな賃金の差が見られ、賃金水準が最も高い公益(1620ドル/週)と最も低い娯楽・ホスピタリティ(388ドル/週)の間には4倍以上の差が存在している。また、就業者数の伸びは低賃金業種に集中しており、専門・業務サービス業において就業者数が増加していることを除けば、高賃金かつ就業者数が増加している業種はない。公益、鉱業、情報といった最も高賃金の業種においては、過去20年以上就業者数の増加がほとんど見られない(第Ⅰ-2-1-3-5図)。
第Ⅰ-2-1-3-5図 米国の業種別就業者数の変化と賃金水準
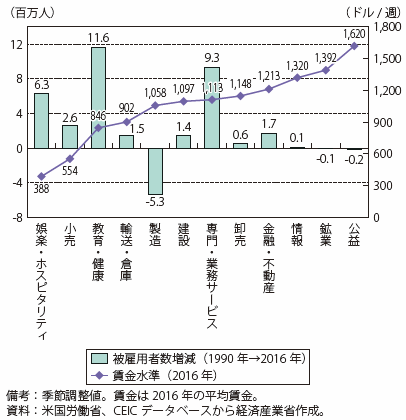
なお、例外的に賃金水準が高く、就業者数も増加している専門・業務サービスは、①専門・科学・技術サービス、②企業マネジメント、③管理・支援・廃棄物処理サービスの3つに分かれており、大半は企業向けサービスである39。そのうち、賃金水準を引き上げているのは専門・科学・技術サービス及び企業マネジメントであり、管理・支援・廃棄物処理サービスの平均賃金とは2倍程度の違いがある40。
次に、賃金の伸び率を見てみると、2006年から2016年の10年間において、賃金水準が高い公益、鉱業、情報、金融・不動産といった業種の賃金はそれぞれ35%前後増加しているのに対し、飲食業及び宿泊業を含む娯楽・ホスピタリティは26%、小売は16%と伸び率が低い。賃金水準が高い業種は賃金上昇も速い一方で、賃金水準の低い業種は伸び方も緩やかであるといえる(第Ⅰ-2-1-3-6図)。
第Ⅰ-2-1-3-6図 米国の業種別賃金水準・変化及び就業者数規模
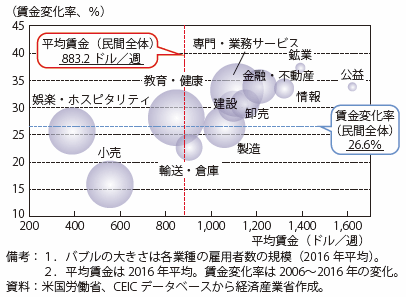
一方で、就業者数の規模については、賃金水準及びその伸びが比較的低い業種(娯楽・ホスピタリティ、小売、教育・健康サービスなど)で規模が大きく、賃金水準、伸びともに高い業種(公益、鉱業、情報など)は就業者数の規模が非常に小さいことも分かる。賃金水準が中位程度と考えられてきた製造業は、現在でもある程度の規模を保ってはいるものの、教育・健康サービス、専門・業務サービス等に比べるとその規模は小さく、米国の中間層を支える業種が変化してきていることがうかがわれる。以上から、高賃金業種ほど賃金水準の伸び率は高いが、雇用の増加幅は小さく、反対に低賃金業種は相対的に賃金水準の伸びが小さいが、雇用の吸収力は高いという所得及び雇用の二極化の動きが分かる。
38 経済産業省(2016)
39 就業者の割合は、専門・業務サービス就業者全体に対して専門・科学・技術サービスが44%、企業マネジメントが11%、管理・支援・廃棄物処理サービスが45%を占める(2016年)。
40 平均賃金(時間あたり、2017年3月)は、管理・支援・廃棄物処理サービスが約20ドル、企業マネジメントが約39ドル、専門・科学・技術サービスが40ドルである。
(3)雇用構造の変化
経済発展に伴って経済活動の重点が農林水産業(第一次産業)から製造業(第二次産業)、非製造業(サービス業、第三次産業)へと移る現象は「ペティ=クラークの法則」として知られている。米国においても、名目GDP及び雇用における財生産部門及び製造業のシェアは長年にわたり低下し続ける一方で、サービス部門のシェアは増加し続けるという産業構造の変化が見られ、現在では非農業部門就業者の約70%が民間のサービス業に従事している(第Ⅰ-2-1-3-7図)。これは過去の通商白書でも見てきたとおり、経済発展に伴い産業のサービス化が進展しているためと考えられる41。
第Ⅰ-2-1-3-7図 米国の製造業・サービス業のシェア
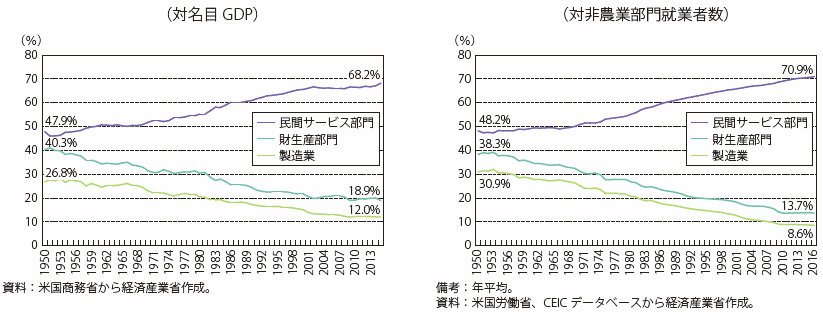
1990年以降の米国の業種別就業者数の推移を見ると、教育・健康サービス、専門・業務サービス及び娯楽・ホスピタリティの3業種の就業者数の伸びが他業種に比べて圧倒的に大きい。特に教育・健康サービスについては景気後退期にも大きな減少が見られず、増加トレンドを保ち続けている。他方、製造及び公益については長期的に緩やかな減少傾向にあり、足下では1990年の7~8割まで就業者数が減少している。また、資源・鉱業についてはシェールオイル・ガスの生産の本格化によって2000年代後半以降は増加が見られるものの、足下では1990年の水準よりも減少している(第Ⅰ-2-1-3-8図)。
第Ⅰ-2-1-3-8図 米国の業種別就業者数の推移(1990年以降)
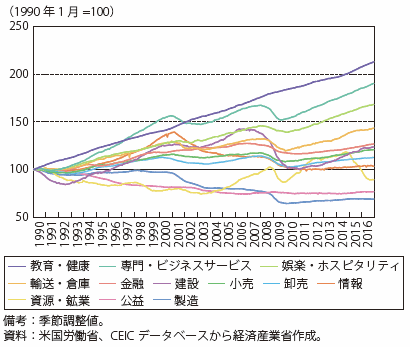
また、2008年以降に限って雇用の増減を見てみると、世界経済危機後の景気後退局面では教育・健康サービスを除く全ての業種において就業者数が減少しているが、その後の景気回復局面においてもその減少分を取り戻せていないのは建設業と製造業のみである。反対に雇用が大幅に伸びたのは、教育・健康サービス、専門・業務サービス、娯楽・ホスピタリティの3業種である。これらの産業の多くの職種は、業務を遂行する上で抽象的な要素が多く必要とされること、及び労働の提供とその消費が同時に同じ場所で行われる必要があることから、機械化やアウトソーシングが困難とされる「非定型業務」に分類される職業である42(第Ⅰ-2-1-3-9図)。
第Ⅰ-2-1-3-9図 米国の業種別就業者数の変化(2008年以降)
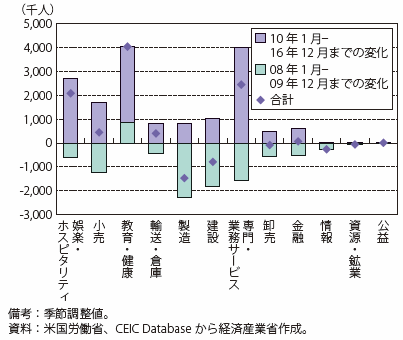
この結果、教育・健康サービス、専門・業務サービス、娯楽・ホスピタリティは全就業者数に占める割合が上昇しており、2016年の業種別雇用構成では、それぞれ16%、14%、11%の割合を占めるに至っている。製造業は1990年1月には就業者数全体の16%と民間部門で最大の雇用を生み出していたが、その後の景気後退期に減少した雇用が景気拡大期においても回復せず、減少を続けた結果、足下では全体の8%まで就業者数が減少している。なお、高賃金業種である公益、鉱業、情報が生み出す雇用は三業種合計で全体の3%弱と非常に少ない(第Ⅰ-2-1-3-10図)。
第Ⅰ-2-1-3-10図 米国の業種別就業者数の割合(2016年12月)
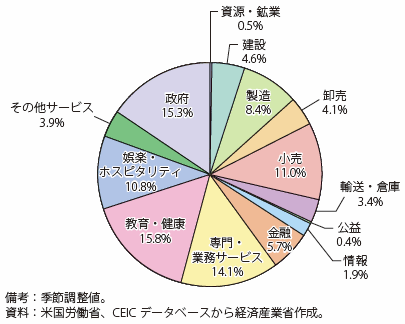
41 経済産業省(2016)
42 非定型業務とは、問題解決、説得、直感、想像力などが必要とされる高度な業務である「非定型・認知業務」と、状況適応性や視聴覚・言語能力、手先の器用さなどが要求される「非定型・手仕事業務」の二つで構成される。前者は医師・弁護士などといった専門的・技術的職業や、企業経営者などの管理的職業あるいは作家・芸術家と言った創造的職業などが該当し、後者には警備員、調理師やトラック運転手など主にサービス業や運輸業に従事する者が該当する(経済産業省(2016))。
(4)製造業の動き
製造業は業種別の所得水準が中位に位置し、就業者数が一定の規模を有することから中間所得層を支えてきた側面が強いと考えられる。中間所得層の変化を見るため、主要指標を概観する。
まず、製造業における就業者数の推移を見てみると、1990年から2016年の間に550万人ほど就業者数は減少し、非農業部門就業者数全体に占める割合は、前述のとおり、16%から8%へとほぼ半減している。しかし、就業者数は2010年を境に下げ止まりが見られ、今回の景気回復期においては、わずかではあるが雇用は回復傾向にある(第Ⅰ-2-1-3-11図)。雇用変化の内訳を見てみると、自動車を含む輸送機器での増加割合が大きく、自動車・関連部品では同期間に26万人ほど就業者が増加している(第Ⅰ-2-1-3-12表)。この結果、同分野での足下の就業者数は、2000年代前半の水準には及ばないものの、世界経済危機による急激な減少分はほぼ回復を果たしている。
第Ⅰ-2-1-3-11図 米国の製造業就業者数と割合
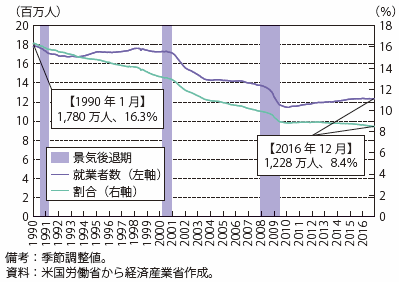
第Ⅰ-2-1-3-12表 米国の製造業における雇用変化(2010年~2016年)
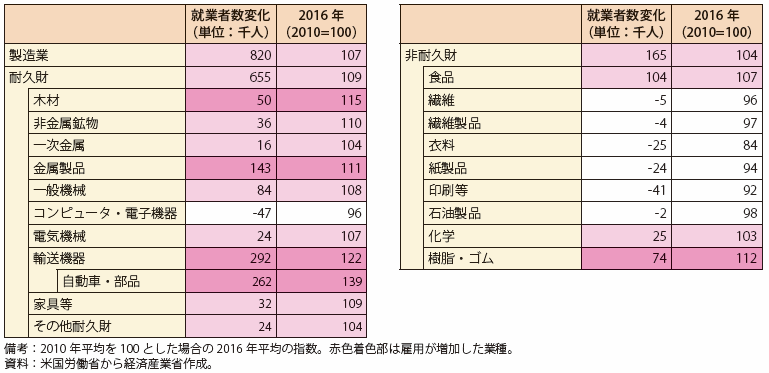
次に、雇用形態(フルタイム就労者・パートタイム就労者)別の割合を見ると、2016年、サービス産業のフルタイム就労者割合は金融業を除いて9割を下回っているが、製造業のフルタイム就労者割合は鉱業・資源(96%)に次ぐ高い水準(94%)となっており、製造業の平均賃金が比較的高い要因の一つとなっていると考えられる(第Ⅰ-2-1-3-13図)。
第Ⅰ-2-1-3-13図 米国の業種別フルタイム就労者・パートタイム就労者の割合(2016年)
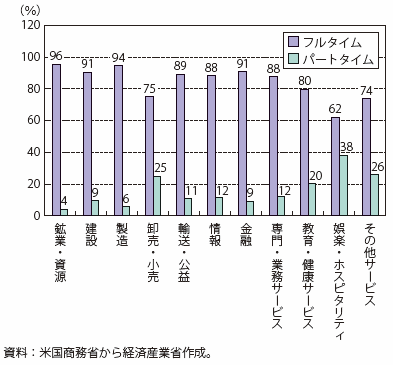
製造業が生み出す付加価値額については、景気後退期に一時的に落ち込むことはあるものの、過去20年間ほど増加を続けており、2016年時点でGDP全体の12%を占める1兆9092億ドルとなっている。これは民間部門では不動産・リース、専門・業務サービスの13%に次ぐ規模で、金融・保険業(6%)よりも大きい。ただし、実質GDP全体に占める割合はわずかだが低下傾向にあり、1997年から2016年の間に1%減少している(第Ⅰ-2-1-3-14図)。製造業の雇用は減少しつつも付加価値額は増加を続けていることから、米国の製造業が生産性を高め続けていることが分かるが、そのシェアは低下傾向にあり、製造業を除く米国経済の成長ペースはより速いものであるといえる。
第Ⅰ-2-1-3-14図 米国の製造業の実質GDPと割合
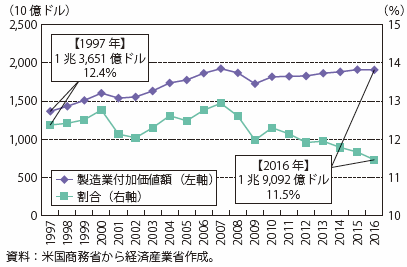
続いて、製造業に関する地域の動向を見ていく43。伝統的に製造業が集積している五大湖地域では、従来製造業の就業者が多かったが、2000年代の景気後退期にはその大幅な減少が見られ、その後の景気回復局面においてもその減少分を回復できていない(第Ⅰ-2-1-3-15図)。この結果、2000年には製造業就業者が非農業部門就業者数の16%を占めていたが、2015年には教育・健康サービス、専門・業務サービスがそれぞれ14%で首位となり、製造業は11%まで減少している44。
第Ⅰ-2-1-3-15図 五大湖地域の業種別就業者数の変化
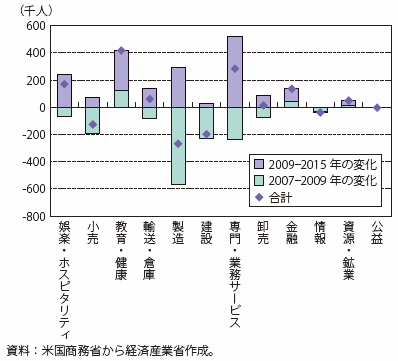
また、同地域の2000年以降の製造業による付加価値額の推移を見ると、景気後退期に落ち込みは見られるものの、緩やかな増加傾向にあるが、実質GDP全体に占める割合は低下が見られる(第Ⅰ-2-1-3-16図)。このように、実質GDPに占める製造業付加価値額の割合が8地域のうち最も高い五大湖地域にあっても、雇用及び付加価値額については全国と同様の動きが見られる。
第Ⅰ-2-1-3-16図 五大湖地域の製造業の実質GDPと割合
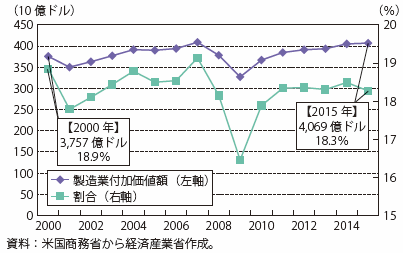
43 ここでは、商務省経済分析局による地域分類(50州とワシントンDCをニューイングランド地域、中東地域、五大湖地域、平原地域、南東地域、南西地域、ロッキー山脈地域、最西地域の8つの地域に分類)を用いている。五大湖地域にはイリノイ州、インディアナ州、ミシガン州、オハイオ州、ウィスコンシン州が含まれる。
44 製造業就業者の割合(2015年:11%)は8地域のうち五大湖地域が最も高いが、2000年~2015年の減少幅(4.8%ポイント減)も五大湖地域が最大となっている。
(5)産業別雇用見通し
次に、米国における雇用の見通しを見ていきたい。
まず、2017年1月の業種別求人数を見てみると、教育・健康サービス、専門・業務サービスといった業種は現在でも雇用の規模が大きいが、未充足の求人数も多い産業であることが分かる。また、求職者に対する求人数の割合の代用として業種別失業者数に対する割合を見てみると45、上記2業種に加えて金融業も高い水準となっている。一般に異業種への転職は同業種内での転職に比べて困難であるが、金融業は比較的高い教育水準及びスキルが求められるため、異業種からの転職者が限定され、失業者に対する求人の割合が高くなっていることが一因として考えられる(第Ⅰ-2-1-3-17図)。
第Ⅰ-2-1-3-17図 米国の業種別求人数及び失業者数に対する割合(2017年1月)
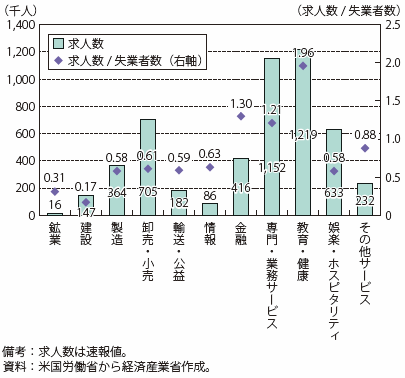
続いて、米国労働省から出されている2024年までの雇用見通し46を見ていく。本見通しによれば、2014年から2024年までの10年間では、「教育・健康サービス」の内訳である「ヘルスケア・社会扶助」で業種別で最多の約380万人の雇用増が見込まれており、2024年には「州・地方政府」及び「専門・業務サービス」を抜いて就業者全体の13.6%を占めると予測されている。ヘルスケア産業は、健康の維持増進に不可欠なことから景気に左右されにくい分野であり、徐々に人口の高齢化が進む米国において今後も拡大していくことが予想される。次に増加幅が大きいのが「専門・業務サービス」で同期間に約189万人、3番目が「娯楽・ホスピタリティ」で同期間に約94万人の雇用の増加が予想されている(第Ⅰ-2-1-3-18表)。これらの産業の多くの職種は前述の「非定型業務」に相当し、今後も増加トレンドが続くことが予想される。
第Ⅰ-2-1-3-18表 米国の2024年の雇用構成見通し
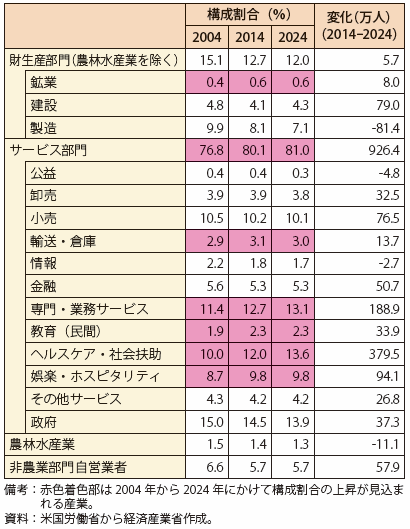
さらに、職種別の見通しを見てみると、2014年から2024年までの10年間で雇用の増加人数が多いと予想されている職種は、1位:介護スタッフ、2位:看護師、3位:在宅医療スタッフと医療関係の職種が上位に並ぶ。また、上位10職種のうち、学歴不問の職種が6職種(予想増加人数は177万人)、何らかの高等教育が求められるのは3職種(同85万人)、そのうち大学卒業の学歴が必要とされるのは2職種(同59万人)となっており、高等教育を必要とする職種よりも学歴を不問とする職種が多いことが分かる(第Ⅰ-2-1-3-19表)。
第Ⅰ-2-1-3-19表 米国で雇用の増加人数が多いと予想される10職種(2014-2024年)
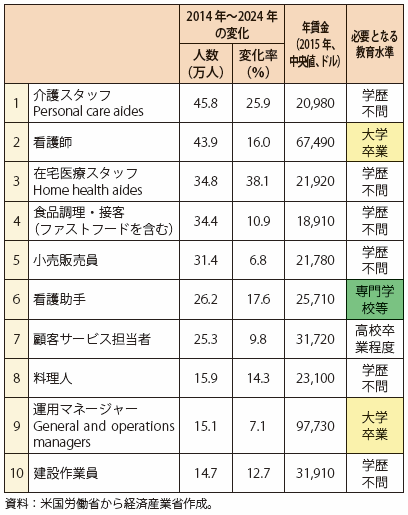
他方で、2014年から2024年までの10年間で雇用の増加率が高いと予想されている職種を見ると、こちらも医療関係の職種が多く並ぶが、上位10職種のうち、学歴不問の職種は1職種(35万人)、何らかの高等教育が求められるのは7職種(18万人)、そのうち大学卒業以上の学歴が必要とされるのは3職種(13万人)となっており、高等教育を必要とする職種が多い(第Ⅰ-2-1-3-20表)。
第Ⅰ-2-1-3-20表 米国で雇用の増加率が高いと予想される10職種(2014-2024年)
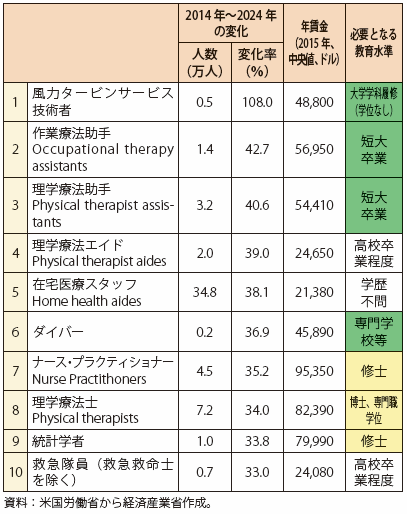
また、雇用の見通しを教育水準別に見てみると、2014年から2024年の間に、博士、修士、学士取得者の雇用増加率はそれぞれ12%、14%、8%と予想されているのに対し、高校未満、高校卒業程度の人々の雇用増加率はそれぞれ7%、4%とされており、高等教育を受けた人々の伸びが高い(第Ⅰ-2-1-3-21表)。現時点では高校卒業以下の学歴があれば就ける職種が6割以上を占めているが、高等教育を必要とする職種は伸び率が高いため、向こう10年間の増加人数の5割程度は何らかの高等教育を必要とすると予想されている。また、高校卒業程度の人と学位取得者では賃金水準が2倍近く異なるなど、教育水準によって賃金水準が大きく異なるため、このような傾向が今後も続けば、高等教育を受けようとする人々が今後も増加していくことが予想される。
第Ⅰ-2-1-3-21表 米国における就職に必要な教育水準と雇用の見通し
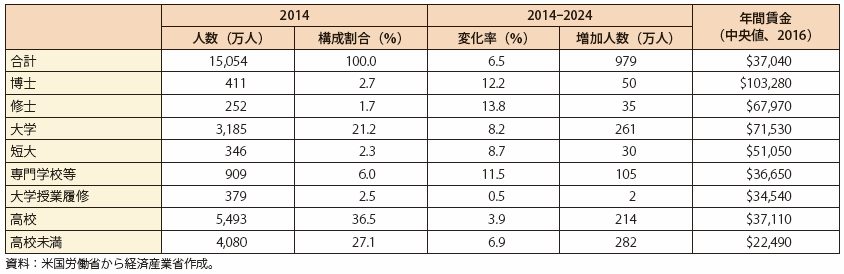
45 失業者とは4週間以内に求職活動を行った人であることから、ここでは失業前と同業種内での職探しを行っていると仮定する。
46 U.S. Department of Labor “Employment Projections―2014-24”、2015年12月8日、U.S. Department of Labor Webサイト
4.今後の米国経済と課題
前項で見てきたとおり、米国は7年以上にわたる景気回復期にあり、労働市場は力強く推移し、経済活動は緩やかに拡大している。こうした状況の下、新政権によって打ち出された様々な政策が今後どのように具体化されていくのか、またそれらが内外に及ぼす影響が注目されている。新政権が打ち出すインフラ投資、税制改正等の財政政策は経済成長を押し上げる可能性がある一方で、今後明らかになる具体的な内容次第では経済の下振れ要因となるリスクもある。また、金融政策においてはFF金利の引上げ、バランスシート縮小などが見込まれているが、これらの動きが為替、株価、内外景気等に影響を与える可能性もある。近年弱めの動きが続いていた企業の設備投資の動向にも注目が集まる。
以下では、2017年1月に始まったトランプ新政権がこれまでに打ち出している政策について概観する。次に、米国経済・社会の長期的課題と考えられる労働参加率の低下及び高等教育の費用に関する問題について整理する。
(1)トランプ大統領の経済・通商政策動向
新政権は米国民の利益の保護を強く打ち出しており、通商政策については、多国間ではなく二国間での交渉を目指している。また、経済関連では税制改正や老朽化したインフラの近代化を含む大規模なインフラ投資を行う意向を示しており、注目が集まる。
まず、選挙期間中には、「米国人有権者との契約」として就任後100日間の行動計画が発表された。ここでは、「ワシントンの汚職と特別な利害関係を一掃する措置」、「米国の労働者を保護するための行動」、「安全と法の支配を回復させるための行動」、「100日以内に法制化を目指す措置」の4項目の下で各種政策が表明されており、経済・通商関連では、NAFTAの再交渉やTPPからの離脱といった通商政策の見直し、法人税の引下げを含む税制改正などが挙げられている(第Ⅰ-2-1-4-1表)。
第Ⅰ-2-1-4-1表 トランプ大統領「100日行動計画」経済関連施策(抜粋)
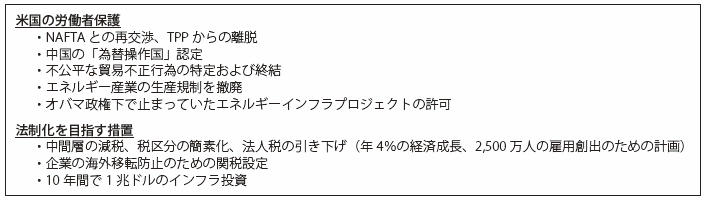
就任後の2017年3月には、2018会計年度の予算案の編成方針を示す予算教書47の原案が議会に対して提出されたほか、通商代表部から「2017年通商政策課題」が公表され、通商政策の骨子が示された。「米国第一:米国を再び偉大にするための予算の青写真」との表題が付けられた予算教書では、国防費や教育関係費といった裁量的支出についての予算案が示され、国防費の上限を540億ドル(10%)増額させる一方で、非国防費の上限を同額減額させる案が提示された。省庁別に見ると、国防省(前年比10%増)、国土安全保障省(6.8%増)等が大幅に増額となり、安全保障分野の重視が明確になった。他方、国務省(28.7%減)、環境保護庁(31.4%減)等多くの省庁の予算が減額となった(第Ⅰ-2-1-4-2図)。
第Ⅰ-2-1-4-2図 2018年度予算教書による主な省庁の予算(2017年度比)
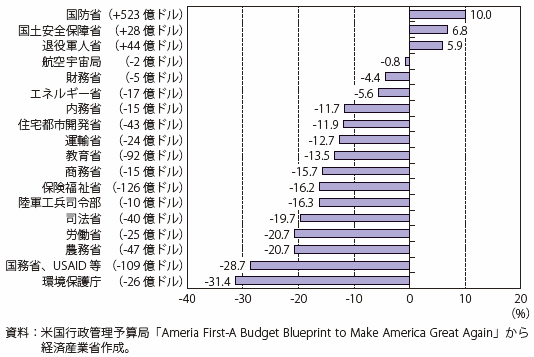
また、「2017年通商政策課題」では、貿易政策の最重要目標は「全ての米国民にとってより自由でより公正な形で貿易を拡大すること」とされており、米国の経済成長及び雇用創出を促進し、貿易相手との相互主義を進展させ、製造業基盤と米国を守る能力を強化し、農業とサービス産業の輸出を拡大するために行動するとの方針が掲げられている。また、これらの目標を達成するための優先事項として、①通商政策における米国の国家主権を守ること、②米国通商法の厳格な執行、③外国市場開放のためのレバレッジの活用、④新たな、より良い通商協定の交渉、の4点が示された。
その他、トランプ大統領は、就任演説において「Buy American, Hire American」というルールを掲げるなど、米国における雇用創出促進の一環として、製造業及びそれによる雇用創出を重視している。就任から1週間後には、製造業の雇用を拡大させるため、ダウ・ケミカル、フォード・モーター、ゼネラル・エレクトリックなどの企業トップを含む産業界のリーダー28名から構成される製造業雇用イニシアティブ(Manufacturing Jobs Initiative)が創設された。トランプ大統領は法人税率の引下げ、規制緩和といった企業を優遇する政策を打ち出すとともに、米国製造業の国内回帰を企業に呼びかけており、今後の動向に注目が集まる。
47 予算編成権を持つ連邦議会に対して大統領が示す予算の編成方針。これを受け、議会が予算決議及び関連法案を作成する。
(2)人口動態が労働力に与える影響
近年、米国では労働参加率48の低下が続いており、景気回復に伴い労働力の確保が課題となりつつある49。G7各国の労働参加率の変化を比較してみると、2000年以降、米国を除く各国が上昇傾向にあるのに対し、米国は1990年をピークとして緩やかな低下傾向にあり、2014年時点では73.7%となっている50(第Ⅰ-2-1-4-3図)。また、男女別の労働参加率を見ると、90年代半ば以降、米国を除く各国では女性の労働参加率が上昇傾向にあるが、米国では2000年をピークとして徐々に低下が見られる。男性の労働参加率は米国以外でも低下が見られる国があるが、米国では1990年をピークとして徐々に低下しており、特に2008年頃から急激な低下が見られる(第Ⅰ-2-1-4-4図)。
第Ⅰ-2-1-4-3図 G7各国の労働参加率(全体)
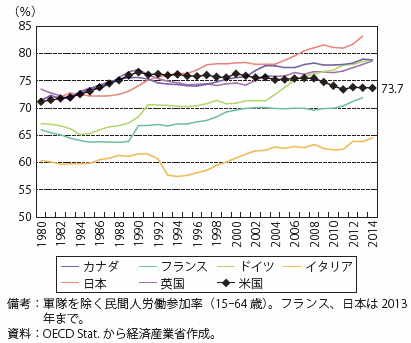
第Ⅰ-2-1-4-4図 G7各国の労働参加率
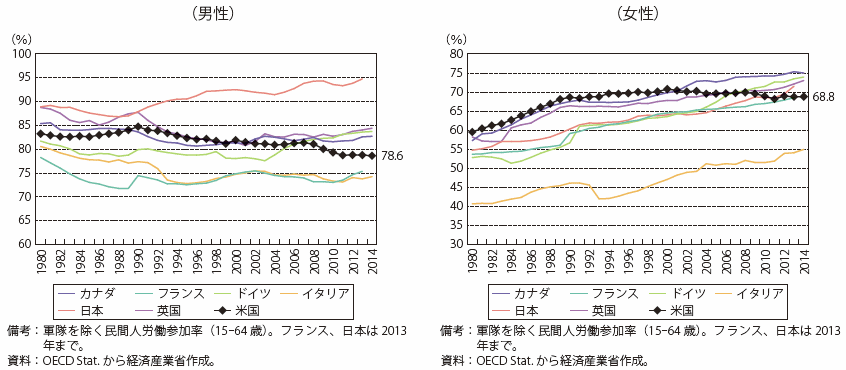
また、性別及び年齢層別の労働参加率51を見ると、16歳~24歳の若年層は、男性は一貫して低下傾向にあり、特に2000年頃からの低下幅が大きい。女性は2000年頃まではほぼ横ばいだったが、男性と同様、2000年頃から低下傾向となっている。プライム・エイジと呼ばれる25~54歳のグループは、男性は緩やかに低下を続ける一方、女性は2000年頃まで上昇を見せていたが、それ以降は男性と同じく緩やかに低下している。55歳以上のグループは、男女ともに90年代半ばから徐々に上昇していたが、2010年頃からはほぼ横ばいとなっている(第Ⅰ-2-1-4-5図)。
第Ⅰ-2-1-4-5図 米国の年齢別労働参加率(1980~2016年)
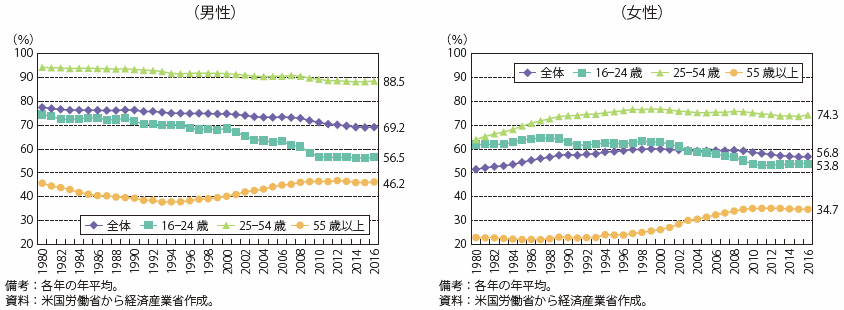
このような労働参加率の低下については構造的な要因が大きいと考えられ、全体としては人口の高齢化が大きな要因であるといわれている。米国は移民を多く受け入れていることに加え、出生率も比較的高いため人口が増加し続けており、高齢化の問題を抱える印象は少ないが、他の先進国と同様に米国社会でも徐々に人口の高齢化が進んでおり、2030年までに国民の5人に1人が65歳以上になると予想されている(第Ⅰ-2-1-4-6図)。高齢者層は相対的に労働参加率が低いため、労働力人口に占める割合が増加することによって全体の労働参加率は低下し、米国の労働力の成長は今後鈍化していくことが予想されている。
第Ⅰ-2-1-4-6図 米国の人口構成の見通し
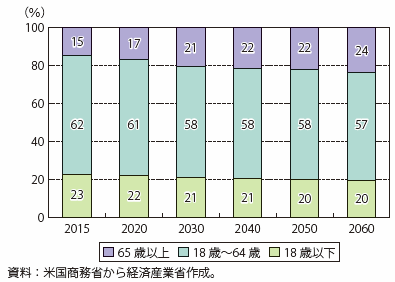
ただし、人口の高齢化だけで全ての要因を説明することはできず、他の年齢層における変化も全体の労働参加率の低下に影響を及ぼしている。例えば、若年層(16歳~24歳)の労働参加率が低下していることについては、90年代以降の就学率の上昇、特に女性の就学率の上昇によって相殺されているとの指摘がある52。また、25歳から54歳までの男性の労働参加率低下については、主に高校卒業以下の学歴を持つ人々の参加率低下が見られることから、技術進歩、自動化及びグローバル化による低技能者の労働需要の減少が要因の一つといわれている53。配偶者の就業、社会保障の受給などを理由として労働市場からの退出を選んだ人々は少ないとされており、不本意ながら労働市場から退出している人々が多くいることが示唆される。このほか、同じくプライム・エイジの女性の労働参加率については、米国以外の先進国では産育休や短時間勤務の制度等を整備したことによって上昇が見られた可能性があるといわれている54。
米国労働省によれば、労働参加率は足下の62.9%(2017年4月)から2024年には60.9%へ減少すると予想されている。世代別に見ると、16歳~24歳の労働参加率は55%(2014年)から49.7%(2024年)へ減少する一方で、65歳以上の労働参加率は18.6%(2014年)から21.7%(2024年)へ増加する見通しとなっているが、高齢者層の労働参加率は元の水準が低いため、全体としては低下が予想される。
労働参加率の低下による労働力の減少は経済成長にもマイナスの影響を与えるため55、労働力の確保は米国経済における長期的な課題と考えられる。また、労働力人口から外れる期間が長期にわたることで、労働市場への再参入がより困難になる可能性もある。労働する意思はあるものの、不本意に労働市場から退出している人々への対応策が今後求められる。
48 刑務所、介護施設、軍隊などにいる人を除いた16歳以上の人口に占める労働力人口(働く意思のある人、すなわち就業者と失業者の合計)の割合。
49 例えば、地区連邦準備銀行経済報告(2017年4月)は、足下で労働市場が逼迫しており、大半の地域で高技能者、低技能者ともに労働力の確保が困難になっていることを指摘している(Federal Reserve District (2017))。
50 当数値はOECDの民間人労働参加率(15歳~64歳人口に対する民間人労働力の割合)による。米国労働省による労働参加率は16歳以上の人口を対象としており、2014年の労働参加率は62.9%。
51 米国労働省による。
52 Krueger (2016)
53 Council of Economic Advisers (2016)
54 Blau and Kahn (2013)
55 米国労働省によれば、労働参加率の緩やかな低下に伴い、米国では2024年までの実質GDP成長率は年率2.2%にとどまると予想されている。
(3)高額な教育費と拡大する教育ローン
米国では学歴によって失業率及び賃金水準に大きな差があり、前述のとおり、今後も教育水準が高いほど高賃金職種への就職機会が大きくなることが見込まれている。そのような状況の下、1980年頃から米国の大学進学率は上昇傾向にあり、現在では18歳及び19歳の約半数が大学へ進学する(第Ⅰ-2-1-4-7図)。
第Ⅰ-2-1-4-7図 米国の18歳及び19歳の就学状況(1967年~2014年)
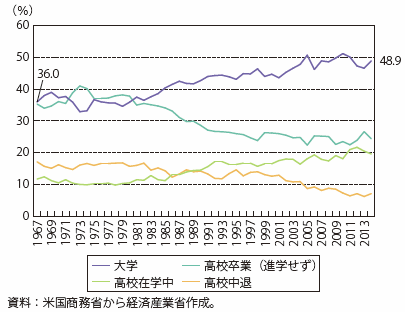
しかしながら、米国の高等教育は授業料が高額であり、2016-2017年度の4年制大学における学部学生の年間授業料等の平均額は公立大学で州内出身者が9,650ドル、州外出身者は24,930ドル、私立大学で33,480ドルとなっている(第Ⅰ-2-1-4-8表)。授業料は上昇傾向が続いており、1986~87年度から2016~17年度までの30年間で、私立大学で2.3倍、公立大学(州内出身者)で3.1倍の上昇がみられる(第Ⅰ-2-1-4-9図)。そのため、多くの学生が教育ローンを利用しており、卒業後の膨大な債務負担が社会的な問題となっている。
第Ⅰ-2-1-4-8表 米国の大学の年間費用(平均、2016-2017年度)
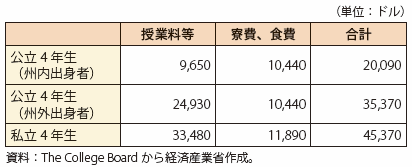
第Ⅰ-2-1-4-9図 米国の大学の年間授業料(平均)の推移
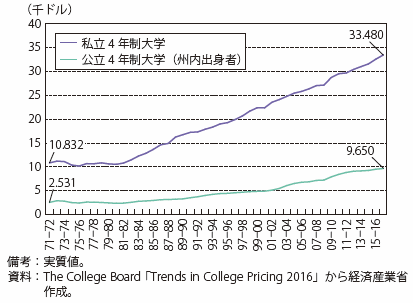
米国では奨学金制度等が整備されており、実際に学生が負担しなければならない正味価格は上記の定価(published price)よりもかなり低額になるといわれているが56、全ての学生が奨学金によって十分な費用を賄うことができるわけではなく、教育ローンを利用する学生も多い。FRBによれば、大学の学士学位取得者の約半数が何らかのローンを組んだことがあり、18~29歳の66%、30~44歳の56%が教育ローンを利用している、又は利用したことがあるなど、年齢層が下がるにつれて債務を抱える人の割合は上がってきている57。
家計が抱えるローンのうち、教育ローンの債務残高は世界経済危機の間も唯一増加を続け、現在では自動車ローン及びクレジットローンによる債務残高を上回り、住宅ローンに次ぐ規模となっている。債務残高は全ての年齢層において拡大傾向にあり、国全体の残高は2005年~2015年の10年間で3倍以上に増加し、2015年時点で1兆2307億ドルに上った(第Ⅰ-2-1-4-10図)。これは、教育ローンの利用者数及び一人あたりローン残高の両方が上昇しているためで、2005年以降、それぞれ年に約6%のペースで増加が続いており、2015年時点の利用者数は4420万人、一人あたりローン残高は27,870ドルとなっている(第Ⅰ-2-1-4-11図)。
第Ⅰ-2-1-4-10図 米国の教育ローン残高(年齢層別)
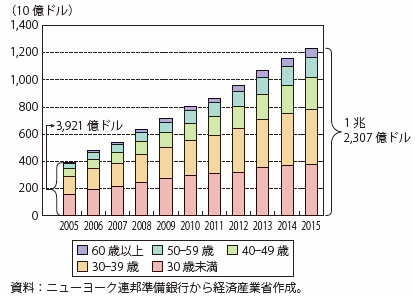
第Ⅰ-2-1-4-11図 米国の教育ローン利用者数及び一人あたりローン残高
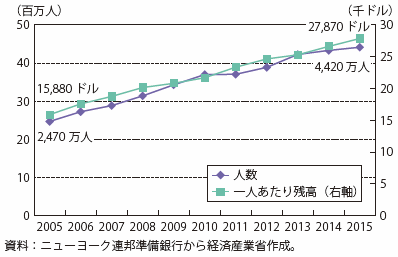
高等教育を受けることは所得の向上につながる可能性が高いため、格差の固定化を防ぐという意味からも教育機会が広く提供されることは重要である。高等教育を受けようとする人々にとって教育ローンは非常に重要な役割を果たしてきているが、卒業後の高額なローンの返済が若年層にとって過度な負担となっている場合もある。また、これらの返済負担は個人支出を圧迫するため、米国経済に対して悪影響を及ぼす可能性があるともいわれている。例えば、高額の債務を抱えていたり、返済延滞又は債務不履行58の状態に陥っていたりする場合は、住宅ローンの借入れが難しくなるため、住宅市場に悪影響を及ぼす可能性がある。配偶者又はパートナーと同居している若年層及び親と同居している若年層の割合の推移を見てみると、1990年以降、前者が徐々に減少しているのに対し、後者は増加傾向にあることが分かる(第Ⅰ-2-1-4-12図)。これには教育ローンの存在以外にも文化、環境など様々な要因が考えられるが、教育ローンの返済負担も一つの背景となっている可能性がある。
第Ⅰ-2-1-4-12図 米国の若年層(18-34歳)の同居の割合
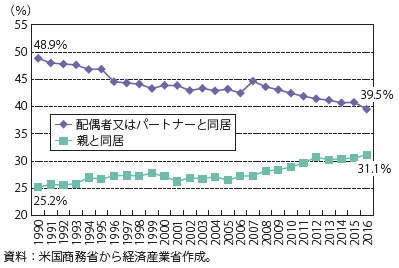
トランプ大統領は、前述した就任後100日間の行動計画において教育関連の法改正についても触れており59、2年制及び4年制大学を手の届く価格とすることを目指している。このような問題の解決には時間がかかると思われるが、今後どのような政策がとられていくのか注目される。
56 寺倉(2015)
57 FRB (2016)
58 教育ローンは返済を270日以上延滞すると債務不履行(デフォルト)と見なされる。
59 School Choice and Education Opportunity Act (学校選択と教育機会法)の法整備を目指すとしている。
